
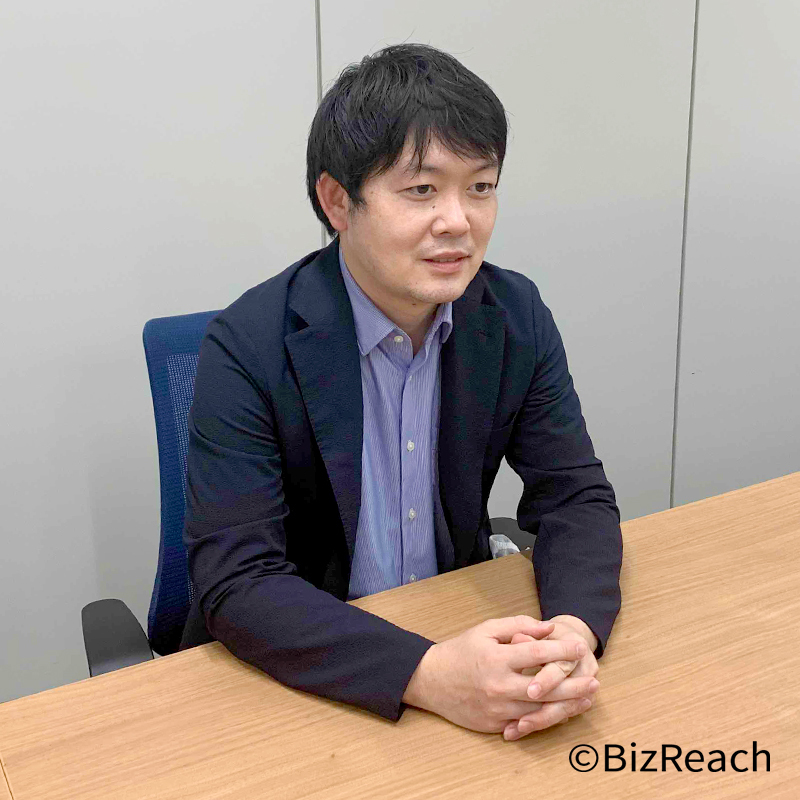
商務情報政策局 商務・サービスグループ 物流企画室
小早川 哲也(2019年入省・一般職係長級)
※役職等はインタビュー当時
日本社会や業界全体にダイナミックな変革を起こす
──小早川さんは2019年に入省したそうですが、転職を考えたきっかけ、入省の決め手について教えてください。
前職では、メーカーに勤務し営業職をしていました。転職は、官民人事交流制度で2年間、経済産業省で働いた経験があったことがきっかけです。官民人事交流制度は、民間企業と国という行動原理が異なる組織間における人事交流を通して、民間と国との相互理解を深め、組織の活性化と人材の育成につなげることが目的で実施されている制度です。 出向期間中は、水銀に関する水俣条約への対応や、断熱性能の優れた建材を用いた住宅の断熱リフォーム促進の業務に携わりました。経済産業省は、省庁のなかでも現場に近い仕事が多いので、社会を変えているという実感を持つことができました。出向が終わってメーカーへ戻った後も、このときの経験や関わった人たちの魅力が心に残っていましたね。民間企業では経験できない、ダイナミックな変革のなかで仕事をしたいと思い、入省を決めました。
──係長級(一般職相当)として、どのような業務を経験されてきたのでしょうか。
入省した当初は、福島復興推進グループに配属され、被災した福島県で産業復興の業務を行っていました。産業復興は被災事業者の事業・なりわい再建と新しい産業の創出の二つの軸で進めていて、私は前者を担当していました。被災された事業者の主な課題の一つとして、住民の避難等に伴う顧客の減少や長期にわたる事業休止に伴う取引先の減少などが挙げられます。そこで、私たちが販路拡大に向けた支援を実施することで、福島の復興を後押ししています。 福島復興の業務で特に大切なのは、被災された方々に寄り添うことです。私は前職の営業職で、関係者と密に情報をやり取りするうえで、相手の現状を受け入れ、傾聴することを意識していたので、その経験を生かして、被災地の方々との関係構築を進めることができました。 その後、現在の商務・サービスグループの物流企画室に異動し、物流の共同化や効率化に取り組んでいます。たとえば、共同配送のためのデータ基盤構築や物流資材の標準化など、物流事業者や発着荷主の方々が、物を運ぶことで競争するのではなく協調して全体最適を目指せるように、関係者の合意形成を行っています。 関係省庁の意見も取り入れながら、業界全体で物流の共同化や効率化に取り組むメリットを各民間企業の方々に示し、いかに納得していただけるようにするかを日々模索しているところです。こうした業界全体のマインドを変えていく仕事は、国にしかできないことであり、経済産業省で働く醍醐味の一つだと感じています。
年齢や肩書関係なく、新たなチャレンジを応援してくれる文化
──今の職場の環境や、経済産業省で働く魅力を教えてください。
私が所属している物流企画室は、官民人事交流制度での出向者や、民間企業からの研修員、地方局から来ている方など、さまざまな バックグラウンドを持った方がいて、人材交流が活発です。年齢や肩書関係なく、お互いに意見を言いやすい環境で、チャレンジする人を応援する文化が強いと感じています。 経済産業省は、世の中に勢いを生み出す役割を担っています。経歴や年齢にかかわらず、よりよい社会のために進めようとしている政策の方向性に共感する人が集まっている場所だと思いますね。私のように入省前に国の仕事を経験していないとしても、入省してから、助けてくれる同僚や先輩方がいます。民間企業とは異なる仕事の進め方にも数カ月したら慣れるので安心していただけたらと思います。
──最後に、この記事をご覧の方へメッセージをお願いします。
日本の社会課題に関わる政策というと、デジタル化といった最先端テクノロジーに詳しい人材だけしか活躍できないのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれません。でも、日本社会を変えるということは、最先端のテクノロジーを取り入れるだけのシンプルな作業ではなく、今ある現場を熟知していないと、机上の空論になってしまいます。
そういった意味で、経済産業省は現場主義を大事にしています。だからこそ、どんな産業でもいいので、現場に詳しい方、現場で一生懸命努力されてきた方は、経済産業省で活躍できる土俵はたくさんあります。民間での経験を生かして、よりダイナミックな社会変革を起こす仕事に、一緒に挑戦したいという方をお待ちしています。
ビズリーチ 公募ページ「経済産業省」(2021年11月30日公開)より転載
最終更新日:2023年9月1日