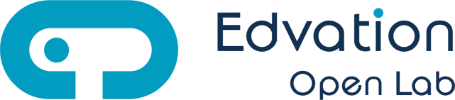- ホーム
- 次代のEdTechイノベーター支援プログラム(Edvation Open Lab:EOL)
- 気鋭のEdtechイノベーターをサポートするキックオフセミナーが開催。Edvation Open Lab 2022イベントレポート
気鋭のEdtechイノベーターをサポートするキックオフセミナーが開催。Edvation Open Lab 2022イベントレポート
2022年11月30日
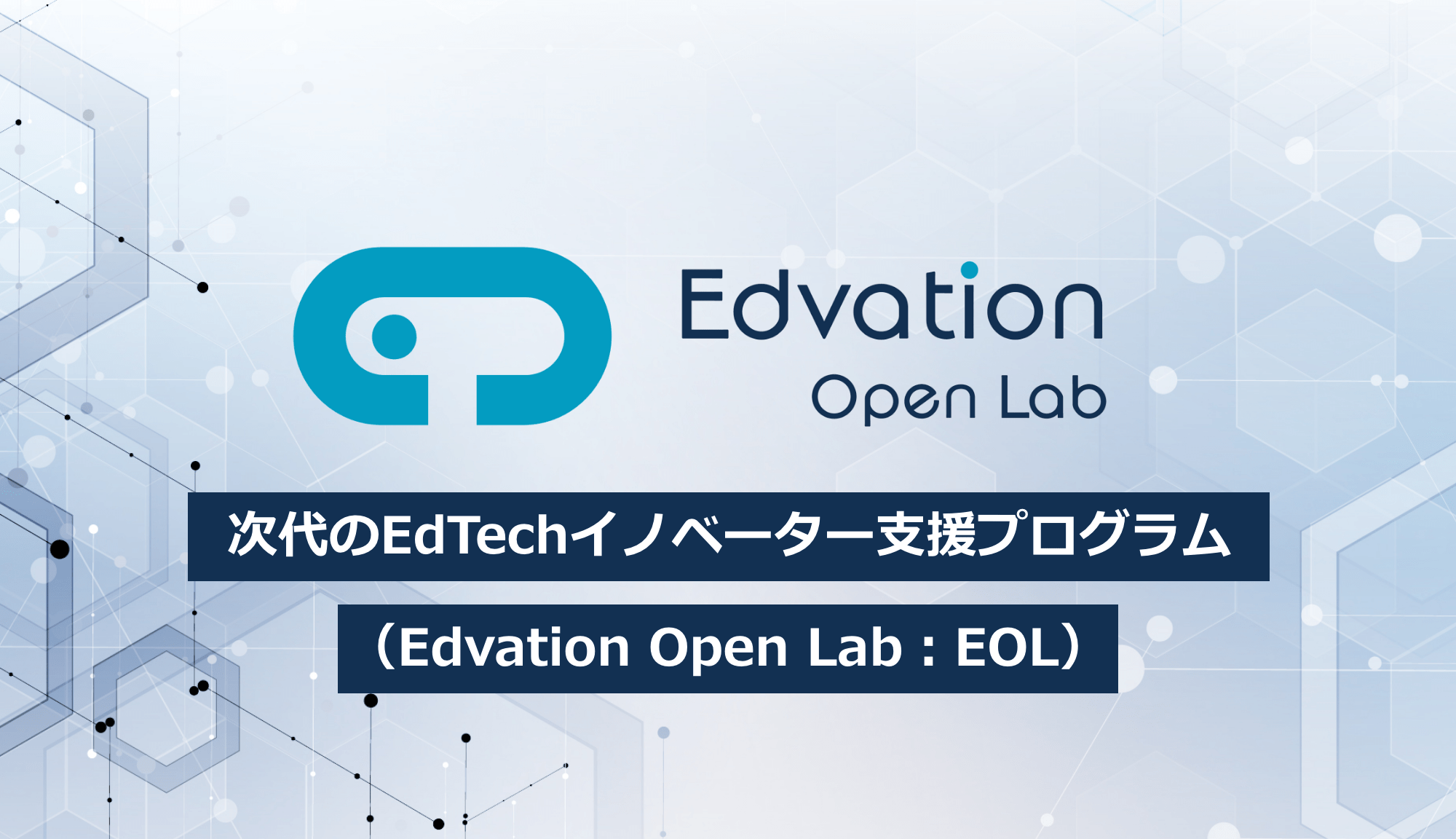
日本の教育イノベーションを担う、次代のEdTechイノベーター育成を目的とする支援プログラム「Edvation Open Lab(通称:EOL)」。2022年度は40数社の応募があった中、12社が採択されました。本プログラムのスタートイベントとして2022年11月30日(水)、BASE Q(東京都千代田区)にて「Edvation Open Lab 2022 キックオフセミナー」が開催されたので、その模様をお伝えします。
イノベーションにはビフォーアフターが伴う
当日は、会場に採択企業が集まり、事前参加登録者向けにオンライン配信を行いました。
冒頭、経済産業省 商務・サービスグループ サービス政策課 教育産業室の五十棲浩二室長による開会挨拶が行われ、「デジタルを使った学びに助けられた」と、自身の体験を交えながら、教育×テクノロジーの重要さ、そして教育分野の現状について言及。さらに、「GIGAスクール構想」によるEdTechの大きな可能性について等、プロジェクトの趣旨説明を行いました。
続いて、同プログラムのコアアドバイザーである、デジタルハリウッド大学大学院 教授・学長補佐、一般社団法人教育イノベーション協議会 代表理事の佐藤昌宏氏が登壇。自身もイノベーターであり、実務経験からのインキュベーションプログラムの必要性を説明。
また、佐藤氏は「GIGAスクール構想」の課題を通して参加者を鼓舞しました。
「児童1人1台端末が支給され、通信ネットワークとクラウド環境が整備されても、実際に上手く使いこなせているのかは疑問です。学習者が簡単に使えるサービスやプロダクトを提供するのは、私たちEdTechイノベーターの役割。日本の教育改革を推進するうえで最も重要なのは、それを仕掛けるEdTechイノベーターの存在、つまり皆さんなのです」
大人と中高生が相互でプラスになるシステムを
最初に登場した株式会社すみかの月館氏は、昨年度のEOL参加者。2022年1月に同社を設立し、働く大人と中高生の対話型越境キャリアプログラム「canau」というサービスを展開しています。言わば、参加者に一番近い立場。今回は、マネタイズ方法に困っている、学校から予算を出してもらえるのかわからないなどの課題を抱える参加者にとって有益な話をしていただきました。

株式会社すみか 代表取締役 月館海斗氏
「私は2021年3月まで教員をしていたのですが、起業をし、中高生が先生以外の大人たちに相談ができるオンライン指導サービスを開発しました。このサービスを始めたきっかけは、教員時代にある生徒から“女優になりたいのですが、どうすればいいですか?”と相談を受けたことでした。私はどうアドバイスしていいのかわからず、似た仕事をしている人を紹介したところ、彼女はそのアドバイスに従い、オーディションを受け、今は大学に通いながら女優活動をしています。その経験から、先生だけでなく、さまざまな大人のサポートを受けて、中高生が悩みや相談事を解決できる仕組みがあればいいと思ったのです」
実際にサービスを開始すると、中高生から相談を受ける立場の大人たちが、実は働くことに誇りを持っていないことに気付いたと月館氏。
「大人自身が仕事に誇りを持っていなければ、中高生に対して“働くことの面白さ”を伝えるのは難しい。そこで大人も同時に“働くことに誇りを持てる”仕組みにしようと考え、単なる中高生向けオンライン指導サービスではなく、大人向けに研修をしながら、大人が学んだことのアウトプット先として、進路相談ができる仕組みにしました」


働く大人と中高生の対話型越境キャリアプログラム「canau」のサービス概要
「具体的には、社間研修と進路相談を組み合わせ、大人は自分のキャリアの棚卸、コーチング、ファシリテーションなどを学びます。ここでポイントとなるのは、中高生と目線を揃えることができること。キャリア教育の場合、大人が偉そうなことを言って終わってしまうケースが多く、過去にはそれが起因して保護者や学校とトラブルになった企業もありました。そういった課題を改善することにも役立っています」

中高生は気になる大人がいたら進路相談を申し込む

相談中の画面。時間は全部で50分、ロボットの進行にそって話をする
「中高生がプラットフォームを見て、“この人と話したいな”と思ったらオンラインで申請。後日、zoomで進路相談をするという仕組みです。弊社の場合、協力企業からお金をいただいて運営しています。単なる研修ではなく、社会の人と一緒に学び越境体験ができること、中高生にアウトプットでき、スキルの定着率が上がっていく点、仕事や会社について語るので社内外のブランディングになるなど、大人(企業)側にもメリットのあるサービスを構築しているからです」
同サービスは2022年夏から実施を始め、現在3校と契約。これまで148名の生徒が利用し、企業側は28社49名が相談役に。その業種や職種は実にバラエティに富んでいます。本年度中には生徒数1000人突破を目指すとともに、今後は大学と提携して学生に進路相談ができる仕組みの構築、アートやスポーツといった横展開も考えていると月館氏は意気込みを語りました。
EOL参加によりスムーズな起業が可能になった
また、前回のEOLに参加したことでどんな変化や影響があったかにも言及。
「ちょうど起業前に参加したのですが、当初は進路相談する大人の対象として、各学校のOBやOGを想定していました。そこへ“間口を広げてさまざまな企業でやってもいいのでは”というアドバイスをいただいたのです。また、EOLをオンラインで観てくれた高校の先生が、私の事業に興味を持ち、連絡をしてくれました。その高校とは今一緒に事業を進めています。まさにEOLに参加したおかげで起業できたと感じています」
さらに、補助金や借入、クラウドファンディングの活用など、資金調達方法にまで月館氏の話は及びます。
「学校と企業それぞれにサービスを提供しているわけですが、それぞれがwin-winになるような世界観を目指して頑張っています。起業、事業展開に必要なマインドセットとして“教育は儲からないという一般論に抗う反骨心”“ビジネスロジックよりも原体験を大事にする”“ハンズオンで関わる人を見極める”ことを忘れないでください」と参加者にエールを送り、講演は終了しました。

日本各地で“探究プロジェクト”を展開
続いて、高校生の必修科目である「探究学習」をITで支援する、株式会社Study Valleyの田中悠樹氏が登壇しました。

株式会社Study Valley 代表取締役CEO 田中悠樹氏
「2020年1月に資本金約1億8000万円で起業しました。EOL参加後に、マイナビさんから資金調達を実施。その後、『東洋経済』の『すごいベンチャー100』にも選出されました。教育分野から選ばれたのは2社。もう1社は東南アジアで展開しているので、実質、“日本のEdTechのスタートアップで唯一選ばれた会社です”と、外向けには少し盛って話しています(笑)。この反響もあり、当時は10人規模の会社だったのですが、現在の従業員数は30人ほどになっています。」
現在、同社が展開している事業が、日本各地の“探究プロジェクト”です。例えば、宮崎県では“ひなた探究”、広島県では“もみじ探究”、沖縄県では“はいさい探究”など、地域に根ざした探究プロジェクトを実施しています。

県内の高校生と企業が地域の課題を協働で探究するプロジェクト
公教育分野は大変ではなく普通じゃないだけ
続いて、同社のメイン顧客である公教育分野の話へと進みます。
「弊社のお客様は公教育分野です。小中学校も手がけていますが、探究科目が必修化されている全国の高校が中心で、現在約10万校、来年度には20万校を超える予定です。公教育分野の場合、学校にセールスするのが大変というイメージがあると思います。営業の視点でいうと、決裁フローが多いですね。まずアポイントを取ってサービス内容を説明し、探究学習の先生が“いいね”と言ってくれたとします。しかしその後、学年主任、教頭、校長、さらには学年会や部会で説明し、承認を得なければなりません。どう整理したら、通常のB to Bセールスの形に持ち込めるのか、科学する必要がある。その点が公教育分野に2年ほど関わってきて見えてきた部分です」

そして事業転換の話へと続きます。実は田中氏、創業当時はto C向けの算数アプリを展開していました。新型コロナウイルスにより休校が増えたことが追い風となり、アプリのダウンロード数が日に日に激増。ところが、ある時期から陰りを見せ始め、コロナが落ち着きだすとピタッと成長が止まったと言います。
「後から気付かされたのですが、アプリは半年経つと使われなくなり始めるんです。疑問に思い、保護者100人ぐらいと会ってヒアリングをすると、“算数アプリ自体はいいが、子どもにそのアプリを開かせるのがすごく大変”との返答。確かにそうだと思いました。親御さんがどんなにいい教材を買い与えても、子ども本人にやる気がなければ使わない。いいAIアプリや教材を作るよりも、“そもそもなんで勉強する必要があるの”という方が重要だと気付かされて事業転換。探究プロジェクトの事業に踏み出しました。
事業転換した当初は、自分の営業力だけが頼りでしたが、並行して使いにくさを改善するなど製品も進化させ続けています。しかし、単にお客様の要望に100%応えるだけでは、“先生の御用聞き”になってしまう。お客様の声に耳を傾けつつ、不要な機能は捨て、お客様が“これはおもしろい”“想像を120%超えた”というものをひたすら作ることが大切です。

学校でいろいろな先生の話を聞いていると、何がファクトで、何が結論なのかわからなくなることがあります。そこを見極めて、どうやって結論に持っていくか。社員全員で探究合宿をやるぐらい、先生の行動心理などを徹底的に科学して、プロダクト開発を進めています」

最後に、ベンチャーとしての心構えについて語っていただきました。
「まずはひたすら動き回る。ウェブマーケティングなど他の手段もあるかもしれませんが、スタートアップ時は泥臭く動き回るしかほぼ道がないと思います。100回断られても、“これを聞けたから1時間割いて良い情報をもらえたな”といったポジティブシンキングを続けてきました。こうしたやり方だと、時に社内で軋轢が生まれるなどありますが、とにかくどんな状況でも動き続けないといけません。裏技はないので、皆さんも正攻法でひたすら動き回ってください」
親御さんにとって教育は1回しかできない子どもへの投資
最後に登壇したのは、Institution for a Global Society株式会社の福原正大氏。「ここに選ばれた方たちは独創性があるか、あるいはインプリメンテーション力が高いか、その双方を兼ね備えていると思います」と参加者を称え、同社の事業内容について説明をスタートしました。

Institution for a Global Society株式会社
代表取締役 福原正大氏
「私どもはEdTechだけでなく、HRTechの両方の領域を手がけていると考えています。供給サイド視点か、需要サイド視点かという考え方。業界でみれば、教育業界があってHR業界があるわけですが、私どもは1人1人の立場に立っているので両方を立ち上げています。そして全体を統合するブロックチェーン領域も含め、この3領域で展開しています。

弊社は2010年に創業し、2021年に上場しました。当初は5年での上場を予定していましたが、そう簡単ではなく12年かかりました。そもそも私は金融業界しか経験がなく、教育業界とはまったく無縁。以前はサンフランシスコやロンドンなど、海外で働いていたのですが、日本で活躍している人たちが、いざ世界の舞台に出てみると全然イケてないと感じ始めたんです。そこで、有能な日本人が海外でも実力を発揮し、世界の多様性に寄与できるようになるにはどうすればよいのかと考え、それを実現したいという想いから起業しました」

福原氏が始めたのは英語塾。それも、物事に対してさまざまな視点から世界の人たちと英語で深く議論できる子どもたちの育成を目的としました。なぜなら、福原氏自身の海外での苦い体験談があったからだと話します。
「海外の晩餐会などの場では、哲学や文化、アートについて英語で議論をしています。しかし、ビジネス英語は問題ありませんが、私の英語力では哲学やアートを十分に議論できませんでした。それで塾を作ったものの、人は集まりません。塾業界のノウハウに乏しく、金融出身だったこともあり、100坪の大きなスクールをいきなり作ってしまって。形から入ってしまったんですね。
塾を始めてから気付いたこともありました。教育とは、親御さんにとっては、“一生涯で1回しか子どもにできない投資”なんだと。私は金融業界にいたので、投資と言えば分散投資させればいいという発想があるんですが、教育は1回しか投資できない。ゆえに親御さんからの信用をどうやって得るかがすごく大切なんです」
VCからの調達には強い特許が必須
「先ほど失敗談をお話しましたが、最初のピボットはどこにあったか。いろいろ調べていくうちに、私どもの塾のカリキュラムなら、ハーバードやスタンフォードにも合格するとわかりました。そこで“ハーバードやスタンフォードを目指す塾”と、ポジショニングを微妙に変えたのです。すると早々に日経BPさんから“東大とハーバードの二兎を追うというテーマでメディア展開しませんか”と話がきました。それで記事を書き、ほかの媒体でも書かせていただくようになったら、一気に生徒が集まるようになったのです」
しかし、塾の規模が大きすぎたため、2011年にキャッシュフローがピンチに。それを乗り切れたのは、講演など人前で話す機会を増やしたことで賛同してくれる人が現れ、出資してくれたからだと言います。その後は、塾だけでは頭打ちになると考え、オンライン英語学習ツールの展開、資本の増強、塾の売却、その資金を基にデータを使ったビジネス展開のスピードを上げるなど、事業を拡大。
「教育に関わるベンチャー企業だからこそ、株式会社ウィザスや、学校法人河合塾等のように、教育関連企業から出資していただくことが重要だと考えました。そこで最初は、東京大学と東京理科大学のベンチャーキャピタルから資金を調達。東京大学のベンチャーキャピタル(UTEC)は、日本で最も成功しているVCですが、教育領域に出資したのは弊社のみ。なぜ弊社は選ばれたのか。実は弊社は圧倒的なテックの特許技術を持っているのですが、特許が世界レベルで成立しているために模倣不能であることが決め手でした。基本的にUTECは模倣不能でなければ投資しない、相当厳しいVCではありますが、弊社は、IAT(Implicit Association Test/潜在連合テスト※)という心理学の応用で画面特許から取得することができたので、それが評価されたのだと思います」

※IATとは、自身で意識することができない潜在的態度を測定するためのテスト方法。固定観念や偏見、差別を見極めるための方法として信頼性が高いと言われている
その後、プラットフォームの難しさについても言及。アプリを切り捨て、Webベースでの展開に切り替えた話へと続きます。
「今回採択された企業の事業内容について、プラットフォーム事業、マッチング事業を目指している方が多いと感じたのですが、プラットフォーム事業の最大のハードルは、両サイドに完全にマッチングをかけるのが簡単ではない点。私の場合、途中からプラットフォームを捨て、片方の企業からお金を取るB to B to C、あるいは学校や自治体からお金を取るB to B to Cという形で、B to Cビジネスを完全に捨てるピボットを行いました。
当初はB to C向けにアプリを作っていましたが、アプリの場合、最初こそダウンロード数が多いのですが、すぐに使えなくなったり、OSがバージョンアップすると毎回調整をしなければいけないなど、どんどんコストがかかってしまいます。そこで、アプリをやめて、全てWebベースにし、サービスもまったく違うB to Bモデルに切る変えるピボットを行い、これが正直、すごくうまくいきました。

その後、京都大学や慶応義塾大学のVCからも資金調達することができたのですが、経済産業省の支援の影響も大きかったです。創業当時から私のメンターである投資家の方に言われていたのが、“国の大きな方向感、マクロ環境に乗らない事業というものは、どこかで失敗に終わる”ということ。とくに教育分野では、それが重要だと思っていて、国が大きく目指している方向に乗っていくことも必要です。
現在、数多くのEdTech企業が成長していますが、それにはGIGAスクール構想が大きく影響しています。私が最初に失敗した当時は学校にWi-Fiはありませんでした。今はGIGAスクール構想でWi-Fiがあるので、学校にシステムやサービスを入れてもらいやすくなりました。
皆さんにはこのEOLを最大限利用していただきたい。そして、出来る限り多く発言してください。SNSやメディアを含め、あらゆる場所に登場すると、声がかかり、賛同者が増え、予測していなかったチャンスがでてきます」
先輩起業家を囲み質疑応答
講演が終わると参加者は3グループに分かれ、それぞれ月館氏、田中氏、福原氏を囲みながら車座トークがスタート。参加者の事業内容を含めた自己紹介のあと、「先輩方からスタート時の話が聞けて参考になりました」「資金調達のヒントを得られてよかった」など、講演の感想を述べていきました。その後、参加者は次々と質問や悩みを先輩起業家にぶつけ、先輩起業家たちも真摯に答えていきました。

先輩起業家を囲んでの車座トーク。自由なディスカッションが行われた
福原氏のグループでは、ある参加者から「仮説を立ててユーザーを募ろうとしても、そもそも人が集まらないのが課題です。SNSの反応も鈍く、最初に知ってもらうためにはどうすればいいでしょうか?」という質問が。それに対して福原氏はこう回答。
「私の場合は本を書いたのですが、それが大きかった。自費出版でもいいので、本を書くと講演会に呼んでもらえて、講演会に呼んでもらえると情報発信ができて、顧客がついてきたりする。また、講演会の時に印象的な言葉を必ず入れます。例えば“このままの教育で、子どもたちの未来は大丈夫ですか”みたいに。そうすると共感を得られて、圧倒的なサポーターが出てきます」
一方、月館氏のグループでは、「メンバーをどのタイミングで入れたのでしょうか?」という質問が。それに対して「最初に入ったのがインターン生。元教え子が私のSNSでの発信をフォローしてくれて。人材募集をかける前だったので、調査など、出来ることからやってもらいました。その後、自分でプログラムを作るのは限界があったので、エンジニアを見つけ、サービスができたので次は営業だなという感じでした」と自らの経験を語ります。
田中氏のグループでは、「具体的な営業の戦略を教えてほしい」という質問が。
「営業のプロセスについては、講演でも話したように、公教育機関の場合、1人でも否定的な意見が出ると商談は流れてしまいます。なので、各決裁プロセスで、どういうことが論点になって、どういう視点でつっこまれるか徹底的に調べて臨む以外に方法はありません。とはいえ、学年会ではこういうことを聞いてくる、主任ならこういうことを聞いてくる、等ある程度パターン化できます。どんなパターンがあるかは数をこなすしかなく、これは検索しても出てきません(笑)」
車座トークの時間はあっという間に過ぎ、約2時間のキックオフセミナーは終了時刻に。その後開かれた懇親会では、参加者たちが先輩起業家たちと熱く語り合う姿が印象的でした。
講演者プロフィール
-

-
月館海斗氏
株式会社すみか
代表取締役 -
立命館慶祥中学校・高等学校にて3年間教員として勤め、2021年3月退職。2021年4月株式会社シーラクンス入社。小中学生向けのプログラミング講師を経て、2022年1月株式会社すみか設立。
-

-
田中悠樹氏
株式会社Study Valley
代表取締役 CEO -
東京大学大学院卒業後、ゴールドマン・サックスにアプリケーションエンジニアとして新卒入社。スタートアップCTO等歴任の後、株式会社リクルートホールディングスにてスタートアップへの出資を担当。2020年1月Study Valley設立。
-

-
福原正大氏
Institution for a Global Society株式会社
代表取締役 -
三菱UFJ銀行に入社後、企業留学生としてINSEADでMBA、およびパリのグランゼコールHEC Parisに留学し国際金融修士取得。その後、バークレイズグローバルインベスターズ現ブラックロックに入社し、日本法人の取締役も歴任。同社で働く傍、2005年に筑波大学にて経営学博士号を取得。2010年、Institution for a Global Society株式会社を創設。
最終更新日:2023年2月15日