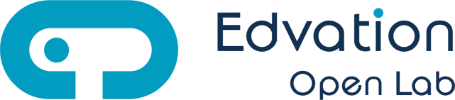- ホーム
- 次代のEdTechイノベーター支援プログラム(Edvation Open Lab:EOL)
- Edvation Open Lab 2022イベントレポート vol.2「教育現場におけるEdTech導入のリアル」
Edvation Open Lab 2022イベントレポート vol.2「教育現場におけるEdTech導入のリアル」
2023年1月26日
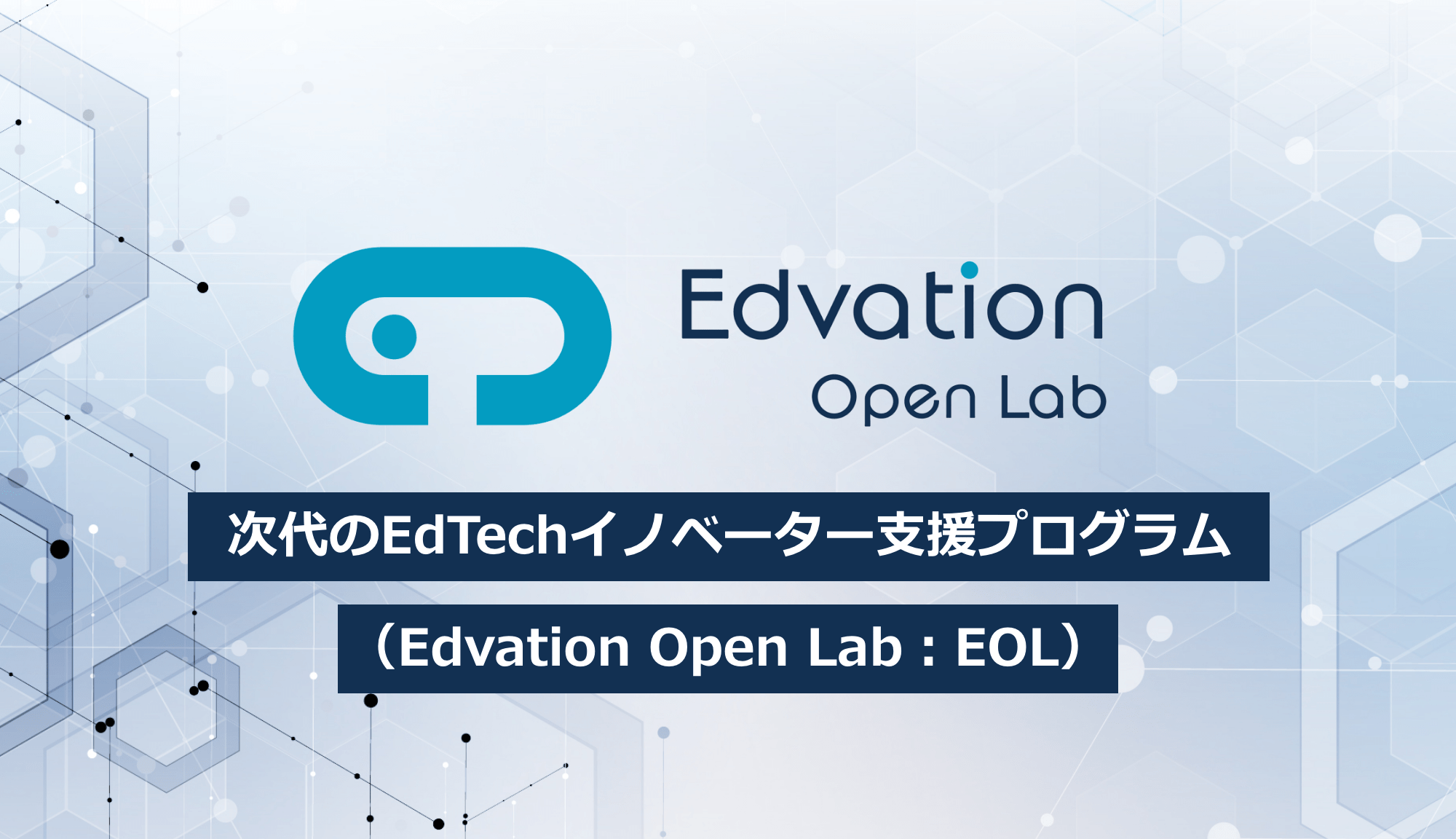
日本の教育イノベーションを担う、次代のEdTechイノベーター育成を目的とする支援プログラム「Edvation Open Lab(通称:EOL)」。本プログラムのセミナーが、2023年1月26日(木)にBASE Q(東京都千代田区)で開催されました。今回のテーマは「教育現場におけるEdTech導入のリアル」。教育委員会等から、3名の方々を招いて行われたパネルディスカッションの模様をダイジェストでお届けします。
パネリストの自己紹介と取り組みについて
今回のパネリストは、群馬県教育委員会事務局総務課デジタル教育推進室指導主事の山岸太郎氏、埼玉県久喜市教育委員会教育部指導課 指導主事兼指導課付GIGAスクール推進室長の山本純氏、そして経済産業省教育産業室係長の齋藤直樹氏の3名。リアルな現場体験の話が聞けるとあって、この日も会場は多くの方で賑わいました。まずは簡単な自己紹介と取り組みに関する話からスタート。
「生まれも育ちも群馬県」と話す山岸氏は、民間企業、県立の高校教諭を経て、9年前に県教育委員会に異動。現在は群馬県の教育のデジタル化を推進するために日々努めています。同県は2020年度に県立高校の生徒に1人1台端末を整備。EdTech導入補助金(※1)の活用例としては、「授業支援サービス」「AI型ドリル教材」「英語学習サービス」「プログラミング学習サービス」「デジタル採点」などがあるそうです。また補助金とは別の成功事例として、民間企業との連携による健康データ「Gライフログ」の活用を紹介。「Gライフログ」では、児童生徒が毎朝、体温や体調、気分を選択入力し、教師は児童生徒の心身の健康状態を確認できるため、生徒児童の心身の健康状態が可視化され不登校やいじめ兆候の早期発見が期待されます。さらに、デジタル人材の育成事業やクリエイティブ拠点化の実現に向けた取り組みにまで話が及びました。
※1 学校等教育現場における先端的教育用ソフトウェア(以下「EdTechツール」という。)の導入に要する経費の一部を補助することにより、EdTechツールの学校等への導入を促進し、学校等設置者等と教育産業の協力による教育イノベーションの普及を支援する補助事業。現在まで3カ年実施されている。
続いて紹介されたのは、大学卒業後、約12年間小学校で教壇に立っていたという山本氏です。2020年から久喜市教育委員会に勤務。GIGAスクール構想がスタートして3年目を迎える同市で、「久喜市版 未来の教室」の実現に向けて奮闘しています。この「久喜市版 未来の教室」には4+1のコンセプトがあると説明。①「時間・距離に制約されないオンライン教室の実施」、②「客観的・継続的データに基づく個別最適な学習の提供」、③「凡用的な能力を養うSTEAM化された学びの提供」、④「統合型アプリケーションによる校務の効率化を実現」、そして+1とされるのが「ICTを使いこなしつつ、人間教師の良さを生かした学びのコーディネーターたる教師を育成」。各コンセプトについて詳しく解説していただきました。

3人目の齋藤氏は県立高校で15年勤務し、その後、三重県教育委員会へ異動。2021年から経済産業省に出向しています。まずは自ら関わるSTEAMライブラリー(SDGs等の課題をテーマにした探究学習コンテンツ集)について紹介。2021年度の開発コンテンツ例や実証授業についても触れました。さらに学校への探究やプログラミングサービス等の導入を支援する令和4年度第2次補正予算「探究的な学び関連サービス等利活用促進事業」についても言及。「学校の課題を把握する」ことの大切さと、その課題を把握するために教師コミュニティ(※2)に参加すること等、アーリーステージのイノベーターにとって、ヒントとなるような具体的な提案についてもご紹介いただきました。
- ※2
-
- 「STEAMライブラリー パートナーコミュニティ」
https://www.facebook.com/groups/steamlibrarycommunity/ - 「情報教育支援プラットフォーム ELDI(エルディ)」
https://eldi.sfc.keio.ac.jp/ - 「公益財団法人東京学校支援機構 TEPRO(ティープロ)」
https://www.tepro.or.jp/
- 「STEAMライブラリー パートナーコミュニティ」
3名のお話が一通り終わり、いよいよパネルディスカッションが始まりました。
先生や子どもたちの評価が実績につながる
最初に、お付き合いのあるEdTechイノベーターとの出会い方について教えてください。
山岸(以下敬称略) : 全てのサービスを確認することはできないため、EdTech導入補助金の際は、関心があったり、注目されている学習支援サービスやプログラミング学習をピックアップして選びました。新たなサービスを知る機会として、展示会等で情報収集をするのですが、そこからはなかなか次の一歩に進めません。“このサービスを”と決め打ちができないんですね。例えば、1人1台端末を導入した際は、プロポーザルにおいて一番高得点だった事業者様のソフトウェアを導入しました。もちろん、紹介という形でお付き合いが始まるケースもあります。

群馬県教育委員会事務局 総務課デジタル教育推進室 指導主事 山岸太郎氏
山本 : まずは実績のある方から紹介をいただくことが1つ。2つ目に、例えばトライアルのような形で、学校単体に試してみてからというケースもあります。そして3つ目は、困っていることに寄り添った提案をいただいた場合です。1人1台タブレット端末を導入した際、「こういうところにお困りではありませんか?」と提案をいただけて有り難かったという話も聞きました。
齋藤 : EdTechサービスについては、各教育委員会の担当者が都道府県をまたいで情報交換することもあります。昨年度、事業者から聞いた中には、進路指導部の先生同士の口コミで広がっていったツールもあったようです。
イノベーター側からすると、教育委員会等に対して突然の電話や訪問をしていいのか気になります。実際はどうなのでしょうか?
山岸 : 電話やメールはよくあります。時間があれば、極力話を聞くようにしています。連絡をいただくというのは、つながりを作る1つのきっかけになるからです。ただし、他の業務との兼ね合いもありますので、そのあたりをご配慮いただけるとありがたいです。
山本 : 私にも連絡はよくありますね。飛び込み営業ももちろんあります。その時点では名刺交換だけで終わったとしても、ちょっとした機会に「そういえば以前、……」となるケースもありました。連絡をいただく際は、国の予算についてなど最新情報を踏まえて提案いただけるとすごく有り難いです。自治体単位では持てない予算でも、補助金を使うことで導入のきっかけにつながるケースも考えられます。
学校の抱える課題をキャッチするのが重要
接点ができたとして、本格的に検討しようとする時の決め手は何ですか?
山岸 : その時の自治体が持つ課題感と提供しようとするサービスが繋がっていること。山本さんが仰ったように、今自治体が解決すべき課題に対し、「こういった解決策がありますよ」というような提案型だと、やはり聞いてみようかなとなります。
どうやって課題をキャッチすればいいのでしょうか?
齋藤 : 学校に聞いたところ、元々繋がりのない事業者との窓口になるのは、FAXや学校の代表メール、チラシなどを管理する教頭先生が多いとのことです。ある先生からは、事業者からメールやFAXでサービスを紹介いただく場合、「チラシなどの資料は、窓口の段階で誰が見ても、どの先生に渡せばいいのかをわかりやすく作成していただければリーチしやすくなる」とお聞きしました。
山岸 : 確かに、「誰に」という点は大事だと思います。多くのメールに埋もれてしまうので、担当(部署)がわかるように送っていただけたらと思います。
山本 : 本市にも様々な連絡が来ます。電話でのやりとりの中で「こう検索してみてください」など、一緒にサイト画面を見ながら説明していただいたりすると、その後の営業に繋がっていきやすいかもしれません。

埼玉県久喜市教育委員会教育部指導課 指導主事兼指導課付GIGAスクール推進室長 山本純氏
どんな情報にアクセスをすれば各自治体が抱える課題をつかみやすいでしょうか?
山岸 : 県や教育委員会のホームページやYouTubeなどを見ていただくのがよいと思います。他にも、先ほど国の予算の話がありましたが、自治体だけではなかなか予算が取れないところを、例えば「国が半分ほど負担します」となると、予算化に向けて一歩前進することがあります。おそらく企業の皆様は各省庁が出している予算要求資料をご覧になっていると思いますが、そういった情報はどの自治体にアプローチをすべきか検討する上で何かのヒントになるのではないでしょうか。
ロングスパンである認識が必要
学校にEdTechツールを導入する際、どういうプロセスで意思決定されるのか。大まかなプロセスをお聞かせください。
山岸 : 各担当が、それぞれ来年度の予算化に向けて動き出すのが、だいたい8月前後です。事業内容、予算規模などを各所属で検討し、それから課での協議、教育委員会内での協議、県予算を管理する部署との協議、副知事、知事との協議へと移ります、最終的には、2月から開催される県の議会で議決され、3月の中旬に予算化という流れになります。
山本 : 本市では6月ぐらいに、次年度の概算という形で、回答を求める文書が各課に届きます。そして夏以降、具体的な資料作成や数字固めをし、議会を経ていくというのが大まかな流れです。ただし、次年度に予算を組みたいと思っても、前年の6月ぐらいには、ほぼ枠が埋まっています。そのため、2年前から、2年先を見通して、市全体の基本教育計画など大きなスパンでのスケジュール感を持って進めていかなければなりません。もちろんそれだけでは対応できない事案もありますので、そのあたりは補正予算で対応していきます。
イノベーターの方が、どの時期に何をすればいいかアドバイスはありますか?
齋藤 : 予算編成の流れは自治体間で大きな違いはないと思います。経済産業省に出向して感じたことは、教育委員会と事業者とでは、スピード感が全然違うということでした。教育委員会としては、これからの教育について、長期的な視点で一緒に相談したいのに、事業者側はスピード重視でついていけないという話をよく聞きました。単年度、導入時だけでなく、2年、3年くらいじっくりと関わっていただく覚悟が必要ではないでしょうか。(自治体予算以外でEdTechを導入する場合)これまでのEdTech導入補助金の活用状況を見ますと、例えば高校では、教材費などを当てて、継続利用されているケースも多くあります。

経済産業省教育産業室係長 齋藤直樹氏
先生や学校に寄り添った提案を
補助金が切れた後、各学校でサービスを継続するためのポイントは何ですか?
山岸 : 「使ってよかった」など、現場での反応がよいサービスについては次につながります。あとは県で調達をする場合、基本的には県立高校全てに導入することになるので、普通高校、商業高校、工業高校、すべての学校にマッチしているかも判断材料です。齋藤さんのお話にもありましたがEdTech導入補助金を活用にした後に、教材費を使って引き続き(サービスを)使っている学校は実際にあります。
山本 : 子どもの成長につながっているか、学校現場がプラスになっているか、先生方の働き方にもつながっているか、そういったところが大きなポイントでしょう。
イノベーターへの要望はありますか?
山岸 : 教育委員会にないものは、企業の皆様の技術力です。教育をデジタル化で解決するためには、技術力はどうしても必要。教育の課題を、皆様の力を借りて解決ができればと考えています。あとは、レスポンスの早さ。企業と連携する際は、教育委員会内外での説明のためにいつまでにこの資料を作ってほしいという依頼をすることも頻繁にあります。そうした時に、早く対応していただけると有り難いです。
山本 : 自治体と事業者間の合意形成が図られてきた段階で、サービスの導入をいつ、どう進めていくかのロードマップをご提案いただけると助かります。例えばサービスの設定にどれくらい必要なのか、研修はどの程度の規模を考えているのか、何時間ぐらい、何回程かかるのかなど。また本市では現在、教育長の指導の下、不登校の子どもへの取り組みを進めています。不登校や、学校に行きたくても行けない子どもにどういったアプローチを示せるか、そういったところにも、ぜひご協力いただけたらと思います。
齋藤 : 教育DXと言われるようになって随分と学びが変わりました。端末をどのように活用していくか、どのようなアプリがあればいいのか、手法も含めて答えが必要とされています。また、世の中には多くのEdTechツールがあり、先生方はどれを選んでいいか迷われていると思います。信頼のできる企業かどうかという点についてどこで判断していますかと先生や教育委員会の方々に尋ねると、「引き出しの多さ」という答えが返ってきます。単にツールの紹介だけに終わらず、例えば、他の学校や地域の状況を把握していて、質問にもすぐに答えられることが大事です。あるいは、最新の教育情勢に詳しいなど。そういった方々からの紹介については、安心して「ではツールを使ってみよう」という気持ちになる。我々教育現場にいる人たちに寄り添っていただくような形でご提案をいただけると有り難いです。
今、教育の中でも特に注目している分野は何ですか?
山岸 : 「情報」が高校の必須科目となりましたが、専門の教員をすぐに採用することは難しいので、そこはデジタル化でカバーする必要があります。こうした分野には注目しています。
山本 : 自治体単位ですと、データ活用というところにアプローチをかけたくても、なかなか難しい部分があります。そういった分野のツールを提案いただきたいです。また、プログラミング教育が小学校の必修科目となりました。では、中学校、高校へとつなげていくのにどういったツールがいいのか。中学校の先生は専門性があり、普段からこだわりのある教材を使っていらっしゃる方もいるので、そういう方へどうやってアプローチをしていけるか。今後の課題と考えています。
齋藤 : 新学習指導要領に基づいた児童生徒の資質・能力の育成に向けて、これまで以上に情報教育の充実が必要となっています。先生の役割自体、これまでとやるべきことは大きくは変わりません。ただ、先生の役割の変化の1つとして、経済産業省で実施する「未来の教室」の実証事業の中でも言われているのが、「ティーチングからコーチングへ」です。他にも教育現場は大きく変化しており、先生方の戸惑いも多くあるので、そのあたりを企業の方も、一緒になって考えていただければと思います。

視聴者からの質問に応対
学校関係者から、EdTech導入補助金を活用して導入したEdTechツールを引き続き利用したいが、補助金なしでの継続利用が難しい。継続するにはどのような方法がありますか? という視聴者からの質問も来ています。
山岸 : 群馬県の場合、先に述べたように高校の教材費として、学校が徴収したお金のなかで次年度使っていくという事例がありました。
山本 : 自治体単独での予算化が難しいという場合、集金といった形でご家庭での負担も発生する懸念があります。ただ、強制的にこのような形式をとることはできないので、ツールの継続利用については校長先生の判断になるかと考えています。
齋藤 : 難しい課題です。教材費などと同様に実際に利用される方々に負担してもらう形でご理解いただく場合もあります。一方で、補助金を活用し、その後も継続利用した例を挙げると、例えば、公立の小・中学校だと学校単位ではそういうことを決められないという思い込みがありますが、地域によっては、教材費のようなものを集め、そこから充当していた小学校もあります。
営業ルートに関しての質問です。教育委員会、EdTech事業に協力してくれる民間事業者、経済産業省、いずれのルートで営業するのがいいでしょうか?
齋藤 : まずは現場の先生方に使っていただく必要があると思います。では、どうやって先生にアプローチするのか。例えば、いろいろな教員コミュニティに入っていただくことが重要です。営業という形は抜きにして、1人の同じ教育関係者として、これからの教育をどうしていくかという観点で先生方との関係を構築していただく。そこから、営業やサービスの提案をする流れになっていくことも一つあるのかなと。
ありがとうございました。では、最後に一言ずつお願いします。
山岸 : もし群馬県の発展のためにご協力いただける企業の方がいらっしゃったら、私のメールアドレス、または代表番号までご連絡ください。
山本 : 今、大きく教育が動いています。そういった歴史的な転換期での様々な課題について、ご協力いただけるご提案をお待ちしています。
齋藤 : 昨年度のEdTech導入補助金で企業の方々にお願いしていたことの1つは、学校に対し、サポート体制をしっかり構築してほしいということでした。ぜひ、学校の状況や現場の先生方を知っていただき、アプローチしてください。よりよい教育のために一緒に頑張っていきましょう。
ミートアップイベントも開催
パネルディスカッションが終了すると、会場ではミートアップイベントが約1時間半開催されました。人脈を広げるチャンスとあって、会場のいたるところで名刺交換や談笑するシーンが見られました。その一方、パネリストである群馬県教育委員会の山岸氏と長い時間話し込む参加者も。参加者にどんな話をしていたのか伺ってみると――。
「弊社の事業内容と群馬県の取り組みが似ていたので、まずその話を詳しく伺いました。次に伺ったのが、我々も課題に関わっていることなのですが、データを現場の先生はどう活かしているのか、データから子どもたちへのリアルなアプローチにどう繋げているのか、などです。山岸さんによると、“先生の声掛けや褒める機会が増えた”そうです」

ミートアップイベントの様子
最後に、今回のイベントの感想を参加者の皆さんに伺ったところ、「普段なかなか聞けない教育委員会の本音をイノベーター目線で話していただき、今後の活動の指針になりました」「営業の掛け方の参考になりました。諦めずに連絡をくださいとの言葉も、無碍にされていないとわかってよかったです」「時間をかけながら、一つひとつプロセスを踏んでいく部分で体力が必要だという課題を感じました」など、参考になったという声が多数聞かれました。
登壇者紹介
-

-
山岸太郎氏
群馬県教育委員会事務局 総務課
デジタル教育推進室 指導主事
-

-
山本純氏
埼玉県久喜市教育委員会教育部指導課
指導主事兼指導課付GIGAスクール推進室長
-

-
齋藤直樹氏
経済産業省教育産業室 係長
(三重県教育委員会からの出向)
最終更新日:2023年3月15日