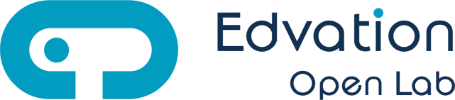- ホーム
- 次代のEdTechイノベーター支援プログラム(Edvation Open Lab:EOL)
- 採択企業12社が集結。EdTechイノベーターが思い描く新たな教育のカタチ~Edvation Open Lab 2022ピッチイベントレポート
採択企業12社が集結。EdTechイノベーターが思い描く新たな教育のカタチ~Edvation Open Lab 2022ピッチイベントレポート
2023年2月27日
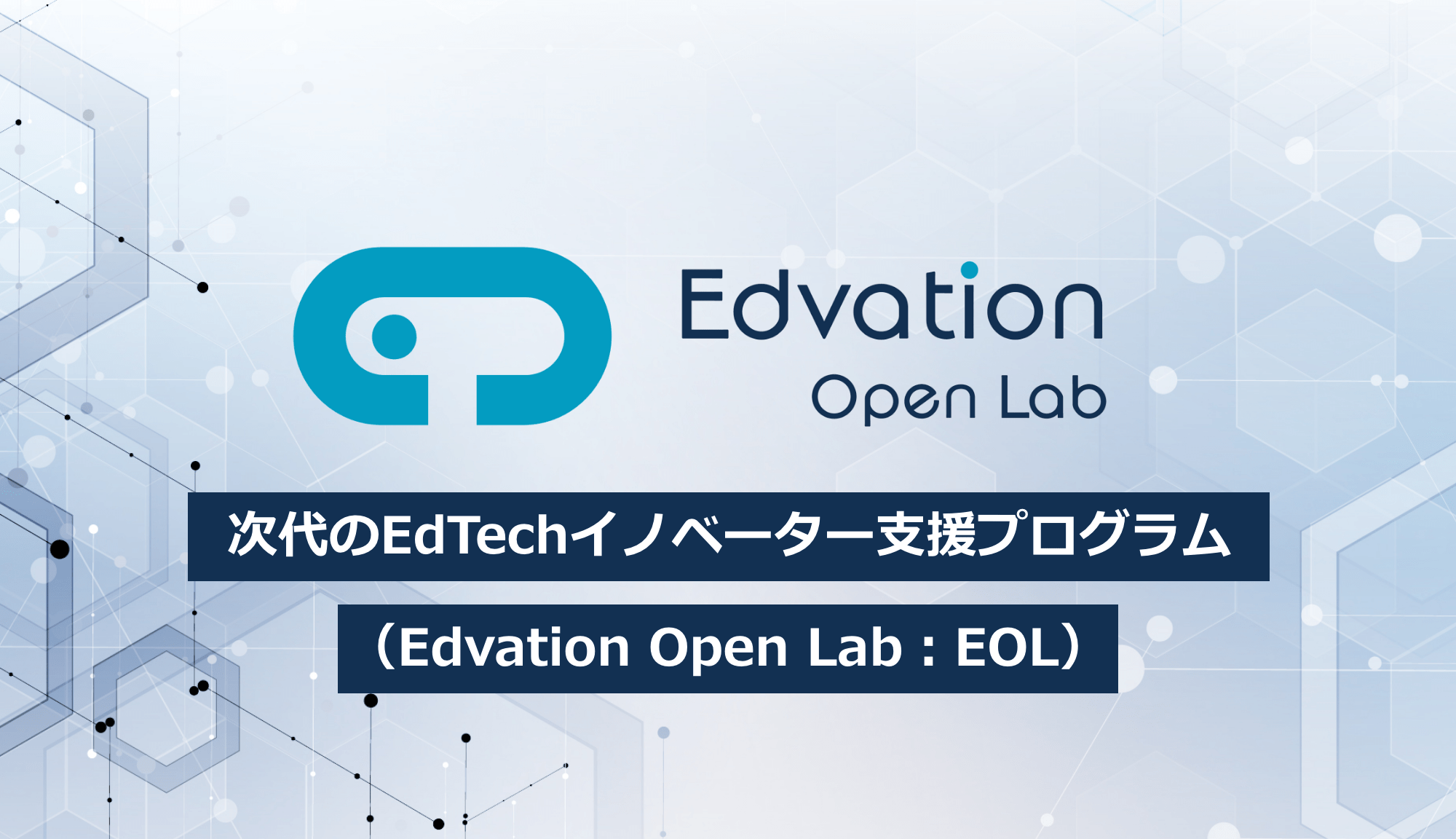
2023年2月27日(月)、BASE Q(東京都千代田区)にて「Edvation Open Lab 2022 ピッチイベント」が開催されました。EdTechイノベーター支援プログラム「Edvation Open Lab(通称:EOL)」の集大成である今回のイベントでは、採択企業12社がピッチを行いました。当日の模様と、採択企業12社のピッチを簡単にご紹介します。
目次
- 【開会挨拶】関心を持った参加者とイノベーターをマッチング/経済産業省 商務・サービスグループ サービス政策課 教育産業室長 五十棲浩二
- 注目されるリスキリング市場で展開/株式会社Arts Japan
- 強みを活かして金融教育サービスを展開/株式会社サークルエデュ
- ターゲットの本命は社会人/株式会社Herazika
- 子どもたちの作品に楽しさをプラスして記録/SHOWCASE株式会社
- 体育授業こそICTの活用が必須/株式会社SPLYZA
- 留学体験を誰にでも手軽に提供/HelloWorld株式会社
- 奨学金により諦めなくていい社会を実現/株式会社ガクシー
- 大学名簿が統合されたデータベースの構築/株式会社Alumnote
- 手を差し伸べ合える社会を創りたい/スタンドバイ株式会社
- 教育と医療を繋ぎ社会を創造する/株式会社Welcome to talk
- 子どもに多様な体験の機会を提供/株式会社meepa
- 次世代の子どもたちの未来を育む/オンライン読み聞かせYOMY!
- 【総評】ターゲットとカスタマーを明確に/鎌倉市教育委員会 岩岡寛人教育長
- 【総評】興味あるアイデアと情熱、信頼が大事/さいたま市教育委員会 細田眞由美教育長
- 【総評】EdTech業界発展のための3つのお願い/コアアドバイザー 佐藤昌宏氏
関心を持った参加者とイノベーターをマッチング
開会挨拶として、経済産業省 商務・サービスグループ サービス政策課 教育産業室長の五十棲浩二氏最初に登壇しました。「本日のイベント自体はプレゼン形式ですが、当然、これがゴールではあるはずがなく、起業家の皆様にとっては本当に小さな通過点だと思っています」と話した後にピッチイベントの進め方について説明。ピッチに対する反響や、採択企業が教育分野の事業者・関係者との関係性を築けることへの期待についてお話しました。

経済産業省 商務・サービスグループ サービス政策課 教育産業室 五十棲浩二氏
今回は、サービス導入や投資、事業提携などのマッチングを促すために、オンラインツール「Slido」を使用して、参加者からのリアルタイムでの投稿を実施。会場参加者およびオンラインでの参加者は、関心を持ったピッチに対して、応援コメントを投稿したり、関心度合いを選択肢の中から選んで投票できます。採択企業には、後日、投稿いただいた方の連絡先を共有。新たなビジネスチャンスの可能性が高まるというわけです。
事務局によるプログラムの説明や、メンター、ゲストサポーターの方々の紹介の後、採択企業12社のピッチがスタートしました。
注目されるリスキリング市場で展開/株式会社Arts Japan

株式会社Arts Japan CEO 久世琢真氏
オンラインの学習環境を誰でも簡単に開発できる教育事業者向けのクラウドサービス「Revot」(レボット)を提供する株式会社Arts Japan。資格取得やプログラミング、語学学習など、リスキリングが注目される中で「社会人をエンドユーザーとする教育事業者様にサービスを導入していただいているのが特徴です」と話します。リスキリングは5年で1兆円の国家予算が決議されるなど、非常に注目されている分野の1つ。リスキリングを通じて自分の可能性を模索したり、視野を広げる手段と考える社会人が多く、特に時間と場所に縛られないオンライン学習のニーズが拡大しています。「来年には多言語対応のアップデートを行い、グローバル展開を計画しています」と展望も語りました。
メンター/ゲストサポーターからのコメント
「リスキリングのマーケット自体は伸びていく領域と考えています。その中でも、いかに効率よくコンテンツを提供できるかが課題となっている中小の教育コンテンツ提供事業者にとって、Arts Japan様のサービスは有意義なものになると思います。また、学ぶ側からしても、いかにモチベーションを維持して長く学習を継続できるかがカギになるので、サービスがきちんとしていることで、学ぶ側にとっても意義のある授業になってくると思います」
強みを活かして金融教育サービスを展開/株式会社サークルエデュ

株式会社サークルエデュ 代表取締役 高野大希氏
EOLに採択されたのを機にピボットを行うという株式会社サークルエデュは、公認会計士でもある高野氏を含め、コアメンバー全員が金融畑出身なのが強み。「我々の知見を活かして新たに展開するのは、子ども向けの金融教育です。2022年から教育指導要領に基づき、高校生の金融教育がカリキュラムに。また、昨夏、保護者向けにアンケートを実施したところ、7割の保護者が金融教育の必要性を感じているなど、金融教育のニーズが高まっています」と手ごたえを実感したそうです。ピッチでは、今後展開予定のオンラインとオフラインをミックスしたパッケージサービスの内容、マネタイズについてのほか、子どもや家庭への効果、長期展望として保護者に向けた金融行動の促進の話にまで言及しました。
メンター/ゲストサポーターからのコメント
「着目したフィールドに可能性を感じます。金融教育は学校ではなかなか扱い難い領域だと思いますが、やはり生活していく上ではすごく大切なことです。私の子どもも先日、キッザニアに行ってお仕事体験をしました。仕事をしてお金をもらうことに喜びを感じていたようです。子どもたちが金融の話題を家で気軽にできたら楽しいし、保護者の方の投資にまで広がれば面白いと思います。期待しています」
ターゲットの本命は社会人/株式会社Herazika

株式会社Herazika 代表取締役 森山大地氏
「水物のやる気に頼る必要のない、最適な学習環境を提供する」という志の下で事業展開をする株式会社Herazikaは、自習室を自宅に再現するオンライン自習室『ヤルッキャ!』を展開し、すでに多くのVCからの投資を受けています。ピッチでは、人間の“やる気”についてレクチャーした後、どういったシステムで子どもに自習室、つまり勉強時間を習慣化させるか、サービス内容を具体的に紹介。リアルな友達とのつながりを作ることで、図書館前で待ち合わせて一緒に勉強を開始するような感覚を再現しているそうです。学習中の様子を録画し親に送付、見えているようで見えていない子どもの努力部分を可視化することで親子関係の良好化もはかっています。また今後の展開について「初期ターゲットは小学校3~6年生の通塾生ですが、本丸は社会人の学習指導。BtoBへの拡充も予定しています」と意気込みを語りました。
メンター/ゲストサポーターからのコメント
「UX(サービスを通して得られる体験)を通して、月次チャーン(サービスの解約率)が8%と低いという事実は、このプロダクトがしっかりと作られていることの証明であり、何よりも説得力がありました。使うと良さがわかるということは、使おうとするまでのマーケットメッセージをどう打ち出していくかがポイントだと思います。事例と効果のデータを活用していけば、このプロダクトはさらに加速していくと感じました」
子どもたちの作品に楽しさをプラスして記録/SHOWCASE株式会社

SHOWCASE株式会社 代表取締役 貝塚高士氏
「取り扱うテーマは子どもたちが作る作品です」と話すのは、SHOWCASE株式会社の貝塚氏。同社は、子どもが作った作品(工作)や描いた絵を撮影して保存、それをQRコード付きのアートワークカードにする成長記録サービス「FUN+」を展開しています。「QRコードを読み込むと、子どもの作品がARによって現実世界に飛び出してきます。記録自体は単調でつまらない作業ですが、そこに“楽しさ”を加えてあげることで、子どもは興奮し、楽しさを感じ、また作りたいと思います。こうしたプラスの循環を生むことで、子どもは追体験ができ、共通言語化によりコミュニケーションも取りやすくなるのです」と効果を説明。さらに保護者には子どもの成長記録になる点、学校ではテストでは測れない部分の記録により、子どもの能力やスキル、声を拾い上げることができるとアピールしました。
メンター/ゲストサポーターからのコメント
「テストの点数以上に、子どもたちのクリエイティビティが評価される学校にしたいと思っています。それをどう展開していこうかと考える中で、ポートフォリオ的に子どもたちの作品が蓄積され、それを楽しく簡単に活用できる仕組みは、とても魅力的に感じました。学校では子どもたちにiPadを支給し、写真で記録を残すことは行っていますが、おっしゃる通りなかなか継続できません。そこにワクワクをプラスさせたのが肝だと思いました」
体育授業こそICTの活用が必須/株式会社SPLYZA

株式会社SPLYZA セールス 成田勝彦氏
株式会社SPLYZAが提供するサービスは「スポーツを通じた探究学習」。運動中に発見した課題やその解決策を映像上に書き込み、主体的・対話的で深い学びを実現する、映像振り返りツール「SPLYZA Teams」と、定量的なデータが算出されることで手軽にスポーツサイエンスに触れられるツール「SPLYZA Motion」を展開しています。ピッチでは、体育授業の目的と課題について詳しく解説、「今後、社会で必要とされる“問題発見力”や“的確な予測力”とった力は、体育現場、スポーツ現場でこそ身に着けることができると考えています」と語りました。体育授業こそICTの活用が必須という考え方、そして同社のツールを活用したある自治体では、コンピテンシー(特に課題設定や創造性、論理的思考、疑う力、主体性など)の向上につながったという話にも触れました。
メンター/ゲストサポーターからのコメント
「これまでの体育の授業は “マットの上にポンッと手をつきましょう”など、感覚的な指導が中心でした。これが、GIGAスクール構想により学校現場に端末が入ったことで、体育の授業も次のフェーズに移りました。子どもたちが自分たちの演技や動作を撮って、それを見比べながら違いなどを言語化していますが、動画を何回観ても、わからないことも多いのです。そんな課題をこのツールが解決してくれると感じました」
留学体験を誰にでも手軽に提供/HelloWorld株式会社

HelloWorld株式会社 COO 今野達眞氏
「突然ですが、皆さんはどの程度英語を話すことができるでしょうか?」。冒頭こう問いかけてスタートしたHelloWorld株式会社のピッチ。同社は同世代の世界中の子ども(教室)をオンラインで繋ぐ「WorldClassroom」と、地域に住む外国人の家庭にホームステイできる「まちなか留学」を展開しています。問いかけの後、カナダへ留学をした今野氏の実体験を題材に、以前から言われている日本の英語教育の課題に言及。「留学体験を誰にでも提供したい」という事業への想いも語りました。途中で中学校の英語教員のインタビューが流れ、「ある生徒がもう一度あの人と英語で話したいと。英語を勉強する上で一番大切な気持ちに気付いてくれたんです」と、「WorldClassroom」の成果を参加者と共有。海外展開も視野に入れているという話で締めました。
メンター/ゲストサポーターからのコメント
「日本の英語教育が抱えている英語の勉強=受験の勉強という課題感は、多くの日本人が共感できる部分です。英語に関する様々な手立て、サービスがあるにも関わらず、いまだに社会課題として解決していないということは、入り込む余地がまだまだあるということ。子どもたちの“英語を話したい”という想いを実現しようとしていること自体が素晴らしいことですし、公教育分野に変革をもたらす気持ちでぜひチャレンジしてください」
奨学金により諦めなくていい社会を実現/株式会社ガクシー

株式会社ガクシー 代表取締役 松原良輔氏
奨学金市場という領域に踏み込み事業展開をする株式会社ガクシー。約16.4兆円と言われる日本の教育費の中で、奨学金は8%しか支給されていない現状を、海外と比較することで指摘。課題感を浮き彫りにした上で「諦めなくていい社会の実現を目指し、若者や日本に対してインパクトを起こしたい」と意気込みを語りました。同社が展開するのは、「ガクシー」という奨学金情報サイトと、SaaS型奨学金業務管理システム「ガクシーAgent」。奨学金を必要とする人と、支給する側の両方にアプローチしています。「日本の奨学金市場には、情報の非対称性とアナログな運営体制という2つの課題があります。まずはサイトという形で情報を集約し、運営面は管理システムを構築。この2つを合わせて奨学金のプラットフォームができればと考えています」と、現状やマネタイズ、将来の展望についても語りました。
メンター/ゲストサポーターからのコメント
「教育費が不十分で、希望する教育を受けられないなど、自分の選択肢を狭めてしまっている人に対して非常に魅力的な活動だと思いました。情報をリーチできない課題感はまだありますが、高校生がよくアクセスする媒体と連携したり、学校経由でアプローチしていくことも有効ではないでしょうか。また、奨学金を使って大学に行く人は目的意識が高い方だと思います。その人たちが大学生活で培ったスキルを活かして成功したら、それを奨学金に還元してもらうという、いいループができるのではないかと思いました」
大学名簿が統合されたデータベースの構築/株式会社Alumnote

株式会社Alumnote 代表取締役 中沢冬芽氏
東京大学在学中に中沢氏が設立した株式会社Alumnoteは、大学・同窓会組織を対象にした名簿・寄付金・会費の管理ソフトウエアの提供と、寄付金を集めるためのチャリティーイベントの開催を行っています。ピッチでは、「様々な数字が軒並み下がっている中で、減っていくパイをどう取り合うかという現状から脱却したいという想いがありました。大学や教育機関のビジネスモデルに課題を感じ、例えばアメリカなどのように、プールした寄付金を金融市場で運用できないかとも考えています」と、現状と課題、その解決策について言及。同社のサービスにより、複数の部局を跨いで統合されたデータベースの構築が可能であったり、決済情報と名簿情報が結びつく構造について説明しました。また、3年間での実績と本年度の目標についても言及しました。
メンター/ゲストサポーターからのコメント
「課題の大きさはよく理解しています。だからこそ、すごく政策的なテーマに取り組まれていると感じました。今後は、寄付の部分を契機に、大学が持ついろいろな側面にチャレンジいただきたいです。寄付文化の根付いていない日本では、寄付を集めるのは難しいと言われていますが、ビジネスモデルを確立して、ぜひ大学を元気にしてください」
手を差し伸べ合える社会を創りたい/スタンドバイ株式会社

スタンドバイ株式会社 代表取締役 谷山大三郎氏
代表の谷山氏自身がいじめ被害者だった経験から、いじめ防止をテーマに事業を展開するスタンドバイ株式会社。同社のサービスは大きく3つ。自社で開発した「いじめ防止授業」を学校で実施すること、健康観察やアンケートにより子どもの予兆に気付けるWEBアプリ「シャボテンログ」の提供、そしていつでも報告や相談ができるプラットフォーム「STANDBY」の運営です。ピッチでは「自分にも他人にも手を差し伸べ合える社会を創りたい」と切実な願いを語る一方で、「7歳と11歳の時にいじめにあっていた子どもが、45歳の時点で自殺傾向やうつ病、不安障害の診断を持つ傾向が高かったなどのデータがあります」と悪影響についても言及。現在、27自治体、1072校、27万3288人の児童生徒が同社のサービスを利用しているそうですが、いじめ抑止を示す具体的なデータを提示することで、ピッチの説得力をさらに高めていました。
メンター/ゲストサポーターからのコメント
「本プログラムを通じて、より人に訴えかける凄味が増している感じがしました。発表者の訴える力が強いと何か協力したいと心が動かされます。今後は、学習進捗アプリやICT関係のドリルと連携するといいのではないかと感じました。また、自治体や学校にはすでに参画しているようですが、その辺りの整理とアピールができれば、さらに広がると思います」
教育と医療を繋ぎ社会を創造する/株式会社Welcome to talk

株式会社Welcome to talk 代表取締役社長/医師・医学博士 関﨑亮氏
「おとなでも言えないこと、こどもはもっと言えない。ココロの会話をもっと身近に」。そんな語りかけからピッチをスタートさせたのは、医師でもある関﨑氏。彼が社長を務める株式会社Welcome to talkは、ICTを活用した国内初の学校向けメンタルヘルスケアサービスを提供しています。まずは、10代後半までに精神疾患を発病する割合や、子どもの自殺率など、シビアなデータを示しながら、学校の対応を含め、子どものメンタルヘルスケアの課題を丁寧に説明。その対応策としてICTを駆使したメンタルヘルスサービスの必要性を説くとともに、ただカウンセリングをするだけでなく、多角的なアプローチにより学校やスクールカウンセラーのサポートを行うと話しました。最後は実績と今後の展開について。「教育と医療を繋ぎ社会を創造する」と新たな市場価値について語りました。
メンター/ゲストサポーターからのコメント
「子どもたちにとっての心のケアに関しては、これからもっと重要なテーマになってくると見ています。中でも小学生にとっては、自分自身で心の不調を認めるのも難しく、不調だと自認しても正しくそれを捉えられているかどうかは疑問があります。心のケアのプラットフォームを作りたいという関﨑さんの想いも伝わりましたし、セーフティネットの考えからも非常に重要なプロダクトだと考えます」
子どもに多様な体験の機会を提供/株式会社meepa

株式会社meepa 代表取締役CEO 山中健太郎氏
「子どもが本当の好きに出合う」をコンセプトに、地元の様々な習い事の先生を幼稚園、保育園、学童へ派遣し、子どもたちに多様な体験機会を提供する株式会社meepaの山中氏。最初は失敗談から話し始めました。「子どもが本当の好きに出合うためのキーポイントは多様な体験」という部分にブレはなかったものの、当初は子どもの多様な体験を阻む原因が保護者にあると考え、保護者の行動変容を促そうとしたそうです。しかし事業として成立せず、EOLの採択を機に、対象を幼稚園、保育園、学童に方向転換。その背景には、園が抱える課題、例えば差別化や保育サービス供給力の確保などがあったと語りました。その後は時間をかけてサービス内容を具体的に解説し、期待できる効果や展望について言及しました。
メンター/ゲストサポーターからのコメント
「山中さんの経営方針のお話を聞いていて、誠実さが伝わってきました。この業界に対する強い想いも感じられましたし、『子どもたちの生活に飛び込みたい』と、子ども視点に変わっていくその発想から事業化していく点も素晴らしいです。これからは園も、運営面で外部の力が入るのは大事なことです。その点でも意義があるし、需要もあると思います」
次世代の子どもたちの未来を育む/オンライン読み聞かせYOMY!

オンライン読み聞かせYOMY! CEO 安田莉子氏
次世代の子どもたちの未来を育むオンライン読み聞かせを展開する、オンライン読み聞かせYOMY!。忙しくてなかなか子どもたちに構ってあげられない子育て世代の日常の様子を流すなど、共感を呼ぶシーンを織り交ぜながら、子育てに関する課題とサービスの意義を説きました。「いつの時代でも最高の教材である絵本の読み聞かせと、子どもの成長に欠かせないコミュニケーションを掛け合わせた、まったく新しいサービスです」と謳い、実際の映像を流しながら、わかりやすく具体的に解説。映像では子どもが随時、登場するため、微笑ましい雰囲気も。持ち時間が短いながらも、アメリカの新しい読み聞かせ方法「ダイアロジック・リーディング」を土台とした独自メソッドの開発について、読み手の紹介、実績、オリジナル絵本の制作、ビジネスプラン、企業理念が一通り語られました。
メンター/ゲストサポーターからのコメント
「保護者が多忙で読み聞かせをしてもらえない環境の子どもに届けられる、とても温かいシステムだと感じました。また事業のスピード感も伝わってきました。キーワードでもある“読書”の大事なところは、習慣化です。この習慣化を効率的に身に付けることができる部分がポイントになっていて、そのあたりもうまく繋げられていると思いました。今後は子育て世代だけでなく、いろいろな教育機関とも連携して事業を拡大してください。」
ターゲットとカスタマーを明確に
以上でおよそ2時間に及んだ採択企業12社のピッチが終了。多くの参加者からの投票や応援コメントが届き、関心の高さがうかがえました。この後、総評に移ります。最初に登壇したのは、鎌倉市教育委員会・教育長の岩岡寛人氏です。サービスを検討する際のポイントとして、課題設定(現実と理想のギャップ)が適切か、課題に対する打ち手が適切かどうか、GoogleやMicrosoftなど既存のサービスと代替できないかどうか、そしてターゲットとカスタマーが明確化されているかどうかという点を挙げました。特にターゲットとカスタマーについて以下のように詳しく述べています。
「ターゲットとカスタマーは一緒じゃないかと思われる方が多いと思いますが、教育業界の不思議な点は、ターゲットとカスタマーが違うケースがあることです。皆様は原体験からくる熱い想いで、子どもたちのためにこのサービスを届けたいとプロダクトを作るのですが、子どもたちはお金を出せないので、カスタマーは別になります。それが学校や教育委員会、あるいは保護者だったりするわけです。子どものために良いサービスを提供しても、それがカスタマーの課題解決に繋がっていなければ、導入していただけませんし、マネタイズができない結果に陥ります。特に公教育の分野では、カスタマーが学校ですらないケースがあります。学校の裁量で使える予算が少なく、教育委員会もお金を配分する権限を持っていません。市長の判断になるケースもあります。そのためカスタマーが誰なのかをきちんと分析し、カスタマーに合わせて丁寧に説明をする事業者が伸びていくのだと思います」

鎌倉市教育委員会 教育長 岩岡寛人氏
興味あるアイデアと情熱、信頼が大事
続いて登壇したのは、さいたま市教育委員会・教育長の細田眞由美氏。ピッチを終えたばかりの採択企業12社を称えたほか、メンターとゲストサポーターの感想やアドバイスの適切さについても触れました。そして、ご自身も実際に行かれたシリコンバレーでの様子を事例として紹介しながら、採択企業12社にエールを送りました。
「2023年1月22日から30日まで、イノベーションプログラムとして、さいたま市の高校生10名と一緒にアメリカのシリコンバレーに行ってまいりました。今回のメインイベントは、高校生10人が、シリコンバレーの投資家たちに実際にプレゼンすること。プレゼンをした際、素晴らしいコメントをたくさんいただきました。例えば、“いいアイデアは量が勝負だ。とにかく、失敗しろ、失敗しろ、失敗しろ”、“失敗は次に進むためのステップだ”と。あのイーロン・マスク氏も、何回も何回もPlug and Play(※1)でのピッチで失敗したそうです。また、“ワイルドなアイデアを作っていくことが大切”“ゴールがちゃんと見えるようにして共有できるように可視化することが大事”というコメントも。そして最後にいただいた言葉は、“それはサービスの受け手が興味を持てるアイデアなのか、起業家に情熱はあるか、起業家は信頼できる人なのか”と、身に沁みるものでした。今日、皆様のピッチを拝見し、まさに、興味があるアイデアであり、情熱があって信頼できる皆様方だと強く実感しました」
※1 Plug and Play:世界最大級のアクセラレーター/VCであり、シリコンバレーのスタートアップ支援組織。

さいたま市教育委員会 教育長 細田眞由美氏
EdTech業界発展のための3つのお願い
最後に、デジタルハリウッド大学大学院 教授・学長補佐、一般社団法人教育イノベーション協議会 代表理事の佐藤昌宏氏による総評です。
「非常に感慨深く全てのピッチを拝聴させていただきました。総評ということで、3つのお願いをさせていただきます。1つ目が、教育関係者及び視聴していただいている皆様へのお願い。イノベーターは宝です。教育に関してはほとんどの方が素人ではありますが、素人の方がピュアに自分の課題意識を持って、自分のソリューションで解決しようとする姿勢があります。今日は時間の関係上、ピッチの内容が商品やサービスにフォーカスされることが多かったのですが、なぜこのサービスを立ち上げたのかという想いをぜひ聞いてあげてください。彼らの根底がイノベーションの源泉であり、とても重要だと思っています。そこにプロの皆様のお知恵をプラスしていただければ、さらに教育は大きく変わると思います。
2つ目は教育イノベーターの皆様へ。教育は難しい、儲からないと散々言われている中、この領域を何とか改善、解決しようという想いを持って挑戦いただいていると思います。岩岡教育長もおっしゃっていましたが、教育領域はちょっとした作法(常識)を勉強すれば難しくありません。そして確かにマネタイズは難しいですが、民間の教育市場は約3兆円と言われています。公教育に関する予算の約10倍です。今後、テクノロジーをどう使っていくかというところにチャンスはあると思いますので、ぜひ挑戦し続けてください。
私も教育イノベーター向けイベントを開催していますが、今回は経済産業省主催であり、国がイノベーターの想いを多くの人に届ける機会は影響力も非常に大きいと思っています。最後に3つ目のお願いになるのですが、こういう機会を今後も継続して作っていただきたいと思います」

デジタルハリウッド大学大学院 教授・学長補佐、一般社団法人教育イノベーション協議会 代表理事 佐藤昌宏氏
ピッチイベント終了後は、ミートアップイベントを開催。会場内の各所で登壇者を囲んで会話の輪ができていました。今回で最後となったEOLのイベント。採択企業にEOLに参加したことで得たものは何かを伺ったところ、「普通ではお会いができない方たちと関係を作れたことが一番の収穫でした。また、メンターの方たちからいただいたアドバイスも的確で本当に参考になりました」という意見が大半を占めていました。

ミートアップの様子。採択者はいろいろな方に声を掛けていた
盛り上がりを見せていたミートアップイベントも閉幕の時間となりました。今回のピッチイベントで、EdTechイノベーター支援プログラム「Edvation Open Lab」は全て終了です。数か月にわたり同プログラムに参加した採択者の方々は、「人脈を広げることができた」「発想の転換ができた」「知見を広げられた」など、予想以上の収穫があったと口を揃えて言っていました。最後の採択者全員による記念撮影では、充実感をたたえた表情が印象的でした。

最終更新日:2023年3月30日