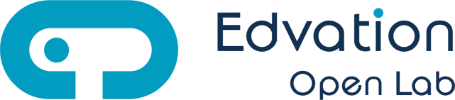- ホーム
- 次代のEdTechイノベーター支援プログラム(Edvation Open Lab:EOL)
- 起業家・杉浦太一氏インタビュー 先輩起業家が語る事業展開における工夫と今後の展望

2023年2月3日
杉浦太一氏
Inspire High, Inc. 代表取締役/CINRA, Inc. 代表取締役
台湾デジタル大臣のオードリー・タンさんやタレントの渡辺直美さん、タイのゲイのパフォーマーにイスラエルの元兵士ほか、普通なら出会えないような世界中の人たちと10代がオンラインでセッション出来る「Inspire High」。このサービスを展開する株式会社Inspire Highの創業者である杉浦太一氏は、学生時代にCINRAという組織を作り、2006年に株式会社化。「CINRA.NET」「HereNow」等の自社メディアを運営するほか、官公庁や地方自治体、企業のブランディング、デジタルマーケティングを展開してきました。実は杉浦氏、CINRA創業時から教育事業への参入を検討しており、2020年1月に満を持して「Inspire High」を立ち上げたと言います。今回は、教育事業への想いや「Inspire High」の立ち上げから事業を展開する上での工夫や苦労など、ここでしか聞くことのできない話を伺いました。

平和への想いが教育事業を手掛ける原点
CINRAを創業した学生時代から教育事業を手掛けたいと思っていたそうですが、きっかけは何だったのでしょうか?
杉浦(以下敬称略):自分が追い求めるものをどうすれば実現出来るかと考えた結果が、教育でした。話は10代の頃に遡りますが、その頃「どうして人は争うのか」「なぜ戦争は終わらないのか」と考えたりする一方で、「大切な人が目の前で傷つけられたら、傷つけた人を自分が傷つけないとは言い切れない」等、平和を求めるのに矛盾を感じる自分がいて。それで、どうして争いが起こるのかを考えた時、相手のことをもっと知っていたら争いや分断は起こらないのではと思いました。結局、争う原因は他者に対する想像力の欠如であって、もっと想像力や好奇心を持って相手と繋がることができたら、たとえ感情的になったとしても、違う結果になるのではないかと。
でも、他者を知る行為は、普段の生活ではなかなか出来ません。YouTubeやInstagram等、世界中と繋がることが出来るツールはありますが、レコメンデーションの機能から自分に関心のあるコンテンツが常に表示されてしまうので、自分の関心があるものにしか出会えません。そういう意味で、教育の場というのは、自分が求めていない情報とも出会える、他者を知るチャンスに溢れている場だと感じていました。
また、高校時代の教育実習の先生との出会いも、教育領域を手掛けることになったきっかけの1つです。私は音楽を仕事にしたくて、音楽関係の専門学校へ行くつもりでした。進路について教育実習の先生に話したところ、「別に音楽の世界は逃げないから、大学に行って4年間という時間の中でいろいろな人と会って経験を積んだ方がいいのでは」とアドバイスを頂きました。親でも先生でもない、ある意味、自分の人生とあまり関わりのない大人から言われたことで、「そういう考え方もあるのか」と視野が広がりました。「誰のどんな一言が自分の人生を動かしていくかなんて誰にもわからない」という原体験が、「Inspire High」をつくっていく上でも軸になっていると思います。
CINRA立ち上げから時間を置いて教育事業に参入したのはなぜでしょうか?
杉浦:2003年にCINRAを創業して、2006年に株式会社化しました。当時はインターネットビジネスでの起業が流行っていましたが、まだEdTechという言葉がない時代でしたし、正直、「教育=学校を作る」以外に思いつかなくて。とは言え、学校を作るにはお金がかかるし、現実的ではない。ゆくゆくは実現出来たらいいな、くらいの感じでした。教育とは無縁に思われがちなメディアを生業としたのは、メディアが、私の考える他者との出会いの場であり、知らないことを教えてくれる場だと思ったからです。メディアや広告の仕事をしながらも、「いつか教育事業をやりたい」と、周囲にはずっと言い続けていました。

画像:Inspire Highより提供
10代同士がフェアに学べる場
杉浦さんの考える教育が「Inspire High」に集約されていると思いますが、どういうサービスなのか教えてください。
杉浦:世界中の大人たちと10代が、探究的な問いを一緒に考え合うというサービスです。世の中には素晴らしい教育機会や魅力的な学校がたくさんありますが、経済的な事情や地理的な事情、保護者の考え方等、様々な要因によって、そういった学習機会へのアクセシビリティは限定されています。SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」で言えば、「質の高い教育」のはたくさん生まれていますが、「みんなに」の部分が置き去りになっている状況です。しかし、端末とインターネット環境さえあれば、全国津々浦々、多くの人たちに教育を届けられます。これまでは、「学校に通って知識を詰め込み、社会に適用できる人を大量生産する」ことが教育とされてきた部分も多いと思いますが、「Inspire High」は、主体性や好奇心を触発するような体験を、学校教育の場において、広く届けるために存在しています。
だからオンラインでの双方向の学びにもこだわったのですね。
杉浦:オンラインは、地域を越えて、より多くの10代にサービスを届けるための手段です。双方向の学びができるようにしたのは、単に「面白い話を聞いた」で終わるのではなく、自分の考えを言語化出来るようにするためです。「Inspire High」は、“すごい大人”の動画を観られるサービスと解釈されることがありますが、それは1つの側面でしかありません。多様な答えのない問いを10代が考え、アウトプットしたことに対して先生がその場で良し悪しを評価するのではなく、全国の10代がフィードバックし合う。それにより、自己肯定感や協調性を養っていく体験をオンライン上で実現しています。先生には学びの伴走者という立ち位置になって頂き、10代同士が答えのない問いに対して考えを出し合う。これが僕らの求める学びの形でした。

画像:Inspire Highより提供
世界中の学校を訪問してリサーチ
「Inspire High」というアイデアはどこで生まれたのでしょうか?
杉浦:教育の事業を具体的に始動しようと思ったのは2018年です。最初の1年半はリサーチに多くの時間を費やしました。フィンランド、デンマーク、イギリス、アメリカと、世界中の学校を実際に訪ね、21世紀に必要な学びを実践している方の話を聞き、“この人だ”と思ったらその場で口説いてアドバイザリーボード(※1)になって頂きました。国内でも、インタビューメディア「QONVERSATIONS」で、新事業のヒントになり得る事例や考え方を探っていきました。一通りリサーチが済んだ後、いくつか上がった事業アイデアの中から、現在の「Inspire High」の原型を決めました。
1年半ものリサーチで得た情報量は膨大だと思います。最終的に、現在のサービス内容に固めた決定打は何ですか?
杉浦:10代と彼らが知らない世界を繋げたいという想いはブレていなかったので、それをどう実現するか、Howの部分だけを検討しました。幸い我々には、CINRAによって構築されたコネクションがあり、20年近くデジタルコンテンツを作ってきた知見と人材がそろっていました。「やりたい」のWant、「出来る」のCan、「求められる」のNeed、この3つが交わる一番濃密なところでないと事業は出来ないので、そこを意識して事業モデルを詰めていきました。
※1 アドバイザリーボード:企業に対して専門的な知識・経験に基づく助言をする人材。
サービスの骨子が出来た後はどうしましたか?
杉浦:まずはプロトタイプをつくり、いろいろな方に協力いただいて、何度もテストしました。最初の頃の映像は、「これはYouTubeを見慣れている10代にとっては退屈かも」というものもあり、何度も何度も繰り返しました。インタビュー形式がいいのか、カメラを何台設置しようか、どんな撮り方だと学校に持ち込んでも生徒が飽きないかなど、ひたすら検証を行いました。高校生にサービスを試してもらうのはもちろん、我々の理念を伝えて、彼らがどう思うか、どんな言葉にすれば彼らが受け取りやすいか、そんなディスカッションも重ねていきました。

10代同士が積極的に意見を出し合うことも
始動するも半年でピボット(※2)
「Inspire High」のサービス開始が2020年でした
杉浦:元々、1月24日は国連総会で制定された「教育の国際デー」なので、2020年1月24日にサービスをリリースし、最初の配信は2月2日。クリエイティブディレクターの辻愛沙子さんにガイドをお願いしました。その後しばらく、個人向けのサブスクリプション事業として始めたのですが、通信トラブルやアプリケーション障害といった予期できないトラブルの連続でした。一方、コンテンツ自体は深くリサーチを続けてきた甲斐もあって、大きくブレておらず、「関心を示すような答えのない問いかけ→大人たちからのインプット→アウトプット→生徒同士のフィードバック→リフレクション」という流れで、現在もその構成は続いています。
※2 ピボット:事業内容やビジネスモデル等について方針転換すること。
杉浦さんも通信やアプリケーションの障害などのトラブルを経験したそうですが、スタートアップはサービスを提供した後、様々なトラブルに見舞われることも多いと思います。そんな時は、どう乗り越えたらいいのでしょうか?
杉浦:まだ自分は序の口だと思いますが、いわゆるハードシングスというやつですよね。目の前に困難がある時は、自分は何を目指したかったのか、ゴールを常に思い出すようにしています。原点に立ち戻ることで、大変なことも1つの通過点だと思えるようになります。また、自分を元気づけてくれる人の存在も大切です。少し無責任かもしれませんが、「大丈夫だよ」の一言は意外と心に沁みます。しんどい時は、現実的な解をくれる人より、精神的な面で元気をくれる人がありがたかったりしますね。
杉浦さんにもハードシングスはありましたか?
杉浦:学生時代に起業して20年近く経つので、ないはずはないです。「Inspire High」に関しては、立ち上げ後、目標としていたKPIが全く達成できなかったことがありました。当初は個人向けのサブスクリプション事業として始めたのですが、それが間違いでした。当たり前ですが、個人向けのサービスは主体的に何かを求める人だけが集まります。「欲しいから、買う」わけです。ただ、それでは我々の想いである「自分の知らない世界を知る」ことにはならないんです。限られたお小遣いの中から教育系のサービスにお金を出そうとしてくれる10代は、むしろ我々がいなくても、自分たちで人生を切り開ける人たちです。例えば、オードリー・タンさんの話を聞きたい10代って、もうすでにインスパイアされているというか、動き出す準備ができている人たちなわけです。触れ合っていると、「日本の未来は大丈夫だな」と思えてしまうほど、素晴らしい人たちです。一方で、真に「Inspire High」を必要とする10代は、自らアクションを起こそうとはまだしていない、いわば潜在的な所にいるのだと感じました。そうなった時に、やはり「学校」という場が我々の想いを最も実現出来る可能性がある場所だと。だから学校教育に「Inspire High」を届けたいと考えたのです。

台湾デジタル大臣のオードリー・タンさんがガイドを務めたセッション
BtoCからBtoBに切り替えたのは2020年8月。オードリー・タンさんのセッションを予定した時、全国の学校から問い合わせや生徒を参加させたいという連絡が来ました。そんな先生方の言葉がBtoBに事業転換しようとする私の背中を押しました。新型コロナウイルスの影響で、学校のオンライン化が一気に進んだ時期でもあり、これも我々にとって追い風となりました。
キーマンを見つけることが重要
学校への営業は大変だとよく言われます。
杉浦:そうですね、その通りだと思います。一方で、簡単なビジネスなんてありませんから、「教育ビジネスは難しい」「教育は儲からない」と言われれば言われるほど、ある意味競合も少なくなるわけで、それはいい点なのではないでしょうか。我々も発展途上なので偉そうなことは言えませんが、結局「ここでやっていく」と腹を括った者勝ちなのかなと思います。民間企業との取引と比べると、学校は合意形成と決裁の仕組みが複雑ですし、スピード感がまったく違います。決まるまでに時間がかかるのです。それが慣習だと理解し、どういうプロセスを経れば合意形成が可能か、少しずつ学んでいっています。
教育現場に対して具体的にどんな働きかけを行いましたか?
杉浦:まずは、プロダクトの応援者を見つけたいと思いました。我々が実現したいと思っていることに共感し、共に歩んでくださる方を探しました。また、「物売り」としてお話をするのではなく、先生がやっていること、目指したいことを聞いたり、どんな学びを届けたいと思っているのかをお話しすることを大切にしています。根底には、日々忙殺されながらも生徒一人ひとりと向き合っていらっしゃる先生に対するリスペクトがあるので、学ばせていただくスタンスですね。また、我々は教育新参者なので、「どのように知ってもらうか」という視点は意識しています。元々CINRAでメディアの仕事をしてきたので、サービスをどうPRし、展開していくかは意識しました。できるだけ「Inspire High」という言葉を目にしてもらえる回数を増やしたいと思って工夫しています。長くて英語っていう、PR上は難ありなプロダクト名ですが(笑)。
杉浦さんの場合はCINRAでの繋がりや知見が活かされたのではないでしょうか。ごく普通のスタートアップでは、露出も難しいように思えます。
杉浦:確かにこれまでの事業経験や様々な人たちとつながりがあるという意味では、これからゼロから立ち上げるスタートアップと比べればアドバンテージは多少あったかもしれません。ただ、これから始められる方々には「年齢」という圧倒的なアドバンテージがありますからね(笑)。一長一短です。いずれにせよ、ただ目立っていてもしょうがないわけですが、すでに歴史ある教育系大企業でもない僕等が学校の先生に知っていただくというのは、とても努力が必要なことだと思います。

自分を信じ顧客に耳を傾ける
BtoBに切り替えて、パートナー校や導入校が増えていると聞きます。現在の「Inspire High」について教えてください。
杉浦:EdTech導入補助金などのサポートもあり、現在は100校以上に使っていただいています。「Inspire High」は特定の教科のための教材ではないため、総合探求やロングホームルーム、道徳等、学校によって活用方法が異なります。一校一校、学校の教育目標や探究での学びの目的に対して「Inspire High」がどう貢献出来るかをディスカッションしてまとめていきます。きちんと計画を立てないと、導入しても使われないことが起きるからです。考える材料として、他の学校での利用の仕方を共有させていただくことで「イメージが湧いた」とおっしゃってもらうことも多いです。
また、当然ながら学校のお話、特に先生がお持ちの課題感を伺うことも大切です。「Inspire High」が主語になるのではなく、学校が主語になることを意識することも重要だと思っています。
「Inspire High」を始めた前後で、教育に対する考え方は変わりましたか?
杉浦:学校や先生に対するイメージは変わりましたね。イメージが変わったというか、解像度が高まりました。結論、当たり前ですが「学校も先生も、いろいろだな」って思うんです。教育事業に携わるまでは、「日本の教育ってここがまずいよね」とか、「先生ってこうだよね」とか、ひとまとめに考えてしまうこともありました。でも中に入ると、本当にいろんな先生がいるし、いろんな学校があるんです。偏見や固定観念にとらわれていたら、何も実現できません。国籍、産業、人種、何でもそうですが、目の前にいる人と、一人の人間として対峙させていただくのは、あらゆる事業活動の基本だと改めて認識しました。
今後はどんな展開を考えていますか?
杉浦:国内の学校に広めていくためにプロダクトを磨き上げていくことが第一です。「探究学習」というワードに囚われることなく、10代をインスパイアし自ら動き出すことを支援する学びを、教育のド真ん中に持っていくお手伝いをしていきたいと思っています。それと同時に、「Inspire High」はすでに半分くらいが海外ガイドによる英語のセッションなので、多国間でのセッション実施も実現していきたいと思います。
最後に、EdTech事業を成功させるための秘訣を教えてください。
杉浦:まず大前提なのですが、私はEdTech事業を成功させていません。謙遜ではなく、この会社はまだ3年目であり、事業もアーリーステージなので、本当にこれから、毎日が正念場です。EdTech事業としては新参者なわけですが、ただ、経営者としては20年近くやってきました。その中で大切にしていることは、自分を信じることと顧客に耳を傾けることを両立してやりきることです。自分への過信はダメですが、実現したい想いを強く持っていないと心が折れます。つまり、Whyは絶対にブレてはいけません。逆にHow、戦略はいくらでも変わり続けていいと思っています。Howは、ともかく顧客や現場社員の声を聞き、信じて、何度でも調整をかけてトライし続けていくものだと思っています。
最終更新日:2023年3月15日