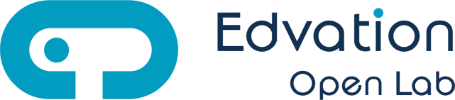- ホーム
- 次代のEdTechイノベーター支援プログラム(Edvation Open Lab:EOL)
- 独立系シードVC・栗島祐介氏インタビュー VCから見たEdTech業界の全体像と投資のポイント

2023年2月7日
栗島祐介氏
HAKOBUNE株式会社 代表取締役
主にPre-Seed(※1)、Seed(※2)ステージの国内スタートアップ企業を対象に投資する独立系ベンチャーキャピタル(VC)のHAKOBUNE株式会社。「想像を超える未来を示し、次世代の当たり前を生みだし続ける」をミッションとして掲げ、“組織の異端児/はみ出し者”に対して積極的に投資を行うことで“大人起業家”が生まれる文化の醸成を目指しています。HAKOBUNE代表取締役の栗島祐介氏は、2014年から株式会社VilingベンチャーパートナーズのCEOとして教育領域に特化したシード投資実績を経て、2016年にスタートアップ支援を行うプロトスター株式会社を設立。昨年から新たにHAKOBUNEを設立して投資活動を行っています。今回はHAKOBUNEの事業を通して、リアルなVCの世界をお伝えします。
- ※1 Pre-Seed:創業や事業を思いついたタイミングであり、会社設立前の段階。
- ※2 Seed:事業をアイデアベースで検討している、もしくは、大枠は決まっているものの具体的に落とし込めておらず事業計画を作成している段階。
次世代を担う大人起業家の受け皿
主な投資対象はPre-Seed、Seedステージの国内スタートアップ企業ということですが、まずは「組織の異端児/はみ出し者」「大人起業家」の定義と、彼らを投資対象とする理由を教えてください。
栗島(以下敬称略):「組織の異端児/はみだし者」とは、例えば趣味の延長として活動しているうちに起業する等、組織の枠に囚われない、常識を覆す変化を起こす大人達です。埋もれてしまっている可能性を発掘し、育成することで、次世代を担う事業家を輩出するのが狙いです。また、「大人起業家」の最もわかりやすいイメージとしては、社会経験のある30~40代ぐらいの方。統計的に40代ぐらいの起業家の方が、若年層よりもユニコーン企業となる確率が高く、事業に対する解像度も兼ね備えています。事業に対する解像度とは、顧客に対する事業領域での深さと広さ、そして市場に対する行動理解を指しています。40代は事業に対する解像度が比較的高いため、投資を受けることで成功確度が上がると考えています。一方で、web3(次世代の分散型インターネットの総称)やeスポーツ等、新たなカルチャー領域では、若年層の方が構造を理解しています。そのため実際には「大人起業家」を年齢で区切ってはいません。年齢に関係なく「大人」であること。事業経験もあればいいのですが、ビジネススキルは後から身に付きます。どちらかといえば、顧客解像度や業界解像度の高さの方が重要です。

HAKOBUNEのホームページ
投資する際に重視することは何ですか?
栗島:誠実さやチャレンジ精神等の人的な部分、経営的な判断目線、事業の切り口や解像度という3つの軸が基本です。そこにプラスαとしてテーマ領域が加わるのですが、テーマというのは、時代を反映して切り口やアイデアが練り込まれていたり、規模が拡大する可能性のある領域です。その領域に挑めるかどうか、挑んだとして成長出来るかがポイント。伸びるかどうかは、その方の思考の解像度によるので、お会いしてお話をして判断します。例えば、挑戦する領域について、その方が業界構造をきちんと理解しているかどうか、仮説の課題についてどのように対応するのかを探ります。結局は、仮説検証していくしかないのですが、事業の成功確度を上げていけるような挑戦が出来そうな方かどうかで評価します。そのため、デューデリジェンス(DD/財務等に関する情報を入手してその情報を調査すること)については最低限しか行いません。特にPre-Seedは、創業前だったりするとDDの行いようがないのです。

ステークホルダーが変わる難しさがある
EdTech事業者に投資する際、何か特有の基準や判断方法はありますか?
栗島:軸としてあるのが、対象が社会人か、大学生以下かどうか。対象が社会人の場合は、普通のビジネス領域と同じなので判断しやすいです。BtoCの場合は、大学生以下になると、ステークホルダーが変わるので難しくなります。大学生は違うかもしれませんが、サービスを受けるのは学生なのに、お金を払うのは保護者となる。こうなると戦い方、アプローチの仕方が複雑になります。保護者にコミットしなければいけませんが、子ども達にもサービスの価値を上手に伝えないと継続しません。この辺りの調整、バランスが難しい。これが教育領域の難しさの原因の1つだと思います。BtoBの場合も、ある学校と合意形成出来たとしても、それが横に広がりません。他の学校とはまた一から始めなければならない。結局はゼロとイチの連続で、その点が他の領域とは異なります。
そうなると、EdTech領域への投資を足踏みするVCも多いのでしょうか?
栗島:教育、EdTech領域でも、社会人を対象としていれば何も問題ありませんが、学生、特に子ども向けは、約1兆円と言われている塾市場がメインで、それ以外の公教育市場はそもそもの市場規模が小さいのです。少子化が進んでいるため、VC目線からみても、挑むには微妙な規模感になっています。しかしそれでは話が終わってしまいます。例えば、子どもを切り口に保護者の領域にどうマネタイズするか。家庭での勉強等、日常の学びに食い込むことが出来れば可能性は広がります。よく「教育は儲からない」と言われますが、「儲けにくい」と言うのが正しいと思います。先ほどのステークホルダーのような構造的な課題もありますし、学校の先生や保護者等、情報通信やテクノロジーに慣れていない方も少なくありません。EdTech事業者側も、いい教育を届けようという想いが強すぎて、techで事業の幅をどう広げるかという思考までいかない方もいらっしゃいます。そうした課題を認識した上でのtech思考的なアプローチが重要ではないでしょうか。
伴走支援型による完全支援
VCのサポート方法も様々だと思いますが、HAKOBUNEの場合、投資を受けた後はどんなフォローがあるのでしょうか?
栗島:事業が形成されるまでにある程度の時間と検証が必要なため、起業家に寄り添い、事業仮説の壁打ちの相手になると同時に、仮説検証を一緒に行う経営パートナーとして関与していく伴走支援型、事業の初期実績作りを中心に支援するグロース支援型の2つでアプローチします。伴走支援型(インキュベーション型)の場合、事業計画の策定から資金調達、人材の確保、マーケティング、顧客の紹介等、実務支援を行っています。担当者が定期的にフォローアップしますが、人によっては中だるみすることがあります。ですので投資先がもう少し増えたタイミングでお互いに刺激し合えるように、スタートアップが一堂に介して情報収集や意見交換を行える機会も設ける予定です。また、弊社ではポータルサイトも作成しているので、スタートアップの事例に基づく実践的な知見を提供したり、顧客リストから事業者にとって気になる相手を繋げたりしています。ポータルサイトでは弊社のスタートアップ情報を検索できるため、約100社のパートナーが登録をしています。このようなネットワークを活用して初期実績作りをグロース支援では行っています。

左の赤枠内がPre-Seed、Seed期の起業家支援
伴走支援型のVCばかりではないですよね。
栗島:そうですね。これはVCの特徴によります。いわゆるハンズオンと呼ばれるVCは一緒にビジネスを構築していくパターン。例えば20~30社ぐらいにしか投資しない等、厳選投資をしているVCに多いです。一方、ハンズオフは、投資をしたら「あとは頑張ってね」と事業者に任せるようなイメージです。ハンズオンとハンズオフのVCの比率は半々ぐらいかと思います。
教育、EdTech領域の事業者向けのフォローはありますか?
栗島:事業領域を問わず、スタートアップの方達が求めるのは資金調達です。基本的には支援体制は同じで、事業領域による色分けをせず、情報等も平等にシェアしています。
例えば段階によってフォローのやり方も違うのでしょうか?
栗島:基本的に、プロダクトマーケットフィット(PMF)と呼ばれる段階まで到達させるのが、Seedの目標となります。つまり、提供するプロダクトやサービスが、市場のニーズに合い、きちんとリピートされる状態です。そのためにマイルストーンを予め設定し、そこから逆算して仮説検証を行います。仮説検証を行った結果に対して、どういう変化が起こるか、どうすれば次の資金調達まで持って行けるか、次にどんなアプローチをしていくか等、担当者が一緒にディスカッションしながら作っていく感じです。

VCとの相性は何よりも重要
教育、EdTech領域の事業者からの相談も多いですか?
栗島:結構多いですね。ほとんどが資金調達についての相談です。EdTech事業者に限らずスタートアップにとって必要なのは事業成長のために人を雇う、マーケティングをするための資金であり、スタートアップの大半は資金調達に多くの時間を割いてしまっているのが現状です。また起業家側から直接相談を受ける以外は、(さまざまな方から)スタートアップを紹介されるケースが多いです。他のVCはどうなのかヒアリングをしたところ、実はTwitterを使ってのファーストコンタクトが約6割もあるVCもいました。
VCとの相性というのもあるのでしょうか?
栗島:あります。これもEdTechに限らず全般的な話ですが、経営者が役員メンバーを選ぶ時の感覚に似ています。組織作りにおいて、組織カルチャーがずれている人を役員に入れると、仲違いをしたり、最悪の場合、組織が崩壊します。「背に腹は変えられないから、投資をしてくれるVCならどこでもいい」という方もいると思いますが、結局は意見が合わなくて悪い結果を生む可能性が高いので、相性のいいVCを選んだ方がいいと思います。相性の良し悪しは、友達作りと同じ感覚だと思います。実際に話してみなければわからないので、経営戦略について等、議論を重ねることが重要です。
EdTech領域について、成功する企業に共通点はありますか?
栗島:なかなか難しい質問です。1つ言えるのが「techを中心に大きな絵姿を描けるかどうか」だと思います。対象の顧客解像度や業界構造の解像度を高める等、リアルな部分も重要ですが、「techを使って教育をどうより良くしていくか」の視点を具体的にしっかりと入れ込めるかだと思います。例えば、AIを用いた学習システムを学習塾に展開することで成功している会社もあります。また、大学生をメンター(講師)として子ども向けのプログラミングスクールを展開していた会社が、学習教材の作成で事業を拡大していった例も。また、ユーザー心理の深読みも必要かもしれません。例えば、保護者が子どもを学習塾に通わせるのは、「夕方の忙しい時間に子どもが家にいると大変なので塾で預かってほしい」という隠れたニーズもあります。そうした顧客の隠れたニーズまで深読み出来る思考力も大切です。
少子化を考えるとグローバル展開も視野に入れた方がいいのでしょうか?
栗島:ケースバイケースです。人それぞれ見解はあるかもしれませんが、日本の学習指導のノウハウが世界から見ても高い水準のため、海外展開している成功事例もいくつかあります。やり方次第では日本の教え方を輸出出来ると思います。しかし、東南アジアは受け入れられても欧米とは相性が悪いといった地域差がある他、現地のローカルルールを理解しなければならない難しさがあります。数学や物理等、理数系は解が明確なので展開しやすいのですが、それ以外の科目は難しいかもしれません。
EdTechの将来性についてはどう思われますか?
栗島:将来性はすごくあると思います。少子化という課題はありますが、GIGAスクール構想による一人一台端末の導入や、学習指導要領の改正等、学校のあり方が変わってきているので、新しいアプローチのチャンスがあります。大学に関しても、ようやくビジネスの門戸が開かれるようになり、大学や大学生をターゲットとするスタートアップが増えました。3年前にはなかった現象です。最近は推薦やAO入試により、12月ぐらいまでに多くの学生が受験を終わらせるそうです。必然的に大学受験への向き合い方も変わってきているので、そのあたりに挑戦するスタートアップも増えてくるのではないでしょうか。また、少子化が進んではいるものの、保護者が子どもにかける教育費用の金額が上がっているため、どのようなニーズに対応出来るか次第で伸びる余地がありますし、成功事例が出てくると、さらに大きく変わるかもしれません。ちなみにVC目線で見ると、子ども向け以上に、社会人向けのEdTechに大きな可能性を感じています。
横のネットワークを広めることにも注力を
VCから出資を受ける時のアドバイスはありますか?
栗島:同じことの繰り返しですが、VCとの相性は重要です。教育というのは、VCの担当者自身も受けてきたものなので、教育に対して一家言を持っている方も少なくありません。冷静にメタ認知出来る方がベストです。また、相性のいいVCを見つける方法としては、過去に教育領域への投資実績のあるVCを探したり、成長しているEdTech企業をチェックしたりして、そこに投資しているVCや個人投資家にアプローチするのがいいと思います。アプローチしていく中で、他の投資家を紹介してもらうのはもちろん、EdTech系の経営者と横の繋がりも作っていきましょう。コツコツと横展開のネットワークを広めていく事は非常に重要です。
最後にEdTechスタートアップの方に向けてエールをお願いします。
栗島:EdTech領域、特に学生をターゲットとする領域は厳しい面もあるのですが、とはいえ、現在、大きな変革期です。このタイミングでユーザーに刺さるサービスを創出出来れば、公教育市場が現在以上に開放された時にインフラとして重要なポジションを取れる可能性があります。一方、社会人向けのEdTech領域では、大きな競合他社がおらず、一人勝ちできる可能性のあるリスキリング市場があります。
ぜひ、新たな市場を切り拓いてください。
最終更新日:2023年3月22日