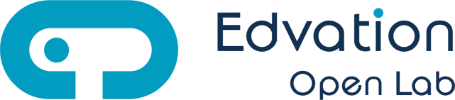- ホーム
- 次代のEdTechイノベーター支援プログラム(Edvation Open Lab:EOL)
- 「SXSW EDU 2023」レポート Vol.1 Institution for a Global Society株式会社~イベントのカテゴリーが豊富で、インプット・アウトプットのバランスが抜群~
「SXSW EDU 2023」レポート Vol.1
Institution for a Global Society株式会社~イベントのカテゴリーが豊富で、インプット・アウトプットのバランスが抜群~
2023年3月6日~9日

教育領域に特化した世界最大級のクリエイティブ・カンファレンスイベント「SXSW EDU 2023」が、2023年3月6日~9日、アメリカ・テキサス州オースティンで開催されました。日本からは採択事業者5社が参加。今回は、Institution for a Global Society株式会社のセッションレポートや参加した感想を紹介します。
参加事業者
-

-
Institution for a Global Society株式会社
中原 成美氏執行役員Co-CFO
経営企画部長
【参加目的】
グローバルの最新トレンドおよび需要を検証
弊社は、「Ai GROW」という非認知能力の評価サービスを日本国内で展開しており、2023年1月末現在40都道府県で導入実績があります。今後の海外展開を見据えて、需要の把握(国や地域の特定)、 非認知能力評価の類似サービスや競合環境、およびUI/UXのトレンドについての情報収集を行う必要性を感じています。
そのため、「SXSW EDU2023」では、主に能力評価、ゲーミフィケーション(※1)、ダイバーシティに関するセッションやミートアップに参加し、テクノロジーの活用によって多様な能力の評価・育成を目指す人材と意見交換をすることで、上記を検証したいと思いました。
- ※1 ゲーミフィケーション:ゲームを本来の目的としないサービスなどにゲーム要素を応用することで、利用者の意欲の向上やロイヤリティーの強化を図ること。
【SXSW EDU2023レポート】
アウトプットせざるを得ない環境で成長
全米から教師など教育関係者が集って意見交換を重ね、よりよい教育を実現するためのカリキュラムデザインやネットワーキングの機会が用意されるなど、非常に活気がありました。Keynoteセッション(※2)、セミナー、ワークショップ、ミートアップをはじめ、セッションのカテゴリーも複数あり、インプット・アウトプットのバランスが良かったです。自分自身のことや自社のサービス、日本のことについて話さなければならないなど、積極的にアウトプットせざるを得ない環境に身を置けたこと、さらにそれに対してのフィードバックを受けられる場であることが非常に有難かったです。サービス開発におけるユーザーアイデンティティの考え方、そこから発展して教育におけるEquity(公平性)の担保について、参加者の皆さんが真剣に考えていることが特に印象的でした。
- ※2 Keynote:各日のメインとなる大規模なセッションはKeynoteと呼ばれ、著名人が登壇するほか、手話による同時通訳とリアルタイム字幕が整備されている。
事業者側の視点では、少なくともDistrict(地区)レベルの意思決定者とコンタクトしない限り、単純な情報交換で終わってしまいます。参加者が非常に多いため、目当ての人物に出会える可能性はかなり低く、事前に個別面談を設定できればよかったと反省しました。高等教育では、米国はいまだに世界の最先端・頂点にいると思いますが、伝統的なPre-K(※3)~K-12(※4)では教師が生徒に教え評価すべきという価値観が一般的で、当社が目指す「生徒同士の相互評価」のハードルは結構高そうな印象でした。
- ※3 PreK:Pre-kindergarten (プレキンダー)のことで、4歳児のクラス(そのスクールイヤーの間に5歳になる)はキンダーガーテン入園前の期間のこと。
- ※4 K-12:幼稚園(KindergartenのK)の年長から始まり高等学校を卒業する(12年生=高校3年生の学年)までの教育期間のこと。

Keynoteセッション。1日1回、一番大きな会場で行われ、著名人が登壇することもあった
個別の議論やセッションを通じ米国のトレンドを概ね把握
サービスの海外展開を見据え、グローバルの最新トレンドおよび需要、競合環境、販売パートナーについて、現地で検討材料を収集したいと思い、参加しました。特に、テクノロジーを活用した非認知能力の評価や育成に関して検証するのが当初の目的でした。公立学校の校長や、生徒主導の教育を実践する新しいタイプの学校経営者、事業者、米国の教員との個別の議論やセッションを通じ、米国のトレンドは概ね把握できました。当社サービスの競合となるような特定のサービスはなかった一方で、非認知能力評価の市場自体もまだ確立されていない印象。啓蒙・ニーズの掘り起こし・営業活動が必要だと感じました。

テーマに沿って有識者が話すパネルディスカッション。会場からも多くの質問が出た
基本的なポイントは大前提として押さえてから参加すべき
米国は50州それぞれが国のようなものなので、人種も多様であることから、日本以上にサービスデザインにおけるアイデンティティへの配慮などが必要です。どういう人と話せるかは運による部分が多いのですが、自社のサービスや事業内容、疑問を端的に伝えることが重要。完全に新規のビジネスやサービスは見当たらないと感じましたが、そんな中でも、差別化ポイント、社会に与えるインパクト、マネタイズの方向性など、基本的なポイントは押さえてから参加すべきと感じました。
現役教員にとっては、カリキュラムデザインの参考になるワークショップなどが多く、学びがより大きそうです。海外における知名度の点からも、参加する場合はUNICEFなど国際的に知られた団体との取り組みや認証があるとアピールしやすいと思います。

ワークショップの様子。丸テーブルで、テーマに沿って議論・実践する
広くアンテナを張りセッションの目星をつけるのが良い
事前準備については、関心を寄せるテーマについてのボキャブラリーを幅広に持っておくべきだと感じます。特に日本語とは定義の幅も違うので、より広くアンテナを張り、セッションの目星をつけるのが良いと思います。事前に日本でアクセスできる現地教育関連情報は非常に限られるので、SXSWのセッションにくまなく目を通し、大まかなトレンドを先に掴むのもおすすめです。
一方、実際は現地に入ってから参加すべきセッションの肌感覚が徐々につかめていった部分も大きく、当初の計画を変更して、関係者との意見交換目的でテーマを絞ったミートアップやCoffee Breakなどに積極的に参加しました。

スタートアップなどによるコンペティションで、ファイナリストが投資家や聴衆の前でピッチを行う
参加セッションの詳細を記載しているレポートはこちら!
参加事業者
- Institution for a Global Society株式会社
-
■ 企業概要
企業名/Institution for a Global Society株式会社
所在地/東京都渋谷区 設立年/2010年 社員数/約50名
HP https://www.i-globalsociety.com/■ 事業概要
学校法人、企業、自治体など向けに、能力評価システム、教育コンテンツ、データ利活用プラットフォームを提供。教育・EdTechサービスのコアである「Ai GROW」(アイグロー)は、「見えない学力」(潜在的な性格やコンピテンシーなど)を可視化する人材評価システムで、対生徒では、メタ認知の機会の提供、自己肯定感・自己効力感を高めることなどに寄与。対教育者では、「見えない学力」の定量化により、生徒を公平かつ多面的に評価する「観点別評価」の実現を支援する。
最終更新日:2023年3月30日