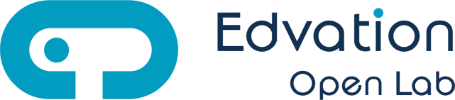- ホーム
- 次代のEdTechイノベーター支援プログラム(Edvation Open Lab:EOL)
- 「SXSW EDU 2023」レポート Vol.4 HelloWorld株式会社~調査の第一歩が踏み出せたと実感! ~
「SXSW EDU 2023」レポート Vol.4
HelloWorld株式会社~調査の第一歩が踏み出せたと実感! ~
2023年3月6日~9日

教育領域に特化した世界最大級のクリエイティブ・カンファレンスイベント「SXSW EDU 2023」が、2023年3月6日~9日、アメリカ・テキサス州オースティンで開催されました。日本からは採択事業者5社が参加。今回は、HelloWorld株式会社のセッションレポートや参加した感想を紹介します。
参加事業者
-

-
HelloWorld株式会社
今野 達眞氏WorldClassroom
事業部・COO
【参加目的】
海外展開の可能性を検証したい
弊社が提供する「WorldClassroom 」は、スピーキング練習機能だけでなく、異文化交流・国際交流プラットフォームの機能を有する英語学習EdTechツールです。この文化交流学習の視点においては、日本よりも英語能力が高い英語圏以外の国でもニーズはあると考えています。「SXSW EDU2023」では、様々な国の有識者から意見を聞き、先のニーズに関する仮設を検証していきたいです。また、米国を主とする英語圏に対しても、授業内での文化交流学習の価値を訴求できると考えています。実際に「WorldClassroom 」を用いた国際交流を昨年度から実施していますが、英語圏の提携校へのヒアリングで手応えを感じました。今回、英語圏でのさらなる調査と有識者へのヒアリングを行うと共に、海外展開を目指す上で、協業の可能性のあるイノベーターやサポーターとのネットワークを構築したいと考えていました。
【SXSW EDU2023レポート】
SXSW EDUは協力してより良い教育を目指す人たちの集まり
SXSW EDUは簡潔に言うと「立場や属性にかかわらず、熱意を持って教育の未来を考える人が集結するイベント」。管理職を含めた学校の先生、教育委員会の先生、教育事業者、チューター、学生、それぞれが独自の視点で教育の現状について意見を語り、新たな視点や仲間を求めてミートアップやトークセッションに参加しており、皆が協力してより良い教育を作り上げることを目指していたように感じました。
トークセッションには、多様性教育やSTEAM教育(※1)などを注目トピックとして捉えたセッションが多かった印象です。ワークショップには、 Design-based learning(探究ベースの学習形式または教育学)などの現在の教育トレンドを押さえた教育実践だけでなく、適切に事業ピッチを行うための指南がもらえる教育事業者向けのコンテンツもありました。セッションやワークショップに関しては、参加することで大きな学びもありましたが、ネットワーキングでインプット・アウトプットを得るためには、積極的に話しかけたり、事業紹介をしたりする必要がありました。
- ※1 STEAM教育:Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学・ものづくり)、Art(芸術・リベラルアーツ)、Mathematics(数学)の5つの単語の頭文字を組み合わせた教育概念。知る(探究)とつくる(創造)のサイクルを生み出す、分野横断的な学びのこと。

初日に行われたKeynoteセッション(※2)の様子
- ※2 Keynoteセッション:各日のメインとなる大規模なセッションはKeynoteと呼ばれ、著名人が登壇するほか、手話による同時通訳とリアルタイム字幕が整備されている。
調査の第一歩を踏み出せたと実感
自社のEdTechツール「WorldClassroom」の海外展開を検討する上で、国外市場でのニーズを調査することが参加目的の1つでした。文化交流学習としては、日本以外の英語が話せる国での需要もあると仮説を立てていたため、まずはその検証を行いたいと考えていました。参加者は米国の方が多く、様々なの国の教育機関決裁者へのヒアリングを実現することは難しかったものの、英語圏におけるニーズ調査に関しては、調査の第一歩を踏み出せたと実感しています。テキサス州の一部の校区を管理する教育機関に勤める教育担当者にヒアリングしたところ、「米国であっても国際交流のニーズはあるだろう」との言葉を頂きました。米国内でも、とりわけ「言語学習や異文化理解多様性学習に力を入れている学校は、米国でのプロダクトテストをする対象として適しているのではないか」との提案も頂くことができました。
協業の可能性のある組織とのネットワーキングとしては、日本の学校も広くプロダクトを導入している北欧初のEdTechスタートアップの役員や、世界各地の学校とのコネクションを持っているNPOの担当者などにピッチをして、連絡先を交換できました。

Expo(※3)では様々な事業者が出展し、独自のソリューションを展示していた
- ※3 Expo:事業者や大学による研究、商品やサービスの紹介がブース形式で行われる。担当者が常駐し、オリジナルグッズや体験による誘客がみられた。
焦らずにステップを踏んで説明することが大切
参加者は教育事業者だけでなく、学校の先生も多かった印象です。ピッチを行っても自分の事業がなかなか相手に伝わらないこともありますが、焦らずにステップを踏んで説明することが大切だと感じました。デモなどをすぐに出せると、一気に相手の理解の解像度が上がり、話が進むことも実感。自分のことを話すのに精一杯になりがちですが、ミートアップなどでは相手についてしっかり質問することが、会話する上では重要だと思います。
メンタリングセッション(※4)は人気のため、早めの予約が必須。一方、ワークショップは基本的に予約制度がないため、人気のブースは人数制限で入れないこともありました。ミートアップは関心が合うものがあれば、参加するのがおすすめです。そしてキーノートセッション全てに参加すると、その年の「SXSW EDU」が何を重視しているのかがわかります。今回は「ダイバーシティ」だと感じました。

トークセッションはソロや2〜4名のパネルディスカッション式など様々な形で実施
- ※4 メンタリングセッション:教育関係の専門家(高等教育・ビジネス・SEL等)と個別にディスカッションをしたり、助言を得ることができる。各12分スロットで、事前に希望するメンターに対して公式アプリを通じて予約をする必要がある。
米国の最新教育事情を把握しておくことが重要
来年度の参加をお考えの人は、米国でのプロダクト展開を検討していないとしても、米国の最新教育事情をある程度把握しておくことを推奨します。また、セッションやワークショップでは、アメリカで制定されたばかりの教育に関する法律を前提として話が進むことがあるので、話を理解し、自分の事例に置き換えて落とし込むためにも、事前準備は必要です。
日本では馴染みがないかもしれませんが、LinkedIn(アメリカ発のビジネスSNS)は必須です。プロフィールを埋めて、いくつか投稿しておくこと。そして「SXSW EDU」の投稿に、イイネやリポストしている人を確認して、自身の事業領域と近い人がいれば、メッセージ付きでつながり申請をしておくといいでしょう。

教育に特化したピッチを観覧できたLaunch(※5)の様子。日本からの登壇者もファイナリストに残っていた
- ※5 Launch:一般及び学生スタートアップのピッチコンテストが開催され、投資家による審査が行われる。審査発表は当日中に行われる。
参加セッションの詳細を記載しているレポートはこちら!
参加事業者
- HelloWorld株式会社
-
■ 企業概要
企業名/HelloWorld株式会社
所在地/沖縄県沖縄市 設立年/2020年 社員数/25名
HP https://inc.hello-world.city/■ 事業概要
「世界中に1ヵ国ずつ友達がいることが当たり前の社会を作る」をミッションとし、国内在住外国人の自宅にホームステイをする「まちなか留学」と、学校向けオンライン国際交流ツール「WorldClassroom」を展開。異文化体験・国際交流の裾野を広げることに努めている。「まちなか留学」は、経済的な理由などで留学を断念していた生徒へ留学の機会を寄与。
最終更新日:2023年3月30日