産業・イノベーション分野産業構造転換(製造業)
小林 正幸製造産業局 自動車課 課長補佐(2022年8月時点)
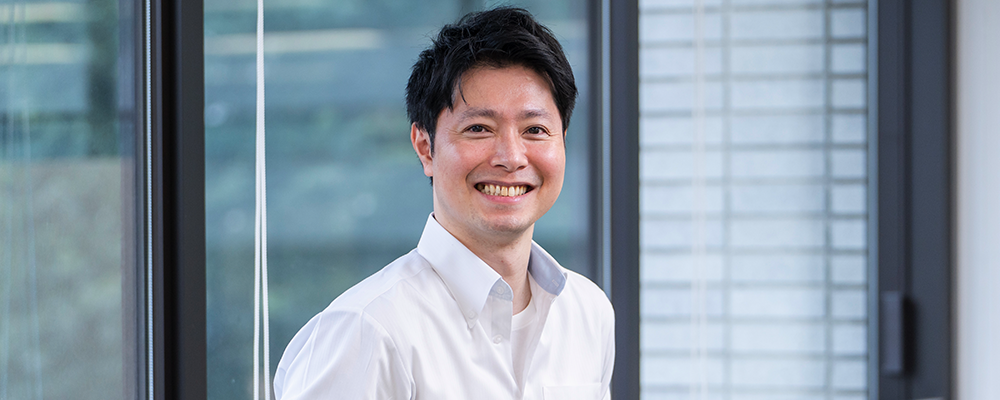
”技術の進化” それは産業構造を根本から変える
技術は急速に変化しています。AI、IoT、ロボット、バイオ、またそれを支える部品、鉄・アルミの製造など、世界ではあらゆる分野で、秒単位で技術的進展が生じています。大きな進展はイノベーションとして、時には産業構造自体を根本から変えてしまい、それは経済・雇用にも莫大な影響を与えます。こうした急速な技術的変化に対し、日本企業はどのように対応し、また経産省に何が求められているか。これまで私が直面した “技術的な変化”を紹介します。
デジタルの波
2018年、高圧ガス保安室に着任しました。全国の石油・化学コンビナートの安全を担う部署であり、AIやロボット等の技術とは程遠い部署と想像していました。しかし、実際は異なっていました。全国のコンビナートの設備は老朽化が過度に進み、検査や改修を頻繁に行う必要がありました。しかし、人材不足も急速に進んでおり、継続的に安全を維持することが難しくなっていました。そんな中、このギャップを埋めるため、ちょうどヒトの代わりをAIやドローンで代替できないかを検討し始めたところでした。
私のチームは、すぐにこの検討を実証に移し、AIやドローンの技術的な可能性を探りました(まずは “やってみる”精神です!)。例えば、過去の検査データをAI分析することにより、設備寿命や事故の確率を予測し検査期間を延長したり、高い塔やタンクはドローンを使った映像チェックで代替するなど、ヒトへの負担を軽減する取組を考えました。こで大きな壁にぶち当たるこ となりました。これま での制度は、ヒトが検査・審査する、まさに「ヒト中心」の制度だったため、これらの実証の結果をもとに、一部をAIやドローンに代替可能な制度設計に変更していく必要があったのです。
技術を正確に理解するため、毎日、企業の方と侃々諤々と議論し続けました。さらに、自ら現場に足を運び、高いタンクに登り、ドローンへの代替の重要性を、身をもって体感しました(高所恐怖症の私は3/4くらいの高さで離脱しかけました(苦笑))。 その結果、我々のチームは2年かかると言われた制度をアジャイル型で検討し、半年で制度変更しました。これは、産業保安の新しい時代への幕開けとなったのです。
グリーンの波
自動車課に着任して3か月後、菅総理(当時)が「2050年カーボンニュートラル」を宣言。 世界的にグリーンの波が一気に押し寄せ、EU及び中国を中心にガソリン車廃止の流れができ、EVが急速に拡大し始めました。
ハイブリッド車で世界を席巻していた日本の自動車メーカーにとっては、大きなゲームチェンジです。このグリーンの流れは、自動車メーカーだけでなく、数多ある部品メーカー、ガソリンスタンド、自動車整備工場など、多くの企業を震撼させました。我が国自動車産業はどう戦えばよいのか、多くの下請け中堅・中小企業はこの動きにどう対応す べきなのか等、多くの課題が一気に噴出しました。特に重要な点は、産業競争力上、コア技術は何か。例えば、EVだと電池がカギを握りますが、電池の中でも負極材・正極材・電解質、それらを制御するシステムなど、どの技術が重要となるのか、これを見極める必要がありました。
そのため、我々のチームは手分けし、有識者と意見交換をしたり、自動車業界と連携し、技術的な課題を検証したり、時には現場に足を運び製造工程を自分の目で確認し、コアとなる技術を突き止めていきました。そして、それらを予算支援(配分)、制度整備、鉱物資源の安定確保など、あらゆる政策に反映し、日本の自動車産業が世界で負けないような政策を遂行しました。これはまさに官民一体での戦いです。
今後も変化は常に生じ、あらゆる分野でイノベーションが生じるでしょう。経産省としては、時々刻々と変わる技術を見極め、迅速に政策に落とし込み、日本企業がビジネス上、競争に勝ち抜くためにあらゆる手を尽くす、それが我々のミッションです。 この変化の速い時代において、経産省のミッションはますます重要になってくると私は確信しています。
経済産業省Ministry of Economy, Trade and Industry, JAPAN
お問い合わせ先
経済産業省 大臣官房 秘書課 採用担当
E-Mail:bzl-recruit@meti.go.jp
TEL:03-3501-0085
※基本は、メールでのお問い合わせをお願いします。
最終更新日:2025年6月5日