経済産業大臣表彰/宮本 佳則 (みやもと よしのり)氏
国立大学法人 東京海洋大学 学術研究院 海洋資源エネルギー学部門 教授
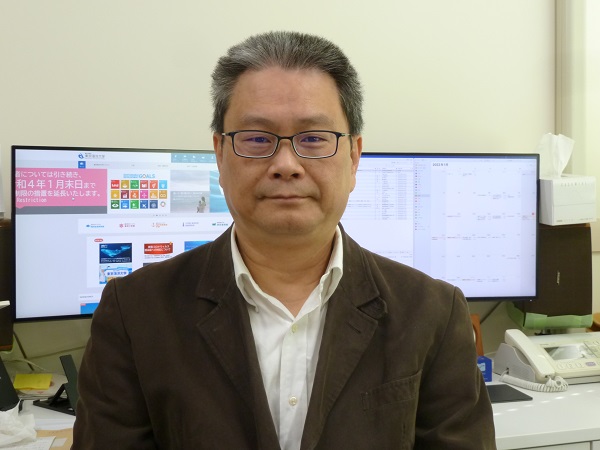
船舶に搭載必須の航海計器に関連する規格改訂を主導
近年、海運業界では安全かつ効率的な航海を実現すべく、最新技術を駆使した船舶機器のDX化が進んでいる。「例えば、自動車業界ではハンズフリー運転がようやく出てきたが、海の上では多くの船舶に自動運航技術が搭載されている。海上の安全を守るため、技術改良は日々進んでいる。」と語るのは東京海洋大学の宮本 佳則氏。コンパスをはじめとする航海計器の第一人者として、国際標準化を推進してきた。
宮本氏が標準化活動に参画したのは、約20年前。「当時、博士課程で指導いただいた先生が、委員会で既に活躍されていた。私の専門分野だった磁気コンパスに関連する規格策定が進んでいたこともあり、活動を引き継がないかとお声がけいただいた。」ことがきっかけとなった。
1998年、ISO(国際標準化機構)/TC 8(船舶及び海洋技術)/SC 6(航海及び操船)国内対策委員会の委員に就任。SC 6は、海上の安全を推進する国連の専門機関であるIMO(国際海事機関)と連携しており、策定された規格は世界中の船舶に適用されるなど、影響力の大きい委員会だ。宮本氏は多くの日本提案による規格策定に携わったのち、2011年に同SCのWG 1(ジャイロコンパス)、2014年にWG 4(磁気コンパス)のコンビーナに就任した。
「ジャイロコンパスと磁気コンパスは、どちらも船の方位を測定し、位置を求めるための航海計器だが、特徴が異なる。」と宮本氏。ジャイロコンパスは電気で駆動し、様々な航海計器へ船首方位を出力できるが、停電の際には使えなくなるデメリットがある。そのため、古くより利用されている磁気コンパスと一緒に搭載することがルールだ。
右:反映式磁気コンパスの機器構成(写真提供:布谷舶用計器工業株式会社)
「今の時代に合うよう既存規格のアップデートが必要。例えば、今は船舶機器のIoT化と併せて、船舶機器が故障した際、何が、どこで壊れているかを瞬時に知るためのシステムの構築が急速に進んでいる。」という。そこで、そのシステムを導入すべく宮本氏の主導の下でISO 8728(ジャイロコンパス)の改訂が行われている。
コンビーナとして心がけていることは「メーカーと丁寧に話し合うこと。」だという。「技術的な性能や安全性を高めることが第一だが、高めれば高めるほど、規格は厳しくなっていく。すると、メーカーのコストが上がって船に搭載できなくなったり、ルールをすり抜けようとする人も出てきたりする。そこで、国際会議の場だけでなく、メーカーからの委員に個別で意見を聞き、安全性を担保しながらどこにラインを設けるかを話し合って決めることが大切だ。」と力説する。
安全性に関しては「他国の委員との調整も大変。」と苦労を語る。「検査機関からの委員のみが委員会に参加している国があり、メーカーからの委員も参加している国との対立が止まない。前者は『もっと厳格な検査が必要』というが、現実的なコストなどを考えると難しい。落とし所をつけるために、調整がうまく行かない国とは一対一でオンライン会議を設定し、対応している。」という。
現在は、上記と同時並行でISO 25862(磁気コンパス)の規格を含む、複数の規格の策定や改訂を行っているとのこと。「日本は、ジャイロコンパス、磁気コンパスなどの船舶機器のシェアが非常に高く、技術も優れている。コンビーナとして今後も期待に応えるべく頑張りたい。」と笑顔を見せた。国内メーカー製品の国際的な普及、そして世界的な海上交通の安全向上への宮本氏の貢献は大きい。
航海計器は、日本が主導することに意義のある分野
「活動でポイントとなるのは、やはり語学だ。」と宮本氏。「国際規格はすべて英語で書かれているが、他国の委員も英語が第一言語ではない人が多く、英語文書でやりとりしていると、意味の取り違えが頻発する。その都度、コミュニケーションをとること、そして、どの国の人が読んでもきちんと理解できる書き方を重視しながら進めなくてはいけない。」。
宮本氏が教鞭を執る東京海洋大学では、1年間の船員養成プログラムがカリキュラムに含まれる。その中で船舶に搭載されている技術を説明する際は、標準化活動の意義や仕組みまで学生に教えるという。「世の中にあるものは勝手に作られたわけでなく、きちんと意図や背景がある。製品はメーカーごとに特色があるが、基本的な性能を維持するために国際規格があることを伝えたい。」と話す。今後の宮本氏による標準化の後人育成が期待される。
「航海計器の分野で日本がこれまでに果たしてきた役割は大きく、今後も主導していくことに意義がある。国際標準を作る作業は大変なことは多々あるが、国際的な影響も大きく、やりがいや達成感がある。専門性が高い活動ですぐに即戦力になれるわけではないため、興味を持った段階で、年齢など気にせずに参加して、実践の場で経験してみてほしい。」と、後進へ応援のメッセージをいただいた。
| 1992年 ~2001年 | 東京水産大学 水産学部 助手 |
| 1998年 ~現在 | ISO/TC 8(船舶及び海洋技術)/SC 6(航海及び操船)国内対策委員会委員 |
| 2001年〜2003年 | 東京水産大学 水産学部 准教授 |
| 2003年〜2015年 | 東京海洋大学 海洋科学部海洋環境学科環境テクノロジー 学部教授 |
| 2011年 ~現在 | ISO/TC 8/SC 6/WG 1(ジャイロコンパス)国内対策委員会委員長 |
| 2011年〜現在 | ISO/TC 8/SC 6/WG 1 コンビーナ |
| 2014年〜現在 | ISO/TC 8/SC 6/WG 3(磁気コンパス)コンビーナ |
| 2015年〜現在 | ISO/TC 8/SC 6/WG 3 国内対策委員会委員長 |
| 2016年〜2017年 | 東京海洋大学 学術研究院 海洋環境学部門 教授 |
| 2017年〜現在 | 同 学術研究院 海洋資源エネルギー学部門 教授 |
最終更新日:2023年3月30日

