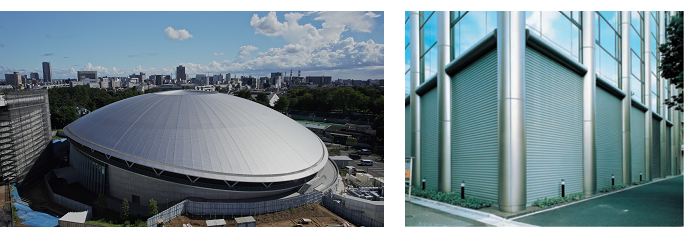経済産業大臣表彰/楠野 春彦(くすの はるひこ)氏
一般社団法人日本鉄鋼連盟 標準化センター事務局 主査

薄鋼板の標準化を日本代表として牽引。中国と交渉し幹事国を獲得
発電所、ビル、自動車、スマートフォン、パソコン。生活基盤を整えるあらゆる製品の源には鉄がある。鉄は安価で加工がしやすいなど多くのメリットがある一方、純度が高いと脆くなるのが弱点だ。そこで炭素を加えると硬度が上がり、鉄鋼が生まれる。「鋼板(こうはん)」とは、その鉄鋼を圧延機にかけ、板状に引き延ばされた鋼材のことを指す。
「戦後日本の経済成長を陰で支えたのが高品質な『薄鋼板』。これは厚さ3mm未満の鋼板で、自動車・家電業界などに必要不可欠。品質は世界的に認められている」と語るのは一般社団法人日本鉄鋼連盟の楠野春彦氏。薄鋼板の国際標準化を、日本を代表して牽引してきた。
1984年、日新製鋼に入社。2018年に前任者との入れ替わりで日本鉄鋼連盟の標準化センターに出向した。JIS原案作成委員会の改正審議に参加する中で転機が訪れた。標準化センター事務局への転籍が決定し、ISO/TC 17(鋼)/SC 12(連続圧延薄鋼板)に日本代表として参加した。楠野氏は、同SCの活性化を牽引する存在となっていく。
2020年、米国がSC 12の幹事国を辞退、同時にカナダも議長国を辞退した。日本と中国が幹事国の引継ぎを申し出、他の国からは立候補がなかったため、日中間での交渉が必要となった。「お互いの希望が重なり、なかなか進捗しなかった。」と楠野氏。なぜなら、幹事国の獲得はSCの活動全体をリードしていくことにつながるからだ。例えば、幹事国になれば、SC内の動向や新たな提案をいち早く確認でき、対応を検討する場合に時間的に有利になる。他にも、規格改訂案の作成を担当する機会が増え、規格改訂案に幹事国の意向が反映されやすくなるという利点もある。
「数ヶ月にわたって中国側に日本の強い意欲を伝えた。その結果、議長を中国が、幹事国を日本が務めることとなった」。交渉の際に心がけたのは「些細なコミュニケーションにも気を配ること。メール1つ出すにしても、文面や言葉遣いを国内関係者と相談し、一字一句の確認作業を怠らなかった。」
国際幹事に就任した楠野氏がまず着手したのがSC 12への参加国を増やすこと。「米国とカナダが撤退して、積極的に参加する国は日本と中国だけだった。制定・改訂作業を進めるには4カ国以上の参加がマスト。そこで、SC12の全てのメンバーに積極的な参加を促す文書を発信し、個別にメールでもアプローチした結果、イランとドイツの参加が得られた」
2カ国の参加により「改訂案について多くの有益なコメントを得られている」と楠野氏。1年間で、ISO 15177(双ロール鋳造法による一般用熱延鋼板)など4件の規格改訂に成功、同SCの標準化活動を軌道にのせた。
「SCの積極的参加国不足を解決するには、メールやZoomなどをできるだけ使ってコミュニケーションをとることが大切。常日頃からの交流が、徐々に仲間づくりへつながっていく。SC 12はまだ始まったばかり。今後、積極的参加国がもっと増えることを期待している」
議事進行を担う議長国の中国とのコミュニケーションも欠かせない。お互いの意向にずれが生じないようこまめに連絡を取り合うことが大切だ。日本の考えを提示し、それに対してどう考えるか質問を投げかける。そのような地道な作業がSCのスムーズな運営へつながるという。
環境問題への意識の高まりを受けJISを改正。国際会議の場で提案も
楠野氏は通常の鋼板より腐食に強い「亜鉛めっき鋼板」の国内外の標準化活動も精力的に推進してきた。
「亜鉛めっき鋼板では、さびを防止するべくめっきの表面に皮膜を作る処理が行われる。従来は環境負荷物質である六価クロムを含む処理が主流であったが、近年の環境問題への意識の高まりを受け、クロメート処理(六価クロムを主成分とする処理液で表面処理する方法)をJISから削除する改正を行った」
改正に際しては、市場における使用実態を細かく調査し、削除の予定を事前に関係先に通知するなどして市場で混乱が起きないよう細心の注意を払った。結果、提案から約6年かかったが、JIS G3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)などの規格改正につながった。しかし、ここで楠野氏の活動は終わらない。
JISの取り組みをISOに反映すべく日本発のクロメートフリー処理をSC 12の国際会議で提案。各国の関心と賛同が得られ、6件の国際規格に順次採用された。「ISO規格に採用されると、当該製品の環境負荷低減アピールが容易となり輸出促進に大きく貢献する。また、めっき鋼板は広く社会で使用されている鋼材。社会環境の持続可能性の観点からも、意義のある提案ができた」
標準化活動の開始から約6年10ヶ月。とにかく忙しかった、と振り返る一方で発行された規格を手に取る瞬間はささやかな達成感があると話す。「標準化活動では、該当分野の専門的知見だけでなく、英会話、文章の作成能力、コミュニケーション能力、調整・交渉能力など多方面の能力が必要となる。まずは活動に参加してみること。そして、先輩から技を盗むことが重要。どんな話し方をしているか? どんな資料のまとめ方をしているか? ぜひ近くで観察して」と次世代へのアドバイスを語った。
| 1984年~2000年 | 日新製鋼 |
| 2015年~2017年 | 日新製鋼 本社 品質保証・技術サービス部 |
| 2015年~2017年 | 一般社団法人鉄鋼連盟標準化センターF1.03分科会(薄板・めっき分野)亜鉛めっき鋼板規格WG 委員 |
| 2015年~2017年 | F1.03分科会 塩ビ鋼板規格改正WG及び腐食促進試験WG 委員 |
| 2015年~2017年 | F1.04分科会 (特殊鋼・棒線分野)委員 |
| 2018年 | 一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター事務局 出向 |
| 2018年~2021年 | ISO/TC 17(鋼)/SC 12(連続圧延薄鋼板)日本代表 |
| 2018年 | ISO/TC 17/SC 9(ぶりき及びぶりき原板)日本代表 |
| 2018年~現在 | ISO/TC 17/SC 9 国際幹事 |
| 2018年~現在 | F1.03分科会(薄板・めっき分野)主査 |
| 2018年~現在 | 一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター事務局 転籍 |
| 2019年〜現在 | ISO/TC 102(鉄鉱石及び還元鉄)/SC 3(物理試験方法)日本代表 |
| 2019年〜2021年 | ISO/TC 102/SC 3/WG 21(パウダー法による体積測定法)コンビーナ |
| 2021年〜現在 | ISO/TC 17/SC 12 国際幹事 |
最終更新日:2023年3月30日