経済産業大臣表彰 荒木 建次(あらき けんじ) 氏
国立大学法人宮崎大学 工学教育研究部 特別教授
IEC/TC 82の規格を整備し、太陽光発電の標準化を推進
太陽の光エネルギーを電気に変換する「太陽光発電」は、代表的な再生可能エネルギーの一つとして知られている。国立大学法人宮崎大学 工学教育研究部 特別教授の荒木建次氏は、IEC/TC 82(太陽光発電システム)/WG 7(集光型太陽光発電作業部会)で型式認証規格(IEC 62108 Ed.3)、安全性試験規格(IEC 62688 Ed.2)をはじめ計10件の規格作成と維持更新に携わり、経済産業大臣表彰を受賞した。
太陽光発電は、火力発電と比較して化石燃料使用による温室効果ガスが発生しないことや、原子力発電と比較して放射能リスクがないこと、水力発電と比較して設備建設のコストがかからないことから急速に普及し、新たな発電方式として注目されている。さらに、ペロブスカイトなどの新材料や新構造、壁面や営農ソーラーシェアリングなどの新しい設置方法、可搬性太陽電池や曲がる太陽電池などの新構造なども登場しているが、これらは材料やデバイス構造からくる特性の違いや太陽エネルギー利用方法の違いなどから、必ずしもこれまでの太陽電池やソーラーパネルの延長で論じることができなかった。そして、設置場所や天候により発電量が変化する点など、解決すべき課題を多く抱えていた。
荒木氏はこれらの課題に取り組むことで太陽光発電普及に貢献するとともに、製品の性能を公正に計測・評価するための仕組みづくりに従事。2004年から19年あまりにわたって標準化に取り組んでいる。


2018年10月に韓国・釜山で開催されたIEC/TC 82の集合写真(写真提供はすべて荒木建次氏)
荒木氏は、太陽光発電の業界ならではの特徴があり、これが標準化を難しくしていると指摘する。「太陽光発電に関するアイデアは、大学などの研究機関や専門メーカーはもちろん、いわゆる“街の発明家”と呼ばれる人たちからも続々と出ています。画期的な発見として注目を集めたものの、数年後には跡形もなく消滅してしまうといったケースが少なくありません。また、エネルギー分野での比較は発電量が重要で、少しでも効率よく、大量の電気を発生させることができる製品が求められます。そこで、標準化によって公正な“ものさし”を作り、正確・公平な形で性能比較できる仕組みを構築するため活動を開始しました」。
標準化が始まる前は、それぞれの企業や研究機関が独自に決めたルールに基づく発電量測定が行われていたため、製品を導入したものの期待していた発電量に届かず、ユーザーが失望して去ってしまう例も多かったという。「このままではいけない」という危機感が活動を後押しした。
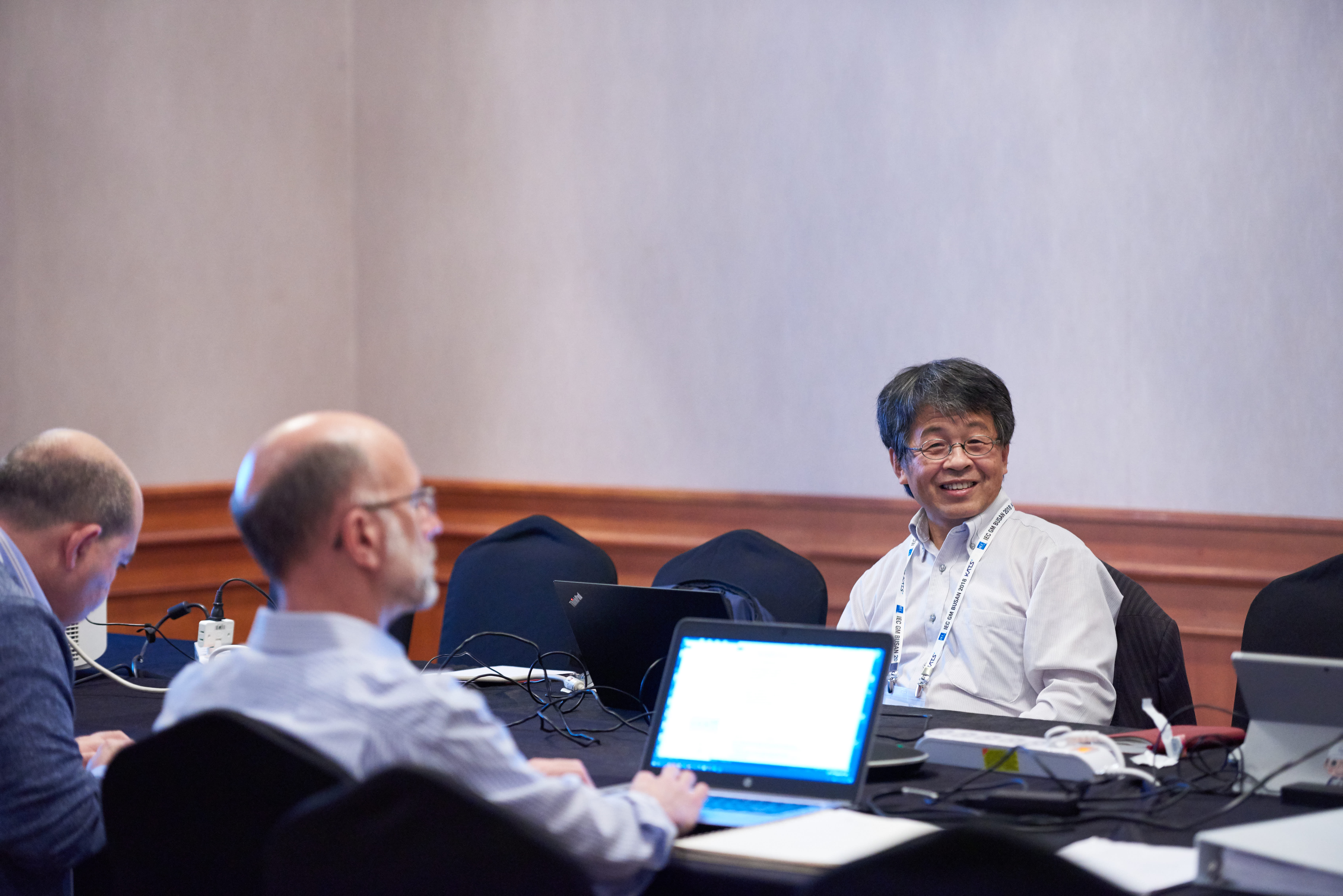
2018年10月に韓国・釜山で
開催されたIEC/TC 82のWG 7
ミーティング
2020年5月、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外渡航自粛により
WG 7ミーティングもWeb会議に移行。画面上段中央が荒木氏。
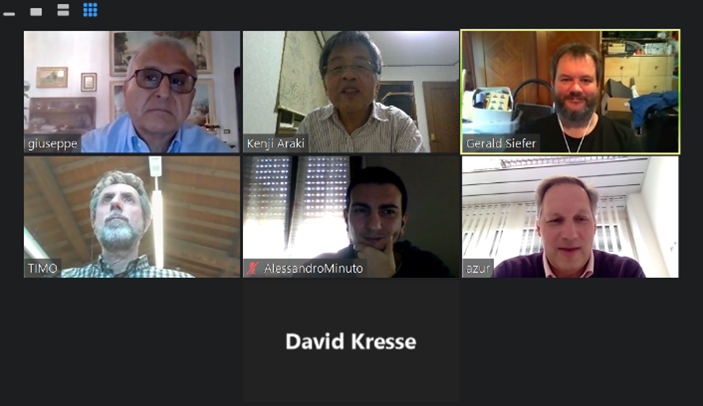
公正な測定を徹底し、正当な評価によって信頼を得る
標準化を進めるにあたり、荒木氏が最も心がけたポイントとして「公正」が挙げられる。 「正しく測定し、評価するためのルール整備は、太陽光発電に関わる全ての人々にとっての“幸せ”につながると思います。私は当初、企業の開発担当として参加したのですが、本分野は技術競争が非常に激しく、測定成績は製品の売上げに直結し、場合によっては企業の存亡にかかわるほど重要な意味を持っています」。
企業にとって、少しでも自社に有利な形で標準化したいと考えるのは当然であろう。しかし、それはあくまで正確な測定と客観的な評価に基づいて行われるものであるべきだ。公正な枠組みのなかで各企業が競い合う環境をつくることで、ユーザーも安心して製品を導入することが可能になる。
規格の策定でも、荒木氏は「公正」を意識して臨んだ。「特定の技術、特定の企業に有利な規格にならないよう注意しました。これはある意味、私が嫌われ者になることとも言えますが、もし公正ではない規格が作られ、実際よりも優れた評価結果が出た場合、その評価結果を信じるユーザーを裏切ることになってしまいます」。

2022年11月、名古屋で開催された「第33回太陽光発電国際会議(PVSEC-33)」では車載用太陽電池の国際標準化に関する学会発表を行った。
また、標準化の過程では、製品を開発する企業や団体との意見調整に苦心したと振り返る。例えば試験条件を決める段階では、新たに開発した製品の高性能をアピールするため、日本ではあり得ない天候下でのデータが他国の企業団体から提示されたことがあったという。このような行為はユーザーを裏切ることにつながり、ひいては太陽電池自体の信用を失うことにもつながってしまう。そのため荒木氏は明確な科学的根拠を要求し、データの科学的妥当性を確認した。
標準化活動は技術進歩を俯瞰する大きなチャンス
荒木氏はIEC/TC 82/WG 2(非集光型モジュール)で、新しい市場である車載用太陽電池のTR(技術報告書)2件を提案し、グループのプロジェクトリーダーとして活躍している。今後の展望について次のように見解を語った。「集光型システムは、日本では維持・更新が中心で、新規開発はほぼ完了している状況です。これに代わり、自動車の屋根などに設置する車載用太陽電池が注目されており、今後はその標準化が大きなテーマになってくると考えています」。そして、標準化人材の育成では、次世代を担う若手が活躍できる環境づくりをめざす。具体的には標準化委員や国内委員代表に就かず、標準化委員会などの求めに応じて助言やアドバイスを行う役割を担いたいとしている。
車載用太陽電池国際標準化関係者、車載用太陽電池研究者との学会打ち上げランニング。会議以外での親睦活動やコミュニケーションで互いの信頼関係を築くことも大切である(名古屋城周回コース、2022年11月)
これから標準化に携わる人たちへのメッセージとしては、とくに企業の研究者たちに向けた言葉を寄せた。「本分野は技術進歩が早く競争も激しいため、私を含め、研究に没頭して周囲の状況が見えなくなってしまう人が多いと感じます。標準化活動はこのような日常から一歩離れ、冷静な視点で世界の技術進歩を俯瞰できるチャンスなので、ぜひ積極的に参加してほしいと願っています」。
最後に、今回の受賞については、「思っていた以上に、大学関係者の皆さんに喜んでいただきました。標準化自体はボランタリーで進める活動なので、現状では研究論文などの成果にはなりませんが、長年の努力が一つの成果として評価されたことをうれしく思います」。
今後も宮崎を拠点に研究を継続したいと抱負を語る荒木氏。「日本のひなた」と呼ばれる地で、太陽光に向き合う日々を送りたいと語った。
| 1984年4月~1993年12月 | 株式会社東芝に入社(その後事業部分社化に伴い東芝ライテック株式会社に転属) |
| 1994年1月~2020年6月 | 大同特殊鋼株式会社に入社 |
| 2020年7月~2020年9月 | 宮崎大学 研究員 |
| 2020年10月~現在 | 宮崎大学 特別教授 |
| 2004年4月~2017年5月 | IEC/TC 82(太陽光発電システム)/WG 7(集光型太陽光発電作業部会)エキスパート |
| 2017年6月~現在 | IEC/TC 82/WG 7 プロジェクトリーダー |
| 2017年6月~現在 | IEC/TC 82/WG 7 コンビーナ |
| 2020年7月~現在 | IEC/TC 82/WG 9(支持構造物作業部会)エキスパート |
| 2021年4月~現在 | IEC/TC 82/PT 600(車載用太陽電池プロジェクトチーム)プロジェクトリーダー |
最終更新日:2024年4月24日