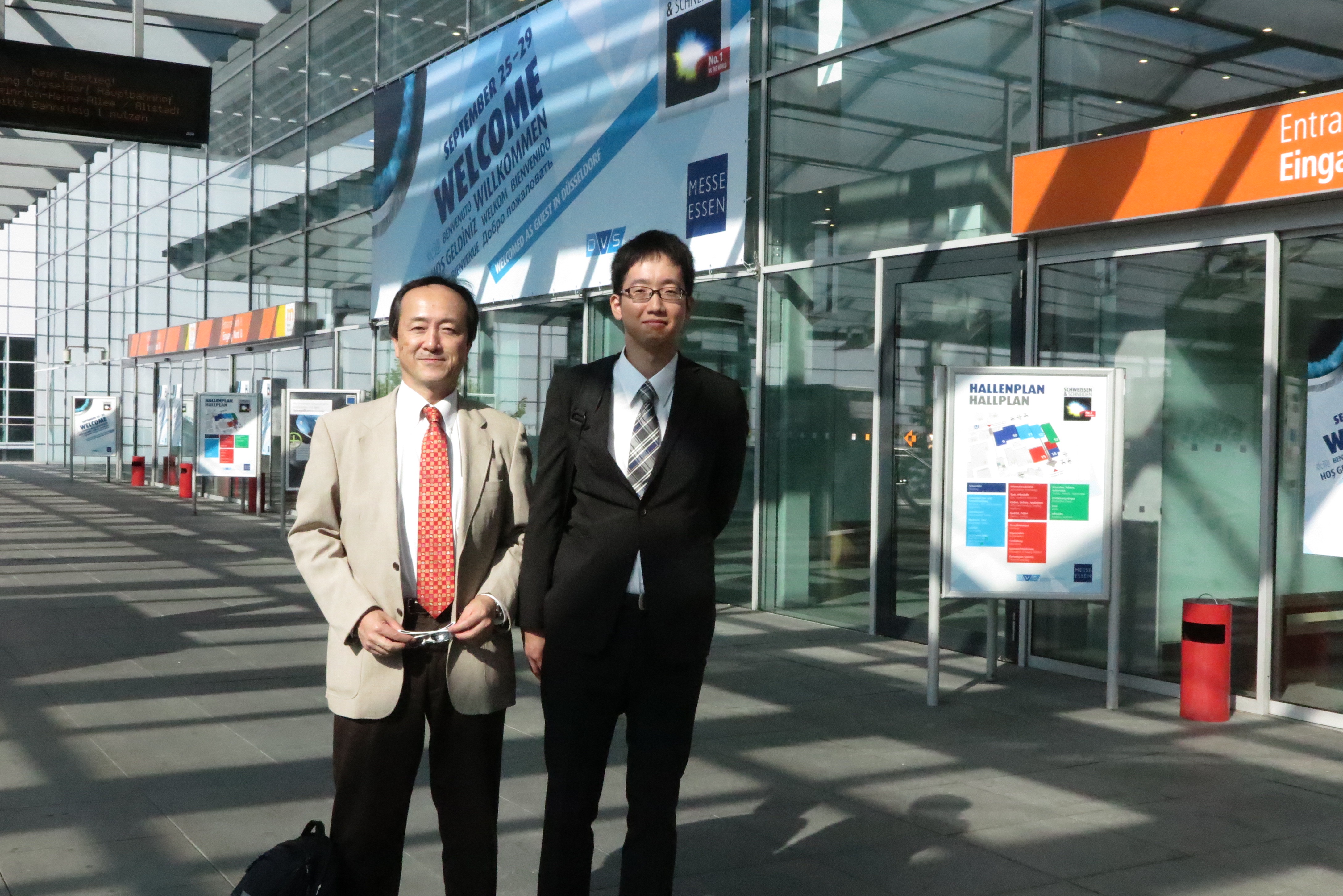経済産業大臣表彰 上本 道久(うえもと・みちひさ)氏
化学計測手法、分析器具や標準化物質の標準化に取り組む
化学計測手法の標準化は、日本において製品や材料の標準化と比べると影が薄い。その中で、25年余り、非鉄金属材料分野や分析化学分野など、複数の関連団体で委員長等を務め、化学計測の分析法にとどまらず、分析器具や標準物質に関する標準化を推進してきたのが経済産業大臣表彰を受けた明星大学の上本道久氏だ。
上本氏は、ISO/TC 79(軽金属及び同合金)/SC 5(マグネシウム及びマグネシウム合金)/WG 4(マグネシウム分析)で9年間にわたりコンビーナを務め、同合金に含まれる極微量の水銀定量方法の国際規格(ISO 20260)をプロジェクトリーダーとして制定した。またISO/TC 79/SC 1(アルミニウム分析)では分科会の再活性化を主導し、議長に就任し、同合金中の一斉定量法の規格化に取り組む。なお、これに先立ち、国内ではJISの水銀の定量方法(JIS H 1370)について委員長として改正している。
さらにISO/TC 44(溶接)/SC 13(ろう付け材料及びプロセス)では、プロジェクトリーダーとしてISO 5179(ろう付け性の試験方法)を改訂。日本提案によるISO 17672(ろう材-溶加材)をエキスパートとして改訂し、日本発のろう材料が国際的に使われる条件を整えた。これらの標準化は、高機能化が進む非鉄金属材料の品質を安定させる上で不可欠で、その功績は極めて大きい。


2013年9月、フランス・パリで開催されたISO/TC 79全体会議での集合写真(後列左から4番目が上本氏)
写真提供:上本道久氏
2017年9月、ドイツ・アーヘンで開催されたISO/TC 44/SC 13会議後、指導してきた日本人若手出席者と(左が上本氏)
写真提供:上本道久氏
上本氏は「化学計測の標準化は、企業にとって利益に直結しないと思われがちです」と語る。しかし、分析法が標準化されていれば、輸出入どちらでも一度の測定で品質を保証することが可能だ。規格に準拠した分析を行うことで、製造した材料や製品が国際的に規格化された合金に合致することが保証され、日本企業はビジネスを優位に進めることが可能になる。
経営者に向けては化学計測の標準化の必要性を説き続け、
国際会議で積極的な役割を果たすことが標準化活動では重要となってくる
標準化の活動を行う上で、上本氏は「あきらめずに、持続的に、楽観的に」をモットーにしてきた。企業を中心に関係者に標準化の意義を伝え、化学計測の標準化の必要性を説いてきた。残念なことに、日本企業は標準規格の否定はしないものの、積極的な関与は不要と考えている経営者が少なくない。
「国内委員会に出てくる企業委員は非常に優秀な人がたくさんいるのです。ところが経営層が集まる上層委員会で講演しても軽く受け流されてしまうところがあります。そこで、標準化への取組が不十分で、ビジネス面でダメージを受けたに日本企業を例に出しながら、経営層が理解できるように、あきらめずに標準化の意義を説明し続けてきました」。
規格化には他国のキーパーソンとの信頼関係や、日本提案なら問題なく意義があるというイメージを持ってもらうことも大切だ。そこで上本氏は毎年日本提案を発表し続けた上で、国際幹事や議長に就任して以降は他国の要望に理解を示しつつ、規格を良い方向に修正するという包容力を意識しながら、SCやWGを運営してきた。

2019年11月、アメリカ・シカゴで開催されたISO/TC 79全体会議後の集合写真(右から4番目が上本氏)
写真提供:上本道久氏
2023年10月、フランス・パリで開催されたISO/TC 79/SC 1会議での集合写真(前列左から2番目が上本氏)
写真提供:上本道久氏
「特にマグネシウム材料は原産国である中国の発言力が強いことから、まず信頼関係を築いて規格化を進めてきました。また、欧州のメンバーはどうしても『アジアで勝手にやっている』と批判しがちなので、そちらへの説明にも腐心しました。ISO会議はまさに『技術外交』の場です。誰がどの会議に参加していたのかは重要で、その証拠となるよう集合写真は必ず撮ってきました。最近ではオンライン参加と対面参加のハイブリッド会議が増えていることから、本人が参加した証としての集合写真の重要度が高まっています」。
日本がISOで主要なポジションを占めるようになると、関心が薄かった産業界の動きも変わってくる。「2年ほど前からISO/TC 79/SC 1の議長を務めています。日本人が分科会の再活性化を主導して議長になり、日本アルミニウム協会が事務局になったことで関係企業の皆さんも標準化活動に関心を持つようになっています」。
大学、大学院での標準化教育の強化や海外で標準化が企業の利益に直結することを学ぶことが大切
これから重要になるのは、高等教育段階での標準化教育である。しかし、現在、日本の大学で標準化に関する教育を行っているところは数少ない。標準化教育を受けていない学生は就職して企業の技術者になると、知識もないのに、標準化の委員会に派遣される。ところが、日本では標準化活動が専門的な、報酬に値する仕事としてみなされておらず、本務の合間に行う慈善的な社会活動のような扱いとなっている。「製品開発で利益を得られるようなテーマであれば別ですが、特に化学計測のような基礎科学領域の標準化活動はなかなか理解されません。そのため、技術者が委員として出てきても、翌年には交代してしまうことも多く、活動の経験が蓄積されません」。
その背景には標準化に関わる国立の専門機関が非常に脆弱なこともあるだろうと上本氏は考えている。
「米国の国立標準技術研究所(NIST)は3,400名が活動していいます。ドイツは2つの系統の標準研究所(BAM、PTB)があって合計で3,600名、イギリスも2系統(LGC、NPL)で合計2,200名です。それに対して日本の産業技術総合研究所 計量標準総合センター(NMIJ)は約300名で、欧米の10分の1程度。標準技術への理解を元にNMIJの増員強化を図ることが急務です。また標準化活動を支える国立標準機関(標準局)は、米国(ANSI)、ドイツ(DIN)、フランス(AFNOR)はもとより中国(SAC)や韓国(KATS)にも存在しますが、日本では該当組織を見出すことができません。他国と互して標準化を推進するためには、国立標準機関にプロジェクトごとのキーパーソンを置いて、関与しうる専門家を個別に招集して標準化活動に関わらせる形で活動を活発にしていく必要があります。標準化機関に大きな意義を見いだして整備してほしいと思います」。
そのような知的基盤の向上こそが国力に直結すると上本氏は述懐している。

2024年10月、中国・北京で開催されたISO/TC 79/SC 1会議で委員のプレゼンテーションに対してコメントする上本氏(写真左)
写真提供:上本道久氏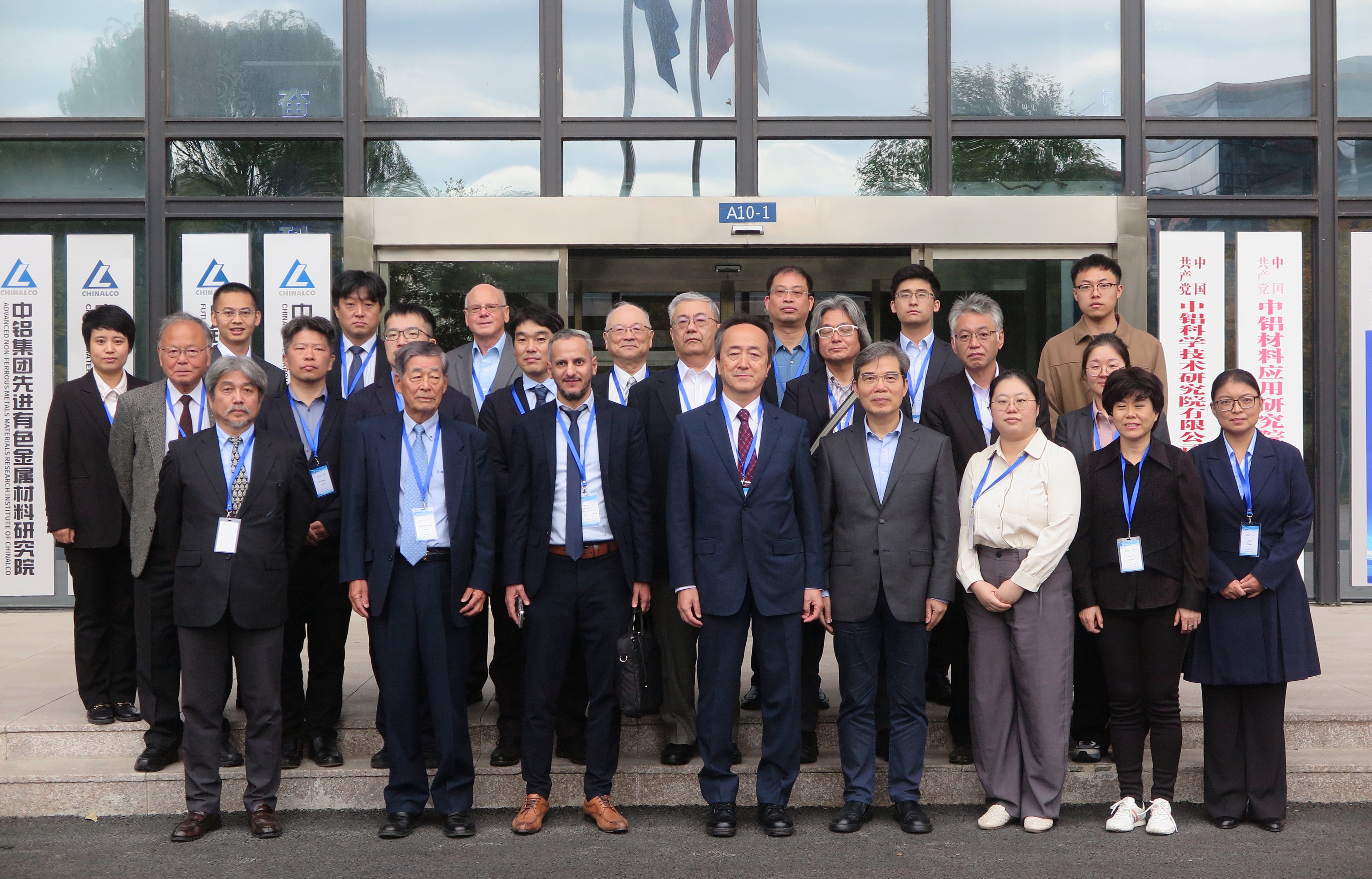
2024年10月、中国・北京で開催されたISO/TC 79全体会議後の集合写真(前列中央が上本氏)
写真提供:上本道久氏
「私が期待しているのは、これから第一線で活動しようとする若い人たちです」と上本氏は語る。
「若いうちに外国に行って、標準化の取組についての見聞を深めてほしい。短期間の留学でも海外に出て行けば、計測分野の標準化は利益にならないという思い込みで凝り固まっている日本企業とは全く異なる世界があることがわかります。それが日本の産業界を救う力になると確信しています」。
| 1987年4月~2017年3月 | 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 研究員 |
| 1996年3月~2012年12月 | 産業技術連携推進会議 知的基盤部会分析分科会 運営委員 |
| 1998年7月~2017年6月 | 日本溶接協会貴金属ろう部会技術委員会分析委員会(分析法標準化委員会)委員 |
| 1999年7月~2014年6月 | 経済産業省 計量士国家試験委員 |
| 2002年8月~2004年1月 | 日本分析化学会 河川水標準作成小委員会委員 |
| 2005年4月~現在 | 日本マグネシウム協会 分析委員会(分析法標準化委員会)委員(2006年4月より委員長) |
| 2005年4月~2008年6月 | JIS H 1342(マグネシウム及びマグネシウム合金中のすず定量方法)原案作成委員長 |
| 2005年4月~2008年6月 | JIS H 1343(マグネシウム及びマグネシウム合金中の鉛定量方法)原案作成委員長 |
| 2005年7月~2006年3月 | JIS K 0133(高周波プラズマ質量分析通則)改正原案作成委員 |
| 2006年4月~2009年7月 | JIS H 1370(アルミニウム及びアルミニウム合金中の水銀定量方法)改正原案作成委員長 |
| 2006年4月~2007年3月 | JIS Z 3910(はんだ分析方法)改正原案作成委員 |
| 2007年4月~2009年7月 | JIS H 1344(マグネシウム及びマグネシウム合金中のカドミウム定量方法)原案作成委員長 |
| 2007年4月~2009年7月 | JIS H 1339(マグネシウム及びマグネシウム合金中のベリリウム定量方法)原案作成委員長 |
| 2007年9月~現在 | 日本アルミニウム協会 分析委員会(分析法標準化委員会)委員(2009年4月より委員長) |
| 2009年10月~2015年2月 | ISO/TC 79(軽金属及び同合金)/SC 5(マグネシウム及びマグネシウム合金)/WG 4(マグネシウム分析)委員 |
| 2009年12月~2017年6月 | 日本溶接協会貴金属ろう部会技術委員会規格調査委員会 委員 |
| 2010年4月~2012年3月 | 日本産業標準調査会(JISC)非鉄専門委員会委員 |
| 2011年4月~2012年2月 | JIS K 0970(ピストン式ピペット)改正原案作成委員 |
| 2011年4月~2016年3月 | 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター城南支所 支所長 |
| 2011年4月~2016年3月 | 東京都城南地域中小企業振興センター長 |
| 2011年8月~2019年7月 | ISO 20260(マグネシウム及びマグネシウム合金-水銀の定量)発行 プロジェクトリーダー |
| 2011年12月~2012年11月 | JIS H 8682-1(アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の耐摩耗性試験方法 —第1部:往復運動平面摩耗試験)原案作成委員 |
| 2011年12月~2012年11月 | JIS H 8682-2(アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の耐摩耗性試験方法 —第2部:噴射摩耗試験)原案作成委員 |
| 2011年12月~2012年11月 | JIS H 8682-3(アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の耐摩耗性試験方法 —第3部:砂落し摩耗試験)原案作成委員 |
| 2011年12月~2012年11月 | JIS H 8683-1(アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の封孔度試験方法 —第1部:染料吸着試験)原案作成委員 |
| 2011年12月~2012年11月 | JIS H 8683-2(アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の封孔度試験方法 —第2部:リン酸-クロム酸水溶液浸せき試験)原案作成委員 |
| 2011年12月~2012年11月 | JIS H 8683-3(アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の封孔度試験方法 —第3部:アドミッタンス測定試験)原案作成委員 |
| 2012年6月~2013年2月 | JIS K 0216(分析化学用語(環境部門))改正原案作成委員 |
| 2012年6月~2013年3月 | JIS K 0116(発光分光分析通則)改正原案作成委員 |
| 2013年3月~現在 | 日本分析化学会 標準物質委員会 委員長 |
| 2013年3月~現在 | ISO/REMCO(現 ISO/TC 334(標準物質))国内審議委員会委員 |
| 2013年6月~2024年6月 | 日本溶接協会 規格委員会委員 |
| 2013年12月~2017年6月 | 日本溶接協会 ろう部会規格調査委員会 主査 |
| 2014年4月~2016年3月 | JIS H 1322(マグネシウム及びマグネシウム合金-スパーク放電発光分光分析方法)改正原案作成委員会 委員長 |
| 2015年2月~現在 | ISO/TC 79/SC 5/WG 4 コンビーナ |
| 2015年4月~2015年11月 | JIS Z 3910(はんだ分析方法)改正原案作成委員 |
| 2015年5月~2017年3月 | JIS H 1331(マグネシウム及びマグネシウム合金-分析試料採取方法及び分析方法通則)改正原案作成委員会 委員長 |
| 2015年10月~現在 | ISO/TC 79 委員 |
| 2016年6月~2023年11月 | ISO/TC 44(溶接)/SC 13(ろう付け材料及びプロセス)委員 |
| 2016年7月~2017年3月 | JIS Q 0033(標準物質-標準物質の適正な使い方)改正原案作成委員会 委員 |
| 2016年7月~2017年3月 | JIS Q 0031(標準物質-認証書、ラベル及び附属文書の内容)改正原案作成委員会 委員 |
| 2016年7月~2017年3月 | JIS Q 0030(標準物質-選択された用語及び定義)改正原案作成委員会 委員 |
| 2016年9月~2021年3月 | ISO 5179(広がり及びギャップ充填試験によるろう付け性の調査)改訂発行 プロジェクトリーダー |
| 2017年2月~2017年10月 | JIS H 1501(ホワイトメタル分析方法)改正原案作成委員会 委員長(最終的に改正せず) |
| 2017年4月~現在 | 明星大学理工学部総合理工学科 常勤教授 |
| 2017年7月~2024年6月 | 日本溶接協会ろう部会 規格調査・分析委員会主査 |
| 2018年4月~2020年3月 | 日本分析化学会標準物質委員会にマグネシウム標準物質作製委員会 委員長 |
| 2018年4月~2023年6月 | ISO 17672(ろう付-溶加材)改訂プロジェクト 専門委員 |
| 2020年7月~2021年3月 | JIS Q 0035(標準物質-値付け並びに均質性及び安定性の評価に関する手引)改正原案作成委員会 委員 |
| 2021年10月~2023年12月 | JIS H 6201(化学分析用白金及び白金合金器具)JIS改正原案作成委員会 委員長 |
最終更新日:2025年4月1日