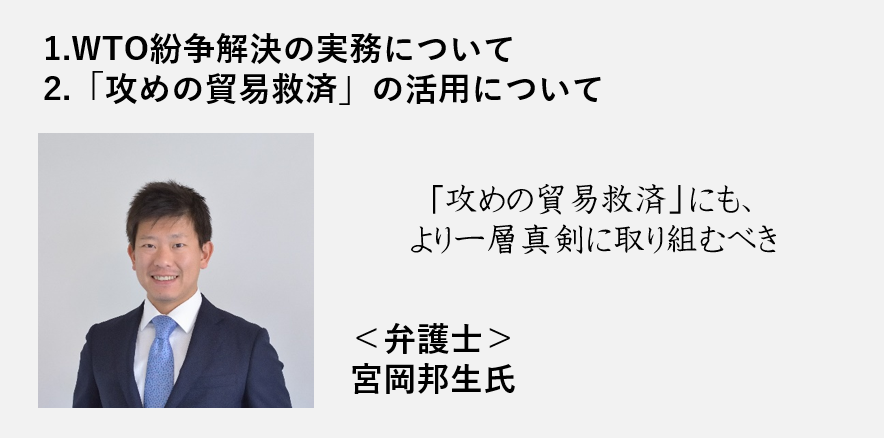
CONTENTS
今回は特別号として、普段お届けしている申請書作成に向けた具体的な解説とは趣向を変えて、そもそも貿易救済措置はなぜ重要なのか、また、WTO交渉が行き詰まる中で貿易救済措置にどのような役割が期待されるのか、といった点について、より身近に感じていただけるように、元WTO上級委員会事務局法務官で弁護士の宮岡邦生氏のコラムをご紹介いたします。
宮岡弁護士は、スイス・ジュネーブのWTO上級委事務局へ法務官として3年間赴任し、WTO協定に基づく国家間紛争解決(DS)手続に従事された後、本年(2020年)4月から日本での弁護士業務に復帰されました。
本コラムの「1.WTO紛争解決の実務について」では、まず宮岡氏のWTOの法務官等としての経験に基づき、WTO紛争解決の現場では日々何が行われているのかをご紹介いただき、通商紛争をめぐる各国の応酬を間近に感じていただきたいと思います。
「2.「攻めの貿易救済」の活用について~経済・外交のツールとして~」では、今日の世界貿易が、ナショナリズムの台頭や多国間貿易体制の揺らぎなど様々な課題に直面する状況下、通商法実務の最前線に身を置いてきた中で、アンチ・ダンピング等の貿易救済について感じたことをお寄せいただきました。
宮岡弁護士は、スイス・ジュネーブのWTO上級委事務局へ法務官として3年間赴任し、WTO協定に基づく国家間紛争解決(DS)手続に従事された後、本年(2020年)4月から日本での弁護士業務に復帰されました。
本コラムの「1.WTO紛争解決の実務について」では、まず宮岡氏のWTOの法務官等としての経験に基づき、WTO紛争解決の現場では日々何が行われているのかをご紹介いただき、通商紛争をめぐる各国の応酬を間近に感じていただきたいと思います。
「2.「攻めの貿易救済」の活用について~経済・外交のツールとして~」では、今日の世界貿易が、ナショナリズムの台頭や多国間貿易体制の揺らぎなど様々な課題に直面する状況下、通商法実務の最前線に身を置いてきた中で、アンチ・ダンピング等の貿易救済について感じたことをお寄せいただきました。
1.WTO紛争解決の実務について
WTOには、加盟国間の貿易紛争をWTO協定に基づいて裁定する二審制の国家間紛争解決(DS)手続が置かれており、第一審をパネル、第二審を上級委員会と呼んでいる。筆者は、第二審の上級委員会の法務官として、約3年間にわたり、判事にあたる上級委員への法的助言や判決の草案作成といった業務に従事した。WTOのDS手続は、国際法の歴史を通じて最も成功した国家間紛争解決システムといわれる。実際、1995年のWTO設立以来600件近い紛争がDSに付託されており、国際司法裁判所(ICJ)など他の国家間裁判機関と比較しても圧倒的に多くの事件が日常的に取り扱われている。こうした活発な制度利用の背景には、手続が高度に司法化されているため、ともすれば政治問題化しがちな機微な紛争であっても、WTO協定に基づいて粛々と処理することができ、この点が加盟国から重宝されていることが挙げられる。日本も常連ユーザー国のひとつであり、最近でもアンチ・ダンピング等の貿易救済案件をはじめ、概ね年間1、2件のペースで紛争をDSに付託している。DSの実務については、筆者自身、WTOでの勤務時はもちろん、日本政府での勤務時にもジュネーブに出張して口頭弁論を担当するなど数多くの現場を経験した。一連の経験を通じて実感するのは、DSに関わるプロ同士の信頼関係が、DS制度の屋台骨を支えているということである。もちろん、国家の重要な利害が俎上に載せられる以上、口頭弁論などの場面で、紛争当事国の担当官同士で激しい論戦が繰り広げられることは珍しくない。
しかし、それはあくまで通商法のプロとしての議論であり、相手を中傷誹謗したり政治問題をあげつらうようなことはなく、WTO協定に基づく論理のみによって勝負するとの考え方が貫かれていることがDSの大きな特徴となっている。むしろ、論戦が激しければ激しいほど、何日にもわたる口頭弁論が終わる頃には、自然とお互いへのリスペクトが沸き上がり、最後は互いの健闘を称え合いながら握手して別れるのが慣例となっている。
このようなプロ同士の信頼関係に基づいて貿易紛争を解決し、ひいては世界平和に貢献できるというのが、WTO DSに携わる者の醍醐味といえる。
2.「攻めの貿易救済」の活用について~経済・外交のツールとして~
中国が豪州産ワインに11月28日から最大200%を超えるアンチ・ダンピング関税を課すことになったというニュースが、通商法関係者の間でちょっとした話題になっている。豪州産ワインが中国に不当に安く輸入されており、国内のワイン産業に損害が生じていることを理由とする。中国産ワイン?と一瞬首を傾げる人も多いと思うが、調べてみると、中国でもワイン生産はそれなりに盛んらしい。もっとも、各種報道などによれば、中国による今回の措置は、必ずしも国内のワイン生産者の保護だけを目的としたものではなく、豪州との政治的緊張の高まりを背景としたものといわれている。中国政府は、豪州が、武漢におけるコロナウイルスの感染拡大に対する中国当局の責任の調査を主張したり、通信規格5Gの整備事業からファーウェイを排除する方針を打ち出したことへの苛立ちを強めている。
そこで、豪州の特産品であるワインに高率の追加関税を課して中国市場から締め出すことで、経済的・政治的な揺さぶりをかける狙いがあるというのである。豪州も負けてはおらず、中国の措置についてWTO提訴する可能性も示唆している。
この例はやや特殊な事例かもしれないが、アンチ・ダンピングをはじめとする貿易救済措置は、世界各国で、自国産業の競争力を維持・促進するためのツールとして日常的に利用されている。貿易救済は技術的な世界であり、発動国の調査当局にもそれなりの専門的知見が必要とされる。
ただ、中国による今回の措置などを見ると、新興国の間でも近年知識や経験の蓄積が急速に進み、単なる個別産業の保護という本来の目的だけでなく、政治や外交のツールとしても自由自在に使いこなすようになってきていることを実感する。また、こうした措置がWTO提訴されたときに、パネルや上級委員会によってどのような法的判断がなされるのか、それを見越して当事国がどう行動するのかといった点も、通商法関係者としては興味深い。
輸出国である日本は、これまで、諸外国と比較してアンチ・ダンピング等の発動に比較的謙抑的であり、むしろ他国の問題措置をWTO提訴するなど守りの姿勢を重視してきた。しかし、新興国の経済的台頭や各国による貿易救済の積極活用傾向も背景に、政府・民間企業を問わず、経済や外交のツールとしての「攻めの貿易救済」にも、より一層真剣に取り組むべき時期に来ているように思われる。
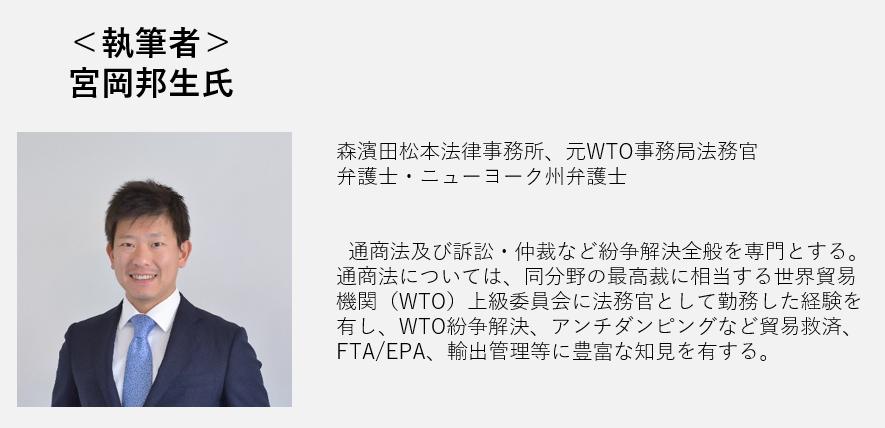
最終更新日:2022年9月12日