
2024/11/28
2024年10月18日(金)、国内最大規模のIT・エレクトロニクスの総合展『CEATEC 2024』において、GENIAC採択事業者が登壇する講演会が開催されました。5つのプログラムでは、第1期の成果報告のほか、第2期採択事業者のプレゼンテーションやパネルディスカッションを通じてGENIACの取り組みが紹介されました。
『ニッポンの生成AI開発力を解き放つ』〜 経済産業省・NEDOが進める生成AI開発支援プロジェクト"GENIAC"の現在地

プログラムの第1部では、経済産業省 渡辺 琢也氏が「GENIAC事業の背景・目的とこれまでの取り組み・成果」をテーマに基調講演を行い、経済産業省とNEDOがGENIAC事業を開始した背景や目的について説明しました。また、2024年8月に終了したGENIAC第1期における採択事業者が世界水準に匹敵する4桁億パラメータの大規模基盤モデルの開発に成功したことなど、これまでの成果についても言及しました。

引き続き行われたパネルディスカッションでは、渡辺氏がファシリテーターを務め、第1期の採択事業者である株式会社Preferred Elements 岡野原 大輔氏、ストックマーク株式会社 林 達氏、東京大学大学院工学系研究科 松尾 豊氏に加え、ハイパースケーラーからGoogle Cloud安原 稔貴氏が登壇しました。トークテーマとして、GENIACの意義や参加理由、第1期で得た学びや課題の克服方法、現在進めているプロジェクト、そして今後の課題について活発な議論が行われました。
GENIACにおける基盤モデル開発企業の開発成果

第2部では、GENIAC第1期で採択された事業者による開発成果のプレゼンテーションが行われました。株式会社Preferred Elements 岡野原 大輔氏は、第1期では1,000億/1兆パラメータからなる大規模マルチモーダル基盤モデルを国内でゼロから構築できる技術基盤を確立し 、1000億パラメータモデルでは日本語性能のベンチマークで世界最高性能を達成したことを報告しました。また、第2期では、最高レベルの日本語性能を1/10の推論コストで実現することを目指していると述べました。

ストックマーク株式会社 林 達氏は、生成AIサービスの利用が進まない主な要因として「ハルシネーション」を挙げ、ビジネスシーンに特化し、時事的な話題やビジネス常識にも強い100BパラメータのLLM(大規模言語モデル)を国内で初めて開発したことを紹介しました。さらに、RAGシステムや独自のLLM開発に向けた企業との協業も進行中であると報告しました。

株式会社ABEJA岡田 陽介氏は、LLMの開発と社会実装における壁についてプレゼンテーションを行い、LLMの精度とコストのトレードオフを解決するためには、個別モデルの開発コストを抑えつつ、RAG+Agentの精度向上が必要であると説明しました。また、LLMをBPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)として活用することで、労働生産性の劇的な向上を目指していると述べました。

富士通株式会社 白幡 晃一氏は、非構造データの活用や規制遵守といった企業ニーズに応える特化型基盤モデルの開発について説明し、GENIAC第1期で「ナレッジグラフ生成LLM」と「ナレッジグラフ推論LLM」の2つを構築し、日本語性能のベンチマークで世界最高性能を達成したことを報告しました。また、日本語に特化した企業向けLLM「Takane」(高嶺:タカネ)の提供開始も発表しました。

株式会社Kotoba Technologies Japan 笠井 淳吾氏は、スパコン「富岳」を活用した国産LLM開発を皮切りに、GENIAC第1期ではEnd-to-Endでリアルタイム日英翻訳などが可能な音声基盤モデル「Kotoba-Speech」の開発に着手しました。第2期では、自治体・メディア・保険業界などで利用可能な音声翻訳モデルや、教育・コールセンター分野で活用できる音声チャットボットなどの商業化を推進していくと述べました。

Turing株式会社 山口 祐氏は、GENIAC第1期の成果として、完全自動運転に向けて視覚と言語を統合したマルチモーダル基盤モデル「HERON」の開発状況を報告しました。さらに、現実世界の物理法則や物体間の相互作用など複雑な状況を理解し、リアルな運転シーンを動画として生成する「Terra」との統合により、人間のような判断能力を持つ自動運転の実現を目指していくと説明しました。
生成AIの社会実装の現状・日本の勝ち筋

第3部では、GENIACの運営サポートを行うボストン コンサルティング グループ 中川 正洋氏が、「グローバルの最新動向と日本における社会実装の現状、今後の展望」をテーマに講演しました。中川氏は、生成AIが仕事に与える影響は主要国の中で日本が最も低く、不安を感じる割合が高いという調査結果を紹介しました。また、GENIACでは昨年までの実験的段階を経て、今年は企業変革に生成AIを活用する事例が増えていることを述べました。

続いて行われたパネルディスカッションでは、中川氏がファシリテーターを務め、「ユーザー企業の現状、各社の取り組み事例、ユーザー企業と開発企業の連携」というテーマで、白幡氏、岡田氏、ハイパースケーラーとして日本マイクロソフト 大谷 健氏が登壇しました。ディスカッションでは、この1〜2年の各社の動き、日本国内のプレーヤーの勝ち筋、社会実装を進めるための鍵についての議論が行われました。
社会実装の加速に向けたGENIACの今後の取り組み

第4部では、経済産業省情報処理基盤産業室 杉之尾 大介氏がGENIACの今後の展望について講演し、国内外の生成AI需要の見通しや、AI革命により再構築される利活用のバリューチェーンにおいて競争力を確保することの重要性について説明しました。GENIACでは、日本の生成AI開発力を強化するために計算資源の提供支援、データホルダーとの連携強化、AI開発コミュニティの交流促進を組み合わせた支援を実施し、第2期でも引き続き社会実装に向けた基盤モデル開発を目指す事業者に対して計算資源の提供などを行うと述べました。

続いて、第2期に採択された事業者によるプレゼンテーションが行われました。京都大学発のAIスタートアップ企業である株式会社データグリッド 斎藤 優氏は、画像・動画生成AIソリューション事業や製造業向けのAIデータ生成基盤について紹介し、GENIACではユーザーの意図通りに画像や動画内にデータを生成できるVision系基盤モデルのプラットフォームを開発、ディープフェイク検知が可能なAIモデルの構築も併せて実施、各業界に特化したプロダクトやソリューションを安全に提供することを目指していると述べました。

東京大学発のAIスタートアップ企業であるカラクリ株式会社 中山 智文氏は、日本のカスタマーサポート向けの高品質なAIエージェントの開発について説明しました。カスタマーサポート業界を取り巻く人材不足やストレスフルな職場環境、少子高齢化といった課題に対して生産性向上が急務であるとし、ハルシネーションを抑えつつ正確な日本語を扱えるローカルモデルの開発を目指していると述べました。GENIAC第2期では、カスタマーサポート特化の学習データセットとベンチマークの作成、開発ノウハウの公開を進める予定です。

SyntheticGestalt株式会社 島田 幸輝氏は、AI創薬実現のための分子情報に特化した基盤モデル開発について説明しました。現状では分子情報に関するデータが数十万件程度しか存在しないため、GENIACプロジェクトでは未知の化合物に対応可能な100億件以上のデータを学習した基盤モデル「SG4D10B」を開発し、創薬分野のベンチマークで世界のトップ3に入るパフォーマンスを目指していくと述べました。

続いて行われたパネルディスカッション「ユーザー企業から見たモーダル・領域の可能性」では、第2期の採択事業者である斎藤氏、中山氏、島田氏に加え、ユーザー企業側から中外製薬株式会社 石部 竜大氏、株式会社ベネッセコーポレーション 大塚 武氏、AGC株式会社 石原 俊也氏、ライオン株式会社 中林 紀彦氏が登壇しました。各ユーザー企業における生成AIの進展状況、特定のモーダル・領域型モデルの可能性やユースケース、日本での生成AI導入に関する課題とその克服方法についてディスカッションが行われました。
GENIACのデータ・AIの利活用促進に向けた支援~データ実証事業の取り組み
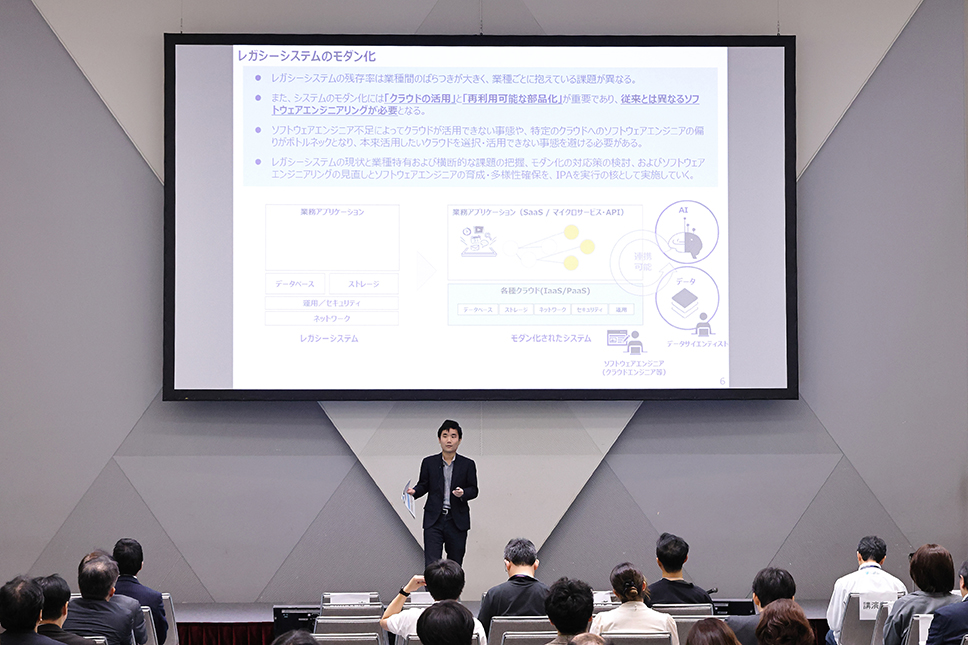
第5部では、経済産業省 杉之尾氏がGENIACのデータ・生成AI利活用実証事業の取り組みについて講演しました。生成AIの開発から利活用までのバリューチェーンに存在する各種の課題解決に向け、データ・生成AIの利活用にかかる実証調査事業を開始し、3つの形態の実証実験の成果を広く共有することを目指していくとしています。

続いて、データ・生成AIの利活用にかかる実証調査事業に採択された事業者によるプレゼンテーションが行われました。映像制作会社、株式会社オー・エル・エム・デジタル 四倉 達夫氏は、「アニメ×生成AI」の利活用可能性を徹底的に調査することを説明し、本プロジェクトではアニメ原画や仕上げなど各作業工程におけるAI活用と、AIを用いたキャラクター描画支援の2つのテーマについて、複数のアニメ会社に加え産官学連携のALL JAPAN体制で実証実験に取り組むと述べました。

クラウド録画ソリューションを提供するセーフィー株式会社 森本 数馬氏は、防犯カメラの映像データの分析を通じて、さまざまな業界の課題解決を促進する取り組みについて説明しました。現在、同社のサービスを利用しているデータホルダーやAI開発者と連携し、それぞれが抱えるプライバシー保護やデータ収集の課題を解決することを目指しています。実証実験では、同社が管理する映像を教師データとして、効率的かつセキュアなMLOpsシステムを開発し、建設分野での不安全行動検知と車両検知、介護分野での転倒検知の3つのテーマで効果を検証するとしています。

ソフトバンク株式会社 福地 健之氏は、国内の生成AI開発を加速するため、学習用データとして利活用できる新たなデータセット構築に関する包括的な調査を実施すると説明しました。
このデータセット構築は、マクロミルおよび日本トータルテレマーケティングと連携し、約3万人を対象に100万件以上のデータ収集を行う予定です。また、データセットの管理と利活用に向け、既存のクラウドに加え、ABCIや基盤モデル開発会社のストックマーク、Kotoba Technologies Japanを含む4社と連携するとしています。プロジェクト終了後には、ソフトバンクと産業技術総合研究所を中心に事業化に向けた検討を進める予定です。
生成AIの開発力強化から社会イノベーションの加速へ向けて
GENIAC採択事業者が登壇したCEATEC 2024のイベントは、各事業者が互いの知識をさらに深め、今後の開発に生かせる有益な情報を得られる貴重な時間となりました。





GENIACでは、大規模基盤モデルの開発に加え、カスタマーサポート、AI創薬、映像生成といった領域で日本特有の課題解決に貢献する取り組みを進め、データ実証支援の推進により業界全体の競争力向上を目指します。今後もAI開発の加速と社会実装の促進を支援するGENIACと、各事業者が生成AI分野で追求するイノベーションにご期待ください。
GENIACトップへ最終更新日:2024年11月28日