
2025/03/14
国産の生成AIの研究開発に挑む、GENIACの採択事業者たち。そのキーマンとは、どのような人物なのでしょうか。今回は、チャットボットツールなどを手掛けるAIスタートアップ、カラクリ株式会社 テックリード 吉田 雄紀さんにお話を伺いました。同社は、GENIACでは、カスタマーサポートに特化した高品質AIエージェントモデルの開発に取り組んでいます。本プロジェクトの中心人物である吉田さんは、AIエンジニアでありながら医師免許の資格を持つ、異色のエンジニアです。そんな吉田さんとAIの出会い、そして今後の目標についてお話を伺いました。
<プロフィール>
吉田 雄紀(よしだ ゆうき)
1989年生まれ、兵庫県出身。カラクリ株式会社 テックリード。高校時代に、「国際数学オリンピック」と「国際情報オリンピック」に出場し、両大会で銀メダルを獲得。その後、東京大学に進学し、医師免許を取得。その後、脳科学に興味を持ち、2016年東京大学大学院 へ進学。データサイエンティストの道を歩み始める。2019年、カラクリ株式会社にテックリードとして参画。2024年、GENIACの計算資源の提供支援事業第2期採択事業者にカラクリが選出される。同社テックリードとして、高品質AIエージェントモデルの開発に挑戦中。
親に反対され、諦めた数学者の道。医学を通じて出会った「脳科学」の世界
──吉田さんは、東京大学へ進学後、医師免許を取得されています。そもそもデータサイエンスと出会ったきっかけとは、どのようなものだったのでしょうか?
吉田:私は物心がついた頃から数字が好きで、高校時代も「数学研究部」に所属していました。
在学中に、数学の問題を解いて競う「数学オリンピック」に出場し、銀メダルを獲得。その実績を知った方から、高校生がプログラミング能力を競う「国際情報オリンピック」に誘われ、そこでも銀メダルを獲得しました。それでも “数学愛”が強く、東大進学後も、数学者の道を目指していました。
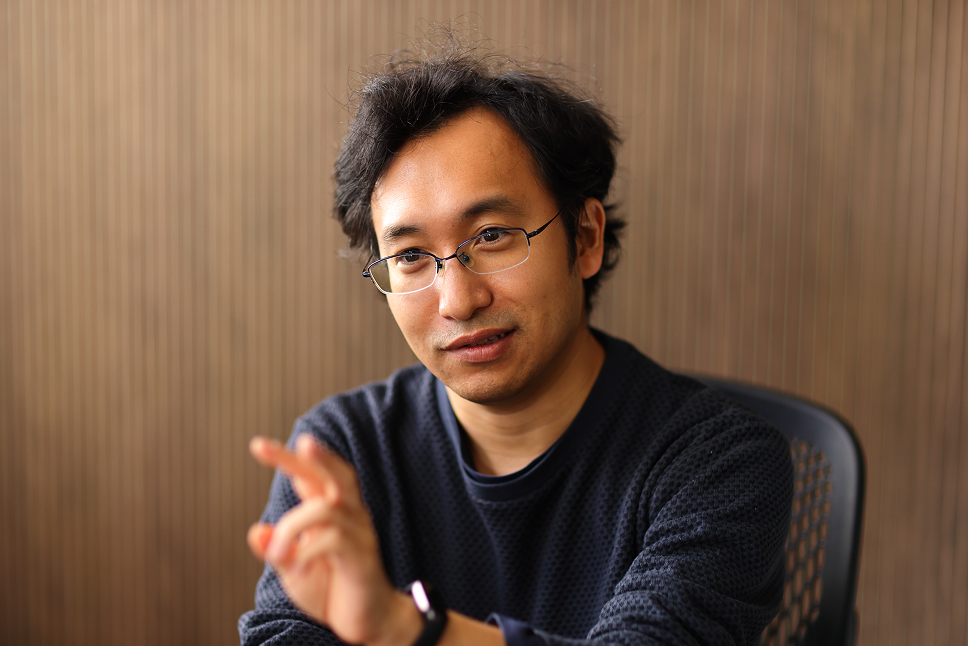
──ですが、東大では医学部に進み、医師免許を取得されていますよね?
吉田:そうですね。東大は、2年生の秋に進学先の振り分けがあるので、その時に数学者の道を選ぶこともできました。ですが、親から「数学では食えないぞ」と強く反対されたこともあり、医学部への進学を決めました。
医師になると決めてからは、医学を必死に勉強しました。しかし、あくまで、私が好きなものは、数学とコンピュータ。その中で、医学とコンピュータが交じり合う場所はないのか、ずっと探していました。そんなタイミングで「脳科学」に出会いました。脳の仕組みをコンピュータで解き明かす。脳の知識であれば、医療の領域にも生かせますし、私は「これだ!」と思いました。
そして医学部生、研修医を経て、東京大学大学院へと進学。大学院で脳の研究を進める中で、人間の脳を知るためには人工知能(AI)を構成する「人工ニューラルネットワーク」の理解が必要だと感じ、データサイエンティストとしての道を歩み始めました。そのときに出会ったのが、カラクリのCTO(当時)だった中山 智文です。私と彼は意気投合し、自然とカラクリの開発に携わるようになりました。
ディープラーニング全盛時代に、カラクリにジョイン
──カラクリは、東大発のAIスタートアップです。カラクリCTOの中山さんと出会ったことは偶然ですが、必然でもあるような印象を受けます。
吉田:そうかもしれません。カラクリの創業は2016年の10月なのですが、2016年というのは、AIのディープラーニング(深層学習)への注目度が急上昇していた時代で、AIを活用したスタートアップが多く誕生した年でもあります。私自身もディープラーニングに大きな関心を寄せていました。カラクリはその中で、チャットボットに着目し、開発を進めていました。公式的には、2019年からジョインとなっていますが、創業直後から、AIエンジニアとしてカラクリの開発に関わっています。
現在は、カラクリの開発部署であるR&Dに所属しています。AIを活用するためには、物事を学習させる必要があるわけですが、そのための手段は多彩です。ディープラーニングや機械学習、それ以外のエンジニアリングの方法もあります。数ある選択肢の中から最適な方法を検討し、実装を進めていくことが、私の仕事なのです。
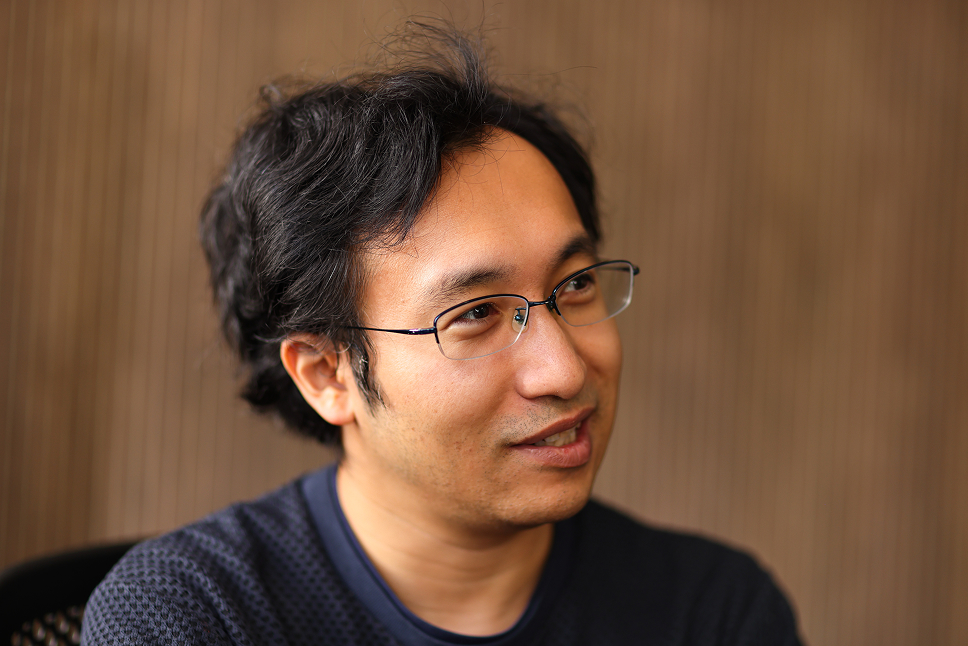
──吉田さんは、カラクリで行っている開発全般に関わっているのでしょうか?
吉田:基本的にはそうですね。カラクリは、カスタマーサポート業界全体を技術(AI)で支援していくことを目指しています。ですが、実は多くの企業は、カスタマーサポート以外の分野にもお困りごとをお持ちです。そうした細かなニーズ、課題解決にもAIを活用したソリューションのご提案をさせていただいています。
ちなみに、チャットボットは、質問に自動応答するだけでなく、顧客の声(VOC:Voice of Customer)の収集にも役立ちます。ユーザーがサービスを利用する中で、「ここがわかりづらい」であるとか、そうした顧客の声を、自動で分析するツールも開発しています。その中で、特定のお困りごとに関するVOCが増えていれば、アラートを出して管理者に伝える。そうした機能の開発にも関わっています。
他には、コールセンターのシフト調整を瞬時に解決するAIツールの開発にも関わりました。これは私が得意とする「数理最適化」という数学モデルを活用したものです。コールセンターでは、多くの人が働いていますから、1ヶ月分のシフトを早い段階で作成する必要があります。加えて、電話が多い時間と少ない時間がありますから、時間帯によって必要な人数も異なるわけです。そうした条件を加味した上で、個人の希望シフトを反映する。この複雑なパズルを、人の手で行うと3日ほどかかるそうです。それが、数理最適化を利用することで、数秒で完了できるようになり、クライアントに大変驚かれました。
喜びを感じるのは、未知の価値を提供し、驚いてもらえた瞬間
──AIエンジニアとして、吉田さんが思う“仕事の醍醐味”とは、どのようなものでしょうか?
吉田:一言でいうと、私は「人を驚かせるのが好き」なんです。テクノロジーによって、こんなことができると知ると、多くの人が驚く。それも、誰も思いつかなかったような方法で、未知の価値を生み出していくことに喜びを覚えますね。
国産オープンモデルで最高性能を有する大規模言語モデル(LLM)シリーズ「KARAKURI LM」の開発もその一つです。OpenAIの「ChatGPT」はたしかに優秀ですが、日本のカスタマーサポートに十分に対応できるかといえば、そうではありません。それほど日本語は複雑で、学習するのが難しい言語だからです。日本企業がより高いレベルでAI活用を推進するためには、やはり国産のLLMが必要です。これは同時に、海外企業への自社の情報流出を防ぐ意味合いもありますから、セキュリティ面でもニーズがあります。
一方で、「ChatGPT」は、私が生成AIに興味を持ったきっかけでもあります。2022年11月の公開後、少し触ってみたら、3日ほどで、AIによるコメント返信機能を有したオリジナルのVTuberを生み出すことができました。そのときに「AIで何でもできる時代が来る!」と大興奮したのを、よく覚えています。

──「AIで何でもできる時代」というのは、多くの課題がAIによって解決される時代が到来する、とも捉えられるのでしょうか?
吉田:はい、私はそう考えています。
AIは様々な場面に活用可能です。今後は、これまで活用できていなかったシーンにAIを活用しようという発想が広がっていくと考えています。極論、課題が1万個あるならば、課題ごとに対応したAIツールを開発すればいい。IoTは、Internet of Thingsですが、そこにAIが加わった、「AIoT」の時代が来ると私は確信しています。すべてのモノに、AIが組み込まれる時代。その時には、自販機が喋り出して、ユーザーをおもてなしする可能性だってあります。私たちが想像すらしていないAI活用の未来が、世界が広がっている可能性が十分にあるのです。
GENIACでは、オムニモーダルモデルのLLM開発に挑戦
──カラクリは、国内の生成AI開発力強化プロジェクト「GENIAC」の採択事業者でもあります。そこでの取り組みについて教えてください。
吉田:カラクリは、AIによる、カスタマーサポートの支援を最大の武器にしています。今回の事業計画では、従来のLLMでは、テキストメインだった入力を、マルチフォーマットに対応した「オムニモーダルモデル」に進化させることを目指して、開発を進めています。
従来のLLMは、テキストしか認識できません。ですから、例えばオンライン会議で資料を共有されても、内容を理解できませんし、目の前で映像が流れても内容を理解することはできません。ですが、そこに視覚情報を認識できる“目”が搭載できれば、資料内の図形やグラフを認識したり、動画の内容を理解できるようになります。
AIが正確に情報を把握、理解できるようになれば、より正確な返答やアドバイスが可能になります。例えば、カスタマーサポートにおける音声認識の精度が向上すれば、AIが会話を正しく理解し、オペレーターにとって、いま必要な情報を画面に自動で表示するといったことも実現可能です。そうなれば、個々の対応の時間短縮になりますし、業務効率化によって、オペレーターの負担も軽減されます。その未来に向かって、現在は開発を日夜進めているところです。
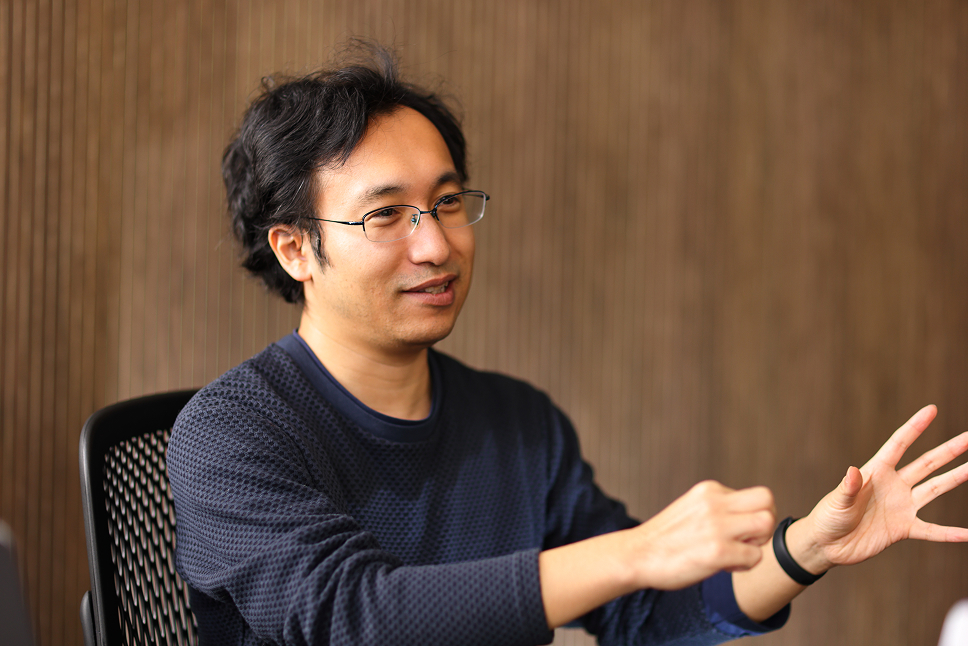
資金面だけでなく、新たに生まれた「つながり」は大きなメリット
──GENIACに参加して感じたメリットなどがあれば、教えてください。
吉田:GENIACでは、開発でコストのかかる、計算資源の補助が出ます。これは非常に助かっています。AIの開発は時間もお金もかかりますから、参画している開発事業者の方は、皆さんが同じメリットを感じていると思います。
そして参画している開発事業者の方との“つながり”も、大きな収穫となりました。私が参加したGENIACでのイベントでは、開発中に直面した課題や知見を共有するだけでなく、ビジネスに直結するパートナー企業との出会いなどもあり、非常に実りの多い場でした。計算資源の提供支援事業に応募して、本当によかったと思いましたね。
──最後に、今後の展望を聞かせてください。
吉田:カラクリのように、カスタマーサポート領域に特化した、AI開発を事業にしている会社は多くありません。弊社の創業背景には、代表取締役CEOの小田が元々、カスタマーサポート運営に携わっていたことが影響しています。顧客視点でモノを考え、ソリューションを提供する。チャットボットの会社は他にもありますが、現場の細かなニーズまで拾ってAI開発を進めているのは、おそらく日本では弊社だけではないでしょうか。
その、唯一無二の歩みを今後も加速させ、ゆくゆくは、「カスタマーサポートのDXといえばカラクリ」と呼ばれる会社になりたいですね。
また、個人的には、AIの医療活用にも関心があります。実は現在も、週一回は医師として働いています。医師としての経験も生かし、ゆくゆくは医療をサポートできるAIの開発にも取り組んでみたいですね。
最終更新日:2025年3月18日