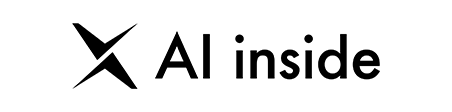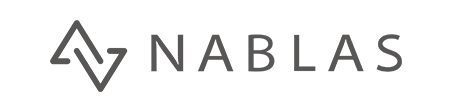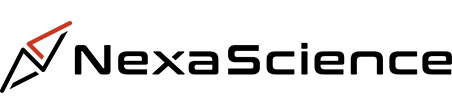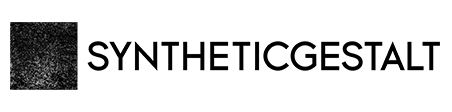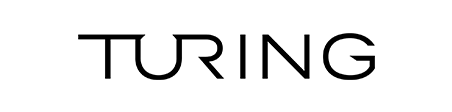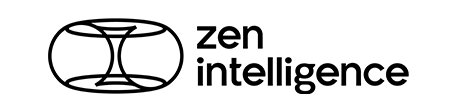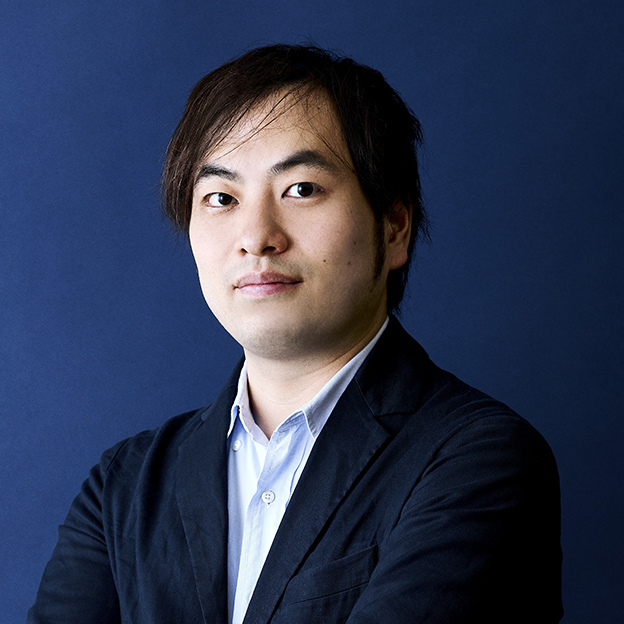
- 会社名
- 株式会社ABEJA
- 所在地
- 東京都港区三田1丁目1番14号 Bizflex麻布十番2階
- 本事業における開発概要
- https://www.nedo.go.jp/content/800028445.pdf(1ページ目)
ABEJAは、「ゆたかな世界を、実装する」を経営理念に掲げ、ミッションクリティカル業務へのAI導入支援のため、基盤システムとなるABEJA Platformの開発・導入・運用を行う「デジタルプラットフォーム事業」を展開しています。
ABEJA Platformは、ミッションクリティカル業務における堅牢で安定した基盤システムとアプリケーション群であり、生成AIをはじめとする最先端技術による運用が人とAIの協調により実現可能です。
ABEJAは、2012年の創業時よりABEJA Platformの研究開発を進めており、顧客企業からの信頼のもと、数多くの導入を進めることで「テクノロジーの力で産業構造を変革する」ミッションに取り組んでいます。
また、「イノベーションで世界を変える」ビジョンに基づき、2012年からディープラーニング、2018年から大規模言語モデル(LLM)、2019年から量子コンピューティングなどの前衛的研究開発を積極的に行っており、研究開発成果を順次ABEJA Platformに搭載することで、社会実装に貢献してまいります。

- 会社名
- 株式会社AIdeaLab
- 所在地
- 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング13F
- 本事業における開発概要
- https://www.nedo.go.jp/content/800028445.pdf(2ページ目)
株式会社AIdeaLabは、筑波大学発のAI領域に特化したスタートアップスタジオで、最先端のAI技術を駆使し、AIを活用した議事録サービス「AI議事録取れる君」、AIアバター「AIひろゆき」などの複数のAIプロダクトを展開しています。
私たちは「AI×Ideaでいまだかつてないプロダクトを生み出す」ことをミッションとして、最先端のAI技術の研究と、AIとアイディアを掛け合わせた製品開発に注力しています。さらに、様々な分野のパートナーとの協業や共同研究を通じて、人々の生活を豊かにする新たな価値を創造することを目指しています。
今回の採択を受け、AIdeaLabは動画生成AI基盤モデルのMoEによるさらなる発展を推進していきます。さらに、これらの基盤モデルを利用できるプラットフォームを提供し、アニメ制作の生産性向上、新たな表現手法の創出など、日本のクリエイティブ産業に革新をもたらすことを目指しています。
AIdeaLabは、AIの可能性を信じて、AIが当たり前に人々の仕事や生活を支える未来を創ります。

- 会社名
- AI inside 株式会社
- 所在地
- 東京都渋谷区渋谷3-8-12 渋谷第一生命ビルディング4階
- 本事業における開発概要
- https://www.nedo.go.jp/content/800028445.pdf(3ページ目)
生成AI・LLMや自律型AIの研究開発と社会実装を行うAI inside は、日本語のドキュメント処理に特化したLLM「PolySphere-3」を開発し、企業保有データを学習させる「カスタマイズSLM」により個々の企業や業務に特化した生成AI活用を可能にするAI基盤を提供しています。
プロダクトとしては、あらゆるタスクを自律的にこなす生成AIエージェント「Heylix」やデータ入力業務を自動化するAIエージェント「DX Suite」に加え、それらを支えるAIインフラ「AnyData」と「AI inside Cube」を開発・提供し、政府機関・地方公共団体・民間企業など約3,000社、約6万ユーザに利用されています。
本事業では、日本語に特化した小型マルチモーダルモデルを開発します。自然な音声対話と業務への即応性を兼ね備え、軽量かつ高性能な設計により、さまざまな現場への導入を可能にします。本モデルは、日本語での音声対話とビジネス課題の解決に特化し、画像や音声に対応。特定タスクにおいて、世界水準の性能を発揮しつつ、ローカル環境でも動作可能なコンパクトさを実現します。
開発したモデルは、主力製品「DX Suite」に搭載する予定です。AIとの協働体験を、より多くの人に提供することを目指し、社会実装を推進していきます。

- 会社名
- Airion株式会社
- 所在地
- 東京都文京区本郷3丁目28番10号 柏屋ビル2(3F)
- 本事業における開発概要
- https://www.nedo.go.jp/content/800028445.pdf(4ページ目)
Airion株式会社は、「世界に誇れる日本を築く」ことを使命に、日本の基幹産業である製造業界にAIを活用し、産業構造の変革を目指しています。自然言語処理・画像認識・3Dモデル×AIなど多様な先端技術を用いて企業の課題を解決し、日本のものづくりが本来持つ高いポテンシャルを最大限に発揮できる社会実装のため、日々技術開発に取り組んでいます。
本事業では、特にFA(Factory Automation)分野における制御設計へのAI応用として、「PLC制御におけるラダープログラム生成用大規模言語モデルの研究開発」を進めています。PLC(Programmable Logic Controller)は、工場設備などの自動制御に用いられる装置で、日本ではラダープログラムと呼ばれる独自言語によって制御設計が行われています。
このラダープログラムは公開データが少なく、既存のLLMでは高精度な生成が困難です。当社は設備メーカーなどとの連携により取得した実データをもとに、独自のLLMを構築し、生産性の向上や属人性の解消を目指しています。将来的には、工場の立ち上げや保守運用時には当社のAI技術がデファクトスタンダードとして活用されるようになることを目標としております。
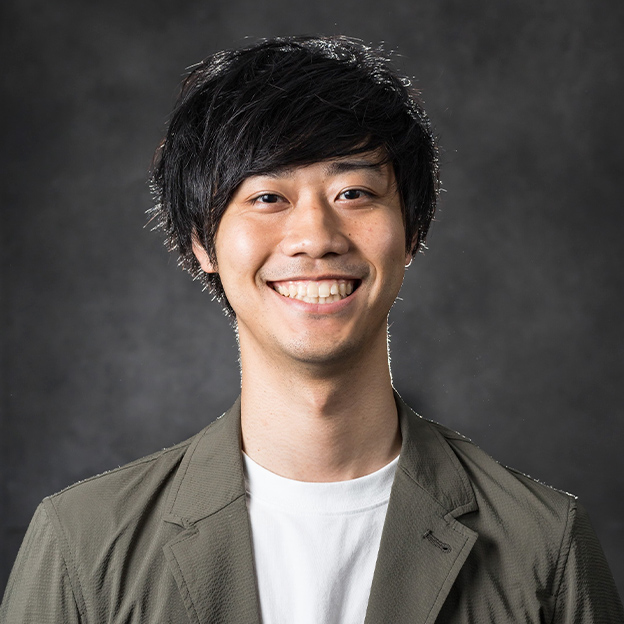
- 会社名
- Degas株式会社
- 所在地
- 東京都港区虎ノ門3-1-1 虎ノ門三丁目ビルディング 2F Quest 虎ノ門
- 本事業における開発概要
- https://www.nedo.go.jp/content/800028445.pdf(5ページ目)
Degasは「Changing people’s lives, dramatically.」をミッションに掲げ、AIと衛星観測データを活用してアフリカをはじめとする発展途上国の農業や金融の課題に挑むスタートアップです。2018年の創業以来、テクノロジーと現場オペレーションを融合させ、地域に根差した取り組みを通じて人々の生活向上に貢献してきました。
衛星観測は、センサーネットワークやドローンではカバーが難しい遠隔地のモニタリングに適しており、広範囲を安定的に観測できるという特長があります。一方で、こうした地域ではモデル学習に必要な教師データ(たとえば農作物の病害の発生範囲や、洪水時の浸水深といった地上データ)の取得には多大なコストがかかるという課題が存在しています。私たちはこの制約を乗り越えるため、限られた教師データでも高精度な解析を可能にする、衛星観測データに特化した基盤モデルの開発に取り組んでいます。
本採択を受け、Degasでは、衛星観測データを高度に解釈可能な独自の基盤モデルと大規模言語モデル(LLM)を統合し、視覚言語モデル(VLM)の開発に取り組みます。より直感的で実用性の高い衛星データ分析手法を実現し、新たな価値の創出を目指します。

- 会社名
- Direava株式会社
- 所在地
- 東京都千代田区麹町3丁目5番地2 ビュレックス麹町
- 本事業における開発概要
- https://www.nedo.go.jp/content/800028445.pdf(6ページ目)
「Direava(ディリーバ)は、「AIを用いて手術の未来を変える」ことをミッションに掲げる、慶應義塾大学医学部発の医療AIスタートアップです。現代の外科手術においては、術中の判断や操作が術者の熟練度や経験に大きく依存しており、それが合併症のリスクや医療の地域格差を生む一因となっています。私たちはこの属人性を打破し、すべての外科医が安全かつ精度の高い手術を行える未来を実現するため、AIによる術中支援技術の開発に取り組んでいます。
これまで、手術中の映像をリアルタイムに解析し、解剖構造を自動で認識したり、合併症につながるような危険行動の予兆を術者にフィードバックすることで、手術の安全性を高めるナビゲーションシステムを開発してまいりました。本事業では、日本語による自然言語説明文を生成する視覚・言語統合型AI基盤モデルを開発し、術中に「今どの操作か」「次に注意すべき構造は何か」といった、外科医の理解・推論・判断・意思決定に関わる問いに即時に応答できる新たな外科支援体験を提供します。
Direavaはすでに国内外の多くの大学病院・研究機関と連携しながら、外科AIの臨床実装を推進中です。テクノロジーと医療の融合によって、外科医療の質と安全性を世界中に届けてまいります。」

- 会社名
- 株式会社Kotoba Technologies Japan
- 所在地
- 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルヂング6階
- 本事業における開発概要
- https://www.nedo.go.jp/content/800028445.pdf(7ページ目)
世界に先行し、音声における基盤モデル技術の研究開発を行う、株式会社Kotoba Technologies Japan。弊社の研究者は、米国のトップ学術機関において最先端でAIを研究し、大規模言語モデル(LLM)が大きく取り上げられる以前から、国内のスパコンを活用したLLMの開発に挑戦してきました。AIトップ会議に多数採択され、ベストペーパー賞などの実績を持つチームが一丸となり、研究開発を行っている点も強みです。
欧米で開発された技術の後追いではなく、挑戦的で独自の切り口で生成AIの「音声基盤モデル」技術開発を目指します。

- 会社名
- NABLAS株式会社
- 所在地
- 東京都文京区本郷6-17-9 本郷綱ビル1F
- 本事業における開発概要
- https://www.nedo.go.jp/content/800028445.pdf(8ページ目)
東京大学発のAI総合研究所NABLASは、「Be a good ancestor(良き先人となる)」をビジョンに掲げ、AI人材育成、研究開発・AIエージェント社会実装支援、生成AIサービスを三本柱に、社会課題の解決に資するAI技術の社会実装を推進しています。特に、生成AIサービスの一つであるディープフェイク検出やファクトチェック技術においては、すでに官公庁や報道機関での通常業務への導入実績があり、信頼性の高い生成AI技術の応用を先導しています。また、製造業や食品・小売業においても、大規模視覚言語モデル(LVLM)を基盤としたAIエージェントシステムをすでに提供しており、業務効率化や意思決定支援に貢献しています。今回のプロジェクトでは、ハルシネーション対策やファクトチェックに特化した報酬モデルと強化学習モデル・推論アーキテクチャを開発し、報道機関と連携して実業務での運用を通じた検証・改善を行います。技術報告書や評価ベンチマークを公開し、社会全体で信頼性の高い生成AIの発展と活用を促進していきます。

- 会社名
- 株式会社NexaScience
- 所在地
- 東京都渋谷区渋谷2-19-15宮益坂ビルディング609
- 本事業における開発概要
- https://www.nedo.go.jp/content/800028445.pdf(9ページ目)
NexaScienceは、エンタープライズの研究開発とその成果を利活用するAIプラットフォームを提供し、科学技術の在り方そのものを革新することを目指しています。AIの急速な進展の中で、日本経済の基盤を担う企業が次世代の技術を効果的に創造・活用できるよう支援してまいります。
従来、企業の各部門向けには多様なプラットフォームサービスが展開されてきましたが、研究開発部門向けのサービスは、長らく単機能の範囲を超えられていません。これは、まだ世にない新たな価値を産み出すという創造的活動を支える基盤技術が十分に整備されてこなかったためです。NexaScienceはこの課題を乗り越え、単機能にとどまらない統合的なプラットフォームの提供を通じて、研究開発の高度化と生産性向上を目指します。
今後は、MCP(Multi-agent Collaboration Platform)やA to A(Agent-to-Agent)といったプロトコルの普及に伴い、マルチエージェントAIによる高度なサービス開発が加速すると見込まれています。NexaScienceでは、GENIACに提案した「AIアダプター技術」を通じて、革新的な技術の創造からその社会実装までを担うAIサービスの開発を推進します。
あわせて、企業が蓄積してきたノウハウや知見をAI化後も有効に活用できるよう支援し、現場のポテンシャルを余すことなく引き出す仕組みづくりにも取り組みます。知の継承と再活用を可能にすることで、AI導入による創造性と生産性の向上を、持続的な競争力へとつなげていきます。
代表の牛久は、長年にわたりマルチモーダル生成AIの研究開発を主導してきた実績を有し、その知見を活かして、来るべきエンボディドAIの時代にも対応可能な基盤技術の構築を進めています。実世界で活躍するAIロボットまで視野に入れた研究開発基盤により、企業のR&D活動を中核から支える技術基盤の実現を目指します。
私たちは、AIの力で科学技術の活用と創造を加速し、人間の創造性が最大限に発揮される社会の実現に貢献してまいります。

- 会社名
- Nishika株式会社
- 所在地
- 東京都港区芝4-4-5 三田KMビル5階
- 本事業における開発概要
- https://www.nedo.go.jp/content/800028445.pdf(10ページ目)
日本を代表する"プライベートAI"カンパニーを目指すNishikaは、国内で初めて音声認識・話者認識・生成AI要約をオフラインで完結したAI議事録ツール「SecureMemo」を開発・提供し、2023年という直近のリリースながら、既に多くの政府機関・エンタープライズ企業にご利用いただいています。
セキュリティを担保したい現場において、高性能なLLMが動作するような高スペックマシンの導入・更新が難しいことがあります。「テクノロジーですべての人が誇りを持てる社会を」をビジョンに掲げる当社としては、たとえ数Bパラメータ規模のLLMしか動作しない環境であっても、LLMを搭載したAIプロダクトを活用し、十分な業務効果を実現することを目指しています。
本事業では、RAM8GB以下・GPUなしでも動作する小型LLMを開発し、要約をはじめとした用途で「出力形式への指示追従能力を高める」ことを目指します。報告書・マニュアル作成・業務テンプレート記入など多様な文章作成タスクへの応用を見据えます。
さらに、出力形式制御の評価および訓練に活用できる日本語データセットを構築し、少ない計算資源で学習から評価まで完結する手法を確立することで、日本発の競争力ある生成AI基盤の構築に貢献します。

- 会社名
- ONESTRUCTION株式会社
- 所在地
- 鳥取市元魚町二丁目201番地 エステートビルⅤ2-2号室
- 本事業における開発概要
- https://www.nedo.go.jp/content/800028445.pdf(11ページ目)
ONESTRUCTION株式会社(ONEST:ワンスト)は「建設とテクノロジーの架け橋になる」をミッションとする、鳥取県発の建設Techスタートアップです。建設×データ×AIをキーワードに建設会社のDXを推進しています。
当社は建設物の3次元データ、BIMの国際標準規格である「IFC」を国際標準化団体に所属し、規格開発をしています。
また、BIMのソフトウェアである「OpenAEC」シリーズの開発・提供を事業の主軸としており、業界全体のデジタル化に貢献してきました。「OpenAEC」シリーズは国内の政府機関・民間企業だけでなく、海外48カ国で既に利用されています。
これまで、BIMのデータ交換のための情報要件(IDS)を活用した基盤モデルは存在していません。今回採択された『openBIMにおけるBIM情報要件の生成基盤モデルの研究開発』では、国際標準技術の民主化を進め、幅広い建設会社がIDSを作成することを容易にし、国際標準に沿ったBIMデータの運用により、建設業界全体の生産性を向上させます。
当社は建設業界の情報連携の障壁を取り除き、業界全体のデジタル変革を加速することで、日本の建設業界の国際競争力向上に貢献してまいります。

- 会社名
- 株式会社Preferred Networks
- 所在地
- 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル(受付3階)
- 本事業における開発概要
- https://www.nedo.go.jp/content/800028445.pdf(12ページ目)
株式会社Preferred Networks(PFN)は、生成AI・基盤モデルからスーパーコンピュータ、チップまで、 AI技術のバリューチェーンを垂直統合することで、ソフトウェアとハードウェアを高度に融合したソリューション・製品を開発し、様々な産業領域で事業化しています。
近年、大規模言語モデルや生成AIの応用先として物理世界、いわゆるPhysical AIが注目されています。 例えばドローン、ロボット、自動車、監視カメラといった自律稼働デバイスにAIを搭載し、これまで実現できなかった広範囲で重要なタスクを実現することが期待されています。しかし、データ量の増大やリアルタイム性の要求から、クラウドだけでなくエッジデバイスで効率的に動作するAIが不可欠です。
GENIAC3サイクル目では、こうした課題に応えるべく、高精度かつ軽量な、視覚情報と言語情報を統合したVision Language Model(VLM)の実現を目指します。GENIAC2サイクル目で開発した、軽量ながらもフロンティアモデルに匹敵する日本語性能を持つ軽量言語モデルを基盤に、高品質な合成データを活用することで、引き続き軽量ながらも高性能を発揮するVLMの構築を目指します。また、複数の企業と連携しながら、ドローンや監視カメラにおけるVLMの性能検証を行い、引き続き社会実装を加速します。

- 会社名
- Sansan株式会社
- 所在地
- 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F
- 本事業における開発概要
- https://www.nedo.go.jp/content/800028445.pdf(13ページ目)
Sansan株式会社は「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理DXサービス「Bill One」、AI契約データベース「Contract One」を国内外で提供しています。
本事業において当社は、文書画像からの情報抽出に特化した社内基盤モデル「Viola」を拡張し、新たに視覚接地機能(位置情報付き出力)を備えたモデル「Cello」の開発を進めています。「Cello」の導入により、名刺・請求書・契約書など、さまざまな文書からテキスト情報とその位置情報を同時に抽出することが可能になります。これにより、既存のOCRシステムやデータ入力プロセスとのスムーズな統合が実現し、データ処理速度と信頼性の大幅な向上を期待しています。当社は、迅速に「Cello」をプロダクトに組み込み、業務効率化と労働生産性の向上に貢献することを目指します。
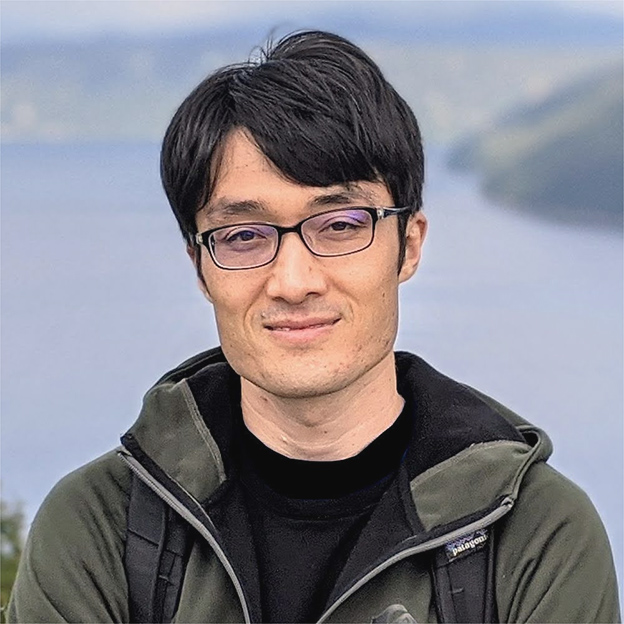
SDio株式会社は、「Deep Search for Deep Insight」というビジョンの下、AIにより企業が保有するデータのさらなる価値を解放することを目指すスタートアップです。創業当初より、映像データに特化したモデルやシステムの開発を行っており、現在TV放送データをマルチモーダルでリアルタイムに解析する国内唯一のAIサービス「TVPulse」を提供しています。
GENIACでは、既存の基盤モデルでは対応が困難な「長尺コンテクスト」に着目し、数時間以上の映像・音声データから時間軸を超えて文脈を深く理解する大規模映像基盤モデル「DeepFrame LVM」アルファ版の構築で技術的なブレイクスルーを目指します。将来的にはこの基盤モデルを中核としながら各カテゴリーへのFine Tuning技術を組み合わせることで、日本の重要産業に特化した、高効率なAIソリューションを提供していく計画です。

- 会社名
- SyntheticGestalt株式会社
- 所在地
- 東京都新宿区内藤町1番地6 ラ・ケヤキ
- 本事業における開発概要
- https://www.nedo.go.jp/content/800028445.pdf(15ページ目)
SyntheticGestaltは、AIによる新しい分子の発明を目指すスタートアップ企業です。医薬品、化粧品、農薬、新素材など幅広い分野での基盤モデルの応用を目指し、AIによる新たな発明を通じて文明の発展に寄与することを使命としています。
当社はGENIAC 2サイクル目では、分子情報の基盤モデルを開発しました。化合物の世界的ベンダーであるEnamine社との共同研究を通じて得られた960億件の化合物情報のうち、100億件を学習データとして、分子の立体構造などの詳細情報を取り入れて開発したモデルは、世界標準のベンチマークにおける3つの重要な指標で世界1位の性能を達成しました。このモデルはNVIDIA GTC 2025でも現地登壇を通じて発表し、複数の製薬会社で活用が検討されています。
GENIAC 3サイクル目では、分子と分子の相互作用情報の基盤モデルを開発し、新しい分子を生成するAIを開発します。指定された相互作用を充足するような分子を、新規性や多様性、合成可能性といった制約条件を加味しながら設計するAIの開発が本事業での目標になります。GENIAC 2サイクル目よりも格段に開発難度は上がりますが、これまでの大規模モデル開発で得られた知見が活用できるからこそ実現できる開発だと考えています。本事業を通じて当社は、難病解決や環境に優しい素材や農薬など、暮らしに役立つ新しい分子を発明するAIを社会にお届けします。

- 会社名
- Turing株式会社
- 所在地
- 東京都品川区大崎1丁目11−2 ゲートシティ大崎 イーストタワー4階
- 本事業における開発概要
- https://www.nedo.go.jp/content/800028445.pdf(16ページ目)
Turingは「We Overtake Tesla」をミッションに掲げ、人類未到の完全自動運転を実現することを目指すスタートアップです。
「自動運転に必要なのは良い目ではなく良い頭である」というコンセプトを元に、多くのセンサーや高精度地図を用いるのではなく、カメラ画像からE2Eで直接運転指示を行う高度な自動運転AIを開発しています。
本事業では、「完全自動運転に向けた車載可能なフィジカル基盤モデルの開発」に取り組みます。
現実の交通環境は常に変化しており、天候や時間帯、人や車の動きによって、予測が難しい状況が日々生まれています。こうした中でも人間のように柔軟に判断し、的確に操作できる自動運転を実現するためには、映像・センサ・制御に関する多様な情報を統合的に理解し、瞬時に最適な行動を選択できる"頭脳"が不可欠です。
このような判断・操作が可能なモデルを実車両に搭載するために、現実世界で起こる物理的な変化を捉え、状況に応じて行動できる知覚と運動の仕組みをAIに習得させるとともに、車載環境でも動作可能なよう軽量化・量子化されたフィジカル基盤モデルの開発を進めます。

- 会社名
- Zen Intelligence株式会社
- 所在地
- 東京都中央区八丁堀2丁目14番1号 住友不動産八重洲通ビル6F
- 本事業における開発概要
- https://www.nedo.go.jp/content/800028445.pdf(17ページ目)
Zen Intelligence株式会社は、「Physical AIで基幹産業を変革する」という理念のもと、AI / 画像解析 / ロボット研究者やエンジニアが集まるスタートアップです。建設業界の大きな課題の一つである施工管理業務の人手不足・属人性の解決に取り組んでいます。
これまでプロダクト展開してきた「zenshot」にて全国の建築現場の三次元空間データを収集・分析しており、それら独自データを活用することで、進捗確認や安全確認といった現場監督業務をAIが補完・代替するソリューションを目指します。
本事業では、現場の空間・物体・意味情報を時系列で統合したマルチモーダルデータセットを構築し、実際の監督者並みの認識・判断・アドバイスを行う現場特化型Large Vision-Language Model(LVLM)を開発します。今回のGENIAC採択を受け、現場に特化したLVLMの開発を加速し、AIによる施工管理の新たな標準を確立することで、日本の基幹産業である建設分野の生産性向上と持続可能な発展に貢献していきます。

- 会社名
- アリヴェクシス株式会社
- 所在地
- 東京都千代田区九段南1-5-6
- 本事業における開発概要
- https://www.nedo.go.jp/content/800028445.pdf(18ページ目)
アリヴェクシス株式会社(Alivexis, Inc.)は日本と米国に拠点を置く技術ベースの創薬企業です。当社は、最新鋭の創薬プラットフォーム・疾患生物学における深い洞察・グローバルで機動性のあるビジネス展開能力を融合することによって、独自の低分子創薬ポートフォリオと様々な研究開発提携を推進しております。現在、当社では、5つのリードプロジェクトにおいて臨床候補化合物を見出し、うち1つを海外バイオテック企業に導出しております。また、後続の複数プロジェクトがリード化合物最適化段階の後期に入るなど大きく進捗しております。当社の画期的なシミュレーション技術であるModBind™は、従来の業界標準の技術であるFree Energy Perturbation(FEP)とほぼ同等の精度を保ちつつ、数百倍から数千倍以上の高速化を実現しており、自社での創薬プロジェクトや社外パートナーとの協業において、有望な臨床候補化合物の発見を加速することに成功しております。さらに、ModBind™は高精度・高速という特徴を有することから、製薬業界におけるAI活用の最大のボトルネックであるデータ不足を解決するポテンシャルを持っています。当社は、ModBind™とAI技術を組み合わせることで、AI創薬の飛躍的な進化を主導していきたいと考えております。

- 会社名
- カラクリ株式会社
- 所在地
- 〒104-0045 東京都中央区築地2丁目7-3 Camel 築地 II 5F
- 本事業における開発概要
- https://www.nedo.go.jp/content/800028445.pdf(19ページ目)
カラクリは、2016年の設立以来、Friendly Technology というビジョンのもと、今までにないカラクリで世の中を豊かにするというミッションを担ってきました。 2018年にリリースしたKARAKURI chatbotをはじめとしたカスタマーサポート特化型AI SaaSである KARAKURI Digital CS Series は、日本のエンタープライズ企業を中心に多くのお客様にご活用いただいております。
リリース当初から独自モデルの開発にこだわり、比較的早い時期から数百億パラメータクラスのモデル開発を行ってきました。昨年の1月には当時国内最大かつ最高性能を記録した「KARAKURI LM」をオープンなモデルとしてリリースし、多くの研究者や開発者の皆様にご利用いただきました。また、弊社は世界的にも先駆けて AWS Trainium などの専用チップを活用することにも積極的に取り組んでおり、それによってコストパフォーマンスの高い開発を実現しています。
本プロジェクトでは「日本のカスタマーサポートのためのオムニモーダルエージェントモデルの開発」というテーマに取り組みます。弊社が創業以来培ってきたカスタマーサポートとそのデータサイエンスの知見をフルに活かし、人手不足と労働環境の悪化に悩む日本のカスタマーサポートを変革していくことに貢献したいと思います。
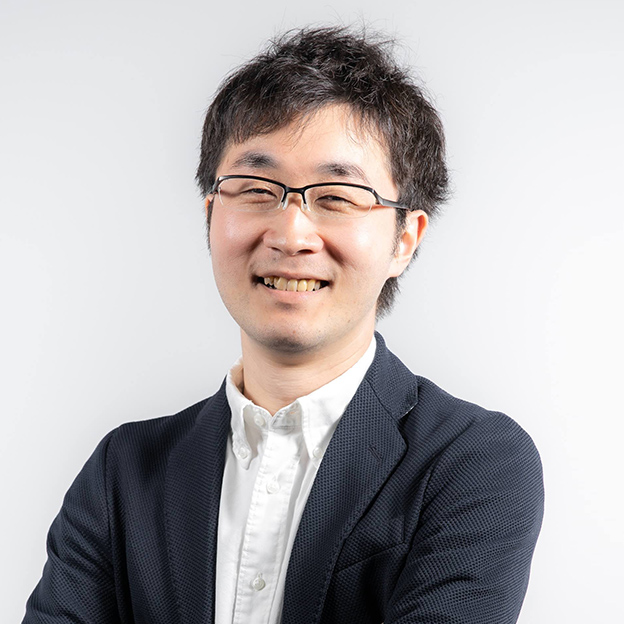
- 会社名
- ストックマーク株式会社
- 所在地
- 東京都南青山1丁目12-3LIFORK MINAMI AOYAMA S209
- 本事業における開発概要
- https://www.nedo.go.jp/content/800028445.pdf(20ページ目)
ストックマーク株式会社は、「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、
最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。
製造業に特化したAIが、ユーザー毎に最適化された情報を瞬時に提供するAIエージェント「Aconnect」や、
図表を含む複雑なビジネスデータを構造化し、RAGシステム構築や高精度化を支援する「SAT(Stockmark A Technology)」を運営しています。
さらに、大規模言語モデル(LLM)やマルチモーダル基盤(VLM)をはじめとした、
日本語&ビジネス特化の生成AI基盤開発や、独自システムの構築支援も行っております。
当社の強みは、これまで分析が困難だったテキストデータを、
最先端の自然言語処理技術で構造化し価値あるデータに変換できる点です。
これにより、社内外に眠る膨大なビジネス情報を知的資産に変換し、企業の持続的な成長と競争力向上を支援しております。

- 会社名
- 株式会社野村総合研究所
- 所在地
- 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ
- 本事業における開発概要
- https://www.nedo.go.jp/content/800028445.pdf(21ページ目)
NRIは、2001年から日本語自然言語処理の研究開発を開始し、テキスト解析基盤や高精度意味解析エンジンの開発を通じて、各産業分野の業務効率化を支援してきました。2022年からは生成AI・大規模言語モデル(LLM)の研究開発に本格着手し、「NRI Solution AI」をはじめとする実用的な生成AIソリューションを提供。AIやデータ活用のコンサルティングから基盤構築、実行支援を通じた成果創出まで、お客様のAI活用をワンストップで支援しています。
NRIの特徴は、基盤モデルの自社開発にこだわらず、商用・オープンを問わず最適なLLMを選択・活用する点にあります。長年にわたりベンダーフリー、マルチクラウドを推進してきた当社は、生成AI分野でも同様のアプローチを採用。お客様の要件や環境に応じて、複数の選択肢から最適なモデルを柔軟に提案し、特定のベンダーへのロックインを回避する自由度の高いソリューションを提供しています。2024年には、この手法により8Bパラメータのオープンモデルをベースに、小規模でありながら大規模汎用モデルを上回る性能を実現する業界・タスク特化型LLMの構築に成功しました。
本採択を受け、NRIでは中規模(10B-40Bパラメータ)のオープンLLMを活用した業界・タスク特化型モデルの本格的な開発を開始します。複数の最新オープンモデルから最適なものを選定し、継続的な技術進化の恩恵を享受しながら、様々な産業分野の専門性に対応した高精度かつコスト効率の高い特化型LLMを提供していきます。

- 会社名
- 株式会社プレシジョン
- 所在地
- 東京都文京区本郷4-2-5 MAビル7階
- 本事業における開発概要
- https://www.nedo.go.jp/content/800028445.pdf(22ページ目)
株式会社プレシジョンは、現役医師である代表取締役・佐藤寿彦が2016年11月に設立した医療AIベンチャーです。「医療のありたい未来を共に創る」をパーパスに掲げ、AI問診を中心とした診療支援サービスを提供しています。
主力サービスである「今日の問診票」は、スマートデバイスを通じて患者が入力した主訴・既往歴などの情報をAIが自動解析して電子カルテの下書きを生成、初診カルテ作成にかかる時間を1/3に削減します。さらに約2,000名の医師に協力を得て開発した、3,000疾患、700の症状所見、全処方薬情報を網羅した医療情報データベース「Current Decision Support(CDS)」との連携により、問診結果から考えられる鑑別疾患や検査・処方の提示、OCRによるお薬手帳の内容の入力支援等も可能で、医療の質向上にも大きく役立つ製品となっており、全国で700超の医療機関で導入されています。
直近では、医療特化の音声認識と生成AIによるカルテ下書きの自動化を組み合わせた「今日の音声認識」も開発・販売開始するなど、AI・ICTを駆使して医療従事者と患者の双方に寄り添う信頼性と利便性の高いサービスを通じ、より安全で質の高い医療の提供を目指します。
本事業では、東大、九州大学、がんセンターと共同研究し、医療特化型大規模言語モデル「SIP-jmed-llm」(13B・8×13B・172B)を活用し、診療録の自動校正、診療情報の匿名化、がん診療支援RAG、X線所見の構造化、DPCデータの分類支援に取り組みます。入力業務を最大50%削減し、医療の質と効率の向上を実現します。

AI サービス統括部 ディレクター
グローバルCDO室 オフィスマネージャー 大越 拓
- 会社名
- 楽天グループ株式会社
- 所在地
- 東京都世田谷区玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス(本社)
- 本事業における開発概要
- https://www.nedo.go.jp/content/800028445.pdf(23ページ目)
楽天は、コマース、デジタルコンテンツ、広告などのインターネットサービス、クレジットカード、銀行、証券、保険、スマホアプリ決済といったフィンテックサービス、携帯キャリア事業などのモバイルサービス、さらにプロスポーツといった多岐にわたる分野で70以上のサービスを提供しています。これら様々なサービスを、楽天会員を中心としたメンバーシップを軸に有機的に結び付け、他にはない独自の「楽天エコシステム」を形成しています。1997年に創業し、「イノベーションを通じて、人々と社会をエンパワーメントする」という企業理念のもと、現在では約3万人の従業員を擁し、世界30カ国・地域の拠点において事業を展開するグループ企業となっています。

リコーは1980年代からAI開発に取り組み、2015年からは深層学習AIの開発を進めて外観検査、振動モニタリングなどに適用してきました。2020年からは自然言語処理技術を活用し、オフィス内の文書やコールセンターに届いた顧客の声などを分析して業務効率化や顧客対応に活かす「仕事のAI」の提供を開始しました。2022年からは大規模言語モデル(LLM)の研究・開発に着手し、2023年3月のリコー独自のLLMを発表したのを皮切りに、2024年にはオンプレミスでも導入可能なLLMを、続いてモデルマージの技術も開発しGPT-4o並みの精度を達成しました。本年4月にはLLMを搭載済みのGPUサーバー製品「RICOH オンプレLLMスターターキット」を発売するなど、お客様のご要望に応じて提供可能な様々なAIの基盤開発を行っています。また、画像認識、自然言語処理に加え、音声認識AIに関しても研究開発をすすめ、音声対話機能を持つAIエージェントのお客様への提供も開始しています。
昨今、企業内で蓄積されるドキュメントは効率的な利用や新たな価値・イノベーションを生み出すための活用が期待されていますが、テキストだけではなく図や表組・画像等も含まれることが多いため、リコーはGENIAC第2期においてLMM(大規模マルチモーダルモデル)の開発を実施し読み取り精度を向上させることができました。今回、第3期の採択をいただき、第2期の結果をもとに多段推論が必要になる更に複雑な図表にも対応させ、実用性能を高める計画です。
最終更新日:2025年8月29日