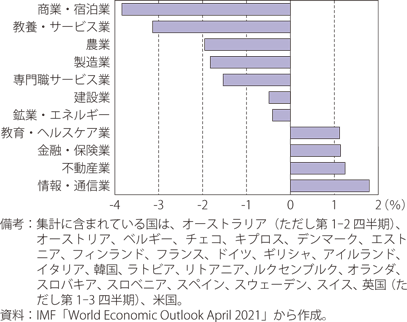第1節 コロナショック後の世界経済
1.世界実質GDP
2020年は、特異な性質を持つショックが一部の国・地域にとどまらず、全世界に影響を及ぼしたという点で特別な一年であったといえる。
2019年終盤から2020年初頭にかけて一部の国・地域で散見される程度であった新型コロナウイルスは、やがて世界的に感染が拡大し、経済の混乱を引き起こした。2000年代後半に起きた世界金融危機や2010年代前半に起きた欧州債務危機は、経済的な影響が世界的な広まりを見せたという点では、コロナショックに類似しているものの、それらは金融不安が引き起こした需要性ショックであった。一方で、新型コロナウイルスの感染拡大は、人の移動や接触・対面型のサービス消費といった需要を抑制すると同時に、従業員が物理的に集合して生産活動を行うなどといった供給活動も抑制するという特異なショックを引き起こした。本節では、世界経済は新型コロナウイルスの感染拡大にどのように影響を受けたのか、そして以降どのように回復しているのかを観察していく。
国際通貨基金(International Monetary Fund: IMF)が2021年4月に公表した見通しによれば、2020年の世界の実質GDP成長率は-3.3%とされ、世界金融危機の影響を受けた2009年の成長率(-0.1%)を大きく下回り、統計が開始された1980年以降でも最低の成長率を記録した。底堅い中国をはじめ例外はあるものの、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が、消費や投資といった幅広い経済活動に負の影響を与えたことが背景にある(第I-1-1-1図)。
第Ⅰ-1-1-1図 世界実質GDP成長率と消費及び投資の寄与度
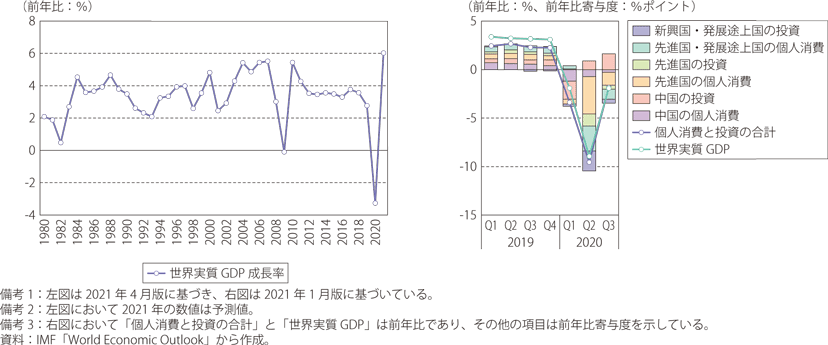
一方で、2021年の世界の実質GDP成長率は6.0%と1980年以降では最も高く、2020年の落込み幅を取り戻す回復が見込まれている(第I-1-1-2表)。新型コロナウイルスのワクチン接種や各国の政策対応が回復に重要な役割を果たし、抑制されていた経済活動がそれらを通じて回復していくとされている。
第Ⅰ-1-1-2表 IMFによる実質GDP成長率の国・地域予測
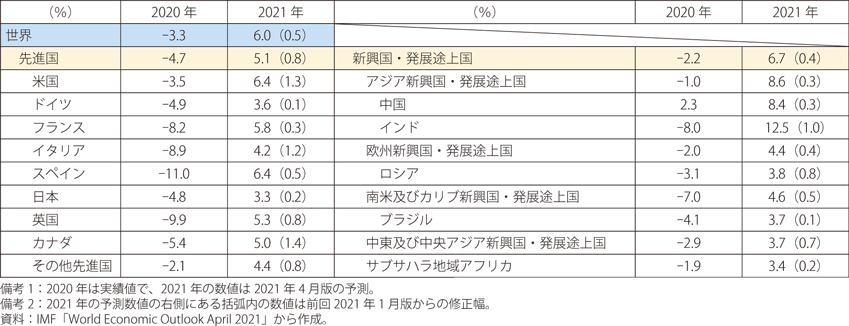
ただし、2021年の世界経済の回復には跛行性が見られることが特徴的である。具体的には、経済の回復には国・地域ごとの差異があり、IMFの2021年の見通しでは、先進国の実質GDP成長率は5.1%と2020年の落込み(-4.7%)を小幅に取り戻す程度と見込まれている一方で、新興国・発展途上国は6.7%と2020年の落込み(-2.2%)を大きく取り戻す以上の回復が見込まれている。
さらに、先進国の中でも特に米国が回復を主導することが見込まれているが、その他の先進国の多くは2020年の落ち込みを取り戻すことができないと見込まれている。後述のとおり、米国の経済回復には、大規模な政策対応に加え、電子商取引の活発化やイノベーションに焦点を当てた企業の設備投資の増加基調が重要な役割を果たしていると考えられる。
また、新興国・発展途上国の中でも、2020年にプラス成長を維持した中国は2021年にも高成長が見込まれている一方で、新型コロナウイルスの感染状況が依然として深刻なアフリカ(サブサハラ地域)や中南米諸国では2021年の回復が鈍いことが見込まれている。中国では、国内の電子商取引規模は2兆ドル近い規模となり1、好調な非接触型消費が回復に寄与すると見られる。
1 経済産業省(2020)。
2.各国の政府は目的が明確化された財政支援を実施
IMFが見込む2021年の世界経済の回復の前提として、各国の政府が取り組む目的が明確化された財政支援(well-targeted fiscal support)の効果が挙げられる。
上述のとおり、新型コロナウイルスの特徴は、需要側と供給側の両方に対してショックを与えた点である。下記(第I-1-1-3表)は、主な政策分野で導入されている政策例と、各国・地域で実際に導入されている経済対策を一覧にしたものである。新型コロナウイルスのショック特性を踏まえ、家計の消費支出を増加させるための需要側対策と、企業の投資を回復させるための供給側対策の両方を含め、目的が明確化された財政支援が実施されている。主に需要側対策として用いられている給付金は、低所得世帯や失業者・一時解雇者等を対象としている。また、主に供給側対策として用いられている企業への信用保証も、中小零細企業を含め、新型コロナウイルスの影響が深刻な産業を対象としている。2021年にはこれらの政策効果が経済回復を後押ししていくと見られる。
第Ⅰ-1-1-3表 政策分野別の政策例と各国・地域の主な経済対策
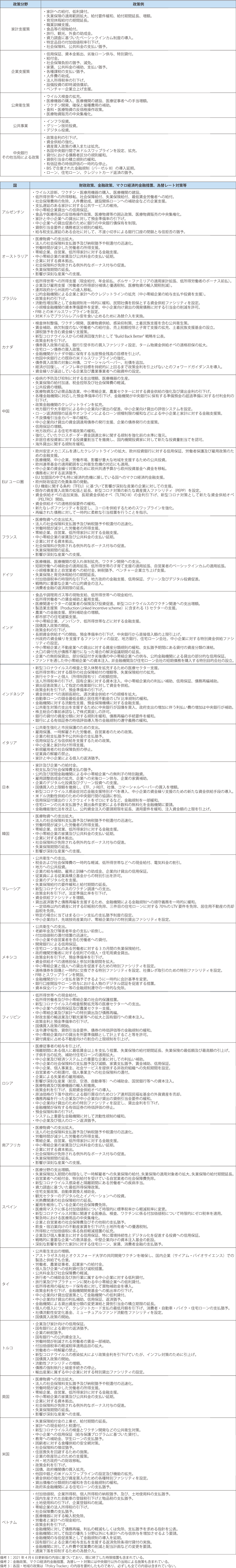
ただし、そうした経済対策には、長期的な影響が伴うことに留意が必要である。具体的には、経済対策の実施のためには、必然的に政府消費支出の大幅な増加を伴い、結果として多くの国で財政赤字が拡大した。下記(第I-1-1-4図)は、一部の先進国と新興国の財政収支の実績と見通しを名目GDP比で示している。それによると、新型コロナウイルス対策のための政策経費として財政赤字が2020年に大幅に拡大し、経済回復が見込まれる2021年にも黒字化しない。こうした財政赤字の大幅な拡大は、新たなショックに対して政策が必要な場合の予算的な制約になり得ることもあり、将来における財政運営の柔軟性に影響を与える。
第Ⅰ-1-1-4図 先進国(上図)と新興国(下図)の財政収支
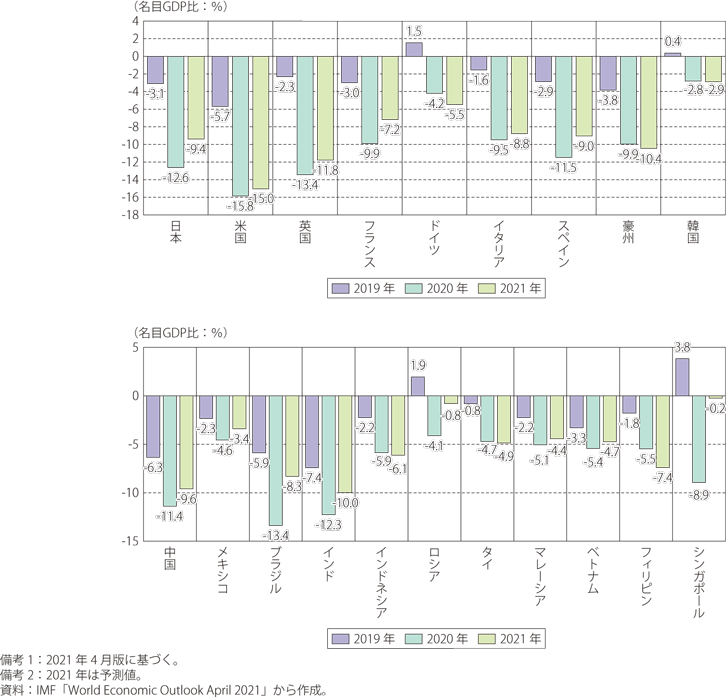
しかし、新型コロナウイルス感染が依然として世界的に深刻な中で、各国政府がそうした長期的な影響を踏まえてもなお対策を実施していることは重要である。上述のとおり、家計や失業者・一時解雇者への給付金や中小零細企業向けの信用保証といった経済対策は、新型コロナウイルスによって特に困窮すると考えられる対象が考慮されており、目的が明確な政府消費支出といえる。
例えば、トランプ前大統領の政権下で可決されたコロナウイルス支援・救済・経済安全保障法(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act)に含まれるパンデミック失業支援プログラム(Pandemic Unemployment Assistance)によってフリーランス労働者に対しても失業保険の適用が認められることとなった米国では、フリーランス労働者が増加傾向にある2。フリーランスの主要なプラットフォームの一つであるUpworkの調査によると、新型コロナウイルスの感染が深刻化した2020年には5,900万人と近年に比較してフリーランス労働者数はやや増加した(第I-1-1-5図)。同調査は兼業としてのフリーランス労働者とフリーランス労働のみから所得を得ている労働者を対象としているが、最新の調査では全体の36%が所得をフリーランス労働のみから得ていると回答しており、その割合が増加している。新型コロナウイルスの感染拡大のような大きなショックが再び与えられた場合には、フリーランス労働者は大きな影響を受けやすい。このような弱い立場にある労働者を支援する政策がなければ、再びショックが与えられた際には、米国の雇用基盤自体がぜい弱化してしまう。新型コロナウイルスのような危機下での経済対策は、平時における経済対策とは区別した評価が必要である。
第Ⅰ-1-1-5図 米国のフリーランス労働者数とそれのみから所得を得ている割合
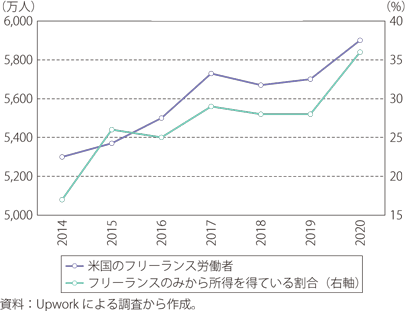
2 フリーランスに関する明確な定義は存在しないが、例えば一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会(2018)では「特定の企業や団体、組織に専従しない独立した形態で、自身の専門知識やスキルを提供して対価を得る人」とされている。
3.世界の貿易・投資の動向
2021年に世界経済が順調に回復するためには貿易の役割も重要となる。世界貿易機関(World Trade Organization: WTO)の見通しによれば、2020年には世界の財貿易量は前年比-5.3%の減少となったが、2021年には同8.0%と回復し、また2022年にも同4.0%と順調な増加になることが予測されている(第I-1-1-6図)。
第Ⅰ-1-1-6図 WTOによる世界の財貿易量の見通し
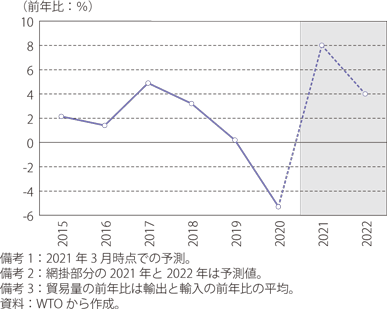
2020年には、世界経済の減退に応じて、世界の貿易・投資にも一時的に大きな減少が見られた。特に、新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、医療分野においては最大で70を超える国が輸出制限を導入し、自由貿易体制への懸念も広がった。世界経済が新型コロナウイルスの影響を克服していくためには、医療関連品が幅広く行き渡っていくことが重要である。医療分野の輸出制限を導入している国の数が高止まりしていることは、医療という局所的な分野での貿易抑制策が経済回復を阻害する要因となり得ることを示唆している(第I-1-1-7図)。
第Ⅰ-1-1-7図 医療分野の輸出制限を導入している国数
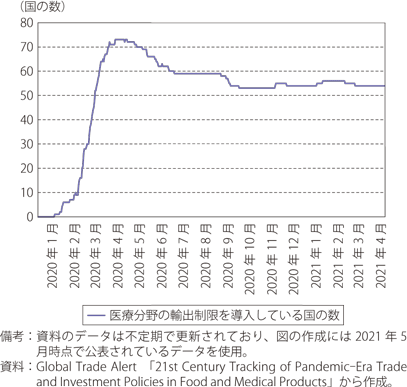
さらに、2021年の世界貿易量を左右する要因として、医療分野に限らない貿易政策にも留意していく必要がある。下記(第I-1-1-8図)は、世界の財、サービス、投資、人の流れに関して、一年間でどれだけの抑制策と促進策が導入されたのかを示したものである。これによると、上述の四項目の中でも、財貿易に関する政策数が特に多いことが分かる。財貿易に関する政策では、輸出補助金、その他の輸出補助政策、関税、緊急貿易保護措置、政府調達に関する保護措置、貿易手続の非自動化、貿易数量規制、価格統制などが導入された場合は抑制策とされ、それらが緩和された場合は促進策とされている(サービス、投資、人の流れについての政策内容は同図の備考を参照)。
第Ⅰ-1-1-8図 世界の財貿易、サービス貿易、投資、移民の抑制・促進政策の導入数
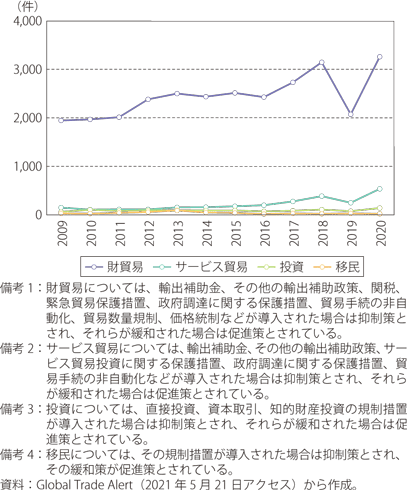
下記(第I-1-1-9図)は、発動されている政策の多数を占める財貿易の抑制策と促進策の数とそれぞれの割合を示している。統計が公表されている2009年以降を見ると、全ての期間において抑制策の方が多く、特に近年では自国を優先する動きが強まった2018年に抑制策の導入が増加し、翌2019年は前年より減少したものの、2020年には再び対前年比で増加した。それぞれの政策の割合でみると、自国優先の動きが強まった2018年以降は抑制策の割合が高止まりしている。
第Ⅰ-1-1-9図 財貿易に関する抑制・促進政策数とその割合
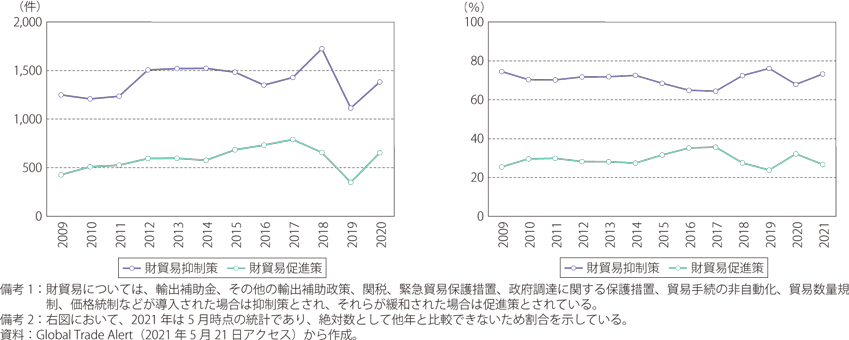
また、新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大した2020年で輸出抑制策と輸入抑制策の採用政策数の割合を見ると(第I-1-1-10図)、輸出抑制策では補助金以外の抑制策がほとんどを占め、輸入抑制策では補助金と関税で七割近くを占める。医療分野での輸出規制を導入している国数が高止まりしていることと同様に、これらの政策が世界貿易量の回復を阻害する可能性には注意が必要である。
第Ⅰ-1-1-10図 輸出制限(左図)と輸入制限(右図)に採用されている政策割合(2020年)
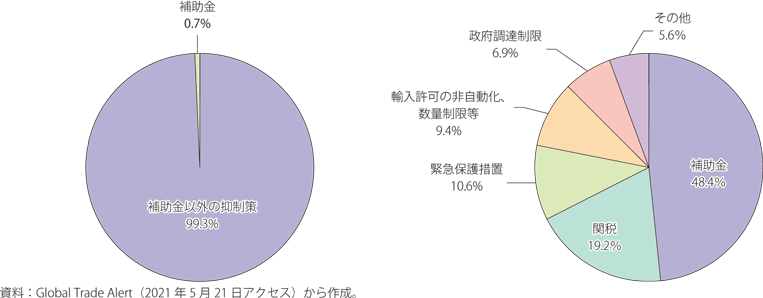
一方で、財貿易全体をみると、輸出数量指数で見た貿易量は2020年後半には回復に転じていることが示されており、財貿易動向を示唆する財貿易バロメータでも当面の貿易量の増加が予測されている(第I-1-1-11図)。財貿易バロメータ(詳細は同図の備考1を参照)は、公表時点から3~4ヵ月程度先の財貿易の動向を示すとされている。2021年5月公表の財貿易バロメータは109.7と財貿易が活発化するとされる100を上回っており、当面の財貿易量が増えていくことを示唆している。
第Ⅰ-1-1-11図 財貿易バロメータと財輸出数量指数
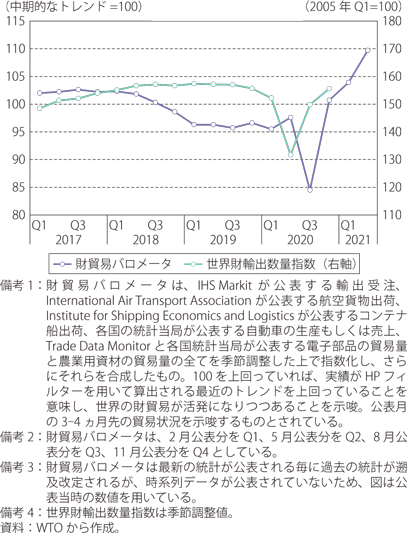
世界の製造業生産の動向からは、医薬品等の生産が足下で持ち直していることが分かる。下記(第I-1-1-12図)は世界の製造業生産の前年比と業種別の前年比寄与度を示している。これによると2021年1月時点で製造業生産への寄与度がプラスであるのは、機械、電子、電気機器、化学である(すなわちこれらの業種では前年比で生産が増加)。多様な分野で半導体の需要が根強いことや、各国の経済対策として家計への現金給付が広く実施されていることによって、家電製品等の需要が回復したことが、機械、電子、電気機器の生産回復に寄与したと見られる。また、化学には医薬品等が含まれることを踏まえると、その増産はワクチン等を供給するための対応が進展していることが示唆されている。
第Ⅰ-1-1-12図 世界の製造業生産の前年比と業種別の寄与度
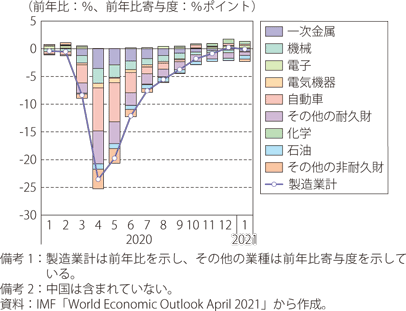
また、2019年10月中旬から2020年10月中旬までの期間に公表または発動された貿易促進策を見ると、新型コロナウイルスの感染対策と見られる医療用品以外にも、幅広い品目で関税の削減や撤廃が決定されている(第I-1-1-13表)。各国の経済回復によって貿易量が自律的に増加するだけでなく、こうした施策も貿易量の回復に寄与していくと見られる。
第Ⅰ-1-1-13表 貿易促進政策(2019年10月中旬から2020年10月中旬に公表・発効)
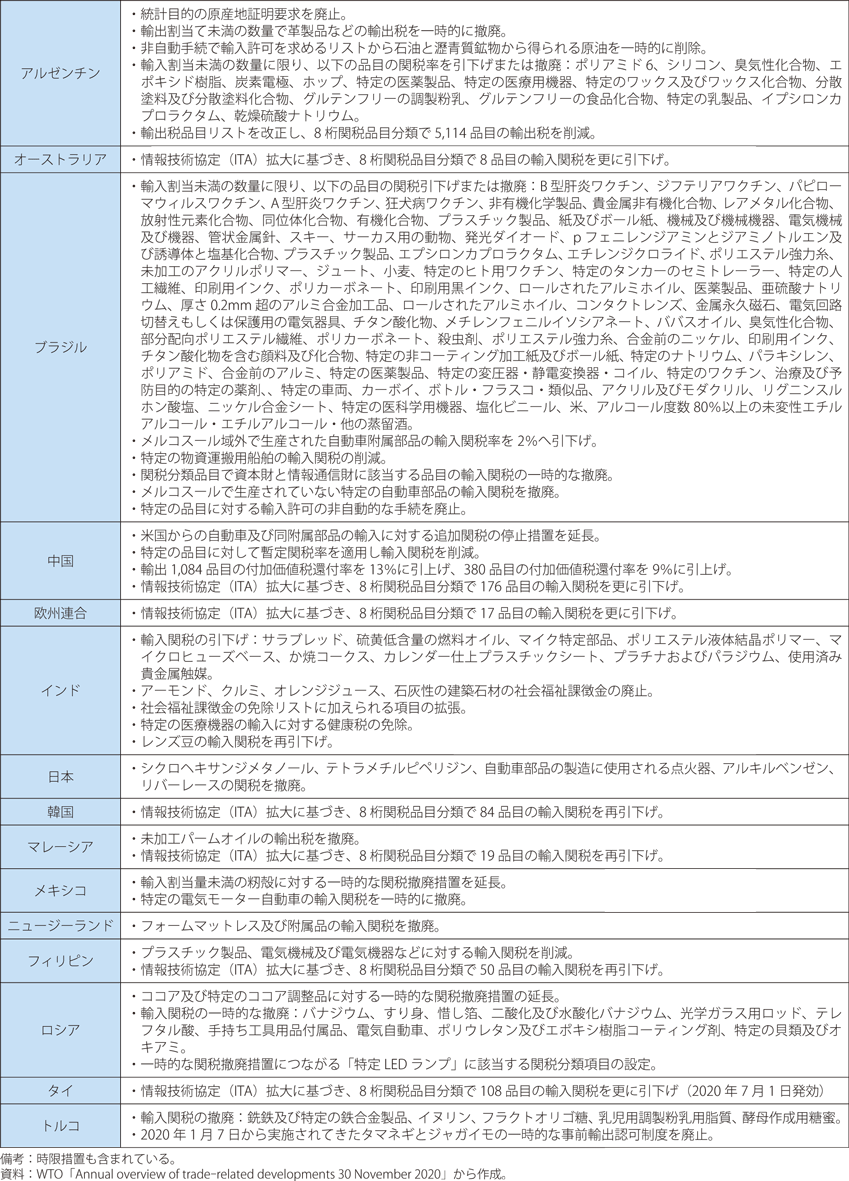
実際に、2020年には世界の輸出金額は減少したものの、新型コロナウイルスの感染拡大によって貿易額が影響を受けた可能性がある医療品目やステイホーム関連の品目に絞って見ると、それらが世界輸出金額に占める割合は増加している(第I-1-1-14図、医療品目とステイホーム品目の詳細は同図の備考2及び3を参照)。医療分野の輸出抑制策を導入している国数が高止まっていることを上述で指摘したが、ここで取り上げた医療品目とステイホーム品目は世界輸出額の下支えになっていることが示されている。
第Ⅰ-1-1-14図 世界の財輸出金額と医療品目・ステイホーム品目のシェア
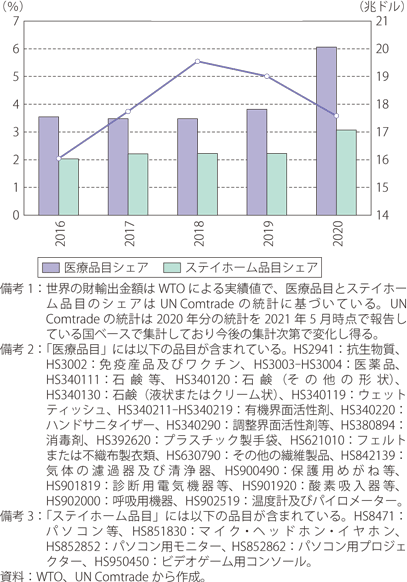
世界の製造業生産も回復に向かっており、それが企業の設備投資の回復を後押ししていくと考えられる。下記(第I-1-1-15図)は世界の製造業生産の水準を産業別に示したものである。それによると世界の製造業生産は2020年前半に大きく落ち込んだものの、その後は回復に転じ、足下では新型コロナウイルスの感染拡大前の水準を取り戻している。回復が速い業種(電子や自動車)と遅い業種(航空や繊維)があり跛行性があるものの、各国政府が実施している信用保証等の企業金融支援策や、インフラ・デジタル投資の促進といったマクロ的な経済対策を通じて、企業の生産体制が整備され、企業の設備投資も回復していくと見られる。
第Ⅰ-1-1-15図 世界の業種別製造業生産
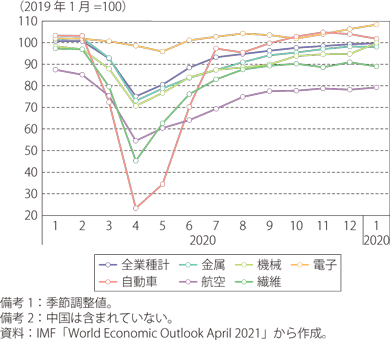
2020年の財貿易量の減少と同様に、新型コロナウイルスのショックは経済見通しを不透明にし、直接投資にも影響を与えた。具体的には、下記(第I-1-1-16図)は国連貿易開発会議(United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD)が公表している対内直接投資フローであり、それによると2020年の世界の対内直接投資フローは9,200億ドルから1兆800億ドルと2005年以来の低水準になったことが予測されている。
第Ⅰ-1-1-16図 世界の対内直接投資フロー
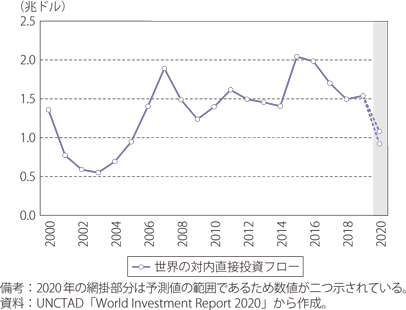
4.新型コロナウイルスの感染拡大に対する企業の順応
新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大した中で、課題となるのは経済社会活動の活発化と感染抑制のバランスを取ることにある。企業景況感を表す代表的な指数である購買担当者指数(Purchasing Manager Index: PMI)を見ると、新型コロナウイルスの感染が世界的に再び深刻化した2020年終盤以降でも、景気判断の境目とされる50を上回って推移している(第I-1-1-17図)。特に景況感が大きく悪化した2020年序盤の感染拡大の初期に比較すると対照的な動きとなっている。企業が新型コロナウイルスの感染が拡大した中でも、新たな経済活動の形を模索し、順応しようとしていることを示唆している。
第Ⅰ-1-1-17図 製造業PMIとサービス業PMI
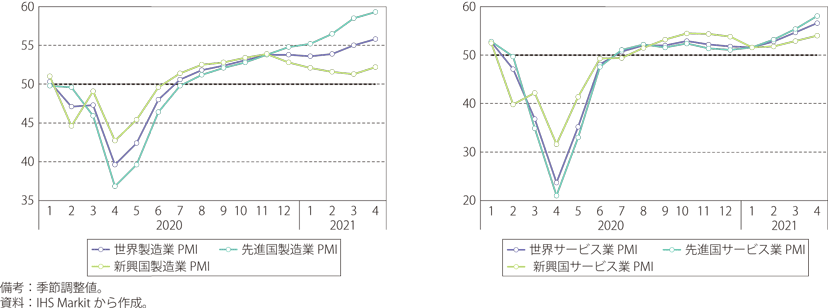
ただし、新型コロナウイルスの感染拡大が、特に接触・対面型のサービスに対して負の強いということには依然として留意が必要である。具体的には、下記(第I-1-1-18図)は、IMFが集計した2020年における業種別の雇用変化率を示している。IMFの分析によれば、新型コロナウイルスの感染拡大によって、2020年に主に失われた雇用は、自動化によって代替されやすい職種と、人との接触型の職種とされた。同図においても、製造業以外で雇用が減少したのは、商業・宿泊業や教養・サービス業といった接触・対面型サービスが主流の業種となっている。一方で、雇用が増加したのは情報・通信業や金融・保険業など非接触型サービスが提供しやすい業種と、不動産や教育・ヘルスケア業といった新型コロナウイルスの感染拡大が特殊な需要(リモートワークの普及による郊外への移住や医療需要等)を喚起したと見られる業種である。このように業種間でも新型コロナウイルスの影響を前提とした経済活動の順応動向には差異があることを認識しておくことは重要である。
第Ⅰ-1-1-18図 2020年の業種別雇用の変化率