第2節 通商を巡る国際潮流
第1節で見てきたように、当面の間、世界各国は新型コロナウイルスの感染拡大防止と経済活動の再開という両者の難しいバランスを探りながらの経済運営を余儀なくされる。また、今後の回復はワクチンの実効性や普及の度合いに加え、変異種の発現及びその感染力といった予見困難な与件にも大きく左右される。こうした感染症との共生を余儀なくされるウィズコロナの状況が継続する環境下で、米中対立を始めとする地政学的な変動は更に動きを増し、我が国を取り巻く国際的な政治環境は、新たな段階に入ってきている。
本節では、先行きが不透明な世界経済と新たな国際政治を踏まえ、我が国における今後の通商政策と企業活動が前提とすべき四つの大きな国際潮流を述べていく。具体的には、①政府の経済面における役割の拡大、②各国における経済安全保障の強化、③国際経済活動における共通価値への関心の高まり、④ビジネスのデジタル化である。これらの潮流はコロナショックにより、これまでも存在していたものが加速したものもあれば、新たに顕在化したものもある。これらの潮流を的確に把握し、適切な行動を取ることが企業に求められよう。
1.政府の経済面における役割の拡大
まず、第一の潮流として捉えておくべきは、「政府の経済面における役割の拡大」である。
コロナショックの影響が長期化する中で、各国・地域は世界金融危機時の対応を上回る規模で、経済的なダメージが集中した産業や家計を中心として積極的な経済対策を講じている。こうした経済対策について、米国、欧州、中国に絞って整理すると第Ⅰ-1-2-1表となる。
第Ⅰ-1-2-1表 米国、欧州、中国の主な経済対策
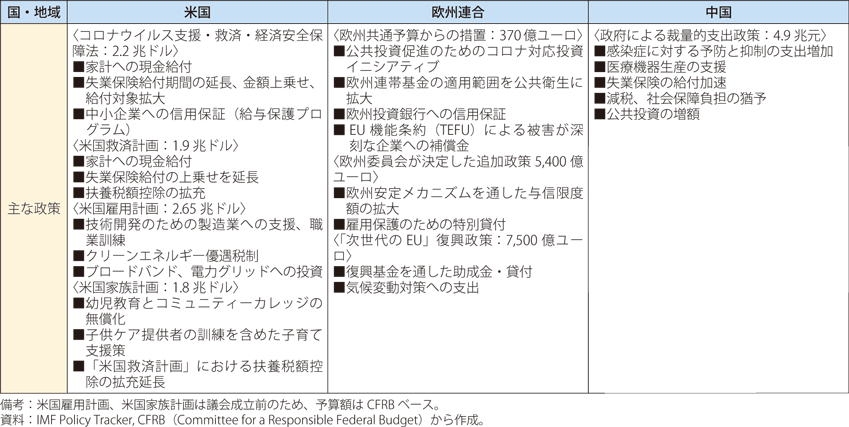
米国においては、コロナウイルス支援・救済・経済安全保障法や米国救済計画において、失業保険給付金の上乗せ及び給付期間の延長や家計への現金給付と税還付といった支援に加えて、中小企業への信用保証などが実施された。さらにバイデン政権下において、米国雇用計画(2021年3月)と米国家族計画(同年4月)という2つの経済政策構想を発表するなど更なる経済政策が予定されている。米国雇用計画は、構想では約2兆ドルに上る経済政策であり、輸送インフラのアップグレード、高速通信網の整備、住宅や商業ビル等の建築・維持・改修、研究開発支援、製造業・小規模ビジネス支援等が盛り込まれ、雇用の質の向上が意識されている。さらに米国家族計画については、①最低4年間の無償の公教育の追加提供、②子どもや家族に対する直接的な支援、③子どもを養う家族や労働者に対する減税の延長を内容とするなど、米国の家族が以前から直面していた課題に対応するものとなっている。また、両計画の発表に併せて、税制改革案を発表し、米国雇用計画は8年、米国家族計画は10年程度を予定している支出の全財源を賄う方針を示している。
また、欧州においては、復興基金(Next Generation EU)が創設され、コロナショックで経済的にダメージが大きかった国に対し、グリーン分野への支援と一体化した支援の方向を示している。中国においては、失業保険給付の加速や、社会保障負担の猶予に加え、公共投資の増額などが実施されている。
このように、政府の経済対策の中には、コロナ禍により特に困窮すると考えられる者を対象とした支援策に加えて、社会のデジタル化やグリーン社会の実現といった、コロナ後を見据えた経済構造への移行や適応のための支援も含まれていることには注視が必要であろう。
主要国・地域の経済対策の規模を名目GDP比で見てみると、第Ⅰ-1-2-2表のようになる。追加財政支出・減税等に含まれる現金給付、企業補助金、減税措置等は、雇用維持や倒産防止を図り、生産活動再開時には即時復帰を実現するため、対象者に直接必要な資金等が届く政策手段として用いられており、政府の財政収支に直接影響を与えるものである。一方で、資本注入・貸付・信用保証等は政府の財政収支に直ちに影響を与えるものではないが、出融資先企業の倒産等により将来的に政府の負担となる可能性もある。
第Ⅰ-1-2-2図 新型コロナウイルスを受けた経済対策の規模
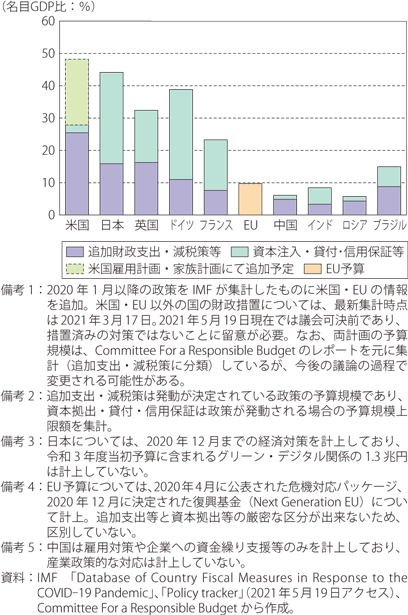
各国・地域において、追加財政支出・減税策等と資本注入・貸付・信用保証等のそれぞれの規模が異なっていることは、それぞれの国・地域の経済の特徴や公的金融機関の役割等を反映していると見ることもできる。例えば、米国においては、外部ショックに解雇で人員調整する労働市場メカニズムを有していることも早期の現金給付や失業保険の給付拡充が実施された背景にあると考えられる。他方、欧州各国や日本は、雇用維持策も行いつつ、資本注入・貸付・信用保証といった多様な資金提供の仕組みも提供されている。また、欧州復興基金は、EU共通債券発行等も財源とし、当該債券の償還財源として、プラスチック賦課金等を導入済または検討することとされており、2026年年末までの支出が可能となっている。また、前述のとおり、米国の雇用計画、家族計画は、将来的な増税も財源にして、長期にわたる支出が予定されているなど、欧州、米国ともに救済から成長基盤の強化へ軸足を移す際に、公的支出についてもより長期のコミットメントがなされているといえる。
成長基盤の強化策の一つの軸である社会のデジタル化について、まずEUの動きから見ていくと、EUは2021年3月に2030年までの欧州のデジタル化への移行実現を目指し、目標などを定めた「デジタルコンパス2030」を発表している。このデジタルコンパス2030は大きく4つの柱で構成されており、①デジタルリテラシーの向上と高度デジタル人材の育成、②安全・高性能・持続可能なデジタルインフラの整備、③ビジネスのデジタル技術活用、④公的サービスのデジタル化を掲げている。こうしたデジタル化の各目標の進捗状況を確認する仕組みとして、EUは報告書を毎年作成し、目標達成に遅れの見られる加盟国に対しては勧告を出すだけなく、技術支援を提供する予定としている。これにより加盟国のデジタル化を加速させていくことを目指すとしている3。
我が国も、デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針を2020年12月に打ち出し、デジタル社会の将来像やデジタル庁の設置を表明している4。特に、データが価値創造の源泉であり、その流通、利用がデジタル社会の重要な礎であることを踏まえ、デジタル技術の善用により、データを効果的に活用した多様な価値・サービスの創出を可能とすることを目指すとしている。これにより、社会課題の解決、持続的かつ健全な発展、国際競争力の強化にも資することが期待されている。
さらに、デジタル庁は、デジタル社会の形成に関する司令塔として、強力な総合調整機能を有する組織とされており、基本方針を策定するなどの企画立案や、国、地方公共団体、準公共部門等の情報システムの統括・監理を行うととともに、重要なシステムについては自ら整備するとしている。これにより行政サービスの質が抜本的に向上され、デジタル社会の実現に大きな一歩となることが期待される。
成長基盤強化のもう一つの軸であるグリーン社会の実現については、コロナショック前からの取組を経済回復策とも組み合わせつつ、脱炭素社会の構築に向けた対応を新たな投資の起爆剤とした「グリーン成長」の実現を目指す動きが各国・地域で見られる(第Ⅰ-1-2-3表)。
第Ⅰ-1-2-3表 各国のグリーン成長実現に向けた政策
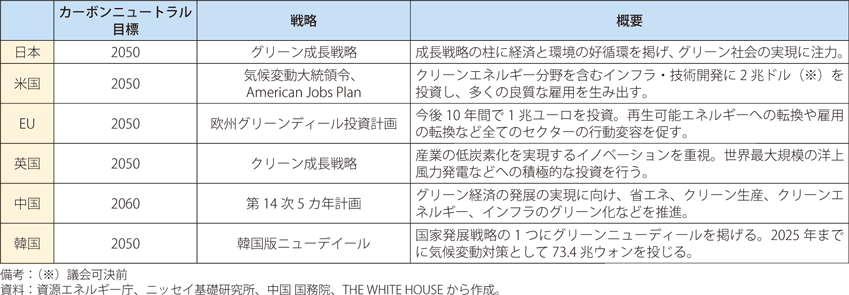
例えば、EUはグリーンディール(2019年12月)5において、環境配慮と経済の両立や、CO2排出量をネットゼロにするというカーボンニュートラルを掲げていることに加え、企業の事業活動をサステナビリティへの貢献といった観点も踏まえて分類するタクソノミー6を策定するなど、資金がよりサステナブルな企業行動に配分されることを企図したサステナブルファイナンス計画7を実行している。
我が国も、2020年10月に2050年カーボンニュートラルを目指すことを宣言し、経済と環境の好循環を作っていく産業政策として2020年12月に「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を取りまとめた8。本戦略では、洋上風力、水素、カーボンリサイクルといった14の重要分野ごとに、高い目標を掲げた上で、現状の課題と今後の取組を明記し、予算、税、規制改革・標準化、国際連携など、あらゆる政策を盛り込んだ実行計画を策定している。
このような政策的支援も背景に、世界全体でカーボンニュートラルを2050年までに実現することにコミットした国・地域の数を見ると、世界125か国・1地域(2021年4月末時点)に及ぶ。これらの国における世界全体のCO2排出量に占める割合は39.0%(2017年実績)となっており、名目GDPでは世界の63%を占めている(第Ⅰ-1-2-4図)。また、中国も2060年のカーボンニュートラルを目指していることから、世界全体へのインパクトがより大きくなってくると考えられる。
第Ⅰ-1-2-4図 2050年カーボンニュートラルに賛同した国(世界125か国・1地域)の世界全体に占めるCO2排出量と名目GDPの割合(%)
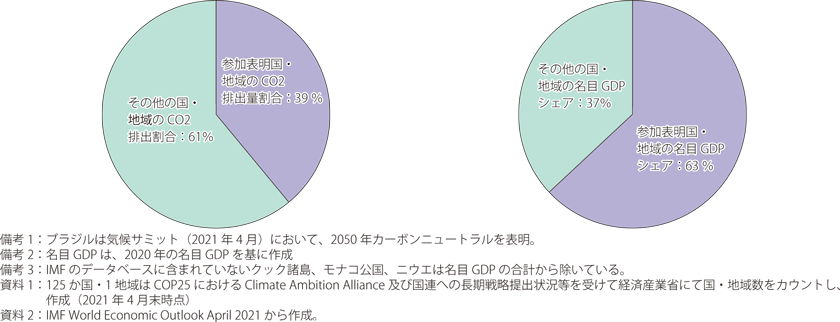
このようなコロナショックからの回復に向けた過去に例のない大規模な経済対策、経済社会システムの変化への対応に向けたデジタル化、グリーン成長の実現に向けた動きは、政府の明確な政策方針や支援策のデザインによる予見可能性の確保が積極的な民間投資へ繋がるという産業政策的な発想にも根拠づけられる。政府の役割の質的な強化を模索する動きともいえ、国家間の協調がますます重要となる。
3 JETROビジネス短信「欧州委、2030年までの官民のデジタル化目標提案」、2021年3月12日。
4 首相官邸「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」、2020年12月25日。
5 EU(2019)「The European Green Deal」
6 EU「EU taxonomy for sustainable activities」
7 EU「Platform on Sustainable Finance report on transition finance - March 2021」
8 経済産業省ニュースリリース、2020年12月25日。
2.各国における経済安全保障の強化
第二に着目すべき潮流は、「各国における経済安全保障の強化」の流れである。
米中の技術覇権を巡る争い等を背景とし、米中を始めとして、経済安全保障に関する取組が強化されており、新型コロナウイルス感染症の拡大によりサプライチェーンのぜい弱性が顕在化したこととも相俟って、そうした傾向に拍車がかかっている。
中国においては、科学技術の自立性の強化やサプライチェーンの強靱化が国家戦略として明確に位置付けられたほか、重要技術の国産化等の取組が更に加速している。
米国の経済安全保障に係る一連の政策展開において、2018年8月に成立した2019年度国防授権法(National Defense Authorization Act 2019: NDAA2019)が一つの転機となった。本法自体は国防総省に予算権限を与えるため毎年制定されるものであるが、この中で最先端技術の研究開発の推進を含む総額7,160億ドルの国防予算、輸出管理及び投資管理の強化、特定企業の通信機器などの政府調達などの制限、サイバーセキュリティ強化などが定められた。
輸出管理の強化については、輸出管理改革法(Export Control Reform Act: ECRA)がNDAA2019の一部として挿入される形で定められた。ECRAは、永続的な輸出管理基本法であり、開発初期段階であっても将来の軍事技術体系を変更し得る新興技術(エマージング技術)や、それらを支える基盤技術を特定し、輸出管理の対象とすることが定められた。また、同法の下位規則として輸出管理規則(Export Administration Regulations: EAR)が位置付けられ、同規則の改正により機動的な輸出管理が行われている。軍民融合戦略への関与が懸念される中国企業等を念頭に、トランプ前政権下で導入された輸出管理強化措置については、政権交代後も継続されている。措置の詳細については、第Ⅱ部で紹介する。
投資管理の強化については、外国投資リスク審査近代化法(Foreign Investment Risk Review Modernization Act: FIRRMA)がNDAA2019の一部として挿入される形で成立し、2020年2月に完全施行された。従来は、米国企業に対して支配を及ぼし得る合併や議決権・代理権などの取得、買収行為に係る取引について、事前通報を義務づけることなく、国家安全保障レビューの対象としていたところ、FIRRMAにより事前確認方式が導入され、外国政府の影響下にある投資家による重要インフラ、重要技術又は米国民の機微個人情報に関する投資で、かつ企業経営に影響を与え得るものに対し事前申告を義務付けられることとなった。また、事後介入の範囲についても、重要インフラ、重要技術又は米国民の機微個人情報に関する「非支配的であっても受動的でない投資」9を対象取引に追加されることになった。
EUにおいても、2016年9月、人権の保護などに関連して輸出管理を強化するとともに、輸出規制運用に係る域内協調を図るため、欧州委員会がEU輸出規則改正案を公表した後、2018年に欧州議会、2019年に欧州理事会がそれぞれ修正案を公表した。詳細は第Ⅱ部で紹介するが、人権保護を理由とする追加の輸出管理強化措置も取られている。
投資管理については、2019年3月、欧州議会及び欧州理事会が欧州投資規則を採択した。同規則は2019年4月に発効し、2020年10月に全加盟国において施行された。同規則は、欧州委員会、加盟国間の情報交換を主な目的としている。また、対内直接投資による国家安全保障又は公の秩序への影響を判断するに当たって、欧州委員会・加盟国は、特に、エネルギー、医療、データストレージ等重要インフラ、AI、半導体等の重要技術等への潜在的な影響を考慮することができるとされている。2020年度末現在、19の加盟国が投資スクリーニング制度を導入しており、本規則に沿った改正が進められている。フランスでは、AIやロボティクス、半導体など重要な技術に関連する投資を事前審査の対象として追加したほか、ドイツでも同様の動きが見られている。
さらに、コロナ禍においては、サプライチェーンのぜい弱性への懸念が高まったことを受け、各国・地域ではその強靱化を通じた経済安全保障の強化が対外政策上も重視されている。米国においては2021年2月に、重要な製品や材料等のサプライチェーン強靱化を確保するための大統領令が署名された。その中では、人権や環境といった価値観を共有する同盟国やパートナー国との国際連携の必要性が強調されている。大統領令では、①先端パッケージングを含む半導体、②電気自動車用バッテリーを含む大容量蓄電池、③希土類(レアアース)を含む重要鉱物及び戦略物資、④医薬品及び医薬品有効成分の4分野については、大統領令発令日から100日以内に、サプライチェーン上におけるリスクを特定し、そのリスクへの対処方針を提言する報告書を大統領に提出するよう担当省庁に求めている。また、①防衛産業基盤、②公衆衛生及び生物事態対処産業基盤、③情報通信技術産業基盤、④エネルギー産業基盤、⑤輸送産業基盤、⑥農作物及び食糧、の6分野については、大統領令発令日から1年以内に報告書を大統領に提出するよう担当省庁に求めている。
EUは、2021年5月に電池や半導体といった戦略的な重要物資の域外依存度を分析し、特定国への依存を低減させ自立化を図っていくこと等を内容とする新たな産業政策「2020産業戦略アップデート」を発表した10。この中で、戦略的な観点からの依存度分析として、EUが輸入している5,200品目のうち、137品目を輸入依存度が高い品目として特定し、そのうち、34品目(エネルギー関連の原材料や化学品、医薬品原薬など)については、代替が困難で、よりぜい弱である可能性を指摘している。こうした分析を踏まえ、EUは加盟国間での標準共通化や適合性評価の迅速化を含む域内の物資供給の円滑化や、戦略分野における特定国への高依存に対処するため、国際的なパートナーシップを進めるとともに、半導体等の分野における官民協働のアライアンスの支援を行っていく旨を表明している。
我が国も、半導体・デジタルインフラ・デジタル産業について、我が国の戦略的不可欠性と戦略的自律性を確保するため、研究開発や事業展開を実施する事業者の確保を図るとともに、米国や欧州と連携した世界的相互依存関係の中で、技術力及び生産能力の面で、日本が中心的な役割や貢献を果たすべく取組が進められている11。
こうした状況の中、先端技術の開発・育成・管理をはじめとして、有志国による連携の具体的な動きが広がりを見せてきている。我が国においても、有志国連携を通じてサプライチェーンの強靭化を図っていくため、2021年4月に開催された日米首脳会談において、重要技術を育成・保護しつつ、半導体を含む機微なサプライチェーンに関する連携を確認している。さらに、2021年5月に開催された日EU定期首脳協議においても、半導体等の重要なグローバル・サプライチェーンの強靭性に関する連携を確認している。
また、日本、米国、オーストラリア、インドの4か国の首脳会談において、重要・新興技術や気候変動の作業部会を立ち上げ、4か国間及びそれ以外の有志国との連携を図ることを発表している。
このように各国が経済安全保障の動きを強めながら有志国連携を形成しようとする流れがある中、企業においては、各国の外交的立ち位置と経済安全保障の政策動向を強く意識した上で、企業戦略を立てることがますます重要になってきている。
9 非支配的であっても、取締役などへの就任、非公開情報へのアクセス、重要な意思決定への関与などが可能となる投資などを指す。
10 European Commission(2021), Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for Europe’s recovery.
11 経済産業省「半導体・デジタル産業戦略」
3.国際経済活動における共通価値への関心の高まり
第三の潮流は、「国際経済活動における共通価値への関心の高まり」である。
人権や環境といった共通価値を実現するため、企業活動の変革を促そうとする国際的な潮流はこれまでも存在しており、国や企業は取組を行ってきた。
2000年以降の大まかな流れを整理すると第Ⅰ-1-2-5図のようになる。2011年には、国連人権理事会において「ビジネスと人権に関する指導原則」が支持され、これに基づき、各国が国別の行動計画(National Action Plan; NAP)を策定している。2021年5月現在で、我が国12を含む24か国がNAP策定済み、3か国が「ビジネスと人権」の要素を含めた人権に関する計画を策定済みとなっている13。さらに、2015年9月には国連総会においても17の目標・169のターゲットからなる持続可能な開発目標であるSDGs(Sustainable Development Goals)14が採択された。また、2015年12月のCOP21(第21回気候変動枠組条約締約国会議)では、地球温暖化対策の国際的な枠組みであるパリ協定の合意もなされ、途上国を含む全ての参加国に、排出削減の努力を求めることとなった。
第Ⅰ-1-2-5図 ESGやSDGsに関連するイニシアティブ
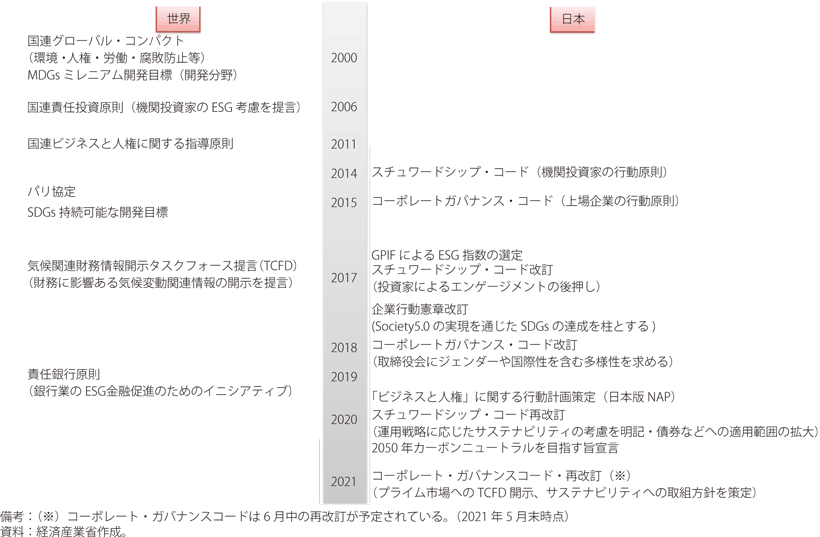
このような、等しく人権を確保し、環境を保護していくという国際的な流れは、企業にとって、社会課題への取組と経済的な価値の創造が両立しやすい方向への変革ともいえる。気候変動といった地球規模の課題の解決が待ったなしになる中、経済活動において大きな影響力を持つ企業が積極的に世界規模の課題を解決することが求められている。
また、このような取組が急速に進んでいる背景には、資本市場からの後押しもある。責任投資原則(Principles for Responsible Investment; PRI)に賛同する署名機関数及び運用資産額を見ると、2010年には734だった署名機関数が、2020年には3,000を超え、運用資産額も約5倍近くとなっていることから、資本市場において環境や社会に配慮した企業の取組や企業のガバナンス体制を重視する方針が広がりをみせていることが分かる(第Ⅰ-1-2-6図)。
第Ⅰ-1-2-6図 PRI署名機関数と運用資産額の推移
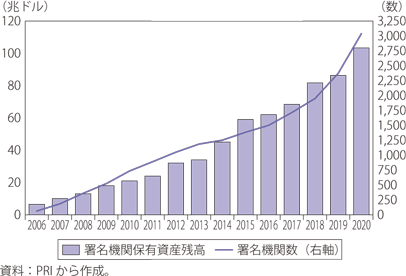
トランプ前政権下の米国においては、パリ協定からの離脱など、環境の持続可能性を高めようとする流れから遠ざかる動きが見られ、新型コロナウイルスの感染拡大への対応時には国際協調への遠心力が懸念された15。国も企業も目下のコロナ対策に注力せざるを得なくなり、国際協調をベースとした経済社会システムを基本的な価値という観点から変革していこうとする流れへの関心は薄れがちとなり、自国優先主義の動きも見られた。
しかし、2021年1月の米国政権交代以降、米欧の連携が意識されるに始まり、国際的な連携を価値という軸からも強化していこうとする流れが再び見られつつある。
環境分野については、パリ協定が求める水準と整合した温室効果ガス排出削減目標(Science Based Targets: SBT)を定める企業が増加している(第Ⅰ-1-2-7図)16。このような企業の自主的な取組の広がりは、資本市場や取引先から、先進的な取組を行う企業に倣った取組を行う要請の強化にもつながり得る。例えばAppleは、サプライヤー行動規範と、詳細な指針であるサプライヤー責任基準を定め、サプライヤーに対して、労働、人権、健康、安全、環境保護といった項目を遵守するように求めている17。
第Ⅰ-1-2-7図 SBTに参加する企業数(世界全体)
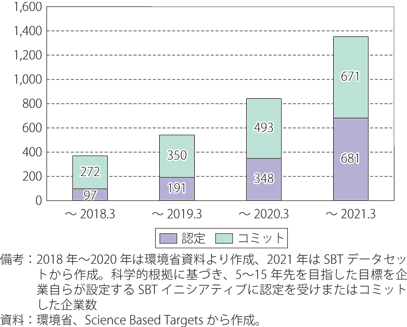
加えて、公的な政策として、米・欧州各国やEUでの制裁措置や人権デュー・ディリジェンスの法制化の動きが挙げられる。前者は、例えばある国において人権侵害が見られた場合、人権保護を目的として輸出管理強化や輸出規制を導入するというものである。後者は、強制労働や児童労働、ハラスメントといった人権侵害のリスクを特定し、予防策や軽減策について必要な開示の実施を企業へ義務付けるものである。これらの法律は、自国で設立された企業以外にも義務を課していることもあることから、既に影響は大きく、英国が現代奴隷法(UK Modern Slavery Act 2015)を制定して以降、欧州を中心に広まってきている。
こうした企業活動を通じて共通価値の実現を求めていく国際的な潮流は、企業同士のビジネス上の契約関係を全体として捉え、人権や環境に対して関係する企業が等しく責任を持つべきであるという考え方に基づくものである。国際的に共有されている価値と合わない事業活動について一定の制約が課されるようなことも想定され、調達先の労働環境、原材料の栽培地や採取現場での環境汚染に対しても、これまで以上の配慮が求められ、深刻な場合には取引が制限されるリスクが顕在化している。
他方、こうした共通価値に関心を払い、社会課題の解決に向けて貢献してくことは、新たなビジネスチャンスともなり得るものである。詳細については、第II部第2章で述べていく。
12 外務省報道発表、2020年10月16日。
13 United Nations Human Rights、「State national action plans on Business and Human Rights」。
14 外務省 仮訳「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」
15 通商白書2020
16 環境省「グリーン・バリューチェーンプラットフォーム」。
17 Apple社ホームページ「Appleサプライヤー行動規範・Apple サプライヤー責任基準」
4.ビジネスのデジタル化
第四の潮流として、「ビジネスのデジタル化」の流れが挙げられる。
コロナショックがもたらした感染拡大防止と経済活動を両立する必要性は、様々な場面でのデジタル技術の利用を一層拡大させ、デジタル化の流れを加速させている。
マッキンゼー・アンド・カンパニーが実施したアンケートによると、新型コロナウイルスの感染拡大以降は、①サプライチェーンのデジタル化、②顧客との接点、③従業員とのコミュニケーション、④自動化とAIのいずれの項目についてもデジタル化が加速したとの回答が目立った(第Ⅰ-1-2-8図)。以下では、個別の項目について詳しく見ていく。
第Ⅰ-1-2-8図 新型コロナウイルス感染拡大以降の企業・事業領域におけるデジタル化・自動化への展開の変化
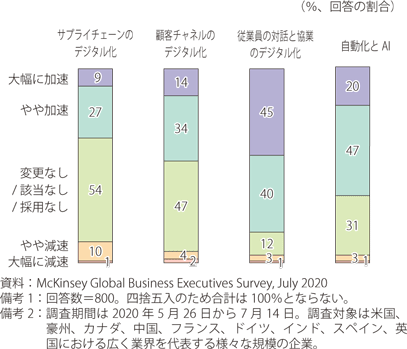
まず、働き方について見ていくと、米国では新型コロナウイルスの感染拡大時にリモートワーク実施率が大きく上昇した。この変化は一時的なものではなく、今後も続くとみられており、2025年においても新型コロナウイルス感染拡大前の約2倍になることが見込まれている(第Ⅰ-1-2-9図)。
第Ⅰ-1-2-9図 米国におけるリモートワークの割合
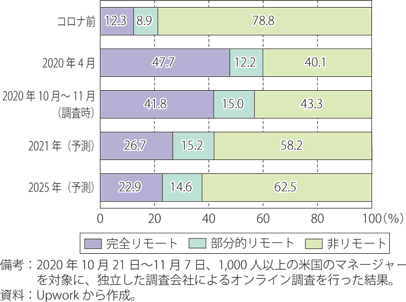
また、対面・接触型の取引に制約がある中、ロックダウンを契機として電子商取引(Electronic Commerce: EC)も拡大している。EC市場は、第Ⅰ-1-2-10図に示すとおり、2020年序盤に新型コロナウイルスの感染が拡大してからは、全体的に拡大している。
第Ⅰ-1-2-10図 各国のEC小売売上の売上げ水準(指数化)
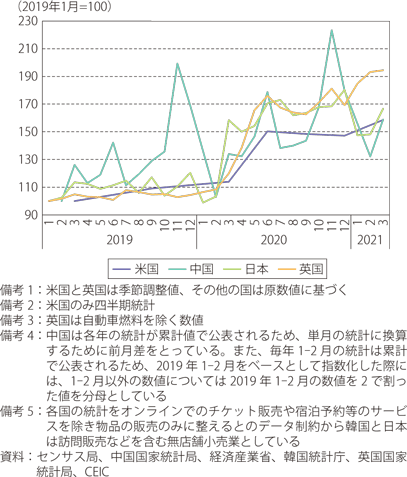
さらに、イベントのオンライン化やネット上でのマッチングも増加しており、日本貿易機構(JETRO)はコロナ禍においてフェイス・トゥ・フェイスの商談が難しい中、デジタルツールを活用した市場開拓の支援、新たなビジネスパートナー発掘に向けた支援を進めている。
このような中で、企業にはデジタルトランスフォーメーションへの取組がますます求められる。コロナショックでぜい弱性が明らかになったサプライチェーンについては、有事に対応した代替生産や増産、柔軟な販売戦略を可能とすることが必要であり、前述の共通価値への対応の観点からも、デジタル技術を活用してサプライチェーン全体を可視化・管理していくことの重要性が高まってきている。詳細は第II部第1章第3節で述べる。
また、デジタル化の導入の進行は上記のような企業活動の側面に限らず、個人の日常生活の様々な場面にも及んでいる。感染確認アプリの普及などを含めた様々な「コロナテック」も実装されつつあるのはその一例である。これらは、防疫措置に直接資する社会実装と、新型コロナウイルスの感染拡大で変化した新たな生活様式に対応する社会実装に大きく分けて考えることができる。前者については、感染確認アプリを始め、AI医用画像診断、オンライン医療などが該当する。後者はオンライン教育、オンライン会議ツール、ライブコマースなどが含まれる。オンライン会議ツール利用者数を見ると新型コロナウイルス感染拡大後に急増していることが見て取れる(第Ⅰ-1-2-11図)。
第Ⅰ-1-2-11図 オンラインコミュニケーションツールの利用状況
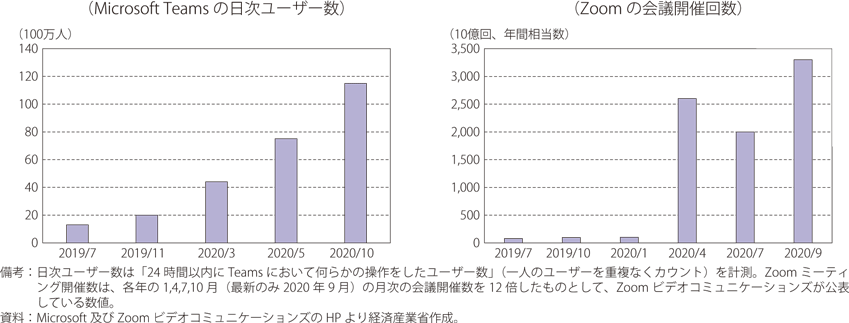
これまで述べてきたデジタル化は、コロナショック以前からも、急速な情報通信技術の発展やそれを支える通信インフラの世界的な拡充を背景に進展してきていた。このことは、世界の直接投資フローが伸び悩む一方でロイヤリティ・ライセンス料の支払いが増加していることに見られるように、世界全体ではアライアンスを組みながら無形資産で稼ぐビジネスモデルが主流になりつつあることにも表れている。他方、日本では資本関係による強固な関係性を保ちつつ、無形資産で稼ぐビジネスが主流である(第Ⅰ-1-2-12図)。日本のビジネスにおける更なるデジタル化が国際的なビジネス展開のあり方を変容させるかどうかについては今後要注目であろう。
第Ⅰ-1-2-12図 無形資産・直接投資から見る世界及び日本のビジネスモデル
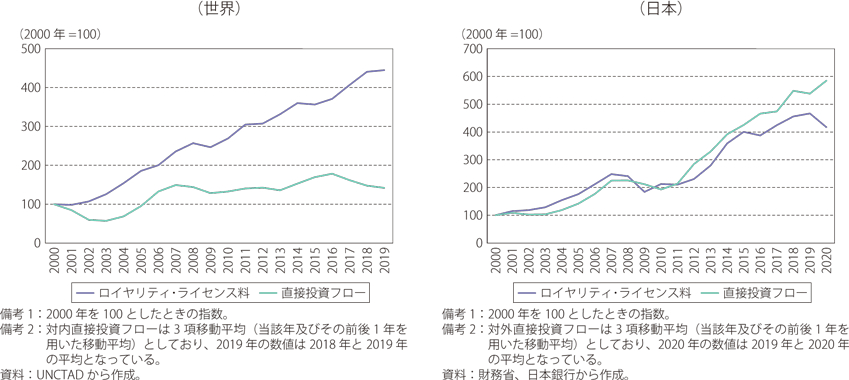
ウィズコロナの世界においても、このような国境を越えた交易のもたらす便益を引き続き享受していくためには、デジタル技術に適応したビジネスモデルや社会インフラの構築が不可欠となっている。同時に、企業の拠点配置や国際分業の在り方も変容させていくことが重要であり、そのためにはプライバシー保護やセキュリティなどの信頼確保と自由なデータ流通が両立する国際ルールの策定が急務となっている。
以上述べてきた四つの大きな国際潮流は、国家のみならず、企業活動に対しても大きな変容を迫り、速やかな適応を求めるものである。これらの潮流を踏まえて、第II部では、レジリエント(強靱)なサプライチェーンの構築、共通価値を取り込む新たな成長の要請、信頼あるグローバルバリューチェーンの構築に向けた対応について、順にみていく。