第1節 回復途上の米国経済
1.実質GDPの回復は順調
2020年の米国経済の実質GDP成長率は-3.5%となり、戦間期の特需が剥落した1946年(-11.6%)以来の低さとなった。需要項目別で見ると、政府消費支出の増加と輸入(GDP統計では控除項目)の減少が成長率にはプラス要因として寄与したが、個人消費、投資、輸出といった主要な項目の減少によって米国経済の成長が低迷した(第I-2-1-1図)。
第Ⅰ-2-1-1図 米国の実質GDP成長率と構成項目の寄与度
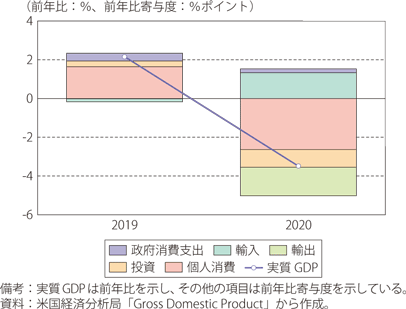
米国の政策当局と国際機関の2021年の実質GDP成長率見通しを比較すると、世界経済と歩調を合わせて米国経済も立ち直ることが予測されている(第I-2-1-2表)。73年ぶりの低成長となった2020年から、2021年にはその落込みを取り戻す以上の高成長率が見込まれている。
第Ⅰ-2-1-2表 米国の実質GDP成長率予測の比較
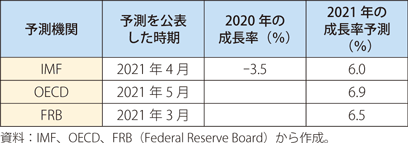
四半期ベースで足下の動向を見ると、新型コロナウイルスの感染拡大が本格化した2020年4-6月期には実質GDPが前期比年率-31.4%となり、過去最大となる落込みとなった(第I-2-1-3図)。需要項目別では年ベースと同様に、個人消費、投資、輸出が大きく落ち込んだ。しかし、それ以降は立ち直り、実質GDPは3四半期連続でプラス成長を維持している。新型コロナウイルスの影響で落ち込んでいた個人消費、投資、輸出が回復を主導している。
第Ⅰ-2-1-3図 米国の四半期実質GDP成長率と構成項目の寄与度
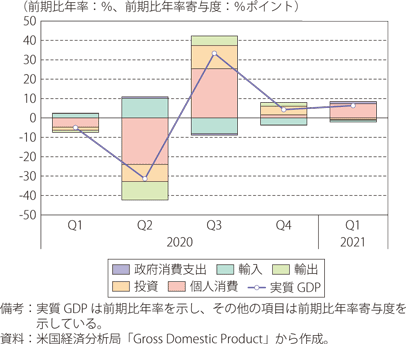
新型コロナウイルスの感染拡大といった特殊要因によって、実質GDP成長率は上下双方向への振れが大きくなっていたものの、2008年から2009年にかけて米国経済に大きな影響を与えた世界金融危機に比較しても、現状の回復ペースは順調である(第I-2-1-4図)。具体的には、米国の実質GDPは、同危機の際に2008年第3四半期から2009年第2四半期まで4四半期連続の減少となり、同危機の直前となる2008年第2四半期に比較して-3.9%となる水準まで落ち込んだ。2009年第3四半期以降は回復に転じたが、同危機前の水準を取り戻すには二年半(10四半期)の時間を要した。
第Ⅰ-2-1-4図 世界金融危機時(左図)と新型コロナウイルス感染拡大時(右図)の米国の実質GDP
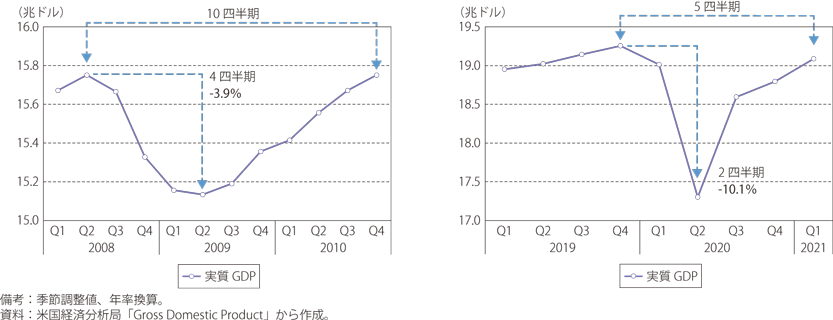
一方で、新型コロナウイルスによる経済の混乱で、米国の実質GDPは2020年第1四半期から同年第2四半期まで2四半期連続の減少となり、経済が混乱する前の2019年第4四半期に比較すると-10.1%と金融危機時よりも大幅に落ち込んだ。しかし、実質GDPは2020年第3四半期から回復に転じ、2021年第1四半期の時点で2019年第4四半期の水準をほぼ取り戻しており、ほぼ一年(5四半期)で落ち込み分を取り戻した。後述のとおり、新型コロナウイルス対策として、米国政府による大規模かつ迅速な対応が行われたことが経済の回復に寄与していると見られる。
2.業種によって異なる雇用回復と労働市場の新たな動き
新型コロナウイルスの感染拡大に影響を受けた米国の労働市場の動きを非農業部門雇用者数より確認する(第I-2-1-5図)。上述の実質GDPと同様に世界金融危機との比較で見ると、同危機時には米国の住宅市場が既に後退期に入っていたことなどもあり、非農業部門雇用者数は2008年1月をピークに減少を始めていた。その26か月後の2010年2月にピーク時から871万人の減少となったところで底を打ち、同危機前のピークに戻すには6年以上(77か月)を要した。
第Ⅰ-2-1-5図 世界金融危機時(左図)と新型コロナウイルス感染拡大時(右図)の米国の非農業部門雇用者数
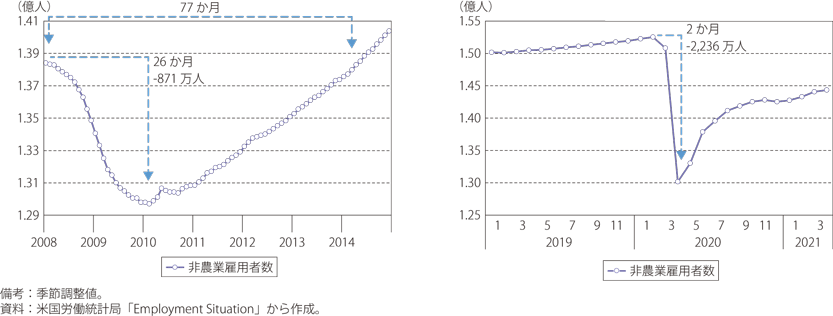
一方で、新型コロナウイルスの感染拡大下では、経済活動が制限され始めた2020年3月から非農業部門雇用者数は2か月連続で減少し、合計で2,236万人もの雇用が失われた。その後は増加に転じているが、足下では新型コロナウイルス感染拡大前のピーク(2020年2月)に比較してまだ840万人少ない水準にある。しかし、雇用が回復し始めてから12か月(2021年4月時点)で失われた雇用の6割以上が取り戻されていることから、雇用全体の回復は比較的に順調であると見られる。
ただし、世界経済でも地域や国別の回復動向に差異が見られるように、米国の労働市場にも跛行性が見らる(第I-2-1-6図)。具体的には、現金給付といった経済対策が家計の財消費支出を下支えしたこともあり、製造業の雇用は新型コロナウイルスの感染拡大前の水準を5%程度下回るまでに持ち直してきた。一方で、非農業部門雇用の大部分を占める民間サービス業の雇用は回復のペースが鈍く、特に娯楽・飲食・宿泊といった業種では感染拡大前を大きく下回った水準にとどまっている。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、接触・対面型の経済活動に対して強い制限がかけられた影響が米国の雇用動向に表れている。
第Ⅰ-2-1-6図 米国の製造業と娯楽・飲食・宿泊業の雇用者数
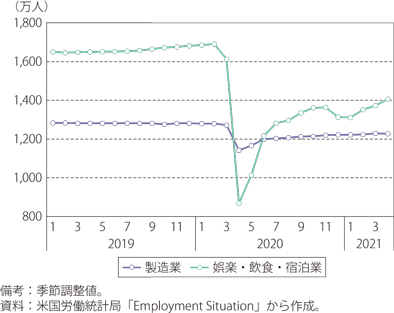
米国の雇用は新型コロナウイルスの影響によって、感染拡大前の水準を依然として下回っているものの、近年には見られなかった新たな動きが出てきている。下記(第I-2-1-7図)は従業員雇用を前提にした起業申請件数の推移を示している。これによると、新型コロナウイルスの感染が拡大し、雇用が大幅に削減された中でも、2020年半ばには起業申請件数が大きく増加している。上述のとおり、新型コロナウイルスの感染拡大によって、米国の実質GDP成長率は歴史的な低水準に落ち込んだが、こうした起業申請件数の増加は、感染症といった新たなリスク要因に対して社会生活を変化させていく必要性を捉えた起業家精神の現れであるとも考えられる。
第Ⅰ-2-1-7図 米国における従業員雇用を前提にした起業申請件数
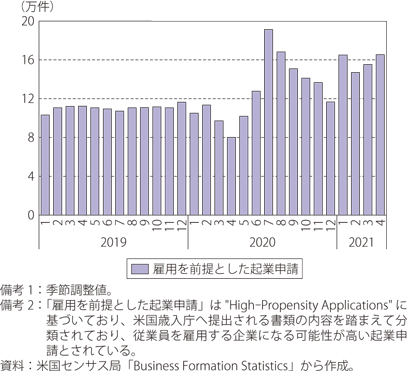
3.世界金融危機時と新型コロナウイルス感染拡大下の経済対策比較
新型コロナウイルスの感染が深刻になってからの米国の経済対策を、世界金融危機時の経済対策と対比する。世界金融危機は、サブプライムローンと呼ばれる低所得者向けの住宅ローンが不良債権化し、世界の金融機関がそれを原資産として組成された有価証券に投資していたため、結果として多大な損失が幅広い地域・国で計上されたことに端を発する需要型ショックであった。一方で、新型コロナウイルスの感染拡大は、未知のウイルス感染症が世界的に蔓延し、人々の外出を抑制するという需要型ショックの特性を有するだけでなく、製造現場に労働者が集合するといった経済活動を抑制する供給型ショックの特性も有している。
こうした違いを把握した上で、世界金融危機と新型コロナウイルスのそれぞれに対する米国の経済対策を比較する(第I-2-1-8表)。世界金融危機に対して、2009年2月に民主党オバマ元大統領は、7,870億ドル規模の米国復興・再投資法(American Recovery and Reinvestment Act: ARRA)を成立させた。一方で、新型コロナウイルスの感染拡大が深刻になる中で、2020年3月に共和党トランプ前大統領は、2兆2,000憶ドル規模のコロナウイルス支援・救済・経済保障法(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act: CARES)を成立させた。
第Ⅰ-2-1-8表 世界金融危機と新型コロナウイルスに対する米国の経済対策
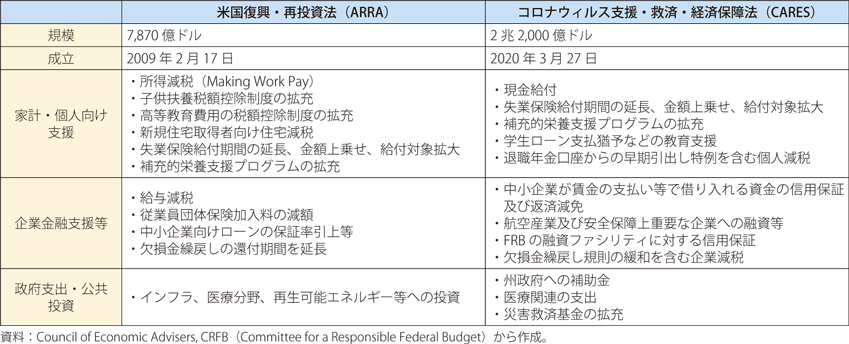
上述のとおり、世界金融危機は需要側ショックであった一方で、新型コロナウイルスが需要側と供給側の両方のショックであることから、CARESはARRAに比較してかなりの大規模となった。ただし、それぞれの対策の具体的な内容を比較すると、家計・個人向け支援策としての失業保険の期間延長及び金額上乗せや、中小企業向けの金融支援策等を含め共通項もある。
ARRAとCARESのそれぞれに失業保険拡充と減税策が含まれていることを踏まえて、これらの家計所得への影響を比較する(第I-2-1-9図)。失業保険や給付金等が含まれる経常移転受取を比較すると、世界金融危機時に成立したARRAによって同受取は危機前との比較で4%程度の増加となっていたが、CARESの下ではARRAにはない現金給付などの効果によって同受取は新型コロナウイルスの感染拡大前との比較で2倍以上となった。税引き後所得である一人あたり可処分所得を見ても、減税策が中心であったARRAの下で同所得が持続的に危機前の水準を上回り始めたのは基準月(2009年1月)から8か月が経過してからであったが、CARESの下では基準月(2020年1月)から3か月後には新型コロナウイルス感染拡大前の水準を取り戻している。減税政策では納税申告後に還付金が支払われるのに対して、給付金にはそうした時差がなく、CARESの即効性が消費回復に寄与したことが示唆されている。
第Ⅰ-2-1-9図 米国におけるARRAとCARESの下での経常移転受取(左図)と一人あたり名目可処分所得(右図)
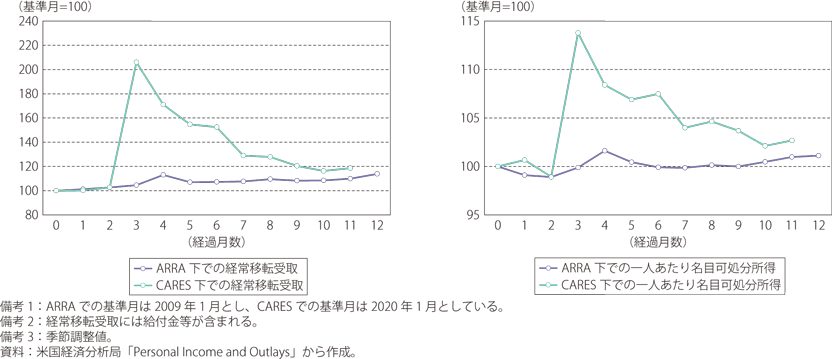
これらの経済対策のもう一つの共通項として、中小企業を中心にした信用保証等の金融対策が挙げられる。これらの対策実行後の金融機関の景況判断指標を見ると(第I-2-1-10図)、二つの局面に共通する点として、①金融機関が「小企業向け商工ローンの貸出態度を厳格化した」と回答した割合の方が「小企業向け商工ローンの貸出態度を緩和化した」と回答した割合よりも多い状態が解消されるのに時間がかかったこと(同左図の赤枠)、②「小企業向けの商工ローンの需要が減少した」と回答した割合の方が「小企業向け商工ローンの需要が増加した」と回答した割合よりも多い状態も解消されるのに時間がかかったことが挙げられる(同右図の赤枠)。
第Ⅰ-2-1-10図 米国における金融機関の小規模企業への商工ローン貸出態度判断(左図)と貸出需要判断(右図)
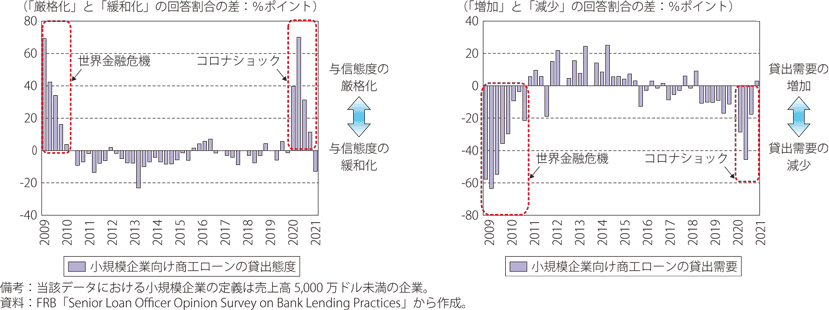
しかし、実際の商工ローン貸出の動向を見ると(第I-2-1-11図)、上述の景況感とは違った実態が示されている。すなわち、世界金融危機が深刻化した2009年には前年比での貸出の減少が続いた一方で、CARESに含まれる給与保護プログラム(Paycheck Protection Program: PPP)などの中小企業金融支援策が2020年に実行されてからは、商工ローンの前年比での貸出は大きく増加した。PPPでは、特定の条件が満たされる場合について融資返済の減免条項が付されており、そうした対策が貸出を増加させたと考えられる。また、後述のとおり、そうした対策で中小企業を中心とした金融不安が緩和されていることも、企業の投資回復を支えていると見られる。
第Ⅰ-2-1-11図 米国における銀行貸出の推移(商工ローン)
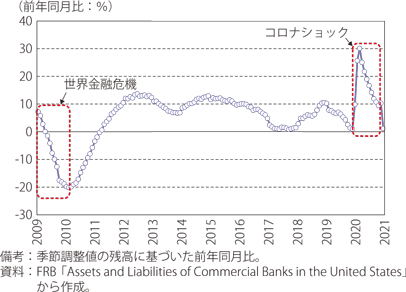
世界金融危機に比較して大規模な政策対応が現状の経済回復を後押ししているものの、課題が残っていることの認識も重要である。上述の通り、現金給付等によって個人消費は回復したが、財消費への支出水準は危機前を取り戻した一方で、個人消費の6割以上を占めるサービス支出の回復は遅れている(第I-2-1-12図)。
第Ⅰ-2-1-12図 米国における家計の実質消費支出の内訳
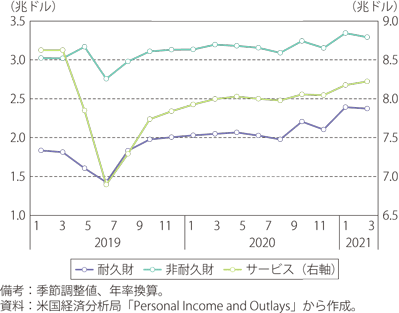
実質サービス消費支出の内訳では(第I-2-1-13図)、非裁量的な支出である住宅・公共料金や金融・保険は、新型コロナウイルスの感染拡大にはほぼ影響を受けておらず、また医療も感染拡大前の水準をほぼ取り戻している。一方で、交通、娯楽サービス、外食・宿泊といった裁量的な支出は、新型コロナウイルスの感染拡大前を依然として大きく下回っている。新型コロナウイルスは、接触・対面型サービスの供給と需要が同時に抑制されるという世界金融危機時にはなかった特殊な制限がある。外出抑止策等の感染症対策と、経済を回復させていくための政策の間で均衡を見出していくことが重要であることが示唆されている。
第Ⅰ-2-1-13図 米国における家計の実質サービス消費支出の内訳
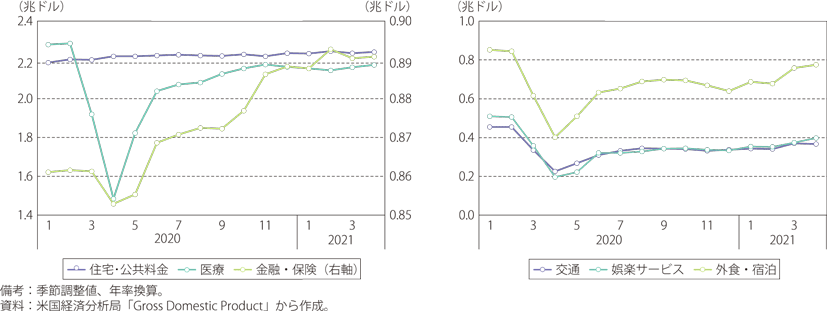
4.新型コロナウイルスの感染拡大に対する消費者と企業の順応
新型コロナウイルスからの経済回復で注目される点として、米国の家計が非接触型消費に柔軟に対応していることも重要な要因であると考えられる。米国の小売売上における電子商取引(Electronic Commerce:以下EC)の動向を見ると、特に2020年序盤に新型コロナウイルスの感染が拡大してからは、EC小売売上と小売売上全体に対する割合が増えている。(第I-2-1-14図)。
第Ⅰ-2-1-14図 米国のEC小売売上と小売全体に占める割合
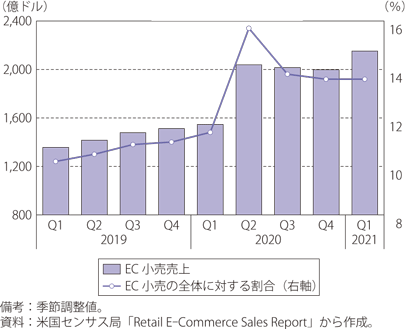
世界のEC市場規模の上位5か国(上位から中国、米国、英国、日本、韓国)18で米国以外の国を見ても、2020年の序盤に新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化してからは、EC小売売上と小売売上全体に対する割合が増加している(第I-2-1-15図)。米国を含めたこうした消費スタイルの柔軟なシフトは、個人消費回復に寄与していくと見られる。
第Ⅰ-2-1-15図 各国のEC小売売上と小売全体に占める割合
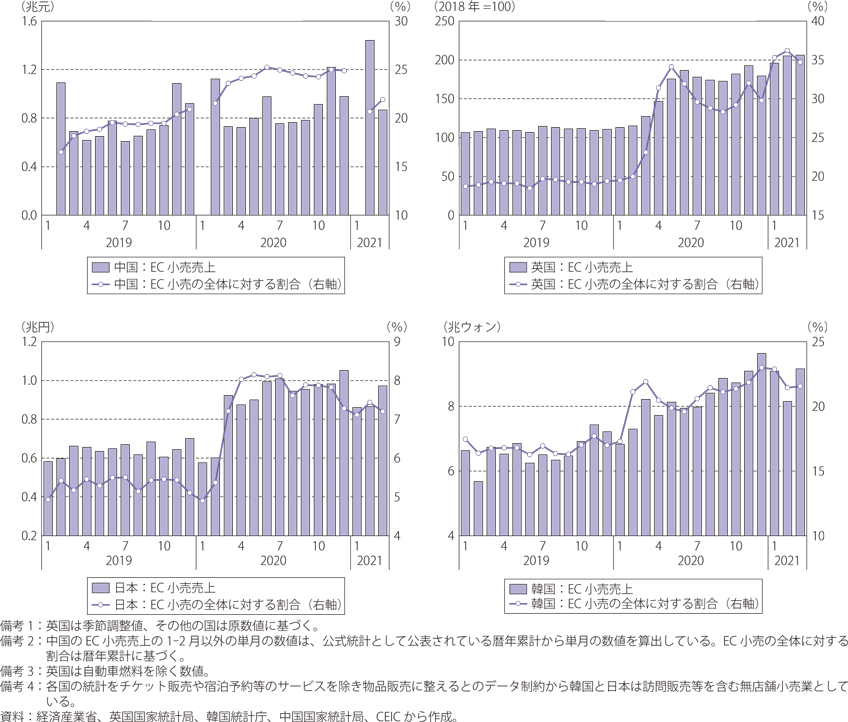
世界経済が回復に向かっている中で、新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大しながらも企業景況感が底堅い推移であることを指摘したが、米国の製造業景況感でも同様の動きが見られている。米国では製造業の景況感指標として、米国全土の製造業に対してサンプル調査を行うInstitute of Supply ManagementによるISM製造業景気指数が代表的であるが、それ以外にも、米国の各地域にある連邦準備銀行がそれぞれの担当地域に対して製造業の景況感調査を行っている(第I-2-1-16表)。
第Ⅰ-2-1-16表 製造業景況感調査を行っている米国の地区連邦準備銀行の担当地区
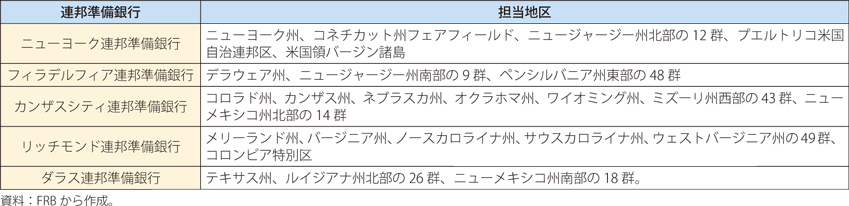
上述の詳細を踏まえて、下記(第I-2-1-17図)は各地区連銀が調査した製造業景況感指数の推移を示している(ただし、備考のとおり、各地域の連邦準備銀行が行っている製造業景況感調査の結果については、ISMと同様に50が景況感の境目となるように独自に再集計している)。それによると、製造業景況感の代表的な指標であるISM製造業景気指数は足下で景況感の境目となる50を上回って推移しており、各地区の連邦準備銀行が実施している製造業景況感指数も同様となっている。ISM製造業景気指数が全米を対象としていること、各地区の連邦準備銀行がそれぞれの地域で景況感調査を行っていることの両方を踏まえると、米国では景気の回復期待が高まっており、新型コロナウイルスの感染拡大に対して製造業が順応の動きを見せていることが示唆されている。
第Ⅰ-2-1-17図 ISMと各地区連邦準備銀行調査の製造業景気指数
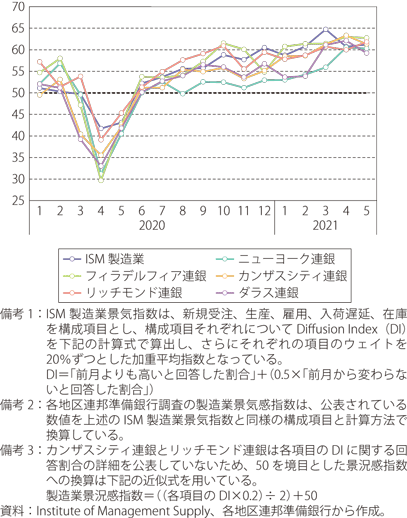
そうした製造業で見られる順応性の高さは、米国の企業全般で見られるイノベーション志向の高さと関係していると見られる。下記(第I-2-1-18図)は、実質GDPの構成項目である実質民間設備投資の内訳を示している。その内訳の中でも特に注目されるのは、研究・開発(R&D)等が含まれる知的財産生産物への投資動向である。知的財産生産物投資は、現行統計が開始された1999年からの当初は構築物投資を下回っていたが、足下では機械投資に次ぐ規模となっている。さらに特徴的である点として、知的財産生産物投資は、世界金融危機、欧州債務危機、そして現況の新型コロナウイルスの感染拡大下でもほとんど減少せず、景気動向にかかわらず一貫して増え続けていることが挙げられる。そうした、設備投資の構造を転換させてきたことに示唆される変化を厭わない姿勢も、新型コロナウイルスの感染拡大下での底堅い企業景況感に表れている。
第Ⅰ-2-1-18図 米国の実質民間設備投資の内訳
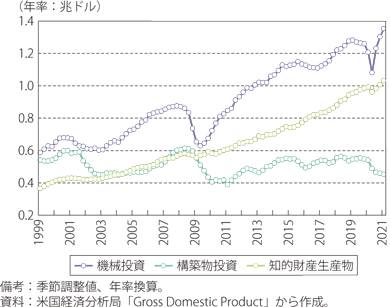
ただし、世界経済の動向でも見られるように、米国経済の中でも非製造業において、回復動向に差異があることには留意が必要である。下記(第I-2-1-19図)は、米国の非製造業の実質付加価値を示したものとなっている。それによると、小売業とヘルスケア・ソーシャルアシスタンス業の実質付加価値は新型コロナウイルス感染拡大前の水準を取り戻しており、米国の経済対策に含まれている家計への給付金の政策効果や、医療需要の高まりが示唆されている。また、情報業、金融・保険業、不動産業においては、実質付加価値が新型コロナウイルス感染拡大前の水準よりも高くなっており、非接触・非対面でサービスが提供可能であることの優位性や、テレワークの普及による郊外への移住需要の高まりが示唆されている。一方で、航空運輸業、教育サービス業、教養・娯楽業、宿泊・飲食業では実質付加価値が新型コロナウイルス感染拡大前の水準を依然として下回っており、接触・対面が主流であると考えられるサービス業の回復が遅れていることが示唆されている。
第Ⅰ-2-1-19図 米国のサービス業の実質付加価値
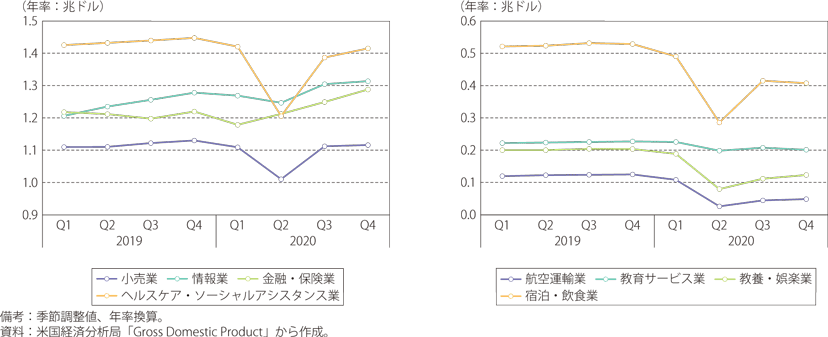
18 経済産業省(2020)。