第2節 経済対策から見る欧州
1.欧州(ユーロ圏)経済の動向19
(1)GDP
新型コロナウイルス感染拡大の影響により2020年の欧州経済は大きく下押しされた(第Ⅰ-2-2-1図)。2020年の実質GDP成長率(前年比)はユーロ圏-6.6%、ドイツ-4.8%、フランス-8.1%、イタリア-8.9%、スペイン-10.8%と特に南欧諸国の下落幅が大きい。感染は第1波では収まらず、各国でロックダウン等の制限措置、解除後の感染再拡大、再びのロックダウンという動きが繰り返されている。2021年に入っても生産や小売といった各種指標の回復スピードは緩慢である。
第Ⅰ-2-2-1図 ユーロ圏の実質GDP成長率
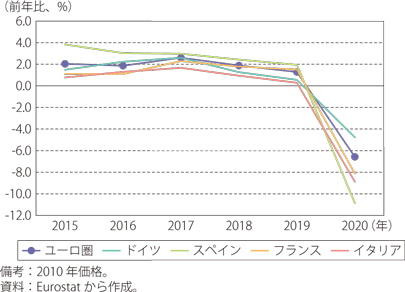
19 GDPはEurostatの5月3日更新データ。GDP以外の指標は4月公表時のもの。
(2)生産
鉱工業生産指数は各国のロックダウンの影響等により2020年春に大きく落ち込んだ。同年4月を底に回復が続いているが、主要国の中ではドイツの戻りが遅い(第Ⅰ-2-2-2図)。
第Ⅰ-2-2-2図 ユーロ圏の鉱工業生産指数
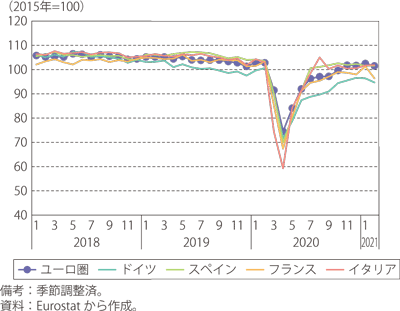
製造業生産の業種別内訳指数の推移(第Ⅰ-2-2-3図)を見ると、2020年春は特に自動車の落ち込みが大きかった。その後の回復のスピードも遅く、2020年初めの水準にも戻らないまま、足下、再び低下している。一方、化学・医薬品やコンピュータ・電子・電気は堅調に推移している。
第Ⅰ-2-2-3図 ユーロ圏の製造業生産指数
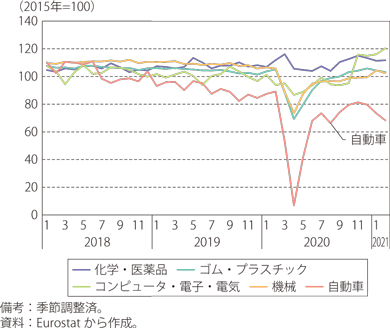
(3)小売
消費(小売売上高指数)の推移(第Ⅰ-2-2-4図)を見ると2020年春に各国とも落ち込んだ。特にイタリア、スペイン、フランスの落ち込みが大きかった。ドイツは他の国々よりも落ち込みは小さく堅調に推移したが、2020年末から2021年初めにかけて大きく低下した。
第Ⅰ-2-2-4図 ユーロ圏の小売売上高指数(国別)
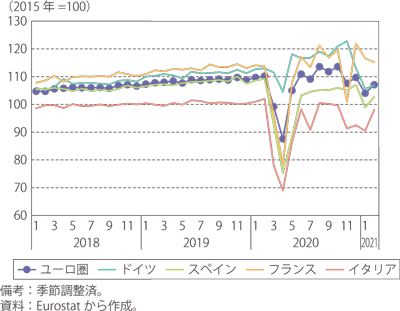
品目別では2020年春に衣料・履物、自動車燃料、コンピュータが大きく落ち込み、同年4月に底を打った後は、コンピュータは急速に回復したが、自動車燃料、衣料・履物の戻りのスピードは緩慢である。一方、通信販売は他のカテゴリーと対照的な動きを見せ、上昇が続いている(第Ⅰ-2-2-5図)。
第Ⅰ-2-2-5図 ユーロ圏の小売売上高指数(品目別)
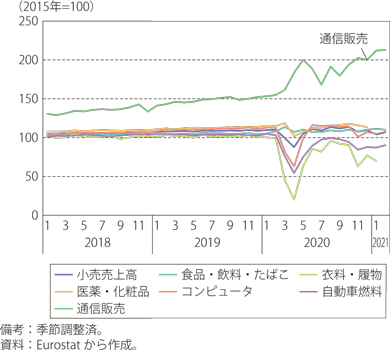
(4)失業率
失業率の推移(第Ⅰ-2-2-6図)を見ると、ユーロ圏、スペイン、イタリアは世界金融危機、欧州債務危機後は、低下してきていた。ドイツもすう勢的に低下が続いてきた。2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響により各国で失業率の上昇が見られたが、足下、更なる上昇圧力は抑制されている。なお、2020年4月にイタリアの失業率が低下したが、これは求職を諦めた人たちが労働市場から退出したことによる見かけ上の減少で労働市場の改善を表したものではないと見られる20。データに表れている以上に雇用環境が悪化している可能性に注意が必要である。
第Ⅰ-2-2-6図 ユーロ圏の失業率
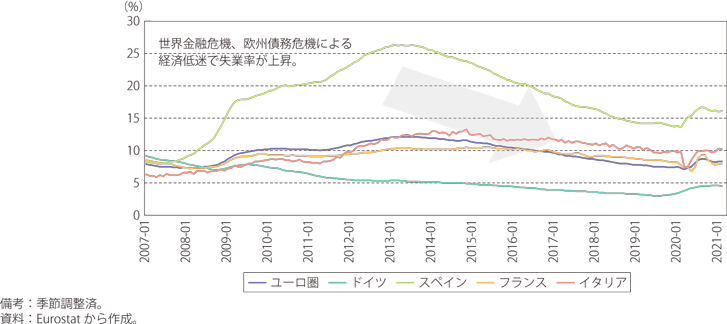
20 高山(2020)
(5)今後の経済見通し
IMFの経済見通し(2021年4月)によれば、2021年のユーロ圏経済は前年比4.4%の成長を見込んでいる。米国が同6.4%、カナダが5.0%の成長を見込んでいるのに比し、上昇幅は小さい。国別に見ると、フランスが5.8%、ドイツが3.6%、イタリアが4.2%、スペインが6.4%となっている(第Ⅰ-2-2-7表)。
第Ⅰ-2-2-7表 ユーロ圏の経済見通し
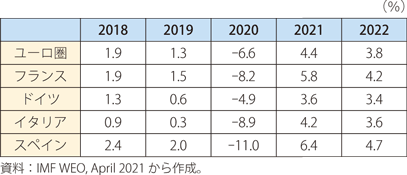
2.EUの経済対策
世界金融危機とそれに続く欧州債務危機等、2000年代末から2010年代前半、欧州は大きな経済ショックに見舞われてきた。ショックによる「傷痕」が深く残り、特に南欧諸国は経済回復へと反転するのに時間を要した。イタリアは足下でも世界金融危機前の経済水準に戻っておらず、2000年の水準も下回っている(第Ⅰ-2-2-8図)。失業についても南欧諸国、とりわけその若年層の失業率が高止まりした。欧州債務危機においてはギリシャなどの南欧諸国の深刻な財政問題が浮き彫りとなったが、ユーロ圏諸国は財政規律の裏付けでユーロの信認を守ることと域内経済を下支えすることの二つの課題に対応していかなければならず、難しい舵取りを強いられた。ギリシャの債務処理の経緯等、当時の動きの詳細にはここでは立ち入らないが、財政規律を重んじるグループとより柔軟な対応を求めるグループがある中で支援策等の協議が難航したことは、よく知られている。また、打ち出された支援スキームも危機の大きさに対応するには規模が不十分ではないか、との指摘もしばしばなされた。
第Ⅰ-2-2-8図 実質GDPの水準の推移(2000年=100)
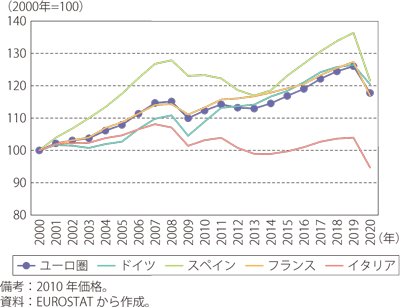
今回の新型コロナウイルス感染拡大への対応においては、そうした過去の反省もあり、EUは財政規律の柔軟化により各国の財政出動を促している。域内では財政状況が厳しい国々もあり、それら諸国を支援するため、雇用維持のための融資枠組(SURE)や欧州投資銀行(EIB)による保証ファンド(EGF)の創設、医療分野の支出に係る支援などからなる緊急支援枠組(5,400億ユーロ)について合意され、SUREやEGFについては利活用の事例が出てきている21。
緊急的措置としてルールや原則の運用を柔軟にする動きも見られる。今回の危機に対応するため、EU機能条約が禁じる特定の企業や製品に対する国家補助について例外措置が認められることとなった。具体的には、企業向けの直接給付や税制面での優遇、銀行の企業向け融資に対する国家補償、雇用維持のための賃金支払い支援、条件を満たした企業に対する資本増強などを欧州委員会の事前承認を得た上で行うものである22。
米国との比較で特徴的な点として、米国の支援策が失業給付や家計への現金給付を中心に行われたことに対し、欧州の場合は雇用維持により重きを置いたものであるとの指摘がある23。ユーロ圏の失業率は2020年初めの7%台半ばの水準から8%台に上昇しているが、財政出動がなかった場合はより高い水準(10%超)まで到達したであろうとされる。
EUはこれらの緊急対応措置に加え、回復過程における成長戦略として7,500億ユーロの復興基金(「次世代のEU」)と、1兆743億ユーロの2021~2027年中期予算計画(MFF)について2020年7月に大枠合意している。このうち「次世代のEU」の資金については全加盟国の批准後、欧州委員会が債券を発行して市場で調達する。7,500億ユーロの約9割が加盟国による復興のための取組への支援(RRF:復興レジリエンスファシリティ)に当てられる。残りの枠で「域内結束のための基金(React EU。感染拡大の影響を強く受けた加盟国・地域に向けた危機対応・復興対策支援)」に475億ユーロ、「公正な移行基金(脱炭素化を目指すにあたり影響を受ける加盟国・地域に対する支援)」に100億ユーロ、「RescEU(災害などにおける物資の備蓄計画、医療体制強化等)」に19億ユーロ、地方開発に75億ユーロ、「Horizen Europe(研究助成金)」に50億ユーロ、「Invest EU(投資促進資金)」に56億ユーロが配分される予定である24。「次世代のEU」は債券で資金調達を図るため、償還のための新たな財源としてプラスチック賦課金、炭素国境調整措置、デジタル賦課金などの導入等のロードマップが示されている25。期待される「次世代のEU」であるが、EU債の発行に必要とされる全加盟国による批准手続きがまだ完了しておらず、実際にスキームが動き出すまでにはまだ時間を要する見通しである(2021年4月現在)。金融政策面では、ECBの条件付長期資金供給オペレーション(TLTRO)の第3弾26の条件緩和、パンデミック緊急長期リファイナンスオペレーション(PELTRO)の実施等、景気下支えのための緩和措置がとられている。
21 伊藤(2021)
22 根津、福井、田中(2020)
23 伊藤(2021)(同)
24 本パラグラフ中の予算内容、規模等について伊藤(2021)(前出)、吉沼(2020a)(2020b)を参照した。
25 欧州連合日本政府代表部「EU情勢概要(2020年8月)」![]()
26 TLTROはECBが域内の景気下支えのためこれまでに計3回、実施している。第1弾は2014年、第2弾は2016年に導入。第3弾は2019年9月から実施(ECB Webサイト)。![]()
3.EUのグリーン戦略
(1)グリーンディールをめぐる動き
2019年12月、フォン・デア・ライエン新委員長率いる新しい欧州委員会が発足し、6つの重点分野が示された。すなわち(1)欧州グリーンディール(2050年までに温室効果ガスの実質排出ゼロに。中間目標として2030年に50~55%削減(1990年比))、(2)欧州デジタル化対応(EUレベルでのAI規制、サイバーセキュリティ、データ戦略、デジタルスキルの向上等)、(3)人々のための経済(公正な域内市場、投資と雇用創出の促進、各国経済政策の協調等)、(4)より強い欧州(人権や民主主義に関する取組、貿易政策を通じた企業活動環境の向上等、対外政策を通じたより強い結束した欧州の実現)、(5)欧州生活様式の推進(正義、欧州の価値の保護、難民や移民に関する措置の近代化等)、(6)民主主義の推進等27である。
このうち特にグリーンディールとデジタル化対応については欧州がグローバルな規範づくりでイニシアティブを取る可能性が高い分野として注目される。実際、デジタル化対応については、個人情報保護の観点から「EU一般データ保護規則(GDPR)」が2016年に発効、欧州経済領域(EEA)内で取得した個人情報の域外移転を原則禁止、違反行為には高額の制裁金を課す可能性もあるというものである。これは欧州企業だけではなく、域外の企業にも対応が求められる規則である28。
もう一つのグリーン分野においては、特にクリーンエネルギーへの転換、脱炭素に向けた動きが活発化している。CO2排出量が多い自動車セクターにとっては、EV(電気自動車)やEVに搭載されるリチウムイオン蓄電池の開発、増産が喫緊の課題となっている。さらに「カーボンフットプリント29」の情報開示を求める動きも出てきている。2020年12月、欧州委員会が提示した「EU電池指令」の改正案によるとリチウムイオン蓄電池のカーボンフットプリントの情報開示が2024年7月から義務づけられる30。
GDPRや脱炭素をめぐる動きは、個人情報保護や人権、気候変動への対応といった「価値」を重視する立場からグローバルなルール形成を先導しようとする欧州の戦略的アプローチとして注目される。特に環境や安全といったサステナビリティ、包摂性を重視するアプローチは、国連のSDGsへの対応としてもタイムリーなものであり、コロナショックからの回復過程において一層重視されていくと見込まれる。新型コロナ感染拡大により産業界が大きな打撃を被ったことからグリーン戦略への取組が後退するのではないかとの見方もなされたが、フォン・デア・ライエン欧州委員長はコロナ禍からの回復過程におけるグリーン戦略推進の重要性を改めて指摘31、欧州における経済のグリーンシフトの方向性は変わらないと見られる。
27 欧州委員会 Webサイト![]()
28 JETRO Webサイト![]()
29 製品のライフサイクル全体で排出された温室効果ガスの量を合算し、それをCO2排出量に換算して表示したもの(環境省 Webサイトから抜粋)。![]()
30 吉沼(2020c)
(2)電気自動車、リチウムイオン蓄電池をめぐる動向
先に見たようにCO2排出量の大きい輸送セクター、自動車産業は脱炭素を目指してEVの生産、販売に注力し始めている。欧州委員会によれば、2020年のEU域内のEV販売台数は過去最大の104.5万台となり、欧州自動車市場の10.5%を占めるまでになった。2019年の市場シェアが3%であったことを踏まえると、急速な拡大ぶりである32。また、2021年までに行われるCO2排出基準の見直しの動きや複数のEU加盟国で5~20年以内に内燃エンジン車を新車市場から排除する方針が打ち出されていることなどを踏まえると、EVの登録台数は2025年までに700万~800万台に上る見通しである33。
EVへのシフトの鍵を握るのは車載用リチウムイオン蓄電池の安定確保である。欧州にとってまさにこの点が大きな課題となっている。リチウムイオン蓄電池は日本や韓国が競争力を示してきた品目であり、近年では中国メーカーのプレゼンスが急速に拡大している。主要メーカー70社のうち46社が中国にあるなど34、グローバルな電池のサプライチェーンはアジアに重心が置かれている。欧州におけるリチウムイオン蓄電池の生産はグリーン戦略上の需要拡大に追いついていない状況であり、アジアからの輸入に頼ってきた経緯がある。
こうした点を踏まえ、近年、欧州における電池の自給を目指した戦略的な取組が本格化している。2017年10月、電池の域内自給を支えるバリューチェーンの構築、競争力のある電池産業の創出を目指して、欧州委員会、加盟国、研究機関の協力により欧州の電池関連企業連合である「欧州バッテリー同盟(EBA:The European Battery Alliance)」が発足、域内企業の連携による電池生産プロジェクトを立ち上げている35。2018年5月に欧州委員会が採択した「電池に係る戦略的アクションプラン(Strategic Action Plan for Batteries)」では、EUの域外からの原材料調達に加え、EU域内でも原材料の産出に力を入れることや、サステナブルな電池バリューチェーンの構築、イノベーション支援、人材育成・スキル向上、製造過程における環境負荷の低減(再生可能エネルギーの使用等)、規制枠組との整合性確保が盛り込まれた。2019年5月にはドイツとフランス両国が次世代電池供給で連携していくと表明36したほか、電池のサプライチェーン構築に係る研究開発、イノベーションプロジェクトのための域内各国による国家補助についても欧州委員会が承認するなど電池産業振興のための態勢の強化が図られてきた。欧州投資銀行(EIB)による域内電池企業への融資も行われている37。こうした官民を挙げての取組が進められる中、EU域内における電池及び電池材料の製造拠点の創設、拡充の動きが加速している。アジアからの投資も活発である。例えばドイツではザールラント州やザクセン・アンハルト州、チューリンゲン州で中国メーカーの工場において電池セル等の生産が行われる予定である38。電池材料部門では、労働力コスト面で競争力があることに加え、政府のEV関連の投資誘致策も奏功してポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキアといった中東欧諸国への投資が活発化している。日本企業の案件も見られるが、中東欧では特に韓国企業の投資件数が多い39。
第Ⅰ-2-2-9表は、ドイツのリチウムイオン蓄電池の輸入相手国・地域の変化を見たものである。2012年における上位10か国・地域中、5か国・地域がアジアで、米国が6位につけ、10位以内にランクインした欧州諸国は4か国にとどまっていた。2020年はポーランドが1位となっており、欧州諸国は7か国がランクインしている。ポーランドのほか、ハンガリー、チェコ、スロバキアといった中東欧諸国が躍進している。上位10か国・地域を地域別にまとめ、2012年と2020年を比較すると10年足らずの間に電池調達の欧州域内比率が大きく上昇したことが分かる(第Ⅰ-2-2-10~11図)。
第Ⅰ-2-2-9表 ドイツのリチウムイオン蓄電池(HS850760)輸入における国・地域別順位(上位10か国・地域)
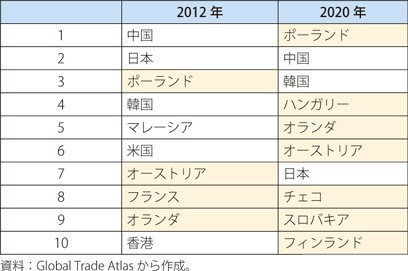
第Ⅰ-2-2-10図 ドイツのリチウムイオン蓄電池輸入先(上位10か国・地域・(2012年))
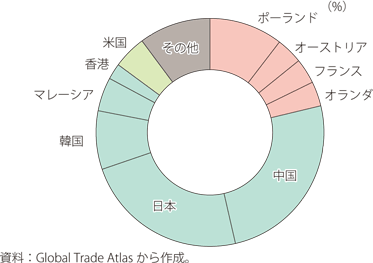
第Ⅰ-2-2-11図 ドイツのリチウムイオン蓄電池輸入先(上位10か国(2020年))
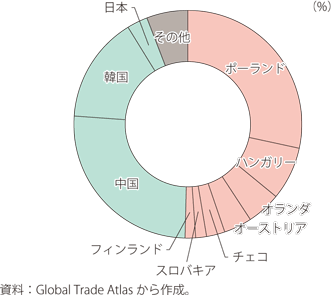
欧州域内でのリチウムイオン蓄電池のサプライチェーンが急速に構築されつつある。欧州委員会のシェフチョビチ副委員長は2021年3月、EBAのこれまでの取組を評価し、これまでに表明されている30の電池プロジェクトが欧州域内の電池需要のおよそ90%を満たせる見通しであると述べている40。リチウムイオン蓄電池をめぐる取組に見られるように、欧州のグリーン戦略をむしろ新しいビジネスチャンスとして捉え積極的に参画していこうとする動きが、欧州域内外を問わず加速していくことが予想される。
33 欧州委員会シェフチョビチ副委員長ステートメント(2021年3月3日)(同)。見通しは電池産業界によるもの。
36 前田(2019)
37 大中(2020)
38 森、マイヤー(2021)
39 山野井(2020)
40 欧州委員会シェフチョビチ副委員長ステートメント(2021年3月3日)(前出)。