第3節 世界に先駆けて回復した中国経済と続く構造問題
本節では、主として2020年の中国経済を概観するとともに、中国の抱える構造問題を考察する。
1.中国のマクロ経済動向
2020年の中国経済の特色は、新型コロナウィルスの影響で、年初に経済が大きく落ち込み、年の後半になるにつれて回復していったことにある。その経過についてGDPを始め、工業生産、投資、消費、貿易など主要な統計指標を追いながら見ていく。
(1)GDP
2020年1-3月期の実質GDP成長率は、新型コロナウィルスの影響で、前年同期比-6.8%と四半期ベースで統計が遡及できる1992年以降で初めてのマイナスを記録した(第Ⅰ-2-3-1図)。需要項目別に見ても、最終消費、総資本形成、純輸出がそろってマイナスに転じた。しかし、4-6月期には総資本形成が経済成長を主導する形で+3.2%とプラス成長を回復。純輸出もプラスに転じた。続く7-9月期には最終消費もプラスに転じて経済成長率は+4.9%へと上昇、さらに10-12月期も+6.5%と回復が続いた。その結果、2020年の実質GDP成長率は+2.3%と2019年の+6.0%からは大きく減速したが、主要国がマイナス成長に陥る中で、プラス成長を維持した。
第Ⅰ-2-3-1図 中国の実質GDP成長率の推移
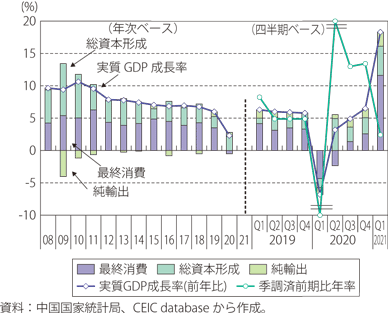
2020年の経済成長を需要項目別の寄与度で見ると、成長を主導したのは総資本形成で、純輸出も小幅ながらプラスに寄与した。あとで見るように固定資産投資では、医薬品や電子・通信機器などの一部の製造業、電気などのインフラ等が投資を伸ばした。金融緩和を背景に不動産開発も回復した。貿易においては主要国が生産を萎縮させる中で、いち早く回復した中国はパソコン、携帯電話、マスクを含む繊維製品等の輸出を拡大した。一方、最終消費は2020年後半に回復したものの、年間合計ではマイナスにとどまっている。雇用状況が厳しい中で可処分所得も落ち込み、消費者は消費拡大に慎重になっていることが考えられる。
2021年に入ると1-3月期は前年の落ち込みの反動で+18.3%と高い伸びとなったが、新型コロナが広がる前の2019年1-3月期からの2年間の年平均成長率は+5.0%と2019年成長率の+6.0%から比べれば成長率は鈍化している41。
なお、季節調整済み前期比の推移で見ると、2020年1-3月期に-32.3%と大きく落ち込み、4-6月期は+46.9%と急回復。その後は伸び率が次第に低下しており、2021年1-3月期は+2.4%となっている42。
このように中国経済は総じて回復基調にあるが、業種別にはかなりの相違が見られる(第Ⅰ-2-3-2表)。第2次産業では、製造業、建設業が1-3月期に落ち込んだものの4-6月期にプラスに転じ、以降は概ね順調に回復している。一方、第3次産業は業種によって動向が大きく異なる。例えば、宿泊・飲食、対事業所サービスは2020年7-9月期まで3四半期連続でマイナスが続き、2020年計でもマイナスとなった。卸・小売も1-3月期の落ち込みが大きく、2020年計でマイナスから抜け出すことができなかった。一方、同じ第3次産業でも情報通信・情報技術サービスは、主要業種がマイナスに転落した2020年の1-3月期においてさえ2桁台のプラスを維持しており、大きな落ち込みは見られない。金融も年間を通じてプラスを維持した。さらに不動産は1-3月期こそマイナスに転じたものの、4-6月期以降は2019年計を上回る伸び率で推移している。新型コロナで外出が制限される中で、通信や情報サービス需要の拡大、事業活動の継続や景気支援のための金融業務の必要性、金融緩和の結果としての住宅価格の上昇など、それぞれ要因は考えられるが、いずれにしても新型コロナは業種ごとに異なる影響を与えたことがうかがえる。
第Ⅰ-2-3-2表 中国の実質GDP成長率(業種別)の推移
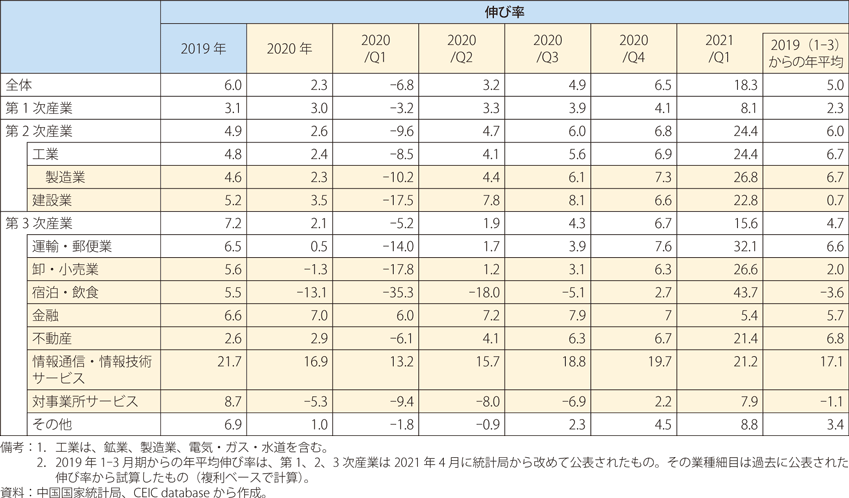
2021年に入ってからは、各業種とも前年の反動で大きく伸びているが、新型コロナ前の2019年1-3月からの平均伸び率を見ると、製造業が2019年を上回って伸びている一方で、宿泊・飲食、対事業所サービスはマイナスにとどまっている。
41 本節では、必要に応じて新型コロナ前の2019年同期との比較を分析に利用する。以後、新型コロナ前の2019年同期からの2年間の年平均成長率(複利ベース)のことを単に「2019年からの平均成長率」と簡略化して表記する。
42 日本や欧米ではGDPの推移を季節調整済み前期比(国によっては年率)で見ることが多く、中国国家統計局では季調済み前期比も併せて公表している。ここでは公表された前期比を年率換算している。なお、中国国家統計局は公表のたびに季節調整をかけ直すため、季節調整値は過去に遡及して更新される。ここに記載された数値は2021年1-3月期GDPが公表された2021年4月時点のものである。
(2)工業生産
ここからは主要な月次統計を参照しながら、2020年の中国経済の動向を確認する。第Ⅰ-2-3-3図は主要月次統計の動きを図示したもので、生産面の指標として工業生産、需要面の指標として、消費を小売売上高、投資を固定資産投資、輸出を輸出統計が代表している43。2019年までは輸出以外は、ほぼ安定したプラス成長を維持していたが44、2019年1-2月期に大幅なマイナスに転じた。最も早くプラスに回復したのは、生産面の指標である工業生産で4月にプラスに転じ、それ以降、月を追うごとにプラス幅が拡大している。それに対して、需要面の小売売上高、固定資産投資は回復が遅れており、その伸び率は2020年中、工業生産を下回った。一方、輸出は6月に小幅なプラスに転じ、7月以降は工業生産を上回る高い伸びが続いている。なお、2021年初めは前年同期の落ち込みの反動等から各指標とも大きな伸びとなった45。
第Ⅰ-2-3-3図 中国の主要月次経済統計の推移
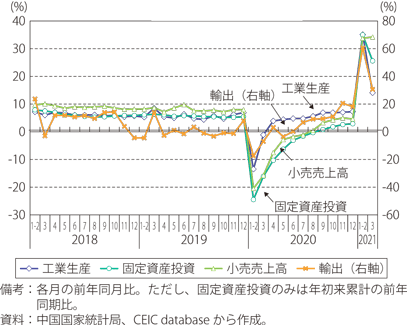
それぞれの月次統計を詳しく見ていく。工業生産の伸び率は2019年には5.7%だったが、2020年は2.8%まで減速した。直近の2021年3月は2019年からの平均伸び率が6.8%と回復している。
月次の推移を見ると、工業生産は比較的早い時期から回復している。1月末に武漢が封鎖され、全土に移動制限や防疫措置が課せられ、帰省した労働者がなかなか戻れないことや部材の調達難など、春節後の工場再開は困難を伴ったと指摘されるが、4月にはプラスに転じ、その後は順調に回復している(第Ⅰ-2-3-4図)。なお、生産が消費や投資など需要に先んじて回復したため、平行して製造業在庫の増加も見られた。
第Ⅰ-2-3-4図 中国の工業生産の伸び率(前年同期比)の推移
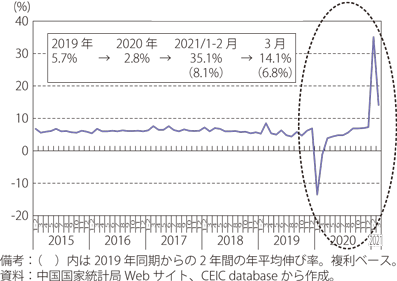
2020年の工業生産は2019年より全体としては減速したものの、業種別には、自動車生産はむしろ加速しており、補助金等の影響が考えられる。パソコン、携帯電話などの電子・通信機器も在宅需要を背景に比較的高い伸びとなった(第Ⅰ-2-3-5表)。
第Ⅰ-2-3-5表 中国の工業生産の伸び率(前年同期比 / 主要業種別)
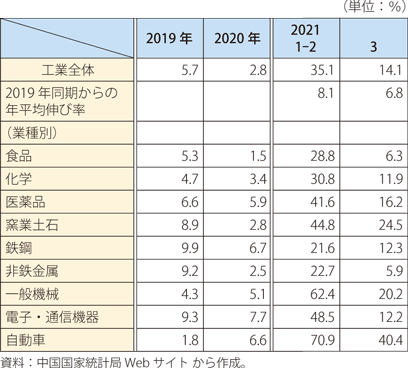
43 各経済統計で仕様が異なる点には注意が必要。例えば、固定資産投資は年初来累計での公表。また、名目伸び率の統計が多いが、工業生産は実質伸び率で公表。
44 輸出については、米国との貿易摩擦の関係で、2018年末から急速に悪化し、2019年はほぼゼロ成長だった。
45 2021年は新型コロナ対策から春節期間中も帰省自粛が呼びかけられ、一部の工場は稼働していた等の要因も指摘されている。
(3)固定資産投資
固定資産投資の伸び率は2019年には5.4%だったが、2020年は2.9%まで減速した。2021年1-3月期は2019年からの平均伸び率が2.9%と鈍化している。固定資産投資も月次の推移を見ると、年初に大きく落ち込んで緩やかに回復していった(第Ⅰ-2-3-6図)。ただし、2020年の実績には業種別に大きな相違が見られる。製造業の中でも、医薬品が2019年を大きく上回る伸びとなったほか、電子・通信機器も2桁台の伸びを維持したが、一般機械、自動車はマイナスとなった(第Ⅰ-2-3-7表)。インフラ関係では、ライフラインを支える電気・ガス・水道は2桁台の伸びに拡大、それ以外の道路、鉄道等のインフラもプラスを維持した。また、病院などの衛生・社会サービスも大きく伸びた。
第Ⅰ-2-3-6図 中国の固定資産投資の伸び率(年初来累計・前年同期比)の推移
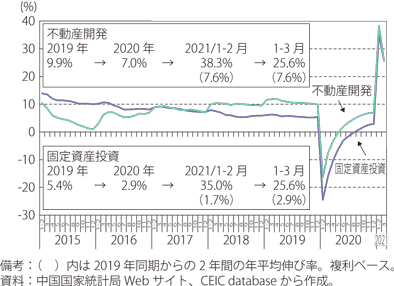
第Ⅰ-2-3-7表 中国の固定資産投資の伸び率(年初来累計・前年同期比 / 業種別)
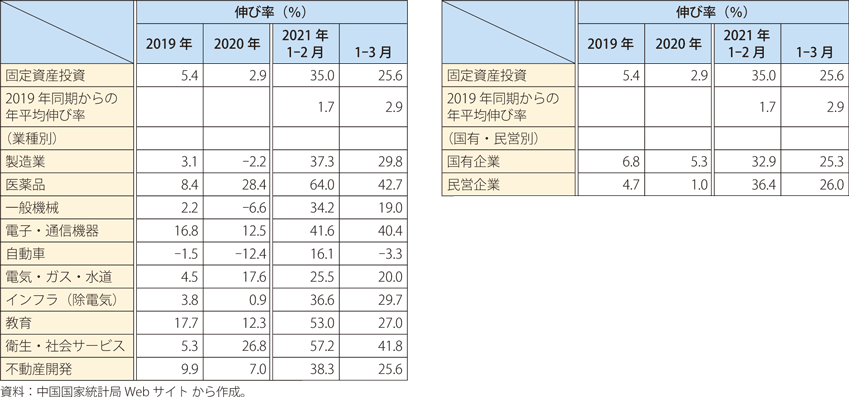
企業形態別には、国有企業に比べて、民営企業の回復が遅れている。10月までマイナスが続き、年計ではプラスに転じたが低い伸びにとどまった。
(4)小売売上高
小売売上高の伸び率は2019年には8.0%だったが、2020年は-3.9%とマイナスに転じた。直近の2021年3月は2019年からの平均伸び率が6.3%まで回復した。小売売上高も月次の推移を見ると年初に大きく落ち込んでいる(第Ⅰ-2-3-8図)。8月にプラスに戻ったものの、年間合計としてはマイナスにとどまった。特に飲食業の落ち込みが大きい(第Ⅰ-2-3-9表)。年初には5割近い減少となる月もあり、年末にほぼ前年同期の水準(±0%)まで回復したが、年計では2桁台のマイナスとなった46。物品販売も、主要品目の中で年計がプラスとなったのは、通信機器、医薬品、食品など必需品に限られる。一方、ネット販売は2019年に比べて伸び率は落ちたものの堅調を保った。新型コロナで外出を控える傾向がある中で2桁成長を維持した。
第Ⅰ-2-3-8図 中国の小売売上高の伸び率(前年同期比)の推移
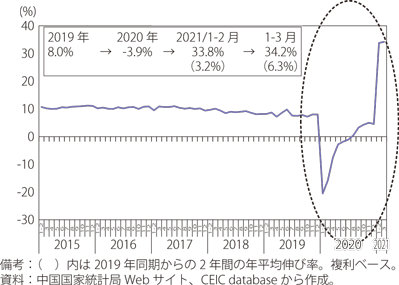
第Ⅰ-2-3-9表 中国の小売売上高の伸び率(前年同期比 / 品目別)
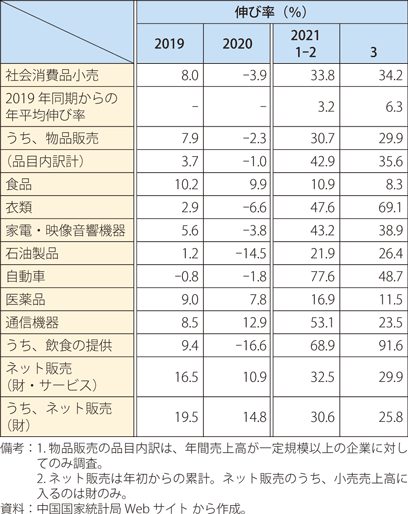
このような小売売上高の回復の遅れは、厳しい雇用環境の下で、可処分所得の伸びが鈍化したことも影響していると考えられる。2020年の都市部新規就業者数は前年比約1割減となった。一人当たり可処分所得の伸びは、名目ベース、実質ベースともに鈍化した(名目:2019年8.9%→2020年4.7%、実質:5.8%→2.1%)。特に実質ベースでは1-6月期まで前年割れとなっており、消費の抑制につながったと見られる。
46 飲食業の年初は1-2月-43.1%、3月-46.8%と大きなマイナスを記録した。年末になって10月+0.8%、11月-0.6%、12月+0.4%と±1%以内を推移しており、ほぼ前年の水準に戻った。
(5)貿易
輸出は年初に大きく落ち込み、年中頃にプラスに転じてから急速に拡大した(第Ⅰ-2-3-10図)。その結果、2020年としてはプラス成長となった。輸入もやや遅れて秋頃からプラスに転じたが2020年としてはマイナス成長にとどまった。相手国別には、貿易摩擦を抱える米国が輸出入ともにプラスに転じた(第Ⅰ-2-3-11表)。対米貿易については品目別の推移も含めて後で詳しく見ることとする。それ以外の国については、ロックダウンで国内生産が停滞したと見られる欧州向けは、総じて輸出が高い伸びとなった一方で、輸入は低調であった。アジアについてはASEAN向けが輸出入ともに堅調、又、電子部品生産の盛んな台湾からの輸入が2桁台の高い伸びを示した。
第Ⅰ-2-3-10図 中国の貿易の伸び率(前年同期比)の推移
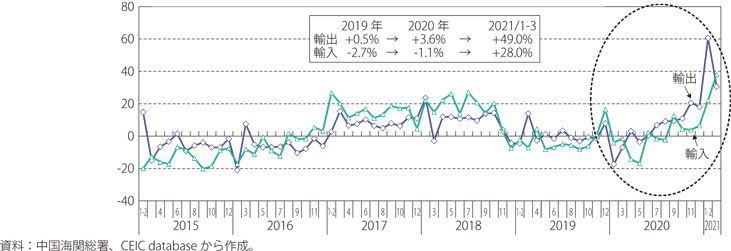
第Ⅰ-2-3-11表 中国の相手国・地域別の貿易伸び率(前年同期比)
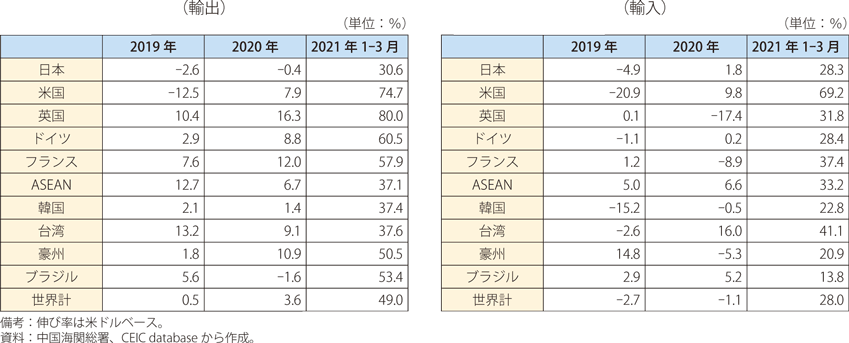
品目別には、輸出は新型コロナの影響で、マスクを含む繊維製品、パソコン等の電子計算機、携帯電話47等の医療関係や在宅機器が好調であった(第Ⅰ-2-3-12表)。輸入はIT機器の生産に必要な集積回路や大豆、鉄鉱石等が好調だった。なお、資源価格の低下から原油、天然ガスは金額ベースで大幅な減少となった。
第Ⅰ-2-3-12表 中国の品目別の貿易伸び率(前年同期比)
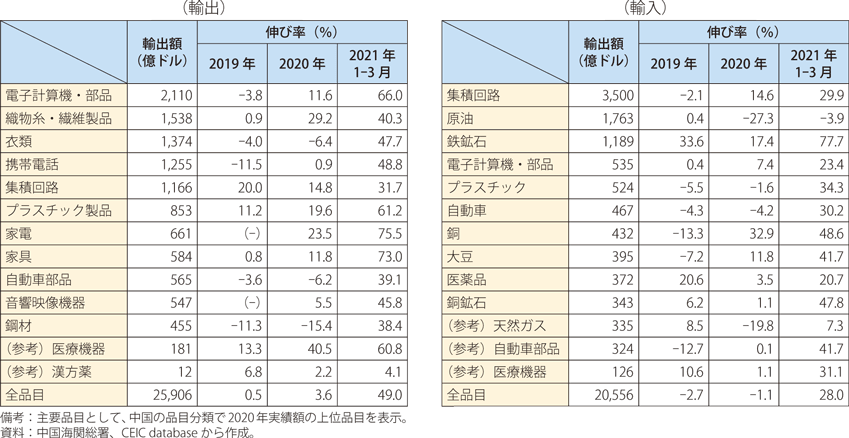
さて、中国の対米貿易の推移を見ると、2018年後半から両国で追加関税が発動され、2019年は輸出入ともに伸びはマイナス圏で推移、特に輸出は伸び率のマイナス幅が次第に拡大した(第Ⅰ-2-3-13図)。2020年1月には米中両国間で第一段階の合意に達したものの、新型コロナの影響で2021年1-3月の輸出は大幅なマイナスが続いた。しかし、輸出は4-6月期にプラスに転じると急速に伸びを拡大した。輸入はやや遅れて7-9月期からプラスに転じた。
第Ⅰ-2-3-13図 中国の対米貿易の推移
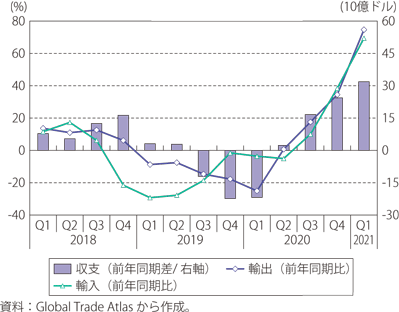
対米貿易収支については中国側の黒字が続いており、2019年後半から前年同期と比べて黒字額は縮小したものの、2020年4-6月期から再び拡大に転じている。
品目別の動向を見ると、2020年の米国向け輸出は新型コロナの影響を受けた品目の寄与が大きい。まず、4-6月期にマスクを含む繊維製品が大きく伸びた48,49。繊維製品の寄与は7-9月期からは縮小していくが、かわってパソコン等の一般機械、10-12月期からは携帯電話等の電気機器50も寄与を拡大している(第Ⅰ-2-3-14図、第Ⅰ-2-3-15表)。また、プラスチックの中でもプラスチック製の衣類・手袋、各種化学品の中の消毒剤なども新型コロナの影響が考えられる。反対に2020年の輸出で減少したものとしては、衣類、履物、革製品など労働集約的な製品が多い。
第Ⅰ-2-3-14図 中国の対米輸出の推移(主要品目別)
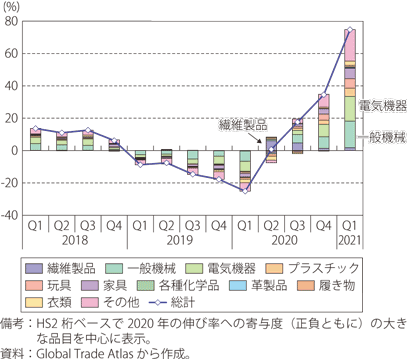
第Ⅰ-2-3-15表 中国の対米輸出(主要品目寄与度)52
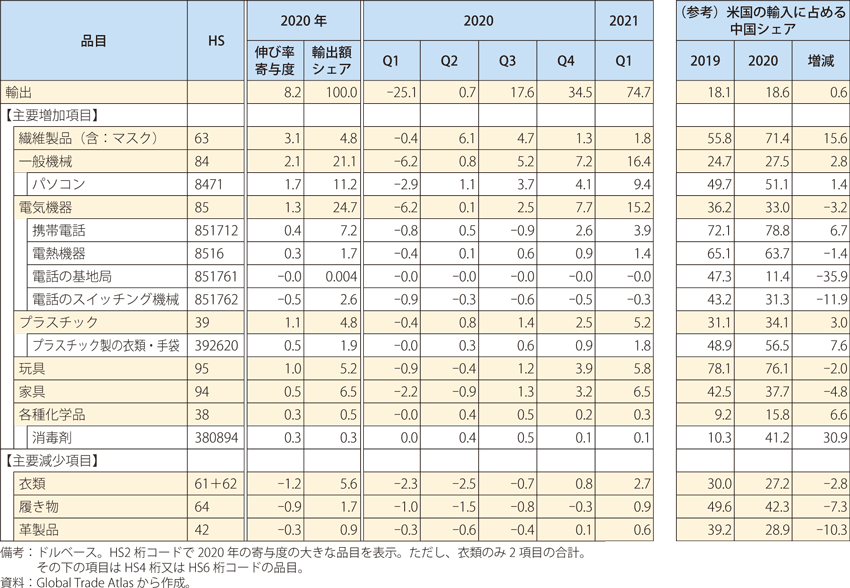
米国側の輸入統計で中国のシェアを併せて見ると51、マスクを含む繊維製品や消毒剤の中国シェアは大きく上昇しており、新型コロナの影響と思われる。中国シェアが低下している品目としては、衣類、履物、革製品のほか、家具、玩具も含めて労働集約的な製品が挙げられる。これらの製品は中国の経済発展に伴う労働コスト上昇や追加関税の影響等で、輸入が他国に代替されたことが考えられる。また、興味深い点としては、電気機器の中でも、携帯電話の中国シェアは上昇する一方で、電話の基地局やスイッチング機械など、安全保障に関わる可能性のある通信用インフラ機器の中国シェアは低下していることが挙げられる。
一方、米国からの輸入については、原油、天然ガスなどの鉱物性燃料、大豆を始めとするオイルシード、肉類、穀物などの食料の寄与が大きい(第Ⅰ-2-3-16図、第Ⅰ-2-3-17表)。集積回路や自動車部品などの部品関係もプラスに貢献した。一方、減少した項目としては、航空機や一般機械(特にジェットエンジン)53が挙げられる。米国側の輸出統計で中国のシェアを見ると、中国側統計で輸入が増加している、原油、天然ガス、大豆、肉類、穀物等の中国シェアが上昇していることが確認できる。
第Ⅰ-2-3-16図 中国の対米輸入の推移(主要品目別)
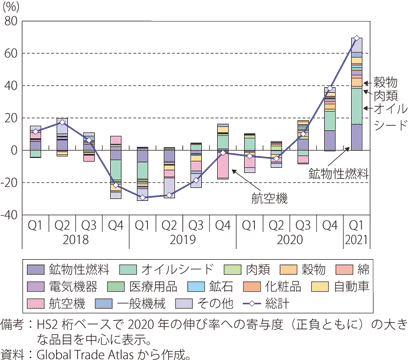
第Ⅰ-2-3-17表 中国の対米輸入(主要品目寄与度)
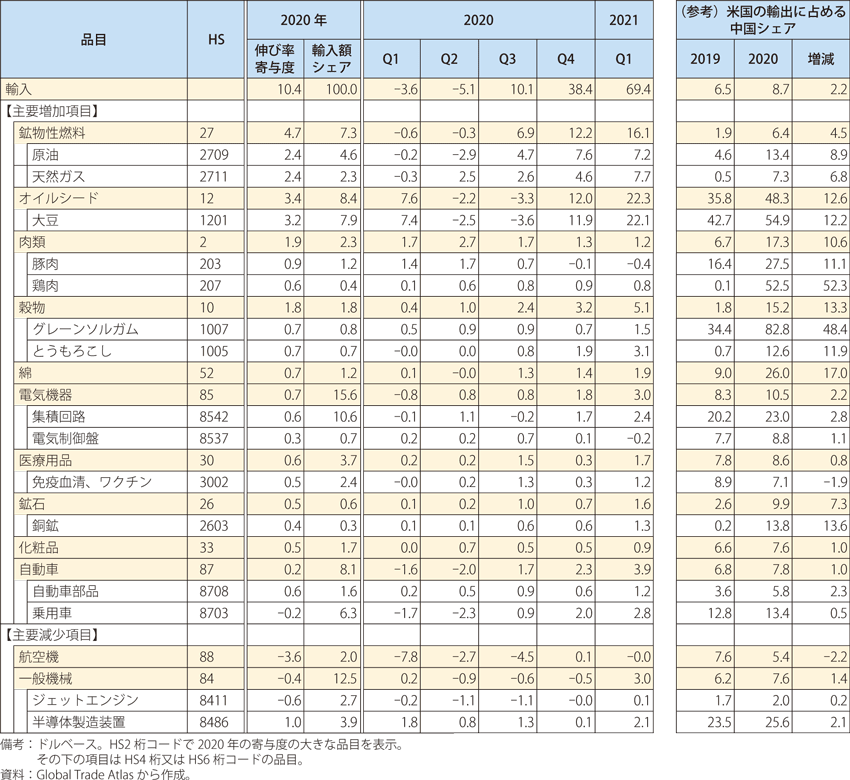
47 携帯電話は年初の落ち込みが大きいため2020年としては低い伸びとなっている。
48 マスクはHSコード上「紡織用繊維のその他の製品」(HS63)の下位項目の「その他のもの」(HS630790)の中に含まれるが、世界共通の6桁コードではマスクだけを特定することはできない。各国はそれ以下の細分コードを設定できるが、中国の貿易コードは8桁までおりてもHS63079000のみでマスクの特定はできない。なお、日本(9桁)や米国(10桁)では新たにマスクに関する項目を設定している。
49 本節でHSコードの品目名称は短く簡略化している。正確な名称や詳細な内容は別途参照されたい。
50 ただし、同じ電話関係でも携帯電話が寄与を拡大する一方で、電話回線網のセキュリティにかかわる基地局の輸出は増加していないし、電話の音声・画像データのスイッチング機械はマイナスのまま推移している。また、携帯電話も7-9月期には一時的にマイナスに転じるなど、品目や時期によって変化は一様ではない。
51 ただし、二国間の輸出入統計が必ずしも同じ動きをするとは限らないことには注意が必要。輸出入でFOBかCIFか基準が異なる上に、香港など第三国を経由する場合の扱いが問題になる等のためである。また、輸出入におけるシェアは他国とのバランスで決まるため、金額は増加していてもシェアは低下するなどがあり得る。
52 原則として、HS2桁コードの下位品目としてはHS4桁コード品目を表示した。ただし、HS4桁では分かりにくいなどの理由がある場合はHS6桁コードを表示した。例えば、「電気機器」(HS2桁)の下の4桁品目としては「電話機」(HS8517)となるが、その中で大きな寄与を占める「携帯電話」(HS851712)と「電話の音声・画像データのスイッチング機械」(HS851762)は反対の動向をしているため6桁コードに分割した。また、「プラスチック」(HS39)の下の4桁品目で最大の寄与は「その他のプラスチック製品」(HS3926)となるが実態が分かりにくいので6桁品目の「プラスチック製の衣類・手袋」(HS392620)を表示した。
53 ただし、一般機械の中でも半導体製造装置は伸びているなど品目による相違は見られる。
2.中国の構造問題
中国経済は世界に先駆けて新型コロナの影響から回復したが、今後も長期的に成長を続けていくためには多くの課題も抱えている。
(1)人口動態・少子高齢化
国連の推計によれば、中国において生産年齢人口は既に2010年にピークを迎え、総人口も2030年以降は減少に転じると予測されている(第Ⅰ-2-3-18図)。その結果、働き手が不足するとともに、子供や高齢者の扶養負担が問題となってくるおそれがある。
第Ⅰ-2-3-18図 中国の人口構成の将来予測(国連推計)
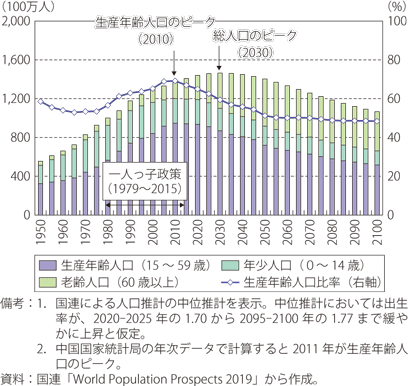
少子高齢化の背景には一人っ子政策の影響が指摘されている。同政策は2015年に廃止され、子供は二人まで認められることとなった。しかし、生活費、養育費の問題や生活様式の変化等から、期待されたほどの効果は見られていない。人口に対する出生数の比率(出生数/人口)は一人っ子政策廃止後、一旦上昇したが、2018年以降は廃止時点よりも下回っている(第Ⅰ-2-3-19図)54。また、中国国家統計局のデータを基に試算すると、一人の女性が一生の間に出産する子供の数の推定値である合計特殊出生率は、依然として人口維持に必要とされる2.1を下回って推移している(第Ⅰ-2-3-20図)。
第Ⅰ-2-3-19図 人口に対する出生率
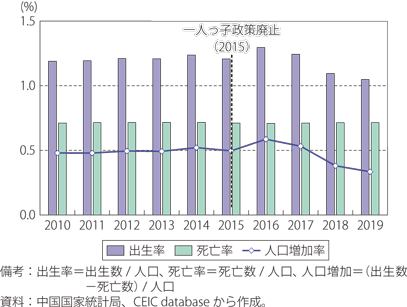
第Ⅰ-2-3-20図 合計特殊出生率の試算
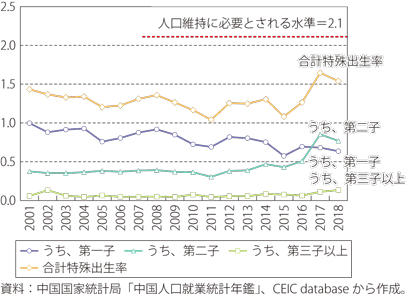
なお、試算した合計特殊出生率は、国連の中位推計の仮定よりも低い(第Ⅰ-2-3-21表)55。統計局データはサンプル調査ではあるが、仮に実態を正しく反映しており、この数値が続くとすれば、中国の人口は国連の中位推計よりも低く、低位推計との間を推移する可能性がある(第Ⅰ-2-3-22図)56。
第Ⅰ-2-3-21表 国連人口推計の出生率の仮定
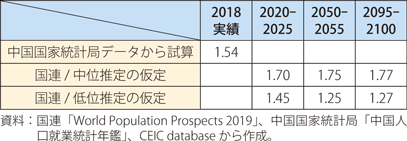
第Ⅰ-2-3-22図 国連中位推定と低位推定の相違
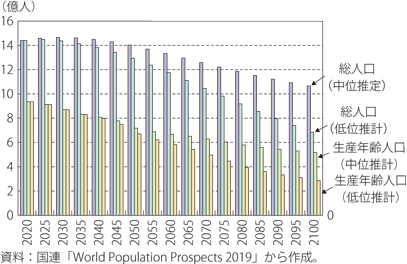
現実の労働者の需給バランスを見ると、世界金融危機時の4兆元の景気対策以後、都市部求人倍率は1.0を越えて上昇しており、既に人手不足で推移している(第Ⅰ-2-3-23図)。特に製造業の工場労働者の人材難が指摘されている。その背景として、既に見た生産年齢人口の減少とともに、都市に流入していた農民工の伸びの鈍化も影響していると思われる(第Ⅰ-2-3-24図)57。このことは農村部の余剰労働力が枯渇してきている可能性を示唆している。また、現在の農民工自身の高齢化も進行していることを踏まえると、今後、中長期的に製造業部門を中心に労働力不足が生じることが懸念される(第Ⅰ-2-3-25図)。
第Ⅰ-2-3-23図 中国の都市部求人倍率
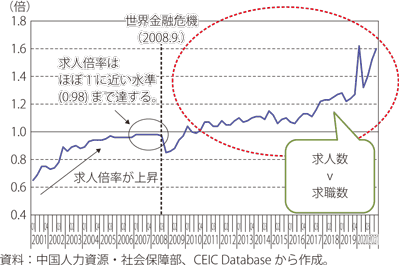
第Ⅰ-2-3-24図 農民工人数の推移
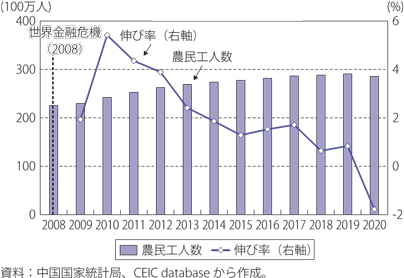
第Ⅰ-2-3-25図 農民工の年齢構成の推移
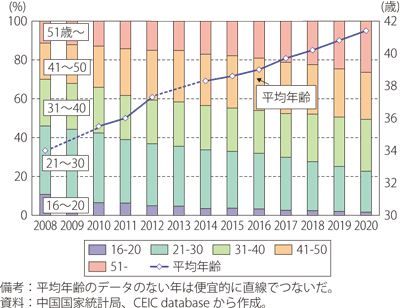
54 2021年5月、第七次人口センサスの結果概要が公表された。2020年の中国の総人口は14億1178万人であった。これまでのサンプル調査では、総人口の伸び率は、一人っ子政策の廃止で一時的に上昇した後、2019年まで低下してきたが、2020年については上昇する結果となった。公表された中には出生率のデータそのものはなかったが、2020時点の年齢層別の人口と過去に公表された出生数との間に相違があることが指摘されている。報道によれば、センサスで示された14歳以下の人口が過去に公表された出生数合計を上回っており、中国国家統計局はサンプル調査であった2011年~2019年のデータを修正する意向を示している。
一方、センサスの結果からも、高齢化が進行していることは裏付けられる。中国の総人口は2010年(前回のセンサス年)からの10年間で約7,100万人増加した。しかし、人口が増加したのは、生産年齢人口が約4,600万人減少したが、それ以上に老齢人口が約8,600万人増加(約5割増)した影響が大きい。なお、将来を担う年少人口も約3,100万人増加した。その結果、生産年齢人口のシェアは低下(70.1%→63.4%)、1人の老齢人口を支える生産年齢人口の割合は上昇(5.3人→3.4人)することとなった。
また、国連の人口推計と比べると、センサス結果の2020年の総人口は国連推計よりも約2,800万人下回っている。その内訳は、年少人口が約200万人、生産年齢人口が約4,000万人、国連推計を下回る一方で、老齢人口は約1,400万人上回るなど、国連推計以上に高齢化が進行している。
55 合計特殊出生率は一人の女性が一生の間に出産する子供の推定値。中国国家統計局「中国人口就業統計年鑑」では、その年における14歳から49歳までの各年齢層の女性の出生率(第一子、第二子、第三子以上別)が掲載されており、その出生率を合計する。便宜的には、データベースにある毎年の各年齢層平均出生率に35年齢層を乗じて試算。
56 報道によれば、第七次人口センサスによる2020年の合計特殊出生率は1.3にとどまることが報告された。
57 ただし、2020年の場合、急にマイナスに転じたのは、新型コロナによる移動制限の影響も考えられる。
(2)雇用のミスマッチ
その一方で、大学等の卒業生は急速に増加しており、緩やかな増加にとどまる都市部新規就業者に対して、大卒者の比率は倍増している(第Ⅰ-2-3-26図)58。その結果、大卒者が能力に見合う十分な就業機会を得られない可能性がある。都市部就業者の業種構成は卸・小売、宿泊・飲食、建設等の比較的労働集約的な業種が拡大し、高度な専門的知識が必要とされるような情報通信・情報サービス、研究・技術サービス、金融等は限られたシェアにとどまっている(第Ⅰ-2-3-27図)。
第Ⅰ-2-3-26図 中国の大学等の卒業生と都市部新規就業者
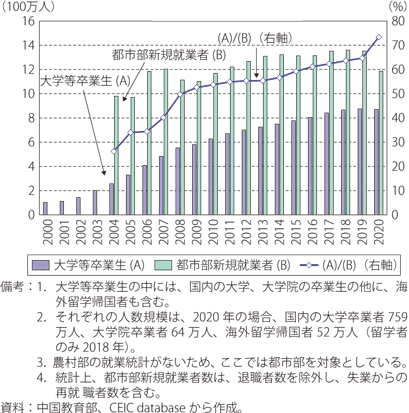
第Ⅰ-2-3-27図 中国の都市部就業者の業種構成
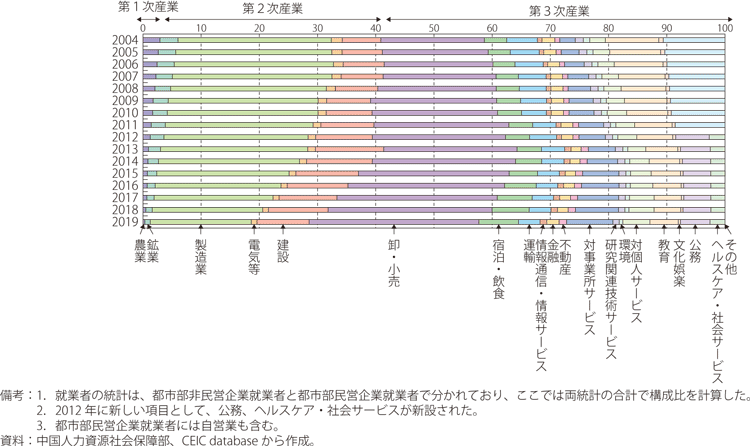
58 ただし、2020年の場合、新規就業者に対する大卒者比率が急増したのは、新型コロナによる新規就業者の減少の影響も考えられる
(3)低い消費水準、高い貯蓄水準
中国では、消費主導型の経済成長を志向してきたが、中国の民間消費のシェアは2000年代に縮小し、2010年代に回復してきたが回復は緩やかなペースにとどまっている(第Ⅰ-2-3-28図)。国際的に比較しても、中国の民間最終消費のシェアは日本、米国に比べて低水準で推移している(第Ⅰ-2-3-29図)。
第Ⅰ-2-3-28図 中国のGDPにおける需要項目別シェア
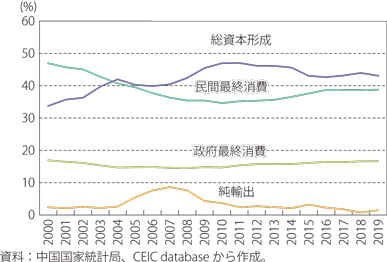
第Ⅰ-2-3-29図 GDPにおける民間最終消費のシェア
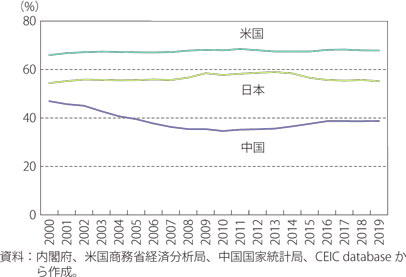
その背景として、GDPにおける雇用者報酬のシェアは米国、日本よりも低水準であることが一因に挙げられる(第Ⅰ-2-3-30図)。その反対にGDPに対する貯蓄の比率は、中国が米国、日本に比べて突出して高い(第Ⅰ-2-3-31図)。この点については中国では社会保障の整備が不十分なため、将来に備える傾向があるなどの理由が指摘されている。この高い貯蓄が投資にまわることで高い投資水準を支えている。
第Ⅰ-2-3-30図 GDPにおける雇用者報酬のシェア
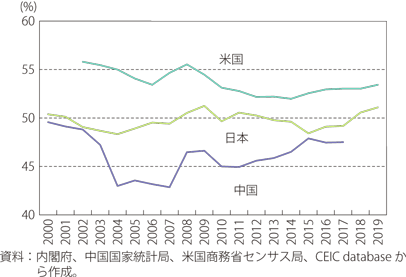
第Ⅰ-2-3-31図 GDPに対する貯蓄の比率
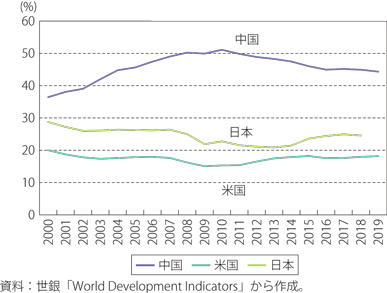
(4)所得格差
中国では、依然として地域間(省別)、都市・農村間、個人間の格差が大きい。例えば、中国の省別一人当たりGDPの差は約5.0倍ある(第Ⅰ-2-3-32図)59。都市・農村間の一人当たり可処分所得の差も縮小してきたものの、依然として約2.6倍の差がある(第Ⅰ-2-3-33図)。また、個人のジニ係数は0.4を上回る水準で推移している(第Ⅰ-2-3-34図)。その一因として、固定資産税や相続税がないなど制度的な所得再分配機能が不十分との懸念が指摘されている。所得格差は社会の不安定要因となり得るとともに、消費の拡大を抑える可能性もある。
第Ⅰ-2-3-32図 中国の省別一人当たりGDP(2019年)
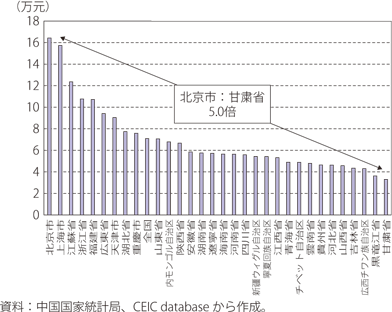
第Ⅰ-2-3-33図 中国の都市・農村別一人当たり可処分所得の推移
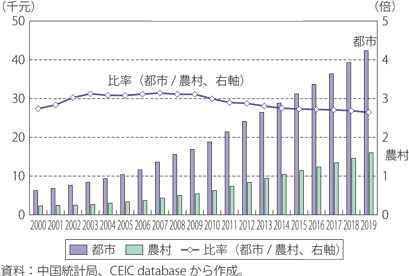
第Ⅰ-2-3-34図 中国のジニ係数の推移
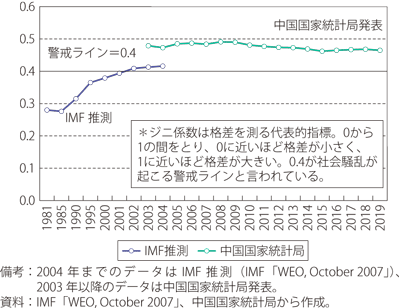
59 同様に米国、日本についても州、都道府県別の差を計算すると、米国の場合、約2.3倍(2019年、ただし、ワシントン特別区は除外)、日本の場合、約2.3倍(2017年)となる。
(5)国有企業問題
国有企業の効率性を利益率(資産総額に対する利益額の比率)で見ると、民営企業に比べて低い水準で推移している(第Ⅰ-2-3-35図)。1990年代後半に中小国有企業の民営化は進んだが、大型国有企業の市場化、民営化は遅れており、むしろ、近年は国有企業をより大きくより強くとの方針を掲げて、大型国有企業同士の合併が見られる(第Ⅰ-2-3-36表)。規模の経済というメリットはあり得るとしても、国有企業の独占を強め、競争を低下させ、かえって効率性を損なうデメリットを指摘する声がある。特に国有企業は、資源、エネルギー分野におけるシェアが高い(第Ⅰ-2-3-37図)。
第Ⅰ-2-3-35図 国有企業・民営企業別の総資産利益率(工業分野)
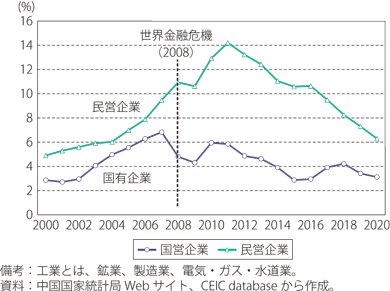
第Ⅰ-2-3-36表 主要な国有企業政策の推移
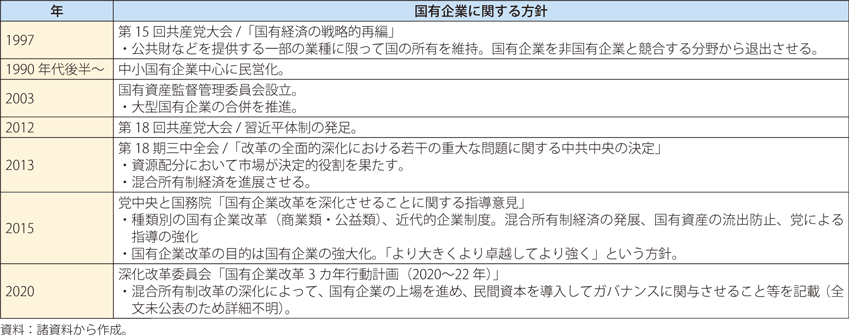
第Ⅰ-2-3-37図 総資産額における業種別国有企業シェア(工業分野/2019年)
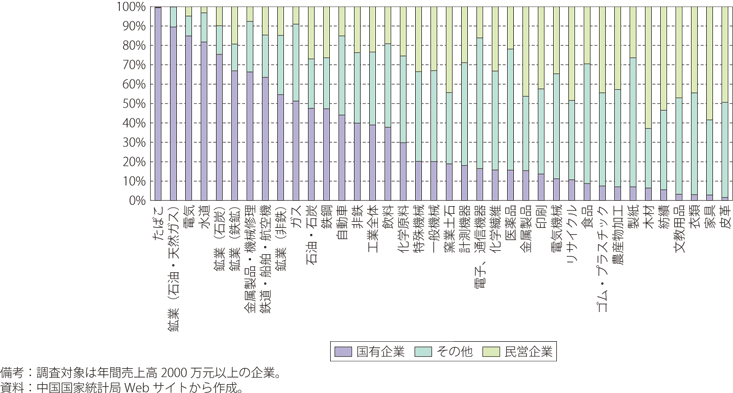
(6)金融リスク
中国では、非金融企業の債務残高(対GDP比)が日本のバブル期を上回る水準まで拡大した(第Ⅰ-2-3-38図)。その後、一旦は低下したものの、コロナショックに際して再び拡大している。家計債務も、まだ水準は低いものの、住宅ローンを中心に急速な拡大が続いている。
第Ⅰ-2-3-38図 日中の債務残高(対GDP比)の推移
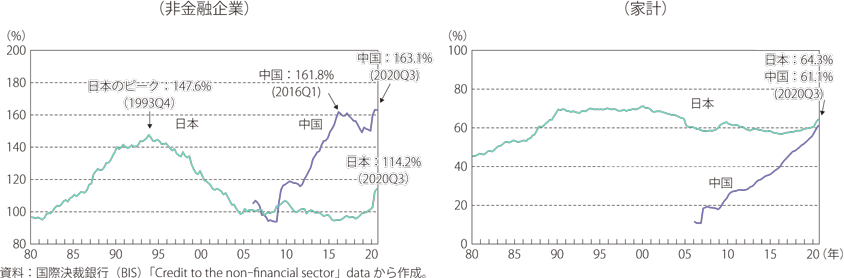
一方で、このような債務が中国の将来の成長に対して重荷なのは事実としても、国際的に比較すると、中国は、非金融企業債務が大きい反面、政府債務は相対的に小さく、全体では米国、ユーロ圏の水準と余り変わらない(第Ⅰ-2-3-39図)。また、2020年のコロナ対応の財政措置や金融緩和の影響を考えると、中国を含め各国とも、更に債務が拡大していく懸念がある。
第Ⅰ-2-3-39図 主要国・地域の債務残高(GDP比 / 2020年Q3)
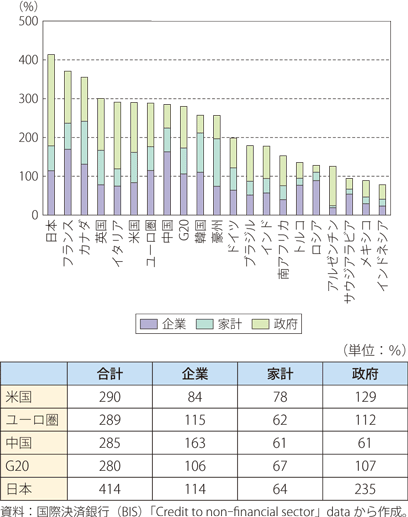
実際に中国の社会融資総量残高は、2020年は感染症に係る景気支援策のため伸びが加速した(第Ⅰ-2-3-40図)。シャドーバンキングに対しては抑制が続く一方で、融資は堅調に伸びており、社債、地方政府債も前年比約2割増の大幅な伸びとなっている。このような債務の増加に対して、通貨供給量の抑制など金融政策を通じて2020年末からは伸びを抑える動きも見られる。
第Ⅰ-2-3-40図 社会融資総量の残高の伸び率
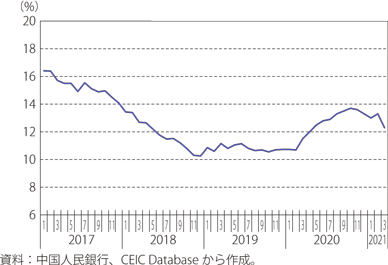
銀行融資については、2019年後半から不良債権比率が再び上昇に向かっており、その他に「要注意先」と呼ばれる不良債権予備軍が、不良債権額以上に存在している(第Ⅰ-2-3-41図)。特に銀行の中でも、地方に立脚する都市商業銀行60や小規模な農村商業銀行は不良債権比率の上昇とともに、利益率が低下して厳しい状況にある(第Ⅰ-2-3-42図)。
第Ⅰ-2-3-41図 中国の不良債権比率の推移
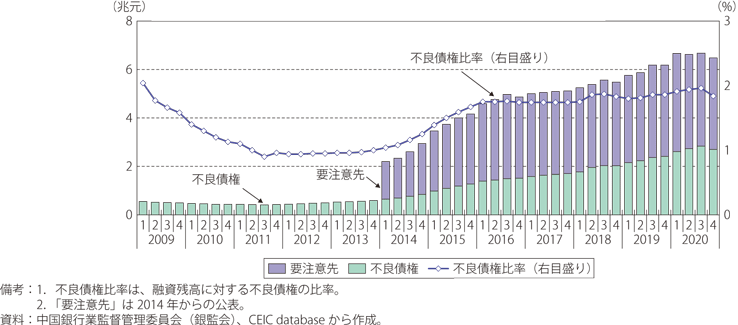
第Ⅰ-2-3-42図 銀行の不良債権と利益率
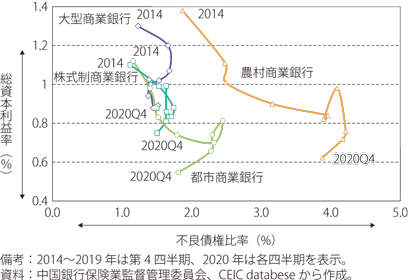
報道によれば、国有企業を含む企業の社債のデフォルトが増加している。特に一部の有名国有企業がデフォルトに陥るなど、企業の資金不足が大手国有企業にまで及んだとして波紋を投げかけている。
また、金融緩和の中で、資金が住宅市場に流入することも多く、バブルの危険性が度々指摘されている。北京、上海のほか、新型コロナ患者が初めて発見された武漢を含め、西安、重慶など内陸部でも住宅価格が上昇している(第Ⅰ-2-3-43図)。現在のところ、住宅需要はあり、在庫が急増している様子はないが、住宅ローン残高は高い伸びを示しており、バブルや債務問題とは別に、家計のローン支払が消費を圧迫する懸念もある。
第Ⅰ-2-3-43図 主要都市の新築住宅販売価格の推移
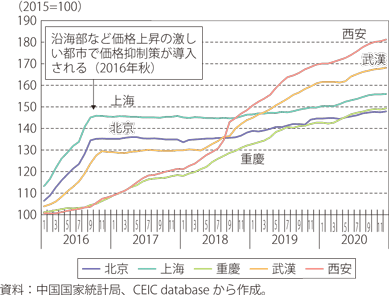
60 日本の地銀に相当。
3.中国政府の政策
このような中で2021年3月に開催された全国人民代表大会(全人代、我が国の国会に相当)において、第14次五か年計画及び2035年ビジョン目標の草案が提出され、その初年度である2021年の重点政策が審議された。
2035年ビジョン目標は、一人当たりGDPを「中等先進国」水準まで引き上げる61等の目標を挙げ、2035年に社会主義現代化を基本的に実現するという理念を掲げている。しかし、具体的な数値目標はなく、その最初の5年間の取組を第14次五か年計画として具体化したものと考えられる。第14次五か年計画の主要な目標を挙げたのが第Ⅰ-2-3-44表である。GDP成長率については、五か年計画としての具体的目標は設定せず、合理的範囲内に保ち、年度ごとに実際の状況に応じて目標を設定するとした。労働生産性はGDP成長率を上回ることが目標とされており、労働人口の減少に対して成長の質を高めることで対応しようとしていることが伺える。同様に研究開発を始めとするイノベーションの促進も、全要素生産性の上昇により成長を促進していく方針と見ることができる。民生福祉分野については、現在の厳しい雇用情勢の中で可処分所得の伸びが鈍化している状況から、雇用を安定化させ、可処分所得を高めることができれば、消費拡大につなげることも考えられる。エネルギー・環境問題に関しては、単位GDP当たりのエネルギー使用量・CO2排出量の削減を目指している。
第Ⅰ-2-3-44表 第14次五か年計画の主要目標
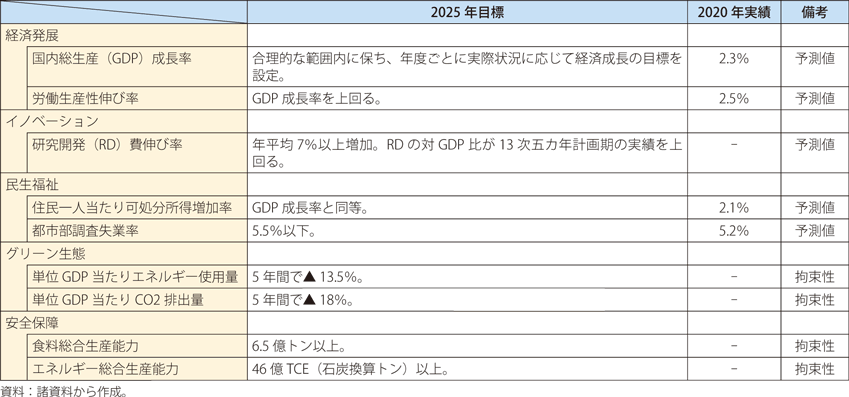
また、2021年の主要目標や重点施策も公表された(第Ⅰ-2-3-45表、第Ⅰ-2-3-46表)。2021年の経済成長率は6%以上と目標が設定された。「積極的な財政政策」は質・効率の向上を図り、より持続可能なものとするとして、財政赤字の対GDP比を3.2%前後(昨年より▲0.4ポイント)に設定し、感染症対策特別国債(昨年1兆元)の発行終了を決めた。また、「穏健な金融政策」は柔軟かつ的確で、合理的かつ適度なものにするとして、マネーサプライ、社会融資規模の伸び率を名目GDPとほぼ一致するようにして、債務総額の対GDP比の基本的安定を保つよう、金融リスクへの配慮も見られる。その他、五か年計画で見られた、イノベーション、民生、環境、安全保障に関する内容も見られる。
第Ⅰ-2-3-45表 2021年の主要目標
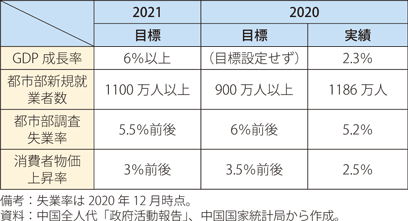
第Ⅰ-2-3-46表 2021年の重点施策
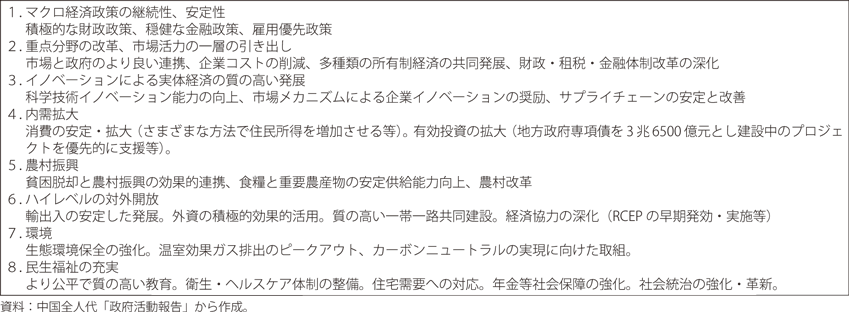
61 2035年ビジョンの中で「中等先進国」の水準は明示されていない。そこで主要国の2020年一人当たりGDPを見ると、6万ドル台の米国、4万ドル台の日英独仏等があり、これに3万ドル前後のイタリア(約3.1万ドル)、スペイン(約2.7万ドル)、2万ドル強のポルトガル(約2.2万ドル)等が続いている(資料:IMF「WEO」データベース)。仮に3万ドル、2万ドルの水準を考えると、2035年までに中国(2020年約1.0万ドル)が同水準に達するためには、それぞれ年平均7.3%、4.4%程度の成長が必要になる(複利ベースで計算)。参考に中国の過去の一人当たりGDP伸び率を見ると、2000年から2020年までの20年間の平均が12.7%、2010年からの10年間が8.8%、2015年からの5年間が5.3%と緩やかになってきている。