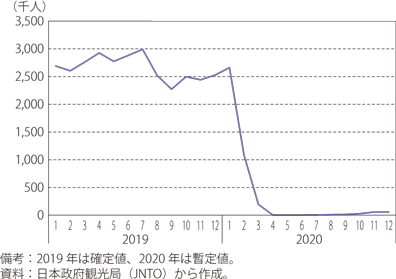第4節 激変する世界情勢の中での日本の貿易投資動向
1.財貿易の動向
2020年の日本の財貿易は、輸出額が68兆4,005億円と前年から11.1%減少、輸入額が67兆8,371億円と前年から13.7%減少したが、輸入額の減少が輸出額の減少を上回ったため、貿易収支で見ると5,634億円と3年ぶりの黒字となった(第Ⅰ-2-4-1図)。
第Ⅰ-2-4-1図 日本の貿易収支の推移
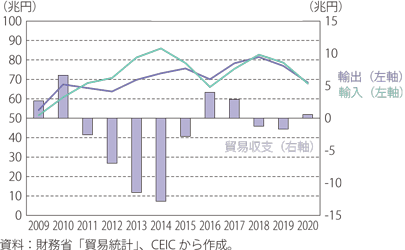
(1)品目別の貿易動向
① 輸出
輸出を品目別に見ると、輸送用機器が輸出全体の21.1%、一般機械が19.2%、電気機器が18.7%と上位3品目で約6割を占めている(第Ⅰ-2-4-2図)62。このような輸送用機器、一般機械、電気機器の上位3品目が輸出額の約6割を占める品目構造は過去5年を見ても変化はない(第Ⅰ-2-4-3図)。
第Ⅰ-2-4-2図 日本の輸出品目(2020年)
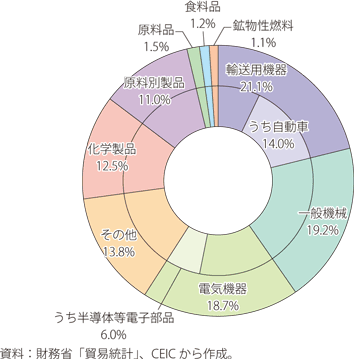
第Ⅰ-2-4-3図 日本の輸出の推移(品目別・年別)
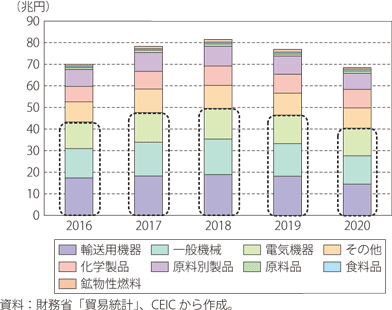
また、月別で見ると、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた諸外国におけるロックダウン等の経済社会活動の制限措置の影響等により、1月から11月にかけて前年同月比でマイナスとなり、特に5月は-28.3%と大きく落ち込んだ。ただし、前年同月比のマイナス幅は5月を底に縮小し、12月にはプラスに転じており、輸出は回復傾向にある(第Ⅰ-2-4-4図)。また、品目別に見ると輸送用機器は5月に前年同月比-60.2%と大きく落ち込んだ。依然として前年を下回る水準で推移しているものの全体のトレンドと同様に5月を底におおむね回復傾向である。一般機械は6月を底に回復し、12月には前年同月比0.3%とわずかに前年を上回る水準となった。同様に電気機器は6月を底に回復し、9月には前年を上回る水準となり、12月には前年同月比6.6%の増加となった。
第Ⅰ-2-4-4図 日本の輸出の推移(品目別・月別)
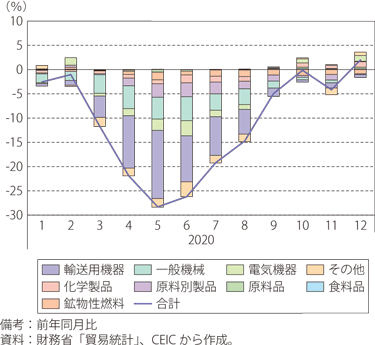
続いて、輸出額の2割を占める輸送用機器の輸出動向を見る。輸送用機械の内、自動車の輸出は5月には前年同月比-64.1%と大きなマイナスとなった。それ以降はおおむね回復傾向にある。また、自動車の部分品も同様に5月を底におおむね回復傾向にある(第Ⅰ-2-4-5図)。
第Ⅰ-2-4-5図 自動車及び自動車部品の輸出の推移
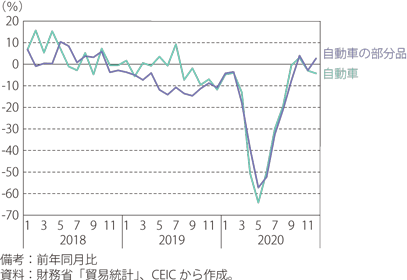
また、自動車の輸出額上位3か国の輸出動向を見ると、輸出先第1位の米国向けは5月には681億円まで落ち込み、過去3年間で一番小さな輸出額となった(第Ⅰ-2-4-6図)。しかし、9月以降には上位3か国とも前年を上回る水準まで回復している(第Ⅰ-2-4-7図)。
第Ⅰ-2-4-6図 自動車の輸出額の推移(2020年輸出額の上位3か国)
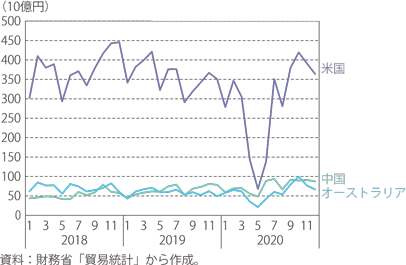
第Ⅰ-2-4-7図 自動車の輸出の推移(2020年輸出額の上位3か国)
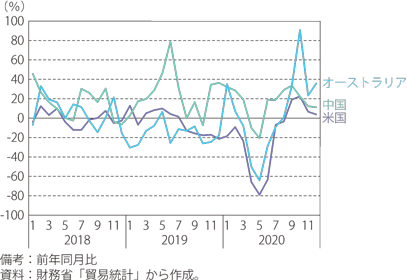
半導体関連の品目の輸出動向については、一般機械に含まれる半導体等製造装置及び電気機器に含まれる半導体等電子部品に着目する。3か月平均値を用いて半導体等製造装置の輸出動向を見ると、輸出先第1位の中国向けでは上半期にかけては輸出額が停滞していたが、下半期にかけては輸出額が増加傾向となっている(第Ⅰ-2-4-8図)。
第Ⅰ-2-4-8図 半導体等製造装置の輸出額の推移(2020年輸出額の上位3か国)
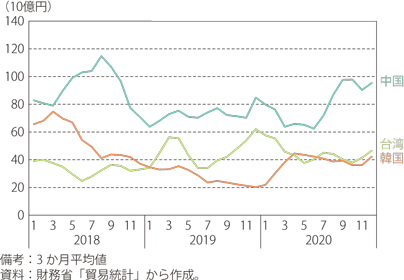
続いて、半導体等電子部品の輸出動向を見ると、2020年1月に輸出額上位3か国はともに輸出額が減少したが、その後は目立った動きは見られない(第Ⅰ-2-4-9図)。
第Ⅰ-2-4-9図 半導体等電子部品の輸出額の推移(2020年輸出額の上位3か国)
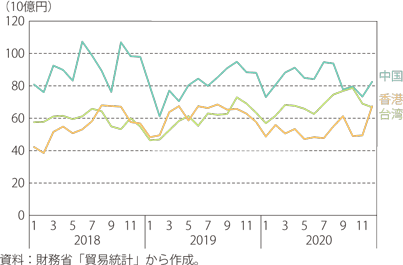
② 輸入
輸入を品目別に見ると、電気機器が輸入全体の16.7%、次いで鉱物性燃料が16.6%を占めている(第Ⅰ-2-4-10図)。過去5年の動向では2016年以降、輸入額全体に占める鉱物性燃料の割合が一番大きく、次いで電気機器が占める割合が大きかった。しかし、2020年には上位2品目の順位が入れ替わり、輸入額に占める鉱物性燃料の割合は小さくなった。この背景には、新型コロナウイルスの感染拡大を受け経済活動が停滞したため、原油の需要が減少しWTI(West Texas Intermediate)原油先物価格が史上初めてのマイナス値になるなど、コロナ禍で価格が下落したことが挙げられる。なお、輸入全体に占める割合は2019年が21.6%だったのに対して、2020年は16.6%と縮小した(第Ⅰ-2-4-11図)。
第Ⅰ-2-4-10図 日本の輸入品目(2020年)
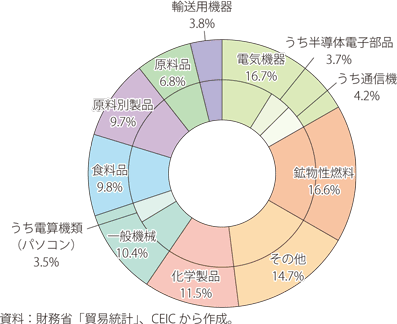
第Ⅰ-2-4-11図 日本の輸入の推移(品目別・年別)
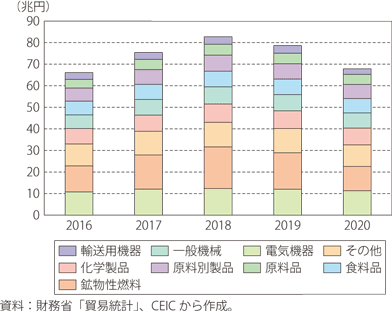
また、月別で見ると、原油をはじめとする資源価格の下落や新型コロナウイルスの感染拡大を受けた感染症緊急事態宣言の発出による消費の抑制・需要の減少により、年間を通して前年を下回る水準で推移している(第Ⅰ-2-4-12図)。
第Ⅰ-2-4-12図 日本の輸入の推移(品目別・月別)
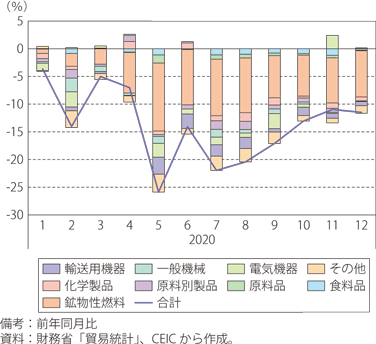
続いて品目別に見ると、鉱物性燃料の輸入額は新型コロナウイルスの感染拡大を受け大きく減少し、5月には6,183億円となり、輸入額全体に占める割合も6月には12.1%まで減少した。しかし、鉱物性燃料の輸入額及び輸入額全体に占める割合は5、6月を底に緩やかな回復傾向にある(第Ⅰ-2-4-13図)。
第Ⅰ-2-4-13図 鉱物性燃料の輸入の推移
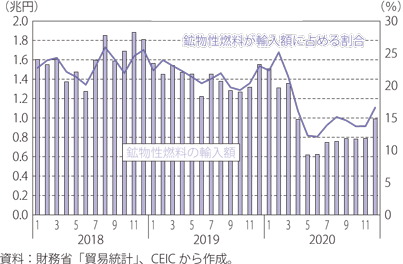
日本のエネルギー自給率63は2018年度時点で11.8%64であり、国内の生産活動や生活を維持するためには一定の鉱物性燃料の輸入が必要であるため、輸入額の増減に与える要因は数量と比較して価格が大きいと考えられる。鉱物性燃料の中でも主要な品目である液化天然ガスと原油及び粗油を用いて、輸入金額に与える要因分析を行ったところ、おおむね数量と比較して価格による要因が大きいことが分かった(第Ⅰ-2-4-14図、第Ⅰ-2-4-15図)。なお、原油及び粗油については2020年において数量による要因も比較的大きく、原油から精製される石油製品の内、ガソリンの消費量については5月に大きく縮小し、前年を下回る水準で推移している(第Ⅰ-2-4-16図)。
第Ⅰ-2-4-14図 液化天然ガス輸入額の前年比要因分解(数量、価格)
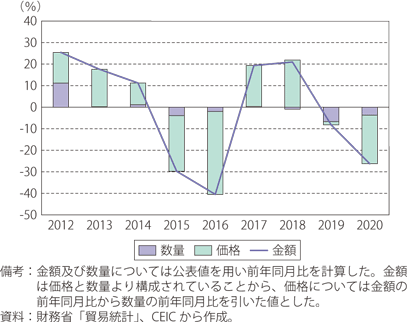
第Ⅰ-2-4-15図 原油及び粗油輸入額の前年比要因分解(数量、価格)
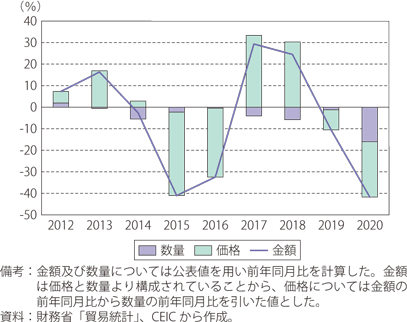
第Ⅰ-2-4-16図 ガソリン消費量の推移
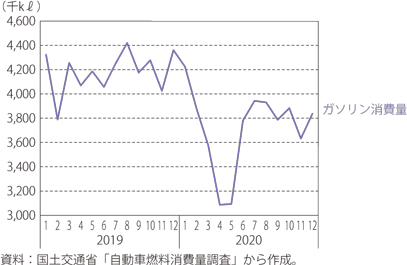
62 原料別製品とは鉄鋼や非鉄金属、織物用糸・繊維製品など。
63 国民生活や経済活動に必要な一次エネルギーのうち、自国内で確保できる比率。
64 経済産業省 資源エネルギー庁「令和元年度エネルギーに関する年次報告」(エネルギー白書2020)
(2)国・地域別の貿易動向
輸出を国・地域別に見ると、アジア向けの輸出額が39兆2,202億円となり、輸出額全体の5割以上を占める。そのうち中国向けの輸出額は15兆819億円と輸出額全体の22.0%を占め、輸出額は前年より増加した。また、米国向けの輸出額は中国に次ぐ、12兆6,122億円であり輸出額全体の18.4%を占めるが、輸出額は前年より減少した。続いてASEAN向けの輸出額は9兆8,430億円と輸出額全体の14.4%を占めるものの、輸出額は前年より減少した(第Ⅰ-2-4-17図)。
第Ⅰ-2-4-17図 日本の輸出入相手国・地域 上位5か国
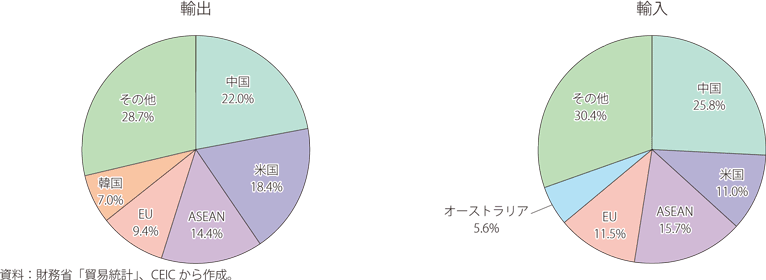
続いて、輸入を国・地域別に見ると、アジアからの輸入額が34兆6,435億円となり、輸入額全体のおよそ5割を占める。そのうち中国からの輸入額は17兆4,931億円と輸入額全体の25.8%を占めるが、輸入額は前年より減少した。また、ASEANからの輸入額は中国に次ぐ、10兆6,646億円と輸入額全体の15.7%を占めるが、輸入額は前年より減少した。続いてEUからの輸入額は輸入額全体の11.5%を占めるものの、輸入額は前年と比較すると減少した(第Ⅰ-2-4-17図)。
続いて、輸出入の指数を用いて2020年の国・地域別の貿易動向を概観する。
まず、輸出金額及び数量については中国と米国・EUでは動きが異なる。中国について、輸出金額・数量ともに2020年3月に一旦減少したが、その後はおおむね回復の傾向にあり、12月時点でどちらも前年を上回る水準となっている。一方で、米国及びEUについては、輸出金額・数量ともに5~7月ごろに大きく落ち込んでおり、12月時点でどちらも前年を下回る水準となっている。それぞれの輸出相手国の感染状況や経済活動の再開に左右されながら、日本の輸出動向も変動している(第Ⅰ-2-4-18図)。
第Ⅰ-2-4-18図 日本の輸出金額・数量の推移(指数ベース)

次に、輸入金額及び数量については、特に中国の動きが顕著であり、2020年2月には輸入金額・数量ともに一番大きな減少となり、回復が鈍い傾向にあるが、12月時点でどちらも前年を上回る水準となっている。一方で、EUや米国についてはおおむね前年を下回る水準で推移している(第Ⅰ-2-4-19図)。
第Ⅰ-2-4-19図 日本の輸入金額・数量の推移(指数ベース)
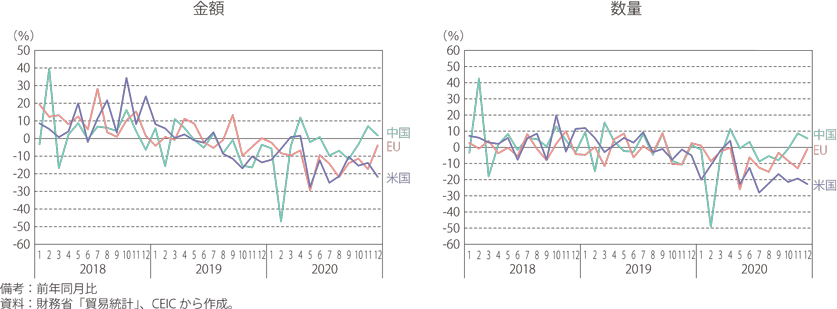
続いて、日本の二大貿易相手国である中国と米国との貿易動向について概観する。
① 対中貿易
中国向けの輸出品目は、一般機械が3兆4,099億円と全体の22.6%を占め、金額は前年比0.4%増加した。次いで、電気機器が3兆2,015億円と全体の21.2%を占め、金額は前年比5.3%増加した。また、化学製品は2兆5,312億円と全体の16.8%を占める。また、輸出品目の構造としては、一般機械、電気機器、化学製品が上位3品目となる構造に変化はない(第Ⅰ-2-4-20図)。
第Ⅰ-2-4-20図 中国への輸出品目の推移
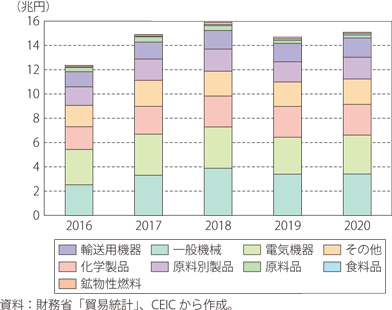
中国からの輸入品目は、電気機器が5兆1,005億円と全体の29.2%を占め、金額は前年比-3.7%と減少した。次いで、その他が4兆908億円と全体の23.4%を占め、金額は前年比-11.7%と減少した。また、一般機械は3兆4,090億円と全体の19.5%を占める。また、輸入品目の構造については過去5年間で大きな動きはない(第Ⅰ-2-4-21図)。
第Ⅰ-2-4-21図 中国からの輸入品目の推移
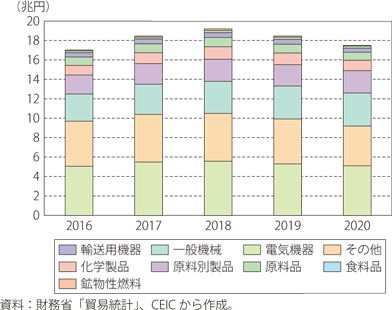
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けた品目として、一般機械に含まれる電算機類(含周辺機器)及び原料別製品に含まれる織物用糸・繊維製品の輸入動向について着目する。
まず、電算機類(含周辺機器)は2月に輸入額が落ち込んだが、4月以降はテレワークの拡大などを背景にパソコンなどの需要が増加し、前年比14.8%と2桁の伸びとなった(第Ⅰ-2-4-22図)。また、一般機械に占める電算機類(含周辺機器)の割合も2020年に入り5割を超えている(第Ⅰ-2-4-23図)。
第Ⅰ-2-4-22図 電算機類(含周辺機器)の輸入額の推移
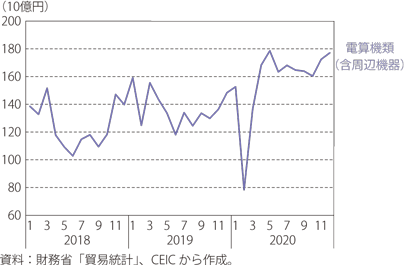
第Ⅰ-2-4-23図 一般機械に占める電算機類(含周辺機器)の割合の推移
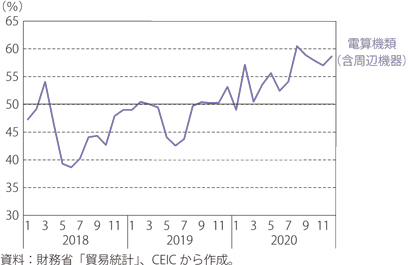
また、マスクを含むその他繊維製品65については新型コロナウイルスの感染拡大を受け、5月には前年同月比およそ1,500%に近い増加となり、その後、輸入額は落ち着いているものの、引き続き前年を上回る水準で推移しており、輸入額の底が上がっているといえる(第Ⅰ-2-4-24図)。
第Ⅰ-2-4-24図 その他の繊維製品(マスクが含まれる)の輸入額の推移
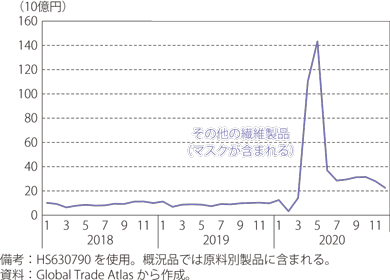
② 対米貿易
米国向けの輸出品目は、輸送用機器が4兆5,219億円と全体の35.9%を占めているが、金額は前年比-19.9%と減少した。次いで、一般機械が2兆8,371億円と全体の22.5%を占め、金額は前年比-21.6%と減少した。また、電気機器は1兆8,073億円と全体の14.3%を占める。過去5年間の品目構成の推移を見ると、輸送用機器、一般機械、電気機器が上位3品目を占める構造に変化はない。また、特に輸送用機器が占める割合が3割~4割程度と大きい(第Ⅰ-2-4-25図)。
第Ⅰ-2-4-25図 米国への輸出品目の推移
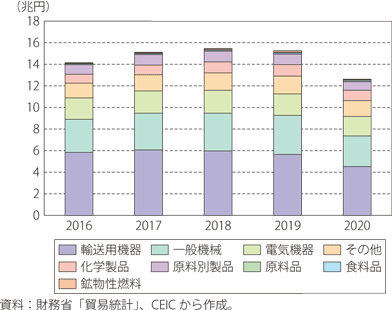
輸送用機器の中でも、自動車は5月に大きく輸出が減少し、前年の同月と比較して-78.9%となったが、9月以降は前年を上回る水準に回復をしている(第Ⅰ-2-4-26図)。米国の自動車の小売売上高の推移を見ると、4月には618億ドルと過去3年間で最も大きく減少をしたが、4月を底に回復傾向にあり、6月以降には新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受ける前の水準を上回った(第Ⅰ-2-4-27図)。前述のとおり、自動車の輸出額に占める米国の割合は大きく、米国での需要回復は日本の自動車の輸出動向に影響を与える可能性がある。
第Ⅰ-2-4-26図 自動車の輸出の推移
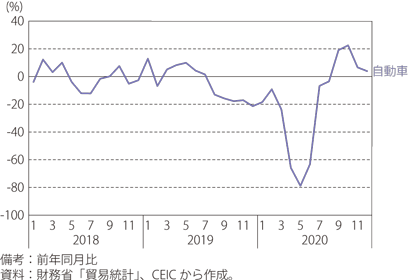
第Ⅰ-2-4-27図 米国の小売売上高(自動車)の推移
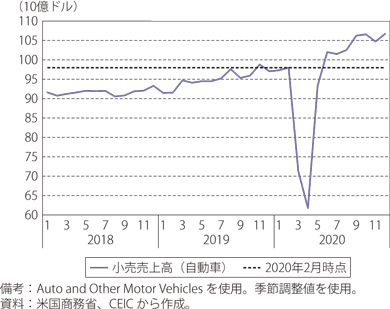
米国からの輸入品目は、化学製品が1兆3,466億円と全体の18.1%を占める。次いで、食料品が全体の1兆3,105億円と17.6%を占め、一般機械は1兆193億円と全体の13.7%を占める。これら米国からの輸入額上位3品目は前年と比較して総じて輸入額が減少しており、輸入額全体で見ても-13.9%の減少となった。また、過去5年間における輸入品目の構造に大きな変化は見られないが、2020年には上位2品目の順位が入れ替わり、化学製品は医薬品の輸入額の伸びを受け、食料品を抜いて、一番大きな構成品目となった(第Ⅰ-2-4-28図)。
第Ⅰ-2-4-28図 米国からの輸入品目の推移
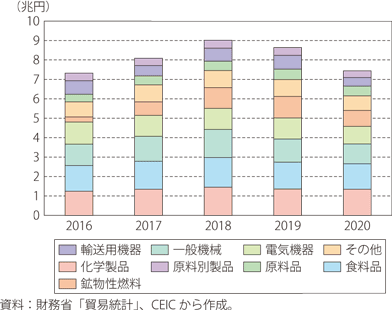
医薬品は3か月平均値を用いて前年同月と比較すると、2020年2月以降は前年を上回る水準で推移しており、年間では+14.4%と2桁での伸びとなった(第Ⅰ-2-4-29図)。また、医薬品の中でもワクチンを含む免疫血清及び免疫産品などの輸入動向については、同様に3か月平均値を用いると2020年2月時点の輸入額を上回る水準で推移をしている(第Ⅰ-2-4-30図)。
第Ⅰ-2-4-29図 医薬品の輸入の推移
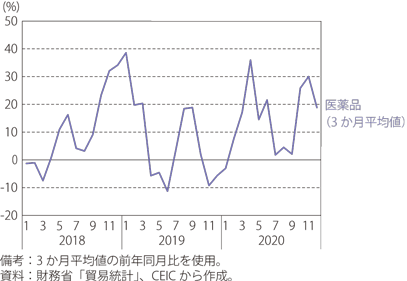
第Ⅰ-2-4-30図 免疫血清及び免疫産品などの輸入額の推移
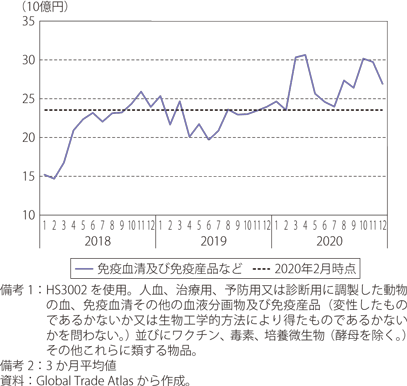
③ 中国と米国に対する輸出品目別シェアと前年伸び率
中国及び米国に対する輸出品目について上位5品目のシェアと前年伸び率について比較を行った。対中国の輸出品目は品目ごとおおむね20%程度かそれ以下であり、多様な構成となっている。また、光学機器や測定機器などを除くと、前年を上回る水準で輸出をしている(第Ⅰ-2-4-31図)。一方、対米国の輸出品目については、3割程度、自動車を含む車両並びにその部分品(鉄道用・軌道用は除く)が占めており、一般機械を合わせると5割を超え、この2品目が大きな構成品目となっている。また、上位5品目について総じて前年を下回る水準となっている(第Ⅰ-2-4-32図)。
第Ⅰ-2-4-31図 対中国への輸出品目上位5品目におけるシェアと前年比
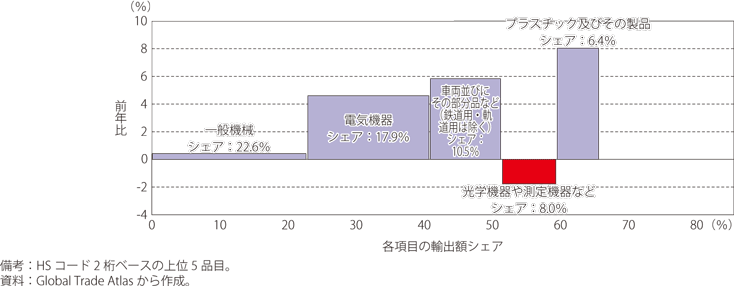
第Ⅰ-2-4-32図 対米国への輸出品目上位5品目におけるシェアと前年比
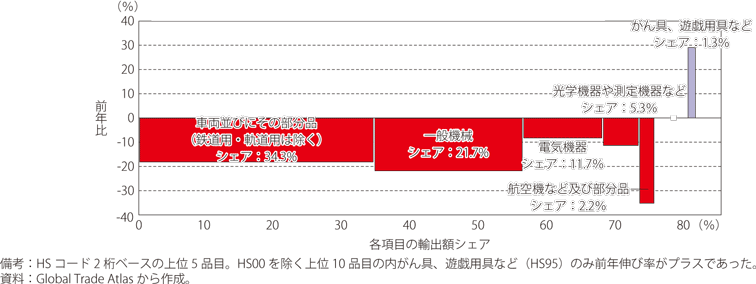
2.経常収支の概観
2020年の日本の経常収支66は17兆5,347億円の黒字だが、黒字幅は前年比-9.0.%の減少となった(第Ⅰ-2-4-33図)。黒字幅が縮小した主な要因はサービス収支の赤字幅拡大である。月別の経常収支では、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が出された4月を底に回復傾向にあり、特に貿易収支は下半期に入り黒字を維持している(第Ⅰ-2-4-34図)。
第Ⅰ-2-4-33図 日本の経常収支の推移(年別)
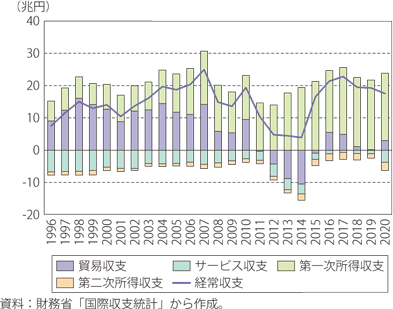
第Ⅰ-2-4-34図 日本の経常収支の推移(月別)
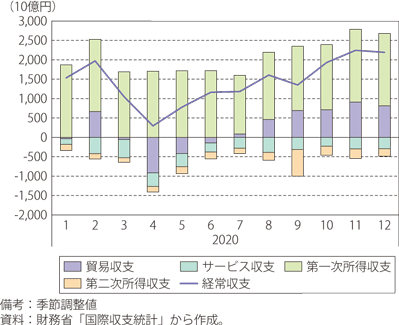
65 マスクを含むその他繊維製品はHS630790を使用。
66 第一次所得収支/再投資収益は、毎年11月に改訂が行われている。
(1)第一次所得収支の動向
第一次所得収支は日本の経常収支を支える最も大きな構成要素だが、2020年は20兆8,090億円と黒字を維持するものの、前年と比較すると黒字幅はわずかに縮小した(第Ⅰ-2-4-35図)。
第Ⅰ-2-4-35図 日本の第一次所得収支の推移
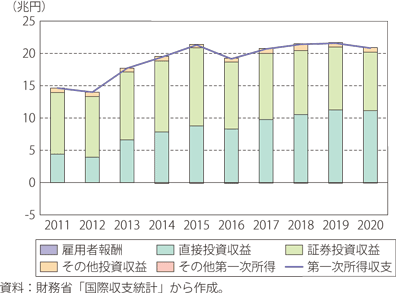
内訳を見ると直接投資収益が最大であり、投資収益に占める直接投資収益の割合は5割以上となり、2011年が3割程度だったことと比較するとその割合は大きくなっている。直接投資収益は支配的または重要な影響を及ぼしている出資先からの配当金及び利子等であり、証券投資収益は配当金や債券利子の内、直接投資収益に該当しないものであるため、日本企業が国外の生産活動に関与し、外貨を獲得している割合が大きくなっていることが分かる(第Ⅰ-2-4-36図)。
第Ⅰ-2-4-36図 投資収益の内訳の推移
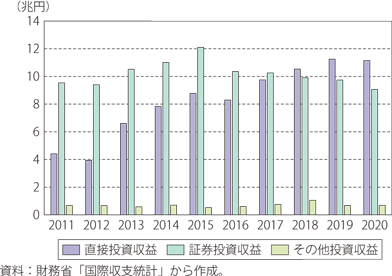
(2)サービス収支の動向
2020年の日本のサービス収支は-3兆7,357億円の赤字であり、前年の-1兆821億円の赤字から更に収支が悪化した(第Ⅰ-2-4-37図)。赤字幅が拡大した主な要因としては旅行収支の黒字幅縮小とその他サービス収支の赤字幅拡大が考えられる。特に、旅行収支については新型コロナウイルスの感染拡大を受けた、入国制限などによる訪日外客数の減少が大きな影響を与えたと考えられる(第Ⅰ-2-4-38図)。
第Ⅰ-2-4-37図 日本のサービス収支の推移
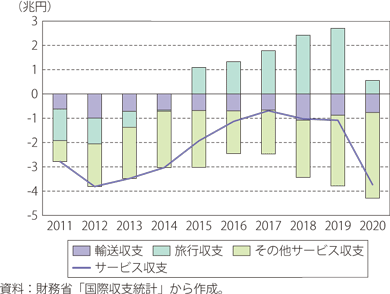
第Ⅰ-2-4-38図 日本の訪日外客数の推移