第1節 アジアワイドのサプライチェーンの変化
我が国製造業はアジアを中心に海外進出を果たし、その生産拠点間での中間財の流れ、サプライチェーンを形成してきた。ここでは、アジアのサプライチェーンの特色や変化を考察していく。
1.アジア域内では国際的な生産分業が展開
(1)国際収支統計で見た企業の立地
我が国企業は、プラザ合意後の為替レートの変化や国際的な労働コストの相違等に対応して、積極的な直接投資を通じて海外進出を果たしてきた。まず、その動きを日本の国際収支統計(直接投資)で概観する。次に企業統計を利用して業種別に見た日系企業の海外展開の実態を考察する。
日本の直接投資残高は、国際金融危機で一時的に足踏みしたものの、拡大基調で推移している(第Ⅱ-1-1-1図)。その中でアジアのシェアは上昇してきており、特に製造業分野に焦点を置くと、アジアのシェアは更に高く、世界金融危機後、北米、欧州を上回って推移している(第Ⅱ-1-1-2図)1。
第Ⅱ-1-1-1図 日本の直接投資残高とアジアのシェア(全産業)
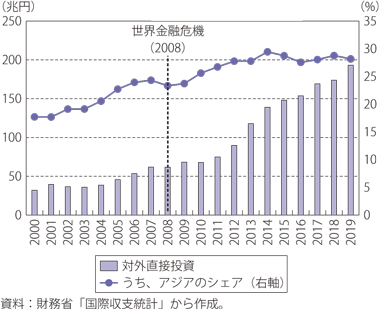
第Ⅱ-1-1-2図 日本の直接投資残高と地域別シェア(製造業分野)
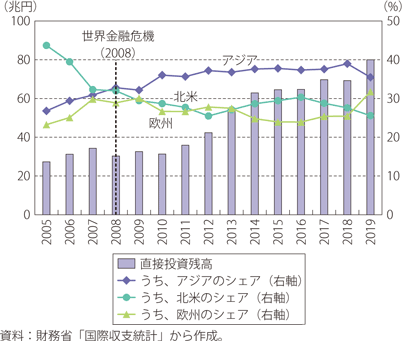
それでは、アジアのどこに製造業分野の直接投資がされているかを見ると、第1位が中国で、直接投資残高約9.1兆円、世界全体の1割強のシェアを占めている(第Ⅱ-1-1-3表)2。第2位がタイで同約5.1兆円と中国の約半分の規模。第3位以下にシンガポール、インド、インドネシア、韓国と続き、いずれも第2位のタイの半分以下の水準となっている3。こうしてみると、中国が突出して大きく、2番手にタイが次いでいる様子がうかがえる。
第Ⅱ-1-1-3表 日本のアジア諸国・地域への直接投資残高(製造業分野/2019年末)
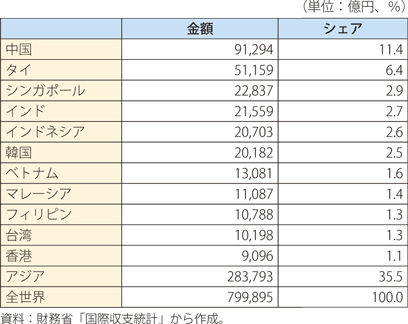
これまでの推移を見ると金額ベースではいずれの国も増加基調で推移している(第Ⅱ-1-1-4図)。特に中国やタイは2010年代前半に急速に拡大し、緩やかになるものの2010年代後半も拡大が続いている。ただし、為替レートの関係から金額ベースの考察だけでは不十分なため、日本の直接投資残高に占める各国のシェアを追うことでプレゼンスの変化を考察する4。中国は2012年をピークにシェアが低下しているのに対して、タイは洪水のあった2011年を含めて緩やかながらシェアを拡大している5。他のアジア諸国は、年による振れはあるものの、ほぼ横ばいで推移する国が多い中で、インド、ベトナムは拡大基調をたもっている。
第Ⅱ-1-1-4図 日本のアジアに対する国別直接投資残高(製造業分野)
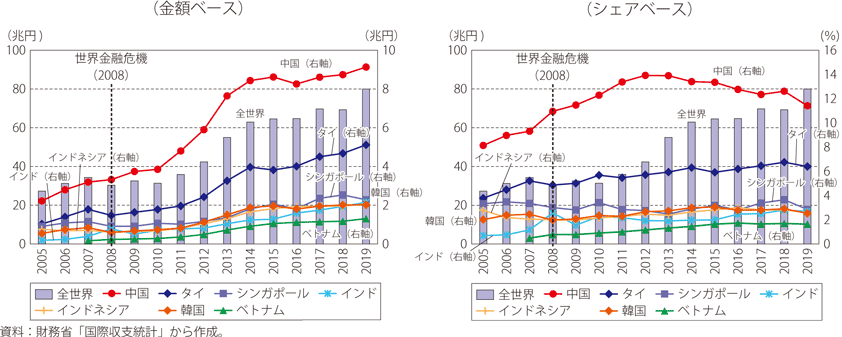
1 国際収支統計で、業種別に直接投資残高が公表されるようになったのが2005年のため、グラフは2005年を起点としている。なお、2019年にアジア、北米のシェアが急減し、欧州のシェアが急増しているのは、アイルランド向けの化学・医薬分野の大型案件があったため。
2 本節において、特に断らない限り「中国」とは本土のみで、香港は含まない。
3 国際収支統計で直接投資残高が公表されている国・地域の中で考察した。なお、ベトナムについては2007年末から公表が開始されたため、時系列のグラフでは同国は2007年からの表示となっている。
4 直接投資残高は為替レートに影響される点には注意が必要。国際収支統計は円ベースで公表されるが、円の為替レートは2011年の約80円から、2015年約121円(年平均)まで円安方向に変化している。直接投資のように現地通貨建ての資産を円換算するに当たって、各現地通貨に対しても円安方向に動いたとすれば、円ベースでは拡大しているように計算される。このため、直接投資の動向として残高の世界全体に占めるシェアを併せて考察した。
5 2012年夏、日本の尖閣諸島国有化後、中国で大規模な抗日運動が起こり、中国投資に対する慎重な姿勢が見られる。
(2)企業統計で見た業種別動向
次に海外現地法人の統計で日系製造業の海外展開を確認してみる。経済産業省「海外事業活動基本調査」で見ると、世界に展開する日系海外現地法人は約2万6,000社(第Ⅱ-1-1-5表)。そのうち、製造業が約1万1,000社で、その8割近くがアジアに立地している6。アジアの中では中国、ASEANの立地が多い。既に見た直接投資残高ベースに比べて企業数ベースで見た方がアジアのシェアの方がはるかに高いことから、アジアには大企業だけでなく相対的に中小規模の企業まで幅広く進出していることがうかがえる。
第Ⅱ-1-1-5表 日系製造業の業種別海外現地法人数(2018年度)7
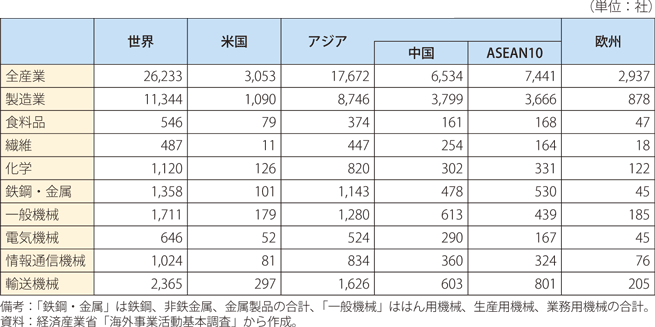
業種別には、アジアに展開するのは、輸送機械、一般機械、鉄鋼・金属、化学、情報通信機械など、部材及び機械関係が多い。
6 「海外事業活動基本調査」は、海外に現地法人を有する日本企業(金融業、保険業及び不動産業を除く)を対象とした調査。海外現地法人とは、海外子会社(日本側出資比率が10%以上の外国法人)及び海外孫会社(日本側出資比率が50%超の海外子会社が50%超の出資を行っている外国法人)を指す。2019年7月の調査(2018年度実績)の回収率は73.4%。法人格を有しない海外事務所は集計に入らないことや無回答企業については把握できないこと等に注意は必要であるが、日系海外現地法人の活動を把握する重要なデータとして利用する。
7 「海外事業活動基本調査」では、各海外現地法人が採用している会計年度で報告されている。このため、現地法人によって会計年度が例えば12月まで、3月までと相違があり得る。
① 海外生産比率
日系製造業の海外進出の結果、日系企業の全生産における海外生産比率は上昇基調で推移してきた(第Ⅱ-1-1-6図)8。特に、輸送機械、情報通信機械等の海外生産比率が高い(第Ⅱ-1-1-7図)。
第Ⅱ-1-1-6図 日系製造業の海外生産比率の推移
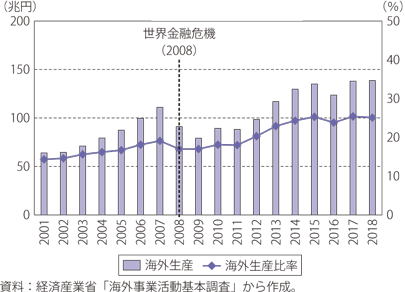
第Ⅱ-1-1-7図 日系製造業の業種別海外生産比率(2018年度)
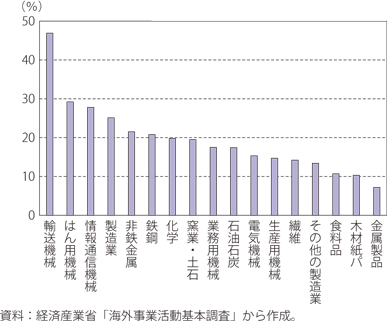
8 製造業に属する法人企業の売上高から計算。国内に立地する製造業企業の売上高(法人企業統計)及び海外製造業現地法人(海外事業活動基本調査)の売上高合計に対する海外製造業現地法人の売上高の比率として計算。
② 海外現地法人の立地国・地域
それでは、海外のどこで生産を拡大していったのか、日系海外現地法人の立地国別・地域の企業数、売上高の推移を概観する。
まず、企業数では、2000年代初めは米国への立地が最も多かったが、中国への立地が急速に拡大、タイも緩やかに増加(第Ⅱ-1-1-8図)。この3か国は法人格を有する製造業の現地法人が1,000社を越え、4位以下を引き離している。それ以外の国では、2012年以降、インドネシアの立地が増加するとともに、2000年代を通じてベトナムの立地も伸びている。それほど水準が大きくはないがインドも堅調に増加し、アジア域外ではメキシコも伸びている。世界に占めるシェアの推移を見ると、ベトナム、インド、メキシコが拡大しており、特にベトナムのシェア拡大が目立つ。
第Ⅱ-1-1-8図 日系製造業現地法人の立地国・地域別企業数の推移
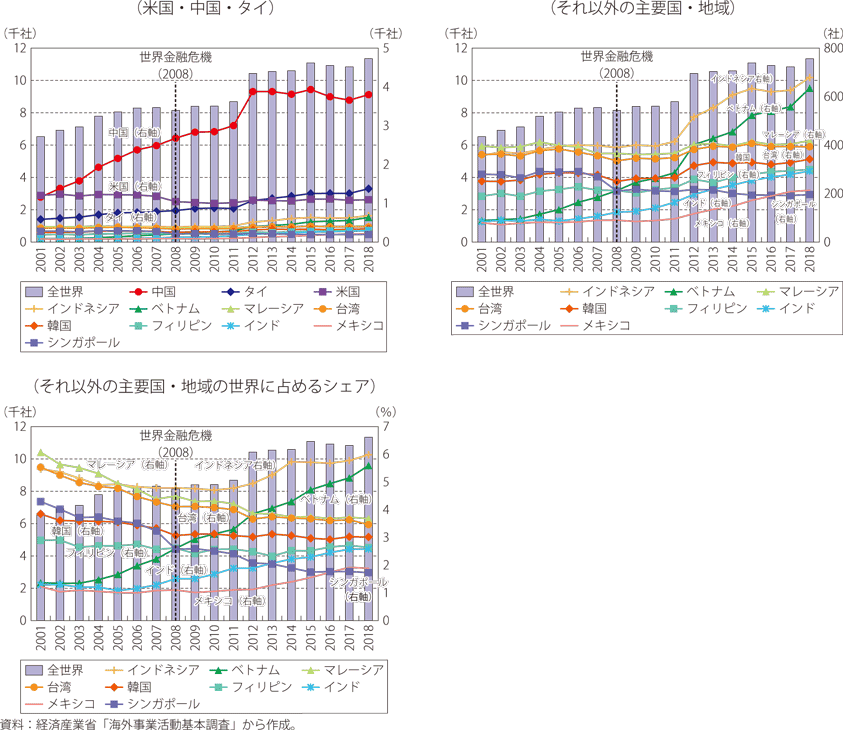
次に海外現地法人の売上高を見ると、世界金融危機後、米国の売上高が急落し、拡大してきた中国とほぼ拮抗する水準で推移している。タイは世界金融危機後、低迷していたが、2011年の洪水後は緩やかに増加している(第Ⅱ-1-1-9図)。シェアで見ると、この3国のシェアはここ数年ほぼ変わっていない。第Ⅱ-1-1-10図は、企業数(横軸)、一社当たり売上高(縦軸)、売上高(円の大きさ)を表示しているが、世界で売上高の大きな国としては、米国、中国が拮抗し、3位にタイが続いている。また、企業規模別には、中国を始めアジアには相対的に中小規模の企業が多数立地しているのに対して、米国など欧米には比較的大きな規模の企業が立地していることも分かる。
第Ⅱ-1-1-9図 日系製造業現地法人の立地国別売上高の推移
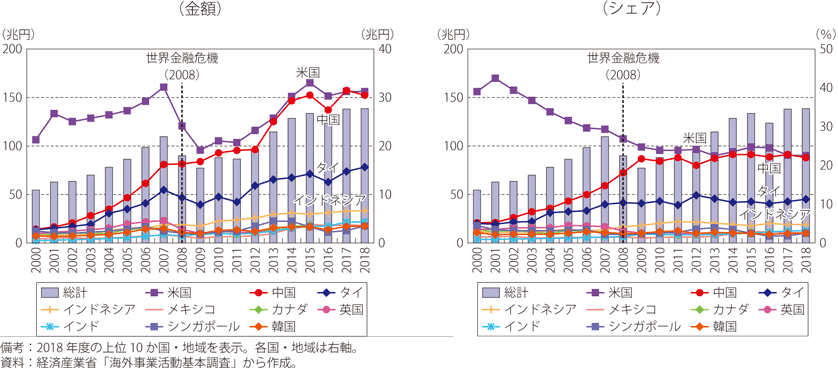
第Ⅱ-1-1-10図 日系製造業現地法人の国・地域別売上高規模(2018年度)
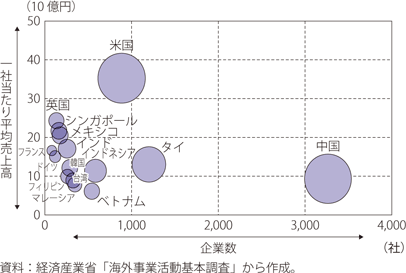
(3)国際的な生産分業
日系製造業がアジアに展開する場合、低い労働コストを求めて、新興国に製造拠点を設置するケースが多い。この場合、日本の本社から、高度な技術・知識を必要とするような基幹部品を輸出し、労働コストが低い新興国で組立てなどの労働集約的作業を行う垂直的な生産分業が基本になっている。完成した製品は、もし現地に十分な市場がなければ、日本や欧米などに輸出することになる。この欧米など第三国へ輸出する場合が三角貿易といわれる形態になる(第Ⅱ-1-1-11図)。
第Ⅱ-1-1-11図 国際的な生産分業のモデル
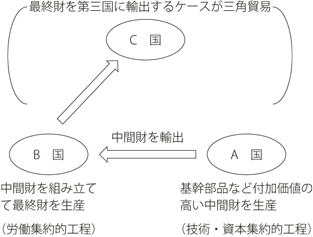
① 企業内輸出比率
このように日本の本社と海外の現地法人との間で垂直的な生産分業を行う場合、企業内で基幹部品の生産工程と最終組立工程が分業されることになる。日本の製造業企業の輸出のうち、資本関係のある関係会社向け輸出比率は高い。特に世界金融危機後、は上昇基調で直近は6割近い(Ⅱ-1-1-12図)9。
第Ⅱ-1-1-12図 日本国内の製造業企業の企業内輸出比率の推移
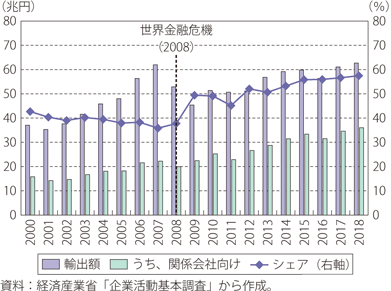
9 「経済産業省企業活動基本調査」を利用して、日本に立地する製造業企業の全輸出額に対する「関係会社」向け輸出額の比率として計算。ここで「関係会社」とは、「親会社」、「子会社」、「関連会社」を意味し、「子会社」とは50%超の議決権を有する会社、「関連会社」とは20%以上50%以下の議決権を有する会社を指す。
② 生産拠点間の中間財の流れ
この生産拠点間の中間財の流れがサプライチェーン(供給網)で、立地地域別に調達額を図示したのが第Ⅱ-1-1-13図である。様々な部材が関係するため、アジアに展開する日系企業は、日本、立地国、その他のアジア域内から調達活動を行っている。地域を越えて北米、欧州からの調達もあるが、規模は限られている。なお、業種によって調達先に特徴があるがこの点は追って論じる。
第Ⅱ-1-1-13図 日系海外現地法人の調達(2018年度)
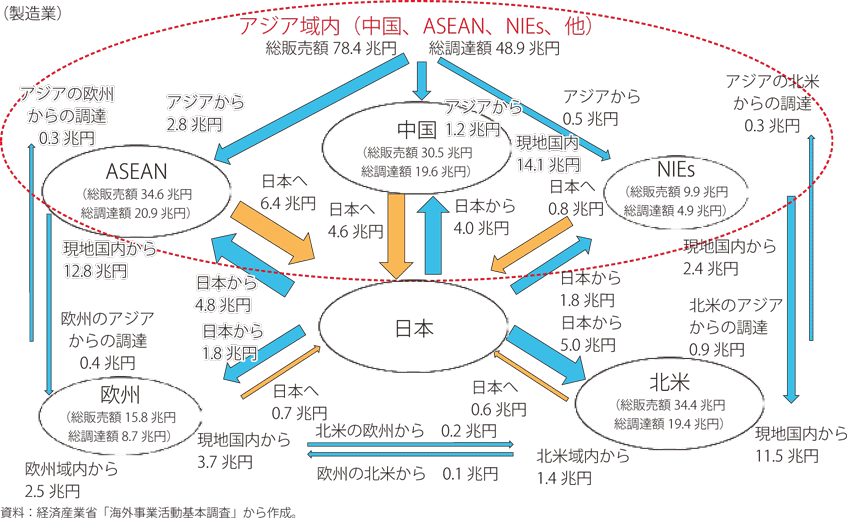
このような国際的な生産分業は、特に機械産業において見られる。第Ⅱ-1-1-14図はアジアを中心とした貿易フローの鳥瞰図で、総じてアジアの貿易は機械のシェアが高い。例えば、アジアの中で、日本、韓国、台湾は、中国、ASEAN向けに機械関係を中心に輸出している。中国の側から見れば、日本、韓国、台湾、ASEANから大きな輸入を受け、その過半は機械が占めている。中国から欧米を含む主要国・地域向け輸出も半分以上が機械である。ASEANも日本を始めとするアジア諸国・地域からの輸入の過半は機械となっている。なお、インドが現状では輸出入ともに機械のシェアが低い。
第Ⅱ-1-1-14図 アジアを中心とした貿易フロー(2019年)
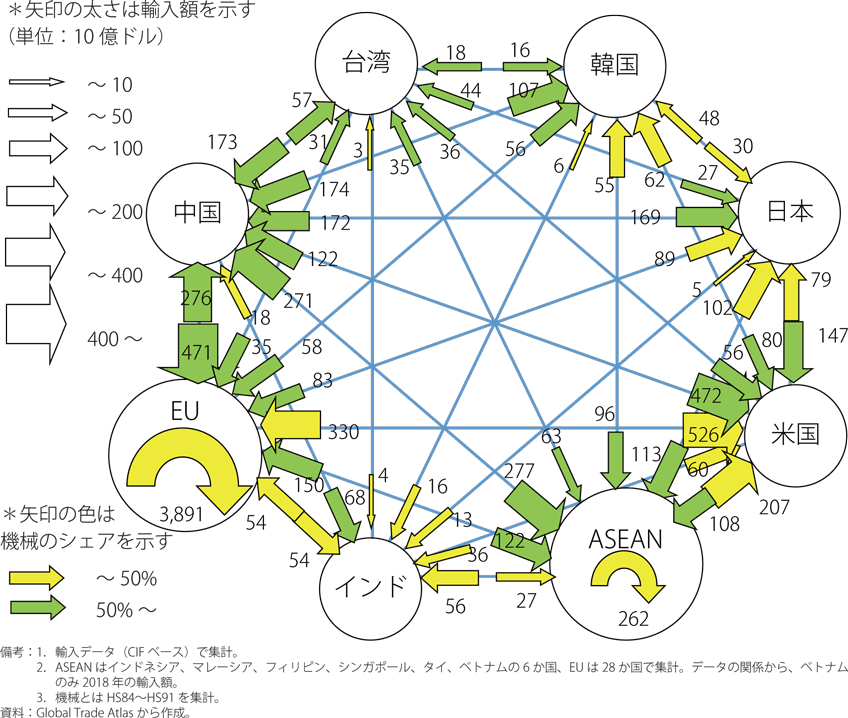
2.国際的生産分業の深化
(1)現地調達率の上昇
アジアに展開する日系製造現地法人の調達先を見ると、総調達額の約23%を日本、約65%を現地国内、残り約11%を第三国から調達している(第Ⅱ-1-1-15図)。なお、現地のうち約1/4に相当する17.5%は現地に進出した日系企業からの調達が占めている。調達先の時系列推移を見ると、世界金融危機以後は、日本からの調達額はほぼ一定額を維持する一方で、現地の日系企業を含めた現地調達額が拡大してきていることが分かる(第Ⅱ-1-1-16図)。その背景には、日系部品サプライヤーの現地進出が進んだこと、生産コストの削減を求め、積極的に地場企業の発掘・指導を行ったこと、技術のスピルオーバーから地場企業のレベルも上昇してきたこと等が指摘されている。その結果、基幹部品は日本の親会社から輸入するものの、相対的に低技術でも生産できる汎用品は現地で調達するとのすみ分けが進んだ。このため、日本からの調達は金額ベースでは維持されているものの、現地に進出した日系企業や地場企業からの現地調達比率が上昇している。
第Ⅱ-1-1-15図 アジアに立地する日系製造業現地法人の調達先(2018年度)
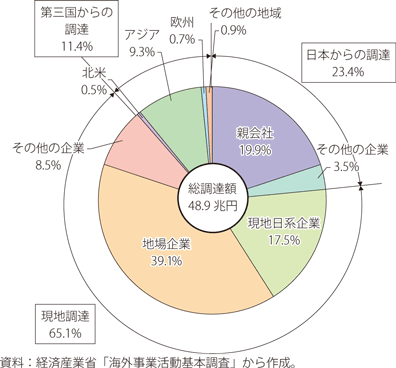
第Ⅱ-1-1-16図 アジアに立地する日系製造業現地法人の調達先の推移
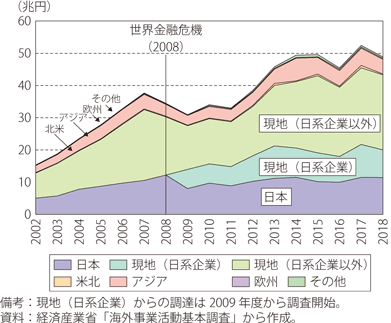
また、業種別の特徴も大きい。例えば、情報通信機械は日本からの調達シェアが大きい一方で、反対に輸送機械、その代表である自動車産業は最終的な組立工場の周囲に部品サプライヤーを配置する傾向が強く現地国内からの調達シェアが高い(第Ⅱ-1-1-17図)。このような違いが生じる背景には、部材の重量による輸送コストの相違、輸送機械のようにすりあわせ型であるか、情報通信機械のようにモジュール型であるかなど、製品の特性による影響が考えられる。現地調達でも現地に進出した日系企業から調達するものを含めれば、2018年度時点で情報通信機械は部材の約7割を日系企業から調達しており、日系企業内でのサプライチェーンの色彩が強い。これに対して、輸送機械、電気機械は部材の約4割を日本企業から調達している。
第Ⅱ-1-1-17図 アジアに立地する日系製造業現地法人の業種別の調達先の推移
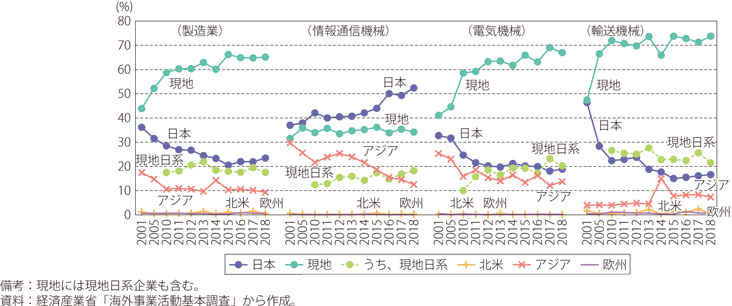
また、時系列の変化を見ると、情報通信機械は日本や現地日系企業からの調達シェアを高める一方で、輸送機械では日本や現地日系企業からのシェアを低下させ、反対に地場企業を中心とする現地調達シェアを上昇させている。
(2)企業の稼ぎ方の変化
このような調達の変化は企業の稼ぎ方にも影響を及ぼしている。日本からの資材調達が、高価格・高品質な基幹部品に限られているため、輸入(本社にとっての現地法人向け輸出)が伸び悩む一方で、現地法人から本社向けの配当金、ロイヤリティは増加基調にある(第Ⅱ-1-1-18図)。本社が基幹部品の輸出で稼ぐ形から、現地法人が稼ぎその配当を受け取るとともに、特許など知的財産の対価とも言えるロイヤリティ収入を得る形に変わってきている10。これは日本の経常収支が、輸出から、配当などの第一次所得収支、特許等使用料などのサービス収支に重心が移ってきていることとも符合する11。
第Ⅱ-1-1-18図 アジアに立地する日系製造業現地法人との取引関係
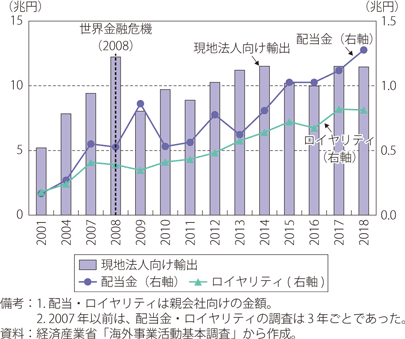
10 本社の立場からは、海外現地法人が連結決算の対象であれば、本社に配当を送付するまでもなく、自動的に本社の利益に計上される。むしろ、本社に配当金を送付するかどうかは、日本に投資機会、資金需要があるかどうか等にも影響される。
11 配当、ロイヤリティ収入が拡大している傾向は同じであるが、図表の海外事業活動基本調査は、回答が義務づけられていないことや日系現地法人以外からの特許料は対象になっていないことから、国際収支統計の数値よりは低い額となっている。
(3)双方向の貿易
このように国内と海外で生産する財のすみ分けが進んだ結果、相対的に低い技術水準でも生産できる汎用品、労働集約的な品目は、海外から輸入するため国内の生産能力は限られる可能性がある。
先に述べた垂直的な生産分業のモデルでは、日本から基幹部品(例えば、自動車のエンジン、パソコンや携帯電話の電子部品)を輸出して、海外で組み立てることを想定している。しかし、反対に日本で完成品の製造を行うケースもある。一般に生産設備の固定費用の観点からは1か所に生産を集約した方が効率的なことが多いことから、部材の中には既に海外に生産拠点の重心が移っているケースも考えられる。業種特性にもよるが、自動車のように部品点数も多く、日本で完成車を製造している場合は、海外からの部材調達が必要になる。しかも安全性等も考えて設計段階から原料や品質など細かな仕様を考慮して作り込んでいる場合は、たとえ基幹部品でないとしても容易に代替できるとは限らないという懸念がある。
例えば、日本の自動車部品の輸出入を見ると、2000年代、輸出入総額に対する輸入の比率は上昇している(第Ⅱ-1-1-19図)。日本からの輸出に対する中国やタイからの輸入の比率が上昇している。2020年の新型コロナウィルスの際は、自動車産業の集積地のひとつである武漢を始め、中国からの部材供給が途絶えた。当初、部材の途絶は中国だけであったが、米国、欧州を始め世界に広まった。
第Ⅱ-1-1-19図 日本の自動車部品の輸出入の推移
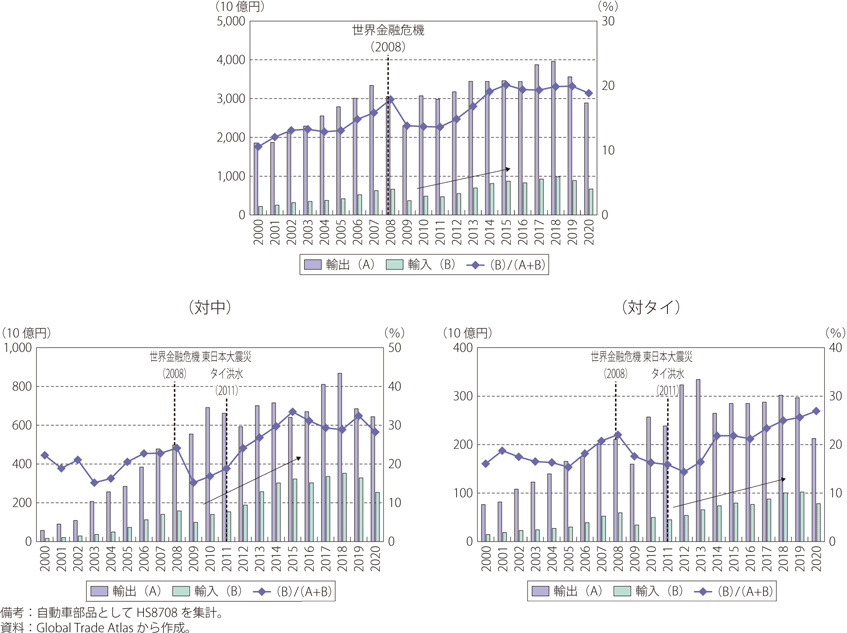
安定的なサプライチェーンのためには日本と海外双方向での部材輸入の拡大、その中には付加価値は低くても生産に不可欠な部材も含まれる点には注意が必要となる。
(4)中国への集中と分散
2020年、新型コロナでサプライチェーンが混乱した要因の一つに、中国からの輸入割合が大きかったことが指摘されている。中国のWTO加盟後、急速に日本を始めとする外資企業の進出が進み、中国は製造業において「世界の工場」と言われるほどになった。その結果、日本の輸入に占める中国からの輸入のシェアは高くなった(第Ⅱ-1-1-20図)。品目別には、低賃金を生かした衣類などの労働集約的な消費財だけでなく、中国現地に部品サプライヤーなどの裾野産業の集積が形成され、機械部品など中間財の輸入も増えた。
第Ⅱ-1-1-20図 日本の輸入に占める中国のシェアの推移
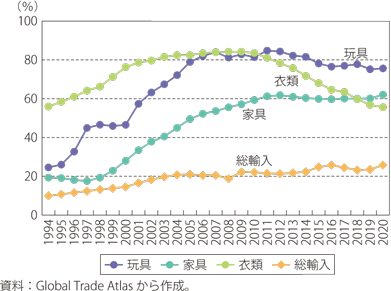
一方、近年では中国の経済発展は賃金水準等のコスト上昇ももたらした。中国への集中はリスクを伴うとの懸念から、「China+1」と言われるようなリスク分散の考え方とあいまって、中国からの分散の動きも見られるようになった。例えば、第Ⅱ-1-1-20図を見ると、賃金水準に敏感な労働集約的産業である衣類や玩具は既にピークアウトしているし、家具も頭打ちとなっている。また、幾つかの主要な機械部品を見ると、中国からの輸入シェアが頭打ち又は横ばいとなり、代わりにタイ、ベトナム、インドネシア等のシェアが増加している様子も見られる(第Ⅱ-1-1-21図)。なお、直近の2020年については、いち早く新型コロナの抑制に成功した中国からの輸入シェアが一時的に上昇しており、この傾向が今後も続くかどうかは注意を要する。
第Ⅱ-1-1-21図 日本の部品輸入における主要相手国・地域
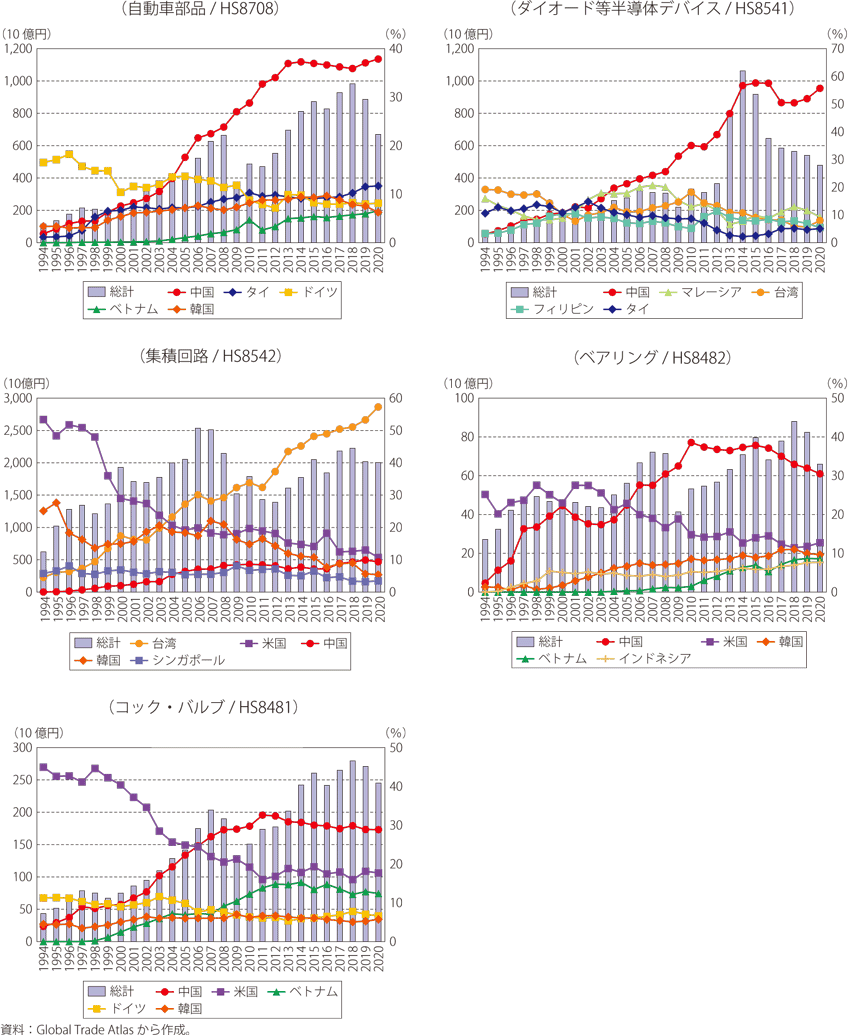
ただし、「China+1」というように、市場としても拡大しつつある中国の重要性を踏まえ、中国から撤退するのではなく、ASEANなど他の国にも進出するという考え方であった。中国の労働コストの上昇、為替レートの上昇から、まず繊維などの軽工業、次いで一部の機械製造業も移転が始まった。米中摩擦はこのような動きを加速した可能性もある。
また、中国に立地する日系現地法人の売上・調達における現地化の進行も見られる。2000年代、売上における現地販売のシェアは上昇し、特に世界金融危機後の4兆元の景気対策(2009年~2010年)の頃にピークに達する(第Ⅱ-1-1-22図)。景気対策終了後は一旦低下するが、その後もほぼ横ばいで推移している。調達においても現地調達のシェアが長期的に上昇している。
第Ⅱ-1-1-22図 中国に立地する日系現地法人の売上・調達先の推移

3.サプライチェーンに対するショック
2020年のコロナ・ショックにおいては、中国からの部材が輸入できなくなり、日本に立地する工場の操業が困難になる事態が起こった。今後、製造拠点の再配置、サプライチェーンの再編成が起こるのであろうか。過去における同様の出来事、サプライチェーンの分断の例として2011年のタイの大洪水を取り上げ、生産拠点の移転などが進んだのか検証してみる。
2011年、タイのチャオ・プラヤ川の洪水で、首都バンコクからタイ北部にかけての広大な範囲で長期間にわたり浸水被害が発生した12。タイには自動車を始めとする日系企業が進出しており、サプライチェーンが影響を受けた。その後のタイのポジションを直接投資、貿易の両面から見てみる。
まず、直接投資残高について洪水後に減少したかについては、既にみたように、製造業全体では金額ベースでは減少していない。世界に占めるタイのシェアは洪水のあった2011年は低下したものの、2012年以降は上昇に向かっている。それでは主要業種ごとに見てみる。タイの洪水前の投資残高のうち、金額的に大きいのは輸送機械、電気機械で、両産業で製造業全体の半分以上を占める13(第Ⅱ-1-1-23表)。
第Ⅱ-1-1-23表 日本のタイに対する直接投資残高(2010年末)
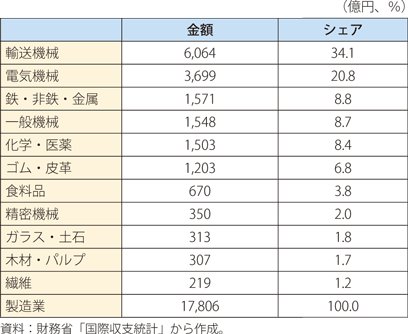
既に製造業については本節冒頭で見たように、タイは直接投資残高の減少はなく、世界に占めるシェアが低下したのも2011年又は直後の2012年だけで2013年から回復に向かっている(第Ⅱ-1-1-24表)。
第Ⅱ-1-1-24表 タイ洪水(2011年)前後の日本のタイに対する直接投資残高
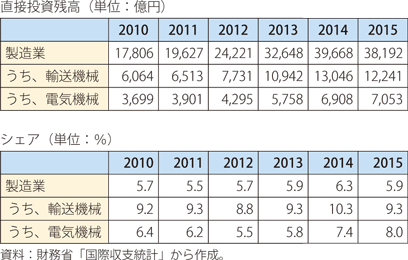
現地法人の立地数で見た場合、タイの輸送機械は洪水後も企業数は増加しており、シェアも緩やかな拡大が続いていることから、タイから日系の生産拠点が移転したとは言えない14(第Ⅱ-1-1-25図)。ただし、既に見たようにメキシコやインドネシアのように、シェアの急速な上昇があったわけでもなく、より一層の拡大・加速の機会を逃した可能性はあり得るかもしれない。
第Ⅱ-1-1-25図 タイに立地する日系現地法人の推移
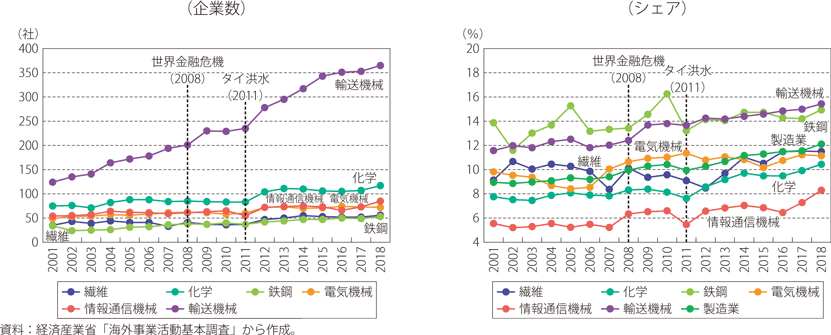
日本、タイ間の貿易を見ると、日本の輸出に占めるタイのシェアは緩やかに低下している(第Ⅱ-1-1-26図)。品目別に見ると、一般機械が洪水後に急増し、その後は低下したのは、浸水した機械設備の復興需要のためと思われるが、自動車のシェアまでも低下している。そこで、日本からの自動車エンジン、自動車部品の輸出額の推移を見ると、自動車エンジンは2013年をピークに減少に転じている(第Ⅱ-1-1-27図)。もし、自動車の生産が落ちたのでないとすれば、考えられることは、タイ国内で製造するようになったか、又は第三国から輸入するようになったなどである。タイの自動車エンジンの輸入を見ると、最近はインドからの輸入が増加して、日本からの輸入を上回っている(第Ⅱ-1-1-28図)。インドがアジアの生産分業に組み込まれてきている可能性がある。
第Ⅱ-1-1-26図 日本の輸出に占めるタイのシェア
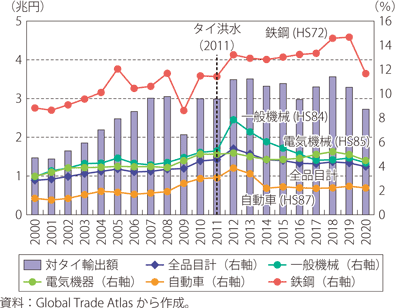
第Ⅱ-1-1-27図 日本の国別輸出(自動車エンジン・自動車部品)の推移
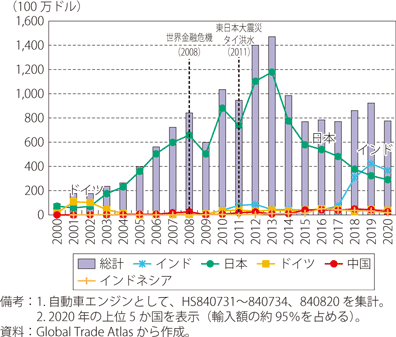
第Ⅱ-1-1-28図 タイの国別輸入(自動車エンジン)の推移
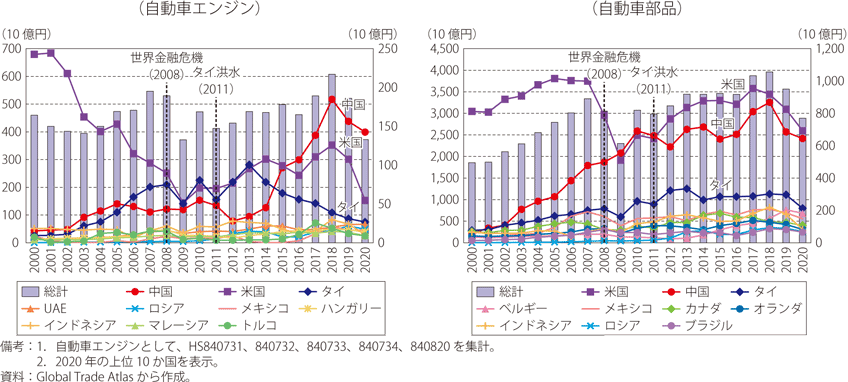
12 タイの雨期(5月~10月)に想定を越える大雨が降ったことにより、10月以降、日系企業も多数入居する7つの工業団地(全804社のうち、日系企業が449社)が浸水。水の滞留により排水までに時間がかかり、11月初旬から徐々に排水が開始され、全ての工業団地で排水が完了したのは12月中旬。詳細は2012年版通商白書第2章第3節参照。
13 国際収支統計(直接投資)と海外事業活動基本調査では業種分類に異なる部分がある。例えば、海外事業活動基本調査では、「情報通信機械」(電子計算機、電話機、電子部品等)と「電気機械」(発電機、冷蔵庫、照明機器等)は分かれているが、国際収支統計では両業種とも「電気機械」に含まれる。
14 同図で2012年度に企業数が急増したように見えるのは、調査実施に当たって補足率が上がったことが影響していると思われる。