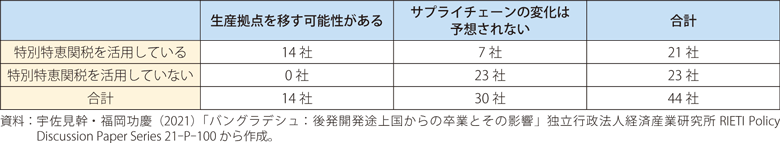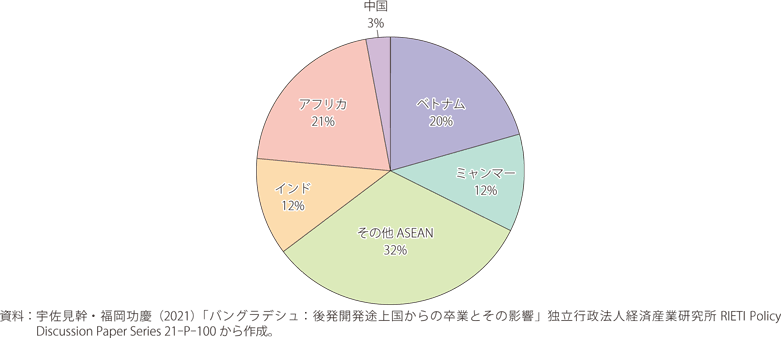第2節 サプライチェーンリスクと危機からの復旧
サプライチェーンとは、商品の企画・開発から、原材料や部品などの調達、生産、在庫管理、配送、販売、消費までのプロセス全体を指し、商品が最終消費者に届くまでの「供給の連鎖」である。サプライチェーンを構築する企業間の関係は「垂直的な関係」と「水平的な関係」の2種類に分類される。「垂直的な関係」とはサプライチェーンの上流から下流の関係を指す。例えば、部品を供給するサプライヤーと最終製品を扱う企業の関係などである。一方で、「水平的な関係」とは同業の企業間における関係のことを指す。例えば、製品や技術を共同開発したり、他社に生産を委託したりといった関係などである15。また、サプライチェーンは経済活動のグローバル化に伴い、国境を越えて構築され、複雑化している(第Ⅱ-1-2-1図)。
第Ⅱ-1-2-1図 グローバルなサプライチェーンと垂直的・水平的な関係の例
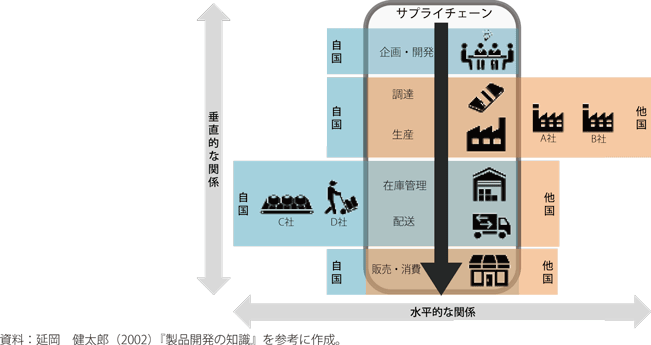
本節では前節の分析も踏まえつつ、サプライチェーンリスクへの対応に関してコロナショックとそれ以前を比較することにより変化がみられるかについて検討する。
15 延岡 健太郎(2002)
1.サプライチェーンとリスク
サプライチェーンが影響を受け得る代表的なリスクとしては自然災害やパンデミックに代表される環境的リスク、テロや政治的な不安などの地政学的リスク、経済危機や原料の価格変動といった経済的リスク、サイバー攻撃やシステム障害などの技術的リスクといった様々なリスクがある。これらのリスクは、発生の予測可能性や頻度、統制や管理のしやすさ、影響の大きさなどの観点から分類され、それぞれの企業が対応を検討することになる。
また、企業のそれぞれのリスクに対する重要度の認識は上記の要素やそのときの社会経済情勢に影響される。2011年に行われた調査16では同年に発生した東日本大震災やタイの洪水を背景に、自然災害や紛争・政治的不安定、需要ショックなどが重要度の大きいリスクとされていた(第Ⅱ-1-2-2図)。中でも調査に参加した専門家の内、6割が「自然災害はサプライチェーンや輸送における体系的な混乱を最も引き起こしやすい」と指摘した。一方で、2020年に行われた調査17ではエピデミック・パンデミック、関税や貿易制限の不確実性、重要な原材料や部品の不足などが「重大なリスク」・「中程度のリスク」と評価された割合が高い(第Ⅱ-1-2-3図)。新型コロナウイルスの感染拡大後に調査されたということもあり、感染症によるサプライチェーンへの影響が懸念されていたことが読み取れる。また、有価証券報告書における事業等のリスクに関する記載の中で「パンデミック」及び「BCP」を含む記載は2018年及び2018年度18には21件だったが、2019年及び2019年度19は138件と増加しており、このことからも企業のリスク認識の変化がうかがえる。
第Ⅱ-1-2-2図 サプライチェーンリスクの認識(2011年)
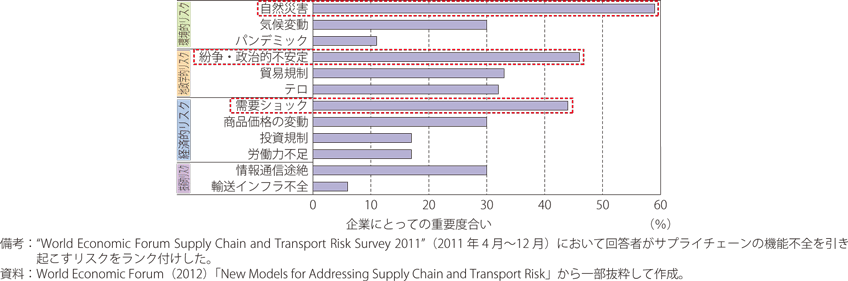
第Ⅱ-1-2-3図 サプライチェーンリスクの認識(2020年)
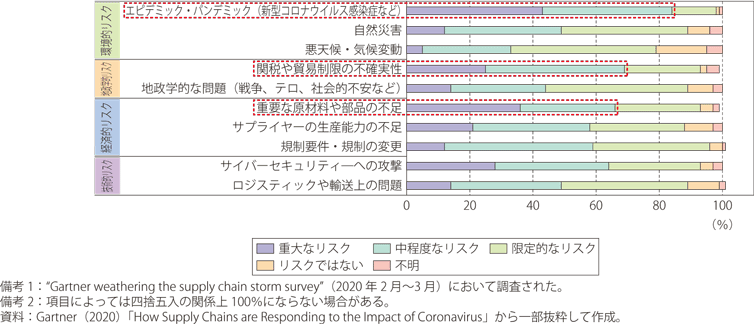
このようにリスクそのものの発生可能性に加え、リスクの重要度がどのように認識されるかも企業行動に影響を及ぼす。これまでも企業は多様なリスクを認識した上でサプライチェーンマネジメントへの取組を行ってきた。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、改めてレジリエントなサプライチェーンマネジメントの在り方を再考する必要性が高まっている。
16 World Economic Forum Supply Chain and Transport Risk Survey 2011
17 Gartner weathering the supply chain storm survey
18 2019年1月1日から6月30日に提出された有価証券報告書。
19 2020年1月1日から6月30日に提出された有価証券報告書。
2.リスクごとのサプライチェーンの動向
(1)自然災害を受けたサプライチェーンの動向
アジア地域における自然災害の発生件数は他の地域と比べると多く、日本においても自然災害によるサプライチェーンへの影響は大きい(第Ⅱ-1-2-4図)。2011年3月11日に発生した東日本大震災は、地震による被害だけでなく、太平洋沿岸部を襲った巨大な津波や原子力発電所の事故によって東北地方を中心に広い地域で甚大な被害が発生した。そのため、被災地域に生産拠点がある産業においてはサプライチェーンへの影響が報じられた。
第Ⅱ-1-2-4図 地域別の自然災害の発生件数
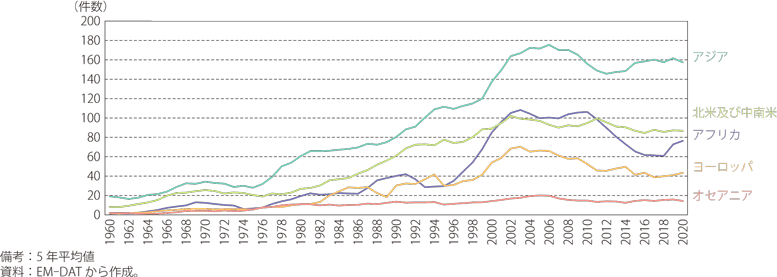
東日本大震災が発生した2011年の実質GDP成長率(前期比年率)は第1四半期が-4.2%、第2四半期が-3.4%とマイナス成長であった(第Ⅱ-1-2-5図)。また、実質輸出入額指数については、実質輸出が3月には93.7と2月が105.0だったことと比較すると減少しており、4月には87.3と大きく減少した(第Ⅱ-1-2-6図)。
第Ⅱ-1-2-5図 日本の実質GDP成長率
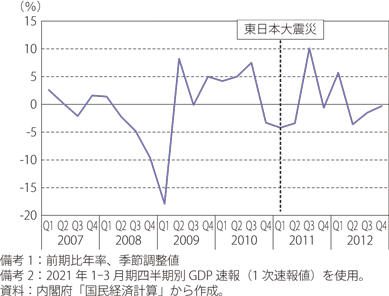
第Ⅱ-1-2-6図 日本の実質輸出入指数
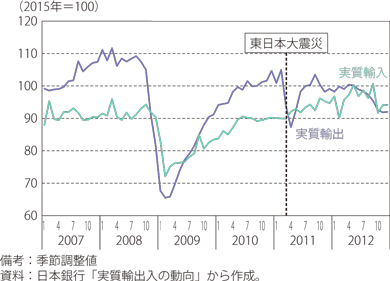
また、鉱工業生産指数を見ると2011年3月は87.3と前月から大きく低下した。地域別にみると震災の被害を受けた東北地方の3月の鉱工業生産指数は69.4であり他地域に比べて大きく低下したが、被災地域から離れている中部地域についても鉱工業生産指数の低下がみられ、被災地域から波及して日本全国に製造業の停滞が生じた可能性が考えられる。他方で、危機による低下幅の6割を回復するまでにかかった期間を比較すると世界金融危機時には7か月程度、東日本大震災時には3か月程度であり、需要ショックを伴わなかった東日本大震災の方が短期間で回復をしている20(第Ⅱ-1-2-7図)。
第Ⅱ-1-2-7図 地域別の鉱工業生産指数
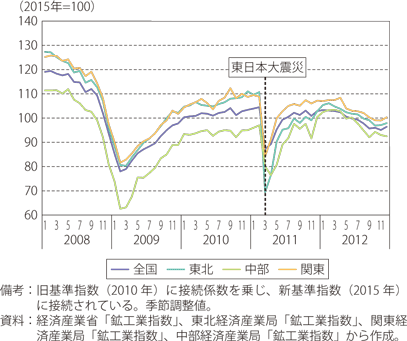
続いて、自然災害の影響を踏まえた企業やサプライチェーンの動向を整理する。
自然災害のうち震災等の災害は局所的に発生するが、サプライチェーンへの影響も被災地域からサプライチェーンを伝って波及をする。自動車の電子部品を扱うあるメーカーは東日本大震災によって自社の工場が被災し影響を受けたが、部品を供給できず1次サプライヤー、完成車メーカーへと連鎖的に影響があった21。
一方で、戸堂ら(2013)では経済産業研究所のアンケート調査22と企業情報ファイル23を基に、定量的に東日本大震災の影響を整理し、サプライチェーン・ネットワークは、生産設備などの被災による操業停止というマイナス面だけでなく、取引先が被災した企業への支援を行ったり、代替できる取引先を見つけることができたりとプラス面を有するとし、サプライチェーン・ネットワークの深化は操業再開や中長期的な売上げ回復に資すると結論付けている。平成28年熊本地震時においても自動車部品を扱うあるメーカーは工場が被災し供給先の国内生産が停止するなどの影響があった一方で、供給先が自社の関連企業の工場を提供するなどの支援をしたことにより、代替生産が可能になったとの事例がある24。このような事例はサプライチェーンの垂直的・水平的な関係の強化がサプライチェーンの強靱化に資することを示唆している。
加えて、例えば震災であれば、揺れといった災害自体は一時的であり、災害後は復旧にむけた集中的な対応をすることができるという点も特徴として挙げられる。2011年の通商白書25では経済産業省が行った「東日本大震災後の産業実態緊急調査26」から、2011年4月初旬時点で回答を寄せた被災をした製造企業の生産拠点の内、約6割強が既に復旧をしており、2011年7月中旬には残りの約3割弱も復旧の見込みとの結果を得ている。
サプライチェーンの国際的な再構築に向けた動きとしては、東日本大震災によるサプライチェーンへの影響はあったものの、その影響がサプライチェーンの国際的な再構築を推し進める要因にはなっておらず、むしろ円高などの他の要因を契機としているとの調査結果がある27。同様に、前節で示した通り、2011年に発生したタイの洪水の前後においても、タイにおける日系企業の立地状況に有意な変化はみられていない。
これらを踏まえると、自然災害によるサプライチェーンの被害が大きい場合であっても、そのサプライチェーンのつながりの深化による企業間の信頼関係の中で早期に復旧が可能であったとみられる。また、自然災害自体が一時的であることで、災害があった後からは復旧にむけた集中的な対応をすることができるため、大きなサプライチェーンの構造的な変化までは結びつかなかった可能性が推察される。
20 世界金融危機時は全国、東日本大震災時は東北の数値で計算をした。
21 佐伯(2013)
22 経済産業研究所「東日本大震災による企業の被災に関する調査」(2012年1~2月)
23 東京商工リサーチ「TSR企業情報ファイル」及び「TSR企業相関ファイル」
24 西岡(2018)
25 経済産業省(2011)
26 東日本大震災後の産業実態(被災地における生産拠点の復旧状況及び見通し、震災を原因とする製品・部材等の供給制約による生産の停滞や自粛ムードの広がりによる消費への影響等)について把握すべく実施された調査。調査期間は2011年4月8日~4月15日、対象企業は80社(製造業55社、小売・サービス業25社)。
27 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(2012)
(2)新型コロナウイルス感染拡大以降のサプライチェーンの動向
新型コロナウイルス感染症は2019年末頃に中国で最初の症例が確認されて以降、世界中で連鎖的に感染が拡大した。新型コロナウイルス感染症が人を介して感染拡大することから、対面でのコミュニケーションの自粛や渡航制限、外出制限等といった強力な措置が講じられた。人や物の交流が制限された結果、サプライチェーンにおける商品調達等の遅延や途絶が起こり世界経済は急速に減速した。また、日々の生活でマスクが必需品となったほか、企業においても新型コロナウイルスの感染拡大後に在宅勤務やテレワーク、バーチャル展示会などの活用の推進に取り組む事例が多くなった28。
新型コロナウイルスの感染拡大は震災などと同様に自然災害に分類されるが、コロナショックの影響を踏まえた企業やサプライチェーンの動向は異なる様相を見せている。そこでコロナショックの特徴を踏まえつつ企業やサプライチェーンへの影響の特徴を整理する。
第一に、コロナショックにおいては人を介して感染拡大することを抑制するため渡航制限や外出制限等といった強力な措置が伴うことで、生産活動や物流の停滞が生じたという点が特徴として挙げられる。
2020年2、3月頃には、港湾に関わる従業員や物流を担うトラック運転手などの不足が国際的な物流に遅延などをもたらした29。サプライチェーンにおいて人的資源の担う機能に障害が起きることで生産活動・物流に影響を与えることになった。また、需要面においても感染拡大の抑制のための外出制限や自粛、渡航制限の導入などに伴い、人同士が接点を持つ対面サービスでは需要が大きく縮小したほか、耐久財の需要が急減した。一方で、医療物資への急激な需要増や巣ごもり消費の拡大といった需要変動も生じた。このような需要変動も、需要・供給、両面の相互の関わり合いの中で供給面へ影響を及ぼし、サプライチェーンの機能障害をもたらした(第Ⅱ-1-2-8図)。
第Ⅱ-1-2-8図 コロナショックがサプライチェーンに与えた影響(製造業)
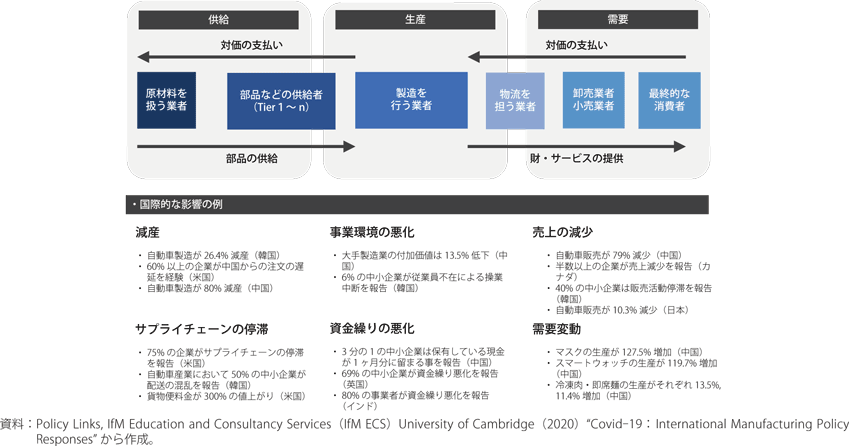
第二に、世界中で連鎖的に感染が拡大したことによりグローバルに経済的な影響が生じる点もコロナショックの特徴として挙げられる。国内企業や海外展開する企業などが直接的に、またグローバルに広がるサプライチェーンを伝って間接的に影響を受け得る。そのため、グローバルに展開される調達・販売網や生産拠点に対する見直しを行う企業もあった。
まず、景況感については日本貿易振興機構(JETRO)の調査30を参照すると2020年の営業利益については、赤字と見通す企業が3割を超え、世界金融危機直後の2009年を上回っていることに加えて、業種・地域間における景況感の違いを指摘している。まず、業種別については、同じく2020年の営業利益について渡航制限や外出制限の影響が大きい「ホテル・旅行」は約9割が、「飲食」は約7割が赤字と見込んでいる。また、地域別についても2020年の営業利益について感染拡大の規模が大きかったインドでは5割が赤字を見込み、一方で他地域と比較して早期に感染拡大に歯止めをかけた中国や韓国では6~7割程度が黒字を見込んでいる。
この調査により、業種ごとに、また進出する地域の新型コロナウイルスの感染拡大状況によって異なる景況感が読み取れる。
続いて、サプライチェーンに対する見直しについて株式会社日本政策投資銀行(DBJ)が行った調査31では「海外の仕入れ調達先の一層の分散・多様化」や「他企業等との共助体制の強化」を挙げる企業が多い(第Ⅱ-1-2-9図)。また、株式会社国際協力銀行(JBIC)の調査32では、多くの企業が新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、何らかのサプライチェーンへの対応策を検討しているとの結果を得ており、特に、「運転資金の確保・積み増し」や「同一製品の複数の生産拠点確保」などを挙げる企業が多く、回答数(複数回答)823件33の内、それぞれ100社超が対策として検討している(第Ⅱ-1-2-10図)。
第Ⅱ-1-2-9図 サプライチェーンの見直し(見直し検討を含む)の内容
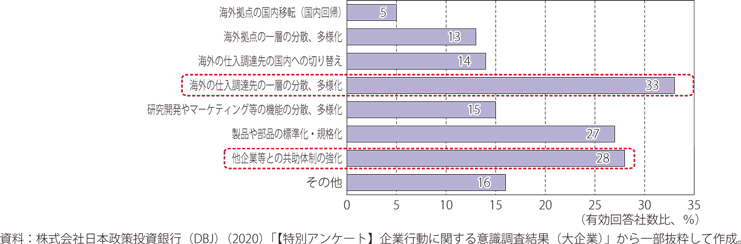
第Ⅱ-1-2-10図 サプライチェーンに関する対応策
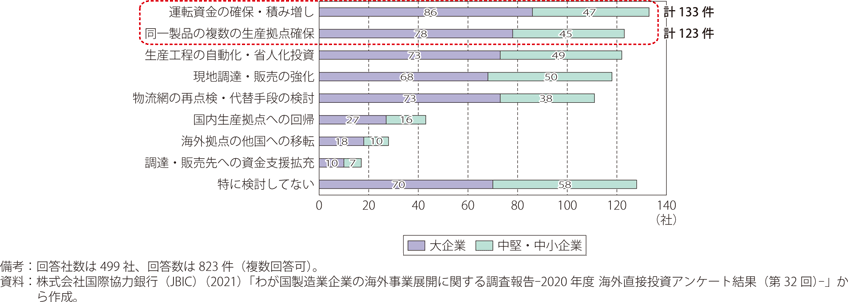
これらの調査によりコロナショックを踏まえ、事業体制の強化のほか、生産拠点や調達先の多元化や他企業等との共助体制の強化を検討する企業が多かった。サプライチェーンの垂直的・水平的な関係の強化を通じたサプライチェーンの強靱化策がますます選択されていることがうかがえる。
他方で、第Ⅱ-1-2-9図、第Ⅱ-1-2-10図に示されるとおり、両調査とも企業が国内生産拠点への回帰や海外拠点の変更といった生産拠点の再編を対応策として回答した数は他の対応策と比較して多くない。背景にはそれぞれのアンケートのタイミングが、DBJは2020年6月、JBICは2020年8~9月であることから、まずは原状の回復を目指すことに注力せざるを得なかったということが考えられる。また、企業からは生産拠点の再編といったコスト面のみならず、様々な要素を勘案して行われる必要がある対応策については先行きの不透明感から慎重な意見があった。
ただし、JBICの調査によると新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、貿易制限的措置などの政治的なリスク回避や通関コストの軽減のため、販売拠点に合わせ、それぞれの生産拠点を設けるといった地産地消型の事業戦略の有効性が指摘されている。また、みずほ情報総研株式会社34が行った調査ではコロナショックを契機に海外生産拠点の切替えを実施した企業は13.3%と1割強程度だが、その対策を「非常に効果的だった」「おおむね効果的だった」と回答した割合は合わせて7割を超えている(第Ⅱ-1-2-11図)。これらの調査結果から、一概に生産拠点の再編について必要性がないとはいえないことに留意する必要がある。
第Ⅱ-1-2-11図 コロナショックを契機に実施した対応策とその評価
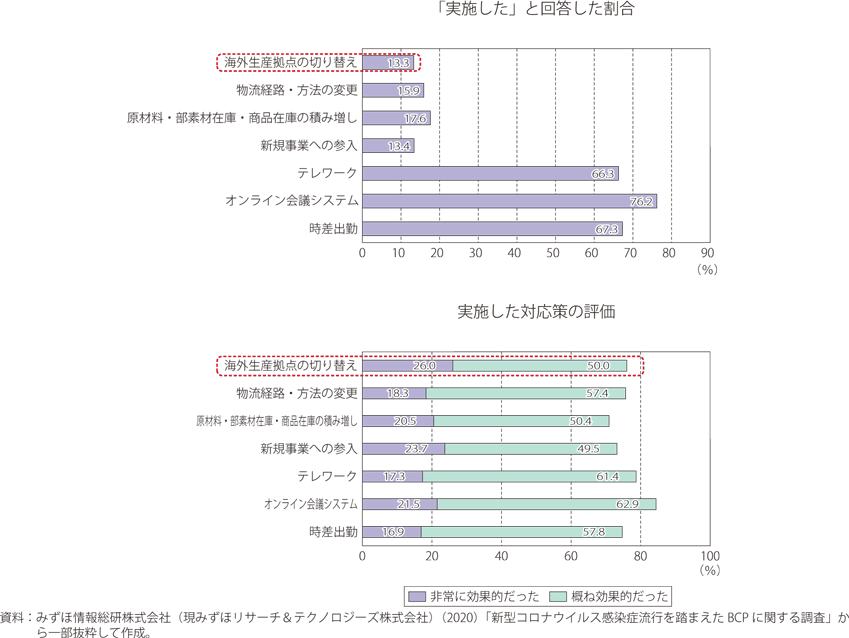
第三に、世界のいずれかの国・地域で新型コロナウイルスの感染が拡大した場合、その影響が当面の間継続するという点もコロナショックの特徴として挙げられる。中長期的な対策が必要になるところ、企業からは次なる危機に備えたBCP(事業継続計画)を見直すとの意見もある。
みずほ情報総研株式会社が行った同調査ではコロナショックに対してBCPが「効果的に機能した」との回答は16.7%にとどまり、「余り機能しなかった」・「全く機能しなかった」との回答は合わせて27.6%であったとの結果を得ている(第Ⅱ-1-2-12図)。機能しなかった理由としては全世界的に長期的な影響が出ることを前提としておらず、策定していたBCPの想定リスクとは異なっていたとの意見が多かった。本調査においてはBCPが包括的なリスクに対して柔軟に、有効に機能するためには「事象特定型」から「オールハザード型」への転換が必要ではないかと推察している。前述のとおり、リスクは世界の潮流とともに変化、また多様化し得る中で、企業が認識するべきリスクも広域化・高度化する必要性があるだろう。
第Ⅱ-1-2-12図 コロナショックに対するBCPの効果
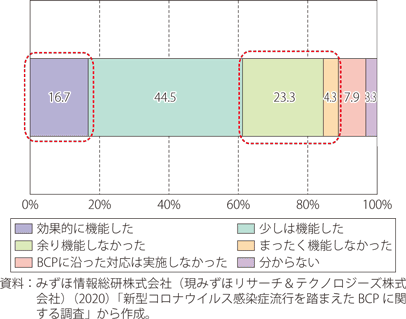
28 JETRO(2020)「2020年度海外進出日系企業実態調査」
29 ロイター通信ニュース(2020年2月21日)「新型ウイルスで物流混乱、海運・港湾業界の業績・コストに影響」。
30 「2020年度海外進出日系企業実態調査」調査時期は国・地域ごとに異なるが、2020年9月頃。調査対象は海外86か国・地域に進出する日系企業。その内9,182社より回答を得ている。
31 「【特別アンケート】企業行動に関する意識調査結果(大企業)」調査期間は2020年6月22日を期日として実施。調査対象は2019年度~2021年度設備投資計画調査の対象企業(資本金10億円以上の大企業)。その内1,212社より回答を得ている。
32 「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告-2020年度 海外直接投資アンケート結果(第32回)-」調査時期は2020年8月末から9月末まで。調査対象は原則として海外現地法人を3社以上(うち、生産拠点1社以上を含む)有する日本企業。その内530社より回答を得ている。
33 回答社数は499社、回答数は823件(複数回答可)。
34 現在の社名はみずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社。「新型コロナウイルス感染症流行を踏まえたBCPに関する調査」調査時期は2020年7月。調査対象は日本全国の従業員51名以上の企業に勤める経営者・役員及び会社員のうち、課長・次長クラス以上の人でかつ事業戦略や経営戦略、BCPの策定に関与する(又は意見できる立場にある)人を対象に調査を行い、事業戦略・経営戦略に関与している(又は意見できる)人361名、BCPの策定に関与している(又は意見できる)人361名の計722名より回答を得ている。
3.これからのリスクとサプライチェーンマネジメント
コロナショックによるサプライチェーンへの影響としては、まず感染拡大防止のために渡航制限や外出制限等といった強力な措置が講じられることでサプライチェーンにおいて人的資源が担う部分に障害が生じ、更にコロナショックに伴い生じた需要変動もまた供給面に影響をもたらした点が特徴である。また、世界中で連鎖的に感染拡大したことにより、グローバルに展開されるサプライチェーンを介して経済的な影響が起こりうる状態が長期的に継続することが明らかとなった。これにより中長期的なサプライチェーンの見直しが求められているといえる。
新型コロナウイルスの感染拡大によるサプライチェーンへの影響を事前に想定することが難しかったことと同様、今後想定していなかった問題がサプライチェーンに障害をもたらすリスクになり得ることが考えられ、今まで以上にリスクに対する認識の広域化・高度化を進める必要性が認識されつつある。また、これまでグローバルに形成されてきたサプライチェーンに存在するチョークポイントをデジタル技術の活用を通して可視化・モニタリングすることが必要不可欠になるだろう。
これまでも企業は多様なリスクの中でサプライチェーンに対する取組を行ってきた。しかし、コロナショックを契機にサプライチェーンマネジメントに更なる変化が求められているといえる。