第3節 サプライチェーン管理における考慮事項の多角化
前節で述べたように、自然災害等を念頭においた拠点分散や複数調達先の確保は引き続き重要である。それに加え、環境や人権といった共通価値への貢献への期待が高まる一方、国家による経済安全保障の観点からの規制の継続が見込まれる国際情勢の中で、サプライチェーン・マネジメントに求められる要素はより複雑化・高度化している。本節においては、サプライチェーンに求められる価値の広がりとも言える様々な要請を概観し、企業への影響について検討する。
1.サプライチェーンにおける脱炭素化への取組
2020年以降の気候変動問題に関する新たな国際的な枠組として、2015年の第21回気候変動枠組条約締約国会議(COP21)においてパリ協定が採択された。パリ協定では、世界共通の長期目標として産業革命前からの平均気温の上昇を摂氏2度より十分下方に保持すること、摂氏1.5度に抑える努力を追求することが掲げられている。そのために、全ての国が自ら設定した目標の達成に向けて温暖化対策を行っていくこととされている36。
パリ協定が本格実施の段階に入る中、120を超える国家がカーボンニュートラルを表明し37、数にして1500を超え、合計12.5兆ドルの売上高規模となる企業がネットゼロの目標を定めている38。2015年1月に発効した、企業向けの温室効果ガス排出量の算定・報告のための民間スタンダードであるGHGプロトコルは、企業活動による温室効果ガス排出として計測する範囲に、事業者自らの排出だけでなく、原材料調達・製造・物流・販売・廃棄などの一連の事業活動の流れから発生する温室効果ガス排出量を含めている。このうち、調達や流通段階、製品の使用・廃棄等の間接排出による排出量はスコープ3と定義されている(第Ⅱ-1-3-1図)。そして、最終製品におけるスコープ3の排出量は、スコープ1とスコープ2を合わせた排出量の3倍以上を占めるとの指摘もあり39、スコープ3の取組の重要性が指摘されている。
第Ⅱ-1-3-1図 温室効果ガス排出量の算定範囲
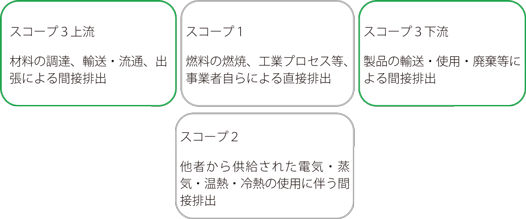
企業によるネットゼロ目標の表明は、温室効果ガスの削減というグローバルな目標に対して、企業が自主的に目標設定をするかたちで行われており、企業の事業形態により取組方法が異なりうる。自社の工場の電源構成を変えることや製造方法の変更など(スコープ1および2の範囲)、自社の努力により一定の削減が見込みうる事業形態なのか、自社で製造せず委託先が製造している場合など、削減効果を上げるためには調達先等への働きかけが必要な事業形態かによって(スコープ3の範囲)、適切な方法をそれぞれの企業が判断をすることとなる。こういった事業形態の違いや実現のための難易度を反映して、コミットメントの範囲にはばらつきがあり、スコープ3を含む目標設定をしている企業は、目標設定をしている企業全体の22%となっている(第Ⅱ-1-3-2図)40。
第Ⅱ-1-3-2図 ネットゼロコミットメントの範囲
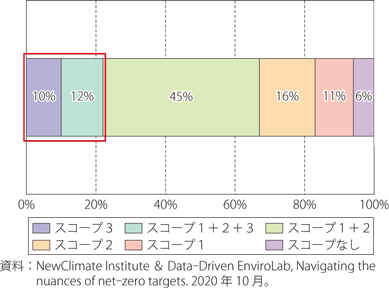
ネットゼロに向けた具体的な取組として、幅広い業種でとられている方法の一つに、自社で使用する電力について再生可能エネルギーの利用率を高めていく方法がある41。加えて、調達先企業に対しても再生可能エネルギーの利用を勧めるといったエンゲージメントが広がりつつある42。こういった企業の取組及びそれについての情報開示は、透明性や信頼性確保の観点等から、国際的なイニシアティブに参加するかたちで行われることが多い。その一つであるSBT(Science Based Targets Initiative)43への加盟企業数は年々増加し、2021年3月末時点で1400社近くに上る44。日本企業については2021年3月末で128社、売上高規模は約175兆円であり、上場企業合計の23%に相当する(第Ⅱ-1-3-3図)。これまでも日本企業においては、グリーン調達ガイドライン、CSR調達ガイドラインを策定し、サプライヤーに対して一定の環境配慮を求める取組は行われていた。今後は、より具体的な取組を求めるかたちでサプライヤーエンゲージメントを行う企業が増加し、より幅広い企業がその対象となると予想される。
第Ⅱ-1-3-3図 SBT参加企業の売上高(上場企業合計対比)
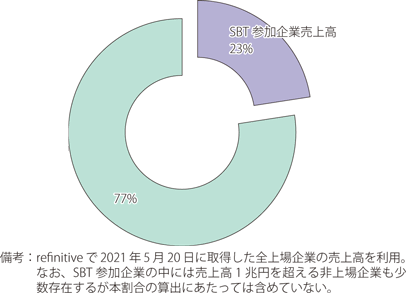
36 パリ協定2条、3条。
38 NewClimate Institute & Data-Driven Envirolab, (2020) Navigating the nuances of net-zero targets, p19
39 World Economic Forum, Net-Zero Challenge:The supply chain opportunity, p9 January 2021.
40 NewClimate Institute & Data-Driven Envirolab, p45, Figure11. なお、同レポートp12, Table2においては、ネットゼロやカーボンニュートラリティといった用語の定義や利用例についての整理がされている。
41 RE100の取組。企業の具体的な取組については、ものづくり白書2021においても紹介されている。
42 CDP(2019/2020), CDP Supply Chain:Changing the Chain, p5.
43 CDP、国連グローバルコンパクト、WRI(世界資源研究所)、WWF(世界自然保護基金)が共同で運営している。
44 SBT![]() のホームページからダウンロード可能なデータを元に、2021年3月31日時点のTarget set及びcommittedの企業数を経済産業省にて集計。
のホームページからダウンロード可能なデータを元に、2021年3月31日時点のTarget set及びcommittedの企業数を経済産業省にて集計。
2.サプライチェーン上の人権侵害に対する問題意識の高まり
(1)人権デュー・ディリジェンス等の法制化の動き
企業のサプライチェーンにおける強制労働、児童労働などの人権侵害については従前より問題提起されており45、国連人権理事会においても2011年に「ビジネスと人権に関する指導原則」が支持された。同原則は、企業が人権を尊重する責任として、自らの活動を通じて人権に負の影響を引き起こしたり、助長することを回避すること、及びそのような影響が生じた場合には対処することを求めている。さらに、その影響を助長していない場合であっても、取引関係によって企業の事業、製品またはサービスと直接的につながっている人権への負の影響を防止または軽減するように努めることを求めている。このように、企業の責任についての国際的な議論が深まるのと並行して欧州諸国を中心に国内法で企業に一定の義務を課す動きが加速している(第Ⅱ-1-3-4表)。
第Ⅱ-1-3-4表 サプライチェーン上の人権について規定する外国の法的枠組
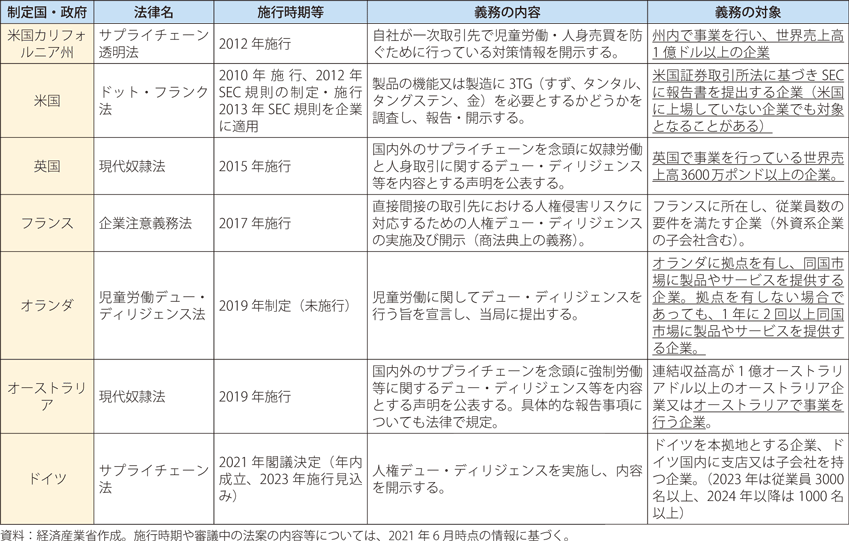
早期の立法例はいずれも米国である。米国カリフォルニア州サプライチェーン透明法(2012年施行)は州法であるが、人身売買や児童労働を防ぐために行っている対策を開示する努力義務を定める。連邦法であるドットフランク法1502条(2013年SEC規則を企業に適用)は、事業者に対し、製品の機能又は製造に3TG(すず、タンタル、タングステン、金)を必要とするかどうかを調査し、報告・開示する義務を課する46。その後、2015年に英国で現代奴隷法が成立・同年施行されたのを皮切りにこの動きは他の欧州諸国にも広がり、2017年にはフランスで企業注意義務法が施行され、オランダでは2019年に児童労働デュー・ディリジェンス法が成立している。ドイツでは、2021年6月11日、サプライチェーン法が連邦議会を通過した。欧米諸国にとどまらず、英国の法制も参考に2019年にはオーストラリアで現代奴隷法が施行されている。
もっとも、各国の法制の規定内容はそれぞれ異なる。ドットフランク法が3TGのサプライチェーンに限定されている一方、英国、フランス、オランダ及びオーストラリアの法律やドイツの法案では分野の限定はなく、自社のサプライチェーンにおける強制労働や児童労働といった人権侵害全般である。義務の対象となる企業も規定の仕方は異なるが、自国で設立された企業のみならず、一定規模以上であれば、(設立地を問わず)自国で事業の一部を行う企業(英国現代奴隷法、豪州現代奴隷法等)と幅広く規定されていることも多い。
サプライチェーンの人権について、幅広い適用範囲を定める法律が成立又は施行されている国への日本の直接投資残高は、対世界投資のシェアの半分を超えており、当該国で事業を行う日本企業もそれぞれの国の法律上の義務を負い、対応している(第Ⅱ-1-3-5図)。
第Ⅱ-1-3-5図 サプライチェーンの人権について定める国に対する日本の直接投資残高割合(2019年)
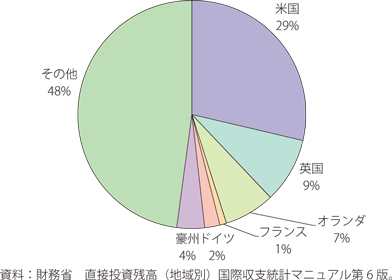
以上に述べたように、各国の法制の具体的な義務の内容には違いがあるものの、共通して取り組まれていることは以下のとおりである。まず、①自社の事業活動における人権侵害リスクの洗い出しを行うとともに、②サプライチェーン上の人権侵害については、少なくとも一次サプライヤーについて、監査を行うなどして人権侵害の防止に努めるといった対応である47。
人権デュー・ディリジェンスに関して複数の国で立法化が進んでいる欧州では、さらに取組の開示義務を強化する検討が進みつつある。英国においては、奴隷労働と人身取引に関する声明で明記すべき事項の一部を強制開示にする方向で検討することが表明されている48。また、EUレベルでも、サステナブルファイナンス行動計画10「持続可能な投資を促進するコーポレートガバナンスを推進し、資本市場における短期主義を緩和する」という目的のもと、自社のバリューチェーンにおける49気候変動、環境、人権リスクを認識、予防するデュー・ディリジェンスを義務づける提案が検討されている。さらに、企業の財務報告とは別に義務づけられる非財務情報の開示制度においても、人権や腐敗防止、環境等に関する取組を開示方法や内容をより具体的に規定する方向で検討が行われている50。
45 2005年のOSCEハイレベルカンファレンスでのILOプレゼンテーション![]() 。
。
46 SEC, FACT SHEET![]() , Disclosing the Use of Conflict Minerals,
, Disclosing the Use of Conflict Minerals,
47 企業活力研究所、『新時代の「ビジネスと人権」のあり方に関する調査研究報告書』(平成31年3月)。
48 英国政府ホームページ![]() 。2020年9月22日公表。
。2020年9月22日公表。
49 欧州議会のプレスリリース![]() においては、バリューチェーンの具体的な内容として、全ての業務、直接間接の事業関係、インベストメントチェーンが挙げられている。
においては、バリューチェーンの具体的な内容として、全ての業務、直接間接の事業関係、インベストメントチェーンが挙げられている。
50 Non-Financial Reporting Directive(NFRD)の改正。腐敗とは、典型的には汚職などを指す。
(2)人権侵害を理由とした輸出入規制等措置
先に述べた人権デュー・ディリジェンスやその開示については、段階的な義務強化のアプローチといえるが、より具体的かつ深刻な人権侵害が認定された場合には、政府により、その侵害に荷担する企業及び個人への制裁や取引停止なども実施されることがある。自社が直接取引を行っていなくても、サプライチェーン上のつながりがある場合には「荷担する」と見なされる可能性があることに注意が必要である。
近年の事例として、米国は、2019年から2020年にかけて、新疆ウイグル自治区における人権侵害への関与を理由として、中国政府機関及び中国監視機器製造大手のハイクビジョン社等の主体を米国輸出管理規則(EAR)51のエンティティリスト(Entity List、規制詳細については次項)に掲載した。この措置により、これらの主体が購入者、中間荷受人、最終荷受人、エンドユーザーのいずれかとして関与する場合に、米国からの輸出及び第三国からの再輸出等について商務省の許可申請が必要になっている。また、2020年3月に米国の「中国問題に関する連邦議会・行政府委員会(CECC:Congressional-Executive Commission on China)」が、企業に対し新疆ウイグル自治区から製品を調達していないことの確認を義務付ける「ウイグル強制労働防止法案」を公表(下院可決)した。その他、米国の関税法307条に基づき2020年9月からは新疆ウイグル自治区からの輸入の一部留保措置、2021年1月からは新疆ウイグル自治区で生産された綿製品とトマト加工品の輸入の全面的留保措置が実施されている52。
EUでも、人権保護を目的とする輸出管理について、2020年11月、欧州委員会、欧州理事会及び欧州議会の三者協議を経て、サイバー監視システムのエンドユース規制の追加を含む暫定合意に達し、2021年5月にEU理事会で採択された。
なお、輸出入規制措置ではないが、EUは深刻な人権侵害に関与した個人や団体を対象に入域禁止、資産凍結などの措置を講じるEU規則を2020年12月に採択した。2021年3月には、米国・EU・英国・カナダは協調して制裁を発動し、人権侵害に関与した中国当局者及び団体に対する資産凍結・資金提供禁止(個人・組織)及び入域禁止(個人)が措置されていることも併せて留意する必要がある。
51 米国輸出管理法(ECRA)に基づく下位規則。
52 米国国土安全保障省 税関・国境取締局ウェブサイト。https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor![]() https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor/withhold-release-orders-and-findings
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor/withhold-release-orders-and-findings![]()
3.安全保障上の観点等からの取引制限
近年、米中両国による技術覇権争いが激化する中で、安全保障上の観点等から、両国を中心に特定の地域や企業との取引を制限する動きが拡大している。
米国のトランプ前政権下で講じられた、中国の軍民融合戦略への関与が疑われる中国企業等に対する輸出管理強化等の措置は、その多くがバイデン政権への交代後も継続されている。以下、代表的な措置を三つ紹介する。
第一に、中国半導体大手のファーウェイ社やSMIC等が、EARのエンティティリストに追加された。第二に、外国直接製品規則(FDPR:Foreign Direct Product Rule)が強化され、ファーウェイ社及びその関連企業向けの再輸出規制が強化された。米国は、半導体製造に不可欠な回路自動設計ツールや一部の半導体製造装置において独占的シェアを有しており、また、本規則は輸出する半導体チップなどの米国原産比率には無関係に適用されて輸出許可申請が必要になるため、サプライチェーン上にファーウェイ社などを持つ半導体関連企業への影響が大きい。
第三に、米国国防権限法(NDAA)2019に基づき、ファーウェイ社・ZTE社等の中国企業5社の通信・監視機器・サービス及びそれらを使用する主体からの連邦政府調達禁止が規定された。2020年8月には、当該5社及びその子会社並びに関連会社の通信、監視機器及びサービスを使用している(米国政府機関の調達事業以外に限定して使用している場合を含む)企業の製品及びサービスも調達禁止となった。
中国においても、2020年12月に「国の安全と利益」を法目的とする輸出管理法が施行された。施行翌日には、輸出管理法及び暗号法に基づく輸出入管理品目リストが公表(2021年1月1日施行)され、暗号通信に係る機器等の輸出入が許可申請の対象となった。同法には、GATT第11条が禁じる輸出制限に該当しうる条文(規制対象品目の過度な拡張や技術開示要求に繋がりうる規定、他国の差別的な輸出規制措置に対する報復措置が可能となりうる規定)や、再輸出規制やみなし輸出規制に係る条文が存在している。依然として制度の全容や規制対象となる取引範囲が明らかでなく、具体的な運用態様によっては対中貿易・投資環境に大きな影響を与えるおそれがある。
また、2021年1月、国家安全法などに基づき外商投資安全審査弁法を施行した。国防・軍事工業やその周辺企業、エネルギー、資源、重要インフラ、重要な運輸サービス、基幹産業、重大な製品製造など国家安全に係る重要領域に投資し、かつ、投資先企業の実質支配権を取得する場合は、国家発展改革委員会に事前申請が必要となった。従来の投資管理制度との相違点としては、グリーンフィールド投資が新たに管理対象となったほか、事前申告が明確に義務化された点が挙げられる。
さらに、同月、国家安全法などに基づき、他国法令の域外適用に対応するための商務部規則を公表、即日施行した。他国の法令や措置について商務部が不当と判断すれば他国法令・措置の遵守を禁止し、対抗措置を講じることが可能となった。これを無視して中国の法人などに損害を与えた場合、当事者には損害賠償を請求でき(当事者の定義は不明)、また、中国法人などが商務部の禁止を遵守したことで損害を被った場合、政府が支援を行える旨を規定している。対象となる外国法令の範囲等は不明ながら、第三国法令の域外適用に従った外国企業が損害賠償請求を受ける可能性がある。
上記で紹介した措置は、突然導入されることや規制の詳細が不明瞭である場合があるため、ビジネスの予見可能性が低下し、企業の事業環境悪化に繋がる可能性がある。企業各社においては、今後の国際環境の変化を経営に直結するリスクと認識した上で、自社のサプライチェーン上のリスクを精緻に把握し、必要に応じて規制当局への許可申請を行う等、海外市場におけるビジネスが阻害されることのないよう万全の備えを講じる必要が生じている。
4.レジリエントなサプライチェーン構築に向けて
(1)一次サプライヤーに止まらないサプライチェーンの把握
ここまでサプライチェーン管理における考慮事項の多角化を示す動きを分野別に述べた。変化のスピードという点からは別の見方も可能である。一つは、サプライチェーン上の環境配慮や人権侵害リスク防止の要請の高まりとして緩やかに進む変化である。法律による義務が生じていなくても、企業が自社の株主であるグローバルな機関投資家や取引先企業から「サステナビリティに配慮した」行動をとる要請を受けることはある53。企業活動がグローバル化し、サプライチェーン上の役割が多くの企業によって担われる中、一連のサプライチェーンに関わる企業全体としてグローバルな課題について取組を求める民間での動きといえる。その際、サプライチェーンにおける影響力が大きい企業であればあるほど、自社の一次サプライヤーに止まらないサプライチェーンの把握および改善のための取組が期待されることが多い。
もう一つの動きは、深刻な人権侵害の抑制や安全保障の観点からの公的な取引制限である。このような取引制限は比較的短期間のうちに実施されることが多く、調達先の変更等の対応のための時間が十分にあるとは限らない。また、少数の企業を対象とする取引制限であっても、多段階のサプライチェーンの中の一部分で集中がある場合には、企業の事業活動に大きな影響を及ぼすことになる。
どちらの動きも、企業の事業分野や規模によって影響の大きさや、対応が求められる時間軸は異なるものの、一次サプライヤーよりもさらに上流のサプライヤーについて把握する必要性が生じる端緒といえ、今後その影響の範囲が広がっていくことが想定される。
53 Veronica H. Villena and Dennis A. Gioia, A More Sustainable Supply Chain, Harvard Business Review March-April 2020にはグローバル企業のサプライヤーエンゲージメントのベストプラクティスが紹介されている。
(2)共通価値がとりこまれた競争環境の認識
サプライチェーンにおける温室効果ガス排出削減や、サプライチェーン上の人権デュー・ディリジェンスの取組には、次に述べるような共通点がある。まず、国内法による義務づけがない場合であっても、グローバルに共有された価値観をベースとして、企業が国際的にも認められたガイドライン等も参照しつつ、自主的に自社で行うべきことを判断するという点である。温室効果ガスの排出削減やサプライチェーン上のどこかで発生しうる人権侵害を予防するという大きな目標に対して、政府のなんらかの規制が設けられるとしても、企業に対して具体的な取組手段を一律に定めることが必ずしも有効とは限らない。そのため、企業がそのビジネスモデルに応じて、効果的な方法を選定する仕組みには合理性がある。
次に、取組内容を開示することが推奨又は法律で義務づけられ、そういった推奨又は義務づけが取組の必要性についての関係企業の理解を高め、企業を取り巻くステイクホルダーからの期待が上昇すること等により、企業の取組がより深化していくというメカニズムを有する点である。ESG格付けのように一般的に投資家によって利用されている比較の仕組みのみならず、企業から開示された情報を集約して開示するプラットフォームが設けられており、投資家やその他のステイクホルダーによる企業間比較が可能となっている(第Ⅱ-1-3-6表)。
第Ⅱ-1-3-6表 企業のステートメント・情報開示の集約・比較の仕組み)
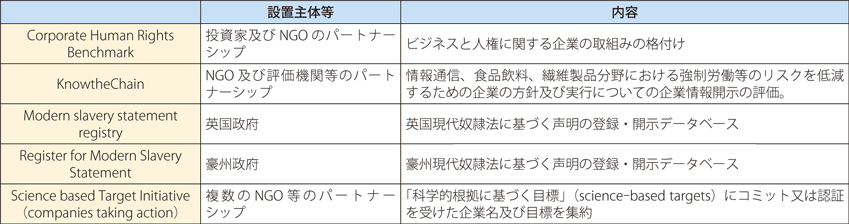
企業の事業分野によっては、このような期待と取組の深化のメカニズムが競争環境にも大きな影響を及ぼすことがある。第1部で述べたようにサステナビリティの分野における諸外国の政策立案のスピードは増しており、企業の事業環境にも大きな影響を与えると考えられる。こういった事業環境や社会の期待の変化を感知し、必要に応じて部署の役割を再定義し、部署間の連携メカニズムを構築するなど、経営資源を再結合・再構成する能力(ダイナミックケイパビリティ)54がますます重要となると考えられる。
54 ダイナミックケイパビリティについては、ものづくり白書2020及び2021においても論じられている。