第4節 デジタル技術の活用によるサプライチェーンの強靱化
これまでに見てきたように、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、世界的な人や物の移動制限や経済活動の制限措置が取られたことにより、グローバルに展開されたサプライチェーンに大きな混乱が生じた。また、例えば中国は世界の中でも新型コロナウイルスの封じ込めに成功し、いち早く経済活動を再開した一方、2020年後半以降、欧米諸国を中心に感染拡大の第2波、第3波、それを受けた再ロックダウンが行われるなど、国によって感染状況や経済活動の回復状況が異なる中、「ジャスト・イン・タイム」方式ではなく「ジャスト・イン・ケース」方式、すなわちその時々の感染状況・経済活動の再開の状況に応じて臨機応変にサプライチェーンを制御する必要性が高まった。一方で、企業は一次サプライヤー以外の在庫等の状況を委細には把握出来ていないのが現状である55。自然災害、感染症といったリスクに加え、地政学リスク、事故(スエズ運河におけるコンテナ船の座礁、半導体工場火災による自動車生産のサプライチェーンの混乱等)等の様々なリスクに対して柔軟かつ早急に対応するためには、従前取られてきたようなBCPによる対応に留まらず、日頃からサプライチェーンを可視化・把握する必要性がますます認識されている。
また、前節でも触れたように、国際的にはサプライチェーン全体での人権侵害を防ぐよう企業に求める動きや、カーボンニュートラルへの取組が議論されており、企業は自社で直接管理する製造や物流のみならず、取引先企業の取組状況についても包括的に把握し、社会に対して説明責任を負う必要が今後増大することが予想される。こういった市場ニーズへの対応にあたっても、デジタル技術は重要な役割を果たすと考えられる。
さらに、サプライチェーン上のリスクや社会的責任への対応の観点からのいわゆる「守り」のデジタル化のみでなく、ビジネスモデルの改革や、サプライチェーンの効率化を目指す観点からのいわゆる「攻め」のデジタル化に取り組むことは企業にとってもメリットをもたらす56。特に、近年は消費者個々のニーズに合わせた多様な商品を提供することや、短縮化する製品サイクルに対応しうるサプライチェーンを構築することがますます重要となりつつあり、「マス・カスタマイゼーション」を支える複雑な生産・在庫・物流管理の実現のためにデジタル化はなくてはならない技術となっている。サプライチェーンマネジメントに関わるサービスを提供する新興企業等も出現しつつある57。
ここでは、主に製造業におけるサプライチェーンマネジメントのデジタル化の状況や、デジタル化がもたらすメリットについて整理し、我が国企業がデジタル技術の利活用を推進するために必要な具体的方策について検討する。
55 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)「我が国のものづくり産業の課題と対応の方向性に関する調査」(2021年3月)
56 2020年版ものづくり白書
57 StartUs insight
1.製造業におけるデジタル化の新局面
第Ⅰ部第1章2節においても触れたように、新型コロナウイルス感染拡大以前からも、ビジネスのデジタル化は世界的に進展しており、企業のビジネスモデルに変化をもたらしている。各国は第四次産業革命への対応を念頭にIndustry 4.0(ドイツ)、中国製造2025(中国)、Society 5.0(日本)等を始めとした戦略を打ち出し、サイバー空間とフィジカル空間の融合、それによる価値の創造を目指している58。このようなデジタル技術の活用への注目が高まる中、近年特に盛んに着手されるようになっているのが、製造現場やエンジニアリングチェーン59のデジタル化に留まらない、マネジメントを含めたサプライチェーン全体のデジタル化である。
政府主導のサプライチェーンのデジタル化戦略の皮切りともいえるのが、2011年にドイツが提唱したIndustry 4.0である。Industry 4.0においては、スマート工場を中心としたエコシステムの構築が推進されている。そのようなシステムの中では、人間、機械、その他の企業資源を可視化し、互いに通信し、各製品がいつ製造され、どこに納品されるべきかといった情報を可視化・共有することを通じて、生産のためのエネルギーや資源の効率性の向上、製品の市場導入時間の短縮、製造工程のフレキシビリティを実現することが目指されている。Industry 4.0においては、サプライチェーンに応用しうる新技術として、クラウドやブロックチェーンといった技術を活用したデジタル化に加え、ロボットを用いた工場の自動化(ファクトリーオートメーション)、3Dプリンターといった技術の利活用が推奨されている。
これらの技術は、これまでの国際分業のあり方を大きく変え得るものであり、それぞれ異なる効果をもたらすと指摘されている(第Ⅱ-1-4-1表)。
第Ⅱ-1-4-1表 製造工程及びサプライチェーンへの先端技術の活用とその影響
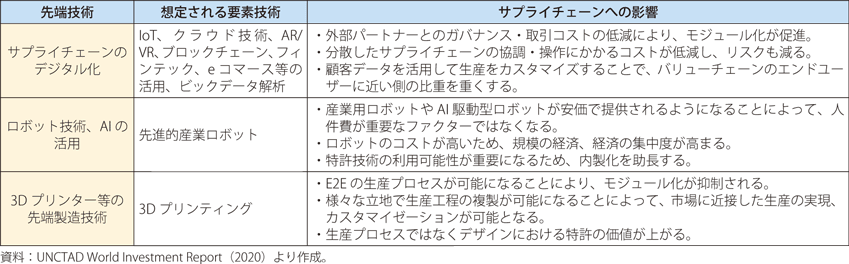
特に、サプライチェーンへのデジタル技術の活用は、距離や組織を超えた取引コストの低減を通じて、自社以外のリソースも含めた資源の利活用・企業間連携を加速させると指摘されている。その結果として、例えばこれまで自社内で行われていた製品設計、製造、販売、といった各セクションが制約なしに分離する(アンバンドリング)ことが可能となり、自社企業外への財・サービス生産の委託・外注(アウトソーシング)、さらには物理的に国境を越えた財・サービス生産の委託・外注(オフショアリング)を促進する効果があるとされ、生産工程が柔軟に分散化できるようになり、サプライチェーンの強靭化に貢献する効果があると指摘されている60(第Ⅱ-1-4-2表)。
第Ⅱ-1-4-2表 デジタル化がもたらす国際分業の構造変化
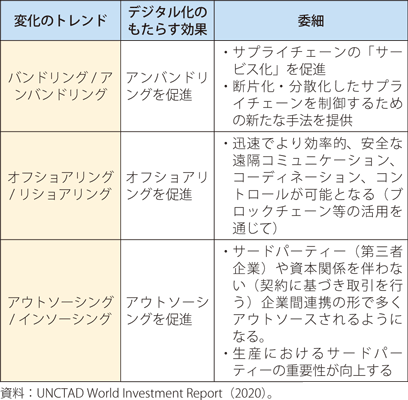
58 総務省「平成29年版 情報通信白書」(2017年)
59 エンジニアリングチェーン:(要出典)。エンジニアリングチェーンのデジタル化を取り巻く動向については、ものづくり白書(経済産業省)も参考にされたい。
60 アウトソーシング/インソーシング、オフショアリング/オンショアリングの定義については、文脈によって異なるが、例えば「アウトソーシングの国際経済学」(冨浦、2014)等も参照されたい。
2.サプライチェーンマネジメントのデジタル化
本項では、特にサプライチェーンの分散化・レジリエンス強化へ与える効果が大きいとされるサプライチェーンマネジメントのデジタル化について、概要を整理する。
(1)サプライチェーンマネジメントのデジタル化の概要
まず、サプライチェーンマネジメントのデジタル化の具体像を見ていく。
サプライチェーンのデジタル化はその進展段階によって①製造工程のリアルタイムでの把握②他社も含めたデータ連携によるサプライチェーン横断的な生産工程の可視化③サプライチェーンリスクの予測分析と計画への反映、の三段階に分けることができる(第Ⅱ-1-4-3図)。
第Ⅱ-1-4-3図 Industry 4.0におけるサプライチェーンのデジタル化の概要
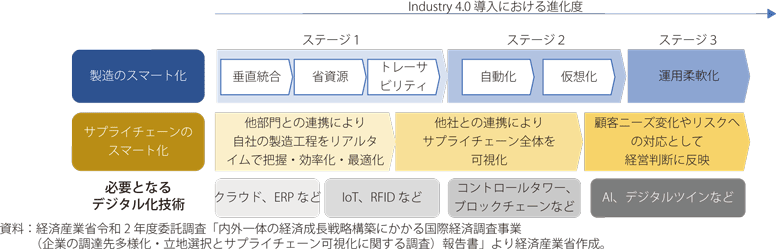
ステージ1では、各製造工程のERP、MES61等を通じた情報のデジタル化を基礎として、クラウド技術等を活用して、発注・在庫状況などを自社内でリアルタイムに可視化する。ステージ2においては、IoT等の無線通信技術を活用して取得・収集したデータをブロックチェーン等を通じて組織を超えて共有し、ビッグデータとして活用することにより、サプライチェーン全体を通じたリアルタイムでの状況把握、サプライチェーンの最適化を実現できる。さらに、ステージ3においては、AI等の技術を用いたデジタルツインなどの構築を通して、様々なリスクを想定したサプライチェーンの予測分析、それを踏まえた在庫・物流計画の検討が可能となる。
61 ERP(Enterprise Resource Planning):総務や会計、人事、生産、販売など企業の基幹情報を連携・集約した統合基幹業務システム。MES(Manufacturing Execution System):製造工程の把握や管理、作業者への指示や支援などを行う製造実行システム。
(2)業種ごとに異なるサプライチェーン把握の目的
サプライチェーンの把握の目的は、その業種の製品やサプライチェーンの特性によって異なる。例えば、自動車などの輸送機械の業界における生産方式は、インテグラル型(摺り合わせ型)と呼ばれ、製品の部品の機能が複数の部品にまたがって複雑に構成されているため、従前からサプライチェーン全体で部品・製品の流通やその品質を管理する必要性が高かった。そのため、自動車業界ではサプライチェーンマネジメントも先進的に導入されてきた。実際に、実需の情報に応じた柔軟な生産を目的とした「ジャスト・イン・タイム」の生産方式が、トヨタを始めとする自動車業界において取り入れられていることからも、そのニーズの高さがうかがえる。他方、電子機器については対照的に、モジュール型62と呼ばれる生産方式となっており、製品の機能が部品ごとに構成され、ある程度規格化が進展している。そのため、業界の特性として、サプライチェーン上でのリスクが生じた際に比較的柔軟に調達先を変更することが可能である。また、食品や素材(ダイヤモンドなどの宝石類など)は、消費者に対する原産地証明の信頼性やトレーサビリティ、鮮度に関する情報把握のニーズが高い一方、医薬品は偽薬の混入、盗難の防止、法的規制への対処の必要性から、サプライチェーンの把握のニーズが高いと考えられる。
加えて、サプライチェーンに備わる柔軟性がこういったデジタル情報の活用の可能性に大きく影響する。たとえば、バイオ医薬品、医療機器、データセンター機器・ソリューションの提供を行う企業といったリスクの高い業種は、危機に応じてサプライチェーンを大きく変更する必要性が高い一方、国際的な規制、産業の特性によってサプライチェーンの変更は容易ではない。対照的に、衣料・装飾品、消費財等の緊急性が低い業種に関しては、サプライチェーンの変更は容易である一方、緊急的にサプライチェーンを変更するニーズは高くない63。
以上のような業界ごとのサプライチェーンの特性と、それに応じた把握可視化のニーズを整理すると、以下の表のようになる(第Ⅱ-1-4-4表)。
第Ⅱ-1-4-4表 業種ごとのサプライチェーンの特性
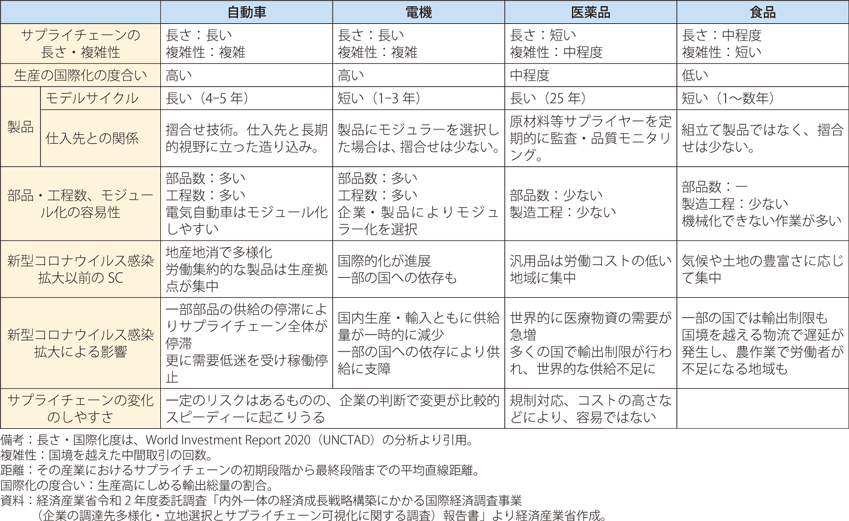
デジタル化の推進にあたっては、上述のような業種・製品特性を踏まえ、サプライチェーンマネジメントの目的や戦略を明確にした上で、企業横断的な取組を進めることが重要である。デジタル技術の中でも、暗号化されたデータを複数の分散したコンピューター上で管理する「ブロックチェーン」の技術は、ブロックチェーンの持つ耐改ざん性が製品のトレーサビリティ向上や企業間の情報共有の信頼性担保に寄与することに加え、スマートコントラクトや暗号資産といった関連技術の活用への期待、次節で述べるような貿易手続の円滑化等を通じたサプライチェーン効率化など、サプライチェーン上の様々なニーズに貢献することが期待されている64。既にブロックチェーンの活用が進んでいる事例として、食品業界では、ドイツおよびオーストリアにおける政府、大学、企業一体となった食品トレーサビリティ向上の取組としてNutrisafeの取組がある。本取組においては、消費者に対する情報開示の向上の目的とともに、災害、集団食中毒等のリスクに直面した際の食料の安全供給といったレジリエンスの観点も重要視されている。医薬品業界においても同様に、医薬品のトレーサビリティの実現を目的として、ブロックチェーンの活用が進められている。
さらに、自動車業界においては、サプライチェーンが長く多岐に渡るため、サプライチェーン全体でのカーボンニュートラル、環境配慮や、バッテリーに用いられるコバルトなどを始めとした原材料の調達を巡る人権デュー・ディリジェンスの問題への対応が急務となっており、ドイツのベンツ、ポルシェ、スウェーデンのボルボ等といった企業はブロックチェーンを活用した新興企業と組むことによって、部素材のトレーサビリティの担保に努めている。
62 製造業の「モジュール化」とは、「それぞれ独立に設計可能で、かつ、全体として統一的に機能するより小さなサブシステムによって複雑な製品や業務プロセスを構築すること」(青木昌彦 他「モジュール化」(2002年)と定義される。
63 経済産業省令和2年度委託調査「2 令和2年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(アジア大でのサプライチェーン強靱化に向けた調査)事業報告書」2021年3月)。
64 World Economic Forum“Inclusive Deployment of Blockchain for Supply Chains: Part 1 – Introduction”(2019年3月)等を参照。
3.デジタル化によってもたらされるサプライチェーンの変化
デジタル技術の導入によって、国際分業の体制に変化が生じうることは先に述べたが、本項では、サプライチェーンのデジタル化のメリット及び影響について、主に理論分析を中心に整理する。
(1)サプライチェーンのデジタル化によるメリット及び影響
サプライチェーンのデジタル化によって、サプライチェーン上の情報をデジタル情報で把握出来るようになることは、企業へ様々な面でのメリットをもたらすと分析されている。以下、強靱化・レジリエンス、効率化や生産性の向上の観点から見ていくこととする。
デジタル化によるサプライチェーンの可視化は、今般の新型コロナウイルスの感染拡大や、自然・人為的災害等のリスクに対して迅速に対応する上で非常に重要である。デジタル化は、従前紙面や電話口、電子ファイルを介した直接取引のある企業間の情報共有に留まっていた情報が、デジタル技術によってさらに上流または下流の多段階のサプライヤーも含めて共有出来るようになる。このことにより、多段階のサプライチェーンの一部に集中がある場合の把握や、そのサプライヤーからの調達ができなくなることによる影響も分析することができる。また、在庫のきめ細やかな把握を通じたサプライチェーンの強靱化は、単に企業のリスク対応能力を上げるのみでなく、サプライチェーンの柔軟性・強靱性を高めた結果として、最終的には高いビジネスパフォーマンスを生むことも示唆されている65。
また、企業間のコミュニケーションのあり方や関係性に変化をもたらすことによるメリットも指摘されている。
WTO(2018)においては、IoT、AIやブロックチェーン等のサプライチェーンマネジメントへの活用によって、サプライチェーンの構造はより柔軟に変化しうるものに変わっていくと指摘されている。
まず、Industry 4.0に代表されるサプライチェーンのデジタル化は、サプライチェーンの垂直方向の企業間でのデータ共有を促進し、垂直方向の関係性(Vertical networking)、すなわちサプライチェーン上の取引企業との連携を強化する。具体的には、デジタル化により全ての生産段階の情報が共有され、材料や部材をどこへでも配置することが可能となり、「マス・カスタマイゼーション」と言われる、顧客一人一人のニーズに対応した生産が可能となる。さらに、デジタル化はサプライチェーンの水平方向の関係性(Horizontal networking)、すなわち類似の製品やサービスを提供する企業間での連携の強化にも寄与することが指摘されている。具体的には、デジタル化された情報が利用できるようになることによって、戦略を持って生産を実施することが必要とされるようになり、結果として水平統合が進み、生産体制にも高度な柔軟性をもたらすと指摘されている66。このように垂直・水平どちらの関係性においても、生産体制の透明性が上がることによって、企業が顧客ニーズの変化や、各生産段階の状況を把握することが可能になり、全ての生産段階において、その変化に柔軟に対応できるようになることが指摘されている。
国際貿易の観点からは、貿易コストの約半分は、製品を最終消費者に届けるまでの輸送・物流に関わるコスト(輸送、積み荷、在庫保管、港湾での手続きなどにかかる金銭・時間・不確実性にかかわるコスト)が占めるが、RFID67や、IoT等の技術を用いた積み荷の可視化と追跡、AIを用いた物流の最適化によって、こういったコストの低減を図ることができると示唆されている68。
さらに、こういったコスト水準の低下は、サプライチェーンに参画するプレイヤーにも変化を与えうる。WTO(2021)では、サプライチェーンマネジメントにおけるブロックチェーンの活用により、貿易への参画コストが低下し、中小企業が国際貿易に参画しやすくなると説明されている。
このように、サプライチェーンのデジタル化は、サプライチェーン全体の把握を通じて生産拠点の選択や柔軟な取引関係の構築、といった経営判断の基礎となりうる。デジタル技術が整備されることによって、多様な関係者がサプライチェーンに参画出来るようになることが見込まれ、より強靱・柔軟なサプライチェーン運用が実現できる。
65 Sajad Fayezi et al.(2016)。
66 B. Tjahjono et al.(2017)。
67 無線通信によって電子タグを識別、管理するシステムのこと。非接触かつある程度離れた距離から、複数のタグを一度に読み取ることができるため、サプライチェーン上でのモノの管理が容易になる。
68 WTO(2018)、the Economist(2017)
(2)業種ごとに異なるデジタル化の恩恵
上記に述べたような強靱化・効率化のメリットが考えられる一方、デジタル化の恩恵を受けやすいか否かは、業種や製品の特性によってばらつきがある。WTO(2018)では、特にデジタル化による恩恵の大きい製品の特性として、①迅速な運搬が必要とされる製品(time-sensitive goods、例:小売業における生鮮食品など)、②原産地や運搬経路に関する証明が必要となる製品(Certification-intensive goods、例:食品、農産品)、③企業間の契約が多く発生する製品(Contract-intensive goods、例:先端技術を扱う機械など)を挙げている。これらの製品は、デジタル化による時間や費用の面での取引コストの低減、トレーサビリティの向上、スマートコントラクトとの連携などのデジタル技術の特性によって、更に取引が容易となり、取引規模が拡大するとされる。他方、製品自体のデジタル化が可能な製品(例:本、CDなど)の取引規模は、電子商取引に移行することによって、物理的な取引量・流通量は減少することが見込まれている。
4.サプライチェーンマネジメントのデジタル化の現状
サプライチェーンマネジメントのデジタル化は、上記のような変化やメリットをもたらすことが指摘されている一方、実際に企業がデジタル技術の導入を実施するためには、そのメリットを理解し、コストパフォーマンスを妥当と捉え投資判断に踏み切る必要がある。本項では、実際の各業種におけるサプライチェーンマネジメントのデジタル化の状況について、データからの把握を試みるとともに、デジタル技術の活用にあたっての課題を整理する。
(1)業種ごとのサプライチェーンマネジメントへのデジタル技術の導入状況
生産プロセスやサプライチェーンマネジメントのデジタル化の進展状況は、業種によって異なる。米国を例にとってみると、企業が保持する情報のデジタル化が最も進んでいるのは、とりわけ金融関係の情報であり、約70%近くの企業が「半分以上のデータをデジタル形式で取り扱っている」と回答している。さらに、製造業では特に製造工程に関わる情報のデジタル化が他の産業と比較して進展していることが分かる。他方、サプライチェーンに関する情報のデジタル化は、金融や製造工程の情報と比較すると低位に留まることが分かる(第Ⅱ-1-4-5図)。また、製造業の中でも、サプライチェーンに関わる情報のデジタル化の進展状況には差が見られており、多くの部品数からなり複雑なサプライチェーンを必要とするコンピューター、電子機器、機械産業等といった産業や、安全基準への法的対応が必要となる化学製品69、石油・石炭製品等においては企業の保持する情報のデジタル化は進展している一方、木材製品や家具・繊維製品等を扱う産業においては、デジタル化の進展は低位に留まっている(第Ⅱ-1-4-6図)。
第Ⅱ-1-4-5図 米国産業全体と製造業における情報のデジタル化の状況
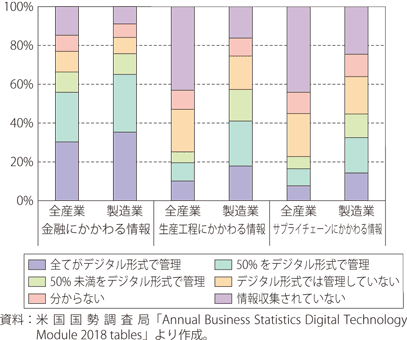
第Ⅱ-1-4-6図 米国製造業における業種別のサプライチェーン関連情報のデジタル化の状況
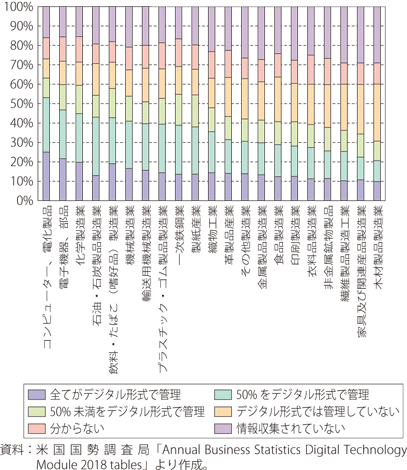
上記は米国の企業を対象とした調査であるが、我が国企業におけるデジタル技術を用いた生産プロセスの可視化の取組に関する調査結果を見ると、製造物・部材のトレーサビリティへの取組については、既に実施している企業・実施する計画がある企業が二割超存在する一方で、実施予定がない・他の手段で足りていると回答した企業も三割以上存在し、企業における意識の差が見られることが分かる。さらに、海外工場も含めた可視化の取組に関しては実際に取組を実施している企業の割合はわずかに留まり、サプライチェーンマネジメントに関わる情報のデジタル化の取組は途上であると言える(第Ⅱ-1-4-7図)。さらに、我が国企業は他国と比較してデジタル技術の導入が遅れており、特に中小企業におけるデジタル技術の導入率が低位に留まっている70。
第Ⅱ-1-4-7図 日本企業における生産プロセスの改善・向上等に関する取り組み
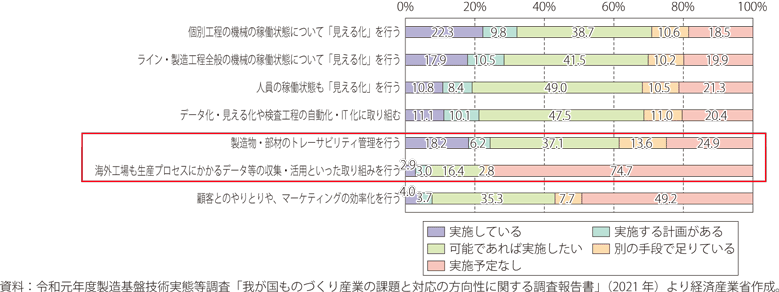
69 米国においては、医薬品の安全性担保を目的とした「医薬品サプライチェーン安全保障法(Drug Supply Chain Security Act)」(2013年成立)において、医療用医薬品の製品コード、有効期限、ロット番号などを電子管理することが義務付けられていることがデジタル化の実施割合の高さに繋がっているものと推測される。
70 総務省『我が国のICTの現状に関する調査研究報告書』(2017年)など。
(2)サプライチェーンマネジメントのデジタル化が抱える課題
上記の通り、サプライチェーンマネジメントのデジタル化には強靱化・効率化といった面での企業へのメリットが存在する一方で、実際のデジタル化は進んでいるとは言えないのが実情である。サプライチェーンの最上流から最下流までの把握と最適化を図るためには、製造現場のデジタル化が進み、サプライチェーンに関わる情報がデジタルデータとして取得できるようになっていること71に加え、コスト・技術面において企業が十分にデジタル化を実施する体力があること、部門・企業間でのデジタル化のメリットの共有と信頼関係の構築、サイバーセキュリティ上の懸念の払拭といった多段階の課題を克服する必要がある。
一般的な企業のデジタル化推進にあたってのコスト・技術の観点では、これまでもDXレポート72等でも指摘されてきた。例えば、既存システムの老朽化・肥大化(レガシー・システムの存在)、既存システムの運用・保守の高コスト化、IT人材の不足、経営層からの理解不足等、様々な問題が指摘されている。ここでは、部門・企業を超えて情報を共有するに際して生じる課題に焦点を当てる。
71 製造現場のデジタル化に関しては、経済産業省「ものづくり白書」も参考にされたい。
72 経済産業省「DXレポート ~ITシステム『2025年の崖』克服とDXの本格的な展開~」(2018年9月)。
① サプライチェーン上のサイバーセキュリティリスクに対する対応
企業間の情報共有に伴う情報セキュリティの観点からの懸念が高まっている。独立行政法人情報処理推進機構が毎年発表する「情報セキュリティ10大脅威」では、2018年までは圏外だった「サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃」が、2019年以降、四位に急遽浮上している(第Ⅱ-1-4-8図)ことに加え、2019年と2020年に発生したサイバー攻撃の件数を比較すると、約2.6倍に増えており、製造業に対する攻撃はヘルスケア・金融業界に次ぎ多くなっている73。サプライチェーン上のセキュリティのぜい弱な企業が攻撃を受けると、そこを起点としてサプライチェーン全体に機密情報の漏えい等の被害が拡大するリスクがあり、上位サプライヤーも含めたセキュリティ対策が必要とされる。データ管理の安全性も含めたサプライチェーンのセキュリティ管理については、ISO28000(サプライチェーンのためのセキュリティマネジメントシステムの仕様)が策定され、システム上での確認事項、それを元にしたPDCAサイクルをサプライチェーン全体で運用する方法について普及啓発が図られていたり、サイバーセキュリティに関する企業の指針として米国国立標準研究所により定められたサイバーセキュリティ・フレームワークの中にも2017年以降サプライチェーンに関する項目が増設されたりと、関心の高まりに合わせ標準策定も取り組まれている。
第Ⅱ-1-4-8表 情報セキュリティにおける10大脅威
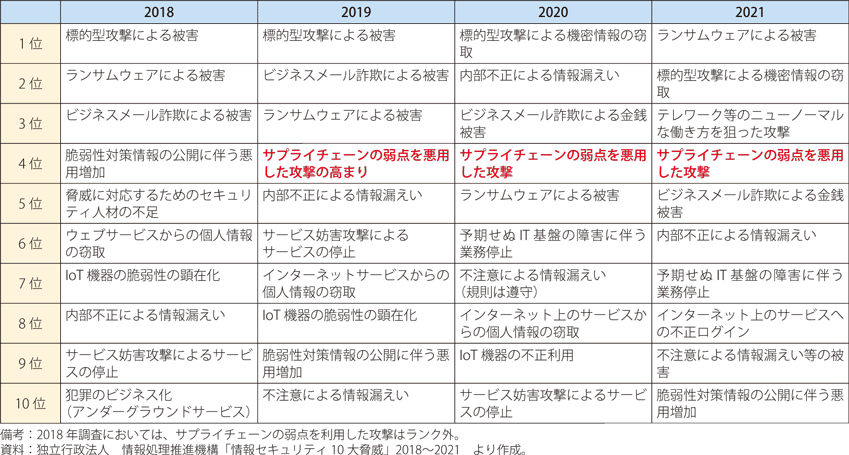
73 zScaler“the 2020 State of Encrypted Attacks report”。調査対象となっているのはSSL/TSLで保護された通信に対する攻撃。
② IT人材の不足の観点
また、上記のようなセキュリティ上の懸念がある一方で、各企業においてはIT人材の確保が十分に進んでいると言いがたい現状がある。デジタル技術を活用したサプライチェーンマネジメントの展開には、ITスキルを持った人材の確保が重要である一方で、ユーザー企業におけるIT人材の不足感は「量」「質」の両面で高まっている74。さらに、我が国企業は海外の企業と比較して、IT企業以外のユーザー企業側に所属する人材の割合が顕著に低い(第Ⅱ-1-4-9図)。このような人材の構造は、ユーザー企業側における情報システムのノウハウが蓄積しづらい問題を生み、ユーザー企業側にとってサプライチェーンマネジメントがブラックボックス化する懸念がある。
第Ⅱ-1-4-9図 IT企業とそれ以外の企業に所属する情報処理・通信に携わる人材の割合
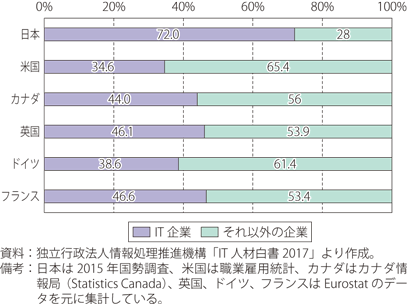
74 独立行政法人情報処理推進機構「IT人材白書2020」。
③ 部門・企業間の利益相反関係
企業内の複数の部門間の情報共有の実施を図る上でも、障壁は存在する。サプライチェーンマネジメントの実施には、調達、生産、物流、販売等の複数の部門、さらには個々の従業員が関与する必要があるが、それぞれの部門が達成すべきと考える運営の目標は、「在庫削減」「安全在庫の確保」「納期の短縮」「需要予測の向上」「サプライチェーン管理の自動化の促進」「雇用の維持」など、それぞれの立場により異なる場合があり、個別最適を超え部門間の連携を目指すことは難しい。
企業を超えた情報共有の推進においては、自社製品を納入した顧客から、データ収集の了解を得られなければ、デジタル・プラットフォーム上での部門を超えた情報共有は困難となることが予想され、特に中規模・小規模企業においては企業秘密の公表に対する抵抗感が強いとの指摘もある75。サプライチェーンが多くの生産工程によって構成されるような業種においては、中間サプライヤーからそのようなサプライチェーン管理に関わる情報提供の理解が得られないと、さらに上流のサプライヤーの情報を得ることがさらに困難になるといった声や、仲介業者を介して上流サプライヤーからの調達を実施している場合には、在庫や生産体制といった情報の入手が困難になる、といった声もある。
さらには、人権、環境問題への対処といった国際的な動向は、国際貿易に直接的に関与する大企業を中心に関心が高まっている一方、直接的に国際貿易を行わない上位サプライヤーにはデジタル技術を用いたマネジメントの必要性や国際動向が十分に理解されていないとの指摘もある。そのため、顧客企業との間のwin-winな関係を構築することが重要である76。
75 Netsuite.com(2020)“Digital Supply Chain Management: What’s the cost of doing nothing?”.
76 企業活力研究所「デジタル・プラットフォーム構築による製造業の競争力強化に関する調査研究 ―デジタル時代における新たな企業成長のあり方―」(2020年3月)。
④ データ連携の実施にあたっての問題
部門・企業間でデータを共有する場合に、①共有するデータの規格、取得する単位が企業間で異なってしまい、接続性が失われてしまう問題、②サプライチェーン連携にあたって、どういった情報を共有すれば適切な部門・企業間連携が構築できるのかといった共通認識の欠如、といった問題が存在する。こういった共通のシステム・フレームワークが存在しないことから、各企業がデジタル化に着手する際に手探りで実施する必要が生じてしまう点もデジタル化を妨げる障壁の一つとなる。
①の接続性の問題に関して、サプライチェーン上の変化に対応しうるシステムの構築を図る際、個々の業務に合わせたデータの運用がなされている場合には、ビジネスプロセスの変更、企業の事業統合、危機時におけるサプライチェーンの柔軟な変更への即座の対応が難しいため、共通の規格を土台とした情報共有の仕組みを構築する必要がある。このような規格の使用推奨にあたっては、下請け企業側から大企業に対して導入を依頼することには、既存の取引関係の維持の観点から難しいことが想定され、大企業、または国から働きかける必要があるという指摘もある77。
②のサプライチェーン連携にあたっての情報共有の共通認識の問題については、例えば取引される製品の原価や原産地に関わる情報や、他のサプライヤーも含めた取引先の全体像といった情報は、企業の競争力に直結する情報でもあり、むやみに公開することは取引におけるパワーバランスの変化、競争力の低下に直結しかねない。
これらの課題の解決に向けては、企業間の情報の取引に際して共有すべき項目についての共通した規格やフォーマットの策定に向けた取組が行われており、例えば我が国の中小企業間のデータ連携を促進するための取組として、中小企業庁では、国連CEFACT標準(UN Centre for Trade Facilitation and Electronic Business)に則った「共通EDI標準」(EDI=Electric Data Interchang)の導入の提唱を通して、参入障壁を低くさせるような工夫が行われている。さらには、一部業界団体では独自の標準設計に取り組んでいる事例もある。自動車業界においては、国際的な業界横断団体であるMOBIがサプライチェーンへのブロックチェーンの活用を目指して標準の策定に向けた検討を進めている。
77 日本経済団体連合「Society 5.0時代のサプライチェーン ―商流・金流のデジタル化に向けて―」(2020年9月)。
5.まとめ
サプライチェーンマネジメントのデジタル化に向けては、上述のような組織間のデータ共有に関わる課題や、それ以前にサプライチェーンに関わる情報のデジタル化、それを支えるデジタル技術を製造現場へ導入するにあたっての課題が多数存在する一方で、事業環境の不確実性が増す中、デジタル技術を活用したサプライチェーンの強靭化、効率化を戦略的に図っていくことは企業にとってますます重要になることが予想される。デジタル技術の導入は、中小企業の参画を促し、これまで取引の拡大機会が少なかった企業の取引機会を拡大する効果もあり、「包摂的なサプライチェーン」実現の鍵ともなり得る。さらに、企業は今後、経済合理性を目指した従前のサプライチェーンマネジメントのみならず、人権、カーボンニュートラルといった共通価値に関して、サプライチェーン全体で対処する必要性は市場の要請に応じてますます高まる可能性が高く、サプライチェーンの把握の状況次第では市場機会を逸する可能性さえ生じうる。こういった共通価値への対応にあたってもデジタル技術が活用され始めている。したがって、企業はデジタル技術によるサプライチェーン把握の必要性と今後起こりうるリスクを、取引先も巻き込んだ形で検討・精査し、積極的にデジタル化の推進に取り組むことが必要である。
同時に、サプライチェーンを支える情報共有の円滑化においては、データ移転規制、ローカライゼーション要求、公権力によるアクセスといった地政学的リスクへの対処が必要となる。今後のサプライチェーンの安定性や信頼性を担保する措置として、データ自由流通ルールへのコミットメント、公権力によるアクセス手続きの正当性といった要素も重要となることが予想される。政府、業界団体による標準化、ルール作りといった観点からの努力も同時に必要とされる。