第5節 国際的な貿易手続の円滑化・デジタル化の推進
前節では、デジタル技術を活用した企業のサプライチェーン強靭化の重要性に触れ、それを実現するためには企業間の情報共有が不可欠であると言及した。このような企業間のデータ共有の取組に加え、通関等貿易手続のデジタル化、それを通じたコストの低減・透明性の向上を図ることで、国境を越えるサプライチェーン管理がより一層可能となる。ここでは、企業のサプライチェーン管理の高度化・可視化に資する貿易手続の円滑化を取り上げる。
関税は代表的な貿易障壁であるが、これまで各国・地域がWTO協定を遵守する78とともに、FTA、EPAを積極的に締結し、相互に関税を撤廃又は削減してきた結果、現在では、関税による貿易コストは低くなっている(第Ⅱ-1-5-1図)。今後、各国が更に貿易を拡大するためには、貿易関連手続の透明性確保、簡素化、標準化といった貿易円滑化による貿易コストの低減がより有効と考えられる。
第Ⅱ-1-5-1図 世界の平均関税率の推移(地域別)
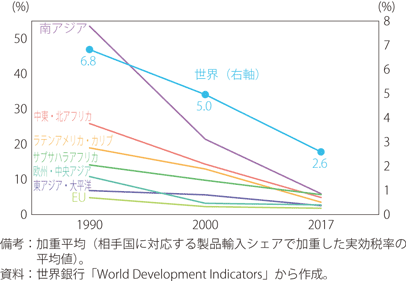
なお、貿易円滑化とは、国際的に取引されるために国を出入りする物品の技術的・法的手続を合理化し、簡素化するための一連の措置を指しており、具体的には、貨物に関するデータの電子的な交換から、貿易文書の簡素化と調和、国境当局の行政決定への不服申立てに至るまで、国境手続の全範囲が対象となる。
近年、電子商取引の拡大に伴い国境を越える貨物も増加しており、今後も一層拡大する見込みである(第Ⅱ-1-5-2図、第Ⅱ-1-5-3図)。越境ECに対して購買者はスピードを重視する傾向があることから、貿易手続の迅速な処理のニーズは高い。さらに、目下のコロナ禍では、必要不可欠な医療品、食料品、IT部品等の迅速な輸送の確保が新たな課題となっており、以前に増して貿易円滑化の必要性が高まっている。
第Ⅱ-1-5-2図 世界のオンライン購買者数(国内取引・越境取引)
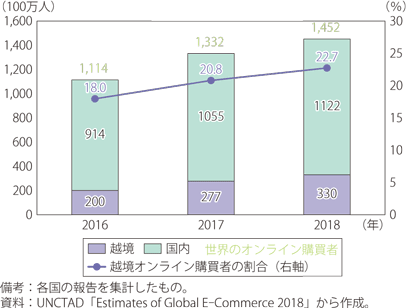
第Ⅱ-1-5-3図 世界の越境EC市場取引額の拡大予測
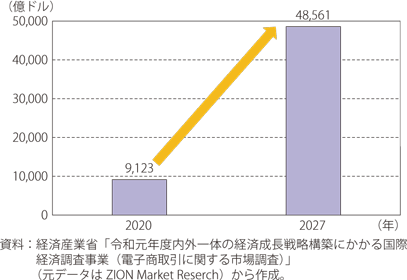
78 WTO協定の基本原則には、ある国に与える最も有利な待遇を、他の全ての加盟国に対しても与えなければならない、という「最恵国待遇」がある。例えば、A国がB国(B国は加盟国であるかどうかを問わない)に対し、ある製品の関税率を5%に削減すると約束した場合、この関税率はB国以外のすべての加盟国に関しても適用されなければならない。なお、地域統合等例外については、基本原則たる最恵国待遇原則を形骸化することがないよう、ルールに整合的に運用されることが必要とされている。
1.国際機関における貿易円滑化の取組
ここでは、国際機関における主な取組を見ることとする。
(1)WTO(世界貿易機関)
先進国、開発途上国のどちらにおいても、国境を越えて商品を移動する際に発生する膨大な貿易手続は、長年問題視されてきた。その解決に向け、2004年11月、WTOではドーハ・ラウンドの一分野として貿易円滑化の交渉が始まり、2017年2月、WTO設立79以降初めて全加盟国が参加して作成した貿易円滑化協定(Trade Facilitation Agreement、以下TFA)80が発効した(第Ⅱ-1-5-4表)。
第Ⅱ-1-5-4表 WTO貿易円滑化協定(TFA)
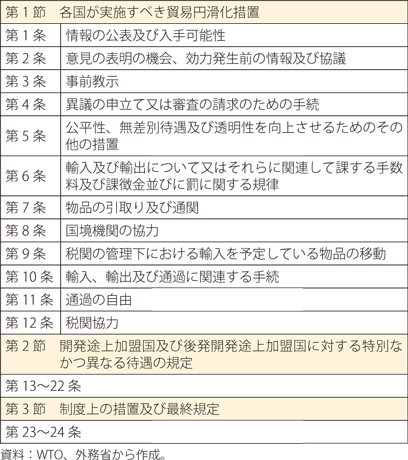
同協定では、貿易規則の透明性の向上、税関手続の迅速化・簡素化といった貿易取引にかかるコストを削減するための包括的なルールが定められている。WTOは、これらルールの達成がグローバルバリューチェーンに参加する重要なチャンスを創出するとしている。
主な条項としては、輸出入にかかる費用や税関手続の情報開示(第1条)、手続や関税分類等について事前に税関の回答を得ることができる事前教示制度の導入(第3条)、認定事業者に対する通関手続の軽減等の優遇措置、急送貨物への特別な対応(ともに第7条)、通関手続の窓口一本化(シングルウィンドウ化)(第10条)等が挙げられる。
WTOは、TFAが完全に実施された場合、世界の貿易コストは平均で14.3%(工業製品は18%、農産品は10.4%)削減されると推定している。ここでの貿易コストとは、ある生産物が最終ユーザーに到達するまでの全てのコスト、例えば、運搬、関税・非関税障壁、情報、税関手続、為替関連、契約実行のほか、時間的コスト等を含んでいる81。なお、時間的コストのみをとりあげると、TFAの実施によって、輸出は平均91%、輸入は平均47%、時間が短縮されるとも推定している。貿易コスト削減のメリットは大きく、世界の貿易、GDPを押し上げることが期待できる82。
次に、WTOのデータベース83を利用し、日本の国際分業、サプライチェーン構築が進展しているアジアに注目して貿易円滑化の実行率をみてみると、日本、中国、韓国と同様100%を達成しているのはASEANの中でシンガポール一か国しかない。なお、ミャンマーの5.5%を筆頭に後発国の実行率の低さがみてとれる。インドも78.2%と改善の余地がある(第Ⅱ-1-5-5図)。
第Ⅱ-1-5-5図 アジア主要国の貿易円滑化実行率
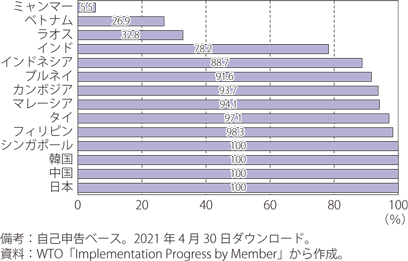
79 1995年
80 2014年11月、同協定はWTO協定に追加するための改正議定書に採択され、2017年2月、発効した。WTO「PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION DECISION OF 27 NOVEMBER 2014![]() 」
」
81 Anderson and van Wincoop(2004)。貿易コストを測るには、直接的・間接的の2つの方法があるが、データに制約がある直接的な方法よりも、貿易フロー量や国境を越えることで生じる価格差から貿易コストの規模(magnitude of trade costs)が推測できる間接的な方法に優位性があるとしており、WTOは、重力モデルを使った間接的方法で推計をしている。
82 WTO「WORLD TRADE REPORT 2015・Estimating the benefits of the Trade Facilitation Agreement![]() 」
」
83 2021年4月時点のダウンロード。WTO「Implementation Progress by Member![]() 」
」
(2)OECD(経済協力開発機構)
WTOの貿易円滑化協定(TFA)の実行を促進するため、OECDはTFI(Trade Facilitation Indicators)84という指標を開発し、TFAで設定された措置を実施した場合の潜在的な影響を評価する手段を提供している。
TFIにより、各国の貿易円滑化措置の導入進捗度を絶対的に測定するだけでなく、他国と比較したパフォーマンスを測定できる。また、各国が貿易円滑化における強みと弱みを明確に認識することで行動すべき分野に優先順位をつけ、より的を絞った方法で技術支援とキャパシティ・ビルディングを実施することができる。
なお、第Ⅱ-1-5-6表における「ガバナンスと公平性(項目(k))」のみWTOのTFAには設定されていない指標であり、ここでは各国国境当局の職員が確固たる行動規範に沿って恣意的ではない国境管理を行っているか等を評価する項目となっている(第Ⅱ-1-5-6表)85。
第Ⅱ-1-5-6表 OECDの貿易円滑化指標(TFI)の全体構成
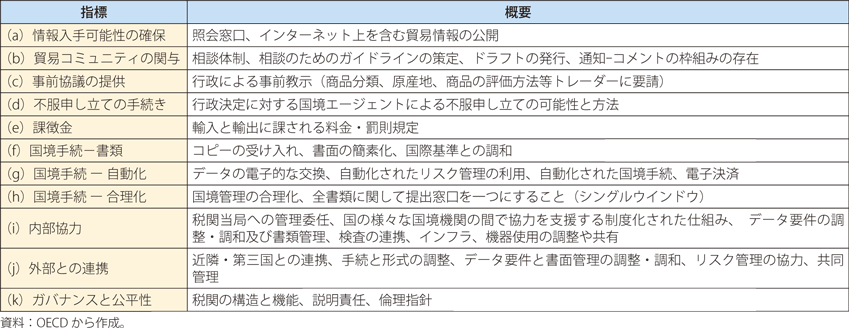
では、どのような貿易円滑化措置が最も効果的なのだろうか。
OECD加盟国について、(a)~(k)の11の指標の中で、貿易コストを最も削減できる可能性のある措置は、削減幅が大きい順86に、国境手続の合理化(2.6%)、国境手続の自動化(2.3%)、情報入手可能性の確保(1.7%)、事前協議の提供(1.6%)という結果となる。一方、低所得国の場合、国境手続の書類簡素化(4.2%)、国境手続の自動化(3.6%)、情報入手可能性の確保(2.8%)、国境手続の合理化(2.8%)となっていることから、書類の簡素化、統一化といった基本的な工夫でも、貿易コストが大きく削減できることが分かる。
以上から、国の発展段階によってコスト削減に効果的な方法に違いがあるほか、発展段階が遅い国の方がより大きくコストを削減できる可能性があるといえる(第Ⅱ-1-5-7図)。
第Ⅱ-1-5-7図 貿易コスト削減に有効な方法(所得階層別・上位4つ)と削減率
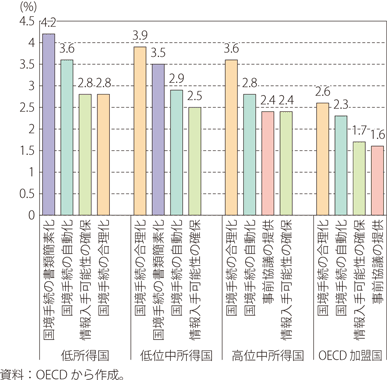
なお、以下(第Ⅱ-1-5-8表)は、主要国の貿易円滑化(項目別)の進捗評価であるが、ASEANにおいては、シンガポール、ベトナムが、また、ASEAN以外では韓国が高いことが分かる。これらの国はGDPに占める輸出依存度が相対的に高い点で共通している(第Ⅱ-1-5-9図)。
第Ⅱ-1-5-8表 主要国の貿易円滑化の項目別進捗
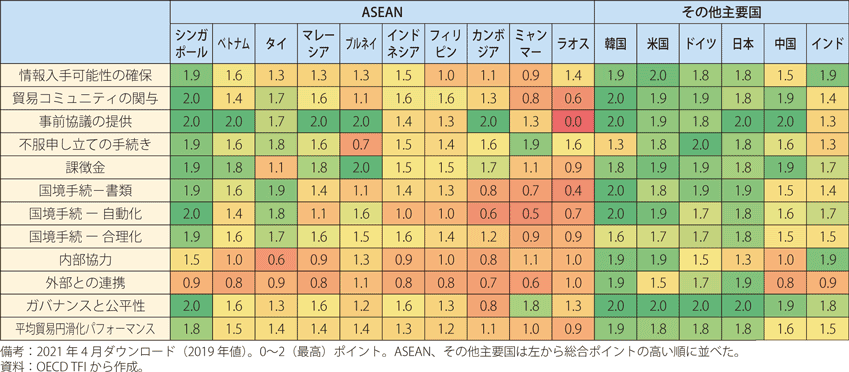
第Ⅱ-1-5-9図 主要国の輸出依存度
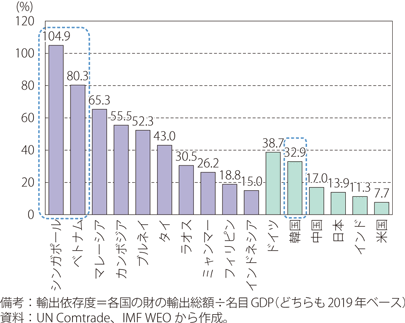
84 OECD「Compare your country・Trade Facilitation Indicators![]() 」国連 ESCAP-世界銀行国際貿易コスト・データセットからの貿易コストの推定値を用いて策定された。所得水準、地理的地域、開発レベルの異なる163の経済が対象。
」国連 ESCAP-世界銀行国際貿易コスト・データセットからの貿易コストの推定値を用いて策定された。所得水準、地理的地域、開発レベルの異なる163の経済が対象。
85 OECD「TRADE FACILITATION AND THE GLOBAL ECONOMY:STATE OF PLAY IN 2017![]() 」
」
86 括弧内は貿易コストの削減率。
(3)WCO(世界税関機構)
WCOは、関税分類87や税関手続に関する諸条約の作成・見直しを行い、これらの統一的解釈を示すほか、国際貿易の安全確保及び円滑化に関するガイドライン等の作成・推進、WTOが主管する関税評価及び原産地規則に係る協定の統一的解釈及び適用のための技術的検討、関税技術協力の推進といった役割を担っている。
2006年にWCOで発効した国際条約である改正京都規約(通関手続の簡素化と調和に関する国際条約)では、税関業務の透明性・予見性の向上のほか、申告や各種貿易書類の標準化・簡易化、手続の簡素化、ITの最大限の活用、規制に基づくコンプライアンスを担保した適切な税関審査等が定められており、加盟国はこの規約を指針に貿易円滑化を遂行している。
なお、コロナ禍においては、同規約別表88に規定されている「救援物資の輸出入について推奨される税関の適切な対応」が迅速かつ簡易な輸出入手続を推奨するものとして注目された89。2020年4月には、WTOと共同声明を出し、医薬品、食品、エネルギーといった必需品の生産・流通に関わるグローバルサプライチェーンの混乱を最小化するために緊密に協力するとした90。
87 関税分類の代表的な統一システムにHS(Harmonized System)がある。ここで規定されるHSコードは国際貿易の98%を超える取引に利用されていることから、世界の貿易にとって不可欠なものとなっている。
88 特定別表J第5。WCO「INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION AND HARMONIZATION OF CUSTOMS PROCEDURES(as amended)![]() 」の241ページ
」の241ページ
89 具体的には、物品申告手続の簡素化や暫定的な措置、輸出の禁止や制限の撤廃、輸出関税等の免除等であり、救援物資の輸送を優先する指針となっている。
90 WCO NEWSROOM「WCO and WTO join forces to minimize disruptions to cross-border trade in goods 06 April 2020![]() 」具体的には、コロナの影響で変更した貿易関連情報を各国から収集し、それらの情報をWCOのホームページで公表することによって透明性の増大を図った。
」具体的には、コロナの影響で変更した貿易関連情報を各国から収集し、それらの情報をWCOのホームページで公表することによって透明性の増大を図った。
2.経済連携協定における貿易円滑化の取組
次に、近年締結された経済連携協定を取り上げ、貿易円滑化に関してどのような目標設定をしているのかを見ることとする。
(1)TPP11協定(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)
2018年12月末に発効したTPP11協定(以下TPP)では、第5章「税関当局及び貿易円滑化」91において、税関手続の予見可能性、一貫性及び透明性を確保するとともに、締約国間の協力の促進、国際基準への調和、通関手続の迅速化、行政・司法上の審査を確保すること等が規定されている。貨物の引取り許可に係る期限を設定し、関税評価を事前教示の対象とする等、WTOや過去の二国間EPAにはない新しい規定が盛り込まれている(第Ⅱ-1-5-10表)。
第Ⅱ-1-5-10表 TPP11による貿易円滑化の施策とメリット
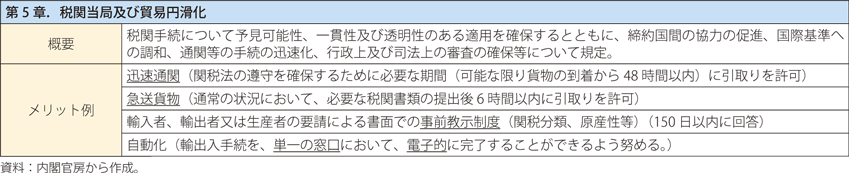
(2)RCEP(地域的な包括的経済連携)協定
まだ発効前ではあるが、2020年11月に署名が行われたRCEP協定では、第4章「税関手続及び貿易円滑化」において、貿易円滑化のルールが規定されている。TPPの条文と同様、従来の二国間EPAにはない数値的目標等が盛り込まれており、より実効性が求められる内容となっている。
目的や主な内容はTPPと重複しているが、TPPでは全12条であるのに対し、RCEP協定では全21条と構成が異なっているほか、照会先の設置(第4.6条)、船積み前検査(第4.8条)、物品引取り許可における腐敗しやすい物品についての規定(第4.11条)、認定事業者のための貿易円滑化に関する措置(第4.13条)、締約国間の協議要請(第4.20条)等、TPPにはない内容も盛り込まれている。
(3)USMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)92
1994年1月に発効したNAFTA(北米自由貿易協定:North American Free Trade Agreement)では、第2部(財の貿易)の第5章93(通関手続)が規定されていたが、2020年7月にその後継として発効したUSMCAでは、第7章(税関当局及び貿易円滑化)のセクションA(貿易円滑化)に置き換えられた。
USMCAの貿易円滑化にかかる内容は、WTOのTFAをモデルとした詳細条項に加えて、急送貨物、事前教示、税関法令遵守、税関手続の透明性等TPPで新たに盛り込まれた規定を加えた広範囲で時代に合った94ものとなった。
92 USTR「CHAPTER 7 CUSTOMS ADMINISTRATION AND TRADE FACILITATION Section A:Trade Facilitation![]() 」
」
93 米国商務省「NAFTA - Chapter Five: Customs Procedures![]() 」
」
94 例えば、7条2項(Online Publication)として、輸入、輸出、輸送(transit)に係る具体的な手続や書面、法律や規則、料金、問合せ先等は、無料で入手できるウェブサイトに掲載・更新しなければならない、という内容が新たに入っている。
3.地域経済における貿易円滑化の取組
ここでは、EUとASEANを取り上げ、貿易円滑化に関する取組や最近の動向を見ることとする。
(1)EU(欧州連合)
EUは、商品の輸出入・輸送について統一した取扱いをするため「連合関税法(UCC:Union Customs Code)」と呼ばれる共通のルールを実施しているユニークな地域である。加盟国間では関税は存在せず、EU域外からの輸入品には一律の関税制度が適用される。域外からの輸入品にかかる関税は、最初にEU圏内に入国したときに支払うが、それ以降は支払う必要はない。さらに、域内においては税関検査がないため、全ての商品はEU関税同盟内で自由に移動している。EU27か国の各税関が一体となって日常業務に当たり税関同盟(Custom Union)を機能させていることで、商品の越境が国内での移動と同様に円滑に行われている。
一方、英国はEU離脱によって2021年1月よりEUとの通関手続が復活した。これにより物流に混乱がおきている事例が報告されている95。例えば、輸出手続・輸送に時間がかかりすぎるために、新鮮な状態で輸送する必要がある魚介類の輸出を断念したり、輸出拠点を英国からEU加盟国の拠点に変更したりする事例である。なお、英国の中小企業連盟によれば、貿易手続コストは特に中小企業への打撃が大きいという96。
英国は離脱後もEUとの貿易には関税はかからないという恩恵は維持できたものの、通関手続が復活したことでこのような混乱が起きている。これは、貿易手続自体が大きなコストであることを改めて浮き彫りにしている97。なお、英国の2021年1月の対EU輸出額は季節調整済前月比-40.5%と過去最大98の落ち込みとなった一方、非EU向けの輸出は同3.6%と対照的な結果となった(第Ⅱ-1-5-11図)。
第Ⅱ-1-5-11図 英国の輸出(対EU・対非EU)
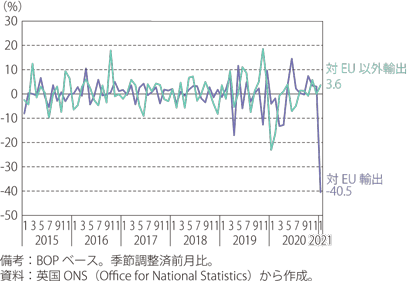
95 2021年1月はEUへの魚介類の輸出が前年同月比で83%も減少したほか、30ポンドのチーズ詰め合わせ1箱を輸出するのに180ポンドの追加コストが必要になったとの報道(日本経済新聞![]() 、2021年3月31日)がある。
、2021年3月31日)がある。
96 Financial Times(2021年1月28日)「UK’s small businesses struggle with Brexit red tape」。
97 なお、英国は物流停滞を防ぐため、EUからの輸入関連の貿易手続については、手続の復活に半年間の猶予を与える等、緩和措置である新たな通関制度を導入した。ここで取り上げたような問題となっているケースは、EUへの輸出関連の貿易手続である。
98 統計を取り始めた1997年以降で過去最大。
(2)ASEAN(東南アジア諸国連合)
ASEANは、「競争力、包括性、共同体意識を高める、シームレスで包括的に接続・統合されたASEANを実現する」というビジョン99のもと、ASEANマスタープラン2025を掲げ、様々なプロジェクト100を進行中である。
域内の貿易促進には優れた物流効率が求められる。ASEANマスタープラン2010101の履行により、物理的接続(ハードインフラ)、制度的接続(ソフトインフラ)の両面で進展はあったものの、輸送にかかる時間とコストについては当初想定したペースまでには至らなかった。その根本的な理由の一つは、政府省庁間の調整問題とベスト・プラクティスの共有不足であったと自ら分析している。
後継となるASEANマスタープラン2025においては、それらの課題に対処するために、物流企業、学術機関、加盟国間の協力関係を強化するメカニズムを構築し、サプライチェーンにおけるボトルネックを特定し、その解決方法に関するベスト・プラクティスを収集・共有し、留意すべき重要な政策分野を見極めることが求められている。
このような取組の蓄積の上に、貿易円滑化にかかる施策が進捗している。具体的には、各国の通関手続を電子化するナショナル・シングルウィンドウ(NSW)を接続した「ASEAN シングルウィンドウ(ASW)」、各国の貿易関連情報のデータベースであるナショナル貿易リポジトリ(NTR)を相互に接続した「ASEAN貿易リポジトリ(ATR)」、貿易投資の課題を解決するシステムである「ASEANサービス・投資・貿易課題解決枠組み(ASSIST)」、出発国から目的国まで、越境ごとの税金支払、荷物の積替えを不要とする税関通過管理システムである「ASEAN Customs Transit System(ACTS)」、貨物のセキュリティ管理と法令順守の体制が整備された事業者に対し税関手続の緩和・簡素化策を提供する「ASEAN認定事業者(Authorized Economic Operator:AEO)制度」、といった様々なシステムの構築が挙げられる102。
以上の様々な取組が実現すれば、貿易コストは大きく低下し、ASEAN域内貿易の拡大が期待される。国の発展段階に大きな開きがあるため、先発国が後発国の取組を引上げるための十分な協力を行えるかが課題の一つであろう。
99 The ASEAN Secretariat Jakarta「MASTER PLAN ON ASEAN CONNECTIVITY 2025![]() 」(2016)
」(2016)
100 ASEAN-BAC Legacy Project、ASEAN Smart Logistics Network、ASEAN Smart City Network等が挙げられる。
101 2015年までのアセアン共同体の創設に向けて、地域的、国家的、物理的、制度的及び人的連携を強化することにより、経済成長、開発格差の縮小及び連結性の改善を目指した。2009年10月、第15回ASEANサミットにおいて、ASEANコネクティビティに関する宣言を発出した。なお、この策定は、アジア開発銀行、世界銀行、UNESCAPと協力しERIAが貢献しており、2010年10月、第17回ASEANサミットで報告された。経済産業省ホームページ![]()
102 JETRO地域・分析レポート「特集:アジアで進展する貿易円滑化と現場の実態」。
4.デジタル技術を活用した貿易円滑化の推進
貿易円滑化における情報技術の活用は深化している。税関手続にかかる書面を紙媒体からPDFに置き換えるといったステージから、ブロックチェーン技術を利用し貿易業務にかかるデータを構造化、一元的に管理するといったステージに移行している。
ここでは、世界中で行われている貿易・物流情報に関するデジタルプラットフォームの開発や実証実験の動きを紹介する。
(1)海外の動き
近年、貿易円滑化を目的に、民間企業によるブロックチェーン技術等のデジタル技術を応用した、貿易手続の電子化サービスを提供する貿易プラットフォームが次々と台頭している。例えば、世界最大手の船会社であるMaersk Lineは、ブロックチェーン技術を活用したデジタルオープンプラットフォーム「TradeLens」を米国IBMと共同開発し、2016年より実証実験に着手、サービスを開始している。これにはPSA(シンガポール)やモダン・ターミナルズ(香港)等の大手ターミナルオペレーターや、ロッテルダム港やフィラデルフィア港等の港湾を含め、世界各国のターミナルや港湾、船会社、税関等が参加している。
以下(第Ⅱ-1-5-12表)は、大手貿易プラットフォームの概要を例示したものである。2020年に次々と登場していること、複数大陸で広くサービスを展開していることのほか、従来の電子化だけではできなかった、サプライチェーン管理、トレードファイナンスといった機能を備えていることが注目される。
第Ⅱ-1-5-12表 世界の大手貿易デジタルプラットフォームの概要
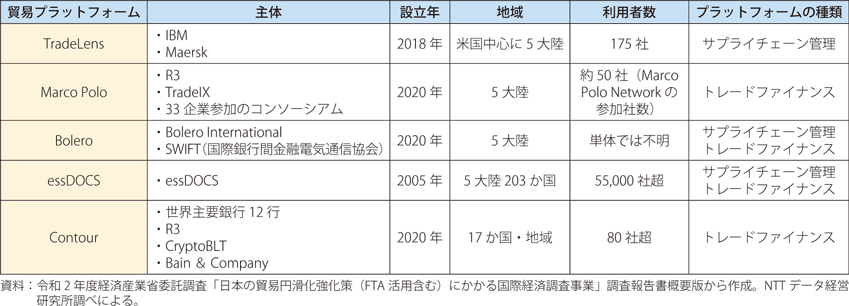
欧米の動きに加え、アジアでも貿易プラットフォームの取組が活発化している。中国、韓国、シンガポール等、アジア系の貿易プラットフォームは、国の公共システムと連携している点が注目される(第Ⅱ-1-5-13表)103。各国政府でも貿易関連手続の電子化政策に基づく、シングルウィンドウの構築等が進められている。
第Ⅱ-1-5-13表 世界の貿易デジタルプラットフォームのサービス範囲と機能

103 日本については、2021年にトレードワルツとNACCSがシステム連携する見込み。
(2)国内の動き
① NACCS
1978年に稼働したNACCS(Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System)は、船舶・航空機及び輸出入される貨物について、税関その他の関係行政機関に対する手続等民間業務のオンライン化を進めてきた。独立して稼動していた航空貨物の手続等を行うAir-NACCSと海上貨物の手続等を行うSea-NACCSを統合するとともに、国土交通省が管理・運営していた港湾EDIシステムや経済産業省が管理・運営していたJETRAS等の関連省庁システムについても統合し、2017年には、新たに損害保険会社を利用者に加えた第6次NACCSが稼働する等利便性の向上を図ってきた。
② TradeWaltz(トレードワルツ)
一方、先にふれた欧米の動きと同様、国内でもブロックチェーンを活用した貿易業務のデジタル化が進捗している。2020年4月、7社104が共同出資した業種横断の企業コンソーシアム、「TradeWaltz(以下トレードワルツ)」が設立された。事業内容は、ブロックチェーンを活用した貿易情報連携プラットフォーム「トレードワルツ」のSaaS(Software as a Service)提供・運営であり、従来は「壮大な伝言ゲーム」だった貿易業務を、業界横断で一元的に電子データにより管理することを目的としている(第Ⅱ-1-5-14図)。
第Ⅱ-1-5-14図 トレードワルツのイメージ
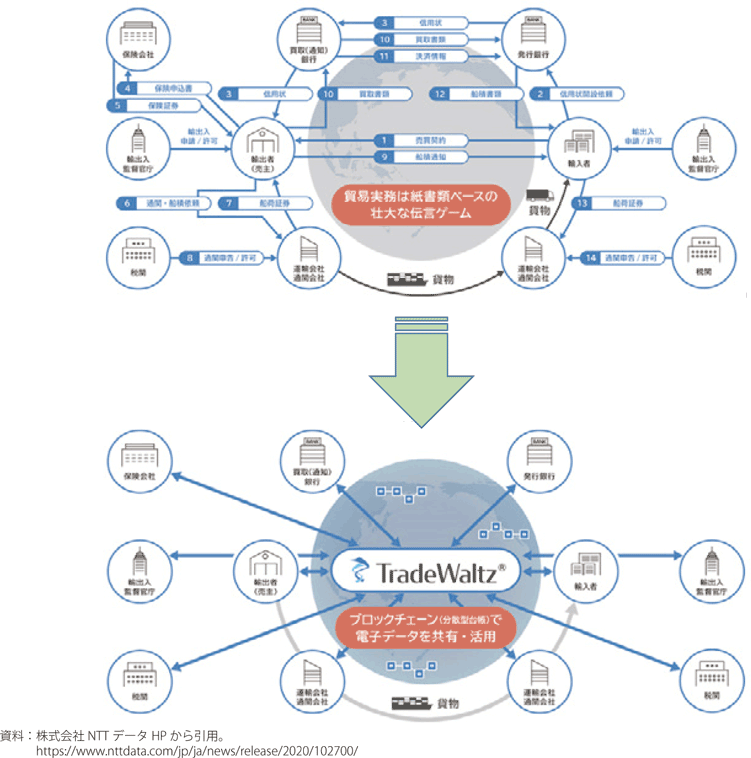
主な機能としては、ブロックチェーン技術105の活用による電子船荷証券・電子原産地証明書等、紙に代わる貿易情報の原本性の確保、企業が保有する自社システムやNACCS等の国内外貿易プラットフォームとのAPI接続による幅広いデータ連携、貿易書類をPDFではなく構造化データとして保存、データ利用時の重複入力排除やデータ利活用が挙げられ、貿易円滑化に大きく寄与することが期待される。
トレードワルツを導入した場合、荷主、銀行、保険会社、船会社、総合物流会社等業態を問わず、貿易プロセスの作業効率化、コスト削減が見込まれている。事前検証では、60%以上といった大幅なコスト削減効果が期待できるという結果106がでている(第Ⅱ-1-5-15表)。
第Ⅱ-1-5-15表 トレードワルツ導入による作業効率化・コスト削減の具体的内容
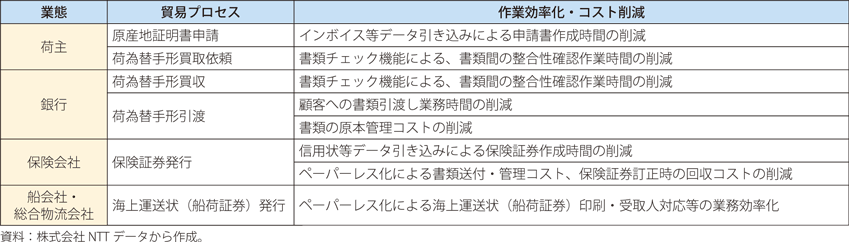
現時点では、サービスの対象地域は日本(及び対日貿易を行う本邦企業・グループ企業海外拠点)であるが、将来的には、世界の貿易取引をカバーすることを目指しており、海外へのノード展開や他の貿易プラットフォームとのアライアンス等による事業領域拡大を進めている。また、プラットフォームに蓄積された情報の活用やリアルタイム共有により、貿易金融、物流情報連携等更なる付加価値サービスが提供される予定である。
なお、「トレードワルツ」と「NACCS」は、2020年11月、国際物流の発展及び日本の国際競争力強化に寄与することを目的として、更なる国際物流・国際貿易業務のデジタル化の促進及び関係者の利便性向上に向けて、貿易情報連携プラットフォームとのシステム連携等を視野に、相互に連携、協力していくとする覚書(MOU)を締結した。
104 NTTデータ、三菱商事、豊田通商、東京海上日動火災保険、三菱UFJ銀行、兼松、損害保険ジャパン。
105 Hyperledger Fabric
106 トレードワルツによるPoC(概念実証)結果を受けた業界横断ヒアリング実施結果。図Ⅱ-1-5-15表の貿易プロセスのうち、銀行の荷為替手形引渡しのコスト削減が30~60%であるが、その他は全て60%以上の削減が見込まれるとの回答を得た。
③ その他の注目される動向
国内における貿易業務・物流に関しては、経済連携協定を活用する際に必要な原産地証明の手続や港湾物流手続のデジタル化を促進する動きも注目される。
(a)原産地証明書(certificate of origin:CO)の電子化
日本からの輸出において、第三者証明制度に基づきEPA上の特恵関税の適用を受けるためには、日本商工会議所が発給する特恵原産地証明書(certificate of origin、以下CO)107を輸出先国の税関当局へ提出する必要がある。輸出者から日本商工会議所への発給申請は全て電子申請で行われているものの、我が国が締結しているEPAでは、運用上の規則等でCOは書面と規定されていることが多く、輸出先国の税関当局はCOの紙原本(original)による提出を求めることが多い(なお、日本国税関当局においては、輸入申告時に、PDFファイル等でのCOの提出が可能となっている。)。このため輸出者がCOの発給を受けてから、輸入者への国際郵送(又は飛行機で人が運ぶ)を経て、最終的に輸入者がCO原本(original)を輸出先国の税関に提出するまでに一定の時間が必要となっている。
この多段階にわたるプロセスは事務コストも高く、COの紛失・遅延リスクもあるほか、非接触が推奨されるコロナ禍において見直しが急務となっている。この一連のプロセスを電子化するため、2020年12月に改訂された「総合的なTPP等関連政策大綱」においてCO等の電子化への取組が定められ、政府全体としてEPAを利活用した貿易ビジネス環境の整備に取り組むこととなっており、現在、関係当局108が連携し、COの電子化109を実現すべく、EPA相手国への働きかけ等に取り組んでいる110。
107 原産地証明法(「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」)上では「第一種特定原産地証明書」とされているもの。経済産業省が発給当局となっており、同法の規定により経済産業大臣が指定した発給機関である日本商工会議所が発給審査・発給事務を行っている。
108 経済産業省、財務省、外務省、日本商工会議所、NACCSセンター
109 CO電子化のアプローチとしては大きく、COをテキストベースのデータとして輸出国の発給機関から直接、輸出先国の税関当局に送信する「COデータ交換方式」と、輸出国の発給機関がCO原本をPDFファイルとして発給し、輸出者を経由して輸入者が当該PDFファイルを輸出先国の税関システム上にアップロード等を行うことによりCOの提出を行う「PDF発給方式」、の2つが存在する。
110 EPA上の特恵関税の適用を目的とした「特恵原産地証明書」に係る電子化に加え、それ以外の目的で使用され、各商工会議所において発給される「一般原産地証明書」についても、オンラインでの申請、発給が可能となるよう、2020年10月1日より順次運用が開始されている。
(b)Cyber Port(サイバーポート)
2021年4月より、「Cyber Port」の運用が開始された。これは、紙、電話、メール等で行われている民間事業者間の港湾物流手続を電子化することで業務を効率化し、港湾物流全体の生産性向上を図ることを目的としたプラットフォームである111。
現状では、各社のグループ内や特定の事業者間での電子化は進んでいるものの、港湾物流に関わるいずれの業種においても約5割の手続が紙、電話、メール等で行われているため、紙やPDFの情報を電子化するための再入力作業や、情報や手続状況の電話問合せ等、非効率な作業が発生している。また、同様の手続でも事業者ごとに書類様式・項目や接続方法が異なるため、個々に対応する必要が生じている。
今後は、利用者の利便性向上を目指し、国内外のプラットフォームとの連携112が期待される113。
111 Cyber Port![]() 。2021年4月時点では、一部の機能の運用を開始していないため、「第一次運用」としている。
。2021年4月時点では、一部の機能の運用を開始していないため、「第一次運用」としている。
112 netNACCSとの連携は実装済みである。NACCSとの直接連携(システム間自動連携)も早期に実現する予定と公表している。
113 なお、貨物の取扱いとして貿易手続が発生するのは、港湾だけでなく空港も該当するが、物流規模としては圧倒的に港湾の方が大きい。
5.貿易円滑化の今後の方向性114
世界的に関税が低水準になっている現在、各国が貿易を拡大し経済成長につなげていくためには、時間・費用両面で貿易コストを削減するといった貿易円滑化の重要性が増している。また特にアジア域内においては、サプライチェーンが深化しており、商品が中間品と最終製品の両方として何度も国境を越えることが多いため、貿易円滑化は企業活動に大きく影響する。
また、冒頭にも述べたように目下の世界規模のパンデミックにおいては、必要不可欠な医療品、食料品、及びIT供給品の迅速な移動を確保するために貿易円滑化が課題として改めて重要視されていることは、近年進捗している貿易手続のデジタル化を一層後押しすると考えられる。
貿易円滑化について政府ができることとして、OECDは以下三つを挙げている。
第一に、すべての手続を透明化し、すべての貿易業者、特に零細・中小企業が利用しやすいようにすること。第二に、標準的な手続を迅速化し、必要なコロナ関連の追加管理を行う余地を残すこと。第三に、可能な限り、全てのプロセスをデジタル化し、処理を迅速化し、国境機関と貿易業者の間の物理的な接触の必要性を減らすこと、である。
貿易手続の透明化と利便性確保は、全ての企業にとってメリットとなるが、OECDの分析では、中小企業の方が大企業よりもその効果が大きいという。税関手続や複雑な税関ルールといった貿易コストが、スケールメリットのない中小企業にとっては不釣合いに大きすぎるゆえに、国際貿易に踏み込めず国内への供給にとどまっている企業が多いという指摘である115。なお、ASEAN企業が輸入者としてグローバルバリューチェーンに参画する決定要因は何かを調査したところ、中小企業が国内通関の効率化を重要視していることに加え、大企業と比較してその重要度がより高いという結果が示されている(第Ⅱ-1-5-16図)116。
第Ⅱ-1-5-16図 ASEAN企業(輸入側)がグローバルバリューチェーンに参画する決定要因
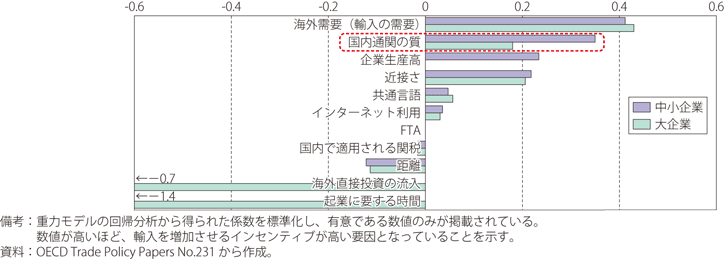
貿易円滑化に向けた取組は、新型コロナウイルスの感染拡大前から重要な課題であり、世界的にも、国内的にも着実に進捗していたものだ。しかし、今般のコロナショックによって最も打撃を受けたのが中小企業であったこと、世界各地でEC市場が拡大していることを考えれば、我が国グローカル企業の取引先を海外の幅広い企業に広げる観点からも重要である。
貿易円滑化は、企業のみならず政府や消費者も含めた関係者に利益をもたらす。例えば、国内市場に閉じていた中小企業が海外市場に供給できるようになるだけでなく、今まで入手できなかった物品を個人が気軽に輸入したりできるようにもなる。
また、貿易コストが下がることで、これまで取引がなかった途上国との貿易も期待されよう。途上国に対する貿易円滑化関連の支援及びキャパシティ・ビルディングへの支援等、国際協力も今まで以上に重要になっている。
114 OECD「OECD Policy Responses to Coronavirus(COVID-19)Trade facilitation and the COVID-19 pandemic![]() 」(2020年4月)
」(2020年4月)
115 Lopez-Gonzalez and Sorescu(2019)![]()
116 ASEANの日本GVCへの参加度合いは高く、日本から部材を輸入し、現地で加工・組立てを行うことが多い。その点では、ASEAN域内、ASEAN各国の輸入にかかる通関業務が効率化すれば、日本の部材供給の拡大が期待できる。OECD Policy Paper「Participation and benefits of SMEs in GVCs in Southeast Asia」(2019年9月)