第1節 サステナブル・インクルーシブな未来社会に向けた企業行動への期待の高まり
1.包括的なサステナビリティへの意識の高まりと金融面からの後押し
1990年代以降、グローバル化が急速に進展し、環境問題や人権問題などグローバル化の「負」の側面が顕在化してきた。このような地球規模の課題に対し、政府や国際機関だけでは対処できず、経済活動に大きな影響を与える企業への期待が大きくなってきている。企業への期待が高まる中、1999年の世界経済フォーラム(ダボス会議)では、国連のコフィ―・アナン事務総長(当時)が企業にグローバルな課題解決への参画を求め、企業と国連が共有できる価値についての世界的合意(グローバル・コンパクト:Global Compact)の形成を呼びかけた。翌2000年には国連グローバル・コンパクトが発足することとなった。その後、2011年には国連人権理事会において「ビジネスと人権に関する指導原則」が支持され、社内のみならずサプライチェーン上の人権問題についても意識が高まってきている117。並行して、世界各国でも国別行動計画の策定が進み、日本においても「ビジネスと人権」に関する行動計画が2020年10月に策定された。
2015年には、国連総会において「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択されたこともあり118、社会課題解決への機運がさらに高まってきた。この中に、17の目標、169のターゲットからなる持続可能な開発目標、すなわち、SDGs(Sustainable Development Goals)が含まれている。2030アジェンダの特徴は、課題の普遍性および不可分性に関する認識にある。SDGs以前の多国間のイニシアティブは、「気候変動」「生物多様性」「感染症」といった個別の課題を切り出して対処するものであった。2030アジェンダは、個々の課題の重要性ではなく、これらの課題がお互いに関連し、相互に依存しているという「相互関連性」を強調し「統合的な解決」を目指すところに大きな特徴があるといえる119。このように、SDGsの目標は広範かつ統合的であり、達成のためには年間5~7兆ドルが必要とも言及されている120。そのため、目標達成には政府や国際機関のみならず経済で中心的な役割を担っている企業を含め、多様な主体の関与が必要不可欠である。
日本においては、機関投資家の行動原則であるスチュワードシップ・コードや上場企業の行動原則であるコーポレート・ガバナンスコードの再改訂においてもサステナビリティの考慮が言及されるなど、意識の高まりが見られる(第Ⅱ-2-1-1図)。
第Ⅱ-2-1-1図 ESGやSDGs等に関連するイニシアティブ
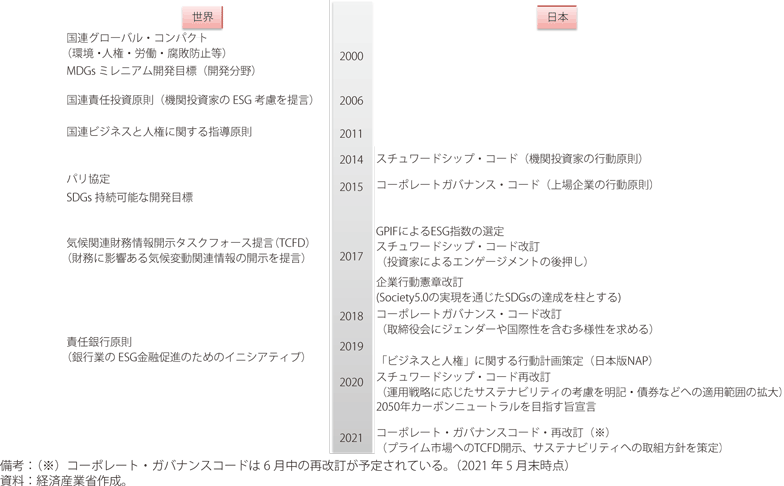
前述のとおり、国際機関などによるイニシアティブが数多く打ち出されたこともあり、ESG投資を始めとするサステナブル投資も拡大している。総資産運用額に占めるサステナブル投資の割合を見ると121、米国の割合は2016年の約21%から2018年には約26%にまで上昇している122(第Ⅱ-2-1-2図)。
第Ⅱ-2-1-2図 欧州・米国・日本の運用総額に占めるサステナブル投資の割合(2016年→2018年)
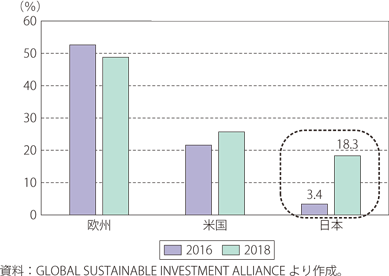
日本においてもサステナブル投資が加速した背景には、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)がPRIに署名したことも挙げられる。日本の割合は欧米の水準には達していないものの、2016年の約3%から2018年には約18%と6倍近くの規模にまで拡大しており、2020年には、さらに上昇している。日本においても、サステナブル投資への資金流入が加速しているといえよう。
先に示したサステナブル投資額123は日本サステナブル投資フォーラムが国内の47の機関投資家124に行ったアンケートに基づくものであるが、調査対象となった47機関の運用資産に占める割合は半分を超えている(第Ⅱ-2-1-3図)。47機関の運用資産は、日本の運用総額の4割以上を占めており日本の資産運用に占める割合は大きく、大手の運用機関であることから企業へのエンゲージメントを通じた影響力は小さくない。
第Ⅱ-2-1-3図 日本の運用総額に占めるサステナブル投資の割合
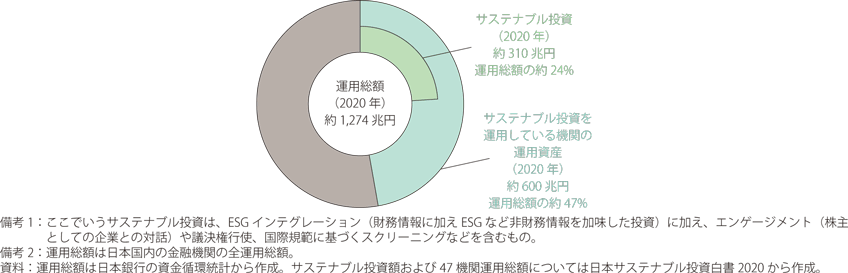
また、2020年の特徴として、個人向け金融商品におけるサステナブル投資の伸びが顕著であることから、サステナブル投資の裾野が広がっていることが伺える125。
117 Global Compact Network Japan(2016)「The Ten Principles of the UN Global Compact![]() 」、2021年6月
」、2021年6月
118 外務省「2015年9月28日報道資料」、(外務省Webサイト)
119 南、稲葉(2020)蟹江(2020)村上、渡邊(2019)
120 UNCTAD(2014)
121 欧州においてはサステナブル投資の基準が厳格化したことが割合低下の要因の一つ。
122 Global Sustainable Investment Alliance(2018)
123 ここでいうサステナブル投資は、ESGインテグレーション(財務情報に加えESGなど非財務情報を加味した投資)に加え、エンゲージメント(株主としての企業との対話)や議決権行使、国際規範に基づくスクリーニングなどを含むもの。
124 45の機関投資家へのアンケート調査に加え、2機関(年金積立金管理運用独立行政法人、地方公務員共済組合連合会)の公開情報を基にしたデータを加え47機関としている。
125 Japan Sustainable Investment Forum(2020)
2.企業へのSDGs/サステナビリティの浸透
こうした世の流れからSDGsを始めとする社会課題に対して取り組む企業が増えている。実際に、JBICの2020年度調査によると126、大企業においては「SDGsを経営方針や事業に組み込んでいる」と回答した企業が約3割、「SDGsを広報・CSRなどに組み込んでいる」と回答した企業が約4割となった。このように、大企業においてはSDGsを意識し取組を実施している企業が少なくない。また、現状としては、大企業の方が中堅・中小企業に比べて取組が先行しており、とりわけ「広報・CSR」については大きな差があるといえよう(第Ⅱ-2-1-4図)。
第Ⅱ-2-1-4図 SDGsの浸透状況(企業規模別)
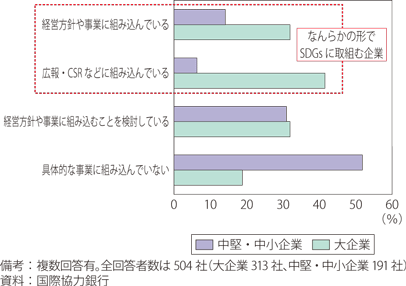
次に、日本企業がSDGsに取り組む動機について業種別にみると、中堅・中小企業の多い自動車や一般機械などでは「調達元・納入先からの要請」が比較的多く見られた(第Ⅱ-2-1-5図)。主要業種以外でも、とりわけ非鉄金属、鉄鋼、紙・パルプ・木材といった素材産業においてこの傾向は強く見られており、今後、グローバルサプライチェーン上で取引先として選ばれ続けるためにもSDGsへの対応が必要な要素となり得ることが伺える。また、「投資家との関係維持」を選択した企業は化学で多く、主要業種以外では石油・ゴム、窯業・土石製品といったエネルギーを多く消費する産業において、投資家からのSDGs対応への要請が高まっていることが分かる。
第Ⅱ-2-1-5図 SDGsに取り組む動機(製造業セクター別)
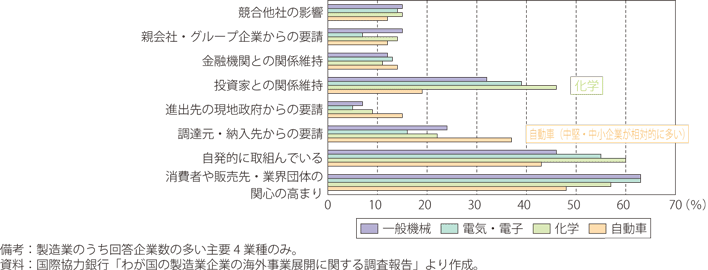
加えて、SDGsに取り組む動機について企業規模別の違いに着目すると、大企業においては「投資家との関係維持」と答えた企業の割合が中堅・中小企業の約6倍近くあった。実際に、企業へのヒアリングにおいても、ESG投資に多くの資金が流れており、こうした外部環境の変化への対応は大きなビジネスチャンスになり得るとの認識が示された127。他方、中堅・中小企業においては「調達元・納入先からの要請」が多かった128。大企業は投資家からの要請が、中堅・中小企業はサプライチェーン上での要請が強い動機付けとなっていることが伺える。
また、製造業以外も含む全業種への企業アンケートにおいてもSDGsへの貢献によって企業価値が向上すると認識している企業は多く、特に企業のイメージアップや社員のモチベーションアップにも資すると考えられている(第Ⅱ-2-1-6図)。
第Ⅱ-2-1-6図 SDGs達成への貢献で向上する企業価値
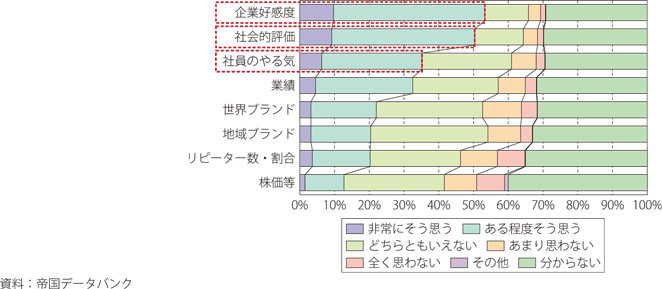
さらに、企業の情報開示という側面からも、統合報告書やサステナビリティレポートの開示等において、非財務情報であるESGなどへの取組を開示する企業も増えている。企業が多様なステークホルダーに対し、こうした取組について説明が求められている現状が伺える(第Ⅱ-2-1-7図)。
第Ⅱ-2-1-7図 統合報告書発行企業数の増加
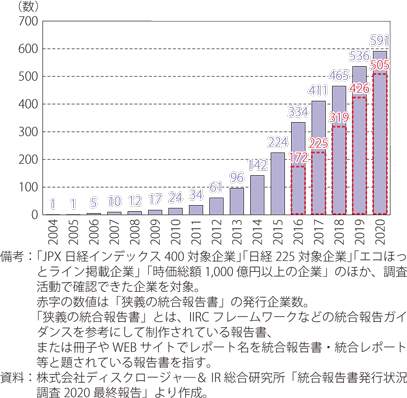
企業がSDGsやサステナビリティ上の課題に取り組み、持続的な価値創造へとつなげていくにはどのようなメカニズムが考えられるだろうか。ここではそういった社会課題に企業が取り組む意義について、企業の価値創造の観点から整理する。
126 国際協力銀行(2021)
127 みずほ情報総研(現みずほリサーチ&テクノロジーズ)(2021)
128 国際協力銀行(2021)
(1)新しい市場機会の創出・獲得
目標達成に向け企業の力を必要としているSDGsは、新しい価値観の元で需要が生まれる新市場の源泉でもある。2017年の世界経済フォーラムで報告されたレポートであるBetter Business Better Worldにおいて、SDGsに関連したビジネス分野として、「食料と農業」、「都市」、「エネルギーと原材料」、「健康と福祉」の4つの経済分野が言及されている129。それぞれの経済分野についてみると、まず、「食料と農業」には食品廃棄物の削減に関わる技術、低所得者層向け食品市場などが含まれる。次に、「都市」を見ると手頃な価格の住宅の建設市場、エネルギー効率の高い建物市場、電気自動車およびハイブリッド車などの市場が含まれている。さらに、「エネルギーと原材料」にはサーキュラービジネスや再生可能エネルギーなどの市場が含まれている。最後に、「健康と福祉」分野には、遠隔医療や患者の遠隔監視のサービス、保険市場などが含まれている。
この4つの経済分野で実体経済の約6割を占めており、この領域において少なくとも12兆ドルの市場を生み出し、3億8,000万人の雇用を創出するとされている。特に、2030年に最も市場規模が大きくなると予想されているのがモビリティ分野である(第Ⅱ-2-1-8図)。実際、CASE(Connected:つながる、Autonomous:自動運転、Shared and Service:シェアリングサービス、Electric:電動化)やMaaS(Mobility as a Service)といったものに代表されるように、様々な新しいサービスが出てきている。自動車産業におけるデジタル社会への変化、脱炭素の追求と都市化への対応という地球環境問題を解決する時代の到来、ミレニアル世代130およびZ世代131の登場という大きな潮流がこういった動きをさらに後押しするとみられている132。世界人口に占めるミレニアル世代以降の人口の割合は、2020年時点でみても既に約6割を超えており影響力は小さくない。さらに、日本においても2035年には全体の過半を超えると予測されている(第Ⅱ-2-1-9図)。
第Ⅱ-2-1-8図 2030年における市場機会
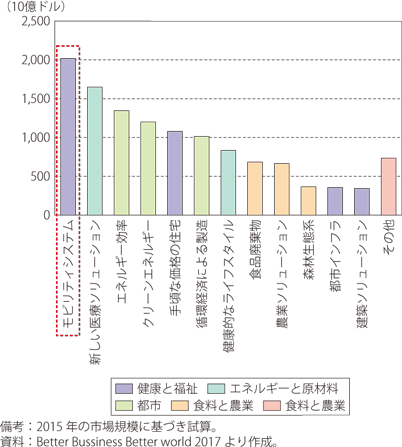
第Ⅱ-2-1-9図 人口全体に対するミレニアル世代以降に生まれた人口の比率増加
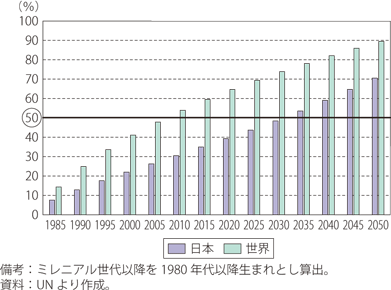
また、前述の4分野を地域別にみてみると「食料と農業」の市場機会のうち71%、「健康と福祉」の60%を途上国が占め、途上国における機会創出が期待される分野といえる。他方で、「都市」「エネルギーと原材料」は途上国のみならず先進国においてもビジネスチャンスは大きいといえよう(第Ⅱ-2-1-10図)。
第Ⅱ-2-1-10図 期待される市場機会のシェア(途上国・先進国)
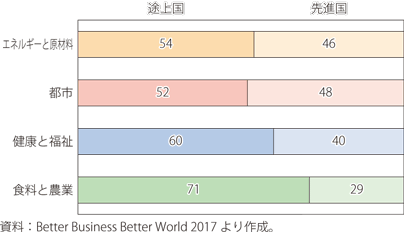
前述の通り、有力な市場となり得る地域は経済分野によって異なってくる。具体的には、「都市」の中でも、建物の効率化は先進国と途上国それぞれで大きな可能性をもつビジネスチャンスの一つである。他方で、手頃な価格の住宅の建設は途上国におけるビジネスチャンスが大きいとされる。手頃な価格の住宅は「都市」の経済分野の中でも、潜在的な7,000万人分の雇用がこの分野から創出されると推計されている。年間約1兆ドルの投資があれば、この分野だけで中国で2,000万人、アフリカでは1,300万人、インドでは800万人の雇用が創出できると推定される133。これは、低・中所得国において、資本投資の必要性が非常に高く、特に手頃な価格の住宅やその他の重要なインフラへの投資の必要性が高いこと、また、途上国経済において労働集約度が高いことから投資による雇用創出効果が大きいことが要因であると考えられる。
また、「エネルギーと原材料」に関しては、先進国・途上国でほぼ均等に市場ポテンシャルが見込まれ、再生可能エネルギーの拡大は、世界的に低炭素への移行が加速していることから、所得水準の異なる地域間においても大きなポテンシャルとなっている。他方、耐久消費財を始めとする循環型経済モデルは先進国市場で先んじて発展することが想定され、特に米国で最大の機会を見込むと言及されている。
次に、「食料と農業」分野においては、アフリカとインドにおいて市場機会創出が大きく見込まれているが、これは耕作地の割合が大きいことや現在の生産性が低いことに起因すると考えられる。
また、「健康と福祉」分野においては、医療へのアクセスが低いとされる途上国や、医療費が高い米国及びカナダに市場ポテンシャルが相対的に集中している(第Ⅱ-2-1-11図)。
第Ⅱ-2-1-11図 期待される市場機会創出額の地域別シェア(食料と農業、都市、エネルギーと原材料、健康と福祉)
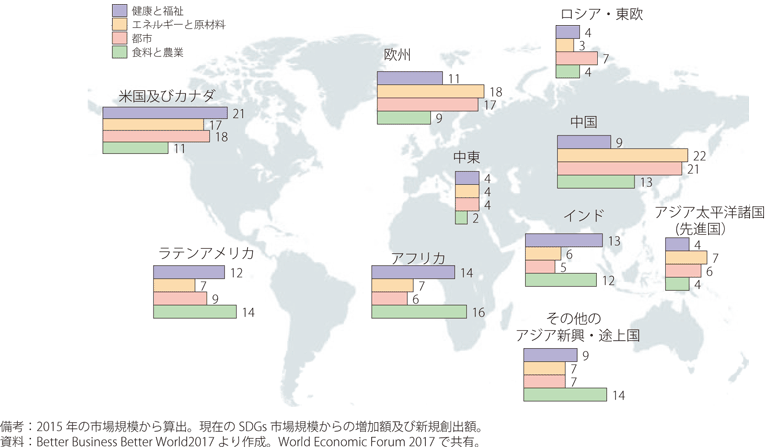
このように、社会課題への貢献から見込まれる市場規模は決して小さくない。人口増加や経済発展に伴う従来型の市場拡大のみを念頭に置くのではなく、SDGsを始めとする新しい価値観に由来するマーケットの拡大を捉えることも今後は求められよう。
経済界においてもそうした必要性を認識している経営者が増加している。世界CEO意識調査によると134、気候変動対策の取組が自社の製品やサービスにとってビジネスチャンスとなり得ると答えた経営者が、世界的にみても10年前と比較し大幅に伸びている。環境問題への意識が比較的高い先進国のみならず、インドやブラジル、中国など新興国においても経営者の意識が変わりつつある。特に、中国においては、10年前は回答全体の2%の経営者に留まっていたものの、2020年には回答全体の約5割の経営者がビジネスチャンスと捉えている(第Ⅱ-2-1-12図)。
第Ⅱ-2-1-12図 気候変動をビジネスチャンスと捉える経営者の増加
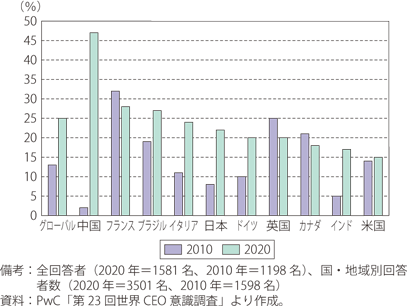
SDGsに象徴されるサステナビリティへの関心の高まりは、経営者のみならず消費者の意識変化としても表れている。欧州5か国の550の小売業者を対象にした国際貿易センター(ITC)2019年の調査によると135、回答者の85%が直近5年間でサステナブルな商品の売上げが増加していると答えている。
欧州と比較すると、日本の消費者の意識はまだ高くない現状も指摘されているが、日本においても少しずつ意識の変化が伺える。消費者庁の調査136によると、2016年に比べ2019年にはエシカル消費・サービスに対し意欲的な人の割合が約6割から約8割に増加する結果となった。さらに、エシカル消費につながる商品・サービスを通常の商品・サービスからどの程度割高であれば購入するかという問いに対し、「1~10%程度」高額でも支出を許容すると答えた人の割合は、家電・贅沢品、衣料品、食料品、その他生活用品いずれの品目においても2016年と比較して増加した(第Ⅱ-2-1-13図)。
第Ⅱ-2-1-13図 エシカル消費への支出額許容範囲
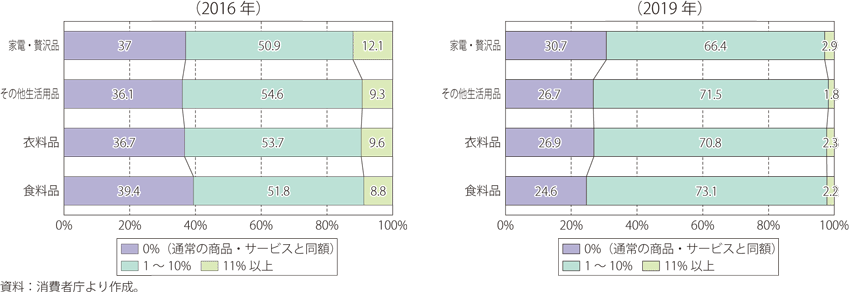
PwCが日本で実施した調査によると、日用品の購入の際に環境に配慮された商品を優先的に考慮する層(ディープグリーン層)が全体の約2割、ある程度考慮する層(ライトグリーン層)が全体の約4割を占める結果となった137。ただし、全ての層において9割以上の人が「サステナブルな商品であっても品質の悪い商品には妥協できない」と回答しており、品質も考慮されていることが分かる。
日本とASEAN諸国と比較してみると、エシカル消費に対して一般的な商品よりも多く金額を支払うと回答した人の割合が81%と日本の77%を上回っている138。国別にみても、インドネシアを除くASEAN諸国において、エシカル消費への支出に対し20%以上多く支払っても良いと考えている人の割合が日本より大きい。日本よりも若年層が多いことにより、若者の意識が反映されていることにも起因していると考えられるが、ASEAN諸国に進出している日系企業にとっても無視できない消費者の意識の変化であることは間違いない(第Ⅱ-2-1-14図)。
第Ⅱ-2-1-14図 エシカル消費への支出額許容範囲(ASEANとの比較)
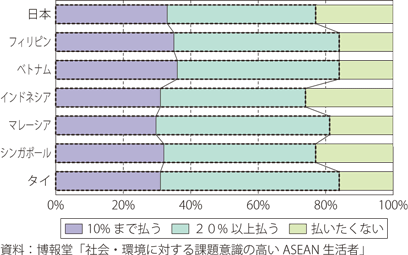
このように、サステナビリティへの意識の高まりが、新たな市場を創出するという端緒となるのみならず、既存の企業の提供する財やサービスの価値が、価格と安全性や耐久性といった品質に加えエシカルなどの価値観をも含めて評価される可能性を示しているといえよう。
129 4つの経済分野から特に市場規模の創出が大きい60市場についても言及されている。
130 ミレニアル世代の定義については様々あるが、ここでは1983年1月~1994年12月生まれと定義。
131 Z世代の定義については様々あるが、ここでは1995年1月~2003年12月生まれと定義。
132 深尾(2018)
133 Better Business Better World 2017
134 PwC(2020)
135 International Trade Centre(2019)
136 消費者庁(2020)
137 坂野、磯貝(2021)
138 博報堂(2020)
(2)人材の獲得・維持
企業の競争優位を支え、イノベーションを生みだす資産は人材である。企業の長期的価値を生み出していく資産となり得る優秀な人材を確保していくうえで、企業の社会課題の解決に向けた取組は不可欠になってきている。一般的に「ミレニアル世代139」「Z世代140」と呼ばれる世代においては、環境や社会問題への意識が高いと言われており、就職の際の優良企業選別の材料としてESGやダイバーシティ経営なども考慮するようになってきている。例えば、「就活生の企業選びとSDGsに関する調査」によると、企業の社会貢献度の高さが就職志望度に影響したと回答した就活生は約65%にもおよび、影響が小さくないことを示している(第Ⅱ-2-1-15図)。実際、大企業・中小企業と会社の規模を問わず、企業がSDGsに取り組むことは優秀な人材の確保につながる可能性があるとの声も企業から聞かれた141。また、こういったSDGsを始めとする社会課題への取組は従業員のエンゲージメントを高めるとも言われている142。
第Ⅱ-2-1-15図 企業の社会貢献度の高さによる就職志望度への影響
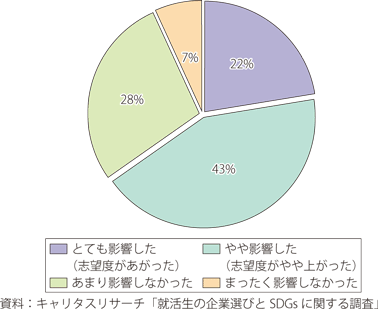
さらに、日本に限らずグローバルでみてもミレニアル世代およびZ世代の社会課題への意識は非常に高い。Pew Research Centerの調査によると、米国において、ミレニアル世代とZ世代は、社会課題解決に向けた政策に対し、関心を向ける人々の割合が他の世代よりも大きいとの指摘もある143。さらに、実際にどういう課題に対し懸念を抱いているかをグローバルで実施された調査結果から見てみると144、例えば、ミレニアル世代、Z世代ともに世界が直面する課題のうち、気候変動・環境保護への意識が最も大きく、その他にも、失業や医療、所得格差など幅広い分野に高い意識が見られている(第Ⅱ-2-1-16図)。
第Ⅱ-2-1-16図 懸念する社会課題
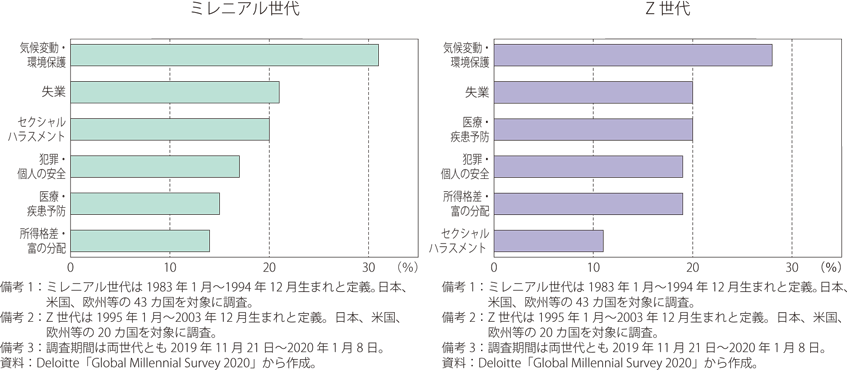
2025年にはミレニアル世代以降の生産年齢人口に対する比率も大きく上昇し、従来の資本主義的価値観からサステナビリティを重視する価値観へより変化していくことが想定され、こうした流れはますます加速すると考えられる。
139 ミレニアル世代の定義については様々あるが、ここでは1983年1月~1994年12月生まれと定義。
140 Z世代の定義については様々あるが、ここでは1995年1月~2003年12月生まれと定義。
141 みずほ情報総研(現みずほリサーチ&テクノロジー)(2021)
142 経済産業省(2019)
143 Pew Research Center(2020)
144 調査では43カ国13,715名のミレニアル世代、20カ国4,711名のZ世代の回答を得た。
(3)企業活動による負の影響への対応の必要性
サプライチェーン上における環境や人権の管理については、多様なステークホルダーの問題意識が高まってきており、企業活動の負の影響にも対応する必要が生じている。実際に、企業のレピュテーションリスクに関わるような問題が生じると、NGOや消費者団体によるネガティブキャンペーンや不買運動が起これば、売上の低下、ひいては株価の低下にも繋がるおそれもある145(第Ⅱ-2-1-17図)。
第Ⅱ-2-1-17図 事業リスクの例
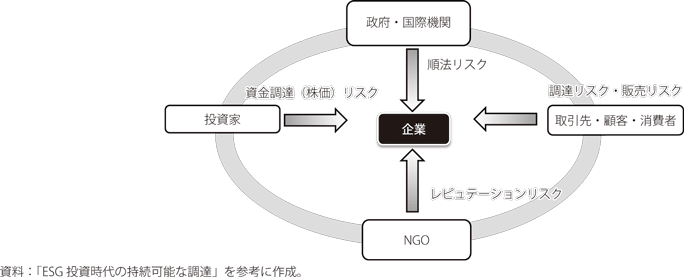
企業のビジネスがグローバル化するにつれ、取引先や顧客も多様化し、自社周辺の限定的な範囲だけでなく、企業活動が影響を及ぼす範囲が拡大してきている。例えば、遠いアフリカの鉱山で働く労働者や原材料を輸入するアジアの環境資源にまで広がってきている。すなわち、サプライチェーン上の作り手が守られ、土台となる「環境」が保護され、将来世代の需要を満たせるような行動が求められてきている146。
そのような要請を法制化したものとして、サプライチェーン上の人権侵害リスクの特定や評価、追跡、開示を求める「人権デュー・ディリジェンス」を企業に義務化させる動きが先進国を中心に複数国に広がりつつある。グローバルに事業を展開しサプライチェーンが各国にはりめぐらされている企業は既に対応を始めている。さらに、人権保護を理由とした輸出管理や輸入規制を導入する欧米の動きも見られ、詳細については第Ⅱ部第1章第3節を参照されたい。
145 冨田(2018)
146 田瀬(2020)
3.企業価値評価におけるサステナビリティの考慮
社会課題に企業が取り組むことへの社会的要請の高まりは、企業価値評価方法の変化という形でも表れている。
まず、企業価値を財務的な面から評価する方法から見ていく。財務的な価値とは企業活動によって得られる収益の総額や有形・無形資産が生み出すキャッシュフローを考慮した金銭的価値のことであり、投資判断の基準であるとともに企業の資金調達において、大きな影響を及ぼしてきた。
そのうち、将来的なキャッシュフローを生み出すという期待の表れ、すなわち、投資家からの将来価値への期待ともいえるPBR147(Price Book-Value Ratio株価純資産倍率)に着目する。
2012年と足下の2020年と比較すると、日本企業のPBRは大きく改善していることが伺える。しかし、従来、日本企業のPBRは欧米企業よりも低いことが指摘されてきた148。2020年の足下で見ても、PBRが1を上回っている企業の割合は欧州企業、米国企業より少ない(第Ⅱ-2-1-18図)。
第Ⅱ-2-1-18図 PBRの国際比較(企業数分布割合)
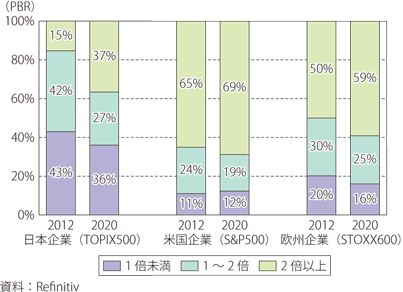
また、全体だけでなく、自動車や建設などを含む耐久消費財の業種、消費財や食品などを含む非耐久消費財に分類される業種を見ても、欧米企業と比して日本企業のPBRが相対的に低いという傾向となっている(第Ⅱ-2-1-19図)。
第Ⅱ-2-1-19図 PBRの国際比較(企業数分布割合)
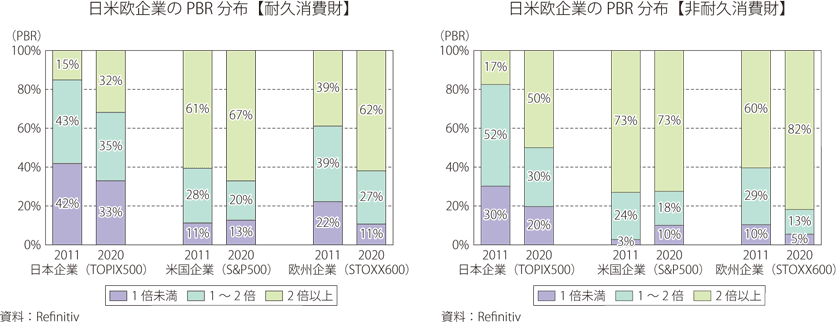
いくつかの調査研究では、財務面における企業価値を決定する要因が有形資産から無形資産に移ってきていることが指摘されている149。先に述べた日本と米国・欧州企業の市場評価の違いの一部は無形資産の評価にも起因すると考えられる。
無形資産とは会社が持っている経営資源(将来、キャッシュフローを生み出すと期待される資産)のうち、知的財産権、人材や技術、ノウハウなどの資産のことを指す150また、高い生産性を有するコンピューターソフトウェアや研究開発などに加え、企業イメージ(ブランド価値)やサプライヤーや金融機関、顧客とのつながりである関係資本、組織構造や文化などの組織力なども無形資産とされる(第Ⅱ-2-1-20図)。
第Ⅱ-2-1-20図 財務情報と無形資産
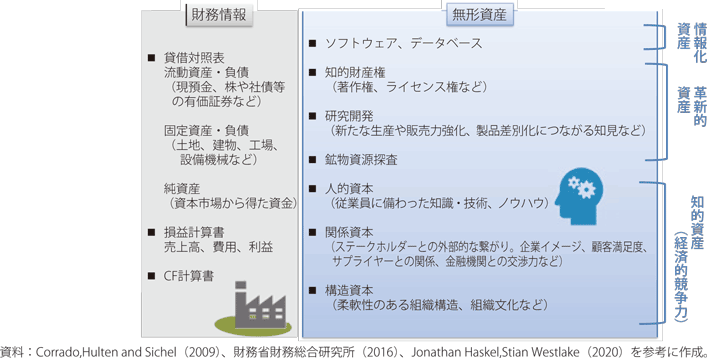
ここで、企業にとっていかに無形資産の重要性が増しているかを示すために、無形資産の特徴について整理していく。
会社が有する建物や機械設備など、目に見えて会計上も認識・計上できる資産である有形資産と違い、無形資産は見えづらく会計上の認識・評価が難しいという特徴がある。これには、有形資産と異なる無形資産の特徴があるからである。無形資産には、①拡張しやすい(Scalable)②組み合わせやすい(Synergy)③模倣されやすい(Spillover)④市場で転売しにくい(Sunk Cost)という4つの特徴があると指摘されている151。
もちろん、有形資産によって安定的にキャッシュフローを生み出すビジネスモデルもある。具体的には、素材産業やインフラ産業のように、巨大な有形資産を抱えることによって、コスト面での優位性を確保してきた例が挙げられる。しかし、デジタル技術が発達したことにより、外部の有形資産を集約するような無形資産の重要性がより増している。また、無形資産は模倣されやすく減価しやすいことから、一過性ではなく持続的に価値を生み出していくような知識創造のプロセス、組織の「仕組み」が必要となってくる。人材育成、経営管理、ブランドマネジメントなど組織の仕組みが企業の価値創造を維持・拡大していく上での基盤となる。知識経済化が進む今日では、人的資本や技術や知的財産などの知的資本などへ投資をしていくことが企業のイノベーションを生み出し、中長期的に企業の稼ぐ力や競争優位性を維持・強化することに繋がる。さらに、自社の技術やノウハウ、アイデアと他社のアイデアなどと結びつけることでシナジー効果で価値を増やし、ビジネスの成長に合わせ規模を大きくしていくことでより大きな価値を生み出せると考えられる。
そこで、ここでは無形資産の一つである知的財産への投資で日米を比較してみる。先ほども述べたように、無形資産は知的財産にとどまらず幅広い資産が対象となるが、国際的に共通に計測されているものを一つの指標として利用する。日本の無形資産への投資額がほぼ横ばいで推移しているのに対し、米国の無形資産への投資は堅調に推移しており安定的に投資が増加していることが見て取れる(第Ⅱ-2-1-21図/第Ⅱ-2-1-22図)。米国企業に比べ日本企業は、競争優位性の源泉となる無形資産への投資が相対的に不十分である可能性がある。
第Ⅱ-2-1-21図 米国の無形資産投資
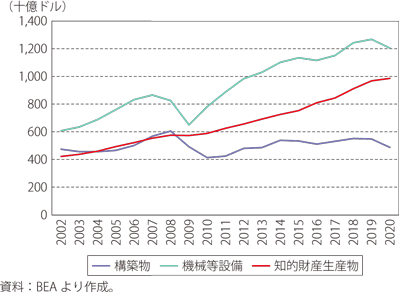
第Ⅱ-2-1-22図 日本の無形資産投資
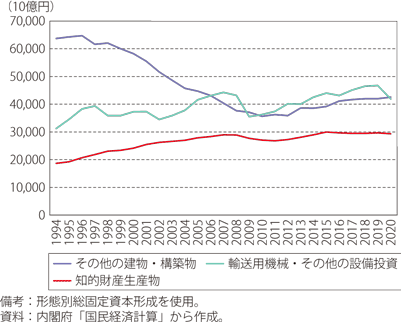
続いて、有形・無形資産の投資合計に占める知的財産投資の割合の推移を見てみると、世界金融危機以降、割合がほぼ横ばいである日本に対し、米国やユーロ圏は堅調に推移していることが分かる(第Ⅱ-2-1-23図)。
第Ⅱ-2-1-23図 実質総固定資本形成に占める知的財産投資
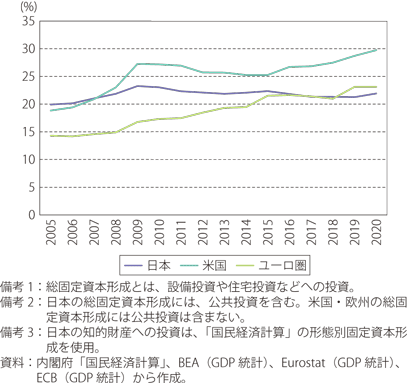
知識経済化が進むとともに、新型コロナウイルス感染拡大など不確実性が高まる状況において、サステナビリティへの関心の高まりや技術革新といった長期的な外部環境変化を想定し、企業にとっての「リスク」と「機会」を把握した上で企業としての稼ぐ力を強化していくために、日本企業には今後より無形資産への投資が求められる。
加えて、ESG投資の拡大は企業の無形資産の評価も変えつつあることにも注意が必要である。ESG投資は、環境(Environmental)や社会(Social)への取組を企業の財務的な価値評価に取り込んだものと言える。実際の企業価値評価については、企業の経営方針やそれに基づく企業行動、情報開示の在り方や評価する側の価値観に依るところが大きいが、例えば、企業が社会課題解決に取り組み、社会価値の向上と経済価値向上を結び付ける経営を継続するための「仕組み」も無形資産と考えられ、評価の対象ともなり得る152。
また、社会課題への貢献を可能にする取引先や顧客との関係などの関係資本や人材といった無形資産もより評価されうると考えられる。
さらにコロナショック後、ESGの中でも特に「S(Social)」に重きをおく流れが加速すると指摘されている153。実際に、世界のESG債発行額は大幅に増加してきており、2019年には総額3,206億ドルだった発行額が6,037億ドルと2倍近くにまで伸びているが、2020年の特徴として特筆すべきは、グリーンボンドの発行額がほぼ横ばいなのに対し、ソーシャルボンドの発行額が大きく伸びていることである。2015年には33億ドルにすぎなかった発行額が1,669億ドルまで増額しており、金融面からもソーシャル部門への後押しが見られる(第Ⅱ-2-1-24図)。
第Ⅱ-2-1-24図 ESG債発行額の推移(グローバル)
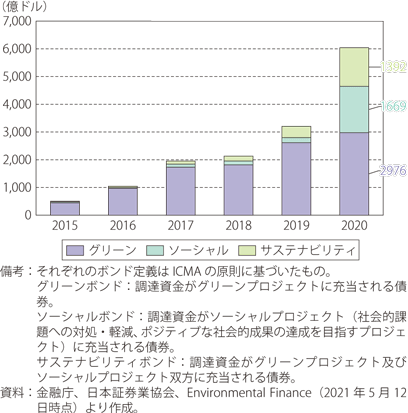
ソーシャルボンドにより調達された資金は、1日あたりの収入が一定以下(1.25~5ドル)の人々に対する食料や飲料水へのアクセス向上のための社会活動への資金拠出や特定の栄養素を必要とする乳幼児や妊婦、高齢者に向けた高度な医療栄養素の研究費用などに充当されている154。
日本におけるESG債の発行額も増加基調にある。さらに、注目すべきは2020年の日本のESG債発行額のうちソーシャルボンドの占める割合が、グリーンボンドを上回ったことである(第Ⅱ-2-1-25図)。ソーシャルボンドにより調達された資金は、例えば、介護を必要とする高齢者向け施設を提供する企業への投融資や自然災害からの復興に寄与する資金供給などのプロジェクトに充当されている。
第Ⅱ-2-1-25図 ESG債発行額の推移(日本)
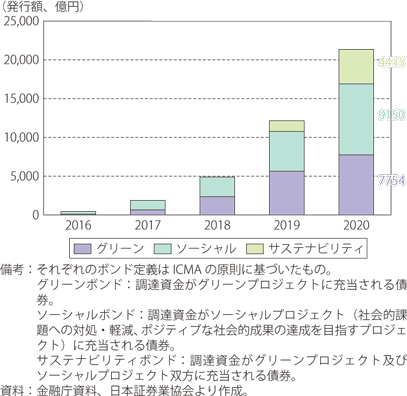
このような社会課題解決に資する取組への評価が高まるのと並行して、従前の株主・投資家には考慮されていなかった「インパクト」を考慮する動きも出ている。
インパクトとは、個人や個社の効用を超えて社会の課題解決に影響を与えることによって生まれる価値のことをいう。ESGが主に企業活動の結果が企業の将来的な財務に与える影響に着目しているのに対し、インパクトは主に企業活動の結果がどのような成果を生み、社会にどのような影響を与えたかという点に注目しているケースが多い。インパクト、アウトカム、アウトプットの違いについて155、国連食糧計画(WFP)の学校給食支援の生み出す価値を例に紹介する。まず、事業を行うために必要な資源(ヒト・モノ・カネ)をインプットすることで、給食を提供するという直接的な結果、アウトプットが出てくる。当該事業の結果がもたらす間接的な変化や便益については、アウトカムと定義される。具体的には、学校で給食が提供されることで、学校に通う児童が増え、児童の栄養状態が改善することが期待される。さらに、定期的に通学する児童が増え、教育機会が確保され、ひいては、就業機会の機会を得やすくなり将来の選択肢が増えるということが効用として期待される。さらには、学校給食で提供される食材を地域の農家から確保することで、地域の農家の農産物の販路を確保することができる。それに伴い、農家の所得安定および生産性の向上につながり、地域経済の活性化が想定される。教育機会の確保や地域経済の活性化から、地域の貧困の解消というアウトカムが生み出される。短期・長期といった時間軸に関わらず事業の結果として生じたアウトカムが社会的インパクトとして捉えられる。
第Ⅱ-2-1-26図 企業価値評価の範囲
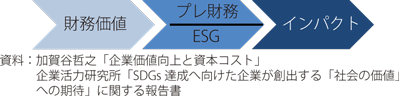
このように、財務の観点及びプレ財務ともみなされるESGの観点において企業のサステナビリティへの課題対応が評価されるようになりつつあり、さらに、より広範な社会的価値を評価するインパクトに着目する動きもでている(第Ⅱ-2-1-27図)。このことは、企業の投資家との対話、情報開示のあり方についても影響を及ぼす。環境や社会課題対応を可能にする企業の仕組みは、有形資産や金融資産のように定量化・可視化が容易でない。そのため、他社との比較も可能なかたちで投資家に伝えることは必ずしも容易ではなく、国際的な標準を作るための議論も行われている156。長期的に事業を継続していく上でも、投資家を含むステークホルダーとの認識の共有は重要である。企業が価値を創造していくにあたり、社会や環境を含めた外部環境をどのように解釈するかについて外部の視点を取り入れることができ、長期的な時間軸での自社のリスクと事業機会を捉えた経営戦略立案に資するからである。また、投資家を含むステイクホルダーによる理解があることが事業を円滑に進める上でも支えとなる。
第Ⅱ-2-1-27図 IR優良企業と市場における評価
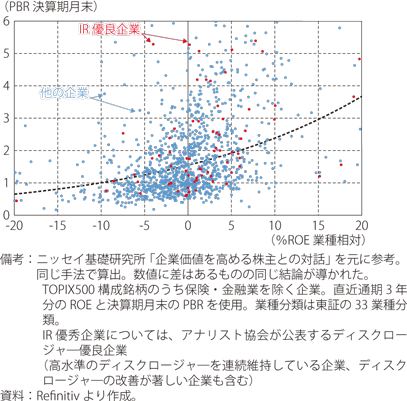
既に、企業と投資家との対話、ディスクローズやIR(Investor Relations)に注力している企業は株式市場で評価が高い傾向にあるとの指摘もある157。ROE(自己資本利益率)とPBRの関係をプロットすると、日本証券アナリスト協会が選定したディスクロージャ―優良企業は全体平均(指数近似した傾向線)よりもPBRが高い傾向が見られた。ディスクロージャ―優良企業として選定された企業のうち近似線よりもPBRが高い企業の割合は55%と、選定されなかった他の企業の45%を1割近く上回っている(第Ⅱ-2-1-27図/第Ⅱ-2-1-28表)。今後、企業の有する無形資産からどのような価値を生み出すか、またそれがどのような社会的価値に貢献するのかについて、企業が外部のステークホルダーに説明することがこれまでよりも一層重要になることは論を俟たない。情報開示を重視する企業においては、自社の無形資産やビジネスモデルが適切に評価されるよう、国際的な基準作り等の議論において提供される意見発信の機会を有効に活用することが望まれる。
第Ⅱ-2-1-28表 近似線を上回るIR優良企業の割合
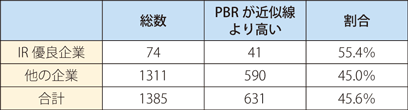
147 PBRは会社の純資産(Book-Value)と現在の株価(Price)の比較
148 経済産業省(2017)
149 Lev Baruch, Gu Baruch, Gu Feng,伊藤邦雄訳(2018)
150 無形資産の範囲については、米国における代表的な研究であるCorrado、 Hulten and Sichel の一連の研究も参考になる。CHSによると、無形資産は「情報化資産(computerized information)」、「革新的資産(innovative property)」「経済的競争能力(economic competencies)」の三つに大別される。情報化資産には、ソフトウェアやデータベースなどが該当する。革新的資産については、研究開発のほか、鉱物資源調査、著作権・ライセンス、デザインなどが含まれる。次いで、経済的競争能力にはブランド資産(広告宣伝費などのマーケティング関連資産)や人的資本、組織構造などが該当する。
151 Jonathan Haskel, Stian Westlake, 山形浩生(2020)
152 経済産業省(2019)
153 MSCI(2021)
154 金融庁
155 社会的インパクト評価イニシアティブ(2017)
156 IFRS財団によるInternational Sustainability Standards Boardについての検討![]() 。
。
157 ニッセイ基礎研究所(2019)「企業価値評価を高める「株主との対話」」。