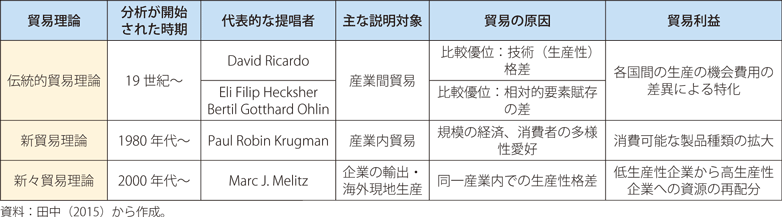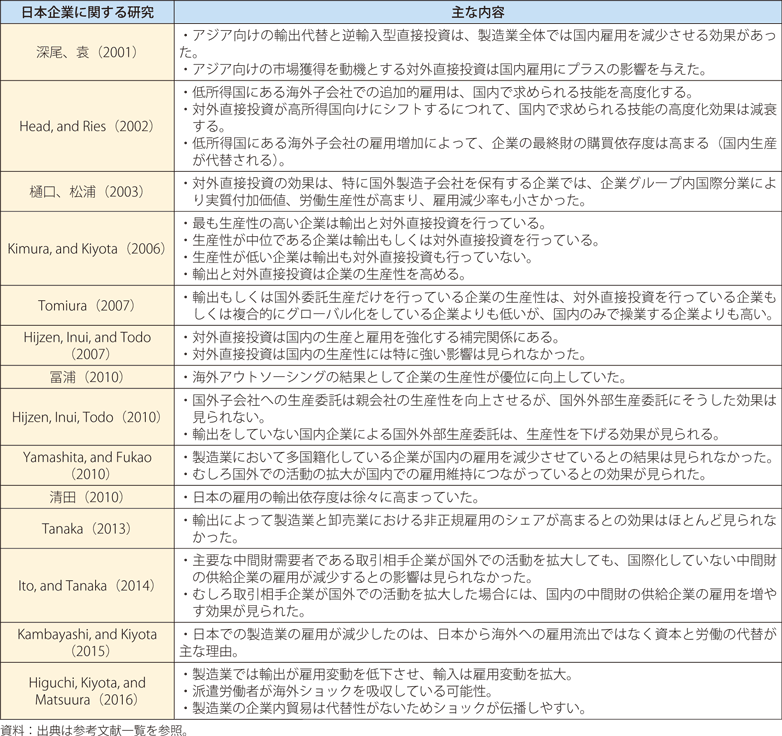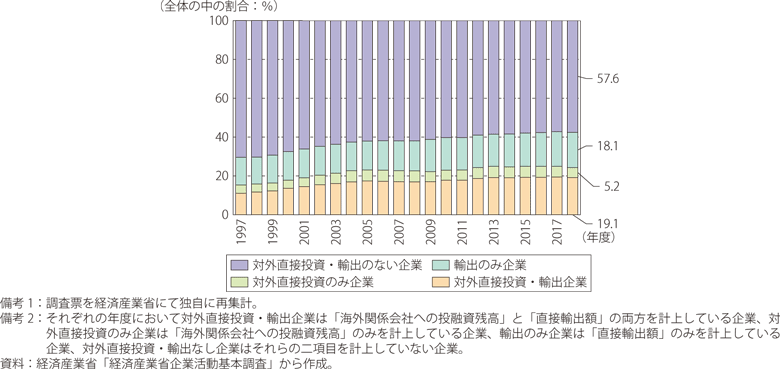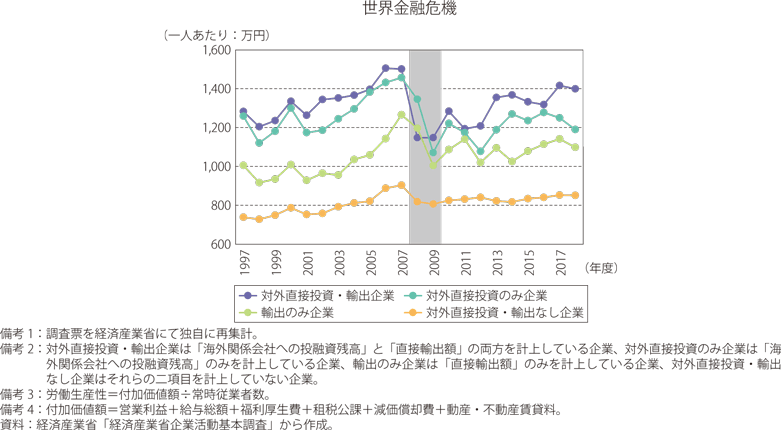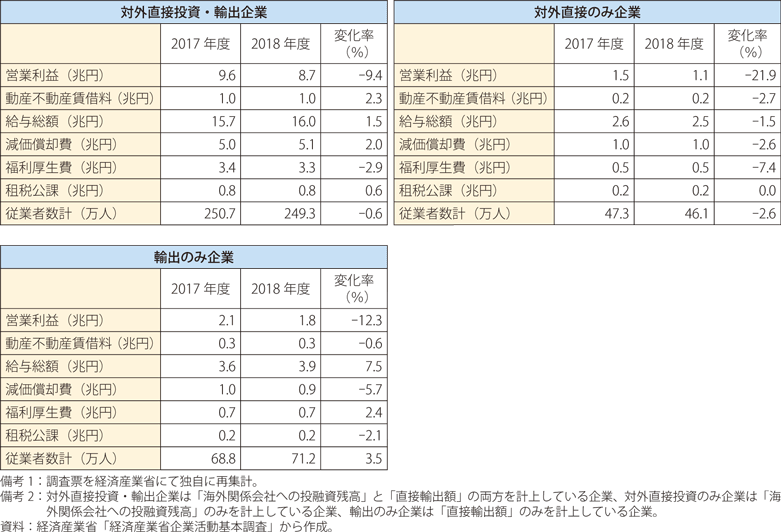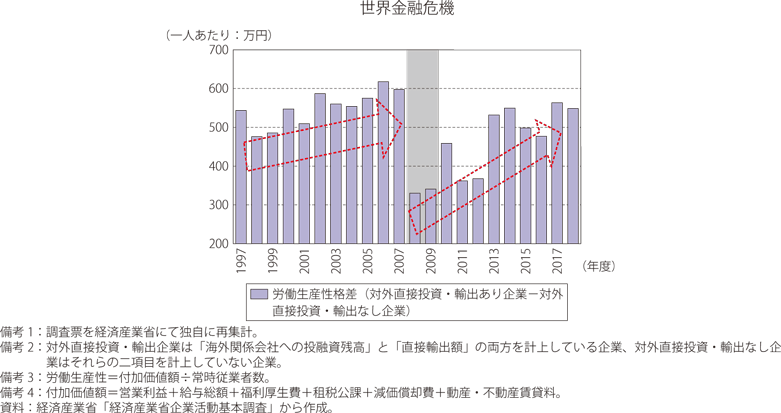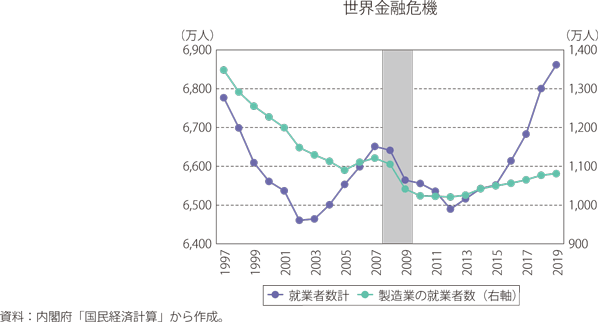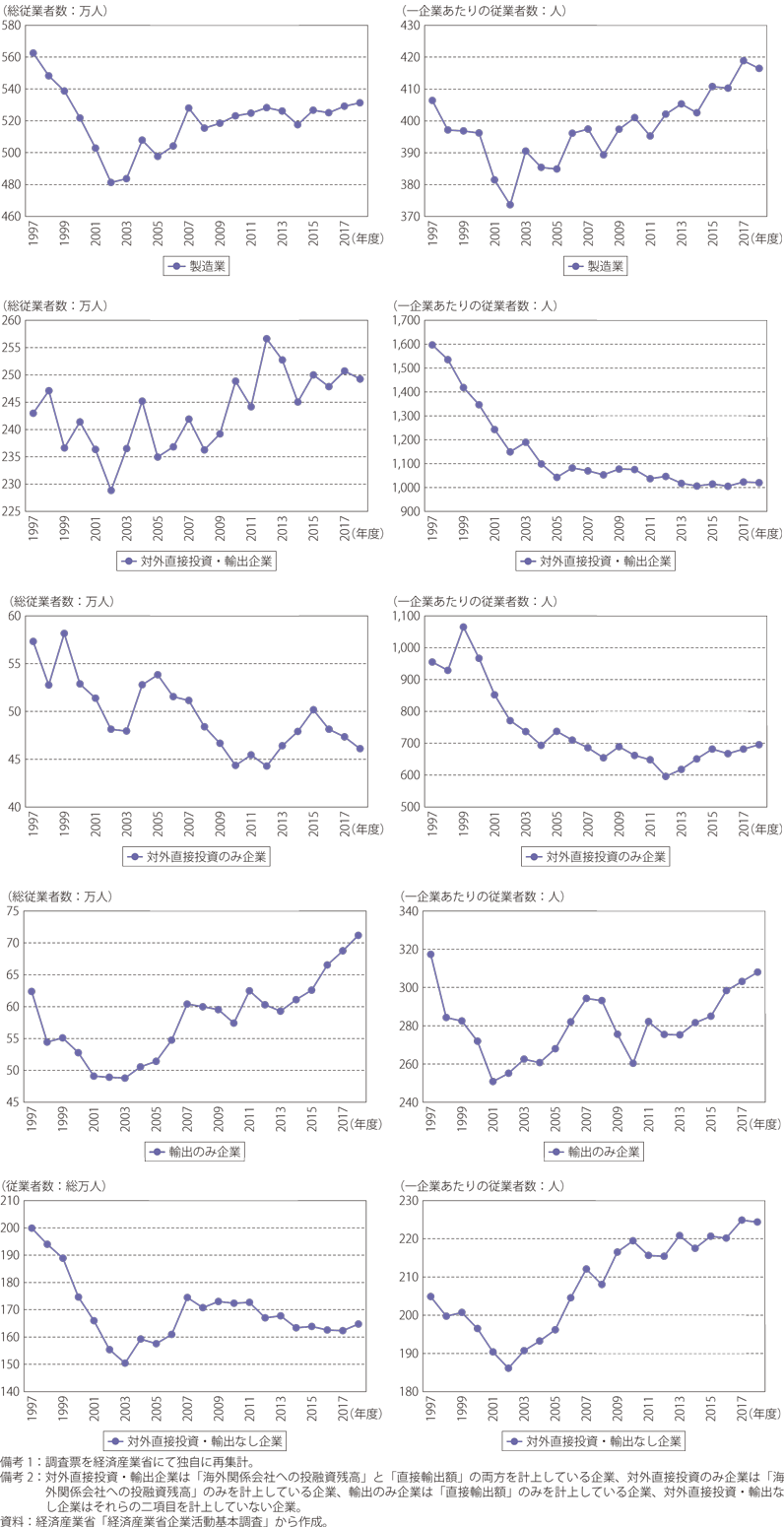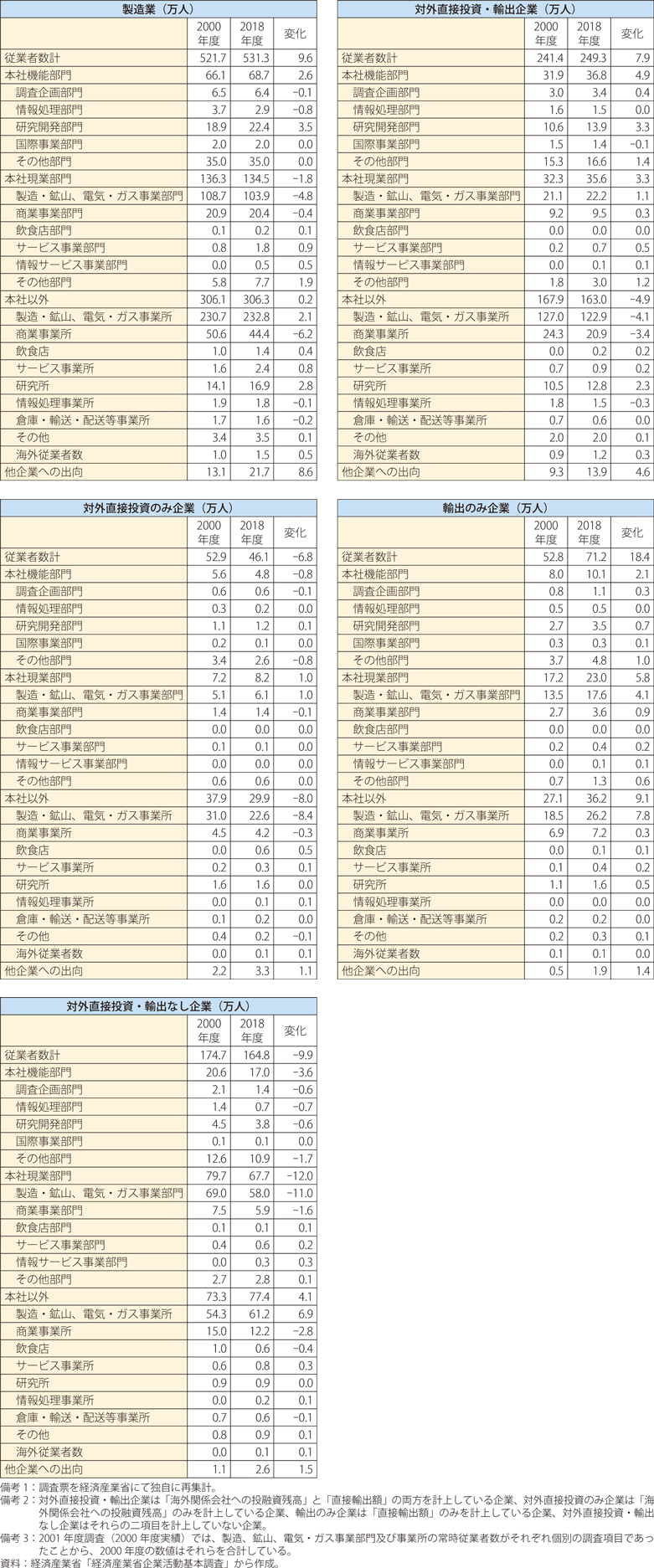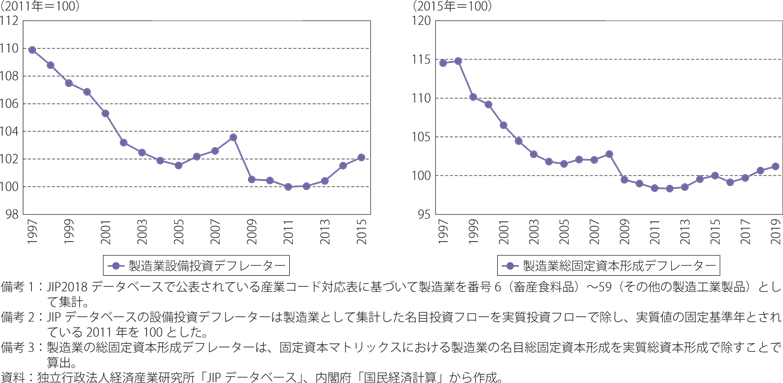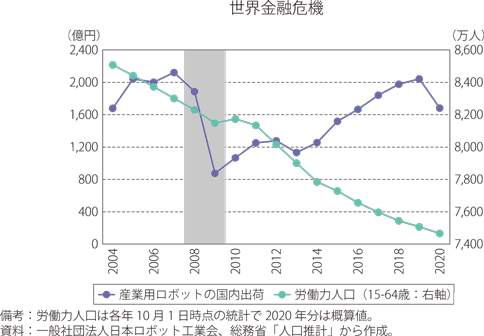第2節 サステナブル・インクルーシブな成長ニーズへの対応
1.ASEAN、インド等への視点
安い豊富な労働力という強みを活かし、工業化と財の輸出、資本の増強等を通じて高成長を遂げてきた中国は世界経済の牽引役であり続けている。その一方で、中国の抱える構造的な問題、経済発展に伴う賃金の上昇などは、特に労働集約的な部門で中国に代わる新たな生産拠点を模索する契機になっている。昨今の米中貿易摩擦や新型コロナウイルス感染拡大もアジア地域におけるサプライチェーン見直しの気運を高めている。
労働集約的な部門の担い手としての「ネクスト・チャイナ」、あるいはサプライチェーン戦略としての「チャイナ・プラス・ワン」の候補地として、高い経済成長率や労働コストなどの観点からベトナムや「ラストフロンティア」としてのカンボジア、ラオス、ミャンマー、中国に次ぐ人口大国であるインドなどに関心が集まっている。またASEANの中でもシンガポールのような高所得国やタイ、マレーシア、インドネシアといった比較的早い段階で低所得国から中所得国に移行した諸国には日本企業も多く進出しており、次世代技術の開発や社会実装など新たなビジネス機会の創出が期待されている。特にアジア新興諸国におけるデジタル経済化の動きは、革命的ともいえるスピードで展開している。日本としてもこれからの経済社会の在り方を考える上で多くの示唆を得ることができよう。
実際、これらアジア新興諸国158の経済成長のスピードは目覚ましい。他地域の新興諸国と比較するとその違いは顕著である。1970年時点を1として途上国・新興国地域の実質GDPの足下までの変化を見ると、おおよそ東南アジアが14倍、南アジアが9倍となっており、アフリカの5倍、南米の4倍を大きく上回っている(第Ⅱ-2-2-1図)。貧困労働者比率159も急速に低下している(第Ⅱ-2-2-3図)。
第Ⅱ-2-2-1図 途上国・新興国地域の実質GDPの変化(1970年=1)
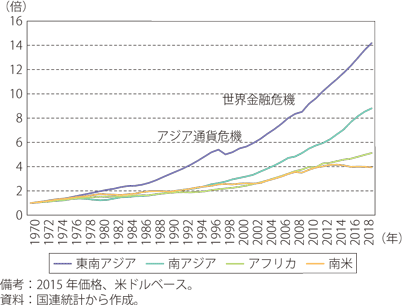
第Ⅱ-2-2-2図 ASEAN諸国、インド等の実質GDPの変化(2019年対1970年)
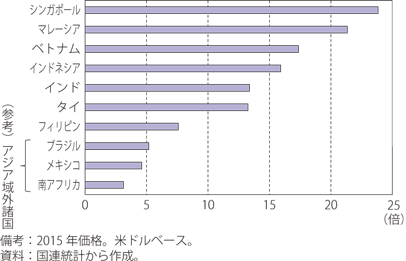
第Ⅱ-2-2-3図 貧困労働者率
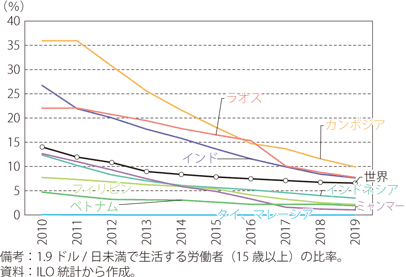
ここではASEAN、インド等のサステナブル・インクルーシブな成長ニーズに関係すると考えられる幾つかの点について概観する。
158 発展途上の国々の分類・定義には「発展途上国」「後発国」「新興国」等、幾つかの概念がある(伊藤(2020))。本節ではインド、ASEAN諸国を便宜上「アジア新興(諸)国」と呼ぶ。
159 人口に占める貧困者数全体の比率の時系列データがそろっていない国もあり、ここではILO統計の貧困労働者(ワーキングプア)比率を用いた。
(1)人口
アジア新興諸国の特徴の一つとして、人口の多さ、人口構成の若さが挙げられる。2020年時点(推計)において東南アジア(ASEAN10か国)で6.7億人160、南アジアで19.4億人(うちインド13.8億人)と合わせて約26億人(世界人口の約33%)がこれらの地域で生活している。同じく2020年時点(推計)の世界人口の中央年齢は30.9歳であるが、東南アジアは30.2歳、南アジアは27.6歳(インドネシアは29.7歳、フィリピンは25.7歳、カンボジアは25.6歳、ラオスは24.4歳、インドは28.4歳)とより若い(ちなみに中国は38.4歳、日本は48.4歳である)。若年人口(15~24歳)は4.6億人と世界の40%近くを占めている。
第Ⅱ-2-2-4~5図はアジア各国の生産年齢人口比率の推移(5年ごと)を見たものである。この比率の上昇に伴う潜在成長力を人口ボーナスと呼ぶ161。同比率が上昇している期間を各国の「人口ボーナス期」と捉えてみると、既に人口ボーナス期が終了した又は終了しつつある国もあるがインド、フィリピン、カンボジア、ラオス、ミャンマーは今後も続く見通しである。
第Ⅱ-2-2-4図 各国の生産年齢人口比率の推移①
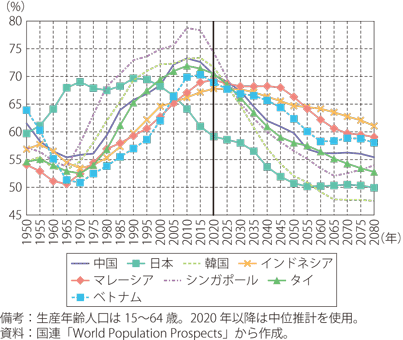
第Ⅱ-2-2-5図 各国の生産年齢人口比率の推移②
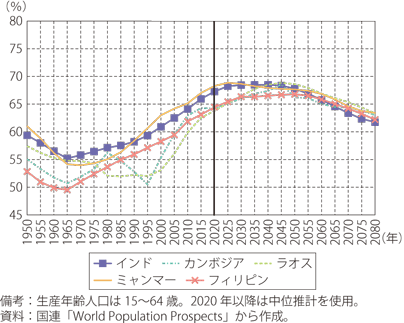
注意すべきは、大泉(2018)が述べているように、生産年齢人口の規模や伸び率が自動的に経済成長に結びつくわけではないという点である。人口ボーナスの顕在化を促すような政治・経済・社会環境や制度、人口構成の変化に適した政策が必要であり、そうした環境整備、政策的措置が十分に行われない場合には、失業者の増大を招くなど、人口ボーナスは逆にリスクにもなる可能性がある。本節2.で取り上げる持続可能で包摂的な成長をめぐる課題は、アジア新興諸国の強みとすべき人の力を活かしていくための課題であるともいえる。
160 United Nations(2019)“World Population Prospects 2019”。本パラグラフ中の人口の数字はこれによる。
161 大泉(2018)。生産年齢人口が非生産年齢人口よりも多い状態を指したり、年少従属人口比率の低下、生産年齢人口比率の上昇による経済成長へのプラス効果を指したり、論点により「人口ボーナス」の定義は複数存在すると述べられている。
(2)多様性(産業構造、輸出、経常収支について)
自然や地理、また、言語や文化といった長い歴史の中で培われてきたものが多様な相を示していることは論をまたないが、ここでは経済的側面、特に産業構造や輸出、経常収支の状況からアジアの多様性について考えてみることにしたい。
アジア新興諸国の多くは貧困段階を脱し中所得国入りしているが、一人当たり所得(一人当たりGNI)の水準は一様ではない。ASEANでは高所得国のシンガポールの約6万ドルからミャンマーの1,390ドルまで大きな開きがある(第Ⅱ-2-2-6図)162。
第Ⅱ-2-2-6図 一人当たりGNI(2019年)
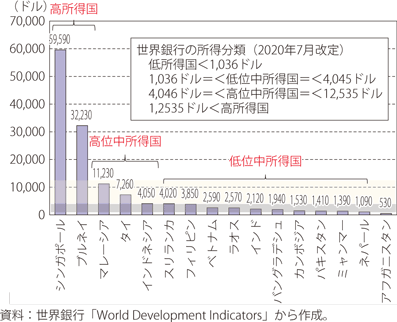
足下の産業構造、就業構造も国により多様である(第Ⅱ-2-2-7~8図)。高所得国であるシンガポールはサービス産業の比率が70%を超えているが、製造業の比率も20%程度ある。ブルネイの産業構造は特殊で鉱業、ユーティリティが40%以上を占める。製造業の比率が相対的に高いのはタイ、ミャンマー、マレーシアであるが、ミャンマーはカンボジア同様、農業の比率も20%以上ある。就業者の産業別内訳では、サービス業の比率が高いシンガポール、ブルネイと農林水産業の比率が高いラオス、ミャンマーと様々である。就業者比率を所得段階や経済発展段階によって単純に特徴づけることが難しい側面もある。高所得国であるシンガポール、ブルネイ、高位中所得国であるマレーシアでサービス業就業者比率が高くなっていることは一定程度想定されるが、高位中所得国のタイではその比率は50%に満たず、低位中所得国のベトナムやカンボジアと同様、農業就業者比率が30%を超えている163。一方、低位中所得国であるフィリピンのサービス業就業者比率はマレーシアに匹敵し、農業就業者比率はタイよりも小さい。またGDPの比率が大きい産業に就業者が多く従事しているシンガポールのような国もあれば、GDPの比率の小さい業種(例えば農業)に就業者が多く従事しているラオスやミャンマー、インドのような国もある。
第Ⅱ-2-2-7図 ASEAN、インドの実質GDPの産業別比率(2019年)
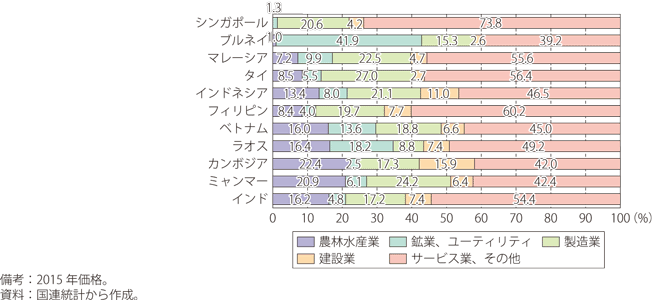
第Ⅱ-2-2-8図 ASEAN、インドの就業者の産業別比率(2019年)
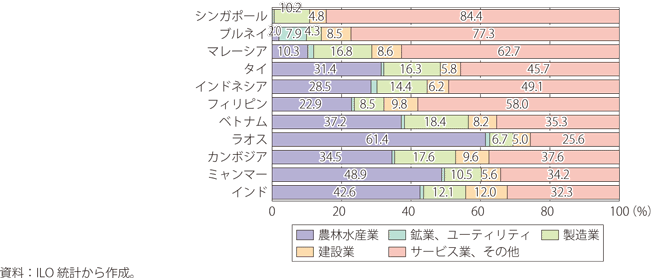
経済発展に伴い、農業から工業へ、工業からサービス産業へといった産業構造が変化していくパターンの表れ方も国によって様々である(第Ⅱ-2-2-9~10図)。シンガポールやマレーシア、インドネシアは2000年頃まで、タイは2010年頃まで製造業比率が上昇しており、工業化の進展が明確に読み取れる。一方、インドでは1970年代から50年近くを経てもGDPにおける製造業の比率はほとんど変化しておらず、足下、20%に満たない。逆にフィリピンは1970年代初頭、他のアジア新興諸国よりも高い製造業比率を示していたが、その後、同比率の低下を見ている。インドもフィリピンも所得段階は中所得国の中でも低位であるが、既にサービス産業の比率が大きい。従来型とは異なる新しいパターンの経済発展経路を進みつつある両国であるが、製造業の発展度合いが十分でないうちに脱工業化する「未熟な脱工業化」164のリスクにも留意する必要があるだろう。
第Ⅱ-2-2-9図 実質GDPに占める製造業比率の推移①
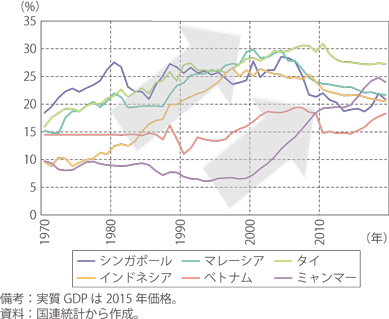
第Ⅱ-2-2-10図 実質GDPに占める製造業比率の推移②
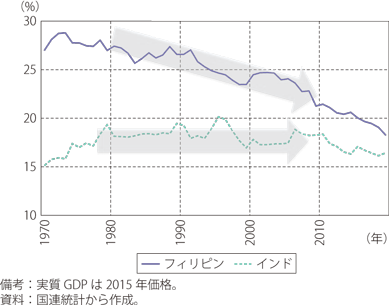
成長パターンの違いは貿易や投資動向においても見ることができる。アジア新興諸国の急速な経済発展の背景の一つには、貿易や対内直接投資を通じてグローバル経済との結びつきを強めたことがあり、特に1980年代以降のシンガポール、マレーシア、タイ、近年のベトナムにおいて、経済に占める輸出、対内直接投資ストックの比率が大きく拡大している。一方、インド、インドネシア、フィリピンはそれらの指標の伸びは一部の時期を除いて相対的に緩慢である(第Ⅱ-2-2-11~12図)。
第Ⅱ-2-2-11図 実質GDPに占める輸出の比率
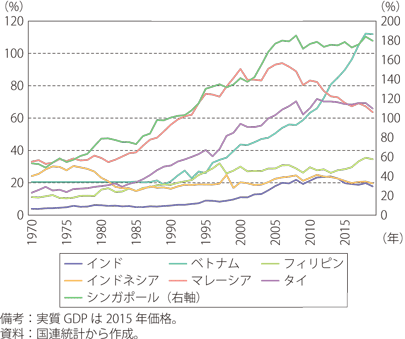
第Ⅱ-2-2-12図 実質GDPに占める対内直接投資ストックの比率
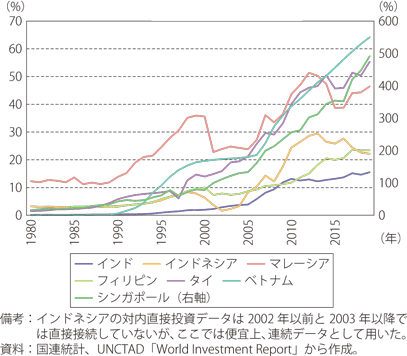
経常収支の状況も多様である(第Ⅱ-2-2-13図)。シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシア、ブルネイ、ミャンマーは黒字、インドネシア、インド、カンボジア、フィリピン、ラオスは赤字となっている。収支の内訳(第Ⅱ-2-2-14~15図)では、シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシアは貿易収支黒字、インド、フィリピンは貿易収支赤字で推移している。インド、フィリピンはサービス収支が黒字で推移している。タイは財、サービス双方の収支が黒字で推移している。サービス収支黒字が大きいインド、フィリピン、タイについてその内訳(第Ⅱ-2-2-16図)を見ると、インド、フィリピンで「その他サービス」(インドでは特に「コンピュータ」、「コンサルティング」が大きい(第Ⅱ-2-2-17図))、タイでは「旅行」が大きい。国によって競争力を発揮しているサービス部門が異なっている。
第Ⅱ-2-2-13図 アジア新興諸国の経常収支(2019年)
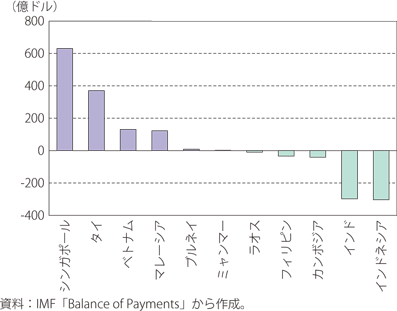
第Ⅱ-2-2-14図 アジア新興諸国の貿易収支
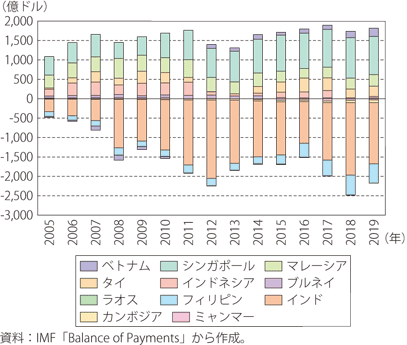
第Ⅱ-2-2-15図 アジア新興諸国のサービス収支
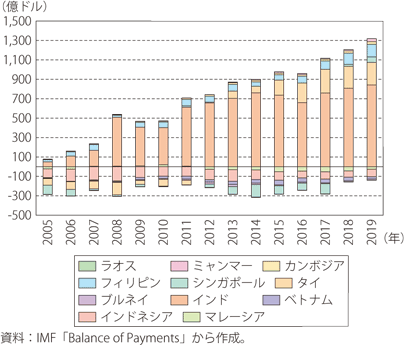
第Ⅱ-2-2-16図 インド、タイ、フィリピンのサービス収支(2019年)
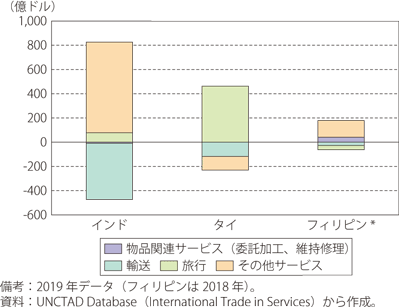
第Ⅱ-2-2-17図 インドの「その他サービス」収支の内訳(2019年)
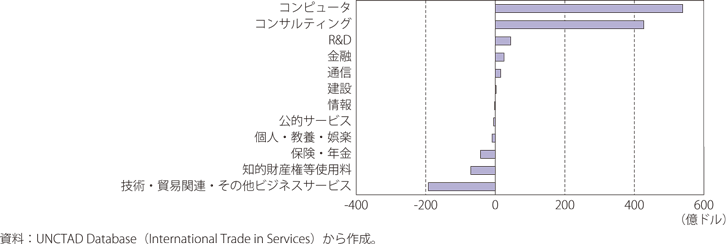
162 インドネシアは2019年のデータに基づき、2020年7月に高位中所得国入りした。
163 タイの場合、高齢化の進展、農村部の年齢別人口構成における高齢層の多さなどが背景にあると考えられる。
164 トラン、苅込(2019)。
(3)デジタル・エコノミー
近年のアジア新興諸国におけるデジタル経済の急速な拡大については、『通商白書(2020)』でも取り上げ、インターネット経済がアジアの人々の生活に深く浸透していることや、アジアのデジタル分野におけるスタートアップ企業の成功事例、豊富なIT人材の存在、デジタル技術を通じて社会的課題を解決していくデジタル・トランスフォーメーション(DX)への期待の高まり、新型コロナウイルス感染拡大を背景にデジタル化の動きが一層加速していく可能性などについて詳細に検討した。
直近のアジア新興諸国のデジタルインフラへのアクセス状況について見ると、例えばモバイルフォンの契約件数(2020年)ではインドが11.5億件、ASEAN10が8.5億件となっており、合わせると世界の全契約件数の約25%を占める165。インターネット人口については、インドが7.6億人(国内人口の約55%)166、ASEAN(インドネシア、タイ、マレーシア、シンガポール、フィリピン、ベトナムの6か国)が4億人(域内人口の70%)167となっている。ASEAN6か国のインターネット経済全体の規模は2019年の1,000億ドルから2025年には3,090億ドルに達すると見込まれている。このうちe-コマース市場については、ASEAN6か国では2015年の50億ドルから2019年に380億ドルまで拡大、2020年は620億ドル(前年比63%増)となり、今後2025年までに1,720億ドル(年率23%で拡大)に到達すると予想されている168。インドでは2017年の385億ドルから2026年には2,000億ドルにまで拡大すると見込まれている169。
新型コロナウイルス感染拡大で人どうしの接触や移動が大幅に制限されたことで、デジタル化の動きは更に加速している。ASEAN6か国のインターネット利用人口は、2015年は2.6億人、2019年は3.6億人と4年間で1億人(平均すれば1年間で2,500万人)の増加であったのに比し、2020年は4億人と2019年から1年間で4,000万人増加している。ロックダウンにより人との接触が減った分、個人のオンライン時間が増えたことも背景にある。ASEAN6か国のデジタルサービス消費者の36%が新型コロナウイルス感染拡大の影響により新しく当該サービスを受けるようになり、その94%がコロナ後も当該サービスを利用したいと考えているという。都市部だけでなく地方におけるデジタルサービスへのアクセスも増えている。ロックダウン解除後、各国における1日当たりのオンライン時間はロックダウン期間中よりも減少しているが、どの国もロックダウン前よりも増加している(第Ⅱ-2-2-18図)。ロックダウンを機に医療、教育などといった従来、対面で行われることが前提であった分野においてデジタル技術を用いたサービス提供が行われるようになってきたことも注目される170。このことは、企業の事業活動においてデジタル・プラットフォームの利活用、デジタル・ツールを通じた販売、デジタル関連の投資が増加していることにも表れている(第Ⅱ-2-2-19図)。
第Ⅱ-2-2-18図 1日の平均オンライン時間
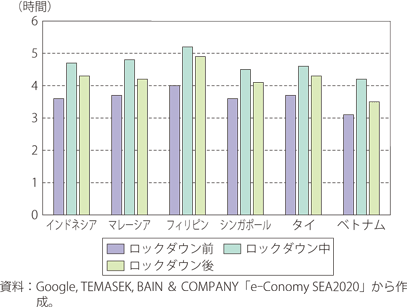
第Ⅱ-2-2-19図 コロナショックを機に増加している企業のデジタル利活用・投資
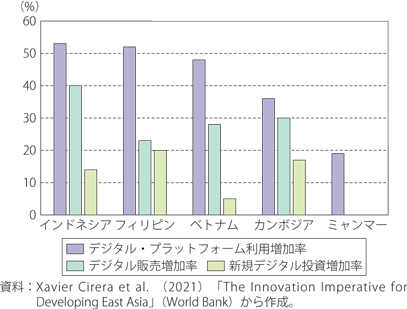
165 ITU Webサイト![]() 。
。
166 India Brand Equity Foundation Webサイト![]() 。2020年8月現在。
。2020年8月現在。
167 Google, TEMASEK, BAIN&COMPANY(2020), “e-Conomy SEA2020”(BAIN&COMPANY Webサイト)![]() 。
。
168 Google, TEMASEK, BAIN&COMPANY(2020)(同上)。
169 India Brand Equity Foundation Webサイト(同上)。
170 本パラグラフ中のデータ等はGoogle、TEMASEK、BAIN&COMPANY“e-Conomy” SEA2020による。
2.サステナブル・インクルーシブな成長のための課題
近年、国際社会では経済成長のあり方をめぐって単に生産性やコスト競争力のみを追求するのではなく、環境負荷の低減や社会の包摂性を問う動きが活発化しており、政府や企業、投資家の意識や行動の変革が求められるようになっている。市場においても、従来の市場価値(価格)では捉えられない「価値」や「豊かさ」への関心が高まっている。2015年に国連で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」は「誰一人取り残さない」という決意表明の下、2030年までに達成されるべき17の持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)を掲げている。「持続可能」という言葉は将来世代にわたって続くということであり、未来から現在を考えるという発想に立っている171。環境破壊や気候変動リスク、人権やジェンダーの問題、法の支配や言論の自由が損なわれることによる社会の歪みなどが次世代に引き継がれてしまうことは深刻な問題であり、若い世代の多いアジア新興諸国としても等閑視できないであろう。またSDGsは「開発」の言葉を使いながらも、途上国の発展だけでなく、先進国に対しても先進国ゆえに直面する多くの課題への取組を促している。1.でみたようにアジア新興諸国の発展段階は多様であり、サステナブル・インクルーシブな成長に向けての課題も各国が置かれている発展段階等に応じて多様であると考えられる。ここではアジア新興諸国が直面している幾つかの課題について、(1)伝統的な開発課題(社会的課題)、(2)経済的課題(成長と雇用をめぐる課題)、(3)環境課題(自然災害、気候変動、廃棄物等をめぐる課題)に分けて見ていくこととする172。
171 南、稲場(2020)
172 課題の分類に当たっては中川(2021)を参考にした。
(1)伝統的な開発課題(社会的課題)
開発をめぐる諸課題の状況は、経済発展の度合いに大きく左右される。アジア域内でも国によって課題の状況や取組の進捗状況にばらつきがある。インドやCLM諸国173、フィリピン、インドネシアは改善への取組を加速させる必要がある。勿論、高位中所得国や高所得国においても社会的課題は残っており、文化や慣習などの要素も考慮されなければならない。
173 C(カンボジア)、L(ラオス)、M(ミャンマー)。
① ボリュームとして大きいアジアの貧困・低所得層
1.で見たように経済成長の過程でアジア新興諸国の貧困率は急速に低下しているが、貧困層の「ボリューム」は引き続き大きいことに留意する必要がある。世界の貧困者(1日当たり1.9ドル未満(2011年購買力平価)で生活する人)の数をみると足下(データがそろっている直近の2014年)、サブサハラアフリカが4.1億人(世界の53%)、アジア(東アジア・太平洋と南アジアの合計)が3.2億人(同41%)となっている(第Ⅱ-2-2-20図)。アジアでは南アジアのボリュームが大きく2.6億人(同34%)である。新型コロナウイルス感染拡大の影響により貧困の問題は一層深刻化している。
第Ⅱ-2-2-20図 貧困者数
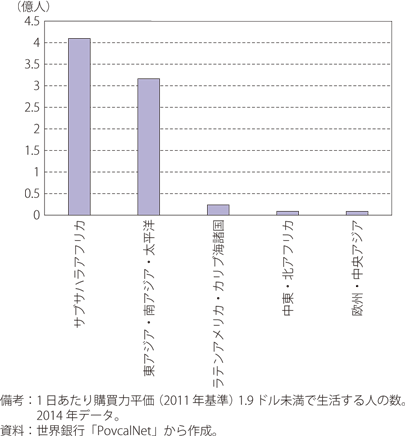
貧困や低所得は人の尊厳や人生の質といった問題に直結し、ひいては社会の活力を削ぐ大きな原因となる。更に深刻なのは、そうした状態が次世代にも引き継がれてしまう貧困の連鎖の問題である。足下の貧困を解消し、貧困の連鎖を断ち切るために、人々の健康な生活の確保や、教育の普及、セーフティネットの整備など様々な課題に取り組む必要がある。貧困から脱却する最初の一歩となり得るファイナンスの役割も重要である。「貧困の罠」論が提起する問題にも留意し、ファイナンスが効果を発揮して貧困層を成長軌道に乗せることができるような制度設計を行っていくべきとの指摘もある174。
174 高野(2021)
② 基本的生活基盤の確保 ~健康や飢餓の問題への対処、安全な水へのアクセスが重要な課題~
SDGsに関係する課題は国連のデータベースで比較可能となっており、ここでは特にアジア新興諸国のスコアが低い指標を取り上げる。国によってばらつきはあるものの、アジア新興諸国は人々の健康の分野において、例えば妊産婦死亡率、大気汚染による死亡その他多くの項目で深刻な課題に直面している。人口1万人当たりの医師数の世界平均は約16人であるが、インド、ベトナム、タイが約8人、ミャンマーが約7人、フィリピンが6人、インドネシア、ラオスが約4人、カンボジアは約2人と世界平均を大きく下回る175。1万人当たりの病床数はシンガポールの約25床に対し、インドネシア、フィリピン、ミャンマーが約10床、インドが約5床とアジア域内で格差がある。病院インフラの問題はコロナ禍で深刻さを増していると見られる。
飢餓、特に子供の飢餓の問題は重く受け止める必要がある。5歳未満の子供の栄養不良による発育不全の比率は、近年、低下してきているもののインド、ラオス、カンボジア、インドネシア、フィリピンで30%を超えている176。同じく5歳未満の栄養性消耗症の子供の比率はインド、インドネシア、マレーシアで10%を超えている177。
健康な生活の基本である安全な飲料水の利用率178は、2017年時点でインド(地方56%)、フィリピン(全国47%、都市部61%、地方34%)となっている。基本的な手洗い施設を有する人の比率179は、2017年時点でカンボジア(全国66%、都市部88%、地方60%)、インドネシア(同64%、同72%、同55%)、インド(同60%、同80%、同49%)となっている。農村と都市のインフラ整備における格差の一例である。
175 WHO“THE GLOBAL HEALTH OBSERVATORY”.
176 国連SDGデータベース![]() のIndicator 2.2.1。カンボジアは2014年、インド、ラオスは2017年、インドネシア、フィリピンは2018年のデータ。
のIndicator 2.2.1。カンボジアは2014年、インド、ラオスは2017年、インドネシア、フィリピンは2018年のデータ。
177 国連SDGデータベース![]() のIndicator2.2.2。マレーシアは2016年、インドは2017年、インドネシアは2018年のデータ。
のIndicator2.2.2。マレーシアは2016年、インドは2017年、インドネシアは2018年のデータ。
178 国連SDGデータベース![]() のIndicator6.1.1。同Indicatorではインドのデータは地方のみ掲載。
のIndicator6.1.1。同Indicatorではインドのデータは地方のみ掲載。
179 国連SDGデータベース![]() のIndicator6.2.1。
のIndicator6.2.1。
③ 人材育成上の課題 ~初等教育、女性への視点~
教育に関する最も基本的な指標である識字率については若年層だけをみると90%を超える程度にまで上昇してきている180が、全体では改善余地のある国が見られる。初等教育の就学率は多くの国で上昇しているが、一部の国では貧困などの理由から退学するケースが見られる。教育は人が貧困から脱却する上で必要不可欠なものであり、その第一歩である初等教育におけるドロップアウトを防ぐ観点から就学継続のインセンティブを高める工夫が求められている181。
女性の問題にも目を向ける必要がある。女性への暴力やその他の人権侵害など看過されてはならない事柄がいまだに多数存在しているが、ここでは人材育成、人的資本の観点から女性の問題に触れたい。例えば就学期間では男性より女性の方が短い国が多い。識字率で特に女性の識字率が低い国もある。World Bank and WTO(2020)は貿易の拡大が途上国・新興国の女性の就業・雇用を促してきた可能性を指摘し、貿易関連企業で就業している女性たちの結婚年齢が上昇し就学期間が長くなった事例を紹介している。一方で、女性が低スキル部門での就業継続を余儀なくされているケースや、金融や技術へのアクセスが限られていることなどを課題として挙げている。就業率、社会や経済活動における意思決定プロセスへの参画状況、デジタル経済へのアクセス等についても男女間の格差の存在が指摘されている182。
180 矢野恒太記念会(2020)『世界国勢図絵(第31版)』(元データはUNESCO)。若年層に限ると男女平均でカンボジアが92.2%、ラオスが92.5%、インドが91.7%と国民全体で見た場合よりも高くなる。
181 井出(2014)
182 Sey(2021)
(2)経済的課題(成長と雇用をめぐる課題)
SDGsは成長そのものの継続にも関心を向けている。途上国・新興諸国にとって、貧困状態や低所得段階に停滞することなく成長を続けていくことが、環境や社会の包摂性を意識した取組を進めていく上でも重要になってくる。
① 中所得国の罠
アジア新興諸国の経済発展をめぐっては、いわゆる「中所得国の罠」の問題が議論されてきた。中所得国の罠とは、低所得段階から中所得段階に達した国の成長が鈍化、経済発展が停滞し高所得国に移行できないまま、中所得段階に長期間とどまることを指す183。シンガポールは高所得国入りを果たしているが、マレーシアは高位中所得国となってから23年、タイは15年、経過している。フィリピンも中所得国ではあるものの、その所得水準はマレーシアやタイに比べて低く、しかも同じ所得段階(「低位中所得」)に長期間(40年以上)滞留している(第Ⅱ-2-2-21図)184。Felipe et al.(2012)によれば、経済発展が成功した諸国の経験を考察した結果、低位中所得から高位中所得まで平均して28年、高位中所得から高所得まで14年かかっている。これに従えば、タイやマレーシアは「高位中所得国の罠」に、フィリピンは「低位中所得国の罠」に陥っている可能性が高い。マレーシアやタイは人口ボーナス期を過ぎた、あるいは過ぎつつあり、労働集約部門の競争力低下が進んでいること、特にタイでは今後、急速に高齢化が進展する見通しであることなどを踏まえると、経済の高付加価値化を可能とする新たな成長エンジンの獲得が急がれる185。
第Ⅱ-2-2-21図 中所得国滞留年数
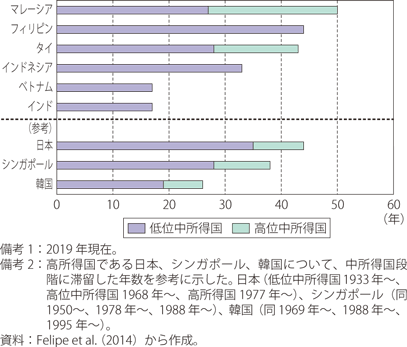
大泉(2018)は人口ボーナス期に国内貯蓄率が上昇することに着目し、生産年齢人口比率が低下に向かった後も国内に蓄積された資金を活用して産業の高度化を図ることで成長を続けることができるとし、中所得国から高所得国入りした韓国などを成功例として挙げている。産業高度化や競争力強化のための投資動向を確認するため研究開発支出の対GDP比の推移を見ると、マレーシアやタイは近年、上昇傾向にあるものの、韓国に比べて低位にとどまっていることが分かる(第Ⅱ-2-2-22図)。足下のASEAN各国、インドの知的財産権等使用料収支は赤字であり(第Ⅱ-2-2-23図)、「知識」や「アイディア」を成長に結びつけるための一層の取組が必要といえる。
第Ⅱ-2-2-22図 アジア諸国の研究開発支出対GDP比の推移
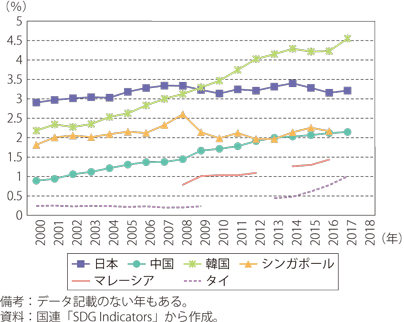
第Ⅱ-2-2-23図 知的財産権等使用料収支(2019年)
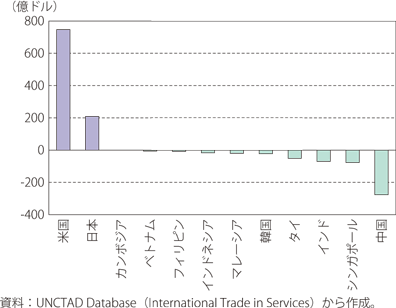
R&Dとともに重要なのは、経済の高付加価値化を支える人材の育成であろう。井出(2014)はASEAN諸国の教育問題の分析において中等教育、高等教育の就学率と所得との相関が高いことを指摘し、タイ、マレーシア、インドネシアについて教育の不足が成長のボトルネックとなっている可能性があり、加工・組立産業にとどまらない成長を続けるためにも教育の質を向上させ人材の高度化を図ることが重要であると述べている。イノベーションとの関係で重要なスキルとしてCirera et al.(2021)は「技術」、「高次認知」、「社会情動」、「マネジメント」を挙げている186。それらのスキルを備え、R&Dの成果を社会実装(Deploy)していく能力187を持った人材をいかに育てていくか考えていく必要があるだろう。
183 トラン(2015)、トラン、苅込(2019)。世界銀行(2007)(「東アジアのルネッサンス(Gill and Kharas(2007)“An East Asian Renaissance-Ideas for Economic Growth”)」)、アジア開発銀行(2011)(「アジア2050」)で「中所得国の罠」の議論が取り上げられていること、Felipe et al.(2012)、同(2014)の指摘を紹介。
184 Felipe et al.(2014)“Middle Income Transitions : Trap or Myth?”. 各所得段階における滞留年数については世界銀行“World Development Indicators”が1987年以降のデータを提示しているが、本節ではFelipe et al.(2014)によった。
185 労働集約部門は近隣のCLM国へと製造工程を移転する動き(タイ・プラス・ワン)が出てきている。
186 Cirera et al.(2021)“The Innovation Imperative for Developing East Asia”, World Bank Group.
187 伊藤(2020)(前出)を参考にした。
② インフォーマル経済と働き方の新しい潮流
雇用・就業の包摂性をめぐって国連SDGsには「包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセントワーク)を促進する」との項目が盛り込まれている。ディーセントワークに関する議論の一つとしてILOは「インフォーマル経済」の問題を挙げている。インフォーマル経済とは「法又は実務上、公式の取決めの対象となっていないか、公式の取決めが十分に適用されていない労働者及び経済単位の行うあらゆる経済活動(不正な活動は含まない)」188のことであるが、ILOはこのインフォーマル経済において「就労に関する権利の否定、質の高い雇用の十分な機会の欠如、不十分な社会的保護、社会対話の不在といった、ディーセントワークの欠如が非常に顕著に見られること」189、「それが多く発生していることは持続可能な企業の発展や公の収入、政府の活動範囲、制度・機構の健全性、市場における公正な競争などに悪影響を与えること」190からインフォーマル経済からフォーマル経済への円滑な移行を目指す勧告を2015年6月に発出している。
アジア・太平洋地域の就業者数に占めるインフォーマル雇用労働者数を見ると東南アジア・太平洋地域で75.2%、南アジアでは87.8%と高い比率である191。国別に見ると、各国とも農業におけるインフォーマル雇用比率が高いが、非農業の同比率はインド、インドネシアで高い(第Ⅱ-2-2-24表)。新型コロナウイルス感染拡大に伴う各国の制限措置が取られる中、こうしたぜい弱な雇用形態で働く人たちの多くが失業していると見られる。極度の貧困は減っていても、感染症のまん延や自然災害の発生などによって容易に貧困に陥る可能性がある人たちが数多く存在する。このほか不当な雇用契約、十分な安全対策が取られていない生産現場における労働、児童労働の存在など人権の問題もディーセントワークに係る諸課題として指摘されている。そして多くのぜい弱な立場に置かれている人の実態が完全に捕捉できていないという根本的な問題も残っている。社会保障のカバー率などセーフティネットをめぐる課題も大きい(第Ⅱ-2-2-25図)。
第Ⅱ-2-2-24表 「インフォーマル雇用」の比率
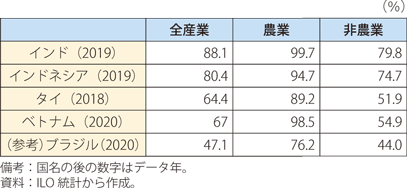
第Ⅱ-2-2-25図 総人口に占める「最低一つの社会保障給付を受けている人」の比率
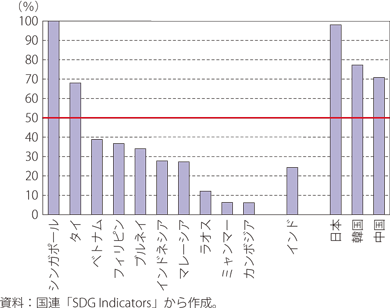
そのような中で、デジタル化は人々の働き方にも新しい潮流をもたらしている。リモートワークの普及のほか、いわゆる「ギグ・ワーキング」(デジタル・プラットフォームを通じて単発の仕事を請け負う働き方)の増加として表れている。需要者と供給者のマッチングを行い取引の安全、信頼を確保するという点で、デジタル技術は就業や所得向上の機会に恵まれなかった人々に収入稼得のための新しい道を開いたといえる。例えば世界のオンライン・ワーカーに占めるアジアの比率はどの部門でも大きい(第Ⅱ-2-2-26図)。伊藤(2020)はインドなどの南アジアにおいてデジタル化の進展の中でフリーランス経済が拡大している点を指摘する。前述したようにインドはインフォーマル雇用の比率が高いが、ここには家族従業者や従来から見られたぜい弱な雇用形態での就業という側面と、オンライン・ワーカーの増加などデジタル化の中で出てきた新しい動きという側面の双方が併存しているとも考えられる。
第Ⅱ-2-2-26図 部門別に見たオンライン・ワーカーの地域別シェア
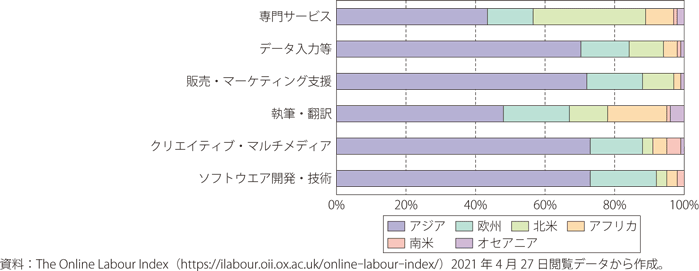
188 ILO Webサイト![]() から抜粋。
から抜粋。
189 ILO Webサイト(同上![]() )。
)。
190 ILO Webサイト(同上![]() )。
)。
191 ILO“Asia-Pacific Employment and Social Outlook 2020”(元データはILO“Women and men in the informal economy:A statistical picture”により、2016年時点のもの)。
(3)環境課題(自然災害、気候変動、廃棄物等をめぐる課題)
自然災害や環境破壊なども人々の生活を大きく脅かし、貧困の原因となり、ひいては社会の包摂性を損なうものである。2000~2019年の世界の自然災害発生件数上位10か国のうち8か国がアジアの国々である192。2019年に自然災害で影響を受けた人の約74%はアジアに住んでおり、同年の自然災害による世界の経済損失のうちアジアが約60%を占める193。2016~2018年の平均でASEAN全体では10万人当たり約3,100人が気候変動関連の災害で影響を受けている(フィリピンでは約6,000人、タイでは約4,700人、インドネシアでは約2,200人)194。
気候変動問題による影響を大きく受けているアジアであるが、CO2の多排出地域でもある。第Ⅱ-2-2-27図を見ると、アジアからのCO2排出量および対世界の比率が急速に増大していることが分かる(2018年時点で世界の50%以上)。アジアの内訳では、中国が52%、インドが12.6%、ASEANが8.1%となっている(第Ⅱ-2-2-28図)。一人当たりの排出量を見ると、ブルネイが突出して多く、シンガポールが続いている(第Ⅱ-2-2-29図)。エネルギー構成にもよるが、経済発展が進んだ高所得国の排出量が多くなっている構図であり、現在一人当たりの排出量が少ない国々も今後の経済発展の過程で排出量が拡大していくことが想定される195。アジア新興諸国には人口が多い国が複数ある。一人当たりの排出量が増えると単純計算で国全体、ひいてはアジア地域全体の排出量が大きく増大することになる。
第Ⅱ-2-2-27図 世界の燃料燃焼による二酸化炭素排出量とアジアの比率
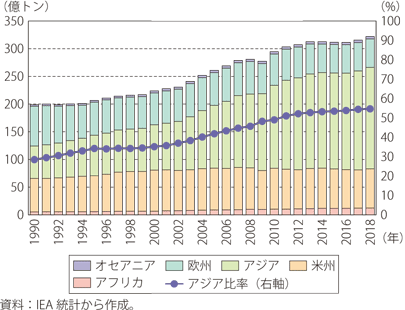
第Ⅱ-2-2-28図 二酸化炭素排出量(アジアにおける各国・地域の比率・2018年)
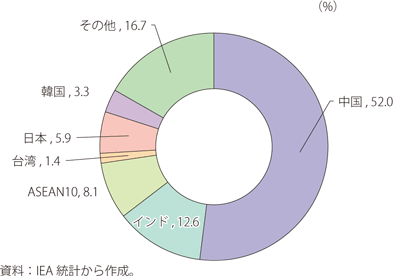
第Ⅱ-2-2-29図 一人当たりエネルギー関連二酸化炭素排出量(2017年)
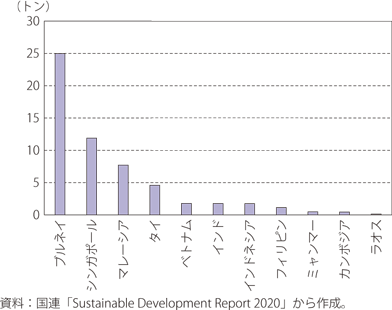
京都議定書に代わる新たな国際枠組みである「パリ協定(2016年発効)」は、先進国、途上国を問わず温室効果ガス排出削減のための取組を行うことを定めており、インド、ASEAN各国も同協定を批准196、国別の目標も設定している。協定発効から5年を経て、特に足下では2030年までの温室効果ガス削減目標(中期目標)に向けた具体的な取組の加速化が求められているが、電源構成における石炭火力の比率が高いアジア新興諸国にとって目標の達成は容易ではないと考えられる(第Ⅱ-2-2-30図)。経済発展のための電力確保という途上国・新興諸国特有の要請と排出削減とのバランスをどう取るかが課題となっている。特にファイナンスの分野で「移行(トランジション)」という考え方がクローズアップされてきており、アジア各国の金融当局もその意義について言及している197。ファイナンスの適否を判断する際、「グリーンか否か」の二項対立で考えるのではなく、経済発展の途上にある国々の「グリーンになるための取組」を後押ししていくことが重要だとするものである。
第Ⅱ-2-2-30図 アジア諸国の電源構成(2019年)
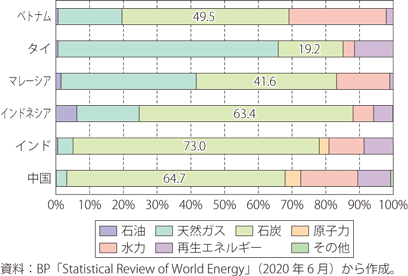
気候変動問題に加えて、多くの国で深刻化しているプラスチックごみの問題が挙げられる。Jambeck et al.(2015)による分析(例えば年間の不適切に廃棄されるプラスチックごみの推計量や陸上から海洋に流出したプラスチックの推計量の上位10か国中8か国がアジア諸国)は、この問題に関する議論が本格化するきっかけの一つとなった。水辺1平方キロメートル当たりのごみの数198を見ると、アジア太平洋の中では東南アジアが圧倒的に多い(第Ⅱ-2-2-31図)。廃棄物の収集サービスの普及やごみの分別・リサイクル等についての知見の共有を通じた適切なごみ処分に向けた行動の促進が急がれる。
第Ⅱ-2-2-31図 水辺1平方キロメートル当たりのゴミの数(2018年)
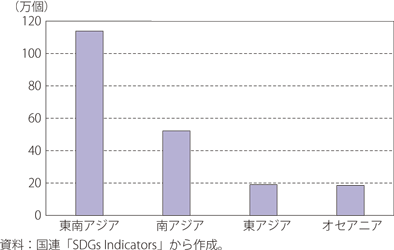
また、多様な用途に用いられるパーム油の原料であり東南アジアが世界シェアのほとんどを占めるアブラヤシの生産については、環境への多大な負荷(森林破壊とそれに伴う人や生態系への深刻な影響、泥炭地の開発・火入れによる温室効果ガスの排出や煙害等)や労働面における課題(安全知識のないまま作業することによる怪我や健康被害、人権の問題)等で批判されている199。森林破壊のほか、陸上の動植物や水産資源の乱獲、違法取引など生物多様性の保全を脅かす諸問題にもより関心が払われなければならない。
192 CRED(2020a).このうちASEAN地域がフィリピン、インドネシア、ベトナムの3か国、南アジアではインド、バングラデシュ、アフガニスタンの3か国。
193 CRED(2020b)
194 ASEAN(2020)“ASEAN Sustainable Development Goals Indicators Baseline Report 2020”p.183より2016~2018年に気候変動関連の自然災害で影響を受けた人の数(10万人当たり)の年平均を求めた(10の位以下は四捨五入している)。
195 堀(2020)
196 国連Webサイト![]()
197 経済産業省「トランジション・ファイナンス環境整備検討会資料(2021年1月27日)」![]()
198 国連“SDG Indicator 14.1.1(Beach litter per square kilometer(Number))”より。
199 この問題は特に欧州で憂慮され、ノルウェーの年金基金が東南アジアのプランテーション事業等から投資を引き揚げたり、欧州連合がバイオエタノールの原料としてのパーム油の禁輸を決めたりするなどの動きがある。
3.課題解決に向けた取組
アジア新興諸国が直面する諸課題の解決に向けて、国際機関等によるもののほか、アジア発の取組も行われてきている。ここではこうした動きを概観し、取組の実効性を高めていく上での課題や日本にとっての示唆について考えてみたい。
(1)現地発の取組
貧困、低所得の状態にあることで、従来、ビジネスの外側に置かれていたいわゆるBOP(Base of the Pyramid)層200を「ビジネスの顧客」として包摂するBOPビジネスについては、貧困層の生活水準を引上げることにより将来の消費市場のボリュームゾーンを創出するというビジネス戦略上の文脈から、企業の社会的責任の側面から、様々な場で議論され、事業の実施事例も蓄積されてきている。現地の様々なステークホルダーとのパートナーシップを構築し最新の環境技術を用いながら浄水設備事業を進めているインド企業Waterlife India社201や、バイク・タクシー(オジェック)運転手と利用者とをプラットフォームを通じて効率よくマッチングさせ、従来、収入が不安定だったオジェック運転手の仕事の機会を拡大したインドネシアのユニコーン企業GO-JEK社などの事例がよく知られている202。新興諸国の人々の金融アクセスを改善するという観点からも多様な取組が進められている。ソーシャル・ファイナンスの事例としては、主に農村の貧困女性向けにマイクロファイナンスを行ってきたバングラデシュのグラミン銀行の取組が先駆けとして著名である。従来、銀行口座を持たなかった貧困層の人々がモバイル決済を行えるようになるという点でデジタル技術も貢献している。
環境問題や社会的課題の解決のための資金調達の動きも活発になっており、市場の規模は欧州に遠く及ばないが、アジアにおけるESG債の起債も増えてきている。新型コロナウイルス感染拡大による教育への深刻な影響を受けたアジア・太平洋地域の途上国に対し、技術・職業教育訓練を含む教育セクター関連事業を支援するため、2021年2月、アジア開発銀行(ADB)が初のエデュケーション・ボンド(7,500万豪ドルの10年債)を発行している203。また、投資家の投資行動にESGの視点を取り入れる動きも広がっており、国連の責任投資原則(PRI)に署名しているアジア新興諸国の企業・機関投資家の数も増えてきている。PRI Webサイト204によると、2020年末時点で東南アジアではシンガポールが37社と存在感を示しているほか、マレーシア10社、インドネシア3社、タイ2社となっている。インドも9社の機関投資家が署名している。
並行してコーポレートガバナンスの観点からもサステナビリティへの意識が高まっている。江崎(2021)によると、アジア新興諸国においてはアジア通貨危機時に顕在化した企業統治をめぐる諸問題への反省(不適切な負債構造、同族による企業支配、少数株主保護、不十分な開示等)を踏まえ、国際機関の指導や支援も受けながら企業統治改革が進められ、企業のCSRに関する情報開示が進んできた。また、近年は企業のESGに関する非財務情報の開示を求める声が大きくなっており、アジアの資本市場でもESGに関する情報開示を義務づける動きが見られる。こうした中でアジア新興諸国企業のESG関連情報の開示率は高くなっており、KPMG(2020)によると、2020年のサステナビリティ情報の開示率はマレーシアが99%、インドが98%、タイが84%、シンガポールが81%である。ただ、開示率は高いものの、開示される情報の範囲や報告内容の質に課題があるといった指摘205もあり、今後の開示情報の充実が期待されている。
サプライチェーンの信頼性を客観的な基準を示すことにより向上させ、サステナビリティを意識する企業との取引を維持する取組もある。2.(3)で触れた東南アジアのアブラヤシ生産については、諸課題の背景にある途上国・新興国の貧困の問題などを踏まえると、アブラヤシから取れるパーム油そのものをボイコットしてしまうのではなく、むしろ認証を付与された油の市場を拡大する方が賢明であるとの考え方がある。これに基づきRSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil)によるCSPO認証が策定されており、途上国の生産者がCSPO認証を取得するための支援を行っている企業も出てきている206。主要なパーム油生産国であるインドネシア、マレーシアもそれぞれ独自のパーム油認証制度を策定している207。海洋資源(水産物等)のサステナビリティに関する認証であるMSC認証やASC認証、BAP認証なども知られている。こうした認証の多くが企業や業界団体、NGOその他の多様な主体の協同によって策定された自主的持続可能性基準(VSS:Voluntary Sustainability Standards)と呼ばれるもので208、生産者や事業者がその基準を生産等のプロセスに取り入れるかどうかは任意であるが、取引先がVSS採用を取引の条件とすることによって一定の拘束力が発生する。生産者にとってはVSS採用による一定の負担が意識される一方で、生産性の上昇や収益の拡大というメリットも大きい。前述のCSPO認証を受けた農家は受けていない農家よりも生産性、収益性が高いという実証研究も報告されている209。こうした国家以外の主体による自主的な取組は、SDGs目標の「パートナーシップ」、特に官民連携の手段としても期待されている210。このほかサプライチェーンの参加者にIDを付しその関連情報を登録させることでサプライチェーンの透明化、トレーサビリティを確保するデジタル・プラットフォーム「ブルー・ナンバー」の取組もある。
課題への取組に当たっては思い切った措置を講じることも重要であるし、漸進的だが現実的なアプローチを取ることも取組の実効性を高めるという点で意義が大きい。様々な取組が行われてきている一方、発展途上にあるアジア新興諸国にとっては、先進諸国と同じ方法、水準、時間枠組みで問題を解決することは容易ではない場合もある。2.(3)でみたような「移行(トランジション)」など、複線的なアプローチも取っていくべきではないか。持続可能で包摂的な成長を実現していくために、公共サービスの質、財源、予算の適切な執行、民主主義、法の支配、デジタル化の過程で顕在化している諸問題への対応(情報の正しさ、情報アクセスの自由の確保等)、安全・衛生面での規制の整備といったガバナンスの課題も残されている。
200 2002年購買力平価で年収3,000ドル以下の世帯(Hammond et al.(2007)では約40億人(世界110か国の家計調査の総対象人口55.75億人の約72%)と推計)。
201 The World Bank(2017)
202 JETRO(2014)「インドネシア 企業訪問調査レポート【2】:PT. GO-JEK Indonesia」![]() 、経済産業省(2020)
、経済産業省(2020)
203 アジア開発銀行Webサイト![]()
204 国際連合Webサイト![]() (2021年4月30日閲覧)。
(2021年4月30日閲覧)。
205 江崎(2021)
206 RSPOはアブラヤシ生産者だけでなく製造・加工・流通といったパーム油のサプライチェーンを構成する主体に対し、持続可能性、包摂性の諸要件を満たしていることの認証であるCSPO(Certified Sustainable Palm Oil)認証を付与している。詳細はWebサイト![]() 参照。
参照。
207 インドネシアのISPO(Indonesian Sustainable Palm Oil)、マレーシアのMSPO(Malaysian Sustainable Palm Oil)がある。CSPOの取得は技術面を含めて、途上国の小規模・零細企業にとって困難な面も多く、ISPO、MSPOは途上国の事情を踏まえた設計になっているとされる。幾つかの認証が併存することの課題(技術面、費用面で認証制度が柔軟なものになることにより途上国企業が認証を取りやすくなり認証油の市場自体が拡大していくことと、基準が緩やかになることによる弊害を取り除くことのバランスをどう取っていくべきか等)も出てきている(道田(2018))。
208 中川(2021)
209 本パラグラフのVSSに関する部分は中川(2020)を参照、一部引用した。
210 中川(2021)
(2)日本への示唆
日本はアジア新興諸国とどう向き合っていくべきか。
かつての援助対象国、労働コスト面でメリットのある製造拠点といった画一的なアジア観を持ち続けているのでは、到底、多様かつ変化の激しいアジアの今の実像を捉えることはできない。アジア新興諸国の多様性は、各国が直面している課題の多様性と言い換えることができ、そこには価値実現のための多様な機会がある。アジアは「価値」の市場である。
高度成長期の公害や頻発する災害、急速に進む高齢化への対応など、課題先進国としての経験を踏まえた取組を行うことや、サステナビリティの観点からの責務を果たしていくことは引き続き重要である。加えて今後は日本が培ってきた様々な「価値」(例えば「安全」、「衛生」、「自然との調和」といった)をアジアに、アジアからグローバルに展開するという視座に立ち、アジア新興諸国の多様な課題に対するソリューションを提示することを新しい軸として位置付けていくべきだろう。現地のニーズをきめ細やかに掘り下げ、現地の人々とともに課題解決の道筋を見つけていく「デザイン思考」の重要性211や現地発のイノベーションを実現していく「リバース・イノベーション」の意義212などにも目を向けたい。特にデジタル・ソリューションの分野ではアジア新興諸国に先行事例が蓄積されつつある。アジアでの成功事例を踏まえ、日本国内の問題解決のヒントとすることも可能であろう。
そうした「価値」創造のための環境整備も重要である。取組を阻害する制度の是正、逆にサステナビリティにとって重要だが適切な規制が存在していない場合は規制の整備を促すこと、グローバルなルール・標準の策定プロセスにおいて各国間で十分なコミュニケーションが取られ制度の調和が図られることで取組の有効性が高まるよう努力することなど、政策面でも新しいアプローチが求められている。
211 井上(2018)
212 大門(2015)