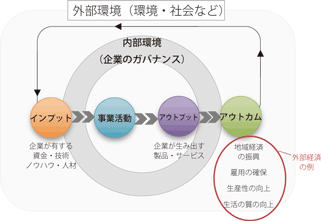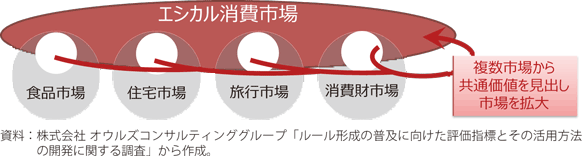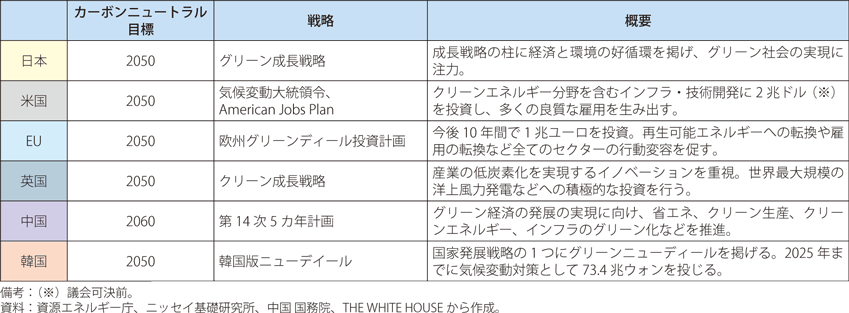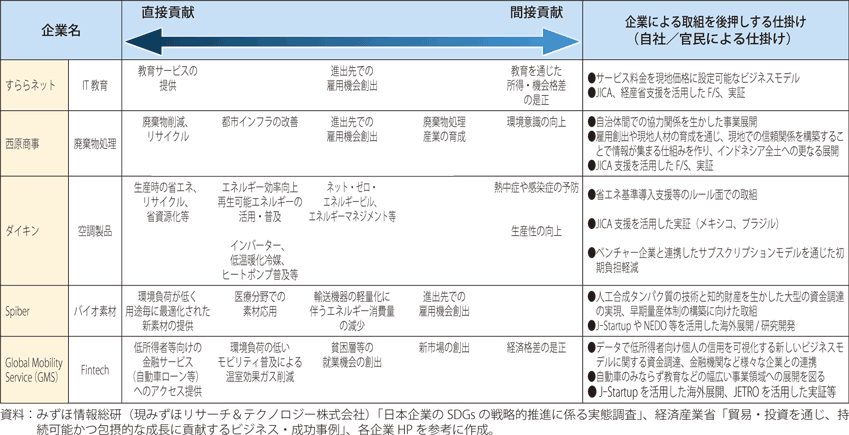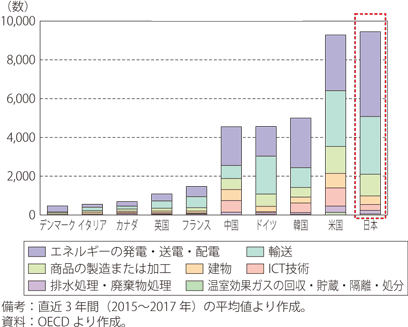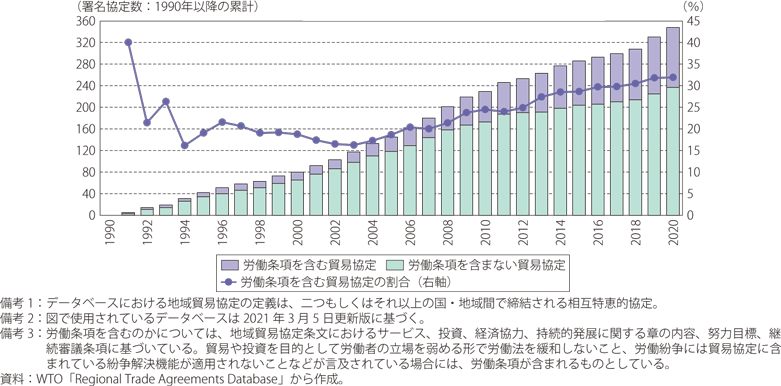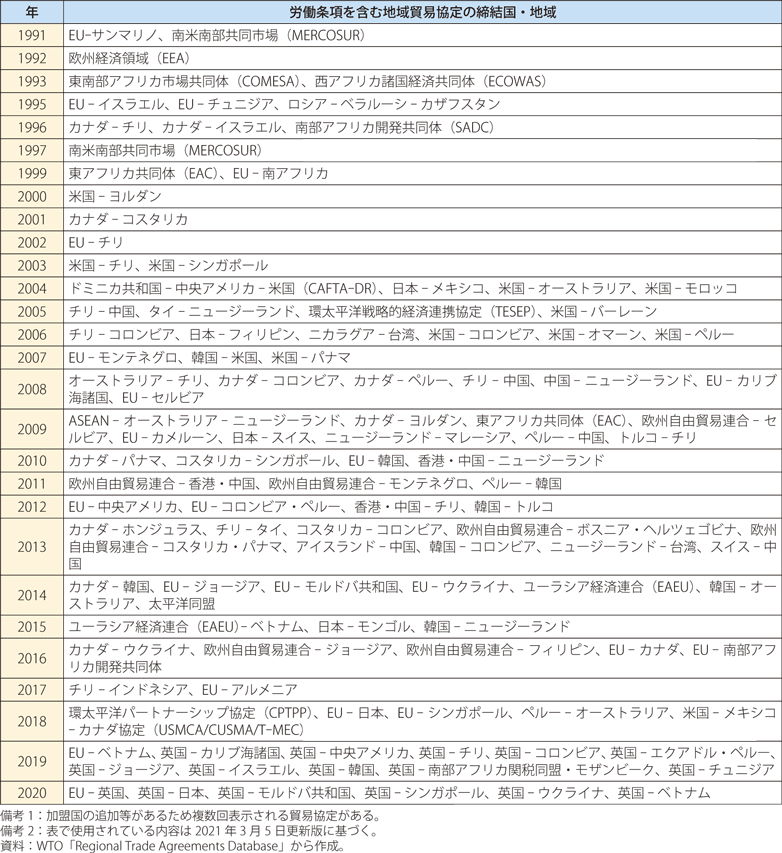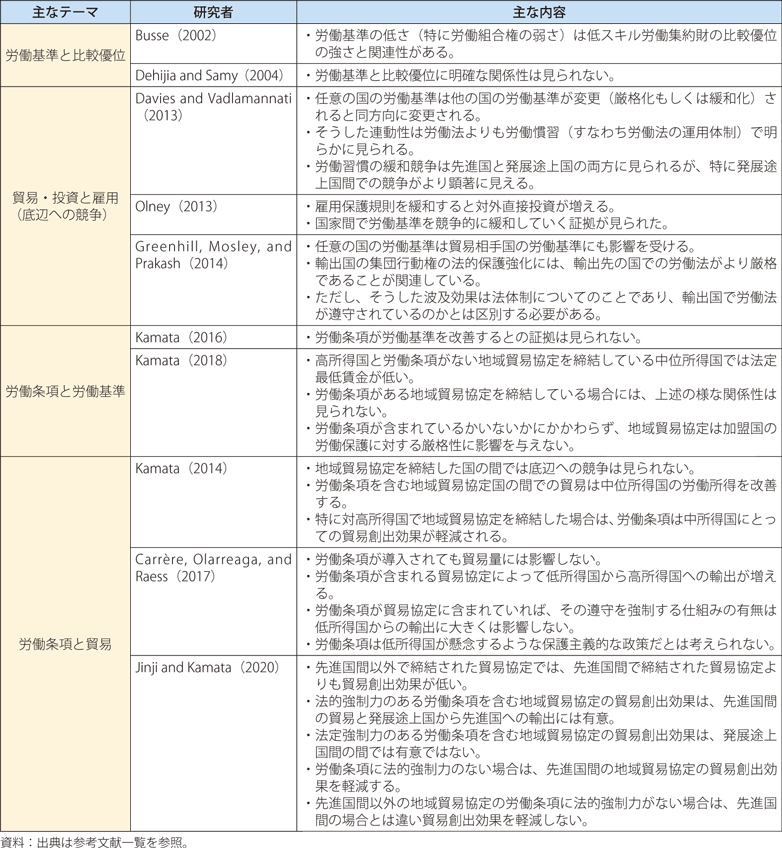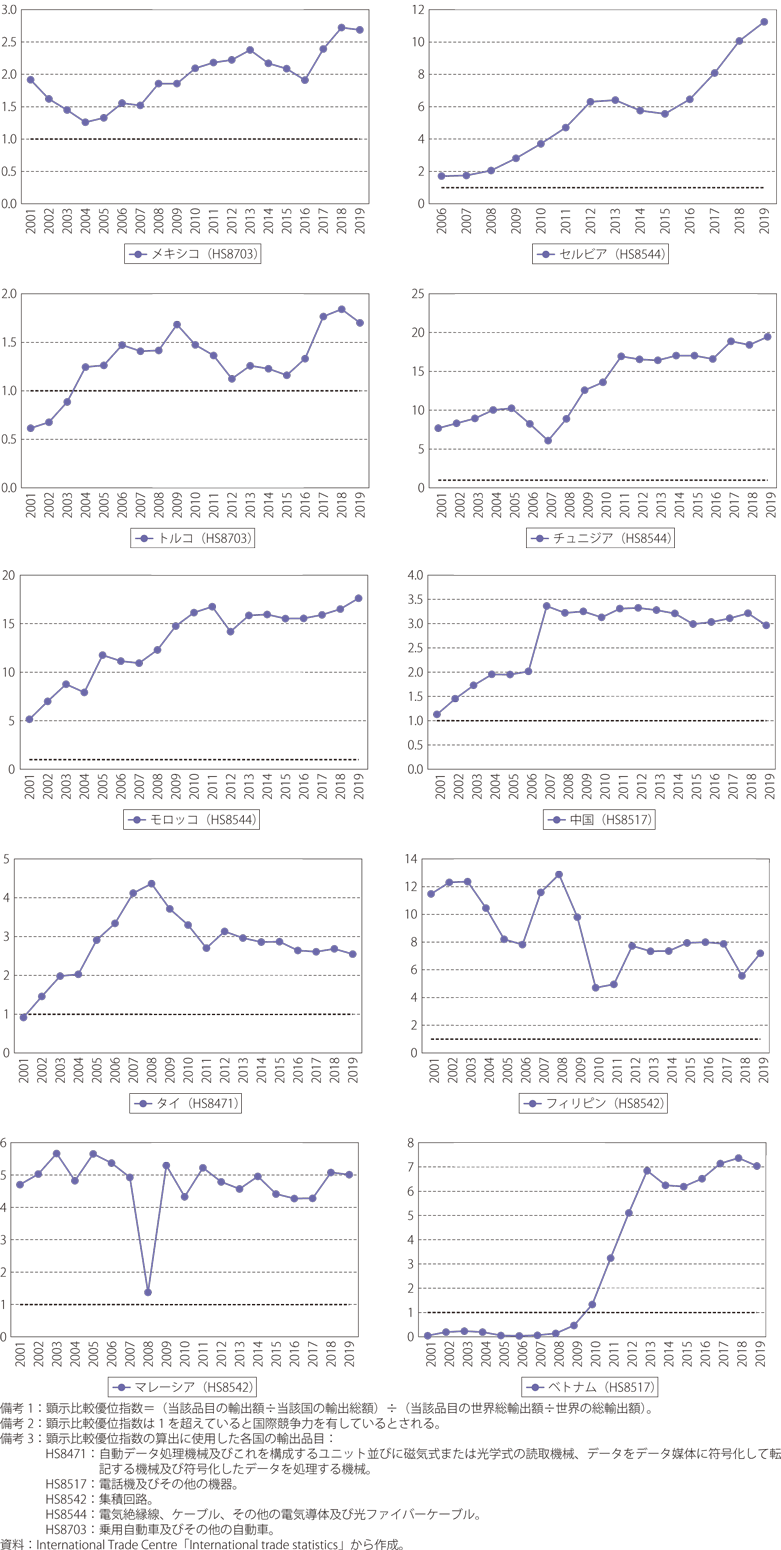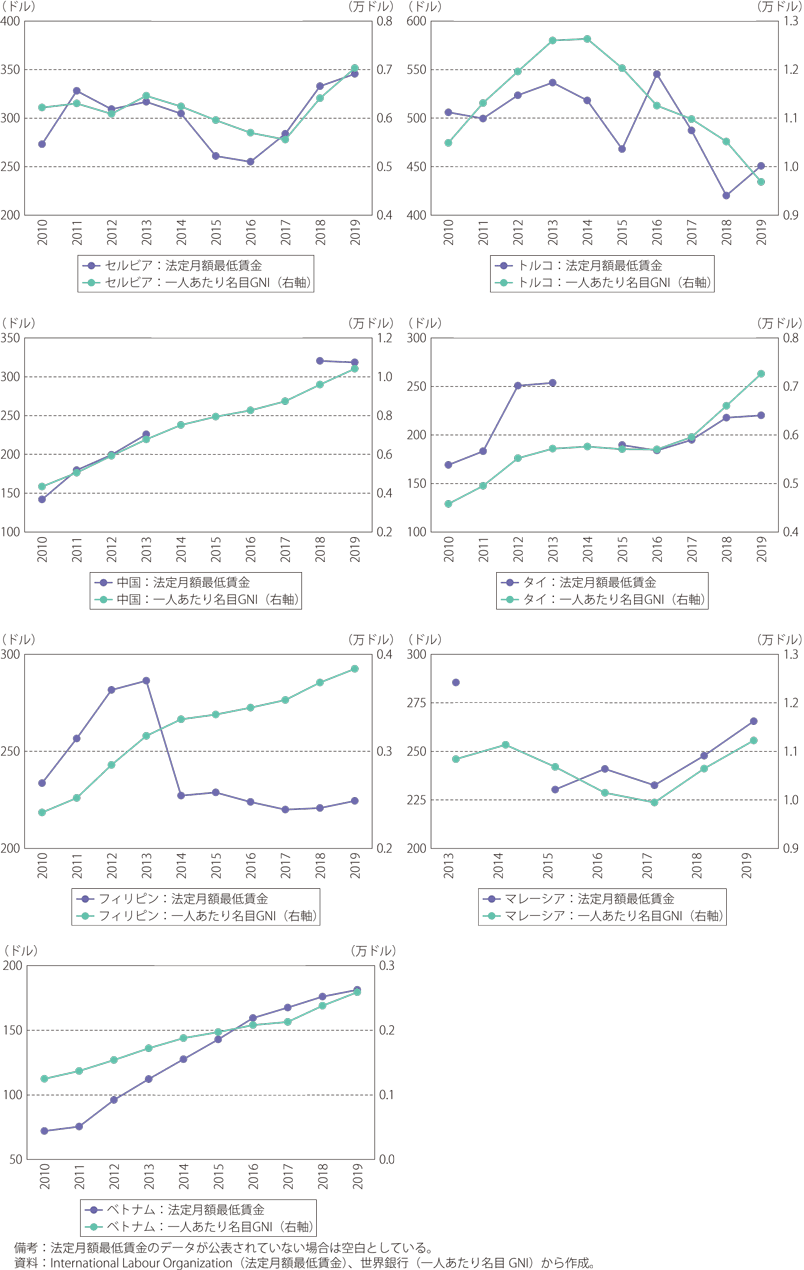第3節 サステナブルな価値創造を行う企業行動に向けて
1.価値創造への企業のアプローチ
これまで見てきたように、企業は事業基盤である環境・社会を維持し、より良いものとしていくような事業の成長を求められている。日本企業は古くから社会課題を捉えて成長を実現してきたとの指摘もあり、その点では社会課題の捉え方、インパクトの捉え方において世界的な潮流の影響を受けるようになったとも言える213。環境や社会など外部環境の変化と事業活動の関係は次のように考えることができる214(第Ⅱ-2-3-1図)。事業活動から生じるアウトプットが何らかの形で環境や社会に作用すれば、自社の経営にまで作用する215。つまり、自社のアウトプットのみならずこれまで外部経済または外部不経済として認識されてきたことが、自社の経営に作用することを理解したうえで、リスクを最小化し生み出す利益を最大化していくアプローチが企業に求められている。
第Ⅱ-2-3-1図 企業の事業活動における循環構造
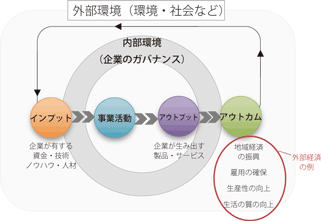
そのためには、企業は長期的な時間軸で目指すべき方向を定め、描く未来から逆算して想定していくことが肝要になってくる216。先んじてこのような課題に取り組むことでチャンスを掴むことに繋がる可能性もある。実際に、環境や社会課題に対する規制やソフトローも生まれつつあり、消費者を始めとするステークホルダーからの要請も高まっているからである。さらに、長期的な到達点を定めるうえで、自社の競争優位性を把握し、経営資源を集中させることでより大きなインパクトを生み出すことができると考えられる217。経済産業省「価値協創ガイダンス」を活用した投資家との対話もそのプロセスにおいて有用である。
また、インパクトを意識した事業活動を行っていくことで、企業のブランド価値という資産獲得にも繋がる218。加えて、事業活動を通じ、自社の社会的な存在意義(パーパス)を示し共感を得ることで、人材や顧客を引きつける求心力となりうる。競争力の源泉ともなりうる人的資本を企業が獲得していくうえでも、企業が長期的な時間軸で社会課題解決に取り組んでいくことは有用であるといえよう219。
213 経済産業省(2019)
214 International Integrated Reporting Council(2015)
215 統合思考では、企業がインプットとして利用しアウトプットとしてはき出す資本を、財務資本、知的資本、人的資本、社会・関係資本、自然資本、製造資本の6つに分類されている。
216 田瀬(2020)
217 坂野・磯貝(2021)
218 名和(2021)
219 経済産業省(2020)
2.価値に裏付けされた市場の顕在化
現在、企業の利益(経済的価値)と環境面や社会面における価値の両立が様々な形で取り組まれている。
その結果、消費行動にはそれほど影響してこなかった環境や社会への配慮が消費者により強く意識され始め、新しい発想に基づく製品やサービス、ひいては市場が創出されてきている。以下では、その例を紹介していく。
先進国において、消費者の意識の変化に伴う行動変容が「エシカル消費(倫理的消費)」という形で表れてきた。エシカル消費とは、地域経済の活性化や雇用創出なども含む、人や社会・環境に配慮した消費行動のことである。欧米を始めとして、食品市場、住宅市場、旅行市場、消費財市場など複数の市場に波及し、エシカル消費は更に拡大している220(第Ⅱ-2-3-2図)。
第Ⅱ-2-3-2図 環境・社会価値に裏付けられた市場の創出(エシカル消費の例)
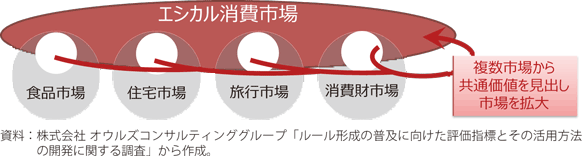
さらに、消費者の購買行動の変化が、小売業者の意識をも変化させつつある。実際に、欧州5カ国の550の小売業者へのアンケートで「今後5年間でサステナブルな商品の売上が増加する」と回答した割合は、92%にまで上り、10%程度の売上げ増加を見込んでいるとの結果が示された221。
このように、企業が提供する製品の持つストーリーにまで「価値」が求められてきていることを生かし事業の成功に結び付けている例もある。
例えば、オランダのチョコレート会社222は「100%強制労働に頼らないチョコレートを当たり前に」という企業理念をもち、幅広い層の消費者の共感と支持を集め、商品の質や広報にも力を抜くことなく事業を継続した。その結果、オランダではナンバーワンの売上げを誇る企業となっている223。その他の例として、石油を使用せず生分解する人工合成タンパク質から環境負荷の少ない素材を生み出すバイオベンチャー企業があげられる224。具体的には、ニーズに応じて分子レベルで素材をデザインすることができ、衣類から自動車部品、医療素材など多様な用途への使用が期待されている。
先述のような企業の事業活動のみならず、近年のサステナビリティに関係する政策も新たな市場を創出しつつある。(第Ⅱ-2-3-3表)。こういった動きは、他の国・地域に先駆けた具体的な政策・情報開示の枠組みを示すものとなっており、資本市場やグローバル企業の行動変容を通じて他国にも影響を及ぼしうるものである。
第Ⅱ-2-3-3表 各国・地域のグリーン成長実現に向けた政策
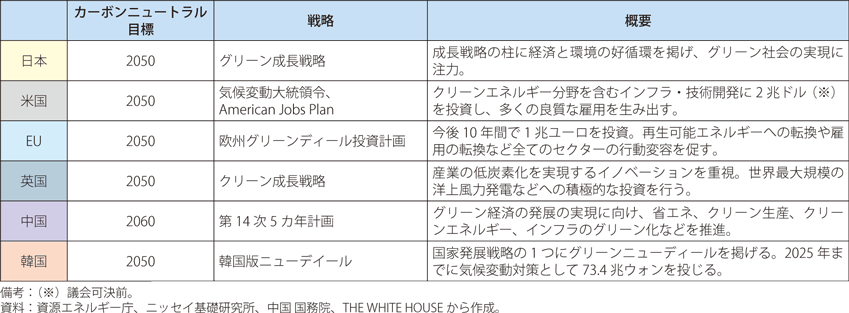
例えば、第一部で述べたような、グリーンディール等の政策によってサーキュラー・エコノミーを始めとする新たな市場が生み出されている。サーキュラー・エコノミーとは、あらゆる経済活動において資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながらサービス化等を通じて付加価値の最大化を図る循環型の経済社会活動のことである225。環境保護と経済活動をトレードオフにしない、この新たな産業の経済規模は2030年までに4.5兆ドルにまで拡大すると言われている226。近年、サーキュラー・エコノミーをテーマとしたファンドも組成され始めており、気候変動に次ぐ投資分野としても重要性が認識され始めている。
220 株式会社 オウルズコンサルティンググループ(2021)
221 International Trade Centre(2019)「EU Market for Sustainable Products」
222 Tony’s Chocolonley HP
223 PwC(2020)
224 Spiber株式会社
225 経済産業省(2020)
226 PwC(2020)
3.価値を共有する仕組みの実現
近年、企業が海外で事業活動を行う際、インフラや市場制度インフラに加え、人々の行動を基礎づける意識を共有できうるか否かといった側面の重要性が増している。例えば、環境資源は有限であり、将来世代のニーズを損なうことなく今日の需要を満たしていきつつ、持続的な繁栄に繋げていくべきだという考え方が広く認識されうる国においては、前述のサーキュラー・エコノミーやエシカル消費といった新しいビジネスや市場が創出されやすい。また、先述してきた消費者の意識の変化に加え、貧困からの脱出や生活の質の向上を含めたwell-beingの実現が企業を取り巻く環境に与える影響は小さくなく、企業にとって未来志向のアイデアやwell-beingの実現といった「価値」を体現する製品・サービスを生み出すことがより重要となる。そのための産業界における貢献の在り方として、提供する製品・サービスが人々の豊かさに直接裨益するような「直接的貢献」に加え、現地での雇用創出や地域経済の振興など、事業活動の「間接的貢献」によって現地の人々の豊かさに資するような事業を企業の本業を通じた取組により、事業の遂行を支える「信頼」を構築していくことが肝要である。地球規模の課題解決に向けて、多くの国との協力も必要不可欠であるところ、社会課題を捉える問題意識や社会課題解決に資する考え方や習慣などをより多くの国と共有していけるような土台を築き上げていくことの必要性が増している。課題解決に向けた目的意識を共有していくために、どういったアプローチがあるのか企業の事例を元に見ていく。
民間企業が社会課題の解決への貢献を通じて目的意識を共有、ひいては、市場を創出している例として、例えば、ノボノルディクスの例をみると、中国市場開拓に向け、時間をかけて市民や患者、医療従事者、政策担当者に、糖尿病に関する知識・意識の啓発活動を実施してきた。従来の糖尿病を治療するための薬のみのビジネスモデルから、食事や運動、心のケアまで生活全体を支援する糖尿病予防・克服プランをも構築した227。経済が発展し食生活が先進国型になると糖尿病の比率は高まる。経済発展に伴い、中国でも糖尿病の患者が増えていることが問題となっていた。そこで、中国政府と一緒にケア全体に取組み、予防の啓発活動を積極的に実施した。それ自体は利益を生み出さないものの、政府や医師に信頼されることで、製品の売上自体も増えていった。結果として、現在中国でのシェアは6割にも及ぶとされている228。まず、問題意識を共に把握するための認識を共有し、市民や患者、医療従事者、政府担当者との信頼関係を構築することで、自社の事業を円滑に進めることができた事例ともいえる。
さらに、企業独自で現地の人々と認識を共有し、社会的課題に対し問題意識の共有を目指している例としてオムロンが挙げられる。インドにおいても中国同様、高血圧や糖尿病などの生活習慣病の患者が急増しており、改善や予防が社会的課題となっている。生活習慣病の改善には、身体状況の把握が不可欠であるものの、インドにおける血圧計の普及率は2%と非常に低く229、電子体温計、体重体組成計、歩数計など健康・医療機器の利用も低水準に留まっている。背景には、健康管理が疾病予防につながるという認識がなされていないということがある。健康管理の重要性を認識してもらうため、インドにおける臨床研究などを支援したり、現地の薬局で働く人に向けて健康管理に関するセミナーなどを開催し、課題に関する共通認識を持てるような事業活動を実施している。こういった活動を通じて、健康管理に関連する他の製品・サービスの潜在市場の創造も期待される。
企業が課題解決に向け、企業独自で現地の人々と関係を構築した事例のように、潜在的な市場を有する地域で社会課題解決に取り組もうとした際に、地域の市民や消費者にその課題に対する問題意識や課題解決の意義が浸透していないことが少なくない。そうした場合には、人々への啓発活動などを通じて、共に問題意識を把握できる認識を共有していくことの意義は大きい。
さらに、企業がこういった社会課題の解決への貢献を継続していくためには、事業として利益を伸長することが不可欠である。サステナビリティへの取組は、「コストがかかる」「十分には儲からない」「短期的には芽が出にくい」など様々な壁に直面する。しかしながら、こういった壁に対し、企業は多様な方法で社会課題解決と事業の利益伸張を両立させようとしている。こういったトレードオンのビジネス構造を目指すことで、従来なかった発想や新しいイノベーションを生み出すことも期待される。
例として、eラーニングによる教育サービス等を提供しているすららネットがあげられる。教育サービスを提供するという「直接的貢献」のみならず、教育サービスにより現地の低所得層の子供の教育格差を是正することで、就業機会を得やすくし、将来の選択肢を増やすことが期待される。さらに、執務はe-ラーニングが担うことから、教務経験のない現地の女性でも数日間の訓練で教室運営者に育て上げることが可能となり、雇用も創出していることで、女性の自立、社会進出を促進し、社会的に不利な立場にある女性を減らしていくことも期待される。こういった「間接的貢献」が現地の人々に裨益することで豊かさにつながっていき、一過性ではない関係性が構築でき得ると考えられる。また、こういった関係はリレーショナルキャピタルという無形資産とも捉えられる。
他の例として、廃棄物処理・資源物リサイクル事業を主力とする西原商事の例を取り上げる。西原商事は、インドネシアのスラバヤ市に、JICA事業として分別リサイクル施設230、環境省事業として生ゴミの堆肥化施設を導入している企業であり、福岡県を拠点に海外でも活躍するグローカル企業である231。いずれの事業でも、資源循環率の向上などによる環境負荷低減という「直接的貢献」のみならず、低所得者層の雇用創出と継続的な人材育成や地域住民の環境意識の向上によって河川への不法投棄回避による水害防止や交通渋滞の緩和等の「間接的貢献」も創出してきた。多角的な貢献によって現地のステークホルダーとの信頼関係を構築してきた経緯もあり、スラバヤ市において長年の課題であった医療系廃棄物の適正処理に向けた新チーム立ち上げの際には、直接指名で協力要請を受けて現地実証を実施し、日本の環境技術の提案を進めている232。背景には、JICA事業としての支援のみならず、北九州市とスラバヤ市との間の自治体間での協力関係があったことも成功の一因としてあげられる。このように信頼関係をもとに成立する技術移転事業では、国・自治体と民間企業が明確な役割の中で連携することで、単発支援に終わらない継続的な事業展開が見込まれ、他都市にも横展開することでより大きな事業規模となることも期待される。
第Ⅱ-2-3-4表 社会課題解決型事業へのアプローチ
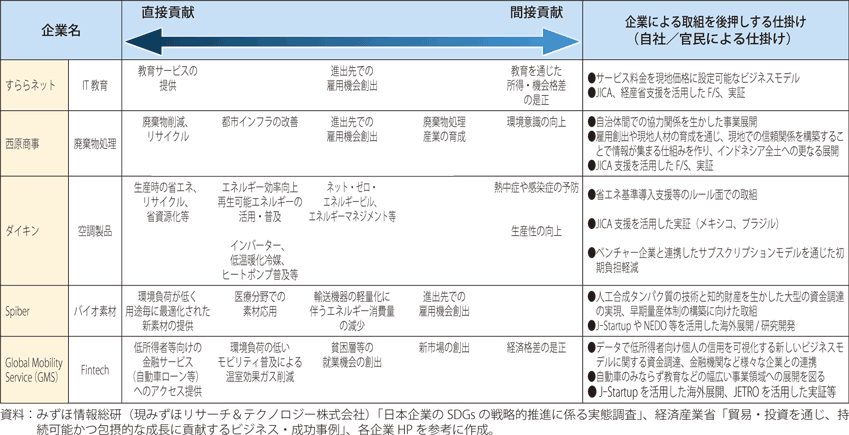
また、環境や社会に資する事業を進めるうえで、市場制度やインフラが整っていなければビジネスは成立し難いという課題もある。そういった課題に対し官民連携でルールを作った例もある。例えば、空調機大手のダイキンが温暖化影響の小さい冷媒「R32」を搭載した空調機を開発し233、それをグローバルスタンダードにするため働きかけを行った例である234。環境問題や空調関連の国際会議に出向き、国際機関の関係者や各国の政府責任者、オピニオンリーダー等との交流を深め、自社の冷媒技術が温室効果ガス削減にどれほど寄与するかデータで説明した235。それらの結果、国際規格の改定を実現し、特許などの開放も実施した結果、グローバルスタンダードとして普及するに至った。さらに、新興国において官民連携でISO国内規格化への働きかけや消費者の判断基準となる省エネラベリング制度の支援も実施し236、商品の普及を後押しした237。インド238や中国239、メキシコ、ブラジル、サウジアラビア、アラブ首長国連邦など幅広い地域で取組を展開させている。
このように、企業は幅広い方法で、環境・社会の価値と経済的な価値(利益の伸長)を両立させ製品・サービスを通じた豊かさへの裨益から、雇用創出や地域経済の振興などに至るまで、直接的貢献と間接的貢献に取り組んでいる。そのためには、先述の多様なパートナーや機関との連携による啓発活動を通じた市場形成、雇用創出を通じた進出先での持続的な関係の構築、現地との信頼関係を通じた新市場の開拓や、ルール形成と組み合わせた新技術や新素材の開発・普及などの方法が一層求められ、企業による本業を通じたこうした取組の推進や、そのための仕組み作りが重要となってくるだろう。
227 坂野・磯貝(2021)
228 名和(2021)
229 オムロン 決算説明資料(2020年度)
230 2014年9月にはスラバヤ市に譲渡、その後は政府予算による運営。
231 みずほ情報総研(2021)
232 2018年3月には、スラバヤ市長より派遣された調査団が北九州市を訪問、北九州市における医療廃棄物処理の実態調査を実施。2018年8月にはスラバヤ市長が来日し、スラバヤ市長と北九州市長との協議が実施、11月に基本合意が形成され現地実証や現地調査に至った。
233 経済産業省(2019)
234 エアコンに搭載するためにはISO817(冷媒安全分類規格)の改訂が不可欠であった。冷媒「R32」は燃えにくく(安全性が高く)、温暖化の影響も小さかったが、旧分類においては「可燃」に分類され製品での使用が難しかった。そこで新カテゴリを求めロビー活動などを実施。
235 坂野・磯貝(2021)
236 インドでは2015年にインバーターによる省エネ効果を適切に評価できる指標(CSPF)を評価基準としたエネルギーラベル制度の導入支援を実施。
237 インドにおいては、国際標準化改定とインドでの国内規格化協力での効果は5年間で販売台数36万台増、売上げ151億円増となり販売首位。中国においては、省エネ基準を改正し(ノンインバーター機の省エネ性能の足きり基準を引上げ)基準を満たさない商品の販売の規制を実施。省エネ基準改正により、5年間で980万台、約1920億円の売上(中国空調部門の約16.6%に相当)となった。
238 経済産業省(2019)
239 株式会社 オウルズコンサルティンググループ(2021)
コラム3 アジアにおける日本の可能性と日本への還流
前節で述べたようにアジアは多様な環境課題に直面している。また、人口の増加や急速な都市化は環境への負荷を増大させるおそれがあり、さらなる環境への配慮が求められる。このようなアジア諸国に対して、日本が貢献できる余地は大きい。かつて日本は公害問題やオイルショックから環境負荷の少ないサービスや省エネ技術を発展させてきた。加えて、日本はアジアの中に位置しASEAN諸国などと地理的に近く、現地に根付いたサプライチェーンを構築していることから、課題を把握・共有しやすいという利点を有する。また、欧州のようなサービス経済化した産業構造の国とアジアの国々のように一定程度製造業が残る国々では直面する課題が異なるとの指摘もあることには留意が必要であろう240。
アジア諸国を中心として低炭素化に向けて莫大な規模の投資が必要とされている中、欧州が進める再生可能エネルギー等の「グリーン」241だけでは経済との両立が難しい場合もある。我が国は着実に低炭素化・脱炭素化を進めていくような省エネ技術を含めた「移行(トランジション)」や、CO2の大幅削減に向けた「イノベーション」などを提供できる技術を有しており、そういった分野への資金投入も期待される242。
CO2を始めとする温室効果ガスの排出削減などに資する「気候変動緩和技術」における各国の特許件数を比較すると、日本が最も多く、米国、韓国、ドイツと続く(コラム第3-1図)。日本は特に、「エネルギーの発電・送電・配電」に関する技術の特許件数が多く、これにはエネルギー貯蔵用の電池や燃料電池が含まれている。次いで、特許件数が多かった分野が「輸送」関連技術である。中でも、電気自動車や環境に配慮したガソリン車及びディーゼル車、電気自動車用電池の特許件数が多かった。さらに、「商品の製造または加工」に関する特許、例えば、金属加工における効率化技術などに関する技術も目立つ。
コラム第3-1図 気候変動緩和技術の特許件数
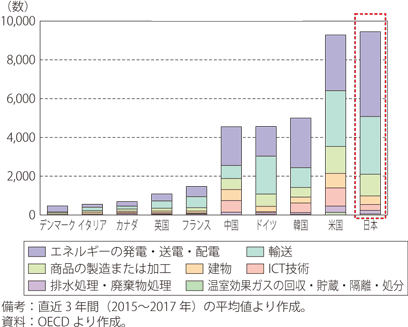
近年、ASEAN諸国やインドにおいてデジタル化が急速に発展し、デジタル技術によって社会課題を解決するようなビジネスが勃興している。アジア諸国に着目した日本政府の動きの一つとして、「アジア・デジタルトランスフォーメーション(ADX)」という構想が進められている243。この事業は、日本企業が有する技術やノウハウ等の強みを活かしながら、アジア諸国の企業との協働を通じ、現地の社会課題解決に貢献するような事業を推進するものである。2020年10月には、「日ASEANにおけるアジアDX促進事業」の公募が実施され、ブルネイを除く全てのASEAN加盟国で幅広い分野244に基づく計23件の日ASEAN企業連携プロジェクトが採択された。そのうち、以下では代表的な事業について紹介する。
島しょ国であるフィリピンが抱えるエネルギーレジリエンスへの課題と低炭素化に貢献したものとして、株式会社チャレナジーの例がある245。同社は、高い発電コストや不安定な電力供給等が課題となっている離島において246、現地エネルギー関連企業や現地政府とも連携し、安価かつ災害時にも安定的に供給できる風力発電を設置した247。風力発電を中心とした電力系統を導入し、電力系統の遠隔監視・制御も可能なバーチャル電力プラットフォームの構築も進めている。
また、少子高齢化を受けた労働生産性の向上、地方における産業基盤の強化等が課題となっているタイにおいて、自然環境の保全とエビ養殖の生産効率を改善した例としてウミトロン株式会社の事例がある。これは、タイの基幹産業であるエビ養殖向けにIoT/AIによる、池の中のエビを自動解析する世界初の同社の技術を活用し、環境負荷が少なく、効率的なエビ養殖を可能とした事業である248。現地企業との連携に加え、農業組合省漁業局との連携も予定している249。
さらに、慢性疾患の増加と人口の高齢化による医療費支出の増大という課題を抱えるシンガポールにおいては、AI問診システムを提供するUbie株式会社の事例が挙げられる250。同社のAI問診技術により、診断に必要な患者情報の多くをデータ化することにより、医師の能力によらず診察の質が向上することが期待されている。また、診察の前に患者情報の多くを取得できることによって、診察時間の短縮(医師の負担減)及び待ち時間の短縮(患者の負担減)、疾患の見落としリスクの低下など、広く医療機関の抱える課題の解決にも取り組んでいくことが可能となっている。
アジア諸国では、その国の事情や発展段階によって様々な経済・社会課題に直面しており、それぞれの国の課題に合わせた、きめ細かなアプローチが求められる。アジア諸国が抱える社会課題の深さや人口規模から考慮されるインパクトの大きさ、ベンチャーフレンドリーな市場環境(先進国とは異なる制度・規制環境)もあり、日本企業が現地企業と連携していく意義は大きい。社会課題解決に向け、内発的に勃興してきているアジア諸国のベンチャー企業に対し、積極的に資金や技術、ノウハウを投資していくことが日本企業にとっても市場の確保や事業経験を積むうえでも有益であると考えられる。これまで製造業の生産拠点を中心に形成してきたアジアと諸国のネットワークは、流通や金融も含めて深化しているところ、デジタルを活用したサービスソリューションを提供していくような事業活動にも広がっていくことで、アジア諸国において日本企業が活躍する幅や深さも広がっていくと期待される。
さらに、将来的には、アジア諸国で行ってきたビジネス経験を日本へ環流させていくことにより、日本のビジネス環境の改善(規制改革等)につなげていくことで、日本自身にも利益が裨益する可能性を秘めていることも、この事業を進めていくべき理由の一つである。
240 経済産業省(2020)
241 2020年6月 欧州議会は「タクソノミー」を定めたEU規則案を可決。同規則では「6つの環境目的」と「4つの要件」を定めている。「6つの環境目的」には①気候変動の緩和②気候変動への適応③水および海洋資源の持続可能な利用と保全④サーキュラーエコノミーへの転換⑤汚染防止と管理⑥健全な生態系の保護が定義されている。同規則に基づくdelegated actにおいて上記目的に資する活動が定義される。
242 多排出産業が脱炭素に向けた道筋を描くための分野別ロードマップを策定予定。
243 経済産業省
244 医療・ヘルスケア、農業、水産業、観光・モビリティ、環境・エネルギー、製造・人材育成の分野。
245 JETRO「日ASEANにおけるアジアDX促進事業」
246 フィリピンの離島では、高いエネルギーコスト・環境負荷・自然災害に対しての電力インフラが脆弱である。900万人以上が未電化地域に居住しているのに加え、1日8時間以下の電力供給しか得られない人々が数千万人存在する。
247 設置面積が小さくてすむ風力発電は太陽光発電に比べ、土地面積が限られる場所では優位である。また、プロペラのない風力発電であるため、台風などの強風に対して従来の風力発電よりも強い。四方を海で囲まれ山が多い日本の場合、風土に適さず、風力発電はあまり導入が進んでいなかった。しかし、日本も四方を海に囲まれ国土が小さく台風なども多いこともあって、発明につながった。同じ島しょ国であるフィリピンの課題解決に貢献した例と言える。
248 タイの基幹産業である水産業は、世界的に需要が見込まれており輸出拡大への関心が拡大。人件費の高騰や高齢化などの課題もあり農林水産業DXに強い関心がある。
249 JETRO「日ASEANにおけるアジアDX促進事業」
250 JETRO「日ASEANにおけるアジアDX促進事業」
コラム4 雇用・労働と通商ルールの関わり
1.地域貿易協定では労働条項を含む割合が増加
特に製造業の国際分業体制の発展でその流れが顕著であるように、経済のグローバル化が進展する中で、他国・地域との関わり方を規定する通商ルールの在り方はますます重要になってくると考えられる。本コラムでは特に雇用・労働と通商ルールがどのように関わっているのかを見ていく。
雇用・労働と通商ルールの直接的な関わりとして、地域貿易協定の締結において労働条項を含む割合が増えてきていることが挙げられる。下記(コラム第4-1図)は、地域貿易協定の締結が盛んになり始めた1990年代から、各年に署名された地域貿易協定数を累積(開始時点は1990年)で示したものである(地域貿易協定と労働条項の定義は同図の脚注を参照)。それを見ると、労働条項が含まれている地域貿易協定は2000年代の序盤からその割合が徐々に高まっている。
コラム第4-1図 地域貿易協定の署名動向
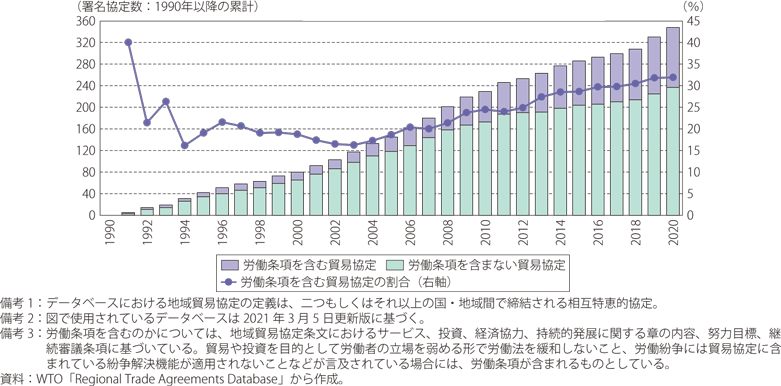
後述のとおり、地域貿易協定に労働条項を含めることに対しては賛否両論がある。しかし、労働条項を含む地域貿易協定の割合が高まりつつあることは、雇用・労働に関するルールの標準化が重要であるとの認識が参加国間で高まっていることを示唆している。近年では、EUと英国(EU離脱に起因すると見られる)による他国・地域との地域貿易協定の締結が目立っているが、それ以外の国・地域同士でも労働条項を含んだ地域貿易協定が締結されていることは、そうした認識が共有されていることを示唆している(コラム第4-2表)。
コラム第4-2表 労働条項を含む地域貿易協定
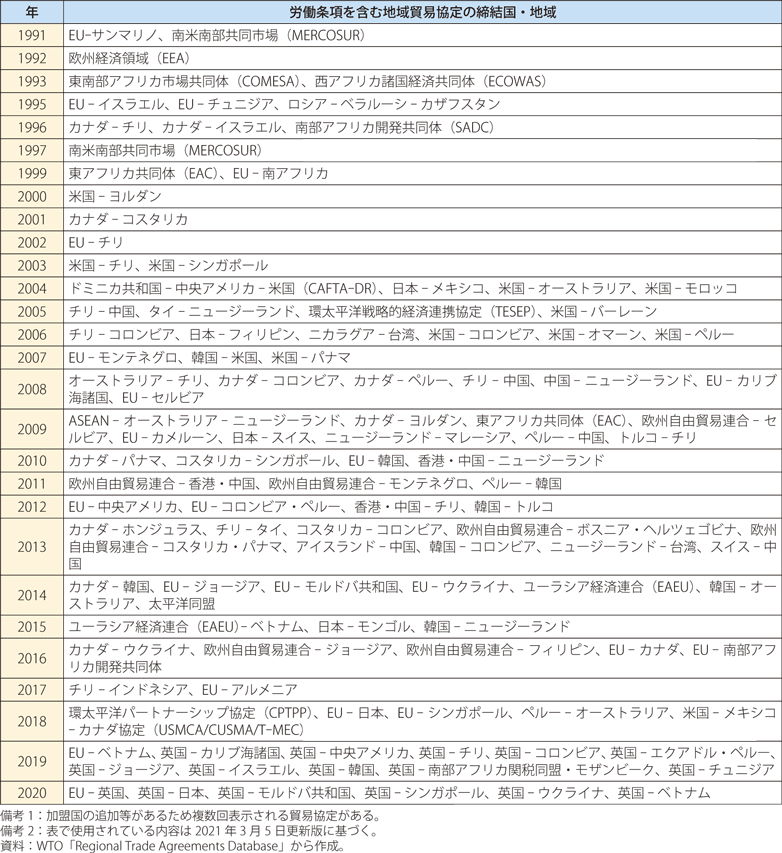
また、通商ルールと雇用・労働の関わりという面では、2018年に署名された米国-メキシコ-カナダ貿易協定(いわゆるUSMCA)が注目される。同協定の原産地規則を満たすためには、自動車生産の工程における一定割合以上が時給16ドル以上の地域でなされることとされているためである。そうした細則の遵守が可能であるのか(いわゆるエンフォーサビリティ)等の点が注目されている。
2.地域貿易協定と貿易投資・労働の関連性
地域貿易協定に労働条項を含めることの賛否に関しては、先進国と発展途上国の経済発展段階に根ざした理由が挙げられている。
先進国側からの見方では、労働条項によって過度な低賃金労働に対する歯止めがなければ、地域貿易協定は発展途上国からの安価な製品供給を過剰にすることで、競合する国内産業の業績を悪化させ、雇用が削減されるとの懸念がある。すなわち、労働条項による規制がなければ、発展途上国による輸出市場の獲得や、直接投資を呼び込むことを目的とした労働基準の過度な緩和競争(いわゆるRace to the bottom:底辺への競争)が止まらなくなるとの懸念がある。したがって、労働条項によって労働基準の平準化が図られるべきだとの議論がなされている。
一方で、発展途上国側からの見方では、比較的に低位な賃金水準の労働力を使って安価な製品を提供できることは比較優位の源泉であり、労働条項はそれを損ねることで経済成長の機会を奪ってしまうとの懸念がある。また、地域貿易協定によって実現される先進国への市場アクセスが労働条項を前提にしている場合があり、労働条項自体が交渉材料として使われてしまっているといった批判もある。
こうした先進国側からと発展途上国側からの議論を踏まえて、通商ルールと雇用の関連を分析した実証研究を見ていく(コラム第4-3表)。実証研究の潮流を追ってみると、地域貿易協定が労働条項を含む割合が高まり始めたのが2000年代の序盤以降であったことから、それ以前の実証研究では労働基準と比較優位の関係が主な分析対象となっていた。地域貿易協定に労働条項が含まれることが増えるにつれて、実証研究の主な分析対象は、発展途上国間で底辺への競争は起きているのか、労働条項によって国・地域間の労働基準は平準化されるのか、労働条項は地域貿易協定の貿易創出効果に影響を及ぼすのかといった点に広まっていった。
コラム第4-3表 通商ルールと貿易・雇用の関連を分析した実証研究例
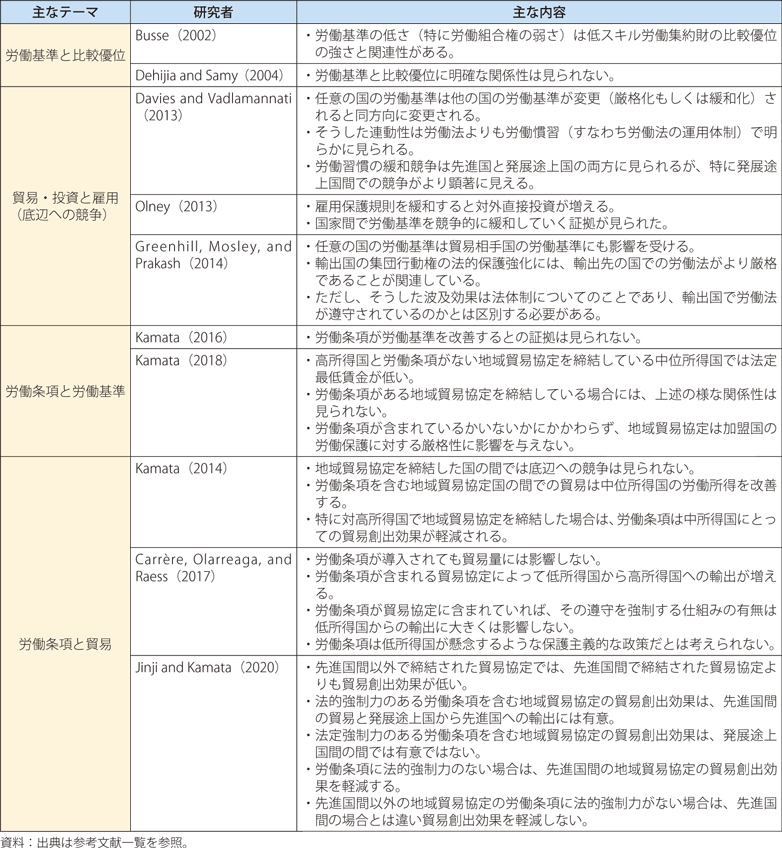
それらの実証研究では主要な論点の議論が分かれており、地域貿易協定には貿易創出効果があるということ以外では、主流な考え方は形成されていないように見られる。具体的には、労働基準は比較優位へ有意な影響があるのか、労働条項は底辺への競争の歯止めとなっているのか、労働条項によって先進国の比較的高い労働基準が発展途上国へと波及しているのか、そして労働条項は地域貿易協定の貿易創出効果に有意な影響を与えるのかといった論点については、実証結果が分かれている。各国を比較する方法としては、国際労働機関(International Labour Organization:以下ILO)が定める国際労働基準(いわゆるガイドライン)の各項目への批准状況といった数値指標が比較対象とはなり得るものの、分析対象が労働法や労働基準といった定性的な側面を持っていることが議論の複雑性を高くしている。
一方で、国際的に競争力や労働基準を比較するために客観的に観察できる指標もあり、本コラムにおいては、競争力に関する指標では顕示比較優位指数に注目し、労働基準に関する指標では法定最低賃金に注目していく。労働条項を含む地域貿易協定に参加している発展途上国についてそれらを観察することで、労働条項が比較優位を失わせてしまっているのか、また労働条項が底辺への競争の歯止めになっているのかを観察していく。
貿易理論で提唱されている比較優位については、実際に観察される統計を用いて数値化する手法が確立されている。具体的には、各国の比較優位を顕示比較優位指数(ある品目についての当該国の輸出割合を当該品目の世界の輸出割合で除することで算出され、1を超えていると国際競争力を有しているとされる)によって観察する手法が実証研究でも用いられている。
労働条項を含む地域貿易協定が世界の多様な国・地域間で締結されていること、そして特に製造業で国際分業が進展していることを踏まえて、下記(コラム第4-4図)では、世界銀行の分類による高所得国(一人あたりGNIが1万2,536ドル以上)以外で労働条項を含む地域貿易協定に加盟しており、かつ機械類や同部品等(貿易品目の国際的な分類であるHSコードの84-87類)が主要な輸出品目である国の顕示比較優位指数を示している。労働条項を含む地域貿易協定の締結が盛んになってきた2000年代の序盤以降で顕示比較優位指数を見ると、メキシコ、セルビア、トルコ、チュニジア、モロッコで上昇している。アジア地域では、中国とマレーシアが横ばい、タイとフィリピンでは2008年の世界金融危機後に低下した後は横ばい、ベトナムでは大幅な上昇となっている。こうした各国の差異はありながらも、地域貿易協定に労働条項が含まれていることが直接的に起因すると見られる顕示比較優位指数の特異な低下(すなわち競争力の低下)は観察されていない。
コラム第4-4図 機械類・同部品が主要輸出品目の国の顕示比較優位指数
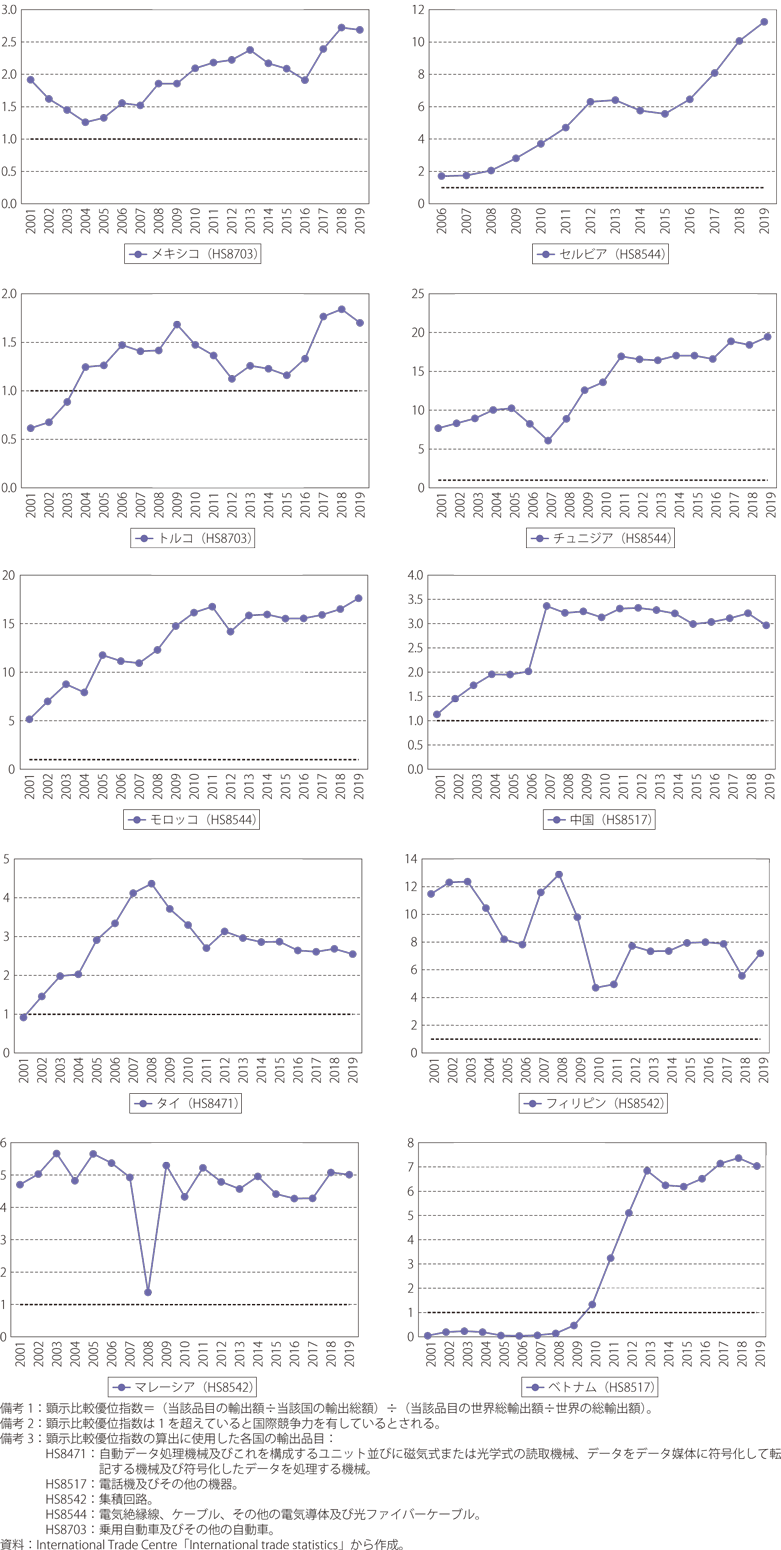
また、各国の労働基準を比較する上で、具体的な数値比較として法定最低賃金を観察することも実証分析で用いられている手法の一つである。上述の国の中で、ILOから公表されている法定最低賃金と、世界銀行から公表されている一人あたり名目GNIを比較すると、両者の動きは概ね連動している(コラム第4-5図)。このことから、法定最低賃金の変動は経済規模の変動によってかなりの部分が説明されることが示唆されており、同図からは労働条項の有無に起因すると見られる特異な変動は観察されていない。すなわち、労働条項の法定最低賃金に対する影響は、経済規模に比較すれば軽微であることが示唆されている。労働条項が比較優位を損なうとの発展途上国の懸念はあるものの、比較的に安価な労働力を供給できるのかは、労働条項の有無ではなく経済発展の度合次第になっているように見える。
コラム第4-5図 機械類・同部品が主要輸出品目の国の法定最低賃金と一人あたりGNI
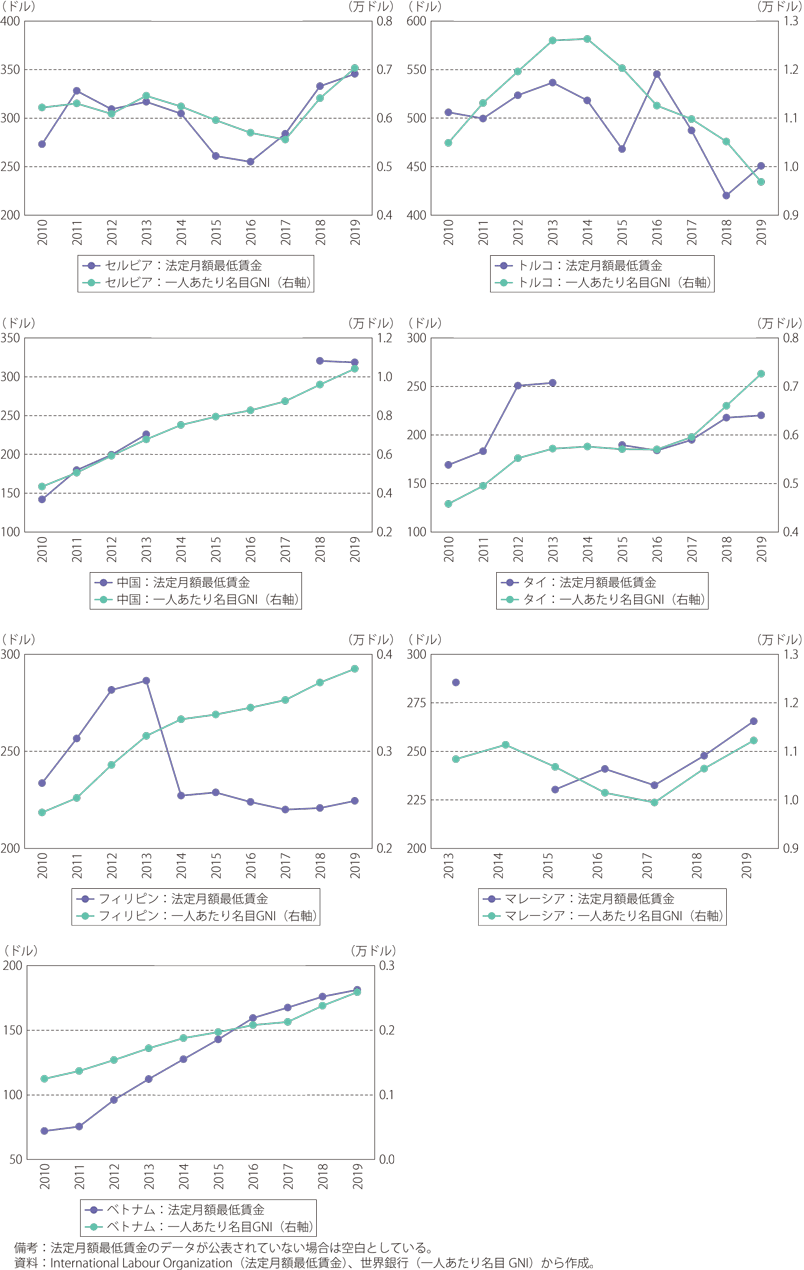
また、輸出市場の獲得や直接投資を呼び込むための労働基準の緩和競争を意味する底辺への競争は、特に同地域に属する国の間で深刻化することが懸念される。それを踏まえて、顕示比較優位指数と法定最低賃金を観察している国の中でも、同じアジア地域に属するタイ、フィリピン、マレーシア、ベトナムを見ると、これらの国の間で法定最低賃金に競争的な低下圧力があるようには見えない。それが労働条項の効果であるとは断定できないものの、いわゆる底辺への競争に対して一定程度の抑止力になっていると見られる。
上述の顕示比較優位指数や法定最低賃金の動向を総合すると、地域貿易協定に労働条項が含まれているとしても、それが各国の競争力や労働基準に対して多大な影響を及ぼすということではないように見える。ただし、いわゆる底辺への競争に対する一定程度の抑止力になっていると見られることからも、労働条項は重要な役割を果たしていると考えられる。さらに、特に先進国の消費者が発展途上国で製造された日用品等を購入する場面においても、製造過程での労働者保護に対する意識が高まっていることも重要である(いわゆるエシカル消費や人権デュー・ディリジェンスへの配慮)。例えば、発展途上国において食品や衣服等が違法労働を用いて生産されていた場合には、それらの輸出先国において労働者の人権が問題視され、結果としてそれらの貿易が停止される事態が起こり得る。そのように、労働基準の低さが貿易相手国によって認識されることで、貿易が滞り得ることがあることからも、底辺への競争に対して一定程度の抑止力がある見られる労働条項の重要性は低くはない。これらのことを踏まえると、地域貿易協定に含まれる労働条項を通して、通商ルールと雇用・労働の関わりを考えていくことは重要である。