第Ⅰ部で示した潮流およびこれまでの分析を踏まえ、通商政策はどうあるべきか。大きな方向性を提示する。
1.世界で進行する地殻変動
コロナ禍がもたらした新たな国際競争環境下で、世界では、コロナ危機からの回復を目的とした雇用維持や、デジタル、グリーンといった将来の成長への投資・産業政策に向けた歳出拡大による「大きな政府」志向が高まっている。また、半導体等の重要技術や物資について、サプライチェーンの強靱化や機微技術管理の強化、研究開発や設備投資の促進等により「経済安全保障」を確保する動きが拡大し、それに伴う有志国連携の動きも具体化しつつある。さらに、国際経済活動において、環境や人権といった「共通価値」への関心が急速に高まってきており、コロナ禍でデジタル技術の利活用が一層拡大し、ビジネスのデジタル化の動きが加速している。
こうした地経学的な地殻変動とも言える「大きなうねり」が世界的に進行する中、グローバルバリューチェーンの管理は、経済安全保障の観点からの「攻め」と「守り」や、環境・人権等の共通価値への関心の高まりへの対応など、考慮すべき変数が増加し、より複雑化している。かかる複雑化へ対応するため、デジタル技術やデータを利活用してバリューチェーン全体を把握し、信頼あるバリューチェーンを確立することが、企業の経営や政策における大きな戦略課題となっている。
加えて、自由主義、開放型経済社会システムを維持・発展させるためにも、「自由貿易」をアップグレードしていく必要性が高まっている。また、これまでの自由貿易体制は、比較優位論の理念に基づく輸出主導型の産業実態と、ビジネスの効率性を実現させるための関税等の貿易障壁削減・撤廃を推進する国際規範といった伝統的なフレームワークをベースにしてきた。今日では、企業が国を選びビジネスの効率化を追求するというグローバル化の理念の下、多国籍企業が国境を超えた複層的なサプライチェーンを構築し、国際規範によってビジネス・投資環境を整備する体制となっている。
しかし、昨今の地経学的な地殻変動を受け、伝統的な自由貿易のフレームワークやグローバリゼーション・モデルに加え、持続可能で公正な経済社会の実現の要請が国際的に高まってきている。ビジネスの実態面では、上述のとおり、様々な変数に対応した「信頼」あるバリューチェーンの構築の要請があり、国際ルールの観点からは、持続可能性や公正性、社会正義の実現に向けた規範づくりが課題となっている。
第Ⅱ-3-1図 「信頼」あるグローバルバリューチェーンの構築の必要性
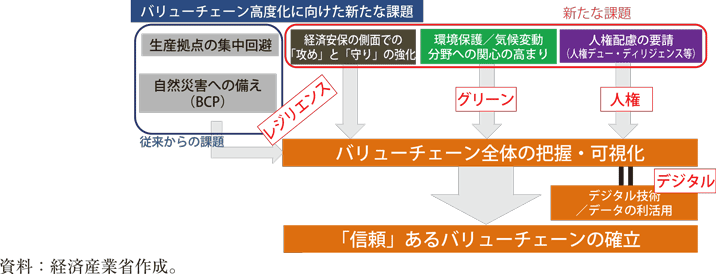
第Ⅱ-3-2図 「自由貿易」のアップグレードの要請
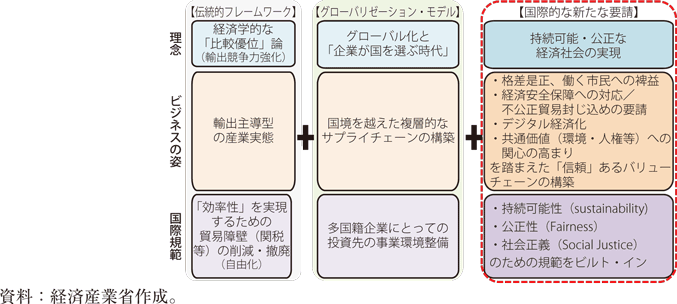
2.経済安全保障と産業競争力の強化に向けた取り組み
第Ⅰ部で示した様に、米中両国による技術覇権争い等を背景として、コロナによるサプライチェーンの脆弱性が顕在化したことも相俟って、各国における経済安全保障の取り組みが強化されている。我が国の経済安全保障を確保するためには、重要技術や物資に係る我が国の優位性と脆弱性を把握した上で、海外における生産拠点の集中度の高い重要物資等の生産拠点多元化支援による調達先の集中度低減や海外企業との戦略的提携の拡大、有志国との「信頼」を軸としたグローバルサプライチェーンの構築が重要である。外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく輸出管理・投資管理の徹底に加え、国際輸出管理レジームを補完する枠組みの検討や、アカデミアにおける技術管理強化を含む技術の流出経路に応じた統合的な流出防止策の構築により、機微技術管理を徹底することが不可欠である。さらに、有志国との連携を含めてチョークポイントとなる技術の研究開発や設備投資を促していくことも重要となる。これらの取組を通じて、有志国との適切な役割分担の下で重要生産基盤の国内整備を進め、先端技術研究開発コミュニティにおける重要な地位を確保し、経済安全保障上の重要技術や物資に係る我が国の「脆弱性の克服」と「優位性の確保」を実現していく。
また、企業経営の観点からは、経済と安全保障を一体として捉えた上で、国際競争力強化に取り組むことがますます重要になっている。日本企業においては、機微技術管理に関する国際動向を本社ベースで把握するための体制整備や、サプライチェーン上のリスクの精緻な把握など、各国による規制強化への適時の対応が求められている。他方で、法令順守を超えた過度な萎縮は不要であり、事業機会を失わないよう米欧の競合他社をベンチマークしつつ、技術流出の適切な防護や公正な競争条件の確保、イノベーティブな主体との連携を図ることで市場での収益拡大や新たな研究開発投資に繋げるような「したたかな」対応を行っていくべきである。
3.デジタル分野での課題と取り組み
第Ⅱ部で示したように、不確実な事業環境の中、企業にとってはデジタル技術を活用してバリューチェーン強靭化を図っていくことが重要である。例えば、貿易手続のデジタル化(ブロックチェーン活用での通関手続デジタル化、原産地証明書の電子化対応、貿易管理手続の電子化推進)は、我が国製造業の購買力の強さ、サプライチェーン管理の強みをプラットフォーム化しバリューチェーンに組み込むだけでなく、中小企業のバリューチェーン参画を促す上でも有効である。また、コロナ禍で拡大するECを活用した販路開拓を通じて、日本企業の更なる海外展開を推進していくことが重要である。ジェトロにおけるECサイト出展支援で、日本企業のEC活用は進んでいるが、更なる販路拡大には、①マーケットニーズに応じた商品改良やECサイトページ作成などの出展前支援や、②海外現地での販路開拓や配送インフラの整備等の一貫した支援が必要である。
コロナ危機への対応として、各国でデジタル化やデータ戦略強化の動きが顕著になってきている。将来産業を生み出すデータを囲い込み、独占的にAI開発をする動きも顕在化している。こうした、企業の自由な活動を阻害する域外へのデータ移転規制、データローカライゼーション(データの域内保存)要求や知的財産や個人情報流出等の懸念にもつながりかねないデータへの無制限なガバメントアクセスは、グローバルにビジネスを展開する企業への影響も大きい。
第Ⅱ-3-3図 デジタル分野における各国・地域の積極対応がもたらす新たな課題
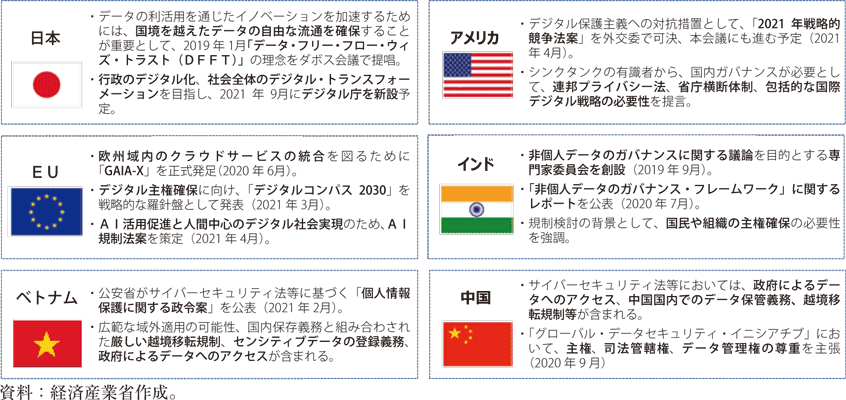
このため、企業のビジネス機会を阻害し得るデジタル保護主義の拡大を防ぎ、プライバシー保護やセキュリティなどの信頼確保と自由なデータ流通が両立する国際ルールの策定、すなわちDFFT251の実現に向け日本が主導して取り組み、データがもたらす新たな価値の創出と更なる経済発展に貢献していく。
今後加速するデジタル社会で、安心・安全なデータ流通・デジタル技術の活用を図るためには、データの適切な保護など、取引における「信頼」が重要な判断要素になると考えられる。既存産業やサプライチェーン事業そのものを覆しうる「デジタル化」があらゆる業態・ビジネスで進むなか、有志国とともに共通の価値軸となる「信頼」を具体化していくことが必要である。
第Ⅱ-3-4図 「信頼」できるデジタル経済の構築
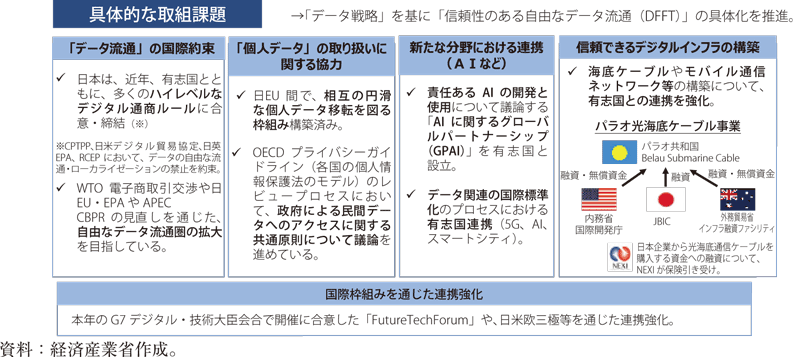
251 信頼性のある自由なデータ流通(データ・フリーフロー・ウィズ・トラスト)。2019年1月ダボス会議にて、安倍前総理が提唱した基本的な考え方であり、同年のG20大阪サミット及びG20貿易・デジタル経済大臣会合等、以降の国際会議でも幅広く合意されている。
4.共通価値(環境・人権等)への対応
(1)グリーン
2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略252に基づき、グリーン成長を巡る戦略競争を主導する側に回り、米欧と連携して協力を具体化するとともに、国際ルールの形成を進めていき、内外一体の産業政策を着実に進めていくことが重要である。
世界全体でのカーボンニュートラル実現に向け、我が国としては各国との国際連携を進めていく必要がある。例えば、日米首脳会談において「野心、脱炭素化及びグリーンエネルギーに関する日米気候パートナーシップ」が発表されるとともに、同年5月の日EU定期首脳協議においても、「日EUグリーン・アライアンス」の立ち上げに合意した。
また、エネルギー需要が拡大するアジアでは、あらゆるエネルギー源と技術を活用した、多様かつ現実的なエネルギートランジションが不可欠である。このため、アジアの持続的な経済成長とカーボンニュートラルの同時達成に向けて、「アジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ(AETI)」を日本が提唱し、ASEAN各国と取り組んでいく。
第Ⅱ-3-5図 アジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ(AETI)
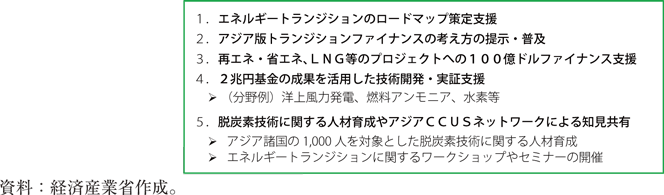
(2)人権
第Ⅱ部で示した様に、グローバルな企業経営にとって、「人権」を含む社会課題への対応を経営戦略に組み込む国際的潮流への適応は、急務となっている。政府としては、ビジネスと人権の国際的フレームワークとしての、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」や「OECD多国籍企業行動指針」等をふまえ、「行動計画(NAP)」を昨年10月に策定し、関係省庁と連携しつつ、産業界への普及啓発に取り組んでいる。
この行動計画では、企業に対して、人権デュー・ディリジェンスの導入を期待する旨を表明している。まずは、本行動計画の周知啓発を行い、産業界の意識向上・取組の促進に努めていくことが重要である。
第Ⅱ-3-6図 人権に関する取り組み
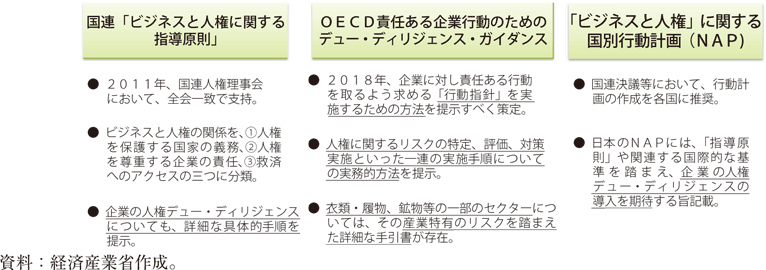
5.自由貿易体制のアップグレード
我が国企業の「強み」を活かしたグローバルバリューチェーンの更なる高度化を実現するためには、現下の諸課題に対応した経済秩序の形成と官民の戦略的連携が必要である。
具体的には、①ワクチン等の輸出制限や国内産業保護のための関税引き上げといった自国優先・保護主義的な貿易制限措置の常態化のおそれや、②外国政府・企業の市場歪曲的措置等による「公平な競争条件」の毀損、③経済活動のデジタル化に対応した国際的なルールの未整備、が課題となっている。このため、WTO、EPAのようなハードローだけでなく、ソフトローとしてのOECDやAPEC等での規範作り(例:データガバナンス)、日本の強みを活かすバリューチェーンの官民作り込み(例:サプライチェーン強靭化イニシアティブ、米欧との協力)など、複層的なアプローチが重要である。
第Ⅱ-3-7図 人自由貿易体制の「アップグレード」を支える経済秩序の形成と日本の強みを活かすバリューチェーンの作り込み
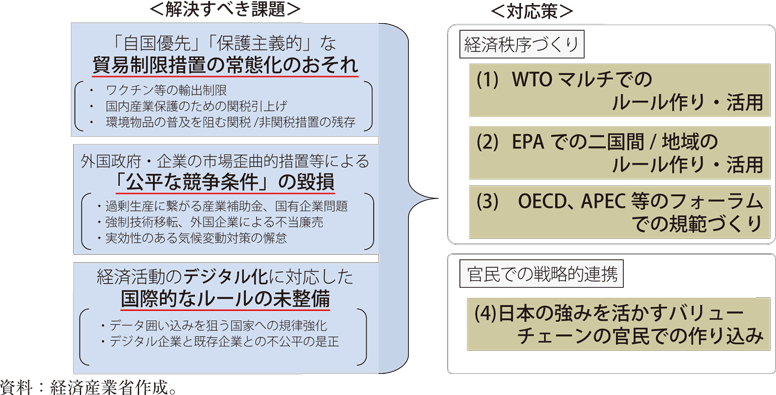
WTOでは、電子商取引、貿易と保健、貿易と環境といった新たな分野における有志国によるルール形成の議論に積極的に関与・牽引するとともに、市場歪曲的措置に対処し公平な競争条件を実現するための有志国連携(日米欧三極貿易大臣会合等)の取組を強化する。また、上級委員会の機能回復等、紛争解決機能の改善に向けた取組を進める。
EPAについては、CPTPP、日EUEPA、日英EPA等により形成した21世紀型の自由で公正な貿易・投資ルールを、アジア太平洋地域の域内で効果的に実行することや、域外への拡大を図ることが今後の課題である。また、RCEPの早期発効やインドの復帰に向けた取組も我が国が牽引していく。なお、CPTPPについては、2021年2月に英国が加入要請を提出した。同年6月のTPP委員会において、CPTPPのハイスタンダードのルールを前進させる必要性を念頭に置き、ハイスタンダードな国際貿易・投資ルールに関する英国の経験、ルールに基づく貿易システムにおいて、透明性・予測可能性・信頼性を推進するという英国のコミットメント等を考慮し、英国の加入手続き開始が決定された。今後、加入作業部会を通じて、英国のCPTPPルールの遵守の手法について確認するとともに、市場アクセス交渉を行っていく。
OECDでは、プライバシーに関するガバメントアクセス原則や、デジタル国際課税のルール見直しに関する議論が行われている。また、APECでは、個人情報の越境移転に関する課題の整理や、関税削減対象となる環境物品リストの更新・拡大、環境サービスのスコープ特定といった議論がある。さらに、鉄鋼の過剰生産能力問題の解決に向けた議論の場である「鉄鋼の過剰生産能力に関するグローバル・フォーラム閣僚会議」については、2021年はイタリアが議長国、日本・米国が共同議長国であり、我が国が議論をリードする立場にある。こうしたOECD・APEC等での規範作りを積極的に進める。
以上のルールや規範作りの取組に加え、日本の強みを活かすバリューチェーンの官民での取組が必要である。アジア・途上国における社会課題解決ニーズを含め、経済社会は大きく変容しており、新興国等でのインフラ整備や現地企業との共創を進めて行くにあたっては、こうした変化を前提とする必要がある。特に、ASEANでは、自動車分野を中心とする域内のサプライチェーンを前提に培ってきたプロジェクトをベースとした「垂直連携」に基づくビジネス展開モデルとは異なる、アライアンス先行のビジネス展開といった協業の在り方を模索する必要がある。
政策面では、日ASEANの経済強靭化に向け、サプライチェーン強靭化支援等を含む「日ASEAN経済強靭化アクションプラン」の発出や、「イノベーティブ&サステナブル成長対話(DISG)」の創設、AETIを通じたASEANの段階的かつ現実的なエネルギートランジション支援の推進等に取り組んでいる。また、2021年4月27日の日豪印経済大臣会合で合意した「サプライチェーン強靭化イニシアティブ(Supply Chain Resilience Initiative:SCRI)」や日豪印ASEANの産官学による「サプライチェーン強靭化フォーラム」等253を活用し、インド太平洋地域大でのサプライチェーンの強靭化及び産業競争力強化の好循環を生み出し、同地域の持続的な経済発展の実現を目指していく。さらに、世界有数の人口を抱え、有為なIT人材を排出するインドと、日本企業が既に高度な製造業サプライチェーンを構築しているASEANを実質的に連結して、広域な地域サプライチェーンを構築していく(「チャイナプラス1」から「インドインクルーシブ」へ)。
253 2021年3月11、12日実施。https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2021/caec93df4c13e5e4.html![]()