第2節 世界的な供給制約の高まり
2020年から続く新型コロナウイルスの感染拡大は、サプライチェーンの上流から下流にわたって大きな影響を及ぼし、今もなおその影響は継続している。ロックダウン等の感染拡大防止のための行動制限、渡航・移動制限といった対策に起因する経済の停滞や人手不足による影響のみならず、大規模な財政措置による急激な需要喚起もあいまって、物流の遅延や価格の高騰を招いている。物流の混乱は、資源・エネルギー価格の高騰を招き、高騰した資源・エネルギー価格は物流価格の高騰を招くという負の連鎖が発生している。
また、世界各地での豪雨、ハリケーン、寒波、干ばつ等の異常気象によって資源・食料等の不足や不作が起き、食料価格の上昇も見られる。特に、半導体や自動車部品は、一部の国・地域に偏って製造されていたものもあり、異常気象等の被害がボトルネックとなり、半導体や自動車といった製品全体のサプライチェーンが停滞する事態を招き、大幅な供給遅延や減産を余儀なくされた。
さらに、2022年2月には、ロシアによるウクライナ侵略が開始され、サプライチェーンの混乱を悪化させた上、石油や天然ガス等のエネルギー、小麦やとうもろこし等の穀物、希ガスや鉱物資源等の原材料など、ロシアやウクライナが豊富に生産・輸出してきた財について、世界的な需給バランスの乱れや供給への不安から価格高騰を招いている。
このように、様々な要因が招く供給制約の影響を受けて、資源やエネルギー等を海外に多く依存する国々では交易条件の悪化もあいまって、広範にわたる財・サービスの需給ひっ迫やインフレの高騰を引き起こしている。
こうしたサプライチェーン全体で発生している供給制約とその関係性は以下の図のようにまとめられる(第Ⅰ-1-2-1図)。
第Ⅰ-1-2-1図 サプライチェーンにおける供給制約の関係図
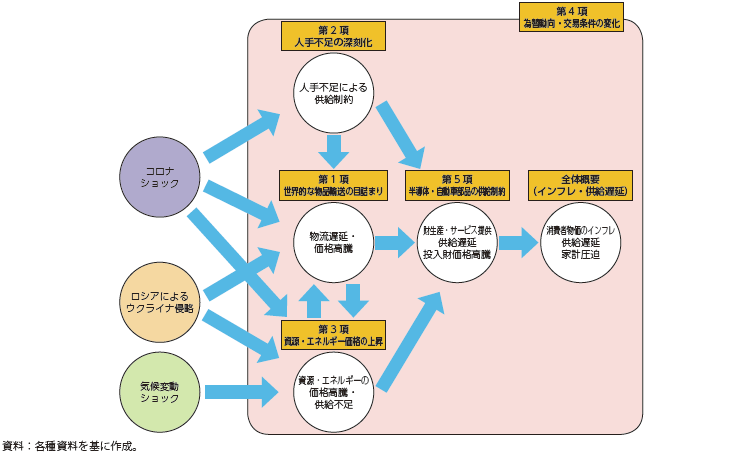
本節では上図に示すような、新型コロナウイルスの感染拡大や気候変動が招く異常気象、ロシアによるウクライナ侵略といった世界規模の不確実性の高まりに伴うサプライチェーンや労働市場、資源・エネルギー供給において多層的に発生している種々の供給制約の実態を見ていく。
1.世界的な物品輸送の目詰まり
物品輸送は新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴う行動制限や渡航・移動制限といった対策や、急激な財政措置による需要喚起によって需給がひっ迫し国際物流コストの高騰を招いた。JETROが2021年11月4日から12月7日にかけて実施した調査3によると、日本企業がサプライチェーンの見直しを行う理由として、「需要の増加」、「国内外における移動制限、操業規制」、「原料、部品不足」などを挙げる中で、「国際輸送の混乱・輸送コストの高騰」は、見直しを行う最大の理由となっており、日本企業にとっても大きな課題となっていることが分かる。
3 JETRO(2022)「日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」、「供給制約、輸送の混乱と企業の対応状況」。
(1)海上運輸
我が国において、国外との物品輸送については、重量ベースで99.6%の貨物輸送を海運が担っている4。金額ベースでも約7割を海運、約3割を空運が担っており、海運が主要な輸送手段となっている。なお、海運において、金額ベースでその約3分の2は海上コンテナによる輸送となっている5。
こうした中、海上運賃を見ると、国際的な海上運賃の指標であるバルチック海運指数は、2020年末より上昇し、2021年10月6日には2021年初の4倍超となった後、11月には急落している(第Ⅰ-1-2-2図)。その後、2022年は2021年の同等の水準で推移している。
第Ⅰ-1-2-2図 バルチック海運指数
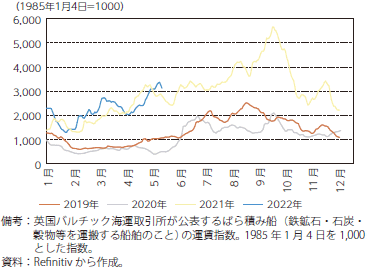
一方、コンテナ船の国際的な運賃指数であるフレイトス・バルチック国際コンテナ指数(FBX)のグローバル指数を見ると、2019年には年間を通じて2,000ドル弱の水準で比較的安定していたが、2021年には2019年の5倍超の水準に達し、2022年においても、引き続き10,000ドル弱の高い水準が続いている(第Ⅰ-1-2-3図)。今般の物流混乱では、コンテナの需給ひっ迫を背景とした運賃の高騰や物流遅延の影響が継続していることがうかがえる。
第Ⅰ-1-2-3図 FBXコンテナ指数(グローバル)
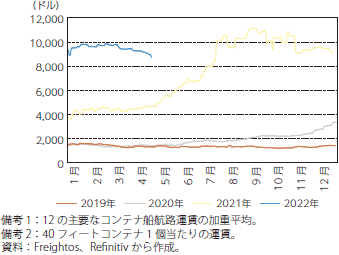
コンテナ船の主要航路の運賃を見ると、中国発の航路では、いずれも2021年後半から高止まりの状況にある。(第Ⅰ-1-2-4図)。
第Ⅰ-1-2-4図 欧州・米国・中国間のコンテナ船主要航路の航路別海運運賃
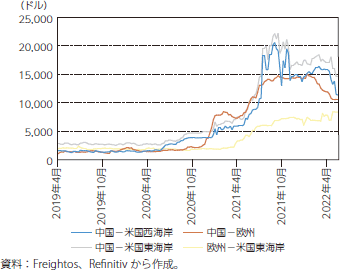
また、日本発の航路別運賃を見ると、欧米向け、アジア向けのいずれも価格が大きく上昇しており、特に欧米向けの運賃は、2019年と比べて5倍超の水準で推移している(第Ⅰ-1-2-5図)。
第Ⅰ-1-2-5図 日本発のコンテナ船の航路別海運運賃
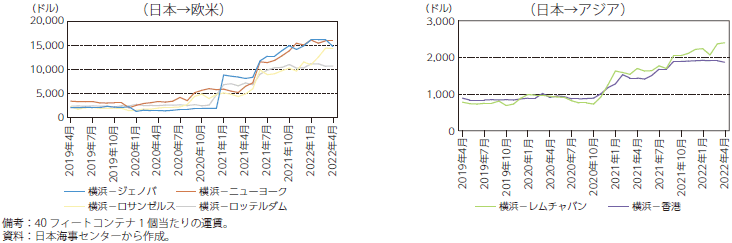
中国に次いで海運取扱量の多い米国の主要港湾である米国ロサンゼルス港やロングビーチ港では、港湾、倉庫、陸運の労働者不足を受けて、港湾における待機日数が長期化した(第Ⅰ-1-2-6図)。
第Ⅰ-1-2-6図 米国西海岸の主要港湾におけるコンテナ船の平均待ち時間
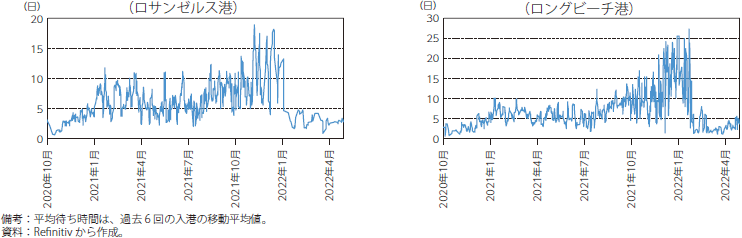
港湾におけるコンテナ船の待ち時間は、特に2021年後半に長期化し、ロサンゼルス港では3週間弱、ロングビーチ港では一時4週間弱にまで悪化した。その後、2022年初にはいずれも1週間以内の水準へと改善しているが、これはコンテナ船の待機プロセスの変更や港湾における滞留空コンテナに対する追加課金の導入6によるものと考えられる。ロサンゼルス港及びロングビーチ港では、入港に伴う待機プロセスが2021年11月15日に変更され7、これまではコンテナ船が港の20海里以内に入ると待機プロセスとされたが、新たなプロセスでは、ロサンゼルス港やロングビーチ港の直前港を出発した時点で待機プロセスとされている。また、72時間以内の着岸予約がないコンテナ船は、港沖合の一定のエリア外で待機しなければならない。こうした待機プロセスの変更に伴い、新たな方式でのコンテナ船滞船数が公表されており、2022年1月9日には109隻が実質的に滞船し、その後も100 隻前後で推移していることから、港湾における待機時間は減少したものの、実態として港湾や港湾近郊を含めた海上輸送における混雑が解消されたとは言えない。
また、2022年3月からの上海における新型コロナウイルスの再拡大を受けた都市封鎖の影響により、中国国内における陸運が停滞し、米国向けの海運や空運への影響が顕在化している8。
米国では、需要喚起策の効果もあり、財輸入の需要が急増したが、入港するコンテナ船が増加する一方で、空コンテナが港湾に滞留する状況が続き、世界的なコンテナ不足に拍車をかけている。財輸入が急増している状況において、コンテナを満杯状態にして輸出をすることは難しくなっている。
なお、コンテナ船の輸出入におけるコンテナの使用率についてはコンテナの可用性インデックスであるCAx(Container Availability Index)から確認できる9。米国最大のロサンゼルス港と中国最大の上海港についてCAxを見ると、ロサンゼルス港では2021年の第13週に0.9を超え高止まりとなっており、相対的に輸入時に満杯のコンテナが多いことが確認できる(第Ⅰ-1-2-7図)。一方、上海港については0.5から0.6前後で推移していることから、コンテナの輸出入に関してバランスが取れた状態と言える(同図)。CAxの代表的な解釈例については第Ⅰ-1-2-8表にまとめている。
第Ⅰ-1-2-7図 コンテナの可用性インデックス(CAx)
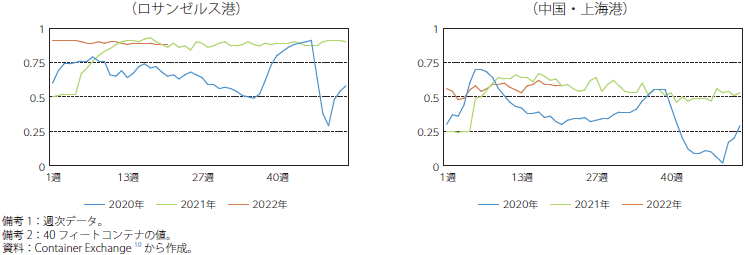
第Ⅰ-1-2-8表 CAxの解釈例
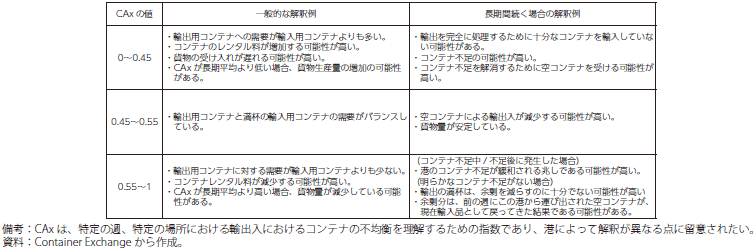
これまでに見てきた港湾におけるコンテナ輸送の不均衡について、往復の輸送のいずれかで輸送容量が全て利用されないことは「バックホール問題」として知られている11。
バックホール問題が生じる例として、関税や輸入割当といった貿易政策の議論が挙げられる。関税や輸入割当といった輸入制限の政策によって自国の輸入量が減少する際、バックホール問題が生じないようにするためには、輸送企業は輸出量を減少させる必要がある。そのため、輸入量が減少することによって自国向けに生産を行う企業には利益をもたらし得る。一方で、輸出量の減少は、外国向けに生産を行う企業には損失をもたらす可能性も併せ持っている。Anderson J. E. and E. van Wincoop (2004)は、海上輸送のコストに関して、従価換算した割合は、関税や非関税障壁のコストは7.7%である一方、輸送費のコストは10.7%と輸送費がもたらす影響の方が大きいことを示している12。これらを踏まえると、平時においても輸送費が与える影響が関税や非関税障壁と比べても大きいことから、サプライチェーンの目詰まりによって輸送費の高騰する昨今の状況下における影響は殊更大きいと言える。
これを輸送費の高騰について照らすと、コンテナ輸送の不均衡がロサンゼルス港等の混雑や倉庫能力のひっ迫を招き、さらに、陸運の供給能力などのひっ迫もあいまって、海上輸送運賃の高騰を招いている。これに対して、バックホール問題が生じないような配送とするためには、港湾の処理能力や輸出量に合わせて好調な財輸入を大きく制限する必要がある。これにより、需給がひっ迫し、インフレ圧力となる可能性が生じてしまう。
このように、輸送運賃は、貿易政策上の課題よりも影響が大きく、これを平時の状態へと戻していくことは、バックホール問題の観点からも重要である。このためには、早期の港湾混雑の解消や倉庫能力、陸運の供給能力といったボトルネックの解消が必要となる。
4 日本船主協会(2021)「Shipping Now 2021-2022」、(https://www.jsanet.or.jp/data/shipping.html![]() )。
)。
5 国土交通省(2021)「輸送機関別の貿易額の推移」、(https://www.mlit.go.jp/common/001358400.pdf![]() )。
)。
6 JETRO(2022)「米ロサンゼルス港、滞留空コンテナに追加課金の方針発表」、(https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/01/64184e850189c59a.html![]() )。
)。
7 国土交通省(2022)「第4 回海外港湾の状況レポート(2022年1月27日前後時点)」。
8 JETRO(2022)「上海の都市封鎖の長期化で米港湾が再び混乱する恐れ、全米小売業協会見通し」、(https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/04/73680d31784f6488.html![]() )。
)。
9 CAxは輸出入における満杯のコンテナのバランスを示した指数であり0.5を基準として0から1で示される。0.5の場合には輸出と輸入で同量の満杯状態のコンテナをやり取りしておりバランスが取れた状態を示している。一方で、0.5を超える場合には輸出よりも輸入時の方が満杯のコンテナが多いことを示している。逆に、0.5を下回る場合には、輸入よりも輸出時の方が満杯のコンテナが多いことを示している。
10 Container Exchange, (https://www.container-xchange.com/features/cax/![]() ).
).
11 Ishikawa J. and Tarui N., (2016), “Backfiring with Backhaul Problems: Trade and industrial policies with endogenous transport costs”RIETI Discussion Paper Series 16-E-006.
12 Anderson, J. E. and E. van Wincoop (2004), “Trade costs”, Journal of Economic Literature, 42, p.691-751.
(2) 航空運輸
これまで見てきた海上輸送における需給ひっ迫を受けて、海上輸送を空運によって代替する動きもあり、国際貨物量は増加し、空運運賃も高騰している。JETROが2022年2月に発表した調査によると、国際物流の混乱による主な影響として、前述したコンテナ船に関する回答のほか、「航空貨物の価格高騰」や「航空貨物のスペース確保が困難」といった空運に関する懸念も見られる。また、海上輸送の混乱や運賃高騰に対する対応として、「特段の対応をとっていない」、「わからない」との回答に次いで、「輸送モードの変更(海上から航空へ、航空から小口海上へ)」が挙げられている(第Ⅰ-1-2-9図)。
第Ⅰ-1-2-9図 国際物流の混乱による影響とその対応
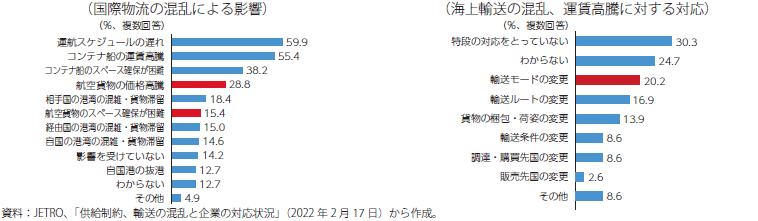
こうした航空運輸の需要の高まりを踏まえて、航空運賃の状況を見ると、上海発の航空運賃は、中国が世界に先駆けて新型コロナウイルス感染拡大が一時収束し、経済が急速に回復したことを受けて、需給がひっ迫したことにより、2020年5月をピークに高騰していることが確認できる。その後、一時運賃が下落するも、米国では、新型コロナウイルスの感染が拡大する中においても財需要が好調であったことや、海運の需給ひっ迫を受けた輸送モードの変更需要の増加、年末商戦を背景として、2021年末の北米着の運賃は再度高騰し、2020年5月におけるピークを越えている。また、フランクフルト発北米着の航空運賃については2020年に急騰して以来高止まりとなっており、年末商戦に向けて価格上昇がさらに加速した。2022年にはロシアによるウクライナ侵略の影響を受けて、減便による需給ひっ迫、ロシア上空を回避する迂回ルートへの変更に伴う燃料費の増加や、燃料価格の高騰もあいまって、航空運賃は高騰している(第Ⅰ-1-2-10図)。
第Ⅰ-1-2-10図 航空運賃の推移
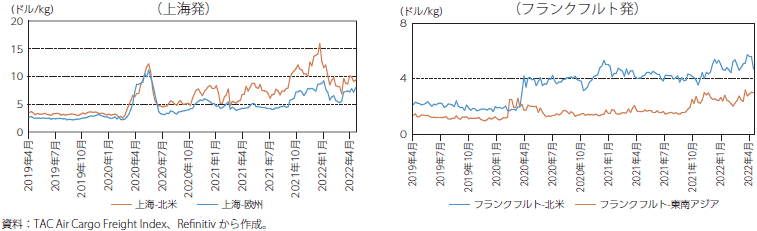
(3)陸上運輸
国外との貿易にあたっては海運、空運に加えて、空港や港湾からの国内輸送や国をまたいだ長距離トラックによる輸送も必要となる。米国の陸上運輸を見ると、港湾の荷役労働者や倉庫業、内陸輸送を担うトラック運転手が不足しており、また、中古トラックの価格高騰もあいまって、港湾に到着したコンテナ船の荷物が国内物流の目詰まりで運送されない事態も発生している。ATA(米国トラック協会)によると、2021年時点で約8万人の運転手が不足しており、2030年には16万人が不足すると試算している13。特に、コロナ禍では貨物需要の増加や早期退職、免許学校の閉鎖等に加えて、カナダにおいても、新型コロナウイルスのワクチン接種の義務化に対するトラック運転手によるデモ活動が広がり、物流の供給ひっ迫に拍車をかけている。米国の輸送部門における離職者数を見ると、一時解雇者数がコロナショック時に急増した後、減少傾向にある一方で、自主退職者は2019年平均の約70万人と比べて2022年3月には102万人と約1.5倍の水準となっている(第Ⅰ-1-2-11図)14。
第Ⅰ-1-2-11図 米国における輸送部門の離職者数
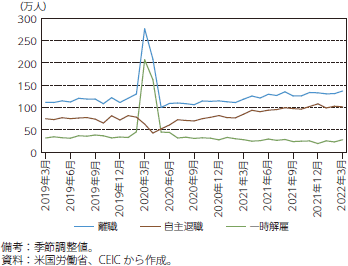
トラック運転手不足を解消するために、賃金上昇の動きが見られるものの、依然として一般民間企業の賃金水準に比べて低いほか、心身への負担の大きさ、職業への偏見、大学進学を目指す若者の増加などから成り手不足が続き、需給ひっ迫の状況が続いている(第Ⅰ-1-2-12図)。
第Ⅰ-1-2-12図 米国のトラック運転手の平均時給
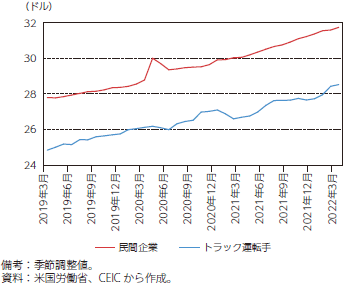
もっとも、こうした賃上げ分は輸送費を押し上げる一因となっており、エネルギー価格の大幅な上昇とあいまって、トラック輸送に関する生産者物価指数は2022年4月時点で前年同月比+29.8%、長距離トラックについては+34.7%と物流コストを押し上げている(第Ⅰ-1-2-13図)。
第Ⅰ-1-2-13図 米国におけるトラック輸送の生産者物価指数(前年同月比)
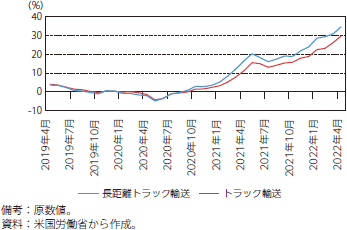
こうした状況において、各国政府は物流混乱の解消に向けた対策を講じている。例えば、我が国では、国土交通省が、世界的な国際海上コンテナ輸送力及び空コンテナの不足を受けて、日本発着の国際海上コンテナ輸送の需給のひっ迫状況の改善に向け、2021年2月5日付で、荷主、船社及び物流事業者等の関係団体に対し、コンテナの効率的な利用や輸送スペースの確保等に係る協力要請文書を発出した。2021年4月からは、横浜港においてコンテナターミナルを複数の船社で利用するなど、運用を柔軟化している。さらに、2021年4月、2022年1月には、経済産業省、国土交通省、農林水産省が合同で「コンテナ不足問題に関する連携の促進に向けた関係者による情報共有会合」を実施している。同会合では、主にコンテナ船の物流混乱に焦点を当て、コンテナ不足の主な要因について、「①新型コロナウイルスの感染拡大以前から、新造コンテナの生産量が低下」、「②アジア発北米向け貨物の急増」、「③港湾作業員不足によるコンテナ処理能力低下15」、「④欧米で空コンテナが滞留し、アジアにコンテナが回送されない」と分析している16。
米国では、物流混乱について、特に海運に関して、港の運営時間を24時間週7日制とする、港湾におけるコンテナの積み上げ制限を緩和する、港湾におけるコンテナ船の停泊やコンテナの保管に対してペナルティを設ける、港湾において海軍が利用するふ頭やコンテナ保管場所の提供を受ける17などの措置により、混雑の解消に向けた取組が行われている。
今のところ物流全体としては一部改善の兆しが見られるものの、市場で期待されていた想定より解消は遅れている18。今後の見通しについて、JETROの2月調査によると、混雑・輸送費高騰等の解消時期の見通しについて、2022年中までに解消見通しが立っているのは全体の27.7%であり、「2023年以降」の回答が27.3%、「見通しが立たない」が15.7%と、物流混乱の影響が長期化することが見込まれる(第Ⅰ-1-2-14図)。
第Ⅰ-1-2-14図 混雑・輸送費高騰等の解消時期の見通し
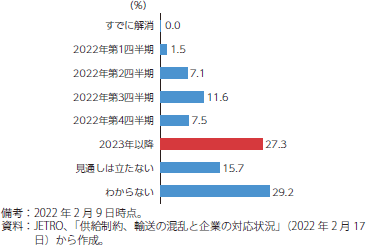
13 ATA (2021) “Driver Shortage Update 2021”, (https://www.trucking.org/sites/default/files/2021-10/ATA%20Driver%20Shortage%20Report%202021%20Executive%20Summary.FINAL_.pdf![]() ).
).
14 自主退職者の増加は輸送部門に限らず、米国の労働市場で拡大している。米国の労働市場の動向については第I部第2章第2節「米国」を参照されたい。
15 中国国内のコンテナ生産は2020年下半期から回復し、2021年は通常の2倍に達している。また、中国では海外から空コンテナの回収も進めており、2021年10月までに490万TEUを回収している。
16 経済産業省、国土交通省、農林水産省(2021、2022)「コンテナ不足問題に関する情報共有会合」、(https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000586.html![]() )。
)。
17 USNI News (2021) “Navy Opens Up Military Deep-water Pier to Merchant Ships to Ease California Cargo Crisis”.
18 デンマークの世界的な海運大手AP モラー・マースクは貨物船の遅延解消にはこれまで同社が見込んでいたよりも時間がかかるとの見通しを示した。コンテナ船の荷下ろしや積み込みの待機日数は2022年初において最大となっているのは米国の西海岸地域と指摘している。北欧においては2022年当初において、やや緩和傾向にあり、ベルギーのアントワープ港においては2022年初に10日間であった待機日数が約2日間へと短縮が見込まれている。ロイター(2022)「海運マースク、輸送遅延解消は期待していたより長期化と予告」、(https://jp.reuters.com/article/maersk-supply-chain-idJPKBN2JM02E![]() )。
)。
2.人手不足の深刻化
新型コロナウイルスの感染拡大は、労働市場にも多大な影響を与えており、多くの雇用が失われた。陸運における人手不足がサプライチェーンの供給制約につながっていたように、雇用の喪失や人手不足、それに伴う賃金上昇が、財生産やサービス提供の価格上昇や供給遅延に与える影響は大きい。ここでは、こうした労働市場における雇用や失業の状況、そうした状況が及ぼす影響について見ていく。
コロナ禍における雇用喪失が労働市場やサプライチェーンに与えた影響について、国際比較を行うために、日本、米国、EUそれぞれの指数化した従業者数を見ると、EUや米国における従業者数はコロナ禍前の水準に戻っているものの、日本では元の水準に戻っていないことが確認できる(第Ⅰ-1-2-15図)。
第Ⅰ-1-2-15図 従業者数の推移
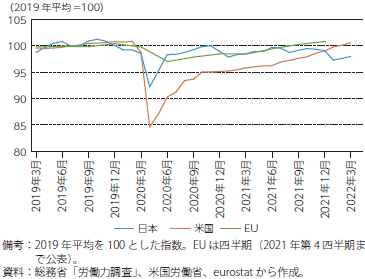
次に、コロナショック後の欠員率について労働需要の回復状況と捉え得ることから、従業者数及び求人数を元に算出される欠員率(第Ⅰ-1-2-16図左図)を確認する。米国の欠員率は、コロナ禍前から日本、EUと比べて高く推移していたものの、コロナ禍での経済回復とともに上昇している。さらに、指数化した欠員率を見ると、米国では、2020年7月にコロナ禍前の水準に達した後、2021年1月以降大きく上昇している。また、EUについても2021年第2四半期以降にコロナ禍前の水準に達している一方で、日本では依然としてコロナ禍前の水準に戻っていないことが確認できる(第Ⅰ-1-2-16図右図)。
第Ⅰ-1-2-16図 欠員率の推移
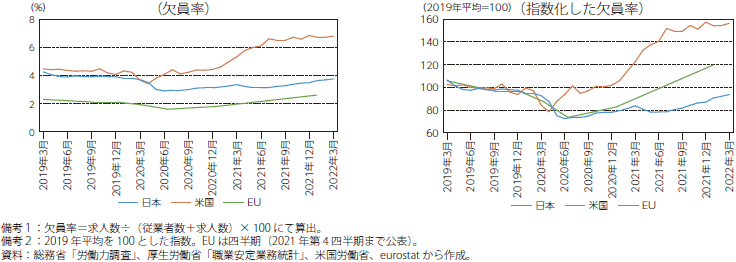
米国やEUでは、経済回復によって労働需要が高まったものの、労働供給が追い付かず、人手不足が生じている一方で、日本ではコロナ禍からの経済回復に遅れがあり、労働需要不足の状況が続いている。
そこで、米国及びEUについて、労働市場における人手不足が経済活動に与える影響について確認していく。米国において製造業や非製造業における仕入れ担当役員へのアンケート結果を指数化した景況指数であるISM製造業・非製造業景況指数を見ると、製造業、非製造業ともにコロナショック後に強い回復をみせている。一方で、雇用指数については景況判断の分岐点となる50前後で推移しており、総合指数に対して低い水準で推移している。このことから、人手不足が景況全体の供給制約要因の一つとなっていることが確認できる(第Ⅰ-1-2-17図)。
第Ⅰ-1-2-17図 米国におけるISM製造業・非製造業景況指数
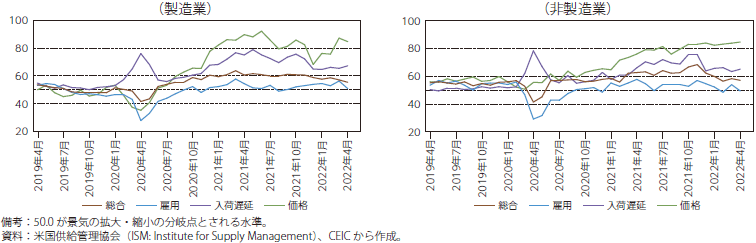
欧州について、製造業の生産制約要因を見ると、新型コロナウイルスの感染拡大当初は、需要の減少が主要な制約要因であったが、2022年3月現在、約半数の企業が設備や原材料を制約要因として挙げており、約4社に1社は労働力不足が生産の制約要因となっていることが確認できる(第Ⅰ-1-2-18図)。
第Ⅰ-1-2-18図 欧州における製造業の生産制約要因
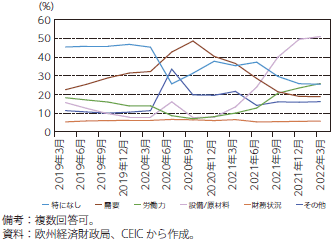
3.資源・エネルギー価格の上昇
資源・エネルギーは、新型コロナウイルスの感染拡大や気候変動に伴う異常気象といった世界規模のショックや他の供給制約要因の動向によって価格変動や需給の状況が左右される財と言える。さらに、ロシアによるウクライナ侵略によって、世界経済の先行きの不透明さが増している中、ロシアやウクライナは一部の資源やエネルギーの主要な供給国であることから、世界全体での供給量に直接与える影響は大きい。多様な要因によって影響を受ける資源・エネルギーの価格や需給は、家計や企業活動における光熱費やエネルギーの安定供給に直接影響するほか、財生産やサービス提供における投入コストの増加として間接的な影響を及ぼし、広範な財・サービスへのコストプッシュインフレの要因となり得る。このような状況下の資源・エネルギーの価格について、全体の価格の傾向を確認した上で、コモディティ別の価格動向や、各コモディティを取り巻く環境変化やその価格動向を見ていく。
まず、資源・エネルギー全体の価格動向について、世銀が公表している資源・エネルギー価格指数を元にエネルギー、食料、肥料、金属・鉱物、貴金属の価格動向を確認していく(第Ⅰ-1-2-19図)。
第Ⅰ-1-2-19図 世界の資源・エネルギー価格指数の推移
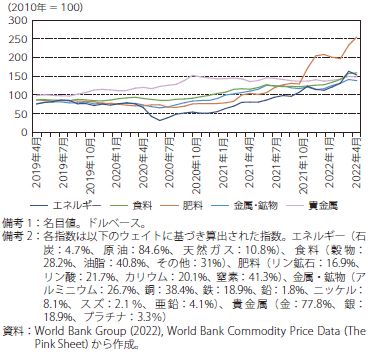
エネルギーの価格指数は、原油、天然ガス、石炭の価格に基づき算出されるが、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて、需要減への見込みから価格が急落するも、その後、経済活動の再開に合わせて価格が元に戻っている。その後、サプライチェーンの目詰まりや原油、天然ガス、石炭それぞれの需給ひっ迫を受けて価格が高騰している。さらに、ロシアによるウクライナ侵略を受けて、原油や天然ガスの需給ひっ迫の状況が悪化し、価格を押し上げている。
食料については、新型コロナウイルスの感染拡大による大きな価格変動はなかったものの、干ばつや洪水、寒波といった異常気象の影響を受けた生産量や質の低下が価格の押し上げ要因となったほか、エネルギーや肥料といった投入財の価格高騰もあいまって、食料価格の高騰を招いた。
肥料については、肥料の原料となる鉱石や、製造プロセスに必要な材料の供給減に伴う価格高騰や、エネルギー価格の高騰により投入コストが上昇したことを受けて、全体の価格を押し上げている。
金属・鉱物については、投入財価格の高騰を映じてコロナ禍で価格が上昇し、2021年中ごろより高止まりの状態が続いている。特に、原材料を製錬するにあたっては電力を多く消費するが、エネルギー価格が高騰した影響は大きい。さらに、世界的な脱炭素に向けた動向を受けて、脱炭素に資する財の生産に必要となる、銅やニッケルといった金属への需要が高まり、需給ひっ迫を招き、価格高騰につながっている。貴金属は、コロナ禍における米ドルの実質実効為替レートの下落や、世界経済の先行き不安などを映じて、安全資産としての価値が高まっている。
これらの資源・エネルギー価格の今後の見通しについて、世銀では毎年4月と10月に翌年の価格指数の予測値を公表しており、併せて、前回予測値からの変化についても示している(第Ⅰ-1-2-20図)。
第Ⅰ-1-2-20図 資源・エネルギーの名目価格指数の推移・予測
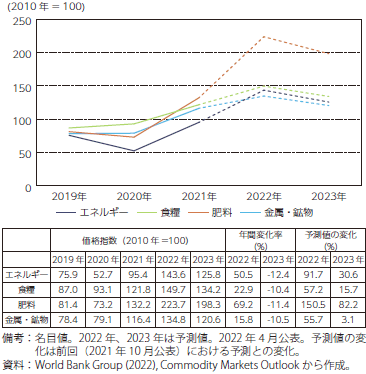
第Ⅰ-1-2-20図によると、2021年におけるエネルギー、食料、肥料、金属・鉱物の価格指数は、2020年に比べて大幅に上昇している。今後は、2022年をピークとして2023年には価格が下落するも、2021年を越える高い水準が見込まれる。また、エネルギーや肥料については、今後の価格予測を2021年10月から大きく上方修正している。さらに、肥料については、2022年のみならず、2023年における価格予測も大幅に上方修正していることが確認できる。こうした資源・エネルギー価格全体の状況を踏まえた上で、個別のコモディティの価格動向について見ていく。
(1)エネルギー
エネルギーは本項冒頭で示したように多様な要因によって価格や需給が変化するが、エネルギーの価格高騰や需給ひっ迫が、家庭における光熱費やエネルギーの安定供給に与える影響は大きい。また、エネルギーは後述する食料、肥料、鉱物・金属を含めた財生産の投入財としても必要不可欠であり、価格高騰や需給ひっ迫は財・サービスの供給制約に直結していく。ここでは、主要なエネルギー価格の動向として、原油、天然ガス、石炭の価格動向について確認していく。
① 原油価格
原油価格は、需給状況や米ドルの為替レート、投機資金の動向といった様々な要因によって変動するが、2000年以降、2019年以降における原油価格の推移は以下の通りとなっている(第Ⅰ-1-2-21図)。
第Ⅰ-1-2-21図 原油価格の動向
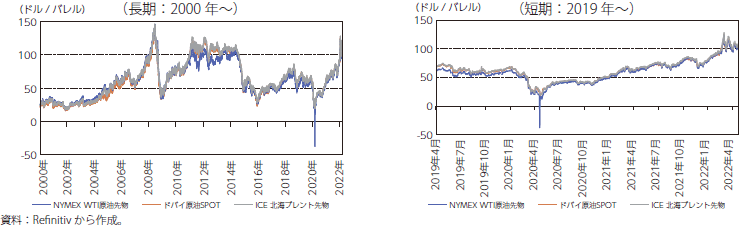
2020年1月から4月にかけて、新型コロナウイルスの感染が拡大したことで、世界各地でのロックダウン等により石油需要が減少し、価格は急落した。その後、2020年11月から現在にかけて価格の高騰が続いている。背景としては、世界的に経済回復する中で、石油需要の回復への期待が高まっていることやハリケーン・アイダの来襲により沖合油田での生産停止による需給引き締まりへの懸念の高まりがあること、欧州やアジアにおける天然ガス、石炭価格の高騰によって、代替燃料として石油需要が高まっていること、石油需給が引き締まり価格が高騰する中においても、OPECプラス産油国が減産措置の縮小に対して慎重であることなどが挙げられる19。さらに、2022年2月には、ロシアによるウクライナ侵略が開始され、石油の一日当たり生産量が世界第3位20であるロシアによる原油輸出が滞ることへの懸念から原油価格が高騰し、WTI原油先物価格が2022年3月6日には一時1バレルあたり130ドルを超えて2008年7年以来の高値となっている。その後、価格は下落するも、100ドルを超える高値で推移している。
② 天然ガス
天然ガスは、2021年春以降、価格高騰が続いている。米国は自国内で生産が可能であり、自給率も高いことから安定かつ低価格で推移している。我が国では、液化天然ガスを長期契約で調達していることから、価格の推移は安定的であるものの、輸送コストを含めて、米国や欧州、アジアにおける価格と比べても高い価格となっている。2021年に入り、欧州やアジアにおけるスポット市場が急騰しており、国際価格の高まりを受けて、日本の平均輸入価格についても上昇傾向にある(第Ⅰ-1-2-22図)。
第Ⅰ-1-2-22図 天然ガス価格の動向
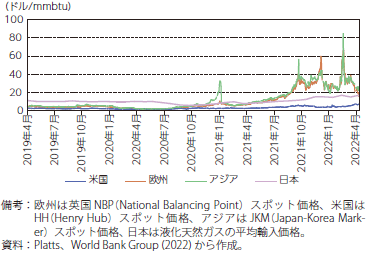
欧州における天然ガスの価格高騰の背景としては、2021年11月、ドイツのエネルギー規制当局が、ロシアから欧州へのパイプラインであるノルドストリーム2の管理会社に関して、独立性に修正が必要であるとして認可手続きを一時停止したことにより、価格が2割程度上昇した。また、2021年1月には、欧州炭素排出権EU-ETS(EU Emissions Trading System:EU域内排出量取引制度)価格が上昇したため、石炭から天然ガスへと発電用燃料の転換が促進されて、天然ガスの需要増加が後押しされた。その他、2021年当初、北東アジアへの寒波来襲によって世界のスポットLNGの大半が、日本、中国、韓国によって調達されたことで、欧州はLNGを輸入できず、貯蔵在庫を使用することとなったが、欧州北西部では気温が例年より5度程度低い時期に需要が増加したことにより、天然ガスの貯蔵ができない状況が続いたことも価格の押し上げ要因となっている。2022年年明けには暖房需要が一服し一時ピークアウトするも、足下ではウクライナ情勢を受けて、ロシアからの供給に対する不安が広がり乱高下が続いている。
欧州では、調達している天然ガスの8割程度がスポット価格で構成されていることから、日々のエネルギー価格の変動が電力・ガス価格にも大きく影響を及ぼすため、各国で混乱が生じている。その上、脱炭素に向けて再生可能エネルギーへのシフトが急速に進められており、火力発電への投資の縮小や廃止の動きも同時に起きている。ポルトガルやスペインは、再生可能エネルギーの中でも太陽光や風力による発電の割合が高い上、石炭や石油による割合が小さく、バックアップ電源として天然ガスを利用する必要があったが、天候不順により日照時間や風量が十分に得られない時期が続いたため、エネルギー需給のひっ迫に見舞われた。
③ 石炭
石炭は、2021年初から価格の上昇傾向が続いている(第Ⅰ-1-2-23図)。
第Ⅰ-1-2-23図 石炭価格の動向
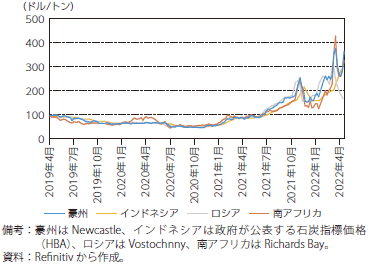
背景としては、世界的な脱炭素の流れの中での石炭開発への投資等の低迷、炭鉱における事故や自然災害による炭鉱の操業停止、豪州と中国の対立の高まりに伴い、中国が豪州産石炭の輸入を削減し、中国が他の産炭国からの調達を活発化させたことによる輸送面の混乱などが挙げられる。
また、世界最大の石炭輸出国であるインドネシアでは、国内供給義務(DMO)に違反して海外への供給を進めた企業の増加によって、インドネシア国内における石炭火力発電所で使用する石炭の在庫が不足した。これを受けて、インドネシアは2022年1月に石炭輸出を一時停止した。DMOを遵守する企業は輸出を再開しているものの、需給ひっ迫によって石炭価格が押し上げられている。
さらに、2022年2月に開始されたロシアによるウクライナ侵略を受けて、欧州ではロシアからのパイプラインを通じた天然ガスへの依存から脱却する動きがある。石炭は、ロシアによるウクライナ侵略前から価格が高騰していた天然ガスの代替資源として需要が高まっており、ロシア産の石炭価格が押し上げられてきた21。しかし、現下の情勢を踏まえて、ロシア産の石炭への依存から脱却する動きから他国の石炭価格の上昇を招いている。
19 JOGMEC(2022)「原油市場他:OPEC及び一部非OPEC(OPECプラス)産油国が従来方針に基づき2022年3月についても前月比で日量40万バレル減産措置を縮小する旨決定(速報)」、(https://oilgas-info.jogmec.go.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/261/2202_d_opec.pdf![]() )。
)。
20 20 BP (2021) “Statistical Review of World Energy 2021”, (https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-ofworld-energy.html![]() ).
).
21 JOGMEC(2021)「ロシア産一般炭価格が高騰」、(https://coal.jogmec.go.jp/info/docs/210916_19.html![]() )。
)。
(2)食料
食料の価格上昇は、家計に直接影響を与えるほか、家畜の飼料や加工品の原材料といった投入財のコストを上昇させるため、エネルギー価格や肥料のコスト等とあいまって、食料品やサービスの価格上昇を招く恐れがある。食料価格全体のすう勢について、FAOが実質食料価格指数として示しており、2014年から2016年の平均を基準とした指数は、以下のような動向を示している(第Ⅰ-1-2-24図)。
第Ⅰ-1-2-24図 実質食料価格指数
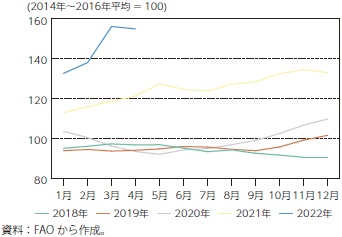
実質食料価格指数は、2020年5月以降、上昇傾向が続いていることが確認できる。背景は、複合的な要因が考えられるが、北米による高温乾燥や南米における干ばつ、といった天候不順によるものが主因で、生産資材の高騰の影響や、世界的な人口増加に伴う食料需要の増加なども考えられる。また、ロシアによるウクライナ侵略の影響によって、世界的にも多くの穀物等を生産し、世界へ輸出しているロシアやウクライナを含むサプライチェーンが一部途絶することで、国際価格の高騰を招いている。
次に品目別の価格指数について見ていく(第Ⅰ-1-2-25図)。
第Ⅰ-1-2-25図 食料の品目別価格指数
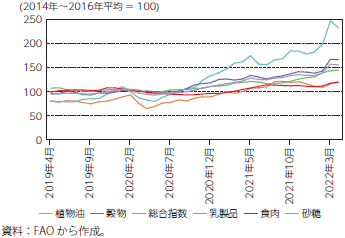
品目別の価格動向を見ると、植物油や穀物が全体を押し上げていることが確認できる。植物油に含まれるパーム油は、世界最大の生産・輸出国であるインドネシアにおける供給量が減少したことを背景として、植物油の価格指数を押し上げた。穀物については、ロシアは小麦が輸出額世界1位、大麦は世界2位、トウモロコシはウクライナの輸出額が世界4位と、両国が世界の穀物輸出額に占める割合が大きく、ロシアによるウクライナ侵略の影響により価格高騰が生じている。日本は、小麦、大麦については、2021年には米国、オーストラリア、カナダの3か国から99%以上を輸入しており、トウモロコシについては、米国とブラジルの2か国から80%以上を輸入している22。このため、我が国には、価格高騰の直接的な影響は少ないものの、世界全体での供給量が減少し、国際的な穀物市場のバランスが変化することによって、価格高騰の影響が波及してくる可能性がある。
また、食料は、生産資材の価格上昇の影響も受けている。農作物の生育に必要な肥料、家畜の飼育に必要な飼料、家畜小屋や園芸施設の温度管理に必要なエネルギー、ハウスやトンネル等に用いられる被覆材は、いずれも必要不可欠な生産資材であり、いずれもコロナ禍で価格高騰に見舞われている(第Ⅰ-1-2-26図)。
第Ⅰ-1-2-26図 生産資材の価格推移(日本国内)
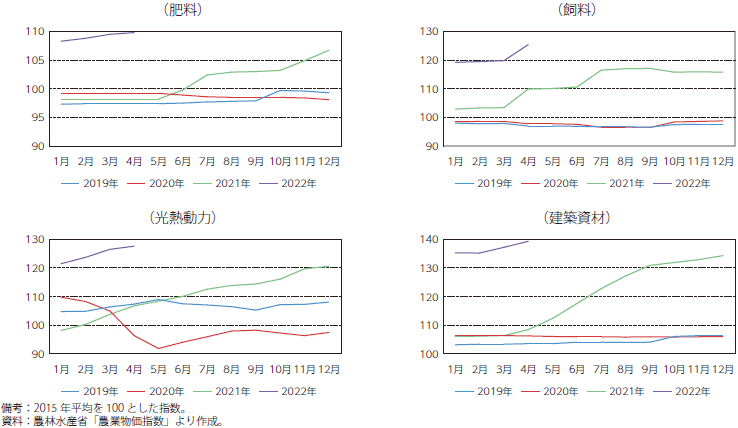
J. D. Winne and G. Peersman (2019)は、異常気象が農業生産量や価格に与える影響は、一部の地域や品目に影響を与えるのみならず、世界的に影響を及ぼすと指摘している23。先進国では、低所得国に比べて家計支出に占める食料の割合が低いにも関わらず影響が大きい。また、農産物の純輸出国である国では影響が小さく、気候変動が先進国に与える影響は、これまで考えられていたよりも大きい可能性を示唆している。地球環境と食料との関係については、2022年1月15日に発生したトンガにおける大規模な海底火山の噴火の影響も懸念されている。1991年にフィリピン・ピナツボ火山の噴火が発生した際には噴出物に含まれる多量の二酸化硫黄が成層圏に達し、地上に届く太陽光が弱まった影響により、地球全体の平均気温が約0.5度下がり、日本では噴火の2年後にあたる1993年には平均気温が2~3度下がる記録的な冷夏となり、米の生産量が減少した「平成の米騒動」につながったとされている。一方で、今回のトンガの噴火における二酸化硫黄は、1991年のフィリピンの噴火の2.3%であり、気温低下は限定的と見られている24。
22 農林水産省(2022)「農林水産物輸出入情報」。
23 J. D. Winne and G. Peersman (2019), “The Impact of Food Prices on Conflict Revisited”, Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 39, Issue 2, 2021, (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07350015.2019.1684301?scroll=top&needAccess=true&![]() ).
).
24 JAMSTEC(2022)「コラム【トンガ海底火山噴火】-トンガ海底火山噴火は気候に影響を及ぼしうるか?-」、(https://www.jamstec.go.jp/j/jamstec_news/tonga/column01/![]() )。
)。
(3)肥料
肥料は、野菜や穀物の生育に欠かせない存在であり、肥料の需給ひっ迫や価格高騰は、食料生産における不作や質の低下、価格高騰につながる恐れがある。肥料は主にN(窒素)、P(リン酸)、K(カリ)の三要素から構成され25、世銀が公表しているコモディティ価格を見ると、上記三要素を含む肥料であるリン酸二アンモニウム、尿素、塩化カリウムについて、リン酸二アンモニウムは、2020年後半から価格が高騰しており、尿素は、2021年から価格が急騰している。塩化カリウムは、比較的価格が安定していたものの、2022年に入り価格が急騰している(第Ⅰ-1-2-27図)。
第Ⅰ-1-2-27図 肥料価格の推移
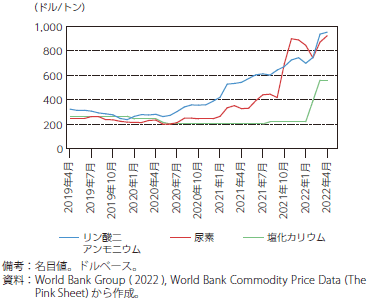
価格高騰の背景としては、物流価格や投入財価格の高騰が挙げられる。リン酸二アンモニウムや尿素の製造に必要なアンモニアは、石炭や天然ガス等の化石燃料を原料に用いて製造されており26、石炭や天然ガスの価格が高騰したことを受けて価格が高騰している。アンモニアの用途の約8割は肥料用途であり、残りの約2割が樹脂や合成繊維の製造、ディーゼルエンジンにおける窒素酸化物の還元プロセスに必要な尿素水の製造といった工業用途27である。また、近年では、次世代エネルギーである水素のキャリア(輸送媒体)としての用途や、燃焼しても二酸化炭素を排出しないカーボンフリーの燃料としての用途に注目されており、今後さらに需要が高まることが予測されている。アンモニアの生産量は、年間約2億トン(2019年)であり、主要生産国は上位から中国、ロシア、米国、インドとなっており、中国は全体の約1/4、上位4か国中の過半数を占めている28。中国では、アンモニアの多くを石炭から製造しており、中国国内における環境問題等への対応に伴う石炭生産量の抑制によって石炭の生産量が減少したことにより、アンモニア生産が減少した。このアンモニアの生産減によって、尿素や尿素水の需給ひっ迫につながり、中国は2021年10月より輸出を制限した。ディーゼルエンジンが排出する窒素酸化物(NOx)について、尿素を加水分解して得られるアンモニアによって、窒素酸化物を水と窒素に還元する性質を利用した尿素SCRシステムを動かすためには、消耗品として「尿素水(Adblue)」が必要となっている29。こうした中、韓国は尿素の消費量のうち約6割を中国からの輸入に依存しており、価格高騰や尿素水不足に見舞われた30。日本では、尿素の約3割を中国からの輸入に依存していたことから、尿素水の不足が生じたが、国内事業者への最大限の増産を要請や、ベトナム等、中国以外からの輸入を増加させることによって対応している31。
25 日本肥料アンモニア協会「肥料の分類」、(http://www.jaf.gr.jp/hiryou.html![]() )。
)。
26 資源エネルギー庁(2021)『エネルギー白書2021』。
27 資源エネルギー庁(2021)「アンモニアが“燃料”になる?!(前編)~身近だけど実は知らないアンモニアの利用先」、(https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/ammonia_01.html![]() )。
)。
28 USGS (2022), “Mineral Commodity Summaries 2022 -Nitrogen”, (https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022-nitrogen.pdf![]() ).
).
29 一部車種においてはCVD(クリーンディーゼル車)として尿素水を用いずに環境基準を越えている。
30 JETRO(2021)「韓国で尿素水が品薄に、物流が混乱する恐れ」、(https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/11/50300a8ceb9a2545.html![]() )。
)。
31 経済産業省(2021)「「AdBlue」の需給緩和に向けた対応を行っています」、(https://www.meti.go.jp/press/2021/12/20211224003/20211224003.html![]() )。
)。
(4)金属・鉱物
金属・鉱物は、様々な財を生産するに当たっての原材料としての役割が大きく、その価格や需給ひっ迫は、消費財の価格高騰や供給遅延につながるほか、生産財や資本財の製造についても影響が及ぶことから、より広範にサプライチェーン上の影響をもたらす。特に、脱炭素化に向けたエネルギーシフトに関連する財生産に必要な原材料である金属は、中長期的に需要が高まり、価格高騰や需給ひっ迫の影響が長期化するおそれがある。
金属・鉱物の分類として、埋蔵量・産出量が多く、精錬が比較的簡単な鉄、アルミ、銅などの金属はベースメタルと呼ばれている。一方、産出量が少なかったり、抽出が難しかったりするチタンやコバルト、ニッケルといった希少な金属はレアメタルと呼ばれている。さらに、レアメタルの一部である17元素はレアアースと呼ばれ、先端技術を用いた製品には不可欠な素材となっている。この他、金、銀、白金などは貴金属に分類され、資産としての役割やアクセサリー等の原材料となるほか、一部の鉱物は自動車等の触媒などとして用いられている。
金属の種類別の価格動向を見ると、すずは、電子回路の製造に用いられるはんだや、メッキの原料として用いられており、大半のすず鉱石を産出しているマレーシアやインドネシアにおいてロックダウンによる生産停止や、マレーシアにおける溶解炉の操業停止によって供給量が減少し、価格が高騰している(第Ⅰ-1-2-28図)。アルミニウムについては、非鉄金属の中でも生産に必要な電力コストが高く、欧州では製錬所の半数以上が減産または一時閉鎖となり、供給減や投入財価格の高騰を受けて、価格が押し上げられている。また、蓄電池の原料となる鉛や、鋼材のメッキ、ダイカストの原料となる亜鉛についても、アルミニウムと同様に電力コストの高さを背景に価格が高騰している。銅は、エネルギートランジションとも関連するが、世界的な脱炭素の潮流の中で、再生可能エネルギーの送電網や自動車の電動化に必要なモータの銅線への需要の高まりから価格が押し上げられている。銅の価格上昇を背景として、原料を銅からアルミニウムへとシフトする動きもみられているが、アルミニウムの価格についても高騰していることから、生産コストが押し上げられている。鉄については、鉄鉱石の価格は一時落ち着いていたが、中国において政府が建設やインフラ部門における景気刺激策を表明したことによって、今後は鋼材需要が増えることが見込まれている。
第Ⅰ-1-2-28図 ベースメタルの価格推移
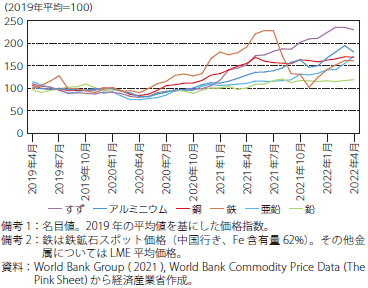
中長期的な金属価格の動向に関して、IMFは、世界が脱炭素に向けて大きく舵を切ることによって、電気自動車の蓄電池など、エネルギーの貯蔵に必要な、銅、ニッケル、コバルト、リチウムといった金属の需要がかつてなく高まり、価格が高騰する可能性について指摘している32。各金属の価格予測について以下のとおり示している(第Ⅰ-1-2-29図)。
第Ⅰ-1-2-29図 エネルギートランジションに必要な主要金属価格のシナリオ
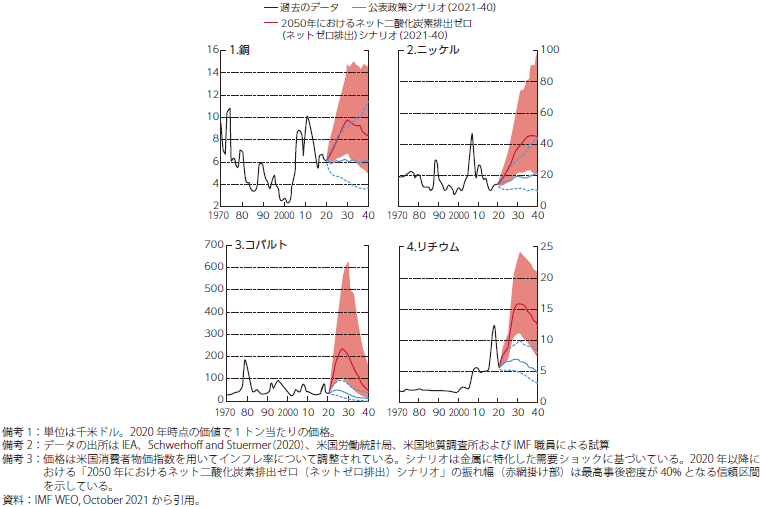
仮に排出量実質ゼロシナリオに基づく消費量を満たさなければならない場合、これらの価格は類例のないほど長期にわたって史上最高値に達する可能性がある。2020年の水準と比較して、コバルト、リチウム、ニッケルは数百%、銅は約60%値上がりし、2030年頃にピークに達することが予測されている。銅については、需要の増加がそれほど急激ではないことから、ボトルネックにはならないとされている。また、同報告では、上述した4種の金属に加え、コンゴ民主共和国がコバルトの生産量が世界全体の約7割、埋蔵量の約5割を占めていることなど、一部の鉱物の産出が一部の国・地域に集中していることから、一部の鉱物産出国・地域にとっては経済成長や財政収支の改善として恩恵を受ける可能性があると指摘している。一方で、こうした重要鉱物の生産を一部の国・地域に依存することは、サプライチェーンにおけるリスク要因となりうるため、エネルギートランジションに当たっては、こうした重要鉱物の需要、生産動向に加えて、地政学リスクを捉えた動向の把握が必要である。
32 IMF(2021)「金属価格の高騰がエネルギー転換を遅らせるおそれあり」、(https://www.imf.org/ja/News/Articles/2021/11/10/blogssoaring-metal-prices-may-delay-energy-transition![]() )。
)。
4.為替動向・交易条件の変化
これまでに物流の混乱や人手不足、資源・エネルギー価格の高騰について概観してきたが、サプライチェーン全体の各プロセスにおける動きと関連する為替動向や交易条件について見ていく。
為替動向を見ると、足下では円安ドル高の状況が続いており、我が国にとっての資源・エネルギーを含む製品の輸入価格が押し上げられている(第Ⅰ-1-2-30図)。
第Ⅰ-1-2-30図 指数化した為替レートの推移(対ドル)
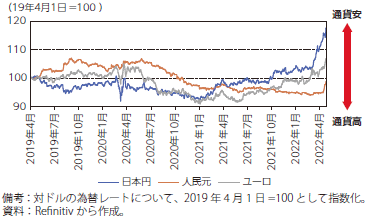
2022年4月13日には1ドル126円台となり、約20年ぶりの円安水準となっている。円安の背景としては日米における金利差や、エネルギー価格の高騰を受けて貿易赤字が定着していることなどが考えられる。
為替動向や、物流価格や資源・エネルギー価格の上昇を踏まえて、交易条件の変化について見ていく。交易条件は財の輸出価格を輸入価格で除することにより算出され、輸出価格が輸入価格に比べて高い場合には交易条件は改善し、逆に輸出価格に対して輸入価格が高い場合には交易条件は悪化する。交易条件は、主に各国通貨の為替動向や輸出構造、輸入構造によって動向が異なる。例えば、食料やエネルギーが豊富で自給率が高い国であれば、コモディティ価格に左右されにくく、交易条件の変動は他国と比べて抑えられるが、我が国を含め食料やエネルギーの多くを海外へ依存する国は、コモディティ価格の影響を受けやすく交易条件の変動は大きくなりやすい。
国別の交易条件の推移は以下のとおりとなっている(第Ⅰ-1-2-31図)。我が国では、資源やエネルギー33、食品34の海外依存度が高く、輸入価格の上昇による影響が大きいことに加えて、円安の影響もあいまって交易条件の悪化につながっている。中国では、輸入価格上昇に伴って交易条件は悪化していたが、2021年中頃から電気機械等の輸出価格上昇に伴って交易条件が改善しつつある。米国では、輸入に比べて輸出のウェイトが大きい工業製品や燃料、農作物等の輸出価格上昇を受けて、交易条件は改善している。ドイツでは、天然ガスや石炭といったエネルギーを海外に依存する割合が大きく、エネルギー・資源価格の上昇を受けて交易条件が悪化している。イタリアでは、原燃料や農産物について海外に依存する割合が大きく、ユーロ安の影響もあいまって交易条件が悪化している。フランスでは、食料自給率(カロリーベース・2018年)が125%と、100%を超えており35、また、エネルギーについても原子力発電の割合が大きいことを背景に、エネルギーの総供給量に占める国内生産比率が高い36ため、コモディティの値動きの影響を受けにくい。コロナショック時に交易条件が一時改善したものの、他国のように大きく変動はせず、2020年4月以降は悪化している。
第Ⅰ-1-2-31図 交易条件
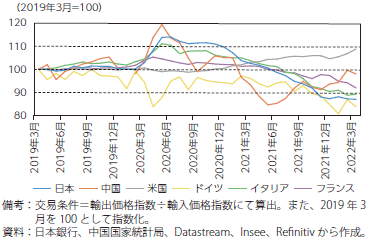
33 資源エネルギー庁(2022)「日本のエネルギー」、(https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/energy2021/![]() )。
)。
34 農林水産省(2021)「食料需給表」。
35 同上。
36 IEA (2021) “France 2021 Energy Policy Review”, (https://www.iea.org/reports/france-2021![]() ).
).
5.半導体・自動車部品の供給制約
最終製品の価格高騰や納期遅延として個人消費や企業活動に大きな影響を与えた半導体や自動車部品の供給制約について見ていく。
JETROが在ASEAN企業に対して行ったサプライチェーンに関する2月調査によると、製造業において特に不足している原材料として、半導体や電子部品、樹脂/ナイロンが挙げられている(第Ⅰ-1-2-32図)。
第Ⅰ-1-2-32図 不足している原材料に関するアンケート結果
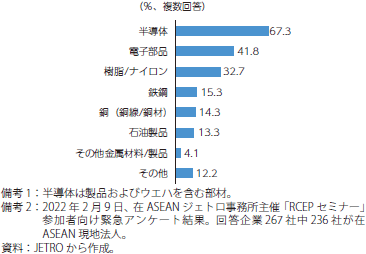
半導体が不足している背景としては、コロナ禍では巣ごもり需要やテレワーク需要の増加に加え、自動車の電動化シフトやサービス・労働のデジタル化を受けたデータセンターでの需要増等が挙げられる。また、国内外の半導体メーカーや半導体製造装置メーカーにおける工場火災や、米国の寒波による工場閉鎖の影響も需給ひっ迫の一因となっている。
世界的な半導体不足の状況についてリードタイム(発注から納品までにかかる時間)を見ると、コロナ禍前には10週から15週程度で推移していたが、2022年3月現在、2017年以来最長となる26.6週を記録し高止まりの状態となっている(第Ⅰ-1-2-33図)。
第Ⅰ-1-2-33図 半導体のリードタイム
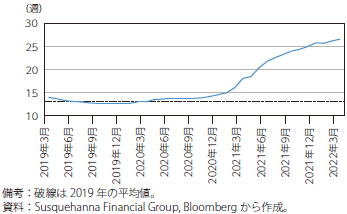
半導体や電子部品に次いで不足している樹脂・ナイロンは、エアバッグやワイヤハーネスなど、多くの自動車部品に多く用いられている。中でも、エアバッグやワイヤハーネスの主な素材であるナイロン66について、原料となるアジポニトリルはコロナ禍前から不足する状況が続いてきた。背景にはアジポニトリルの製造業者が世界で数社と限られている中、2015年に発生した中国の生産工場における爆発事故、2018年における欧州でのストライキや自然災害による工場停止、米国におけるハリケーンによる停電や工場火災が供給不足の原因となっている。こうした中、2021年2月の米国テキサス州における寒波の影響を受けて化学プラントが停電し、生産停止を余儀なくされたことにより、原料不足を招き、複数の関連企業がフォース・マジュール(不可抗力条項)を宣言するに至った37。さらに、国内のワイヤハーネス製造企業が多く製造拠点を持つASEANでは、ロックダウンによって生産が抑制、停止し、供給不足を招いてきた38。これに、原材料価格の高騰や物流の混乱の影響もあいまって、入荷遅延や価格高騰が引き起こされている。
コロナ禍ではテレワーク需要の急増や、データセンターの能力増強の必要性から半導体の需給ひっ迫を招いてきたが、今後はこうした要因の影響が一服し、半導体市場の拡大は減速する可能性がうかがえる。世界半導体市場統計(WSTS: World Semiconductor Trade Statistics)によると、2020年の世界半導体市場は約4,400億ドルと前年比+6.8%であったが、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展に伴う経済活動の再開を受けて、2021年には約5,530億ドルとなり同+25.6%と大幅な拡大が予測されている39。一方、2022年は同+8.8%と伸び率が鈍化する予測となっている(第Ⅰ-1-2-34図)。
第Ⅰ-1-2-34図 世界の半導体市場規模の推移
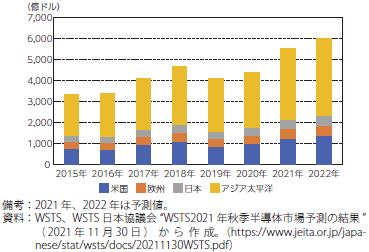
半導体関連製品の需要増加が今後も継続する見込みがあることに加えて、半導体市場では、ロシアは自動車の触媒に用いられる白金や、半導体製造に用いるネオンガス等の希ガス、パラジウムといった原材料を多く生産、輸出していたことから、ロシアによるウクライナ侵略を受けて、世界的な供給減への懸念が高まり、サプライチェーン見直しの必要性が高まっている40。
こうした状況を踏まえて、各国は半導体産業の成長や経済安全保障に向けて大規模な投資や戦略策定を進めている(第Ⅰ-1-2-35表)。
第Ⅰ-1-2-35表 各国・地域の半導体産業支援策の動向
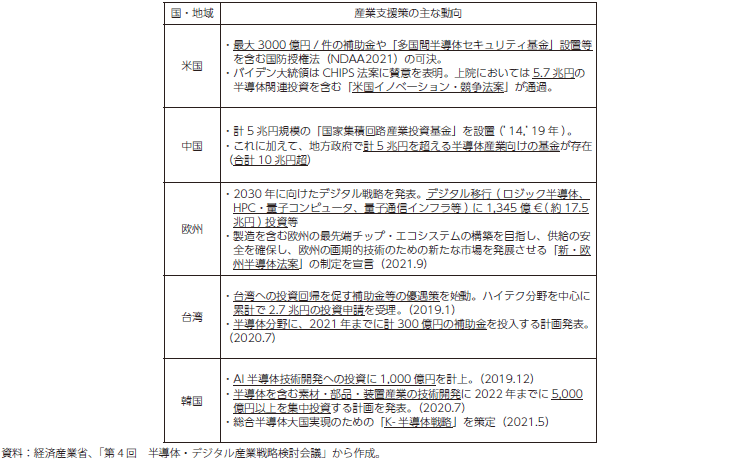
我が国では、国内における半導体に関連する原材料の供給確保を進めるほか、半導体や製造装置・素材の生産能力の増強を進めている41。半導体産業基盤の強化や人材育成・確保に向けた取組として、TSMCとソニー株式会社、株式会社デンソーが合弁で熊本県にJASM(Japan Advanced Semiconductor Manufacturing)株式会社を設立し、約86億ドルを投じて、10~20nmプロセスの半導体製造を行うことが予定されている。また、同拠点の設立によって約1,700名の先端技術者の雇用創出が見込まれている。
半導体をめぐっては、中長期的な生産体制の強化に向けた投資が進められる一方、工場の新設や増産体制の構築には時間を要することから、ファウンドリーや半導体製造装置メーカー、最終財メーカーによると、半導体不足の解消は2023年、部品によっては2024年や2025年にずれ込むという見通しとなっている。また、半導体ウエハを製造するメーカーは、2026年までに製造する半導体ウエハについて、新設の工場による増産分を含めて長期契約を済ませており、今後も需給ひっ迫が続く見通しを示している例も存在する42。今後、脱炭素に向けた世界的な潮流の中で、前述したような自動車の電動化に加えて、ロボットやAI、5G/6G、IoT、メタバース等様々なデジタル関連技術の活用需要が高まっており、こうした新興技術に必要不可欠な半導体等の製品、部品、素材については今後も需要けん引型の需給ひっ迫が続いていく可能性がうかがえる。
37 Bloomberg(2021)「東レ、自動車向けの一部ナイロン製品で顧客に供給免責求める」、(https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-03-17/QQ3UK5DWRGGD01![]() )。
)。
38 ニュースイッチ(2021)「コロナで東南アジアのワイヤハーネス工場が低操業、電線各社はコスト増を懸念」、2021 年9 月7 日、(https://newswitch.jp/p/28681![]() )。
)。
39 2021年11月30日時点。
40 経済産業省(2022)「戦略物資・エネルギーサプライチェーン対策本部(第1回)-ウクライナ情勢を踏まえた緊急対策-」、(https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220331013/20220331013.html![]() )。
)。
41 経済産業省(2022)「第5回半導体・デジタル産業戦略検討会議」、2022年4月14日、(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/semicon_digital/0005.html![]() )。
)。
42 株式会社SUMCO(2022)「2021年12月期決算説明会」、2022年2月9日、(https://ssl4.eir-parts.net/doc/3436/ir_material_for_fiscal_ym13/112680/00.pdf![]() )。
)。