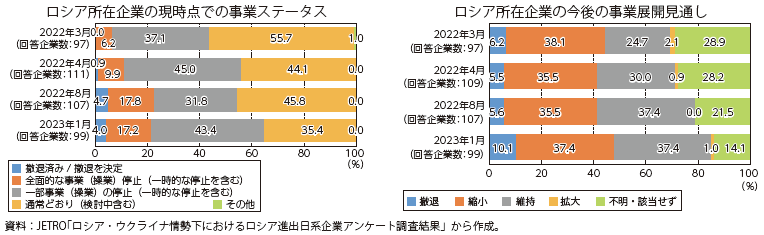第2節 ロシアによるウクライナ侵略を巡る状況とその影響
2022年2月24日にロシアがウクライナへの侵略を開始し、一年以上が経過しているものの、依然としてロシアによる決して正当化できない侵略や、国際法に反する市民や民間施設を狙った攻撃が続いている。2023年2月23日にウクライナにおける包括的、公正かつ永続的な平和を求める国連総会決議案が141票の賛成を得て採択されたことは、国際社会の大多数が、ロシアに即時、完全、かつ無条件の撤退を求める強い意思を改めて表明したものであった。しかし、G7を始めとする同志国が連携して対露制裁を科す一方で、一部の新興国・途上国ではロシアとの経済的関係を強める動きも見られる。
今般のロシアによるウクライナ侵略が開始されてからは、我が国を含めたG7を中心とする先進国・地域では、前例のない大規模な経済制裁を迅速に実施している11。一方、以下で示すとおり、一部の新興国・途上国ではエネルギー調達を従来の状態に維持し、食料調達については、物流網の関係などから、必ずしも多角化が容易ではないことなどが考えられる。これらの点を踏まえ、本節では、ウクライナ侵略後に世界経済の不確実性を高める要因となったエネルギーと食料の動向を中心に見ていく。
11 各国・地域による対ロシア制裁を概観する資料は、一例として、ピーターソン国際研究所による「Russia's war on Ukraine: A sanctions timeline」が挙げられる。
1.ロシアとウクライナの経済動向
ロシア連邦国家統計庁の速報値によれば、2022年のロシアの実質GDP成長率は-2.1%であった。同国中央銀行とIMFが2022年中に公表してきた見通しよりは成長率は落ち込まなかった(第I-1-2-1表)。
第Ⅰ-1-2-1表 2022年のロシア実質GDP成長率見通しと実績
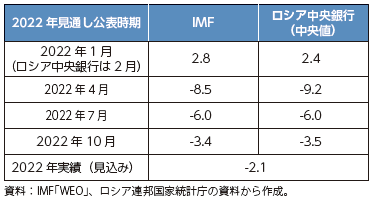
四半期ベースでロシアの実質GDPの推移を見ると(第I-1-2-2図)、2022年第4四半期の実質GDPは前期比+0.5%となったが、その水準はウクライナ侵略前後の時期となる同年第1四半期を大きく下回っている。構成項目の推移を見ると、2022年第1四半期の実質GDPの大幅な落ち込みの大部分は個人消費の落ち込みが背景であり、第2四半期以降には個人消費は持ち直している。在庫変動を含めた民間部門と公的部門の設備投資にあたる総資本形成については、2021年に新型コロナウイルス感染症拡大の影響から回復してからは、ウクライナ侵略の直後に落ち込んだ後は横ばいの推移を維持しており、その内の生産設備等の投資にあたる固定資本形成は緩やかに増加している。また、貿易面については、輸出が2022年第4四半期に増加したものの、ウクライナ侵略による経済の混乱や、ロシアに対する貿易制限措置の影響もあり、同年には輸出と輸入の両方が大幅に減少した。輸出と輸入の差を示す純輸出は、年間で見れば黒字となった。
第Ⅰ-1-2-2図 ロシアの実質GDPと構成項目の推移
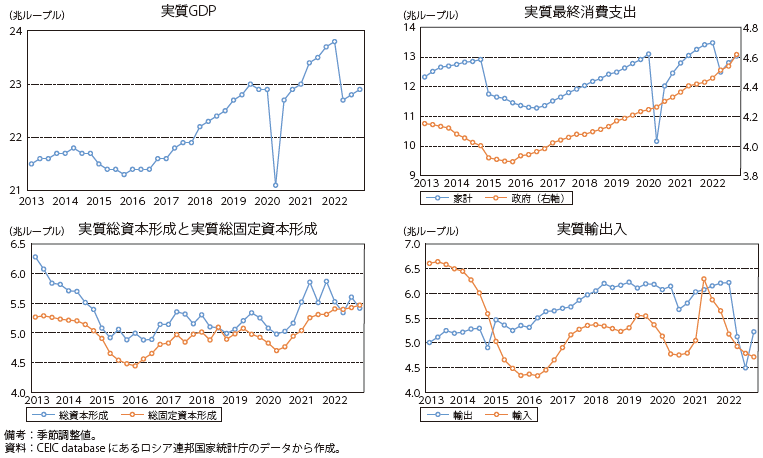
ロシアの主要な輸出品目であるエネルギーの生産動向を見ると(第I-1-2-3図:左図)、ウクライナへの侵略を開始した後の2022年4月以降では、原油とガスの掘削動向を示す原油・ガス鉱業の生産が前年比でゼロ%近傍の推移となっている。
第Ⅰ-1-2-3図 ロシアの原油・ガス鉱業生産と原油価格
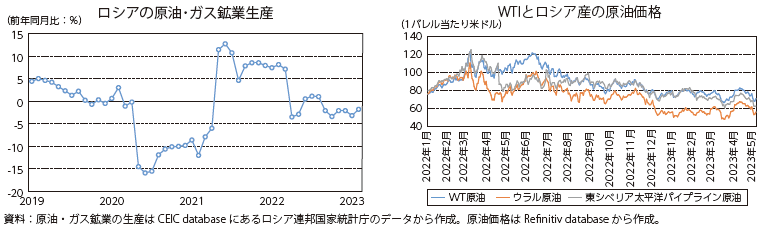
また、同国産の原油価格(主に欧州向けであるウラル原油と主にアジア向けである東シベリア太平洋パイプライン原油)を国際的に代表的なWTI原油価格と比較すると(同右図)、ウクライナへの侵略を開始した2022年2月下旬以降では、G7を始めとする国際社会がロシアに対する制裁を強めることで同国産原油への需要が減退するとの見通しのもとで同年5月にかけて価格が下落した。その後は価格が持ち直す動きもあったものの、G7及び豪州の課したロシア産原油への上限価格措置等の効果もあり、2022年の終盤にかけて、ウラル原油価格の下落が顕著になるといった特徴的な動きも見られた。
ロシア連邦政府の財政を見ると(第I-1-2-4図)、原油・ガス関連の歳入は、G7やEUを始めとする国際社会による制裁措置等の影響もあり、2022年12月以降は大幅な落ち込みを見せているが、非原油・ガス関連の歳入は安定した推移が見られる。支出面では、ウクライナ侵略の開始後も特異的な動きは見られなかったが、足下では財政赤字が拡大している。
第Ⅰ-1-2-4図 ロシア連邦政府の歳入
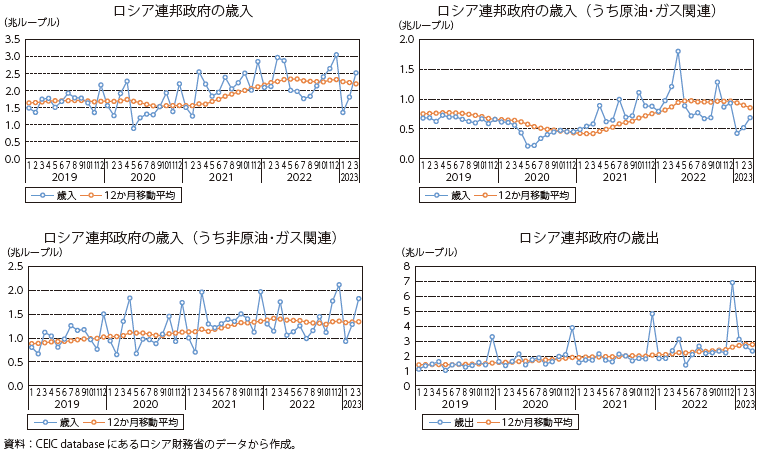
ロシアの雇用は2022年序盤にやや減少しているが(第I-1-2-5図)、その後は持ち直しており、名目賃金の前年比変化率にも労働需給の大きな変動を示すような動きは見られていない。一方、業種別の雇用を見ると(第I-1-2-6図)、国内では戦時経済への移行をうかがわせるような状況も看守される。たとえば、公共・防衛部門の雇用が2022年末にかけて増加した一方で、その他の主な業種ではおおむね安定ないし増加傾向であった。
第Ⅰ-1-2-5図 ロシアの雇用と名目賃金
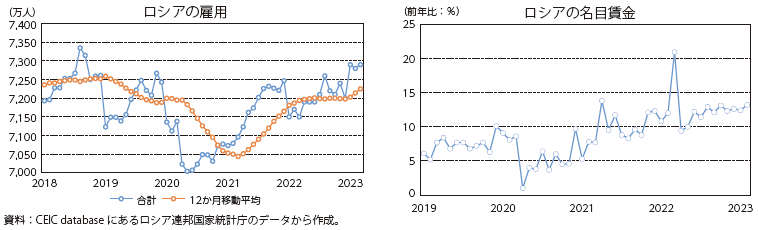
第Ⅰ-1-2-6図 ロシアの業種別の雇用
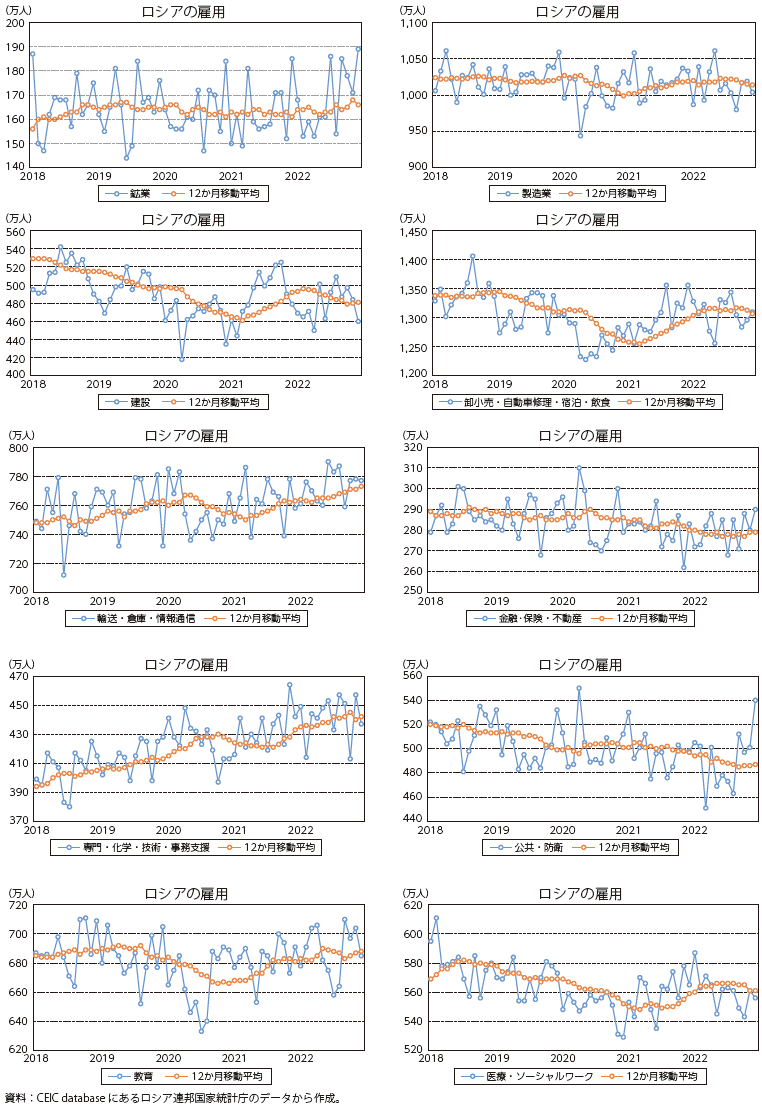
ロシアによるウクライナ侵略が開始されてからは、我が国を含めG7を始めとする国際社会は、ロシアに対する技術産品の輸出を規制している。技術産品の代表的な例として集積回路のロシアへの輸出動向を見ると(第I-1-2-7図)、ウクライナ侵略前の2021年においてロシアへの主な集積回路の輸出国であった国及び我が国については、2022年にはロシアへの輸出が大幅に減少している。一方で、2022年にもロシアへの集積回路の輸出を大幅に増加させている国も見られた。
第Ⅰ-1-2-7図 ロシアへ集積回路の輸出(2022年)
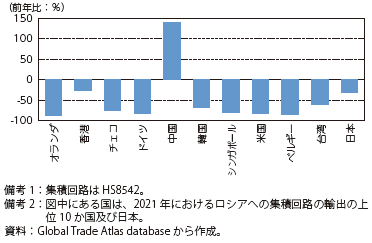
今般のロシアによる侵略によって経済が大きく混乱しているウクライナにおいては、同国経済省の公表によれば、2022年の実質GDP成長率は-30.4%と大幅に落ち込み、同国が独立した1991年以降で最低の成長率を記録した。ロシアによる侵略によってウクライナのインフラが深刻な打撃を受け、輸出を中心とした経済活動が停滞したこと等が背景にあると見られている(第I-1-2-8図)。
第Ⅰ-1-2-8図 ウクライナの実質GDP成長率
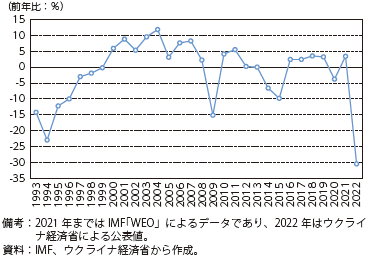
ウクライナの主要な輸出品目であるトウモロコシ、ひまわり油、小麦の動向を見ると(第I-1-2-9図)、2021年には世界第三位であったトウモロコシの輸出金額は、2022年もほぼ横ばいの推移となっていた。一方で、2021年には世界第一位であったひまわり油の輸出金額は、2022年にも同順位であり続けたものの、他の主要国の輸出金額が増加した一方で、ウクライナでは前年比-14.5%の減少となった。さらに、2021年には世界第五位であった小麦の輸出金額は、2022年には前年比-47.2%とほぼ半減しており、ロシアによるウクライナ侵略による影響は、品目によって差異があることが示されている。
第Ⅰ-1-2-9図 トウモロコシ、ひまわり油、小麦の主要な輸出国の輸出金額
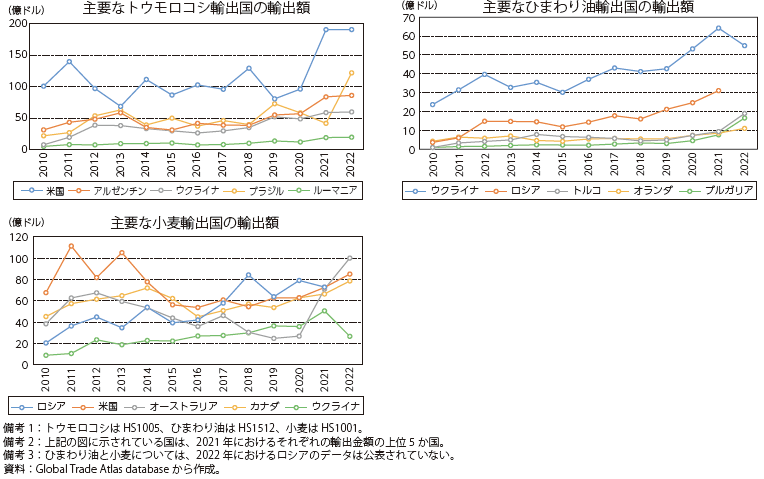
2.エネルギー調達における多角化の動き
今般のロシアによるウクライナ侵略は、特にG7を中心とした先進国・地域が、ロシアの主要な輸出品目であるエネルギー資源について、同国に対する依存を低減させる方針を強めた。
ロシアの主要なエネルギー輸出品目の一つである天然ガスの世界生産動向をウクライナ侵略前で見ると(第I-1-2-10図表)、同国は2021年時点で世界生産の17.4%を占め、米国との生産量の差は拡大しているものの、依然として世界第二位の生産国であった。ロシアの天然ガス輸出の大宗を占めるパイプラインを通した天然ガスは、主にEU諸国に輸出されており、2021年にEUではパイプライン経由の天然ガス輸入の49.0%をロシアに依存していた。EU以外のロシアのガス状天然ガスの主な輸出先は、トルコ、ベラルーシ、カザフスタン、中国となっていた。
第Ⅰ-1-2-10図表 世界の天然ガス生産動向とロシアの貿易動向

ウクライナ侵略に対する制裁措置の一環として、G7を始めとする国際社会は一致してロシアに対し厳しい制裁を科してきており、なかでも、ロシア産原油及び石油製品に係る上限価格措置(プライス・キャップ制度)及びEUによるロシア産原油・石油製品の段階的輸入禁止はエネルギー調達先の大きな変化をもたらしている。特に、ロシアに対する天然ガスの輸入依存度が高いEUでは、天然ガスについての具体的な貿易措置は講じられてはいないものの、ノルドストリーム1においてパイプラインが破損する事案が起きたこと等を踏まえると、天然ガス調達についても多角化を進展させることが重要な課題となっている。European Network of Transmission System Operation for Gasが公表しているEU向けの天然ガスの供給動向を見ると(第I-1-2-11図)、ロシア・ウクライナ産天然ガスの供給は2022年4月頃から顕著に減少し始めているものの、特に液化天然ガスの供給が増加しており、ロシア・ウクライナ産の供給減少分を部分的にではあるものの補うことができている。さらに、EUは米国からの天然ガスの調達を大幅に増加させている。
第Ⅰ-1-2-11図 EU向けの天然ガス供給動向
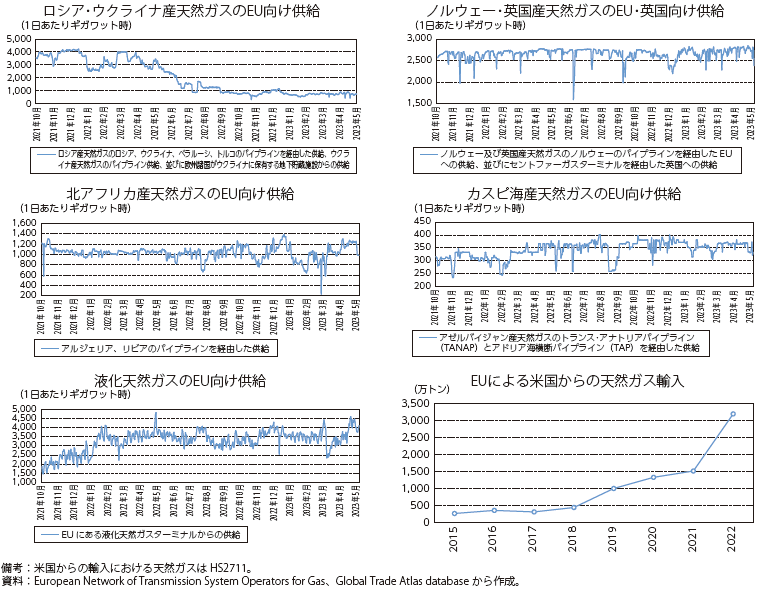
一方、EU以外でロシアからの天然ガスの輸入動向を見ると(第I-1-2-12図)、一部の例外はあるものの、2022年に世界からの天然ガスの輸入金額が増加した国では、ロシアからの輸入金額もおおむね増加しており、特にトルコによるロシアからの天然ガス輸入の増加が目立っている。天然ガスの輸入金額に占めるロシアの割合を見ると、セルビアでロシアの割合が低下しているものの、2022年におけるロシアの割合は2021年からおおむね大きな変化は見られておらず、ロシアからの輸入を急増させたトルコでも同国からの輸入割合は6.0%と大きくはない。
第Ⅰ-1-2-12図 天然ガスの輸入動向(EUを除く)
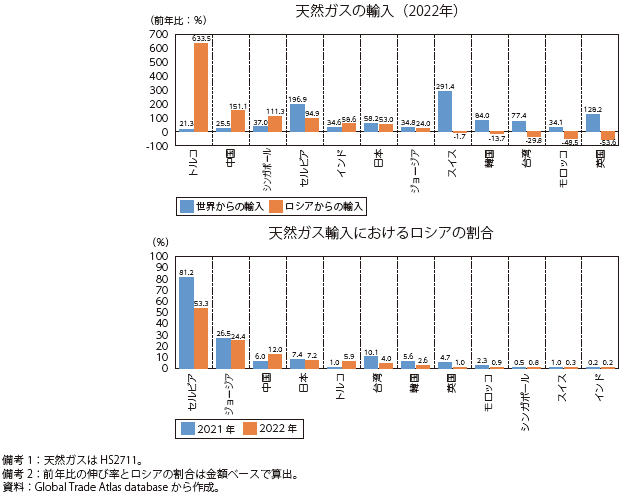
ロシアのもう一つの主要なエネルギー輸出品目である原油についてウクライナ侵略前の動向を見ると(第I-1-2-13図)、同国は2021年の原油生産において、米国とサウジアラビアに次いで、世界生産の12.2%を占める世界第三位の生産国であった。ロシアからの主な輸出先は、天然ガスと同様にEU諸国となっており、EU以外では中国、ベラルーシ、韓国、米国等となっていた。
第Ⅰ-1-2-13図 世界の原油⽣産動向とロシアの貿易動向
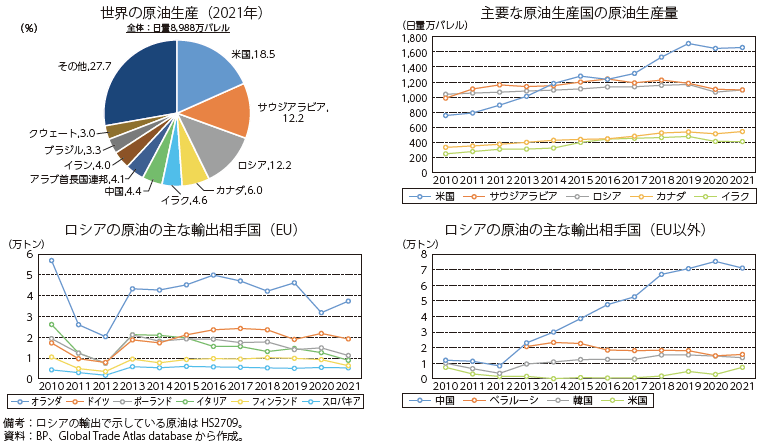
原油の輸入動向を見ると(第I-1-2-14図)、我が国や欧米諸国を中心とした先進国では、世界からの輸入が増加した中でロシアからの輸入はおおむね減少し、ロシアが輸入に占める割合でも、2021年と比較して同割合が減少している。ただし、一部の国ではロシアからの原油輸入を増加させており、エネルギー調達における多角化の動きが一様に進展している訳ではないことが示唆されている。
第Ⅰ-1-2-14図 原油の輸入動向
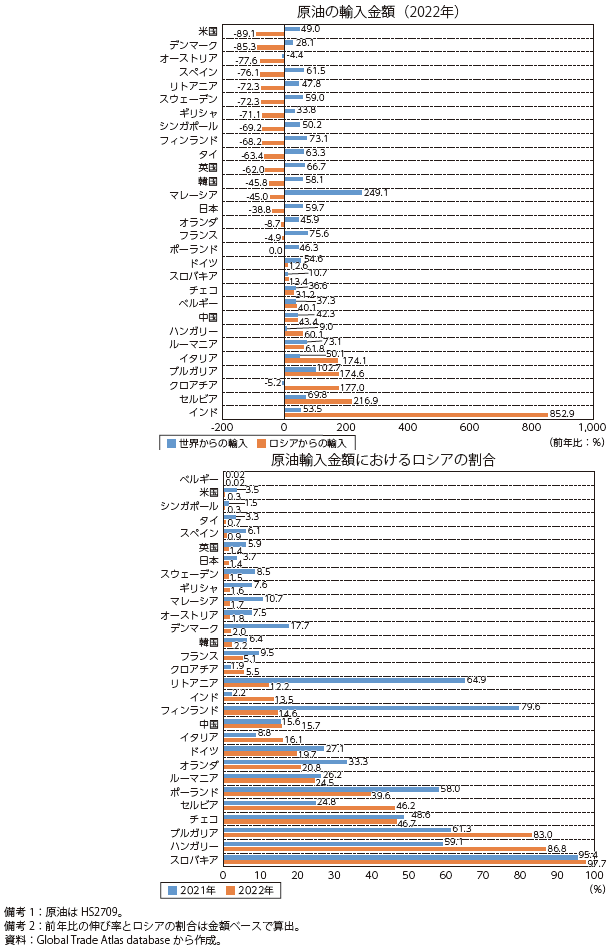
2022年終盤には、主に欧州向けであるウラル原油の価格は、WTI原油価格と比べて低水準で推移している。また、ロシアに対するエネルギー依存の低減は、天然ガスにおいて、欧州を中心とした先進国で進展が見られるが、新興・発展途上国の一部ではロシアからの調達を維持若しくは強化する動きも見られている。
3.多角化が進展していない食料調達
今般のウクライナ侵略の特徴として、同侵略による物流を始めとした経済の混乱が広がるとの懸念が強まったことにより、広範な品目において食料確保に対する意識が高まり、価格の高騰や原産国の輸出規制の動きが広まったことが挙げられる。それによって、同侵略の影響を直接には受けないと見られる品目でも、原産国内での供給を確保するために輸出規制が実施され、食料安全保障に関連して、自由貿易を制限する動きが強まった(第I-1-2-15表)。
第Ⅰ-1-2-15表 2022年2月24日以降に実施された食料・エネルギー関連の輸出規制
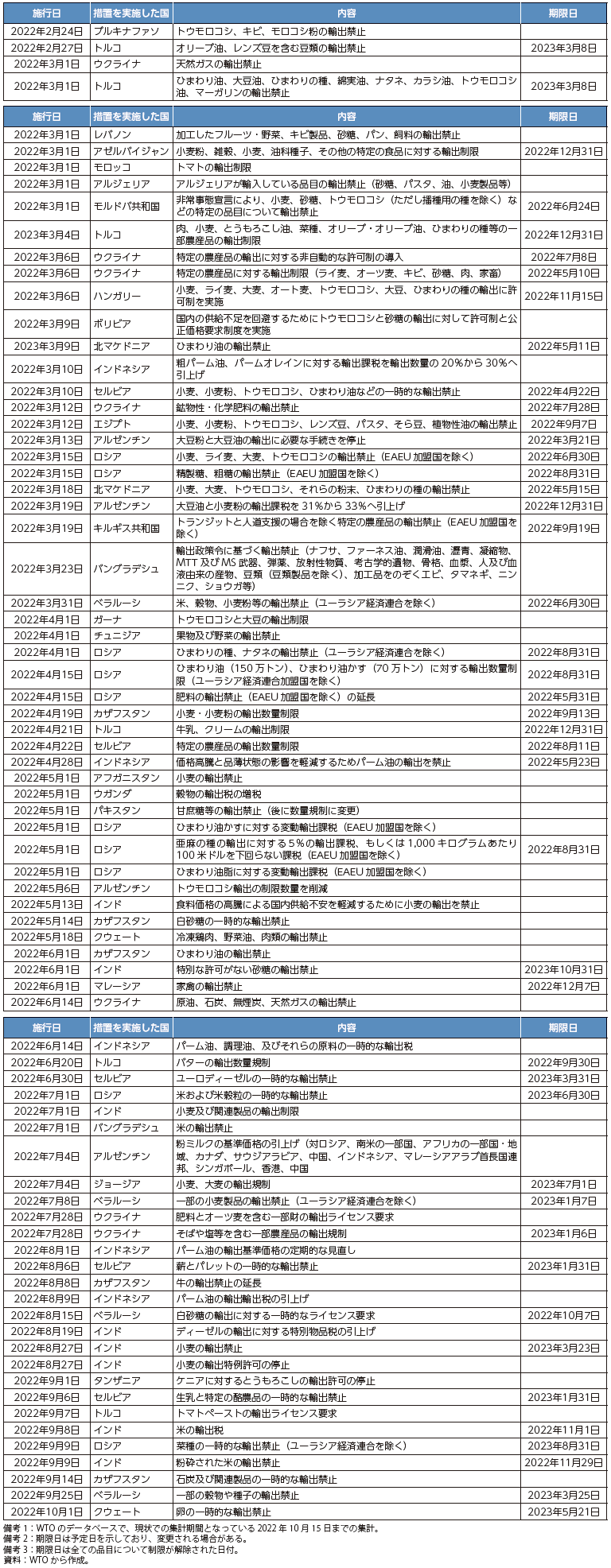
ロシアとウクライナは、経済規模は大きくはないものの、穀物を中心とした特定の食料において、世界で主要な輸出国である。特に、両国で共通の品目では、ロシアによるウクライナ侵略が開始される前の2021年には、小麦の輸出金額でロシアは世界第一位、ウクライナは同第五位となっていた(第I-1-2-16図)。
第Ⅰ-1-2-16図 主要な小麦輸出国の小麦輸出金額の推移
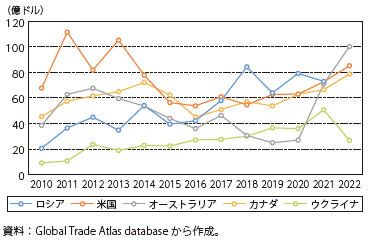
各国の小麦輸入金額の動向を見ると、2022年において世界からの小麦輸入が増加した国はおおむねロシアからの輸入も増加しており、小麦輸入に占めるロシアの割合にも特異的な変化は見られていない(第I-1-2-17図)。一方、ウクライナからの小麦の輸入動向については(第I-1-2-18図)、2022年にウクライナからの輸入も急増した国と、ウクライナからの輸入が大きく減少した国が混在しており、ロシアによる侵略によってもたらされた混乱の影響が偏在している。
第Ⅰ-1-2-17図 ロシアからの小麦輸入の動向
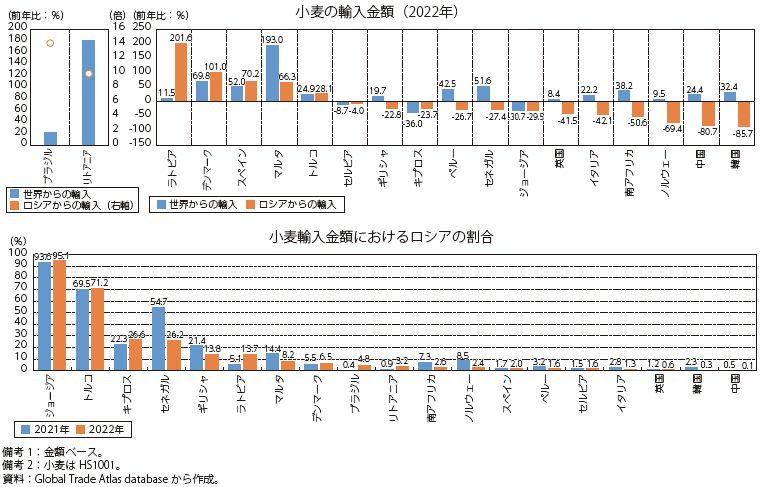
第Ⅰ-1-2-18図 ウクライナからの小麦輸入の動向
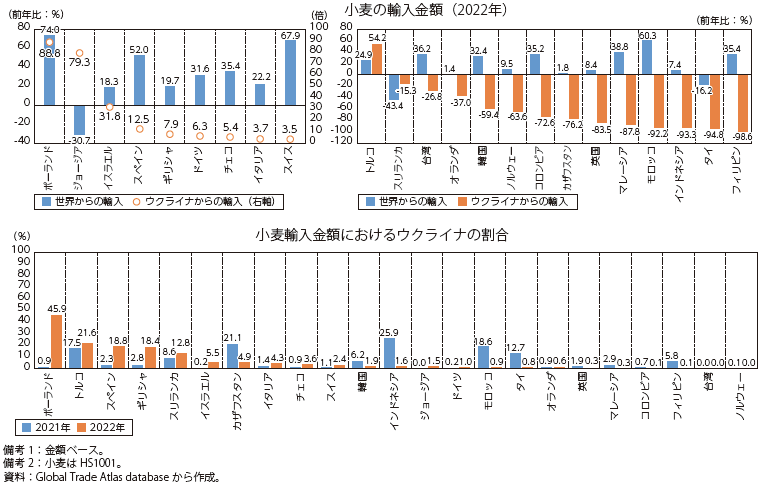
また、ロシアは2021年の肥料輸出において世界第一位となっており、食料生産への影響という観点からも重要な位置を占めている(第I-1-2-19図)。
第Ⅰ-1-2-19図 主要な肥料輸出国の輸出金額の推移
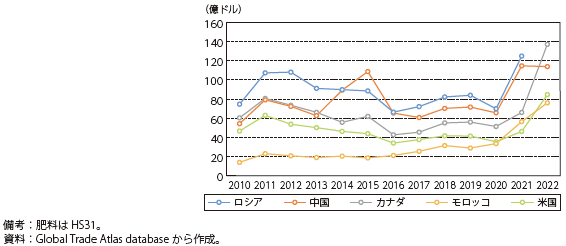
ロシアからの肥料の輸入金額の動向を見ると(第I-1-2-20図)、2022年に世界からの肥料輸入を増加させた中でロシアからの輸入を増加させた国と、世界からの肥料輸入を増加させた中でロシアからの輸入を減少させた国が混在している。一部のエネルギー品目において調達の多角化が進展していない状況と同様のことが肥料輸入にも見られている。
第Ⅰ-1-2-20図 ロシアからの肥料輸入の動向
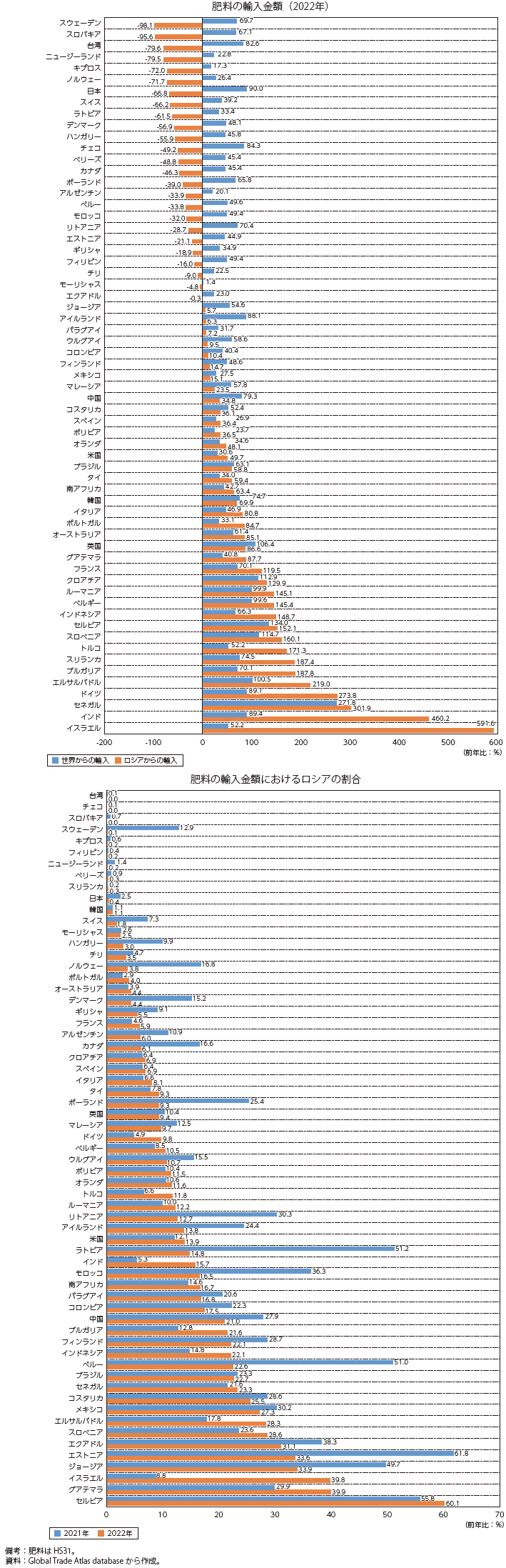
4.G7及び我が国の対応
総じて、エネルギー需要面では欧州が調達先の多角化を進展させた一方で、新興国・発展途上国の一部でロシアからの調達を維持若しくは促進するような動きが見られた。また、小麦輸入や肥料輸入といった食料安全保障面では、同侵略がもたらした混乱による食料価格の高騰によって、原産国による一時的な輸出規制が行われるなど、ロシアに対する小麦や肥料の輸入依存度を解消するような動きは強まっていないように見られた。
このような状況で、G7を始めとした主要国・地域は、ロシアによるウクライナ侵略による影響に対応すべく、結束を強めている。
G7広島サミットにおいて、ロシアによるウクライナ侵略をめぐる情勢についてG7間で率直な意見交換が行われ、ウクライナに対して外交、財政、人道、軍事支援を必要な限り提供するという揺るぎないコミットメントを改めて確認すると共に、制裁の回避・迂回対策含め、対露制裁の強化に向けた具体的な取組について一致した。あわせて「ウクライナに関する首脳声明」(2023年5月)を発出し、ロシアによる明白な国連憲章違反及びロシアの戦争が世界へ与える影響を最も強い言葉で非難するとし、G7メンバーが全ての政策手段を動員し、可能な限り早くウクライナに包括的、公正かつ永続的な平和をもたらすために、ウクライナと共にあらゆる努力を行うとした。
2023年4月15日及び16日に、北海道札幌市において、G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合が開催された。同会合における閣僚声明(仮訳)について、下表(第I-1-2-21表)はロシアによるウクライナ侵略について言及がある部分を抜粋している。同声明では、ロシアのウクライナ侵略により引き起こされたエネルギー価格の高騰やエネルギー安全保障の不安は、特に発展途上国において、環境、経済、社会的な悪影響を及ぼしていること、天然ガス・LNGへの投資については、この危機により引き起こされている将来的なガス市場の不足に対応するため適切であり得ることが強調されている。
第Ⅰ-1-2-21表 G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合声明におけるウクライナ侵略への言及
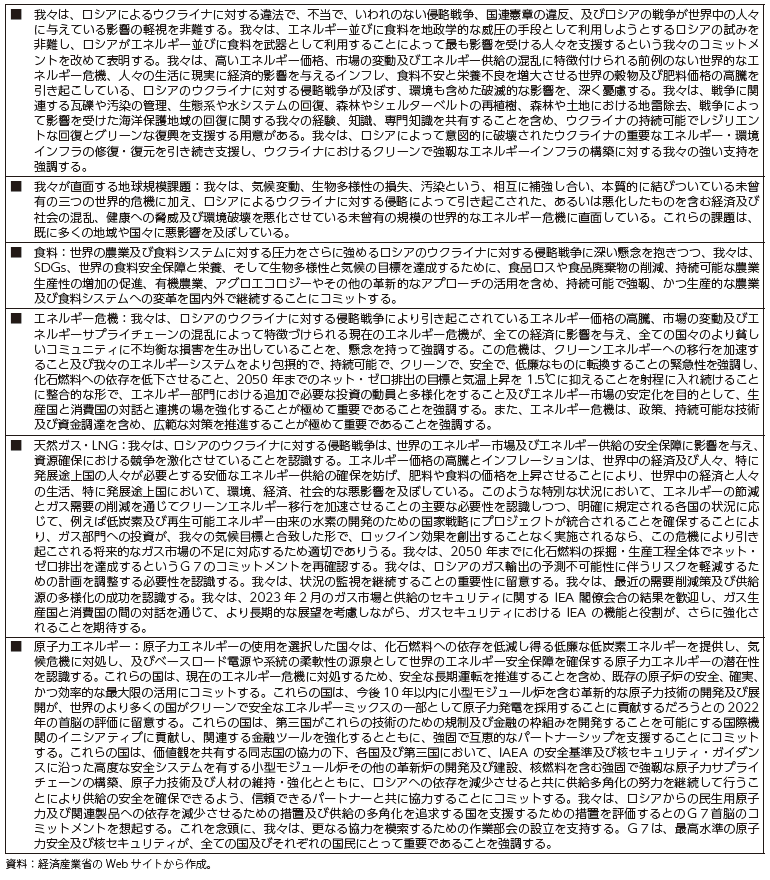
さらに、2023年4月22日及び23日に、宮崎県宮崎市において、G7宮崎農業大臣会合が開催された。採択されたG7農業大臣声明(仮訳)について、下表(第I-1-2-22表)はロシアによるウクライナ侵略について言及がある部分を抜粋している。同声明文では、ロシアに対するウクライナ侵略を強く非難しつつ、ロシアによる食料調達の武器化から影響を受ける人々への支援のコミットメント、ロシアに対する制限措置においては食料及び肥料を対象としないことで支援を必要とする人々に配慮すること、そして特にぜい弱な発展途上国における食料安全保障への悪影響を緩和することの重要性などが述べられている。食料調達の多角化は、それぞれの国・地域が抱える多様な要因があると考えられることから、それを一方的に推進していくことは困難であることを踏まえ、食料安全保障が国際社会の分断を深めていかないように配慮がなされている。
第Ⅰ-1-2-22表 G7宮崎農業大臣会合声明におけるウクライナ侵略への言及
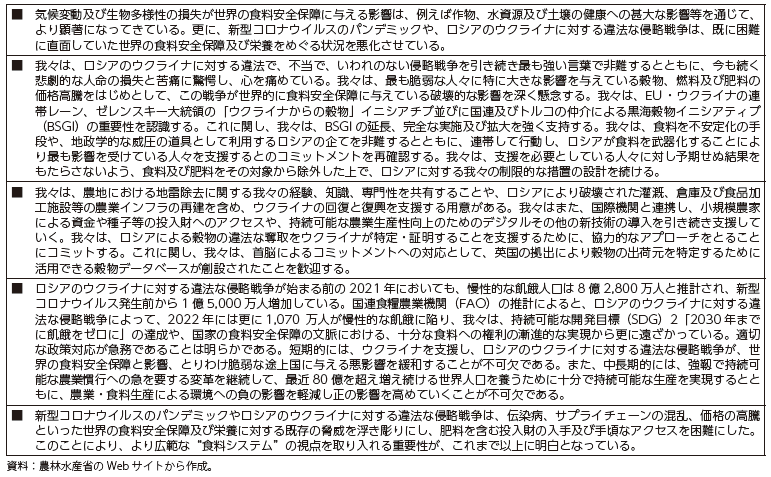
G7広島サミットにおいては、G7及び招待国の首脳が「強靱なグローバル食料安全保障に関する広島行動声明」(2023年5月)を発出し、手頃な価格で安全かつ栄養がある食料へのアクセスは人々が尊厳を持って生きるための基盤であることを再確認し、世界が現世代で最も高い飢饉のリスクに直面し、悪化するグローバル食料安全保障の危機に対応するため、また、国際市場における安定性と予見可能性の強化を通じたものを含め、より強靱で持続可能かつ包摂的な農業・食料システムを構築するため緊密に協力する重要性を共有した。
また、我が国としては、引き続きウクライナ及び周辺国の復旧・復興を全力で支援していくとともに(第I-1-2-23表)、力による一方的な現状変更という国際秩序の根幹を揺るがすロシアによるウクライナ侵略、そして、後述する権威主義国家の台頭に対して、自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値を重視する国々と団結し、自由で開かれた経済秩序の維持・強化を進め、自由貿易を推進するとともに、不公正な経済活動に対する対応を強化していく必要がある。
第Ⅰ-1-2-23表 ロシアによるウクライナ侵略を踏まえた我が国の対応
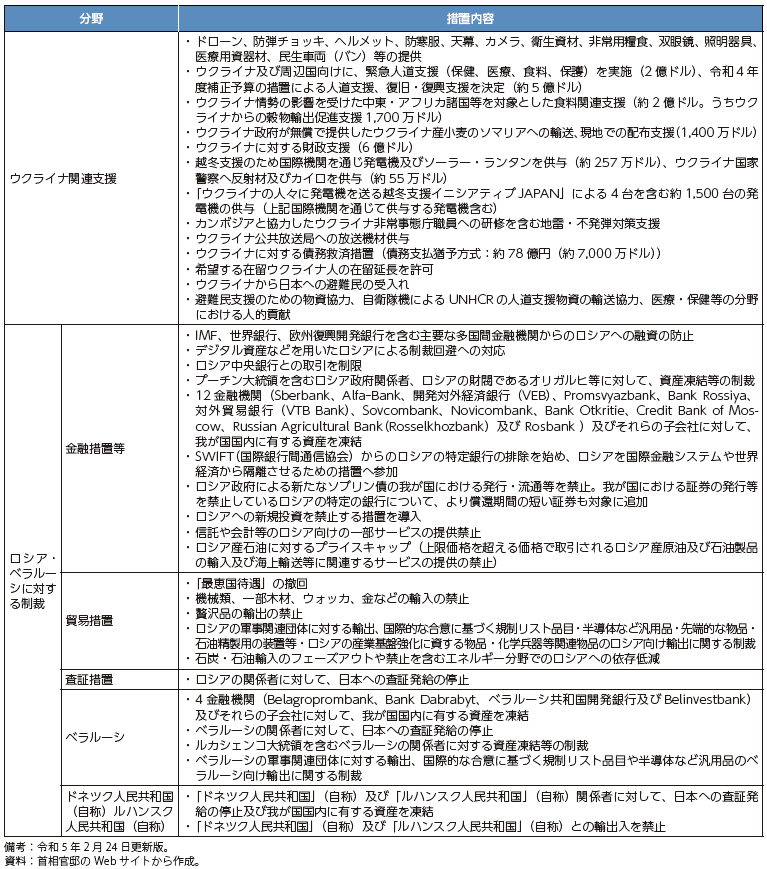
続いて、ロシア及びウクライナに進出している我が国企業の状況について見ていく。外務省が行っている調査によれば、我が国の企業は、ロシアとウクライナにはそれぞれ416と36の拠点を有しており、両国において製造業と卸売・小売業を中心とした企業活動が行われている(第I-1-2-24図)。JETROがロシアによるウクライナ侵略開始以降に行った調査では(第I-1-2-25図)、ロシアにおける事業(操業)を全面的または一部停止させている我が国の企業の割合がこの1年で増加し、全体の6割に達している。また、今後半年から1年後の事業展開見通しでは、「不明・該当せず」の割合が減少して「撤退」「縮小」の割合が増加した。ウクライナ侵略によって、我が国の企業は、事業からの撤退・縮小などの経営判断を迫られている。そのような状況下において、経済産業省としても、日本企業に対して、経営判断に資するよう現地制度に関する情報提供等を実施している。
第Ⅰ-1-2-24図 ロシアとウクライナにおける我が国企業の拠点
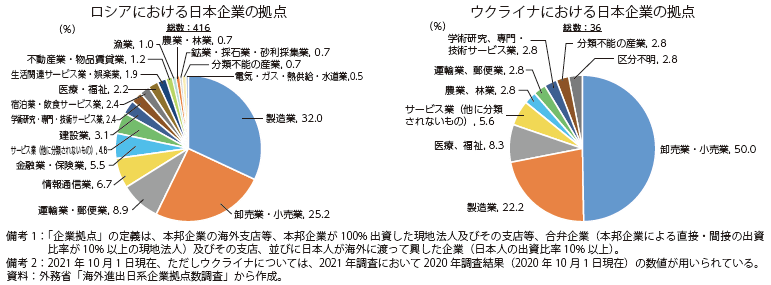
第Ⅰ-1-2-25図 ロシアにおける我が国企業の事業動向