第3節 高まるインフレ圧力
1.インフレの高進
第1章第1節第1項で見たように、世界的なインフレの高進が経済の成長鈍化の一因となっている。本項ではこうしたインフレの状況についてIMFのデータを基に世界、先進国、新興国・途上国のインフレ率の見通しを概観する。また、先進国については国ごとに異なる背景やインフレの状況について見ていく。
(1)インフレの現状
① 世界のインフレ率
世界のインフレ率は、グローバル需要の弱さによる燃料価格やコモディティ価格の下落、金融引締めの影響により、IMFによると、2022年をピークに2023年や2024年にはインフレ率が低下していく見通しとなっているが、2023年に7.0%、2024年に4.9%といずれも2021年や2022年時点から見通しを上方修正しており、インフレ圧力の高さがうかがえる(第I-1-3-1図)
第Ⅰ-1-3-1図 世界のインフレ率の見通し
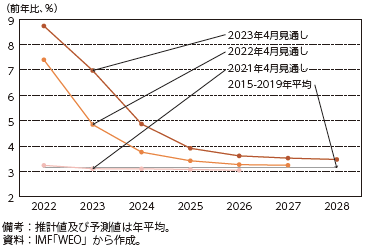
② 先進国のインフレ率
2023年4月のIMF世界経済見通しによれば、先進国のインフレ率は、各国中央銀行の積極的な金融引締めを受けて、2022年をピークとして、2023年に4.7%、2024年に2.6%となる見通しとなっている(第I-1-3-2図)。
第Ⅰ-1-3-2図 先進国のインフレ率の見通し
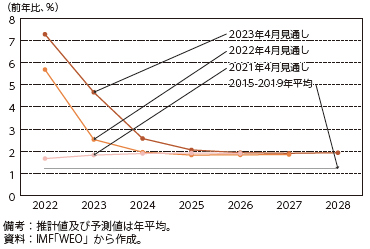
先進国における各国・地域の状況として、日本、米国、EU、ドイツ、フランス、英国におけるインフレ率の推移や、食料やエネルギー、その他財・サービスの寄与度についてみると、いずれも2022年にインフレが高進しているほか、エネルギー価格の上昇の影響が共通して大きいことが確認できる(第I-1-3-3図)。
第Ⅰ-1-3-3図 先進国におけるインフレ率の寄与度の推移
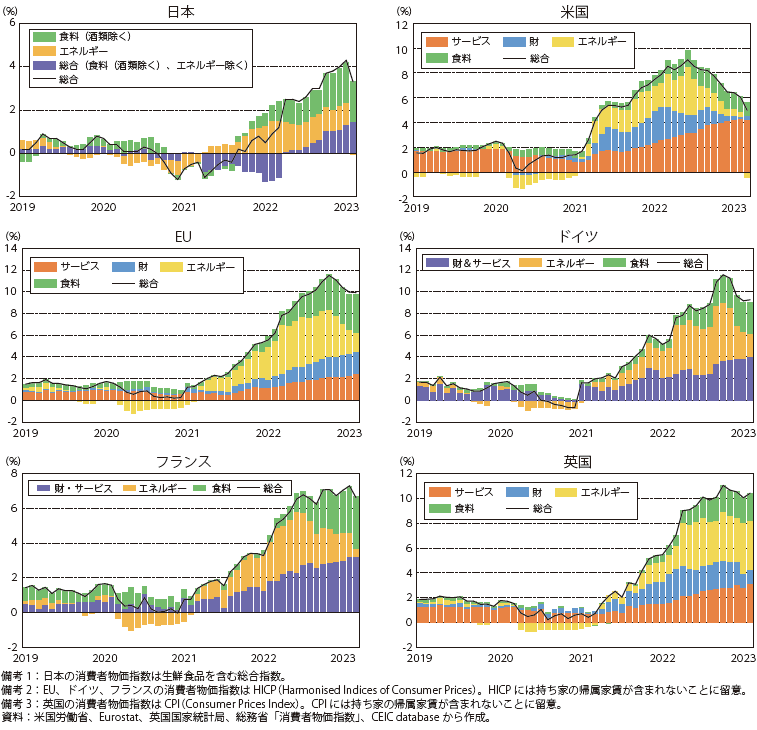
一方、足下での動向については、国・地域ごとの背景の違いによって状況が異なっている。
日本は他の国々と異なり、2021年には他国でインフレが高進するなかでも食料やエネルギー以外がマイナスに寄与して、食料・エネルギーを除く総合指数(コアコア指数)も高い水準にはなかった。一方、2022年に入ってからは食料・エネルギー価格の上昇によってインフレ率が上昇し、2022年半ば頃からはコアコア指数にも物価上昇が波及しており、2023年1月には前年同月比+4.3%となっている。全体としては2023年1月にピークアウトしているものの、コアコア指数の上昇傾向は続いている。
米国については、2022年6月に前年同月比で+9.1%となり、その後、ピークアウトするも依然高い水準が続いている。2023年3月の総合指数は同+5.0%となっているが、その内訳は2021年とは大きく異なっている。2021~2022年にかけてはエネルギーや財がインフレ率を押し上げていたが、足下ではそれらの影響は小さく、食料価格とサービスの影響が大半を占める状況となっており、2023年3月にはコア指数が総合指数を上回っている。
EUでは、ロシアによるウクライナ侵略の影響を受けて、特にエネルギー価格が大きくインフレ率を高めたほか、エネルギー不足が懸念されたが、記録的な暖冬によりエネルギー価格の寄与は鈍化している。一方、食料、財、サービスについては高い水準が続いており、2023年2月の総合指数は前年比+9.9%となっている。特に、ドイツは原油や天然ガスの多くをロシアへ依存してきており12、エネルギー不足やエネルギー調達先の多角化を背景にインフレが高進し、2022年10月に前年同月比+11.6%となった。その後、エネルギー価格の寄与は低下しているものの、食料や財・サービスのインフレを背景に、2023年2月で前年同月比+9.3%と依然高止まりの状況となっている。英国はエネルギー価格の寄与が約4割と依然として大きく、2023年2月における総合指数は前年同月比+10.4%と高止まりの状況が続いている。
12 資源エネルギー庁(2022)『エネルギー白書2022』。
③ 新興国・途上国のインフレ率
2023年4月のIMF世界経済見通しによれば、新興国・途上国のインフレ率は、2023年に前年比+8.6%、2024年に同+6.5%となっており、世界全体や先進国と比して、大きく上方修正されている(第I-1-3-4図)。
第Ⅰ-1-3-4図 新興国・途上国のインフレ率の見通し
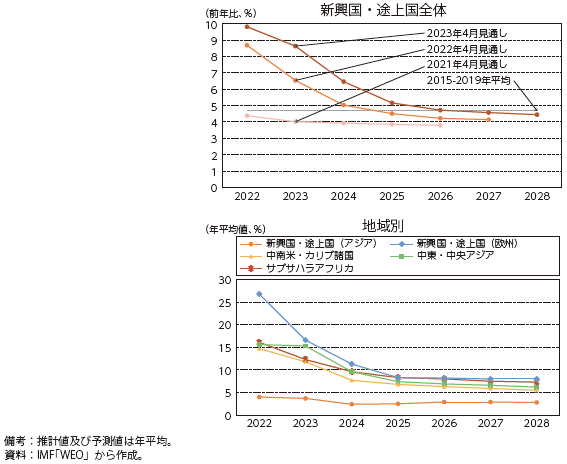
新興国・途上国のインフレ率は輸入物価上昇を受けて2022年に大幅に上昇したが、コモディティ価格上昇の影響の一服を受けて、2023年、2024年は鈍化の見通しとなっている。
(2)インフレの要因と対応の方向性
これまでに世界全体や各地域のインフレの状況、先進国については各国の状況について確認してきた。国・地域ごとに水準や背景が異なるが、その中でも共通するインフレの要因と各要因への対応の方向性については以下のように整理することができる(第I-1-3-5表)。
第Ⅰ-1-3-5表 インフレの主な要因と対応の方向性
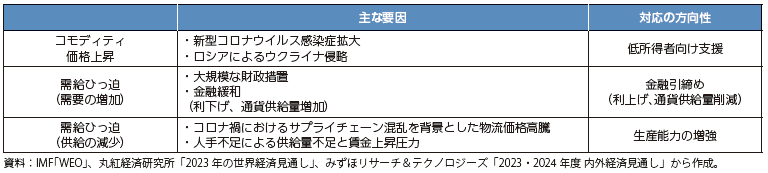
世界的なコモディティ価格の上昇はコロナ禍においても生じていたが、ロシアによるウクライナ侵略が拍車をかけており、食品やエネルギー価格のさらなる高騰を招いている。また、各国政府は、食品やエネルギー価格高騰の影響を最も受ける低所得者層向けの重点的な物価高騰対策を行っており、詳細は後述する。
次に、需給のひっ迫のうち、特に需要の増加については、コロナ禍での大規模な財政支援や行動制限緩和を受けた繰越需要によって生じている。また、コロナ禍当初における大幅な利下げや、通貨供給量の増加といった金融緩和が需要超過を招いている。これらへの対応としては2022年から各国中央銀行によって積極的に進められている利上げや通貨供給量削減といった金融引締めがある。各国における金融引締めの対応やその影響については次項で詳述する。
さらに、需給ひっ迫のうち、供給サイドをみると、労働力不足を背景とした供給量不足が生じている。また、労働力不足は賃金上昇圧力となるため、インフレの長期化を左右する重要な要因となっている。中長期的なインフレ抑制における供給力強化の重要性については次章で詳述する。
① コモディティ価格の上昇
コモディティ価格は新型コロナウイルス感染症拡大、ロシアによるウクライナ侵略、気候変動等といった不確実性を伴う要因によって大きく変動している。コモディティ価格の上昇は生産コストへの転嫁につながり、インフレ圧力となる可能性を有している。
エネルギー価格の高騰はピークを越え、それぞれ徐々に落ち着きを取り戻しつつあるものの、引き続き動向に注視が必要であることが分かる(第I-1-3-6図)。
第Ⅰ-1-3-6図 主要なエネルギー価格の推移
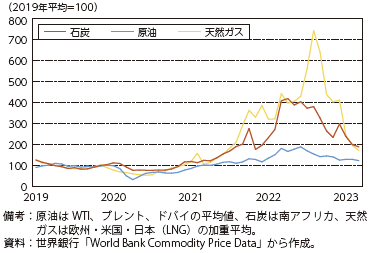
次にFAOによる食料価格全体及び品目別の価格指数の動向をみると、以下のような動向を示している(第I-1-3-7図)。
第Ⅰ-1-3-7図 食料の品目別価格指数
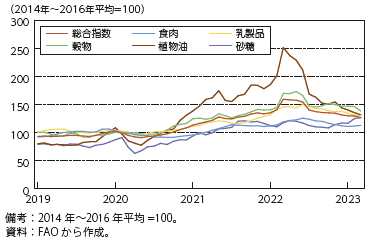
穀物や植物油の価格高騰を受けて高まった総合価格指数は2022年3月をピークとして高騰したが、その後、価格が下落しており、植物油については足下でピーク時の半分程度となっている。一方で、いずれの品目についてもコロナ禍前と比べると高い水準が続いており、新興国・途上国のほか、先進国においても特に低所得者層に与える影響には引き続き注視が必要となっている。
② 需給のひっ迫
需給のひっ迫については、サプライチェーンにおける供給制約や、労働市場の状況といった供給サイドに焦点を当てて、関連する価格指数や経済指標の動向を見ていく。先述したように需要超過への対応としての金融引締めについては次節で詳述する。
サプライチェーンにおける供給制約について、令和四年版通商白書ではコロナ禍での行動制限や港湾労働者不足、財政措置に伴う財需要の急増を背景とした物流混乱の状況を示していた。2023年4月時点でコンテナ価格指数の状況をみると、コロナ禍前の水準となっていることが確認できる(第I-1-3-8図)。
第Ⅰ-1-3-8図 バルチックコンテナ価格指数の動向
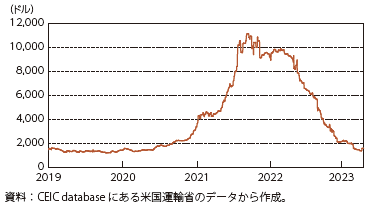
航路別でみても、特に、昨年高騰していた上海からロサンゼルスへの運賃の水準はコロナ禍前の水準に戻っており、日本から欧米へのコンテナ運賃についてもコロナ禍前の水準へと戻りつつある(第I-1-3-9図)。
第Ⅰ-1-3-9図 コンテナ運賃の動向
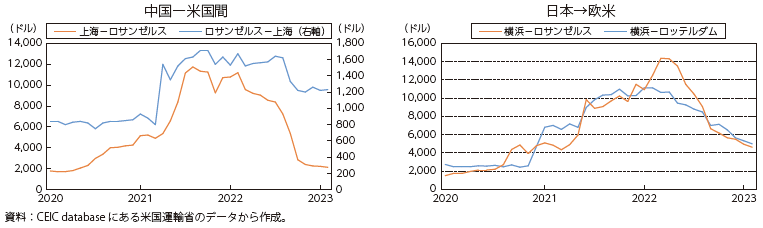
こうした状況を踏まえて米国における製造業及びサービス業に関する景況感を示すISM景況指数を見ていく。2021年や2022年当初においては、需要の急増を映じて受注や生産に関する指数が上昇し、また、物流混乱を受けて、入荷遅延や運賃高騰を映じて価格指数が上昇していた。足下では物流混乱の緩和を受けて、製造業及びサービス業ともに入荷遅延の指数が低下してきているが、特に製造業においては需要の低下の動きがみられ、新規受注が50を割り、総合指数についても50を割る状況となっている(第I-1-3-10図)。
第Ⅰ-1-3-10図 米国のISM景況指数(製造業・サービス業)
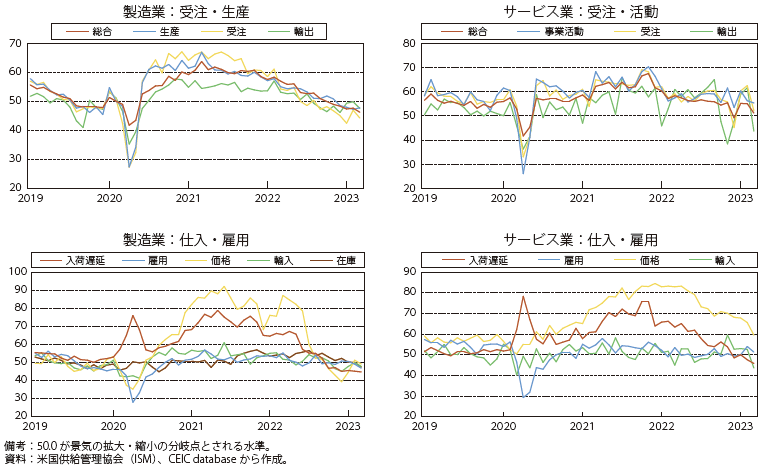
次に、欧州における製造業の制約要因の動向について、欧州委員会による企業調査の結果をみると、コロナ禍当初においては制約要因の主因は需要であったが、2022年当初にはエネルギー不足や価格高騰を映じて設備/原材料が主因となっていた。足下ではピークアウトしているものの、依然として主たる制約要因となっている。設備/原材料と併せて、需要と労働力についても主要な制約要因になっている(第I-1-3-11図)。
第Ⅰ-1-3-11図 欧州における製造業の制約要因
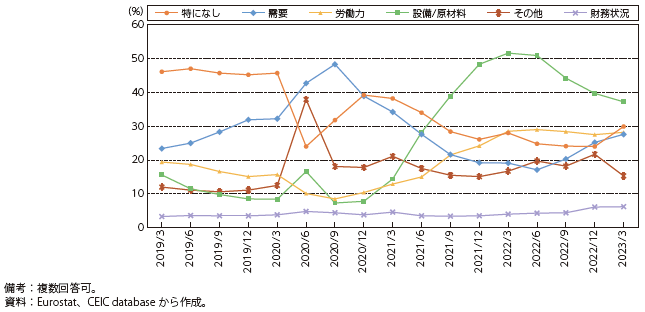
労働力不足は需要に対する財・サービスの供給不足を招くことに加えて、賃金上昇圧力にもなりインフレに拍車をかけかねない。インフレ率の状況を勘案した先進国各国の名目賃金及び実質賃金成長率の動向を確認すると共通して実質賃金成長率がマイナスで推移していることが確認できる(第I-1-3-12図)。
第Ⅰ-1-3-12図 先進国における名目賃金と実質賃金の成長率の推移
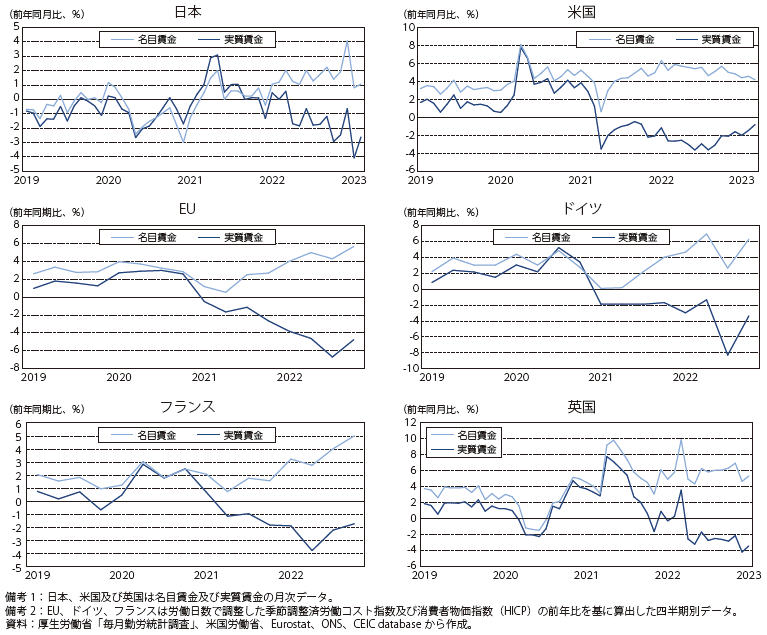
コロナ禍前において、多くの国では消費者物価指数の上昇率を上回るように名目賃金は上昇し、実質賃金上昇率はプラスで推移していた。米国はインフレがピークアウトしたことで徐々に実質賃金のマイナス推移が改善されつつあるが、依然として名目賃金上昇率が高止まりしており人手不足の様子がうかがえる。EU各国や英国については名目賃金上昇率の増加していることに加え、インフレ率についても依然高い水準にあることから実質賃金上昇率のマイナス幅が大きい状況となっている。
(3)先進国における物価高騰対策
これまでに見てきたインフレの状況に対して、IMFはインフレへの対応措置として一律の財政支援措置は廃止すべきであり、食品やエネルギー価格の高止まりの影響を最も受けた層に的を絞るべきとの方向性を示している13。我が国における所得分位別のエネルギーや食料に係る負担増加について確認すると、低所得者ほど収入に占める負担増加の比率が高いことが確認できる(第I-1-3-13図)。
第Ⅰ-1-3-13図 日本のエネルギー及び食料に係る2019年平均からの負担増(対収入比)
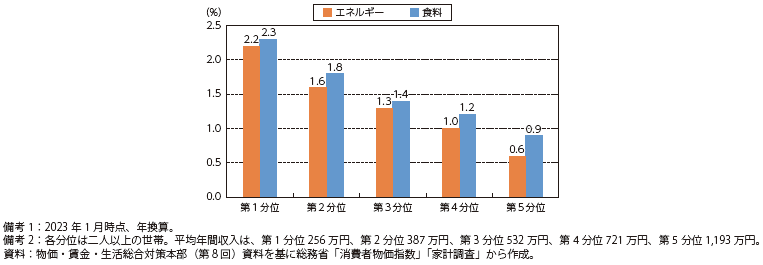
米国においては食料のほか、住宅や輸送手段に関して所得別のインフレの影響を分析している(第I-1-3-14図)14。
第Ⅰ-1-3-14図 所得分位別支出財の割合と所得分位別インフレ率とのギャップ(米国)
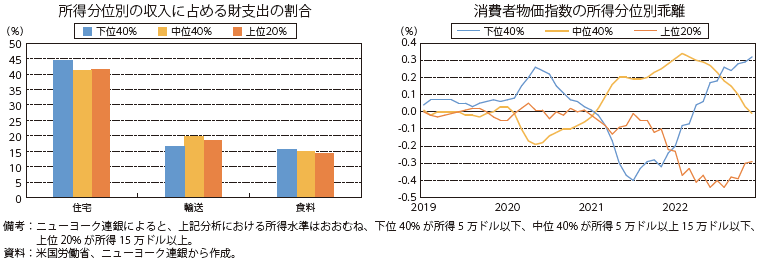
まず、所得分位別の収入に占める財支出の割合をみると、住宅と食料については低所得者層の支出割合が最も高いことが分かる。一方で輸送関連の支出については中所得者層が最も高くなっている。このため、エネルギー価格を主因としてインフレが高進していた2021年から2022年にかけては中所得者層のインフレ率が対前年比で全体よりも高くなり、最も影響を受ける所得階層となっていた。一方で、先述したようにエネルギー価格の高騰が一服する足下においては、低所得者層への影響が最も大きくなっている。
上述したような状況を踏まえた先進各国の主な消費者向け物価高騰対策は以下の表のとおりとなっている(第I-1-3-15表)。
第Ⅰ-1-3-15表 主要国での物価高騰に対する消費者向け対策の概要
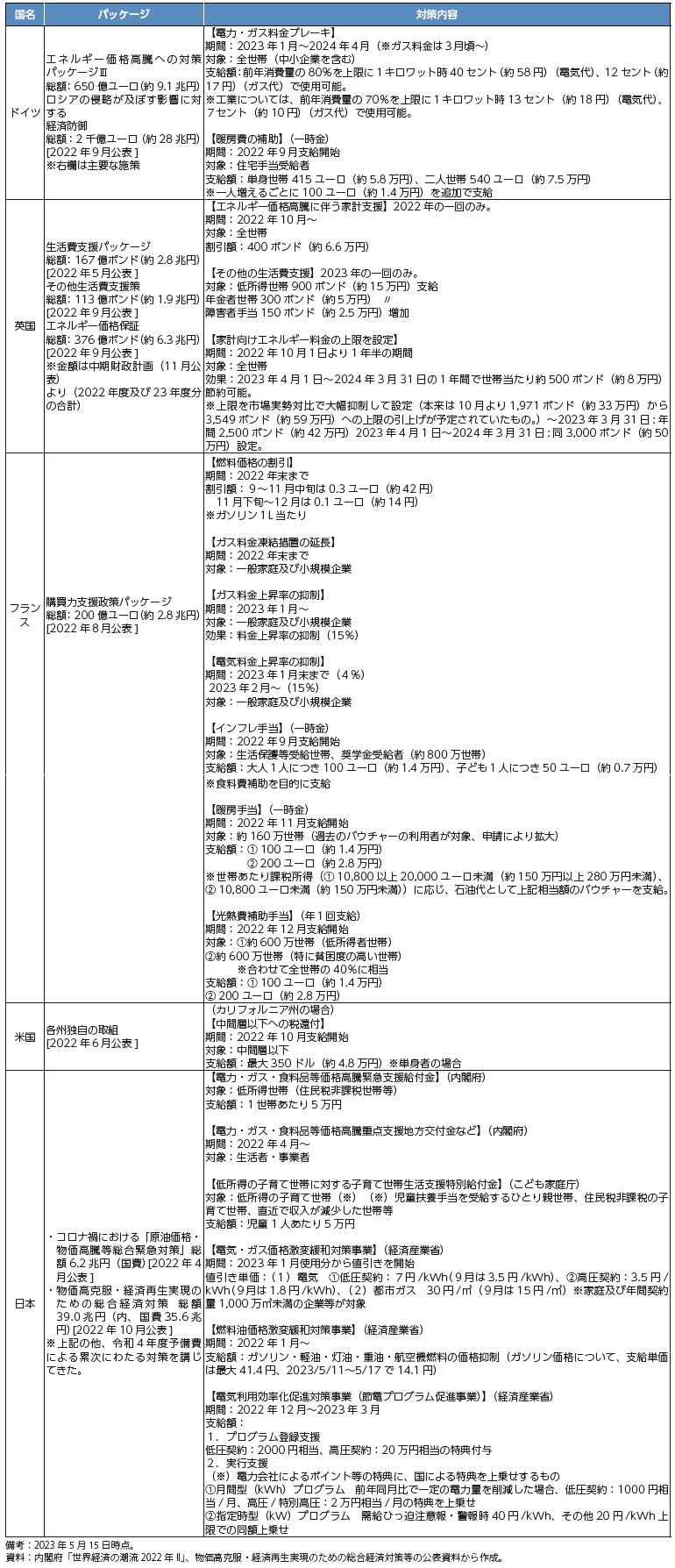
このように、世界的なインフレの高進に対して、各国政府はインフレに苦しむ低所得者層に対しては的を絞った財政措置を講ずる一方で、各国中央銀行はインフレ抑制に向け、金融引締めを加速している。次節では各国中央銀行による金融引締めの加速について詳述する。また、次章では、今般のインフレが供給不足に起因している側面が強いことに鑑み、中長期的には供給力を強化していくことの重要性について指摘する。
13 IMF「WEO」(https://www.imf.org/ja/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023![]() )。
)。
14 ニューヨーク連銀「Inflation Disparities by Race and Income Narrow」(https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2023/01/inflation-disparities-by-race-and-income-narrow/![]() )。
)。
2.金融引締めの加速
(1)インフレ抑制を主眼に据える中央銀行
前項までは、世界的に高まった物価上昇圧力の詳細を見てきたが、本項以降では、そうした物価上昇圧力が経済に対してどのような影響を持ち得るのかを見ていく。
世界的なインフレの高進に対して、経済に対する新型コロナウイルス感染症拡大の影響が残りながらも、各国・地域の中央銀行は機動的な対応を実施してきた。下図(第I-1-3-16図)は、G20各国・地域の中央銀行の政策金利を示したものである。これによると、各国・地域の大半の中央銀行は、米国のFRBに代表されるように、世界的なインフレ圧力が高まってきた2022年半ば頃から、急速かつ大幅に政策金利を引き上げてきた。
第Ⅰ-1-3-16図 G20各国・地域の政策金利の推移
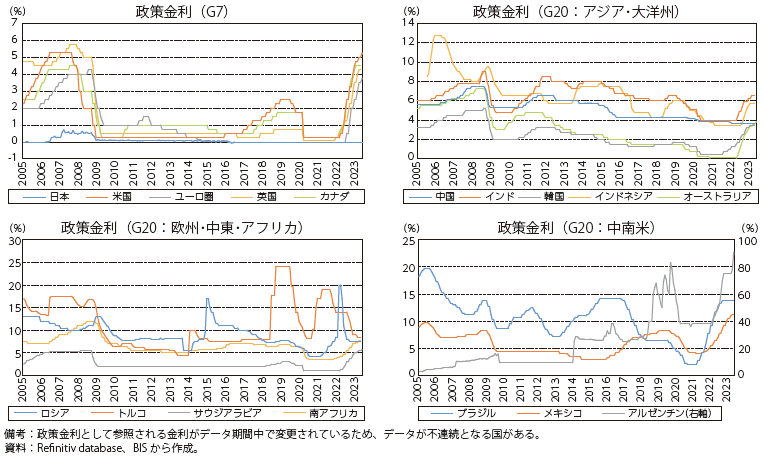
こうした政策対応から示唆されるのは、中央銀行は金融引締めが景気動向に対してリスクになり得ることを認識しながらも、インフレの抑制が重要であるという姿勢を示していることである。具体的に、下表(第I-1-3-17表)は、上記の各国・地域について、中央銀行が公表している経済見通しであり、2022年については、ロシアによるウクライナ侵略の混乱の影響もあり、多くの国・地域の実質GDP成長率見通しは継続的に下方修正され、一方でインフレ率見通しは継続的に上方修正されてきた。2023年については、インフレ率の高進は一巡するものの、物価の高騰や大幅な金融引締めの影響によって、実質GDP成長率は低迷するとの見通しがおおむね示されている。このように、各国・地域の中央銀行は、経済成長率が減速するという見通しを持ちながらも、インフレを抑制するための金融引締めを実施してきたことになる。
第Ⅰ-1-3-17表 G20各国・地域の経済見通しの変遷
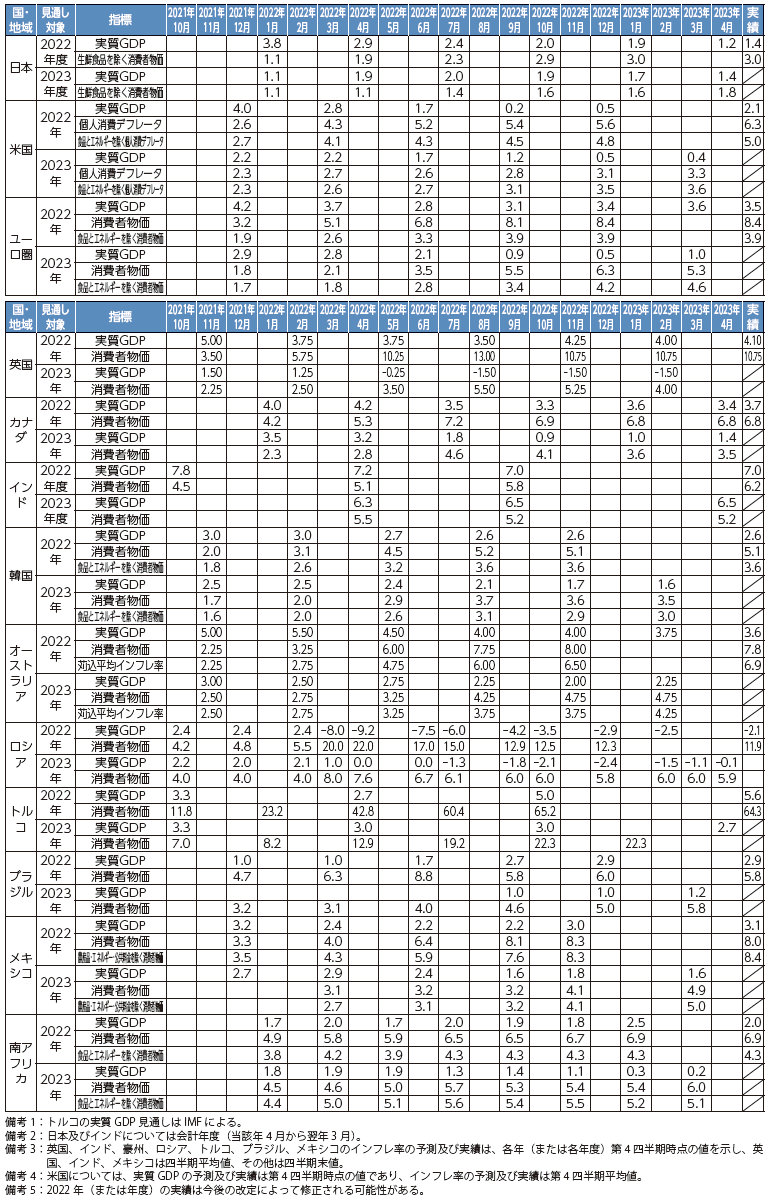
(2)金融環境の引き締まりとその多様な影響
上述のように各国・地域の中央銀行は、インフレを抑制するために金融引締めを進展させてきたが、そうした措置は経済に対してどのような影響を持ち得るのだろうか。
世界金融危機や新型コロナウイルス感染症拡大といった突発的な危機を除けば、中央銀行の金融政策は、金融環境が緩和的であるのか引締め的であるのかに対して重要な影響を及ぼす。下図(第I-1-3-18図)は、多様な金融関連指標を用いて、各国・地域の金融環境を総合的に表す金融環境指数の推移を示したものであり、同指数は数字が大きいほど金融環境が引締め的であることを示し、数字が小さいほど金融環境が緩和的であることを示す。これによると、各国・地域の中央銀行が本格的な引締めを開始した2022年には、先進国では同年前半に指数が上昇し、新興国では中国を除いた新興国での指数の上昇が顕著となり、世界的に金融環境が引締め的な状況になっていたことが示されている。
第Ⅰ-1-3-18図 各国・地域の金融環境指数
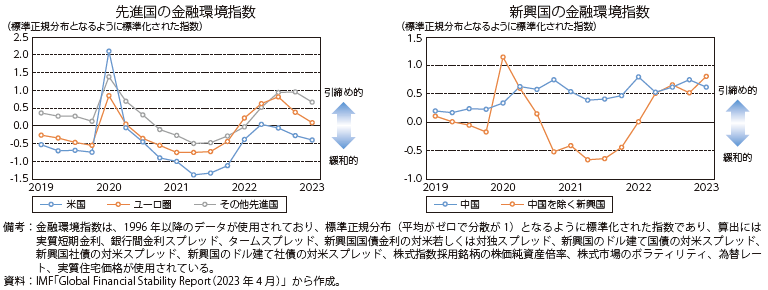
金融政策の変更が実体経済に及ぼすと想定される主な経路の一つとして、金融機関による企業や家計への与信行動の変化が挙げられる。一般的に、中央銀行による政策金利の引上げは、金融機関による家計や企業への貸出金利へ波及し、金融機関にとっては貸出による利ざやが拡大する。一方で、そうした金利の上昇は、資金の借り手による返済負担の増加を意味し、金利の上昇自体が景気減速とそれに付随する債務不履行の懸念を高めることから、金融機関による与信判断の慎重化にもつながり得る。総じて、政策金利の上昇を通じた市中金利の上昇は、金融機関にとっては与信基準の緩和化と慎重化の両方向への誘因となり得る。それを踏まえて、主に各国・地域で実施されている銀行貸出アンケート調査の結果を見ると(第I-1-3-19図)、世界的に政策金利が引き上げられてきた2022年以降では、金融機関の貸出運営スタンスはおおむね慎重化の方向となっており、金融機関としては政策金利の引上げが景気を減速させるとの見方を強めていることが示唆されている。
第Ⅰ-1-3-19図 各国・地域の銀行による貸出運営スタンスの推移
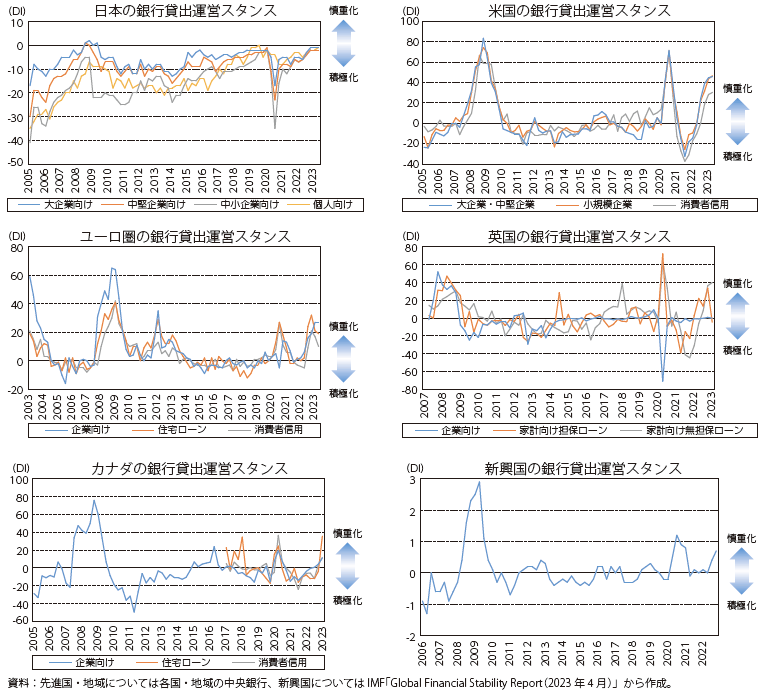
同時に、銀行貸出アンケート調査で、需要側の結果が公表されている国・地域の結果を見ると(第I-1-3-20図)、特に中央銀行による金融政策の引締めが顕著になってからは、個人を中心として貸出に対する需要がおおむね減退していることが示されている。こうした結果からは、資金の需要側から見れば、貸出金利の上昇は、返済負担の増加を通じて資金需要の抑制要因になっていることが示唆されている。
第Ⅰ-1-3-20図 各国・地域の資金需要の推移
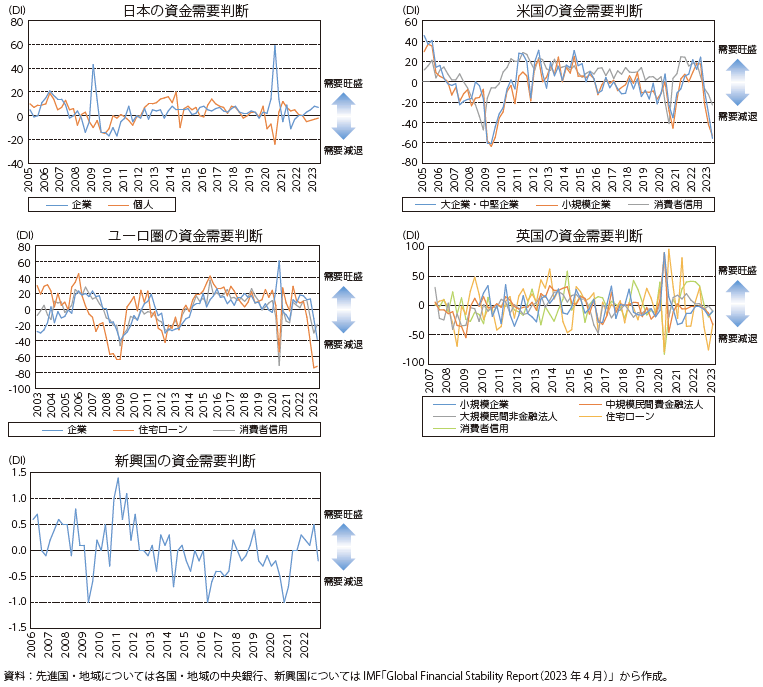
以上の銀行貸出アンケート調査の結果を踏まえて、先進国と新興国における非金融法人と家計への与信残高の推移を見ると(第I-1-3-21図)、2020年以降は新型コロナウイルス感染症拡大による経済の混乱で、名目GDP比での大幅な変動は見られているものの、非金融法人と家計への与信は、残高水準には大きな変動は見られておらず、大幅な貸出の減少を意味する信用収縮のような状況にはなっていないことが示唆されてる。
第Ⅰ-1-3-21図 先進国と新興国の非金融人と家計への与信残高の推移
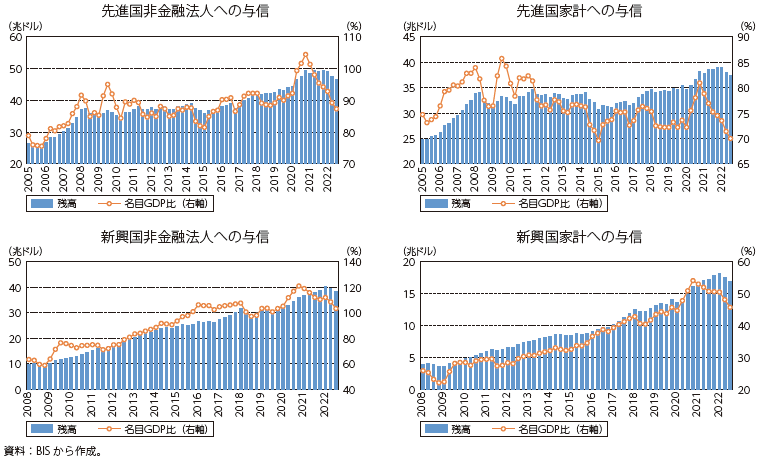
そうした信用収縮による景気への懸念が過度に高まってはいない一方で、特に家計への与信残高水準が増加していることに関連して留意する必要があるのは、住宅価格の動向である。新型コロナウイルス感染症拡大は世界的な景気後退をもたらしたものの、中央銀行による緩和的な金融政策と、テレワークの促進によって、住宅価格が上昇した可能性がある15。住宅価格の動向を見ると(第I-1-3-22図)、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行が深刻化し、景気後退が顕著であった2020年にはむしろ住宅価格は上昇し、そのような傾向は2021年にも継続した。物価上昇圧力が強まったことで、2022年には中央銀行が金融政策を引締めたことで金利が上昇したものの、カナダ、中国、豪州といった一部の国を除けば、G20各国・地域で見ると住宅価格の緩やかな上昇が続いた。しかし、上述のとおり、金融引締めによる金利の上昇は、家計による資金需要を減退させており、それが時間差をもって住宅価格に影響してくる可能性もある。実物資産である住宅価格の急激な下落は、金融負債である住宅ローン残高の実質的な増価になるため、家計のバランスシートを悪化させる要因になり得る。現状はそうした懸念は当てはまらないものの、金融引締めが住宅価格に与える影響には留意が必要である。
第Ⅰ-1-3-22図 G20各国・地域の住宅価格
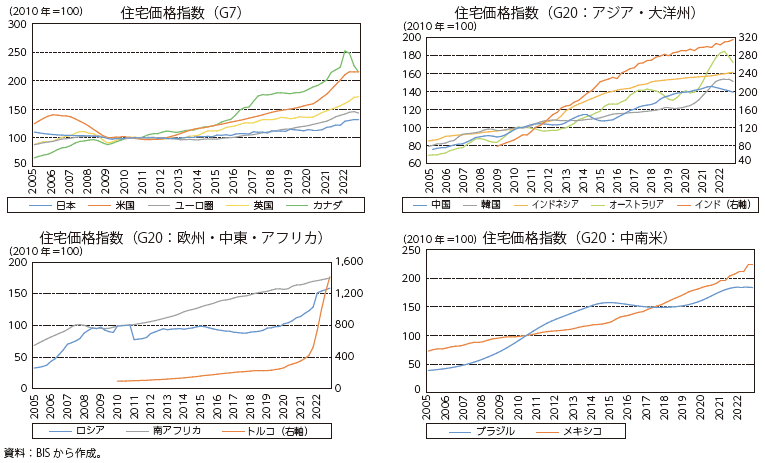
さらに、金融政策の変更は、政策金利等の変更を通じて企業の借入コストに影響を与えるため、企業業績とそれへの市場の見方を反映する株式市場への影響も重要である。株価の変動は、家計の金融資産残高を変動させることを通じて、個人消費に影響を与える場合もあり、そうした影響は資産効果として呼ばれ、金融政策の効果伝達経路の一つとされている。
下図(第I-1-3-23図)は、先進国の株式市場の動向を代表的に示すMSCI世界指数と、新興国の株式市場の動向を代表的に示すMSCI新興市場指数であり、特に先進国での政策金利の急激かつ大幅な引上げを反映して、世界指数は2022年当初からの下落が顕著になり、新興市場指数も2021年から見られている下落傾向が2022年の終盤まで継続した。こうした株価の下落は、企業株式への直接的な投資や、投資信託持分といった間接的な投資を通じて、家計の金融資産を減少させることで、個人消費を下押しする負の資産効果が懸念される。
第Ⅰ-1-3-23図 先進国と新興国の株式市場
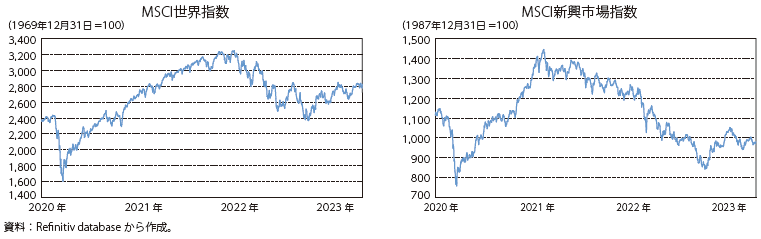
実際に、各国・地域の家計の金融資産残高を見ると(第I-1-3-24図)、先進国では大幅な金融引締めを行っていない日本の家計の金融資産残高に大きな変化は見られないものの、他国・地域においては2022年に入ってからの家計の金融資産残高の減少が顕著になっている。新興国においては、先進国に比較してデータの入手性が限られるものの、トルコといった例外を除き、家計の金融資産の2022年に入ってからはおおむね減少している。こうした家計の金融資産の目減りが、家計の景況感の悪化と相まって、消費に対して下押し圧力を強める可能性に留意が必要である。
第Ⅰ-1-3-24図 各国・地域の家計の金融資産残高
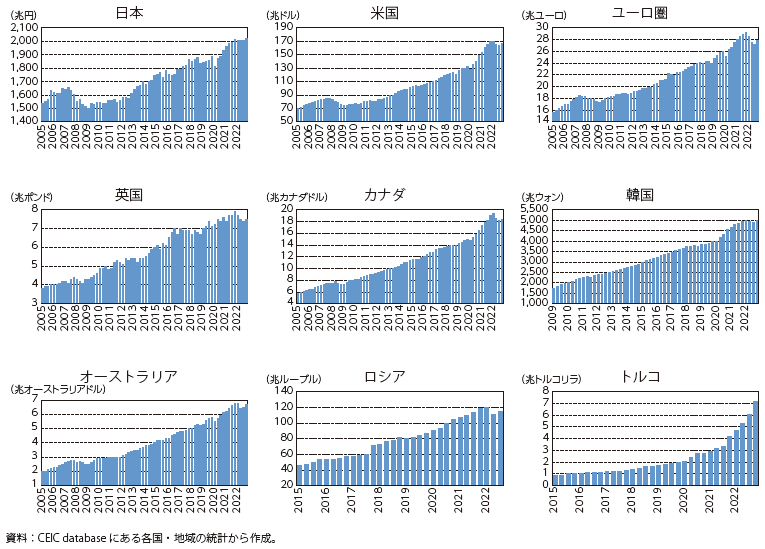
15 経済産業省(2022)『令和四年版通商白書』。