付注1 生産性の上昇によるインフレ抑制効果
概要
本分析では、全要素生産性の上昇率がインフレ率に与える長期的な影響について分析を行う。
推計モデル・データ
i国におけるt期の労働力をL、物価をP、総雇用者報酬をW、実質GDPをY、高齢化率をEとすると、労働生産性Y/L及び一人当たり賃金の変化率が物価上昇率(インフレ率)に与える影響は、対数差分dln及び各国固有の影響v、その他の誤差項εを用いて下記①式のとおり表すことができる。なお、物価上昇率の自己相関を考慮し、1期前の物価上昇率を説明変数として加えている。
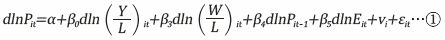
ここで、生産要素が資本ストックKと労働力Lの二要素である場合、コブ・ダグラス型の生産関数は、全要素生産性をA、資本分配率をα、労働分配率1-αをとすると下記のとおりとなり、②のように整理することができる。
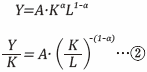
また、労働生産性は、資本装備率K/Lを用いて、下記③のとおり分解することができる。
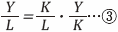
③式に②式を代入し、自然対数を取ると、労働生産性は下記④式のとおり、全要素生産性と、資本装備率と資本分配率の積に分解される。
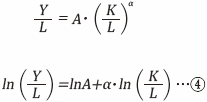
よって、①式におけるY/Lは、④式を用いて、下記⑤式のとおり整理される。本モデルでは、この⑤式について推計を行う。

データとしては、Penn World Table version 10.01290及び国際連合の人口推計から下記のデータを使用する。データは118か国、1950年から2019年までの期間からなるアンバランスなパネルデータである。Penn World Table version 10.01より、労働力Lにはemp(労働者人口(百万人))、資本ストックKには rnna(実質資本ストック(2017年の百万米ドル基準))、全要素生産性Aにはrtfpna(全要素生産性の実質値(2017=1))、総雇用者報酬Wにはlabsh(名目GDPに占める総雇用者報酬の割合)とv_gdp(名目GDP)の積、実質GDPY にはq_gdp(実質GDP(2017年基準))をそれぞれ用いる。なお、物価PとしてはGDPデフレータを算出し変数として用いる。また、高齢化率Eは国際連合の人口推計より各国の65歳以上の人口の比率を取得し、変数とした。なお、④式におけるα∙ln(K/L)は、 L、A、Yを用いて算出した。
推計結果
推計結果を下記のとおり表す。固定効果モデル及び変量効果モデルを推計し、ハウスマン検定を行ったところ、変量効果モデルが採択された。各変数のパラメータを見ると、全要素生産性の変化率及び、資本分配率と資本ストック変化率の積には、GDPデフレータ変化率に対して有意水準0.1%で統計的に有意な負の影響が見られ、一人当たり賃金の変化率には、GDPデフレータ変化率に対して有意水準0.1%で統計的に有意な正の影響が見られた。一方で、高齢化率には、GDPデフレータに対する統計的に有意な影響は見られなかった。この結果より、全要素生産性の上昇及び資本への投資の増加は物価上昇率を抑制させ、労働への投資の増加及び労働者一人当たり賃金の上昇はインフレ率を増加させることが示唆された。また、高齢化による労働人口の減少は物価上昇には影響を与えないことが示唆された。
<推計結果>

付注2 貿易開放度と生産性の関係
概要
本分析では、日本経済研究センター(2019)291及び内閣府の平成23年度年次経済財政報告292を参照し、貿易の促進が全要素生産性に与える影響について分析を行う。
推計モデル・データ
まず、貿易の促進の程度を測る指標として、貿易開放度を用いる。貿易開放度は日本経済研究センター(2019)と同様に、Squalli and Wilson(2011)の提唱した下記の定義を用いる。

ここで、i国のt期の貿易開放度をCTS、全要素生産性をTFP、高齢化率をE、実質GDPをY、2023年1月時点でのOECDへの加盟国であれば1を取るダミー変数をOECDとし、自然対数lnを取ると、貿易開放度が全要素生産性に与える影響は各国固有の影響v、その他の誤差項εを用いて下記式のとおり表すことができる。なお、式ではOECD加盟国とそうではない国の間でのCTSがTFPに与える影響の差を検証するため、OECDとCTSの交差項を入れて推計を行う。また、CTSとTFPの関係性には逆の因果関係が存在する可能性があるため、日本経済研究センター(2019)にならい、CTSおよびOECDとCTSの交差項については、1期前の値を操作変数として用いる。
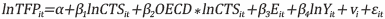
データとしては、Penn World Table 10.01及び国際連合の人口推計のデータを用いてデータセットを作成した。データは1980年から2019年の期間における、118か国のアンバランスなパネルデータである。貿易開放度CTSは、Penn World Table 10.01のcsh_x(実質GDP(PPPベース)に占める輸出のシェア)、csh_m(実質GDP(PPPベース)に占める輸入のシェア)、rgdpo(支出面から見た実質GDP)のデータを用いて算出した。全要素生産性TFPは、Penn World Table 10.01のrtfpna(全要素生産性の実質値(2017=1))とctfp(全要素生産性の相対水準(米国=1))の積を算出し、2017年の米国の全要素生産性が1となる変数を作成した。実質GDPであるYには、Penn World Table 10.01のrgdpo(支出面から見た実質GDP)を用い、高齢化率Eには国際連合の人口推計より各国の65歳以上の人口の比率を取得し、変数とした。
推計結果
推計結果を下記のとおり表す。固定効果モデル及び変量効果モデルを推計し、ハウスマン検定を行ったところ、固定効果モデルが採択された。各変数のパラメータについて見ると、CTSにはTFPに対して、有意水準0.1%で統計的に有意な正の影響が見られた。また、CTSがTFPに与える影響は、OECD加盟国であれば、有意水準1%で統計的に有意に大きいという結果であった。また、EはTFPに対して有意水準0.1%で統計的に有意な負の影響が見られ、YはTFPに対して有意水準0.1%で統計的に有意な負の効果が見られた。この結果より、貿易開放度の上昇には全要素生産性を上昇させる効果があり、その効果はOECD加盟国であればさらに大きいことが示唆された。また、高齢化率の上昇には全要素生産性を低減させる効果が、実質GDPの増加には、全要素生産性を増加させる効果があることが示唆された。なお、固定効果として変数OECDを説明変数に加えたモデルについても検討を行ったが、OECDは多重共線性の影響により推計からは排除されるという結果であった。
<推計結果>
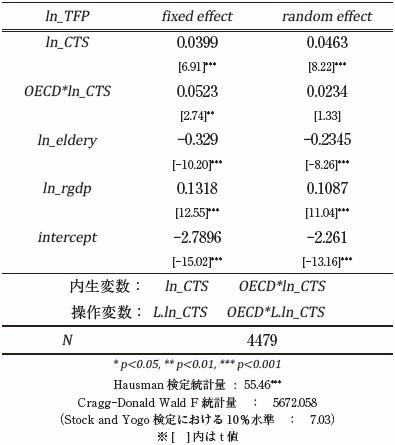
291 日本経済研究センター(2019)「貿易取引の停滞、世界的な生産性低下の恐れ -自由貿易の枠組み広げる取り組み重要に-」
292 内閣府(2011)「平成23 年度年次経済財政報告」
付注3 ガバナンス指標と不確実性による貿易損失
概要
本分析では、二国間の貿易量はいわゆる貿易の重力モデル293に基づいて決定されるものと仮定し、その上で、ガバナンス指標の悪化による不確実性の上昇が貿易に対して与えるマイナスの影響について分析を行う。
推計モデル・データ
t期における輸出国をi、輸入国をjをとし、量的変数については自然対数lnを取ると、t期のi国からj国への輸出額Exportは、i国、j国の名目GDPをGDP、貿易不確実性指数をTUI、2国i j間で経済連携協定を締結していれば1となるダミー変数をRTA、輸出国iごとのダミー変数をExporter、輸入国jごとのダミー変数をImporter、貿易ペアi jごとのダミー変数をtradepairとすると、貿易の重力モデルをもとに誤差項εを用いて以下のとおり表すことができる。
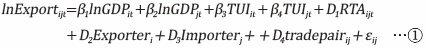
データとしては、貿易不確実性指数にはIMFに在籍するエコノミスト等の作成しているTrade Uncertainty Indexを用いた。また、その他のデータについては、フランスの研究機関であるCentre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales(CEPII294)の作成したグラビティデータセットより、2000年から2019年の期間のデータを取得した。具体的には、Exportにはtradeflow_imf_o(輸出国により報告された、ある国への輸出額(千米ドル、出典:IMF)、GDPにはgdp(名目GDP(千米ドル))、RTAにはrta(貿易ペア間で経済連携協定を締結していれば1となるダミー変数、出典:WTO)を用いた。
説明変数として用いている貿易不確実性指数とは、データセットの掲載されているウェブサイト295によると、各国の報告書において貿易に関連する文脈で“uncertainty”という言葉が使用された回数を基に作成される指数である。報告書の文脈は各国の貿易額やGDPの変動等の影響を受けると考えられることから、貿易不確実性指数の内生性が疑われるため、貿易不確実性指数の操作変数として、世界銀行の作成しているWorldwide Governance Indicatorsから作成した変数(WGI)を用いる。Worldwide Governance Indicators296とは、政治への参加と説明責任、規制の質、政治的安定・非暴力、法の支配、政府の有効性、腐敗の抑制の六つの指標から構成された、各国政府のガバナンスの質を総合的に評価した指標である。上記の六つの指標について主成分分析を行い、その第一主成分のスコアをWorldwide Governance Indicatorsの変数(WGI)として推計に使用する。このスコアにおける六つの指標の固有値ベクトルは全て負の値を取っており、六つの指標同士には正の相関関係があることが分かる。なお、第一主成分のスコア(変数WGI)は、値が小さいほど総合的なガバナンスの質が高いことを示すものとなっている。
<主成分分析の結果>
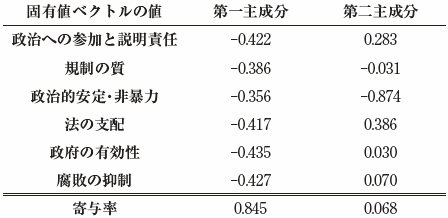
これらの変数より、下記②式及び③式を第一段階推計式、上記①式を第二段階推計式として二段階最小二乗法を用いて推計を行う。なお、推計にあたっては、貿易額、および名目GDPの外れ値による推計バイアスの除去のため、外れ値の割合を5.0%とした局所外れ値因子法を用い、外れ値の除去を行った。
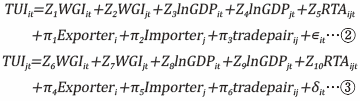
推計結果
本分析による推計結果を以下のとおり示す。(ただし、輸出国ダミー、輸入国ダミー、貿易ペアダミーの結果については省略する。)データは期間が2000年から2019年、個体数(貿易ペアの数)が17,052のアンバランスなパネルデータである。推計結果の変数のパラメータについてみると、まず、操作変数である輸出国、輸入国のWGIには、輸出国、輸入国の貿易不確実性指数それぞれに対して有意水準0.1%で統計的に有意な正の影響がみられた。かつ、第一段階推定式におけるF統計量がStock and Yogo検定における10%境界値より大きく、操作変数の弱相関の可能性は小さいことが示唆された。また、輸出国、輸入国の貿易不確実性指数には、輸出国から輸入国への輸出額それぞれに対して有意水準1%以下で統計的に有意な負の影響がみられた。これらの結果より、各国の総合的なガバナンスの質が低いほど貿易不確実性は高まること及び、貿易不確実性の上昇は、輸出額の減少をもたらすことが示唆された。
<推計結果>
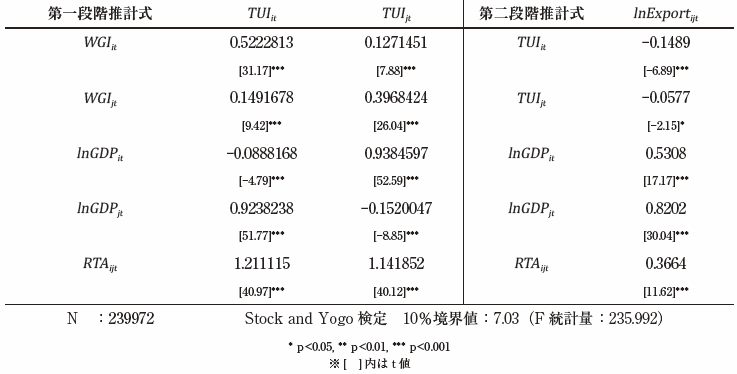
政治の質による貿易損失額の試算
得られた推計結果より、ガバナンス指標の悪化による貿易不確実性の上昇がもたらす貿易損失額について試算を行う。まず、①式について、j国を輸出相手国とした時、輸出額のうち、j国の貿易不確実性指数の影響により説明される部分のみを抽出する。

ここで、①’式に、②式、③式を代入して整理し、輸出額のうちj国のWGIにより説明される部分のみを抽出することで、各国がj国を輸出相手国とした場合の、j国のガバナンス指標の悪化による不確実性の上昇がもたらす輸出損失額explossが試算される。このexplossの平均を取ることで、ある国のj国への輸出におけるj国のガバナンス指標を要因とする輸出損失額の期待値を算出する。
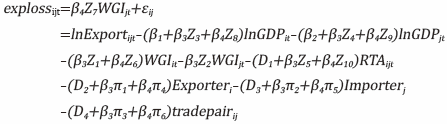
同様に、j国からの輸入におけるj国のガバナンス指標の悪化を要因とする輸入損失額の期待値を算出し、輸出損失額の期待値との和を取ることで、j国との貿易におけるj国のガバナンス指標の悪化を要因とする貿易損失額の期待値を算出することができる。
293 重力モデルの詳細についてはhttps://www.rieti.go.jp/users/tanaka-ayumu/serial/013.html![]() 等を参照。
等を参照。
付注4 円安による輸出促進効果の分析
概要
本分析では、円安による輸出促進効果について輸出品目ごとのデータを用いて分析を行う。具体的には、為替レートの変化が各輸出品目の輸出単価の変化に影響を与え、輸出単価の変化が輸出数量の変化に影響を与えるというパスを仮定し、二段階最小二乗法により推計を行う。つまり、被説明変数に輸出数量の変化率、説明変数に輸出単価の変化率を用い、輸出単価の変化率は為替レートの変化率により決定される内生変数であると想定して分析を行うということである。
推計モデル・データ
推計にあたっては、Global Trade Atlasより、1994年から2022年の期間の日本からの輸出について、HSコード6桁品目ごと、輸出相手国ごと、年ごとの、輸出数量(第二数量)297及び、輸出金額(ドル換算)のデータを取得した。取得したデータより、輸出金額を輸出数量で除することにより輸出単価を算出し、輸出数量、輸出単価についてそれぞれ対数差分を取った(以下、dln_exv、dln_expとする)。なお、輸出品目の取得に使用したHSコードは5年に1回程度(1996年、2002年、2007年、2012年、2017年、2022年)の頻度で改訂が行われており、改訂の際には一つの品目の複数の品目への再分類や複数品目の一つの品目への統合が行われている。そのためHSコードの変換を行ったとしても、本モデルの推計の際に利用可能であった情報のみでは再分類や統合のあった品目を完全な形で接続することは不可能であった。そのため、各HSコードの適用期間ごとのダミー変数(以下、HS96、HS02、HS07、HS12、HS17、HS22とする。)を用いることにより、HSコードの再分類や統合が推計結果に与えるバイアスの制御を試みる。
為替レートについては日本銀行統計より、インターバンク市場の東京市場中心相場のドル円スポット価格月中平均の値を年次変換したデータを取得し、対数差分を取った(以下、dln_usd_yenとする。)。貿易の分析においては、一般的に実行為替レートを用いることが多いが、本モデルでは輸出単価が一律でドル換算されていることから、ドル円の為替レートを用いている。また、輸出数量は輸出相手国の需要の変動の影響を受けると想定し、コントロール変数として輸出相手国の実質GDPを用いる。実質GDPのデータはIMFから取得し、対数差分を取った(以下、dln_rgdp)。
以上のような処理により、1994年~2022年の期間の、個体(HSコード6桁品目×輸出相手国)数が162,443のアンバランスなパネルデータが作成された。作成したデータセットを用いて、下記のモデルにより個体ごとの固有の効果vを考慮したうえで推計を行った。
<第1段階推計式>
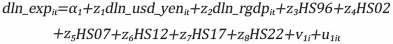
<第2段階推計式>
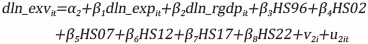
(上式において、iは年、tは個体(品目×輸出相手国)、vは個体固有の効果、uは誤差項を表す。)
推計結果
上記モデルの推計結果を下記のとおり示す。推計結果のパラメータを見ると、ドル円レートの上昇(円安方向への変化)には輸出単価に対して有意水準0.1%で統計的に有意な負の効果が、また、輸出単価の増加には輸出数量に対して有意水準0.1%で統計的に有意な負の効果が見られた。この結果より、為替レートの下落には輸出価格を減少させ、それを通じて輸出数量を増加させる効果があることが示唆された。一方で、パラメータより、平均的には1%の為替レートの上昇は輸出価格を0.84%下落させ、輸出数量を0.41%増加させる効果があることが示唆されるが、 平均的には輸出数量の増加分が輸出価格の下落分を下回っている点には留意する必要がある。
<推計結果>
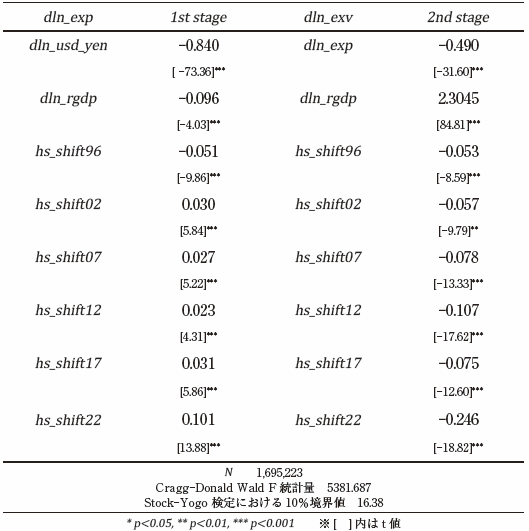
297 輸出数量については計上する単位がキログラム、トン、メートル等多岐にわたるため、輸出単価を適切に評価できていない品目が存在する可能性がある。
付注5 海外展開が企業に与える影響の再検証
概要
本分析では、企業の輸出の開始及び海外直接投資による海外現地法人の所有(以下、海外直接投資とする。)の開始による雇用者数、売上高、全要素生産性、資本ストック額、一人当たり雇用者報酬の変化について分析を行う。具体的には、傾向スコアマッチングを用いて、ある年度に輸出・海外直接投資を開始した企業と、その企業と輸出・海外直接投資を開始する確率が近しいが実際には輸出・海外直接投資を開始しなかった企業のマッチングを行い、マッチングしたサンプルを用いて上記5変数の変化について、差の差分析を実施した。なお、分析手法の検討にあたっては内閣府「令和元年度経済財政報告」を参照している。
推計データ・モデル
推計にあたっては、経済産業省「企業活動基本調査」及び「海外事業活動基本調査」を用いた。まずは、平成9年度から2021年度までの統計から、全要素生産性(以下、tfpとする。)、雇用者数(以下、empとする。)、資本ストック額(有形固定資産額)(以下、capとする。)、売上高(以下、earnとする。)、付加価値額、国内子会社の数(以下、affとする。)、総雇用者報酬のデータを取得した。全要素生産性については、付加価値額、雇用者数、資本ストック額及び、中間投入財として売上高から付加価値額を引いた値を用いて、Levinsohn and Petrin法により算出した。資本ストック額については、内閣府のGDPの年度デフレータの民間企業設備の値で除することにより実質値とした。加えて、雇用者数が、50人以上99人以下の場合、100人以上299人以下の場合、300人以上の場合にそれぞれ1となるダミー変数(以下、scaleとする。)、年度ごと、産業ごとのダミー変数(以下、それぞれyear、indstとする。)を作成した。
次に、ある企業が輸出を開始した年度については、内閣府の分析における手法を参照し、ある年度tに企業が輸出を開始(企業の「直接輸出額」の値がある年度の前年度t-1までゼロで、ある年度tから「直接輸出額」の値がゼロより大きい値を取っている場合を指す。)した後、3年間継続して輸出を行っていた(3年間継続して「直接輸出額」の値がゼロより大きい値を取っていた)場合、その企業はある年度tに輸出を開始したとみなすこととした。そして、ある企業が輸出を開始した年度であれば1となるダミー変数(以下、exportとする。)を作成した。なお、各企業の輸出の統計が存在するのは平成10年度の調査からであるため、輸出開始効果の分析においては平成10年度から2021年度のデータを使用する。
また、ある企業が海外直接投資を開始した年度には、海外事業活動基本調査における各海外現地法人の「設立・資本参加年」のデータを用いる。海外現地法人の「設立・資本参加年」のうち、本社企業ごとに最も古い年を抽出し、その年をある企業が海外直接投資を開始した年とした。このデータセットについて、永久企業番号を用いて企業活動基本調査との接続を行い、ある企業が海外直接投資を開始した年を1とするダミー変数(以下、abroadとする。)を作成した。
以上の手順により作成したデータセットについて、以下のロジットモデルを用いてある企業iがある年度tに輸出をする確率(傾向スコア)p1it及び、ある企業iがある年度tに初めて海外直接投資をする確率p2itの推計を行う。推計にあたっては、企業は前年度の企業の状態を基に、輸出・海外直接投資開始の意思決定を行うと考え、ロジットモデルの説明変数は1期のラグを取った。ここで、企業によっては上記の変数exportが1となる年度が複数あるケースがある。これは、企業の輸出が断続的なものであったことや欠損値があることなど様々な要因が考えられるが、データ上で要因を区別することは困難であるため、本分析では輸出を開始した企業について、初めてexportが1となる年度のみを使用し、それより後の年度のデータはサンプルから除外している。また、海外直接投資を開始した企業については、海外直接投資を開始した年度以外の年度のデータはサンプルから除外している。
<輸出開始確率を求めるロジットモデル>
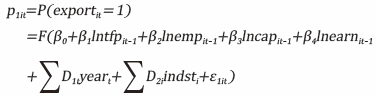
<海外直接投資開始確率を求めるロジットモデル>
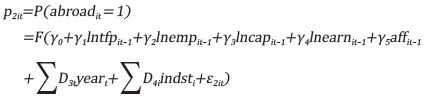
※上式におけるlnは自然対数、εは誤差項を意味する。
上記ロジットモデルより得られた傾向スコアを元に、輸出を開始した企業については、同一年度、同一産業、同一規模内で最も傾向スコアが近いものの、実際にはその年度内に輸出をしなかった企業を抽出して、1:1のマッチングを行い、海外直接投資を開始した企業については、同一年度、同一産業内で最も傾向スコアが近いものの、実際にはその年度内に海外直接投資をしなかった企業を抽出して、1:1のマッチングを行った。そして、マッチング後のサンプルについて、それぞれ以下のような差の差分析を行った。この差の差分析では、輸出開始から1~5年後、海外直接投資開始から1~10年後の雇用者数、売上高、全要素生産性、資本ストック額、一人当たり雇用者報酬(総雇用者報酬を雇用者数で除したもの。以下、wageempとする。)それぞれについて、輸出・海外直接投資開始の1期前からの対数差分と、輸出・海外直接投資を開始しなかった企業の同期間の対数差分との間の差について分析を行っている。また、輸出を開始した企業については雇用者数の規模scaleごとに差の差分析を行い、海外直接投資を開始した企業については製造業、非製造業それぞれについて、差の差分析を行った。
<輸出開始企業の差の差分析の推計式>
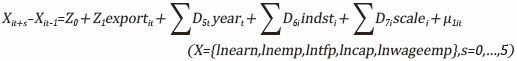
<海外直接投資開始企業の差の差分析の推計式>
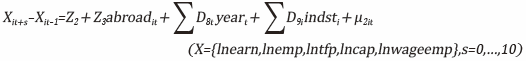
※上式におけるlnは自然対数、μは誤差項を意味する。
推計結果
本分析におけるロジットモデル及び差の差分析の結果について以下のとおり示す。
まず、ロジットモデルについてみると、前年度の従業者数、売上高、全要素生産性、資本ストック額、子会社数は、ある企業がある年度に海外直接投資を開始する確率を有意水準5%以下で統計的に有意に上昇させるという結果がみられた。また、前年度の従業者数、売上高、全要素生産性は、ある企業がある年度に輸出を開始する確率を有意水準0.1%で統計的に有意に上昇させるという結果がみられた。
次に、差の差分析についてみると、輸出開始企業では、50人以上99人以下の企業では、売上高及び全要素生産性の輸出開始前からの増加率は、輸出開始年~5年後の期間において、一人当たり雇用者報酬の輸出開始前からの増加率は、輸出開始年~3年後の期間において、輸出を開始しなかった企業の同期間の増加率と比較して統計的に有意に大きいという結果が得られた。100人以上299人以下の企業では、全要素生産性の輸出開始前からの増加率は、輸出開始年~5年後の期間において、売上高の輸出開始前からの増加率は、輸出開始年~4年後の期間において、一人当たり雇用者報酬の輸出開始前からの増加率は、輸出開始年~3年後の期間において、雇用の輸出開始前からの増加率は、輸出開始年~2年後の期間において、資本ストック額の輸出開始前からの増加率は、輸出開始年において、輸出を開始しなかった企業の同期間の増加率と比較して統計的に有意に大きいという結果が得られた。300人以上の企業では、売上高、雇用者数、全要素生産性の輸出開始前からの増加率は、輸出開始年~5年後の期間において、資本ストック額の輸出開始前からの増加率は、輸出開始年~4年後の期間において、輸出を開始しなかった企業の同期間の増加率と比較して統計的に有意に大きいという結果が得られた。
海外直接投資開始企業については、製造業の企業では、売上高の海外直接投資開始前からの増加率は、海外直接投資開始年~8 年後、10年後の期間において、雇用者数の海外直接投資開始前からの増加率は海外直接投資開始年~9年後の期間において、資本ストック額の海外直接投資開始前からの増加率は海外直接投資開始年~6 年後の期間において、海外直接投資を開始しなかった企業の同期間の増加率と比較して統計的に有意に大きいという結果であった。また、非製造業の企業では、売上高の海外直接投資開始前からの増加率は、海外直接投資開始年~4年後、7年後の期間において、雇用者数の海外直接投資開始前からの増加率は海外直接投資開始年~8年後の期間において、資本ストック額及び一人当たり雇用者報酬の海外直接投資開始前からの増加率は海外直接投資開始の1 年後~2 年後の期間において、海外直接投資を開始しなかった企業の同期間の増加率と比較して統計的に有意に大きいという結果であった。
<ロジットモデルの推計結果>
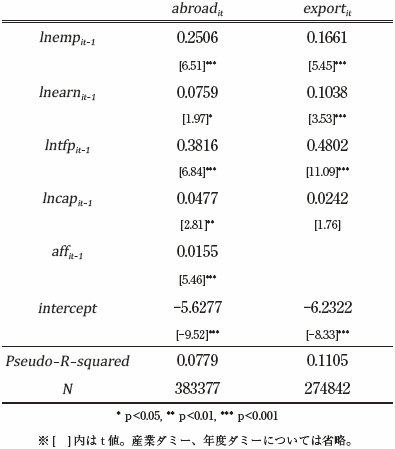
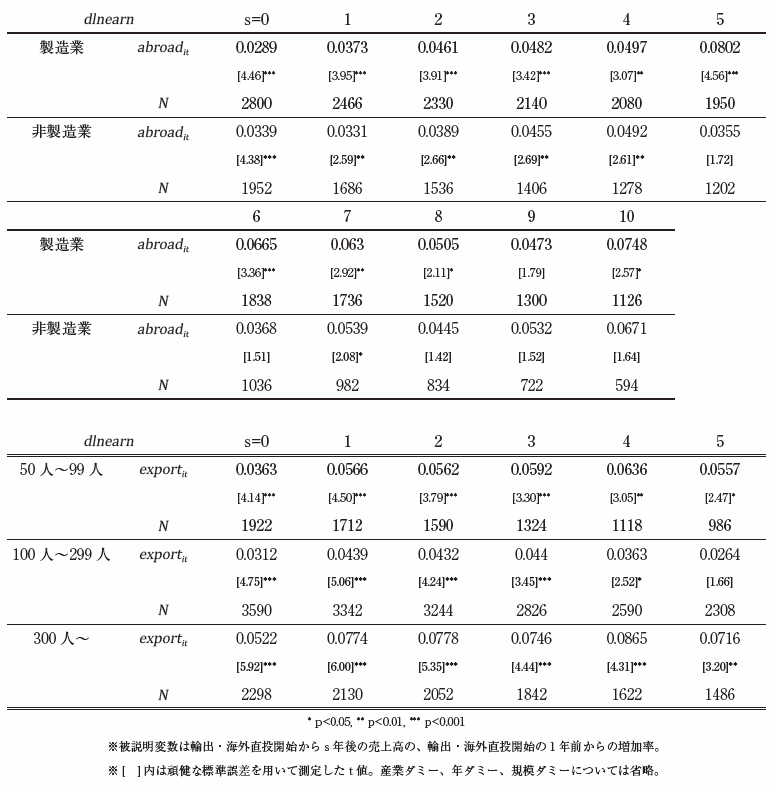
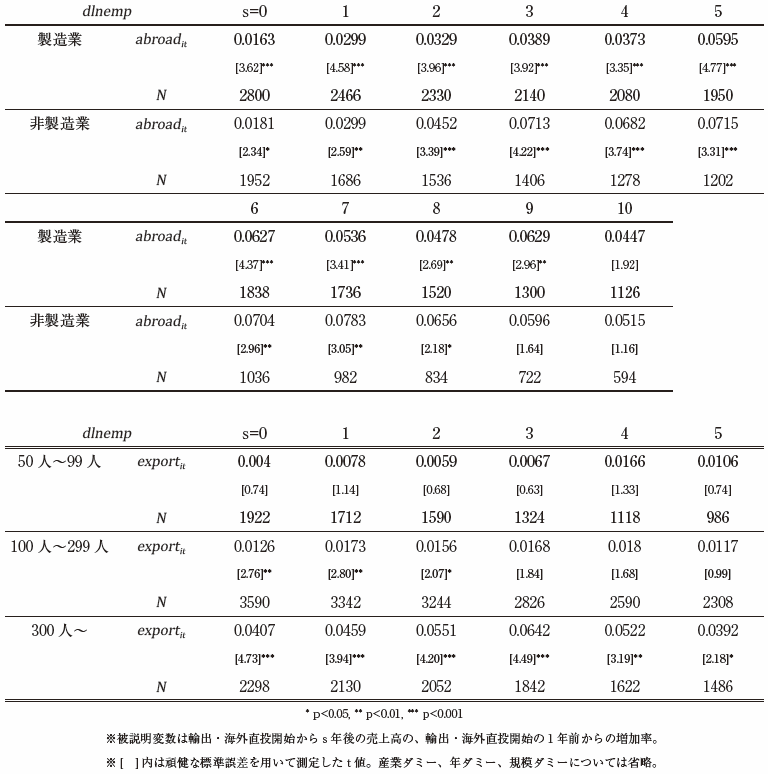
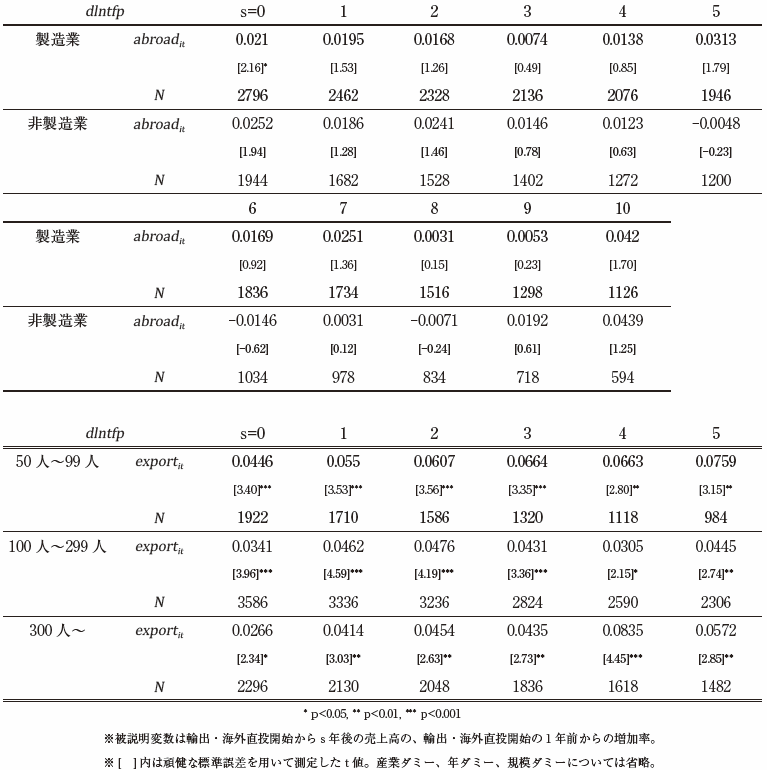
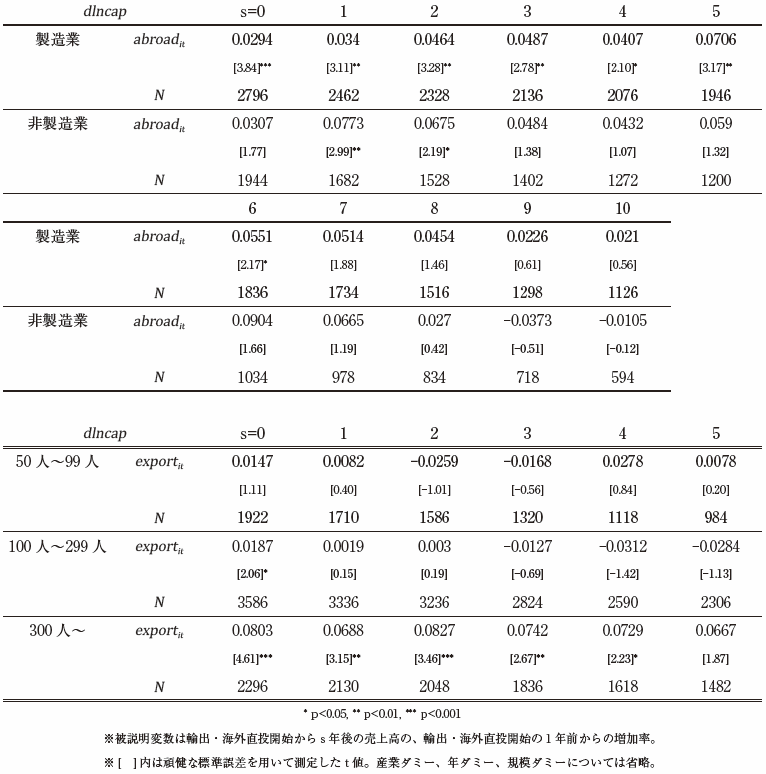
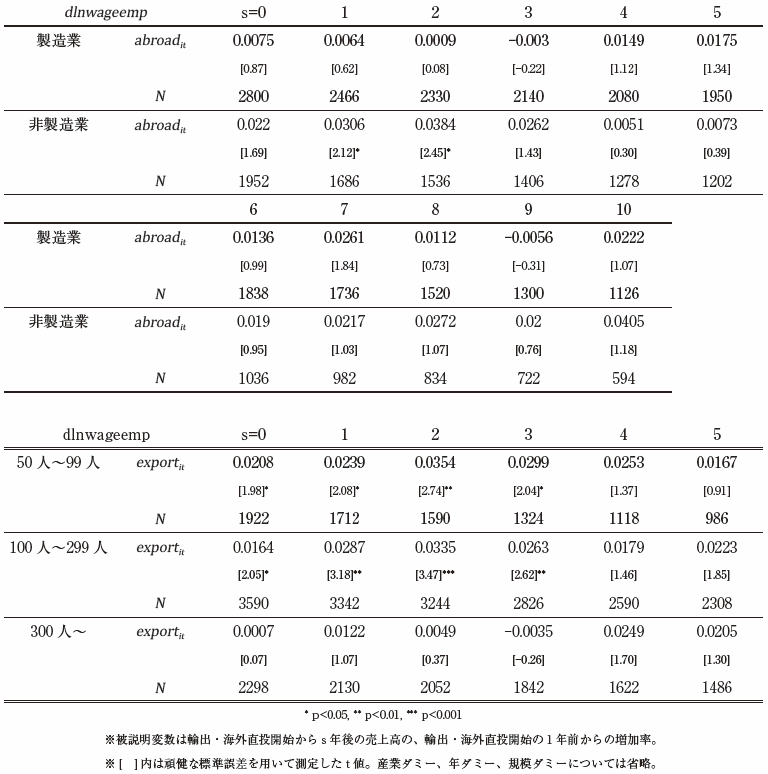
付注6 海外展開による地域経済への影響
概要
本分析では、グローバル企業の海外生産比率の上昇がその企業の事業所の周辺地域の輸出に与える影響について分析を行う。具体的には、グローバル企業が財を生産する場合、その事業所(以下、中心事業所とする。)の周辺に位置する事業所(以下、周辺地場企業とする。)から材料等を調達して製品を製造し、出荷及び輸出を行っていると考えられることから、グローバル企業の海外生産比率が上昇したとき、その企業の事業所の周辺に位置する事業所も波及的に影響を受けるという考えに基づき、Kiyota, Nakajima, Takizawa(2022)の手法も参照して分析を行う。
推計モデル・データ
まず、分析に先立ち、言葉の定義を行う。企業の海外展開の度合いの指標としては海外生産比率を用いる。なお、海外生産比率は海外進出企業ベースの海外生産比率298(現地法人売上高/(現地法人売上高+本社企業売上高))を用いるが、海外現地法人の売上高には業種が製造業に該当する海外現地法人の値のみを集計する。中心事業所とは、海外生産比率が0%よりも大きく、かつ資本金10億円以上の企業の事業所とする。周辺地場企業とは、資本金10億円未満の企業の事業所とする。なお、中心事業所、周辺地場企業としては、日本標準産業分類中分類における化学工業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業に該当する企業についてのみを分析対象とする。周辺地域とは、中心事業所を中心とした半径5km圏内の円の内側の領域を指す。
次に、統計データの再編加工を行う。本分析では経済産業省の「企業活動基本調査」、「海外事業活動基本調査」、「工業統計調査」を用い、下記の様な手順でデータの再編加工を行った。なお、分析にあたっては経済産業省にて作成している平成24年から2020年までの工業統計及び平成28年経済センサスのうち製造業に該当する事業所の緯度経度情報を用いて各事業所の周辺地場企業に該当する企業の特定を行っている。具体的な再編加工の手順としては、まず、企業活動基本調査と海外事業活動基本調査について永久企業番号を用いて統合を行い、海外生産比率を算出する(①)。次に、①を工業統計と統合し、①で抽出した本社企業の事業所を特定する(②)。統合の際には令和元年度調査以降については法人番号を用い、それ以前のものについては企業名から株式会社、有限会社等の形態情報を削除したものを用いた299。次に、②について、現地法人売上高が0より大きく、かつ資本金が10億円以上の企業を本社に持つ事業所のデータセット(②-1)と、資本金10億円未満の企業を本社に持つ事業所のデータセット(②-2)に分割し、②-1に属する企業と②-2に属する企業の全ての組み合わせ間の距離を算出したあと、②-1と②-2を再結合する。そして、再結合したデータセットにおける、②-1に属する企業それぞれについて、②-2に属する企業のうち、②-1に属する企業との距離が5km以下の企業のみを抽出し、抽出されたデータについて、②-1に属する企業ごとに、②-2に属する企業の、出荷額と輸出額の合計を集計した。以上のような集計により、2012年から2019年の期間における、中心事業所の本社の海外生産比率(以下、share とする。)、周辺地域の総出荷額(以下、shipとする。)、総輸出額(以下、expとする。)、からなるデータセットが作成される。また、これらの変数に加え、日本銀行統計より、大企業製造業の海外での製商品需給のDIの実績値を取得し、外需DI(以下、diとする)の変数とした。
上記のとおり作成した変数を用いて、周辺地域iの、t期における輸出額は、各地域の固有の効果をvi、その他の誤差項をεitとすると、下記式のとおり表すことができる。なお、推計にあたっては、固定効果モデルを用いた。推計に使用したデータは、個体(周辺地域)数が2,132、期間が8年のアンバランスなパネルデータである。
<推計式>

推計結果
本モデルの推計結果を下記のとおり示す。
推計結果のパラメータについて、変数ごとに見ると、本社の海外生産比率には、周辺地域の総輸出額に対して有意水準0.1%で統計的に有意な正の影響が見られた。外需DIには周辺地域の輸出額に対して有意水準0.1%で統計的に有意な正の影響が見られた。また、周辺地域の総出荷額には、周辺地域の輸出に対して有意水準0.1%で統計的に有意な正の影響が見られた。この結果より、中心事業所の本社の海外生産比率の上昇により周辺地域の輸出額が増加すること及び、海外での需要の増加により周辺地域の輸出が増加することが示唆された。
<推計結果>
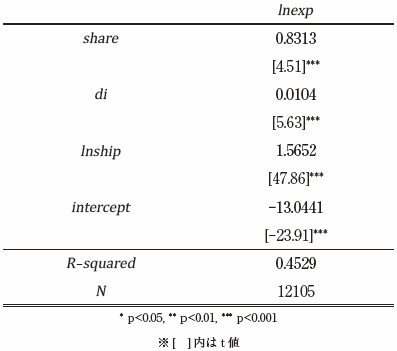
留意点
本分析の結果を解釈する際には、以下の点に留意しなければならない。まず、本分析では、中心事業所同士の距離が近いことから複数の中心事業所の間で周辺地域の領域に重複が見られるケースについて、中心事業所がその周辺地域に与える影響同士はそれぞれ独立であると仮定している。しかし、現実では、複数の中心事業所の周辺地域に含まれる領域では、ある中心事業所から強い影響を受けたことにより、他の中心事業所から受ける影響が弱まるケースなど、このような仮定が担保されないケースも考えられる。そのため、本分析の推計結果には一部バイアスが生じている可能性がある。また、本分析ではある一つの中心事業所がその周辺地域全体に与える影響のみを推計しており、周辺地場企業個社が受ける個別の影響については考慮していない。そのため、ある周辺地場企業個社が受ける個別の影響を観察することや、複数の中心事業所の周辺地域に与える影響を合算して解釈を行うことは、モデルの仮定上適さない。
298 海外進出企業ベースの海外生産比率についてはhttps://www.meti.go.jp/press/2021/07/20210730011/20210730011-1.pdf![]() 等を参照。
等を参照。
299 企業活動基本調査と工業統計の間の完全な接続は困難であり、企業名の情報では接続に失敗した企業も存在する。今回は接続に失敗した企業はサンプルから脱落させているが、接続の精度の向上は分析における今後の課題である。
付注7 ベンチャー投資額と全要素生産性
概要
本分析では、ベンチャー投資額と全要素生産性の関係について分析を行う。
推計モデル・データ
推計にあたっては、Penn World Table 10.01より全要素生産性(以下、TFPとする。)、OECDstatより名目値の百万米ドルベースのベンチャー投資額(以下、su_invとする。)、国際連合の人口推計より高齢化率(以下、elderとする。)のデータを用いてデータセットを作成した。データは2006年から2019年の期間(t)における、32か国(i)のアンバランスなパネルデータである。なお、全要素生産性TFPについては、Penn World Table 10.01のrtfpna(全要素生産性の実質値(2017=1))とctfp(全要素生産性の相対水準(米国=1))の積を算出し、2017年の米国の全要素生産性が1となる変数を作成した。また、elderは国際連合の人口推計より各国の65歳以上の人口の比率を取得し、変数とした。TFP及びsu_invについては自然対数lnを取り、各国に固有の影響をv、その他の誤差項をεとすると、推計に使用したモデルは下記のとおり表すことができる。
<推計モデル>

推計結果
上記モデルの推計結果を下記のとおり示す。推計にあたっては固定効果モデル及び変量効果モデルの両方を用いて推計を行っている。推計結果の係数を見ると、ベンチャー投資額が全要素生産性に対して与える影響は有意水準0.1%で統計的に有意に正であった。この結果は、ベンチャー投資の増加には全要素生産性を上昇させる効果があることを示唆するものである。なお、ハウスマン検定を実施したところ、変量効果モデルが採択されているが、推計モデルの説明変数であるベンチャー投資額は、各国の政策や文化、経済状況など各国固有の影響にも依存して決定される(説明変数と各国固有の影響の間に相関がある)と考えるのが妥当であることから、本白書においては固定効果モデルを採択することとする。
<推計結果>
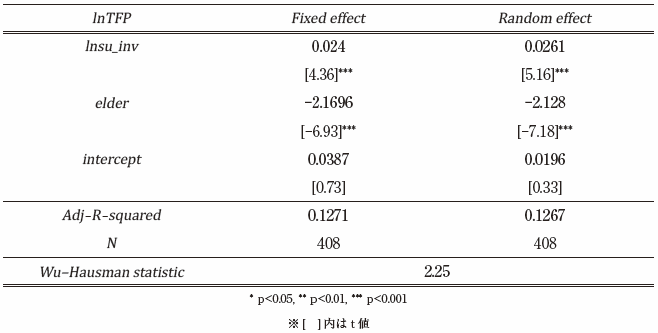
付注8 対内直接投資のトレンド変化
概要
本分析では、2014年に対日直接投資促進施策が実行段階に移ったことによる対内直接投資額のトレンドの変化について分析を行う。なお、分析手法はHoshi(2018)を参照している。
推計モデル・データ
推計にあたっては、日本銀行「国際収支関連統計」より対内直接投資額、内閣府「国民経済計算(GDP統計)」より名目GDPのデータを1996年から2022年の期間(t)について取得し、対内直接投資額対名目GDP比(以下、idi_gdpとする。)を算出した。また、1996~2022年の各年について、それぞれ1~26の値を取るトレンド項(以下、trendとする。)、2014年以降であれば1を取るダミー変数(以下、abeとする。)、トレンド項とダミー変数の交差項(以下、trend*abeとする。)を作成した。これらの変数より推計に使用したモデルは誤差項をμとすると下記のとおり表すことができる。
<推計モデル>
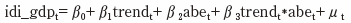
推計結果
上記モデルの最小二乗法による推計結果を下記のとおり示す。推計結果の係数を見ると、トレンド項及びトレンド項とダミー変数の交差項はいずれも、対内直接投資額対名目GDP比に対して有意水準0.1%以下で統計的に有意に正の影響が見られた。この結果は、対内直接投資額対名目GDP比には増加トレンドが見られること及び、2014年に対日直接投資促進施策が実行されたことによりその増加トレンドに拍車がかかったことを示唆するものである。
<推計結果>
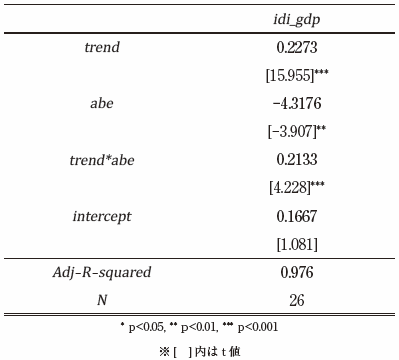
反実仮想の試算
推計式より、対内直接投資額対名目GDP比の推計値は下記のとおり算出されるが、2014年以降についても①式を用いて算出することで、仮に対日直接投資促進施策が実施されなかった場合の2014年以降の対内直接投資額対名目GDP比の値について試算することができる。
<対内直接投資額対名目GDP比の推計値>
