第1節 我が国グローバル企業の動向と我が国グローバル企業を取り巻くグローバル・バリューチェーンの動向
本章では、まず第1節で我が国グローバル企業の動向及び我が国グローバル企業を取り巻くグローバル・バリューチェーンの動向について見ていくとともに、第2節では我が国の経常収支や貿易収支の動向について見ていく。
1.我が国グローバル企業の動向
(1)日系製造業の海外展開
米中貿易摩擦や地政学的リスクを始めとして、我が国を取り巻くグローバル・バリューチェーンに関わるリスクへの関心が高まっている。その中で、我が国のグローバル企業はどのようなグローバル・バリューチェーンを構築しているのかを考える。まず、日系製造業の海外展開を概観し、次に日本国内に立地する企業の海外からの調達を見ていく。
令和5年版通商白書でも記載したが、日系製造業の海外展開を対外直接投資統計で見ると、2008年に起きた世界金融危機や2020年に起きた新型コロナウイルス感染症拡大など一時的な減少はあるものの、金額ベースで投資残高は拡大してきている(第I-3-1-1図)。その中でアジアは、北米、欧州を上回る投資先となっており、2022年末時点で世界全体の約4割を占めるに至っている。
第Ⅰ-3-1-1図 日本の対外直接投資残高(製造業分野)の推移
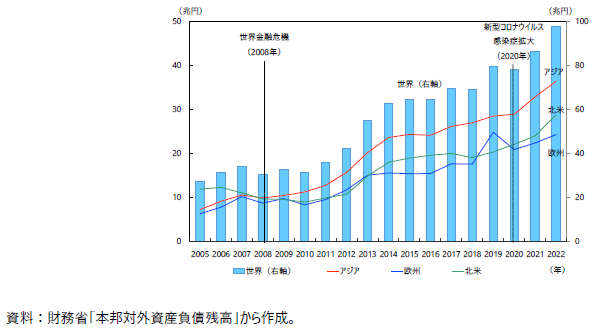
アジアの中での立地先としては、中国が最大でタイが続いている(第I-3-1-2図)15。中国への投資は金額ベースで拡大が続くが、総投資残高に占めるシェアは2012年をピークに縮小に転じた。代わって、タイ、インド、ベトナムなどが上昇しており、分散化が緩やかに進行している。また、ASEANを一つの地域と考えれば、中国を上回る投資規模を有しており、2010年代半ば以降、中国より速いテンポで残高が拡大している。なお、2020年以降は、新型コロナウイルス感染症拡大で世界経済が減速する中で、中国のシェアが拡大に転じたが、2022年は再び小幅ながら縮小した。
第Ⅰ-3-1-2図 日本のアジア主要国・地域向け直接投資残高(製造業部門)
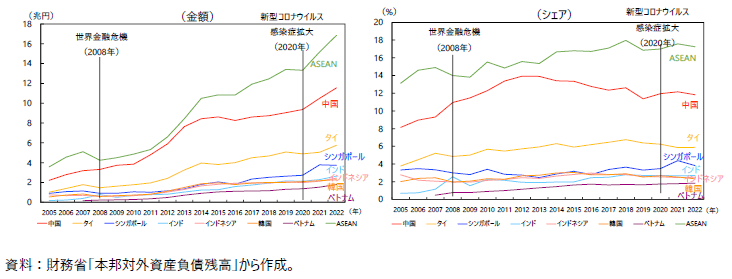
日系企業の立地について企業統計を使って確認する。経済産業省「海外事業活動基本調査」によれば、世界で日系製造業現地法人は約11,000社が操業しており、そのうち約8割に当たる約8,400社がアジアに立地している(第I-3-1-3表)。アジアのシェアが対外直接投資残高ベースでは約4割であったことを考えると、企業数ベースでは製造業のアジア展開はより顕著に現れている。日本からの距離の近接性により、相対的に小規模な企業も多くアジアに展開していることが考えられる。仮に一社当たりの平均売上高で事業規模を計算すると、アジアは米国の3分の1、欧州の2分の1となっている。アジアの中では、中国、ASEANへの立地が多く、ASEANの中ではタイが最多で、ベトナム、インドネシアが続いている。業種としては、化学、鉄鋼・金属などの素材関係、一般機械、電気・情報通信機械、輸送機械などの機械関係が多い。
第Ⅰ-3-1-3表 日系海外現地法人の企業数(2021年度)
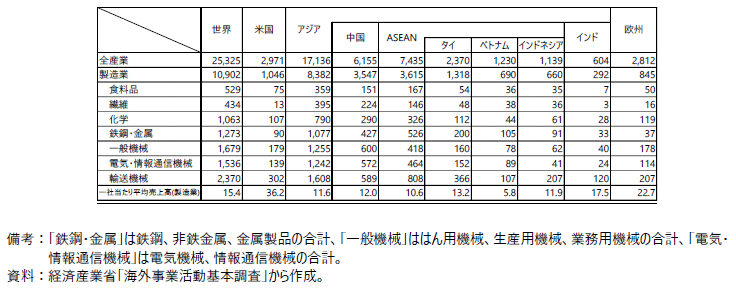
海外事業活動基本調査の売上高を利用して、地域別の海外現地法人の活動規模を見ると、2021年度、海外製造業現地法人の総売上額約139兆円のうち、中国、ASEAN、NIEs3で半分以上を占め、アジアは最も生産活動の活発な地域であることが分かる(第I-3-1-4図)。
第Ⅰ-3-1-4図 日系製造業の立地地域別売上げ(2021年度)
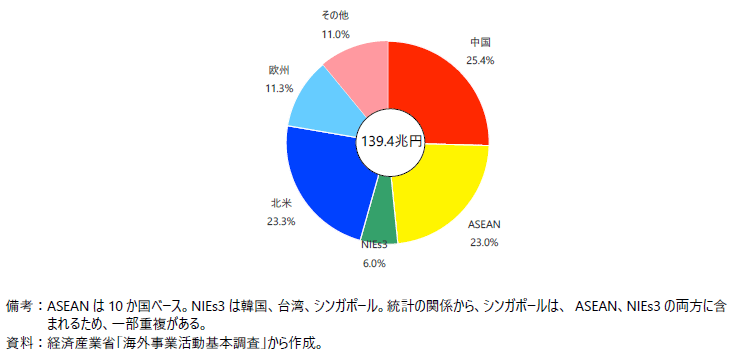
また、海外現地法人の立地の見直しという観点から、「海外事業活動基本調査」で、「新規設立」、「解散・撤退・出資比率低下」(以下「撤退等」と略す)の動向を見てみる。世界金融危機の後には、新規設立件数の低下、解散等の増加などの事業見直しの動きが観察される(第I-3-1-5図)。反対に2011年に起きた東日本大震災やタイ洪水の際は、新規設立件数が増加しており、災害を踏まえて被災した施設の再配置が行われたことが示唆される。最近では新型コロナウイルス感染症拡大後の2020年度、2021年度は、新規設立は低調で、撤退等は高水準が続いている。
第Ⅰ-3-1-5図 日系製造業現地法人の新規設立、撤退等の企業数
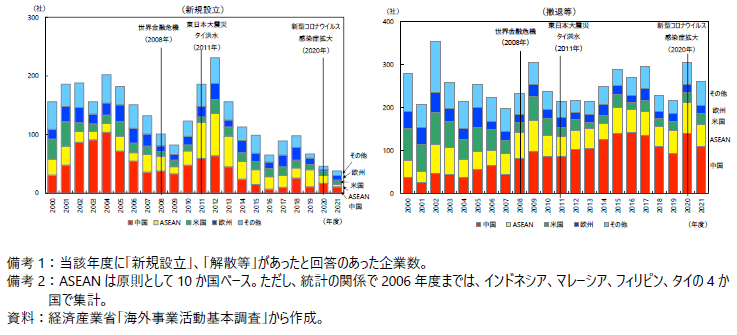
立地国・地域別の特色を見ると、各国・地域とも毎年一定数の新規設立、撤退等が見られるが、2000年代は中国への新規設立、2010年代以降は中国からの撤退等を選ぶ企業が増えている16。中国については、立地している企業総数も多く、多くの企業は操業を続けている点には注意が必要であるが、企業は事業環境やリスクに応じて、常に立地の見直しを進めていることがうかがえる。
さらに、既に海外に進出した日系企業の今後の事業展開の方向性をJETRO「2023年度海外進出日系企業実態調査(全世界編)」を基に見てみる。海外進出日系企業では、インドを始めグローバル・サウス諸国で事業拡大志向が旺盛であることが分かる(第I-3-1-6図)。
第Ⅰ-3-1-6図 海外進出日系企業の今後1~2年の事業展開の方向性(主要国・地域別)
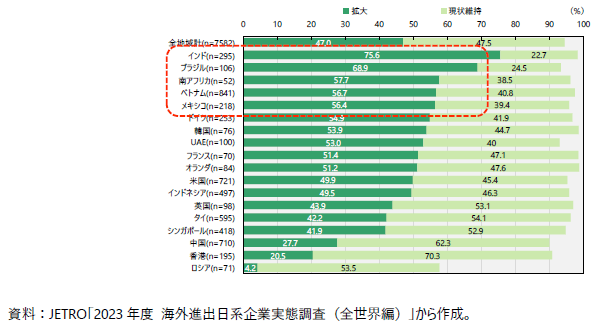
15 本節において、特に断らない限り、中国は本土のみで香港は含まない。ASEANは10か国ベース。
16 2000年代の中国への新設の増加は、2001年末にWTOに加盟したことへの期待が高まっていたことがうかがえる。2010年代の撤退等の増加は、2012年の尖閣諸島国有化による抗日運動の高まり、2015年の上海株式市場の急落、人民元切下げ等による中国経済への信認低下、2018年からの米中貿易摩擦、2020年の新型コロナウイルス感染症拡大の影響等が背景にあることが考えられる。
(2)我が国企業の海外調達
このような世界展開の下で、我が国国内に立地する企業がどこから部材を調達しているか考えてみる。日本国内の機械製造業の調達動向を「経済産業省企業活動基本調査」で見ると(第I-3-1-7図)、2008年に起きた世界金融危機から2010年代中頃にかけて、海外からの調達シェアが上昇しており、特に中国を含むアジアの上昇が著しい。2010年代後半はほぼ横ばいで推移し、2020年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、国内生産が滞り、調達額も減少した。この時、海外、特に中国からの部材の供給が寸断され、サプライチェーンに係るリスクへの懸念が高まるきっかけとなった。翌2021年度は国内生産の回復に伴い、調達額も回復に向かったが、海外からの調達が国内以上に回復し、海外比率が急上昇した。
第Ⅰ-3-1-7図 在日機械製造業の調達額と調達先別シェア
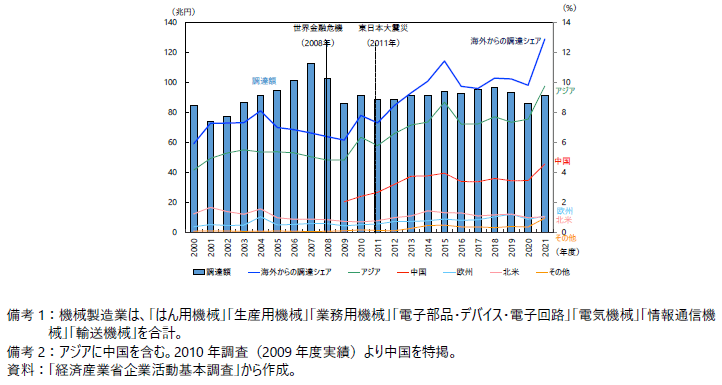
業種別に見ると、電子部品、情報通信機械等で海外からの調達シェアが高く、特に情報通信機械では中国からの調達急増を受けて、海外シェアが大きく上昇している(第I-3-1-8図)。一方で、輸送機械は海外からの調達シェアは必ずしも高くないが、代表的な製品である自動車は部品点数が多い、すりあわせ型の製品といわれ、少数の部品でも不足すれば生産に大きな影響が生じる可能性がある。新型コロナウイルス感染症拡大の際、海外からの部材供給途絶が国内生産に大きな影響を与えたことで、供給途絶のリスクが大きく認識される契機ともなった。
第Ⅰ-3-1-8図 在日機械製造業の調達額と調達先別シェア(業種別)
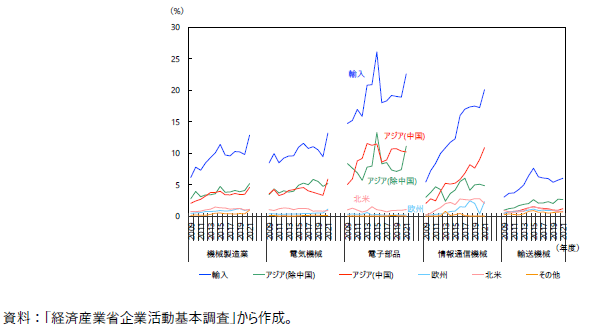
また、海外からの調達は、国内からの調達に比べて、資本関係のある関係会社からの調達シェアが高く、企業内取引の面が強い(第I-3-1-9図)17。地域別に海外調達を見ると、総じて中国を含むアジアからの調達において資本関係のある関係会社からの調達シェアが高い。既に見たようにアジアには多くの日系製造業現地法人が展開しており、アジアにおいて日系企業のサプライチェーンが発達していることがうかがえる。海外の関係会社からの調達は、生産コストの低い国で生産するという経済合理性とともに、本社のコントロールが効きやすく、品質の確証も得やすいことなども影響していると考えられる。近年は、北米、欧州からの調達においても関係会社のシェアが上昇する傾向にある18。
第Ⅰ-3-1-9図 在日機械製造業の調達における関係会社からの調達シェア
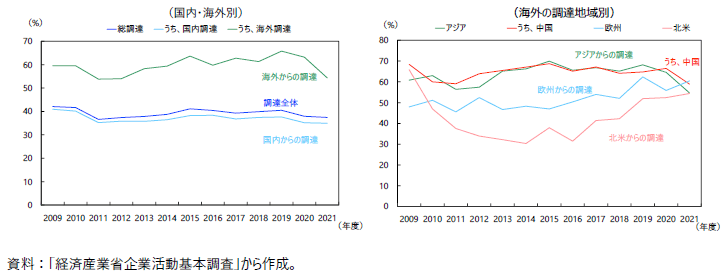
17 「経済産業省企業活動基本調査」において、「関係会社」とは、「親会社」、「子会社」及び「関連会社」をいう。「親会社」とは、企業の議決権の 50%を超えて所有している会社。「子会社」とは、ある会社(親会社)が 50%超の議決権を所有する会社。「関連会社」とは、ある会社(親会社)が 20%以上 50%以下の議決権を所有する会社。なお、この基準に達しなくても、経営を実質的に支配している場合を含む。
18 海外からの調達において、2020、2021年度は、関係会社のシェア低下の動きが見られるが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、緊急時の調達先が限定された影響などが考えられる。
2.我が国を取り巻くグローバル・バリューチェーン
(1)グローバル・バリューチェーンにおける前方参加と後方参加
前項では、我が国製造業に焦点を当て、海外展開や海外からの調達(グローバル・バリューチェーン)を見てきたが、本項では日本以外の諸外国を併せて見ていくことで、我が国を取り巻くグローバル・バリューチェーン全体の動向を考察する。分析に当たっては主としてOECDの付加価値貿易統計(OECD TiVA)を利用する。これはグローバル・バリューチェーンにおいては、中間財の形で海外において生産された付加価値が累積していくため、通常の貿易統計では各国・地域の役割の把握が困難なためである。既に令和5年版通商白書でも分析されているが、統計が2021年版から2023年版に改訂され、過去に遡及して修正されているため、2023年版でデータがとれる最新時点までの動向を概観する19。
グローバル・バリューチェーンへの参加には二通りのタイプがあり、単純な例を挙げれば、第I-3-1-10図のA国のように生産工程の上流に位置して、中間財を供給するケース(前方参加)とB国のように自国の生産のために中間財の供給を受けるケース(後方参加)がある。
第Ⅰ-3-1-10図 グローバル・バリューチェーンへの前方参加・後方参加
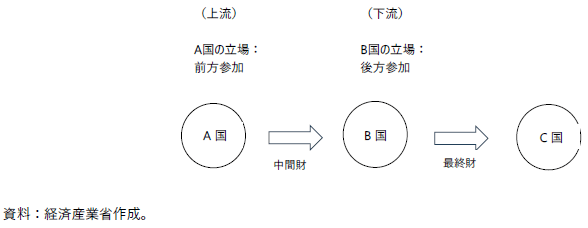
主要国の特徴を見ると、かつては日本や欧米先進諸国は基幹部品など中間財を供給する前方参加が大きく、中国、ベトナムなど新興国は中間財の供給を受けて、国内の豊富で安い労働力を生かして組み立てる後方参加の形でグローバル・バリューチェーンに参加することが多かった(第I-3-1-11図)。しかし、この関係は産業・貿易構造の変化によって変わってきている。例えば、日本は、前方参加が安定的に推移する一方で、安価で汎用的な中間財を輸入して活用することで後方参加も拡大してきている。反対に中国は、後方参加から、むしろ中間財を他国に供給する前方参加にシフトしてきている。それは貿易相手国側から見れば中間財の中国依存が強まっている可能性を意味し、新型コロナウイルス感染症拡大時に起きたようなグローバル・バリューチェーン途絶のリスクも高まっていることを示唆している。
第Ⅰ-3-1-11図 主要国のグローバル・バリューチェーンへの参加
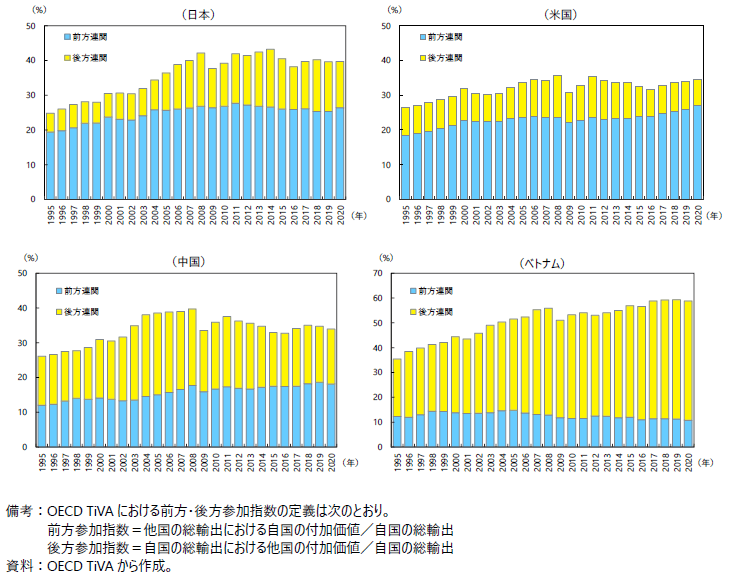
19 OECD TiVAは財・サービスを対象とした付加価値貿易統計。対象期間は2021年版が1995年~2018年、2023年版は1995年~2020年。2023年版では過去に遡及してデータが修正されている。
(2)主要国・地域と中国との関係
それでは、主要国・地域と中国とのグローバル・バリューチェーン上の位置関係を見てみる。令和5年版通商白書と同様に、横軸にOECDが定義するグローバル・バリューチェーンへの前方参加指数、縦軸に後方参加指数をプロットし、円の大きさは各国・地域の総輸出額を反映している。昨年の通商白書では2018年時点の位置関係をプロットしたが、OECD TiVAの最新時点である2020年時点で表示したのが第I-3-1-12図である。ある程度の変動はあるが、2018年とほぼ同様の傾向が見て取れる。例えば、台湾、韓国は前方参加を中心に中国と特に強い関係を有している。ASEANも、ベトナムのように、中国から中間財の供給を受けて加工・組立てを行う後方参加指数の高い国やインドネシアのように資源国であり前方参加に強い関係を持つ国など、国によってある程度の相違は見られるものの、いずれにしても中国と強い関係を有している。日本も前方・後方ともに強い関係を有している。なお、豪州、サウジアラビアなど資源国は強い前方参加の関係を持っている。米国や欧州諸国は、貿易額は大きいものの、ほかに関係の強い国(欧州諸国にとっては同じ欧州諸国、米国にとってはカナダ・メキシコ)があるために中国とのグローバル・バリューチェーン指数は必ずしも大きいわけではない。アジアの中で中国との関係が比較的薄いインドもこの位置にいる。
第Ⅰ-3-1-12図 主要国・地域の中国との前方連関・後方連関(2020年)
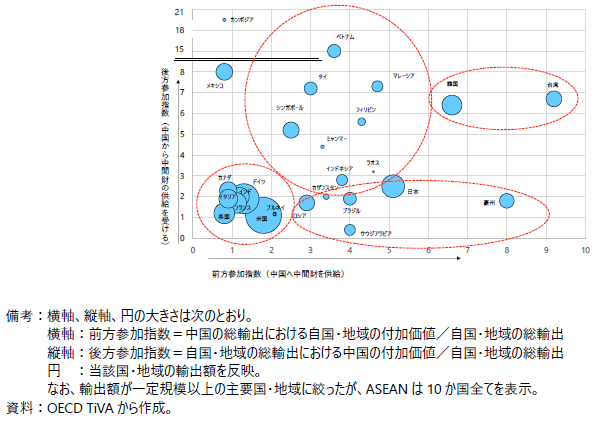
時系列での推移を見ると、総じて各国・地域とも中国との関係を深めており、特に中国がWTOに加盟した2000年から2005年までの間に大きく関係が強まった(第I-3-1-13図)。例えば、日本の場合、2000年から2005年にかけて前方参加を中心に関係を強め、日本から中間財を輸出し、中国で組み立てる形での国際的生産分業、グローバル・バリューチェーンが展開されたことが示唆される。ただし、その後は緩やかな関係強化にとどまっている。むしろ垂直方向の移動も多く、中国から中間財の供給を受ける後方連関を緩やかに強めていることが分かる20。韓国、台湾は、日本以上に大きく中国との結びつきを強めてきたが、2010年代後半以降は動きが緩やかになっている。
第Ⅰ-3-1-13図 主要国・地域の中国との前方・後方連関の変化
(1995年→2000年→2005年→2010年→2015年→2018年→2020年)
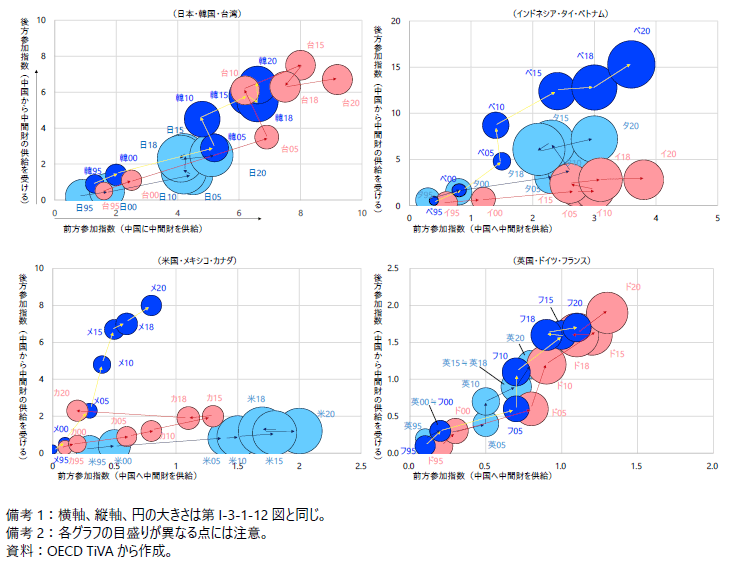
ASEANに目を向けると、ベトナムが大きく後方参加の形で中国との関係を強めているのが目立つ。グラフの縦軸目盛は横軸の5倍で表示しており、部材の供給を受ける後方連関の強さが際立っている。タイもベトナムほどではないが、後方参加を中心に中国との関係が強まっている。一方、インドネシアは、むしろ横軸方向に水平移動し、資源輸出による前方参加が強まっている。
米国との間では、米国から中間財を輸出して中国で生産する前方参加の形で関係が深まってきたが、米中貿易摩擦が始まった2018年に逆行する動きが見られた。ただし、2020年には再び関係が強まる方向で動いている。メキシコは後方参加の形で中国と関係を強めており、中国からの部材を利用して加工組立てを行って、近隣の米国等へ輸出する姿が想定される。欧州の英国、ドイツ、フランスは、前方・後方ともバランスのとれた形でゆっくりと関係が強まっているが、距離が離れていることもあり、必ずしも強い関係にあるわけではない。
業種別に中国との関係を見たのが第I-3-1-14図である。各国・地域が電気・電子機器、自動車の輸出を行うに当たって、中国の付加価値がどの程度含まれているか(縦軸)、反対に中国の輸出に各国・地域の付加価値がどの程度含まれているか(横軸)を示している。例えば、日本、韓国、台湾の電気・電子機器輸出の5~10%程度が中国で生産された付加価値となっている(縦軸)が、中国の電気・電子機器の輸出額の中で日本、韓国、台湾で生産された付加価値はそれぞれ3%程度である(横軸)。ASEANのベトナム、タイ、マレーシアの電気・電子機器輸出における中国の付加価値シェアは約15%あるが(縦軸)、反対に中国の電気・電子機器輸出におけるこれらの国の付加価値は1%にも満たない(横軸)。OECD TiVAからは具体的品目は分からないものの、化学、金属、電子部品などが考えられ、中国に中間財を大きく頼っていることが示唆される。
第Ⅰ-3-1-14図 主要国・地域の中国との連関(電気・電子機器、自動車/2020年)
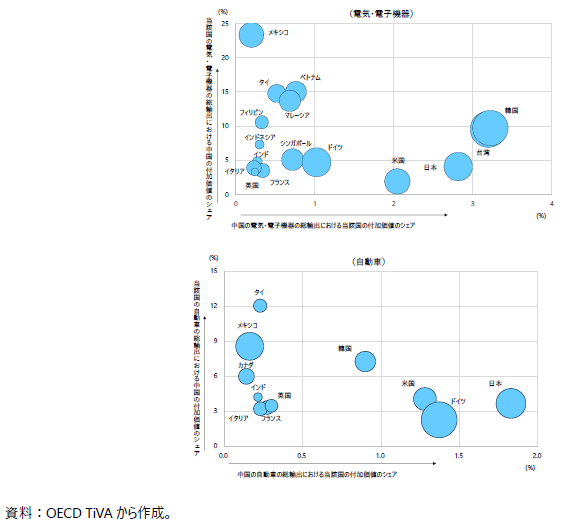
同様に中国の自動車輸出に対して、日本、ドイツ、米国などが中間財を供給しているが、その程度は限定的である(横軸)。一方、ASEANのタイが中国の中間財供給を受けるとともに、メキシコ、カナダも中国から中間財の供給を受けて国内で組み立てる後方連関の関係が強い。
20 OECD TiVAでは、付加価値を生産国ベースで集計しており、外資系企業の生産した付加価値も立地国の付加価値と見なしている。このため、日本の中国との後方連関の高まりも、中国に進出した日系サプライヤーから部材の逆輸入が行われるようになった影響も含まれる。
(3)貿易摩擦と迂回輸出
最近の国際貿易上の大きな出来事として米中貿易摩擦が挙げられる。米国の中国に対する追加関税は米国の輸入に影響を与えたが、その意味を付加価値貿易という観点から考えてみる。通常の貿易統計で見て、中国の米国の輸入に占めるシェアは追加関税の適用が開始された翌年の2019年に確かに低下している(第I-3-1-15図)21。しかし、付加価値貿易統計で見ると二つの留意点がある。一つ目は、中国のシェアは付加価値ベースでは、貿易統計の総輸入ほど低下していないということであり、二つ目は、2018年以前は中国のシェアは貿易統計ベースで見る方が付加価値ベースで見るよりも高かったが、2019年を境に逆転していることである。
第Ⅰ-3-1-15図 米国の輸入に占める中国のシェア
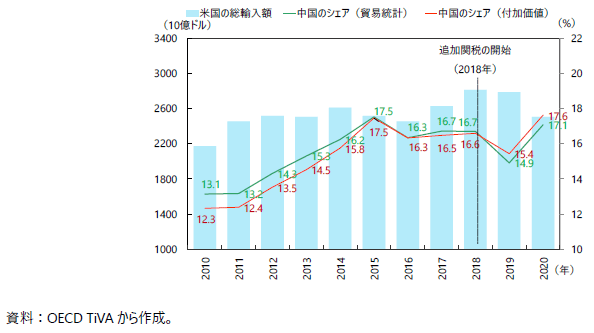
米国の中国からの輸入について、両統計で経由国を比べたものが第I-3-1-16図である22。通常の貿易統計では二国間の直接的な貿易だけが計上されるのに対して、付加価値貿易統計では、中国の付加価値は、対米輸出に含まれて直接米国に輸出されるとともに、一部はグローバル・バリューチェーンに沿って第三国での加工組立てを経由して間接的に輸出される。米国の輸入に占める中国の付加価値は、約8割が中国から直接輸入され、約2割がASEAN(特にベトナム)やメキシコなど第三国からの輸入に含まれている(第I-3-1-17図)。通常の貿易統計と付加価値統計でどちらが大きいかは、その国のグローバル・バリューチェーンにおける位置付けに影響される。既に見てきたように中国は前方参加を強めてきており、中国から中間財が第三国に輸出され、組み立てられた製品が第三国から米国に輸出される傾向が強まっていることが考えられる。
第Ⅰ-3-1-16図 米国の中国からの輸入(2020年)
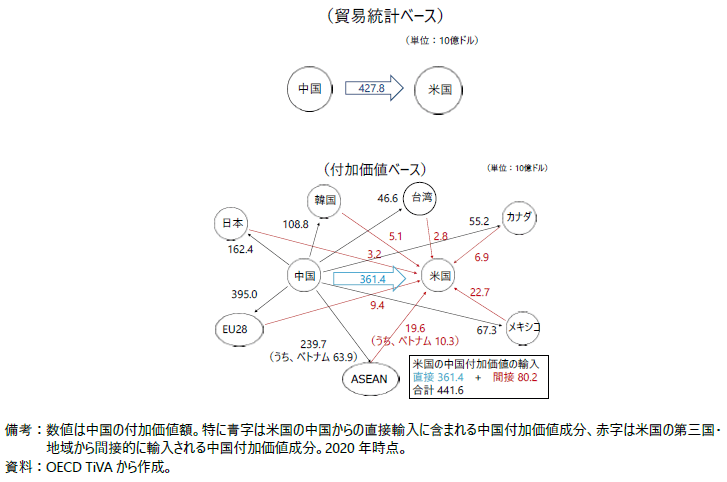
第Ⅰ-3-1-17図 米国の中国からの輸入(直前の経由国)
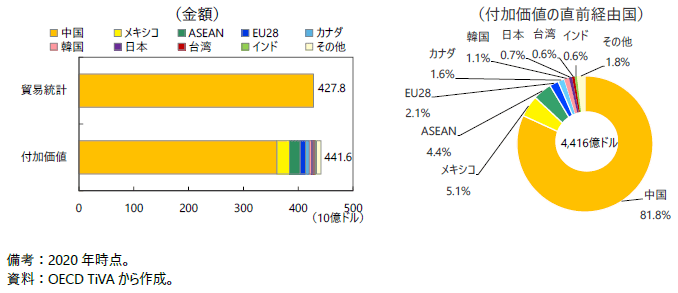
米国が輸入する中国付加価値の経由国・地域の推移を見ると、2019年に中国から直接輸入される部分のシェアが急低下し、代わりに間接的にASEAN、特にベトナムを経由して輸入される部分のシェアが上昇している(第I-3-1-18図)23。その背景として、①貿易統計で見て、米国のこれらの国・地域からの輸入シェア自体が上昇している(第I-3-1-19図)とともに、②付加価値貿易統計で見て、これらの国からの輸入に占める中国付加価値の濃度も上昇している(第I-3-1-20図)ことが挙げられる。貿易摩擦や地政学的リスク等の対応として、中国からの輸入の代替として、ASEANやメキシコからの輸入に切り替えたとしても、実質的には中国から輸入している可能性に留意が必要である。
第Ⅰ-3-1-18図 米国の輸入における中国付加価値の直前経由国
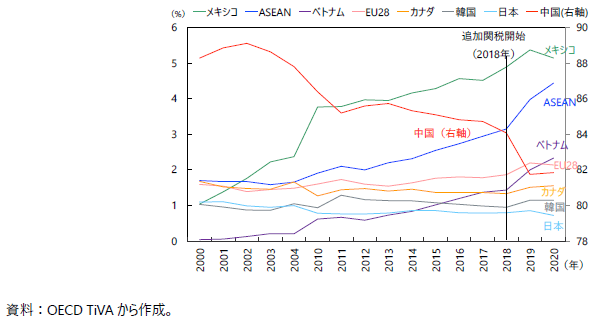
第Ⅰ-3-1-19図 米国の輸入における地域別シェア
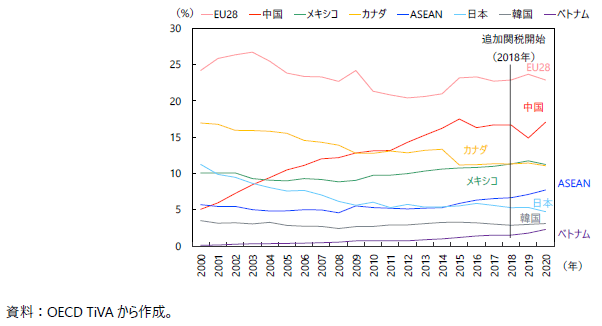
第Ⅰ-3-1-20図 各国・地域の対米輸出に占める中国付加価値のシェア
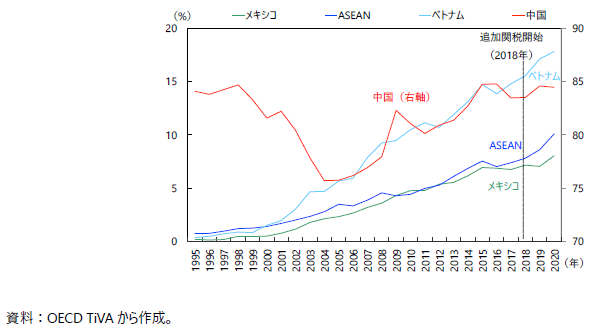
21 2020年に中国のシェアが再び上昇しているが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、米国のほかの国からの輸入額が減少したため、結果的に中国シェアが上昇したものと考えられる。
22 ここでは、通常の貿易統計という表現を使っているが、財のみでなく、サービスも含む。また、中国の付加価値は第三国間の貿易にも含まれているが、簡略化のため省略している。
23 第I-3-1-18図及び第I-3-1-19図において、EUは2000~2020年の間に加盟国の変化があるが、推移を見るために全期間統一的に28か国ベースで表記した。また、これに合わせて、第I-3-1-16図及び第I-3-1-17図など2020年だけの図表においても28か国ベースにそろえた。同様にASEANも、第Ⅰ-3-1-18図~第Ⅰ-3-1-20図において、全期間統一的に10か国ベースで表記した。
(4)主要国・地域の輸出における米中のバランス
ここまで中間財の調達という観点からグローバル・バリューチェーンのリスクを考えてきたが、米中対立が深まる中で、各国・地域にとっての輸出先という視点から米中のバランスを見てみる。第I-3-1-21図は主要国・地域の輸出における両国のシェアの推移を示している24。主要国・地域、特に日本、韓国、台湾、ASEAN等は、中国がWTOに加盟した2000年代初頭から中国向けシェアを大きく拡大してきた。その背景に、アジアにおける国際的生産分業、それに基づく生産拠点間の資材の流れ、言い換えればグローバル・バリューチェーンの拡大があった。機械分野の輸出を中間財・最終財に分けてプロットすれば、2000年以降、アジア諸国・地域の中間財輸出は、加工組立地である中国向けのシェアが45度線を越えて大きく拡大している。反対に最終財輸出においては米国の存在の方が大きく、45度線の左側を推移している。また、時系列の推移を見ると、2010年代の半ば以降、揺り戻しの動きが見られる。例えば、輸出全体の動きとしては、ASEANは、米国シェアの低下・中国シェアの拡大が続いていたが、2015年以降はほぼ45度線に沿って、米中シェアが均衡する形で推移している。日本、韓国、台湾は、反転・逆行の動きが見られる。その背景には、グローバル・バリューチェーン拡大の一服、米中貿易摩擦や地政学的リスクから、サプライチェーン寸断への懸念の高まり等が考えられる。財別に分ければ、中間財で日本、韓国、台湾、ASEANなどで中国シェアの頭打ち、縮小の動きが観察される。一方、最終財は45度線の左側を推移し、ASEAN、台湾などで米国シェアが大きく拡大している。
第Ⅰ-3-1-21図 主要国・地域の輸出における米国・中国のシェア
(2000年→2015年→2020年→2023年)
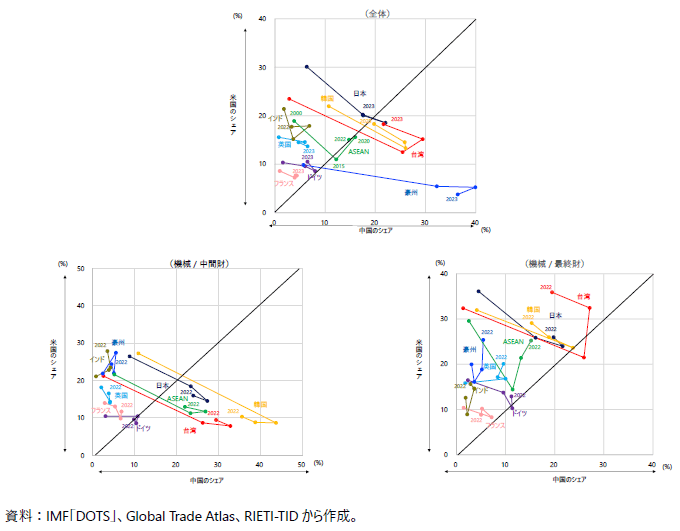
この節の考察をまとめると、日系製造業はアジアを中心に海外展開を果たしてきた。国際的に展開した素材や機械などの製造業現地法人が、日本本社を含めてグローバル・バリューチェーンを形成した。国内に立地する製造業はこのような海外現地法人への部材供給とともに、海外からの部材調達も進めたが、新型コロナウイルス感染症拡大を契機にグローバル・バリューチェーン寸断のリスクにも関心が高まった。一方、世界的に見てもグローバル・バリューチェーンにおける中国の中間財供給者としてのプレゼンスが高まってきており、特に電気・電子、自動車産業等で日本を始め、韓国、台湾、ASEAN等のアジア諸国・地域の中国との関係が強まっている。
24 複数の統計を組み合わせており、統計の関係から図表によって平仄が異なることがある。例えば、輸出全体の統計では原則として2023年まで推移を追っているが、ASEAN(10か国ベース)、インドの最新年は2022年となっている。また、RIETI-TIDの中間財・最終財別統計では最新年は2022年となっている。この統計ではASEANは、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの8か国ベース。2000年、2015年はSITC分類から財別に集計されていたが、近年はHS分類からの集計も併せて公表されており、2020年、2022年はHS分類からの集計データを利用した。
