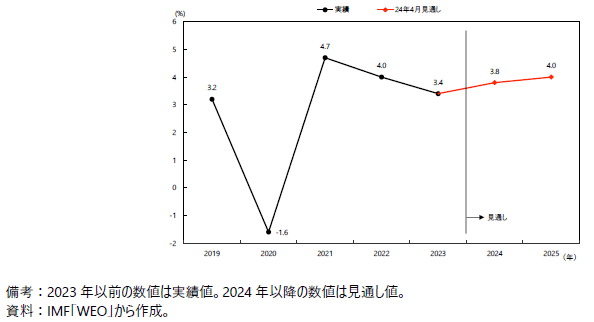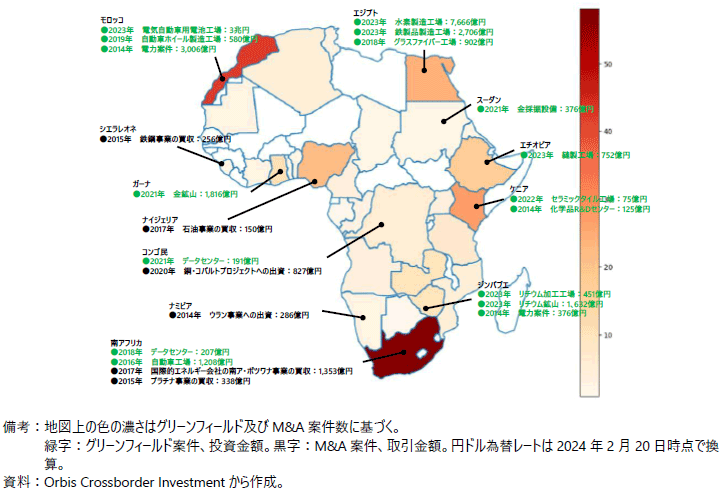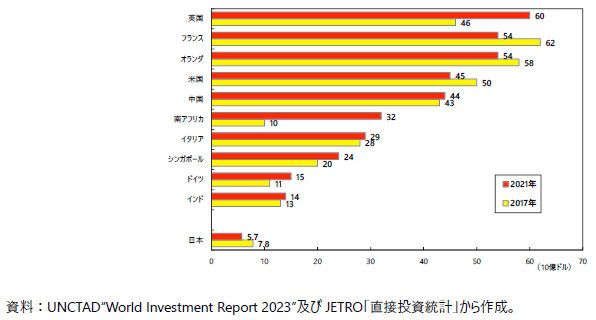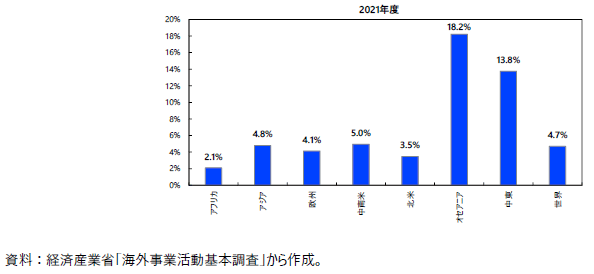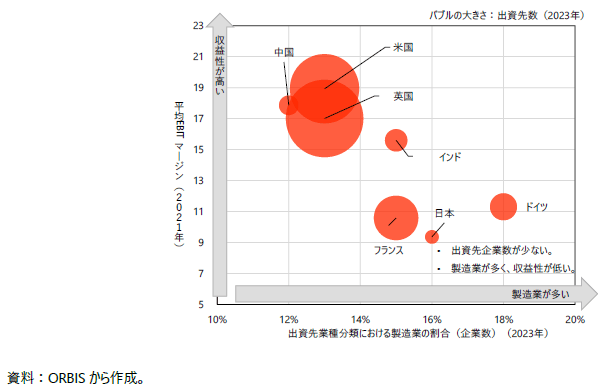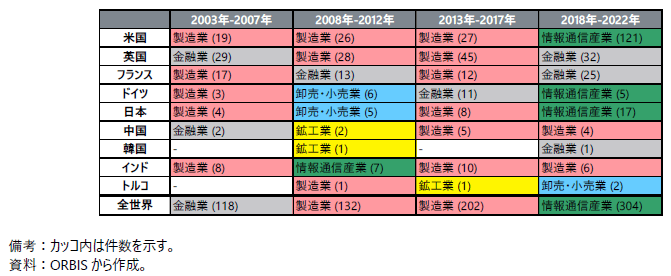第4節 グローバル・サウス経済
本節では、グローバル・サウス経済について取り上げる。グローバル・サウス経済は、各地域や国によってそれぞれ固有の事情を抱えているため、第1項ではASEAN・インド経済、第2項では中南米経済、第3項では中東・アフリカ経済とそれぞれ項を分けながら、最近の経済動向について個別に振り返る。
1.ASEAN・インド経済
本項では、グローバル・サウス諸国の中でも、成長著しいASEAN経済、インド経済の推移について見ていく。ASEAN経済は、2020年から2021年にかけての新型コロナウイルス感染症拡大による経済の落ち込みからの回復で、2022年は高成長となったが、中国経済が減速感を強める中で、2023年は外需の弱さから前年よりも緩やかな成長となった。インド経済は、好調な内需に支えられ、2023年も前年に引き続き高い経済成長を維持している。
(1)GDP
① ASEAN
ASEAN主要6か国の2023年の実質GDP成長率は、主に輸出低迷の影響により、各国とも前年から低下した(第I-2-4-1図、第I-2-4-2表)。特に、マレーシア、ベトナムで大幅に減速したほか、タイ、シンガポールは1%台の低い成長率となり、外需依存度の高い国で減速が顕著となった10。
第Ⅰ-2-4-1図 ASEAN各国の実質GDP成長率
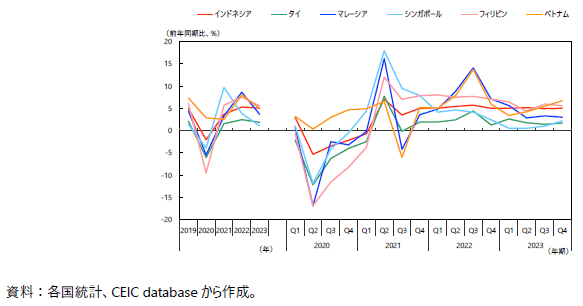
第Ⅰ-2-4-2表 ASEAN各国の実質GDP成長率
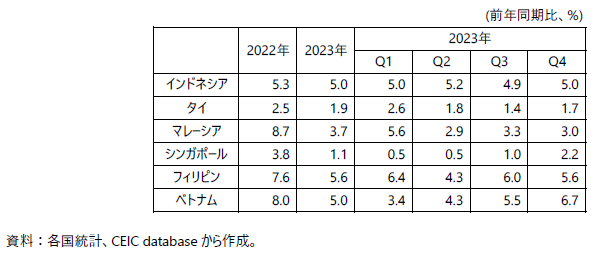
インドネシアの2023年通年の実質GDP成長率(前年比)は、+5.0%と前年(同+5.3%)から減速した。民間消費(同+4.9%)や総固定資本形成(同+4.4%)は堅調だったが、輸出(同+1.3%)の鈍化が影響した(第I-2-4-3図)。産業別では、製造業(同+4.6%)、サービス業(同+6.1%)等が小幅に鈍化した(第I-2-4-4図)。
第Ⅰ-2-4-3図 インドネシアの実質GDP成長率と項目別寄与度(需要側)
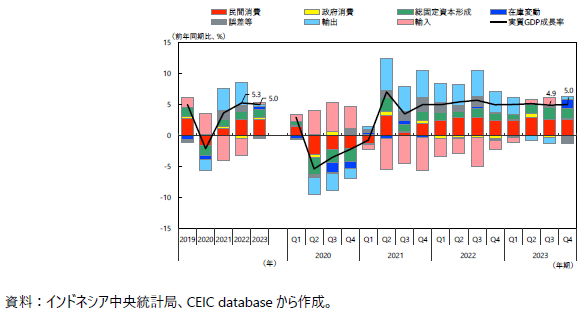
第Ⅰ-2-4-4図 インドネシアの実質GDP成長率と項目別寄与度(供給側)
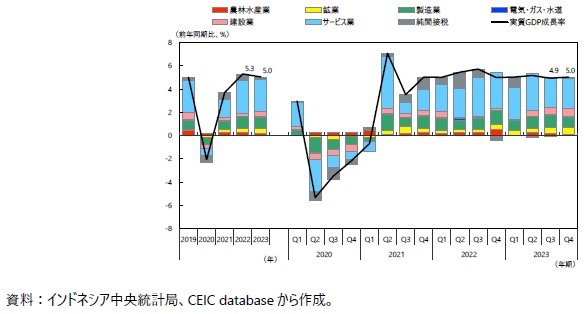
タイの2023年通年の実質GDP成長率(前年比)は、+1.9%と前年(+2.5%)から減速した。民間消費(同+7.1%)は堅調だったが、政府消費(同-4.6%)の減少や輸出(同+2.1%)の低迷が影響した(第I-2-4-5図)。産業別では、サービス業(同+4.3%)が堅調だった一方、製造業(同-3.2%)がマイナスとなり、成長を押し下げた(第I-2-4-6図)。
第Ⅰ-2-4-5図 タイの実質GDP成長率と項目別寄与度(需要側)
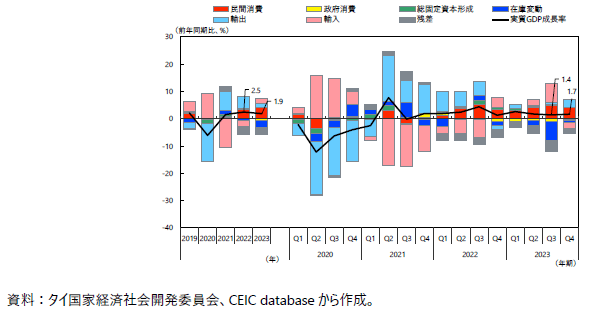
第Ⅰ-2-4-6図 タイの実質GDP成長率と項目別寄与度(供給側)
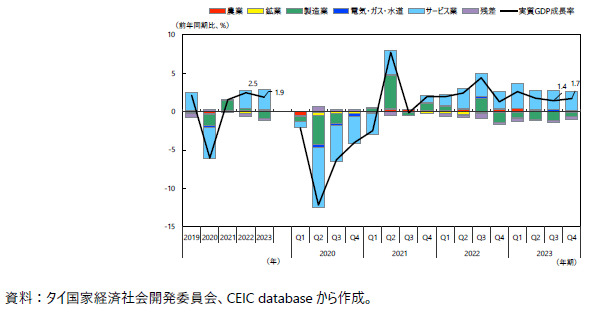
マレーシアの2023年通年の実質GDP成長率(前年比)は+3.7%と、高成長を記録した前年(同+8.7%)から大幅に減速した。輸出(同-7.9%)の減少や民間消費(同+4.7%)の鈍化が成長率の低下につながった(第I-2-4-7図)。産業別では、製造業(同+0.8%)が大幅に鈍化したほか、サービス業(同+5.3%)も伸びが低下した(第I-2-4-8図)。
第Ⅰ-2-4-7図 マレーシアの実質GDP成長率と項目別寄与度(需要側)
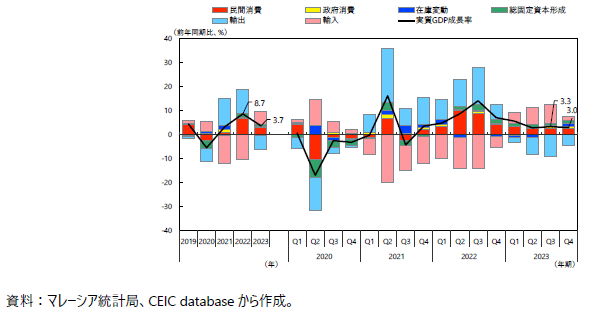
第Ⅰ-2-4-8図 マレーシアの実質GDP成長率と項目別寄与度(供給側)
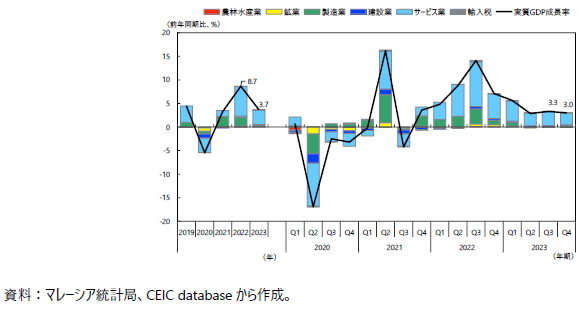
シンガポールの2023年通年の実質GDP成長率(前年比)は、+1.1%と前年(同+3.8%)から減速した。輸出(同+2.4%)が鈍化したことや、在庫変動が押し下げ要因となった(第I-2-4-9図)。産業別では、製造業(同-4.3%)が大幅なマイナスに転じたほか、サービス業(同+2.3%)も鈍化した(第I-2-4-10図)。
第Ⅰ-2-4-9図 シンガポールの実質GDP成長率と項目別寄与度(需要側)
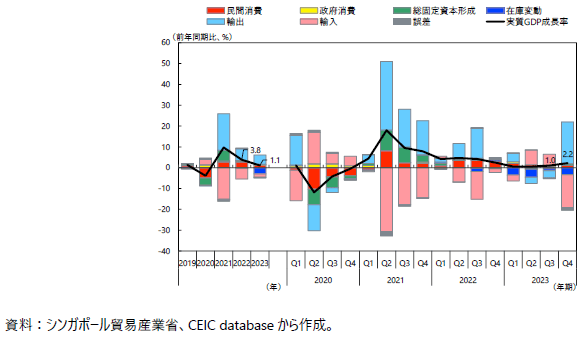
第Ⅰ-2-4-10図 シンガポールの実質GDP成長率と項目別寄与度(供給側)
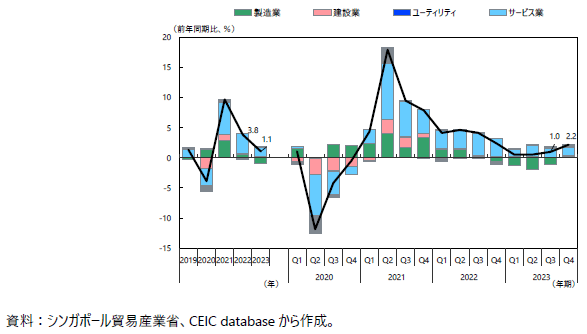
フィリピンの2023年通年の実質GDP成長率(前年比)は+5.6%と、高成長を記録した前年(同+7.6%)から減速した。輸出(同+1.3%)や民間消費(同+5.6%)の鈍化が成長率の低下につながった(第I-2-4-11図)。産業別では、主にサービス業(同+4.4%)の鈍化が成長率の低下につながった(第I-2-4-12図)。
第Ⅰ-2-4-11図 フィリピンの実質GDP成長率と項目別寄与度(需要側)
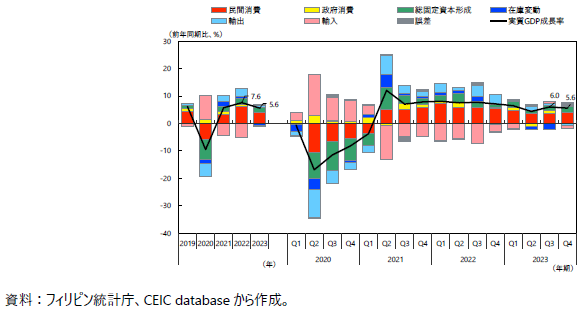
第Ⅰ-2-4-12図 フィリピンの実質GDP成長率と項目別寄与度(供給側)
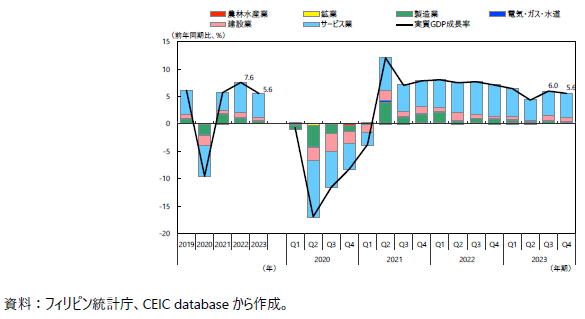
ベトナムの2023年通年の実質GDP成長率(前年比)は+5.0%と、高成長を記録した前年(同+8.0%)から減速した。民間消費(同+3.2%)の鈍化や純輸出のプラス寄与の縮小が成長率の低下につながった。産業別では、製造業(同+3.6%)とサービス業(同+6.8%)の鈍化が成長率の低下につながった(第I-2-4-13図)。
第Ⅰ-2-4-13図 ベトナムの実質GDP成長率と項目別寄与度(供給側)
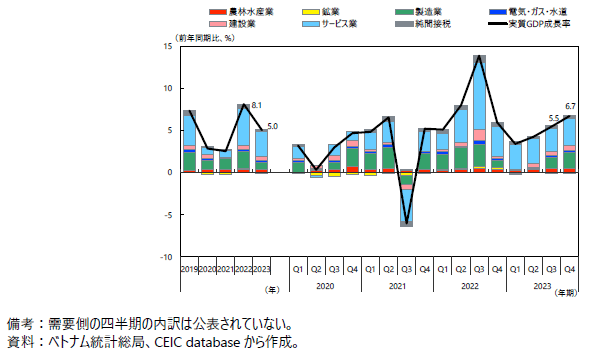
10 各国の名目GDPに占める財・サービス輸出の割合(2022年)は、インドネシアが24%、タイが66%、マレーシアが77%、フィリピンが28%、シンガポールが187%、ベトナムが94%となっている。
② インド
インドの実質GDP成長率は、2023年度第1四半期(4-6月期)以降、3四半期連続で8%台の高成長が続いている。第3四半期(10-12月期)の実質GDP成長率は、前年同期比+8.4%と前期(同+8.1%)から加速した(第I-2-4-14図)。民間消費(同+3.5%)が持ち直したほか、総固定資本形成(同+10.6%)が二期連続で二桁成長と好調を維持し、成長を牽引した。インド政府は、2月時点で2023年度(2023年4月~2024年3月)の実質GDP成長率を+7.6%と見込んでいる。また、実質GVA成長率11は、前年同期比+6.5%と前期(同+7.7%)から鈍化した(第I-2-4-15図)。製造業(同+11.6%)が二期連続で二桁成長となり成長を押し上げた。インドではサービス業の付加価値比率が上昇している一方で、製造業の付加価値比率は伸び悩んでおり、製造業の振興が課題となっている(第I-2-4-16図)。
第Ⅰ-2-4-14図 インドの実質GDP成長率と項目別寄与度
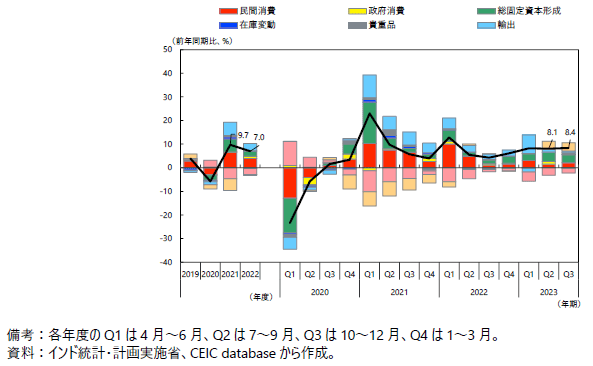
第Ⅰ-2-4-15図 インドの実質GVA成長率と項目別寄与度
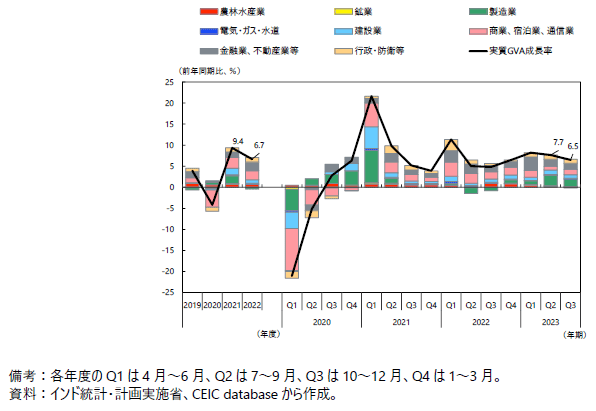
第Ⅰ-2-4-16図 インドの産業別付加価値比率の推移
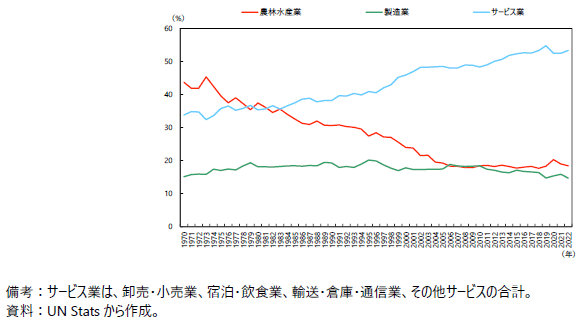
11 GVA(Gross Value Added)は、生産側から推計される総付加価値。GDPはGVAに純間接税(間接税から補助金を引いたもの)を加算したもの。
(2)消費動向
① ASEAN
ASEAN各国の小売売上高の推移(前年同月比)を見ると、シンガポール、ベトナムは2023年を通じて堅調に推移した。タイは低調だったが、2023年後半にかけて回復に転じている。マレーシアは年間を通じてプラスだったが、徐々に伸びが鈍化している(第I-2-4-17図)。
第Ⅰ-2-4-17図 ASEAN各国の小売売上高の推移
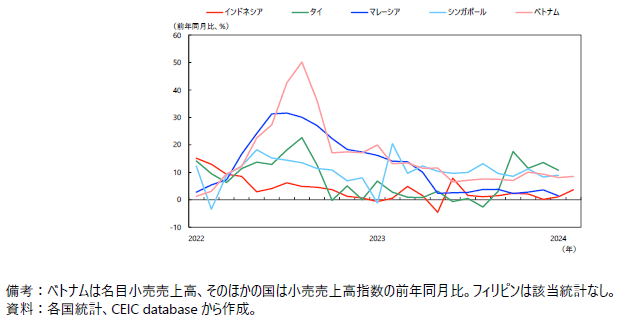
② インド
インドについては、購買意欲を反映する代表的な指標である自動車の国内販売台数の推移を見る(第I-2-4-18図)。2022年度(2022年4月-2023年3月)の乗用車の国内販売台数は、389万台超となり、過去最高を記録した。2023年4月以降も前年を上回って推移しており、2024年1月は単月で過去最高となるなど、好調を維持している。
第Ⅰ-2-4-18図 インドの国内乗用車販売台数
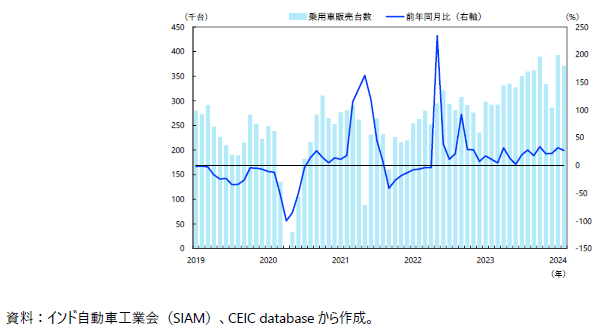
(3)外需動向
① ASEAN
ASEAN各国の財輸出を見ると、2023年通年では、各国ともに前年から減少した(第I-2-4-19図)。特にインドネシア(-11.3%)及びシンガポール(-13.1%)は2桁の減少となった。インドネシアは商品価格の低下を受け、主要輸出品目であるパーム油や石炭の輸出額が大幅に減少した(第I-2-4-20表)。シンガポールは全体の約2割を占める電子製品が-19.7%と大きく減少した。
第Ⅰ-2-4-19図 AASEAN各国の財輸出の推移
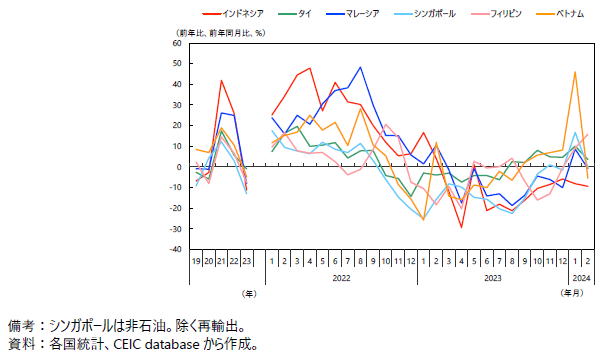
第Ⅰ-2-4-20表 インドネシアの主要輸出品目
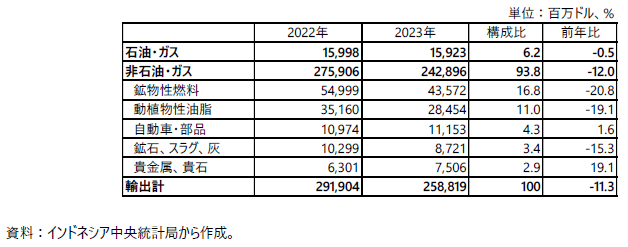
月ベースでは、欧米や中国等の需要減少を受け、2022年半ば以降減少傾向が続いていたところ、足下では持ち直しの動きが見られる(第I-2-4-19図)。ベトナムは9月以降、前年比プラスに転じており、コンピュータ・電気製品等の輸出が増加している(第I-2-4-21図)。タイも8月以降前年比でプラスに転じている。
第Ⅰ-2-4-21図 ベトナムの輸出の推移(品目別寄与度)
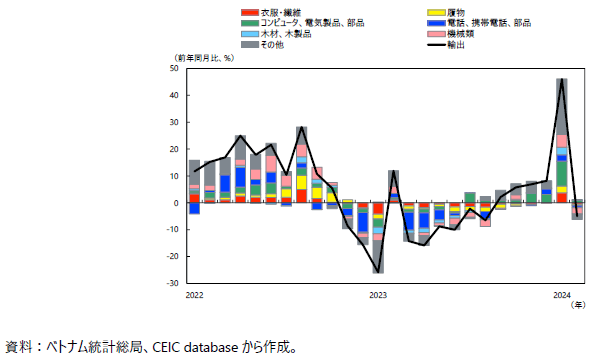
② インド
インドでは内需拡大を背景に慢性的に貿易赤字となっており、2023年もその傾向が続き、10月には単月で過去最大の貿易赤字となった。2023年通年では、輸出入とも前年から減少し、赤字幅は縮小した(第I-2-4-22図)。輸入相手国は前年に引き続き中国が最大となった。また、原油輸入が大幅に増加した影響で、ロシアが前年の6位から2位に上昇した。輸出相手国は前年に続き米国が最大となった。
第Ⅰ-2-4-22図 インドの貿易収支の推移
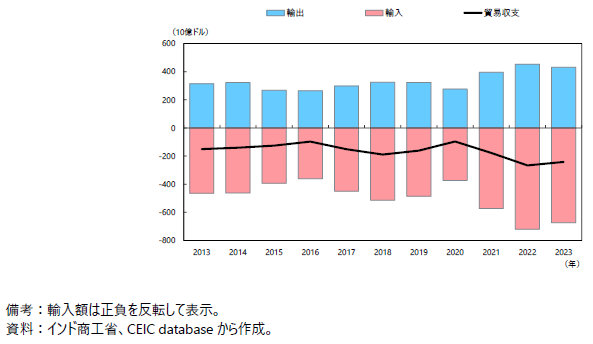
(4)生産活動
① ASEAN
ASEAN各国の鉱工業生産指数の推移(前年同月比)を見ると、2022年末頃から落ち込みが見られ、特にタイやシンガポールは低調に推移した(第I-2-4-23図)。輸出の減少が生産活動への下押し圧力となったと見られる。タイは年間を通じてマイナスで推移し、業種別では、コンピュータ、電子・工学製品が2022年に続き年間を通じてマイナスだった(第I-2-4-24図)。ベトナムは2023年後半にかけて回復を示した。
第Ⅰ-2-4-23図 ASEAN各国の鉱工業生産指数の推移
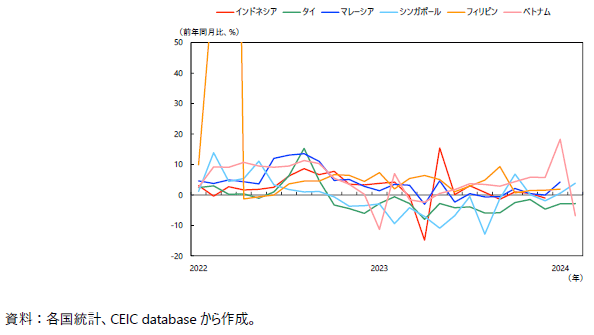
第Ⅰ-2-4-24図 タイの鉱工業生産指数の推移(業種別)
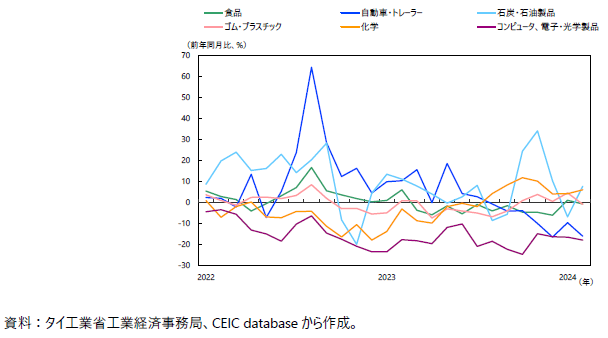
② インド
インドの鉱工業生産指数(前年同月比)を見ると、2023年は年間を通じて前年比プラスで推移した(第I-2-4-25図)。製造業の業種別内訳を見ると、金属や自動車が年間を通じてプラスで推移した(第I-2-4-26図)。
第Ⅰ-2-4-25図 インドの鉱工業生産指数の推移
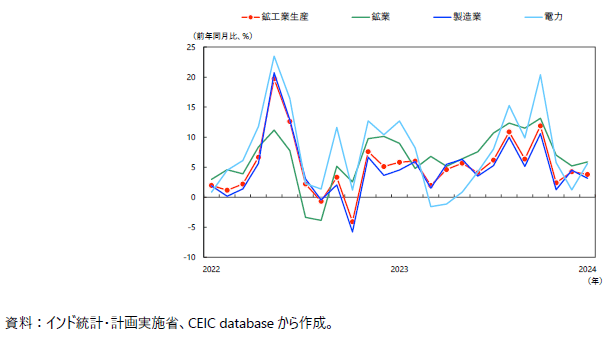
第Ⅰ-2-4-26図 インドの製造業生産指数(業種別)の推移
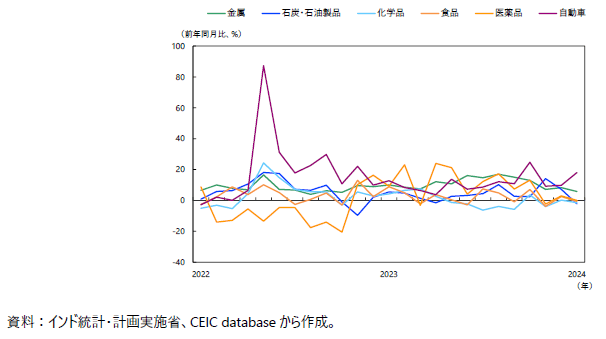
(5)雇用動向
① ASEAN
ASEAN各国の失業率は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済活動制限の影響を受け2020年に大幅に上昇したが、その後は改善傾向が継続している(第I-2-4-27図)。
第Ⅰ-2-4-27図 ASEAN各国の失業率
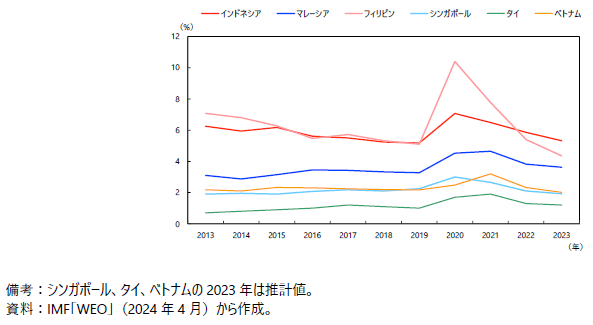
② インド
インドの都市部失業率を見ると、2021年第3四半期以降改善傾向が継続しており、足下では6%台となっている(第I-2-4-28図)。
第Ⅰ-2-4-28図 インドの都市部失業率
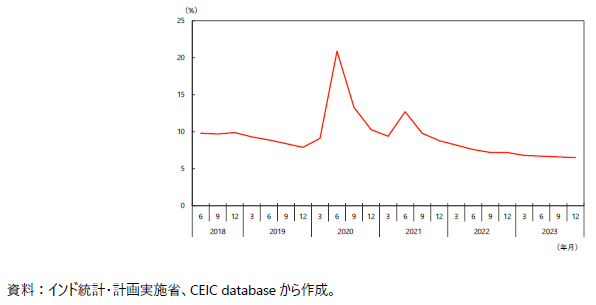
(6)物価動向
① ASEAN
ASEAN各国の消費者物価上昇率は、2022年に入ってその上昇ペースが加速したが、エネルギー及び食品価格の低下により、2022年後半をピークに鈍化傾向が継続している(第I-2-4-29図)。特に、タイは政府による燃料価格抑制措置の影響もあり、2023年10月以降、前年比マイナスで推移している。一部の国ではインフレ再燃を警戒した再利上げの動きがあったが、2023年11月以降は各国とも政策金利を据置いている。
第Ⅰ-2-4-29図 ASEAN各国の消費者物価上昇率
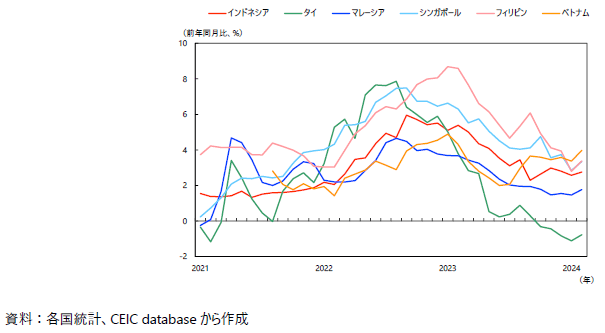
② インド
インドの消費者物価上昇率は、燃料価格や食品価格の低下により、2023年初から徐々に低下していたが、7月には野菜等の食品価格の高騰により前年同月比+7.4%へと急上昇した。9月以降は再度低下し、インド準備銀行(中銀)が定めるインフレ目標の上限(+6%)を下回って推移しているが、食品価格は高止まりしている(第I-2-4-30図)。中銀は2023年4月以降、政策金利を据え置いている。
第Ⅰ-2-4-30図 インドの消費者物価上昇率と項目別寄与度
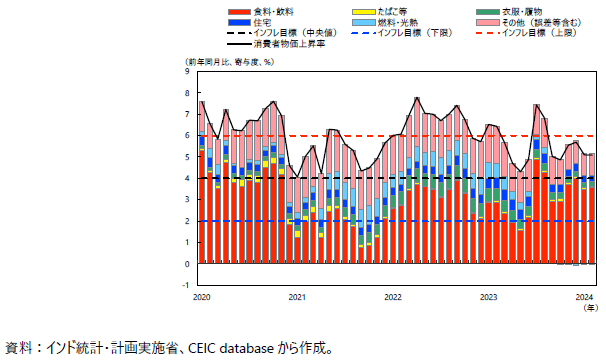
(7)今後の見通し
直近の国際機関(IMF)の実質GDP成長率の見通しについては第I-2-4-31表のとおりである。2024年、2025年のASEAN諸国・インドのGDP成長率は、輸出の回復と堅調な内需により、回復又は高い水準を維持することが見込まれている。
第Ⅰ-2-4-31表 実質GDP成長率の見通し(IMF)
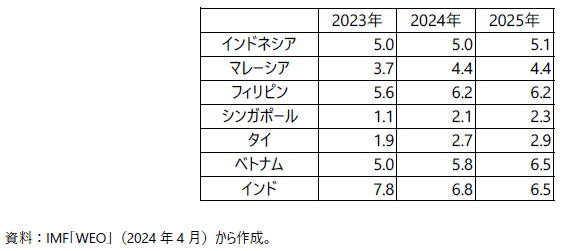
2.中南米経済
本項では、中南米地域主要3か国(ブラジル、メキシコ、アルゼンチン)の経済の推移について見ていく。3か国ともに2020年は新型コロナウイルス感染症拡大に伴い経済成長率はマイナスとなったが、翌2021年以降は回復してきている。一方、インフレに関しては、徐々に落ち着きを見せているブラジル・メキシコと、歴史的な高水準に苦しんでいるアルゼンチンに状況が分かれている。
(1)GDP
① ブラジル
ブラジルの2023年の実質GDP成長率は+2.9%と、ほぼ前年(+3.0%)並みの好調な結果となった。需要項目別では、インフレの落ち着きや低所得者向けの現金給付に支えられた民間消費と、特に上半期に豊作であった農産物の輸出が成長を牽引した。産業別では、サービス業と農畜産業が主に成長に寄与した(第I-2-4-32図)。
第Ⅰ-2-4-32図 ブラジルの実質GDP成長率、実質GVA成長率と項目別寄与度
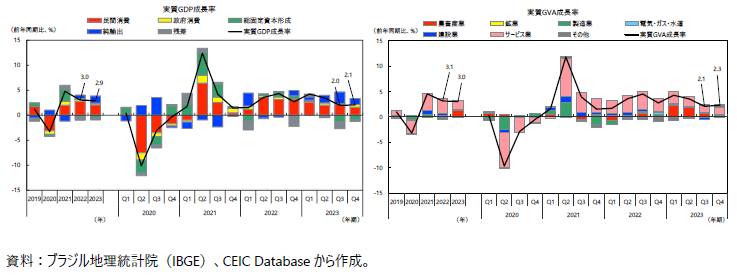
② メキシコ
メキシコの2023年の実質GDP成長率は+3.2%と、前年(+3.9%)から減速したものの引き続き堅調に推移した。需要項目別では、総固定資本形成と民間消費が成長を牽引した。総固定資本形成での成長寄与の大宗を占めたのは民間部門であり、これは具体的には民間企業による工場建設や生産設備購入などのいわゆる設備投資と呼ばれるものである。設備投資の顕著な伸びは、昨今のニアショアリング(隣国への生産拠点の移転)の拡大による米国市場への供給を睨んだ投資であることがうかがえる。一方、自国通貨高の影響もあり輸出が伸び悩んだ結果、純輸出はマイナス寄与となった。産業別では、サービス業と建設業がプラス寄与となったが、製造業はプラス寄与であるものの限定的な成長にとどまった(第I-2-4-33図)。
第Ⅰ-2-4-33図 メキシコの実質GDP成長率、実質GVA成長率と項目別寄与度
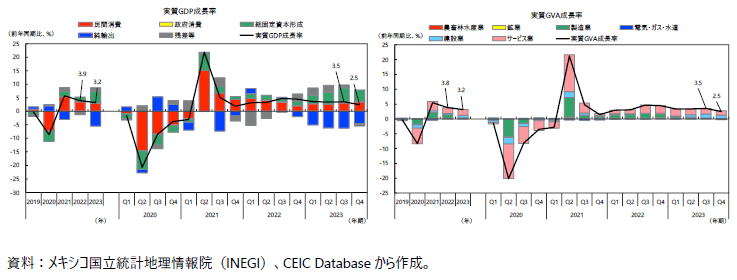
③ アルゼンチン
アルゼンチンの2023年の実質GDP成長率は-1.6%と、前年(+5.0%)から大きく減速しマイナス成長となった。需要項目別に見ると、歴史的な大干ばつによる農産物輸出の減少を受け純輸出がマイナス寄与となり、急激なインフレや経済の混乱により民間消費の伸びも限定的となった。産業別では、先述の大干ばつによる農業不振の影響が特に2023年第2四半期に現れている(第I-2-4-34図)。
第Ⅰ-2-4-34図 アルゼンチンの実質GDP成長率、実質GVA成長率と項目別寄与度
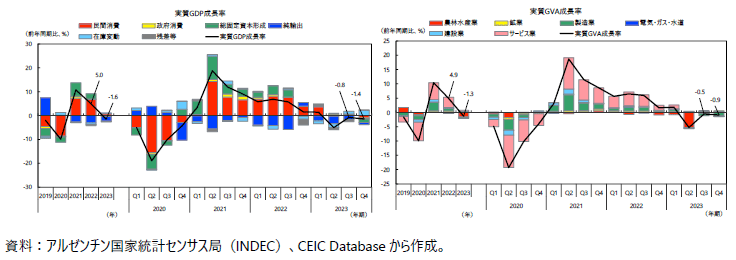
(2)生産
中南米の鉱工業生産の推移(第I-2-4-35図)を見ると、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済社会活動の制限の影響により2020年春に大きく落ち込んでいるが、その後はおおむね堅調に推移しており、特にメキシコでは安定的な成長が見られる。ただし、アルゼンチンについては、2023年6月から前年同月比の伸び率がマイナスとなり、12月以降はマイナス幅が著しく拡大している。この背景には、米国の政策金利引上げに伴う通貨安が進行している中で、12月にマクロ経済安定化のための措置の一環として対米ドル通貨切り下げ(約-54%)を実施したことで更なる急激な通貨安が生じ、工業生産の原材料輸入に支障をきたしているといった事情がある。
第Ⅰ-2-4-35図 中南米の鉱工業生産の推移
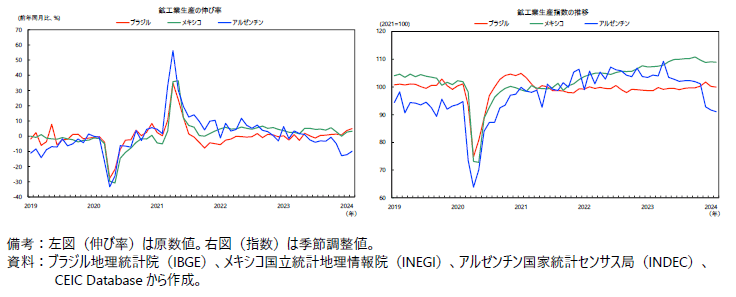
(3)貿易
ブラジルは貿易黒字を堅調に積み上げており、2023年は過去最大の黒字額となった。メキシコは通年での貿易赤字が続いているが、2023年の赤字額は過去3年間で最少となった。アルゼンチンは歴史的な大干ばつによる農産物の輸出減少を受け、2023年は貿易赤字に転じた(第I-2-4-36図)。
第Ⅰ-2-4-36図 中南米の輸出入額の推移
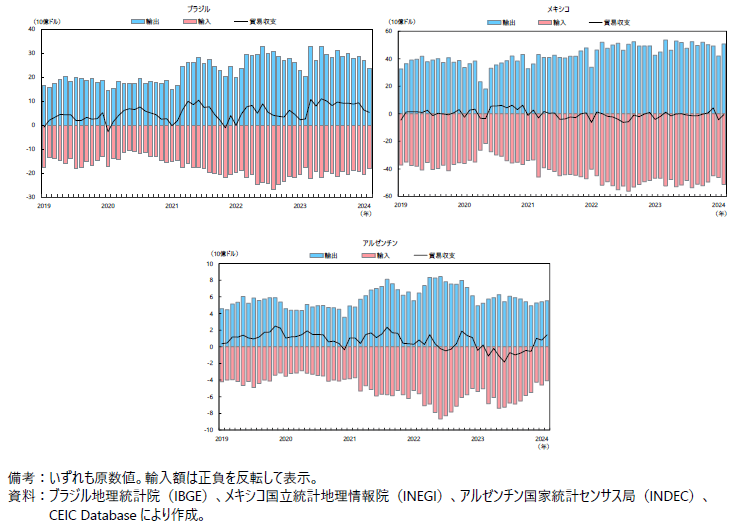
(4)消費者物価
ブラジルとメキシコは、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う景気の減速が回復基調に戻った2021年から物価上昇のペースが加速した。その後、ブラジルでは2022年夏、メキシコでは2022年秋をそれぞれピークとして物価上昇のペースが減速し、足下では安定基調に戻っている(第I-2-4-37図)。こうした動きを背景として、政策金利については両国ともに引下げの動きが見られている(第I-1-1-5図)。
第Ⅰ-2-4-37図 中南米の消費者物価の推移
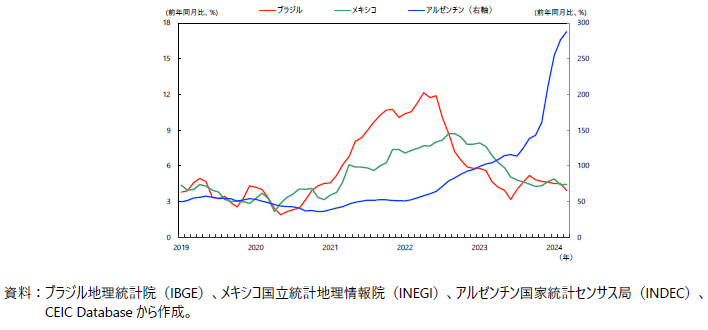
アルゼンチンは、急激な物価上昇が続いている。2022年夏からは通貨安による輸入物価の上昇と、歴史的な大干ばつによって引き起こされた農業生産・輸出の減退によって物価上昇のペースが加速し、2023年12月の通貨切り下げによって一段とそのペースが加速した(第I-2-4-37図)。
(5)今後の見通し
直近の国際機関(IMF)の実質GDP成長率の見通しについては第I-2-4-38表のとおりである。中南米地域の成長見通しは、ASEANや中東・アフリカなどほかの新興国・発展途上国に比べて低いものとなっているが、それでも先進国と同等かそれを上回る成長が予想されている。なお、アルゼンチンについては、2023年12月に誕生した新政権によるマクロ経済安定化のための大幅な政策調整を織り込み、短期的なマイナス成長が見込まれているが、2025年には回復する見通しとなっている。
第Ⅰ-2-4-38表 中南米の実質GDP成長率見通し
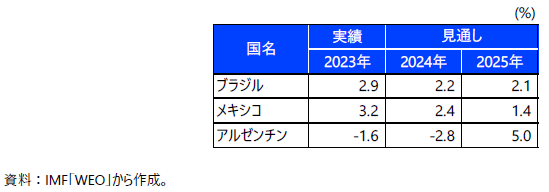
3.中東・アフリカ経済
本項では、中東(中央アジア、北アフリカを含む)経済及びアフリカ(北アフリカを除くサブサハラアフリカ)経済の推移を見ていく。中東・北アフリカは石油や天然ガスなどの豊富なエネルギー資源を抱え、特に湾岸諸国では経済の多様化や脱炭素化に向けた投資が盛んに行われている。中央アジアはエネルギー資源とともにウランやレアメタルなどの貴重な鉱物資源を抱えており、サブサハラアフリカは豊富な鉱物資源と高い人口増加率が特徴的である。このように、これらの地域はそれぞれの特徴を有しながらも、豊かな天然資源を背景とした高い経済成長率が見込まれていることが共通している。
(1)中東経済
① GDPと今後の見通し
中東・中央アジア・北アフリカ地域の実質GDP成長率は、2020年は新型コロナウイルス感染症拡大に伴いマイナスとなったが、2021年には回復した。その後、2022年は5.3%、2023年は2.0%の成長率となった。2022年はロシアによるウクライナ侵略を背景としたエネルギー価格の高騰により、こうした資源を産出する同地域では大きなプラス成長を記録した。一方、2023年はOPECプラス加盟国による価格安定化を目的とした戦略的な原油減産の影響などにより、成長率は緩やかなものとなった。今後の見通しについては、豊富な天然資源を背景とした底堅い成長が継続していくことが見込まれるものの、地政学的リスクに伴う影響に留意が必要である(第I-2-4-39図)。
第Ⅰ-2-4-39図 中東・中央アジア・北アフリカの実質GDP成長率見通し
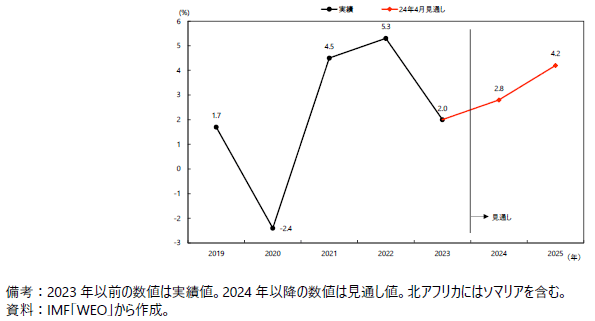
② 中東情勢の緊張
中東地域には歴史的に様々な紛争や対立が存在し、多くの不安定要因・課題を抱えている。その中でも2023年は、ハマスを含むパレスチナ武装勢力によるイスラエルに対する急襲と、それに対するイスラエルによる報復という武力衝突が発生し、2024年4月現在においても収束の兆しは見えていない。
このイスラエル・パレスチナ武装勢力間の衝突は、2023年10月7日にハマスを含むパレスチナ武装勢力がガザ地区からイスラエル領内に向けて多数のロケット弾を発射し、さらに武装した戦闘員を侵入させイスラエル軍兵士だけでなく外国人を含む市民の殺害や誘拐を行うなどの急襲を行ったことに端を発する。この急襲に対してイスラエルは即時に報復の空爆を行い、また、2023年10月28日には大規模な砲撃・空爆を伴いながらガザ地区への地上部隊による軍事行動を開始した。2024年4月現在においてもガザ地区では引き続き激しい戦闘が行われている。ガザ地区での武力衝突の影響は地区内にとどまらず、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラとイスラエルとの間での武力衝突や、紅海を航行する商船に対してのイエメン国内のホーシー派勢力による武力攻撃とそれを取り締まる米国及び英国による反撃、ヨルダン・イラク・シリアに駐留する米軍をめぐる武力衝突、また、イランとイスラエルとの間での緊張の高まりなど、周辺地域への拡大が見られる(第I-2-4-40表)。特に紅海を航行する商船をめぐる武力衝突については、従来エジプトのスエズ運河により地中海とインド洋とを接続していた航路が南アフリカの喜望峰を経由する航路へ変更を余儀なくされるなど、物流のリードタイムの長期化とともにコストの増加を招いている(第I-2-4-41図)。
第Ⅰ-2-4-40表 イスラエル・パレスチナ武装勢力間の衝突以降の中東情勢
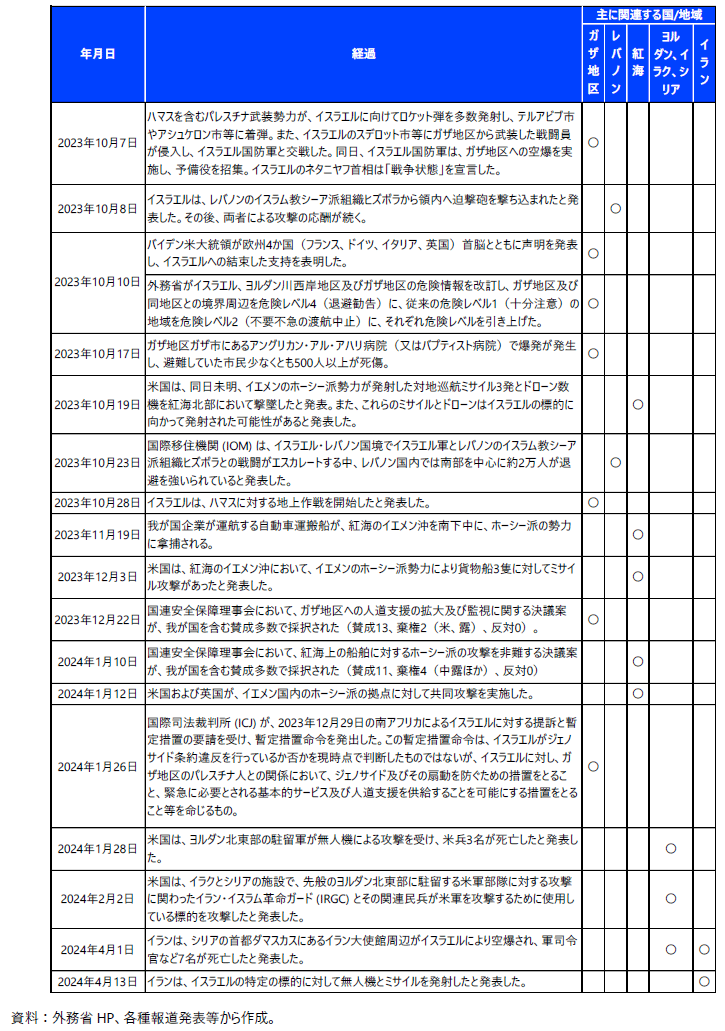
第Ⅰ-2-4-41図 バルチックコンテナ価格指数の動向
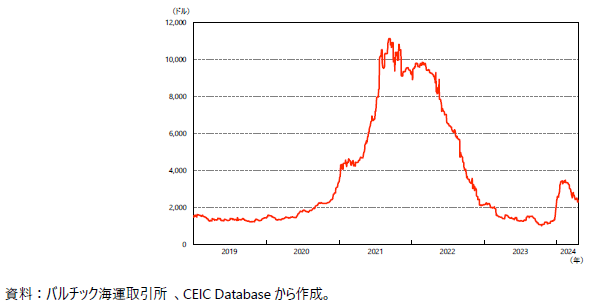
また、武力衝突の中心地となっているガザ地区では、多数の子ども・女性・高齢者を含む民間人の犠牲者が日々発生しており、人道状況は極めて悪化している。こうした状況を踏まえ、南アフリカ共和国による提訴を受けた国際司法裁判所(ICJ)は、2024年1月26日にイスラエルに対して暫定措置命令を発出し、ガザ地区のパレスチナ人との関係において、ジェノサイド及びその扇動を防ぐための措置をとること、緊急に必要とされる基本的サービス及び人道支援を供給することを可能とする措置をとること等を命じた。
こうした情勢の緊張を受けて、JETRO海外進出日系企業実態調査によると、イスラエルに進出している我が国企業は駐在員の一時的な国外退避などを実施しているが、事業そのものの撤退にまで至ったケースは確認されていない。なお、イスラエルに進出している我が国企業の業種については、製造業が約半数弱で第1位となっており、その次に情報通信業、卸売業・小売業、金融業・保険業と続いている。また、イスラエルに拠点を構えている理由としては、技術探索が約8割弱で第1位となっており、当地のもつハイテク産業やスタートアップ企業の魅力がうかがえる(第I-2-4-42図)。
第Ⅰ-2-4-42図 イスラエルにおける我が国企業
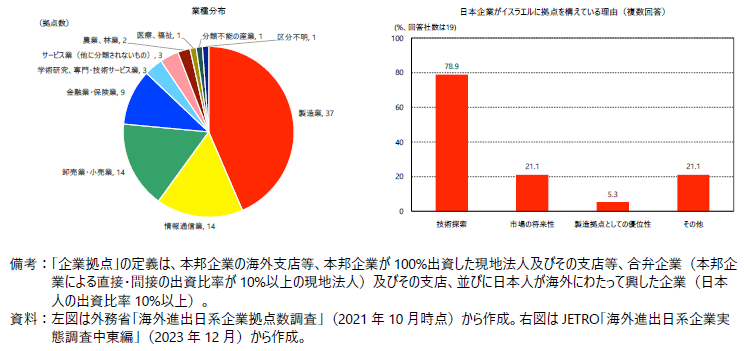
(2)アフリカ経済
サブサハラアフリカ地域の実質GDP成長率は、2020年は新型コロナウイルス感染症拡大に伴いマイナスとなったが、2021年には回復した。その後、2022年は4.0%、2023年は3.4%の成長率となった。ロシアによるウクライナ侵略に伴うエネルギー・食料価格の高騰、また、インフレ抑制のための米国を中心とした政策金利の引上げにより自国の通貨安が生じ、対外債務の返済負担が増し投資余力が縮小したことなどが、成長率が緩やかとなった背景となっている。今後の見通しについては、豊富な天然資源を背景とした底堅い成長が継続していくことが見込まれている(第I-2-4-43図)。
第Ⅰ-2-4-43図 サブサハラアフリカの実質GDP成長率見通し