第3節 中国経済
2023年の中国経済は、ゼロコロナ政策の終了後、景気に持ち直しの動きが見られたが、年央から持ち直しに足踏みが見られるようになった。趨勢的には、不動産問題等の構造的な課題を抱える中、経済成長の減速が続いており、先行きについても、国際機関等の見通しを踏まえれば、当面はこうした傾向が続くことが見込まれている。
1.GDP
2023年の中国の実質GDP成長率は、通年で+5.2%と、政府の目標「5%前後」を達成した(第I-2-3-1図)。ゼロコロナ政策が終了し、特に最終消費が大きく回復したことが経済成長を牽引した(第I-2-3-2表)。投資もほぼ前年並みの寄与を維持したが、世界経済の鈍化等から純輸出の寄与はマイナスに転じた。その四半期推移を見れば、2024年1月にゼロコロナ政策が終了し、第1四半期の中国経済は消費を中心に持ち直しの動きを見せた。第2四半期は持ち直しの動きが進み、前年の上海都市封鎖の反動もあって前年同期比で見たGDPの伸びが更に加速した。しかし、第3四半期は、反動による押上げ効果も弱まり伸びは鈍化し、需要項目別には消費の寄与がやや縮小し、投資も息切れが見え始めた。第4四半期は、消費の寄与縮小は続いたが、純輸出のマイナス幅が縮小したことで、経済の伸びは小幅ながら加速した。2024年に入ると、消費、投資とも内需は寄与が縮小するものの、外需の寄与がプラスに転じることで経済の伸びを保った。
第Ⅰ-2-3-1図 中国の実質GDP成長率の推移
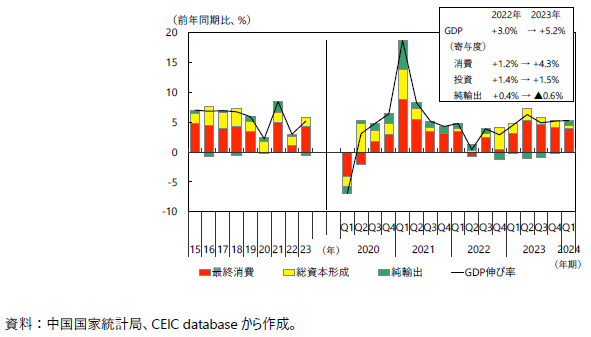
第Ⅰ-2-3-2表 中国の実質GDP成長率(需要項目別寄与度)の推移
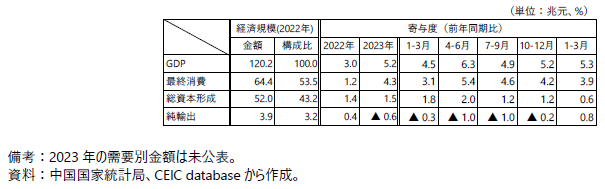
業種別の動向を見ると、2023年は第二次、第三次産業が伸びを加速させている(第I-2-3-3表)。特に第三次産業では、情報通信・情報技術サービスが2桁台の伸びを続けるとともに、ゼロコロナ政策の終了を受けて、対面サービス業である宿泊・飲食の伸びがプラスに転じ、2023年の4四半期全てを通じて2桁台の成長を達成した。同様に運輸・通信業も伸びを回復した。一方、第三次産業の中で、不動産業だけは第1四半期こそ一時的にプラスに転じたが、第2四半期以降は、マイナスに戻り、むしろマイナス幅が拡大する傾向が見られる。
第Ⅰ-2-3-3表 中国の実質GDP成長率(業種別)の推移
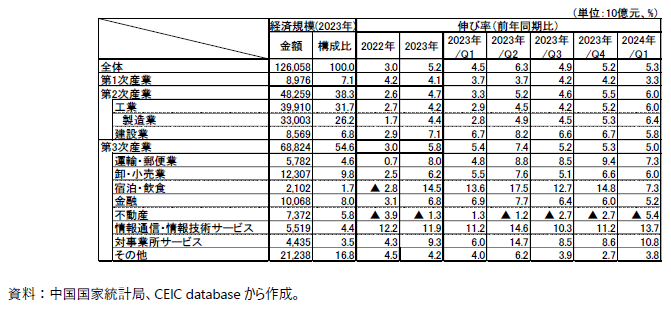
2.工業生産
主要な月次統計を参照しながら、経済動向を見ていく。まず、工業生産は2023年通年で前年比+4.6%と2022年(同+3.6%)から加速した(第I-2-3-4図)。月次の推移を見ても、2023年初めからおおむね堅調に伸びが拡大している。主要な業種別に見ても、感染症の脅威が薄れて医薬品がマイナスとなっているほかは、各業種とも伸びを拡大している。
第Ⅰ-2-3-4図 中国の工業生産
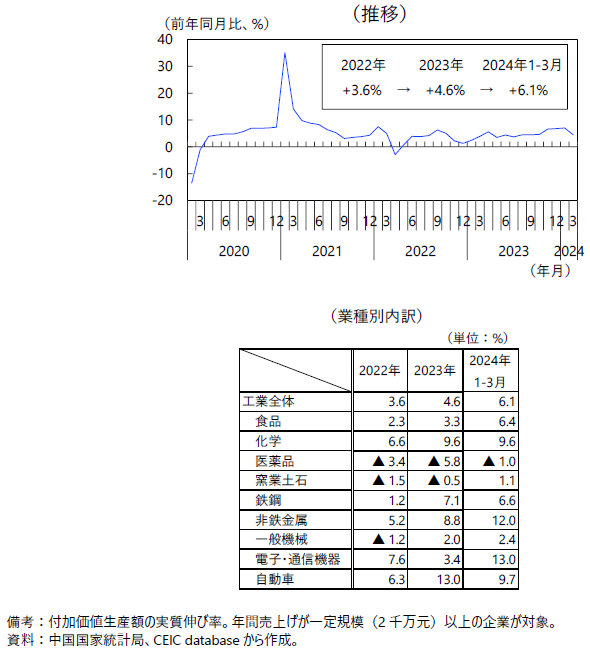
3.固定資産投資
2023年の固定資産投資は前年比+3.0%と、2022年(同+5.1%)から鈍化した(第I-2-3-5図)。月次の推移を見ても、2023年中は伸びの鈍化が続いている。業種別には医療関係の衛生・社会サービスがマイナスに転じたほか、製造業の設備投資やインフラ投資が鈍化した。国有・民営企業別には、国有企業の+6.4%に対して、民営企業は-0.4%の減少と厳しい状況にある。
第Ⅰ-2-3-5図 中国の固定資産投資
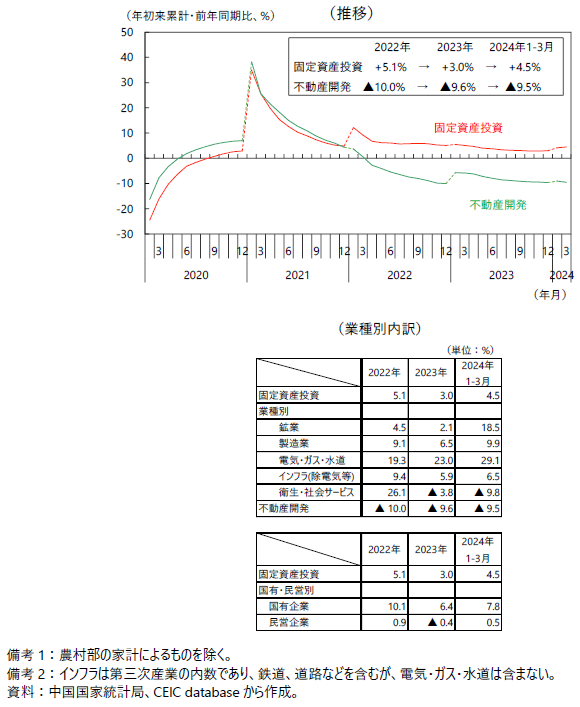
また、2020年に不動産バブルを警戒して導入された規制を契機とする不動産開発の不調は2023年も続いている。不動産開発は2023年の通年で前年比-9.6%と2桁近い減少となった。月次推移では次第にマイナス幅が拡大する様子が見られる。この傾向は2024年に入ってからも続いている。不動産問題については、構造的課題として後でより詳しく見ることにする。
4.小売売上高
小売売上高は2023年通年で前年比+7.2%と、2022年の同-0.2%の減少からプラスに転じた(第I-2-3-6図)。特に飲食業が前年比+20.4%と、前年(同-6.3%)の落ち込みの反動もあって高い伸びを記録した。物品販売も、大型商品の自動車を含め、+5.8%と堅調な伸びとなった。主要品目の中では、外出規制がなくなり衣類が2桁の伸びとなったのが目につく。
第Ⅰ-2-3-6図 中国の小売売上高
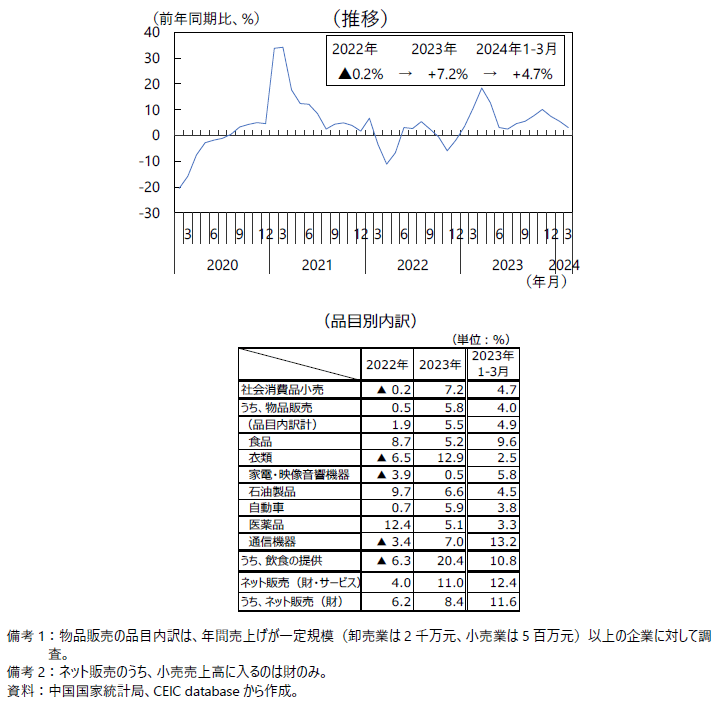
5.貿易
2023年の輸出は前年比-4.6%、輸入は同-5.5%と、輸出入ともに減少に転じた(第I-2-3-7図)。月次の推移を見ると、3月、4月の輸出が前年の上海の都市封鎖の反動で大きく伸びたほかは、総じてマイナスの伸びとなった月が多い。しかし、2023年後半は次第にマイナス幅が縮小した。
主要相手国・地域別には、2023年の輸出は米国、EU、ASEANなど大半の主要輸出国・地域向けがマイナスに転じた。輸入は2022年から引き続き、マイナスとなった国・地域が多い。一方、ロシアに対しては、輸出入とも2桁台の高い伸びが続いた。
主要品目別には、輸出では、自動車、自動車部品等がプラスとなったほかは、電子計算機、携帯電話、集積回路などのIT製品や衣類、繊維製品、家具などの労働集約型製品、プラスチック、鋼材等の幅広い品目がマイナスとなった。このような中で、自動車は新エネ車が好調で、前年比+69.0%と前年(同+74.7%)に引き続き高い伸びを示した。輸入では、IT製品の輸出不調を受けて、最大の輸入品である集積回路が2桁台のマイナスとなったほか、マイナスを記録する品目が多い。なお、自動車については輸出が好調な一方、輸入のマイナス幅が拡大するなど、輸出入で対照的な動きとなった。
第Ⅰ-2-3-7図 中国の貿易
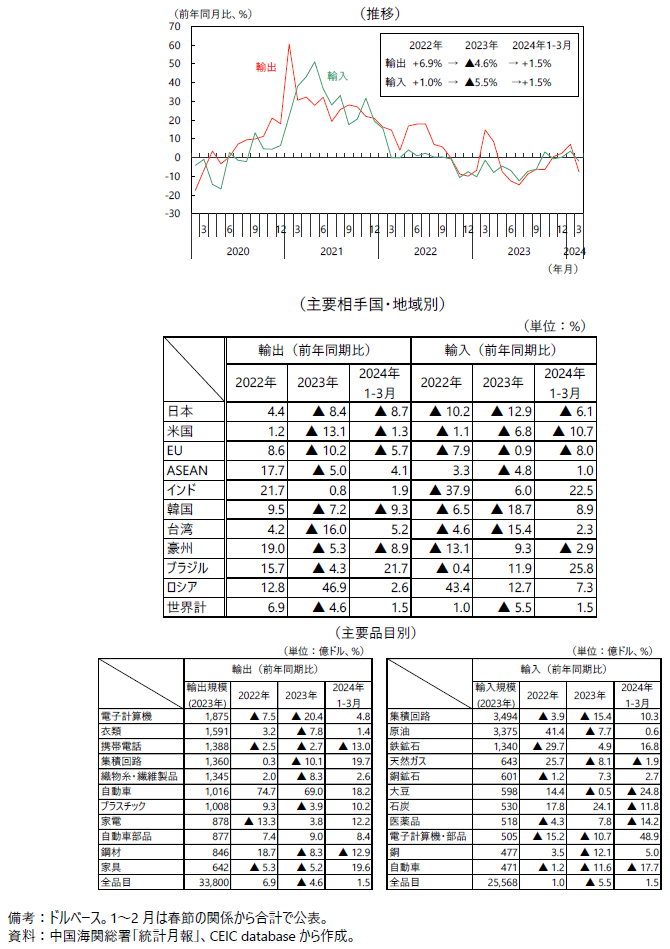
6.物価
2023年の消費者物価は通年で前年比+0.2%と、政府目標の「3%前後」を大きく下回った(第I-2-3-8図)。自動車燃料などエネルギー関係のほか、豚肉を中心とする食品価格の伸びがマイナスとなり物価を下押しした。食料、エネルギーを除いたコアで見ても、前年比+0.7%と低い伸びにとどまった。月次の推移を見ると、消費者物価は年央からマイナスに転じた。
生産者物価は2023年通年で前年比-3.0%とマイナスに転じた。石油、石炭、天然ガスなどエネルギー資源の採掘から、化学、鉄鋼、非鉄金属など素材関係、一般機械、情報通信機器、自動車など機械関係まで、幅広い業種でマイナスとなった。時系列の推移を見ると、2022年後半にマイナスに転じ、以降、約1年半にわたってマイナスが続いている。
第Ⅰ-2-3-8図 中国の消費者物価・生産者物価の推移
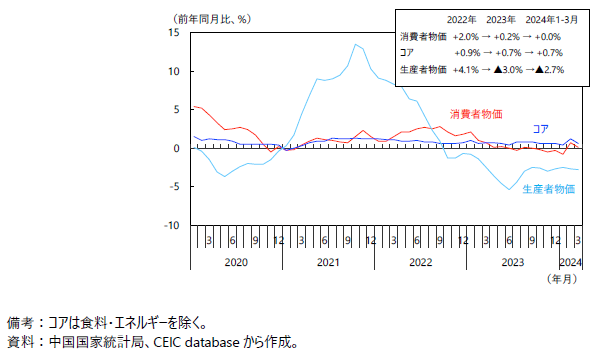
7.雇用
都市部調査失業率は、2023年通年で5.2%と政府目標の「5.5%前後」を達成した。2023年はほぼ年間を通じて2022年よりも低い失業率で推移した。2022年が、ゼロコロナ政策の下で、上海の都市封鎖などが行われていたことに比べて、2023年はゼロコロナ政策が終了し、経済が持ち直した影響が大きい。一方で、大学卒業者の増大等を背景に、若年層の失業率の高止まりが懸念されている。年齢別の失業率は、2023年12月時点で、16~24歳14.9%、25~29歳6.1%、30~59歳3.9%と、若年層の失業率が高い6。
第Ⅰ-2-3-9図 中国の都市部調査失業率の推移
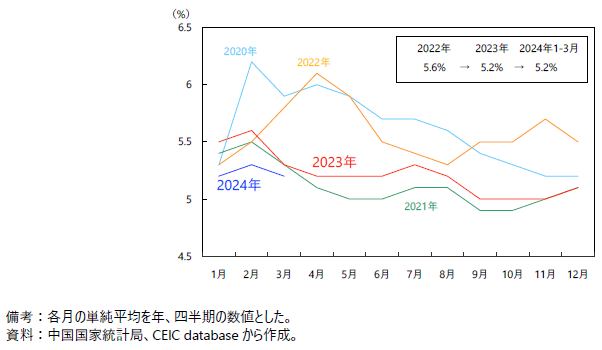
都市部新規就業者数を見ると、2023年は1,244万人と政府目標の「1,200万人前後」を達成した。ゼロコロナ政策が終了し、年間を通じて2022年よりも高水準であった。
第Ⅰ-2-3-10図 中国の都市部新規就業者数の推移
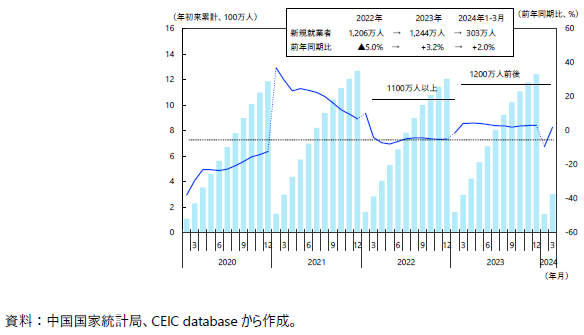
6 年齢別の失業率は、2023年7月実績から従来の統計の公表が中止され、2023年12月実績から、学生を失業率の計算から除外する形で公表が再開された。なお、最後に公表された2023年6月時点の従来統計では、16~24歳21.3%、25~59歳4.1%と若年層の失業率が過去最高を記録していた。
8.政策金利
中国経済は、年初のゼロコロナ政策終了後、持ち直しの動きが見られたが、年央から足踏みが続き、景気下支えのため2023年以降も政策金利等の引下げが行われた(第I-2-3-11図)。特に不動産部門の不調が長引いていることから、住宅ローン金利に参照される5年物最優遇貸出金利(LPR)が2023年6月に0.10%引き下げられたほか、2024年2月には0.25%の大幅引下げも実施された。また、政策金利だけでは、銀行の利ざやに影響すること等から、預金準備率も活用された7。預金準備率は、2023年以降、3回にわたって引き下げられ、金融機関の貸し出し余力を高めた。
第Ⅰ-2-3-11図 中国の金融政策の推移
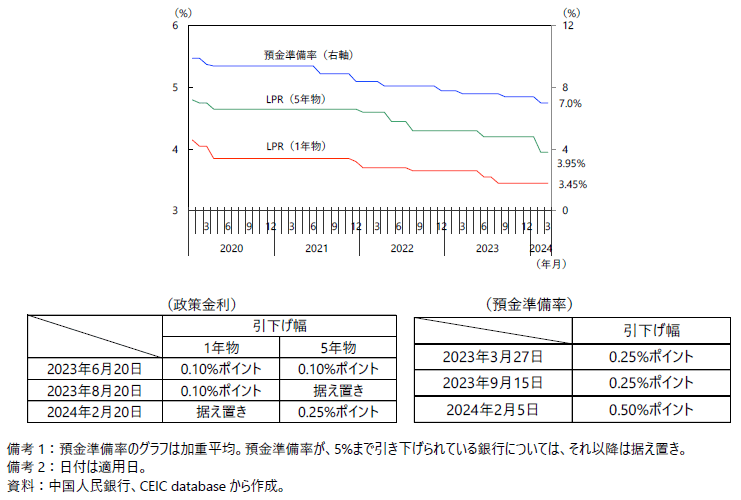
7 政策金利の引下げは、利ざやを圧縮し、銀行の体力を圧迫する懸念も指摘されている。また、2022年以降、米国始め世界的に政策金利の引上げが進む中で、反対に中国は引下げを行ってきたことから、為替レートは元安方向に推移し、資金流出を懸念する声もある。このような政策金利の制約もあり、預金準備率の引下げも活用されている。
9.人口動態
これまでは最近の中国の景気動向を見てきたが、以降、中長期的な成長に影響を及ぼす構造的課題についても考察する。
まず、人口動態を考えてみる。最新の2022年版国連人口推計では、中国の総人口は既に減少に転じており、仮に国連の中位推計どおりに推移すれば、2050年までに総人口は約1億人減少する(第I-2-3-12図)。その内訳は、生産年齢人口が約2.2億人減少し、反対に老齢人口は約2.3億人増加、そして将来を担う年少人口は約1億人減少する。その結果、現在約60%ある生産年齢人口比率は約50%まで低下することが見込まれている。
第Ⅰ-2-3-12図 中国の人口の将来予測(国連推計)
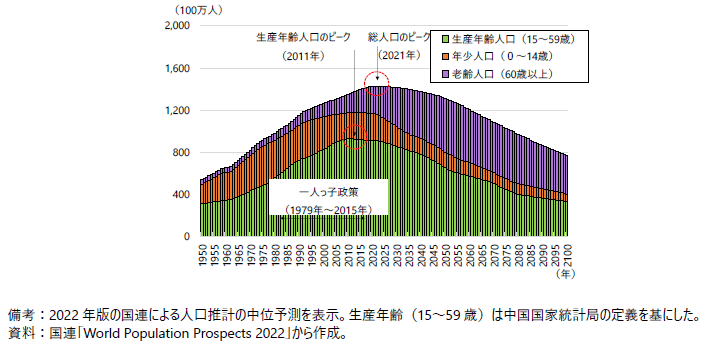
中国側の統計で最近の動向を見ると、人口に対する出生率は7年連続で緩やかに低下してきており、2022年に死亡率と逆転した(第I-2-3-13図)。これは人口増加率がマイナスに転じたことを意味し、この傾向は2023年も続いている。その背景には、長年にわたる一人っ子政策の影響が指摘されている。既に一人っ子政策は廃止されたが、緩和や廃止の翌年は出生率が一旦上昇するものの、生活費や養育費の問題、生活パターンの変化等から再び低下に転じて、出生率は期待されるほど上がっていない。このような少子高齢化は将来の生産面、需要面での成長鈍化をもたらす懸念がある。
第Ⅰ-2-3-13図 中国の人口に対する出生率・死亡率の推移
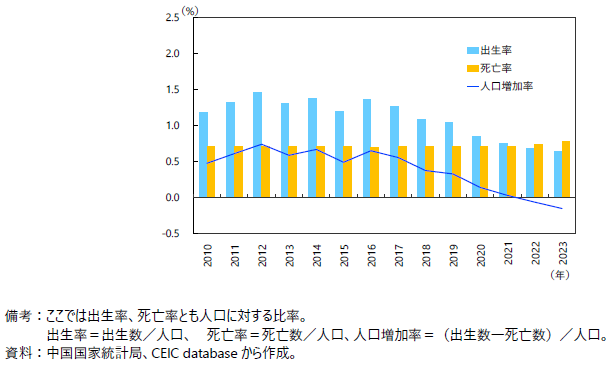
10.不動産問題
不動産開発の動向は、建設資材や耐久消費財等の製造業、建設業など関連部門への影響が大きい。一方で、住宅市場に資金が流入して価格が高騰し、バブルの危険性もたびたび指摘されてきた。既に見たように、2020年に不動産バブルを警戒して導入された規制を契機とする不動産開発の不調は2023年も続いている。
発端となった住宅価格は、2020年8月の不動産会社への財務規制や12月の銀行への不動産融資規制の導入後、低下に向かった。2021年中頃から、二線都市(省都クラスが多い)や三線都市(それに次ぐ地方都市)が低下に転じ、一線都市(北京、上海、広州、深圳)でも2023年中頃から低下に向かっている(第I-2-3-14図)8。
第Ⅰ-2-3-14図 中国の新築住宅販売価格の推移
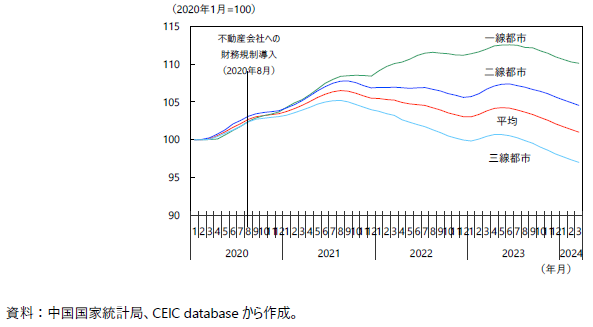
不動産開発投資は2021年をピークに、2022年、2023年と減少が続いている(第I-2-3-15図)。むしろ、2023年の月次推移を見ると、月を追うごとにマイナス幅が拡大している。住宅の販売面から見ても、面積ベースで2023年は伸び率のマイナス幅こそ縮小したものの、依然としてマイナスが続いている。
第Ⅰ-2-3-15図 中国の不動産開発
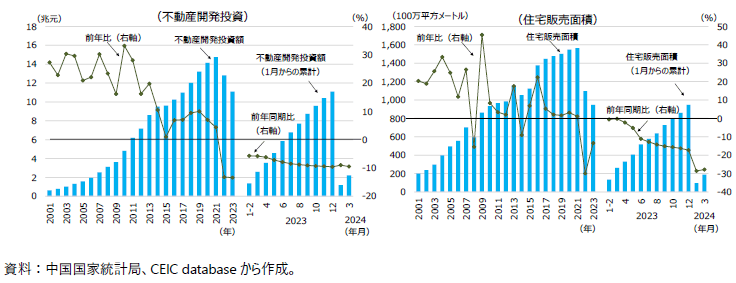
第I-2-3-16図は、長期的に面積ベースで、着工、販売、在庫の動向を見たものである。2022年、2023年は着工、販売とも大きく落ち込んでおり、2023年の着工は世界金融危機以前、販売も10年以上前の水準まで低下した。ピークの水準からは着工は半減以下、販売も6割の水準となった。反対に在庫は増加してきている。また、販売の中で、建物竣工後の販売と竣工前の予約販売は統計の取れる2005年頃は大きな差がなかったが、予約販売が増加することで市場が拡大してきた。今回大きく落ち込んでいるのが、この予約販売の形式で、その背景には前払い金や借り入れに依存していた恒大集団など不動産会社の資金繰りが悪化し、建設工事の中断や引渡しの停滞が発生していることが指摘されている。その不動産会社の資金繰りについては、依然として資金調達額の縮小が続いている(第I-2-3-17図)。また、先に見た少子高齢化は、将来結婚して新たな家庭を築くと思われる年齢層の先細りを示唆しており、不動産開発に多くを依存する成長モデルは持続が難しい。
第Ⅰ-2-3-16図 中国の住宅開発の動向(面積ベース)
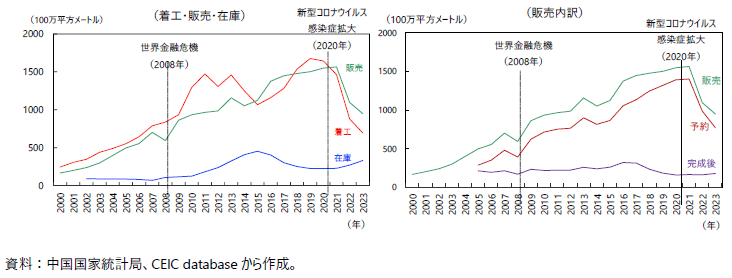
第Ⅰ-2-3-17図 中国の不動産会社の資金調達の推移
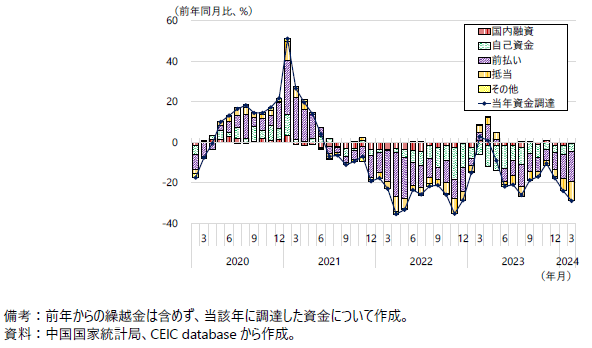
8 2023年から2020年=100とする都市別の価格指数が公表されなくなったが、前月に対する伸び率は公表されているため、便宜的に2020年1月=100とし、2020年2月から前月比を順次掛け合わせていくことで指数化した。なお、今回は一線・二線・三線別の指数としたが、都市の分類は、統計局発表によれば、一線都市は、北京、上海、広州、深圳の4都市。二線都市は、天津、重慶など直轄市のほか、河北省の省都である石家庄や山西省の省都である太原など31都市。三線都市は、河北省の唐山など、二線都市に次ぐ地方の35都市。
11.地方政府財政
不動産市場の低迷は地方政府財政にも影響を及ぼしている。これまで、地方政府は土地の使用権を不動産開発会社等へ譲渡することで大きな収入を得ており、このような土地使用権譲渡収入は2021年には、約8.7兆元と、地方政府収入の約3割を占めるまで拡大した。しかし、土地使用権譲渡収入は2022年から減少に転じ、2023年も減少幅こそ縮小したものの、依然として減少傾向が続いている(第I-2-3-18図)9。地方政府収入の大きな柱である土地使用権譲渡収入が減少に転じる一方で、財政支出は年々拡大しており、その歳入不足を補うための地方債の残高はGDP以上に早いペースで増大し、特に景気刺激策として実施されるインフラ整備に充当される専項債の拡大が顕著となっている(第I-2-3-19図)。さらに、ここには含まれていない地方政府傘下の地方融資平台の債務問題を懸念する声もある。このような中で、地方政府収入が減少し、特に財政基盤の弱い地方政府の債務不安が指摘されている。
第Ⅰ-2-3-18図 中国の地方政府の土地使用権譲渡収入の推移
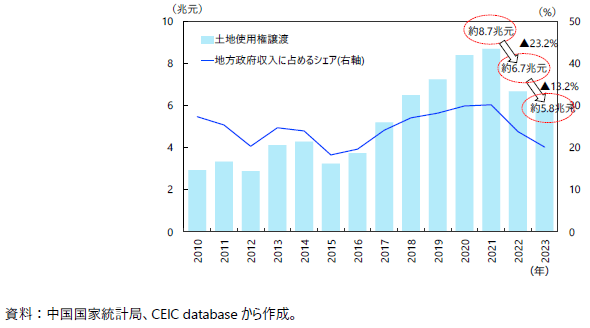
第Ⅰ-2-3-19図 中国の地方債務残高の推移
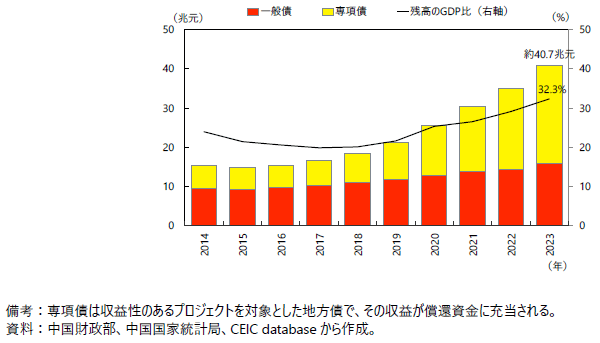
9 2024年1~3月期においても、土地使用権譲渡収入は、8,147億元、前年同期比-6.7%と減少が続いている。
12.今後の見通しと中国政府の政策
今後の中国の経済成長の見通しと中国政府の目標や政策を見ていく。まず、主要な国際機関等による中国の経済成長率見通しによれば、2024年は4%台の半ばから後半、2025年はやや減速し4%台前半と見込まれている(第I-2-3-20表)。
第Ⅰ-2-3-20表 中国の実質GDP成長率の見通し
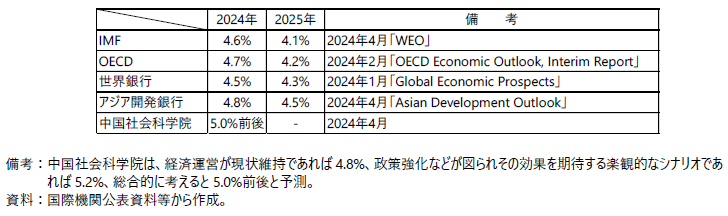
次に中国政府の経済運営方針を2024年3月開催の全国人民代表大会(全人代、我が国の国会に相当)における「政府活動報告」を基に見ていく。2024年の基本方針としては、昨年に引き続き「安定を保ちつつ前進を求める」という安定重視の姿勢が表明された。2024年の成長率目標は「5%前後」と昨年と同じ水準に設定された(第I-2-3-21表)。そのほかの主要な数値目標も公表され、都市部新規就業者は1,200万人前後、都市部失業率は5.5%前後、消費者物価上昇率は3%と、昨年と同じ目標が設定された(第I-2-3-21表)。
第Ⅰ-2-3-21表 中国の2024年の主要数値目標
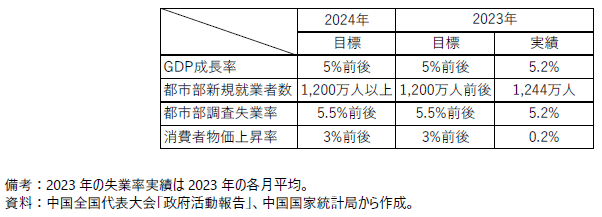
財政については、財政赤字の対GDP比の目標を3%程度とした。昨年も3月の全人代においては3%とされていたが、10月に災害復旧や防災のため1兆元の新規国債の発行が決定されたため、最終的な赤字幅は拡大した。今回の全人代では、重要な国家プロジェクトのために数年連続して超長期特別国債を発行する方針が公表され、まず2024年は1兆元が発行されることになった。地方政府特別債は3兆9,000億元と、昨年から1,000億元増額した。