CONTENTS
1.「ADの調査対象となった場合の対応」シリーズ~第Ⅷ回 仮決定・重要事実開示等への対応~
~第Ⅸ回 最終決定後への対応~
2.相談窓口
3.FAQ
1.「ADの調査対象となった場合の対応」シリーズ
~第Ⅷ回 仮決定・重要事実開示等への対応~
今回は、AD調査の終盤における手続についてご説明します。順に、仮決定、暫定措置、価格約束、重要事実開示です。
これまでご紹介した申請書、調査開始公告、公聴会等から得られる情報はあくまで申請者が主張する情報であり、調査当局の考えについては、調査当局からの追加質問状や、公聴会での発言ぶり等から推測し得る程度でした。しかし、仮決定に関する公告又は報告書は、調査開始後、ダンピング・マージンの算定方法や損害・因果関係の決定理由等について初めて調査当局の判断が公にされる機会であり、調査対象企業にとっては非常に重要です。
上記の通り、仮決定の公告又は報告書には、「事実及び法令に係る問題であって調査当局が重要と認めたすべてのものに関して得られた認定及び結論を十分に詳細に記載」しなければなりません。具体的には、ダンピング・マージンの算定方法、損害・因果関係等の争点について、申請者の主張、各調査対象企業の主張、そしてそれらを踏まえた調査当局の判断が記載されるのが普通です。
仮決定の後、利害関係人に反論の機会を与える国は多くありますので、調査対象企業側の主張が理由なく却下されていないか、不合理な認定がないかを確認しましょう。
各要件についての留意点は第Ⅰ回・第Ⅴ回等ですでに解説していますが、例えば、ダンピング・マージンの算定に関しては、輸出価格と正常価額の比較は公正に行われるものとするとされており(AD協定2.4条)、比較される取引段階が同一になっているか(通常は工場渡し段階)、物理的特性が異なるような産品間で比較が行われていないかなど確認することが考えられます。また、損害に関しては、国内産業の損害の状況を示す指標が改善しているにもかかわらず損害が認定されていないか、国内産品との価格比較において、恣意的な方法で比較が行われていないかなどを確認することが考えられます。
仮決定後に出された意見によって、最終決定のダンピング・マージンの認定が仮決定時のものから変わることもあります。仮決定の内容に問題があると思われる場合には、反論を提出することをお勧めします。また、政府意見書も、このタイミングで出すことが一般的とはいえませんが、仮決定にAD協定上の過誤があると思われるような事例であれば改めて発出することも可能ですのでご相談ください。
暫定措置(provisional measures)とは、調査当局が、AD調査期間中、最終決定前に、暫定的にAD課税を始めることをいいます(AD協定7.1条)。名称が紛らわしいですが、仮決定(preliminary determination)とは別の手続です。調査完了後に課税するというAD手続の原則に対する重大な例外であり、調査対象企業への影響も大きいので、下記のような厳格な要件のもと例外的に認められます。
① 調査開始が公告され、利害関係者に意見表明の機会が与えられたこと(AD協定7.1条(i))
② 調査開始から60日以上が経過したこと(AD協定7.3条)
③ ダンピング、損害、因果関係の各要件を認定する仮決定が行われたこと(AD協定7.1条(ⅱ))
④ 損害が調査中に生ずることを防止するために暫定措置が必要であると調査当局が認定したこと(AD協定7.1条(ⅲ))
⑤ 最終決定までのできる限り短い期間であること(AD協定7.4条)(※原則4ヶ月以内だが、対象産品の輸出の大部分を占める輸出者か
ら要請があった場合は6ヶ月以内。ただし、ダンピング・マージンより低い額のAD税の賦課を検討する場合にはそれぞれ6ヶ月以内・9
ヶ月 以内まで延ばせるとされる。)
⑥ 最終決定でAD税を賦課しない場合は徴収済み暫定課税の全額を、暫定措置の税率を下回るAD税のみ賦課する最終決定である場合はそ
の差額を、それぞれ迅速に還付すること(AD協定10.3条・10.5条)
上記③の要件から、暫定措置は、仮決定を前提として、その後に行われることがわかりますが、仮決定の時期は調査当局によって異なる
ため、暫定課税が賦課される時期も様々です。AD課税を申請する輸入国の国内生産者としては、可能な限り早期のAD課税開始を求める
のが自然であり、申請書に暫定措置を望む旨の記載がある場合もあります。申請書にこうした記載を見つけた場合には、早めに暫定措置を講じる必要性はない、暫定措置が必要な理由の説明が不十分である等の反論を行いましょう。
また、上記⑥の要件について、最終決定の税率が暫定措置の税率を下回る場合には、その差額は還付されます(AD協定10.3条)。他方、最終決定の税率が暫定措置の税率を上回る場合は、その差額は徴収されません。また、AD税を賦課しない旨の最終決定が出た場合は、全額還付(暫定措置の形式は暫定的な課税のほか、現金の供託、債券等による保証によることができるとされているところ(AD協定7.2条)、現金は還付、債券等の担保は解除)されます(AD協定10.5条)。暫定措置が取られたとしても、引き続き調査対象企業にとって有利な最終決定になるよう反論することは有用です。
価格約束のメリットは、AD調査を早期に終了させることで、AD調査自体の影響(輸出先の企業との取引が停止してしまう等)を軽減できることです。また、輸出の都度輸入国の税関でAD税を賦課・納入するよりも、「ダンピングによる損害が除去されると認める」輸出価格を約束した方が、税関手続上も企業のレピュテーション上も有利であるという判断もあり得ます。
ただし、価格約束を認めるか否かは調査当局の裁量であり(AD協定8.3条)、輸出企業が価格約束を申し出ても、認められるとは限りません。また、約束するのは「ダンピングによる損害が除去されると認める価格」ですから、仮決定で大きなマージンが出ていれば、結局輸出価格の大幅な値上げを余儀なくされることに注意が必要です。
価格約束締結後、通常AD調査は終了しますが、輸出者の希望や当局の決定によっては、最終決定まで調査が継続する場合があります。万一最終決定で否定的な結果が出た場合には、約束は自動的に消滅します(AD協定8.4条)。
通常、価格約束の期間は、AD税の課税期間と同じ期間(通常5年間)になると思われます。この間、輸入国は、約束の履行の確認のために、輸出者に定期的に情報を求めることができ、約束違反があった場合には、違反があった時点からAD税が賦課される可能性があります(AD協定8.6条)。他方、輸出者の方から価格約束の内容の見直しを求めることも認められています(AD協定11.2、11.5条)。
調査当局は、最終決定を行う前に、「検討の対象となっている重要な事実であって、確定的な措置をとるかとらないかを決定するための基礎とするもの」を利害関係者に通知しなければなりません(AD協定6.9条)。これを重要事実開示といいます。重要事実開示は、あくまで情報開示手続であって調査当局の判断内容の公表ではありませんが、上記の通り、開示の対象は「検討の対象」及び「決定するための基礎とするもの」であり、その選定の仕方によって調査当局の最終決定における判断内容とその理由がある程度明らかになります。仮決定がない場合は、調査当局の判断を事前に知ることができるのはこの重要事実開示のタイミングしかなく、また、調査の手続内で反論できる最後の機会になります。また、仮決定があった場合には、仮決定後に出された利害関係者の意見・反論に調査当局がどう対処したかを知る機会にもなります。
重要事実開示の際は、利害関係者が「自己の権利を擁護するための十分な時間的余裕をもって行われる」(反論等の機会の付与)とされているものの(AD協定6.9条)、実際の「時間的余裕」は各国実務により様々で、最終決定の数日前に重要事実開示がなされる例もあります。短期間でも十分な反論を準備できるよう、これまでお伝えしてきたとおり調査の初期段階から反論ポイントを検討しておくことは重要です。
一方で、重要事実開示において、ダンピング・マージンや損害、因果関係で当然検討すべき事実関係をそもそも開示していない、十分検討されていないといった事情があれば、重要事実開示が不十分(AD協定6.9条の違反)として、そのこと自体が反論事項になりえます。
今回は、最終決定(AD税賦課が決定された場合)後の対応をご説明します。
多くの国では、調査当局による最終決定を踏まえて、調査当局以外の省庁(税関当局等)や上級庁による別途の課税決定を要します。実際の課税までの手続・期間は、輸入国の国内法・制度によって様々です。国によっては、調査当局が課税を決定しても、調査当局以外の省庁・上級庁の決裁の段階で判断が覆る場合もあります。
しかし、最終決定をもってAD調査は終了しているので、最終決定の内容について輸出企業が意見を表明する機会は原則としてありません。Ⅷ.4でご説明した重要事実開示が、輸出企業にとって、調査手続における最後の反論の機会になります。
ただし、ADのような専門的な手続について、そもそも輸入国の国内裁判所が公平な司法審査の場として適しているかどうかは、議論の余地があるところです。
賦課開始後、その賦課の継続の必要性につき疑義がある場合は、輸出企業として見直しを要求することができます(AD協定11.2条)。また、最終決定による課税期間は最大で5年とされていますが(AD協定11.3条)、その延長の要否を決定するためのサンセット・レビューと呼ばれる見直し調査が開始されることもあります。この場合、輸出企業は、初期調査と同様、質問状や公聴会等の対応を行います。
見直し手続の詳細については、第Ⅹ回でご説明します。
WTO紛争解決手続の利用は、日本政府による政策判断ですが、その適否の検討の際は、輸出企業とも意見交換を行うことが一般的です。
WTO提訴及びその後の訴訟手続にあたっては、事実関係(調査対象製品に関する情報や調査手続中に表明した輸出企業の意見の内容等)や、それを踏まえた訴訟戦略や法的論点の策定について、輸出企業と日本政府との間で多くの議論を重ねながら、対応します。特に、輸出企業が調査手続中に主張・反論していた事項が調査当局によって無視されたり、適切に判断されなかったりしたといった事情は、日本政府にとっても、WTO紛争解決手続における有力な主張になり得ます。上記の事情は、調査手続中の輸出企業の各種提出書面と、重要事実開示や最終決定書等を比較検討すれば、ある程度客観的に明らかになるからです。
ところが、現在、第二審の上級委員会は、2019年12月から機能を停止(上級委員が選任されていないため)しており、パネル判断が上訴されると上級委での審理待ちが続く(いわゆる「空(から)上訴」)状態になるという問題があります。この問題に対処するため、有志国が「多国間暫定上訴仲裁アレンジメント(Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement, "MPIA")」という枠組みを創設しました。上級委員会の機能が停止している間、MPIAに参加している加盟国との間の紛争については、上級委員会の代わりに仲裁手続きを第二審として利用し、空上訴を防ぐことになっています。日本は、2023年3月にMPIAに参加しました。現状、日本のほか、EU、中国、オーストラリア、カナダなど、53か国・地域が参加しており、これらの国のAD措置についてWTO紛争解決手続で争えば、同枠組みを使った解決を図ることができます。最近の例では、日本が中国による日本製ステンレス製品に対するAD措置をWTO提訴したDS601案件で、パネル報告書が2023年6月に公表され、翌月のDSBで採択されました(中国は上訴しませんでした)。現在は、中国がパネルによる是正勧告を履行するための期間となっています。
他方、日本企業に対するAD課税の例が多い米国、韓国、インド、インドネシア等は残念ながらMPIAには参加しておらず、これらの国との間の紛争で、措置の是正を勧告するパネル判断を得ても、それが空上訴され、紛争係属中のままAD税が課税され続けるリスクは存在します。他方で、AD措置の問題点を詳細に指摘するパネル判断が公開されるのは、輸入国にとって一定の心理的な圧力にはなりますので、パネル報告書も交渉の一材料としつつ、二国間で措置の是正を働きかけていくことは可能です。実際、MPIA参加国以外の国も当事国として参加する紛争におけるパネル報告書が上訴されずに採択され、紛争が解決した事例も最近はいくつか見られます。
Ⅷ.1 仮決定
Ⅷ.1.1 仮決定とは
仮決定(preliminary determination)とは、最終決定(final determination)の前に、調査当局が利害関係者から提出された証拠等を元に仮の判断を行うことをいいます。AD協定上義務づけられている手続ではないため、調査当局によって、最終決定の前に仮決定を行う場合もあれば、仮決定を挟まず、重要事実の開示(下記Ⅷ.4)を経てすぐに最終決定に進む場合もあります。また、仮決定を行う場合の決定時期も多様で、調査開始から約4ヶ月~6ヶ月後の国もあればさらに遅い時期に仮決定がなされる場合もあります。ただし、仮決定を行う場合には、「事実及び法令に係る問題であって調査当局が重要と認めたすべてのものに関して得られた認定及び結論を十分詳細に記載」して公告するか、別途報告書の形にまとめて利害関係者へ送付しなければならないとされています(AD協定12.2条)。これまでご紹介した申請書、調査開始公告、公聴会等から得られる情報はあくまで申請者が主張する情報であり、調査当局の考えについては、調査当局からの追加質問状や、公聴会での発言ぶり等から推測し得る程度でした。しかし、仮決定に関する公告又は報告書は、調査開始後、ダンピング・マージンの算定方法や損害・因果関係の決定理由等について初めて調査当局の判断が公にされる機会であり、調査対象企業にとっては非常に重要です。
Ⅷ.1.2 仮決定への対応
上記の通り、仮決定の公告又は報告書には、「事実及び法令に係る問題であって調査当局が重要と認めたすべてのものに関して得られた認定及び結論を十分に詳細に記載」しなければなりません。具体的には、ダンピング・マージンの算定方法、損害・因果関係等の争点について、申請者の主張、各調査対象企業の主張、そしてそれらを踏まえた調査当局の判断が記載されるのが普通です。 仮決定の後、利害関係人に反論の機会を与える国は多くありますので、調査対象企業側の主張が理由なく却下されていないか、不合理な認定がないかを確認しましょう。
各要件についての留意点は第Ⅰ回・第Ⅴ回等ですでに解説していますが、例えば、ダンピング・マージンの算定に関しては、輸出価格と正常価額の比較は公正に行われるものとするとされており(AD協定2.4条)、比較される取引段階が同一になっているか(通常は工場渡し段階)、物理的特性が異なるような産品間で比較が行われていないかなど確認することが考えられます。また、損害に関しては、国内産業の損害の状況を示す指標が改善しているにもかかわらず損害が認定されていないか、国内産品との価格比較において、恣意的な方法で比較が行われていないかなどを確認することが考えられます。
仮決定後に出された意見によって、最終決定のダンピング・マージンの認定が仮決定時のものから変わることもあります。仮決定の内容に問題があると思われる場合には、反論を提出することをお勧めします。また、政府意見書も、このタイミングで出すことが一般的とはいえませんが、仮決定にAD協定上の過誤があると思われるような事例であれば改めて発出することも可能ですのでご相談ください。
Ⅷ.2 暫定措置
暫定措置(provisional measures)とは、調査当局が、AD調査期間中、最終決定前に、暫定的にAD課税を始めることをいいます(AD協定7.1条)。名称が紛らわしいですが、仮決定(preliminary determination)とは別の手続です。調査完了後に課税するというAD手続の原則に対する重大な例外であり、調査対象企業への影響も大きいので、下記のような厳格な要件のもと例外的に認められます。 ① 調査開始が公告され、利害関係者に意見表明の機会が与えられたこと(AD協定7.1条(i))
② 調査開始から60日以上が経過したこと(AD協定7.3条)
③ ダンピング、損害、因果関係の各要件を認定する仮決定が行われたこと(AD協定7.1条(ⅱ))
④ 損害が調査中に生ずることを防止するために暫定措置が必要であると調査当局が認定したこと(AD協定7.1条(ⅲ))
⑤ 最終決定までのできる限り短い期間であること(AD協定7.4条)(※原則4ヶ月以内だが、対象産品の輸出の大部分を占める輸出者か
ら要請があった場合は6ヶ月以内。ただし、ダンピング・マージンより低い額のAD税の賦課を検討する場合にはそれぞれ6ヶ月以内・9
ヶ月 以内まで延ばせるとされる。)
⑥ 最終決定でAD税を賦課しない場合は徴収済み暫定課税の全額を、暫定措置の税率を下回るAD税のみ賦課する最終決定である場合はそ
の差額を、それぞれ迅速に還付すること(AD協定10.3条・10.5条)
上記③の要件から、暫定措置は、仮決定を前提として、その後に行われることがわかりますが、仮決定の時期は調査当局によって異なる
ため、暫定課税が賦課される時期も様々です。AD課税を申請する輸入国の国内生産者としては、可能な限り早期のAD課税開始を求める
のが自然であり、申請書に暫定措置を望む旨の記載がある場合もあります。申請書にこうした記載を見つけた場合には、早めに暫定措置を講じる必要性はない、暫定措置が必要な理由の説明が不十分である等の反論を行いましょう。
また、上記⑥の要件について、最終決定の税率が暫定措置の税率を下回る場合には、その差額は還付されます(AD協定10.3条)。他方、最終決定の税率が暫定措置の税率を上回る場合は、その差額は徴収されません。また、AD税を賦課しない旨の最終決定が出た場合は、全額還付(暫定措置の形式は暫定的な課税のほか、現金の供託、債券等による保証によることができるとされているところ(AD協定7.2条)、現金は還付、債券等の担保は解除)されます(AD協定10.5条)。暫定措置が取られたとしても、引き続き調査対象企業にとって有利な最終決定になるよう反論することは有用です。
Ⅷ.3 価格約束
価格約束(price undertaking)とは、調査対象企業がダンピングとそれによる損害を認め、ダンピング価格による輸出をしないこと、又は、ダンピング・マージンを生じないような価格でのみ輸出することを約束し、それと引き換えに、調査当局がAD税を課さずに調査手続を停止、終了する制度です(AD協定8条)。価格約束は、仮決定でダンピング及び損害が認められた後にのみ締結可能と規定されています(AD協定8.1条、8.2条)。価格約束は、輸出企業の側から申し出ることが多いですが、調査当局の側から価格約束を勧奨することも認められています(AD協定8.5条)。ただし、輸出企業が勧奨を受け入れる義務はありません。価格約束のメリットは、AD調査を早期に終了させることで、AD調査自体の影響(輸出先の企業との取引が停止してしまう等)を軽減できることです。また、輸出の都度輸入国の税関でAD税を賦課・納入するよりも、「ダンピングによる損害が除去されると認める」輸出価格を約束した方が、税関手続上も企業のレピュテーション上も有利であるという判断もあり得ます。
ただし、価格約束を認めるか否かは調査当局の裁量であり(AD協定8.3条)、輸出企業が価格約束を申し出ても、認められるとは限りません。また、約束するのは「ダンピングによる損害が除去されると認める価格」ですから、仮決定で大きなマージンが出ていれば、結局輸出価格の大幅な値上げを余儀なくされることに注意が必要です。
価格約束締結後、通常AD調査は終了しますが、輸出者の希望や当局の決定によっては、最終決定まで調査が継続する場合があります。万一最終決定で否定的な結果が出た場合には、約束は自動的に消滅します(AD協定8.4条)。
通常、価格約束の期間は、AD税の課税期間と同じ期間(通常5年間)になると思われます。この間、輸入国は、約束の履行の確認のために、輸出者に定期的に情報を求めることができ、約束違反があった場合には、違反があった時点からAD税が賦課される可能性があります(AD協定8.6条)。他方、輸出者の方から価格約束の内容の見直しを求めることも認められています(AD協定11.2、11.5条)。
Ⅷ.4 重要事実開示(最後の反論の機会)
調査当局は、最終決定を行う前に、「検討の対象となっている重要な事実であって、確定的な措置をとるかとらないかを決定するための基礎とするもの」を利害関係者に通知しなければなりません(AD協定6.9条)。これを重要事実開示といいます。重要事実開示は、あくまで情報開示手続であって調査当局の判断内容の公表ではありませんが、上記の通り、開示の対象は「検討の対象」及び「決定するための基礎とするもの」であり、その選定の仕方によって調査当局の最終決定における判断内容とその理由がある程度明らかになります。仮決定がない場合は、調査当局の判断を事前に知ることができるのはこの重要事実開示のタイミングしかなく、また、調査の手続内で反論できる最後の機会になります。また、仮決定があった場合には、仮決定後に出された利害関係者の意見・反論に調査当局がどう対処したかを知る機会にもなります。 重要事実開示の際は、利害関係者が「自己の権利を擁護するための十分な時間的余裕をもって行われる」(反論等の機会の付与)とされているものの(AD協定6.9条)、実際の「時間的余裕」は各国実務により様々で、最終決定の数日前に重要事実開示がなされる例もあります。短期間でも十分な反論を準備できるよう、これまでお伝えしてきたとおり調査の初期段階から反論ポイントを検討しておくことは重要です。
一方で、重要事実開示において、ダンピング・マージンや損害、因果関係で当然検討すべき事実関係をそもそも開示していない、十分検討されていないといった事情があれば、重要事実開示が不十分(AD協定6.9条の違反)として、そのこと自体が反論事項になりえます。
【今回のポイント】
○AD調査終盤の手続として、仮決定、暫定措置、価格約束、重要事実開示がある。
○仮決定と重要事実開示は、最終決定前に当局の判断をあらかじめ知ることができる機会であり、反論の機会としても利用すべき。
○仮決定と重要事実開示から最終決定までの期間は様々であり、非常に短い場合もあるので、調査の初期段階から指摘できるポイントは
精査しておくべき。
~第Ⅸ回 最終決定後の対応~
今回は、最終決定(AD税賦課が決定された場合)後の対応をご説明します。
Ⅸ.1 最終決定について
Ⅸ.1.1 最終決定とは
AD調査は、通常、最終決定(final determination)によって終了します。最終決定は、AD税賦課を決定するかしないかに関わらず、最終決定における「事実及び法令に係る問題であって調査当局が重要と認めたすべてのものに関して得られた認定及び結論を十分詳細に記載」してHP等に公告するか、あるいは別途報告書の形にまとめて利害関係者へ送付しなければならないとされています(AD協定12.2条)。この点は、仮決定の場合と同様です。ただ、最終決定の場合には、調査当局の調査内容及び結論は報告書の形にまとめられることがほとんどであり、この報告書をもって「最終決定」ないし「最終決定書」と呼びます。Ⅸ.1.2 最終決定から発動まで
最終決定においてAD税賦課が決定されたからといって、課税が即時に開始されるとは限りません。多くの国では、調査当局による最終決定を踏まえて、調査当局以外の省庁(税関当局等)や上級庁による別途の課税決定を要します。実際の課税までの手続・期間は、輸入国の国内法・制度によって様々です。国によっては、調査当局が課税を決定しても、調査当局以外の省庁・上級庁の決裁の段階で判断が覆る場合もあります。
しかし、最終決定をもってAD調査は終了しているので、最終決定の内容について輸出企業が意見を表明する機会は原則としてありません。Ⅷ.4でご説明した重要事実開示が、輸出企業にとって、調査手続における最後の反論の機会になります。
Ⅸ.2 最終決定後にとりうる手段
最終決定により調査手続は完結しており、課税を回避できる可能性は低いと言わざるを得ませんが、事後的にAD調査結果の不当性を主張する機会は以下の通り存在します。Ⅸ.2.1 国内裁判
輸入国の国内法次第ですが、AD税賦課の最終決定が輸入国の国内法に違反するとして、輸入国の裁判所に提訴することが考えられます。賦課決定は、行政機関による行政行為又は処分に当たり、多くの国で行政裁判や民事裁判での司法審査の機会が設けられています。AD協定でも、WTO加盟国はこうした「訴訟手続を維持」し、その訴訟手続は最終決定を行う当局から「独立したものとする」(AD協定13条)とされ、司法審査の中立性を確保しなければなりません。ただし、ADのような専門的な手続について、そもそも輸入国の国内裁判所が公平な司法審査の場として適しているかどうかは、議論の余地があるところです。
Ⅸ.2.2 ADの見直し手続
もう一つは、輸入国の国内法によって手続の詳細は異なりますが、AD税賦課決定に対する事後的な見直し手続(AD協定11条)を活用することです。賦課開始後、その賦課の継続の必要性につき疑義がある場合は、輸出企業として見直しを要求することができます(AD協定11.2条)。また、最終決定による課税期間は最大で5年とされていますが(AD協定11.3条)、その延長の要否を決定するためのサンセット・レビューと呼ばれる見直し調査が開始されることもあります。この場合、輸出企業は、初期調査と同様、質問状や公聴会等の対応を行います。
見直し手続の詳細については、第Ⅹ回でご説明します。
Ⅸ.3 政府の関与(WTO関連委員会での懸念表明、二国間での働きかけ、WTO紛争解決手続)
この段階では、輸出企業が活用できる手続はどうしても少なくなりますが、日本政府としての対応の余地は依然としてあります。輸入国政府に対する二国間での状況改善の申し入れのほか、年二回開催されるWTO AD委員会(AD協定16.1条)における「協定の実施・・・について協議する機会」の一環として、決定済みないし賦課中のAD課税について懸念を表明することもあり得ます。Ⅸ.3.1 WTO紛争解決手続の検討について
上記はあくまで輸入国に対しAD課税の問題点の自発的な是正を求めるものですが、問題点が改善されずに課税が開始され、その後も改善の見込みがなければ、日本政府によるWTO紛争解決手続の活用の検討も視野に入ってきます。WTO紛争解決手続の利用は、日本政府による政策判断ですが、その適否の検討の際は、輸出企業とも意見交換を行うことが一般的です。
WTO提訴及びその後の訴訟手続にあたっては、事実関係(調査対象製品に関する情報や調査手続中に表明した輸出企業の意見の内容等)や、それを踏まえた訴訟戦略や法的論点の策定について、輸出企業と日本政府との間で多くの議論を重ねながら、対応します。特に、輸出企業が調査手続中に主張・反論していた事項が調査当局によって無視されたり、適切に判断されなかったりしたといった事情は、日本政府にとっても、WTO紛争解決手続における有力な主張になり得ます。上記の事情は、調査手続中の輸出企業の各種提出書面と、重要事実開示や最終決定書等を比較検討すれば、ある程度客観的に明らかになるからです。
Ⅸ.3.2 WTO紛争解決手続の流れと留意点
紛争解決手続は、第一審:小委員会(パネル)、第二審:上級委員会、という二審制であり、パネル報告書/(上訴されれば)上級委員会報告書がWTO全加盟国の会合であるDSB(紛争解決機関)により採択された時点で最終判断となり、確定します。最終判断にAD措置の是正勧告が含まれている場合は、輸入国は一定期間内に是正勧告に基づいてAD措置を是正ないし撤廃する義務を負い、不履行の場合は申立国による対抗措置の対象となりえます。ところが、現在、第二審の上級委員会は、2019年12月から機能を停止(上級委員が選任されていないため)しており、パネル判断が上訴されると上級委での審理待ちが続く(いわゆる「空(から)上訴」)状態になるという問題があります。この問題に対処するため、有志国が「多国間暫定上訴仲裁アレンジメント(Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement, "MPIA")」という枠組みを創設しました。上級委員会の機能が停止している間、MPIAに参加している加盟国との間の紛争については、上級委員会の代わりに仲裁手続きを第二審として利用し、空上訴を防ぐことになっています。日本は、2023年3月にMPIAに参加しました。現状、日本のほか、EU、中国、オーストラリア、カナダなど、53か国・地域が参加しており、これらの国のAD措置についてWTO紛争解決手続で争えば、同枠組みを使った解決を図ることができます。最近の例では、日本が中国による日本製ステンレス製品に対するAD措置をWTO提訴したDS601案件で、パネル報告書が2023年6月に公表され、翌月のDSBで採択されました(中国は上訴しませんでした)。現在は、中国がパネルによる是正勧告を履行するための期間となっています。
他方、日本企業に対するAD課税の例が多い米国、韓国、インド、インドネシア等は残念ながらMPIAには参加しておらず、これらの国との間の紛争で、措置の是正を勧告するパネル判断を得ても、それが空上訴され、紛争係属中のままAD税が課税され続けるリスクは存在します。他方で、AD措置の問題点を詳細に指摘するパネル判断が公開されるのは、輸入国にとって一定の心理的な圧力にはなりますので、パネル報告書も交渉の一材料としつつ、二国間で措置の是正を働きかけていくことは可能です。実際、MPIA参加国以外の国も当事国として参加する紛争におけるパネル報告書が上訴されずに採択され、紛争が解決した事例も最近はいくつか見られます。
【今回のポイント】
○最終決定後は、国内裁判や各種見直し手続等の利用の可能性はあるが、調査中に比べ、意見表明の機会は減る。
○不当なAD措置が強行される場合には、政府による対応の余地があり、AD委員会での意見表明や二国間での働きかけのほか、WTO紛争
解決手続の利用も選択肢に入る。
2.相談窓口
経済産業省では、皆様からのアンチダンピング調査に関する個別相談を常時承っております。アンチダンピング措置は、海外からの不要な安値輸出を是正するためWTOルールにおいて認められた制度です。公平な国際競争環境が担保された中で、日本企業の皆様が事業活動を展開できるようにするためにも、アンチダンピングを事業戦略の一つとして捉えていただき、積極的に御活用いただきたいと考えております。申請に向けた検討をどのように進めればよいのか、複数の事業者による共同申請はどのようにすればよいのかなど、相談したい事項がございましたら、まずは気兼ねなく経済産業省特殊関税等調査室まで御連絡ください。
また、2023年7月から「ADの調査対象となった場合の対応」の連載を開始しておりますが、「日本企業がアンチダンピング調査の調査対象となった場合」の御相談は、経済産業省 国際経済紛争対策室まで御連絡ください。
経済産業省 貿易経済協力局 特殊関税等調査室
TEL:03-3501-1511(内線3256)
E-mail:bzl-qqfcbk@meti.go.jp
経済産業省 通商政策局 通商機構部 国際経済紛争対策室
TEL:03-3501-1511(内線 3056)
E-mail:bzl-wto-soudan@meti.go.jp
3.FAQ
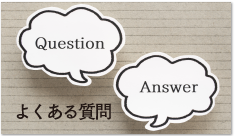
最終更新日:2025年3月26日