 |
 |
 |
 |
| 廃棄物の定義、廃棄物処理業者に対する許可、廃棄物処理施設の設置許可、廃棄物処理基準の設定などを規定した法律です。 |
 |
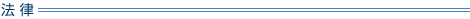 |
 |
| 正式名称 |
 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
| 改正法の施行 |
平成15年12月(平成15年6月公布) |
| 目 的 |
廃棄物の排出抑制、適正な処理(運搬、処分、再生など)、生活環境の清潔保持により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。 |
|
 |
| |
 |
| 「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって固形状又は液状のもの」と定義されています。言い換えると、占有者が自ら利用または他人に有償で売却することができないために不要になったものをいいます。
廃棄物に該当するか否かは、そのものの性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無および占有者の意志などを勘案して総合的に判断。例えば、野積みされた使用済みタイヤが約180日以上の長期間にわたり放置されている場合には、廃棄物とみなされます。
また、事業活動から生じる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、畜産業から排出される動物のふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、畜産業から排出される動物の死体など20種類の廃棄物を産業廃棄物とし、それ以外の廃棄物を一般廃棄物と定義しています。 |
 |
| |
 |
| (1) |
事業活動に伴い生じた廃棄物を自らの責任で適正処理、または文書で廃棄物処理業の許可を有する処理業者に委託。 |
| (2) |
産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度にのっとり排出事業者が最終処分まで把握することも義務付け。 |
| (3) |
多量排出事業者(前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上または前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上)は処理計画を作成。 |
| (4) |
廃棄物処理基準に従って行う焼却、他の法令による焼却、あるいは公益上、社会の慣習上やむを得ないもの等として政令で定める焼却を除き、廃棄物を焼却することを禁止し、罰則の対象となる。 |
|
 |
| |
 |
| 家電リサイクル法、容器包装リサイクル法で定められたリサイクルを行う際にも本法により廃棄物処理施設の許可が必要です。 |
 |
| |
 |
| 廃棄物処理業・施設の許可を不要とする特例制度として、広域再生利用指定制度、再生利用認定制度があります。 |
 |
| 廃棄物処理業・施設に関する特例制度の概要 |
 |
広域再生利用指定制度 |
再生利用認定制度 |
| 特例の内容 |
| ● |
一定の条件を満たす廃棄物の再生利用を行う者について、廃棄物処理業の許可を不要とする。 |
|
| ● |
一定の廃棄物の再生利用について、その内容が基準に適合していることを環境大臣が認定。認定を受けた者は、廃棄物処理業及び廃棄物処理施設設置の許可を不要とする。 |
|
対象となる
廃棄物 |
| 〈一般廃棄物〉 |
| ● |
広域的な再生利用に対する環境大臣の指定(廃スプリングマットレス) |
| ● |
家電リサイクル法に係る収集運搬を行う運輸事業者に対する環境大臣の指定 |
| ● |
再資源化等に協力することが適切である製造業者等に対する環境大臣の指定(廃パソコン、廃二次電池) |
| ● |
廃タイヤの処理について産業廃棄物処理業の許可を受けていること等の要件を満たせば、一般廃棄物処理業の許可が不要 |
| 〈産業廃棄物〉 |
| ● |
広域的な再生利用に対する環境大臣の指定(廃パソコン、石膏ボード、廃パチンコ等) |
|
| 〈一般廃棄物〉 |
| ● |
廃ゴムタイヤ(セメント原材料として再生利用) |
| ● |
廃プラスチック類(製鉄還元剤として再生利用) |
| ● |
廃肉骨粉(セメント原料として再生利用) |
| 〈産業廃棄物〉 |
| ● |
廃ゴムタイヤ(セメント原材料として再生利用) |
| ● |
廃プラスチック類(製鉄還元剤として再生利用) |
| ● |
建設無機汚泥(スーパー堤防の築造材として再生利用) |
|
|
 |
| 廃棄物処理法 [html] [pdf] |
| 廃棄物処理法関連のページ(環境省)へリンク |