| ■EUの取り組み事例 |
 |
| ■EUの取り組み |
| ●3Rに関する個別法令 |
| ○EUの容器包装に関する指令 |
| 1. |
包装廃棄物指令発行の背景 |
EUでは「包装および包装廃棄物に関する欧州議会および理事会指令(European Parliament Council Directive 94/62/EC of 20 December, 1994 on packaging and packaging waste)」(以下、包装廃棄物指令とする)が発行され、加盟国においては、各国内法により施行されている。
包装廃棄物指令は、ドイツ、フランスなど一部の国で既に実施されていた包装廃棄物に関する政令と政令に基づくリサイクルシステムが構築・運用されていたために、EUとして包括的な指令を作成するにあたって、加盟国間の意見調整が難航した。
このような背景の下で作成された包装廃棄物指令では、加盟国政府に対して、リサイクルシステムの構築や目標提示といったガイドラインのような内容となっている。
|
| 2. |
包装廃棄物指令の概要 |
| (1) |
指令におけるリサイクルのしくみ |
EUと加盟国政府と加盟国内のリサイクルシステムの関係は下図のようになっている。
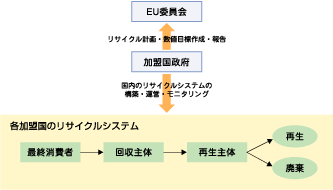
|
| (2) |
関係者の役割 |
① 加盟国政府
各加盟国政府は以下の内容を実施することが求められている。
・リサイクル目標達成のための計画と数値目標の作成、実施状況に関する欧州委員会への報告義務(欧州議会が5年毎にレビューし改定)
・目標達成のための具体的な措置、回収、再生、リカバリー・システムの創生
・包装のリサイクルに関する表示および識別システムの整備
・自国リサイクルの現状に関するデータシステムの構築、情報公開
・包装のライフサイクル分析などにおける基準の統一
② 生産者の役割
本指令で求められている対策を実施するにあたり、廃棄物に対する責任を負う事が必要であり、かつ、本指令に規定されている対策を加盟国が達成するためにあらゆる関係者の密接な協力が必要とされている。
加盟国では、国内の回収・再生システムを構築するため、以下の措置を行うこととなっている。
・包装や包装廃棄物の処理を最適化するため、最終消費者から包装廃棄物を回収、再利用、再生、回収を行う。
・関係事業者や公的機関が回収・再生システムに参加するようにする。
・輸入商品を含め全ての包装および包装廃棄物に適用できる回収・再生システムとするため、取引上の障壁や包装される商品の安全性、財産権の保護などを考慮の上、障害を回避する。
また、リサイクルシステム構築に関して、以下のような情報提供を十分に行うこととなっている。
○ 消費者に対して
・回収・再生システムに関する情報
・包装使用者の役割に関する情報
・包装物のリサイクル表示の意味などに関する情報
○ 加盟国政府に対して
・回収・リサイクルに関する国内データベース作成への協力
|
| (3) |
目標とするリサイクル率 |
2001年6月までに以下のリサイクル率を達成することとしている。
・包装廃棄物の回収率 :50%~65%(重量比)
・リサイクル率 :25%~45%(重量比)
・包装材ごとのリサイクル率 :15%以上(重量比)
|
| (4) |
リサイクル率の達成状況 |
1994年のEU指令における目標リサイクル率は、2001年6月末までに達成するように規定されている。99年末に欧州委員会が実施した調査によると、素材のリサイクルについては指令が実施される4年前に全ての加盟国で達成されていたとのことである。
|
| 3. |
包装廃棄物指令の改正 |
| (1) |
目標とするリサイクル率 |
1994年の指令における目標リサイクル率は2001年6月に目標値を引き上げることとなっており、2001年12月7日付けで指令94/62/ECの改正案が提案された。この改正案を基に、2004年2月18日付けで発効された。
EU加盟各国は2008年12月31日までに以下の目標を達成することが義務付けられた。尚、ギリシャ、アイルランド、ポルトガルおよび5月にEUに加盟する10カ国は2011年~2015年までにこの目標を達成しなければならない。
・包装廃棄物全体の回収率 :60%以上(重量比)
・リサイクル率 :55%~80%(重量比)
・包装材毎のリサイクル率 ;品目ごとに以下のとおり(重量比)
・廃ガラス 60%
・古紙/ダンボール 60%
・金属 50%
・廃プラスチック 22.5%
・木材 15%
|
| (2) |
その他の留意点 |
この改正では、エネルギー回収を伴う焼却は引き続き本指令における廃棄物回収目標達成にカウントされる。ただしこの点については別の声明の中で、できるだけ早い段階で見直すことを公約している。
欧州委員会は2005年6月30日までに実施状況を報告する必要があり、「廃棄物排出抑制に関する追加措置」、「包装に関する環境指標の策定」、包装廃棄物の排出抑制計画、リユースの促進、製造者責任、そして2010年までに包装材中の有害科学物質削減あるいは段階的な廃止に取り組む必要があるとされている。
EU各国政府および欧州議会は遅くとも2007年12月31日までに、2009年~2014年における新たな回収およびリサイクルの目標を決定することとなっており、これらは5年ごとに見直しを繰り返すこととなっている。
|
 |
| ○EUの使用済み自動車に関する指令 |
| 1. |
使用済み自動車指令の概要 |
使用済み自動車(ELV:End of Life Vehicles)に関する指令は2000年5月に加盟国の関係閣僚理事会と欧州議会の間で合意が得られ、2000年9月に成立、翌月の10月に発効された。本指令は各加盟国で実施されている廃車リサイクルを調和させて、環境保全と省エネルギーに貢献するとともに、EU内での競争上の不公平を回避することを考慮したものである。また、リサイクルに適した車輌構造、廃車の引き取り規制、廃車処理施設の環境基準、リサイクル達成目標を加盟国間で統一することも目指している。
本指令では、メーカーが廃車の最終所有者から引き取ることを原則としており、これらに必要となるコスト負担は全てメーカーが行うこととされている。また、本指令のもう一つの重要事項として、車輌製造において重金属(鉛、カドミウム、水銀、六価クロム)は認められた用途以外では使用禁止とされた。
本指令が求める使用済み自動車リサイクルシステムは下図の通りである。
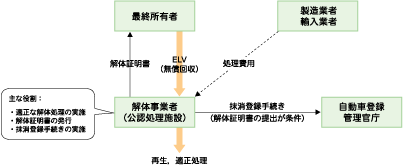
|
| 2. |
関係者の役割 |
加盟国は18ヶ月後にあたる2002年4月までに本指令に基づく国内法、規制および規定を発効させることが必要とされた。各関係者別の具体的な役割は以下のとおりである。
|
| (1) |
加盟国政府 |
-
・全てのELVが公認処理施設に引渡されることの保証
-
・処理業者の公認制度の保証
-
・最終所有者に負担をかけないELV回収の保証
-
・製造業者が回収・処理費用の全てまたは相当部分を負担するシステムの保証
-
・リサイクル目標の設定
-
2006年1月1日までに、廃車の年間リサイクル率を平均重量比85%とする。うち80%はサーマルリサイクルを除くリサイクルにより確保する。
-
なお、1980年1月1日以前に製造された車輌のリサイクル率の目標値は加盟国の判断で低くできるが、リサイクル率は70%
-
2015年1月1日までに、廃車の年間リサイクル率を平均重量比95%とする。うち85%はサーマルリサイクルを除くリサイクルにより確保する。なお、このリサイクル目標は2005年末までに再検討される。
-
・リサイクル性の認証要件導入
-
・欧州委員会に対し3年ごとに実施情報を報告(第1回目の報告は、2002年4月1日から3年間の状況を把握したもの)
-
・解体証明書とリンクした抹消登録制度の設置
-
解体業者により発行される解体証明書の提示を条件とする抹消登録手続き
|
| (2) |
製造業者・輸入業者 |
-
・解体業者が廃車を引き取り処理する費用を全額あるいは多くの部分を負担
-
2002年7月1日から市場に出る車輌についてはその時点から適用
-
それ以前に市場に出ていた車輌については2007年7月1日から無償引取
-
・関連業者と協力してELVの回収・処理システムを構築
-
・リサイクル促進のため、解体業者に対して解体・保管・検査に関する情報を提供
-
製造業者は新車を上市後6ヶ月以内に有害物質の使用場所などを示す解体情報を提供する
-
・部品や材料のリサイクル性を高めるため識別しやすいように作成される表示規格を使用
-
・リサイクル性を考慮した設計と製造
-
・リサイクル製品や材料の使用量増加
-
・有害物質使用の制限
-
2003年7月1日以降、認められた用途以外では鉛、水銀、カドミウム、六価クロムの使用は禁止される。
-
これらの使用条件は定期的に検討・改善される。
|
| (3) |
解体業者 |
-
・適正な解体処理の実施
-
・解体証明書の発行
-
・抹消登録手続きの実施
|
 |
| ○EUの廃電気・電子機器に関する指令類 |
廃電気・電子機器リサイクルについては、廃電気・電子機器の引き取り、リサイクルおよび処分に関する指令と電気・電子機器に使用される有害物質を制限する指令の2つが欧州委員会から2000年6月に提出され、2002年10月に欧州議会とEU加盟国政府は合意した。これら2つの指令案は「廃電気・電子機器(WEEE)指令2002/96/EC」と「電気・電子機器 への有害物質の使用制限(RoHS)指令2002/95/EC」として2003年2月13日に発効した。これを受け、加盟国では18ヵ月後である2004年8月13日までに国内で法制化が義務付けられた。これらの指令の実施最終期限は6年後とされている。
WEEE指令によると、加盟国ではその1年後の2005年8月13日までに最終所有者から廃電気・電子機器を無料で引き取る制度を導入することとなっている。
一方、RoHS指令によると、製造業者は2006年7月1日から販売される製品中の鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、難燃剤ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)およびポリ臭化ビフェニール(PBB)の使用を停止するよう定めている。
|
| 1. |
廃電気・電子機器(WEEE)指令 |
| (1) |
法的根拠 |
EU条約第175条(環境保護)に基づく指令であるため加盟国の裁量権が広く、国内事情に応じてより厳しい規則を導入できる。
|
| (2) |
適用対象製品 |
定格電圧が、交流1000V、直流1500V以下の電流・電磁界利用機器で、ANNEX IA/IBに示される以下の10製品群である。
| 製品群 |
具体例 |
| 1. 大型家電機器 |
冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、食器洗浄器、電気コンロ、電子レンジ、電気ストーブ、クーラーなど |
| 2. 小型家電機器 |
掃除機、ミシン、アイロン、トースター、コーヒーミル、電気かみそり、フォライヤー、目覚まし、はかり、など |
| 3. IT機器 |
中央処理装置、大型コンピュータ、パソコン、プリンター、モニター、キーボード、マウス、ノートブック型パソコン、PDA、コピー機、電気タイプライタ、小型計算機、ファックス、電話機、携帯電話、留守番電話機など |
| 4. 娯楽用電気機器 |
ラジオ、テレビ、ビデオカメラ、ビデオレコーダ、ステレオ装置、アンプ、電気式楽器など |
| 5. 照明器具 |
電球、蛍光灯など |
| 6. 電気電子工具 |
ドリル、のこぎり、研磨機、電気式ドライバー、溶接用工具、はんだ用工具、芝刈り機など |
| 7. おもちゃ、スポーツ器具 |
電気式鉄道モデル、ビデオゲーム機、自転車等の計器、電気式スポーツ器具、自動ゲーム機械など |
| 8. 医療機器 |
各種医療機器 |
| 9. 監視点検計器 |
サーモスタット、各種測定器(家庭用、実験室用)、煙探知機など |
| 10. 自動販売機 |
現金自動支払機を含めた各種自動販売機 |
ただし、これらの定義が明確でない部分があるため、境界線にある製品やグレーゾーンにある製品が多くでてきている状況にある。TAC(Technical Adaptation Committee:技術適用委員会)において、これらの問題について検討されている。
|
| (3) |
リサイクル目標 |
リカバリーはリユース、リサイクルおよびエネルギー回収を示すものと定義されている。
・一人あたり平均4kgをリカバリーする。(これは2008年末までに見直しされる。)
・リサイクル率は以下のとおりと規定されており、2006年末までに達成しなくてはならない。
表1
| 製品群 |
リカバリー率 |
リユースおよびマテリアルリサイクル率 |
| 1. 大型家電機器 |
80%以上(1台毎の平均重量比) |
75%以上(1台毎の平均重量比) |
| 2. 小型家電機器 |
70%以上(1台毎の平均重量比) |
50%以上(1台毎の平均重量比) |
| 3. IT機器 |
75%以上(1台毎の平均重量比) |
65%以上(1台毎の平均重量比) |
| 4. 娯楽用電気機器 |
75%以上(1台毎の平均重量比) |
65%以上(1台毎の平均重量比) |
5. 照明器具
蛍光灯 |
70%以上(1台毎の平均重量比)
--- |
50%以上(1台毎の平均重量比)
80%以上(重量比) |
| 6. 電気電子工具 |
70%以上(1台毎の平均重量比) |
50%以上(1台毎の平均重量比) |
| 7. おもちゃ、スポーツ器具 |
70%以上(1台毎の平均重量比) |
50%以上(1台毎の平均重量比) |
| 8. 医療機器 |
70%以上(1台毎の平均重量比) |
50%以上(1台毎の平均重量比) |
| 9. 監視点検計器 |
70%以上(1台毎の平均重量比) |
50%以上(1台毎の平均重量比) |
| 10. 自動販売機 |
80%以上(1台毎の平均重量比) |
75%以上(1台毎の平均重量比) |
|
| (4) |
関係者の役割 |
① 製造業者
-
・電気・電子製品を解体、リサイクル構造とする
-
・単独あるいは複数業者により一般家庭由来の廃電気・電子機器の引き取りシステムを構築する
-
・一般家庭以外由来の廃電気・電子機器の収集は製造業者あるいは製造業者から委託された業者が行う
-
・2005年8月13日以降、一般家庭由来の廃電気・電子機器の引き取り、リサイクル、処理に必要となるコストを負担する。
-
2005年8月13日以前に上市されていた製品はコスト発生時に存在する全ての製造業者がシェアに応じて共同負担する。
-
生産者責任として無償引取りが必要とされており、その費用を別額として表示してはいけないこととされている。
-
2005年8月13日以降に上市する場合には、製造業者はリサイクル費用が保証されていることを製品に表示する必要がある。
-
・2005年8月13日以降、一般家庭以外からの廃電気・電子機器の引き取り、リサイクル、処理に必要となるコストを負担する。
-
・それ以前に購入されていた機器の同費用は排出者負担としてもよい。
-
・一般家庭ユーザーに対する、電気・電子機器製品中の有害物質についての情報、表示マークに関する情報を提供する。
-
・製品中の有害物質などの情報を上市語1年以内に処理業者へ情報提供する。
② 販売業者
-
・新製品と交換時に同機種あるいは同程度の機種の廃品を無償引取りする
③ 処理業者
-
・リカバリーに関する記録を付けること。
|
| 2. |
電気・電子機器への有害物質の使用制限(RoHS)指令 |
| (1) |
法的根拠 |
EU条約第95条(域内市場の統一)に基づく指令であるため加盟国の裁量権は限定されており、指令以上に厳しい規制を導入できない。
|
| (2) |
適用対象製品 |
WEEE ANNEX IA(表1)のうちの1, 2, 3, 4, 5, 6,7および10製品群に適用される。
2006年7月1日以前に上市した電気・電子機器のリユースおよび補修用スペアパーツなどは適用除外となる。
また、科学的な見地から、代替が不可能等の場合として小型蛍光ランプ中の水銀などANNEXに示されている製品での利用が認められている。
|
| (3) |
禁止物質 |
2006年7月1日以降に上市される電気・電子機器に対して使用してはいけない物質は以下のとおりである。
- 鉛
- 水銀
- カドミウム
- 六価クロム
- ポリ臭素化ビフェニル(PBB)
- ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)
但し、ここで示される「上市」の解釈として、最終所有者に販売される日、域内生産の場合は工場から出荷された日とも考えられるなど明確でないという問題がある。
|
| (4) |
禁止物質の閾値 |
RoHS指令で禁止される物質が、意図的な使用ではなく原材料自体に混入しているなどという場合の問題に対応するためRoHS指令第5条1.(a)には、自然に存在するレベルあるいは不純物のようなものについては許容するという「最大許容濃度」について示されている。
欧州委員会による2003年12月にTACへの提案では、上記禁止物質のうちカドミウムに対しては0.01%(重量比)、それ以外の物質はそれぞれ0.1%(重量比)とされている。
|
 |