| ■製品別にみた各国の取り組み |
| ●容器包装リサイクル |
| ○EU包装廃棄物指令 |
| ○PRO EUROPEによるグリーン・ドット |
| 1. |
PRO EUROPEとは |
1994年のEU包装廃棄物指令を受けて、各加盟国では国内における包装廃棄物の回収およびリサイクルシステムを構築した。
グリーン・ドットとは容器包装材に表示される商標(以下、マークという)で、このマークが容器包装材に表示されている場合、その容器包装材は使用後に収集されてリサイクルされることが保証されている(=収集・リサイクル費用が支払われている)ことを意味している。つまりこのマークは、マーク利用権を購入した企業だけが利用できるものであり、マーク利用権を購入し自社製品の容器包装材に表示することで、それらの容器包装材は収集されリサイクルされるシステムの中で利用されているものである。このグリーン・ドットシステムに参加する複数の企業から支払われるマーク利用料は、マーク付容器包装材を回収してリサイクルする費用として使用される。
PRO EUROPE(Packaging Recovery Organization EUROPE)は、このグリーン・ドットの普及と維持を目的として1996年に設立された組織である。もともとグリーン・ドットを利用したこのシステムはドイツの容器包装法を達成するためにドイツでDuales System(デュアルシステム)として運用されてきたものである。
以後、フランスのEco-Emballages、オーストリアのARA、ベルギーのFOST Plusなど各国のリサイクル機関が国内におけるグリーン・ドットの使用契約をPRO EUROPEと結んでいる。
現在ヨーロッパではEU加盟国の18カ国およびEU加盟国以外の3カ国、計21カ国がグリーン・ドットシステムに加入している。
|
| 2. |
PRO EUROPEの役割 |
PRO EUROPEはドイツで先行実施されていたDSD社(Duals System Deutschland AG)によるグリーンドットの譲渡を受け、以下のような役割を担っている。
- グリーン・ドットの管理、登録、保護、ライセンス運営
- EU包装廃棄物指令や予防・リサイクル戦略策定などへのロビー活動
- web運営など、メンバーへの情報提供
- 各種会議の開催などといった各国での経験・意見交換をするための場の提供
|
○ドイツ
・DSD社によるデュアルシステム
|
| 1. |
ドイツで流通する商品の容器包装材 |
ドイツでは商品の容器包装材に関する法律(ここでは、以下ドイツ容器包装法とする)があり、容器包装材メーカー、容器包装を利用する商品の製造者および輸入者はこの法律の適用対象者となっている。このドイツ容器包装法では、これらの対象者が製造・輸入した商品の使用済み容器包装材を引き取り、商品に利用する容器包装材の70%までリサイクル利用し、それらの証明書を提出することになっている。この法律に反した場合には罰金処分となる。
ドイツ容器包装法はドイツ市場を流通する商品の製造・輸入に関係する外国企業にも適用されるため、それらの企業が独自に収集、引き取り、リサイクルのシステムを構築するには多大な時間とコストが必要になると考えられるが、Dual System(デュアルシステム)というシステムが整備されており、このシステムを利用することが可能な状況となっている。
|
| 2. |
Dual System(デュアルシステム)とは |
Dual systemとは、自治体によって運営されている廃棄物処理システムとは別に、容器包装のリサイクルを実行するために構築されたシステムであり、DSD(Dual System Deutschland AG)社という非営利企業によって運営されている。
容器包装メーカーおよびそれを利用する商品の製造・販売・輸入者はDSD社が保有する「グリューネ プンクト(Gr?ne Punkt)」、つまりグリーンドット(緑の点)という商標利用の権利をDSD社から購入することにより、自社製品の容器包装にこのマークを表示できる。このマークの表示されている容器包装材は消費者によって分別されてDSD社によって引き取りされリサイクルされることになるが、これらの運営費は前述のマーク使用料によって賄われる。つまり、商品の容器包装の収集、輸送、選別・梱包、リサイクルは全て容器包装に関係する企業によって負担されている。
|
| 3. |
DSD社の役割 |
DSD社は、使用済み容器包装材の引き取りからリサイクルに至る全工程、つまり収集、輸送、選別・梱包、リサイクルを、マーク使用権を購入している企業に代わって実施する。
実際には、それぞれの工程ごとに実施企業と契約して運営管理のみを行っている。
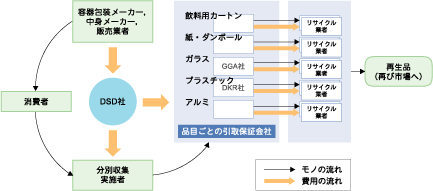
|
| (1) |
分別収集 |
分別収集は、家庭で分別された容器包装材について、DSD社が地域および品目ごとに個別契約を結んだ事業者あるいは自治体によって実施される。それに伴う費用はDSD社に集まるマーク使用料によって賄われている。
|
| (2) |
リサイクル |
① 引取保証会社
DSD社は品目ごとに引取保証会社と契約し各品目のリサイクルを委託している。例えばプラスチックについてはDKR(Deutsche Gesellschaft f?r Kunststoff-Recycling mbH)社と契約することにより、DKR社がプラスチックリサイクルの責任を果たす仕組みとなっている。
② リサイクル業者
品目ごとの引取保証会社はそれぞれ複数のリサイクル業者と契約を結び、リサイクル業者が分別収集された容器包装材から2次素材を製造することにより、使用済み容器包装材は再び商品として利用される。
リサイクル業者によるリサイクルが適正に実施されているかどうかについては、引取保証会社、技術検査協会および第三者監査法人による厳しい監査が実施され、監査に合格できない場合にはリサイクル業者と引取保証会社の契約は解除される。
|
| 4. |
Dual Systemへの消費者の関わり方 |
ドイツでは自治体により収集・処理される一般廃棄物は有料化されている。容器包装材については家庭で分別に取り組みDual Systemによる収集を積極的に活用することにより、ごみの排出費用を削減することができるため、消費者の分別排出に対するインセンティブにつながっていると考えられる。
|
| ・ドイツ強制デポジット |
| 1. |
デポジット制度導入の経緯 |
ドイツでは伝統的にリターナブル容器を保護する政策がとられてきたが、91年6月に施行された容器包装令はリターナブル容器よりワンウェー容器の普及を加速する懸念があった。実際、飲料用容器包装ではワンウェー容器の割合が増加してしまう傾向が見られるようになり、ドイツ政府はデポジット制度の導入を検討し始めた。
91年6月施行の容器包装令第9条は、リターナブル容器の割合がこの容器包装令施行時より下がった場合にはデポジット制度の導入を規定している。ただし、ここでの判断基準は91年時点でのリターナブル容器普及率となり。一部の容器にしかデポジット制度を導入できない。従って、ドイツ政府は容器包装令を改正することにより、容器の種類別にデポジット制度を導入することとなったが、2001年に提出された改正案に対して合意が得られず廃案となった。
しかし、2000年5月~2001年4月の容器包装のデータから、全ての飲料で91年のリターナブル容器の比率より低下していることが確認されたことから、2003年1月から強制デポジット発動が決定された。
対象容器となったのは、91年に比較してさほど比率が低下していないガス抜き飲料とワインを除き、ビール、ミネラルウォーターおよび炭酸清涼飲料とされた。
|
| 2. |
強制デポジット制度 |
強制デポジットシステムは下図のようになっている。リターナブルシステムでは、容器とデポジット料金の流れが完全に一致する仕組みとなっているのに対して強制デポジットシステムではそうではない部分がある。回収された容器は製造者に返して再使用する必要がなく、販売店から直接リサイクル業者に委託することが可能である。
販売店は自分のところで販売している製品の容器と同じ形状であれば、それが他店で販売されたものであっても引き取らなければならない。従って、販売店によっては、販売した量よりも多くの容器を回収することになってしまう店、あるいは販売量が回収量以下となってしまう店が出てくることになる。
このような販売店による金額差を精算するために、製造業者と販売業者はそれぞれ販売量と回収量のデータを精算機関に提出するような仕組みが構築されている。
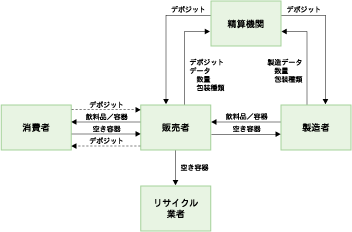
|
| ○フランス |
| 1. |
フランスの容器包装リサイクルシステム |
フランスでは、1992年4月に定められた「包装廃棄物に関する政令」に基づき、リサイクルが実施されている。
商品に利用されている容器包装材のメーカー、商品の中身メーカー、容器包装材を利用している商品の輸入業者は、家庭から排出される全ての容器包装材のリサイクルに対して責任をこととなっており、リサイクル実施方法としてデポジットシステムの導入による自主回収やEco-Emballages社によるリサイクルシステムに参加する方法が選択できるようになっている。
Eco-Emballlages社(以下、EE社とする)は、包装廃棄物に関する政令を達成するために認可された企業であり、フランスの容器包装材の80%はEE社によって運営されているシステムによってリサイクルされている。
|
| 2. |
Eco -Emballages (エコ・アンバラージュ)社のシステムとは |
| (1) |
エコ・アンバラージュ社の役割 |
① le point vert (ポアンヴェール)の管理
EE社によるリサイクルシステムに参加する企業は、ポアンヴェール、つまりグリーン・ドット(緑の点)というマークを商品の容器包装材に表示しEE社にマーク使用料を支払うことによってEE社によるリサイクルシステムが運営される。
② マーク使用料の管理
フランスでは、分別収集されたものは全て有価での取引となっているため、分別収集以降はすべて通常の取引で実施可能となっている。従って、マーク使用料として企業から徴収された料金は主に分別収集費用として利用されることとなる。
エコ・アンバラージュ社は非営利企業であり利益を出せないため、余剰金発生の場合は翌年度の準備金として利用し、不足の場合はマーク使用料を値上げすることにより収支のバランスをとるシステムとなっている。
③ リサイクル業者の管理
EE社では品目ごとにリサイクルの責任を負う引取保証会社と契約を行ってリサイクルを確実に実施できるように管理している。
|
| (2) |
分別収集 |
① 分別収集の実施者
フランスでの分別収集は従来どおり実施されてきた市町村による行政サービスの一環として実施される。市町村では主に業者への委託で分別収集が実施されている。
② 費用負担
前項にあったとおり、EE社のシステムを活用する自治体に対しては、分別収集費用の一部はEE社から資金援助がなされる。また、分別基準に適合している分別品に対しては、有価物として取引されるため買取料金が支払われる仕組みとなっている。
③ 選別・保管
フランス国内にある300ヶ所の選別センターに集積された分別収集品はさらに選別されてリサイクル業者へ引渡しされている。
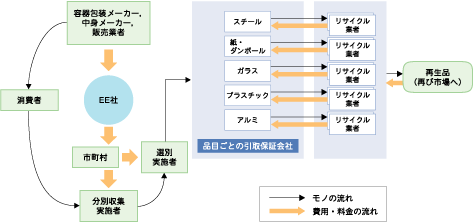
|
| ○スウェーデン |
| 1. |
REPAとは |
製造業者は容器包装の収集とリサイクルを運営管理する非営利目的の資材企業を容器包装材種別に5つ設立した。これら5つの企業はSvensk Kartongatervinning AB(ボール紙)、Plastkretsen(PK) AB(プラスチック)、Svenska MetallKretsen社(金属)、RWA Returwell社(段ボール)、Svensk GlasAtervinning社(ガラス)である。これらの企業はいずれも各関連業界の企業や団体などにより設立されている。
資材企業は収集およびリサイクルに関する調整、連絡を行うための共同会社としてSvenska Forpackningsinsamlingen社を設立した。
資材企業の運営資金は包装使用料(packaging fee)により賄われている。包装使用料は包装材の重量により、包装材への充填企業、その輸送企業、包装材製造業者から徴収されている。
ガラス以外の包装使用料は4つの資材会社が共同で設立したReparegistret 社(REPA:=Register for producer responsibility)に支払われる。 REPAは包装使用料の管理を行う非営利企業である。ガラス容器に関する包装税はREPAが管理しておらず、Svensk Glasatervinning(スウェーデンガラスリサイクル)自身が管理している。容器包装製造業者は包装税を納めることで製造者責任を果たしているとみなされる。
これらの関係を示したものが下図である。
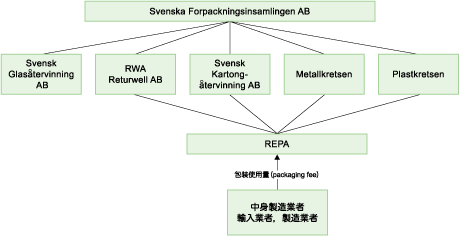
|
| 2. |
容器包装の収集方法 |
容器包装の収集は自治体あるいはこれら資材企業との契約業者により実施される。各自治体に契約業者が品目別に存在するようになっているが、自治体によっては複数の容器包装を扱う契約業者もいる。契約業者はリサイクルステーションの設置、収集/洗浄、除雪などを行うこととなっている。
REPAに属さず独自に収集システムを構築している製造業者は環境庁への結果報告が必要となる。
|
 |