第3節 欧州経済の動向
1.アフターコロナの経済動向と足下のウクライナ情勢
欧州では、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、多くの国で行動制限が長期にわたって実施されてきた。2021年春以降、行動制限が段階的に緩和されたことに伴い、経済活動が再開され、個人消費が持ち直したことから、ユーロ圏経済は、2021年第2四半期にはプラス成長へと回復した。その後も、経済回復のトレンドは継続していたものの、2022年2月24日のロシアによるウクライナ侵略を背景に、エネルギーや食品など幅広い品目の価格が大幅に上昇し、急激なインフレが家計を圧迫している。欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は、2022年3月に、「経済の先行きのリスクが高まっている。エネルギー・商品価格の高騰や国際貿易の混乱、信頼感の低下という形で、ロシアとウクライナとの戦争が、経済活動やインフレの動向に重大な影響を及ぼしている95」と指摘し、ウクライナ情勢による欧州経済への影響を警戒している。2022年3月発表の欧州中央銀行(ECB)のスタッフ経済見通しにおいても、2022年のインフレ率を5.1%と、2021年12月時点の3.2%から大幅に上方修正し、実質GDP成長率の見通しを3.7%と、昨年12月時点の4.2%から下方修正した。
(1)新型コロナウイルスの感染状況及びワクチン接種の状況
欧州各国では、2021年末からオミクロン株の感染拡大の勢いが鈍化し、2022年に入った後ピークアウトを迎えた(第Ⅰ-2-3-1図)。ワクチンの追加接種(ブースター接種)の効果により、重症者数の増加や医療体制の逼迫懸念が抑えられていることから、欧州各国は経済活動を優先し、水際対策や行動制限の緩和を進めている96。もっとも、2022年3月以降、既存のオミクロン株より伝播力が高いとされるステルスオミクロン変異株の感染者数が英国やドイツ、フランス等で拡大している。なお、ブースター接種人数の人口当たりの割合は、各国ともに2021年の10月から2月にかけて大きく増加したものの、2月以降は横ばいとなっている(第Ⅰ-2-3-2図)。
第Ⅰ-2-3-1図 欧州主要国の新型コロナ新規感染者数の推移(7日平均)
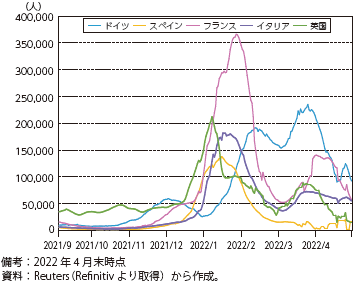
第Ⅰ-2-3-2図 欧州主要国のブースター接種人数の割合(人口当たり)
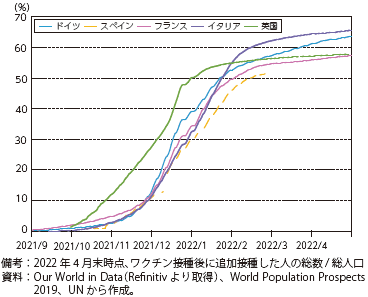
96 例えば、ドイツが3月18日に規制の全面解除を発表し、買物時のワクチン接種証明書の提示が不要となり、大規模イベントの開催も解禁された。フランスでは、3月14日からマスク着用義務が撤廃され、飲食店等で接種証明書を提示する義務もなくなった。イタリアでは、3 月末で非常事態が解除された。英国では、2月24日以降、陽性者の隔離義務が撤廃され、濃厚接触者となった場合のワクチン接種未完了者の隔離義務や接種完了者の7日間の検査実施推奨が終了した。
(2)GDPの動向
2021年は、各国で年初から新型コロナウイルス感染拡大の収束に目途が立たず、行動制限措置が継続された。サービス業の悪化やワクチン接種普及の遅れ等から、ユーロ圏経済は、第1四半期に2四半期連続でマイナス成長となり、景気後退に陥った。その後は、ワクチン接種の進展や行動制限の段階的緩和に伴う経済活動の再開により、サービス業を中心に個人消費が持ち直し、3四半期連続でプラス成長となった。
2021年末は、オミクロン株の感染拡大を受けた行動規制の強化がサービス消費を抑制したことから、個人消費が3四半期ぶりに低下したものの、その後は、供給制約が緩和に向かったことや、オミクロン株の感染拡大に対してロックダウンのような厳しい行動制限を実施した国が少なかったことを背景に、経済の回復基調は維持されていた。
2021年通年のユーロ圏実質GDP成長率は、前年比5.3%となったものの、前年にユーロスタットの統計開始以来、最大の落ち込み幅(-6.4%)を記録したことから、2021年の回復はその反動といえ、前年の落ち込み幅を挽回するまでには至っていない(第Ⅰ-2-3-3図)。
第Ⅰ-2-3-3図 ユーロ圏の実質GDP 成長率の推移(需要)
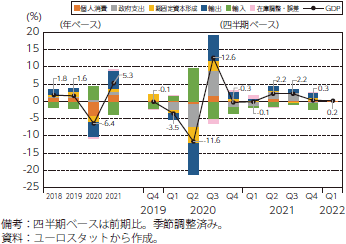
2022年は、2月24日のロシアによるウクライナ侵略に伴って先行きの不透明感が強まり、直近の2022年第1四半期のユーロ圏の実質GDP成長率は、速報値で前期比0.2%と低成長にとどまった。オミクロン株の感染拡大による行動制限が段階的に緩和されたものの、ロシアのウクライナ侵略に伴う資源高やサプライチェーンの混乱等の影響により、ユーロ圏経済の成長は鈍化した。
2022年第1四半期の実質GDPの水準を見ると、ユーロ圏及び英国ではコロナショック以前(2019年第4四半期)の水準まで回復した。ユーロ圏の主要国では、フランスのみがコロナショック以前の水準まで回復した(第Ⅰ-2-3-4図)(第Ⅰ-2-3-5図) 。
第Ⅰ-2-3-4図 ユーロ圏と英国の実質GDP の推移(国別)
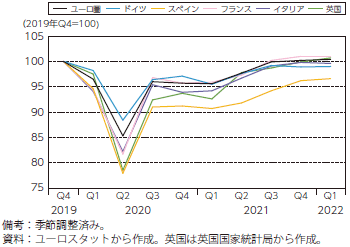
第Ⅰ-2-3-5図 ユーロ圏と英国の実質GDP 成長率の推移(国別)
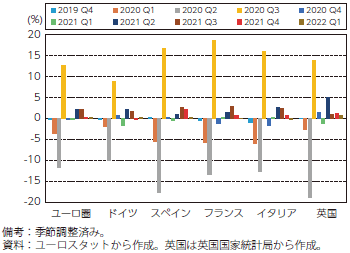
今後のユーロ圏経済の見通しは、新型コロナウイルスの感染状況の改善や、供給制約緩和に伴い、徐々に持ち直していくものと期待されるが、新たな変異株による感染再拡大のリスクや、ロシアのウクライナへの侵略に伴う不確実性の高まり、それに伴う天然ガス等のエネルギー価格を始めとする資源、原材料、食料、物流費等の価格上昇により、インフレ圧力が一層高まるリスクについて注視が必要である。
IMFの見通しによれば、2022年の実質GDP成長率は、ユーロ圏が2.8%、国別では、ドイツが2.1%、フランスが2.9%、イタリアが2.3%、スペインが4.8%と見込まれている。IMFは、ロシアによるウクライナ侵略がもたらす経済損失は、2022年に世界の経済成長が大幅に減速する一因となるほか、物価上昇を加速させると予測している97(第Ⅰ-2-3-7表)。
2022年のECBのスタッフ経済見通しは、ロシアによるウクライナ侵略後の状況変化を反映して、消費者物価(HICP)を昨年12月時点の3.2%から1.9%ポイント引き上げて5.1%、実質GDP成長率を4.2%から-0.5%ポイント引き下げて3.7%と予測している(第Ⅰ-2-3-6表)(第Ⅰ-2-3-7表)。
第Ⅰ-2-3-6表 欧州中央銀行(ECB)の経済見通し(%)
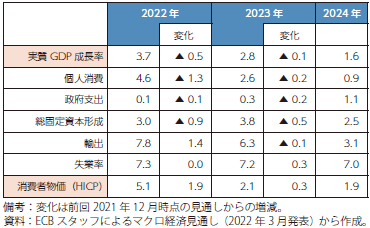
第Ⅰ-2-3-7表 国際機関の実質GDP成長率の見通し
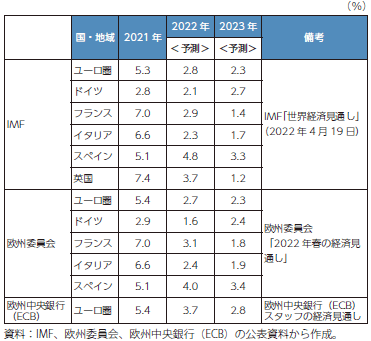
(3)生産の動向
ユーロ圏の鉱工業生産指数は、2021年に入った後、供給制約により生産が減少した月もあったが、その後は、供給制約の緩和と需要の拡大を背景に、堅調に推移している。他方、ウクライナ情勢の緊迫化により、サプライチェーンの混乱やエネルギー価格高騰によるコスト高などによって生産が停滞するおそれもあり、予断を許さない状況となっている(第Ⅰ-2-3-8図)(第Ⅰ-2-3-9図)。
第Ⅰ-2-3-8図 ユーロ圏の鉱工業生産指数の推移(国別)
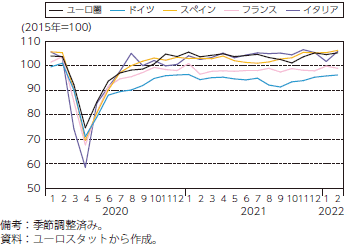
第Ⅰ-2-3-9図 ユーロ圏の鉱工業生産指数の推移(業種別)
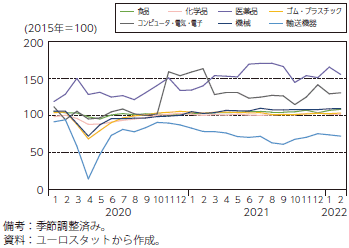
ドイツの乗用車の生産について見ると、2021年春以降、半導体や部品等の供給制約により生産が減少した。2021年の乗用車の生産は、8月を底に回復傾向を示しており、供給制約は次第に緩和する兆しが見られたものの、引き続き伸び悩み、新型コロナウイルスの感染拡大前の水準を下回って推移した。2021年通年のドイツの乗用車生産台数は、約310万4,600台と前年より-12%低い水準となった98。2022年には、1月~2月を合わせた乗用車生産台数が前年同期比でプラスに転じたが、ロシアによるウクライナ侵略や半導体等の供給不足の影響が反映された3月の乗用車生産台数は、前年同月比-29.3%の26万7,600台と大きく落ち込んでおり、先行き不透明な状況となっている(第Ⅰ-2-3-10図)(第Ⅰ-2-3-11図)。
第Ⅰ-2-3-10図 ユーロ圏主要国の自動車製造業生産指数の推移
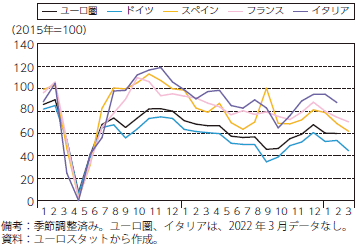
第Ⅰ-2-3-11図 ドイツの乗用車の生産、販売、輸出台数の推移
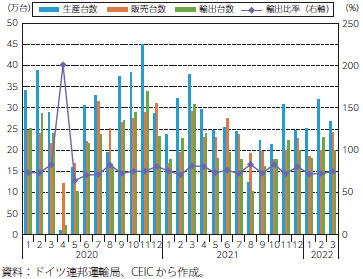
98 ドイツ自動車工業会(VDA)の速報値、マークラインズ(2022年1月6日公表)
(4)消費の動向
ユーロ圏の小売売上高は、2020年末に新型コロナウイルスの再度の感染拡大により、一部の国において行動規制が再強化され、消費者の慎重姿勢も高まったことから減少した。その後、2021年4月にロックダウンの影響を受け再度減少したが、以降は堅調な個人消費に支えられ、スペインを除き増加基調を維持し、同年12月はクリスマス商戦の時期にもかかわらず消費者物価の上昇などを背景に落ち込んだ。2022年に入ってからは小幅な上昇傾向が見られたが、ウクライナ情勢の影響を受けた同年3月に、前月比-0.4%と減少した。2022年3月時点の小売売上高指数は、ユーロ圏で2020年初の水準を超えており、国別でも、フランス、ドイツ、イタリアで同水準を超えている一方、スペインでは同水準を大きく下回る水準となっている。業種別では、非対面型の需要から好調を続けていた通信販売が、消費者が実店舗に購入ルートを戻す動きなどから、2021年半ばに減少し、それ以降は小幅な上下変動を伴いつつコロナ前よりも高い水準を維持している。今後は、エネルギー価格高騰など、ウクライナ情勢の深刻化に伴うインフレ圧力が家計の購買力を押し下げるリスクがある(第Ⅰ-2-3-12図)(第Ⅰ-2-3-13図)。
第Ⅰ-2-3-12図 ユーロ圏の小売売上高指数の推移(国別)
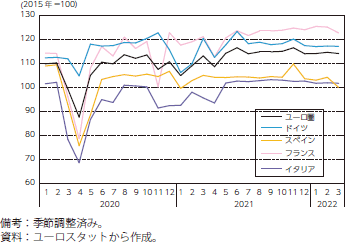
第Ⅰ-2-3-13図 ユーロ圏の小売売上高指数の推移(業種別)
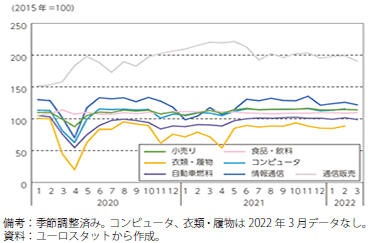
(5)消費者物価
ユーロ圏の消費者物価は2021年入り後から上昇を続け、2022年4月(速報値)は前年同月比7.5%を記録し、統計開始以来の上昇率を6か月連続で更新した。国別では、前年同月比で、スペインが8.3%、ドイツが7.8%、イタリアが6.6%、フランスが5.4%と、それぞれ大幅に上昇した。当初、2022年1月以降は、ドイツの付加価値税の減税終了に伴う反動の影響が剥落し物価上昇の勢いは和らいでいくものと見られていたが、ロシアによるウクライナ侵略を受けて、エネルギーや食品など幅広い品目の価格が大幅に上昇している(第Ⅰ-2-3-14図)(第Ⅰ-2-3-15図)。
第Ⅰ-2-3-14図 ユーロ圏の消費者物価上昇率の推移(国別)
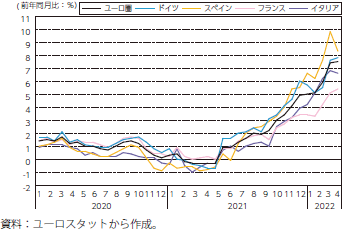
第Ⅰ-2-3-15図 ユーロ圏の消費者物価上昇率の推移(品目別)
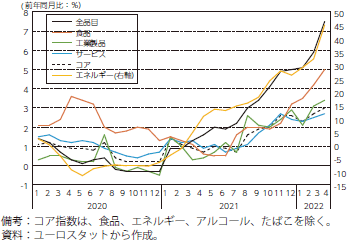
特に、エネルギー価格の大幅な上昇が見られる。2021年夏以降、天然ガス価格が上昇しており、欧州のエネルギー市場の天然ガス価格(オランダTTF)は、2022年3月7日に過去最高値の1メガワット時当たり200ユーロ台を記録した。経済活動の回復に伴う需要増加に加え、英国での風量不足による風力発電の出力低下、脱炭素の流れによる天然ガス生産の投資の減少等により価格高騰が進んでいた中で、2月24日のロシアによるウクライナ侵略により、欧州の主要な輸入元であるロシアからの供給不安と在庫の減少や、ロシアとドイツを結ぶ天然ガスパイプライン「ノルドストリーム2」の無期限停止99等の要因が加わり、天然ガスの価格変動に拍車が掛かっている。このような状況を受けて、欧州委員会は3月8日、2030年までにEU域内のロシア産化石燃料への依存解消と安価で持続可能なエネルギーの安定供給に向けた政策文書を発表し、エネルギー価格やガス貯蔵に関する新たな対応策を提案した100(第Ⅰ-2-3-16図)(第Ⅰ-2-3-17図)(第Ⅰ-2-3-18図)。
第Ⅰ-2-3-16図 天然ガス価格の推移(オランダ TTF)
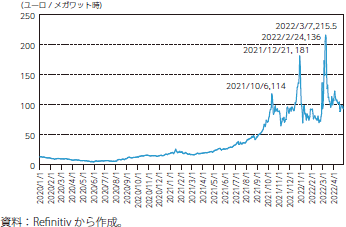
第Ⅰ-2-3-17図 欧州の一次エネルギー構成(2020年)
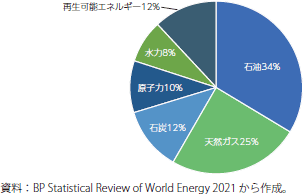
第Ⅰ-2-3-18図 EUの天然ガスの輸入先(2020年)
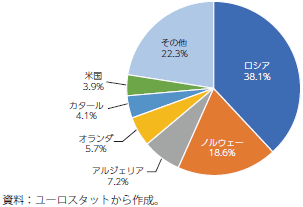
また、食料についても、2021年以降コロナからの急速な経済活動の再開により、世界的に需要が急増し、供給が不足する事態となっている中で、ロシアによるウクライナへの軍事侵略を受けて、価格がより一層高騰している。
99 ロシアがウクライナ東部の親ロシア派支配地域の独立を承認したことを受け、2022年2月22日ドイツのショルツ首相は、ノルドストリーム2のプロジェクト承認停止を明らかにした。ハベック経済相は記者団に対し、ノルドストリーム2による追加供給なしでもドイツへのガス供給は確保されるとしたが、短期的には価格は上昇するとの見方を示している。
100 JETRO 短信「欧州委、ロシア産化石燃料への依存からの脱却目指すエネルギー政策発表」(2022年3月11日)
(6)雇用
ユーロ圏の失業率は、2022年3月に6.8%と、統計開始以来の最低値を更新した。雇用情勢は、景気の回復を受け緩やかに改善が進んでいる。新型コロナウイルスに対する行動制限の段階的な緩和により、サービス業の雇用環境も回復してきている(第Ⅰ-2-3-19図)。
第Ⅰ-2-3-19図 ユーロ圏と英国の失業率の推移
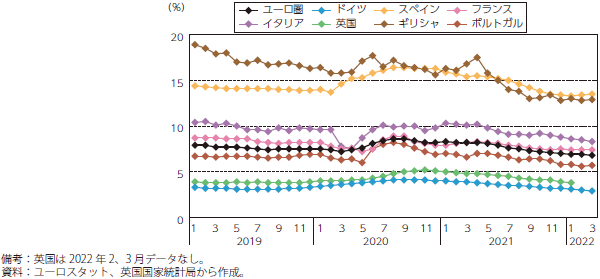
2.欧州経済の特徴と課題
(1)世界金融危機後とコロナショック後の経済回復過程の比較
2008年の世界金融危機後、欧州経済は、落ち込みから緩やかに回復したものの、その後の欧州債務危機の顕在化により、景気が急激に悪化した。財政健全化に向けた各国の財政引締め政策等の結果、需要が減退し、雇用の悪化や公共投資や民間投資の減少による域内の格差拡大を招き、景気は再び失速し、停滞状態が長期化した101。
世界金融危機およびコロナショックにより落ち込んだユーロ圏の実質GDPが、それぞれ危機前の水準に戻るのに要した期間について見てみると(第Ⅰ-2-3-20図)、コロナショックでは、世界金融危機後よりGDPの落ち込み幅がより大きかったにもかかわらず、危機前の水準までの回復に要した期間は、コロナショック後が7四半期と、世界金融危機後の10四半期と比べ短くなっている。これは、世界金融危機時の経験を教訓に、EUおよび各国政府、欧州中央銀行等が、大規模かつ迅速な対応を実施したことが寄与したものと考えられる。
第Ⅰ-2-3-20図 世界金融危機後とコロナショック後のユーロ圏の実質GDPの推移の比較
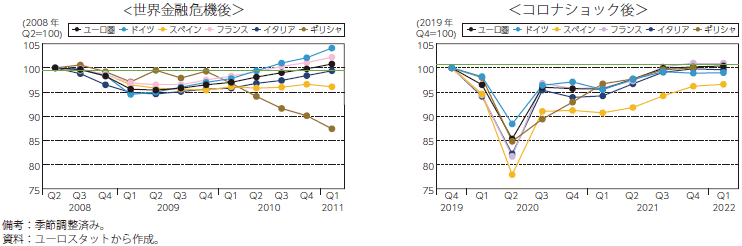
また、国別に見ると、世界金融危機後は、財政状況の悪化により、ギリシャやスペイン等の南欧諸国の一部では、GDPの回復が遅れた。自力での債務返済のための資金調達が困難となったギリシャはEUやIMFに支援要請を行ったほか、スペインは財政再建に加え住宅バブル崩壊の後遺症の影響も受けた。一方、コロナショックでは、欧州域内外で人の移動が制限されたことで、観光や小売、外食等のサービス産業が打撃を受け、特に観光業への依存度が高いイタリアやスペインへの影響が大きかった。ドイツでは、世界金融危機後は、外需と設備投資が景気回復をけん引し、個人消費が景気を下支えしたことから102、他国に比べ早期に回復したのに対し、コロナショック後は、コロナの感染拡大時のワクチン普及の遅れや半導体等の供給制約の生産活動への影響等があり、2022年4月末時点で、コロナショック前の水準まで回復が及んでいない。
101 伊藤さゆり(2021)
102 経済産業省(2011)『通商白書2011』
(2)EUのコロナショック対応の特徴
EUは、世界金融危機や欧州債務危機の教訓から、コロナショック時には、雇用の維持や企業の資金繰り支援のための大規模な財政・金融支援策を実施した。具体的には、EU国家補助規制の例外的容認や財政規律からの一時的な逸脱の許容といった財政ルールの柔軟化や、5,400億ユーロの危機対応の経済対策パッケージ103、7,500億ユーロの欧州復興基金といった政策支援(2018年物価による)により、加盟国に財政出動を促すとともに、加盟国間の格差是正に尽力した。さらには、欧州中央銀行(ECB)によるパンデミック緊急対策プログラム(PEPP)による資産購入や貸出条件付き長期資金供給オペ第3弾(TLTROIII)等の資金供給による金融政策が各国政府の取組を支えた。
103 EUの対コロナの経済支援策においては、雇用や事業を守るため総額5,400億ユーロの3つのセーフティーネット(1)欧州投資銀行(EIB)の支援による企業の保護、(2)欧州安定メカニズム(European Stability Mechanism=ESM)の支援による国家予算の保護、(3)欧州委員会が運用する一時的助成金による雇用と労働者の保護が策定された。このうち(3)のEU市民の失業や企業破綻のリスクを予防・緩和する「緊急時の失業リスク緩和のための一時的支援策(SURE: Temporary Support to mitigate Unemployment Risks an Emergency)」により、EUから加盟国に総額上限1,000億ユーロの融資が行われた。
(3)各国の財政措置
IMFのデータベースを基に、主要国のコロナショック対応のための財政措置の規模について、コロナショック発生直後の2020年6月時点と2021年10月時点で比較すると、英国、イタリア、フランス、スペインの財政出動の規模は大幅に拡大している(第Ⅰ-2-3-21図)。なお、欧州主要国の対応策の内容は、第Ⅰ-2-3-22表にまとめたとおりである。
第Ⅰ-2-3-21図 主要国のコロナショック対応時の財政措置の規模の比較(対GDP比)
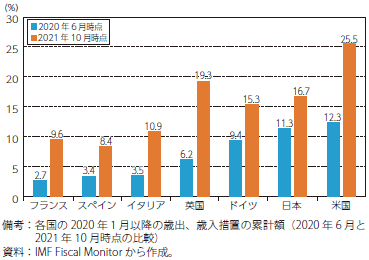
第Ⅰ-2-3-22表 欧州主要国のコロナショック対応時の財政措置の内容
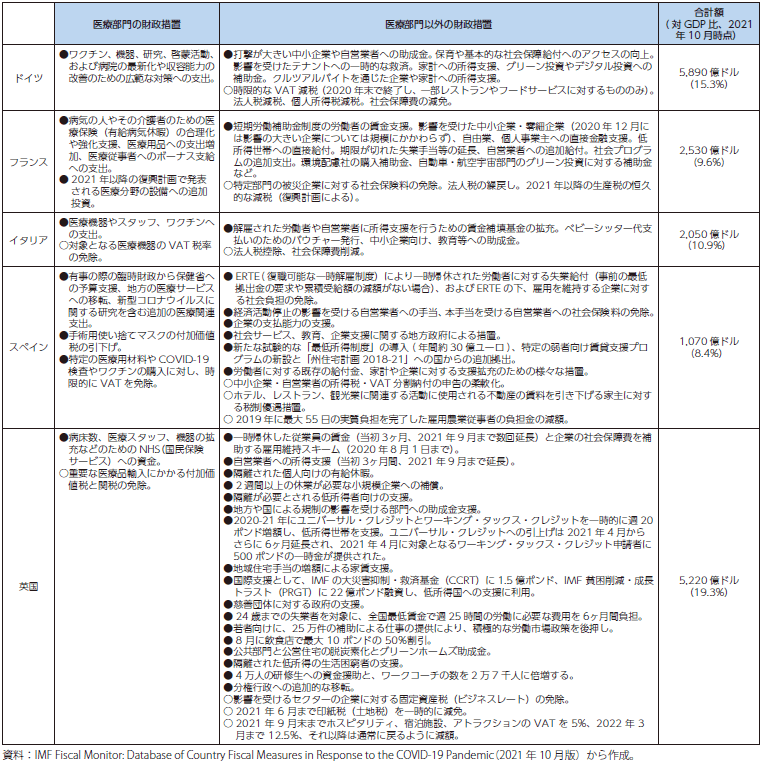
EUでは、ユーロの信認を守るため「安定・成長協定」の財政規律のルール上、加盟国の財政赤字を対GDP比3%以内、公的債務残高を対GDP比60%以内に抑えることとしているが、各国のコロナ対応の財政出動を促すため、2020年3月に2022年度までの一時的な逸脱を許容した104。2022年3月2日、2023年の財政政策ガイダンスに関する政策文書105を発表し、今後も経済成長に向けた公共投資を維持しつつ、政府債務残高のGDP比が高い加盟国に対しては、2023年から財政再建に向けて徐々にかじを切るべきであるとの方向性を示した106(第Ⅰ-2-3-23図)(第Ⅰ-2-3-24図)。
第Ⅰ-2-3-23図 ユーロ圏主要国の財政赤字の比較(GDP比)
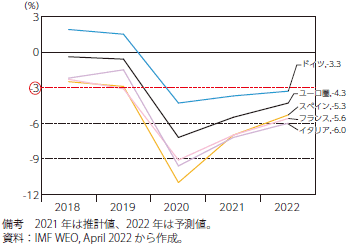
第Ⅰ-2-3-24図 ユーロ圏主要国の公的債務残高の比較(GDP比)
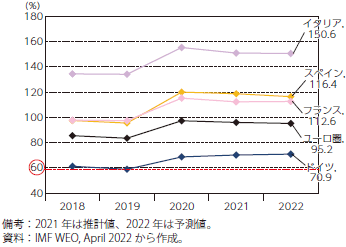
104 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/2_en_act_part1_v3-adopted_text.pdf![]()
106 JETRO短信「欧州委、成長投資を維持しつつ、2023年からの財政再建を加盟国に求める」(2022年3月4日)(https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/03/7af5f1a399e4d575.html![]() )
)
(4)新型コロナからの復興計画 「次世代のEU」((注)各金額は2018年物価による)
2020年7月21日、EUは特別欧州理事会で、1兆743億ユーロの「2021~2027年多年度財政枠組み(以下MMF)」と7,500億ユーロの復興基金「次世代のEU」の総額1兆8,243億ユーロ(約230兆円相当)のEU復興パッケージに大筋合意し、同年12月10日に欧州理事会で採択した。
MMFは、EUの最低5年以上(通常7年間)の期間の予算を規定する計画で、中期的なEU予算全体の歳出上限を設定している107。
また、復興基金の中核が、6,725億ユーロ(うち補助金:3,125億ユーロ、融資:3,600億ユーロ)の「復興強靱ファシリティ(以下RRF)」であり、コロナショックからの経済復興と構造改革の促進を目的とし、グリーン化やデジタル化への移行といったEUの共通課題に重点的に資金が配分されることになっている。具体的には、少なくともその37%以上をグリーン化に、20%以上をデジタル化に振り向けることが求められている(第Ⅰ-2-3-25図)(第Ⅰ-2-3-26図)。
第Ⅰ-2-3-25図 EU復興パッケージの構成
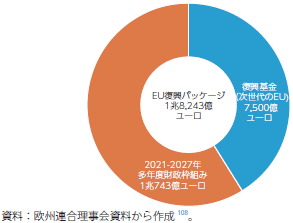
第Ⅰ-2-3-26図 復興基金(次世代のEU)の構成
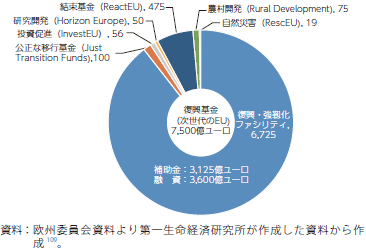
財源は、欧州委員会が復興基金の債券を発行し、市場から資金を調達することになっている。償還期間は2028年から2058年までの最長30年で、償還のための新たな財源として、プラスチック賦課金(2021年1月に導入済み)のほか、炭素国境調整措置の導入、排出量取引制度の拡充(対象を海運、陸上輸送、建築に拡大)、国際課税の見直しの「第1の柱」等が検討されている。
復興基金は、コロナショックへの対応のための一時的な措置との位置付けであるが、グリーンやデジタル化への移行といった各国の共通課題に基金の財源が活用され、域内の投資が拡大し、経済成長が高まることが期待されている。
復興基金による資金提供を受けるためには、各加盟国は、「復興・強靱計画(2021~2023年)」を作成し、欧州委員会による計画の適合性の審査と承認を受けることとなる。復興基金の補助金の配分状況を国別に見ると(第Ⅰ-2-3-27図)、金額ベースでは、イタリアとスペインへの配分が圧倒的に多いものの、対GDP比で見ると、南欧や中東欧の国への割り当てが手厚くなっており、経済規模が小さい国の経済復興や構造転換への支援効果が期待される。
第Ⅰ-2-3-27図 EU各国への復興基金の補助金の配分
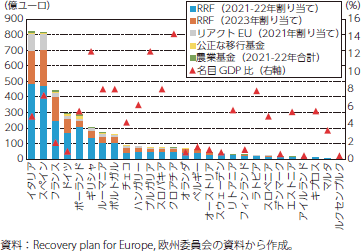
RRFのうち、補助金は、コロナによる打撃が大きい国や所得が低い国、失業率が高い国等に傾斜配分される。また、RRFとは別の補助金である「リアクトEU」は、コロナショックにより打撃が大きい国や地域の復興の支援、「公正な移行基金」は、化石燃料依存度の高い中東欧諸国等のグリーン化への移行の支援、「農村開発のための農業基金」は、農業従事者の支援等に充てられ、EU域内の格差是正効果が期待されている110。
次のグラフ(第Ⅰ-2-3-28図)は、欧州各国のコロナショック発生時(2019年第4四半期から2020年第2四半期までの期間)のGDPの減少率と、その後の回復時(2020年第2四半期から2021年第4四半期までの期間)のGDPの上昇率を比較したものである。コロナショック後の低下率を各グループの平均値で見ると、北欧や西欧に比べ、南欧と中東欧で落ち込みが大きかったが、2021年第4四半期までに、EU域内の全ての国で、減少幅を上回って上昇した。
第Ⅰ-2-3-28図 EU各国のGDP変化率の比較
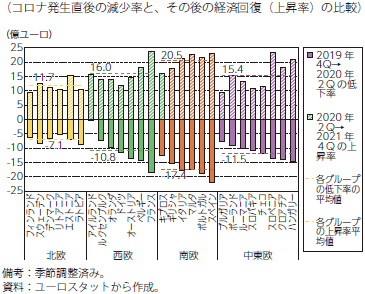
107 JETRO短信「2021~2027年中期予算計画とその背景を読み解く(EU)」(2020年9月23日)(https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2020/874b61dfcf80663b.html![]() )
)
110 伊藤さゆり(2021)
(5)EU離脱後の英国の貿易動向
① EU離脱後の概況
2020年1月31日、英国は、EUを離脱したが、EUと英国との間で締結された離脱協定により、緩和措置として同年12月末まで移行期間が設けられ、EUの単一市場と関税同盟にとどまった。その間、EUと英国の将来関係に関する新たな協定の交渉が行われ、交渉は難航を極めたが、移行期間終了間際の12月24日に「通商・協力協定(TCA)」が合意に達した。
同協定は、①自由貿易協定(FTA)、②市民の安全確保のためのパートナーシップ、③ガバナンスに関する水平的協定の3つの柱から構成されており、関税および関税割り当てが全品目で撤廃された。2020年中に、英国側の批准手続、EU側の暫定適用の手続が終了し、2021年1月1日から同協定の暫定適用が開始された。その後、欧州議会の同意を経て、同年4月29日にEU理事会が批准を決定し、同年5月1日に同協定は正式に発効した。
一方で、EU離脱協定に付随する北アイルランド議定書の運用については、北アイルランドは英国の関税領域でありながら、EU規則が適用されることになったため、グレートブリテン島から北アイルランドへの食品移送の際に、EUの衛生証明書が必要となり、その結果、北アイルランド内で物流の混乱や商品不足が発生するなどしている。同議定書の運用に関しては、EUと英国の間で協議が続いている111。
② 英国の貿易動向
英国の貿易の動向を見てみると、対世界では、貿易赤字の状態が続いている(第Ⅰ-2-3-29図)。2020年4月のコロナショック発生時と移行期間終了直後の2021年1月に、輸出入ともに前月比-20%を超える大幅な減少を記録したが、いずれも翌月以降回復を見せている。2020年4月以降は輸出入ともにやや減少傾向にあったが、足下では輸入が回復をみせている(第Ⅰ-2-3-30図)。英国国家統計局(ONS)は、輸入の増加については燃料の輸入増加によるものであり、輸出の減少は、歳入関税庁(HMRC)が最近実施したオペレーション上の変更によるものしている。
第Ⅰ-2-3-29図 英国の輸出額の推移112
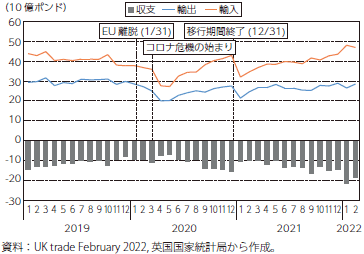
第Ⅰ-2-3-30図 英国の輸出入額の伸び率の推移
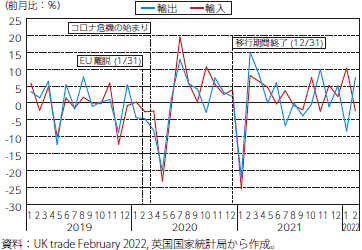
英国・EU間の輸出入は、2020年12月31日の移行期間終了後大きく落ち込んだ(第Ⅰ-2-3-31図)(第Ⅰ-2-3-32図)。その後、輸出は回復したものの、輸入は輸出ほど回復せず横ばい傾向となっていた。現時点で、EU離脱の影響と新型コロナウイルス感染症の第二波による影響を明確に切り分けることは困難であるものの、英国とEU間の輸出入の落ち込みは、同時期のその他の地域との貿易の落ち込みよりも大きく、EUとの貿易においては、新型コロナウイルスの感染拡大以外に、輸出入業者が移行期間終了に伴って発生した追加的な手続やコストの増加、国境通過に要する時間の増加等の困難に直面していることを示唆している。
第Ⅰ-2-3-31図 英国の輸入額の推移(対EUと非EU)
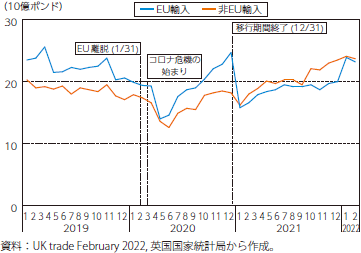
第Ⅰ-2-3-32図 英国の輸出額の推移(対EUと非EU)
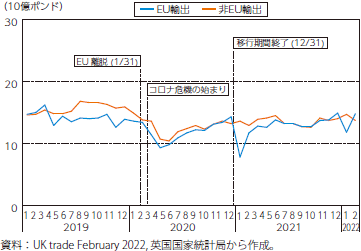
英国のEU離脱とその後の移行期間に加え、新型コロナウイルスの感染拡大、世界景気の低迷、サプライチェーンの混乱等の影響により、過去2年間の貿易統計のボラティリティがより大きくなっている。
こうした貿易の変動が、短期的な貿易の混乱や長期的なサプライチェーンの調整をどれほど反映しているのかを評価することは困難であるものの、ONSは景況感調査(BICS)において、2022年1月下旬から2月上旬にかけて、輸出業者の67%、輸入業者の72%が、追加的な書類作成、輸送費用や関税の変更等で困難に直面したと発表している113。
111 JETRO 世界貿易投資動向シリーズ
EU(https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/gtir/2021/31.pdf![]() )
)
112 Office of National Statistics, UK trade February 2022
(https://www.ons.gov.uk/releases/uktradefebruary2022![]() )
)
113 英国国家統計局「Business insights and impact on the UK economy」(10 February 2022) (https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/business/businessservices/bulletins/businessinsightsandimpactontheukeconomy/10february2022#business-insights-and-conditions-survey-data![]() )
)
(6)金融政策
① 欧州中央銀行(ECB)のコロナショックへの対応
ECBは、2022年3月10日の理事会で、記録的な高水準にあるインフレ率が、ロシアによるウクライナ侵略の影響により一層上昇する懸念から、量的緩和の縮小を加速させる方針を決定した。資産購入プログラム (APP) の終了を早め、購入額を、2022年4月に月額400億ユーロ、5月に300億ユーロ、6月に200億ユーロとし114、今後のデータ次第ではあるものの、早ければ7月~9月にも終了することを決定した。また、パンデミック緊急購入プログラム (PEPP) による資産購入については、以前の決定通り、2022年3月末で終了する方針を改めて確認した。主要政策金利については据え置き、利上げは、量的緩和終了後、しばらくしてから開始し漸進的なものになるとした。
4月14日の理事会では、ウクライナ情勢の緊迫化により経済の見通しの不確実性が高まる中でも、インフレ高進が根付く可能性を懸念し、3月会合にて決定した量的緩和策の段階的縮小方針を維持した。資産購入プログラム(APP)の終了時期については、具体的時期は明言せず、6月の理事会で協議する方針を再確認した。利上げについては、量的緩和終了後、しばらくしてから開始し、漸進的なものになるという方針を維持した。ラガルド総裁は、「景気の下振れリスクが大幅に高まった」旨と同時に「インフレ圧力が広がり、物価の上振れリスクが高まり、インフレ期待が高まる兆しに注意が必要」と景気減速とインフレ高進の双方向のリスクに言及しつつ、 「不確実性の高い現在の状況を踏まえ、金融政策における選択性、漸進性、柔軟性を維持する」と述べており、景気や株式市場の下振れリスクを警戒しつつ、資源価格高騰による物価の上振れリスクが顕在化した際にも柔軟な対応ができるよう、利上げ開始のタイミングの自由度の確保を図ったものと見られる(第Ⅰ-2-3-33表)。
第Ⅰ-2-3-33表 欧州中央銀行(ECB)のコロナ対応
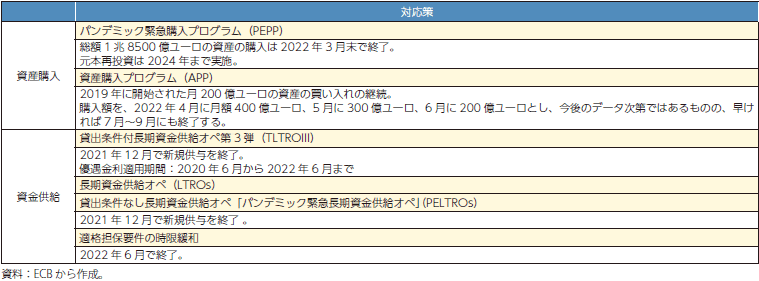
② イングランド銀行(BOE)のコロナショックへの対応
2022年5月4日のイングランド銀行(BOE)金融政策委員会は、政策金利を0.25ポイント引き上げ、1.0%に決定した。2021年12月から4会合連続で利上げを実施しており、政策金利は、2009年以来の水準となった(第I-2-2-34図)。
第Ⅰ-2-3-34図 イングランド銀行の政策金利の推移(%)
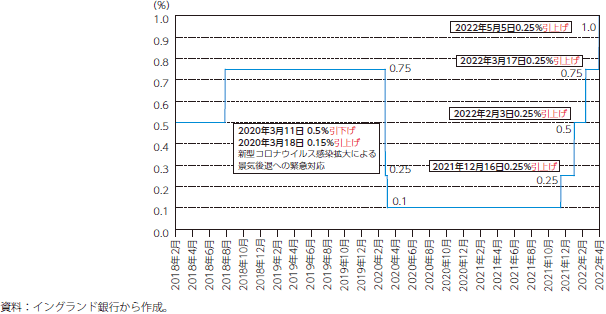
英国の3月の消費者物価指数は、前年同月比で0.8ポイント上昇し+7.0%となり、約30年ぶりの高水準を更新した(第Ⅰ-2-3-35図)。これを受けて、BOE金融政策委員会は、ロシアのウクライナ侵略により、エネルギーや食品を含むその他の商品価格が大幅に上昇していると判断し、インフレ率が2022年4月から6月の期間に8%程度に達し、今年後半には一層上昇するとインフレ率の見通しを引き上げていた。
第Ⅰ-2-3-35図 英国の消費者物価指数の推移
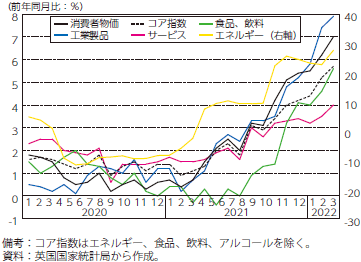
114 2021年12月の会合で、APPの購入額を、当時の月額200億ユーロから、2022年4~6月に400億ユーロ、7~9月に300億ユーロに一時的に増額し、10月以降は200億ユーロとすることを決定していた(2月会合では維持)。
3.欧州の成長戦略等
EUは、欧州経済の復興と成長のため、グリーン化とデジタル化への移行を政策の中心的な柱とし、様々な施策や方針を相次いで打ち出している。特にグリーンや人権といった共通価値に関する取組のルールづくりで先行することにより、新たなグローバルスタンダードの構築を主導する動きが伺える。炭素国境調整措置等はその一例といえる。こうしたEUの政策動向は、EU市場でビジネスを行う日本企業を含む外国企業にも影響を及ぼすことから、その動向を注視する必要がある。また、中国等、EU域外の特定国への依存度の低減を目指し、戦略的自律の必要性を強調した産業政策や通商政策を展開していることも特徴である。ここでは、EUおよび欧州主要国の成長戦略について概観する。
(1)EUの成長戦略
2019年12月に就任したフォン・デア・ライエン欧州委員長は「欧州グリーンディール」(グリーン化)や「デジタル時代にふさわしい欧州」(デジタル化)を含む6つの優先課題を提示した(第Ⅰ-2-3-36表)。
第Ⅰ-2-3-36表 欧州委員会の6つの優先課題
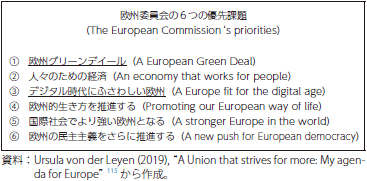
①グリーン化政策
優先課題の一つに挙げられている「欧州グリーンディール」(グリーン化)は、「2050年までの気候中立(温室効果ガスの排出量実質ゼロ)」を拘束力のある目標とし、EUを資源効率的で、競争力のある公正で繁栄した社会に変えることを目指すものである。2019年12月に、欧州委員会は、それを題した「欧州グリーンディール」の成長戦略を取りまとめた。成長戦略では、2050年までの温室効果ガス排出実質ゼロ、経済成長の資源利用からの分離、現代的で資源効率の高い競争力のある経済の実現、人々の健康と幸福の環境リスクからの保護等により、EUを公正で豊かな社会に変えることを目指すとされている。
2021年7月には、「欧州気候法」が成立し、2030年までに温室効果ガス排出量を1990年比で55%の削減を法的拘束力のある目標とすることが正式決定された。EUは同月、目標の達成に向けて「Fit for 55パッケージ」を発表し、2035年までに内燃機関車販売禁止や炭素国境調整措置等、既存法の改正や新法を含む13の法案を提案した(第Ⅰ-2-3-37表)。また、12月には既存法改正、新法案を含む4法案からなる「Fit for 55パッケージ」第二弾も公表されている(第Ⅰ-2-3-38表)。
第Ⅰ-2-3-37表 Fit for 55 パッケージ(2021年7月14日発表)の概要
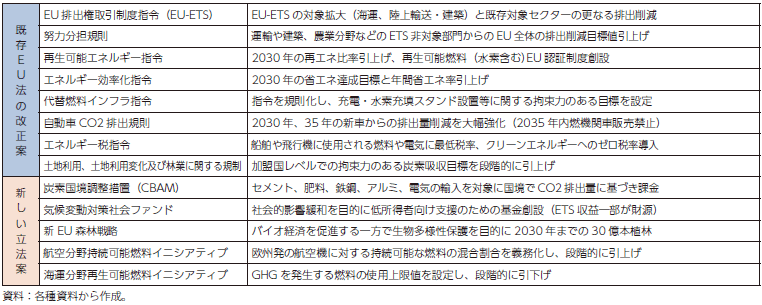
第Ⅰ-2-3-38表 Fit for 55 パッケージ第二弾(2021年12月15日公表)の概要
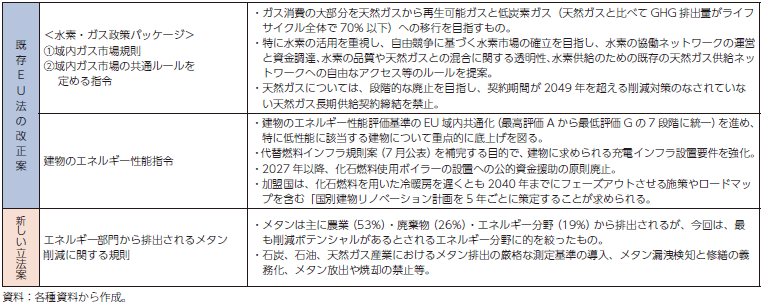
② デジタル化政策
欧州委員会は、デジタル化は、人々を優先し、企業の新たな機会を開く万人に有益なものとすべきとの考えの下、万人に恩恵をもたらすデジタル変革に向けての取組を進めている116。2020年2月、EUは、「欧州のデジタルな未来の形成」と題した「デジタル戦略」を発表した。同戦略では、人間を中心に据えたデジタル技術の構築、公平で競争力のあるデジタル経済の成長、民主的で持続可能な社会への貢献、デジタル市場における世界的リーダーの地位確立等の目標が提示されている。
また、2021年3月、EUは2030年までの10年間を「デジタルの10年」とし、市民や企業などのデジタル技能や対応力を高めるための施策を推進すると発表した。そこでは、インターネットの世界で「EUの主権を確立」し、人間中心で持続可能なデジタルの未来の実現を目指す「デジタルコンパス」が策定され、具体的な取組の指針が示されている。
③ 新産業戦略
2020年3月、欧州委員会は、「新産業戦略」を策定した。同戦略は、①欧州の産業競争力の維持、②欧州グリーンディール、③欧州デジタル化への対応を3本柱として、欧州産業の世界におけるリーダーシップ向上を目指すものとなっている。
さらに、2021年5月には、「2020年産業戦略アップデート」を公表し、①単一市場の強靱性の強化、②戦略分野の特定国への高依存への対処、③グリーン・デジタル移行の加速の重要性について強調した(第Ⅰ-2-3-39表)。また、コロナショックから学んだ教訓を新たな産業戦略に反映し、当初の産業戦略で掲げた「気候変動やデジタル化に対応した社会への移行」という優先課題を再確認しつつも、「開かれた戦略的自律性」の強化を図っていくことが目的として設定されている。
第Ⅰ-2-3-39表 2020年産業戦略アップデートの概要
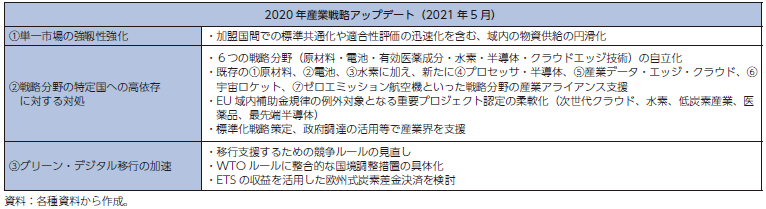
同戦略では、「原材料、電池、有効医薬成分、水素、半導体、クラウドエッジ技術」といった6分野で特定国への依存の低減を目指し、具体的には、半導体や電池、水素といった戦略分野を重点的かつ包括的に支援する「産業アライアンス」の形成を進めるとされている(第Ⅰ-2-3-40表)。また、EUでは、域内市場の公平な競争環境確保の目的で加盟国政府による特定企業への補助金支援を禁じているものの、EUにとって重要な政策であり、便益が反競争的効果を上回る範囲において、「欧州共通利益に適合する重要プロジェクト(IPCEI)」により、国家補助を認める例外規定を設けている117。
第Ⅰ-2-3-40表 主要な産業アライアンスの概要
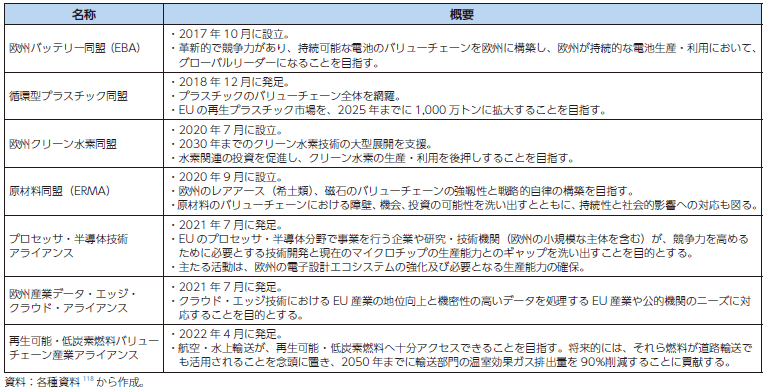
さらに、2022年2月、欧州委員会は、半導体のEU域内供給を強化し、2030年までに世界市場の20%のシェアを目指す欧州半導体規則案を公表した。同規則案は、半導体を重要な戦略分野と捉え、民間企業に対する補助金ルールの例外規定を活用することにより域内の新規工場建設に対し補助金の交付を可能とする等、EU域内のサプライチェーンの強靱化と欧州の戦略的自律に向けた政策が挙げられている。
④ 通商戦略
2021年2月、欧州委員会は、新たな通商戦略「開かれた、持続可能で主張する通商政策119」を発表した。同戦略は、「開放性」、「持続可能性」「EUの利益の擁護」120を3つの柱とし、①グリーンおよびデジタル化の目標に沿ったEU経済の回復と根本的な転換の支援、②より持続可能で公正なグローバリゼーションのための世界的ルールの形成、③EUの利益を追求し、必要な場合は自律的に権利を行使する能力である「開かれた戦略的自律」の向上をその目的として明示している。
また、EUが今後、通商政策において優先する6つの課題として、①WTO改革、②グリーン化への移行と持続可能なバリューチェーンの推進、③デジタル化への移行とサービス貿易の推進、④EU規制の影響力の強化、⑤近隣諸国やアフリカとの関係強化、⑥通商協定の実施・執行の強化による公平な競争条件の確保が挙げられている。
航空機大手への補助金問題の解決や鉄鋼・アルミ追加関税賦課の停止等、EUと米国間の最近の通商問題については、急速に両国の関係に進展がみられた。2021年9月には、米国ピッツバーグにおいて、「第1回米国EU貿易技術評議会(TTC)」が開催され、新興技術の管理や国際的な通商課題での米国とEUの協力について議論された。
また、EUは、2021年9月、欧州委員会と外務・安全保障政策上級代表は、同地域との協力強化のための「インド太平洋地域における協力に関するEUの戦略」を公表し、インド太平洋におけるEUのプレゼンスの向上を目指している。
なお、中国との間で2020年末に大筋合意に至ったEU中国包括的投資協定については、新疆ウイグル自治区の人権状況を巡り、欧州議会の審議が凍結されており、早期の発効に見通しが立たない困難な状況となっている。
⑤ イノベーション戦略(ホライズン・ヨーロッパ)
EUでは、域内企業のイノベーションのための戦略も進めており、1984年以降、研究開発支援プログラムとして、多年次の資金助成枠組み計画を作成し、実行してきている。2021年からは、第9次の枠組み計画にあたる「ホライズン・ヨーロッパ(2021年~2027年)」121が開始されている。
直面する社会課題に対応し、基本的価値を共有する国々との国際連携を通じて欧州の国際競争力の強化を図ることを目的に、EUの多年度財政枠組み(MMF)に復興パッケージ「次世代のEU」からの50億ユーロを加え、2027年までの7年間で総額955億ユーロの予算が確保されている。同計画は、①卓越した科学(フロンティア研究支援)、②グローバルチャレンジ・産業競争力(社会課題の解決)、③イノベーティブ・ヨーロッパ(市場創出支援)の3本柱122で構成されており、また、グリーン化やデジタル化といった欧州グリーンディールへの対応を優先し、予算額の35%を充当することとしている。
注目される施策としては、トップダウンにより特定された課題につき、ロードマップに従い社会実装を進める「ミッション方式プログラム」や複数の産官学がパートナーシップを形成して推進する「パートナーシップ方式」の導入のほか、スタートアップ支援強化のため「欧州イノベーション会議(EIC)」を設立し、革新的アイディアや技術を持つスタートアップの技術開発や商業化、スケールアップを支援し、ハイリスクな投資への支援を強化することが挙げられる。
116 JETRO海外調査部ブリュッセル事務所(2021)「EUデジタル政策の最新概要」
(https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/0a88cad7cdac3e5a/20210038.pdf![]() )
)
117 欧州委員会の承認を得ることで国家補助ルールを緩和し、複数の加盟国による共同支援等を可能とするとともに、最大で費用の全額を支援する。基本的には欧州委員会が策定した産業戦略等に基づき対象分野を選定し、産業界から幅広くメンバーを募りコンソーシアム形式にて研究開発を実施する。
119 An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy
120 JETRO海外調査部ブリュッセル事務所(2021)「EUの新通商戦略および最近のFTA動向」
122 日欧産業協力センター、Horizon Europeのサイト、(https://www.ncp-japan.jp/about/![]() )
)
(2)欧州主要国の成長戦略
① ドイツ
ドイツでは、2005年から16年間首相を務めたアンゲラ・メルケル氏が退任し、2021年12月8日、社会民主党、自由民主党、緑の党の3党の連立によるショルツ新政権が発足した。新政権の外務大臣には、人権や環境等を重視し、中国との関係について厳しい姿勢を示している緑の党の共同党首、ベーアボック氏が就任した。また財務大臣には、健全財政を唱える自由民主党のリントナー党首が就任し、財政赤字拡大に一定のブレーキをかける役割を果たすとみられている。環境政党の緑の党と産業界に近い自由民主党は基本的な考え方に隔たりも多く、今後の政権運営に課題も多いと見られる。
2021年11月、3党は共同記者会見を行い、「さらなる進化に挑戦する 自由・正義・持続可能性のための連立」と題する連立合意文書を発表した(第Ⅰ-2-3-41表)。連立合意文書の主な内容として、①2045年まで気候中立を実現する、②2030年までに1,500万台の電気自動車の普及を目指し、2035年に内燃機関搭載車の新規登録を禁止する(ただし、e-fuelを燃料とする車両の新規登録は認める)、③コロナショック対応で免除してきた債務ブレーキを2023年から再適用する、④法定最低賃金を時給9.6ユーロから12ユーロに25%引き上げる、新規住宅の建設の年間40万戸のうち10万戸に補助金を交付する123、⑤連邦政府の人権及び人道支援部門の機能を強化する、デュー・ディリジェンス法に沿い「ビジネスと人権に関する国家行動計画」を改定するといった事項が挙げられる。
第Ⅰ-2-3-41表 ドイツの連立政権の合意文書のポイント
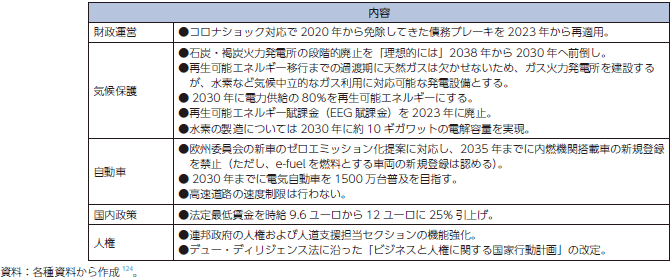
② フランス
フランスでは、2021年10月、マクロン大統領が、国内の製造業振興、研究開発推進、雇用創出等を目指すとともに、原材料や電子部品等の海外への依存度を下げ、国内調達を増加させるため、5年間で300億ユーロを投資する新たな投資計画「フランス2030」を発表した125。同計画では、更に40億ユーロを成長企業に直接に出資することも予定されている。
計画の詳細や資金の配分についてはまだ具体的に示されていないが、小型原子炉の開発やグリーン水素の製造、産業の脱炭素化、低炭素航空機の製造、電気自動車の生産拡大、創造・文化産業の振興、バイオ医薬品20種の生産、宇宙・深海の探査等を含む10分野に政府の資金の投入が検討されている。
マクロン大統領は、本投資計画の狙いをフランスおよび欧州のための生産における自立のための枠組みの再構築であるとして、自律性の強化を強調している126。
③ 英国
2021年7月、英ビジネス・エネルギー産業戦略省(BEIS)は、同国が世界のイノベーション競争で最前線に立つことを目指す新政策「英国イノベーション戦略」を公表した。同戦略は、民間部門の研究開発投資を促し、企業が最先端の科学を製品やサービスに活用できる環境を整備することを目的とした長期計画で、2021年3月に発表した新たな産業政策「より良い復興:成長のための計画(Build Back Better)」を重要な柱の一つとしている。コロナからの復興対策として、インフラ、スキル、イノベーションに重点的に投資を実施し、「グリーン産業革命に向けた10項目」の計画の120億ポンドに加え、インフラ部門に1千億ポンド規模の政府支出を計画しており、スタートアップ支援に37.5億ポンドの支援が予定されている。
123 第一生命経済研究所 田中 理「ドイツでショルツ氏率いる信号連立が誕生へ」(2021年11月25 日)(https://www.dlri.co.jp/report/macro/175513.html![]() )
)
124 JETRO短信 「「信号機連立」の3党が合意、連立協定書を発表」(2021年11月26日)
第一生命経済研究所 田中理「ドイツでショルツ氏率いる信号連立が誕生へ」(2021年11月25日)
125 JETRO 短信「マクロン大統領、戦略分野に300億ユーロの投資計画を発表」(2021年10月14日)
126 ‘Emmanuel Macron unveils €30bn plan to boost French industries’, Financial Times, 12 October 2021, https://www.ft.com/content/5da38637-292f-4c2f-ae48-8e0c74b6014c![]()