第2節 米国経済の動向
米国は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、大規模な財政措置による需要喚起に加えて、失業保険への加算給付や給与保護プログラムといった経済回復を重視した対策により、中国に次いでコロナショックによる景気低迷を脱し、急速な経済回復を見せてきた81。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、世界の中でも特に多くの雇用を失った労働市場において、失業率がコロナ禍前の水準に戻りつつある。一方、コロナ禍における高齢者層の早期引退を示唆する労働参加率は停滞しているほか、自主退職者の急増に合わせて、求人数が増加するなど、労働需給がひっ迫している。また、昨年に引き続き起業申請数が増加するなど、労働市場の構造変化を示唆する動きも見受けられる。もっとも、米国経済が回復する一方で、サプライチェーンの混乱や人手不足、資源・エネルギー価格の高騰等に伴うインフレの高進は、米国経済における最優先課題となっている。さらに、ロシアによるウクライナ侵略によって、サプライチェーンの混乱やエネルギー・食料等の商品価格の高騰に拍車がかかっており、企業活動や家計へのインフレ圧力が高まっている。以下では、こうした米国における経済回復の動向や労働市場の状況、米国経済が抱えるインフレ圧力、財政・金融政策について見ていく。
81 NBER(全米経済研究所)は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う景気後退は2か月で終了し、景気の谷を2020年4月と発表した。
NBER (2021), “Determination of the April 2020 Trough in US Economic Activity”,
(https://www.nber.org/news/business-cycle-dating-committee-announcement-july-19-2021![]() ).
).
1.経済回復の動向
(1)新型コロナウイルスの感染状況及びワクチン接種の状況(2022年4月30日時点)
米国は、2022年4月30日時点で、新型コロナウイルスの累計感染者数が世界最多となっており、累計感染者数は8,000万人を超えている。国・地域別人口に占める累計感染者数の割合を見ると、米国は2020年、2021年については他の国・地域と比べて大きい水準で推移してきた(第I-2-2-1図)。オミクロン株の感染拡大を受けて、2022年1月10日には新規感染者数は約136万人、7日間平均でも一時80万人を越えたが、(第Ⅰ-2-2-2図)。2022年1月をピークに新規感染者数は減少し、2022年4月30日時点で、1日当たりの新規感染者数(7日間平均)は約3万人となっている。一方、ユーロ圏では2022年3月に感染の再拡大が起きており、2022年4月30日時点で人口に占める感染者数の割合はユーロ圏が米国を上回っている。
第Ⅰ-2-2-1図 新型コロナウイルス感染者数とワクチン接種者数の人口に占める割合
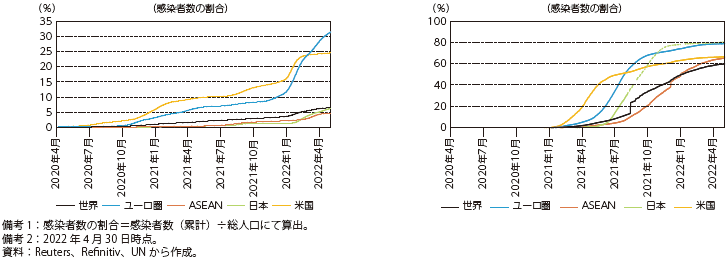
第Ⅰ-2-2-2図 米国における新型コロナウイルスの新規感染者数(7日間平均)
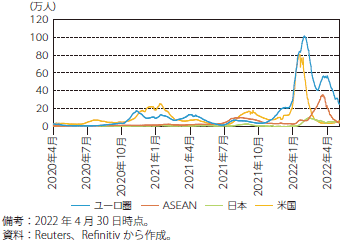
こうした新型コロナウイルスの感染状況が労働市場や家計、企業活動に与えた影響を踏まえながら米国経済の動向について見ていく。
(2)GDP・貿易収支
2020年は、新型コロナウイルスの感染拡大によって、経済が第2四半期に一時急速に落ち込んだ後、財政出動に伴い第3四半期から一部回復が見られたものの、通年では前年比-3.5%とマイナス成長となった。一方、2021年の実質GDP成長率(季節調整済)は、2021年第2四半期にはコロナ禍前の2019年第4四半期の水準を越え、通年では5.7%とプラス成長になり、1984年以来37年ぶりの高い成長率を記録した(第Ⅰ-2-2-3図)。背景として、前年の落ち込みの反動のほか、変異株拡大の中でも底堅い消費需要によって、耐久財消費や機器への設備投資、輸入の成長が寄与したことなどが挙げられる。
第Ⅰ-2-2-3図 米国の実質GDP
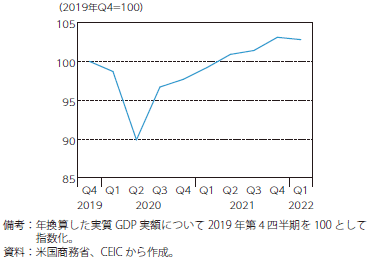
四半期別成長率を見ると、2021年第1四半期が前期比年率換算+6.3%、第2四半期が同+6.7%、第3四半期が同+2.3%、第4四半期が同+7.0%と年間を通じてプラス成長となった一方で、2022年第1四半期には同-1.4%となっている(第Ⅰ-2-2-4図)。
第Ⅰ-2-2-4図 米国の需要項目別実質GDP成長率
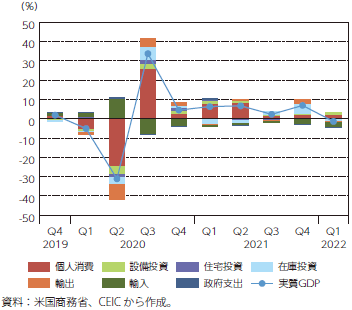
2021年の第3四半期は、前2四半期と比べて成長が減速している。背景としては、デルタ株の感染拡大や政府の経済対策の縮小を受け、GDPの7割を占める個人消費の勢いが大幅に減速したことに加え、物流の混乱などによる供給面の制約や、ハリケーンアイダがエネルギー業界を中心に多大な被害をもたらした影響が影響したと見られる。第4四半期には再度高い成長率となっており、成長率に寄与しているのは在庫投資であり、輸出は輸入の伸び率に概ね相殺されたほか、個人消費や設備投資、住宅投資は大きく伸びていない。
2022年の第1四半期は、前期比年率でマイナスとなったものの、輸出の伸びが減少し、内需の増加に伴って輸入が増加したことによる純輸出の減少と前期に急増した在庫投資の反動減が主な要因であり、個人消費や設備投資など内需は堅調に推移しており、景気は拡大基調を維持している。
今後も堅調な個人消費や設備投資は成長を押し上げ得るが、ウクライナ侵略や中国での新型コロナウイルス再拡大を受けたロックダウンによって、サプライチェーンの混乱や、資源・エネルギー価格を中心としたインフレ高進が継続すると、消費マインドが抑制され、成長を押し下げる要因となり得る。
次に、コロナ禍における米国経済の回復状況について対外経済の観点から見ていく。
財貿易に関する収支構造や財取引の国・地域について見ると、2021年には輸出額と輸入額のいずれも前年より増加しているものの、輸入額が輸出額よりも大きく伸びたことによって、貿易赤字が拡大している(第Ⅰ-2-2-5図)。
第Ⅰ-2-2-5図 米国の貿易収支
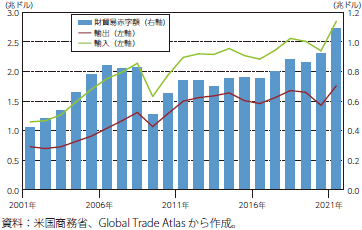
財貿易赤字は、トランプ政権においては追加関税措置等により縮小していたものの、2021年に3年ぶりに拡大し、初めて1兆ドルを超え、過去最大を更新した。貿易赤字の上位相手国としては、中国が最大で米国の財貿易赤字の約1/3を占め、次いで、メキシコ、ベトナム、ドイツ、日本と続いており、上位5か国で全体の約2/3を占めている(第Ⅰ-2-2-6図)。
第Ⅰ-2-2-6図 米国における財貿易赤字額の上位5か国(年次)
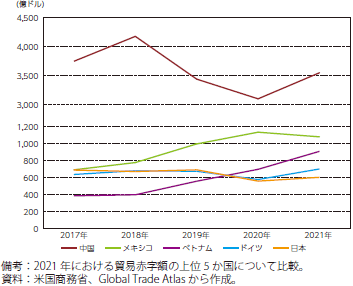
対中貿易は、2018年から2020年にかけて財貿易の赤字幅が縮小していたものの、2021年には対中輸出が前年比21%増で過去最大の1,511億ドル、対中輸入が前年比16%増の5,064億ドルとなり、貿易収支は3,553億ドルの赤字となっている。
(3)労働市場の動向
米国経済は、デルタ株やオミクロン株といった変異株の感染拡大によって一時的に経済活動が急速に停滞した時期が見られたものの、その後は、経済回復を続けてきた。コロナショック時には他国と比べて特に多くの雇用を失った米国だが、失業率がコロナ禍前の水準に戻る一方で、第Ⅰ部第1章第2節第2項で示したように、2021年以降、人手不足の状況が続いており、財・サービスの供給制約要因の一つとなっている。以下では、こうした米国の労働市場の実態について分析していく。
① 失業率
労働市場の実態を捉える上で、米国の失業率について見ていく。米国における失業率は6つの区分があり、それぞれ以下のとおり定義されている(第Ⅰ-2-2-7表)。
第Ⅰ-2-2-7表 米国の失業率区分
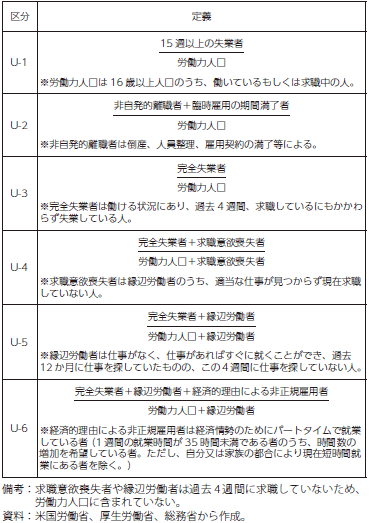
一般的に失業率は、労働力人口に占める完全失業者の割合から算出される失業率(U-3)が用いられる。失業率(U-3)は、2020年4月には14.7%に達していたが、2022年4月時点で、失業率(U-3)は3.6%へと改善している(第Ⅰ-2-2-8図)。なお、米国において、完全失業者は、就業を希望しており、過去4週間以内に1度でも求職活動をしている又は就業可能な人と定められている。また、失業率(U-3)を算出する際の分母にあたる労働力人口は就業者数と失業者数の合計によって算出される。このため、仮に就業を希望していても、過去4週間以内に求職活動をしていない場合には失業者として含まれないほか、労働力人口にも含まれず失業率(U-3)は、この非労働力化を捕捉することができない。
第Ⅰ-2-2-8図 失業率及び非雇用指数の推移
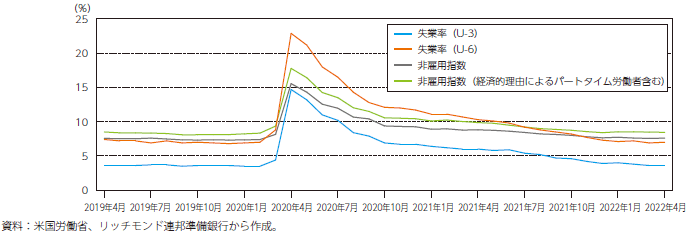
一方で、より広義の失業率として、失業率(U-6)がある。失業率(U-6)は、就業を希望しており、過去1年以内に求職活動をしているが、過去4週間以内には求職活動を行っていない縁辺労働者と労働力人口の合計が、算出する際の分母と用いられているため、対象範囲が広い。また、分子には、完全失業者のみならず縁辺労働者や経済的理由によりフルタイム労働ではなくパートタイム労働を行っている人を含めていることから、失業率(U-3)と比べてより広義の失業率と言える(同表)。この失業率(U-6)で見ると、2020年4月には22.4%に達していたが、財政措置によって需要が喚起されたことにより、労働需要が回復し、2022年4月時点で、7.0%へと改善している(第Ⅰ-2-2-8図)。
② 非雇用指数
リッチモンド連邦準備銀行は、前述した失業率(U-3)や失業率(U-6)について、労働市場の実態を適切かつ定量的に捕捉しきれていないと指摘している82。これを踏まえて、リッチモンド連邦準備銀行は、非雇用指数(NEI: Non-Employment Index)を推計し、米国労働省の雇用統計が公表される2週間後に月次指数として公表している83。非雇用指数は、失業率(U-3)や失業率(U-6)と異なり、生産年齢人口84を母数とした上で、労働市場における未活用状態にある労働力を表現した指数となっている。具体的には、既存の失業者を短期失業者と長期労働者に分け、さらに、非労働力人口についても、就労希望の有無や、学生、退職者など、合わせて9つのサブカテゴリーへと分類している。この各サブカテゴリーに属する人々が再度就業する確率を過去の統計から推計し、それらを加重平均した期待値を算出する際の分子として用いている。また、非雇用指数は、失業率(U-6)と同様に経済的な理由によるパートタイム労働者を考慮した場合の指数についても併せて公表している。
これらの失業率(U-3、U-6)や非雇用指数の推移を見ると、いずれも2020年4月にピークを迎えたものの、その後、失業率(U-6)は失業率(U-3)とともに急速に改善している。2021年後半には、パートタイム労働者を考慮した非雇用指数が失業率(U-6)を上回っており、失業率(U-6)の算出の分母に含まれていない非労働力人口の影響が徐々に大きくなっていることを示唆している(第Ⅰ-2-2-8図)。
③ 労働参加率
非労働力を考慮することの重要性は、生産年齢人口に占める労働力人口によって表される労働参加率からも確認できる(第Ⅰ-2-2-9図)。
米国の労働参加率はコロナショック後、上昇傾向にあるものの、コロナ禍前の水準には戻っておらず、2022年初めの段階においても2019年平均に対して約1%のギャップが存在しており、労働市場において労働力人口が少ない状態にある。
第Ⅰ-2-2-9図 米国の労働参加率の推移
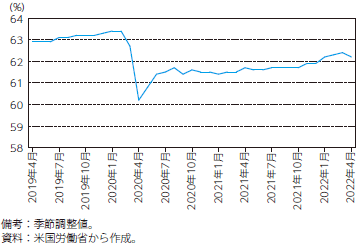
また、年齢階層別の労働参加率を見ると、若年層(16~24歳)は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、最も減少幅が大きかった年齢層であったが、その後、他の層よりもいち早く2019年平均の水準へと回復していることが確認できる(第Ⅰ-2-2-10図)。プライムエイジ(25~54歳)は、若年層と同時期に労働参加率が減少したものの、若年層よりも減少幅が小さかったほか、既に回復基調となっており、コロナ前の水準に迫る状況となっている。高齢層(55歳以上)については、若年層やプライムエイジと比べて、コロナショックに伴う減少幅がさらに小さく、一時回復の兆しを見せたものの、再び減少に転じており、コロナ禍を契機とした退職が構造的変化となっている可能性を示唆している。
第Ⅰ-2-2-10図 年齢階層別労働参加率
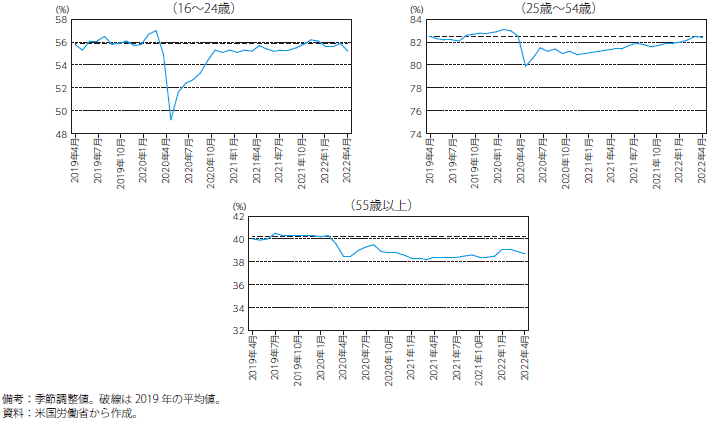
④ 求人率と失業率の推移
次にこうした非労働力人口が増加している背景について、労働市場における求人と失業の関係から見ていく。リッチモンド連邦準備銀行では、コロナ禍において求人率と失業率の反比例関係を示すベバリッジ曲線が、コロナ禍前には見られなかった特異な動きをしている点を指摘している85(第Ⅰ-2-2-11図)。
第Ⅰ-2-2-11図 ベバリッジ曲線
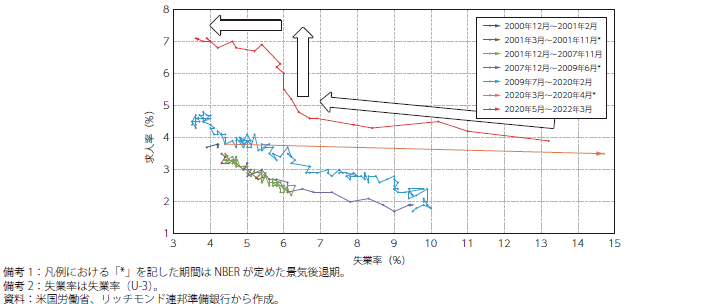
通常、ベバリッジ曲線は反時計回りに循環する動きをして、右上にシフトすると失業率と求人率のいずれも高い状態となり、雇用のミスマッチが大きくなっていることを示す。2020年3月から4月にかけて、新型コロナウイルスの感染拡大によって失業率が急上昇したことで、大きく右側へとシフトしていることが確認できる(第Ⅰ-2-2-11図中の橙色線)。その後、ベバリッジ曲線は、求人率の増加と失業率の減少が同時に進んでいく一般的な動きとなるが、失業率が6%前後となった2021年初段階で、それまでの失業率と求人率の反比例関係とは異なり、求人率のみが大きく上昇する動きとなっている。さらに、その後2021年後半になり、求人率がほぼ一定の状態で失業率のみが減少する動きとなっている。
リッチモンド連邦準備銀行は、こうした状況について、理由がまだ明らかとなっていないとした上で、一般論として、雇用のミスマッチの背景として、マッチングの質の低下の可能性について言及している。近年は、雇用マッチングのデジタル化が進展しており、求人側はプラットフォームを通じて求人を行うコストを削減し、求職者側についても手軽に多くの求人情報にアクセスすることや応募することが可能となった。他方、より多くの応募書類から雇用者を決定する必要があることにより採用コストが増大し、マッチングの質低下につながっている可能性があると指摘されている86。リッチモンド連邦準備銀行は、こうした特徴を踏まえて、今後、失業率を元の水準に戻すためには、企業側がより多くの求人を出す必要性について言及している。
先述したベバリッジ曲線において、失業率(U-3)を失業率(U-6)やパートタイム労働者を考慮した非雇用指数に置き換えてみると、それぞれベバリッジ曲線が失業率(U-3)による曲線よりも右側にシフトしていることが確認できる。また、非雇用指数については2021年後半からの動向によって、右側へのシフトの度合いが失業率(U-6)よりも強いことが確認できる(第Ⅰ-2-2-12図)。ベバリッジ曲線のシフトの動向をみると、今後、求人数の増加のみによっては元の水準には戻らないような構造的変化が労働市場において起こっている可能性も示唆される。
第Ⅰ-2-2-12図 失業率及び非雇用指数に基づくベバリッジ曲線(2020年5月以降)
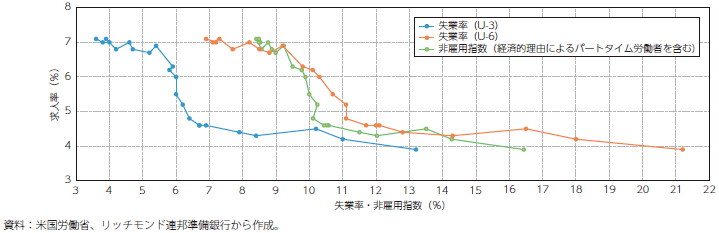
⑤ 求人数と自主退職者
次に、こうした動向の背景を探るべく雇用のマッチングの状況について、求人数や離職者数の観点から確認する。米国労働省によると、2019年の求人数は年平均で716万人であったが、2021年6月には1,000万人を超えている。また、コロナ禍前の2019年にはほぼ一定数で推移していた自主退職者がコロナ禍で増加する動きが見られ、2021年11月には自主退職者が過去最多の450万人に達しており、大退職時代(The Great Resignation)の到来といわれている(第1-2-1-13図)。
第Ⅰ-2-2-13図 米国における求人数と自主退職者数
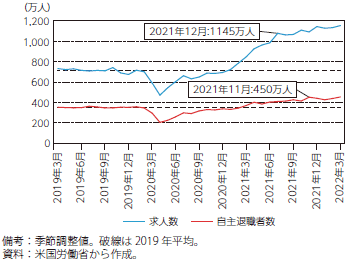
離職者と自主退職者の動向を見ると、2020年後半から離職者に占める自主退職者の割合が増加していることが確認できる(第Ⅰ-2-2-14図)。また、この自主退職者の割合がコロナ禍前の平均を上回った時期は、求人数が急増する時期に対応しており、同様に前述したベバリッジ曲線の特異なシフトの時期に対応している。
第Ⅰ-2-2-14図 米国における離職者の推移
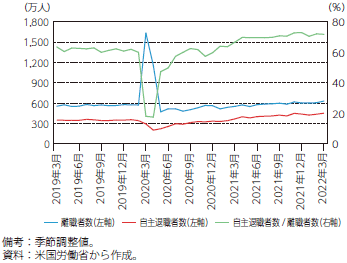
こうした自主退職者の急増について、コロナ禍における労働への意識の変化と捉える見方がある。一方で、サンフランシスコ連邦準備銀行は、戦後の労働市場を分析し、景気後退後の急激な経済回復において、これまでも自主退職者の急増は見られており、コロナ禍における特異な動きではないと指摘している87。戦後の米国経済における雇用者数の変化と併せて離職率を長期時系列で確認すると、景気後退や回復に合わせて雇用者数は大きく増減する一方で、離職率については大きく変動していないことが確認できる(第Ⅰ-2-2-15図)。
第Ⅰ-2-2-15図 米国における雇用者数の変化率と離職率の推移
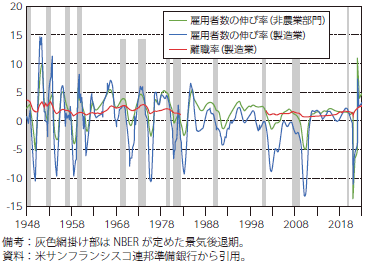
景気後退期においては一時的な解雇が急増するが、その後、企業側は財・サービス需要の回復を満たすための人員を補充するために求人を増加させる。こうした求人には、失業者のみならず、他の労働者がより良い労働環境を求めて応募したり、現在の職場に対して賃金や福利厚生、勤務形態等について再交渉を行ったりする。こうした点を踏まえて、同分析では、現下の状況は大退職(Great Resignation)ではなく、大再交渉(Great Renegotiation)として解釈している。
⑥ 参入・退出企業数の動向
前述したように、2021年における自主退職者の増加がコロナ禍における特異な動きではないとの分析を踏まえつつ、短期的な動向に着目して、自主退職者の増加の背景について考えていく。自主退職の背景としては、転職、リタイア、起業、子育て世代の一時的離職など複数の要因が考え得るが、ここでは、通商白書2021でも触れた起業の動向について見ていく。コロナ禍における米国の起業は2020年にコロナショック後増加したが、2021年も、コロナ禍前より多い水準で推移している(第Ⅰ-2-2-16図)。
第Ⅰ-2-2-16図 米国における従業員雇用を前提とした起業申請件数
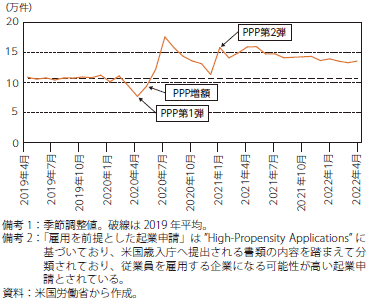
米国労働省が公表している従業員の雇用を前提とした起業申請件数を見ると、コロナショックに伴い申請件数は一時減少したものの、その後反動とみられる増加の後、ピークアウトした。もっとも、2021年入り後、再び申請件数が急増する動きが見られている。これは、同時期にPPP(給与保護プログラム)の第2弾が開始された時期にあたり、政策効果によって起業の申請件数が増加している可能性が示唆される。John C. Haltiwanger (2021)によると、2020年後半に急増した起業の申請件数は業種によってばらつきがあるが、最も急増した業種は無店舗型小売業であり、次いで、専門・科学・技術サービス、トラック輸送、宿泊・飲食サービスなどが挙げられる(第Ⅰ-2-2-17図)。新型コロナウイルスの感染拡大によって既存の小売業や宿泊・飲食サービス業が大きく減少したことを踏まえると、新たに起業申請された業種別の動向と整合的であると考えられる88。
第Ⅰ-2-2-17図 米国における起業申請件数(上位5業種)
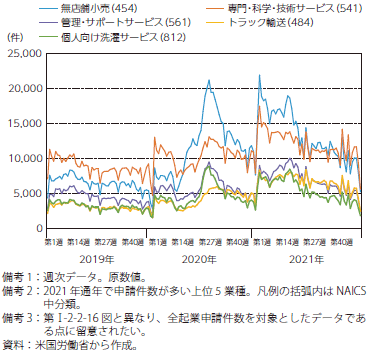
コロナ禍で起業の申請件数が増加する一方で、倒産件数については減少傾向にある(第Ⅰ-2-2-18図)。
第Ⅰ-2-2-18図 米国における破産件数
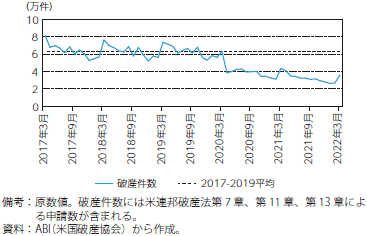
米国破産協会が公表する米国企業の破産件数を確認すると、コロナ禍前には2017年から2019年の3年間で平均して1か月あたり約6.3万件あったが、新型コロナウイルス感染拡大当初に大きく減少し、その後も減少基調にある。背景として、PPP(給与保護プログラム)による従業員への給与支払い補填といった公的支援や金融緩和によるものと考えられる。Leland D. Crane (2021)によると、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って一部セクターでは事業の撤退が増加したものの、多くのセクターではコロナ禍前よりも少なく、新型コロナウイルス拡大当初に予測されていた事業撤退の規模を下回る可能性が高いとしている89。
82 リッチモンド連銀は、失業率と非雇用指数の線形関係を確認しており、それぞれの指標のコロナ禍前の水準と現在の値を比較して、元に戻っているかどうか判断するといった場面においてはこれらの指数間に差が生じないことを併せて指摘している。
83 Federal Reserve Bank of Richmond, “Hornstein-Kudlyak-Lange Non-Employment Index”, (https://www.richmondfed.org/research/national_economy/non_employment_index![]() ).
).
84 米国における生産年齢人口は16 歳以上の文民人口(軍人や服役中等の施設内人口を除いた人口)。
85 Federal Reserve Bank of Richmond, (2021), “Revisiting the Beveridge Curve: Why Has It Shifted so Dramatically?”, Economic Brief, (https://www.richmondfed.org/publications/research/economic_brief/2021/eb_21-36![]() ).
).
86 近年の雇用のデジタルマッチングプラットフォームといった労働市場におけるデジタル化の動向については第Ⅱ部第2章第1節第3項を参照されたい。
87 Federal Reserve Bank of San Francisco, (2022), ““Great Resignations” Are Common During Fast Recoveries”, FRBSF Economic Letter.
88 John C. Haltiwanger, (2021), “Entrepreneurship During the COVID-19 Pandemic: Evidence from the Business Formation Statistics”, NBER Working Paper 28912, (https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28912/w28912.pdf![]() ).
).
89 Crane, Leland D., Ryan A. Decker, Aaron Flaaen, Adrian Hamins-Puertolas, and Christopher Kurz (2021), “Business Exit During the COVID-19 Pandemic: NonTraditional Measures in Historical Context,” Finance and Economics Discussion Series 2020-089r1,
(https://www.federalreserve.gov/econres/feds/files/2020089r1pap.pdf![]() ).
).
2.米国経済におけるインフレの実態
前項で示したように、米国経済は回復している一方で、急激な財政出動によって喚起された財・サービス需要の増加がサプライチェーンにおける供給制約を誘引した側面も指摘されている。第Ⅰ部第1章第2節においても言及しているように、サプライチェーンにおける供給制約は、世界的なインフレを招いており、とりわけコロナ禍の米国経済においては歴史的な水準でインフレが高進している。さらに、ロシアによるウクライナ侵略によって、エネルギー供給、資源・食料等のサプライチェーンの一部途絶や見直しによって混乱が生じ、資源価格の高騰に伴うインフレ圧力を一層高めている。こうした米国経済で生じているインフレについて、消費者物価の観点から観察した上で、家計の状況や、企業活動の状況について生産者物価を見ていく。
(1)消費者物価指数
① 総合指数・コア指数
消費者物価指数について日本、米国、EUで比較すると、EUや日本と比べて米国では大きく上昇していることが確認できる。また、IMFの予測によると、2022年には2021年を超える水準となり、2023年以降に影響が緩和し、2025年に2%へと収束する見通しとなっている(第Ⅰ-2-2-19図)。
第Ⅰ-2-2-19図 日本・米国・EUにおける消費者物価指数の推移と予測(前年比)
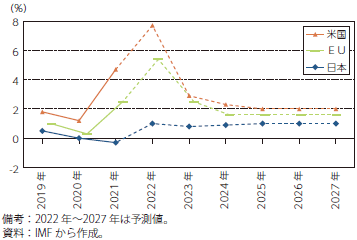
米国の消費者物価指数(CPI)について、前月比の動向を見ると2020年5月以降上昇を続けていることが確認できる。また、前年同月比の推移を見ると、2021年9月以降一貫して上昇率が拡大してきており、2022年3月には+8.5%と、1981年12月以来の水準となっている。その後、2022年4月には+8.3%と上昇率が僅かに鈍化している。また、食品やエネルギーを除いたコアCPIについても、前年同月比で、CPIと同様に2021年9月以降上昇率が拡大しており、2022年3月には+6.5%と、1982年8月以来の上昇幅となり、2022年4月には+6.2%となっている(第Ⅰ-2-2-20図)。
第Ⅰ-2-2-20図 米国における消費者物価指数(CPI)
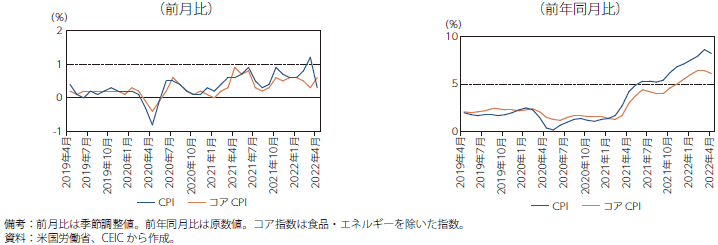
財・サービス別の消費者物価指数を見ると、財の消費者物価指数はコロナ禍で上昇を続けており、2022年4月には前年同月比+9.7%と、コアCPIの同+6.2%を大幅に上回っている。また、サービスに関する消費者物価指数は、コロナ禍前には前年同月比で+3%前後で推移していたが、2021年に入り経済活動が再開される中で、物流混乱や人手不足といった供給制約や、それによる賃金上昇圧力を映じて上昇している(第Ⅰ-2-2-21図)。
第Ⅰ-2-2-21図 米国における消費者物価指数(財・サービス別、前年同月比)
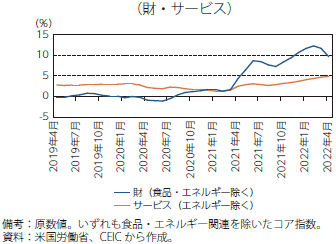
② エネルギー・食品
次に、上述したコア指数には含まれないエネルギーや食品の消費者物価指数の動向を見ていく。エネルギー、食品の消費者物価指数は国際価格の高騰に伴い大きく上昇している。エネルギーの消費者物価指数については前年同月比+20%を越える上昇率となっている(第Ⅰ-2-2-22図)。もっとも、ガソリン価格が前年同月比+40%程度とエネルギー価格の上昇を押し上げている。
第Ⅰ-2-2-22図 米国におけるエネルギーの消費者物価指数(前年同月比)
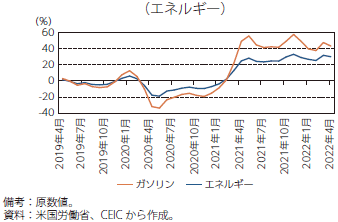
食品の消費者物価指数について前年同月比の動向を見ると、コロナ禍前から+2%程度で推移しており、コロナショック時において+4%前後上昇で推移した。その後、サービス産業を含めた経済活動の回復を受けて、上昇が一服したが、2021年後半からは上昇が続いており、2022年4月には同+9.4%とCPIを越える水準となっている(第Ⅰ-2-2-23図)。
第Ⅰ-2-2-23図 米国における食品の消費者物価指数(前年同月比)
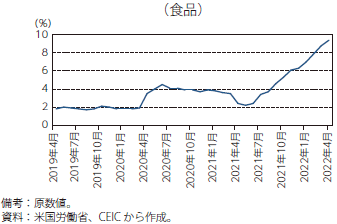
第Ⅰ部第1章第1節や第2節において言及しているように、ロシアによるウクライナ侵略を受けて、エネルギーや穀物等の食料が豊富なロシアやウクライナが世界の供給網に与える影響は大きいため、今後、エネルギーや食品の国際価格の高騰を通じて、米国経済に与える価格上昇圧力も高まることが想定される。
③ 住宅
次に、消費者物価において約3割と大きなウェイトを占めている住宅に関する物価指数について見ていく。住宅に関する消費者物価指数は2021年初めより上昇している(第Ⅰ-2-2-24図)。
第Ⅰ-2-2-24図 米国における住宅の消費者物価指数(前年同月比)
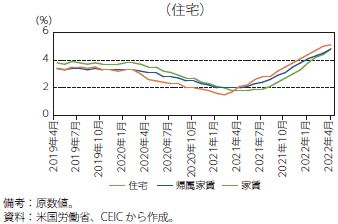
併せて、住宅価格指数を見ると、統計開始以来の水準で推移している(第Ⅰ-2-2-25図)。
第Ⅰ-2-2-25図 米国における住宅価格指数(前年同月比)
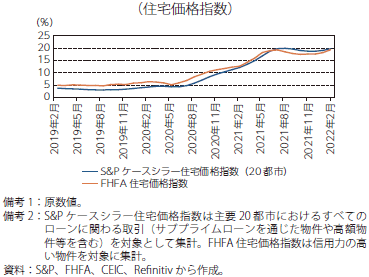
こうした住居に関する消費者物価や住宅価格指数が前年同月比で上昇している背景として、コロナ禍において居住地の好みが変化したことに加えて、歴史的な低金利を背景に住宅需要が過熱していることが挙げられる(第Ⅰ-2-2-26図)。
第Ⅰ-2-2-26図 米国における住宅ローン金利
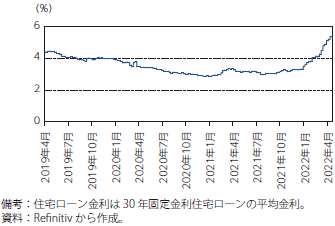
もっとも、住宅ローン金利は2021年8月以降上昇しており、住宅価格の高騰と相まって購買意欲を一段と減退させるリスクになるとの指摘もあるが、金利がさらに上昇する前の駆け込み需要で増加するとの見方も存在する。さらに、住宅需要の過熱は木材の需給ひっ迫の一因となり木材価格の高騰を招き、住宅価格をさらに押し上げている(第Ⅰ-2-2-27図)。
第Ⅰ-2-2-27図 米国における木材価格
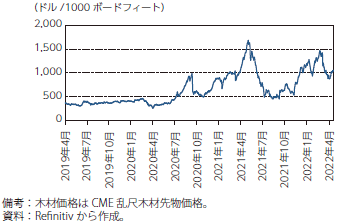
住宅価格の増加率の上昇は鈍化が続いているが、依然として価格上昇は続いており、今後、住居費用の大半を占める帰属家賃が家計を圧迫することが見込まれる。
④ 自動車
次に、第Ⅰ部第1章第2節第5項において示したように、半導体の供給不足により、企業の生産活動や個人の消費市場に大きな影響を与えた自動車の物価動向について見ていく。車両の消費者物価指数として、新車・トラックと中古車・トラックについて前年同月比をそれぞれみると、新車・トラックは2022年4月時点で、前年同月比+13.2%、中古車・トラックの消費者物価指数は同+22.7%と、中古車・トラックの物価上昇がより大きいことが確認できる(第Ⅰ-2-2-28図)。
第Ⅰ-2-2-28図 米国における自動車の消費者物価指数
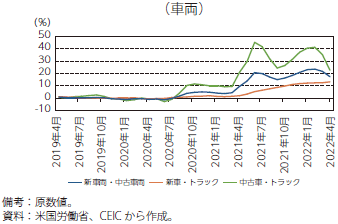
こうした自動車における物価指数の上昇を招いている複合的な要因について、OECDは以下の5段階に分けて示している90(第Ⅰ-2-2-29図)。
第Ⅰ-2-2-29図 自動車価格高騰の背景
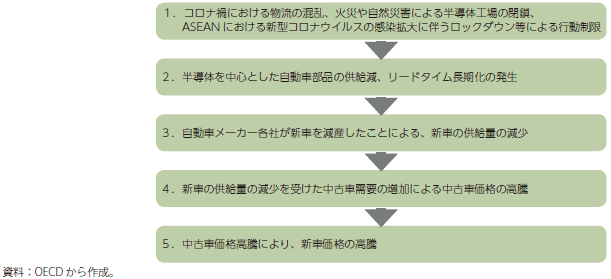
足下では、オミクロン株の感染が世界的に広がっているが、ASEANにおいては、デルタ株の拡大時における非常事態宣言ほどの行動制限は行っていないことから、行動制限による供給減の影響は大きくない。一方で、自動車製造工程における重要部品の1つである半導体の不足は、今後も継続する見込みとなっており、足下でも、各社が減産を続けることにより、自動車の供給量の減少が続いている。米国内の自動車販売台数について、2020年4月時点における米国の季節調整後年間販売台数はリーマン・ショック時の最低台数を下回る861万台となり、その後、幾分回復したものの、上述した物流の混乱や工場の閉鎖、ロックダウンや半導体等の部品不足を背景に供給量が減少し、販売台数が大きく減少している(第Ⅰ-2-2-30図)。自動車の需要は強いことを踏まえると、需給のひっ迫は今後も続く可能性がある。
第Ⅰ-2-2-30図 米国における自動車販売台数
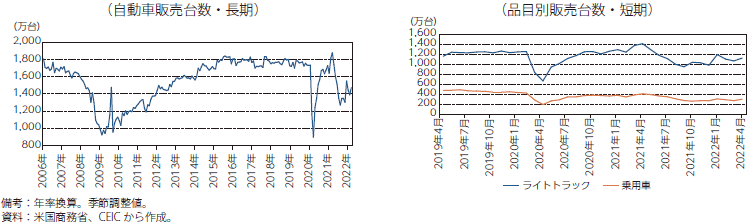
90 OECD, (2021), “Economic Outlook”, Vol. 2021 Issue 2: Preliminary Version, (https://doi.org/10.1787/66c5ac2c-en![]() ).
).
(2)家計の所得と消費支出
米国の個人消費は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、2020年4月に大きく落ち込むも、その後、大規模な財政措置によって需要が喚起され、コロナ禍前の水準を超えている(第Ⅰ-2-2-31図)。足下、オミクロン株の感染拡大によって引き続き経済活動に制約がある中でも、個人消費は底堅く推移しており、貯蓄率もコロナ禍前の2019年平均の7.6%を下回る低水準となっている(同図)。
第Ⅰ-2-2-31図 米国における個人消費支出と貯蓄率の推移
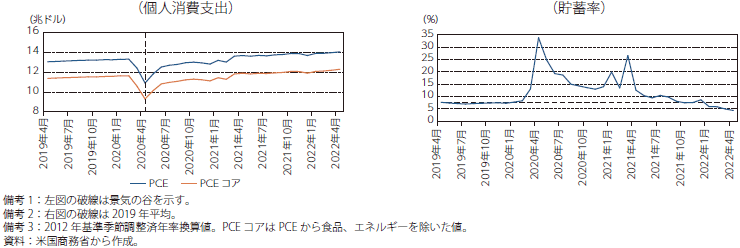
個人所得は、2021年9月の失業保険の加算支給の終了に伴う下押し要因が剥落し、増加している。失業保険の加算措置は、就職意欲を阻害するとの懸念から約半数の州について早期打ち切りが行われたが、こうした懸念について、リッチモンド連邦準備銀行では、失業保険の補填が個人消費や労働市場に与える影響について分析しており、失業保険が個人消費を刺激する点については幅広いコンセンサスが得られているとした上で、労働供給の意思決定への影響については複数の研究例を基に僅かにマイナスもしくはほとんど影響しないとしている91。
こうした失業保険の加算支給、CARES法92や米国救済計画法による個人への直接給付に加え、これらが底上げした所得によって財需要が喚起され、需要主導型で経済活動の再開が進められたほか、インフレや人手不足に伴う賃金上昇の影響もあいまって個人所得は増加しているものの、賃金上昇がインフレに追いついておらず、実質可処分所得については減少しており、2021年4月以降前年同月比はマイナスで推移している(第Ⅰ-2-2-32図)。
第Ⅰ-2-2-32図 米国における個人所得と実質可処分所得
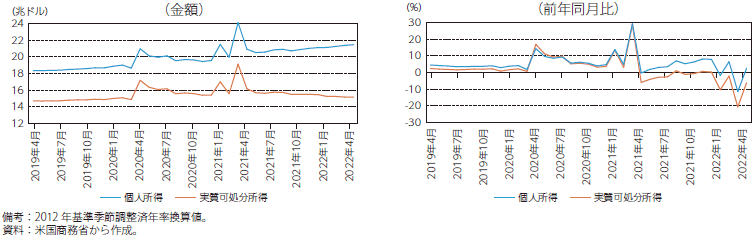
また、原材料等の供給制約を背景としたインフレや人手不足を受けて賃金は上昇傾向にあるが、2021年に入りCPIが上昇を続ける一方で、平均時給上昇率(前年同月比)が追い付いておらず、実質賃金はマイナスで推移している(第Ⅰ-2-2-33図)。
第Ⅰ-2-2-33図 米国における実質賃金上昇率(前年同月比)
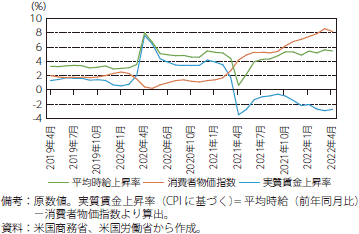
インフレ下における消費者のマインドを確認するため、ミシガン大消費者態度指数を見ると、新型コロナウイルスの感染拡大によって悪化したセンチメントは経済回復が進む状況を映じて改善されてきたが、インフレ率が急上昇した2021年4月をピークに再度悪化しており、2021年10月には2020年4月の水準を下回る71.7となり、それ以降についても下落基調が続いている(第Ⅰ-2-2-34図)。収入別の違いを見ると、収入上位の1/3については、2021年に減少に転じるピークが全体よりも遅れており、インフレの影響が相対的に小さいことが確認できる。2022年に入り、全ての層において指数が減少しており、インフレ圧力が強く消費マインドを下押ししていることが示唆される。
第Ⅰ-2-2-34図 ミシガン大消費者態度指数
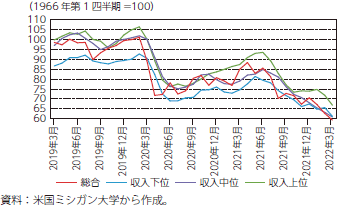
91 Federal Reserve Bank of Richmond, (2021), “Unemployment Insurance: Economic Lessons from the Last Two Recessions”, Economic Brief, (https://www.richmondfed.org/publications/research/economic_brief/2021/eb_21-26![]() ).
).
92 2020年3月に共和党トランプ前大統領が成立させた2兆2,000億円規模のコロナウイルス支援・救済・経済保障法(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security: CARES)。
(3)生産者物価指数
次に、企業活動におけるインフレの状況として生産者物価指数の動向について見ていく。生産者物価指数は、コロナ禍前には前年同月比+2%程度で推移していたが、経済活動の回復に伴い上昇し、2022年4月時点で最終需要の総合指数が同+11.0%、コア指数については同+6.9%となっている(第Ⅰ-2-2-35図)。
第Ⅰ-2-2-35図 米国における最終需要の生産者物価指数(前年同月比)
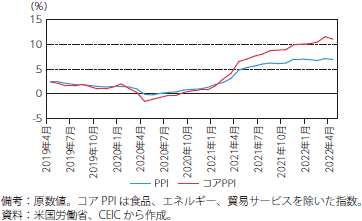
また、中間財や原材料の動向を見ると、中間財については、2021年11月の同+26.6%をピークとして、2022年4月に同+21.9%、原材料については、2021年4月の同+59.2%をピークに、2022年4月に同+48.1%となっている(第Ⅰ-2-2-36図)。
第Ⅰ-2-2-36図 米国における中間財・原材料の生産者物価指数(前年同月比)
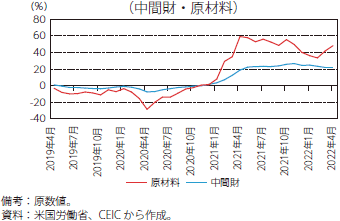
背景としては第Ⅰ部第1章第2節で示したように、物流の混乱や人手不足、資源やエネルギーの需給ひっ迫といったサプライチェーン上の供給制約によるものと考え得るが、最終需要、中間財、原材料の生産者物価指数の動向を見ると、より川上の工程ほど物価増減の程度が大きいことが確認できる。
これまでに消費者物価指数や生産者物価指数の推移についてそれぞれ見てきたが、両指数の推移を比較してみると、2021年以降、生産者物価指数の上昇とともに消費者物価指数が上昇していることから、サプライチェーン上の供給制約による影響が価格へと転嫁されている様子がうかがえる(第Ⅰ-2-2-37図)。
第Ⅰ-2-2-37図 米国における生産者物価指数と消費者物価指数(前年同月比)
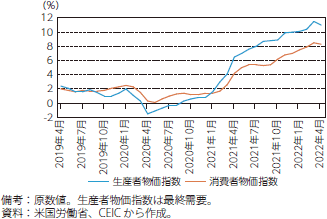
3.財政・金融政策
これまでにコロナ禍における経済回復の動向や、労働市場の状況、サプライチェーンにおける需給ひっ迫を背景としたインフレが家計や企業に与える影響について見てきた。ここでは、これらのコロナ禍における経済回復を後押しした財政出動や、現下の米国経済において最優先課題となっているインフレと対峙する金融政策について見ていく。
(1)財政政策
バイデン政権は就任当初より、新型コロナウイルス対応、経済対策、気候変動対策等に重きを置いた政権運営を行ってきている。2021年の財政収支を見ると、財政赤字が過去最大となった2020年に次ぐ大きさであり、約2.8兆ドルの財政赤字となった(第Ⅰ-2-2-38図)。
第Ⅰ-2-2-38図 米国の財政収支(年次)
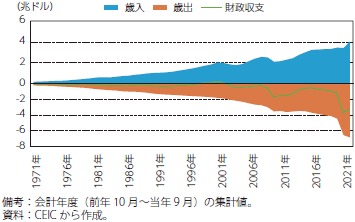
背景としては、トランプ政権に続き、新型コロナウイルス対策に巨額の措置を講じており、歳出額は過去最大となっていることが挙げられる(第Ⅰ-2-2-39図)。
第Ⅰ-2-2-39図 米国における新型コロナウイルス関連予算
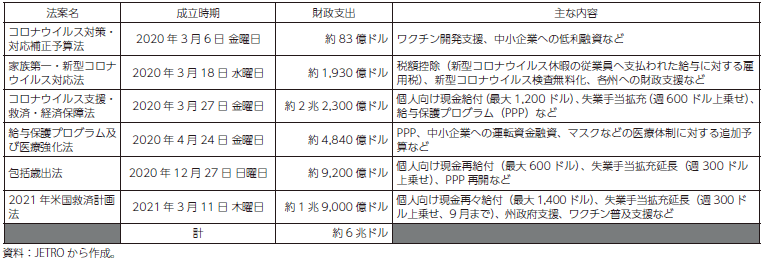
一方で、経済の再開が進められたことを受けた、就業者数の増加による所得税の増加や、企業収益が回復したことによる法人税の増加によって、歳入が2020年より増加しており、2020年より財政赤字が縮小したことにつながっている。
バイデン政権は当初、10年間で約4兆ドル規模となる「米国雇用計画」と「米国家族計画」の2つの経済対策を打ち立てていたが、その後、議会通過のために「超党派インフラ投資計画」と「Build Back Better(BBB)法案」として再構成された。前者のインフラ投資計画については、米国雇用計画のうち、共和党も合意可能なインフラ投資に焦点を当て、規模も縮小し、2021年11月15日に成立に至った。
一方で、BBB法案については、共和党の支持が得られない中で財政調整措置93を使い2021年11月19日に米下院を通過したが、上院ではインフレ懸念等を理由に民主党中道派の強い反対により、成立の見通しが立たない状況となっている。
93 一定の制約の下で、当初予算案に則った歳出ないし歳入の計画を議会が単純過半数で可決するための仕組み。
(2)金融政策
2021年の米国経済においては、大規模な財政措置が需要を喚起したことや新型コロナウイルスのワクチン接種が進められたことで経済回復が進み、失業率は新型コロナウイルス感染拡大前の水準となっており、FRBは経済活動や雇用の指標における強さへの認識を示してきた。一方で、人手不足による賃金上昇やサプライチェーンにおける供給制約を背景としてインフレ率が目標の2%を大幅に上回る状況となっており、金融政策に関して目下の最優先課題はインフレ抑制となっている。
インフレの状況について、個人消費支出(PCE)価格指数、食品やエネルギーを除いたコアPCE価格指数の前年同月比をそれぞれ確認すると、いずれも2020年5月以降上昇を続けており、2022年4月のPCE価格指数が前年同月比6.3%、コア指数が同4.9%と目標の2%を大きく上回っている(第Ⅰ-2-2-40図)。
第Ⅰ-2-2-40図 PCE価格指数の推移
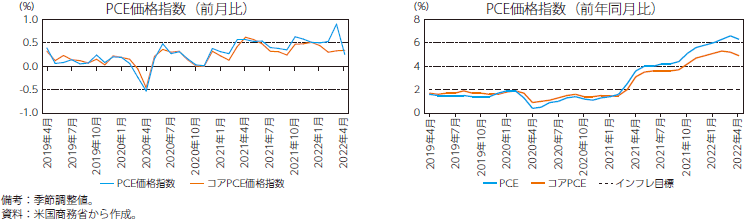
インフレ率が目標の2%を越える状況について、2021年9月のFOMCの声明文においては、あくまで一過性のインフレであるとの認識を示してきたが、FRBのインフレに対する認識はFOMCの開催を重ねるにつれて、インフレが一過性ではなく継続的であり、かつ大幅に水準を越えたものへと認識が改められてきた(第Ⅰ-2-2-41表)。
第Ⅰ-2-2-41表 FOMCにおけるインフレに関する声明文及び発言内容
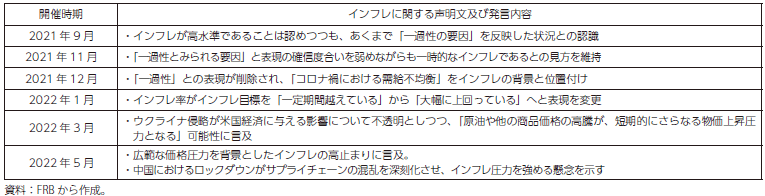
2022年1月までのFOMCにおいては、インフレの水準や影響を及ぼす期間について言及してきたが、2022年3月のFOMCにおいては新たにウクライナ侵略の影響について言及しており、米国経済への影響は不透明としつつ、原油や他の商品価格の高騰が、短期的に物価上昇圧力となる可能性を示している。
インフレを抑制するため、2022年1月のFOMCでは、まもなく利上げを行う状況にあるとして、2020年3月15日以降据え置いてきた政策金利について、2022年3月のFOMCにおける利上げを事実上予告した。このように事前に利上げを事実上予告することによって市場の混乱を未然に防ぐ意図がうかがえる。その後、2022年3月の会合において政策金利を現行の0.00%~0.25%から0.25%~0.50%へと引き上げることを決定し、2018年12月以来約3年ぶりの利上げとなった。さらに、2022年5月には2000年5月以来の0.5%ポイント利上げとなり、0.75%~1.00%へと引き上げられた(第Ⅰ-2-2-42図)。
第Ⅰ-2-2-42図 米国における政策金利の推移
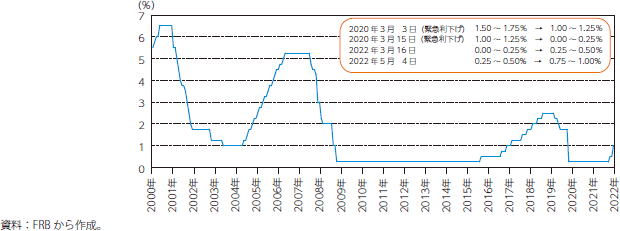
今後の米国の経済見通しについて、FRBは失業率に関しては改善基調を映じて見通しを修正してきた一方で、目下のインフレ高進を受けて、PCE価格指数やコアPCE価格指数については上方修正を繰り返してきた。特に2022年3月時点での経済見通しにおいては実質GDP成長率とインフレ率が大幅に修正されている。実質GDP成長率見通しが、2022年を+2.8%と前回(+4.0%)から大幅に下方修正し、2023年、2024年は前回から変更していない。また、インフレ率を示すPCE価格指数は2022年を+4.3%と前回(+2.6%)から大幅に上方修正。2023年以降もインフレ目標である2%を小幅に上回る見通しとしている(第Ⅰ-2-2-43表)。
第Ⅰ-2-2-43表 FRB による経済見通し(2022年3月時点)
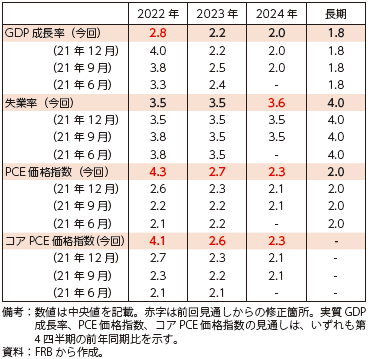
また、現下のロシアによるウクライナ侵略の状況について、パウエル議長は、ウクライナ侵略に関連する出来事がインフレに更なる上振れ圧力を生み出しており、経済活動の重しとなる可能性について述べている。また、そのため、今後も事態の変化や、経済に与える影響に関する分析が進むことに伴い、上記の経済見通しについても見直され得る。
このような経済見通しを踏まえて、FOMCの参加者による政策金利の予測を可視化したドットチャートは上方シフトを続けている(第Ⅰ-2-2-44図)。
第Ⅰ-2-2-44図 FOMCにおける政策金利の予測(ドットチャート)
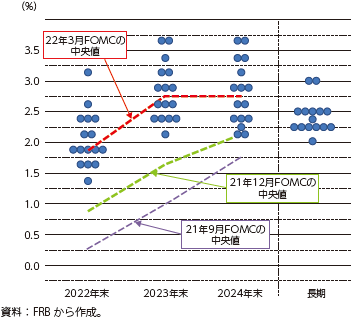
上図におけるドットチャートの中央値に従えば、2022年に7回の利上げを示唆しており、2021年12月予測(3回)から利上げを急ぐ姿勢が鮮明となっている。2023年は累計で11回と2021年12月(6回)から上方シフトし、2024年には政策金利が据え置かれる見通しとなっている。
これまで利上げ開始後に議論を具体化することとしてきた量的引き締め(QT: Quantitative Tightening)については、2022年5月に開催されたFOMCにおいて、2022年6月1日より削減を開始することを決定した。2022年6月から8月の米国債の減額ペースの上限を月300億ドル、その後は月600億ドルに引き上げることとした。また、政府機関保証の住宅ローン担保証券については2022年6月から8月は月175億ドル、その後は月350億ドルとしている。これは2017年から2019年にかけて行われた量的引き締めよりも速いペースで縮小する内容となっている(第Ⅰ-2-2-45図)。
第Ⅰ-2-2-45図 FRBの保有資産の推移(4週間移動平均)
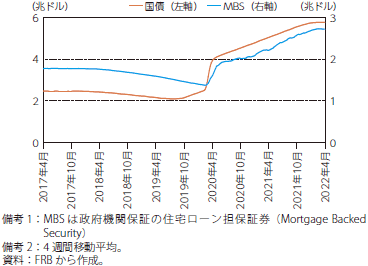
2021年11月のFOMCで開始が決定されたテーパリング94は2022年3月に終了し、インフレが高止まりする中で、2022年3月には政策金利の引き上げ、2022年5月には量的引き締めの開始がそれぞれ決定された。ゼロコロナ政策に伴う中国における新型コロナウイルスの再拡大やロシアによるウクライナ侵略によってインフレ圧力が高まり、経済への影響の不透明さが増す中、今後の政策金利や量的引き締めのペース、それらの経済への影響が注目される。
94 2021年11月からテーパリングの開始を決定し、月当たりの資産購入ペースを「米国債については100億ドル、MBSについては50億ドルずつ減額する」とした。さらに、2021年12月のFOMCでは毎月の資産購入ペースを、米国債は月200億ドル、MBSについては月100億ドルずつ減らすこととし、テーパリングの速度を2倍とすることを決定した。2022年1月のFOMCにおいては、同年3月上旬に資産購入を終了することを決定した。