第5節 インド・東南アジア経済の動向
1.経済の動向
(1)実質GDP成長率
新型コロナウイルス感染拡大の影響により2020年のインド、東南アジア(ここではインドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン、シンガポール、ベトナムを指す。)の経済は大きく下押しされ、ベトナム以外はマイナス成長となった。2021年はその反動でプラス成長となっている(第Ⅰ-2-5-1図)。
第Ⅰ-2-5-1図 各国の実質GDP成長率(前年比・前年同期比)
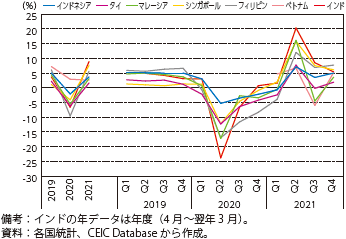
2021年の実質GDPについて2019年比で見ると、ベトナム、シンガポール、インドネシア、インドは2019年の水準を上回ったものの、タイ、マレーシア、フィリピンは回復が遅れ、同水準を下回った(第Ⅰ-2-5-2図)。2021年の四半期の動きを2019年同期比で見ると(同図)、変異株による感染の再拡大やワクチン接種の遅れもあり、インドでは第2四半期、東南アジアでは第3四半期にシンガポール以外の国々で下押しされた。季節調整値が公表されているシンガポール、フィリピン、タイ、マレーシアについて2019年の第4四半期を100として推移を見ても、シンガポールは2021年第1四半期に100を超え、その後も堅調に推移しているが、タイ、マレーシア、フィリピンは回復に時間がかかっており、直近の2021年第4四半期においても100を下回っている(第Ⅰ-2-5-3図)149。
第Ⅰ-2-5-2図 2019年比で見た2020年、2021年の実質GDP成長率
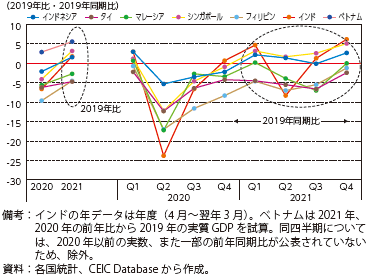
第Ⅰ-2-5-3図 実質GDPの推移(季節調整済、2019年Q4 = 100)
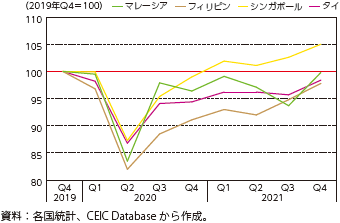
149 本節は2022年4月末時点で記述。
(2)輸出
各国の財輸出(原数値ベース)について、2019年各月の平均を100として2020年1月以降の推移を見ると、感染拡大とそれに伴う制限措置が取られた時期には落ち込みが見られるものの、中国や米国の経済回復等を背景におおむね堅調に、特に2021年後半以降はここで取り上げている全ての国で100を上回って推移している(第Ⅰ-2-5-4図)。
第Ⅰ-2-5-4図 各国の財輸出(2019年平均= 100)
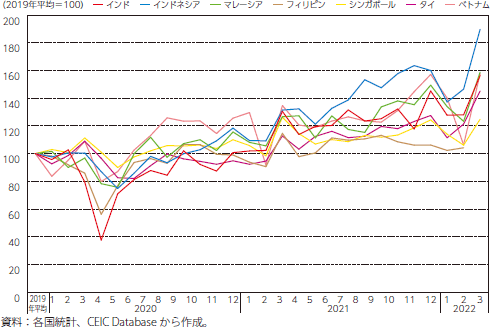
<世界のサプライチェーンへの影響>
東南アジア諸国は、エレクトロニクス関連製品や自動車部品等の生産により、世界の製造業のサプライチェーンにおいて重要な位置を占めている。第Ⅰ-2-5-5~6図は、米国、ドイツの集積回路の調達先、第Ⅰ-2-5-7図は、日本の点火用配線セット(自動車部品)の調達先の国別内訳を見たものである。2021年夏にデルタ株による感染再拡大が起こった際には、マレーシアやベトナムで工場の操業が制限された。これらの国からの部素材調達が困難になったことで、例えば、各国の自動車生産に影響し、特に日本の落ち込みが大きかった(第Ⅰ-2-5-8図)ほか、ASEAN域内の生産拠点においても調達に支障が生じたことから、現地製造企業から調達先の切替えによるコスト増や、切替え先の感染拡大による調達困難リスク等を懸念する声が聞かれた150。
第Ⅰ-2-5-5図 ASEANからの輸入比率(米国・集積回路・2021年)
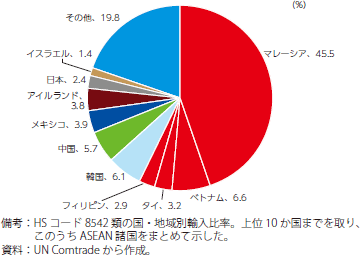
第Ⅰ-2-5-6図 ASEANからの輸入比率(ドイツ・集積回路・2021年)
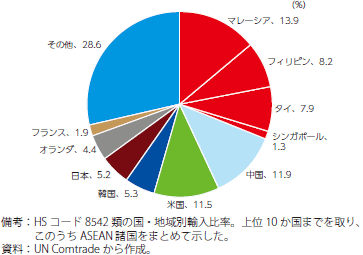
第Ⅰ-2-5-7図 ASEANからの輸入比率(日本・自動車部品(点火用配線セット)・2021年)
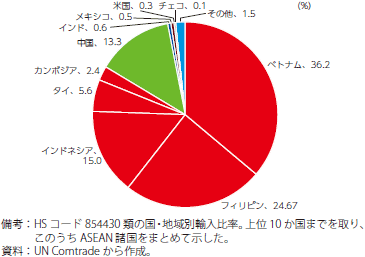
第Ⅰ-2-5-8図 日本、米国、ドイツの自動車工業の生産指数の推移
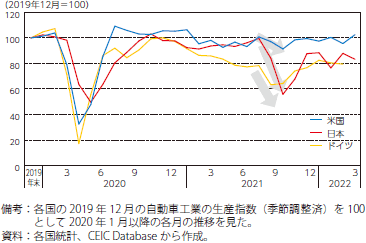
150 上野渉(2021)「新型コロナ感染拡大による製造業サプライチェーンへの影響懸念、インドネシア日系企業(インドネシア、タイ、マレーシア)」(2021年8月19日)(JETROウェブサイト)、野木森(2021)を参考にした。
(3)消費者物価
2019年の各月の原指数平均を100として、2020年以降の各国の消費者物価指数の推移を見ると、特にインドの物価上昇ペースが速い(第Ⅰ-2-5-9図)。インドでは、新型コロナウイルス感染拡大に伴う活動制限でサプライチェーンが寸断されたことによる供給制約や天候不良等により、2020年は食料価格が急速に上昇している。同年末から2021年春までは同価格の上昇ペースが鈍化したものの、その後は再び上昇ペースが加速した。また、2021年を通じて燃料価格が上昇しており、足下(2022年3月時点)、更に上昇ペースが加速している(第Ⅰ-2-5-10図)。2021年半ば以降、世界各国の経済活動に伴う需要の拡大や世界的なコンテナ不足に伴う輸送コストの上昇、国際的な資源高の影響を受け、インド以外の国々の物価上昇スピードも増している。今後は、ウクライナ情勢に伴う原油や小麦の価格上昇の影響を注視する必要がある。
第Ⅰ-2-5-9図 各国の消費者物価
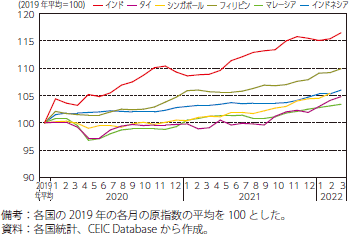
第Ⅰ-2-5-10図 インドの消費者物価内訳指数の推移
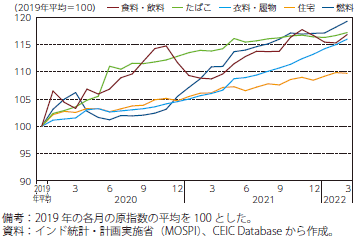
(4)財政・金融政策
① 財政政策
各国では、新型コロナウイルス感染拡大による経済社会への多大な影響に対処するため、各種の財政措置が講じられている。そうした措置として、貧困層や失業者向け支援や雇用対策、コロナ禍で特に打撃を受けた産業セクターへの支援といった下支え策のほか、医療物資や食料の安定的な確保等、経済のレジリエンスの強化策等が盛り込まれている(第Ⅰ-2-5-11表)。
第Ⅰ-2-5-11表 各国のコロナ対応のための財政措置の例(2020~2021年)
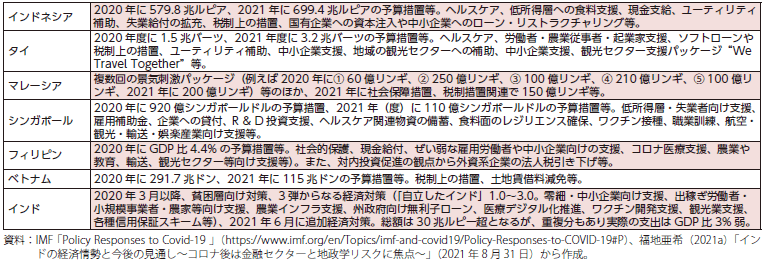
2010年からの各国の財政収支対GDP比の推移を見ると、シンガポールや国によってはいくつかの単年の動きを除いておおむね赤字で推移してきており、コロナ対策による財政出動で2020年は、各国とも財政状況が大幅に悪化した。経済活動の再開により財政状況の改善が期待されるものの、シンガポールを除いて2022年も財政赤字が続く見通しである(第Ⅰ-2-5-12図)。
第Ⅰ-2-5-12図 各国の財政収支対GDP比
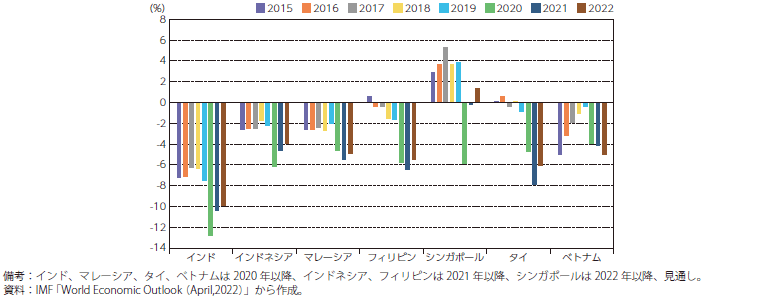
② 金融政策
新型コロナウイルス感染拡大による経済の落ち込みを金融面から下支えするため、各国中央銀行は政策金利を引き下げ(第Ⅰ-2-5-13 図)、緩和的な政策スタンスを維持している151が、物価上昇圧力の強まりを受けて金融正常化を探る動きもある。シンガポールは、為替管理を通じた金融政策を行っているが、2021年10月、2022年1月及び4月に、名目実効為替レート(NEER)の政策バンドの傾きを上昇させる金融引締めの措置を取っている152。また、インド準備銀行(RBI)は2022年4月6~8日の金融政策会合で政策金利を過去最低の4%に据え置いた一方、新たに常設預金ファシリティ(SDF: Standing Deposit Facility)を導入し、誘導性調整ファシリティ(LAF)のコリドー(金利コリドー)の下限を従来のリバース・レポレート(3.35%)からSDF(3.75%)に変更、コリドーの幅をコロナ前の50bpに戻した。なお、インド準備銀行は6月の定例会合を待たず、5月に利上げ(4.0%から4.4%)に踏み切った(利上げは3年9か月ぶり)。
第Ⅰ-2-5-13図 各国の政策金利の推移
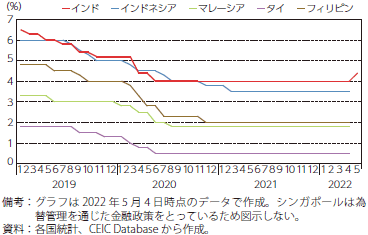
151 2022年4月現在。
152 西濵(2022)
2.経済回復の特徴と課題
(1)ウィズ・コロナへの政策シフトと今後のリスク要因
東南アジア諸国やインドでは、複数回の新型コロナウイルス感染拡大の波が起こっており(第Ⅰ-2-5-14図)、経済の動向も感染拡大(とそれに伴う活動制限)の状況に左右されてきたといえる。ワクチン接種の進展の程度(第Ⅰ-2-5-15図)にも大きく影響された。シンガポールは、比較的早い時期にワクチン接種が進んだこともあり経済回復も堅調に進んだが、ワクチン接種が遅れたタイやマレーシア、フィリピンでは経済回復のスピードも緩慢である。
第Ⅰ-2-5-14図 ASEAN、インドの新型コロナウイルス新規感染者数の推移(7日平均)
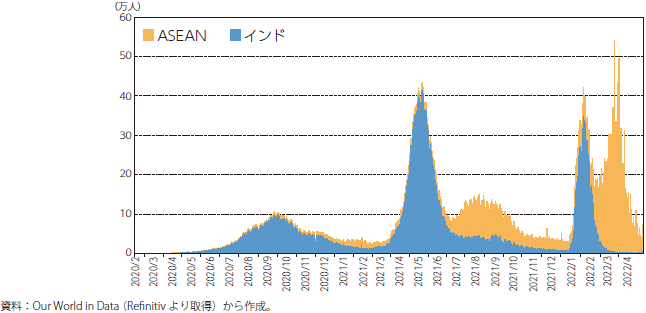
第Ⅰ-2-5-15図 ワクチン接種完了人数の割合(人口当たり)
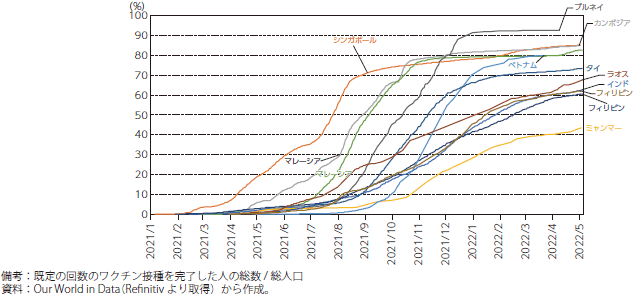
海外からの入国制限や消費の下押しで、内需の回復には時間が掛かっているが、世界経済の回復に伴う輸出の伸びもあり、2021年第4四半期には各国経済も回復基調を強めている。また、徐々にワクチン接種が進んだことで、各国では新型コロナウイルス感染症を「エンデミック(流行の定常化)」とみなし、ワクチン接種を進めながら経済活動を継続する「ウィズ・コロナ」へと政策をシフトさせている。2022年1~3月は、オミクロン株による感染が拡大したが、重症化率が低く医療体制がひっ迫する事態にはなっていないことから、ロックダウンなどの厳格な制限措置は採られていない153。海外からの入国制限の緩和(ワクチン接種済みの入国者に対する隔離措置の免除等154)も徐々に進められており、これまで低迷を余儀なくされた観光関連セクター等の回復やビジネス人材の往来の本格再開による貿易・投資活動の活発化等が期待される。
こうした「ウィズ・コロナ」政策の下で、経済回復の動きが加速することが期待されるものの、ロシアによるウクライナ侵略に伴う地政学的緊張の高まりによる国際的な資源・コモディティ価格や輸送費等の上昇に伴うインフレの進行、米国の金融政策の正常化の影響(資本流出や通貨下落、金融の不安定化リスク等)に注意が必要である。また、「ゼロコロナ」政策を敷く中国において足下(2022年4月時点)、オミクロン株の感染拡大に伴うロックダウン等、制限措置の厳格化が見られ、経済の下押しが懸念される。中国経済の減速に伴う需要減や、中国における生産停止によるサプライチェーンへの影響等に注意が必要である。直近の国際機関(IMF)の実質GDP成長率の見通しについては第Ⅰ-2-5-16表のとおりである。
第Ⅰ-2-5-16表 実質GDP成長率の見通し(IMF)
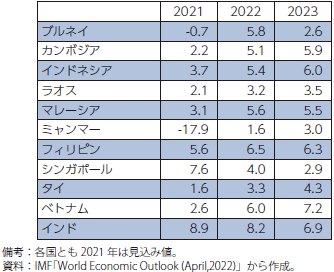
153 斉藤(2022)
154 対象国やPCR検査の要否等、国により運用は異なる。
(2)中長期的な成長に向けた取組
東南アジア諸国やインドにおいては、コロナショックからの回復のための予算措置が講じられ、各種政策パッケージが実施されているところであるが、経済の回復が進むにつれ、足下の問題への対応に加えて、これまで各国が直面してきた構造的な問題や中長期的課題への取組の重要性が改めて意識されると考えられる。例えば、根強く残る貧困や社会的弱者をめぐる課題、いわゆるインフォーマル経済に包含されてぜい弱な雇用環境にある人々や衛生・安全面で問題のある労働環境等のディーセントワークをめぐる課題、医療や水、電力といった基本的なインフラ不足の問題、サプライチェーンの寸断による供給途絶の問題、気候変動問題を始めとするサステナビリティをめぐる課題、また「中所得国の罠」(第Ⅰ-2-5-17図)として捉えられている経済発展と成長をめぐる課題等が挙げられる。各国はコロナ禍前より、中長期的な成長戦略を策定して取組を進めてきている。近年のテーマとしては、デジタル経済化や、デジタル技術を通じた第四次産業革命の推進、投資促進といった経済の高付加価値化・産業高度化を目指す取組、気候変動問題への対応などサステナビリティの実現を目指す取組が大きな軸となっている(第Ⅰ-2-5-18表)。
第Ⅰ-2-5-17図 中所得国滞留年数
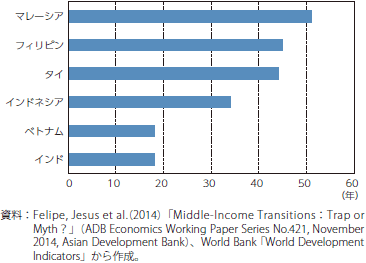
第Ⅰ-2-5-18表 ASEAN諸国、インドの産業戦略の例
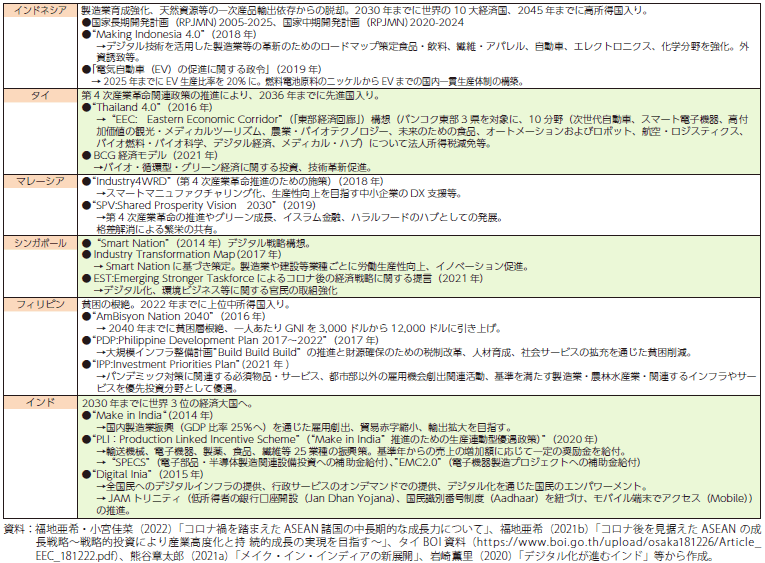
① 経済の高付加価値化・産業高度化に向けた取組
経済の高付加価値化・産業高度化に向けた取組について、中所得国の滞留年数が長く高齢化が進みつつあるタイ、輸出における一次産品の比率が高いインドネシアに加えて、人口規模とデジタル経済の発展がもたらす成長のポテンシャル155に期待が集まる一方、製造業の発展に課題があり貿易赤字を抱えるインドの3か国を例にとり、各国の取組と課題について概観する。
●タイ
タイは東南アジアの中でも早くに産業化が進み、貿易や対内投資の拡大によって成長を遂げてきた。日本からの直接投資も活発に行われており、現地に立地して生産や販売を行っている日本企業の数もASEANの中で最多となっている(2020年10月1日時点で5,856社156)。
ASEANの中の一大製造拠点として発展してきたタイであるが、中所得段階に40年以上滞留しており(第Ⅰ-2-5-17図)、「中所得国の罠」のリスクに対応していく必要がある。今後も人口ボーナス期が続くと見込まれるアジアの後発国や、"China plus One"の有力な候補地として注目を集めているベトナムなどが労働集約部門の担い手として関心を集めている中、人口ボーナス期を過ぎたタイにとって、産業の高度化・高付加価値化が大きな課題となっている。特にベトナムがイノベーション面でもタイを追い上げてきていることも意識されていると考えられる157。タイは、2036年の先進国入りを目指し、産業戦略上の重要分野、将来の成長分野として、次世代自動車やスマート電子機器といった製造部門のほか、高付加価値の観光・メディカルツーリズム、バイオテクノロジー、自動化・ロボット技術、ロジスティクス、デジタル経済などの分野に法人所得税減免の優遇措置を設け、タイ東部3県にまたがる経済特区(「東部経済回廊」)への投資促進により第四次産業革命を推進していく成長戦略"Thailand 4.0158"を推進している。新型コロナウィルス感染拡大によりプロジェクトには遅れも見られるが、入国制限の緩和や経済の回復に伴い再開、進展していくことが期待される。
タイは、少子・高齢化が急速に進展しており、慢性的な人手不足という構造的な問題に直面しており、2020年を除き、近年の失業率は1%台で推移している(第Ⅰ-2-5-19図)。ASEAN域内の他の国々(シンガポールを除く)やインドに比べても、足下の高齢化率は既に高く、今後も急速に高齢化が進んでいく見通しである(第Ⅰ-2-5-20図)。マネジメント、エンジニア、ワーカー等、様々な職種で人材不足が指摘されており、コロナ禍により、外国人材の入国が制限されたことで、人手不足の問題にさらに拍車がかかっている。産業高度化を支える高度人材の育成も急がれる。また、タイは、後述のインドと似て、GDPに占める比率の低い農業に従事している就業者の比率が高い(2020年時点で31%)。特に農村においてベビーブーム世代の滞留が指摘されており159、高齢化も都市部より早いスピードで進展していくと考えられる。それに起因する様々な社会課題の解決に向けた取組も求められている。
第Ⅰ-2-5-19図 タイの失業率の推移
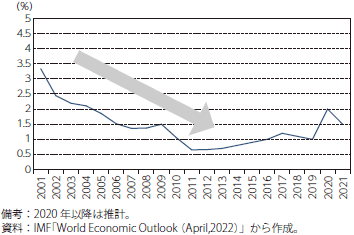
第Ⅰ-2-5-20図 アジア各国の高齢化率(65 歳以上人口比率)の見通し(中位推計)
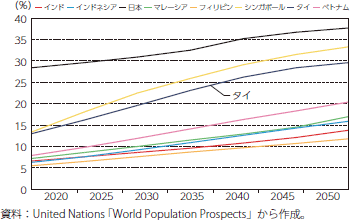
●インドネシア
インドネシアも中所得国段階に30年以上とどまっており、「中所得国の罠」のリスクが懸念される。インドネシアは、2030年までに世界の10大経済国に、2045年までに高所得国になることを目指して、中・長期の国家開発計画や、デジタル技術を活用した製造業等の革新のためのロードマップ"Making Indonesia 4.0"を策定し、天然資源等の一次産品輸出依存(第Ⅰ-2-5-21図)からの脱却と国内付加価値の増大に向けた取組を行っている。特に、サステナビリティとの関係で成長が期待され、インドネシアの脱炭素のコミットメント160でも言及されている電気自動車の開発・製造について、リチウムイオン電池原料のニッケル鉱採掘から自動車本体までの国内一貫生産体制の構築を目指している。このうちリチウムイオン電池の製造については、ニッケル鉱採掘・製錬、電池製造、充電設備整備、電池のリサイクル等全般にわたる役割を担うため、2021年3月、国営インドネシアバッテリー公社(IBC)が設立された。リチウムイオン電池のサプライチェーン構築には大規模な投資161や高度な技術が必要とされており、海外企業との連携が重要になってくる。日本企業のほか、中国や韓国、台湾の企業などが合弁会社への出資を行い、電気自動車関連の製造拠点設置に向けた動きを見せるなど、インドネシアの電気自動車サプライチェーン構築に積極的に参画している。
第Ⅰ-2-5-21図 インドネシアの輸出における品目別内訳(2021年)
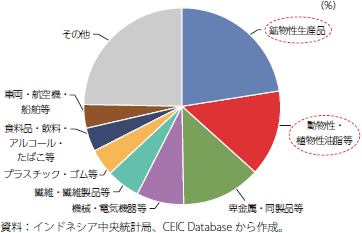
こうした取組がインドネシアの産業高度化、経済の高付加価値化につながっていくことが期待されるが、課題もある。例えば、電気自動車用の充電設備については、インドネシア政府は2030年までに一般充電ステーションを3万1,859台、電動二輪用の一般電池交換ステーションを6万7,000台に増設する計画だが、2021年末時点で前者は267台、後者は266台にとどまっている162。リチウムイオン電池の国内製造推進の取組は、世界最大のニッケル鉱埋蔵量を有するインドネシアならではの強みを活かした産業戦略といえるが、鉱物資源の国内付加価値向上のために実質的なニッケル鉱の輸出停止を行っていることなどには、国際貿易ルール上の懸念がある163。
●インド
インドの経済規模(名目GDP)は、2021年時点で世界6位164であるが、インド与党(BJP)は2030年までに世界3位となることを目指している。しかしながら、世界の工場としてグローバルなバリューチェーンに参画することで高成長を実現した中国と比べ、GDPの伸びは緩慢である(第Ⅰ-2-5-22図)。GDPに占める比率が18%程度の農業に就業人口の40%以上が従事しており(第Ⅰ-2-5-23図)、農業の生産性の向上とともに、農村に滞留する労働力を吸収する産業の育成が求められているといえる。新興国では、繊維加工や機械の組立てといった製造業の労働集約部門の雇用創出力が期待されるが、インド経済における製造業の比率は1970年代に若干上昇したものの、その後は同程度の比率にとどまり、2010年代は低下傾向にある(第Ⅰ-2-5-24図)。インドの場合、経済における農業の比率の低下とともに、製造業ではなくサービス業の比率が上昇している点が特徴的である(同図)。製造業の付加価値が伸び悩む中、貿易収支も大幅な赤字となっており、インドの経常収支は慢性的に赤字である(第Ⅰ-2-5-25図)。通貨や物価安定の観点からは経常収支赤字の縮小が望ましく、赤字の主要因である貿易収支の改善が求められている。
第Ⅰ-2-5-22図 インドと中国の名目GDP の推移
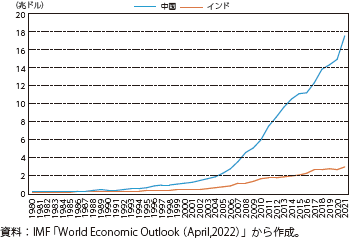
第Ⅰ-2-5-23図 インドの産業・就業構造(2020年)
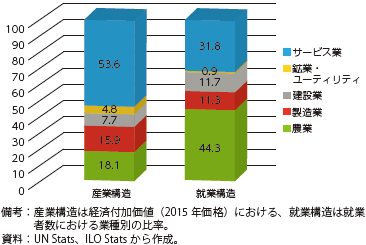
第Ⅰ-2-5-24図 インドの産業別付加価値比率の推移
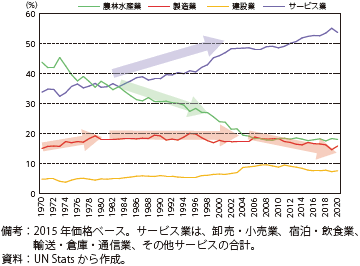
第Ⅰ-2-5-25図 インドの経常収支の推移
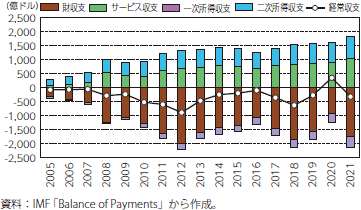
モディ政権は、2014年に産業振興策"Make in India"を打ち出し、投資環境の整備を通じた直接投資の促進、国内製造業振興を通じた雇用創出、貿易赤字縮小、輸出拡大を目指すとともに、GDPにおける製造業の比率を25%に引き上げるべく取組を進めている165。2020年には、"Make in India"推進のための生産連動型優遇政策である"PLI:Production Linked Incentive Scheme"が導入された。これは、輸送機械、電子機器、製薬、食品、繊維等の振興のため、基準年からの売上の増加額に応じて一定の奨励金を給付するものである。これまでに自動車や自動車部品、白物家電など、産業分野ごとのPLI対象企業が順次決定されており、日本企業も選定されている。PLIと平行して"SPECS"(電子部品・半導体製造関連設備投資への補助金給付)、"EMC2.0"(電子機器製造プロジェクトへの補助金給付)、"FAME"(電気自動車購入補助金)などのスキームも用意されている。インドでは海外の携帯電話メーカーやその受託生産企業等の集積が進んできており、通信機器の国内生産額も2010年代半ば以降、急速に増大している(第Ⅰ-2-5-26図)。これと並行して携帯電話の輸入の減少が見られ、特に2019年以降は、輸出が輸入を上回って推移する(第Ⅰ-2-5-27図)など、携帯電話の生産・輸出拠点としてのポテンシャルを示しつつある。PLIについては携帯電話等のエレクトロニクス分野のほか、自動車・自動車部品、白物家電、医薬品等についても対象企業の認定が行われており、今後の動きが注目される(医薬品については既に2000年代半ば以降、急速に輸出が拡大している(第Ⅰ-2-5-28図))。その一方で、輸入依存度を下げ国内生産を増やすために製造品目の関税を段階的に引き上げる「段階的製造プログラム(PMP:Phased Manufacturing Programme)」を導入していること等には、GATT等、国際貿易ルール上の懸念がある166。また、中間財等の関税引き上げを行っていることで加工組立て産業の立地誘致には逆効果である可能性もあるとの指摘もある167。
第Ⅰ-2-5-26図 インドの通信機器の生産額の推移
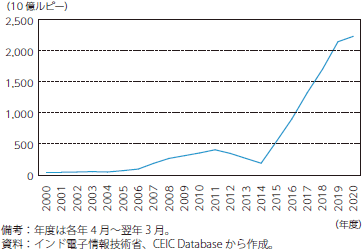
第Ⅰ-2-5-27図 インドの携帯電話機(HS851712)の輸出入額の推移
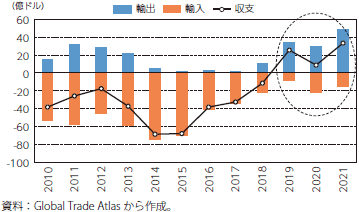
第Ⅰ-2-5-28図 インドの医薬品、エアコン、自動車、自動車部品の輸出額の推移
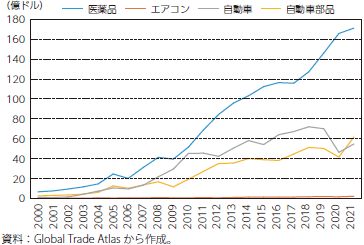
<アジアの成長と課題~投資の不足~>
インドやASEAN諸国等、アジアの新興諸国が現在の経済成長を維持しつつ、貧困を撲滅し、気候変動にも対応していくためには、膨大なインフラ投資が必要となる。第Ⅰ-2-5-29図は、各国の投資率(名目GDPに占める総固定資本形成の比率)の推移を見たものである。ASEAN諸国では1997年のアジア通貨危機後、投資率が大きく落ち込んだ。インドネシアは、2010年代に30%台に回復しているが、タイやマレーシアでは、より低位にとどまっている。アジア開発銀行の推計によれば、2016年から2030年までの間に必要となるインフラ投資額は東南アジア168で、ベースラインで1,470億ドル、気候変動への対応を含んだケースで1,570億ドル(うち、インドネシアがそれぞれ700億ドル、740億ドル)、インドでそれぞれ2,300億ドル、2,610億ドルを見込む(第Ⅰ-2-5-30図)。不足額(2015年時点の投資額との差)の対GDP比は、気候変動対応を考慮したケースの場合、東南アジアで4.1%(うちインドネシアでは5.1%)、インドでは5.3%に相当する(第Ⅰ-2-5-31図)。なお、GDP比で見た場合のインフラ投資の不足は、アジア全体では気候変動対応を考慮したケースで2.4%となっており、インドや東南アジアではアジア平均を大きく上回っていることが分かる169。
第Ⅰ-2-5-29図 アジア諸国の投資比率(総固定資本形成対GDP比)の推移
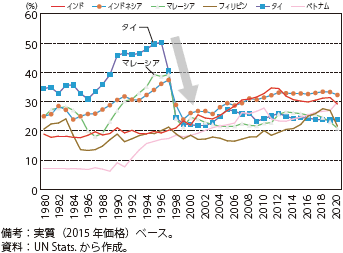
第Ⅰ-2-5-30図 2016~2030年までの年間インフラ投資需要額
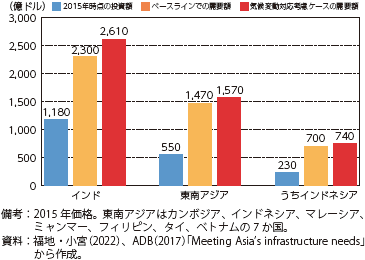
第Ⅰ-2-5-31図 2016~2030年までの年間インフラ投資需要額に対する不足額対GDP比
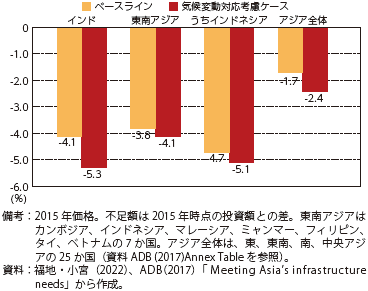
また、中所得国の罠を回避し経済の高付加価値化を目指すためには、研究開発投資の増大が必要であるが、インドやASEAN諸国のGDPに占める研究開発支出は低位にとどまっている(第Ⅰ-2-5-32図)。
第Ⅰ-2-5-32図 アジア諸国の研究開発支出対GDP比の推移
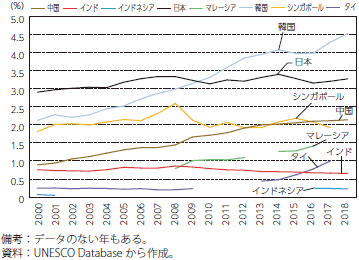
② サステナビリティをめぐる課題 ~気候変動問題への対応から~
東南アジアでは、近年、気候変動を原因とする災害が多発しており、経済社会にも深刻な影響が及んでいる。各国も、カーボンニュートラル目標や再生エネルギー導入目標を表明し、取組のためのマスタープランを策定している(第Ⅰ-2-5-33表)が、アジア諸国の足下の電源構成を見ると、CO2排出比率の高い石炭火力に依存している国々も多く(第Ⅰ-2-5-34図)、再生エネルギーの利用についても、天候や地理的な条件に鑑みると世界の他地域に比べ安定的な確保は容易ではない(具体的には、降水量が多く、未利用の遊休地が少ないため、中東やアフリカ、豪州内陸のような砂漠地帯と比べて太陽光による実発電効率が低い、また、一部の沿岸部を除き欧州と比べて風速が弱く、台風等の影響から年間を通じた安定的な風力エネルギーが得にくい等の実情がある170)。東南アジアの電力需要は2020年時点の1,111TWhから2050年時点で2,843TWhと今後30年間で2.5倍以上になる見込みであり、当該増加分を全て再生エネルギーで賄うといったアプローチは、アジア諸国にとって必ずしも現実的ではない171。また、カーボンニュートラル目標達成のためには、エネルギーの脱炭素化、各分野でのエネルギー効率の改善、土地の利用方法の変更等といった大規模な取組が求められる。ある試算では、パリ協定の目標達成のために2050年までの毎年東南アジアが必要とする投資額は約1,410億ドルに上る172。こうした資金需要を満たすためのファイナンスの拡充が求められるほか、アジアの実情を反映した多様なアプローチで脱炭素化への移行の取組(トランジション)を支援するプログラムが必要である。
第Ⅰ-2-5-33表 ASEAN諸国、インドのカーボンニュートラル達成時期、再生エネルギー導入に関する目標
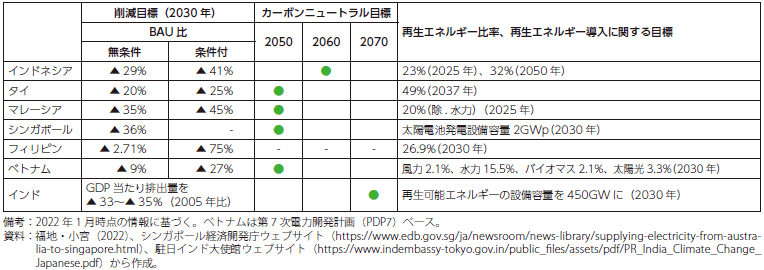
第Ⅰ-2-5-34図 ASEAN諸国、インドのエネルギー別電源構成(2020年)
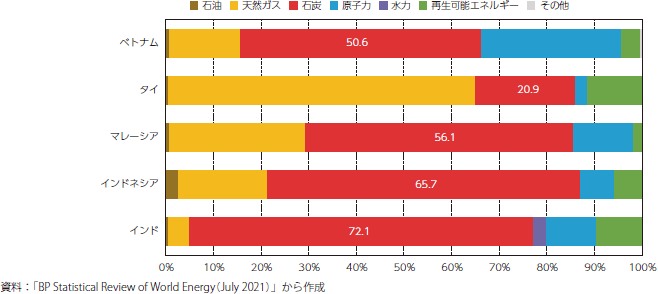
③ アジアの課題解決に向けた日本政府の取組
東南アジアやインド等、アジア新興諸国の諸課題の解決に向けて、日本としてもアジアのパートナーとしての役割を果たしていくことが求められている。経済の高付加価値化、産業の高度化への取組における技術面、人材面での協力や、環境問題や少子高齢化の問題等、日本が課題先進国として取り組んできた分野について、その経験を活かした協力、アジア諸国と類似したエネルギー構造を有する日本ならではのカーボンニュートラルに向けた支援等が挙げられる。また、デジタル技術の活用を通じてアジアの社会課題を解決する取組やアジアのサプライチェーンの強靭性を高める取組においてアジアとの連携を深めることは、日本の成長にとっても重要な意味を持つ。
経済産業省は、2021年5月、「アジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ(AETI)」を公表し、各国のカーボンニュートラルの実現のためのロードマップ策定支援や、現実的なエネルギートランジションに向けた1億ドル規模の先導的な事業展開(アンモニア混焼等によるゼロエミッション火力発電の推進等)、アジア版トランジションファイナンスに向けた検討、再生可能エネルギーやエネルギーマネジメントビジネスに関する官民一体となった協力の推進等、具体的な支援に取り組んでいる。また、2021年10月の日ASEAN首脳会談において日本から提唱した「日ASEAN気候変動アクション・アジェンダ2.0」に基づき、ASEAN地域の脱炭素社会への移行に向けた取組を推進している。日本政府は、このAETIや「日ASEAN気候変動アクション・アジェンダ2.0」を強化・具体化しつつ、ゼロエミッション技術の開発や水素インフラでの国際共同投資、共同資金調達、技術等の標準化、カーボンクレジット市場を含む「アジア・ゼロエミッション共同体構想」の実現を目指し、アジア諸国との連携を推進していく。このほか、本白書第Ⅱ部第2章でも触れているように、アジアの社会課題解決と価値創造のためのDX事業支援にも取り組んでいる。2022年1月に公表した「アジア未来投資イニシアティブ(AJIF: ASIA-Japan Investing for the Future Initiative)」で示されているように、例えば、国内産業の育成によりサプライチェーンでより付加価値の高い分野を担うことや、新たな産業づくりに向けた基盤となるデジタル化等の技術・ノウハウ・人材を獲得・育成すること、デジタル化・電子化を通じて貿易手続コストを削減し貿易を拡大すること、サプライチェーン管理を高度化すること、社会課題の解決とサステナビリティを実現すること、高齢化が進んでいく中で高齢者等へのケアサービスや健康促進の取組を導入することといった課題に関するASEAN諸国の深い関心を踏まえ、サプライチェーン、連結性、デジタル・イノベーション、人材、グリーン・脱炭素の五つの分野で協力が実施されていく。こうした取組を通じて、日本とアジアが一体となって持続的な成長を実現していくことが期待される。
155 本書第Ⅱ部第2章第2節参照。
156 外務省(2021)「海外進出日系企業拠点数調査」(2021年7月20日)(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page22_003410.html![]() )、タイ
については元データとして示されているJETRO バンコク事務所「タイ日系企業進出動向調査2020 年」の数値で他の国々と比較した。
)、タイ
については元データとして示されているJETRO バンコク事務所「タイ日系企業進出動向調査2020 年」の数値で他の国々と比較した。
157 世界知的所有権機関(WIPO)の“Global Innovation Index” におけるイノベーションに関する国別ランキング(2021 年)で、タイは43 位、 ベトナムは44 位であった。
158 タイ政府は、農業中心の「1.0」、軽工業中心の「2.0」、重工業中心の「3.0」、デジタル技術による産業の高度化を目指す「4.0」と経済の段 階的移行を説明(上原(2017))。
159 大泉(2019)
160 インドネシアは2060年のカーボンニュートラルを目指しており、NDCにおいて脱炭素化された電気の利用、効率的な交通機関システムや電気自動車の開発を明記している(上野渉、シファ・ファウジア(2022)「EV車両・電池のサプライチェーン拠点化を目指す(インド ネシア)」(2022年3月25日)(JETROウェブサイト)。
161 IBCによると年間最大140GWhの電気自動車用電池のサプライチェーン構築には総額約153億ドルの投資が必要となる(上野・ファウジ ア(同))。
162 上野・ファウジア(同)。
163 インドネシアは鉱物資源の高付加価値化のため、2009年の新鉱業法に基づき、2014年以来、未加工鉱物の輸出制限を行ってきた。一部緩和措置が採られる等の運用の変更もあるが、ニッケル鉱については、現在、完全禁輸措置が採られている。日本は新鉱業法の成立以降、WTOの物品理事会・TRIMs委員会、日インドネシアEPAに基づく投資小委員会において繰り返し懸念を表明。首脳レベルや閣僚レベ ルでも懸念を表明している。2019年11月、EUは本件についてWTO紛争解決手続上の協議要請を行い、2021年2月、パネルが設置さ れている(経済産業省(2021)「不公正貿易報告書2021」)。
164 IMF「World Economic Outlook (April, 2022)」による推計。米ドルベース。
165 坂本 純一(2021)「メイク・イン・インディアの成果に夜明け? 貿易赤字からひも解く経済構造」(2021年4月22日)(JETROウェブサイト)。なお、2014年時点の製造業の比率は約16%。
166 日本政府はインドとの二国間対話において懸念を表明し、措置の改善を求めてきたが、解決には至っていない。2020年3月、日本はインド政府に対し、パネル設置要求を行い、同年7月にパネルが設置された。本件については、2020年6月にEU、2020年7月に台湾のパネルが設置されている(経済産業省(2021)「不公正貿易報告書2021」)。
167 熊谷章太郎(2021b)。なお、本パラグラフの記述は、同資料を参考にした。
168 ここでは、カンボジア、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、タイ、ベトナムの7か国。
169 本パラグラフの記述は、福地・小宮(2022)「コロナ禍を踏まえたASEAN諸国の中長期的な成長力について」、ADB(2017)「Meeting Asia’s infrastructure needs」を参考にした。
170 経済産業省(2022)「カーボンニュートラル実現に向けた国際戦略」(産業構造審議会産業技術環境分科会グリーントランスフォーメーション推進小委員会/総合資源エネルギー調査会基本政策分科会2050年カーボンニュートラルを見据えた次世代エネルギー需給構造検討小委員会合同会合第4回事務局提出資料)(2022年3月1日)
171 経済産業省(2022)
172 清水(2022)。試算はIRENA( International Renewable Energy Agency)による。