第2節 グローバルで加速するトレンド
2020年初のコロナショックによって大きく落ち込んだ世界経済は、その後の政府の支援を主な要因として、力強く回復した。経済回復過程における需要の増大はインフレ圧力を顕在化させており、米国などにおいて金融緩和からの転換が見られる。このような需要増はいずれ収束すると見られ、先行きは新型コロナウイルス感染症の再拡大やロシアによるウクライナ侵略の影響など不確実性が存在するものの、日本にとって、当面は、世界の経済成長を取り込み、日本経済の成長につなげることが重要である。
外需の拡大には、企業にとって、RCEP、CPTPP、日EU・EPA、日米貿易協定、日英EPAといった経済連携協定を活用しつつ、輸出の促進や対外直接投資、現地生産の拡大に取り組むことなどが求められる。また、輸出や現地生産の拡大という既存のビジネスモデルの延長線上にとどまらず、海外人材の活用、海外企業との連携など、グローバル経営の徹底により組織能力を強化するとともに、海外市場の実情を踏まえた高成長市場開拓戦略、特に、日本のサプライチェーンが張り巡らされ、市場のポテンシャルも有するアジア戦略を策定・展開するという、海外市場獲得に向けた新たなビジネスモデルを構築することも求められる。
企業活動を後押しするため、政府としては、引き続き多角的貿易システムの下でルールベースの秩序を堅持すべく取り組むとともに、米欧市場への関与のレバレッジを確保しつつ、アジア各国と連携を高め、アジアと一体になった成長戦略を描くことが必要となる。
これに加えて、コロナショックを契機に、デジタル変革、地政学リスクの増大、共通価値の重視、政府の産業政策シフトという4つのグローバルなトレンドが加速している。これらは、今後の国際関係や世界経済の動向を左右し、企業経営に大きな不確実性を生み出すとともに、企業の付加価値の源泉に変化をもたらしている。
特に、地政学リスクや共通価値に関しては、各国政府の国際ルール形成や政策ポジションの違いによってルールのブロック化が発生しており、それを受けた市場のブロック化も進行している。さらに、政府の産業政策強化の動きにより、米国、欧州など主要国・地域の特定セクター(航空宇宙、半導体、グリーン関連等)において大規模な市場が形成されており、立地国の政策ポジションによって企業の市場獲得の機会に違いが発生する可能性がある。
このような状況において、企業にとって、従来のコスト削減・低価格製品提供の重視から、差別化・高付加価値化や効率的なオペレーションに取り組むビジネスモデル・産業構造への変革を積極的に促し、企業の稼ぐ力を引き上げることが重要である。その上で、さらに、コロナ禍で加速した4つのトレンドを踏まえて、デジタル化による企業変革、政府が創出する需要の取り込み、経済安全保障・社会的インパクト・共通価値を中核事業における付加価値に転換するビジネスモデルへの変革まで促し、新しい資本主義における付加価値創造型のビジネスモデル・産業構造を実現させていくことが必要であろう。
企業活動を後押しするため、政府としては、G7等における経済秩序構築に関する議論に初期段階から参加し、日本企業が市場支配力や国際ルール形成力に優れる米欧市場において社会実装に取り組むことができる環境を整えることが必要である。また、アジア諸国の現状も踏まえた共通価値の実現を図る、包摂的ルールメイクにつながる橋渡しに努めるとともに、課題先進国としての経験から生まれた共通価値を発信し、課題設定・市場形成を行うことが重要である。
1.デジタル変革
21世紀に入り、デジタル技術とグローバルなデータフローの指数関数的な発展・成長が経済のルールを書き換えつつある。特に2010年代以降、世界規模でデジタル変革が急速に進展し、経済・社会システムの再設計や企業経営のデジタル・トランスフォーメーション(DX)など、モノのインターネット(IoT)やビッグデータ、人工知能(AI)といったコアとなる技術の革新である第四次産業革命が進展している。
第四次産業革命の技術革新により、①大量生産・画一的サービス提供から個々にカスタマイズされた生産・サービスの提供、②既に存在している資源・資産の効率的な活用、③AIやロボットによる、従来人間によって行われていた労働の補助・代替などが可能となる179。
実際、AI、ビッグデータ、IoT、フィンテック、3Dプリンティング、ドローン、ロボット、バイオテクノロジー、量子コンピュータ等の新興技術が飛躍的に進歩し、これらの分野への投資や研究開発が世界的に増加している。今後も、こうした第四次産業革命による更なる技術進歩により、産業構造が大きく変化する可能性がある。
こうした状況の下、我が国においても、経済の優位性の維持と発展のためには、イノベーションが必要不可欠である。我が国の既存企業にとって、DXによる顧客接点の拡大や価値提供のほか、DX投資、R&D投資、人的資本投資、無形資産投資の拡大による企業変革や生産性向上を図るとともに、スタートアップとの連携やDX等を活用した新たな付加価値を生み出す新しいビジネスモデルに転換することの重要性が従来以上に高まっている。
また、イノベーションが技術の開発競争から生まれることに鑑みても、国家間で公平かつ公正な競争環境(レベルプレイングフィールド)の整備のほか、新興技術開発等のイノベーション促進やそれを担うスタートアップ、付加価値源泉としてのデータの自由な越境活動が重要であり、通商協定がそのために果たす役割も大きい。
(1)第四次産業革命による産業構造の変化
第四次産業革命のブレークスルーにより、あらゆる分野で、革新的な製品・サービスが創出され、これまで解決が困難であった社会課題や構造的課題への対応が可能となり、産業構造が大きく変化しつつある(第I-3-2-1図)。
第Ⅰ-3-2-1図 第四次産業革命による革新的な製品・サービスの創出
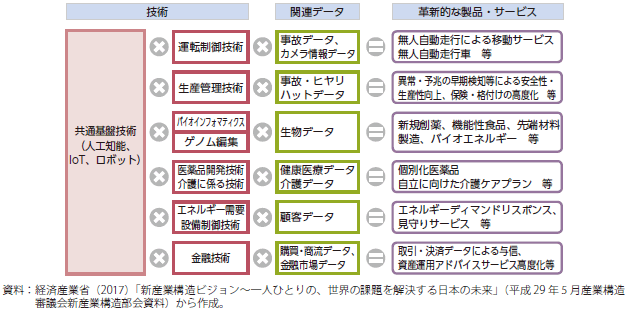
こうした、技術の大きな革新を踏まえ、新たな付加価値を創出する企業が世界的に多く創出されてきている。実際、革新的な技術を活用し、生み出された世界のユニコーン企業(評価額10億ドル以上で、10年以内の非上場ベンチャー企業)は、2022年4月時点で、世界46の国と地域に存在(1,083社、3兆6,294億ドル)している。もっとも、全体の評価額の約70%を米国・中国が占めているほか、上位10の国と地域で評価額・社数のどちらも約90%をカバーしている。なお、技術領域としては、フィンテックが上位を占めている(第I-3-2-2図)。
第Ⅰ-3-2-2図 ユニコーン企業の国別分布(2022年4月)
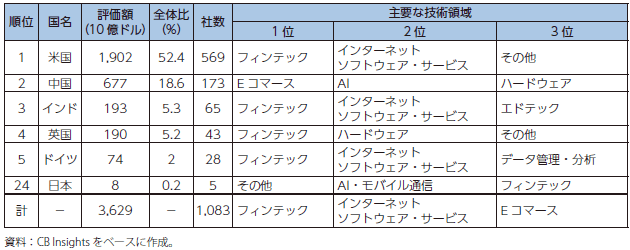
こうした中、我が国のユニコーン企業は、2022年4月時点で、5社にとどまっており、米国の569社から大きく溝を開けられている。評価額ベース(78億ドル)でも世界24位に甘んじており、世界全体の0.2%を占めるにすぎない。もちろん、いわゆる米国のGAFAM(グーグル、アップル、フェイスブック(現メタ・プラットフォームズ)、アマゾン、マイクロソフト)や中国のBAT(バイドゥ、アリババ、テンセント)等といった、技術革新をいち早く捉え、付加価値の創出を行っている主要なデジタル関連企業の時価総額で比較してみても、我が国は、大きく劣位する状況となっている(第I-3-2-3図)。
第Ⅰ-3-2-3図 日米中の主要なデジタル関連企業の時価総額の推移
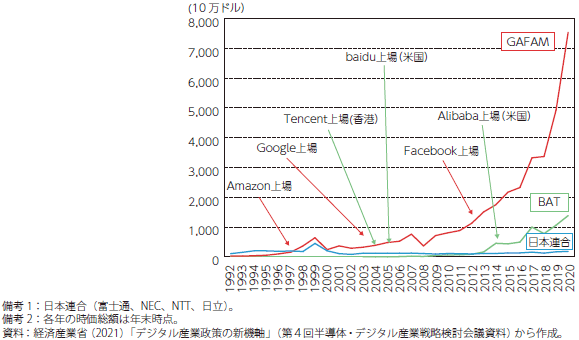
(2)我が国のデジタル投資の状況
世界中でデジタル変革が加速し、産業構造が変わりつつある中、既存企業にとっては、DXによる顧客接点の拡大や価値提供、DX関連投資による企業変革、生産性向上が重要となってくる。こうした中、我が国のDXに目を向けて見ると、投資額等で他国に比べ劣後している側面がある。世界では、新たな技術やビジネスモデルの多くを、デジタル関連企業が創出している中、我が国はデジタル技術のもたらす「重要性」、「変革の大きさ」、「スピード感」について官民双方とも認識が不足し、また、既存の組織・業務・生活様式の継続を前提にした個々のパーツのデジタル化に終始した結果、デジタル大変革への対応が遅れ、産業全体で競争力を喪失した。
第I-3-2-4図を見ると、デジタル投資額と名目GDPが大きく連動しており、国全体におけるデジタル投資の遅れが、経済の低成長の原因の一つとなっている。このため、今後、成長のドライバーとして、産業全体における幅広いデジタル投資の活性化が必要となる。米国は、積極的なデジタル投資に連動する形で、名目GDPが大きく成長している。また、スウェーデンやフランスもデジタル投資は年平均5%台の伸びとなっており、相応に積極的なデジタル投資を行っている一方、我が国では、デジタル投資額が年平均0.8%と低水準で推移しており、名目GDP成長率も0.9%にとどまっている。ドイツも、我が国と同様にデジタル投資額の伸びは1.8%と低水準で低迷しており、名目GDP成長率も1.4%にとどまっている。
第Ⅰ-3-2-4図 我が国と各国のデジタル投資額と名目GDPの水準の推移
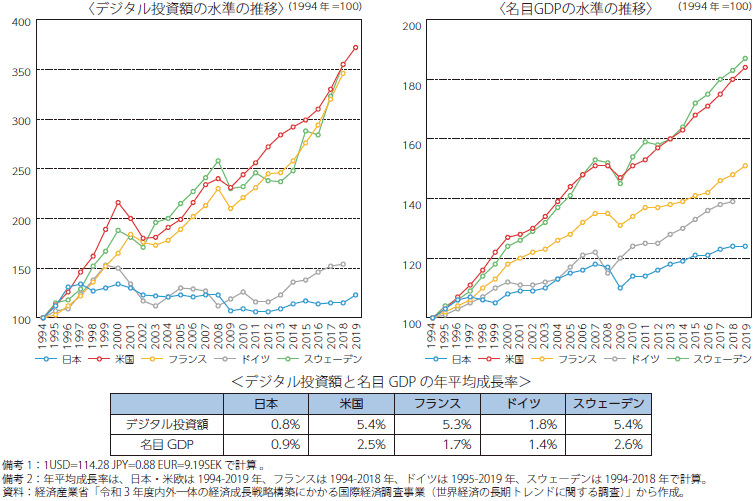
我が国のデジタル投資額が他国と見劣りする背景として、企業において、多様性ある経営体制の確立や事業再編の実行に遅れが見られ、これらが「効率化中心のデジタル投資」の一要因にもなっているものと考えられる。
実際に、IT予算の用途を日米で背景を比較すると、米国企業は、市場・顧客対応やビジネスモデル変革、製品・サービス開発強化を目的にデジタル投資を実施しているのに対し、日本企業はコスト削減や働き方改革に投資が集中(第I-3-2-5図)しており、今後、本物のDXを通じたビジネス変革が必要となってくる。
第Ⅰ-3-2-5図 日米のIT予算の用途
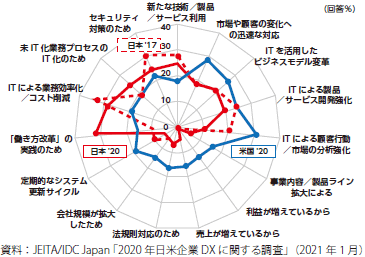
また、IMDのデジタル競争力ランキングを見てみると、我が国は、28位と低迷している。項目別に見ると、「生徒・教師の比率」や「ロボットのグローバルシェア」、「行政への電子参加」、「ソフトウェア著作権侵害対応」などはランキングが高いものの、「国際経験」、「企業の俊敏性」、「ビッグデータの分析と活用」、「デジタル/技術スキル」については、ランキングが相応に低くなっている(第I-3-2-6図、第I-3-2-7図)。
第Ⅰ-3-2-6図 IMDデジタル競争力ランキング
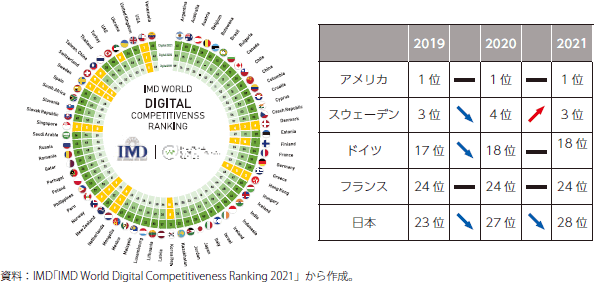
第Ⅰ-3-2-7図 IMD「デジタル競争力ランキング」における日本の評価
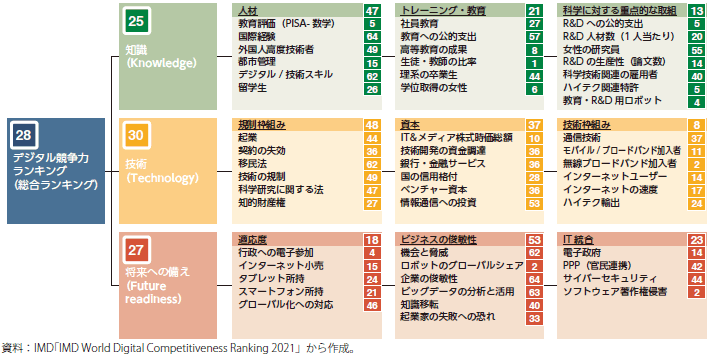
(3)アジアDX180 等を活用した付加価値の創出
こうした状況の下、新興国市場であるASEANに目を転じると、ASEANは、「中所得国の罠」からの脱却や拡大する地域間格差、医療アクセスの充実等、様々な社会課題に直面する中、デジタル技術を活用して課題解決を行うビジネスが勃興している(第I-3-2-8図)。ASEANでは、これまで社会インフラや法整備が不十分だったことで、逆にフィンテックやライドシェアなど先進国の技術を一足飛びで導入する、いわゆる「リープフロッグ」現象が起きている。
第Ⅰ-3-2-8図 東南アジアにおけるデジタル経済の規模の推移
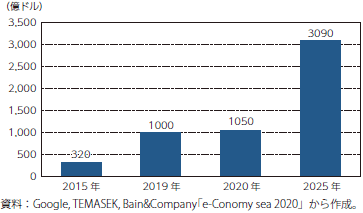
ASEAN各国政府においても、ビジネスを起点としたデジタルイノベーションの社会実装が重要な政策課題となっている中、新型コロナウイルス感染拡大もあって、こうした動きが更に加速している(第I-3-2-9表)。我が国としても、アジア新興国へ資金・人材・技術・ノウハウを戦略的に投入し、現地企業との連携による新規事業の創出を図る「アジアDX」を推進する必要がある。
第Ⅰ-3-2-9表 アジアDX実証事業採択事例

180 日本企業がアジアの新興国企業と連携し、デジタル技術を活用して社会課題を解決するための新事業創出。
(4)デジタルに関するルールの動向
デジタル変革を実現する上では、国家間で公平かつ公正な競争環境が整備されていることが重要となってくる中、各国・各地域の政府は巨大化したプラットフォーマー企業に対して、適正な市場活動を行ってもらうべく、横断的なルール整備を進めている(第I-3-2-10表)。
第Ⅰ-3-2-10表 デジタルプラットフォームを巡る諸外国の動向
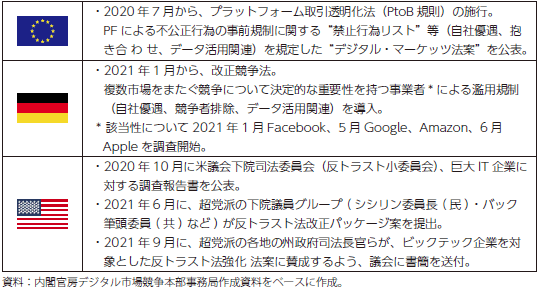
また、データがもたらす新たな経済的価値を活かすためには、データの自由な越境流通が不可欠であるが、一部の国においては、データを囲い込むなどのデジタル保護主義・権威主義といわれる動きの拡大が懸念される。このため、企業のビジネス機会を阻害し得るデジタル保護主義・権威主義の拡大を防ぎ、プライバシー保護やセキュリティなどの信頼を確保することで、自由なデータ流通を促していくこと、すなわち DFFTの実現に向け日本が主導して取り組み、データがもたらす新たな価値の創出と更なる経済発展に貢献していくことが重要となる。
2.地政学リスクの増大
足下、米中対立の激化、英国のEU離脱に加え、新型コロナウイルス感染収束までの長期化や、ロシアによるウクライナへの侵略といった大きな政治的ショックもあって、地政学リスクが非常に高まり、世界全体で不確実性がこれまでにない水準で高まっている。
(1)不確実性の高まり
世界経済フォーラムが公表している『グローバルリスク報告書2022年版』の調査181において、グローバルな潜在リスクが現実的な脅威となるまでの期間を短期(0-2年)、中期(2-5年)及び長期(5-10年)に分けてリスク別に示している(第Ⅰ-3-2-11図)。
第Ⅰ-3-2-11図 グローバルリスク別に見たリスク顕現化までの期間 (回答率)
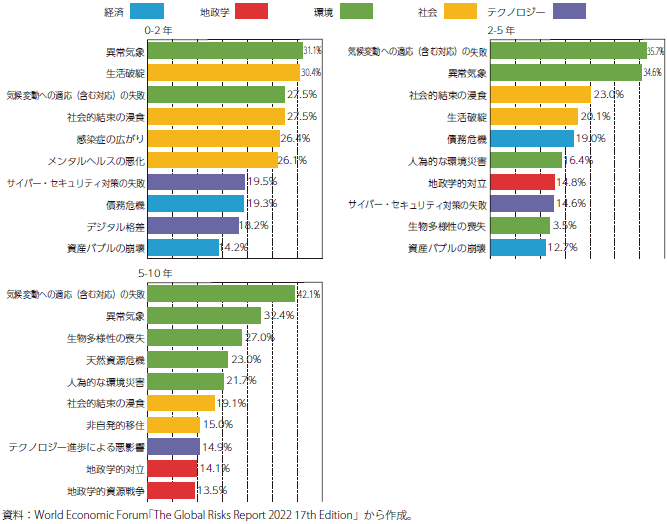
この調査によると、環境、社会、テクノロジー、地政学に関連するリスクが長期的に顕在化するものとして挙げられている。環境リスクのうち、気候変動対応への失敗や異常気象といった気候関連リスクは、全期間においてリスクとして挙げられる割合が高く、長期になるほど、生物多様性の喪失や天然資源危機、人為的な環境災害といった気候関連以外の環境リスクも上位に上がってくる。また、地政学的対立や地政学的資源戦争といった地政学的リスクは、中長期的に顕現化していくと見られている。このほか、デジタル化が進展する中で顕在化するリスクも各期間で挙げられており、サイバー・セキュリティ対策の失敗やデジタル格差は主として短期のリスク、テクノロジー進歩による悪影響は長期のリスクとして見られている。
一方、2022年のリスクについて、政治リスクコンサルティング会社のユーラシアグループが年初に公表している『2022年10大リスク182』を見ると、最も大きなリスクとして、「中国によるゼロコロナ政策の失敗」を挙げ、新型コロナウイルスの変異型を完全に封じ込めず、経済の混乱が世界に広がるリスクを指摘している。
また、次に大きなリスクとして、「テクノポーラーな世界」を挙げており、巨大ハイテク企業による経済・社会の支配が懸念されている。米欧中の各政府は規制強化に動くが、ハイテク企業の投資は止められないほか、AIの倫理的な問題については、政府と企業が合意できていないため、米中、米欧間の緊張を高めるリスクがあると指摘している。
また、5番目のリスクとして「ロシア」を挙げ、2022年初段階でウクライナ情勢を巡るプーチン大統領の次の一手に注目し、米欧の譲歩がなければ、ウクライナにおいて何らかの形態の軍事作戦を行う可能性があるとしていた。2022年2月24日に実際に、ロシアによるウクライナへの侵略が行われ、指摘されていたリスクが顕現化している(第Ⅰ-3-2-12図)。
第Ⅰ-3-2-12図 2022年10大リスク
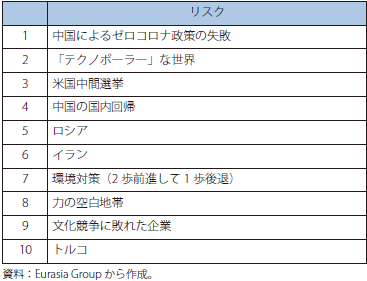
今般のロシアによるウクライナ侵略は、世界が連帯して築き上げてきた国際秩序の根幹を揺るがす行為であり、断じて許容できるものではない。G7諸国を始めとする国際社会は、迅速に資産凍結・金融制裁・貿易制裁などを含む包括的な経済制裁を講じている。こうした状況を受けて、権威主義的国家と自由民主主義的国家との間における世界経済の分断やブロック化、多極化の動きがこれまで以上に加速している。また、欧州や途上国を中心に世界中で、エネルギーや食料を特定国に依存するリスクが顕在化しており、エネルギー・食料の安定供給を含めた経済安全保障の重要性が再認識される事態となっている。今後は、地政学的リスクも踏まえた各国の戦略的な動きがより一層活発化する可能性もある。
我が国としては、こうした不確実性の高まる世界の中でも、G7諸国を始め、法の支配や民主主義といった基本的価値を共有する国々と緊密に連携しながら、これまで世界経済の発展を支えてきた多角的貿易体制を基礎として、新興国や途上国も含めて同じ考えを持つ国々と一層の連帯を深めつつ、経済安全保障という新たな課題にも共同して取り組んでいくことが必要である。
このような地政学的リスクの高まりは、以下の代表的な4つの不確実指数183にも反映されている。
日米の「マクロ経済不確実性指数」を見ると、コロナショックによる不確実性の高まりが、日米ともに、それぞれ東日本大震災や世界金融危機など、相応に不確実性が高まった時期の水準を超えている(第Ⅰ-3-2-13図)。
第Ⅰ-3-2-13図 マクロ経済不確実性指数(日米比較)
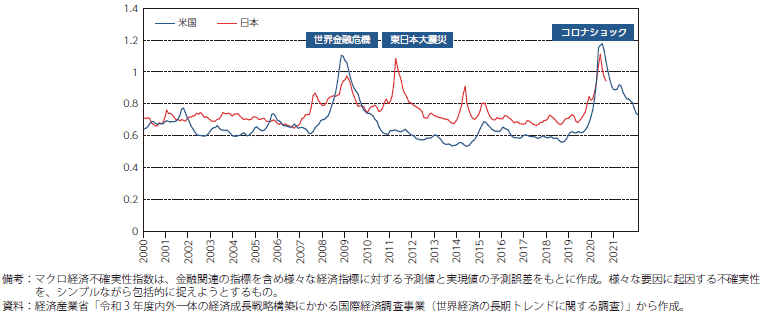
また、「経済政策不確実性指数」や「エコノミック・サプライズ指数」を見ても、新型コロナウイルス感染拡大により、世界全体で顕著に指数が上昇しており、近年で最も不確実性が高まったといえる(第Ⅰ-3-2-14図、第Ⅰ-3-2-15図)。なお、我が国における「経済対策不確実性指数」の新型コロナウイルス感染拡大の反応を見ると、世界や米国より低い水準となっている。これは、我が国において死亡率や失業率が抑えられたため、政府による介入が比較的少なかったことが背景の一つと考えられる。
第Ⅰ-3-2-14図 経済政策不確実性指数(世界・日本・米国比較)
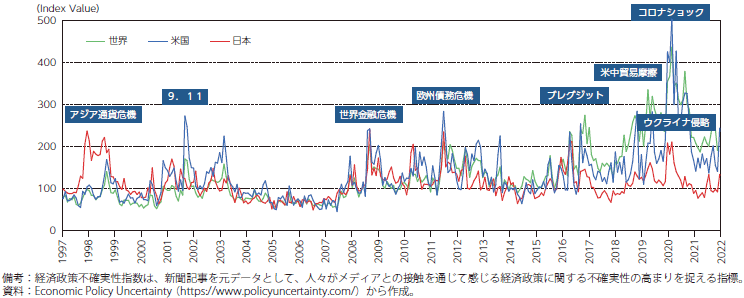
第Ⅰ-3-2-15図 エコノミック・サプライズ指数(世界・日本・米国・EU比較)
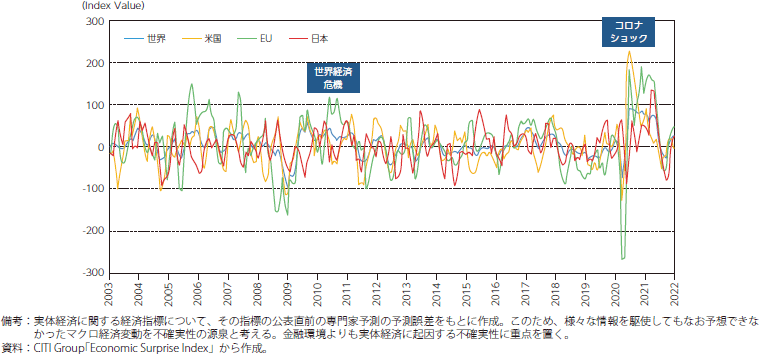
このほか、「株式ボラティリティ指数(VIX指数)」においても、世界金融危機以来の指数の上昇を示すなど、我が国も含め、金融環境においても不確実性が高まっていることを反映している(第Ⅰ-3-2-16図)。
第Ⅰ-3-2-16図 株式ボラティリティ指数(VIX指数)
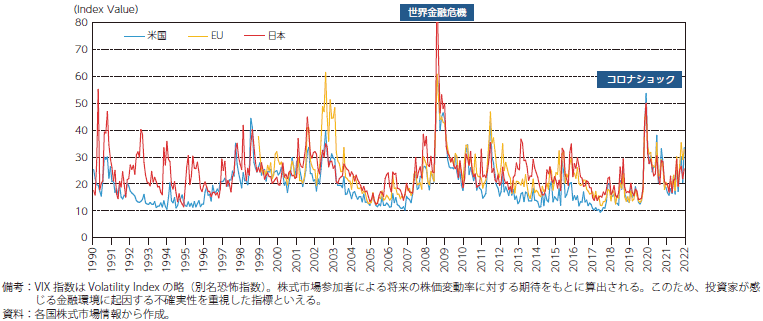
さらに、地政学リスク指数(geopolitical risk index184)を見ると、ウクライナ侵略によって、指数が、米国同時多発テロやイラク戦争以来の高い数値を示しており、地政学リスクが高まっていることが分かる(第Ⅰ-3-2-17図)。
第Ⅰ-3-2-17図 地政学リスク指数(geopolitical risk index)
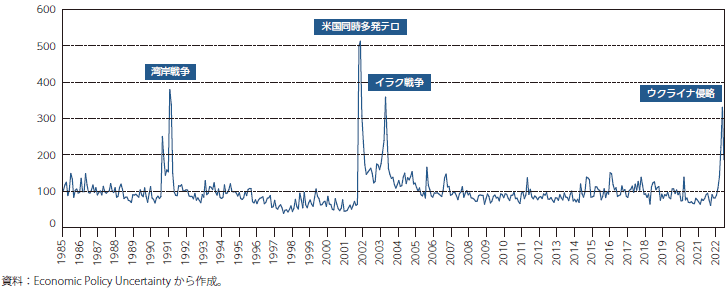
181 WORLD ECNOMIC FORUM “The Global Risks Report 2022 17th Edition”
WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf
182 Eurasia group TOP RISKS 2022 https://www.eurasiagroup.net/siteFiles/Media/files/EurasiaGroup_TopRisks2022_Japanese.pdf![]()
183 日本銀行「マクロ経済に関する不確実性指標の特性について」
https://www.boj.or.jp/research/wps_rev/wps_2020/wp20j07.htm/![]()
(2)経済安全保障の要請の高まり
このように、不確実性が高まっている中、新型コロナウイルス感染拡大に伴うサプライチェーン途絶リスクの顕現化への対応など、経済安全保障の要請が強まっている。米中間では、AI・量子等の新興技術や、それを支える基盤技術での技術覇権争いが行われているほか、先端半導体製造などの重要技術の輸出管理強化や、各国が自国に技術を囲い込もうとする動きが活発化しており、米中対立の影響がグローバルに広がっているといえる(第Ⅰ-3-2-18図)。こうした動きを背景に、戦略産業の育成やグローバルサプライチェーンの見直しなど、各国で経済安全保障に関する取組が強化されている。米国では、競争力のある新産業育成と技術イノベーション政策(経済安全保障の「攻め」の側面)のほか、輸出管理強化や新興技術の輸出管理など(経済安全保障の「守り」の側面)を重視した政策に取り組んでいる(第Ⅰ-3-2-19表)。我が国においても、経済安全保障担当大臣の新設や経済安全保障推進法(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律)が制定されるなど、経済安全保障への取組が強化されている。
第Ⅰ-3-2-18図 半導体産業における米中対立の影響
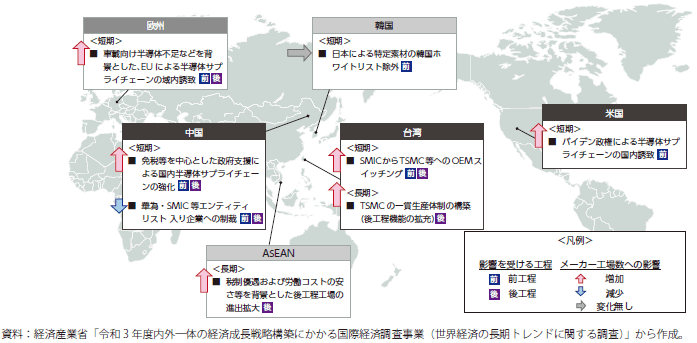
第Ⅰ-3-2-19表 米中技術覇権争いにおける米国による主な規制等
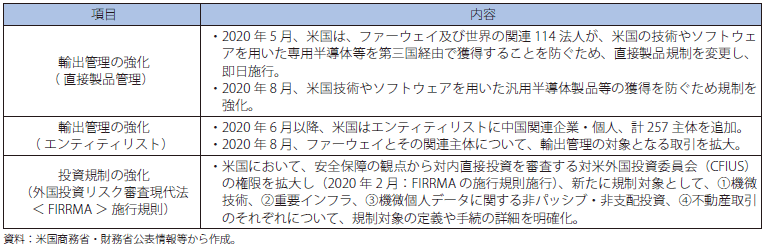
企業行動としては、新型コロナウイルス感染拡大によるグローバル経済の減速、生産拠点の多元化の要請もあり、グローバルサプライチェーンの一部に国内回帰の動きも見られる。今後も、企業にとって、地政学リスクや経済安全保障戦略の動向を注視するとともに、突然の状況変化やルール変更に迅速かつ柔軟に対応できるレジリンスを高めるためのサプライチェーン戦略を策定することの重要性が高まっており、リスクの大きさや持続する期間等を勘案しつつ、生産拠点や調達先の変更及び多様化、在庫の積み増し、リサイクル、備蓄等を柔軟に実施していくことが求められる。
各国政府は、国内産業政策とあわせ、強靱・多様・安全なサプライチェーン構築を支援する動きを強めており、特に半導体については、国内生産能力強化・研究開発への投資等を進めるとともに、信頼できるパートナーと協力する動きが顕著となっている(第I-3-2-20表、第I-3-2-21表)。また、有志国連携の一つである日米豪印(通称クアッド)においても、重要技術を巡る連携について議題に上がっている。第1回日米豪印首脳会議において設立された、重要・新興技術作業部会では、重要・新興技術が共通の利益と価値観に従って管理・運用されることを目指し、「技術の設計・開発・ガバナンス及び利用に関する日米豪印原則」を策定したり、重要技術のサプライチェーン強靱化に向け、4か国の半導体及びその重要部品について議論を深めたりしている。また、日米首脳会談(2021年4月)においては、デジタル経済・新興技術に関して、①生命科学及びバイオテクノロジー、AI、量子科学、民生宇宙分野の研究及び技術開発における協力の深化、②5Gの安全性・開放性へのコミットメント、信頼に足る事業者の重要性、③重要技術を育成・保護しつつ、半導体を含む機微なサプライチェーンに関する連携を確認している。こうした中、中国においては、「科学技術の自立自強」を掲げ、「自主的・コントロール可能なサプライチェーンの能力強化」として、サプライチェーンの主要部分は国内にとどめておくなど、コア技術の国産化を推進している。
第Ⅰ-3-2-20表 デジタル基盤技術への各国の取組
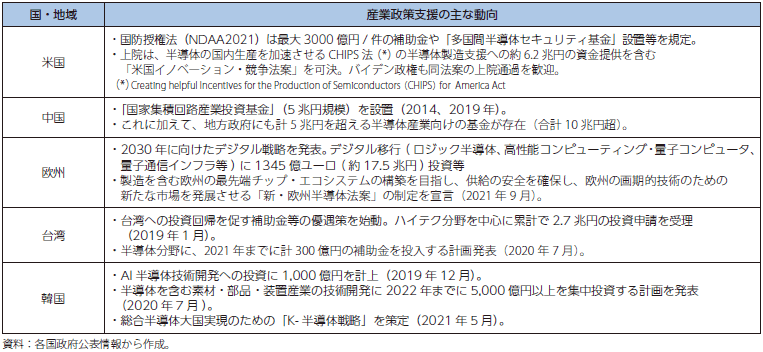
第Ⅰ-3-2-21表 米国イノベーション・競争法案
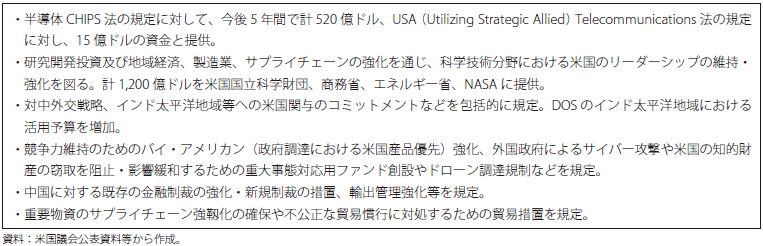
3.共通価値の重視
気候変動に対する脱炭素化や資源制約に対する循環経済、生物多様性、環境保全といった環境価値、労働や人権の尊重といった社会的価値を始めとする共通価値は、政府の政策面のみならず、持続可能性・社会課題解決・社会価値創造(CSV)の観点から消費者市場や金融市場においても重視されるようになっている。
企業は、自社の存在意義(パーパス)を意識し、株主にとっての付加価値のみならず、顧客、従業員、地域社会、政府、自然環境などあらゆるステークホルダーにとっての付加価値を追求することが求められている。若い世代を中心に消費者の多くが社会や環境等への配慮に基づいて商品・サービスの購入を決定するようになっている中で、企業にとって、従来型の企業の社会的責任(CSR)活動という付随的側面にとどまらず、共通価値への配慮を中核事業の付加価値に転換し、新たな優位性構築の手段とすることの重要性が高まっている。共通価値に関連するルール形成に主体的に関与することによって自社に有利な競争環境を構築することも重要であろう。
また、投資家によるESG投資の機運が上昇していることから、金融市場における資金調達確保の観点からも、企業にとって共通価値への取組が重要となっている。
(1)気候変動・環境
① カーボンニュートラルに向けた取組
近年、気候変動・環境問題への関心は、グローバルで、従来より一層加速する形で高まっており、気候変動への対応自体を企業の中核事業の付加価値に転換する変革の重要性が高まっている。
2015年のCOP21でパリ協定が採択され、全てのパリ協定締約国が、温室効果ガスの削減目標を策定することとなった。パリ協定では、世界の平均気温の上昇を、産業革命以前に比べ、2℃より十分低く保ちつつ、1.5℃に抑える努力を追求しており、今世紀後半に世界のカーボンニュートラルを実現することを目標としている。
2050年までのカーボンニュートラルを表明している国は140か国以上となっており、これらの国における世界全体のCO2排出量に占める割合は42%となっている185 186。中国は、2060年カーボンニュートラルを表明しているほか、インドも、COP26において2070年カーボンニュートラルを表明している。また、欧州、中国、インドなどの主要国はガソリン車の販売を禁止し、日本においても、2035年までに乗用車新車販売で電動車100%とするなど、カーボンニュートラル実現に向けた様々な施策を展開している(第I-3-2-22図)。
第Ⅰ-3-2-22図 主要国におけるカーボンニュートラル宣言の状況
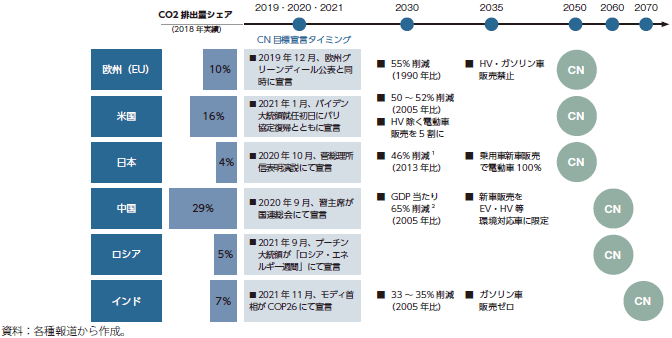
こうした中、カーボンニュートラルの実行手段に目を向けると、2015年のパリ協定採択以降、EUを中心としてサステナブルファイナンスが世界的に浸透してきている。2020年には、投資総額が35.3兆ドルまで拡大するなど(第I-3-2-23図)、その関心は非常に高い。2021年には、再生可能エネルギーといった、既に脱炭素の水準にある事業を対象としたグリーンボンドの発行額も4,992億ドルまで拡大している(第I-3-2-24図)。他方、債券全体の発行額に占める割合は5%程度にとどまっており(第I-3-2-25図)、気候変動対策の観点から、「グリーン」のみならず、着実な低炭素化を実現する「移行(トランジション)」へのファイナンスも、サステナブルファイナンスの一環として目を向ける必要がある。
第Ⅰ-3-2-23図 サステナブル投資額の推移
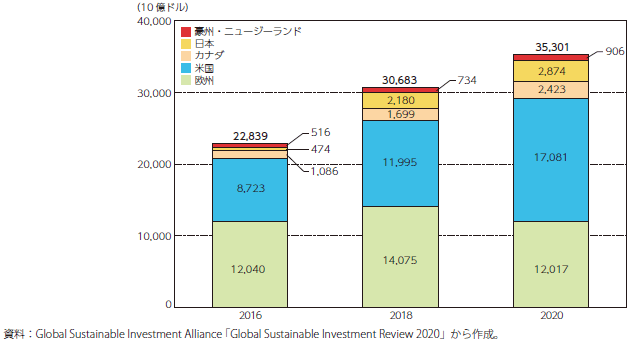
第Ⅰ-3-2-24図 世界のグリーンボンド発行額の推移
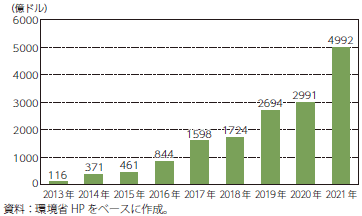
第Ⅰ-3-2-25図 債券発行額に占るグリーンボンドの割合
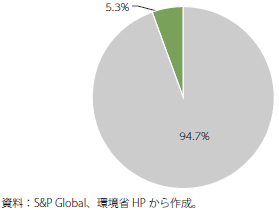
脱炭素社会に向けた「移行」(トランジション)については多額の資金が必要となる。EUでは、ファイナンスに係る「タクソノミ-」(分類体系)を策定し、環境的に持続可能な経済活動(いわゆるグリーン)を定義しており、事業会社に対して、売上におけるグリーン比率の開示を義務付けているほか、金融機関に対しても、自らの貸出債権等の金融資産のグリーン比率の開示等を義務付けるなどの取組を行っている。もっとも、全ての産業が一足飛びに脱炭素化できないのも事実であり、グリーンだけでなく、いかに、脱炭素化に向けた移行(トランジション)を進めるかが、今後、重要となってくる(第Ⅰ-3-2-26図)。
第Ⅰ-3-2-26図 脱炭素への移行(トランジション)
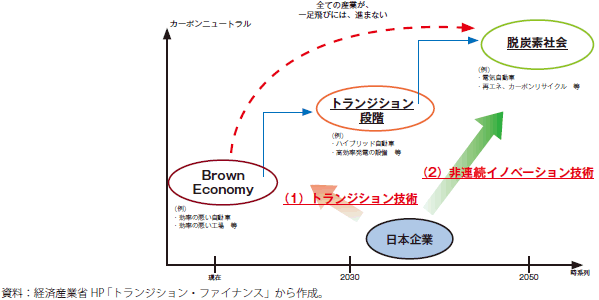
このほか、気候変動がトリガーとなって新たなグローバル金融危機を引き起こすリスクとして、いわゆる「グリーン・スワン」が注目されており、中央銀行、規制当局、監督当局の新たな金融システム上の課題とされている。「グリーン・スワン」という言葉は、国際決済銀行(BIS)とフランス中央銀行がまとめた論文187の中で初めて使用され、「ブラック・スワン」という、従来の知識や経験から予想しがたいが、リスクが仮に顕現化したときの影響が大きい事象を意味する言葉から派生したものである。
当論文の中では、①気候変動対策に伴う市場や社会環境の急激な変化により座礁資産が増加し、投資家に投売りが発生し、金融危機を引き起こすリスク、②気候変動に伴い、金融機関の信用リスク・市場リスクが高まり、短期での資金調達が困難となり、金融市場で緊張が高まるリスク、③気候変動による災害の影響で、金融機関のシステム運用等に悪影響が生じて、オペレーショナルリスクが顕現化する可能性などが挙げられている。
また、「ブラック・スワン」と異なる点として、①気候変動リスクが将来顕現化することに一定の確実性がある点、②気候変動による災害はこれまでのシステミックな金融危機より深刻なものとなる点、③気候変動に関する複雑さはより高次にあり、環境、社会、経済へ大きく、かつ複雑に連鎖反応を起こしかねない点が挙げられている。
こうした気候変動リスクの下で、長期的に金融安定を保つべく、中央銀行と政策当局に対して、①不可欠な新しいポリシーミックスの探求と社会的な議論、②気候変動を公共財と捉え、金融システムの手段と改革に取り組むことなどが必要であると指摘されている。
② 「循環経済」への転換
また、「循環経済」への転換の必要性が高まっている。世界的な人口増加・経済成長に伴う資源・エネルギー・食糧需要の増加のほか、廃棄物量の増加、海洋プラスチックを始めとする環境問題の深刻化が進んでいる。こうした中、従来の「線形経済」(大量生産・大量消費・大量廃棄の一方通行の経済)に対して、近年では「循環経済」への関心が高まり、あらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、付加価値の最大化を図る経済へシフトすべきだという考えが強まっている(第Ⅰ-3-2-27図、第Ⅰ-3-2-28図)。
第Ⅰ-3-2-27図 循環経済の概要
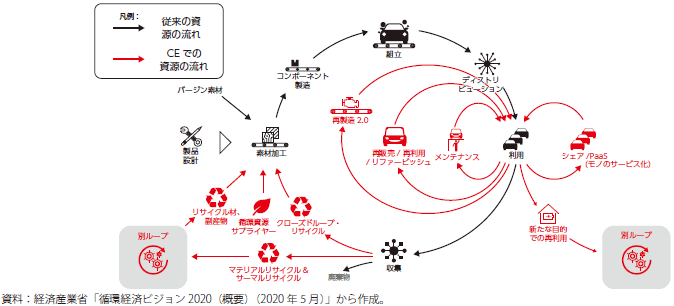
第Ⅰ-3-2-28図 EUと日本における循環経済の政策動向
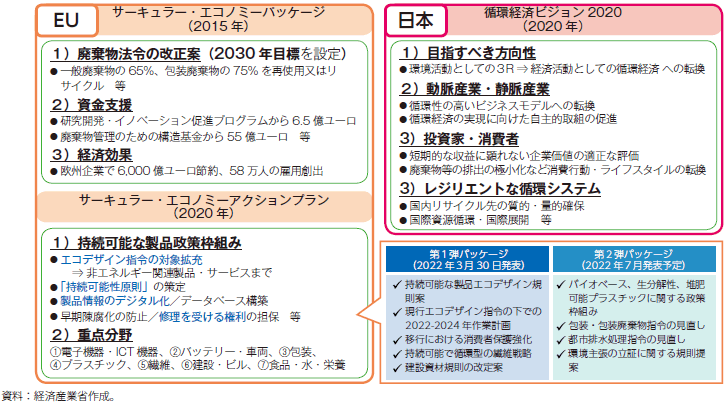
世界的な人口増加・新興国の経済成長に伴う消費拡大と将来的な資源制約のリスクが高まっており、世界の資源採掘量は約40年で2倍以上に増加(2015年:880億トン→2060年:1,900億トン)し、資源価格の高騰や希少鉱物の安定確保が困難となることが懸念される。また、国内外の廃棄物問題が顕在化しており、新興国での廃棄物量の増加や不適切な処理が見られる。世界の一般廃棄物量は、30年余りで2倍弱(2016年:20億トン→2050年:34億トン)となることが予測されているほか、ASEAN6か国の家電廃棄量は15年で3.5倍(2014年:1,000万台→2030年:3,500万台)となることが予想されており、アジア諸国の廃棄物輸入規制とグローバルでの廃棄物処理システムの機能不全、国内処理システムへの影響が懸念されている。
さらには、地球温暖化や海洋プラスチックごみ等の環境問題の深刻化と環境配慮要請の高まりにより、2050年には海洋中のプラスチック量が魚の量を上回るとの推計も2016年の World Economic Forumにて示されており、民間主導でグローバル企業を中心とした自主的な取組の加速が見られる。国際的にも、2022年2月28日から3月2日にかけて開催された国連環境計画(UNEP)第5回国連環境総会再開セッション(UNEA5.2)において、海洋プラスチック汚染を始めとするプラスチック汚染対策に関する法的拘束力のある国際文書(条約)について議論するための政府間交渉委員会(INC)を立ち上げる決議が採択された。日本は、2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の提唱国として、今後のINCにおける国際交渉にも積極的な役割を果たしていく。また、国連は、持続可能な発展に向け、資源効率性向上、経済活動と資源消費・環境影響の切り離しの実現を提唱している188。
③脱炭素化に向けた希少鉱物の確保の重要性
近年のデジタル化の進展やカーボンニュートラルの世界的な潮流から、先端産業において、必要不可欠なレアメタル等の希少鉱物の安定供給が、より一層重要となっている。カーボンニュートラルに向けて、省エネを始め大規模なエネルギー転換が必要となることから、そのために必要となる希少鉱物資源の安定的な確保が課題となる。電気自動車(EV)を始めとする電動車の製造に必要不可欠なレアメタル等の一部は、特定国での埋蔵・生産の偏りが見られ、カントリーリスクなどに起因する供給リスクが存在する。
世界銀行が公表した『Minerals for Climate Action』等によると、2050年にはアルミニウム、グラファイト、ニッケルの需要が大きくなり、2020年の生産量に対する需要率で見ると、リチウム、コバルト、グラファイトが大きく、2020年生産量の4~5倍の需要がある(第Ⅰ-3-2-29図、第Ⅰ-3-2-30図、 第Ⅰ-3-2-31図)。
第Ⅰ-3-2-29図 重要鉱物の2050年年間需要
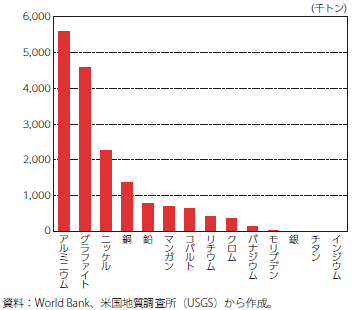
第Ⅰ-3-2-30図 2020年生産量に対する需要率
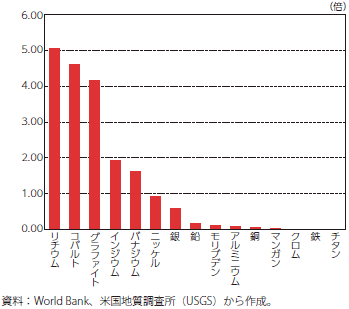
第Ⅰ-3-2-31図 安定調達が重要となる鉱物資源(元素記号表)
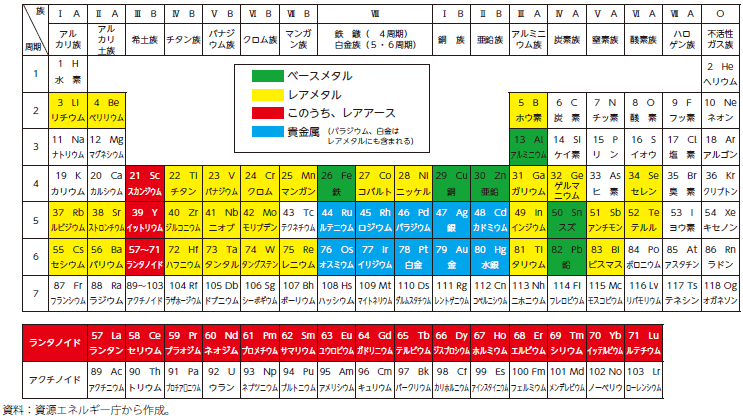
代表的な希少鉱物である「レアアース」は、我が国における、自動車、電気電子機器を構成する重要な部品類製造等に使用されている消費量は年間数万トンに過ぎないが、そこから得られる機能は産業上必要不可欠なものが多い(第Ⅰ-3-2-32図)。
第Ⅰ-3-2-32図 産業におけるレアアースの用途
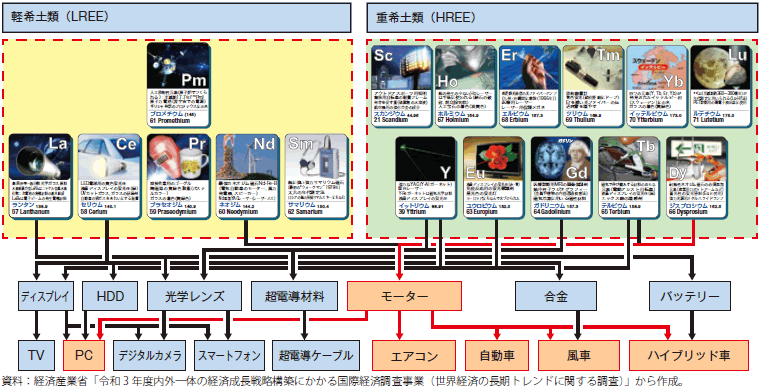
こうした中、世界におけるレアアースの生産高の推移を見ると、1995年以降、中国産鉱石の世界シェアが50%を超え、中国に大きく依存する形となっており、各国は重要鉱物確保のための政策を強化している(第Ⅰ-3-2-33図)。
第Ⅰ-3-2-33図 世界におけるレアアース生産の推移
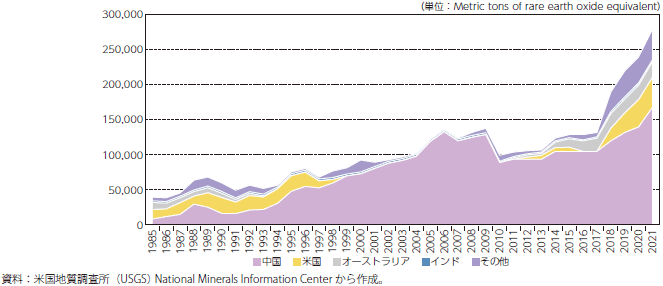
このような状況を踏まえた各国の動きを見ると、中国では、サプライチェーン全体でレアアース産業への統制を強めつつあるほか、米国でも、トランプ政権時に、敵対外国への重要鉱物依存による国内サプライチェーンへの脅威に対する大統領令が発令されたほか、バイデン政権でも、2022年3月に、1950年国防生産法に基づいて、国防長官に、大容量蓄電池などに使用するリチウムなど重要鉱物の国内生産増に向けた取組を指示する覚書に大統領が署名した。覚書では、大容量電池用の重要鉱物が国防に不可欠と指定した上で、国防長官に対して、重要鉱物の国内生産能力を高めるためのフィージビリティースタディなどの支援や、重要鉱物の国内生産基盤に関する調査内容をまとめた年次報告書の作成などが指示されている。バイデン政権は、国防生産法の活用により、重要鉱物セキュリティの取組を加速させている。また、EUは、域内に加えて、カナダやアフリカ等の第三国との重要鉱物の循環型サプライチェーン構築を企図している。EUは、脱炭素化を推進する中で、EU域内でのサプライチェーン構築を推進し、域内に関連企業を誘致することを計画している(第Ⅰ-3-2-34表)。
第Ⅰ-3-2-34表 重要鉱物を巡る各国政策の動向
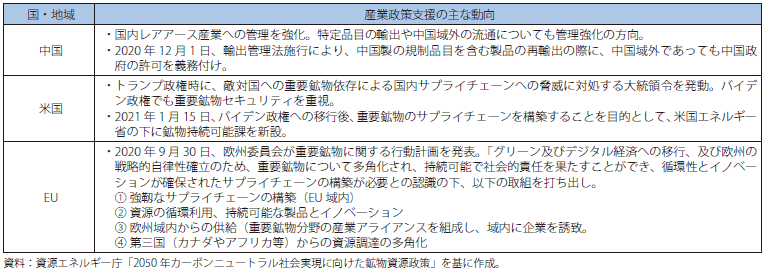
一方、重要鉱物保有国においても、資源ナショナリズムが高揚しており、インドネシアの鉱業法改正による事実上の鉱石輸出禁止措置や、メキシコのリチウム開発における外国企業排除といった動きは、他の資源国にも広がりつつある(第Ⅰ-3-2-35表)。
第Ⅰ-3-2-35表 重要鉱物保有国における資源ナショナリズムの高揚
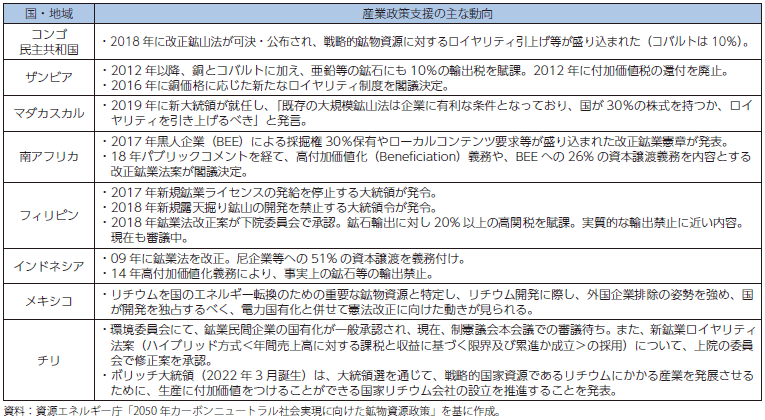
185 ①Climate Ambition Allianceへの参加国、②国連への長期戦略の提出による2050年カーボンニュートラル表明国、2021年4月の気候サミット・COP26等における2050年カーボンニュートラル表明国等をカウントし、経済産業省作成(2021年末時点)
186 CO2排出量は、IEA (2020), CO2 Emissions from Fuel Combustionを基にカウントし、エネルギー起源CO2(2018年)のみ対象。
187 BIS and Bank of France (2020), “The green swan: Central banking and financial stability in the age of climate change” (Jan, 2020).
188 経済産業省「循環経済ビジョン2020」 https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522004/20200522004.html![]()
(2)企業経営における人権への取組
企業経営における共通価値たる人権への取組について、グローバルで関心がより一層高まっている。人権に対する意識の高まりが国際的に加速する中、サプライチェーン上の人権配慮のコミットメントや取組が不十分とみなされた場合には、不買運動、投資の引揚げ、既存顧客との取引停止など多くのリスクに直面する可能性が存在している。企業にとって、このような潜在的経営リスクを排除し、企業の付加価値を向上する観点からも、サプライチェーン上の第三者によるものも含めて人権問題について適切な対応が必要である。
元々、ビジネスと人権の関係については、2011年の国連人権理事会において、「ビジネスと人権に関する指導原則」が全会一致で支持(endorse)された。この指導原則は、ビジネスと人権の関係を、①人権を保護する国家の義務、②人権を尊重する企業の責任、③救済へのアクセスの3つの柱に分類した上で、被害者が効果的な救済にアクセスするメカニズムの重要性を強調している。本原則は、企業活動における人権尊重の在り方に関する基礎的な国際文書となっている。
欧米各国では、「人権保護」と「対外経済政策」を連動させる動きが加速している。
米国のバイデン政権は、外交政策における人権重視を掲げ、欧州とも連携して、新疆ウイグル自治区における人権侵害への関与を理由とした制裁を含む措置を実施しており、2021年7月には、新疆ウイグル自治区での強制労働のほか、人権侵害に関与する事業体が、サプライチェーンに含まれていないか産業界に注意を促す「新疆サプライチェーンビジネス勧告書」を公表した。また、同年12月、中国の新疆ウイグル自治区で一部なりとも生産等された製品や、米国政府がリストで示す事業者により生産された製品は、全て強制労働によるものと推定し米国への輸入を禁止する「ウイグル強制労働防止法」が成立した。同法では、輸入禁止を避けるには、輸入する製品が一部なりとも強制労働に依拠していないこと等を輸入者が証明する必要がある。法律を執行する上での細則やガイドライン(「執行戦略」)を定め、2022年6月に施行される予定である。
欧州では、EUが2021年7月に、「EU企業による活動・サプライチェーンにおける強制労働のリスク対処に関するデュー・ディリジェンス・ガイダンス」を発表した。また、2022年2月には、欧州委員会が一定規模の企業に対して人権及び環境に関するデュー・ディリジェンス(DD)を義務化する「企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令案」を公表した。このほか、デュー・ディリジェンス指令案に併せて公表された文書において、強制労働関連産品の上市禁止に関する立法手続の準備を進めることを表明している(第I-3-2-36図)。
第Ⅰ-3-2-36図 EU企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令案の概要
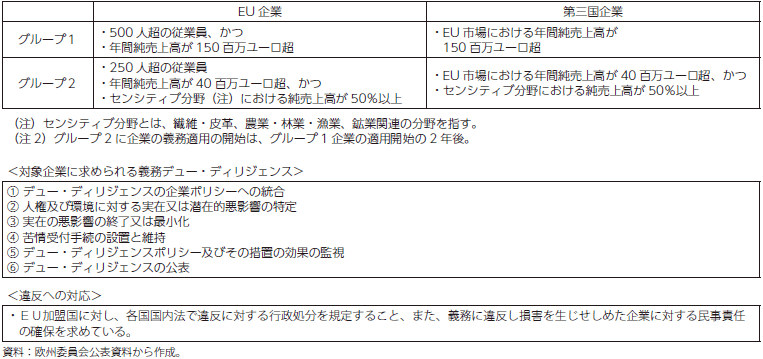
こうした状況の下、我が国企業も企業経営やサプライチェーンにおいて人権尊重の取組がより一層求められている。実際に、グローバル企業がNGO等から名指しで批判されるケースも生じており、我が国産業界においても、足下の各国の動向等も受けて、大企業を中心に取組を加速する動きが見られる。
このような国際的な潮流の中で、日本政府は、2020年10月、「ビジネスと人権」に関する行動計画を策定した。本行動計画では、日本企業に対して、人権デュー・ディリジェンスのプロセスの導入を期待する旨を表明している。
また、経済産業省は外務省と連名で、2021年9月~10月にかけて、政府として初めて、行動計画のフォローアップの一環として、日本企業のビジネスと人権への取組状況に関する調査を実施(「日本企業のサプライチェーンにおける人権に関する取組状況のアンケート調査」189)した。
調査結果を見ると、回答企業のうち、人権方針を策定している企業は約7割となっているほか、人権デュー・ディリジェンスを実施している企業は、約5割程度にとどまっている。また、人権を尊重する経営を実践する上での課題としては、「サプライチェーン上における人権尊重の対応状況を評価する手法が確立されていない」、「サプライチェーン構造が複雑で、対象範囲の特定が難しい」、「十分な人員・予算を確保できない」との回答が多く見られた。
一方で、人権を尊重する経営を実践した結果、得られた成果・効果としては、「自社内の人権リスクの低減」、「SDGsへの貢献」、「サプライチェーンにおける人権リスクの低減」、「ESG評価機関からの評価向上」との回答が多く見られた。
サプライチェーンの範囲が拡大かつ深化している中で、我が国企業においても、人権問題について十分に配慮した上での企業経営が求められる。
このような調査結果等も踏まえ、2022年3月、経済産業省は、サプライチェーンにおける人権尊重のための業種横断的なガイドライン策定に向けて検討会を立ち上げた。2022年夏までに策定する国内のガイドラインの整備と併せて、国際協調により、企業が公平な競争条件の下で積極的に人権尊重に取り組める環境、各国の措置の予見可能性が高まる環境の実現に向け取り組んでいくこととしている。
4.政府の役割強化・産業政策シフト
地政学リスクや不確実性の高まりや、グリーン技術を始めとする先端技術分野の革新もあって、米欧中を中心に国内産業競争力強化のための積極的な産業政策の役割が見直されている。我が国においても、グリーン関連産業や防衛宇宙産業、半導体産業を中心に政府における需要創出が進む中、政府の経済動向や関与方針を踏まえ、政府調達や投資によって創出される市場を上手く取り込むことを念頭に置き、企業戦略を形成することの重要性が高まっている。
(1)産業政策の重要性の高まり
産業政策については、我が国では、戦後復興期、高度経済成長期、バブル後の調整期、安定成長期等の過程で様々な産業政策が行われてきた。他の国についても、例えば、新興国では、1960年代以降、韓国、シンガポール、台湾などの新興工業経済地域(NIEs)や中国、ASEAN主要国は輸出志向型工業化の産業政策を実施し、その後の成長段階に応じて産業政策を変化させてきている。中国では、改革期を通して、国家が経済発展に大きな役割を果たしてきた。労働集約的工業化から資本深化的工業化への移行により、生産性向上が加速し、政策目標を達成するための強固な下地が形成された190。アジア四小龍と呼ばれる韓国、シンガポール、香港、台湾は、中所得の罠から抜け出せなかった各国と対照的に、技術・イノベーション政策を数十年にわたって遂行し、高成長を達成した。また、これらの国は、自動車やエレクトロニクスといった産業の開発という長期的でリスクの高い計画に挑み、こうした分野で独自の技術を構築してきた。先進国でも、米国は、1980年代に市場主義への傾斜が強まるまでは、防衛宇宙産業を中心に産業政策を実施してきた。特定の技術のブレークスルーは、シリコンバレーのような民間の技術普及によるところがあるものの、資金調達等の政府の積極的な政策的支援が果たした役割も大きい。欧州においても、1980年代前に政府間で連携して、産業政策を展開する動きが見られた。産業政策イニシアティブを立ち上げ、フランスとドイツの企業連合としてエアバス社を設立し、その後スペインや英国が参加するなど、共同で産業政策を進め、域内の産業競争力を強化してきた。他方、1980年代以降は、米国、欧州など先進国を中心に、政府の役割を最小限に抑え、産業政策を前面に出す動きを控える潮流が続いていた。
もっとも、足下では、米中対立等による地政学リスクの高まり、半導体やレアメタルといった重要物資のサプライチェーンぜい弱性、カーボンニュートラルを目指す各国の取組の進展などから、再度、産業政策を積極的に打ち出す動きが進んでいる。
企業にとっては、米欧中を中心とする積極的な産業政策の動きが強まり、グリーン関連産業や防衛宇宙産業、半導体産業を中心に政府による需要創出が進む中、政府の政策動向や関与方針を踏まえ、政府調達や投資によって創出される市場をうまく取り込むことを念頭に置いて企業戦略を形成することの重要性が高まっている。
産業政策の有効性については、経済学者や政策担当者の間でこれまでも議論されてきたものの、2010年代後半以降、新産業政策や21世紀の産業政策の在り方に関する学術的な議論が活発になっている。例えば、グリーン技術に対する積極的な産業政策は、①脱炭素は世界的な公共財であり、新しいグリーン技術の開発は、投資家の私的リターンより大きな社会的リターンを生み出すにも関わらず、過小投資につながること、②技術の発展は経路依存的であり、産業政策の後押しによってグリーン分野の技術革新にインパクトを与え、汚染を引き起こす旧来の生産技術の終焉を促すことが可能であることなどから、経済学的観点からも正当化され得ると説明できる191。産業政策に関する議論の高まりは、経済学の英文書籍・学術論文で、「Industrial Policy」をタイトルと要約に含むものが、48本(2000年)から287本(2020年)と大幅に増加している192 ことからも見てとれる。その中でも、例えば、ハーバード大学のダニ・ロドリック教授は、「21世紀のためのアジェンダとして、産業政策を復興・再生する必要がある。産業政策にとって、市場形成、持続可能性、責任あるグローバリゼーションなど社会的目標が最重要であり、市場の失敗の是正を乗り越えるべきである。産業政策は未知の領域での探求プロセスである」という趣旨の主張をしている。また、MITのダロン・アセモグル教授は、「政府が産業政策で教育や研究に資金提供し、ハイテク設備の主要な購買者になることで、決定的な支援を提供できる」旨を主張している。このほか、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのマリアナ・マッツカート教授は、『企業家としての国家』(2014)や『ミッション・エコノミー』(2021)の中で、「国家は、民間主体が負えないリスクを負って、画期的イノベーションを実施すべき。イノベーション・システムの形成において、国家の役割は根本的に重要である。国家が壮大なミッションを設定して、様々なリソースを広範に動員することで、単なる『市場の失敗の是正』ではなく、『市場の創出』を行うべき」という趣旨の主張をしている。さらに、IMF、国連貿易開発会議(UNCTAD)や国際労働機関(ILO)といった国際機関も、いわゆる「ワシントン・コンセンサス193」から脱却し、最近では、経済発展戦略としての産業政策を提言している(第Ⅰ-3-2-37表)。
第Ⅰ-3-2-37表 国際機関による産業政策推進の提言194 195 196
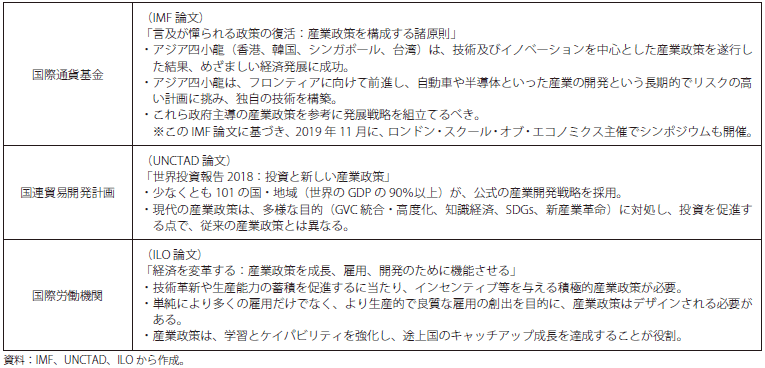
また、ウクライナ危機前後においては、世界情勢の変化を踏まえて、有識者から、今後の産業政策の在り方について、「世界市場の安定に向けた大胆かつ協調的な行動を開始することが不可欠で、供給のボトルネック解消や再生可能エネルギーに関する政府の大規模な資金投入などが必要」といった見解や「長期的な安全保障を強化するためには、対外戦略に経済的レジリエンスも必要」といった見解が表明されている(第Ⅰ-3-2-38表)。
第Ⅰ-3-2-38表 ウクライナ危機前後に出された今後の産業政策に関する有識者見解
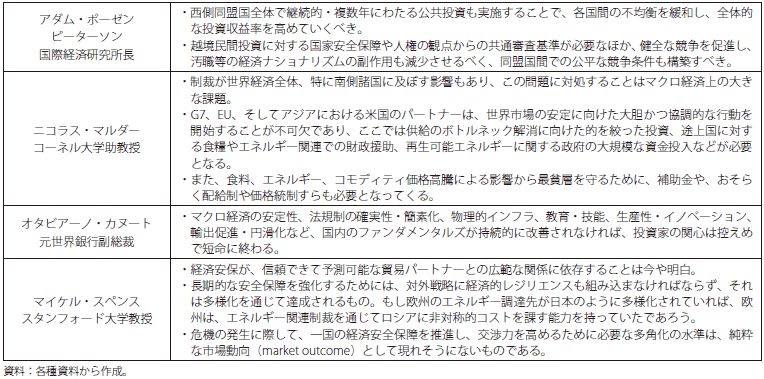
190 Dic Lo, Mei Wu (2014), “The State and Industrial Policy in Chinese Economic Development”
191 Alessio Terzi, Aneil Singh and Monika Sherwood (2022) “Industrial Policy for the 21st Century: Lessons from the Past”
192 デジタルサイエンス社「Dimensions」より作成。学術誌の種類を”Economics”、対象範囲をTitle and Abstract”、キーワードを”Industrial Policy” として検索。
193 IMFや世界銀行等の間で広く合意された、かつての米国流の新自由主義的「新古典派経済学的」戦略で、市場原理主義、小さな政府、健全財政、規制緩和、貿易・投資の自由化等に基づいた経済政策運営を世界中に輸出。
194 Reda Cherif and Fuad Hasanov, “The Return of the Policy That Shall Not Be Named: Principles of Industrial Policy”, WP/19/74, 26 March 2019.
195 UNCTAD, “World Investment Report 2018: Investment and New Industrial Policy”, June 2018.
196 ILO,“Transforming Economies: Making Industrial Policy Work for Growth, Jobs, and Development”, May 2014.
(2)米国における産業政策(サプライチェーン強靱化)
次に各国の産業政策の動向を見ていく。米国では、バイデン政権のジェイク・サリバン大統領補佐官(国家安全保障担当)が、2020年に発表した論考において、過去40年間の「新自由主義」を改め、大規模な産業政策を展開することを提唱している。サリバンは、「産業政策は、かつては恥すべきものとみなされていたが、今はほぼ当然のものとみなすべき」とし、「もし、ワシントンが、長期的、変革的ブレークスルーよりも短期的な利益を目指す民間企業のR&Dに依存し続けるのであれば、米国企業は中国企業との競争に敗北し続けるだろう」としている。米国の産業史を見ると、イノベーションが起きる初期段階で、産業政策が行われている。DARPA(国防高等研究計画局)において、当初、軍事目的で開発されたインターネットやGPS、自動音声認識といった技術は、その後、連邦政府の資金を投入することでシリコンバレーを中心に民間企業の設立を促し、ブレークスルーと商業化につながっていった。
米国は、1980年代以降、産業政策から距離を置いてきたものの、足下、米中対立等の地政学リスクや、サプライチェーンの維持といった課題を受けて、これら課題に対応するべく、安全保障に関わる重要物資の安定供給確保や、国内産業競争力強化のための産業政策を展開している。例えば半導体については、国内生産能力強化・研究開発への投資等を進めるとともに、信頼できるパートナーと協力して、強靱・多様・安全なサプライチェーン構築を支援することとしている(第Ⅰ-3-2-39表)。
第Ⅰ-3-2-39表 米国におけるサプライチェーン強靱化のための産業政策
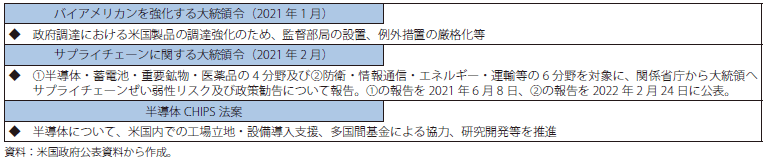
また、ホワイトハウスは、2021年2月の「サプライチェーンに関する大統領令」に基づき、報告書『強靱なサプライチェーンの構築、米国製造業の再活性化、幅広い成長の促進』及びこれに基づくファクトシートを公表し、サプライチェーン強靱化の具体策を提示している。報告書の中で、米国のサプライチェーン強靱化に向けた長期的戦略として、半導体生産・研究開発への拠出や、EV購入促進に向けた財政支援、蓄電池生産支援・投資、重要鉱物・物資の備蓄強化、公正かつ強靱なサプライチェーン支援のための包括的な貿易戦略の策定を挙げている(第Ⅰ-3-2-40表)。
第Ⅰ-3-2-40表 米国サプライチェーンに関する報告書197(2021年6月)
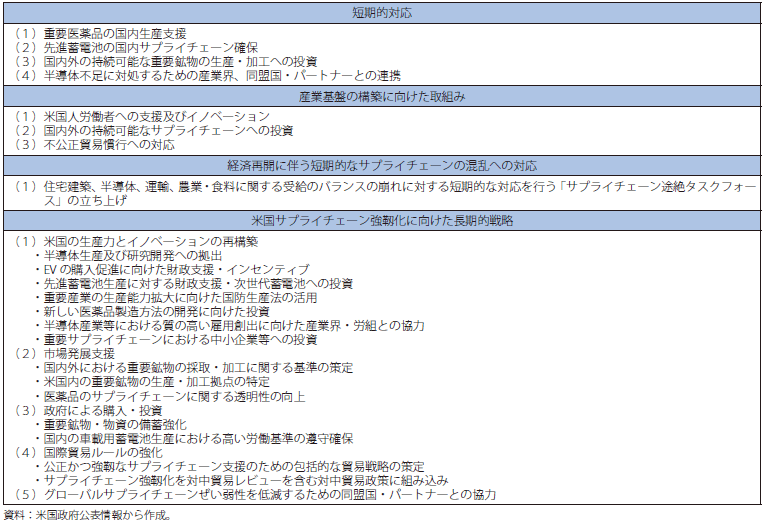
さらに同大統領令発出から一年後の2022年2月にはエネルギー産業基盤、運輸産業基盤、公衆衛生・生物事態対処産業基盤、情報通信技術、防衛産業基盤、農産物・食品の6分野について担当省庁から報告書を公表するとともに、ホワイトハウスから過去一年間の行動・成果にかかる報告書及び超党派インフラ法(2021年11月成立、8年間で総額約1兆ドルの投資)に基づく投資を中心とする「米国製造業の活性化及び重要サプライチェーンの確保のためのバイデン・ハリス計画」を発表している。
197 BUILDING RESILIENT SUPPLY CHAINS, REVITALIZING AMERICAN MANUFACTURING, AND FOSTERING BROAD-BASED GROWTH, June 2021
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/06/100-day-supply-chain-review-report.pdf![]()
(3)欧州における産業政策
欧州では、ICTや半導体、電気自動車用バッテリーといった新興技術分野を中心に、米国や中国に遅れをとっており、サプライチェーンで重要な位置を占めることができず、またユニコーン企業数でも劣位にあるなど、厳しい競争に直面しているという問題意識の下、ドイツやフランスなどEUの主要国が主導し、EU加盟国で連携しつつ、産業政策を展開している。
欧州は、グリーン・デジタルへの移行を柱とした経済復興と成長の実現を目指す中、米国や中国との経済・技術競争の激化に直面している。地政学的な緊張がより一層高まる中、中国など域外への依存度の低減を目的として、戦略的分野(原材料、電池、医薬品原料、水素、半導体、クラウド・エッジ技術)における自律の確保を目指すとともに、グリーンや人権といった共通価値の実現のための取組を域外も含めて求めている。そのような戦略的自律と共通価値の実現のためのツールとして、EUは一丸となって産業政策に取り組んでいる。
欧州は、地政学的な緊張が高まっている中、グリーンとデジタルへの移行を行い、経済面及び技術面の自立性を確保することが重要であり、そのために産業政策は必要なツールであるとしている。グリーン・デジタルへの移行を柱とし、経済復興と成長の実現を目指しており、中国を始め、域外依存の低減を図ることを目的とした戦略的分野における「戦略的自律」を強調している。また、グリーンや人権といった「共通価値」の実現のための取組も域外に求めている。
2021年5月には、「2020年産業戦略アップデート」を公表し、アップデート版では、新型コロナウイルスによる環境変化を背景に、こうした危機からの教訓を新たな産業戦略に反映させている(第Ⅰ-3-2-41表)。主にコロナショックの影響・教訓、戦略的依存性についての分析を重点とし、①単一市場の強靱性強化、②戦略的分野への高依存の対処、③グリーン・デジタル移行の加速の重要性を強調しており、新型コロナショックなどによる国際的なバリューチェーンの混乱を教訓に、戦略上懸念されるEU域外への依存に対する対応が必要だとしている。
第Ⅰ-3-2-41表 サプライチェーン強靱化・自立に向けたEU の取組
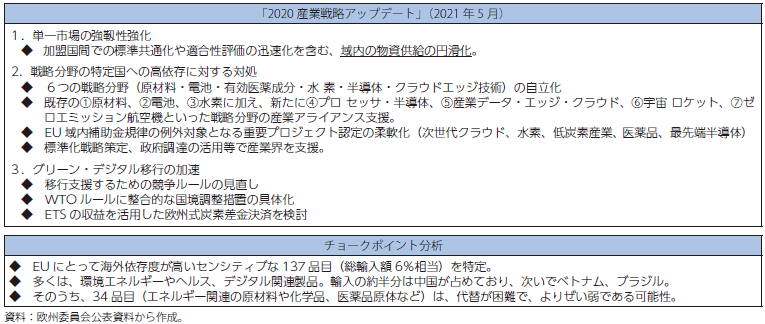
また、EUは、バッテリーや水素、重要な原材料等の域内調達比率を高めるべく、重点産業を包括的に支援するべく、欧州バッテリー同盟(EBA)やクリーン水素同盟、原材料同盟(ERMA)といった産業同盟を形成している(第Ⅰ-3-2-42表)。2021年7月には、欧州委員会は、次世代マイクロチップと産業用クラウドの進歩、デジタルインフラ・製品・サービスの強化を目的に「プロセッサ・半導体技術アライアンス」、「産業用クラウドテクノロジーアライアンス」を発表している。このほか、2021年9月、フォンデアライエン欧州委員長は一般教書演説において、アジアに過度に依存する半導体の生産能力の強化の必要性に言及した上で、製造を含む欧州の最先端チップ・エコシステムの構築を目指し、供給の安全を確保し、欧州の画期的技術のための新たな市場を発展目的とする欧州半導体法案を提案している。
第Ⅰ-3-2-42表 欧州における産業同盟
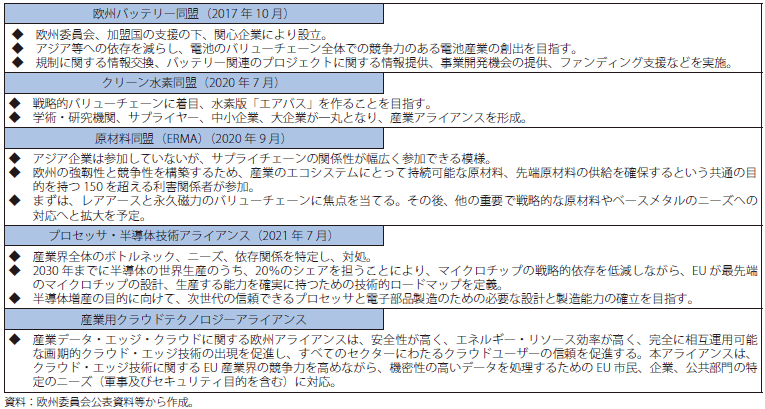
(4)中国における産業政策
中国も、国家主導の産業政策を展開しており、半導体製造装置などのコア技術や高度な部品・素材の海外依存度が高い産業構造にある中、2015年5月に「中国製造2025」を発表し、次世代情報技術や省エネ・新エネ自動車といった10の重点分野について2025年までに7割を国産化することを掲げ、科学技術力・サプライチェーンの強化やコア技術国産化により、サプライチェーンのチョークポイント解消を推進してきている(第Ⅰ-3-2-43表、第Ⅰ-3-2-44表、第Ⅰ-3-2-45図)。
第Ⅰ-3-2-43表 「中国製造2025」の10の重点分野
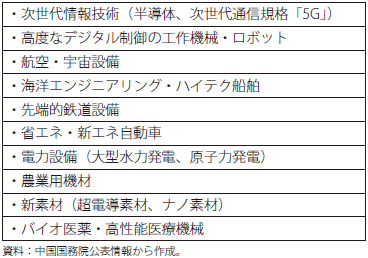
第Ⅰ-3-2-44表 「中国製造2025」3段階戦略目標
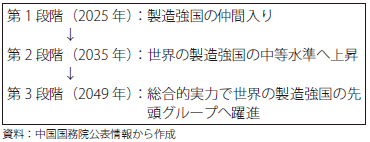
第Ⅰ-3-2-45図 主要技術に関する国内調達目標
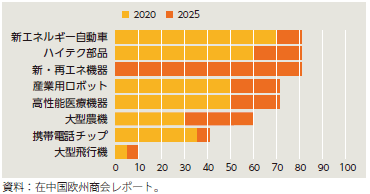
新興技術による産業育成の重点分野を設定し、中国国内に当該分野の研究開発機能を設ける内外資企業に優遇税制を提供するなど、積極的に自国内の技術育成を支援している。
なお、2014年と2019年に計約5兆円規模の「国家集積回路産業投資資金」が設置されており、これに加えて、各地方政府にも、計約5兆円を超える半導体産業向けの基金が存在し、合計10兆円超の資金が半導体関連技術に投じられていると見られる。
また、第1部第2章第4節で見たように、中国の政府補助金の動向を見ると、まず、国有企業だけでなく、民営企業に対しても幅広く交付されており、むしろ、2010年代半ば以降は、補助金総額としては、民営企業が中央政府や地方政府所管の国有企業を上回っている。産業の高度化に当たって、民営企業を含め幅広い企業に対して柔軟な支援を行っている様子がうかがえる。次に、対象業種としては、2015年の「中国製造2025」の公表後、全体に占める関連分野向け補助金のシェアが上昇しており、同分野への補助金が手厚くなっている。その重点10分野の中で、次世代情報技術産業、バイオ医薬・高性能医療機械においては、国有企業よりも民営企業の補助金が大きく拡大しており、民生に近い新分野においては民営企業が先導するという特徴が見受けられる。また、補助金の手厚さ、補助金の売上高に対する比率の上位グループと下位グループで財務状況等の違いを見ると、業種特性など考慮すべき点があるので、直ちに結論付けることはできないが、事実上、補助金が赤字補填を果たしている可能性や研究開発や設備投資を促進していることを示唆している。