第1節 グローバルバリューチェーンの実態と課題
1.世界の貿易投資構造の変化
(1)財貿易
ここでは長期的な世界の貿易投資構造の変化を考察し、併せて直近の動向も確認する。財貿易は長期的に拡大が続いているが、貿易構造は貿易財の内容、貿易相手国ともに構造変化が見てとれる。
輸出の伸び率は、世界金融危機までGDPを上回って大きく成長しており、その背景には、国際的生産分業とそれを支える中間財貿易の拡大があった(第Ⅱ-1-1-1図)。対外直接投資の結果、生産拠点の海外移転が進み、国際生産分業の進展とともに、取引される財の内容が最終財から中間財へシフトしてきた。輸出では、グローバルバリューチェーンに沿って中間財が国境を越えるたびに重複して計上され、中間財を含まない純粋な付加価値の合計であるGDPを上回って拡大したことが指摘されている。世界金融危機以降は、輸出の伸びがGDPを下回るような動きも見られるようになってきている。こうした動きは、スロートレードと言われる現象で、中間財の現地生産が拡大して、中間財貿易の拡大に一服感が出てきたことが要因として指摘されている。近年の動きを見ると、2020年はコロナの影響で輸出、GDPともに大きく落ちこんだが、2021年は反動で大きく伸び、輸出額は過去最高を記録している。今後は、ロシアによるウクライナ侵略により世界経済の不確実性が高まっているものの、WTOやIMFは、2022年以降も輸出、GDPともに拡大を続けていくと予測している。
第Ⅱ-1-1-1図 世界のGDP 及び輸出の成長率の推移
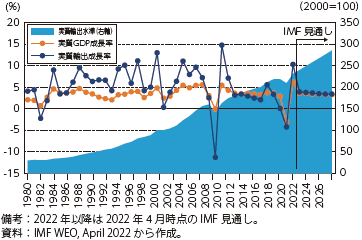
また、貿易相手国についても、遠隔地との地域間貿易から近距離の地域内貿易へ重点がシフトしていることが指摘できる。一般的に貿易は、輸送費の関係から近距離間の取引が好まれる傾向があるが、経済連携協定を通じて関税など貿易コストを引き下げる動きとあいまって、近距離である域内諸国との貿易取引がより拡大し、域内貿易比率が上昇している(第Ⅱ-1-1-2図)1。これを見ると、EUでは、加盟国の変化による断続は見られるものの、概ね1980年代は域内貿易比率が上昇し、その後も60%を超える高い水準で推移している2。北米では、2000年頃まで域内貿易比率が上昇し、2008年頃まで低下した後、40%前後で安定的に推移している。アジアでは、域内の自由化を進めるASEAN10か国(ASEAN10)に日本、中国及び韓国を加えた13か国(ASEAN+3)や、ASEAN+3と豪州及びニュージーランドの地域的な包括的経済連携(RCEP)協定の参加国にインドを加えた16か国(ASEAN+6)の間で、現在に至るまで域内比率の上昇が続いている3。
第Ⅱ-1-1-2図 主要地域の域内貿易比率の推移
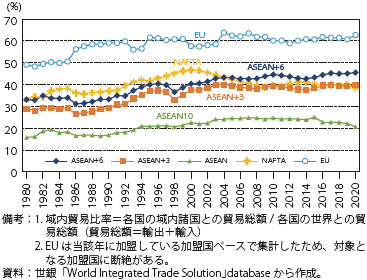
このように、貿易における中間財のシェアが上昇し、近距離の相手国との域内貿易がより拡大する傾向が見られる。
1 貿易の計量分析に利用される重力モデルでは、貿易当事国間の距離は貿易額に有意にマイナスの影響を及ぼすことが広く知られている。
2 本来は継続的に同じ対象国を見ていく必要があるが、EUの場合は加盟国に頻繁な変更があるため、ここでは当該年に加盟していた加盟国ベースで集計した。このため、加盟国に断絶がある点には注意が必要。具体的には、1980年はイタリア、オランダ、ドイツ、フランス、ベルギー、ルクセンブルク、デンマーク、アイルランド、英国の9か国ベース。1981~1985年はギリシアを含む10か国ベース。1986~1994年はホルトガル、スペインを含む12か国ベース。1995~2003年はオーストリア、フィンランド、スウェーデンを含む15か国ベース。2004~2006年はキプロス、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラシビア、リトアニア、マルタ、ポーランド、スロバキア、スロベニアを含む25か国ベース。2007~2012年はブルガリア、ルーマニアを含む27か国ベース。2013~2019年はクロアチアを含む28か国ベース。2020年は英国が離脱したため27か国ベース。
3 ASEAN10は、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、ラオス、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの10か国。ASEAN諸国は1992年に合意されたアセアン自由貿易地域(AFTA)に基づく共通効果特恵関税(CEPT)等を通じて域内の貿易自由化を推進してきた。正確にはベトナム(1995年)、ラオス(1997年)、ミャンマー(1997年)、カンボジア(1999年)は1990年代後半の加盟となるが、近年加盟国に変更はなく、継続的に同じ対象国を見る方が推移の変化を見るのには適していることなどから、便宜的に全期間を通じて10か国ベースで集計した。
(2)サービス貿易
次に世界のサービス貿易を概観する。サービス貿易も世界金融危機などによる一時的な後退は見られたが、長期的に拡大基調で推移しており、UNCTADのデータベースで把握できる2005年からコロナショック直前の2019年までの14年間で約2倍の規模に拡大した(第Ⅱ-1-1-3図)。ただし、近年、2020年は新型コロナウイルス感染症の影響で旅行サービスを中心に大きく減少した。四半期別の伸び率の推移を見ると、2020年は旅行サービスが大きくマイナスに落ち込んだほか、輸送サービスもマイナスとなった(第Ⅱ-1-1-4図)。2021年は前年の反動もあり、第2四半期に伸びがプラスに転じ、次第に回復しつつあるものの、2019年までの水準からは程遠い状況となっている。
第Ⅱ-1-1-3図 世界のサービス輸出の推移(年次)
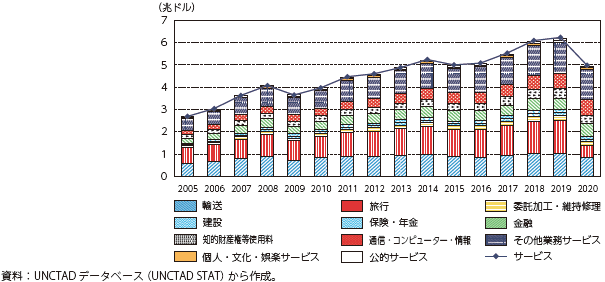
第Ⅱ-1-1-4図 最近のサービス輸出の伸び率の推移(四半期 / 前年同期比)
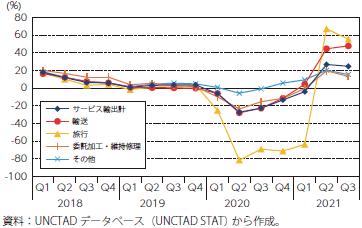
長期的なサービス輸出の構成の変化を2005年と2019年で比べてみれば、「輸送」、「旅行」のシェアが縮小する一方で、IT化の進展により「通信・コンピューター・情報サービス」が大きく拡大している(第Ⅱ-1-1-5図)4。また、研究開発サービス、法務、会計・経営コンサルティング等の専門サービス、建築、工学等の技術サービスなど多様な業務サービスを含む「その他業務サービス」もシェアを大きく拡大した。
第Ⅱ-1-1-5図 サービス輸出の長期的な構成の変化
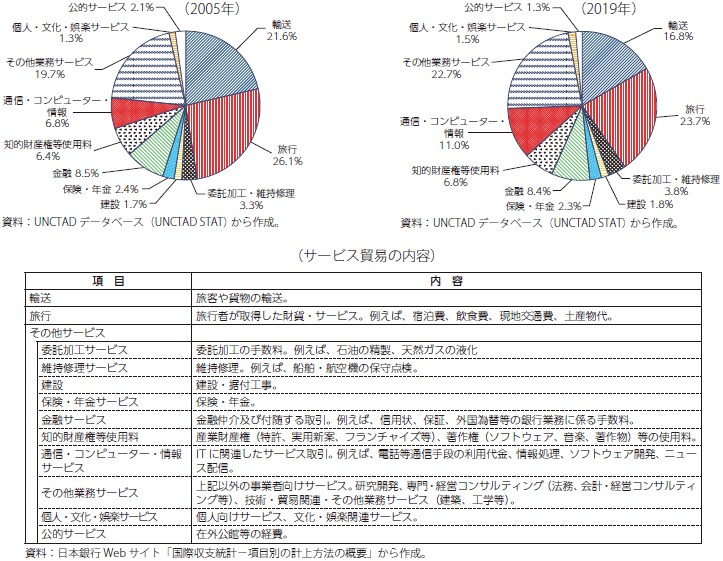
情報通信技術の発達は、国際的な生産分業やそれに基づくグローバルバリューチェーンの深化と深く関わっていることが指摘されており、サービス貿易における「通信・コンピューター・情報サービス」の拡大はグローバルバリューチェーンの深化を反映している。ボールドウィン(2016)は、技術の発達が移動コストを低下させ、国境を越えた分業をもたらしてきたと指摘している5。まず、蒸気船や鉄道の発明によって物資の移動コストが低下し、生産活動が産業単位で海外に移転することが可能となった(第1のアンバンドリング)(第Ⅱ-1-1-6表)。次に情報通信技術の発達によってアイデア(技術・データ等)の移動コストが低下して、生産技術や経営ノウハウを新興国に持ち込み、複雑な活動を遠隔地から調整することが可能となった(第2のアンバンドリング)。このことが生産工程のタスク単位での国際分業を進展させ、グローバルバリューチェーンの深化を促した。さらに情報通信技術が発展すると、それまでは直接顔をあわせる必要があったサービスが国境を越えて提供できるようになり、個人単位でタスクが分割されるようになると指摘している(第3のアンバンドリング)。
第Ⅱ-1-1-6表 3つのアンバンドリング
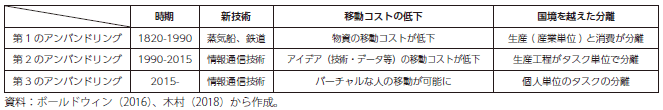
サービス貿易の主要輸出国を見ると、首位は米国で、2位以下に、英国、ドイツ、中国、アイルランド等が続く(第Ⅱ-1-1-7図)6。なお、米国は、財貿易では赤字国であるが、サービス貿易では黒字国となっている。
第Ⅱ-1-1-7図 サービス輸出の国別動向
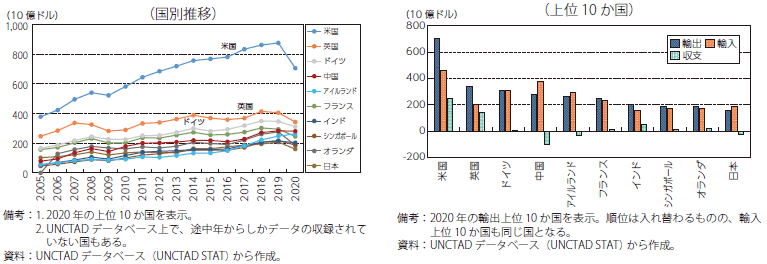
これらの国の主要輸出項目を見ると、「その他業務サービス」が大きい点はほぼ共通しているが、国ごとの特徴も見られる(第Ⅱ-1-1-8図)。例えば、米国は「旅行」、「金融」、「知的財産権等使用料」が大きく、コロナ前まで旅行者を集めていたことや金融サービス、知的財産を世界に供給していることがうかがわれる。英国は、「その他業務サービス」に次いで、金額ベースでやや低下気味ながら「金融」が大きく、ドイツは「輸送」が大きい。中国は「旅行」が2010年代半ばから緩やかに低下する一方で、「通信」が急拡大しており、「輸送」も伸びている。アイルランドは「通信」が突出して拡大しており、法務・会計・コンサルタントなどの「その他業務サービス」、「金融」が続いている。
第Ⅱ-1-1-8図 主要国のサービス輸出
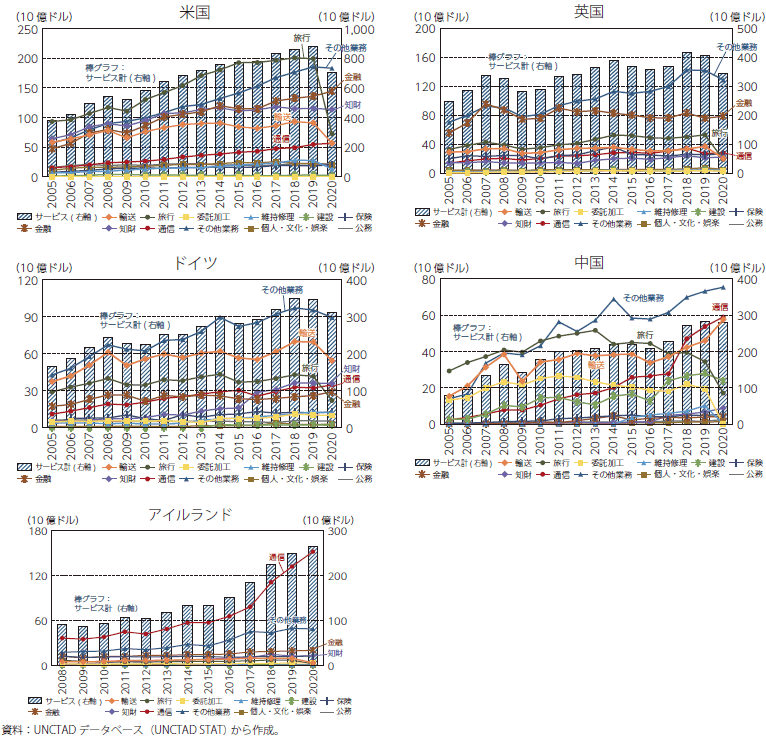
4 2020年はコロナの影響が大きいことから、前年の2019年との比較をした。
5 詳細は、通商白書(2020)の第Ⅱ部第2章第1節「3つのアンバンドリングから見るグローバリゼーションの過去・現在・未来」参照。
6 本節において、特に断らない限り「中国」とは本土のみで香港は含まない
(3)対外直接投資
世界の対外直接投資は残高ベースで長期的に拡大してきている(第Ⅱ-1-1-9図)。米国を筆頭に主要先進国の対外直接投資が拡大するとともに、2010年代に入ってからは中国も対外直接投資を拡大した。投資相手国としては、UNCTAD統計の区分によれば、先進国向けが約7割と大きな割合を占めるが、中国など新興国向けも拡大している(第Ⅱ-1-1-10図)7。特に中国の対内直接投資残高は、世界金融危機後、突出して拡大している。これは、直接投資を通じて、中国を始めとする新興国に生産拠点が設置され、低賃金労働を生かした国際的な生産分業が拡大されてきたことを反映している。そのような生産拠点間の中間財貿易がグローバルバリューチェーンへとつながる。
第Ⅱ-1-1-9図 世界主要国の対外直接投資残高の推移
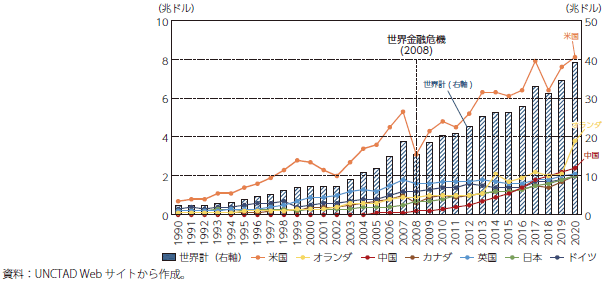
第Ⅱ-1-1-10図 世界主要新興国の対内直接投資残高の推移
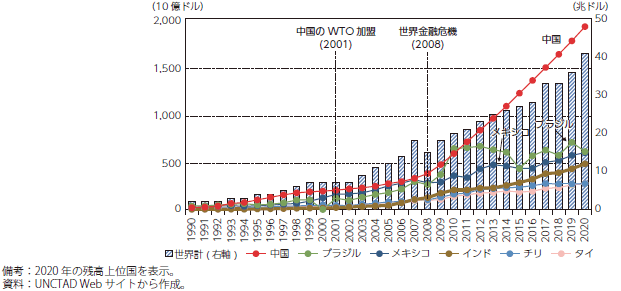
(中国の対内・対外直接投資)
ここで対内直接投資が急増している中国の投資元を見てみる。2020年は中国へのアクセスが良く、自由な経済活動が可能な香港が全体の約7割を占め、ケイマン諸島、バージン諸島、シンガポール、オランダなどの税負担の軽い金融センターも多い(第Ⅱ-1-1-11図)。それ以外は、アジア域内の韓国、日本、台湾、地域外では米国、ドイツの投資が多い。金融センターを経由しているため、実際の投資元は明らかではないものの、中国には主要国からの対内直接投資を通じて生産拠点が立地していることが分かる。
第Ⅱ-1-1-11図 中国の対内直接投資(フロー)の推移
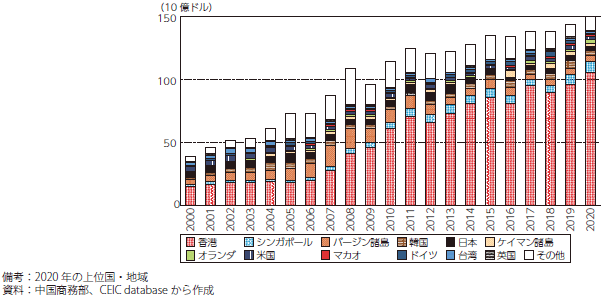
中国には主要国からの対内直接投資が多いが、中国自身も2000年代に入って、「走出去」政策の下、対外直接投資を拡大している。そして2010年代半ばに残高ベースで対外直接投資は対内直投を追い抜くこととなる。その中国の投資先は、対内直接投資と同じように、税負担が軽く対外直接投資等の規制の少ない香港が全体の過半を占め、ケイマン諸島、バージン諸島、シンガポール、オランダなどの金融センターが多い(第Ⅱ-1-1-12図)。
第Ⅱ-1-1-12図 中国の対外直接投資(フロー)の推移
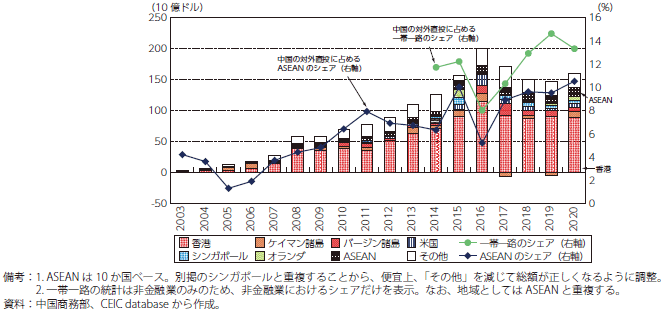
ここで中国とASEANの関係も見ておく。金融センターをはさむため、中国の実際の投資先の実態は明らかではないものの、統計上、2010年代後半、中国の対外直接投資に占めるASEANのシェアは拡大している8。ASEAN諸国へ中国の対外直接投資が進み、中国の経済的なプレゼンスが高まっている。また、一帯一路沿線国のシェアも上昇している。
7 UNCTAD統計によれば、2020年末の対内直接投資残高は、世界全体で約41.4兆ドル、うち、先進国は約28.7兆ドル(69.4%)、新興国約11.8兆ドル(28.5%)、市場経済移行国約0.9兆ドル(2.1%)。なお、ここでの国の区分はUNCTAD統計に従った。
8 念のため、ASEAN側統計で中国からの対内直投を見てみると、2010年代後半、中国からの投資額、中国の占めるシェアはともに大きく拡大している。
2.日本の貿易投資動向
ここまでは世界の貿易投資動向を見てきたが、ここでは我が国の貿易投資動向を概観する。
(1)日本の貿易動向
2021年の日本の財貿易は、輸出額が83兆914億円と2020年から21.5%増加、輸入額が84兆7,607億円と2020年から24.6%増加した。新型コロナウイルス流行前の2019年と比べて輸出入とも金額ベースで上回っており回復の動きが見られる。鉱物性燃料等の資源価格の高騰を背景に輸入の増加が輸出の増加を上回り、貿易収支で見ると▲1兆6,694億円と2年ぶりの赤字に転じた(第Ⅱ-1-1-13図)。
第Ⅱ-1-1-13図 日本の貿易収支の推移
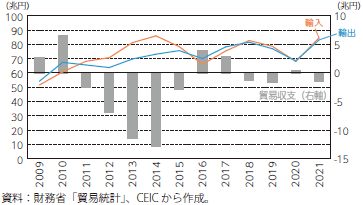
① 品目別の貿易動向
(輸出)
2021年の輸出の品目構成を見ると、輸送用機器が輸出全体の19.5%、一般機械が19.7%、電気機器が18.4%と機械関係の上位3品目で約6割を占めている(第Ⅱ-1-1-14図)。
第Ⅱ-1-1-14図 日本の輸出の品目構成(2021年)
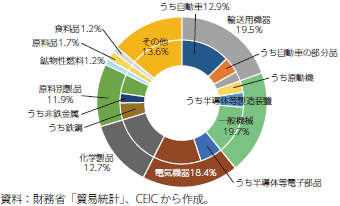
輸出の月別推移を見ると、新型コロナウイルスの影響で大きく落ち込んだ2020年半ばから次第に回復してきている(第Ⅱ-1-1-15図)。また、品目別に見ると電気機器、一般機械が回復傾向にある。輸送用機器は、新型コロナウイルス流行前と比較すると、世界的な部品調達難による自動車の減産の影響で、2019年の水準をおおむね下回って推移したものの、2020年よりは回復傾向にあることが分かる。電気機器や一般機械は、おおむね感染拡大前の水準を上回っており、また、2020年よりも高い水準での推移を維持している。
第Ⅱ-1-1-15図 日本の輸出の伸び率の推移(品目別・月別)
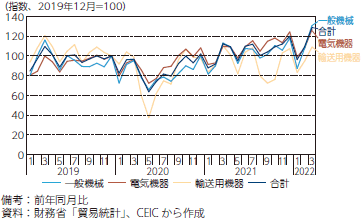
(輸入)
2021年の輸入の品目構成を見ると、鉱物性燃料が輸入全体の20.0%、次いで電気機器が16.1%を占めている(第Ⅱ-1-1-16図)。輸出と異なり、輸入の特徴として、鉱物性燃料(原粗油や天然ガス等)、食料品(肉類等)、原料品(非鉄金属鉱や鉄鉱石等)等の資源・食料の割合が高いことが挙げられる。また、機械関係でも、半導体等電子部品など中間財もあるが、新型コロナウイルス感染拡大を受けたテレワーク需要等により、通信機、電算機類(パソコン)など最終財の輸入が多い点も特徴である。
第Ⅱ-1-1-16図 日本の輸入の品目構成(2021年)
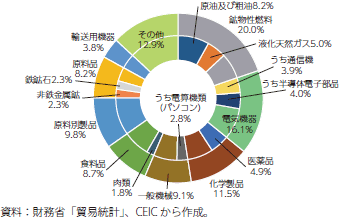
輸入の月別推移を見ると、2020年半ばから次第に回復してきている(第Ⅱ-1-1-17図)。品目別に見ると、鉱物性燃料は、資源価格の高騰等を背景に年後半にかけて新型コロナウイルス流行前を上回る水準となった。新型コロナウイルスのワクチン需要の増加の影響により、医薬品が金額ベースで約4割を占める化学製品も、年間を通して感染拡大前を大きく上回る水準で推移している。その他に、電気機器や一般機器も、2020年の落ち込みから回復し、感染拡大前とほぼ同程度の水準まで回復したことが分かる。
第Ⅱ-1-1-17図 日本の輸入の伸び率の推移(品目別・月別)
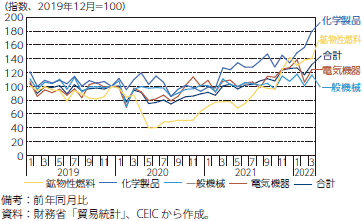
② 国・地域別の貿易動向
2021年の輸出の相手国・地域別構成を見ると、中国、米国、ASEAN、EUが輸出入ともに上位4か国・地域に入り、その合計は世界全体の約6割を占める(第Ⅱ-1-1-18図)。また、地域としては、中国、ASEANに台湾、韓国等を含めたアジアが輸出では世界全体の約6割、輸入では約5割を占め、貿易相手として重要であることが分かる。
第Ⅱ-1-1-18図 日本の輸出入の主要相手国・地域の構成
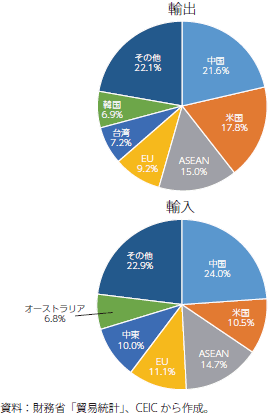
2021年の国・地域別に貿易動向を概観する。まず、輸出入について、国・地域別に伸び率を見ると、いずれの国・地域も2020年に感染症の影響を受け落ち込んだ反動により、2021年はプラスの伸び率となった。特に、中国を始めとするアジアの国・地域の輸出の伸び率は20%前後の高い伸び率となった。また、鉱物性燃料の価格高騰の影響を受け、中東からの輸入は52.4%増加と大きく伸びた(第Ⅱ-1-1-19表)。
第Ⅱ-1-1-19表 日本の輸出入の主要相手国・地域別の伸び率
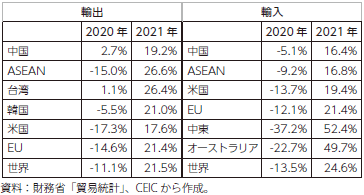
輸出相手国・地域別に月次の推移を見ると、中国と米国については、新型コロナウイルス流行の影響で落ち込んだ2020年から回復し、年間を通して感染拡大前の2019年とほぼ同程度の水準で推移している。EUは、年初、2020年よりは回復しているものの、年間を通して感染拡大前の2019年の水準を下回っており、半導体不足の影響による自動車輸出の減少を背景に、回復が遅れたことが分かる。(第Ⅱ-1-1-20図)。
第Ⅱ-1-1-20図 日本の輸出金額の推移
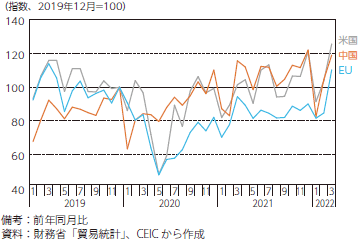
輸入については、中国、米国、EUのいずれも2020年の落ち込みから回復し、また、2019年をほぼ上回る水準で推移している。(第Ⅱ-1-1-21図)。
第Ⅱ-1-1-21図 日本の輸入金額の推移
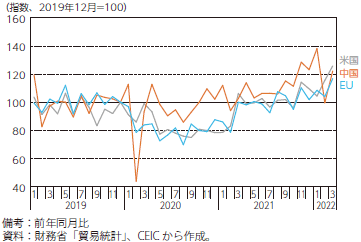
③ 経常収支の動向
2021年の日本の経常収支は15兆4,359億円の黒字だった。第一次所得収支、貿易収支が黒字となる一方で、サービス収支、第二次所得収支の赤字が続いた。黒字幅は前年と比べて4,431億円(2.8%)の縮小となった(第Ⅱ-1-1-22図)。黒字幅が縮小した要因は、第一次所得収支の黒字幅が拡大した一方で、半導体不足による自動車輸出の減少と原油価格の高騰を背景に貿易収支の黒字幅が縮小したことが挙げられる。旅行収支の黒字幅縮小のため、サービス収支の赤字幅が拡大したことも影響した。経常収支の月別推移では、8月以降、貿易収支が赤字に転じたことで、経常収支の黒字は減少している(第Ⅱ-1-1-23図)。
第Ⅱ-1-1-22図 日本の経常収支の推移(年別)
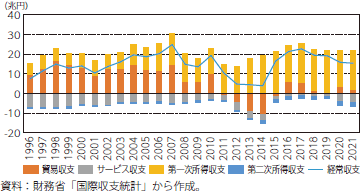
第Ⅱ-1-1-23図 日本の経常収支の推移(月別)
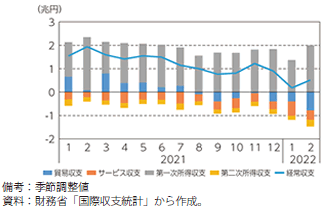
我が国の経常収支は、近年、貿易収支とサービス収支の縮小が主因となって黒字幅が縮小傾向にある。電気や素材産業等の輸出産業の競争力低下といった構造的要因に加えて、足下では、原油等の資源高騰やワクチン等の医薬品の輸入増加が貿易収支を押し下げ、インバウンドの大幅減少等がサービス収支の赤字を拡大することで、大きな下方圧力となっている。こうした経常収支のマイナス要因について対応を検討していくことは重要である。
(2)日本の対外直接投資
日本の対外直接投資、特に後のパートで分析する日本のグローバルバリューチェーンに係る日系製造業の対外直接投資の動向を確認する。まず、日本の地域別直接投資残高を見ると、2000年代、欧米が緩やかな増加に留まる中で、アジア地域が堅調に拡大して、製造業においてアジアが最も大きなシェアを占めるに至っている9(第Ⅱ-1-1-24図)。ここから、日系製造業のアジア展開に焦点を置いて見ていく。そのアジアの中での国・地域別推移を見ると、「世界の工場」と呼ばれる中国が金額ベースで突出して拡大しており、第二位にはタイが続いている(第Ⅱ-1-1-25図)。アジアの中では、中国、タイの存在が大きく、第三位のシンガポール以下を大きく引き離している。一方、日本の直接投資残高総額に占めるシェアで相対的なプレゼンスを見ると、既に中国は2012年をピークに低下に転じており、これに対して、タイ、インド、ベトナムは上昇が続いている10。なお、シンガポール、韓国、インドネシアはほぼ横ばいで推移している。
第Ⅱ-1-1-24図 日本の対外直接投資残高(製造業分野)の推移
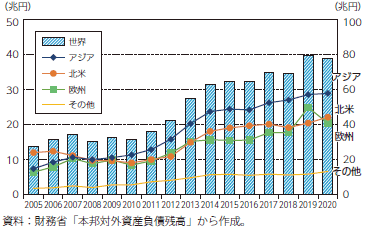
第Ⅱ-1-1-25図 日本のアジア主要国・地域向け直接投資残高(製造業分野)
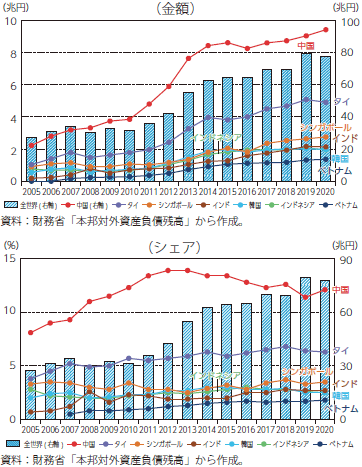
主要国の中国向け直接投資残高(製造業分野)のシェアの推移を見ると、日本が2012年をピークに低下に転じているが、米国も米中貿易摩擦の高まりの中で2018年をピークに頭打ちの動きが見られる(第Ⅱ-1-1-26図)。一方、EUは、近年、むしろ拡大の方向に動いている。
第Ⅱ-1-1-26図 日本、米国、EUの中国向け直接投資残高のシェア(製造業分野)
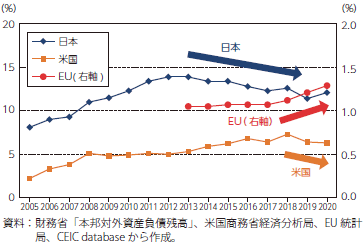
アジアにおける業種別の直接投資残高の動向を見ると、金額ベースで輸送機械が大きく拡大しており、それに電気機械が続いている(第Ⅱ-1-1-27図)。その他には、一般機械や化学など、機械、素材関係が多く、繊維や食品など軽工業は少ない。各業種の世界全体におけるアジアのシェアを見ると、アジアは製造業において約4割のシェアを占めており、特に輸送機械におけるアジアのシェアが上昇してきている。
第Ⅱ-1-1-27図 日本の業種別対外直接投資残高の推移
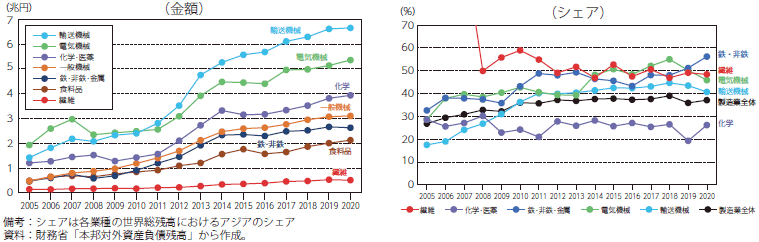
業種・国のマトリクスで対外直接投資残高の推移を見ると、労働集約的な繊維業では、人件費の上昇とともに中国のシェアが低下して、タイ、ベトナムが上昇している(第Ⅱ-1-1-28図)。電気機械では、中国、タイが上昇してきたが近年は頭打ちの兆しがある。まだ水準が低いものの、インド、ベトナムが上昇している。輸送機械では、中国、タイ、インドネシアのシェアが高いが、インドが急速にシェアを拡大してきている。
第Ⅱ-1-1-28図 日本の主要業種別の対外直接投資残高の各国・地域別シェア
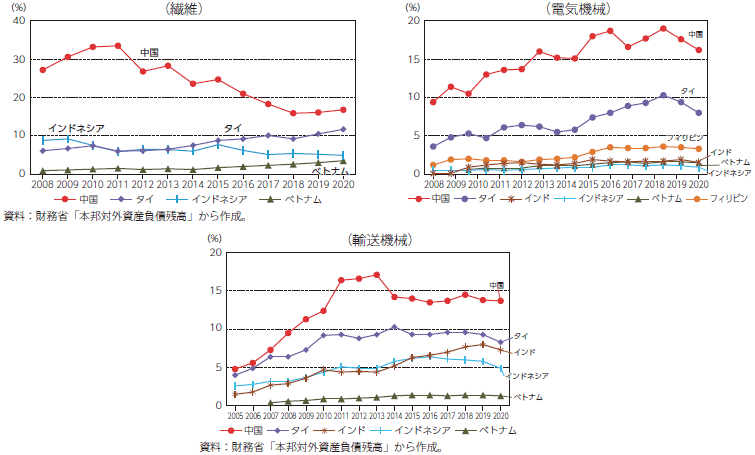
さらに国・業種のマトリクスで整理し直したのが第Ⅱ-1-1-29図である。最も直接投資残高の多い中国は、各業種において高いシェアを持つが、人件費の上昇とともに繊維におけるシェアが低下してきており、一般機械、電気機械など機械関係におけるシェアも頭打ちの傾向が見られる。次に残高の多いタイは、輸送機械における存在感が高かったが、近年は電気機械や鉄鋼・非鉄金属におけるシェアも上昇してきている。インドネシアは、繊維、木材など軽工業におけるシェアが低下する一方で、輸送機械、鉄鋼・非鉄金属においてシェアが高まっている。ベトナムは、まだ投資残高は低いものの、製造業全体で増加基調にあり、特に繊維におけるシェア拡大が著しく、併せて近年は電気機械におけるシェアも上昇している。インドの場合は、輸送機械におけるシェアが突出して拡大している。
第Ⅱ-1-1-29図 日本の国別対外直接投資残高の業種別シェア
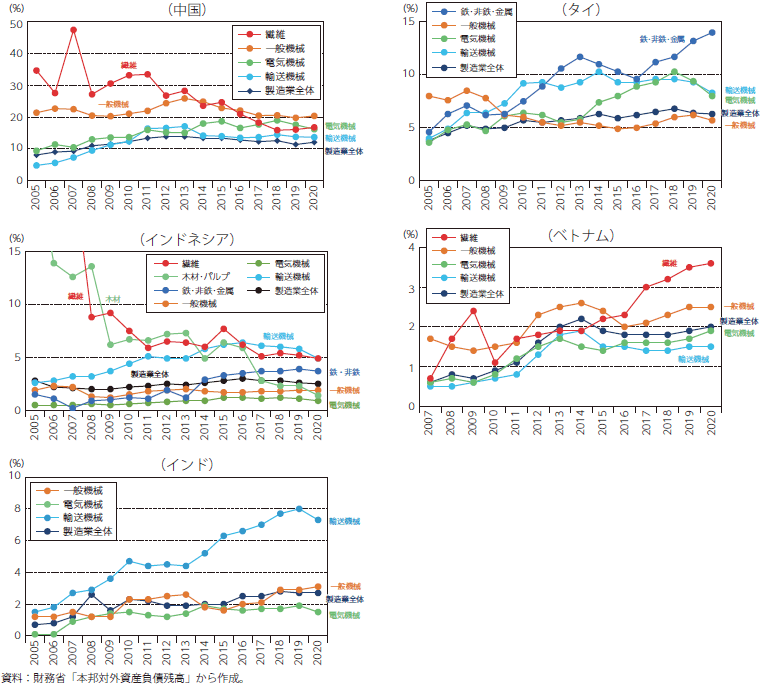
ここまで見てきたように、日本の製造業の対外直接投資は、中国やタイなどアジアを中心に、輸送機械、電気機械などの機械、化学、鉄鋼・非鉄金属などの素材関係の生産拠点を建設してきた。後で見るように、日本とこれら生産拠点間を結ぶサプライチェーンが構築されたが、人件費の上昇などの経済的要因や米中摩擦を契機とする地政学的リスクが高まる中で、中国への投資の集中を緩和し、タイ、インド、ベトナム等へ投資が分散する動きが見られる。
9 図表は国際収支統計で業種別残高の公表が始まった2005年以降を表示。
10 直接投資残高は円ベースで公表されるが、現地通貨建ての資産を円換算するに当たって為替レートの影響を受ける。このため、円ベースの残高の増減が必ずしも実態をあらわすとは限らない点に注意が必要。例えば、円の為替レートは2011年の約80円から、2015年約121円(年平均)まで円安方向に変化している。このため、国別残高の世界全体に占めるシェアを併せて見ることで、その国の日本にとってのプレゼンスの大きさを考察した。
3.中間財貿易と付加価値貿易
(1)中間財貿易へのシフト
既に見たように、世界貿易は、国際的な生産分業の展開を反映して、最終財の貿易から中間財主体の貿易へシフトしてきている。近年、中間財へのシフトはスロートレードと言われるように頭打ちの兆候も見られるが、グローバルバリューチェーンの展開が進んでいるアジア域内では機械産業を中心に中間財が高い水準で推移している(第Ⅱ-1-1-30図)11。アジア主要国を中心に貿易フローと中間財の占めるシェアを図示したのが第Ⅱ-1-1-31図である。アジア域内を見ると、日本・韓国・台湾から中国・ASEANへの輸出は中間財のシェアが高く、域内で生産分業が行われていることを示唆している。一方、中国・ASEANから欧米への輸出は最終財のシェアが高く、組み立てられた最終財が輸出されている様子がうかがわれる。
第Ⅱ-1-1-30図 世界の財別輸出の推移
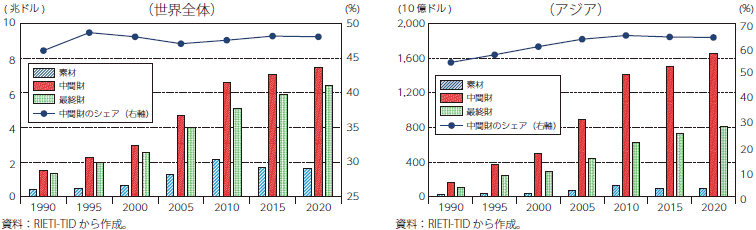
第Ⅱ-1-1-31図 機械産業の中間財貿易
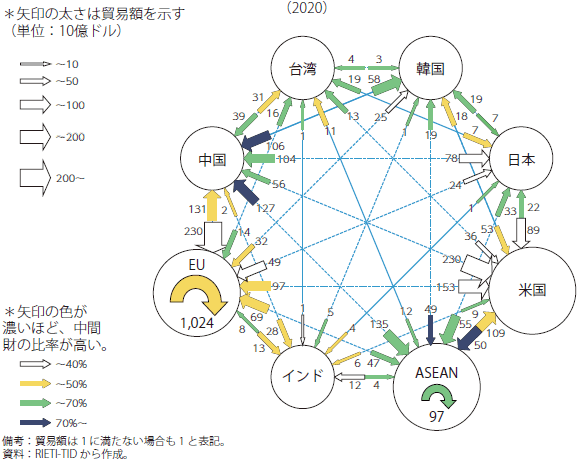
11 RIETI-TIDのデータを利用した。同データベースでは、データの制約から、アジアは、日本、中国、韓国、香港、台湾、ブルネイ、カンボジア、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム。ASEANは、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの8か国ベースとした。
(2) 付加価値貿易
このような国際的な生産分業とそれに基づくグローバルバリューチェーンの様子は、通常の貿易統計だけでは実態の把握が困難になってきている。ある財の中には、中間財の集積という形で、諸外国で生産された付加価値成分が含まれているためである。そこで、財の中に含まれる付加価値をその原産国ごとに分けて考察することで貿易動向を整理してみる。そのために、OECDが作成した付加価値貿易統計(OECD TiVA)を利用する12。
① 日本のグローバルバリューチェーンと前方参加・後方参加
グローバルバリューチェーンへの参加は、その国の立ち位置で二とおりのケースがある。第Ⅱ-1-1-32図のような単純なグローバルバリューチェーンを想定した場合、A国のように生産工程の上流に位置して他国に中間財を供給する場合が前方参加、B国のように下流に位置して自国の生産のために他国からの中間財供給を受ける場合が後方参加となる。
第Ⅱ-1-1-32図 グローバルバリューチェーンの前方参加・後方参加
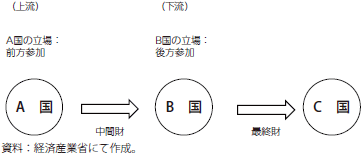
第Ⅱ-1-1-33図は日本から米国への輸出をめぐって、総輸出額とその中の日本の付加価値成分を表示している13。日本にある親会社から中国やASEANに立地する子会社に基幹部品などの中間財を輸出して、現地で組み立てた完成品を米国に輸出する、いわゆる三角貿易のような場合の日本の立ち位置が前方参加となる。中国やASEANから米国への輸出の中には、日本で生産された付加価値成分が含まれており、この額が大きいほど前方参加の度合いが大きいことになる。反対に中国やASEANから中間財を輸入して、日本で組み立てた完成品を米国に輸出する場合が後方参加に当たり、日本の輸出の中には、中国やASEANなどの付加価値成分が含まれることになる。
第Ⅱ-1-1-33図 日本を取り巻くグローバルバリューチェーンの例
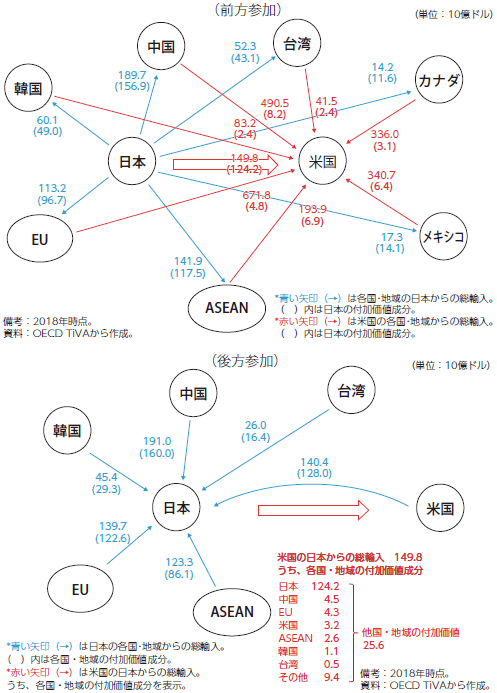
OECD TiVAでは、ある国の総輸出に対する、これら付加価値の比率から、前方参加、後方参加の程度を指標として公表している。日本のグローバルバリューチェーン参加の変化を長期的に見ると、2000年代まで前方参加の程度が緩やかに拡大し、それ以降はほぼ20%台半ばの水準を安定的に推移している(第Ⅱ-1-1-34図)。一方、後方参加は、2000年代に入ってから急速に拡大し、OECD TiVAが対象としている1995年から2018年までに約3倍に拡大した。
第Ⅱ-1-1-34図 日本のグローバルバリューチェーンへの参加
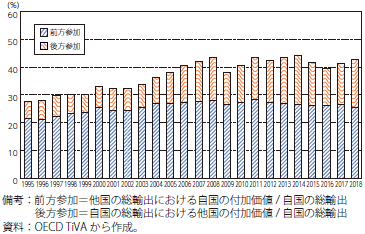
どちらのタイプの参加形態かによって、生じる課題も異なってくる。例えば、前方参加を巡る問題としては、米中貿易摩擦とそれによる生産拠点の見直しのように、後方参加国とその貿易相手国との関係の変化による影響を受けることが挙げられる。一方、後方参加が近年拡大した背景には、中間財が労働集約的又はそれほど高い技術水準を要求されない汎用品である場合など、国内生産を輸入で代替することで日本における生産をより高付加価値な部門に調整することができるというような効率化に向けた企業の動きが指摘できる。しかし、コロナショックのときのように、何らかの理由で供給網が有効に機能しなくなった場合には、前方参加国からの輸入が途絶し、日本における生産活動が停止するなどの供給混乱の背景ともなり得る。近年はむしろ、後方参加がグローバルバリューチェーンの問題として注目を集めるケースが増えている。
② 中国の対米輸出における付加価値
まず、日本が前方参加する場合、例えば、日本が中国に中間財を輸出して、中国が日本の付加価値を含む形で米国に製品を輸出する場合を考える14。これは日本に限らず、アジア・欧米主要国の「世界の工場」である中国を介した前方参加の例といえる。
付加価値貿易の分析で、よく指摘されるのは、中国の対米輸出額が通常の貿易統計で見た場合と付加価値ベースで見た場合で相違することである。既に見たように中国は日本、韓国、台湾、ASEAN等から中間財を輸入しており、その中間財を利用した完成品の輸出には、これら諸国・地域の付加価値成分が含まれることになる。第Ⅱ-1-1-35図は、中国から米国への輸出における付加価値成分を原産国・地域別に推移を示したものである。これを見ると、2018年の総輸入の8割強が中国国内で生産された付加価値で、2割弱が中国以外で生産された付加価値で構成されている。中国以外の付加価値の原産国・地域としては、EU、韓国、ASEAN、米国、日本、台湾が挙げられ、さらに豪州、ロシア、サウジアラビア、ブラジルなどの資源国が続いている(第Ⅱ-1-1-36図)。
第Ⅱ-1-1-35図 中国の対米輸出における主要国・地域の付加価値シェア
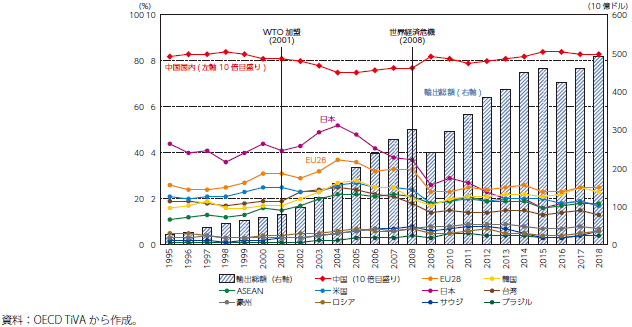
第Ⅱ-1-1-36図 中国の対米輸出における各国・地域の付加価値シェア(2018年)
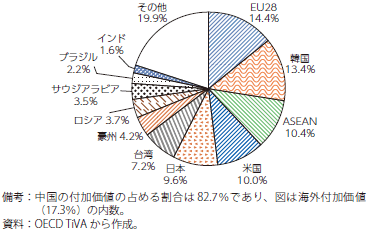
原産国・地域の長期的変化を見ると、日本やEU等の付加価値シェアが2000年代中頃まで拡大したものの、それ以降は縮小に転じている。OECD TiVAが対象としている1995年から2018年までの変化幅を見ると、日本、EUのシェアが低下し、中国国内やアジア域内の韓国、ASEANのシェアが上昇していることが分かる(第Ⅱ-1-1-37図)。サウジアラビアなど資源国のシェアも上昇している。日本のシェアが大きく低下した背景としては、当初、日本から基幹部品などの中間財輸入が拡大したが、日本を始め、部品サプライヤーの現地進出や現地地場企業の技術向上等から、次第に中国の現地調達比率が上昇したことなどが関係していると考えられる15。また、ASEANのシェアが上昇している背景には、国際生産分業においては、新興国でも技術レベルに見合った工程への参加が可能である点が大きい。
第Ⅱ-1-1-37図 中国の対米輸出における付加価値シェアの変化(1995年→2018年)
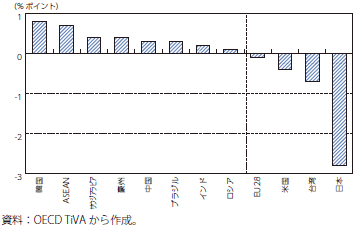
中国の付加価値シェアが総じて上昇しているものの、業種別の特徴も見られる。例えば、労働集約的な繊維業においては中国の付加価値シェアが高く、反対に高度な部品を必要とするコンピューター・電気電子産業においては中国のシェアはより低い。後者については、外国からの中間財を比較的多く受け入れているためと考えられる(第Ⅱ-1-1-38図)。
第Ⅱ-1-1-38図 中国の対米輸出における業種別相違(中国国内の付加価値シェア)

③ 日本の対米輸出における付加価値
ここまで見た中国の輸出は日本の前方参加の例であったが、ここからは、日本の後方参加の例として、日本の対米輸出における付加価値の動きを見てみる。第Ⅱ-1-1-39図は、日本の対米輸出の中に含まれる各国・地域の付加価値を示したもので、日本国内の付加価値のシェアは緩やかに低下していることが分かる。一方、米国及びEUのシェアも上昇しているが、何より中国のシェアが急速に上昇していることが目につく。さらに、ASEANのシェア上昇などアジア域内との結びつきも強まっている。既に見たように、日本のグローバルバリューチェーンへの後方参加が拡大していることが確認できる。そして、このことが、中間財輸入の途絶による日本国内の生産停止という比較的新しい問題に脚光を当てている。
第Ⅱ-1-1-39図 日本の対米輸出における主要国・地域の付加価値シェア
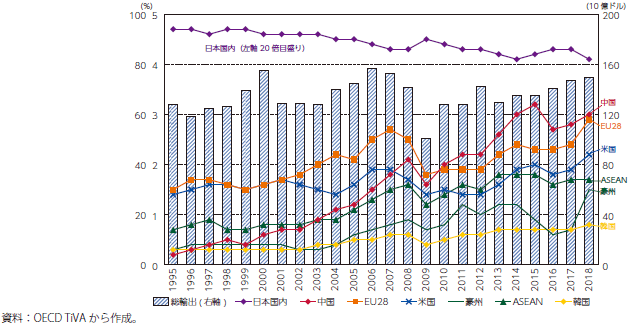
12 ここではOECD TiVA の2021年版のデータを利用して分析する。OECD TiVAは財貿易だけでなくサービス貿易も対象としており、2021年版は1995年から2018年までを対象期間としている。なお、OECE TiVAでは付加価値の原産国とは、生産が行われた国を意味している。このため、例えば、中国に立地する日系企業が生産した付加価値も中国のものとして計上されている点には注意が必要。
13 ここでは説明の分かり易さから「輸出」という表現を使ったが、正確にはOECD TiVAのデータ上、「輸入」における付加価値を表示している。
14 OECD TiVAのデータベース上、正確には米国の中国からの輸入と表記されているデータから作成したが、分かり易さからこのように表現した。通関統計では、輸出はFOBベース、輸入はCIFベースで集計されるため、二国間で輸出入の数値がずれるが、財・サービスを対象とする国際産業連関表から作成されているOECD TiVAでは、一方の輸出は他方の輸入と一致する。
15 その他の要因として、2011年は、東日本大震災によって日本側の輸出に困難があったこと、2012年以降は、日本の尖閣諸島国有化に伴って中国における抗日運動が起こったこと等の影響も考えられる。
(3)モノの貿易に対価されたサービスの間接貿易
ここまで財の輸出を中心に考えてきたが、財の中にはサービス業からの中間投入も活用されていることを見ておく16。第Ⅱ-1-1-40図は日本の製造業者の輸出における付加価値をOECD TiVAを利用して生産業種別に分割したものである。これを見ると、製造業からの付加価値が約2/3を占めるが、農業及び鉱業からは原料となる一次産品として、電気・ガス・水道業からはエネルギーという形で中間投入がされていることが分かる。それに加えて様々なサービス分野で生産された付加価値も含まれている。
第Ⅱ-1-1-40図 日本の製造業者の輸出における付加価値の業種別内訳
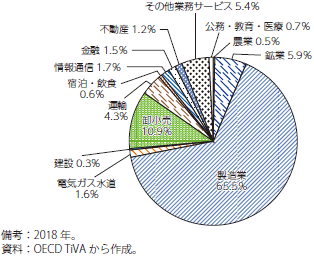
サービスに属する各業種のシェアの変化を長期的に見ると、「卸小売業」や「運輸業」のシェアが大きいものの、近年は縮小傾向にあり、反対に「その他業務サービス」のシェアが拡大してきている(第Ⅱ-1-1-41図)17。既に世界のサービス貿易のところで見たように、研究開発や法務など専門サービスが拡大しているという世界的趨勢とも符合する。日本のモノの輸出に当たっても、研究開発活動やコンサルタント、法務・財務・経理等の貿易に付随する活動が、製品の高度化や競争力向上にますます重要になってきていることをうかがわせる。
第Ⅱ-1-1-41図 日本の製造業者の財輸出におけるサービス分野の付加価値シェアの推移
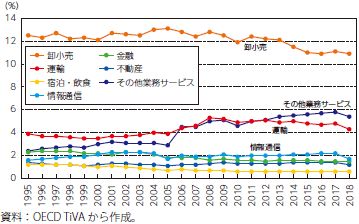
16 ここでは「サービス業」の範囲をOECD TiVAにそろえて、「卸小売」、「運輸」、「宿泊・飲食」、「情報通信」、「金融」、「不動産」、「その他業務サービス」、「公務・教育・医療」として論じる。
17 OECD TiVAの分類では、「専門的・科学的・技術的活動」及び「事務・支援サービス活動」が含まれる。
4.調達先・生産拠点の変化
(1)日系製造業の海外展開とグローバルバリューチェーンの現状
まず、日系製造業の海外展開の現状を確認する。経済産業省「海外事業活動基本調査」によれば、世界で操業中の日系製造業現地法人は、約11,000社(第Ⅱ-1-1-42表)18。そのうち、約8割に当たる約8700社がアジアに展開している。アジアの中では、中国、ASEANの立地が多い。業種別には、輸送機械、一般機械、情報通信機械、電気機械など機械関係、鉄鋼・金属、化学など素材関係が多い。
第Ⅱ-1-1-42表 日系製造業の海外現地法人数(2019年度)
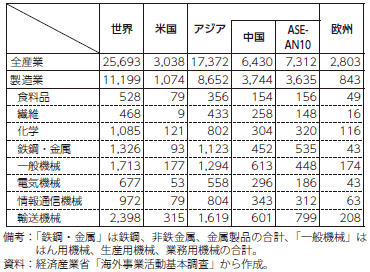
これら日系製造業の生産拠点間の調達の流れを示したのが第Ⅱ-1-1-43図である。これを見ると、アジア域内の日本、中国、ASEAN、NIEs間に相互に調達の流れがあり、特に中国、ASEANには日本やアジアの他の地域からの資材が流入している。既に世界貿易において中国やASEANにアジアから中間財が集まっているのを見たが、日系製造業の調達網においても同様の動きが見える。一方、アジアと北米、欧州のように地域をまたがる調達も存在するが規模は限られている。本節冒頭で見たように、輸送費の関係から近距離の貿易が多く、域内貿易比率が高まる動きと整合的である。
第Ⅱ-1-1-43図 日系製造業の立地・調達(2019年度) 19
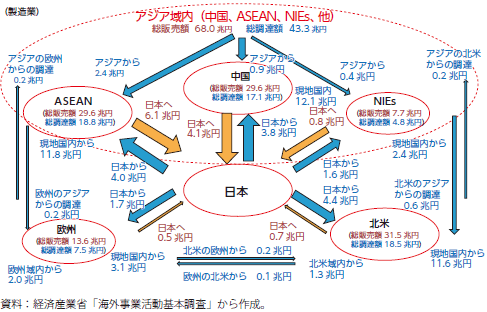
18 経済産業省「海外事業活動基本調査」は、海外に現地法人を有する日本企業(金融・保険業、不動産業を除く)に対する調査。ここで、「海外現地法人」とは、「海外子会社」と「海外孫会社」を総称し、「海外子会社」とは、日本側出資比率が10%以上の外国法人を指し、「海外孫会社」とは、日本側出資比率が50%超の海外子会社が50%超の出資を行っている外国法人を指す。回収率は73.8%(2019年度実績調査)。
19 「海外事業活動基本調査」では、各海外現地法人が採用している会計年度で報告されている。このため現地法人によって、会計年度が12月まで、3月までと異なることがあり得る。
(2)日系製造業の調達活動の特徴、長期的変化
アジアに立地する日系製造業の調達活動について、長期的な変化を見ると、日本から一定の調達額は維持されているものの、現地に進出した日系企業からの調達も含めた現地調達額が次第に拡大してきていることが分かる(第Ⅱ-1-1-44図)。その背景には、最終組立業者だけでなく、部材の供給業者が現地進出するとともに、現地地場企業の指導・開拓が進んだことなどが指摘されている。
第Ⅱ-1-1-44図 アジアに立地する日系製造業現地法人の調達先
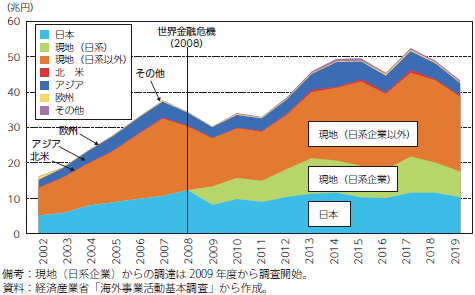
このため、総調達額に占めるシェアは日本からの調達比率が低下して、現地調達率が上昇している(第Ⅱ-1-1-45図)。また、調達においては、業種別の特徴も見られる。情報通信機械は、日本からの調達率が大きい一方で、反対に、輸送機械の代表である自動車産業は、組立工場の周囲に部品サプライヤーを配置する傾向が強く、現地調達率が高い。このような違いが生じる背景の一つには、部材の重量による輸送コストの相違がある。また、自動車のように、すりあわせ型で、何かあれば企業間の連絡調整が必要な製品なのか、情報通信機械のように、モジュール型で、規格化が進んだため、比較的連絡調整の必要のない製品なのかといった製品の特性による影響も指摘されている。その他に、情報通信機械の場合、高度な電子部品など現地では生産できない高付加価値な基幹部品の有無などの要因も考えられる。先の付加価値の分析で、コンピューター・電気電子製品は、中国の国内付加価値が比較的低い業種であることを見たが、その基幹部品は国内生産が難しいことを示唆している。
第Ⅱ-1-1-45図 アジアに立地する日系製造業現地法人の調達先(業種別)
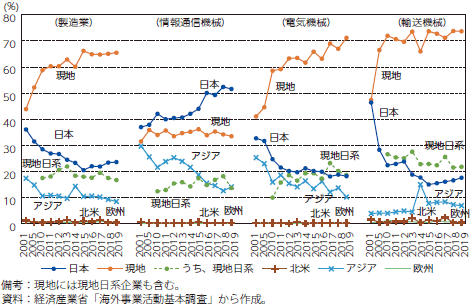
(3)調達等の直近の動向、見直しの方向
① 調達先
直近の調達・立地動向やその見直しの方向性を見ていく。アジア・オセアニアに立地する日系企業に対してJETROが行った調査によれば、調達の約5割を現地、約3割を日本、残りをASEAN、中国、その他で分け合っている(第Ⅱ-1-1-46図)20。立地国・地域別に見れば、中国が最も現地調達比率が高く、タイが次いでいる。これらの国では、日系企業や地場企業など関連企業の産業集積が進んでいることが示唆される。反対に、カンボジア、ラオスは、現地調達率が低く、現地の関連産業が未成熟なことを表している。このため、これらの国では、他のASEAN諸国や国境を接する中国などアジア域内からの調達比率が高い。日本からの調達は、韓国、台湾、フィリピン、シンガポールの順に高くなっている。
第Ⅱ-1-1-46図 アジア・オセアニア主要国の日系企業の原材料・部品の調達先
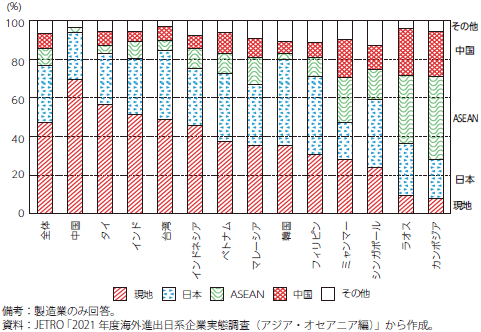
また、同調査では、サプライチェーンに関連して、今後の調達の見直し等についても調査しており、2割強の企業が調達を見直す予定があると回答している(第Ⅱ-1-1-47表)21。見直しの内容については、見直しを行う企業のうち、8割以上が「調達先の見直し」、5割以上が「複数調達化」を挙げており、適切な調達先の模索や調達先の多様化が志向されていることがうかがわれる。その理由としては、既に第Ⅰ部で見たように世界的な供給制約の下で生産コストが上昇していることから、「コスト適正化」が最大の理由として挙げられ、次の理由として「新型コロナ感染の拡大」、さらに「通商環境の変化」が続いている22。
第Ⅱ-1-1-47表 アジア・オセアニアに立地する日系企業の調達の見直し
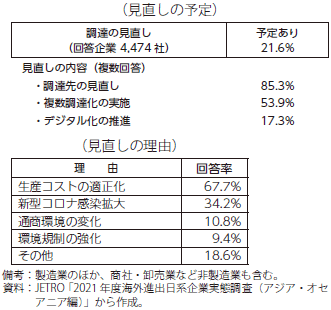
調達先をどこからどこへ変更するのかを見ると、見直し対象として件数ベースで最も多く挙げられたのが日本からの調達で、変更後は現地調達に切り替えるケースが多く、中国、ASEANからの調達となる場合も見受けられる(第Ⅱ-1-1-48表)23。次いで多いのが中国からの調達で、ASEAN、現地、日本からの調達へと変更されている。総じて見れば、日本からの調達は減り、代わりに現地調達やASEANからの調達が増える傾向にある。中国からの調達は増減両方の動きがあって、結果として大きくは変わらない見込みとなっている。
第Ⅱ-1-1-48表 アジア・オセアニアに立地する日系企業の調達先の変更
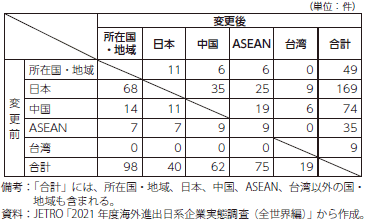
ここまでは現地日系企業にアンケートした結果を紹介したが、JETROが海外ビジネスに関心の高い日本国内の企業(本社)に対して行った調査も同様の傾向が見られた24。本社の立場で対象地域も特定されていないが、調達の見直しを行うと回答した企業は2割強で、2020年度調査に比べて2021年度調査の方が見直しを行う企業割合は増えていることが注目される。そのうち、調達については、「調達先の切り替え」「複数調達化の実施」の回答が増え、適切な調達先の模索や調達先の多様化が志向されていることがうかがえる。
② 生産拠点
JETROのアジア・オセアニアの日系企業に対する調査では、生産拠点の見直しについても調査しており、回答の2割弱が見直しを予定している(第Ⅱ-1-1-49表)。受注増、生産コストの適正化等を背景に、「新規投資・設備投資の増強」、「自動化・省人化の推進」の割合が高いほか、見直しを行う企業の約1/4が「生産地の見直し」を予定している。
第Ⅱ-1-1-49表 アジア・オセアニア日系企業の生産の見直し
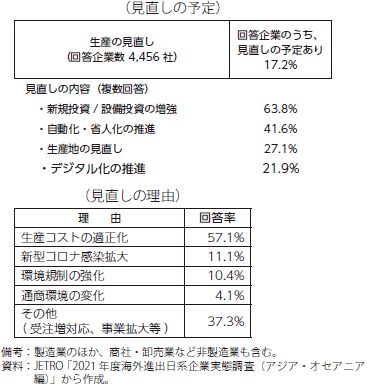
JETROの日本国内の企業(本社)への調査において、海外で事業展開を図る国・地域を調べた結果が第Ⅱ-1-1-50図である25。中国については、賃金の上昇などの課題や米国との貿易摩擦などリスクが指摘されるが、2010年代初頭からは低下したものの、近年は50%弱というほぼ一定の水準を推移している。その他には、米国、ベトナム、タイなどが高水準にある。国際協力銀行による国内企業を対象とした有望投資先の調査でも、中国は長期的に低下してきたものの、近年は一定の水準を維持している。また、米国、ベトナム、タイも有望視されており、インドも高水準にある(第Ⅱ-1-1-51図)。
第Ⅱ-1-1-50図 海外で事業拡大を図る国・地域(対象:全産業)
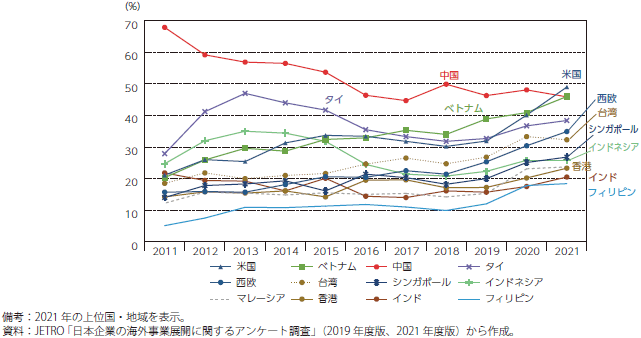
第Ⅱ-1-1-51図 中期的な有望事業展開先国・地域(今後3年程度)
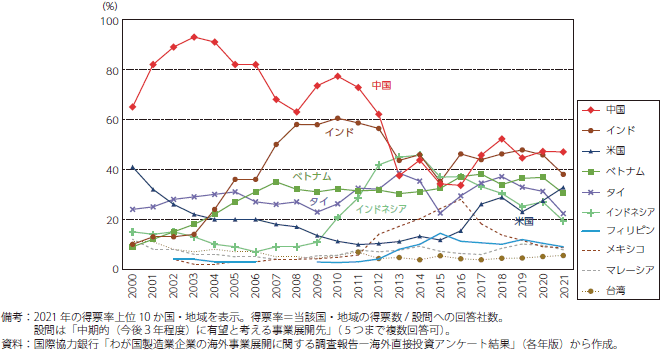
中国について、現地に立地する日系企業に事業展開の方向性を聞いた調査では、過去10年にわたって「現状維持」又は「拡大」との回答が9割以上を占め、「縮小」は1割以下、「第三国への移転・撤退」は非常に限られている(第Ⅱ-1-1-52図)。中国は、通商環境の変化のほか、賃金や生産コストの上昇、競争相手の台頭など課題も多いが、企業から見て有望なマーケットとして魅力が高いことを物語っている。
第Ⅱ-1-1-52図 今後、1~2年の事業展開の方向性(在中国日系企業/全産業)
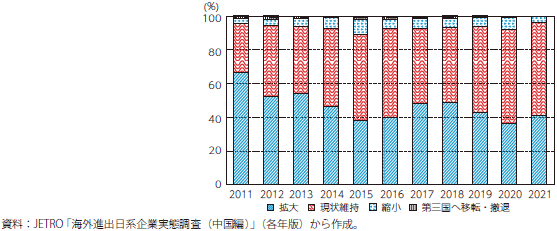
20 JETRO 「2021年度海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」。アジア・オセアニアに進出している現地の日本企業を対象に調査したもの。経済産業省「海外事業活動基本調査」とは回答企業が必ずしも一致しないため、調査結果の数値自体は異なるが、国別内訳があること、最新時点までのデータがあること、今後の方針についても調査している等から、動向を考察するために掲載した。
21 一般に、グローバルバリューチェーンは、企画、研究開発から、製造、販売、メンテナンスに至る広い範囲を指すが、サプライチェーン(供給網)は主に製造過程における原料資材・製品の供給網を指すことが多い。本節では両者の厳密な区別をしていない。ここでは、調査報告書にある「サプライチェーン」の表記にならった。
22 見直しの理由は、その時々の状況に応じて変わってきている。例えば、2020年度も同様の調査項目があったが、調達先の見直しを行う理由として、第一位は「新型コロナウイルス感染拡大」(29.4%)で、「通商環境の変化(追加関税賦課など)」が22.6%で続いていた。2019年度調査では、通商環境の変化が関心を集めており、質問形式が異なるものの、通商環境の変化を受けて1割程度の企業が調達先の変更ありと回答している。企業はその時々の状況に応じた対応をしていることがうかがわれる。
23 JETROによる海外進出日系企業へのアンケート調査の結果は、地域横断的には「海外進出日系企業実態調査(全世界編)」、アジア・オセアニア地域については「海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」、その中でも中国については、「海外進出日系企業実態調査(中国編)」と、複数の報告書に掲載されている。
24 JETRO「日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」。調達の見直し等については2020年度及び2021年度両方の調査において質問されている。
25 年度によって細かな集計内容には相違がある。2011年度、2012年度は「新規投資または海外の既存事業の拡充」、2013年度~2015年度は「現在、海外に拠点があり、今後さらに拡大を図る」、2016年度以降は「現在、海外に拠点があり、今後さらに拡大を図る」又は「現在、海外に拠点はないが、今後新たに進出したい」を選択した回答を集計している。
(4)研究開発
ここまで調達や生産に焦点を当ててきたが、現地生産の高度化に伴って、企業の研究開発も現地で行う部分が拡大してきている点も確認する。経済産業省「経済産業省企業活動基本調査」及び「海外事業活動基本調査」の集計を利用して、日本国内の製造業の設備投資と日系製造業海外現地法人の研究開発費の推移を比べてみる26。日本国内の製造業企業の研究開発費が緩やかな伸びに留まっているのに対して、海外製造業現地法人の研究開発費は2005年と比べて、金額ベースで倍近くに拡大している(第Ⅱ-1-1-53図)。また、売上高に対する研究開発費比率を見ると、米国に立地する企業の研究開発費比率が上昇しているほか、中国に立地する企業はまだ水準は低いものの、次第に上昇してきている。
第Ⅱ-1-1-53図 製造業企業の研究開発費の推移
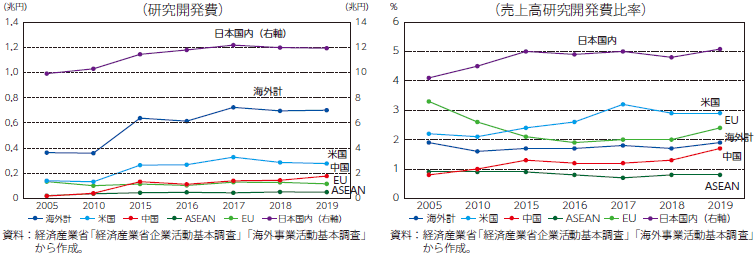
26 「経済産業省企業活動基本調査」の対象は、従業者50人以上かつ資本金3000万円以上の企業。必ずしも全ての製造業企業を対象としているわけではないが、時系列での傾向を観察することはできる。
5.グローバルバリューチェーンのぜい弱性
(1)間接貿易
ここまで国際的な国・地域間のバリューチェーンを考えてきたが、国内においてもバリューチェーンは広がっている。例えば、自らは直接輸出に携わっていない企業でも、他の製造業者に資材を提供し、その製品が輸出されることで間接的に輸出に携わっている場合がある。輸入においても、自らは直接資材を輸入していなくとも、輸入資材を組み込んだ中間製品を他の製造業者から調達して自らの製品に組み込む場合も、国際的なバリューチェーンの一端に参加していることになる。また、単純に貿易手続きや海外の取引相手の情報に知見がなく、自らは輸出入を行っていないが、商社などの国内の卸売業者との取引を通じて海外とつながっているというケースもあり得る。
これらの企業もグローバルバリューチェーンにつながっているが、その広がりを正確に把握することは難しい。ここでは一つの目安として、石川・齊藤・田岡(2017)をもとに間接貿易を行っている製造業企業のシェアを概観する27。同ペーパーでは、東京商工リサーチの企業取引データを利用して、直接輸出入を行っている製造業者又は卸売業者と取引がある製造業者は、間接に輸出入を行っているものと見なして分析をしている28。第Ⅱ-1-1-54図は集計結果で、間接貿易を行っている製造業企業がかなりの広がりを見せていることが分かる。例えば、間接貿易を行っている製造業企業は、全国で、企業数ベース、従業員ベースで約4割、売上高ベースで約3割、付加価値ベースで約5割にのぼる。大都市圏と地方に分けて比較すると、直接貿易を行っている企業のシェアは大都市圏の方が大きい一方で、間接貿易に携わっている企業のシェアは、従業員、売上げ、付加価値のいずれの面で見ても地方の方が大きい29。一見、貿易に関係がないように見える企業も間接的にグローバルバリューチェーンにつながっており、特にその傾向は地方の方が強い。このことは地方の企業もグローバルバリューチェーンによる影響を受けることを示唆している。
第Ⅱ-1-1-54図 直接・間接貿易を行っている企業のシェア
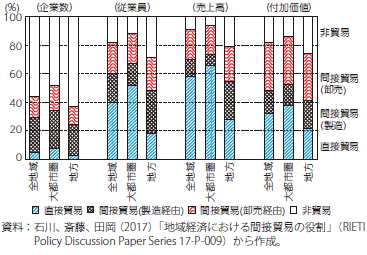
また、同様に東京商工リサーチの企業取引関係データを利用して分析を行ったIto and Saito (2018) は、輸出・輸入とも、直接貿易・間接貿易の両方の場合で、売上高や従業員数に有意に正の影響があることを実証して、貿易の重要性を示した30。
このように見てくると、貿易は地方の中小企業のビジネスの国際化にとっても重要であり、世界市場に対して直接製品・サービスを提供する「グローカル成長戦略31」の実現に加えて、ローカルな企業が直接輸出企業を通じてグローバルなバリューチェーンにつながることで一層の成長を実現するグローカル成長の視点を併せて考えることも重要である。
27 石川、齊藤、田岡(2017)「地域経済における間接貿易の役割」(RIETI Policy Discussion Paper Series 17-P-009)。
28 データの制約からこのように定義しているが、実際には、その製造業者の資材が組み込まれた製品が必ずしも輸出されているとは限らず、また、取引相手が輸入した資材が必ずしもその製造業者の生産活動に利用されているとも限らない点には注意が必要。
29 大都市圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県。その他の都道府県を地方と区分した。
30 Ito and Saito (2018), “Indirect Trade and Direct Trade: Evidence from Japanese firm transaction data”, RIETI Discussion Paper Series 18-E-065.
31 経済産業省 (2019)「グローカル成長戦略」
(2)グローバルバリューチェーンのぜい弱性と強靱性
コロナショックの際の日本の国際生産ネットワークへの影響をAndo, Kimura and Obashi (2021)をもとに考察する32。同ペーパーは、コロナショックが一時的に日本の貿易の減少をもたらしたものの、機械産業を中心とする国際生産ネットワークは、それを乗り越えて維持されたとしている。
まず、2020年の日本の機械分野の輸出の月次の動きを見ると、中国における新型コロナウイルスの感染拡大によるサプライチェーンを通じた直接及び間接の影響により、3月以降は例年に比べて大きく落ち込んでいる。しかし、5月に底を迎え、10月頃にはほぼ例年の水準まで回復している(第Ⅱ-1-1-55図)33。輸入も、輸送機械を中心に同様の傾向が見られる。
第Ⅱ-1-1-55図 日本の2020年の機械貿易の推移
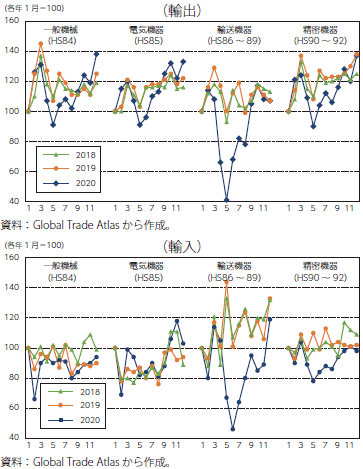
その上で、この1-5月の落ち込みを、日本の二国間貿易を最小単位まで降りて、ある国・製品の取引が続いている「Continuing」、取引がなくなった「Exit」、取引が新たにできた「Entry」に分解して分析している34。その結果、輸出入とも「部品」は、「製品」に比べて「Exit」の取引関係が少なく、部品と生産の間にはより安定的な関係がある、言い換えれば、部品のサプライチェーンには強靱性があることを指摘している(第Ⅱ-1-1-56図)。少なくとも一時的な需要の落ち込みは、サプライチェーンを破壊するものではなかった。同著者は、別のペーパーにおいて、同様の手法から、世界金融危機や東日本大震災の際にも、日本の部品のサプライチェーンが強靱であったことを指摘している35。企業は、コストを投じてサプライチェーンを調整してきており、そのように深化したサプライチェーンは、容易に消滅するものではないことが示唆される。
第Ⅱ-1-1-56図 日本の初期の貿易の落ち込み(1-5月の前年同期比)の分解
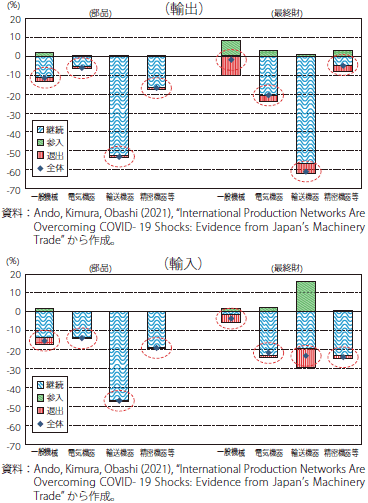
また、同ペーパーは、新型コロナによる日本の貿易の変動を価格と数量の変化に分解して、初期の供給が減少する負のサプライショックの他、その後に需要を増加させる正のデマンドショック及び需要を減少させる負のデマンドショックが異なるタイミングで異なる国に起こったことも指摘している(第Ⅱ-1-1-57表)。
第Ⅱ-1-1-57表 日本の貿易に対するコロナの際のショックの内容
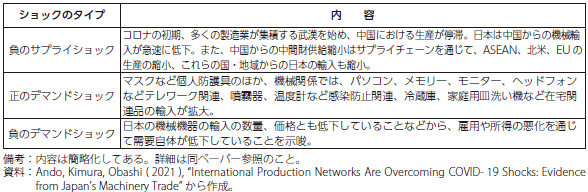
このようなサプライチェーンの強靱性の裏には、サプライチェーンを維持しようとする企業による取組が重要であることには注意しなければならない。先の日系企業に対するJETRO調査で見たように、企業は、サプライチェーンの供給元や生産地など、時々の状況に応じて調整をしようとしている。
ここではさらに、サプライチェーンの重要性について、企業相互の幅広い結びつきという面から考えてみたい。戸堂、中島、Matous(2013)は、東日本大震災の被災地企業へのアンケート調査等から、サプライチェーンが企業の経済的強靱性にどのような影響を与えるかを考察している36。2011年3月に起こった東日本大震災の影響は、被災地だけでなく、サプライチェーンを通じて、日本全国や海外へも波及した。同ペーパーは、サプライチェーンは負の効果をもたらすだけでなく、災害からの復旧を促進する効果もあり、むしろ総合的にはプラスの効果の方が大きいと指摘している。
東京商工リサーチによる個別企業ごとの企業取引先データとアンケート調査の結果を結びつけて、「被災地内・外」の「仕入先、販売先の企業数」が、「操業停止日数」、「取引先企業からの支援の有無」等にどう影響するかを分析している。第Ⅱ-1-1-58表がその分析結果で、例えば、「被災地外の仕入先」及び「被災地外の販売先」の企業数は、「操業停止日数」に有意に負の効果を持つ。言い換えれば、被災地域外に取引先が多くなればなるほど、企業の操業の再開は早まる。その他に、被災地域外に販売先企業が多いと、復旧に対する支援を受ける可能性が高まることなどが示されている。
第Ⅱ-1-1-58表 取引先企業数が倍増した場合の復旧に及ぼす影響
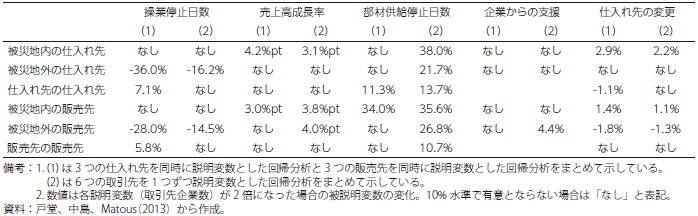
このようにサプライチェーンは、災害の影響を伝播させるというマイナス面がある一方で、被災地外の取引先が多いほど操業再開が早まったり、取引先から被災企業が支援を受けたり、代替企業を探すのに企業ネットワークが有効であるなどプラスの面も指摘できる。分析では、被災地と被災地外を分けているが、当然のことながら事前にどこで災害が起こるかは分からない。普段から幅広い企業間のネットワーク、企業リンケージを構築し、サプライチェーンの多様性を高めておくことが企業及びサプライチェーンの強靱性を高めることにつながる。
32 Ando, Kimura and Obashi (2021), "International Production Networks Are Overcoming COVID-19 Shocks: Evidence from Japan's Machinery Trade"。
33 同ペーパーでは、中間財と最終財を分けて表示しているが、ここでは合計で表示した。
34 日本の輸出及び輸入について、HS9桁品目別・貿易相手国別に、ある財のある国に対する貿易がt期とt-1期の両方で行われていれば「Continuing」、t期のみに行われていれば「Entry」、t-1期のみに行われていれば「Exit」と区分する。
35 Ando and Kimura (2012), “How did the Japanese Exports Respond to Two Crises in the International Production Network?: The Global Financial Crisis and the East Japan Earthquake”。
36 戸堂康之、中島賢太郎、Petr Matous(2013)「絆が災害に対して強靱な企業をつくる-東日本大震災からの教訓」(RIETI Policy Discussion Paper Series 13-P-006)。なお、ここではサプライチェーンは日本国内の企業同士の取引関係で、必ずしも海外とつながっている必要はない。
(3)半導体、自動車部品のぜい弱性
2021年、日本が後方参加するサプライチェーンにおいて、特に問題となったのが半導体と自動車部品であった。両部品に共通することは、長期的に見ると日本国内でも製造・輸出していたが、近年は輸入が拡大して海外シェアが高まっていることである。
2021年の輸入状況を考察する。まず、半導体については、新型コロナ後、テレワークを始めとするIT機器の需要急拡大や政府の景気支援策を受けた自動車等への需要回復などを背景に、世界中で半導体需要の急速な増大が見られた。その一方で、半導体の生産設備の拡大には多大な費用と時間がかかるため、半導体製造企業に供給能力以上に受注が殺到した。さらに日本では大手半導体企業の主力工場の火災事故、北米では寒波、東南アジアでは感染拡大による稼働制限など供給制約が相次ぎ、受給逼迫に拍車をかけた。
日本の半導体の輸入相手国・地域を見ると、ダイオードなど単機能の部品(HS8541)は中国が5割を占め、マレーシア、台湾などアジア諸国が続いている(第Ⅱ-1-1-59図)。近年、需要が拡大基調にある高機能の集積回路(HS8542)の場合は、台湾が輸入の5割以上を占め、長期的に見ても、台湾のシェアは拡大を続けている(第Ⅱ-1-1-60図)。
第Ⅱ-1-1-59図 日本の半導体の輸入相手国・地域(2021年)
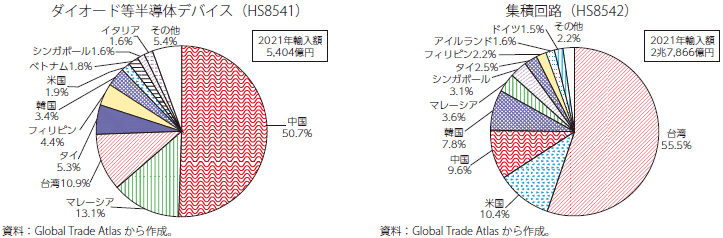
第Ⅱ-1-1-60図 日本の半導体の輸入相手国・地域の推移
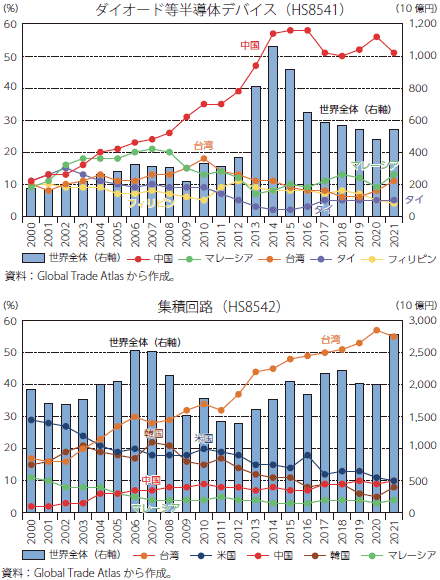
また、自動車に用いられる部品には、先に挙げた半導体を含めて多様な品目があるが、ここでは、関税番号HS8708の自動車部品を例に考えてみる37。日本の輸入の約4割は中国が占めており、そのシェアは、一時頭打ちとなったものの、ここ2~3年は、再び上昇する兆しが見える(第Ⅱ-1-1-61図、第Ⅱ-1-1-62図)。
第Ⅱ-1-1-61図 日本の自動車部品の輸入相手国・地域(2021年)
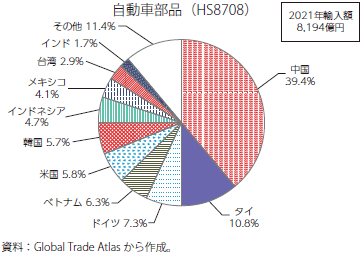
第Ⅱ-1-1-62図 日本の自動車部品の輸入相手国・地域の推移
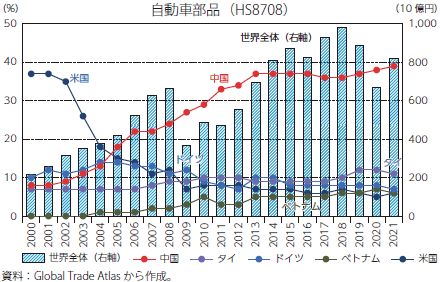
これまで本節で見てきた内容をまとめてみよう。我が国企業は、アジアを中心とする直接投資によって、生産拠点の海外展開や国際的な生産分業、そして、これら拠点を結ぶグローバルバリューチェーンを形成した。日本は、グローバルバリューチェーンに対して、中間財を供給する前方参加とともに、海外から中間財を受け取る後方参加の形の関与を拡大してきた。しかし、近年、前方参加と後方参加の両面にわたって、グローバルバリューチェーンに関する課題が顕在化している。例えば、米中対立や新型コロナなど感染症や自然災害等による供給制約等である。これに対して、企業サイドでは、米中対立を見据えた生産拠点及び供給元の見直しや、中間財供給元が一部の国のシェアが大きいことから、供給元の多様化や現地化の動きが見られる。そのような取組を上手く進めるためには、デジタルを活用したネットワークの可視化も重要であろう。政府としては、このような企業によるネットワーク形成及び再構築の選択肢を増やすことができるよう、事業環境を整えることが重要な役目といえる。そのために、経済連携協定等を通じた国際ルールの明確化及び強化やサプライチェーン多元化のための補助などの施策を行っている。本章第2節以降では、サプライチェーンの強靱化に向けた課題や取組、特に経済安全保障との関わりについてより具体的に分析する。
37 この項目には、バンパー(HS870810)、シートベルト(HS870820)、ブレーキ(HS870830)、ギアボックス(HS870840)、駆動軸・非駆動軸(HS870850)、車輪(870870)、懸架装置(870880)、ラジエーター(HS870891)、消音装置(HS870892)、クラッチ(HS870893)、ハンドル(HS870894)、安全エアバッグ(HS870895)等が含まれる。