第2節 経済安全保障とサプライチェーンの強靱化
米中対立の激化やロシアによるウクライナ侵略といった地政学的リスクや新型コロナウイルス感染症のような健康リスクの高まりにより、世界の不確実性が増大する中、経済安全保障推進の重要性が高まっている。安全保障の対象範囲が経済・技術分野に急速に拡大し、国家間の競争が激化する中で、企業にとって、地政学リスクや政府の経済安全保障政策の動向を踏まえて、突然の状況変化やルール変更に迅速かつ柔軟に対応できるように、サプライチェーンのレジリエンスを検討することが重要となっている。ロシアによるウクライナ侵略によるサプライチェーンへの影響は、第Ⅰ部第1章第1節で見たところ、ここでは、米中対立による影響を含めて、それ以外の動きを検討する。
1.中国の台頭と主要国・地域との経済的結びつき
中国は、改革開放以来、40年以上にわたって高い経済成長率を維持し、経済面で大国へ躍進したほか、科学技術分野でも世界を牽引する存在となるなど、中国の台頭が顕著となってきている。もっとも、急速に発展した中国のテクノロジーが、軍民融合発展戦略の下で効率的かつ非対称的に軍事能力を高めていることとあいまって、技術覇権を巡る米中対立へとつながり、米国バイデン政権においても引き続き政治的な緊張感が増している状況にある。
ここでは、中国の経済・科学技術に関する各種指標や投資動向から、米中対立の経済面での背景を概観する。
(1)中国の経済成長と科学技術分野の発展
日本、米国及び中国の名目GDPの推移を見ると、中国は2010年に日本を抜いて世界第2位の経済大国へと成長し、さらに首位を堅持する米国に迫る勢いにある。日本経済研究センターの試算38によると、中国の名目GDPは、2033年に米国の水準を上回る39と予測されている(第Ⅱ-1-2-1図)。
第Ⅱ-1-2-1図 日米中の名目GDPの推移
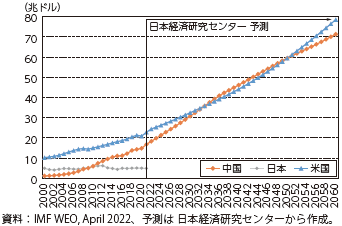
中国は、科学技術分野においても国際的な存在感が増している。イノベーション創出の源泉となる研究開発費総額の推移を見ると、日本の研究開発費はこの20年間、ほぼ同水準で推移している一方、米国、中国はともに年率3.1%、年率14.2%と大きく増加しており、中国は米国に迫る勢いとなっている(第Ⅱ-1-2-2図)。研究開発費を対名目GDP比で見ると、2%後半から3%前半の間の水準で推移している日本や米国と比べ、中国の水準は依然低いものの、年率5.1%で上昇している。中国の研究開発費のうち、産業別では、コンピュータ・通信・その他電子機器製造業、電気機械・装置製造業、自動車製造業に対する研究開発費が多くなっている40。
第Ⅱ-1-2-2図 日米中の研究開発費の推移
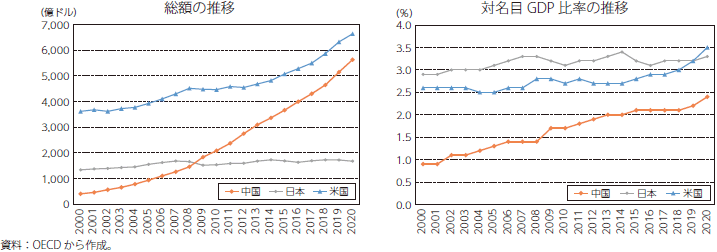
技術力の指標となる国際特許出願件数について、世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization、以下WIPO)の統計を見ると、日本や米国はそれぞれ年率8.2%、2.7%で増加しているものの、中国は、日米を大きく上回る年率23.8%増加し、2019年には出願件数で世界トップとなった(第Ⅱ-1-2-3図)。中国の国際特許出願件数を科学技術の分野別で見ると、コンピュータ技術の出願件数が2000年からの21年間で約650倍の1万件超(全出願件数の16%)に急増しているほか、デジタル通信、音響・映像技術など各分野の大幅な増加が見られる(第Ⅱ-1-2-4図)。
第Ⅱ-1-2-3図 日米中の国際特許出願件数の推移
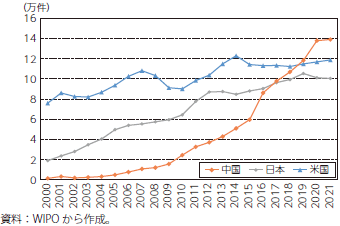
第Ⅱ-1-2-4図 中国の科学技術分野別の国際特許出願件数の推移と全体に占める割合
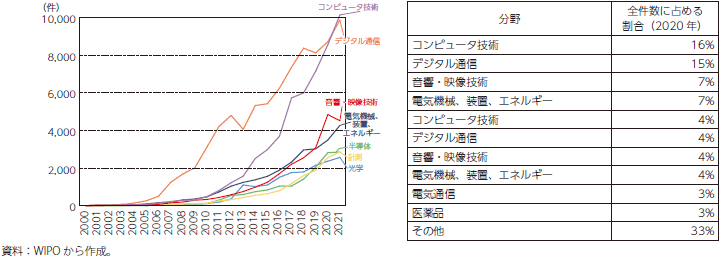
経済協力開発機構(OECD)の統計によると、情報通信技術(Information and Communication Technology、以下ICT)と人口知能(Artificial Intelligence、以下AI)関連技術においても中国の出願件数は増加しており、ICTにおいては2017年に中国は米国を追い抜いたほか、AI関連技術においても、中国は大幅に増加し、日本・米国の水準に迫る勢いにあるなど、中国がイノベーションのための研究に積極的に取り組んでいる様子が見てとれる(第Ⅱ-1-2-5図)。
第Ⅱ-1-2-5図 日米中の特許出願件数の推移(ICTとAI関連技術)
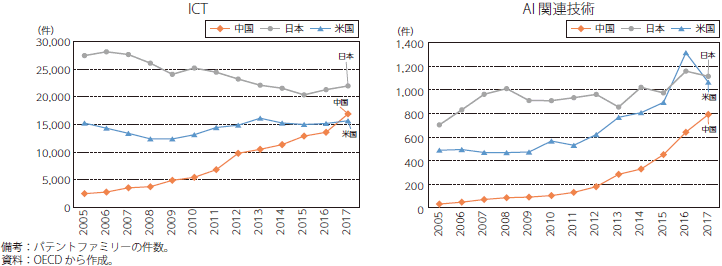
また、科学研究活動の成果である論文について、「量」を示す総論文数(整数カウント法)41を見ても、中国は他の主要国に比べて急激に増加しており、2006年に日本とフランスを抜いて第4位、2006年に英国とドイツを抜いて第2位となり、2018年には米国を抜いて世界第1位となっている。さらに、論文の「質」を示すトップ10%・トップ1%の補正論文数42でも、中国は急増しており、トップ10%補正論文では、2006年に日本を抜き、2019年に米国を抜き世界第1位に、トップ1%補正論文では、2006年に日本を抜き、2013年に英国を抜いて世界第2位となるなど、量、質ともに中国の科学研究活動での成果が著しい(第Ⅱ-1-2-6図)。
第Ⅱ-1-2-6図 主要国の論文数の推移(整数カウント法)
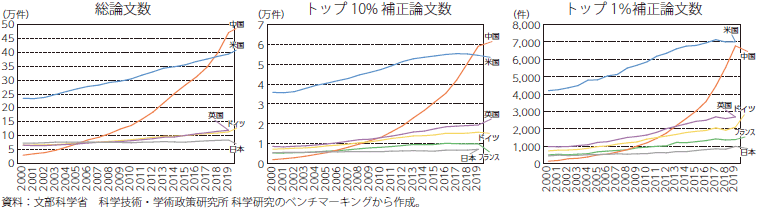
38 公益社団法人日本経済研究センター(2021)「2033 年、中国が世界最大の経済大国に」、2021年12月
39 その後、中国は人口減少が成長を下押し、米国は人口や生産性を維持することから2050年には米国は中国を再び上回ると予測している。
40 中国国家統計局(2021)「2020年全国科経費投入統計公報」、2021年9月
41 文部科学省(2021)「科学技術・学術政策研究所、科学研究のベンチマーキング2021」
42 トップ10%・トップ1%補正論文数は、他の論文に引用される回数が多く、質で評価されていることを示す指標であり、被引用数が各分野で上位10%・1%に入る論文を抽出後、実数で論文数が全体の10%、1%になるように調整した論文数。
(2)中国の対外直接投資の動向
ここでは、中国の対外直接投資動向から、中国と世界の経済的な結びつきを見ていく。2000年以前の中国は、対内直接投資を受け入れ、海外資本を取り込むことで経済成長につなげる投資受入国であったが、2000年以降は、海外資源の獲得、産業競争力強化などのため、積極的に対外直接投資を進めている。
世界各国の対外直接投資額の推移(第Ⅱ-1-2-7図)をストックで見ると、中国は2010年代から他国を上回る勢いで急増し、2020年にはオランダに次ぐ第3位となった。2015年には中国人民元が切り下げられ、通貨安や外貨準備高の減少により中国政府が対外直接投資を制限したことから、フローでは、2016年をピークに中国の対外直接投資は減少傾向にある。2020年に新型コロナウイルスの感染拡大により、世界経済が大きな打撃を受けて落ち込む中、中国経済がいち早く回復したこともあり、2020年の中国の対外直接投資額は前年とほぼ同水準に維持された(第Ⅱ-1-2-8図)。これにより、1990年代中盤以降引揚げ超過時を除き首位を保っていた米国を抜いて、中国は世界第1位となった43。
第Ⅱ-1-2-7図 世界各国の対外直接投資額の推移
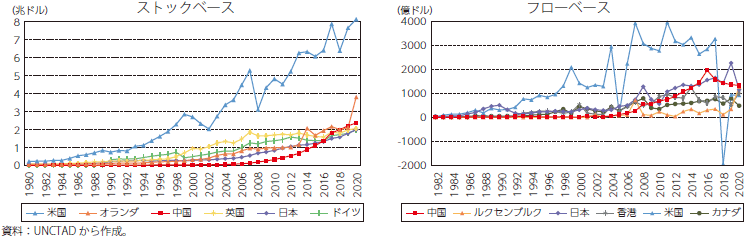
第Ⅱ-1-2-8図 中国の対外直接投資額の推移(対世界)
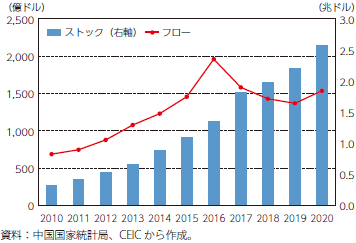
投資相手先を見ると、香港やケイマン諸島、バージン諸島といった税負担の軽い地域が上位を占めており、これらの地域から他国に再投資していると見られる(第Ⅱ-1-2-9図)。
第Ⅱ-1-2-9表 中国の対外直接投資(相手国・地域別)
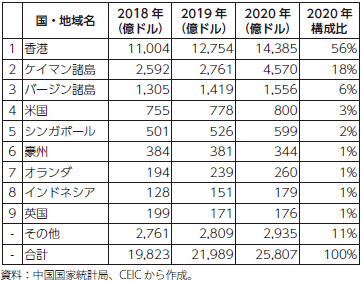
続いて、米国、欧州、アジア、日本に対する中国の対外直接投資動向を見ていく。中国による米国向けの対外直接投資額は、2020年にストックベースで800億ドルとなっており(第Ⅱ-1-2-10図)、2010年からの10年間で約15倍に増加している。2018年には、米国が対内直接投資を審査する対米外国投資委員会(The Committee on Foreign Investment in the United States、CFIUS)の審査権限を強化したことなども影響して、中国の対米直接投資額は、2019年のフローで前年比-49%と一時的に減少したものの、2020年はコロナ禍にも関わらず同+58%と、一転増加に転じている。ストックの増加幅は、2019年から縮小しているものの、引き続き増加基調にある。
第Ⅱ-1-2-10図 中国の対外直接投資額の推移(対米国)
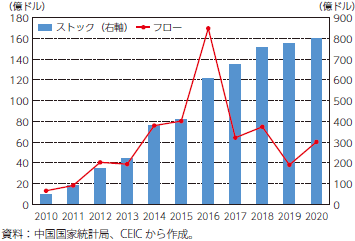
中国による米国向けの対外直接投資を業種別で見ると、不動産やリース・商業サービス等で減少したものの、情報通信・ソフトウェア・情報技術サービス業等は堅調に増加を続けており、直接投資の観点からは、米中対立による影響は限定的であったと見られる。(第Ⅱ-1-2-11図)。
第Ⅱ-1-2-11図 中国の対外直接投資額の業種別の推移と内訳(対米国)
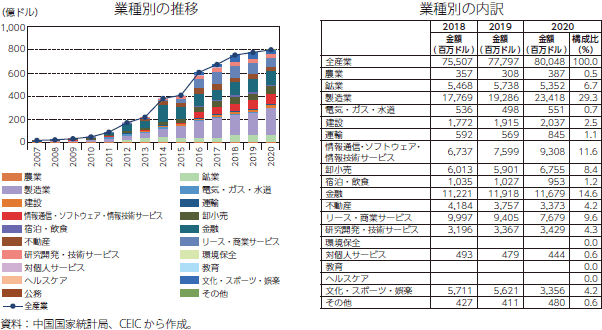
中国による欧州向けの対外直接投資額は、2020年にストックで1,224億ドルとなっており、2010年から10年間で約8倍に増加している。足下では依然、増加傾向にあるものの、EUや加盟国における対内直接投資審査制度の整備や強化の動き等を背景に、2018年頃から増加の勢いが弱まっている(第Ⅱ-1-2-12図)。
第Ⅱ-1-2-12図 中国の対外直接投資額の推移(対欧州)
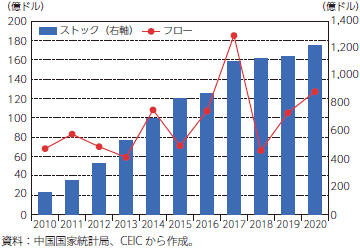
中国によるEU向けの対外直接投資を業種別で見ると、2020年は金融業、リース・商業サービス製造業、製造業で大きく減少したものの、情報通信分野では増加基調となっている。(第Ⅱ-1-2-13図)。
第Ⅱ-1-2-13図 中国の対外直接投資額の業種別の推移と内訳(対EU)
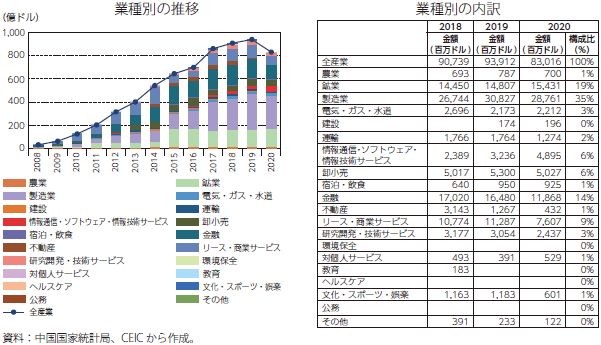
中国によるアジア向けの対外直接投資額は、2020年にストックで1.6兆ドルと、中国の一帯一路構想の推進などを背景に安定して増加しており、2010年からの10年間で約6倍となった。(第Ⅱ-1-2-14図)。
第Ⅱ-1-2-14図 中国の対外直接投資額の推移(対アジア)
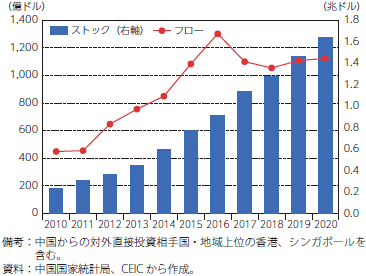
投資相手国・地域を見る(第Ⅱ-1-2-15図)と、前述したとおり、香港向けが約半分を占め、シンガポールも上位であるが、その他のアジアの国ではインドネシア、マカオ、マレーシア、ラオス等の増加が大きい。
第Ⅱ-1-2-15図 中国の対外直接投資残高の推移(対アジア主要国・地域)
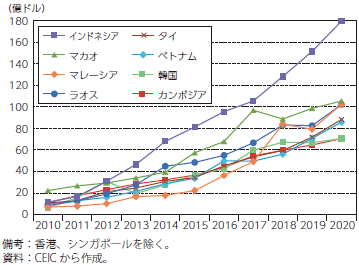
なお、中国による日本向けの対外直接投資額は、2020年にストックで42億ドルとなり、2010年からの10年間で約4倍程度増加しているものの、米国や欧州など、他の国・地域に比べると小幅な増加にとどまっている(第Ⅱ-1-2-16図)。
第Ⅱ-1-2-16図 中国の対外直接投資額の推移(対日本)
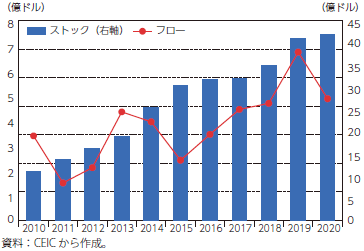
43 UNCTAD(2021)、真家陽一(2021)
(3)米国の対中国直接投資の動向
一方、米国の対外直接投資動向を見ると、対世界直接投資残高は2018年及び2019年は大幅な引揚げ超により一時的に減少した44ものの、増加基調にある。米国の2020年の対外直接投資残高6.2兆ドルのうち、地域別の構成は、対欧州が3.6兆ドル(全体の59%)、対アジアが9,696億ドル(全体の16%)となっているのに対して、対中国は1,239億ドル(全体の2%)とその割合は小さい(第Ⅱ-1-2-17図)。
第Ⅱ-1-2-17図 米国の対外直接投資(対世界)
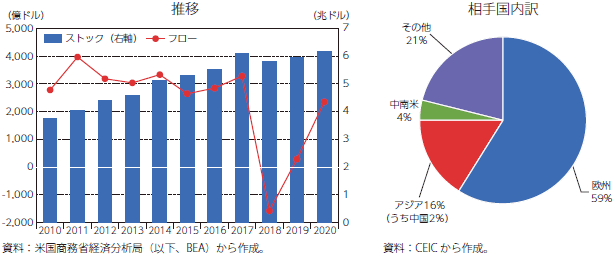
米国による中国向けの対外直接投資額の推移を見ると、2011年及び2012年は引揚げ超となったものの、2013年以降増加を続けており、世界全体に対する対外直接投資額が激減した2018年及び2019年においても中国向けは増加している(第Ⅱ-1-2-18図)。
第Ⅱ-1-2-18図 米国の対外直接投資(対中国)
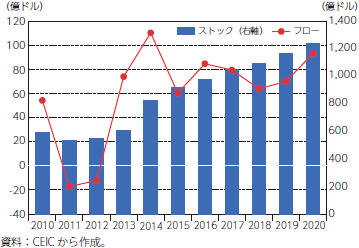
米国による中国向けの対外直接投資残高を業種別で推移を見ると、情報分野が2019年、2020年と僅かに減少傾向にあり、コンピュータ・電子部品分野や輸送機器分野では2019年に小幅減少したものの2020年には増加に転じている。一方、卸売業、化学分野等では堅調に増加しており、対外直接投資の面からは米中対立による影響は確認できない。
第Ⅱ-1-2-19図 米国の中国に対する対外直接投資の推移(業種別)
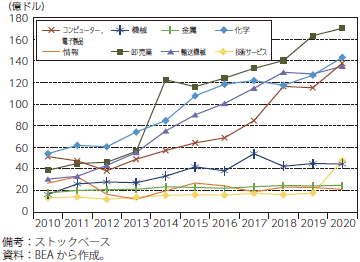
44 米国への投資を促す目的で、米国企業が海外で得た利益を米国へ還流させる際の税負担を軽減させる税制改革が2018年に行われたことが背景。
(4)主要国・地域の対中貿易と対中依存の動向
中国は、部品・汎用品の製造や組立工程において、低いコストで労働集約的作業を行うことができる生産拠点として集中度が高まり、世界の工場としての役割を果たしてきた。もっとも、生産拠点が集中していると、災害や緊急事態が発生した場合に、サプライチェーンが途絶し、生産工程全体へと影響が拡大する懸念がある。ここからは、米国、欧州及び日本がサプライチェーンにおける中国への依存度を高めていく過程を貿易額の推移から見ていく。
米国の対中貿易については、1979年に米国と中国との国交が樹立して以降、両国間の貿易額は年々増加し、2009年には米国にとって中国が最大の輸入相手国となり、2021年の輸入総額に占める中国のシェアは18%となった(第Ⅱ-1-2-20図)。輸出では、カナダ(輸出総額の18%)、メキシコ(輸出総額の16%)に次ぐ輸出相手国であるものの、対中輸入額が対中輸出額を大きく上回っており、米国の対中貿易赤字額は高い水準で推移している。その背景として、中国企業の海外進出や鉄鋼等の過剰生産問題等により中国の対米輸出が増加した一方、閉鎖的な中国市場や商習慣、知的財産権の侵害、技術移転の強要等により米国の対中輸出が停滞したと米国側から指摘されている45。トランプ前大統領の対中強行姿勢により、2018年以降米中対立が本格化し、2021年に就任したバイデン大統領も、中国との経済・科学技術における対立基調を維持しているものの、2021年は財を中心とする米国の個人消費の回復により電子機器やプラスチック製品の輸入が増加するとともに、天然ガスの輸出が増加したことを背景に米国の対中輸出入額は過去最大となった。
第Ⅱ-1-2-20図 米国の貿易相手国の割合と貿易総額の推移
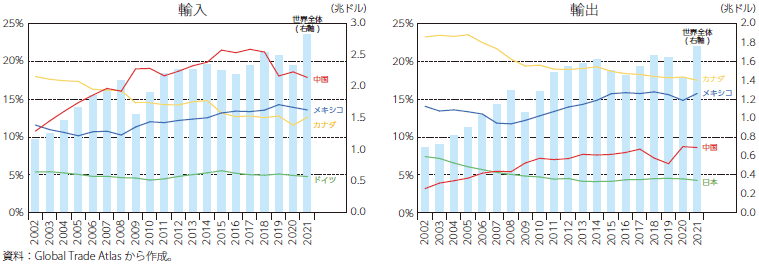
EUの対中貿易も増加基調にある。中国は2005年に米国を抜いて最大の輸入相手国となった(第Ⅱ-1-2-21図)。2021年のEUの輸入総額のうち中国の占める割合は22%となっており、2002年から19年間で対中輸入額は7.4倍に増加した。輸出については、輸入より規模は小さいものの、中国は2010年にスイスを抜いて、米国(輸出総額の17%)に次ぐEUの輸出相手国となっている。2021年のEUの輸出総額のうち中国の占める割合は10%で、2002年から19年間で対中輸出額は8.5倍に増加した。
第Ⅱ-1-2-21図 EUの貿易相手国の割合と貿易総額の推移
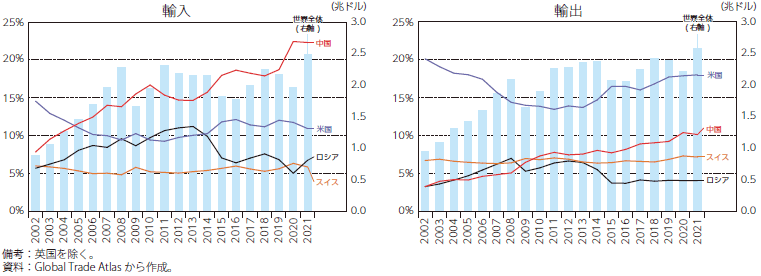
EUの輸出入ともに中国のシェアが高まっているものの、EUでは価値観を共有しない中国による経済面での影響力の高まりに対して警戒感が増大している。
日本の対中貿易も増加基調となっている。中国は日本にとって最大の輸入相手国の地位を維持しており、2021年の日本の輸入総額のうち中国の占める割合は24%となっている(第Ⅱ-1-2-22図)。2002年からの19年間で、対中輸入額は3.0倍に増加している。輸出については、米国の割合が低下した一方、中国の割合が上昇したことから、中国が2009年に米国を抜いて首位となった。その後、中国と米国で首位と第2位の逆転を繰り返し、2020年と2021年は、中国が首位となっている。2021年の日本の輸出総額のうち中国の占める割合は22%で、2002年から19年間で対中輸出額は4.1倍に増加している。
第Ⅱ-1-2-22図 日本の貿易相手国の割合と貿易総額の推移
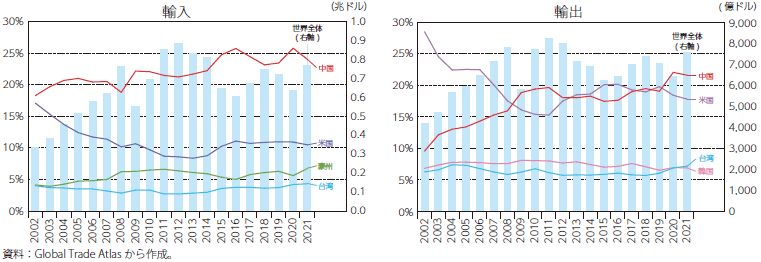
次に、サプライチェーンにおける中国に対する依存度を測る観点から、日本、米国、EUの部品輸入額において中国が占める割合の推移を見ると(第Ⅱ-1-2-23図)、三か国・地域ともに2000年代は中国からの部品輸入額の割合が急激に上昇していたものの、米国では2010年代からほぼ同水準で推移した後に、2018年の21%をピークとして2020年には15%まで低下した。ここ数年において、米国の部品輸入では、中国依存度が抑えられてきている。一方、EUの部品輸入では、中国からの部品輸入額の割合が2011年の27%まで上昇したしたものの、その後小幅に低下し、再び上昇基調に転じており、2020年には28%を占めている。日本の部品輸入では、2015年までEUと米国を上回る高い割合で上昇しており、その後も高い水準を維持し、2021年に37%となっている。欧州では、2021年5月に欧州委員会から公表された「新産業戦略2020アップデート版」の中で中国依存の低減を掲げており、日本でもサプライチェーンの強靱化を推進していることから、今後の中国をめぐるサプライチェーンの動向に変化が生じる可能性がある。
第Ⅱ-1-2-23図 日米EUの部品輸入に占める中国の割合の推移
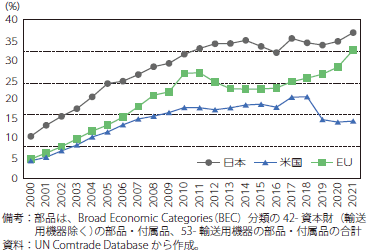
45 通商白書2018
2.サプライチェーンにおける特定国への依存の状況
(1)米国と欧州における重要品目の輸入依存の分析
米中対立を始めとする地政学的状況の変化を受けて課題となっていた特定国への生産拠点の集中度の高まりとサプライチェーンのぜい弱性が、新型コロナウイルスの感染拡大によって、改めて浮き彫りとなった。そのような状況において、2021年、米国とEUは、より多様で強靱なサプライチェーンを構築するために、サプライチェーンのぜい弱性に関する調査を政府主導で実施した。
米国では、2021年2月に署名された大統領令(Executive Order 14017)に基づき、サプライチェーンのレジリエンスを強化するため重要品目(半導体、大容量電池、重要鉱物・素材、医薬品)の調査が行われ、同年6月に結果が報告された。同報告書46の中で、重要品目に共通している米国のサプライチェーンぜい弱性として、①米国内の生産能力不足(低賃金国との競争による雇用損失)、②民間市場におけるインセンティブ不足と短期成果主義(利益は投資家に還元されることで研究開発に回らない)、③同盟国や競争国が採用した産業政策の影響(他国での公的産業支援増加)、④調達相手国の過度な集中、⑤国際協調の欠如(サプライチェーン関係国との外交的交渉の不足)の5点が指摘された。安価な労働力と生産国の産業支援政策の影響等により、サプライチェーンが一部地域に地理的に集中した結果、特に先進的な電池や医薬品の原薬の多くを中国に依存していることが判明し、米国のサプライチェーンのぜい弱性につながっていると結論づけた。
欧州では、2021年5月、相互依存関係から脱却し、欧州委員会の目指す開かれた戦略的自律性を推進するため、「新産業戦略2020アップデート版(2020 New Industrial Strategy)47」が公表された。同レポートでは、5,200の輸入品目のうち、137品目は輸入依存度が高く、その中で特にぜい弱である34品目(輸入総額の6%)は内外価格差が大きいため、輸入相手国の分散と代替生産が特に困難であるとの結果が示された。また、輸入依存度が高い137品目のうち52%が中国に依存していることが判明した(第Ⅱ-1-2-24図)。同レポートでは、新型コロナウイルスの感染拡大や半導体不足問題をきっかけに、不測の事態が発生した場合、特定国への過度な依存はサプライチェーンの混乱につながるという認識が共有されたことから、可能な限り調達先を多様化し、必要に応じて備蓄や自律的行動を行うとされている。
第Ⅱ-1-2-24図 欧州の輸入依存度が高い137品目の国別内訳
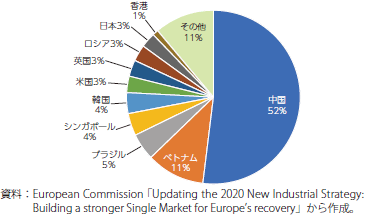
2020年9月には、欧州の原材料における特定国への依存を減らすため、「原材料アライアンス」が発足され、さらに半導体、電池、水素等の戦略分野の「産業アライアンス」の立ち上げ等が進められている。
46 The White House(2021)
47 European Commission(2021)
(2)日本における重要品目の輸入依存の分析
日本について、地政学的状況の変化や新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえて、特定国への生産拠点の集中度やそれがもたらすサプライチェーンのぜい弱性を把握するため、日本の重要品目等の輸入依存度を分析する。なお、ロシアによるウクライナ侵略による影響を踏まえた分析については、本書第Ⅰ部第1 章第1 節「世界経済に対する地政学的不確実性の高まりと経済リスク」で実施していることから、ここではそれ以外の部分について取り扱う。
欧州委員会の「新産業戦略2020アップデート版」で用いられた分析手法を用いて、産業連関表における鉱工業品、特に半導体、電池、レアメタル・レアアース、医薬品の重要品目について、3つの指標(輸入依存度、輸入品の国内代替生産可能度、ハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI・輸入相手国への集中度)から日本の対外依存度を見ていく(第Ⅱ-1-2-25表、26図)。
第Ⅱ-1-2-25表 重要品目等の依存度、国内代替可能度
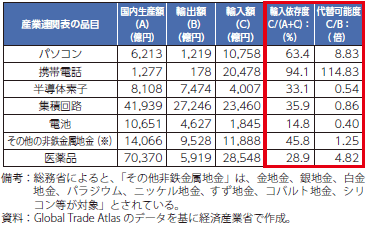
第Ⅱ-1-2-26図 輸入相手国・地域
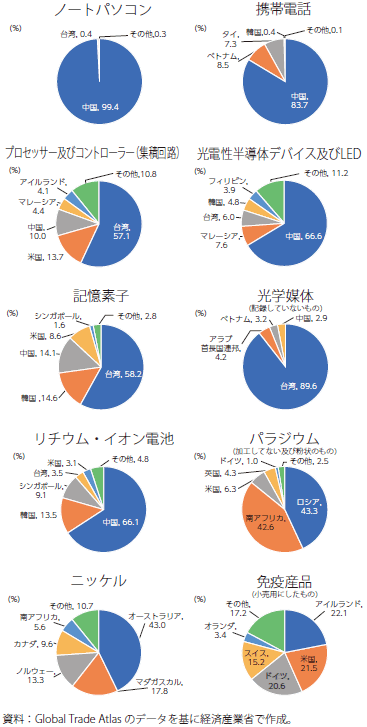
鉱工業品の中で輸入依存度48が高い品目は、パソコンや携帯電話で、それぞれ63.4%、94.1%となった。輸入依存度は50%を上回っており、国内生産より輸入の方が多いことが示されている。また、国内代替可能度49は、それぞれ8.83倍、114.83倍と輸入額が輸出額を大きく上回ることから、国内での代替可能性は低いことが示されている。輸入相手国は、中国が大半を占めている。この分析では、パソコンも携帯電話も共に、完成品の輸入が中国に依存していることが示されているが、バリューチェーンにおける中流工程の組立ては、上流工程の製品設計・デザインや下流工程の販売・アフターサービスに比べて付加価値が低くなることから、費用の面で中国が選ばれていると推測される。このような付加価値の低い品目では、生産拠点の多元化等による供給体制の強化の検討が求められるであろう。
幅広い産業で欠かせない半導体関連品目では、半導体素子の輸入依存度が33.1%、代替可能度が0.54倍、集積回路の輸入依存度が35.9%、代替可能度が0.86倍、電池の輸入依存度が14.8%、代替可能度が0.40倍となっている。輸入依存度は50%を下回っており、代替可能度が1倍を下回っていることから、輸入依存度と国内代替可能度の面においては、供給途絶リスクは高い水準ではないものの、一定程度のリスクが示されている。もっとも、この後に説明する、ハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI)が示す輸入相手国の集中度にも注意する必要がある。
生命の安全に直結する医薬品では、輸入依存度は28.9%と低いものの、代替可能度が4.82倍と輸入額が輸出額を大きく上回っており、国内代替生産が困難となっている。輸入相手国は品目により異なるが、アイルランド、米国、ドイツ、スイス等から輸入されている。
輸入依存度が高く、代替可能性が低い場合、輸入が特定国に集中しているとさらなるリスクとなりうる。
次に、ハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI)50を用いて、輸入相手国への集中度を見ていく。HHIは、最大値(=100)に近いほど輸入相手国が少なく、HHIが低いほど輸入相手国が多いことを示す。
重要品目であるレアメタル、レアアースは、電気自動車を始め様々な産業で欠かせない素材であり、デジタル社会を支える重要基盤にもなっている。レアメタルとレアアースに該当する貿易品目のHHIを見ると、輸入が少数の国に集中するものが多く、供給途絶リスクの高さが示されている。
HHIが高い値を示している品目をまとめると(第Ⅱ-1-2-27表)、携帯電話、ノートパソコンのHHIはそれぞれ71.3、98.7で高い値を示しており、輸入相手国は中国が大半を占めている。半導体素子では光電性半導体デバイス及びLEDのHHIが45.9を示し、中国からの輸入が突出している。集積回路のうちプロセッサー及びコントローラーと記憶素子のHHIはそれぞれ36.0、38.8となっており、台湾からの輸入が過半数を占めている。重要品目の中でもHHIが高い値を示す品目が多くあることから、輸入相手国の集中度や輸入依存度が高く、国内生産代替可能性が低い重要品目については、経済安全保障の観点から早期に国内での供給体制整備や輸入相手国の多様化等の安定供給確保に向けた対応が求められるといえる。
第Ⅱ-1-2-27表 ハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI)の高い主な品目
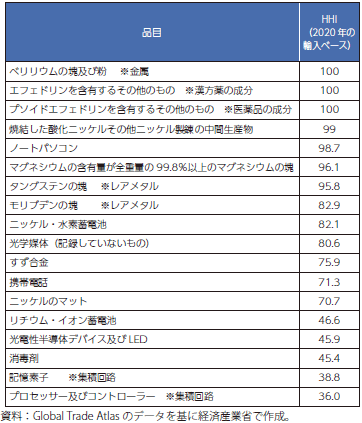
また、我が国は、石油や天然ガスのほぼ全てを輸入に依存しており、石油や天然ガスの安定供給確保のためには、我が国企業が直接その開発・生産に携わる海外の上流権益確保と国内資源開発を通じた自主開発を進めることが極めて重要である。特に、国内資源開発は、地政学リスクに左右されず安定的なエネルギー供給の確保が可能となることから、引き続きメタンハイドレート51を含む国内資源開発を推進することが重要である。このため、日本周辺海域に相当量の賦存が期待されるメタンハイドレート について2027年度までに、民間企業が主導する商業化に向けたプロジェクトが開始されることを目指し、可能な限り早期に成果が得られるよう技術開発等を推進している。
48 輸入依存度(%)= 輸入額 ÷(国内生産額+輸入額)× 100
49 国内生産による代替可能度(倍)= 輸入額 ÷ 輸出額(数値が大きいほど国内生産での代替可能性が低くなることを示す)
50 輸入相手の国数の集中度を計測する主要な指標。HHI=Σ(任意の国が占める輸入シェア)2÷ 100
51 メタンと水が低温・高圧の状態で結晶化した物質。
(3)サプライチェーンの地理的集中リスク
サプライチェーンが地理的に集中することに伴うリスクは、国際産業連関表からも確認できる52。自然災害リスクが大きい日本と、地政学的リスクが大きい中国を対象国として、主要6産業(食料品(10T12)、織物、衣類(13T15)、化学製品、医薬品(20T21)、ICT、電子機器(26)、電気機器(27)、自動車(28))について国際産業連関表を用いてグローバルサプライチェーンの地理的集中度を見ると、以下の散布図のようになる(第Ⅱ-1-2-28図)。ここでは、縦軸が対象国(左:日本、右:中国)の産業を経由する頻度(頻度の集中リスク)、横軸が付加価値源泉としての対象国のシェア(数量の集中リスク)となっている。各国のサプライチェーンは、日本に対して数量、頻度ともに低い値に分布が固まって示されている一方、中国については、正の相関関係を示す右上の方向に分散しており、国、産業によっては数量、頻度ともに高い値も示していることから、日本よりも中国に地理的にサプライチェーンが集中していることが分かる。サプライチェーンの依存度を分析する場合、前の項目で見た輸入依存度の観点からは、直接的な貿易取引における量的リスクのみしか分からないが、国際産業連関表を用いることで、量的集中リスクに加えて、長く複雑に構築されたグローバルサプライチェーンの中で途中様々な国を経由する頻度の集中リスクの二つの側面からより実態に即した分析が可能となる。
第Ⅱ-1-2-28図 主要な製造業のグローバルサプライチェーンのリスクポジション(2018)
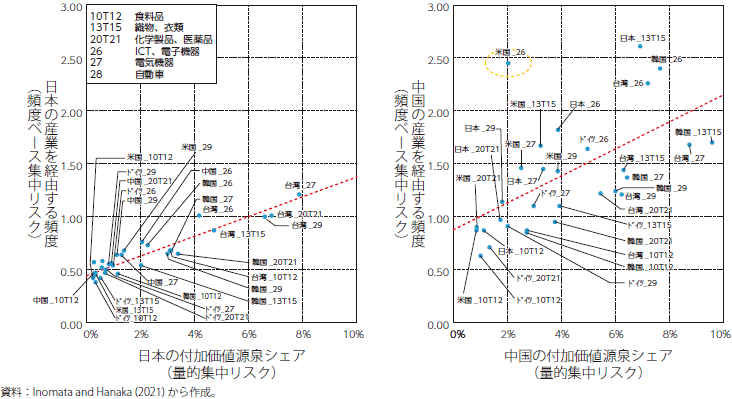
米国のICT、電子機器分野(米国_26)を見ると、量的集中リスクは低い値を示す一方、頻度の集中リスクは高い値を示している。これは、米国のICT、電子機器分野は、中国での付加価値依存度は低いものの、頻度の集中の面からは部品加工の一部を中国で行う等、非常に高い頻度で中国の産業を経由していることを示している。数量的な付加価値集中の側面だけで見た場合、サプライチェーンのリスクを過小評価してしまう可能性があることから、グローバルサプライチェーンの経由国のサプライチェーン依存度も見ていくことが有意義である。
52 Inomata and Hanaka (2021)
(4)サプライチェーン強靱化に向けた各国の取組
サプライチェーンの混乱要因は、自然災害、地域紛争、パンデミック、政情不安等多様化している。2020年には、新型コロナウイルスの感染拡大により、マスクやワクチン等の医療関係物資に関して供給途絶が生じるなど、サプライチェーンのぜい弱性が世界各地で顕現化したことから、各国において、生産拠点の集中度が高く、サプライチェーンの途絶リスクが大きい重要品目や、国民が健康な生活を営む上で欠かせない品目について、リショアリング(海外移転した生産拠点の国内回帰)も含めた国内生産拠点の整備と海外生産拠点の多元化の両輪で、サプライチェーンの強靱化が進められている。
重要品目の中でも、特に半導体は、自動車、通信、医療機器等の様々な分野で活用され、5G、ビッグデータ、AI、IoT、ロボティクス等のデジタル社会を支える重要基盤であり、安全保障にも直結する重要な戦略物資・技術であることから、世界各国で大規模な資金を投入した生産基盤の強化が進められ、産業政策による競争が展開されている。
米国では、半導体産業の支援策として1件最大3,000億円規模の補助金や「多国間半導体セキュリティ基金」の設置を含む、国防授権法(National Defense Authorization Act 2021、NDAA2021)が可決された。米国内の半導体サプライチェーン強化を目指す「CHIPS法(Creating Helpful Incentives for the Production of Semiconductors(CHIPS)for America Act)」の規定に対し、半導体の生産や研究開発に520億ドルの大規模な予算を組み込む「米国イノベーション・競争法案」が上院で可決され、同内容を含む「アメリカ競争法」が下院で可決された。今後、上下両院の合同委員会にて調整された統一法案が可決された後、大統領署名を経て成立となる見込みである。
欧州では、2030年に向けたデジタル戦略が発表され、その中にデジタル移行(ロジック半導体、HPC・量子コンピュータ、量子通信インフラ等)への1,447億ユーロ(約18.8兆円)の投資や、2030年までに最先端半導体製造の世界シェアを現在の10%程度から20%以上とする目標等が盛り込まれた。さらに、欧州域内での最先端チップの製造も含めたエコシステムの構築を目指す「新・欧州半導体法案」の制定が2021年9月に宣言され、2022年2月に規則案が提出された。
中国では、2014年と2019年に計約5兆円規模の「国家集積回路産業投資基金」が設置されている。これに加えて、各地方政府にも、計約5兆円を超える半導体産業向けの基金が存在し、合計10兆円超の資金が半導体関連技術に投じられていると見られる。
日本では、半導体も含めたサプライチェーン途絶リスクが大きい重要品目や国民が健康的な生活を営む上で不可欠な品目全体について、「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」として、令和2年度第1次補正予算で2,200億円、第3次補正予算で2,108億円、「海外サプライチェーン多元化支援事業」として、令和2年度第1次補正予算で235億円、第3次補正予算で116.7億円が確保された。さらに、令和3年度補正予算では、「先端半導体の国内生産拠点の確保」として6,170億円、「サプライチェーン上不可欠性の高い半導体の生産設備の脱炭素化・刷新事業」として470億円と、大規模な予算が確保され、不測の事態にも滞りなく経済活動、国民生活が継続できるような生産基盤の国内整備が進められている。同じく令和3年度補正予算において、「経済安全保障重要技術育成プログラム」として、経済安全保障の確保・強化のため、量子、AI等の先端分野における重要技術の研究開発から実証・実用化を迅速に促進する予算として、2,500億円規模の資金が確保された。
また、2022年5月に成立した経済安全保障推進法(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律)の中では、国民の生存に必要不可欠な又は広く国民生活若しくは経済活動が依拠している重要な物資等を特定重要物資に指定し、安定供給確保を図るための規定が盛り込まれている。特定重要物資として指定した物資については、当該物資の安定的な供給を確保するために必要な生産基盤の整備、供給源の多様化、生産技術の導入・開発・改良等の取組を通じて安定供給確保を図るため、特定重要物資ごとに施策の方向性及び支援対象となる取組の内容を定めた取組方針を当該物資の所管大臣が定めることとなる。その上で、取組方針を踏まえて、民間事業者が供給確保計画を作成し、所管大臣による認定を受けた場合、認定事業者は助成等の支援を受けることが可能となる。
ロシアのウクライナ侵略により、ロシアからの輸入依存度が高いエネルギーや資源などの戦略物資についてサプライチェーンの供給リスクへの認識がこれまで以上に高まっていることを踏まえ、経済安全保障の観点から早期に重要な物資の国内での供給体制整備や供給源の多様化等の取組が求められる。
(5)サプライチェーン強靱化に向けた有志国との連携
経済活動や国民生活への影響が大きい重要品目やぜい弱性が高い品目の生産拠点多元化のためには、価値観を共有する有志国との連携が重要である。質の高いサプライチェーンを確保するため、各国は、多国間での有志国連携の強化に取り組んでいる。
例えば、2021年4月には、インド太平洋地域におけるサプライチェーンの混乱に日豪印三か国で協力して対応するため、日豪印三か国の貿易大臣によってSCRI(サプライチェーン強靱化イニシアティブ)が立ち上げられた。2022年3月には第二回のSCRIについての日豪印貿易大臣会合が実施され、インド太平洋地域大のサプライチェーン原則を策定・促進すること、三か国協力がサプライチェーン強靱化に貢献しうる主要な産業分野を特定し、同分野への投資やビジネスを促進していくこと、サプライチェーン強靱化に向けてベストプラクティス及び共同プロジェクトの促進・推進のため、産業界及びアカデミアと協力していくことの重要性等が確認され、向こう約一年間日本が議長国としてSCRIを推進していくことが合意された。
重要品目等の供給地の囲い込みや閉鎖的な経済体制に進むのではなく、このように有志国と協力しながら、開かれた供給体制を整備することが求められる。
3.機微・新興技術の発展と輸出管理・対内直接投資管理等による経済安全保障の推進53
米中対立やロシアのウクライナ侵略等の地政学的リスクの顕在化によって安全保障リスクが高まる中、前述したサプライチェーン依存の低減を始めとする重要物資の確保の取組に加えて、安全保障上の重要技術の保全・育成といった取組を通じた、経済構造の自律性向上と、技術優位性の確保ひいては不可欠性の獲得を目指す統合的な取組が重要性を増している。
機微技術、特に軍事にも民生にも利用可能なデュアルユース技術は、民生サプライチェーンの存在と軍事転用の可能性から、その流出は、安全保障上の脅威の一つとなっている。特に、AI・量子・バイオ等の技術については、開発の初期段階にあっても将来の軍事技術体系を変える可能性がある。こうした新興技術や、それを支える基盤技術については、その進展の著しさや保有主体の多様化により昨今その流出形態が多様化・複雑化しており、アカデミアやベンチャー企業を含む中小事業者における管理や、管理の機動性はその重要性を一層増している。
このような経済安全保障上の懸念から、機微技術・新興技術及びこれら技術を用いて製造された製品に対して、輸出管理や対内投資管理規制を強化する動きが世界各国で拡大している(第Ⅱ-1-2-29表)。
第Ⅱ-1-2-29表 主要国・地域の輸出管理制度と対内直接投資制度の概要
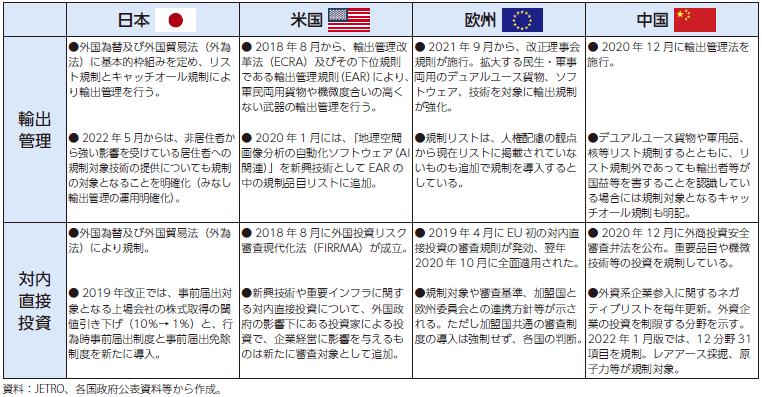
53 角田 昌太郎(2021)
(1)主要国・地域の輸出管理制度
機微技術・新興技術は、将来の国家の競争力を左右する重要な技術であることから、国際平和を脅かすおそれのある国家やテロリスト等への流出を防ぎ、経済安全保障を確保するため、各国において輸出管理制度の強化を含めた様々な対策が進められている。ここでは米国、欧州、中国、日本の輸出管理制度について、経済安全保障の側面から概観する。
米国では、2018年8月に成立した輸出管理改革法(Export Control Reform Act、以下ECRA)によって、軍民両用のデュアルユース貨物等の輸出管理が実施されている。ECRAは、国防総省に予算権限を与える2019年会計年度国防授権法(NDAA2019)の一部として成立しており、ECRAの中で「新興技術」(emerging technologies)や「基盤的技術」(foundational technologies)を追加することとしている。さらに、ECRAの下位規則である輸出管理規則(Export Administration Regulations、以下EAR)には、対象となる規制品目リスト(Commerce Control List 、CCL)やエンティティリスト(Entity List)等が含まれており、米国原産品等の輸出・再輸出等が規制されている。ECRAでは、商務省に対して「新興技術」と「基盤的技術」を指定するように定めているが、2018年に出されたパブリックコメントにおいて新興技術14分野54が例示された後は明確なリスト化の動きはなかったところ、2020年1月に、「地理空間画像分析の自動化ソフトウェア(AI関連)」が新興技術として新たにCCLに追加され55、2021年には、「ブレイン・コンピュータ・インターフェイス(BCI)」の追加についてのパブリックコメントが実施された。
エンティティリストは、国家安全保障・外交政策上の利益を害する活動をした者(企業、研究機関、団体、個人等を含む)を掲載しており、リスト掲載者に対して輸出する場合、事前に米国商務省に申請し許可を得ることが必要となる。
欧州では、規則において輸出管理体制を定めており、規制対象は規則の付属書リストに掲載されている。2021年9月に施行された改正規則No 2021/821(Export Control Regulation)56では、安全保障上のリスクや新興技術に対応するため、民生・軍事両用のデュアルユース貨物、ソフトウェア等の輸出規制が強化された。規制対象リストは、情報セキュリティリスクの拡大と、テクノロジーの急速な発展等に対応するために定期的に見直しがされており、人権配慮の観点からも規制対象リストへの追加掲載が検討されている。
また、欧州と米国は、技術、経済、貿易問題等に対し協力して対処するための場として、米国EU貿易技術評議会(TTC)を設置しており、2021年9月に開催された第一回会合57において、重要技術・新興技術分野や輸出管理における協力を含めた共同声明を発表している。
中国では、2020年12月から輸出管理法が施行されている。デュアルユース貨物や軍用品、核等やその関連技術についてリスト規制をするとともに、リスト規制外であっても輸出者等が国益等を害することを認識している場合には規制対象となるキャッチオール規制も明記されている。また、米国と同様に、みなし輸出・再輸出規制を講じることが予定されている。輸出禁止・制限技術リストには、「国家の安全と利益」を目的として、AIやソフトウェアセキュリティ関連が掲載されているものの、規制対象品目の範囲が極めて不明確であり、当局の裁量が大きいことに懸念の声が上がっている。
日本では、外国為替及び外国貿易法において輸出管理の枠組みが定められている。具体的には、リスト規制とキャッチオール規制の二つの規制があり、これらの規制に該当する貨物の輸出や技術の提供は、事前申請の上、経済産業大臣の許可が必要となる。リスト規制は、国際輸出管理レジームにおいて輸出管理の対象とすることに合意された内容が反映されており、先端材料を含む軍事転用のおそれの高い機微な品目等が対象となっている。キャッチオール規制は、リスト規制に非該当であっても、用途や需要者が大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合や、経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受けた場合に、その貨物の輸出又は技術の提供が対象となる。このうち、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある需要者か否かを判断するための資料として、経済産業省は外国ユーザーリストを公表しており、輸出先又は技術提供先が外国ユーザーリストに該当する場合には慎重な審査と、必要に応じて事前申請の上で、経済産業大臣の許可が必要となる。また、企業だけではなく、大学や研究機関での人的交流や共同研究等による安全保障上の機微な技術の流出対策を強化する観点から、2022年5月から、居住者であっても非居住者から強い影響を受けている場合には、当該居住者に規制対象技術の提供をする場合には当該技術提供が規制対象となる(いわゆる、みなし輸出管理の運用明確化)等、輸出管理の見直しを行っている。
54 (1)バイオテクノロジー、(2)人工知能(AI)・機械学習技術、(3)測位技術、(4)マイクロプロセッサー技術、(5)先端コンピューティング技術、(6)データ分析技術、(7)量子情報・量子センシング技術、(8)輸送技術、(9)付加製造技術(3Dプリンターなど)、(10)ロボット工学、(11)ブレイン・コンピュータ・インターフェイス、(12)極超音速、(13)先端材料、(14)先進監視技術
55 JETRO「米商務省、地理空間画像分析用のAI技術を輸出管理対象に追加」、2020年1月
56 EU Commission 「Strengthened EU export control rules kick in」、2021年9月
57 EU Commission「 EU-US Trade and Technology Council Inaugural Joint Statement」、2021年9月
(2)主要国・地域の対内直接投資管理制度
機微技術・新興技術の流出は、輸出管理だけでは防ぐことはできない。近年では機微技術・新興技術獲得を目的とした企業の買収・合併等の対内直接投資が増加していることから、各国において対内直接投資管理制度の強化が進められている。
米国では、外国人による対内直接投資等を審査する権限を有した省庁横断的組織として対米外国投資委員会(CFIUS)が、米国の経済安全保障に及ぼす影響を判断している。前述した2018年8月成立の2019年会計年度国防授権法(NDAA2019)の一部として盛り込まれた外国投資リスク審査現代化法(Foreign Investment Risk Review Modernization Act of 2018、以下FIRRMA)により、CFIUSの審査権限が強化された。具体的には、新興技術や重要インフラに関する対内直接投資について、外国政府の影響下にある投資家による投資のうち、企業経営に影響を与えるものは、新たに事前審査が義務化された。
CFIUSの年次報告書58では、重要技術の研究、開発、生産に携わる米国企業59に対する対内直接投資の国別の件数が報告されている。重要技術は、輸出管理規則(EAR)や規制品目リスト(CCL)で規制されているものや、武器、原子力、特定毒物に関する技術と定義されている。重要技術保有企業に対する買収の全申請件数は、2018年は76件、2019年は92件、2020年122件となっており、新型コロナウイルスの感染拡大期にも関わらず、重要技術の保有企業に対する買収件数は増加している。2020年の買収件数を国別で見ると(第Ⅱ-1-2-30図)、日本の件数が最も多く、カナダ、ドイツ、英国と続く。日本は、2018年からの3年間で最も買収件数が多く、中国は、2018年に日本、カナダに続き3番目の投資国(8件)であったが、2019年は3件と大幅に減少した。買収件数が少ないため一概にはいえないが、CFIUSの審査権限の強化による影響がうかがえる。
第Ⅱ-1-2-30図 米国の重要技術保有企業に対する買収
上位六か国の国別の件数(2018~2020年)
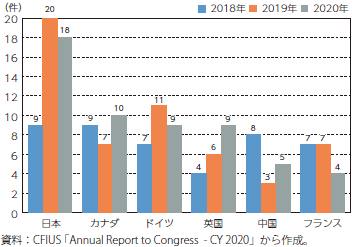
欧州では、2019年4月にEUで初となる「対内直接投資の審査に関する規則No 2019/452(the screening of foreign direct investments into the Union)」が発効し、2020年10月に全面適用された。この規則では、規制対象、審査基準、加盟国と欧州委員会との連携方針等が示されているものの、共通審査制度の導入は、加盟国に対して強制せず、各国の判断に委ねられている。全面適用が開始された2020年10月から2021年6月末までの実績に関する報告書60が2021年月11月に公表されており、11加盟国から265件の直接投資審査の通知があった。通知件数のうち90%超は、オーストリア、フランス、ドイツ、イタリア、スペインの五か国が占めており、このうち36件(通知件数の14%)が加盟国に影響がある等と判断されて第二段階に進んだ。第二段階に進んだ案件を分野別で見ると、製造が50%を占めており、情報通信技術(ICT)(17%)、金融(8%)と続く(第Ⅱ-1-2-31図)。2020年10月から全面適用されたため、その推移を見ることはできないが、投資元国別では、米国(45%)、英国(9%)に続き、中国が第3位で約8%と存在感を示している。
第Ⅱ-1-2-31図 EUの対内直接投資(第二段階)
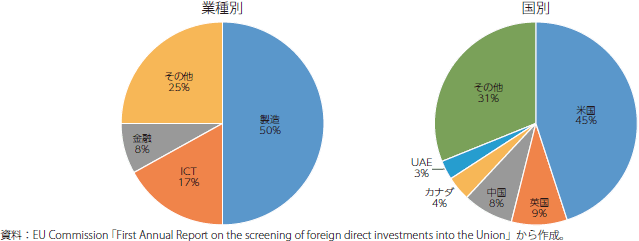
中国では、2020年12月、国家発展改革委員会と商務部が、外商投資法及び国家安全法に基づき、外資企業が中国に投資する際の安全審査に関する「外商投資安全審査弁法」を公布した。具体的には、「軍事関係、国家の安全にかかわる重要な農産物、重要なエネルギーと資源、重大な装備製造、重要なインフラ、重要な運輸サービス、重要な文化製品とサービス、重要な情報技術とインターネット製品・サービス、重要な金融サービス、鍵となる技術及びその他の重要な分野」と規定されている。規制対象に機微技術・新興技術が含まれていることから、これらの技術の流出防止が意図されている。対象となった場合、国家発展改革委員会への事前の申請が義務となっており、審査が実施された上で、国家の安全に影響を及ぼすおそれがない場合に中国への対内直接投資が許可される。
また、外資系企業参入に関するネガティブリストが毎年更新されており、外資企業の投資を制限・禁止する分野が示されている。2022年1月から施行されたリストでは、12分野31項目が規制対象となっており、2021年と比べると、完成車の製造等の市場が開放されたものの、引き続き原子力発電所の建設・経営等が規制されている。
日本では、外国為替及び外国貿易法(外為法)により対内直接投資が規制されている。主要国の規制強化の流れを受けて、日本でも機微技術・新興技術の流出のおそれがある対内直接投資に対して適切に規制が見直されてきた。2017年の改正では、無届けで対内直接投資を行った外国投資家に対して株式売却の行政命令を行うことができる事後措置命令の導入等や、国の安全を損なうおそれが大きい業種について、外国投資家による他の外国投資家からの非上場株式の取得を事前届出対象に追加する等の見直しを実施した。2019年の改正では、事前届の対象となる上場会社の株式取得の閾値を引き下げる(10%→1%)とともに、行為時事前届出制度と事前届出免除制度を新たに導入し、外国投資家が一定の基準を遵守することを前提に、株式取得時の事前届出を免除し、事後報告のみによる投資を可能とした。財務省が2021年7月に公表した「対内直接投資等に関する事前届出件数等について」61によると、2019年の改正により、2020年度は取得時事前届出の件数は減少し、新たに導入された行為時事前届出の731件を加え、全体の件数は2,171件と前年比で約11%増となった(第Ⅱ-1-2-32図)。分野別では、2018年度までは武器等、インフラ関連、その他がそれぞれ3割程度を占めていたが、2020年度は、前年度に新たに加わったサイバーセキュリティ関連業種(情報処理サービス業、ソフトウェア業、集積回路製造業、半導体メモリメディア製造業等)が66%を占めている(第Ⅱ-1-2-33図)。
第Ⅱ-1-2-32図 日本の上場会社の株式取得に係る事前届出件数の推移
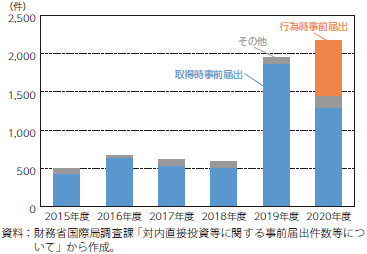
第Ⅱ-1-2-33図 日本の上場会社の株式取得に係る取得時事前届出の業種別割合
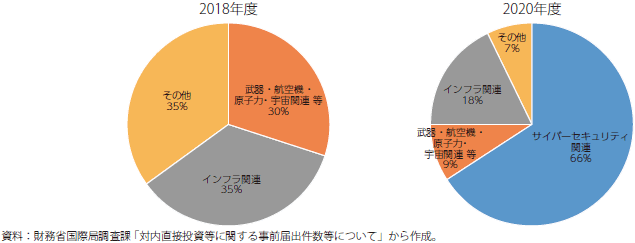
外為法に基づく株式取得中止勧告が出された案件としては、2008年に英国の投資ファンドであるザ・チルドレンズ・インベストメント・マスターファンド(TCIファンド)による電源開発株式会社の株式取得の例がある。この案件では、電気事業は電気の安定供給の維持、日本の原子力政策への影響、公の秩序維持を妨げるおそれ等があるとして、外為法に基づいて初めての勧告がなされた。これまでに勧告はこの1件のみであるものの、直接投資規制の中止勧告の体制が整えられていることは抑止力にもつながるため、いつでも発動しうる備えをしておくことは重要である。
経済安全保障の観点から、規制強化の動きが拡大しているが、経済安全保障の懸念を超えて、経済活動に対して不公正な影響を及ぼすことがないよう、各国政府による規制の整備には留意が必要である。
58 CFIUS (2021)
59 重要技術の研究、開発、生産に携わる米国企業で、2008年11月21日に連邦官報に掲載された31 C.F.R. §800.209, Regulations Pertaining to Merg, Acquisitions, and Takeovers by Foreign Persons(「CFIUS規制」)に規定されている。
60 EU Commission (2021)
61 財務省国際局調査課(2021)
(3)経済安全保障推進のための総合的な取組
米国を始めとする主要国では、大学や研究機関での人的交流や共同研究等による機微技術・新興技術の流出の懸念の顕在化に対して対策が講じられてきている。例えば、米国では2019年に、ある大学教授が、複数の中国の研究機関との契約について当局に報告しなかったことから起訴されたほか、別の大学教授が、中国政府が優秀な研究者を招へいする「千人計画」への参加の事実を隠して虚偽申請を行い、不正に補助金を受領したとして起訴されるなど、相次いで起訴事例が発生している。これを受けて、米国国立科学財団(NSF)は、申請書類及び手続を変更し、透明性・情報開示の重要性を明確化している。日本でも、こうした研究の国際化やオープン化に伴う新しいリスクに対応するとともに、他国との交流や協力関係も重視しながら、国際的に信頼性のある研究環境を構築するために、研究機関等に透明性と説明責任を求める「研究インテグリティ」の確保に向けた方針が2021年4月に公表された。具体的には、①研究者自身による研究活動等の適切な情報開示、②大学・研究機関の人事・リスク管理のためのマネジメント強化、③研究資金配分機関等において情報の提出を求めることが対応方針として示されており、研究機関等における経済安全保障の確保が強化され、機微技術・新興技術の流出防止を推進している。
さらに、2022年5月には、経済安全保障推進法(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律)が可決、成立した。この法律は、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進することを目的としており、安全保障に関する経済施策として、①重要物資の安定的な供給の確保のためのサプライチェーン強靱化、②基幹インフラ役務の安定的な提供確保、③先端的な重要技術の開発支援、④特許出願の非公開化の四つを定めている。この法律によって、新たに先端的な重要技術の研究開発を促進させるとともに、情報提供や資金支援、官民伴走支援のための協議会設置、調査研究業務の委託等を措置する。また、安全保障上極めて機微な発明が含まれる特許出願については、公開や流出を防止するとともに、安全保障を損なわずに特許法上の権利を得られるようにするために、保全指定をして出願公開等の手続を留保する仕組みや外国出願制限等を規定している。前述した輸出管理や直接投資管理だけでなく、この法律による措置に加え、先端的な重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用により、経済安全保障がより一層推進されることが期待される。
4.貿易・投資・金融面での措置を巡る動向
(1)主要国による最近の措置
近年、グローバル化と情報通信技術の発展により、国境を越えたグローバルサプライチェーンや金融・情報通信ネットワークが世界中に構築されている。これに伴い、世界各国の相互依存関係が形成され、国際秩序の安定に寄与している。他方、強まった相互依存関係のネットワーク構造において、貿易・投資・金融面で、そのような相互依存関係を前提とした様々な措置がとられてきている。
米国では、トランプ前大統領が2018年3月、1974年通商法301条による中国に対する追加関税措置を発動することを決定した。1974年通商法301条では、不公正な貿易により通商協定における米国の権利が侵害される場合、WTO等の国際ルールに基づく紛争解決手続を経ず、米国のみの判断に基づき、相手国に対し関税引上げや輸入数量制限等の一方的な貿易制裁措置を課すことができる。中国の産品に対する追加関税措置発動の決定は、中国による知的財産や技術の移転に関して中国政府が介入しているとの調査結果を受けたもので、これ以降、米国と中国で貿易制裁措置の発動が続いたものの、2020年1月には米中経済貿易協定(第一段階)に合意した。新型コロナウイルス感染拡大の影響で世界経済が落ち込む中、中国としては合意内容の履行に努めたとしているが、米国は、中国が合意内容の6割程度しか米国産品を輸入していないと主張している62。その後、2021年1月に就任したバイデン政権は、中国人民解放軍と関連する中国企業等への投資を禁止する大統領令に署名するなど、基本的に中国に対する厳しい措置を維持している。
米国では、歴史的に一方的措置の発動件数が多いが、その要因としては、貿易自由化による輸入急増が米国の国内産業に与える損害に対して迅速に対応するため、強い権限を与えてきたこと等が挙げられる。
WTOを設立するマラケシュ協定附属書二(紛争解決に係る規則及び手続に関する了解)第二十三条(多角的体制の強化) は、WTO協定上の利益が害されたか否かの判断について紛争解決手続によることなく、一方的に是正を求めるための措置を発動することを明示的に禁止している。もっとも、2019年以降、紛争処理を担うWTO上級委員会が委員任期満了や退任により機能していない状態に陥っているため、WTO紛争解決機関において、機能していない上級委員会に上訴することによって、パネルによる判断が確定せず塩漬けとなるケースが複数累積している。このようなWTO紛争解決機関の機能不全が続けば、一方的措置を含むルール不整合な措置に対して十分に対応できなくなることが懸念される。
さらに、米国は、域外適用にも積極的な姿勢を見せている。通常、立法管轄権の範囲は、国内の法律の適用範囲は自国内のみにとどまり、国外には及ぶものではないという属地主義の考え方に基づいている。公正かつ自由な競争の実現のため、競争法においては従来から属地主義を拡張した効果理論の考え方による域外適用が指摘されていた。例えば、米国の1979年輸出管理法63では、米国原産品の再輸出や米国原産品だけではなく米国産部品等が一定割合使用された海外産の製品も規制対象となっており、同法に代わり2018年に制定された米国輸出管理改革法においても同様に再輸出を含めて規制されている。1997年に制定された米国海外腐敗防止法は、外国の公務員への贈賄行為を規制する法律であるが、米国外で起きた贈賄行為であっても米国子会社が関係している場合や、米ドルによる送金で支払いされた場合等も米国が関連した行為とみなされ多数の摘発が行われている。このように、米国による域外適用の範囲は拡大し、適用頻度が活発化している。
62 Peterson Institute for International Economics「US-China phase one tracker: China’s purchases of US goods」、2022年3月
63 上原有紀子(2022)
(2)対抗措置にかかる法整備
中国は、法律の下位の規則として、2020年9月「信頼できない実体リスト」、2020年12月「輸出管理法」、2021年1月「外国の法律と措置の不当な域外適用を阻止する弁法」等を相次いで施行した。2021年6月には、これまでの規則より上位に位置付けられ、国家が制定する法律である「反外国制裁法」が施行され、同法に基づき中国当局者等に対する米国の制裁措置に対応して、米国の個人、政府機関、企業に対する制裁措置が累次発表されてきた。
欧州では、第三国からの経済的威圧を念頭に、2021年12月に対抗措置を可能とする規則案を公表した64。EUの利益を保護するためにWTOの承認を経ずに独自に関税引上げや資金支援の停止等の対抗措置を可能とする内容で、第三国の一方的な威圧的措置を抑制することを主な目的としている。ここでは、第一段階としては対話を通じて措置の解消を目指し、対抗措置は最終手段とすることが想定されている。この規則案については、今後EU理事会と欧州議会にて審議が予定されている。
64 European Commission Press release 「EU strengthens protection against economic coercion」2021年12月
(3)日本の企業への影響
こうした状況の下、日本の産業界からは懸念の声が示されている。2020年11月に一般財団法人安全保障貿易情報センター(CISTEC)、一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所等の業界団体は、連名で経済産業省に対して中国及び米国の域外適用に関する要望書を提出した(第Ⅱ-1-2-34表)。要望書では、米国、中国の輸出管理規制の強化の流れの中で、過剰な域外適用や報復措置等の抑制のために政府間の働きかけを求め、過剰な規制により、予見可能性や法的安定性が著しく欠けた状態になり、ビジネス活動の委縮につながるという懸念が表明されている。
第Ⅱ-1-2-34表 「中国及び米国の域外適用規制について」の要請書骨子
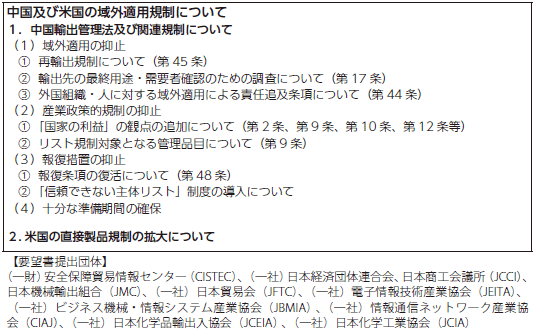
梶山経済産業大臣(当時)は、2020年11月17日の閣議後記者会見の中で、経済産業省としては産業界との対話を進めるとともに、各社に各国の規制状況を踏まえたリスクの把握等を求め、規制以上に過度に委縮しないように喚起した。また、政府が収集した詳細情報の積極的かつタイムリーな発信と、米中始め他国においてサプライチェーンの不当な分断がある場合には、経産省が前面に立って支援する旨を表明した。
日本機械輸出組合を事務局とする貿易・投資円滑化ビジネス協議会が2021年12月に公表した調査65では、米国、中国での貿易上の問題点として、「中国輸出管理法の運用が不透明。規制の域外適用などが含まれるが、国際輸出管理レジーム合意に基づき、その原則に即しバランスのとれた制度・運用の必要性」があり、「輸出管理改革法(ECRA)や外国投資リスク審査近代法(FIRRMA)の規制等について、米中両国と取引のある日本企業も対象」となっており、「米国のEAR規制の対象顧客が日に日に増しており、市場が狭まっている」等という懸念の声が示されている。
突然の域外適用は予見性が低く、企業の事業環境が不安定化し経済活動の委縮へとつながることから、不公正な影響を及ぼすような過剰な域外適用の動きには注視していく必要がある。
65 貿易・投資円滑化ビジネス協議会(2021)(事務局:日本機械輸出組合)「各国・地域の貿易・投資上の問題点と要望」、2021年11月