第3節 共通価値の可視化とサステナブルなグローバルバリューチェーンの構築に向けて
共通価値への関心の高まり
大地震や洪水等の気候変動要因の自然災害や新型コロナウイルス等の感染症、米中対立やウクライナ情勢等の地政学リスクによる供給途絶など、グローバルバリューチェーン(GVC)マネジメントには様々な課題が存在する。こうした課題とともにGVCにおいて向き合うべきものとして近年クローズアップされているのが、サステナビリティや包摂性といった「共通価値」への関心の高まりとそれに伴う企業活動への要請である。
個々の企業においては、その社会的責任(CSR)の観点から事業を展開し、環境・社会・ガバナンス(ESG)にかかる情報開示を取引先や金融機関、投資家、ESGに関する企業の取組を評価する評価機関等、様々なステークホルダーに対して十分に行っていくことが求められている。事業活動におけるサステナビリティの向上を目指す各種の国際イニシアティブに参加し、取組に関するコミットメントを表明するほか、関連する情報の開示を行う企業も増えている。その際には、自社だけでなく、自社に関わるGVC全体で共通価値の実現を目指し、取組に関する情報開示を行っていくことが重要である。複雑化・重層化する取引関係における共通価値の問題をいかに可視化し、適時に適切な対応を取っていくかが、マネジメント上の大きな課題となっている。本節では、「気候変動への対応」、「ビジネスと人権の課題への対応」を軸に共通価値の可視化をめぐる動向を概観し、企業の取組や政策面の課題について検討する。
1.気候変動への対応
気候変動への対応は、国際社会が一体となって取り組むべき喫緊の課題である。
1995年から国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)が毎年開催され、実効的な温室効果ガス(GHG)排出削減に向けた議論が行われてきた。1997年のCOP3では、2020年までの排出削減の枠組みである「京都議定書」、2015年のCOP21では、2020年以降の新たな枠組みである「パリ協定」が採択され、2021年10月末から11月に英国のグラスゴーで開催されたCOP26では、合意文書に工業化以前からの気温上昇幅を1.5℃に抑える66ための努力を追求する決意があらためて示された。企業や金融市場においても脱炭素への関心が高まっており、脱炭素に向けた取組を進めていく上で、個々の経済主体の活動やバリューチェーンにおける炭素排出の状況を可視化し、把握する必要がある。
66 気候変動の影響は、摂氏1.5度の気温上昇の方が、摂氏2度の気温上昇に比べてはるかに小さいことを認め、気温の上昇を摂氏1.5度に制限するための努力を継続することを決意する。世界全体の温暖化を摂氏1.5度に制限するためには、世界全体の温室効果ガスの排出量を迅速、大幅かつ、持続可能的に削減する必要があること(2010年比で2030年までに世界全体の二酸化炭素排出量を45%削減し、今世紀半ば頃には実質ゼロにすること、及びその他の温室効果ガスを大幅に削減することを含む。)を認める(「グラスゴー気候合意」環境省暫定訳より抜粋)。
(1)バリューチェーンにおけるCO2排出
バリューチェーンにおけるGHG(ここではCO2)排出の可視化に係る試みの一つとして、OECDの「CO2 emissions embodied in international trade」が、産業連関表の仕組みを用いて各国の生産や輸出、最終需要に包含されるCO2排出量を推計している(データは2018年まで。第Ⅱ-1-3-1図はその概念図)。例えば、A国の最終需要に包含されるCO2排出について見ると、A国内及び海外(ここではB国、C国)の排出源となる産業から国内取引や輸出によって各国の中間財生産プロセスに投入され、同様に最終財生産プロセスに投入された後に、A国における最終財の国内取引や、B国、C国からの最終財の輸入を通じてA国の最終需要に包含されていく。A国からの中間財・最終財の総輸出の中には、それぞれの財の生産プロセスに投入されるB国、C国の排出分も間接的に包含され、A国のB国、C国からの中間財や最終財の総輸入の中には、B国、C国の生産プロセスに投入されるA国の排出分も間接的に含まれる。
第Ⅱ-1-3-1図 貿易と最終需要に包含されるCO2 排出
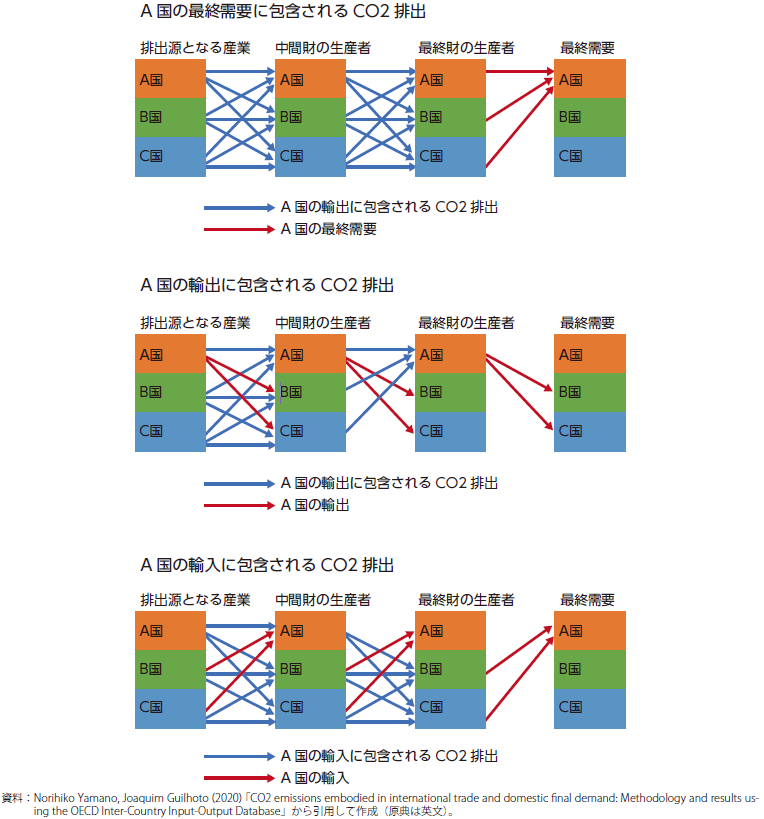
ここで世界の生産からみたCO2排出量の推移を見ると、先進諸国(ここではOECD諸国)では減少している一方、新興諸国(非OECD諸国)では増加しており、世界全体の排出量は増加し続けていることが分かる(第Ⅱ-1-3-2図)。非OECD諸国の排出に占めるアジア新興諸国(中国、インド、ASEAN67の合計)の比率は、2018年時点で60%を超え、その中でも中国の比率が圧倒的に高い(第Ⅱ-1-3-3図)。これら新興諸国におけるCO2排出の増加は、世界の生産拠点としての役割の増大によるところが大きいと考えられる。
第Ⅱ-1-3-2図 生産からみた世界のCO2排出
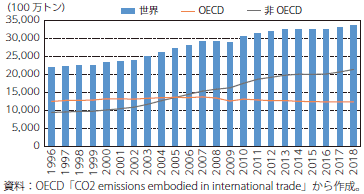
第Ⅱ-1-3-3図 生産からみた世界のCO2排出
(非OECDに占めるアジア新興国の比率)
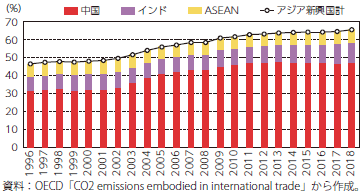
中国におけるCO2の国内排出を内需向けと外需向け(CO2の輸出)に分けた上で、中国の内需向けの海外排出(CO2の輸入)と併せて推移を見たものが第Ⅱ-1-3-4図である。外需向けの排出は、2000年代初めから急速に増加した後、世界金融危機時の一時的な落ち込みを挟んで同程度の排出水準を維持したが、2010年代後半には減少傾向にある。一方、内需向けの排出は、国内排出分のほか輸入分も増えており、中国の位置づけが「世界の工場」から「消費大国」へと変化してきていることが、CO2排出の側面からもうかがえる。
第Ⅱ-1-3-4図 中国におけるCO2の国内排出(内需向け、外需向け(輸出))、内需向けの海外排出(輸入)の推移
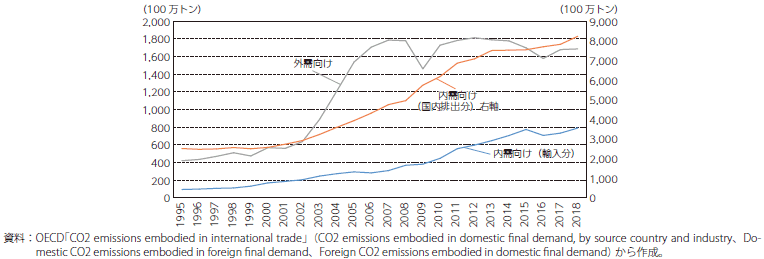
例えば海外の最終需要に包含される各国の国内排出と国内の最終需要に包含される海外排出は、それぞれ当該国のCO2の最終需要ベースの「輸出」と「輸入」に当たる。第Ⅱ-1-3-5図は、各国・地域のCO2の輸出先・輸入先の上位5か国と、参考としてEU28、ASEANとのCO2の輸出入データ(2018年)を取ったものである。中国のCO2輸出は、米国向けが最大で、日本、インドが続き、CO2輸入は、韓国、ロシアからが大きい。インドのCO2輸出は、米国向けが最大である。日本を含め各国・地域とも、CO2輸入は中国からが最も多い。米国は、CO2の輸出入とも中国が最大の相手国となっている。
第Ⅱ-1-3-5図 各国のCO2 輸出入先(2018年)
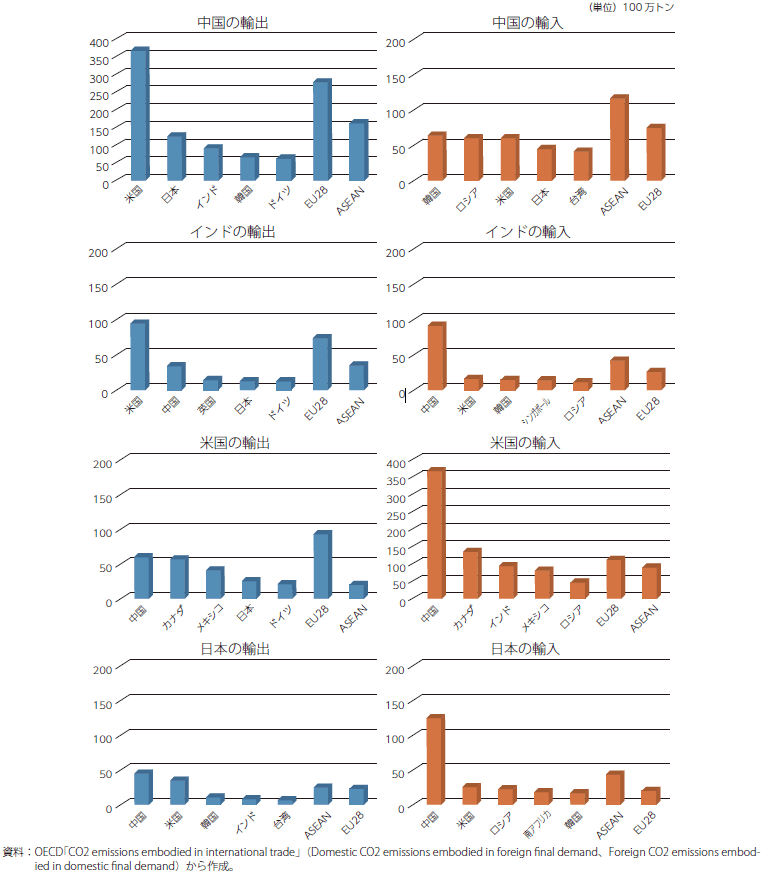
また、各国・地域のグロス輸出に含まれるCO2排出を、当該国・地域内の排出分と、原材料や中間財その他の形で輸入された国外・地域外の排出分とに分けて見ることもできる(第Ⅱ-1-3-6図)。このうち中国の輸出に内包される国外排出分の内訳を見ると、米国、日本、韓国、インド等での排出分(CO2の「輸入」分)が多く含まれていることが分かる(第Ⅱ-1-3-7図)。
第Ⅱ-1-3-6図 各国・地域の輸出に含まれるCO2排出の内外別内訳(2018年)
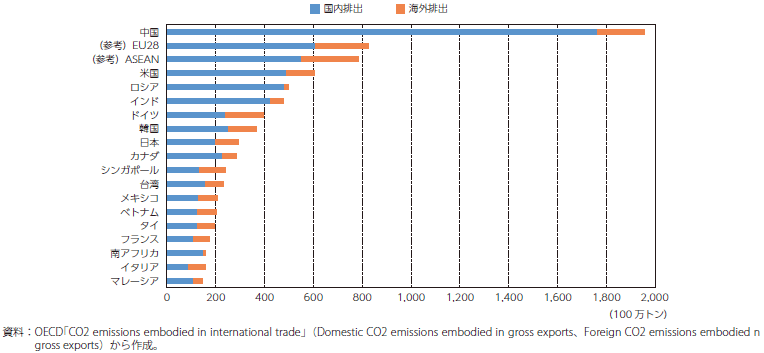
第Ⅱ-1-3-7図 中国の輸出に含まれる国外のCO2排出(2018年・上位10か国)
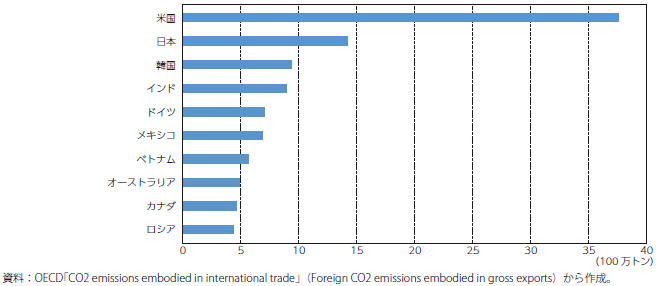
これらのデータから、CO2が貿易に内包されて各国・地域間でやりとりされていることが分かる。財やサービスのやりとりの中で付加価値が生まれていくことと表裏をなす形で、CO2の負の「バリューチェーン」が形成されているともいえるだろう。グローバルなカーボンニュートラルの実現のためには、バリューチェーンの一か所(企業でいえば自社内)だけでなく、全体で排出削減の取組を行っていく必要がある。生産、輸出入、消費、そして廃棄・循環といった経済活動のライフサイクル全体を見据えた取組が必要である。
67 ラオスとミャンマーを除いた8か国。
(2)GVCにおけるCO2排出の把握・情報開示の動きと日本企業の課題
近年、企業は、バリューチェーン上のCO2排出の把握、情報開示の取組を急速に進めている。パリ協定以後、気候関連財務情報や環境影響を開示する枠組み(TCFD68、CDP69)や脱炭素に向けた目標設定(RE10070、SBT71)に関わるイニシアティブ等に対して、日本企業も積極的に参加している(第Ⅱ-1-3-8図)。
第Ⅱ-1-3-8図 各種脱炭素経営への取組を行う企業の国・地域別比率
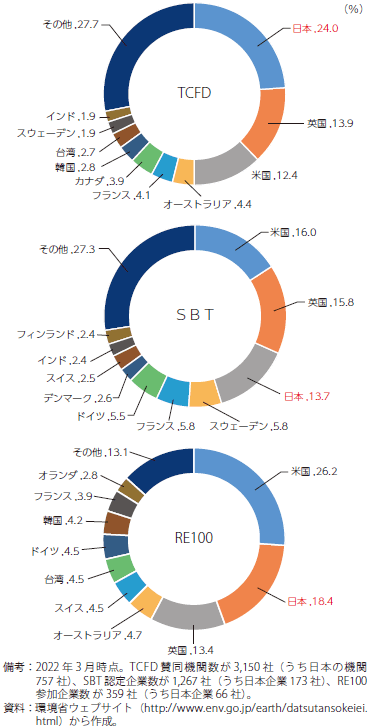
このような枠組みにおいて、企業の排出量の算定・報告基準の一つとして採用されているのが、GHGプロトコル基準(GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard)である。この基準には、Scope1(事業者自らによる直接排出)、Scope2(他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出)及び、Scope3(Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出))の分類があり、Scope1から3の合計が当該企業のGVC全体から発生する排出量になる72。取組企業の事業形態の違いや取組の難易度を反映して、排出削減コミットメントにScope3を盛り込んでいる企業の比率は今のところ限定的である73。
グローバル大企業の中には、GVCの脱炭素化を実現するために自社のサプライヤーに対して100%再生可能エネルギー電力の使用等を求める企業が出てきている(第Ⅱ-1-3-9表)。こうした動きに対して、日本のサプライヤー企業も対応を進めており、これらの需要家が主導して再生可能エネルギーの調達に取り組むUDA(User-Driven Alliance)モデルによる取組が拡大し、このような導入モデルに対する政府支援が行われるなど、徐々に取組の増加が見られる。第Ⅱ-1-3-10図、第Ⅱ-1-3-11図は、均等化発電原価(LCOE)ベース74で各国の再生可能エネルギー(太陽光、風力)発電コストの推移を見たものである。日本を含め、各国とも低下してきているが、足下では、日本の発電コストは諸外国に比べて高くなっている。再生エネルギーの特徴として、日照条件や風況、平地面積といった地理的条件などにより、コスト競争力に大きな差が生じる。日本は諸外国に比べて、こうした諸条件で不利な立場にある。他方、顧客の脱炭素要請に応えられなければ、商品やサービスの調達先として選ばれなくなり、ビジネス機会を失うことになる。再生可能エネルギーへのアクセスが難しい場所からは、企業が退出したり、投資を引き上げたり、アクセスが容易な場所に拠点を移したりするなど、GVCの再構築に向けた行動が促されるであろう。エネルギー面のイコールフッティングの確保は、日本にとって喫緊の課題である。
第Ⅱ-1-3-9表 サプライチェーン全体で脱炭素に取り組む企業の例
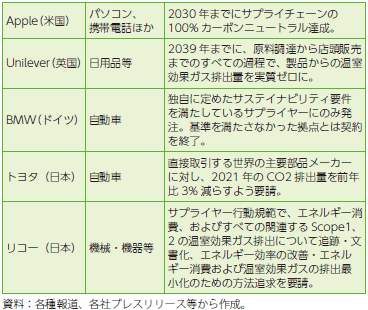
第Ⅱ-1-3-10図 再生可能エネルギー発電コストの推移(太陽光)
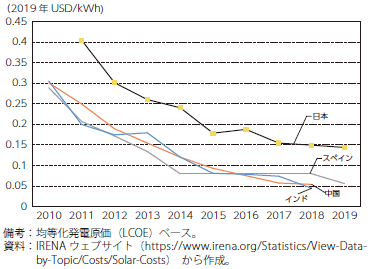
第Ⅱ-1-3-11図 再生可能エネルギー発電コストの推移(風力)
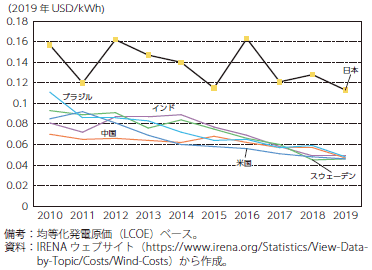
68 2015年、G20の要請を受けて金融安定理事会(FSB)によって設立された「気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」。企業等に対して気候変動関連のリスクや機会の開示を推奨している。
69 2000年設立の英国のNGOで、企業のみならず政府や自治体、都市などによる環境影響を評価するための情報開示システムを運営している。
70 企業が自らの事業の使用電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指すイニシアティブ。
71 企業が設定した中長期の温室効果ガス排出削減目標の認定を行うイニシアティブ。
72 Greenhouse Gas Protocol (2017) 「A Corporate Accounting and Reporting Standard」、同(2013)「Technical Guidancefor Calculating Scope 3 Emissions」、環境省「サプライチェーン排出量算定の考え方」(環境省ウェブサイト)
(https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/supply_chain.html![]() )
)
73 2020年10月時点で20%程度(経済産業省(2021a)「通商白書(2021)」。出所はNewClimate Institute & Data-Driven EnviroLab, Navigating the nuances of net-zero targets.)。このほか、JETRO(2022)「2021年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」によれば、海外での脱炭素化の取組状況について、「すでに取り組んでいる」とした企業は全体(本設問への回答企業490社)の23.1%(うち大企業(同158社)では39.2%、中小企業(同332社)では15.4%)。
74 LCOEは各種発電設備における資本費、運転維持費、燃料費等、発電に必要な費用を生涯の発電量で割りkWhあたりの電力単価を求めたもの。
(3)カーボンプライシングの世界的動向
CO2排出の「可視化」の観点から、企業等排出者の脱炭素に向けた行動変容を促す経済的手法として、世界各国で導入が進んでいるカーボンプライシングについて見ていく。カーボンプライシングには様々な種類があるが、代表的手法としては、政府による炭素税(燃料・電気の利用によるCO2排出量に比例して課税)や排出量取引制度(一般的には、全体の排出量の上限を決め、企業等に排出枠・排出権を配分する手法。排出枠・排出権を超過する企業と下回る企業が排出枠・排出権を売買)、企業等によるインターナル・カーボンプライシング(企業が独自に自社のCO2排出に対して価格付けし、投資判断等に活用)、クレジット取引(CO2削減価値をクレジット化して取引)等がある75。それぞれの措置・制度の選択や組み合わせ、実施主体や実施方法については脱炭素化の段階に応じた適切なポリシーミックスが求められる76。
世界では、2021年4月時点で64の国・地域でカーボンプライシングが稼働しており、世界のCO2排出量の21.5%をカバーしている。国や地域により、導入されているカーボンプライシングの水準は一様ではない。例えば、EUの排出量取引価格(ETSのオークション価格)は、2020年12月にEUが排出削減目標を引き上げてから急速に上昇しており(第Ⅱ-1-3-12図)、欧州の産業界(欧州鉄鋼連盟)は、ETS価格の上昇が、炭素排出規制が厳格でないEU域外企業に対する域内企業の競争力に及ぼす負の影響について懸念を表明している77。なお、カーボンプライシングの評価については、エネルギー本体価格や再エネ賦課金、エネルギー税制も含めたエネルギーコストへの影響も含めて勘案する必要がある。
第Ⅱ-1-3-12図 EU ETS価格の推移
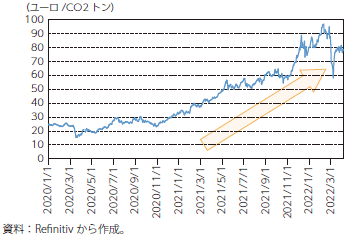
●EUの炭素国境調整措置
EUの炭素国境調整措置導入の動きは、こうした排出削減コストをめぐる内外の公平性重視の文脈からも捉えることができよう。EUは、2050年に気候中立、通過点である2030年に1990年比で55%のCO2排出削減を目指している。その先進的な排出削減の取組は、一方で、それに伴う厳格な規制を回避し、排出基準の緩やかな国や地域で生産や調達を行おうというインセンティブを助長するリスクを孕む。そうした「排出削減のフリーライド」が生じることによる競争条件の歪みや、炭素効率の低い輸入品に国内市場が脅かされるという意味での炭素リーケージ78を防止すべく、2021年7月、欧州委員会は炭素国境調整メカニズム(CBAM:Carbon Border Adjustment Mechanism)に関する規則案を公表した79。CBAMは、EU域外から輸入する製品の数量や炭素排出量、炭素コスト等に応じて、EU-ETSに基づく炭素価格分をEUの輸入業者に負担させる仕組みで、規則案では、鉄鋼、セメント、肥料、アルミニウム、電力が対象となっており、2023年の導入が予定されている。炭素国境調整措置についてはWTOルールとの整合性が確保されること、炭素排出量の計測においては、正確性と実施可能性の観点からバランスのとれた信頼性の高い計測・評価手法が採られることなど80、国際ルール、標準の観点からの議論や検討が深められるべきである。一方で、対応する企業においては、炭素排出や炭素コストの一層の可視化と情報開示の強化が求められていくことに留意する必要がある。
75 経済産業省(2021b)
76 経済産業省(2021c)
77 滝澤祥子(2021)「欧州鉄鋼連盟、鉄鋼需要の回復を予測、今後の国際競争環境には懸念」(2021年5月12日)(JETROウェブサイト)、欧州鉄鋼連盟ニュースリリース(2021年5月1日)(https://www.eurofer.eu/news/eu-ets-price-rally-rams-home-the-competitiveness-challenge-facing-the-sector/![]() )
)
78 日本エネルギー経済研究所(2021)
79 欧州委員会ウェブサイト(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3541![]() )
)
80 経済産業省(2021c)
2.ビジネスと人権の課題への対応
経済活動における人権の尊重についても関心が高まっている。2011年、国連人権理事会において、「ビジネスと人権に関する指導原則」が全会一致で支持(endorse)された。同原則は、ビジネスと人権の関係を、「人権を保護する国家の義務」、「人権を尊重する企業の責任」、「救済へのアクセス」の三つの柱に分類し、被害者が効果的な救済にアクセスするメカニズムの重要性を強調している。このうち、企業の責任としては、人権方針の策定、デュー・ディリジェンスの実施、苦情処理メカニズムの設置等が求められている。同原則の履行として、各国に対し国別行動計画(NAP:National Action Plan)の策定が推奨されており、20か国以上が行動計画を公表している。我が国政府においては、2020年10月に「ビジネスと人権」に関する行動計画を策定し、その中で、規模、業種等にかかわらず、日本企業に対して、人権デュー・ディリジェンスのプロセスの導入を期待する旨を表明している。人権デュー・ディリジェンスについては、OECDの「多国籍企業行動指針(1976年)」に2011年の改定で追記され、実務向けのガイダンスも示されている(第Ⅱ-1-3-13図)。
第Ⅱ-1-3-13図 人権に関する主なガイドライン
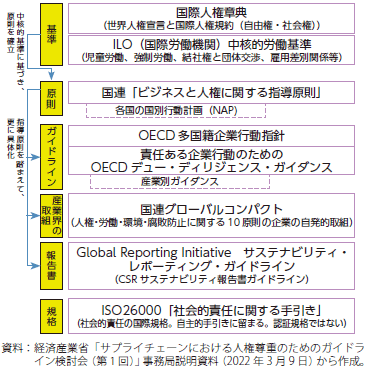
欧米各国では、「人権保護」と「対外経済政策」を連動させる動きが加速している。ドイツでは、2021年6月、「サプライチェーン法」が成立した。同法では、一定規模以上の企業に人権デュー・ディリジェンスの実施や、その結果に関する報告書の作成・公表等を義務づけており、2023年1月から施行される予定となっている。また、EUでは、2021年7月に、欧州委員会・欧州対外行動庁が、「EU企業による活動・サプライチェーンにおける強制労働のリスク対処に関するデュー・ディリジェンス・ガイダンス」を発表し、企業に対し、強制労働のリスクに対処するために必要な取組を実践面から指南している。加えて、加盟国レベルで人権デュー・ディリジェンスを義務化する動きはこれまでもみられたが、これをEU域内全体に広げる議論が加速しており、2022年2月に、欧州委員会は、「企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令案」を公表した。本指令案は、EU域内の大企業(域内で事業を行う第三国の企業も含む)に対し、人権や環境のデュー・ディリジェンス実施等を義務づけるものである。今後、指令案は欧州議会等での議論を経て、採択されれば、各国は2年以内にこれを踏まえた国内法を制定することが求められることになる。さらに、米国では、2021年12月、中国の新疆ウイグル自治区で一部なりとも生産等された製品や、米国政府がリストで示す事業者により生産された製品は、全て強制労働によるものと推定し米国への輸入を禁止する「ウイグル強制労働防止法」が成立した。同法では、輸入禁止を避けるには、輸入する製品が一部なりとも強制労働に依拠していないこと等を輸入者が証明する必要がある。法律を執行する上での細則やガイドライン(「執行戦略」)を定め、2022年6月に施行される予定である。
こうした国際社会の動きも踏まえ、企業としても事業活動における人権尊重の取組を行っていく必要がある。CO2排出削減・脱炭素の取組と同様、人権の問題に関しても、自社内だけでなく自社のサプライチェーンやバリューチェーン全体を見据えた対応と情報開示が求められている。
(1)バリューチェーンにおける人権の問題
2030年までの国連の持続可能な開発のためのアジェンダであるSDGs(Sustainable Development Goals)は、強制労働や児童労働、人身売買等の「現代奴隷制」を終わらせることを目標としている。ILOによると、2016年時点で、世界で約4,000万人が現代奴隷制(約2,500万人が強制労働、約1,500万人が強制結婚)に該当するとされる81。
こうした人権侵害を伴う形で採取・生産された原材料や部素材の使用、あるいは最終製品の購入等、様々な取引に関与するリスクに注意する必要がある。特にGVCの広がりの中で、人権リスクの高い国・地域内に財やサービスが留まらず、貿易に内包されてGVCに組み込まれていくリスクに留意すべきである。ILO、OECD、IOM(国際移住機関)、UNICEFは、この点を踏まえたレポート82の中で、生産工程やそれ以前の原材料採取の段階における人権リスクが輸出入に内包される可能性について産業連関表の手法を用いた検討を行っている。
GVCマネジメントの観点からは、グローバルに展開するサプライチェーンにおいて、自社だけでなく、取引先やサプライヤーの人権リスクについても把握する必要がある。
81 ILO et al.(2017)
82 Ali Alsamwi et al.(2019)
(2)我が国の取組
我が国政府においては、2020年10月に「ビジネスと人権」に関する行動計画を策定し、その中で、規模、業種等にかかわらず、日本企業に対して、人権デュー・ディリジェンスのプロセスの導入を期待する旨を表明している。経済産業省と外務省は、2021年11月、同計画のフォローアップの一環として企業の取組状況を把握するため、日本企業のビジネスと人権への取組状況に関する、政府として初めて実施した調査の結果を公表した83。調査の結果、回答企業において、売上規模が大きい企業や、海外売上比率が大きい企業は人権に関する取組の実施率が高い傾向にあることが明らかになったが、全体としては、人権デュー・ディリジェンスの実施率は約5割程度にとどまっているなど、日本企業の取組にはなお改善が必要であることが明らかになった。また、人権への取組の実施率が高い企業ほど、国際的な制度調和や他国の制度に関する支援を求めていることが明らかとなった。政府に対する要望として、ガイドライン整備を期待する声が最も多く寄せられ、人権尊重への取組が進んでいない企業の半数からは、具体的な取組方法が分からないとの回答も寄せられた。このような状況を踏まえ、2022年3月、経済産業省は、サプライチェーンにおける人権尊重のための業種横断的なガイドライン策定に向けて検討会を立ち上げた。2022年夏までに策定する国内のガイドラインの整備と併せて、国際協調により、企業が公平な競争条件の下で積極的に人権尊重に取り組める環境、各国の措置の予見可能性が高まる環境の実現に向け取り組んでいくこととしている。
●責任あるサプライチェーン実現に向けた取組(繊維産業の場合)
繊維産業は、糸や生地の製造、製品の企画・製造、流通・販売と川上から川下まで長いサプライチェーンを築いていることが特徴である。サプライチェーンが長く、事前の需要予測が難しいことから、適量生産・適量供給を行いにくく、大量供給・大量廃棄等が生じうるという問題やサプライチェーン上の人権リスクへの対応など、サステナビリティに関する多様な課題に直面している。国際社会においては、2013年のバングラデシュにおける縫製工場入居ビル(ラナ・プラザ)の崩壊事故や、多国籍企業の現地工場の労働環境問題等、繊維産業の人権の問題に厳しい目が向けられてきた。2015年のG7サミット(エルマウ・サミット)でも、「責任あるサプライチェーン」が議題となり、首脳宣言において繊維および既成衣類部門を含むイニシアティブの強化について盛り込まれた84。
経済産業省は、2021年2月から「繊維産業のサステナビリティに関する検討会」を開催し、多岐にわたる有識者とともに、繊維産業におけるサステナビリティに関する取組を促進するための議論・検討を進め、同年7月に報告書をとりまとめた。同報告書では、環境配慮、責任あるサプライチェーン管理、ジェンダー平等、供給構造を取り上げ、こうした取組を進めていく上でデジタル技術の活用が有用であるとしている85。なお、責任あるサプライチェーン管理については、取組を通じて人権の尊重や労働環境の整備等を目指すとしている。また、本報告書を踏まえ、2021年11月、日本繊維産業連盟とILOが経済産業省立会いの下で繊維産業の責任ある企業行動の促進に向けた協力のための覚書を締結、これに基づき、同連盟においてILOと連携し、「繊維産業の責任ある企業行動ガイドライン(仮)」の策定を進めている。
83 経済産業省・外務省(2021)
84 経済産業省(2021d)
85 適量生産・供給のための需要予測(AIによるSNS画像分析で商品トレンドを把握)や生産に関する情報の全てを管理する取組(タブレット端末による各スタッフの工程管理、IoT技術を用いた工場における機械の状況管理、サプライチェーン上の企業とのコミュニケーションをデジタル化)等の事例が出てきている(経済産業省(2021d))。
3.多様化する考慮事項
共通価値のような非経済的価値を可視化しようという動きは、特に世界金融危機後の国際社会において顕著になってきた。「豊かさ」を市場価値のみで計測することの限界や矛盾が意識され、経済活動の外部効果や将来への影響、主観的価値等を可視化することにより、経済社会の現状を多面的に捉えようとする努力が講じられてきている。2009年のスティグリッツ委員会報告を踏まえて開発されたOECDの「Better Life Index」や、現在各国が取り組んでいる国連の持続可能な開発目標(SDGs)の進捗度を示す「SDGs Index and Dashboards」、2010年に発表され、SDGsに関する取組を総合的に評価する方法として国連環境計画(UNEP)が推進している「新国富指標(Inclusive Wealth Index: IWI)」、各国における社会進歩・幸福度に関するマクロ統計等はその例である。我が国でも、2021年6月18日に策定された「グリーン成長戦略」において、「国連が定める国際基準である環境経済勘定体系(SEEA)や国際機関等による研究に則しつつ、環境要因を考慮した統計(グリーンGDP(仮称)など)や指標に係る研究やその整備を関係省庁が連携して行う」ことが表明された。
近年、経済活動で考慮されるべき共通価値が多様化している。地球環境との関係では、気候変動問題に加えて、地球の供給限界を勘案した「自然資本の減耗(生物多様性の毀損)」の問題が論じられている(Dasgupta(2021)”The Dasgupta Review”)。また、従来のように川上から川下(消費者)への一方向の流れ(動脈部分)だけでなく、廃棄から再生に至る流れ(静脈部分)を価値創造の場として包含することによりサプライチェーン、バリューチェーンを循環型のモデルで捉える必要性が論じられ、「循環経済」に関する指標の開発、同指標に基づく投資等も行われている86。さらに、社会における所得格差の拡大や中間層の衰退を指摘する声や、企業の役割について再考する動きもある。米国のビジネスラウンドテーブルが2019年8月、企業の役割(パーパス)について、株主第一主義から全てのステークホルダーの利益を重視する方向へと考え方を転換したことは大きな反響を呼んだが、このステークホルダーへの配慮の可視化については、2020年9月、世界経済フォーラム(WEF)が「Stakeholder Capitalism Metrics (SCM)(ステークホルダー資本主義指標)」を発表している。日本政府においても、2021年10月から「新しい資本主義実現会議」が開催され、こうした多様な共通価値に関する議論を踏まえながら、「成長と分配の好循環」、「コロナ後の新しい社会の開拓」に向けた諸課題(例えば、ステークホルダー論、人的投資、分配の問題といった資本主義の再構築に関わる論点や、サプライチェーンの強靱化、スタートアップ、デジタルトランスフォーメーション(DX)、イノベーション等)について検討が行われている。
●共通価値に関する情報開示
捕捉するべき非経済的価値、共通価値の多様化・増大は、一方で、企業等の取組や開示すべき情報の多様化・増大と表裏をなすという点に留意したい。国際イニシアティブやNGO等の評価機関、認証の数も増え、情報の開示基準やガイドラインも多岐にわたることから、取組に関する企業の理解や対応が十分に進んでいないとの指摘もある87。サステナビリティとは何か、情報開示にあたって具体的に何を報告すべきなのか、といった具体的な定義や指針が求められていると言えるだろう。
サステナビリティの定義をめぐっては、持続可能な経済活動等を促進するための投資(サステナブルファイナンス)拡大の観点から、サステナブルな経済活動を分類するための基準である「タクソノミー」の策定に向けた動きが、予定段階のものも含めて、EUやオーストラリア、アジア新興諸国等、各国・地域で見られるようになっている。「グリーン」への移行(「トランジション」)についても、ASEAN諸国やカナダなどがタクソノミー制定に動いている88。タクソノミーは、これまで定義が曖昧だった「グリーン」などの概念について基準を明確化することで、表面的なサステナビリティ配慮(グリーンウォッシュ等)を防止し、真にサステナブルな活動に対する投資を推進することを目的としている。一方、タクソノミー基準設定における科学性の担保、中央集権的・硬直的な基準設定に伴うコストやリスク、各国の発展段階や地理的条件、エネルギー事情等の差異への留意等、タクソノミーの有効性を確保する上で、様々な課題も指摘されており、日本も、例えば、IPSF(International Platform on Sustainable Finance)等における検討など、タクソノミーに関する国際的な議論に、適切に参画していくことが期待される89。
企業等による非財務情報の開示基準についても、足下、EUの非財務情報開示指令の改定(前述のEUタクソノミー等に留意しながらEUが定める報告基準による開示を義務付け)やIFRS財団による国際サステナビリティ基準策定のための新たな審議会設置(ISSB: International Sustainability Standards Board)等、国際的に一定の収斂に向かう動きが見られる。日本としても、その考え方や問題意識の発信を通じて基準設定に関与していくことが必要である。経済産業省では、そうした問題意識を踏まえ「非財務情報の開示指針研究会」において、質の高い非財務情報の開示を実現する指針のあるべき方向性について検討を行い、2021年11月に中間報告をとりまとめた。さらに、2022年3月にはISSBが公表しているISSB気候関連開示プロトタイプについての基礎的見解を公表し、国際的な非財務情報開示基準の議論に対する発信を行っている。
86 経済産業省(2020)「循環経済ビジョン2020」(2020年5月)で、イタリアで開発された循環経済に関する指標を用いてフランスの金融機関が投資信託商品を開発した事例を紹介。
87 企業活力研究所(2018)
88 金融庁(2021a)
89 金融庁(2021b)
4.デジタルによるグローバルバリューチェーンの可視化
災害や感染症、地政学リスク等による突然の供給途絶への対応、本節で見てきた多様な共通価値の実現など、GVCマネジメントの課題は複雑化、高度化している。GVC上の新たな課題に対応するためには、旧来のマネジメントのあり方やレガシーシステムの大胆な見直しが必要である。
デジタル技術・サービスの活用は、経営革新の重要な鍵である。GVCマネジメントに関して言えば、GVC全体を可視化し、問題の所在をリアルタイムで明らかにすることで迅速な経営判断を可能にするほか、取引先とそのGVCのサステナビリティに関する取組状況の情報をデータとして蓄積・分析することで、リスクの予見可能性を高めることなどが期待される。具体的には、IoT情報の企業間連携によるサプライチェーンやバリューチェーンの最適化(各段階における時間的ロスの削減、生産進捗の確認、供給途絶ポイントの把握等)、衛星情報を活用した物流のトレーサビリティの向上、ビッグデータの分析による需要予測や在庫管理、SNS情報の活用による業務・ガバナンスの向上(災害や事件の迅速な把握、消費者ほかステークホルダーの声の把握・分析等)、デジタルツイン技術を用いた仮想空間(メタバース)での様々なシミュレーションによるバリューチェーン設計の効率化・高度化など、活用の場は多岐にわたる。また、デジタル化を通じた貿易手続きコストの削減はGVCマネジメントにおいて重要な要素となる。通関手続き書類や港湾事務フローの電子化のほか、トレードワルツ90のようなブロックチェーン技術を用いた貿易手続電子化サービスのプラットフォームが立ち上げられ、膨大な貿易データを一元管理することでサプライチェーン管理に貢献しており、各国の公共部門と連携して手続きのシングルウインドウ化を図る動きなどが見られる91。GVCの最適化とデジタル化は密接な関係があると言え、GVCマネジメントにおいてデジタルネットワークへの「接続性」や「データ」の重要性が一層、増していくと考えられる。
90 トレードワルツウェブサイト(https://www.tradewaltz.com/![]() )。
)。
91 経済産業省(2021a)
(1)日本企業の課題
しかしながら、日本企業のデジタルによるGVCマネジメントの進展スピードは、全体的に緩慢である。
通商白書2021でも取り上げた日本企業におけるデジタル技術を用いた生産プロセスの可視化の取組に関する調査結果92によれば、デジタル技術を用いて海外工場も含めたサプライチェーンの可視化の取組を行っている企業は、回答企業の2.9%にとどまり、実施予定がない企業が74.7%に上った。
欧米企業がデジタル技術によるサプライチェーンの強靱化やサステナビリティの確保といった段階に進んでいるのに比べて、多くの日本企業は未だ最初の段階(電話・メール・FAXのマニュアル作業の削減やペーパーレス化、サプライチェーンの各段階のデジタル化が中心)に止まっているとの指摘がある93。また、日本企業のIT活用に注力するテーマとしては、「会計の適正化や精度向上」、「間接業務全般の改善や効率化」、「調達・生産・効率にかかわる業務プロセスの改善や効率化」といった項目についての積極度が高く、「新たな事業領域の開拓や新しいビジネスモデルの開発」、「新たな営業・販売チャネルの導入やチャネル全体の再構築」といった新規分野の開拓、また「サプライチェーン全体の最適化」といった項目については積極度が相対的に低いとする調査結果がある94。また、企業のIT予算の増額要因に関する日米企業の比較調査によれば、米国では「顧客行動や市場の分析強化」や「市場や顧客の変化への迅速な対応」を挙げる企業の比率が高いのに対し、日本では社内の「働き方改革の実践」や「業務効率化・コスト削減」を挙げる企業の比率が高く、戦略的な見地からのIT活用の事例は相対的に少ない95。
共通価値やデータをめぐる各国の措置の透明性や、実践上のわかりやすさ、既存の枠組みとの調和等、企業の取組を推進していくためのグローバルな環境整備も求められる。データに関して言えば、各国の規制や措置の「透明性の確保」に関する課題(「個人情報」やデータの「越境移転」の定義や要件・規制対象の範囲が曖昧であること、規制や措置の急な変更への対応に苦慮していること等)、「技術と標準化」に関する課題(第三国への越境移転時にも移転元国と同等の保護・管理を行うことが企業の責任として課せられ対応に苦慮していること、セキュリティ関連情報の取り扱いについて地域・国独自の認証の取得を要求されることがあり、取得等にかかるコストが多大であること等)が挙げられている96。
福岡・坂本(2021)は、共通価値やDXに取り組む企業を支援するための政策的アプローチとして、ガイドラインの策定や、予算や人員等が十分ではない中堅・中小企業向けの支援(専門家等による相談体制の確立やサプライチェーンの可視化・冗長化支援)、サプライチェーン可視化の実装支援(可視化サービス提供企業とのマッチング等)、データ連携のための標準策定等のほか、デジタル、サプライチェーンに関する豪州やインド、ASEAN等との連携の強化により信頼あるサプライチェーンの構築支援を挙げている97。
92 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(2020)
93 Makiko Fukai (2021)「サプライチェーンジャーニー」(2021年10月21日)(https://blogs.opentext.jp/supply_chain_journey/![]() )
)
94 有賀(2020)
95 一般社団法人 電子情報技術産業協会・IDC Japan 株式会社(2021)
96 経済産業省(2022)「データの越境移転に関する研究会報告書」(2022年2月28日)
97 福岡・坂本(2021)
(2)データ連携基盤を通じたバリューチェーンマネジメント
GVCマネジメントにも深く関わる統合的なデータ連携基盤(プラットフォーム)構築の取組は、欧州で先行して進められている。国際データスペース協会(International Data Space Association: IDSA)による国際データスペース(IDS)は、データ主権を担保した「データエコシステム構築」のため、データ交換の標準アーキテクチャー、ルール・ガイドライン、データ交換のための技術要素(コネクター)等を定義・提供し、データ連携のユースケース整備を進めている。2016年の設立以降、130の参加組織が存在し、既にビジネスレベルで企業・異業種間データ連携でのユースケースが蓄積され、サービスが生まれてきている。ユースケースの例としては、独ボッシュ社によるインシデント時共同サプライチェーンデータ管理サービス、中国ハイアール社によるプラットフォームサービスCOSMOPlat、日本NTT社及び独SIEMENS社によるCO2削減と循環型経済実現を目的とした、データ主権の保護とサイバーセキュリティの確保に向けた実証事業等が挙げられる。また、IDSでは、欧州に留まらず、よりグローバルなオープンスタンダード化が目指されており、日本や中国を始めとした各国にハブを設立する動きも出ている。ドイツとフランス両国の政府が2019年10月に発表したGAIA-Xは、認証や契約手続に基づいてデータへのアクセスを制御し、データ主権を保護しつつ、様々なクラウドサービスとの相互運用性を確保する技術的な仕組みである98。例えば、機械が利用される現場やサプライチェーンの各段階に存在するオペレーター、機械メーカー、部品メーカー、サービスプロバイダーが、GAIA-Xプラットフォームにおいて機械の稼働情報を共有することにより、生じている課題に適時適切に対応することが可能となるほか、機械のライフサイクルの各時点で必要なソリューションのやりとりが可能となるといったメリットが想定されている99。また、サステナブルなエネルギーの利用についても、ブロックチェーン技術を用いた、バリューチェーンを一気通貫する証明システムの構築等も想定されている100。このほか、ドイツの自動車メーカーが2021年3月に設立を発表した自動車関連企業間の安全なデータ共有のアライアンスであるCatena-X Automotive Network(以下Catena-X)もある。Catena-Xには、自動車メーカーだけでなく自動車のバリューチェーンに関与する企業(部素材メーカー、機械メーカー、通信・IT関連企業)や研究機関等が参加しており、Catena Xのプラットフォーム上でデータを共有することにより、品質管理や物流、保守・保全、管理、サステナビリティの実現等をサプライチェーン、バリューチェーン全体で行うことが可能となる。これらのデータ連携基盤への中小企業の参加も重視されている101。
日本企業にとっても欧州のデータ連携基盤構築の動きは大きな関心事項である。日本の産業界においては、例えば、脱炭素や資源循環のための製造データの企業間共有に向けた議論や取組、IDSAと国内のデータ連携推進団体との協業の動きも見られる102。データ連携基盤に関する欧州のアプローチは、企業等の実世界での活動について取得されるリアルデータを複数の企業間で活用するモデルであり、製造現場において蓄積されてきたデータやノウハウ、ハード面の優位性といった日本企業の強みが生かされるべき領域でもある。そうした観点からも、特に日本のサプライチェーンやバリューチェーンに深く関わるアジア地域の企業と一体となったデータ共有・連携に向けた取組促進や、そのためのルール整備が急がれる。
経済産業省では、アジアと一体になった成長の実現に向けて、日本が長くアジア各国と共有してきたサプライチェーンを高度化し、日本企業の競争力強化や環境・人権等の共通価値への対応等に繋げる観点から、アジアにおける企業間のデータ共有・連携を促進する取組を進めるべく検討を行っている。具体的には、欧州で進むデータ連携基盤(前述のIDSやCatena-X、GAIA-X)の取組を参考にしながら、アジア各国との経済関係強化のために打ち出した「アジア未来投資イニシアティブ(2022年1月公表)」においても表明しているように、今後5年で100件のデータをフル活用したサプライチェーンのユースケースを創出していく(第Ⅱ-1-3-14図)。
第Ⅱ-1-3-14図 データ連携によるアジアのサプライチェーンのアップグレードの検討
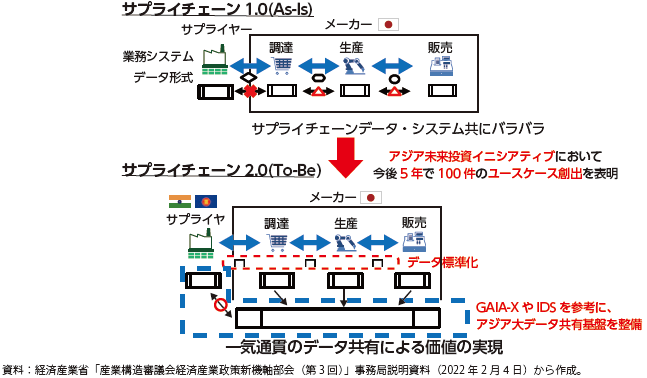
98 「包括的データ戦略」(2021年6月18日閣議決定)
99 ドイツ連邦経済・気候保護省ウェブサイト(https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Artikel/Digital-World/GAIA-X-Use-Cases/integration-of-data-along-the-life-cycle-of-production-machines.html![]() )
)
100 ドイツ連邦経済・気候保護省ウェブサイト(https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Artikel/Digital-World/GAIA-X-Use-Cases/system-for-automated-certification-of-renewable-energy-and-management-of-certificates.html![]() )
)
101 Gaia-X European Association for Data and Cloud AISBLウェブサイト(https://www.gaia-x.eu/what-gaia-x/factsheet![]() )、Catena-Xウェブサイト(https://catena-x.net/en/#intro
)、Catena-Xウェブサイト(https://catena-x.net/en/#intro![]() )。
)。
102 一般社団法人データ社会推進協議会プレスリリース「The International Data Spaces e.V. (IDSA)とのコラボレーション契約締結」(2021年10月10日)(https://data-society-alliance.org/notice/4592/![]() )
)